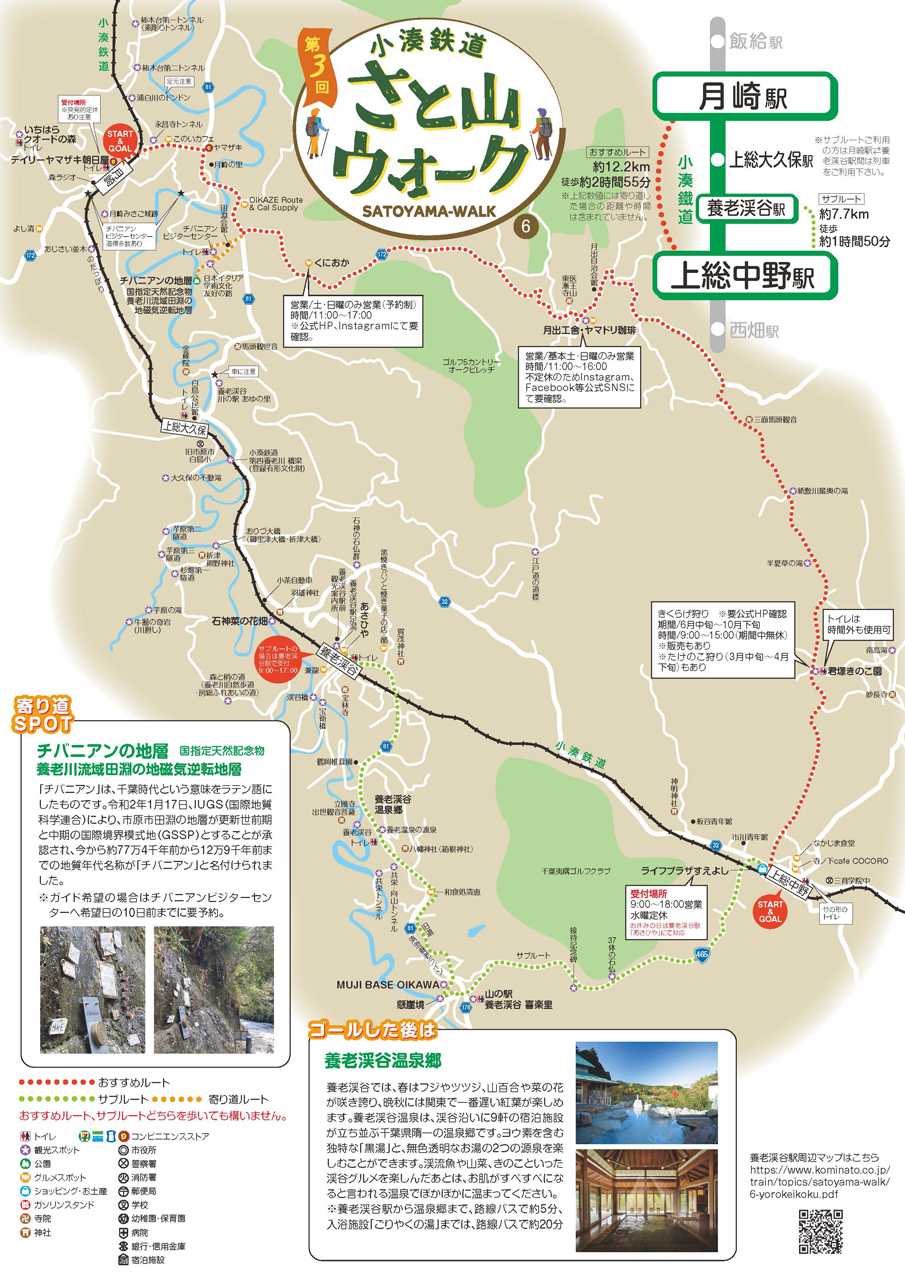2014年03月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
江戸の金山奉行 大久保長安の謎(感想)
2013年は、死後に一族誄殺という過酷な処分を受けた、大久保長安の没後400年にあたっていました。 佐渡の逆修塔は幕末まで荒縄で縛られ続け、八王子の興林寺では、奉納した石塔が藪のなかに打ち捨てられていたといいます。 ”江戸の金山奉行 大久保長安の謎”(2012年3月 現代書館刊 川上 隆志著)を読みました。 江戸時代に逆賊扱いを受けた、大久保長安の実像と歴史的な意義を求めた大紀行文です。 川上隆志さんは、1960年川崎市生まれ、東京大学文学部東洋史学科卒業、岩波書店に入社し、単行本、岩波新書の編集を手がけ、雑誌編集長等を歴任し、現在、専修大学文学部教授、日本文化論・出版文化論を専攻しています。 大久保長安の謎を追求すべく、佐渡、石見、伊豆、甲斐黒川、高麗川、八王子等のゆかりの地から、秦氏の故地・朝鮮半島までを旅しています。 大久保長安は1545年に猿楽師の大蔵太夫十郎信安の次男として生まれ、祖父は春日大社で奉仕する猿楽金春流の猿楽師でした。 応神天皇14年に百済より120県の人を率いて帰化したと記される、弓月君を祖とする秦氏の末裔ということです。 秦氏は、東漢氏などと並び有力な渡来系氏族です。 派手で多能な徳川家官僚でもあった長安の活躍の源泉は、秦氏末裔の遺伝子の働きと見ています。 父の信安の時代に、大和国から播磨国大蔵に流れて大蔵流を創始しました。 父の信安は猿楽師として甲斐国に流れ、武田信玄お抱えの猿楽師として仕えるようになりました。 長安は信玄に見出されて、猿楽師では無く家臣として取り立てられ、譜代家老土屋昌続の与力に任じられました。 この時、姓も大蔵から土屋に改めています。 長安は蔵前衆として取り立てられ、武田領国における黒川金山などの鉱山開発や税務などに従事したといいます。 信玄没後は武田勝頼に仕え、甲斐武田氏が滅亡すると、織田信長による残党狩りが行われましたが、本能寺の変によって難を逃れました。 徳川家康は武田の配下の者たちを自軍に引き入れることを積極的に行いましたが、特に厚遇で登用されたのが長安でした。 鉱山や治水に関する技術に長けていた長安は、大久保忠隣の配下となり、忠隣に気に入られました。 長安はまた、家康に対して武蔵国の治安維持と国境警備の重要さを指摘し、八王子五百人同心の創設を具申して認められました。 関ヶ原の戦いが起こると、長安は忠次と共に徳川秀忠率いる徳川軍の輜重役を務めています。 家康政権下で幕府直轄地の統治に手腕を発揮し、石見や佐渡、伊豆などの鉱山の開発にも貢献しました。 最終的に120万石相当に達したと言われるほど上りつめましたが、1613年に病死すると、徳川の態度が豹変しました。 長安の葬儀の中止、莫大な遺産の没収、遺子7名の切腹に親類縁者の改易などです。 金山をはじめとする様々な管理権・統轄権を与えられていたことで不正な蓄財をくり返し私腹を肥やしていた、というのが一般的な見方のようです。 また、家康より政宗のほうが天下人にふさわしいと考え、政宗の幕府転覆計画に賛同していたという見解もあります。 さらに、直属の上司である大久保忠隣と政治的に対立関係にあった本多正信との権力抗争に巻き込まれてしまったという見解もあります。 その上、キリシタンであったため、その後の過酷なキリシタン弾圧につながったという見解もあります。 いずれも決定打がなく、いまだに謎に包まれているようです。第1章 謎の能楽師第2章 甲斐の金山を歩く第3章 佐渡金銀山の栄華第4章 石見銀山・伊豆金山の繁栄第5章 海と陸のネットワーク第6章 秦氏の末裔第7章 秦氏の原郷を訪ねて
2014.03.24
コメント(0)
-
成熟ニッポン、もう経済成長はいらない(感想)
日本は経済規模ではすでに十分に大きくなっており、いまさら新興国と張り合って経済成長を目指すのではなく、これからは世界に冠たる成熟国家を目指すべきだ、という見解があります。 ”成熟ニッポン、もう経済成長はいらない”(2011年10月 朝日新聞出版刊 橘木俊詔/浜 矩子著)を読みました。 グローバル化が進む中で成熟化する日本の、これから目指すべき方向について議論しています。 橘木俊詔さんは、1943年兵庫県生れ、1967年小樽商科大学商学部卒業、1969年大阪大学大学院修士課程修了、1973年ジョンズ・ホプキンス大学大学院博士課程修了、大阪大学教養部助教授を経て、1979年京都大学経済研究所助教授、1986年教授、2003年同経済学研究科教授、2007年定年退任、名誉教授、4月より同志社大学経済学部教授、同志社大学ライフリスク研究センター長です。 浜 矩子さんは、1952年東京都生れ、1975年一橋大学経済学部卒業、1975年三菱総合研究所入社、1990年から98年まで英国駐在員事務所長兼駐在エコノミストとしてロンドン勤務、帰国後、三菱総合研究所経済調査部長、同社政策・経済研究センター主席研究員、2002年に同志社大学大学院ビジネス研究科教授に就任、2011年にビジネス研究科長に就任しています。 橘木教授が個別の事象について問題提起を行い、浜教授がそれを受けて深掘りしつつ、両者がともに日本の将来像を描いています。 かつて、交通安全の関係で、せまい日本そんなに急いでどこに行くという標語がありましたが、当時の日本人たちは、突っ走りながら突っ走ることに一抹の疑念を感じていました。 だからこそ、あの交通安全の領域を超えた流行語の位置付けを持つにいたったのでした。 当時のGNPはいまではGDPとなっていますが、老いた大人の日本には、そんなに焦って何するのと言いたいということです。 日本は成熟した経済・社会を築いているのですから、これ以上の経済成長は不要と国民は納得すべきです。 そして、アメリカ型の競争原理に基づいた小さな政府よりも、ヨーロッパ型の大きな政府によって社会保障の充実を目指すべきです。 また、中央集権的な政府の体制よりも、基礎的自治体を中心とした分権型の政治・行政体制を目指すべきです、といいます。 このような、大人の段階に踏み込むことになぜか誰もが二の足を踏んでいるのか。 なぜか焦り、なぜか意気消沈しているのか。 一番だの、二番だの、三番だの、誰かが作ったランキングの上位を占めなければ、もうダメだなどと思って焦るのは大人のすることではないだろう。 いいじゃないか、抜かれたって、世界に冠たる成熟国家として、新しい生き方を目指せばいい。 優雅に大人化する日本を見たい。 その姿を地球社会に向かって小粋に披露する日本を見たい、といいます。 でも、そう言う前に、やはり、真の豊かさと経済成長の関係について、もう少し考える必要があるという気がしました。第1章 高度経済成長モデルを脱せよ第2章 無縁社会、格差社会を克服せよ第3章 それでも1ドル50円時代が来る第4章 消費税増税で社会保障改革を第5章 日本の強みと弱み第6章 優雅に衰退しよう
2014.03.17
コメント(0)
-
ある明治リベラリストの記録(感想)
竹越與三郎は、三叉と号して、記者としてまた歴史家として知られ、政治家となっても筆を離さず、つねに時事を説き歴史を語り、独自の文明論、文明史観を論じ日本の発展を主張し続けました。 しかし、今日ほとんど忘れられた存在となっています。 ”ある明治リベラリストの記録”(2002年8月 中央公論新社刊 高坂 盛彦著)を読みました。 孤高の戦闘者であった、リベラリスト竹越與三郎の生涯を記録しています。 高坂盛彦さんは、1937年東京都出身で、1960年東京大学法学部を卒業し、日本国有鉄道勤務を経て、1997年に東京大学法学部に学士入学し、日本政治史・政治思想史を専攻しました。 竹越與三郎は、明治中期以後、大正、昭和前期までの三代において、歴史家として、批評家およびジャーナリストとして、さらに政治家として、広く世に知られた人でした。 著者は、大学時代、丸山真男の論文を読んで、自由民権運動における地方豪農層の役割を説いた竹越與三郎の名をはじめて知った、といいます。 卒業後、サラリーマン生活を送る間も、政治思想史への関心は絶えることがなく、大学再入学を期として、竹越與三郎の業績を調べる機会に恵まれたということです。 竹越與三郎の後半生について短いレポートを書き、軍国主義の風潮に抵抗する老知識人の姿に感銘したそうです。 彼の思想と人物像を知るにつれ、現代において再評価すべき人物であるとの思いか強くなった、といいます。 竹越與三郎は、1865年に武蔵国本庄宿の酒造業清野仙三郎の次男として生まれ、新潟県中頸城郡で成長しました。 上京して中村敬宇に学び、1881年に慶應義塾に入学し、翌年、福沢諭吉から時事新報社への入社を薦められ、在学中から新聞に執筆し始めました。 1883年に、新潟県柏崎出身の伯父・竹越藤平の養子となりました。 時事新報社に入社しましたが、官民調和の臨調に反発して翌年退職し、小崎弘道の勧めで群馬高崎教会に住んで英語塾を開きました。 1886年に、小崎弘道よりキリスト教の洗礼を受け、同年、前橋英学校の教員に招かれました。 その後、”基督教新聞”や”大阪公論”の記者を務めました。 その頃、湯浅治郎の紹介で徳富蘇峰と知り合い、民友社及び”国民新聞”の創刊の手伝いをしました。 1889年に正式に民友社に入り、1890年の国民新聞創刊時から政治評論を担当しました。 この年、オリバー・クロムウェルの伝記”クロムウェル”を刊行して、在野史家としてデビューを飾りました。 1891年から全3巻の予定で、明治維新史を政治・外交・経済・宗教の側面より分析した”新日本史”の刊行を開始しました。 ただし、下巻は未完に終わりました。 1893年に、民友社の十二文豪シリーズの1冊として、マコウレーの伝記を担当しました。 山路愛山とも親交を結び、民友社を代表する史論家として知られるようになりました。 伊藤博文、陸奥宗光、西園寺公望に見出されて高く評価されましたが、原敬、桂太郎、大隈重信とは対立しました。 その後、日清戦争を機に国粋主義に傾倒していった蘇峰を竹越が批判したことから対立し、1895年に民友社を退社しました。 その後、再び時事新報社に入りましたが、陸奥宗光・西園寺公望らの世話を受けて、1896年に”世界之日本”の主筆に迎えられました。 同年に開拓社から、代表作となる日本通史”二千五百年史”が刊行されました。 陸奥の死後は西園寺の側近としても活躍し、1898年に成立した第3次伊藤内閣に西園寺が文部大臣として入閣すると、竹越は大臣秘書官兼文部省勅任参事官に任命されました。 その後、欧州視察を経て、1902年の第7回衆議院議員総選挙において、新潟県郡部区より立憲政友会から立候補して初当選し、以後5回連続で当選を果たしました。 その後、台湾総督府の児玉源太郎総督や後藤新平民政長官とも近くなり、欧米や南洋地域の視察を行って日仏協会設立に尽力したり、1906年に読売新聞主筆に就任するなど、評論活動を続けました。 1915年の第12回衆議院議員総選挙で大隈信常に敗れて落選すると、日本経済史編纂会を結成し、1919年から翌年にかけて”日本経済史”全8巻を刊行しました。 1922年に宮内省臨時帝室編修局御用掛に任命され、ほどなく編修官長に転じて”明治天皇紀”編纂の中心的役割を担いました。 この年貴族院議員に任じられ、政友会系の交友倶楽部に属しました。 1930年に、西園寺公望の半生を記した伝記”陶庵公”を執筆しました。 1940年に枢密顧問官に転じましたが、軍部の圧迫で”二千五百年史”が発売禁止になるなどの圧迫を受けました。 東京大空襲では、蔵書や原稿を焼失しました。 戦後、枢密院廃止後は一切の公職から退き、1947年に公職追放処分を受け、1950年に老衰のため死去しました。第1章 遊学時代第2章 民友社時代第3章 『世界之日本』時代第4章 衆議院議員時代第5章 修史家時代第6章 貴族院議員・枢密顧問官時代
2014.03.10
コメント(0)
-
2045年問題(感想)
レイ・カ-ツワイルは著書の”ポスト・ヒューマン誕生”の中で、コンピュータが人類の知性を超えるときについて言及しています。 映画”マトリックス”などで描かれてきたSFの世界が、現実になるかもしれないというのです。 ”2045年問題”(2013年1月 廣済堂出版刊 松田 卓也著)を読みました。 2045年に意識を備えたコンピュータが人類を支配するという、SF映画の世界が現実になるかもしれないといいます。 松田卓也さんは、1943年生まれの宇宙物理学者・理学博士で、神戸大学名誉教授、NPO法人あいんしゅたいん副理事長、中之島科学研究所研究員です。 1970年に京都大学大学院理学研究科物理第二専攻博士課程を修了し、京都大学工学部航空工学科助教授、英国ウェールズ大学ユニバーシティ・カレッジ・カーディフ応用数学天文学教室客員教授、神戸大学理学部地球惑星科学科教授、国立天文台客員教授、日本天文学会理事長などを歴任しています。 レイ・カーツワイルは、1948年生まれの、アメリカの発明家、実業家、フューチャリストです。 特に、技術的特異点に関する著述で知られています。 マサチューセッツ工科大学在学中20歳のとき起業し、諸大学のデータベースを構築して大学選択のプログラムを作りました。 1974年にカーツワイル・コンピューター・プロダクツ社を設立し、以後数々の発明を世に送り出してきて、アメリカ発明家殿堂に加えられています。 技術的特異点は、強い人工知能や人間の知能増幅が可能となったとき出現するそうです。 具体的には2045年にそこに達すると主張していて、これがいわゆる2045年問題です。 フューチャリストらによれば、特異点の後では科学技術の進歩を支配するのは人類ではなく強い人工知能やポスト・ヒューマンであり、これまでの人類の傾向に基づいた人類技術の進歩予測は通用しなくなると考えられています。 意識を解放することで、人類の科学技術の進展が生物学的限界を超えて加速すると予言しました。 1章では特異点の概念について解説し、2章ではスーパー・コンピュータの実力について論じ、3章ではコンピュータのインターフェイスの最先端を概括し、4章では米国防省やEUが人工知能開発に巨額予算を投じる現状を紹介し意識を持つコンピュータは誕生するかについて論じ、5章では特異点後の人類の未来について展望し、6章ではITによる大量失業の可能性についても言及し、7章では2045年問題が欧米で注目されている背景を解説し人類の文明が繁栄をながらえるための方策について論じています。 コンピュータの話はつい級数的なものになりますが、はたしてどうなのでしょうか。1章 コンピュータが人間を超える日――技術的特異点とは何か2章 スーパー・コンピュータの実力――処理速度の進化3章 インターフェイスの最先端――人体と直結する技術4章 人工知能開発の最前線――意識をもつコンピュータは誕生するか 5章 コンピュータと人類の未来──技術的特異点後の世界6章 コンピュータが仕事を奪う――大失業時代の予兆7章 人工知能開発の真意――コンピュータは人類を救えるか
2014.03.03
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1