2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2005年04月の記事
全33件 (33件中 1-33件目)
1
-
樋口一葉日記のブログ開設と、今後のブログ展望など。
★徳川家康の出自の謎★ここのところ、興味は、「徳川家康」。なぜかというと、娘の名前、「葵(あおい)」と「透萌(ともえ)=巴」をあわせると、「葵巴(あおいどもえ)」紋、すなわち、「葵の御紋」になるから。「葵の御紋=葵巴紋」は、言わずと知れた、徳川家の家紋。そして、葵紋を使うことを決めたのは、徳川家初代将軍の「徳川家康」。と、いうことで、シンクロ的に、徳川家康に興味がいくようになりました。そして、徳川家康、という人物を見ていくと、この人物、なかなか一筋縄ではいかない人物であるようです。思ったほど資料も残っていなくて、いくつかはあるものの、徳川家のお抱え御用学者の書いたものばかりなので、はっきり言って、徳川家康に、都合の良いことしか書かれていないようなのです。しかし、実際に見ていくと、徳川家康の「出自」について、特に、いろいろな噂があることが分かりました。徳川家は松平家、ですが、どうも、家康は、松平家ではなく、よそ者ではないか、という指摘があります。そういった興味から、家康の出自に秘められた謎について書かれた『史疑 幻の家康論』という本を、アマゾンで購入してみました。読むのが楽しみ。今しばらく、「徳川家康」を追い続けてみるつもりです。結論から言えば、彼の出自は、「賀茂氏」であり「秦氏」である可能性があります。「賀茂氏」「秦氏」と来れば、ここ数年、私自身が興味を持っていた、氏族なので、娘の名前から、「秦氏」に結びついてくる、となると、これも偶然ではないのだろうか、などと思ってしまいます。また徳川家康について、進展があれば、触れてみたいな、と思います。★樋口一葉ブログ、始めました★どうしようか、迷っていたのですが、「ヤプログ」で、中途半端になっていた樋口一葉の日記、独立して立ち上げました。まだ、しっかりした形には、なっていませんが。この楽天ブログでも、アップアップの状態なのに、もうひとつ立ち上げて、続けられるかな、と少々自分でも心配なのですが、一葉のブログは、チョビチョビ更新していこうと思います。いろいろなブログを、見てみたのですが、文字的に、デザイン的に、見やすいものを、ということで「gooブログ」にしました。興味がある方は、「お気に入りリンク」からご覧ください。考えてみれば、これで、「楽天」「ヤプログ」「gooブログ」の3つも、ブログをつくってしまいました。(^^;ちょっと手を出しすぎです。●「gooブログ」…樋口一葉ブログ●「楽天ブログ」…個人的な趣味、日常、歴史、古代、謎。「楽天」では、もう少し、歴史、古代の謎、日本の謎、太陽系の謎など、「謎」に焦点を当てた話題も増やしていきたいな、と考えています。やっぱり、「謎」が大好きなので。また、過去の「シンクロニシティ」のエピソードも「楽天に」移動させていこうかな、と考えています。健康関連も、仕事柄、増やしていきたいな、と。うーん、詰め込みすぎだ…。いろいろ欲張ってしまいます。もう少し書きながら、テーマを絞っていきたい、と考えたりしてますが、とにかく、当面の目標は、毎日更新!!といいつつ、過去のを引っ張ってきたりしてますが…。●「ヤプログ」…???どうしよう…このブログ。(^^; まったく現在は、機能してません。ただいま、考案中、というところですが、当面、この状態が続きそう。
April 30, 2005
コメント(2)
-
ロシア王朝最後の「皇帝ニコライ2世」と「樋口一葉」(シンクロニシティの不思議 episode 28)
いよいよ、ゴールデンウィーク、と意気込みたいところですが、私の場合、全く関係がない、というのが実情なんです。サービス業の場合は、祝日も関係ないので、この時期は、淡々と日々出会いを大切に、過ごしていきたいと思います。★本屋は至福の時間★今日は、帰りに本屋に、寄りました。ちょっとの時間でも、本屋に立ち寄るのは、何よりの楽しみのひとつ。買うつもりはなかったけど、2冊購入。(^^;いくと、買いたいのが、出てしまうので、困ります。まあ、いいんですけど。●『一葉のたけくらべ』ビギナーズ・クラシックス (角川ソフィア文庫)●『ロシア幽霊軍艦事件』(島田荘司・角川文庫)樋口一葉に関しては、どちらかというと、作品より、評伝や日記のほうを中心に、よく読んでいるので、作品も、少しずつ、しっかりと読んでいきたいと思っています。本書は、総ルビ付の原文、現代語訳、解説までついた、懇切丁寧な書で、手にとって、これはいい!とすぐ買いたくなりました。島田荘司の『ロシア~』は、名探偵・御手洗潔シリーズの一作品。最近は、というか、ここ数年、いや、もっとかな、本は読むものの、「小説」が、ほとんど読めていないので、少しずつでも読んでいきたいな、と思います。本作品は、ロシアの最後の王朝である、ロマノフ王朝にまつわるミステリー。★ニコライ2世と「大津事件」★ロマノフ王朝最後の皇帝、ニコライ2世は、1917年に起こった「ロシア革命」によて、退位させられます。そして、8月に皇后や5人の子どもとともにシベリアのトボリスクに流されます。その後、レーニンの命令を受けたチェーカー次席のヤコフ・ユロフスキー率いる処刑隊により、1918年7月16日に、皇帝一家はイパチェフ館で全員銃殺され、近くの村に埋められた、と言われています。皇帝一家の最後の状況については、長年さまざまな噂が流れていました。特に、末娘である、第4皇女「アナスタシア」を名乗る女性が、ヨーロッパ各地に現れたりして、世間の話題をさらうこともあった、といいます。本作品では、彼女に関して、歴史の謎に迫る作品となっているようなので、おもしろそうです。一方最後の皇帝、ニコライ2世といえば、1891年に、日本で起きた事件、「大津事件」の被害者としても、有名です。滋賀県の大津といえば、仕事先や実家の隣りの市なので、こんな近くで、かつて、この事件があったのか、と思い、ちょっとドキッとします。大津事件について、インターネットより引用してみます。「シベリア鉄道の式典に出席するため、ニコライは艦隊を率いてウラジオストクに向かう途中、日本を訪問していた。弱小国家として日本は政府を挙げてニコライの訪日を接待し、京都では季節外れの大文字焼きまで行われていた。 そして5月11日に、大津を訪問中に警備の津田に突然斬りつけられた。命に別状は無かったが、ニコライは負傷を負った。津田が切りつけた理由についてはよくわかっていない。 また明治天皇自らが神戸港のロシア軍艦を訪問し、軽傷のニコライを見舞った。」この事件のことも、本作品には、出てくるようです。そして、ちょっと今、書きながらびっくりした事があります。個人的な、「シンクロニシティ(偶然の一致)」かな、と。★まさに、書いている今、起こった、「偶然の一致」?★実は、最近、樋口一葉の日記を、訳あって、読み直したりしているのですが、今も、パソコンの隣りには、一葉の日記が開かれています。そして、この、大津事件が起きた年代を見ていて、まず、「え?」と思いました。事件が起きた年は、1891年ですが、元号でいうと、明治24年です。大津事件が「明治24年」に起きている、というのを目にして、なぜびっくりしたかというと、最近、「明治24年」というのが、自分の頭の中を占めていたからです。なぜ、「明治24年」が、頭にあったのか?それは、「樋口一葉の日記」です。今、小学館の一葉のほぼはじめの日記「若葉かげ」原文を見ながら、パソコンに向かっていたのですが、「若葉かげ」は、まさに「明治24年」4月11日から、書き始められているのです。しかも、今は、「明治24年4月22日」の日記を、見ていました。「大津事件」が起こったのは、1891年、つまり「明治24年5月11日」。「近いじゃない!!」「もしかして…」、と、一葉の日記のページを先へ繰ってみると、5月15日の記述にありました! 大津事件にまつわる記述が!以前読んでいるはずなのに、今になるまで、結びつきませんでした。あいかわらず、「鈍い」です…。原文では分かりにくいので、せっかくなので、現代語訳で載せてみます。一葉の日記・明治24年5月15日より。「昼過ぎから、約束どおりに、半井先生を平河町のお宅に訪ねる。今度のお宅はたいへんすばらしい所でした。私が着いてしばらくしてから先生がご帰宅になる。何のご用かとお尋ねすると、「いや、実は、知り合いの大阪の出版社で、今度雑誌を発行することになり、小説を書く人を世話してほしいというので、あなたを第一に推薦しておいたのです。ところが、あいにく、ロシア皇太子殿下の事件で急用が出来たといって、今朝の汽車で帰阪してしまったのです。お断りの手紙を差し上げようと思ったのですが、もう間に合わないと思ってそのままにしたのですが、この罪をお許しください」とおっしゃる。心苦しい思いでした。今日は少しお話だけして帰る。日暮れ前でした。」日記文中にある、「ロシア皇太子殿下の事件」がすなわち「大津事件」です。結局、一葉にとっては、「大津事件」が起こってしまったために、大阪の出版社の人と会うことができなかった、という事です。つまり、ニコライ2世のために、樋口一葉は、この時点で、少なからず、運命の行き先を「変更」させられた、と。もし、大津事件が起こらずに、この時点で、出版社の人と会っていたら、一葉の行く先は変わっていたのでしょうか…。いやいや。歴史に「もし」は禁句ですね。ただ、出来事というのは、波紋のように、いろんなところで影響を与えあい、人々は流れていくのだなあ、とそんな事を思いました。ニコライ2世と、樋口一葉。ふたりは、一見、何の関連もないように思いますが、「運命」の糸は、かすかではありますが、絡まって、特に一葉のほうへ影響を与えたようです。「運命」というのは、ちょとしたことで、大きく変わることもあるのでしょうし、JR福知山線で起きた列車事故にしても、あの日、あの時間、あの場所で、乗り合わせてしまったというのは、どう解釈していいのか、新聞などを読んでいると、言葉もありません。亡くなった方がたには、心よりご冥福をお祈りします。今日の新聞を読んでいると、1両目に乗っていた人で、事故が起こる直前の伊丹駅で、さまざまな偶然が重なって、急に降りて、助かった、という人の話も載っていました。「運命」とは「人生」とは「巡りあわせ」とは、何だろう、と思ってしまいます。一葉の日記のこの日、5月15日といえば、「葵祭り」のクライマックスを迎える日でもありますが、京都では、葵祭りが盛大に行われていたのでしょうか…。うちの娘の名前が「葵」なので、「葵祭り」とも、無関係には思えなくて…。(^^;一葉の日記を読むと、一葉の生きた、一葉の見た「明治」という時代が、鮮やかに描かれていて、明治という時代を、もっと知りたくなってきます。「歴史」って、こういう風に見ていっても、おもしろいな、と思います。
April 29, 2005
コメント(0)
-
『波にきらめく月の幻』
たゆたう波のように ゆらゆらと想いは いつまでも途切れることなくあなたのいる岸辺へと 打ち寄せる波間に忍び込むような あなたのため息さえすぐ側で しっかりと感じていたい音もなく流れる雲は 揺れ動く心模様消えそうになりながらも どこかを求めて さまよっているくっきりと浮かぶ満月は あなたへの揺るがぬ想いまたたく星は 嬉しさと寂しさが融けあって 震えている波は空の宇宙を映し出す たゆたう鏡波間はきらきらと輝く白い星昏い波に揺らめく月の姿は かき消されそうなほど 頼りなく涙をこらえきれずに歪んでいく 泣き顔のようすべては とどまることなく流れていく心のありかは定まらず すくってもすくっても 零れ落ちる水のようそれでも波の旋律が とめどなく 湧き出てくるように波に揺らめく月の幻が かき消されてしまわないように小さな心は はぐれることなく どこかにつなぎとめられている果てしのない海の果てを 見つめよう限りのない空の果てを 振り仰ごう天空に浮かぶ 揺らぎのない月を見つめようそして波間に漂う 月の幻と もう一度向き合ってみれば揺らめく月はあふれんばかりの輝きで闇世のなか 喜びに満ちた踊りを 繰り広げていた君の泣き顔は 少し角度を変えれば 微笑みたいに 変化していたたぶん物事は ずっと単純で ほんの少しの見方で 変わる永遠にとどまることのない 流れの中に 僕たちはいる月の幻は ゆらめき いくつもの生命の旋律を奏でていた
April 28, 2005
コメント(1)
-
『流されて』
母親の胎内に 魂が宿った瞬間羊水に浮かぶ肉体に 記憶が生まれるこの世界で生きたいと思って 自分で選択した道戻る事のできない 流れに 身を投じたら流れの中に潜り込んで 後はただ身を任せるばかり逆流するように 記憶の糸を 丁寧に手繰っていくといくつもの宇宙を旅している 大いなる流れの中いつかは あの場所へと進みながらも同時に 戻っていくのだろう流れに 流されながら…よどみなく流れる流れに 光が射し込んで流れのあちこちで きらきら輝く 水の粒子はこの世界に生きている人たちの 今・今・今みんな何かを夢見て 何かを求めて今を輝きたいと 流れている時に速く 時にゆったりと それぞれの流れに 合わせながら…かたくなに 自分を高みに引き上げようと無理をしても川の流れは 容易に変わらないこの流れの中から 誰も逃れることができない 宿命の流れ水の中 岩が流れを遮って 水しぶきをあげるのは苦しみながらも 越えていこうとする 強い意志の現れ雨が絶え間なく降り続き 水が増幅し やがて あふれ出す川の意思が 宿命を変えようとするかのように 暴走を始めるそれでも 時の流れには 逆らえないようにやがては 安定した元の流れに 戻っていくひとつひとつの出来事は 何の脈絡もないような 気がするけれども心にあふれてくる想いを 遮ることなく 流してやれば途切れることのない 一本の光の糸が 漂っているのが分かるだろう僕たちは数限りない 水の粒子の ひとしずく ひとしずく果てしない流れの中を 流されていくそしていつかは 大海原へ たどりつくだろうとどまることをしらない流れのなかにいつもいる…※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※【散文詩『流されて』について】この散文は、わりあいすっと「流れ」のままに書けた記憶があります。物事には、あるいは、その人の人生は、ある程度「流れ」というものが存在するように思います。そして、その「流れ」に身を任すことが、案外重要なのではないかと。別に楽な生き方というわけではなく、そのほうが、人間の可能性を、一段と高めるように思います。自分の頑張りだけでは、限界がある。むしろ、頑張り、力が入りすぎると、逆に思うようにいかないことも多い。すべてはつながっているのだとしたら、自分を一歩外から見るような感覚で、物事を見て、そこに、見えない繋がり(シンクロニシティ)を感じた時、自分だけでない周りの「流れ」に乗ってみる。そうすると、案外するするっ…とうまくいくことが多いのも事実。力を抜く事は、手抜きのことではなく、余分な力を抜くという感じ。余分な力は必要ない、というのは、案外すべての事に通じることではないか、とも思います。そのほうが、すっと的をついた場所へと到達する事ができるのではないでしょうか。この世界は、一見ばらばらな様でいて、実に巧妙に天の糸(意図)が張り巡らされているように感じる事もあります。偶然と必然が表裏一体であるのと同じように、どちらの見方も、間違いではないのかもしれません。ただ、私は、断然、天の糸や、必然を感じる生き方がしたいなと思いました。
April 27, 2005
コメント(0)
-
『春の日は過ぎゆく』
もの憂いほどの あたたかい日ざし新芽がでて 緑が少しずつ 景色の編み目に 縫いこまれていく色とりどりの花が咲き あちこちで 光の霊(たま)が乱舞する「時」が寄り道をするように 緩やかに流れていく この季節春の日は 穏やかに過ぎていく …けれど 耳をすませば草木と花と風と空と雲と光の奏でる共鳴音が波紋が広がるように そこかしこから 静かに …でも激しいほどに 生命あふれた音色が 響き合う絶え間ない変化が 見えないところで せめぎあっているあなたとの出会いは 春の日の 穏やかな一日のように気がついたら ふたり 一緒にいた太陽に向かって 植物が生育していくように日々 大いなる源へと向かって 歩んでいくあたたかい春の日が 永遠に 続くものと思っていたけれども この世界は 光と闇から成り立つように陰陽のバランスが ほんの少し 崩れていくだけでいつの間にか 小さな軋みを 無数に生み出していたそのことに気づかず あなたへの想いを 愚直に抱き続けた季節が移りゆくように あなたは違う季節を 見つめ始めたというのになぜ季節は… 想いは… 移り変わっていくのだろうその大いなるうねりを 止めることなど 何ひとつできなかった春の日は過ぎゆく… 穏やかに 緩やかに今はただ 金色の草原の真ん中で 無数のささやきに 耳を傾ける風と光と金色のうねりが ひとつになりすべての音が 「無」の狭間に 吸い込まれた時かすかに… いや はっきりと明日へと導かれてゆく 確かな音色が 心に響き渡った※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※【散文詩『春の日は過ぎゆく』について】この散文詩は、タイトルをそのまま拝借した映画『春の日は過ぎゆく』を、イメージしました。春の日の物憂いほどのあたたかさ。春の日ざしを浴びて、いつまでも草むらの上に寝転んでいたいほどの開放感。ともすると、「永遠」に続くのではないかと錯覚しそうになる、この季節の時のゆったり感。けれども、移り変わらないものなどない、という現実。その自然の「流れ」を、止められないというやるせなさ。映画では、春=青春の「恋」の初々しさと重ね合わせて、表現されています。そして季節が移り変わっていくように、ふたりの間に流れる感情も、同じままではなく、変化していく様が、淡々と、しかしせつなく、描かれていきます。
April 26, 2005
コメント(1)
-

ようやく一人でお座りできる葵(あおい)
上の写真は、きのうの日曜日、自宅にて。透萌(ともえ)と葵(あおい)もうすぐ9ヶ月の葵は、ちょこん、と座ることができるようになりました。ぐらぐらしているものの、安定感が出てきました。こっちをみて、笑うくらいの余裕は出てきたようです。きのうは、昼から、時々行く公園へ行きました。公園でも、ちょこん、と座ってます。土をいじったり草をさわったり、とにかく何か、さわりたがります。上の写真は、お花をいじっています。すぐに、口に持っていきたがります。今度は帽子をかぶせました。まだ、はげはげちゃん(透萌が葵のことを時々、こう言う)なので、隠すのにもちょうどいいし(?)、かぶると、より「まるさ」が強調されます。わが子ながら、見ているだけで、笑えてきます。(^^;こういう時期、って当たり前だけど、今しかないし、子どもと過ごす時間というのも、普段、あまりとれないだけに、大切にしたい、とふと思ったりしました。
April 25, 2005
コメント(0)
-

魅力的な韓国の女優たち
★止まらない! 女優「ソン・イェジン」への傾倒★前にも書きましたが。妻が借りて観ていた『夏の香り』というドラマ。そこに出ていた女優ソン・イェジェンが、気になっていました。しばらくして、タイトルに惹かれ『永遠の片想い』という映画を借りてきます。女優ソンイェジェンが出ていました!まずい…。また気になる女優が出てきてしまった…。続いて、彼女出演の『ラブストーリー』を、4月22日と23日にかけて、観る。いいです! ソン・イェジン。もうこの流れは、止められない。参りました。『ラブストーリー』のサントラCDを妻がすでに借りてくれていたので、観終ってから、繰り返し、聴く。朝起きてからも、やっぱり、繰り返し、聴く。しかも、途中からは、メインテーマの音楽を繰り返しリピートして、しつこくかけるものだから、妻は、「いつまでこの曲、聴いてるの?」と呆れられる。と、これを書いている今も、やっぱりBGMは『ラブストーリー』うーん、我ながら、かなり、しつこい性格だ。日本では、こういう「純愛」もの、ここまでストレートには、できないかもしれないです。まあ、ともかく、韓国映画やドラマに、というか韓国の女優に(?)、はまっていきそうです。と、いうか、もうすでに、はまってます。やばいです。(^^;個人的には、だいぶ前に見た『イルマーレ』と『リメンバー・ミー』が、韓国映画のベストと思っていたのですが、『永遠の片想い』『ラブストーリー』なども、そこに食い込む作品となりました。★まだまだいる、魅力的な韓国女優★韓国映画は、女優さんが、かわいらしくてきれいな人が多いです。魅力的な女優さんが多くて、困りますね…。先の「ソン・イェジン」はじめ、『イルマーレ』の「チョン・ジヒョン」、『リメンバー・ミー』の「キム・ハヌル」と「ハ・ジウォン」。それと、『春の日は過ぎゆく』の「イ・ヨンエ」今日は、その「ハ・ジウォン」の『真実ゲーム』という映画を借りて見ましたが、彼女の小悪魔的な魅力が全開の作品で、なかなか楽しめました。『真実ゲーム』ハ・ジウォン「キム・ハヌル」…『リメンバー・ミー』で初々しい役を。「ハ・ジウォン」もこの作品で好演。注目の2人の女優が出演。贅沢な作品です。「イ・ヨンエ」『春の日は過ぎゆく』『ラスト・プレゼント』など好演。
April 25, 2005
コメント(2)
-
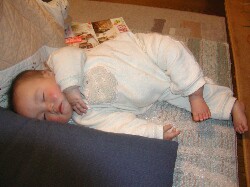
どこでもコロリと寝る葵(あおい)
もうすぐ9ヶ月の葵(あおい)は、はいはいして、よく動くようになり、また、あうあう、とよくしゃべる(?)ようになりました。葵は、目的物があると、はいはいというか、くねくねして移動して、行動範囲も広くなりましたが、あれ、何か静かだなあ…と思って、ふと見ると、横向いたまま「コロリ」という感じで、寝入っている事が多い。今日も、朝と夕方、2回、横になったまま寝入ってしまったので、そこでデジカメを撮ってみました。手と足が、変に曲がっていて、おもしろい。かなり器用な寝方してます。
April 24, 2005
コメント(0)
-

『春の日は過ぎゆく』(2001年・香港=韓国=日本)
「竹の音が一番いいのはどんな時?」「風や吹雪の日がいいね。サーッとかスーッという音が聞こえると、沈んだ気分が軽くなるんだよ。」★『八月のクリスマス』ホ・ジノ監督の第2作★監督のホ・ジノは、静謐な感動を与えてくれた『八月のクリスマス』を撮った人。死を目前にした青年と、無邪気な女子大生の淡い恋を描いた、味わいのある作品でしたが、本作でも、その静かな流れは継承され、じわじわと心に染み込んでくる作品に仕上がりました。★物語の概要★録音技師の青年サンウ(ユ・ジテ)と、ラジオ局のDJ兼プロデューサーのウンス(イ・ヨンエ)は、自然の音を録音し、ともに番組制作をする事になります。ふたりは一緒に仕事をするうちに、徐々に近づき、ごく自然に付き合うようになりますが、季節が移りゆくように、「愛」も変化していくのですが…。★春の物憂さを見事に表現した音楽★この映画を、再鑑賞するために、ビデオを借りた時、示し合わせたわけでもないのに、妻は『春は過ぎゆく』のサントラCDを借りてきていました。ちょっとした、偶然の一致に驚くとともに、映画を観る前に、この映画の音楽をじっくりと聞けたことは、よりこの映画を、深く味わう事ができて、良かったと思っています。そういう、今、まさに、このCDをかけながら書いています。実は、ちょっと前まで『ラブストーリー』を見ていて、その余韻をいまだ引きずっているのですが、「ソン・イェジン」いいですねえ。(名前が難しくて、毎回、あれ、何ていうんだっけ?と見ては書いてます。)(^^;あのラストにはやられました…と、今回は『ラブストーリー』では、なくて、ですね!『春は過ぎゆく』でした。えっと。ごめんなさい。話を戻します。『春は過ぎゆく』の音楽は、メインテーマの音楽が、すばらしいの一言。春の物憂い感じ、春の穏やかなひととき、春のゆったりと過ぎゆく時の「流れ」を感じることができて、それでいて、春が過ぎ去っていく「寂しさ」「せつなさ」をもが、合わせて表現されています。この音楽が、映画のテーマを象徴しているといってもよく、すばらしいと感じました。映画の情景が、せつなさとともに甦ってきて、改めて音楽の力を見せつけられました。★春は過ぎゆく、穏やかに、緩やかに★この映画のテーマは、一言でいえば、すべてのものは移り変わっていくということ。それは、見えない「愛」や「想い」といったものも、変容していってしまう、と言う、ある意味当たり前の現実が、実に淡々と描かれています。そして、その「流れ」を止めることができない「どうしようもないやるせなさ、せつなさ」といったものが、切々と伝わってきます。映画は、映像、台詞、ともに、非常に淡々としています。でも、非常に淡々としているだけに、逆に日常の何気ない一コマ一こまが大切な瞬間の連続である、という事を突きつけられて、同時にこの映画も、じわじわと余韻が心に広がっていく感じがします。そう、まさに春は穏やかに緩やかに、過ぎゆくけれども、この流れ、大いなるうねりは、だれにも止めることができない…。★「ユ・ジテ」と「イ・ヨンエ」★この映画にあって、忘れてはいけないのが、主演のふたりの存在でしょう。「ユ・ジテ」は『リメンバー・ミー』でも好演してた俳優ですが、本作では、一途な愛を貫こうとする、純朴で、ひたむきな青年役を「痛い」くらいに好演。一方の「イ・ヨンエ」は、離婚暦のある、年上の女性役を演じますが、彼を好きでありながら、愛に夢中になるのをどこかで、恐れている節が見受けられ、彼のことを真正面から受け入れられないもどかしさが、感じれられます。彼女の心の移り変わりは、春の穏やかさに似て、本当に微妙な感情の波の変化で、「ユ・ジテ」演じる青年には、つかみきれません。だから翻弄されます。私も見ながらにして、はじめは、彼女の心が、全く理解できず、自分勝手なものにしか思えなかったのですが、今は、うまくは言えませんが、彼女の気持ちが、何十分の一かでも理解できるかな、と思うようになりました。ただ、女心は、永遠の謎である、という事を、改めて思いました。まあ、イ・ヨンエの、透明感ある美しさと、時折見せるかわいらしさは、本作品でなかなかの存在感を出していますので、私としては、それで満足なのですが…。(^^;決して、明るい話ではないけれども、春=「青春」の初々しい喜びと、せつなさ、移りゆく愛の不確かさ、といったものがすべて詰まった、秀作であり、見るほどに味わいが深くなる作品です。竹の音や、水の音、森林の音、この映画では自然の「音」が、とても効果的に使われていて、自然の音が、ラストの場面へと収斂していく様は、春が移りゆくなかで見せた、「きらめく一筋の光」を思わせ、見事なラストを演出してくれました。
April 23, 2005
コメント(1)
-
『新緑の彩りのなかで』
鮮やかに浮かび上がる 緑の波木漏れ日は 天使が奏でる音色のように そこかしこで踊っている木々の間から 透かし見た空はきらめく光と 鮮やかな新緑と 澄んだ空が混じりあいすべてに調和した空間を 映し出していたたとえ再び この季節が巡ってこようとも今と全く同じ景色を見ることは もう永遠にないだからこそ君は かけがえのない宝物をこの僕に 与えてくれたそれなのに 僕が 君に残せるものは 何もなく与えられるものも 何ひとつない…それまでの僕は 何かが映っていても 何も感じることなく 見過ごしてしまい大切なものを ひとつ ふたつと 見失ってばかりいたふと遠くを見据えると 少し前まで くすんでいた山の色が一気に存在感の浮き立つ 新緑の世界へと 変化する不思議を見た君は何を問いかけてくれているの?今すぐにでも変わっていくことができるということ?五月の爽やかな風を受けた君の姿はなぜこんなにもまぶしく映るの?このまま君が変わることなく ここにいてくれたなら…それでも木々の鮮やかな緑は 永遠に続きはしないわかっている…それはわかっているから…だからこそ君といる 大いなる流れの中の ほんの一時を大切にしたい喜びとも 哀しみともつかぬ気持ちを 抱きながら季節は 木々は 緑は…君は… すべてが 移り変わっていく淡い緑から 深みのある緑へ… さらに色とりどりの 緑の輝きへいつか再び巡り会う日まで 君は君にしかない緑を大切にして僕は 僕の緑を自分らしく変化させ 一歩一歩進んでいくから君と僕の緑が再び重なる時 鮮やかな「新緑」へと 変わってくれるだろうか君と綴っていく 一日一日は さまざまな彩りに満ちているどの色も欠けてはならない大切な色ばかり忘れない…忘れないから…この瞬間の景色の鮮やかさを…この新緑の彩りを…君と過ごす日々を一葉一葉が 柔らかく風にそよぐように 心に積み重ねていく※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※【散文詩『新緑の彩りの中で』】少し前から、山の緑が、新緑の鮮やかな緑に移り変わってきつつあり、景色が一段と明るくなっていくような、そんな感じを受けます。この鮮やかな緑が永遠に続いてほしい、と思うのですが、季節は日々少しずつ変化していき、その流れを止めることはできない、だからこそ、この瞬間の季節の移りゆく姿を目に焼き付けておきたいと思うし、大切にしていきたい、そういう思い、感動が、「新緑」を見て、湧き上がってきました。緑の間からつつじの紫が、時々見えて、それがまたきれいでした。
April 22, 2005
コメント(4)
-

女優「ソン・イェジン」への永遠の片想い
最近は、妻が、韓国映画やドラマを、借りることが多いです。週一回、ビデオを借りにいくのですが、最近は、『夏の香り』というドラマを借りてきています。何でも、『冬のソナタ』の監督ということです。『冬のソナタ』は、私も妻も、時流に乗り遅れて、いまだ観ていないのですが、うちの父親が、観て、けっこうはまってました。『冬のソナタ』のCDを早速買ってきていました。(^^;『夏の香り』というドラマ、私は仕事などで、見る時間がなく、家に帰ってきて、少し見るという感じでしたが、そこに出ている女優が、清楚な感じで、すっきりとした顔立ちで、ちょっと惹かれるものがありました。少し前に、妻が『ラブストーリー』という韓国映画を借りてきてましたが、これも、私は見損なったのですが、この映画にも、この女優さんは出ていたとか。そんなところ、私は、『永遠の片想い』という映画を、タイトルに惹かれて借りたところ、その注目していた女優「ソン・イェジン」も出演していて、この映画を観て、ますます彼女に惹かれてしまいました。最近韓国映画は、類型的な作品が多くて、正直なところ、食傷気味だったのですが、『永遠の片想い』については、個人的に久々のヒット作となりました。「純愛」ものが、韓国は好きだなあ、と思いつつも、大好きな作品になりました。「ソン・イェジン」が見れた、というのもあるかもしれませんが…。彼女は、一見どこにでもいそうな女の子でもあるのですが、よくよく見ると、そうめったにはいない女の子である事が、分かります。(うーん、我ながらよく分からん…)まあ、それ程、かわいらしいということです。はい。と、いうことで、今週は、『ラブストーリー』を、「ちゃんと」借りてきました。見るのが楽しみです。この女優に、はまっていきそうな予感です(^^;
April 21, 2005
コメント(2)
-
『風と緑と赤紫色の輪舞』
一面の緑に浮かびあがる 赤紫色の柔らかな更紗風と戯れて生じる ゆるやかなうねり春の陽射しに映えるれんげはそこだけ「異空間」へと 入り込んだように鮮やかな幻想の色を 浮かび上がらせるそして大地から 春のぬくもりが空へ向かって 解き放たれるれんげの輪舞が 繰り広げられる このひと時赤紫色の花は やがて朽ちて 土に還り稲穂の成長を しっかりと 支えてくれるだろう華やかな舞台の裏には 地道でたゆみない営みが息づくあんなに色鮮やかに 咲いているのは土の中の無数の命が 喜びで 満ちあふれているからぼやけていた景色が くっきりと 彩られる消えていく迷い 進むべき道標 定まった行方あなたと 真っすぐに向き合う勇気心の中に湧いてくる 光の渦と芯の強さ何を求めて 何を目指して 生きていくとしてもひとつひとつの 小さなれんげの花のようにいつか それぞれの夢が 美しく染まっていく透き通る光を浴びて 花のひとつひとつが微妙に違う それぞれにぴったりの色を ふりまいているそう… ありのままの自分を 飾ることなく 表現していけばいいふと 肩の力が 抜けた気がした…何が起きても 今この足元を見つめていようれんげが花開き 朽ちて 命を繋いでいくように物事は 進化の方向へ進んでいる赤紫色のうねりは 大きく広がって 光と風と雲にまみえて この空を 優しく 染めあげていく ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※【散文詩 『風と緑と赤紫色の輪舞』 について】今日、仕事の配達中、今年初めて、れんげの花が咲いているのを目にしました。というわけで、「れんげ」だったら、タイミングよいのですが。ただ、実際は、最近は時間が取れなくて、やむなく、ヤプログに掲載した散文を、こっちに載せているというのが現状です。いろいろ書きたいな、とは思うのですが。えっと、話を散文について、に戻します。れんげの花が、田んぼに一面咲いている様は、本当に幻想的できれいです。その感動を言葉にしてみたい、と思ったのと、もうひとつ、れんげは、稲がしっかりと育つように、土壌を良い環境にしてくれる、といったようなことを聞いたときに、これまた感動したのがあって、イメージが浮かんできました。華やかに見えるけれども、土という環境がしっかりとしていてこその、れんげであり、稲である、ということを思ったときに、舞台の華やかさよりも、それを支えてくれている見えない力がいかに大切であるか、それを組み込みたいと思いました。それは植物でも人間でも同じことであると感じました。そして今、自分のいる場所の大切さ、ありがたさ、みたいなものに改めて気がつかなくてはいけないな、とも思いますし、「ここ」をおろそかにして、何事もはじめることはできない、といったようなことを「れんげ」に託してみました。
April 20, 2005
コメント(0)
-
『雨上がりのきらめき』
無数の雨粒が 地面の鍵盤を 重々しく奏でるとひとときの間 景色は色をなくして 透明な滴の膜に包まれる天の奏でる厳かな調べが 大詰めにくると空の彼方には 慈愛に満ちた光が 微かに灯って少しずつ 空いっぱいに広がっていく暗闇に射しこむ 光への反転ゆらゆらと立ち上る 水の精霊葉や茎を伝う 滴の流れまるで天使が 無数の滴と光をつれて 舞い降りてきたみたい光を透かした滴が 地面の鍵盤を 軽やかに奏でると地に降り注ぐ光が 名残の水に微笑んでそこかしこで きらきらと輝き始めるさまざまな緑が 生き生きと濡れそぼる無数の滴と 光と 緑の交じり合いが景色をより鮮やかに くっきりと 浮かび上がらせる昨日と同じ場所に立って見つめてみてもそこに広がる景色は 全く違うみたい恋を知った少女のように 日常の一コマ一コマが 艶やかに輝いている日の光を凝縮した滴は ありふれた景色を 瑞々しく包み込み天に向かって 力強く昇華していくそして光という見えない波が 揺れ動き数々の音色が この緑の中を 駆け抜けていく零れ落ちそうな滴が 光を浴びて ふるふると 震えたあなたが久しぶりに見せてくれた少し恥ずかしげな…でも精一杯の笑顔のように…いつも この雨上がりのような心を 持ち続けていたい雨上がりのきらめきは 光と滴が織りなす 一瞬の魔法踊るような無数の旋律が そこかしこで あふれている ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※【散文詩 『雨上がりのきらめき』について】この散文詩は、よくあるモチーフでもあるのですが、雨上がりの後に、景色を見ると本当にくっきりとしていて、今までと違って見えることがあって、そのちょっとした感動を言葉にしてみようというのが、きっかけだったと思います。また、雨上がりのくっきりとした景色のように、いつも新鮮な気持ちで、生きていけたらなあ、という想いもありました。そういったことを込めたつもりです。そして、無数の雨粒が、地面という鍵盤をたたいて、雨上がりの軽やかなメロディが聞こえてくる、そんな気がして、それを言葉にしたのが、この散文の「核」となったと思いますし、はじめと終わりにもってきて、少しは、まとまり感が出たのではないかと思います。雨上がりの後の、晴れ間というのは、それまでの灰色の天を見ているだけに、感動がより大きいのかもしれないですね。
April 19, 2005
コメント(5)
-
『雪に舞うひとひらの葉』
そのひとひらの葉は 確かにあの人のもとへ 舞い落ちたやさしく映える陽だまり 静かにたたずむ大地 頬に触れる風目にする中心に いつも 穏やかに根づく一本の桃の木触れるもの 目に映るもの すべてがいとおしく 心に響くあの人の面影を 初めて目にして 灯った想いはふつふつと膨れ上がり とめどなくあふれてくるうれしくて哀しくてやるせない想いが 雪のように空を舞うあの人のもとで ひとひらの葉は激しくなすすべもなく 渦まいていたそれでも この景色が永遠に続くものと思っていたけれど 一陣の冷たい風が 突然吹きつけて頼りないひとひらの葉は ふわり…と浮き あっけなく飛ばされたあたたかいぬくもりを 抱きしめるまもなく恋の喜びに ひたる余裕さえなくこのかけがえのない 永遠の瞬間を 手放すしかなかった…けれど…だからこそ 今になって思う花は散っても 実をつけ 新たな命が芽生えてくるように内に眠っていた未知の力を「別れ」が解き放ってくれたあの人と向き合った日々は忘れない…忘れられない…あの日 しんしんと降り積もる雪の音に 耳を傾けながらすぐ向こうにいる あの人のことを ただひたすら 想ってたあの日のことを 雪に閉じ込めて 永遠に二人だけの思い出にするあてどなく落ちる雪片は 恋の暑さと冷たさを抱えながら心に積もり 涙の結晶となって はかなく消えて流れゆくそして春になれば 朝露となって光に透けて桃の葉に浮かび上がるあの時散った桃の花びらは いまもこの胸で 鮮やかな匂いを放ついつの日もすぐ側で 桃の花びらに触れていたかった…今なら言える…あの日どこに生まれ どこで生きていたとしてもこの「一」ひらの「葉」は そう… まぎれもなくあの「桃」の木のもとへ 流れる「水」の如く運ばれ巡り会う運命だったのだと※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※【散文詩『雪に舞うひとひらの葉』について】この散文は、光透波の泉【アナログ版】2004年12月下旬号に掲載しましたが、【デジタル版】に掲載するにあたり、少し改訂しました。内容は変えずに、文章を訂正しました。この散文は、今はまっている「樋口一葉」と、一葉が生涯想い続けた「半井桃水(なからいとうすい)」を思い浮かべながら、書きました。それも、一葉の日記に書かれている明治25年2月4日の「雪の日」のことをイメージしました。一葉の日記のなかに、「桃」の花に託して桃水のことを詠んだものがあります。それで、同じように、「桃」を桃水、ひとひらの「葉」を一葉に託してみました。風になすすべなく翻弄される「葉」。それに対して、大地に根付いて悠然といつも優しげな「桃」の木。一葉は、桃水を知って、恋をしましたが、桃水と別れることで、才能を開花させます。それは皮肉な出来事でもありますが、それが一葉にとって必要なことであったという意味では、やむをえないのかもしれません。
April 18, 2005
コメント(0)
-
『饗ふ日(あふひ) ~誕生~』
人体の小宇宙に 光を生みだす 遥か以前からあなたは 宇宙を漂う光の記憶となってこの世界の情景を 彼方から見ていた流れ流されて 巡り巡った果てに 居場所を見つけた小さな小さな あなたの想いはどんな未来を この暗闇の天幕に 灯すのだろうか1本の木に咲く 花々のように この瞬間を ともに生きることは本当に ありえないほどの偶然が生んだ 魔法のようこのまばたきの時を 分かち合うために あなたはここに来たあなたは言う…そんなことは 偶然でも奇跡でもない とただ自分が 必然の道程を たどってきただけだとそれでもあなたが来てくれたことに 大いなる感謝と喜びを感じおそらく過去に 何度か絡まりあってきた 不可思議な縁を 想うあなたの描く未来と あなたの決めた試練すべては滞ることなく 流れていくものだとしても淀みはあちこちで幾度も生じているけれど…水がうずまくように終わりがあってまたはじまる 巴紋のようにすべては循環している…だから「信じる心」を持ち続けてほしい「透き」通った水の粒子に 光が触れた時天空に幻想的に 「萌え」いづる虹古代の人は そこに大地と天空を繋ぐ「蛇」を見た触れることができなくても確かに 存在するものがあるようにあなたはあなた自身の未来を すでに心に持っている人の手では 造ることができない 空の橋ここを通って 人は生まれてくるのかもしれない…風が吹く 水面がざわめき 渦を巻く 生まれた「巴」日を仰ぐように 月に触れるように 日月を求めて 背伸びする「葵」天と人の距離が 近づくようにと祈った 「饗ふ日(あふひ)」 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※【散文詩『饗ふ日 ~誕生~』について】この散文詩は、もともと、上の娘の透萌(ともえ)が生まれる前後に『誕生』という題名で、書いていたもの。ですから、かなり前に書いたものなのですが、2004年7月31日に「葵」が生まれたので、手書き通信「光透波の泉」【アナログ版】は、その生まれたことなどを中心に書きました。せっかくだからということで、冒頭の散文詩も、それにまつわる詩がいいんじゃないかな、と思い、この『誕生』を引っ張り出してきました。しかし、前半こそ原形をとどめているものの、後半は、大幅に変更、というかまったく別物に書き換えた、というほうが正しいかもしれません。はっきりいって、いろいろなことを詰め込みすぎて、最後は訳がわからないようになってしまったというのが、本当のところです。自分の悪い点は、複雑にというか こねくりまわして、ややこしくしてしまうところ。もっとシンプルなのを書きたいな、といつも思っているのですが。話がそれました。今回の詩は、後半部分、何を込めたのか、ということだけ触れておきます。まず題名を『饗ふ日』としたのは、娘の名前「葵」と重ねました。「饗ふ日」という言葉の意味は、「神を饗応する日、もてなす日」という意味があります。そして「葵(あおい)」の言葉の語源は、ひとつは、「饗ふ日(あふひ)」からきているという説があるそうです。これを知ったときは、少し感動して、今回の散文を【アナログ版】に載せるにあたって、組み込みたいと思いました。もうひとつの説として「仰日(あおひ)」から来ているというのもあるそうです。「葵」という花が日を仰ぐように咲くことからだと思うのですが、「日を仰ぐ」という言葉を入れました。そして、上の娘の「透萌(ともえ)」の名も、入れたいと思い、『「透き」通った、「萌え」いづる』という部分に組み込み、さらに、「ともえ」から「巴」も重ね合わせて表現しました。「巴」といえば、家紋である「巴紋」が有名ですが、これは、渦を巻く水の流れをあらわしたり、円の中に巴がふたつ描かれた「二つ巴」は、「陰陽」を表していて、「太極図」なども、同じ構造です。「終わりであり、始まりを表している」と。 そこから「永遠の循環」「水の流れの循環」を意識しました。そして、「巴」は、もともと「巳(み)」という漢字から来ている、つまり「蛇」をも表していることにもなり、確かに「蛇」のとぐろを巻く姿、というのは「巴紋」を象徴しているようでもあります。そして、天空の「虹」も、古代の人は天と地を繋ぐ「蛇」に見立てたといいます。実際「虹」という漢字は「蛇」と同じ「虫偏」です。そして、上の娘「透萌(ともえ)」と生まれた「葵」の名を組み込んだのだから、ついでにお遊び的に妻の名前も組み込んでしまえ、と思い入れたのが、「日」と「月」とを合わせた漢字というわけです。それを「日月を求めて」という部分に込めました。名前は想像がつくと思いますが。あと、「葵」の花言葉は、「信じる心」だということで、これも絶対に、入れたかったので、入れました。はっきり言って、欲張りすぎて、結局最後のほうは、何が言いたいかわからない詩になってしまった感があります。さまざまな想いを込めた、という意味では、思い入れのある散文かな、と思っています。他の人が読んでも分からないマニアックな部分がたぶんにあるのですが…。
April 17, 2005
コメント(0)
-

『小さな泥棒』(1989年・フランス)
「空では誰も働かない。」「そう? お星さまは?」「いや、働かない。輝いているだけ。君のように…。」★シャルロット・ゲンズブールの最高傑作は、コレ!★ソフィー・マルソーに続いての、フランス女優。シャルロット・ゲンズブールという女優もまた、この『小さな泥棒』を見た途端、運命的なものを感じ、強烈に惹かれました。この作品の何に惹かれたのか、と言われれば、シャルロット・ゲンズブールに尽きるのではないか、と思います。そして、現時点で、というか、おそらく永遠に、彼女の最高傑作は、誰が何と言おうと、この作品であるという気がします。それ程、自分にとってはインパクトのある作品でした。シャルロット・ゲンズブールは、父は音楽家であり、映画監督のセルジュ・ゲンズブールで、母は女優のジェーン・バーキンの間に生まれました。生まれた時から、女優になる素質と才能に恵まれていたといえるのでしょう。★物語の概要★16歳の少女ジャニーヌ(シャルロット・ゲンズブール)は、伯父夫婦のもとで暮らしています。母親は彼女を見捨てて、行方不明。彼女は、学校の帰り道、映画館にもぐりこんだり、町へ出て、服や下着を盗むクセがあり、小さな盗みを繰り返します。ある日、洋品店の主人に盗みがバレてしまい、彼女は、家を出る決意をすのですが…。★不思議な魅力をたたえたシャルロット・ゲンズブール★本作品では、シャルロット・ゲンズブールが、等身大の女の子を、実に見事に演じます。思春期特有の、あの不安定な、やりどころのない苛立ちや、恋愛に対する憧れ、早く大人になりたい、といった内面心理が、「痛い」くらいリアルに描かれます。彼女は、中性的な不思議な魅力をもっています。美人というよりも、どこか哀しみを帯びた瞳、とがったあごや、薄くて少し突き出た唇など、個性的な顔立ちをしています。また、体をやや斜め前にして歩く姿や、ささやくような声、ふてくされているような表情、そして時折見せる笑顔が実にいいんです!そう、この笑顔に、やられてしまいました。(^^;★シャルロット・ゲンズブールの「青春」のすべて★「音楽は絵画や詩と同じようなものだと思う。この世のものはすべてはかなく消えてゆく。そのはかなさを音楽はつかまえる。過ぎ去っていく時間を永久にとどめる。」「思い出みたいに?」「そう、その通りだよ。」この、最初の恋人との、会話が、同時に、シャルロット・ゲンズブールの「青春の断片」をも象徴していて、印象に残ります。少女から大人へと移り変わる、光と影の入り混じった、ほんの一瞬の時の狭間を、映像で、美しくも鋭く切り取った青春映画の傑作であり、シャルロット・ゲンズブールのかわいらしさと危うさをすべて封じ込めた奇跡的作品。えっと、何だかシャルロット・ゲンズブールのことしか書いてないような気がしますが、まあ、気のせいと言うことにしておきましょう。(^^;シャルロット・ゲンズブールこの笑顔がいい!
April 16, 2005
コメント(0)
-
『絵の具』
僕はこれから 自分の画用紙に何色の絵の具で どんな絵を 描いていくことが できるのだろう見えない階段を 一段 一段 登っていって抱えきれないほど広がる 空の画用紙に 触れられる距離まで近づいてたくさんの絵の具の色を 散りばめて 果てしのない夢を 描いてみたい空一面に広がる 青色は誰があんなにきれいに そして 微妙な色合いで 塗りつぶしていったのだろう青色だけで 数え切れないほど多くの種類が 使われている僕もそんなふうに 多くの色を使って 想いを 表していきたい冬の空は 澄み渡って いつもより果てが 遠くにいったみたい透徹した厳しさに 体が包まれていくなか陽だまりのぬくもりが 心をふわっ…と 柔らかく 溶かしてくれる見上げた空には 誰かが 白い雲をさあっ…と 描いていく吹き込まれた命は ほんの微かな変化を 繰り返しながら風と手をつないで 画用紙の上を 流れ始める何かにつまづいて 目の前に壁が立ち塞がった時今まで身につけた色では 何もできなかった…けれどもそれらの色を パレットに広げて 混ぜ合わせてみるとまだ知らない色が 生まれてくる未知(みち)の色を使っていけば 新たな道(みち)が開けるような気がした人と人との出会いを重ねるたびに ひとつ ひとつ 色が増えていく君と出会った瞬間 心に響く色を 君の中に見つけたそれは 心の中のくすんだ色を 一気に打ち消してまだ見たことのない色を あたたかく そして 懐かしく広げてくれた君は僕の中に 新しい色を 優しく染め上げてくれた僕は君の中に 勇気の色を 力強く染め上げてみせる僕と君の絵の具が 混じり合ってこれからどんな色を 空の画用紙に 塗りこんでいけるのだろういつか見つけたいと思った… ふたりの「永遠の色」を
April 15, 2005
コメント(3)
-
『ファイアーライト』(1999年・イギリス=フランス)
「どこにいようと あなたを忘れない。片時も 忘れない…。」★ソフィー・マルソーの美貌と抑えた演技の妙★『恋人たちのアパルトマン』で、その魅力に取り付かれてしまった「ソフィー・マルソー」。『恋人たちの~』では、自分の感情を、体全体で、あふれんばかりに解き放って表現。自由奔放な役柄が、実に魅力的でした。しかし、本作品では、それとは対照的に、感情を内に秘めた「静」の演技で、見るものを魅了してくれます。表面上は「静」の演技ですが、抑えた表情から滲み出てくる感情の渦、娘への万感の想い、などが、強く伝わってきて、改めて彼女の演技の確かさに、すばらしいと思いました。★物語の概要★時代は1837年イギリス。22歳のエリザベス(ソフィー・マルソー)は、父の負債を救うために、イギリス人貴族チャールズからの、ある申し出を引き受けます。チャールズの妻は植物人間になってしまい、後継ぎのほしかった彼は、子どもを生んでくれる女性を探していました。チャールズと、契約の三夜だけ関係を持ち、やがて身ごもったエリザベスは、女の子を出産します。しかし、「あなたの仕事は終わりよ」と、わが子を抱きしめる間もなく、引き離されてしまいます。彼女は、娘を、忘れられずに、探し求めます。7年の歳月の後、ようやく娘の居所を見つけて、チャールズの屋敷に、家庭教師として入ることになるのですが…。★娘への消えない愛★テーマは母と娘の絆。たとえ契約で、愛のない中で生んだ娘だとしても、やはり自分のお腹を痛めて生んだ子。忘れられるはずもありません。生まれた瞬間、抱きしめる事も、じっくり見つめる事もできなかった娘。また、どこへ行ったのかも、何と言う名前をつけられたのかも分からない娘。それでも、自分が生んだという事実は拭いようもなく、毎年、娘の誕生日には、水彩画を描いて、どこかで生きている娘へメッセージを書き付けていきます。そして言い聞かせます。「どこにいようと あなたを忘れない。片時も忘れない」と。7年の後、巡り会った娘は、ルイザと名付けられていました。父であるチャールズにだけ甘え、他人には心を開かない娘に育っていました。家庭教師として雇われたエリザベスを、本当の母親と知らないルイザは、彼女に対して、いきなりこう言います。「従わないわ。使用人なんかに」と。エリザベスは、厳しさを伴った「愛情」で、娘ルイザに読み書きを教えていく事を決意します。★ファイアーライト★ファイアーライトとは、劇中の暖炉の炎の明かりを現わすのと同時に、娘を想う愛情でもあり、そして、愛のなかったはずのチャールズへの想いが、再燃する様をも含ませている、さまざまな「炎」を象徴しているのかな、と思いました。全体的には、穏やかな波が打ち寄せるように、静けさを湛えた作品です。作品のもつあたたかい雰囲気、静々と湧き上がってくる感動は、好きです。映像が美しく、神秘的でさえあります。サン・セバスチャン国際映画祭で、最優秀撮影賞を受賞しているのもうなずけます。雪の降りしきる様や凍りついた水面など、全体的に透明な青や白の色調が、効果的に使われています。だからこそ、それと対照的なファイアーライト、暖炉の明かりがよりいっそうぬくもりを感じさせてくれます。暖炉の話をエリザベスが、娘に語り聞かせる場面が、この作品全体の世界、人間模様をも象徴していて印象に残ります。「暖炉の光は時を止めるの。ランプを消すと暖炉の光が広がりルールがなくなるの。何でも言えるし 何でもできる 何にでもなれる。……」娘のルイザは聞きかえします。「何にでもなれるの?」この娘の問いかけが、胸に迫ります。抑え気味の演技が光る、ソフィー・マルソー主演の静かな感動作。
April 14, 2005
コメント(6)
-

透萌(ともえ)の幼稚園デビューと「ちょっぴり」気になる先生
いよいよ、透萌は、幼稚園へ。上の写真は、前日撮りましたが、この服装で入園式にも行きました。私は、仕事を休めなくていけませんでしたが、まずまず無難に、切り抜けられたようです。もともと、行くのは楽しみにしていたので、何はともあれ、元気に楽しく幼稚園に行ってくれればいうことなしです。「もも組」だそうです。「もも」と聞いて思い出すのは、私の場合、「半井桃水(なからいとうすい)」かなり、マニアックというか、変わってるかも…。樋口一葉に、はまってからは、「桃」と聞けば、「桃水」なんです…。一葉の小説の唯一の師であり、同時に、生涯、忘れられなかったであろう、一葉の初恋の相手でもある、桃水。ふたりのことは、日記を見れば見るほど、真実が見えなくなっていくようで、いまだよく分からないというのが現状です。そういえば、桃の花ももうすぐでしょうか。話を戻します。妻に聞いたところによると、担任の先生が、大学を卒業してまだ1年くらいの女の先生だったということです。「へーえ。若いんだね」と言うと、妻は、「ほんとにかわいらしくて、女優さんみたいだったよ」と。「うん?何だって! 女優さんみたい!?」と、瞬間、反応する私。(^^;仕事休んででも、担任の先生を見に…あ、いや、娘を見るついでに、ちょっと担任の先生もみるために入園式行ったらよかったな、と、かなり後悔しました。(^^;「4月に家庭訪問来るんだって」と妻。「あ、そしたら、その日、(何が何でも)家にいるようにするよ。」と私。(^^;そして、「いやあ、今日はたまたま仕事が休みでして(本当はほったらかしにしてきた)…」と、先生に言い訳をする状況を、素早くシュミレーションまでしてました。「でも、ま、無理だろうな。」と言うと、妻は、「来た時に、写真撮っておこうか?」と。「あ、頼むよ!!!」と即答する私。(^^;ま、半分冗談(半分本気)という事で、聞き流してください。2日前は、そんな会話を交わし、ちょっと(ほんとはかなり)先生のことが気になってしまった夜でした。えっと、話が変な方向へ行きそうなのでこの辺で。ところで。楽天での写真は、ひとつの記事に1個しか掲載できないと思っていましたが、何枚も載せている方もいらして、どうやっているのだろう?と感じていました。ようやくやり方がわかりました!と、いうことで、早速、載せてみました。8ヶ月の葵(あおい)は、最近、コタツの中にもぞもぞと入りたがるようです。で、入った時に、「ともちゃんも!」と、透萌も一緒に入ったところです。
April 13, 2005
コメント(2)
-
「謎」が生じる事、すなわち、尽きない魅力
★ナンバープレートのぞろ目★車のナンバープレートのぞろ目のシンクロニシティについては、以前に書きました。「4444」と「5555」を一日のうちに、連続して見たということ。それから少しして、今度は、「3333」のナンバープレートを見ました。これは、どういう意味だったかな、と家に帰って、パソコンに書いたことを見たら、「●「3333」…家族間の愛情、または異性間の愛情など、なんらかの愛情面で、激しい焦りを感じている時。」と、あります。「あれれ? 何で?」と、思いました。別に家族の間の愛情面で「激しい焦り」を感じた覚えはないし、かといって、他の異性の愛情って言っても、そういったことは、思い当たらないしなあ、と。強いてあげれば、女優に入れ込んでしまうというのは、あるかもしれないけど、ミーハー的なもので「焦り」は感じてないし、と、結局よく分かりませんでした。しばらく時が経ち、今日の車での帰り道、ちょうど、停まった時に、前の車のナンバーを見たら、今度は「9999」を見ました。そして、その時ちょうどタイミング良く高架近くで目の前を、新幹線が通過していきました。思わず、「おお!」と一人叫んでいました(^^;私にとっては高架下に来たとき、ちょうど新幹線が通るのを目にする事は、まさに「タイミング」良く物事は進んでいる、という暗示であり、「シンクロニシティ」なので、「よし、大丈夫」との想いを強くしたのでした。何が大丈夫かって、今の自分に自信をもって進んでいけば、大丈夫、物事はうまくいく、という風に、思えるということです。いわば、ゲンかつぎみたいなものですが、こういう意識を「前向き」に方向転換する装置みたいなのが、お遊び感覚で持っていてもいいかな、と思っています。もともと、娘が、新幹線が通ると喜んでいたのに影響されて、新幹線を意識するようになったのですが、今では、私のほうが「新幹線」に入れ込んでいます…。ちなみに、「9999」のナンバープレートは、どういう意味があるかというと、「●「9999」は統合。「9」は元々、物事が統合される、「括られる」数字である。物事が、まとまる、終わる、締めくくられる。」と、いうことです。物事が統合に向かっているというのは、良い方向に向かっていると解釈してよいのでしょう。★「謎」が生じる事、すなわち、尽きない魅力★話は全く変わりますが。おおよそ現代の「定説」と言われる事が、どうも怪しくなってくる、つまり「定説」を覆すような事実がでてくると、素人が考えるに、通常であれば、その「事実」が本物であれば、素直に検証していき、もし、「定説」が覆ったら、それはそれで、新しい「定説」に作り変えていくべきで、そうして、科学というのも、発達してきたはずです。しかし、「定説」を覆すような事実が出てくると、それを認めるどころか、覆い隠そう、あるいは、潰してしまおう、とする動きが、起こってくるのが「普通」のようです。その「定説」がたとえ、誤っていたとしても、自分の保身、権力の保持、そういったもののために、動いてしまう、と。それを批判するために書いたわけでもないのですが、それが現状のようです。日本でも、そうして歴史とか古代の分野を見てみると、それこそ、今の「定説」「常識」とされる事が、「真実」である、というのも、本当にそうだろうか?と考えてみる事も、またおもしろい、と思います。また、現状の現代科学では、解き明かせない事柄もたくさんあるでしょうし、そうなると、そこに、「謎」が生じるわけで、「謎」があると、生き生きとしてきて、実際はどうなっているのだろう、と思ってしまう私としては、大歓迎でもあります。たとえば、なぜ、今になっても、「邪馬台国」の位置が特定されないのか、というのも不思議といえば不思議ですが、だからこそ、歴史はロマンがあっておもしろいのかもしれません。でも、もし、ここにも、「権力」「保身」が絡んできているとしたら…。実際、考古学的にみれば、邪馬台国の位置はかなりの確率で、範囲が特定されてきているようです。考古学で、物証が出てくれば、はっきり言ってこれほど強いものはなく、「論理」も通用しなくなる「力」を持つ場合があります。仮にある場所が、「邪馬台国」の地である確率が高くなると、そうでない地域の説を出している人たちから、圧力がかかったり、妨害にあったり、実際するそうです。こうなると、もう「真実」を探るというより、自分たちの立場を守るのに、必死になって、ますます「真実」からは遠ざかっていく。ある本を読んでいて、そういうことを、今日は思いました。日本だけ見ても、「謎」はまだまだあります。思いつくままあげてみると、「邪馬台国」の謎、卑弥呼とは何者か? 日本とユダヤの関係、聖徳太子の正体、秦氏や賀茂氏、物部氏の謎、天皇家の謎、日本人はどこからきたのか、古事記と聖書の関係、神話の象徴、50音の秘密…etc それこそ、謎は尽きませんが、謎があるからこそ、おもしろい。まさに「事実は小説よりも奇なり」です。
April 12, 2005
コメント(2)
-

『恋人たちのアパルトマン』(1995年・フランス)
「彼女を永遠に愛し続ける。決して愛を打ち明けずに。キスもしない。死ぬまで。」★ソフィー・マルソー、ああ、ソフィー・マルソー、ただそれだけ★この作品は、とにかく衝撃でした。映画を見始めた、初期の頃の作品で、画面に登場した「ソフィーマルソー」を見た途端、そのあまりの美しさに、一目惚れしてしまい、もうどうしようもありませんでした。参りました。(^^;そして、フランス映画をよく観るきっかけとなった作品であり、ソフィーマルソーはじめ、5、6人のフランス女優に、入れ込むきっかけともなった作品でもあり(^^;、そういう意味でも、思い入れの深い作品となりました。この後、フランス映画の、好きな女優の出ている作品を、連続して借りてくることが、多かったので、妻からは「フランス女優マニア」というレッテルを張られてしまう始末…。えっと、余計な事を書いてしまいました…。要は、ソフィーマルソーが、美しすぎたということです。はい。★物語の概要★婚約者のいるアレクサンドル(ヴァンサン・ベレーズ)は、自由奔放なファンファン(ソフィー・マルソー)と出会い、一目惚れしてしまいます。彼は、ファンファンに、思いっきり惹かれているものの、自らの理想主義的な考えから、この情熱はいつまでも続くはずがないし、お互い付き合っても、結局は別れてしまうと、確信しています。それを解決する方法として、彼は欲望を封じ込め、彼女に愛を告白せずに、愛し続けようと、決心します。婚約者が別にいるというのに、ファンファンとも、付き合っていこうというのです。果たして、この奇妙な三角関係はどうなるのか…。★一風変わったフランスらしいフレンチ・ラブストーリー★まず、この男が、何と言っても「変」です。美しい婚約者がいるというのに、惰性で付き合っていたのか、ファンファンと出会ったら、婚約者そっちのけで、彼女に入れ込んでしまいます。そして、彼女に愛を告白するのかとおもいきや、自分から愛を告白しないで、肉体的な欲望を排して、一生涯ファンファンを、勝手に愛そうとします。理想主義というか、何とも、独り善がりで、自分勝手な男です。女性から見たら、こんな男「許せない」となるに違いなく、確かにそうなのですが、しかし、彼の独善的考えに嫌気がさして、甘っちょろいロマンチストぶりに、呆れつつも、観ているうちに、そういう気持ちも、分からないでもない、と感じたのも事実。男は、こういう理想主義的なところが、多かれ少なかれ、あるのかもしれません。途中から、どんどん男の独善的傾向は強まっていき、ついに、「鏡越しの愛」に行き着くのには、さすがにやりすぎ…と思いましたが、でも、けっこう楽しめました。彼の気持ちが、理解できなければ、この映画、「何だこの男は!」と、腹が立つだけで終ってしまうかもしれません…。彼に感情移入できるか、あるいは感情移入できないまでも、少しでも彼の気持ちが理解できるかどうか、が、この映画の賛否の鍵を握っていると言っていいでしょう。★勢いのあるジェットコースター的ストーリー★物語は、はっきり言って、無駄な部分がほとんどなく、途中川が蛇行するように、多少の横揺れはありますが、あれよ、あれよ、と乗せられて、実にスムーズに結末まで運ばれていきます。笑える場面あり、楽しい場面あり、心の痛む場面あり、最後にドキッとする場面もありで、最後まで気が抜けませんでした。★躍動感あふれるソフィー・マルソーの最高傑作★ソフィー・マルソーの出演作品は、そんなに多いほうではないのですが、彼女の魅力が最大限発揮されているのは、自分にとっては、本作品以外ありえません。「動」の躍動感あるれるソフィー・マルソーは、本作中、本当に生き生きしています。「静」の代表作は、『ファイアーライト』という事で、また近いうちに取り上げるつもりです。ソフィー・マルソー 恋人たちのアパルトマン ◆20%OFF!<DVD> [TSDS-75205]ファイアーライト -情炎の愛-
April 11, 2005
コメント(2)
-
「金環日食」(シンクロニシティの不思議 episode 27)
★映画『ひまわり』に描かれた金環日食★あまり意味のない、偶然の一致ですが。4月9日の日記で『ひまわり』という邦画を紹介しました。記事には書きませんでしたが、この映画のなかでは、「金環日食」という現象が、映像で非常に効果的に使われています。主人公の小学校時代のエピソードで、土手のところで、主人公の少年が、土手の上にいる初恋の相手の少女を見つめています。そこで、金環日食が起こり、太陽がリング状の「金環」となって現れます。そして、光があふれ出してきて、少女がその時少年の方を振り向きますが、まばゆい光に少女の顔が覆われて、表情が見えない…。と、そんな情況だったと思います。映画全体でも、まばゆい光を、効果的に取り入れた映像が、印象に残ります。★4月9日に実際起こった金環日食★映画を紹介した次の日、4月10日の朝、新聞を見ていると、金環日食についての記事が、目に入りました。「おお。」と思いました。4月9日に、「金環日食」の映像が効果的に使われていた邦画『ひまわり』を、楽天日記に紹介したら、たまたま、同日、4月9日に、実際「金環日食」が起きていたという「偶然の一致」まあ、それだけ、といえば、それだけなんですけど…。以下記事を引用してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー太陽が月にすっぽりと隠れる皆既日食と、真っ黒な月のシルエットの周りにはみ出した太陽がリング状に輝く金環日食が、日本時間の9日早朝、中南米から太平洋にかけて、相次いで観測された。同じ日に皆既日食と金環皆既日食、あるいはハイブリッド日食と呼ばれる珍しい現象。1987年以来、18年ぶりの観測で、次回は2013年になる。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★太陽は、実際は熱くない?★太陽と月のことがでたので、ついでに。太陽は、「永久的に核融合反応が続いている。成分はほとんど水素で構成され、水素原子が核融合でヘリウム原子に変わり膨大なエネルギーを生む。」(インターネットより引用)というのが、定説です。つまり太陽は、超高温で、中心温度は、1400万度になる、といいます。しかし、本当に太陽は「超高温」の星なのか?ということも、ごく一部でしょうが、言われてもいます。事実、太陽が超高温では、説明のつかない現象も、観測されてきているようです。また、機会があれば紹介したいと思います。また、水素とヘリウムからなり、いわゆる、木星などと同じ、ガス天体と言われていますが、果たしてこれも、そうなのか?という疑問があります。それこそ、太陽が「地殻」をもった天体である、などと言えば、そんな馬鹿なことはない、と言われるのがオチですが、果たして実際はどうなのでしょうか。個人的には、太陽は、定説で言われているような、超高温の星ではない、と思っていますし、誤解を恐れずに言えば、「地殻」をもった天体である、と考えています。そして、もっと言えば、木星も、ガス天体と言われていますが、実際は「地殻」をもった天体の可能性が、非常に高いと思います。そして、これは、惑星が、どうやって誕生したか、という事にも関わってくる問題のようです。★月は空洞になっている?★また、月については、重力異常があったり、月で地震が起こると、いつまでも振動が続いていたり、どうも、月の核の部分に異常があるようなのです。一言でいえば、何らかの原因で、月の核の成分が表面に出てきている、と。そして、核の部分が、空洞状態になっている、と。また、それだけではなく、月は、人工建造物ではないかとも言われる、「異常地形」が、NASAが公開している写真からも、指摘されています。さらに、未確認飛行物体も撮影されています。また、クレーターも月の裏側に異常に集中しています。これは、過去に、大きな災厄が月を襲ったことを物語っていますし、この事件と、月の「空洞」は関連があるのか、ということも、気になるところです。地球の衛星である、月は、空を見上げれば、たいてい見えるわけですし、知ったつもりでいますが、実態は意外に分からない事もまだまだあり、起源含めて「謎」の衛星といってもいいのではないかと思います。
April 10, 2005
コメント(0)
-
『金色の光透波(ことば)が眠る空間』
喧騒から 解き放たれた空間射しこむ 光の渦小さな微粒子が 命を吹き込まれたかのようにそこかしこで きらきらと漂っている音のない空間で かすかに聞こえてくるのはページを繰る 紙と紙が交わす ささやき声ここに眠っている 語り尽くせない 言の葉は誰かが探りあててくれるまで声のない空間で じっと待っているあなたたちから 何も言わないのは 巡り逢うべき人が 必ず来てくれると 知っているから人と人の出逢いには ひとつとして 偶然はなく一人一人が 同じ重みをもって 出逢いと別れを 重ねていくあなたたちの出逢いにも 偶然など あるはずもなくその時 その場所で その時必要な 巡り逢いを 重ねていく見渡せば 無数に広がる 言の葉の海に 飲み込まれてしまいそうそれでも 僕は 今一番大切なあなたを 見つけることができるあなたの 密やかな息づかいや 真っすぐに見つめてくる視線そのあなたに 僕は何のためらいもなく ただ 手を差しのべるだけおそらく 一生かかっても 言の葉の海の果てには たどり着けないだろうそんな 深くて尽きない世界に 僕は 魅せられた波間にきらめく 一瞬の光を すくい取るかのようにその時に必要な 言の葉が 金色の光をともなって目の前へ 流れてきてくれる言葉は 光透波であった…終わりのない旅路であってもいい何かを求めるのではなく 何かを考えるのでもなくただ 一つ一つの出逢いに 喜びを感じ 味わっていきたい※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※【散文詩『金色の光透波(ことば)が眠る空間』についてこの散文のきっかけは、松たか子の『四月物語』という映画。松たか子が演じる楡野卯月(にれのうづき)が、武蔵野堂という小さな本屋で、本を見る場面が、実に良くって、その空間をイメージして、綴ってみました。「本」との出逢いには、偶然はない、というのが、自分の思いでもあります。本屋で何気なく目に付いて、手にとって、ましてや買って、「読む」本というのは、よっぽどの事だと思いますし、その時の自分にとって、必要な本が、来てくれている、と私としては本気で思っています。実際、あ、やっぱり今の自分に必要な本だ、と思ったことが多々ありますし、本を選ぶことは、自分の感覚を信じることだと、と思います。
April 10, 2005
コメント(0)
-

『ひまわり』(2000年・日本)
「ねえ… 初恋のこと覚えてる?」「私は 覚えている」★「世界の中心で愛を、さけぶ」の行定勲監督初期の「秀作」★この監督は『GO』『世界の中心で愛を、さけぶ』などがメジャーになりましたが、個人的には、初期の作品群の方に、より愛着があります。私が勝手に「裏」ベストに認定している『贅沢な骨』や、この『ひまわり』そして、『閉じた日』など、初期の作品は、荒削りなところがあるものの、原石の輝きのような「情熱」が感じられて、好きです。本作品も、『贅沢な骨』と共通する「どこに行くのか分からない危うさ」が、逆に魅力となっています。★物語の概要★東京で暮らす輝明(袴田吉彦)は、恋人といる時、小学校の同級生だった真鍋朋美(麻生久美子)が、海難事故で行方不明になっていることを、TVのニュースで知り、驚きます。と、いうのも、彼女は数日前、輝明の留守番電話に、なぜかメッセージを入れていたからです。「あの… 真鍋朋美といいますが…。覚えていますか?」と。彼女は何のために、輝明にメッセージを入れていたのか?また、なぜ釣りの漁船などに乗っていたのか?結局彼女は、見つからないまま、葬式をすることになります。輝明は、幾人かの同級生とともに、故郷へ帰って、彼女の葬式に出ますが、そこで彼女の恋人たちに出会い、話をするうちに彼女の死の前の行動が徐々に明らかになっていきます。そして、それとともに輝明の小学校時代の記憶も蘇ってくるのでした。そう…。「初恋」の記憶が…。 ★「麻生久美子」との衝撃的な出会い★この作品に惹きつけられた第一の要因は、「麻生久美子」行方不明の「真鍋朋美」の過去が明らかになってくる段になり、画面に登場した朋美である、「麻生久美子」という女優を見たとき、「うん?」と、俄然この映画に、というか、この女優に目が釘付けになりました。(^^;彼女の死の影を帯びたような影の薄さ、孤独感、哀しさ、どこか遠くを見る目つき、それでいて妙に引きつける存在感。そういったものを彼女に感じ、「真鍋朋美」というか、「麻生久美子」をもっと知りたい、と思ったわけです…。★「初恋」の瑞々しさ★そして、もうひとつの要因は、「初恋」誰の胸にも記憶がある、「初恋」の懐かしくも切ない、そして暖かい記憶を、瑞々しく美しい映像で浮かび上がらせた、という点に、惹かれました。初恋の記憶は、時とともに、風化するのではなく、少しずつ形を変えながらも、より美しい形へと変容していくのかもしれません。「記憶」とは、ある意味自分の都合のよいように、記憶をすり替えていく、というのはあるでしょう。特に、初恋の記憶というのは、より美しい記憶に昇華していくように感じます。少なくとも自分の体験からいけば、そうかな、と。そういった記憶のあいまいさも、作品のなかに、仕掛けとして取り入れつつ、誰もが共感できるような、普遍的な世界が、郷愁的かつ、思い入れたっぷりに描かれています。★「ひまわり」という花の象徴★小学校のエピソードで、真鍋朋美は、輝明から、「君はまるでひまわりみたいだ」と書かれた紙をもらって、彼女自身、自分にはひまわりなんて、ふさわしくないと思った、というのがあります。確かに真鍋朋美は、小学校の時もひかえめで「ひまわり」という華やかな存在にはふさわしくありません。ただ、輝明にとっては、やはり、彼女は、まぶし過ぎる「ひまわり」のような存在であったのでしょうか。「ひまわり」とは、漢字で書くと「向日葵」と書き、「日」に「向かう」「葵」となります。そういえば「葵」は、私の娘の名前でもあるので、思い入れはあります。……と、そんなことはどうでもよくて、ですね。(^^;勝手な解釈ですが、むしろ、朋美のイメージは、「ひまわり」というより、この「葵」の方が似つかわしい気がします。ただ、どちらも太陽へ向かっていく花であり、そういう意味では、共通するものがあります。いつも「日」である「太陽」という明るい方を求めて、咲こうとしている存在。真鍋朋美は、大人になって、何人もの恋人を渡り歩くのですが、それも、「太陽」という「愛」を求めてさまよう姿、「ひまわり」や「葵」を象徴しているのでしょう。そういう意味でも、輝明が「ひまわりみたいだ」と書いたことは、初恋の告白であるのと同時に、彼女の未来を的確に表していたことにも、なります。それは、真鍋朋美だけでなく、むしろもう一人の主人公輝明(袴田吉彦)も、忘れかけていたものを思い出し、そして乗り越えていく物語である事を見ても、「ひまわり」を象徴しているのかもしれません。そして、主人公ふたりだけではなく、この「ひまわり」という映画自体が、「愛」や「光」を求めてさまよう、若者たちの群像劇的な物語にもなっています。初恋の記憶を叙情性たっぷりに謳い上げた作品は、せつなくなってくるメインテーマの音楽と、見事な共鳴音を響かせて、鑑賞者の「初恋」の記憶をも、喚起させて、「情感」に訴えてくる作品に仕上がっています。『贅沢な骨』『ひまわり』は特に、行定勲監督初期の秀作として、おすすめです。ひまわり ◆20%OFF!<DVD> [KSXD-24229]
April 9, 2005
コメント(2)
-
『宇宙(そら)を巡る桜の息吹』
再び この季節が 巡り来て あなたにまみえるとえも言われぬ想いが 疼きだすコノハナサクヤ姫が 富士山から 種をまいたという 神代の伝説何者をも惹きつけてやまない 日本の大地に息づく あなたの姿満開の花びらは 何故かくも心躍らせ 心震えて 心ぬくもり そして心寂しくなるのだろうそれは四月には さまざまな出会いと別れが 複雑に絡み合い無数の花びらが 舞うようにいくつもの物語が この世界を 駆け巡るから前を見据える事ができずに 地に目を落として 歩いているとそこにあなたが ふわり…と 舞い降りてきた見上げれば 雪のように降りしきる 桜の花びら底に沈んでいた 光と闇にくるまれた 記憶がとめどなく あふれてくるよう柔らかな 春の風にのる花びらは どこへ行くのかまるで 行く当てもなく さまよっている 自分の心みたい絡まったしがらみを 解き放つようにあなたも 一時のあと 旅立っていく僕も いつか一歩を 踏み出さなくてはいけないあなたが散っていくのは 悲しいことではないし決して 雨や風のせいで 散るのでもない初めから あなたが散る事は あなた自身が 決めてきたことこの大いなる巡りの中で 生命を育み 再び花を咲かすために…その揺るぎない心に 日本の「精神美」を 強く感じた音もなく降りしきる 桜の花びらの 向こうには四月の すがすがしい空が 泣きたいくらいに静かに 広がっていたあるがままの宿命を 淡々と受け入れる あなたの姿心に降り積もった わだかまりを すべて 吹き払えるような…そんな気がした桜の花びらは 広い空の海に 心地よさそうに 浮かんでいた流れゆく 花びらの行く先を 今しばらく 見つめていたい不器用な一歩でもいい…はじまりの一歩を 今度こそ 踏み出せる気がした…
April 8, 2005
コメント(0)
-

『四月物語』(1998年・日本)
「私は残り半年の高校生活のすべてを 武蔵野に捧げた…」★四月に込められたもの★そういえば、今、四月だし、今のうちに紹介してしまわないと、ということで、『四月物語』。手書き通信の「光透波の泉」【アナログ版】では、この映画を、何を血迷ったのか「12月」に紹介してしまい、大失敗をしました。その時は、寒い時期こそ、心があったまるものを見るのがいいの!とよく分からない論理を持ち出して、言い訳をした覚えがあります。(^^;だから、今回は、その失敗を教訓にして、この作品を、四月に紹介しなくてはならなかったと、そういう訳なんです。はい。のっけから、余計な事を書いてしまいました。本題です。四月。それは、新しい始まりの時期でもあり、出会いと別れ、喜びと悲しみ、さまざまな相反するものが混じりあい、草木が芽吹き、景色に少しずつ緑が増えていき、そしてさまざまな花が開き始める時期でもあります。日本を象徴する桜も、ほんの一瞬鮮やかに咲き誇り、そして、散りゆく「四月」なぜか一年の中でも、特別な気持ちになる四月を通じて、ひとりの女子大生が、少しずつ成長し、これから花開いていく、人生のほんのひとひらの花片のような、「断片」を、鮮やかに切り取って提示してくれた、作品。見ていてピュアな気持ちを思い出す、そして、心があたたかな陽だまりに包まれるような、いつまでもぎゅっ…と抱きしめていたい、そんな作品です。力の入った作品や重厚な大作もいいけれど、こういうホッとできる、ぬくもりのある掌の小品も素敵です。★岩井俊二という才能★監督は岩井俊二。この監督は、中山美穂主演の『Love Letter』を観て、興味を持った監督です。たとえば、『スワロウテイル』は、才能は十分認めるし、完成度もかなり高いと思うのですが、お腹いっぱいになりすぎて、再鑑賞はちょっと…というのもあれば、『Love Letter』や『四月物語』、そして、その延長上に位置する『花とアリス』など、ほのぼのした、心があったまる作品もあれば、そういう叙情性は一切排除した、世界が描かれる「痛い痛い」映画『リリィシュシュのすべて』など、いろんな作風があります。総じて、この監督の作品は好きなものが多いです。★物語の概要★東京の武蔵野大学に進学する事になった楡野卯月(にれのうづき/松たか子)は、北海道を離れて一人暮らしをする事になります。冒頭、駅での家族との別れの場面では、松たか子の実父である、松本幸四郎が父親役でほんの少しだけ出てくるのも一興です。武蔵野大学での、新しい「一人暮らし」の生活が、ある想いを胸に秘めて、期待と不安を抱いたままスタートするのですが…。★キーワードは「一人暮らし」と「本屋」★上記のふたつのキーワードが、私自身、この映画を観て、より気に入った理由でもあります。それと、忘れてはならないのが「松たか子」…。(^^;ただ、松たか子目当てで見たのではなく、彼女の存在自体そんなに知らなかったですし、この作品で、彼女を初めてまともに見ました。そして一気に、彼女の魅力に取り付かれてしまいました…。彼女の演技は非常に初々しく、あざといと言われようが、彼女の魅力が最大限発揮された作品に結実しています。東京での一人暮らしをはじめた、楡野卯月(松たか子)。映画というのはある意味、自分の体験と重ね合わせたりして、より深く入り込めるときがあるのですが、この作品で言えば、ひとつは「一人暮らし」。私も大学の時に、一人暮らしをしたのですが、その時の頃を思い出しました。特に一人暮らしをした事のある女性であれば、この主人公に大いに共感できるのではないかと思います。何が起こるって訳ではないのですが、日常の出来事や何気ない一コマ一コマを、岩井俊二は、実に丁寧に、何気なく、すくいとっていきます。夜、作りすぎたカレー(理由はあるのですが)を、一人ぽつんと食べる姿。一人で手を合わせて「いただきます」と小さく口にして食べ始め、何か手持ち無沙汰で、リモコンを持ってきて、ぱちんとテレビをつける。でもテレビは、全然見る気はなくて、なんとなく寂しさを紛らすために、つけている。身につまされるというか、その時の気持ち、わかるなあ、と印象に残る場面です。★「本屋」というキーワード★彼女は武蔵野堂という本屋へ良くいくのですが、私自身、本屋は大好きなので、本屋での場面も、いいなあ、と感じました。楡野卯月が、静かなこじんまりとした「武蔵野堂」で、すーっ…と本の背表紙の上、指をすべらせて、時折、これ、という本のところで、ぴたりと指の動きを止める。そして、その本を取り出しては、パラパラとページをめくって、見てみる。また、すうっ…と指を滑らせていく。こういう何気ない描写が、じつにいいです。絵になる映像、というのでしょうか、そういう場面がいくつもあり、あくまでさらりとスケッチ風に、彼女の日常を映していきます。私は、本が大好きなので、本屋に入って、本を眺めるだけで「しあわせ」になるようなところがあります。また、どんな本に出逢えるのだろうか、というわくわく感は、たまらないものがあります。そういう感覚を、楡野卯月こと、松たか子は、触発してくれました。★武蔵野大学にかけた理由★「何でこの大学受けたんですか?」「そうですね…。えっと…何というか…。いろいろ… 環境… ていうか…。……。すみません…。」大学での自己紹介の時に、大学を受けた理由を聞かれますが、彼女はしどろもどろな受答えになってしまいます。何故か?理由がなかったから、ではなく、むしろ彼女には明確な理由が存在していたからです。そして、それを皆の前で言うのが恥ずかしかったから。この「理由」は観ているうちに、大方予想はつきます。楡野卯月は、そのために、「残り半年の高校生活のすべてを武蔵野に捧げます」★楡野卯月の人物造詣★今の時代に、果たして、楡野卯月のような純粋でひたむきで内気な女性が、どれくらいいるのだろうか、と思ったりもするのですが、むしろこの人物造詣は、監督岩井俊二を通しての、男性から見た女性の理想像が、多分に投影された結果、生み出された人物なのでしょう。そして、物語は、これから、という時に、幕を閉じます。美しい記憶の断片だけを繋ぎ合わせて映像にしたような、汚れのないきれいな物語です。ある意味拍子抜けした感が最初はありましたが、「四月」という流れゆく季節のほんの一時を映し出せば、こうなるしかなく、次への希望、深い余韻を漂わせて、見事な仕上がりではないかと思いました。そして、この映画は、一度だけではなく、2度3度と再鑑賞することをおすすめします。はじめて見た時には、彼女の心理がよくわからなかった場面が、再鑑賞の時には、理解できているので、その場面の彼女の表情、しぐさなどから、内面の心理をより深く味わう事ができます。なかなか、きめ細やかに作られた作品である事もわかります。★松たか子のための映画★そして、松たか子のプロモーション的な、松たか子のための映画であることも、間違いなく、彼女の魅力が最大限発揮された作品であり、松たか子自身の「青春」の断片を、鮮やかに切り取った作品として、記憶されるでしょう。作品中に流れるピアノ曲は、松たか子本人の演奏だそうです。この作品で、彼女に突如、惹かれたため、この後、CDも全部買って、聞くはめになったことはいうまでもありません…。繰り返し繰り返し、これでもか!というほど、聞き続けたものだから、妻は、驚きを通り越して、唖然としていたことも、いうまでもありません。(^^;四月物語 ◆20%OFF!<DVD> [NND-1]
April 7, 2005
コメント(2)
-

『イルマーレ』(2001年・韓国)
「最初の手紙 覚えてる?「イルマーレの幸運を祈る」って。今度は僕が祈るよ。君の愛に幸運が訪れる事を…。これまで手紙をくれてありがとう。 ……さようなら。」★『リメンバー・ミー』と双璧をなす出色の作品★『リメンバー・ミー』を紹介したので、勢いで、もうひとつの韓国映画の最高峰『イルマーレ』も紹介します。個人的には、この2作品は、甲乙つけがたい韓国映画のベスト作品。ともに、透明感のある美しい映像、ピュアな気持ちを思い出す作品であり、今まで見た韓国映画のなかでは、この2作品をこえる作品は、まだ出てきていません。冒頭の場面、透き通るようなピアノの音色が奏でられ、海辺の神秘的な家「イルマーレ」が映し出された時点で、『リメンバー・ミー』と同様、この映画が大好きになることを約束されたも同然の作品となりました。物語の軸は、時空を超えて、ふたりが交信するという話で、『リメンバー・ミー』と設定が似ています。『リメンバー・ミー』が、「無線機」を媒介したのに対して、本作では「手紙」。デジタルとアナログの違いはあるものの、現在と過去を繋ぐという点では、ほぼ同じ役割を果たします。本作の「手紙」は、「イルマーレ」の「郵便ポスト」が、現在と過去の橋渡しをしてくれます。★物語の概要★イルマーレを引越すことになったウンジュ(チョン・ジヒョン)は、次に入居する人にあてて、メッセージをポストに残していきます。しかし、そのポストに入れられた手紙は、不思議なことに、時空をさかのぼって2年前の過去、彼女の前の住人であるソンヒョン(イ・ジョンジュ)のもとへと届けられてしまいます。それをきっかけに手紙を通じて、時空を越えたふたりの文通が始まるのですが…。★決して出会うはずのないふたり★「郵便受けのいたずらだわ…」「きっとそうだね」気まぐれの偶然がもたらした運命のいたずらによって、過去へと配達された手紙。そのちょっとした運命のいたずらが、ふたりの間を繋ぎとめている唯一の絆であり、奇跡。決して出会うはずのないふたりは、「文通」を重ねていくにつれて、少しずつ心を通わせていきます。けれども、実際会うこともできないし、触れ合うことも、声を聞くこともできない。会えないからこそ、降り積もる雪のように、想いは少しずつ募っていきます。そして…。★「文通」で喚起されるもの★『リメンバー・ミー』と『イルマーレ』先にも述べたように、現在と過去を繋ぐものは、前者が「無線機」、後者が「手紙」「無線機」は使った事がないので、個人的に思い入れのあるものといえば、断然「手紙」私自身、社会人になるまでは、手紙なんてほとんど自分から書くことなどなく、書くことは、苦手でした。しかし、雑誌などをきっかけに「文通」を、数人の方とするようになってからは、わりと頻繁に書くようになりました。そして「文通」には、一時期本当にはまってしまい、多いときで、5,6人、もしかしたら10人近くの人と、同時並行で文通をしていたかもしれません。ポストに投函する時の、期待と不安、返事を待つ時の、あの短くも長い時間は、何ともいえない「時間」でもあります。メールだと瞬時ですが、あの手紙を待つ「時間」って、待ち遠しいけれど、あれこれ書いたことや、返事のことを考えたりして、一人、期待と不安と願いと焦りといった、もろもろの想いが、渦巻くひと時でもあります。今日は、返事か来ているかな、とポストをのぞく時の期待。「あ、早いな」と、うれしかったり、「あれ?今日も来てないなあ」とちょっとがっかりしたり、今思うと、ほんと懐かしい。楽しかったし、いい思い出ですね。この「イルマーレ」を見て、そういった「文通」のことが、思い出されたりしたので、そういう意味でも、思い入れのある作品です。「文通」は、相手の表情やしぐさや声はもちろん分かりませんし、見えない分いろいろと想像も膨らんでいきます。言葉や文章や、相手の字体から、その人の「心」は、間違いなく伝わるし、見えない分、より伝わってくるものがあるような気がしました。メールでも、字体こそ分からないけれども、文章のニュアンスなどから、「心」を感じられるという点では、手紙と共通するものは、あると思います。ただやっぱり、「手紙」をもらったときのうれしさは、「メール」とは変え難い喜びがそこにはあります。文面や字体はもちろん、便箋や封筒まで、トータル的に含めた「手紙」のもつあたたかさ。そんなものを感じます。★神秘的な美しさをもった海辺の家「イルマーレ」★…と、話がそれました。「イルマーレ」に戻します。「寂しそうに見えたイルマーレが暖かく感じられたのは、愛が込められていたからなのね」この映画は、題名にもなっている海辺の家「イルマーレ」が、何といっても素敵です。この映画の影の主役である時空を越えて配達される「郵便ポスト」この「郵便ポスト」から、海に向かって緩やかに伸びている木の桟橋。その先に高床式のような柱の上に建つ家「イルマーレ」。満ち潮になると、支えている柱のところまで水に覆われて、水の上に浮かぶ家が、また幻想的で美しい。ここで、一人静かにたたずみ、波の音を聞く…。憧れますねえ。映画を見ながら、思わず、こういうところに住んでみたい、と思わせる家です。「イルマーレは時々人を寂しくさせる。私が住んでいるときもそうだった。」この印象に残る「イルマーレ」を舞台に綴られる、現在と過去の神秘的で透明感のある作品。美しい映像が、心により強く残る傑作です。イルマーレ THE PERFECT COLLECTION
April 6, 2005
コメント(4)
-

『リメンバー・ミー』(2001年・韓国)
「人は香りをもって生きているの。そしてその香りを感じながら生きている…」「私には彼の香りが伝わってくる。 いつでも、どこでも、瞳を閉じれば香ってくる…」★韓国映画の最高峰のひとつ★冒頭、せつないピアノの調べが奏でられるとともに、雪の降りしきる映像が映し出されます。この場面で、この映画は好きな映画になると、確信した作品です。そして、その期待にたがわず、心に残る作品となりました。内容はファンタスティックなラブストーリー。登場人物に「あんたの話って、まるでSF恋愛小説ね」と言わしめるように、現実では考えられない舞台設定が、まず、なされています。その設定とは、壊れた無線機を通じて、過去と未来の住人が交信するというもの。ほぼ同時期に公開された、『イルマーレ』という韓国映画も、似た趣向でした。この2作品が、現時点では、韓国映画の最高峰に、自分としては、位置づけています。★物語の概要★時代は1979年のソウル。女子大生のソウン(キム・ハヌル)は、一年先輩のトンヒ(パク・ヨンク)に、密かに想いを寄せています。ある時、ソウンは、壊れた無線機をもらい受けて、家に持ち帰ります。そして、皆既日食の夜、無線から男の声が聞こえてきます。話を交わすうちにイン(ユ・ジテ)という青年は、ソウンと同じ大学に通っている事が分かり、無線の本を彼から借りるために大学の時計塔の前で、待ち合わせをします。2人は同じ時刻、同じ場所で、待っていたはずなのに会うことができません。かみ合わない話の中で浮かび上がってきたのは、予想外の現実でした。「そう、君は1979年にいる。そして僕は2000年。つまり、どちらかがホラを吹いているか、頭がイカレてるって訳。」ふたりは、まさに時空を隔てて交信してしているという奇妙な事実に突き当たりますが…。★キム・ハヌルとハ・ジウォン★過去の1979年に生きるソウン役にはキム・ハヌル。先輩との恋が描かれますが、恋をしている時のあの何ともいえないときめきやせつなさ、甘酸っぱい気持ちを、彼女は実に初々しく表情に出していて好感が持てます。容姿や雰囲気といい、どことなく、松たか子に似ているような気がして、より好感がもてました。(^^;1979年という時代もあるのでしょうが、この時代のふたりの恋愛は、より純粋に美しく描かれているように感じました。一方の2000年のイン(ユ・ジテ)は、ヒョンジという女友達がいます。ヒョンジを演じたハ・ジウォンの存在感もすばらしい。ふたりは恋人というより、友達です。ただ、ヒョンジは、インのことを想っているけれども、そんなそぶりは見せずに、強がっているところが、かわいらしくて、魅力的。毒舌の掛け合いといった、ふたりのやりとりは、ソウンたちとは対照的に、現代的で、とても楽しいものがあります。★ふたつの時代を結びつけるもの★過去と現在、このふたつの世界を結びつけるものは無線機だけ。いったいこのふたつの世界はどういう関わりがあるのか?また、ふたつの世界は物語のなかで、どう結びついていくのか?これ以上は踏み込みませんが、後半、意外な形でふたつの世界は急接近します。後半、ある人物の下した選択。現在と未来を見据えた、愛情に満ちたひとつの決断は、心に深くしみます。★20年後の未来★ソウンは、未来に生きるインに聞きます。「人を一生懸命好きになると結ばれる方法ってある?」「そんなの永遠にありえないよ」時代がどんなに進歩しても、変わらないでいてほしい事があるとともに、人を好きになるという人間の感情は、いつまでも純粋であってほしいと思いました。今から20年後の世界はどうなっているのでしょうか。また20年後の自分に出会えるとすれば、どんな自分がそこにいるのでしょうか。そんな事を、この映画を見たあと思いました。いろいろな想像がかき立てられるとともに、せつなくて、あたたかい余韻を与えてくれる素敵な作品です。リメンバー・ミー
April 5, 2005
コメント(6)
-

『贅沢な骨』(2001年・日本)
「嫌いな人が聞いていたはずなのに、私、この歌大好きなんです。この歌にずいぶん励まされたし。音楽って不思議な力あるんですね。」★現時点、思い入れ度No.1映画★こういうと、やや恥ずかしいものもあるのですが、でも、やっぱり、この映画、大好きです。ただ、声を大にしておすすめできる作品でもなく、嫌いな人は、嫌い、好きな人ははまってしまう、という、好き嫌いのはっきりと分かれる作品ではないかと思います。全編を覆う虚無的なけだるさが、何故か心地いい。そして、記憶に留めておきたい数々の映像が、それに輪をかけるように物語をゆったりと導いていきます。ただ、物語は、予定調和ではなく、どこに行くのか分からない「危うさ」を抱えていて、少しずつ「歪み」と「あいまいさ」を伴いながら、何かが壊れていきます。その壊れゆく様が美しくさえあります。見終わっても、すっきりしない部分もいくつかあります。そのあいまいな部分が、逆に見る者の想像力を刺激して、粘りつくような余韻を残します。★監督は「世界の中心で、愛をさけぶ」の行定勲★行定勲監督は、『GO』で映画賞を総なめ、一躍メジャーな存在になり、その後『世界の中心で、愛をさけぶ』では、大ヒットを記録しました。『贅沢な骨』は、『GO』の前に当たり、まだ、あまり知られていなかった時の作品。個人的には、メジャーになる前の作品の方が、未完成ながらも監督の情熱が感じられて、好きです。★物語の概要★ホテトル嬢をしているミヤコ(麻生久美子)は、いつもジャージ姿のサキコ(つぐみ)と一緒に暮らしています。ミヤコはうなぎの骨が喉に刺さったのか、喉に違和感を覚えるようになります。サキコは過去の傷が尾を引き、仕事をするでもなく家にこもりがちで、ミヤコの帰りを待つ日々。二人は少し強く触れれば壊れてしまいそうな現実のなか、それなりに充実した日々を送っています。ミヤコはある時、仕事で新谷と名乗る客(永瀬正敏)の相手をして、初めて心から満たされます。ぬるま湯のような二人の日々に新谷が加わることで、3人の間には微妙な緊張関係が生まれていきますが…。★麻生久美子とつぐみ★そもそも、本作品をなぜ、手に取ったのか?正直に申し上げれば、行定監督の前作『ひまわり』で、かなり気になっていた女優「麻生久美子」が、この『贅沢な骨』にも出ていたから、というのが1番の理由です…。動機はいたって単純、というか、不純です。しかし、人生何が起こるか分からないもので、麻生久美子目当てで見たはずが、もう一人の初見の女の子、つぐみのほうに、目移りしてしまい、結局、彼女から目を離すことができませんでした。麻生久美子は、悪くない。うん、はまり役です。しかし、サキコ役のつぐみの体全体から滲み出てくる「哀しみ」「孤独」、じっと一ヶ所を見つめる瞳の「寂しさ」に惹きつけられて、つぐみの視点から、彼女に感情移入して、物語を見ていました。彼女の少しはにかみながらギターを弾く姿、屋上で一人影踏みをしている姿、足に怪我をして松葉杖で階段を登る姿など、印象的で、彼女の「哀しみ」は見ているだけで、息苦しくなるほどでした。つぐみと麻生久美子、このふたりに、ベテランの永瀬正敏が加わって、奏でられる物語。不器用で、傷つけあい、それでも離れられない、そんな3人のさまよう先には、どんな結末が待っているのか…。★幻のバンド、ザ・ハンプバックス★また、最後に、付け加えるとすれば、音楽も非常に印象に残ります。サキコが映画の中で弾いている曲、「トーチソング」。それがエンディングテーマともなっていますが、この作品全体の、けだいるいなかにも、張り詰めた雰囲気を、集約した曲でもあり、この曲があるからこそ、物語に、より深みが出たのではないかと思います。決して明るい曲じゃないけれど、繰り返し聴いてしまう曲です。これを書いている今も、この「トーチソング」をエンドレスでかけています。あまりに印象的な曲なので、私はこのサントラ買ってしまいました。この映画のためだけに結成されたという、ザ・ハンプバックス。出演している永瀬正敏がボーカルです。行定監督の「裏」ベスト作品は、この『贅沢な骨』で決まりです。贅沢な骨 【KSXD-24307】 =>20%OFF!《発売日:02/03/22》
April 4, 2005
コメント(5)
-

『ユメノ銀河』(1997年・日本・90分)
「そう、私、無茶だと思う。でも無茶でもいいの。私のホントにつまらない人生に、初めて大きな冒険が現われたのよ。私、もちろん覚悟しています。これこそホントの命がけの恋よ。」★石井聰亙がモノクローム灼きつける、幻惑の恋情絵巻★上記は、パッケージの言葉を拝借しました。先日4回目の鑑賞をしましたが、思い入れのある作品です。ということで、この映画に関しては、ヤプログ版で紹介したのですが、今回、内容を一部変更して、再度こちらへ載せました。★夢野久作の原作を見事映像化★原作は、奇作『ドグラ・マグラ』で有名な、夢野久作。ちなみに、この『ドグラ・マグラ』は、読んだけどさっぱり分からなかった記憶があります。しかし、あの独特の雰囲気は、強烈な印象を記憶に残してくれました。機会があれば、また、再読したいと思います。この映画は、彼のわずか数10ページの短編『少女地獄』を、映画化したもの。この作品を鑑賞した後、原作を読みましたが、原作の雰囲気を継承しつつ、さらに脚本段階で魅力的なエピソードを加えながら、原作を遥かに越えた作品として結実したのではないか、と感じました。特に、石井聰亙監督のモノクロ映像が、本当にすばらしい。これこそ、映画らしい映画、映像での表現において、映画でしかできないような映像。一時たりとも目を離せない緊張感が、映像から伝わってきました。★物語の概要★バスの女車掌のトミ子(小嶺麗奈)は、憧れから女車掌になりますが、だんだんと現実を知るにつれて、女車掌なんてやるもんじゃない、と思うようになります。そんな中、親友の女車掌が、バスの事故で亡くなってしまいます。彼女にはバスの運転手である婚約者がいましたが、その頃、変な噂がありました。その噂とは、何でも、女車掌をひっかけては、付き合い、飽きると、事故に見せかけては殺していくと。そして、どうも、その婚約者が、その男に似ているのではないかと、トミ子の友達は言います。それからしばらくして、その殺人鬼の疑いがある、新高(浅野忠信)が、何と、トミ子のいる職場に、やってきます。トミ子は驚きますが、親友の敵を討つことを密かに誓い、危険と知りつつも、新高に近づいていきます。しかし、彼とバスに同乗して仕事をするうちに、逆に、この危険な男に、抗うことのできない魅力を感じて、惹かれていってしまうトミ子。そして、トミ子は「運命」に挑んでいきますが…。★小嶺麗奈と浅野忠信の主演ふたり★この見事な映像に、ピタリとはまったのが、小嶺麗奈と浅野忠信のふたり。特に、小嶺麗奈の、じっと一点を見つめる瞳の強さや、きりっとした表情は、見ていてぞくぞくするほど美しいです。彼女を初めて見たのは、たまたま見ていた金八先生のドラマでした。この時のシリーズでは、彼女が、一人ずば抜けて目立っていた感があり、抜群の存在感を発揮していて、女優としての格の違いを、改めて感じます。しかし、この後は目立った活躍をしていないだけに、本当に残念。『ユメノ銀河』の2年前に主演した、同じく石井監督の作品『水の中の八月』でも、好演していただけに、もっと作品に出てほしいと思います。浅野忠信の、無口な、どこか危険な匂いのする、謎ありげな運転手役も、抜群の存在感があります。★「間」のもつ緊迫感★この作品は、「間」というものが、本当に効果的に用いられています。ふたりは何度か見つめ合うのですが、見つめ合う時間の長さといったら、半端じゃないです。見ているこちらが、「おいおい、なんかしゃべってよ!」と、ともすれば痺れを切らしてしまうほど、「間」が長いです。といって、だれているわけでは全然ないし、見ていて退屈にはならない。むしろふたりの間に漂う空気は、驚くほど張り詰めています。特に、小嶺麗奈の沈黙に秘められた「万感の想い」がひしひしと伝わってきて、こちらも、その「間」に引き込まれていきます。原作では、結末を割合きっちりとつけていましたが、映画の結末のつけ方の方が、個人的には、深い余韻が感じられて好きです。ある意味、観た人の判断に委ねられています。タイトルも、作品の幻想味と非常にマッチして良いと思います。夢野久作の「ユメノ」をかけて、また、同時に「夢」「夢幻」の世界観を現わして、いくつかの意味を重複させたような、なかなか深いタイトルです。ゆったりと物語は流れますが、濃密なドラマが、90分という時間に目いっぱい凝縮されて、張り詰めた空気の中繰り広げられていく、傑作です。ユメノ銀河 ◆20%OFF!<DVD> [KSXD-24487]
April 3, 2005
コメント(2)
-
リックサックを背負う透萌(ともえ)
透萌(ともえ)は、4月11日から、いよいよ幼稚園。と、いうことで、今日は、また幼稚園でつかうであろう、リックサックを買ってきました。キティちゃんのピンク色のリックサック。透萌はピンクが好きみたいです。写真は、リックサックを背負っての透萌。8ヶ月の葵(あおい)は、動く時は、よく動くようになってきました。寝返りをうったり、手足をばたばたさせて、「あびゃあぁぁぁ~」と奇声を発したり、髪はあいかわらず少ないままですが(^^;、元気です。透萌に、「あおいちゃんは、はげはげちゃんやねぇ~」と言われてしまってます…。「ともちゃんもな、あおいちゃんのように、はげはげのときが、あったんだから、人のことは、言えないよ。」みたいな事を、透萌には、言うのですが。
April 3, 2005
コメント(2)
-
「ナンバーの一致」( シンクロニシティの不思議) episode 26-2
(episode 26-1の続き)車のナンバープレートのシンクロニシティについて。前回のあらすじ。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※前を走っている車をみたら、まず、「4444」というナンバープレートを見ました。そして、4,5時間後くらいに、前の車のナンバーをふと見ると、今度は「5555」のナンバープレートが目に入りました。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※★シンクロニシティの連鎖★以上の、ちょっとした「シンクロニシティ」が、一日のうちに、起こったのですが、ぞろ目で、しかも、「4444」「5555」と数字の順番に見たので、何かあるのだろうか、と不思議な気持ちになったのは、確かです。そういう偶然もあるんだな、というくらいで、もちろん、それが何を意味するのかは、わかりません。そして、2,3日経ち、この「偶然の一致」も記憶が薄れつつあった頃、休憩時間に喫茶店で、本を読んでいたときに、再び、この事実を思い出させるような、更なるシンクロニシティが起こりました。読んでいた本は、『実際に起きた驚異の偶然の一致』(秋山眞人・二見文庫)この本の、221ページの小題が目に飛び込んできました。「ナンバープレート」の「2222」は「出会い」先の「4444」「5555」のナンバープレートのことは、頭の片隅に、残っていましたので、「おお!タイムリー!」と感じました。しかも、その4と5について書かれたページが、「222ページ」。ぞろ目が、よっぽど好きみたいです。少し引用してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「どういうわけか、街なかですれちがう車のナンバープレートをふと見ると、同じ数字が四つ並んでいるというシンクロニシティがよくある。おもしろいのは、冷静に観察してみると、その数字が、それを見たときの自分の精神状態とシンクロしているのである。他の数字がシンクロする場合もあるが、走っている車のナンバープレートが、いちばん端的に、怖いくらいに一致するのである。」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「シンクロニシティ」は、自分の内面の波動と、外の世界、あるいは、他の人や物質との「共鳴現象」である、とすれば、この数字のシンクロニシティは、なかなかおもしろい現象であると思います。★1~9の数字の象徴するもの★ 数字は、それぞれ、象徴的な意味があるようです。以下、せっかくなので、おおよその意味を本書から引用して見ます。●「1111」…今まで積み重ねていた事が、すべて崩れてしまって、初心に返らざるを得ない、本当に空っぽの状態の時にこのナンバーが来る。●「2222」…新しい情報を含めて、何かと新しい「出会い」があるとき。逆に自分の感情の状態が悪いときにそのナンバーを見ると、それは「離別」の暗示である。●「3333」…家族間の愛情、または異性間の愛情など、なんらかの愛情面で、激しい焦りを感じている時。さて、わたしの場合、問題の数字「4444」と「5555」です。●「4444」…なんとなくほのぼのと幸せな気分でいる時。●「5555」…これから何かに向かおうとしているとき。今やっていることがダメで何かに移行しなければならないとき。●「6666」…愛情に満たされている時。●「7777」…なんらかの上下関係、または権力の闘争が待っているとき。易でもおなじことがいわれている。「七」というのは本来、「三」と「四」という違う性質の数字の融合体で、「急転」「激突」を表わす数字なのである。だが、いい感情の状態でそれを見た場合には、文字通り、ラッキーセブンで、物事がよい結果に終る。●「8888」…よい感情で思っていたことはよい方向にゆっくりと変わっていく。「八」という数字は、ほんとうに末広がりなのである。●「9999」は統合。「9」は元々、物事が統合される、「括られる」数字である。物事が、まとまる、終わる、締めくくられる。さらに車のナンバーに限っていうと、「1010」「3838」など対称番号になっているものを続けざまに見るのは、あまりいいときではない。また、「1881」「3113」など、山番谷番が来る時も、あまりよい状態ではない。感情的にあまり安定していないのだ。そして、本書には、車のナンバーのシンクロニシティを徹底的に研究した、関西の女性の見解も載せています。上記とやはり、似ていますが、一応書いておきます。「1」…初心に戻る「2」…対立と離別「3」…焦り「4」…幸せ「5」…プラスもマイナスもない状態「6」…愛情面に満たされる「7」…上司から怒られるとき、または下から突き上げが食う時。「8」…末広がりか八方ふさがり「9」…統合★最後に★「4」は幸せ。ほのぼのと幸せな気分。「5」はプラスもマイナスもない状態。何かに向かおうとしているとき。「4444」「5555」のプレートを見たときの、自分なりの心理状態を表わしてみます。「4」は休日で、娘もいて、のんびりした気分になっていたでしょうし、「幸せ」の気分だったかな、と。「5」は、今の仕事を、もっと飛躍させたいという想いを、このところ、確かにずっともっていたことなので、それが、出たかな、と。まあ、いずれにせよ、「4444」と「5555」のナンバーを見た「シンクロニシティ」が、まず起こり、次に数日後、たまたま、数字の意味について書かれた本を、読んで、「4」と「5」の持つ意味について、知ることができました。
April 2, 2005
コメント(0)
-
「ナンバーの一致」( シンクロニシティの不思議) episode 26-1
数字の「シンクロニシティ(偶然の一致)」って、多かれ少なかれ、誰にでも体験はあるのではないでしょうか。ある数字が、頻繁に目に付いたり、自分の住所の番地や部屋番号、電話番号、郵便番号などに、共通する数字が使われていたり、自分の誕生日の時刻をよく目にしたり、あげればキリがないですが、そういった数字の一致。果たして、すべての現象において、そこに意味があるのかまでは、はっきりいって疑問ですし、むしろ分からない事のほうが多いかもしれません。数は「数霊(かずたま)」ともいうように、数字には、「言霊」同様、ある種のパワーが宿っていることは十分考えられる事です。数字の織り成す偶然は、時として、全くの偶然にも見えますが、それでいて不可思議で神秘的でさえあります。仕事柄、商品の配達などで、車に乗ることが多いのですが、目に入るともなく入ってくるのが、車のナンバープレート。そこには、4桁の数字が並んでいますが、今回は、この数字に関する、シンクロニシティ。★3,6,9の不可思議な一致★私は、個人的に、ふと見ると、3、6、9の数字を含んだ、ナンバープレートが、目に入ってくることが、多いような気がします。ただ、これは、私自身が、3,6,9は369(弥勒・ミロク)に通じる、という事を意識しているから、そう感じるだけかもしれません。順番は、この順の「369」という訳ではなく「936」「639」だったりします。要は、4桁の中に369が順不同で含まれている、という事です。車のナンバーだけでなく、デジタル時計なども同じでしょうが、パッと目にした時、よく目にする、あるいは印象に残るナンバーが、この「3、6、9」を含む数字です。「9時36分」とか「6時39分」とか。そういえば、皇太子殿下と雅子さんの結婚式は、1993年6月9日でした。これも、199を除くと、見事に「369(ミロク)」となるから、おもしろいですし、何か意味深な日付です。★ナンバープレートの不思議★話がそれました。少し前に、会社が、休みの時、自家用車に乗っているときでした。車の運転の途中で、前の車のナンバープレートを何気なし見たら、「4444」と言う数字、いわゆる、ぞろ目でした。「4のぞろ目かあ。あまり縁起良くないんだろうか。」とその時は、思いました。それだけだったら、そのまま、忘れていた出来事だったかもしれません。しかし、その日のうちに、4,5時間後だったでしょうか、また何気なく、前の車のナンバープレートをみたら、今度は、「5555」のぞろ目。「え?」と、この時はびっくりしました。確率的には、どのくらいかは、予想がつきませんが、しかし、それにしても4桁のナンバープレートで、一日2回、ぞろ目を見るというのは、そんなに高い確率ではないはずです。しかも、「4444」に続いて「5555」と律儀にも、順番になっています。「これには、何か意味があるのだろうか…」とその時は思いました。しかし、意味など分かるはずもなく、「シンクロニシティ」かな、くらいに思っていました。結局、その日は、少し心にひっかっかりを覚えたまま、過ぎ去っていきましたが、まさか、その2,3日後に、このことで、ひょんなことから、回答をもらう事になるとは、思ってもみませんでした。 (epiodp26-2へ続く)
April 2, 2005
コメント(3)
全33件 (33件中 1-33件目)
1
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月11日分)
- (2025-11-25 00:32:59)
-
-
-

- 読書
- 選ばれる人の100の習慣 26 情熱は言…
- (2025-11-24 21:00:05)
-
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- お絵描き成長記録 DAY3
- (2025-11-22 19:22:48)
-







