2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年09月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
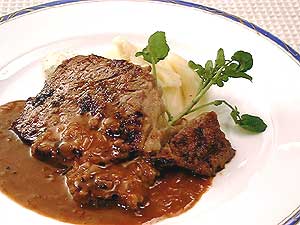
音楽家の名前を冠した料理/コスモス
「クラシック音楽エピソード」 シャリアピン・ステーキ作曲家の恋のエピソードとそれにまつわる曲を書き綴っていますが、今日はそれも一休みして胃袋を刺激するような話題はいかがでしょうか。料理に名前を付けるのは古今東西どこでも同じですが、中には変わった名前の料理があります。まるでこじつけのような類のメニューもありますが、今日紹介しますメニューは演奏家と作曲家の名前をつけられたもので、それぞれに由来のあるものです。シャリアピン・ステーキロシアの歌手でフェオドール・シャリアピン(1873-1938)という有名なバス歌手がいました。 盤で言うとSP時代の人です。 私も残された写真でしか知らない歌手で、15年ほど前に大阪のSPコレクターのおうちを訪問した際にムソルグススキーの「蚤の歌」を聴かせていただいた経験が、唯一のシャリアピン体験で後にも先にもこの歌手の声を聴いた体験はありません。そのシャリアピンが1936年(昭和11年)に来日公演を開催していますが、その折に東京の「帝国ホテル」に滞在したそうです。 彼はその頃歯が丈夫でなかったので、肉料理を食べるのに苦労していたそうです。日本の肉は柔らかくて旨いのですが、それでも歯に答えるのでホテルのレストランに特別注文をしました。 シャリアピンはとても喜んだそうです。 以来このステーキは彼の名前を冠して「シャリアピン・ステーキ」として帝国ホテルの自慢のメニューとなり人気を博して今日に至っているそうです。このメニューは欧米にも紹介されて人気を呼んでいるステーキ・メニューの一つとなっています。レシピ(4人分)リブロース肉・・・520g玉ねぎ・・・1個クレソン・・・適宜(マッシュポテト)じゃがいも(男爵)・・・1個牛乳・・・40cc生クリーム・・・10ccバター・・・10g塩・・・各少々(シャリアピンソース)赤ワイン・・・80cc玉ねぎ・・・120gデミグラスソース・・・80c生クリーム・・・40ccバター・・・40g塩こしょう・・・少々(わさびソース)マヨネーズ・わさび・・・各60g作り方 (1)リブロース肉を切り分け、すりおろした玉ねぎに1時間くらい冷蔵庫で浸ける。 (2)浸け終わったら、きれいに玉ねぎを除き、両面きれいに焼く。 (3)焼き終わったら、肉を取り出して、赤ワインを加える。 (4)玉ねぎ・デミグラスソース・生クリーム・バターを加え、塩こしょうで味を調える。 (5)わさびソースは、わさびとマヨネーズを混ぜ合わせる。 (6)マッシュポテトは、ジャガイモをゆでて皮を剥いてつぶし、牛乳・生クリーム・バター・ナツメグ・塩を加えて混ぜ合わせる。 (7)マッシュポテトをしいた皿に、シャリアピンソースをしいて肉をのせ、わさびソースをのせ、クレソンを添えたらできあがり。 私は学生時代に一度だけ東京・四谷のステーキ・ハウスで食べたことがありますが、確かに肉はとても柔らかい美味しい料理でした。またイタリアの作曲家ジョァッキーノ・ロッシーニ(1792-1868)は、美食家としても知られており自分の発案で色々なメニューを考えて、それらが現代でも「ロッシーニ風・・・・・」という名前で残っているがあります。 それはまた次の機会に紹介したいと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 コスモス
2007年09月30日
コメント(6)
-
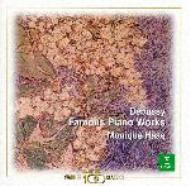
ドビッシー~愛の遍歴/イヌタデ
「今日のクラシック音楽」 ドビッシー~華麗なる愛の遍歴クロード・ドビッシー(1862-1918)はフランスの印象派を確立した作曲家で、生まれも没年もほぼグスタフ・マーラー(1860-1911)と同じ時期に活躍した人です。彼の恋愛遍歴を辿ってみるとまさに「手当たり次第」という様相を呈しています。 しかもその恋愛によって二人の女性が自殺を図った(未遂)という、血なまぐさい事件もあります。 フランスやスペイン、ポルトガル、イタリアなどのラテン民族は情熱的とも言われていますから、恋愛についても盛んな面があるのかも知れません。多彩な恋愛・女性関係があったと言われていますが、かの有名な「牧神の午後への前奏曲」は印象派として確立した音楽ですが、その頃には生活を共にする女性がいました。 ガブリエル・デュポンという女性でドビッシーをしっかりと支えた人だそうです。 「牧神の午後への前奏曲」の初演が1894年ですからその頃の交際でしょう。デュポンと同棲をしながらテレーズ・ロジェと恋愛関係となって婚約までしています。 この話はデュポンとの同棲が発覚して破談になっています。ところが、まだテレーズとの恋愛・婚約・破談の残り火がくすぶっている1895年に、今度は別の女性に結婚を申し込んでいたそうです。 さすがにデュポンは心を痛めて、ピストルで自殺を図ります。 1897年のことです。 一命はとりとめて彼女はその後1945年まで生きながらえたそうです。ドビッシーの女性遍歴はまだまだ続きます。 1899年にはロザリー・テクシェという女性と正式に結婚式を挙げています。 ところがこの結婚生活での蜜月は5年もたないはかないものでした。 彼のいつもの病気ー恋愛遍歴ーがまた始まったのでした。今度の浮気の相手は銀行家バルダック夫人のエンマ。 この女性もなかなか艶満家のようでガブリエル・フォーレともドビッシー以前に関係していた人でした。二人はお互いが家庭を持っているので恋愛につきものの情事が想いのままにならない。 二人は思い切って駆け落ちという手段を選びます。 この事件でドビッシーの妻ロザリーは相当な心痛とショックが重なります。 あれほど熱いを愛を語ったドビッシーが他の女性、それも他人の妻と駆け落ちしたことにショックを受けて、ピストル自殺を図ります(未遂)。ロザリーは愛情のみならず人生に疲れ果てたと言われています。エンマの方も結局バルダック氏と離婚となり、ドビッシーもすでにロザリーの許へ帰る意思はなく、双方の離婚が成立します。 1905年のことでした。 同年ドビッシーはエンマと結婚して、その年にクロード・エンマという娘が誕生しています。 この娘は生涯「シュウシュウ」と呼ばれたドビッシーの愛娘となったのです。 しかしこの事件でドビッシーはサティなどの多くの友人を失ってしまいました。やっとドビッシーに子供ができて彼は嬉しく、有頂天になりました。 そこで生まれたのがピアノ曲「子供の領分」です。 1906年から1908年に書かれています。 子供がピアノを弾いて遊ぶという音楽ではなくて、かつて子供だった大人が懐かしげに子供時代を憧憬するような内容の音楽となっています。 音楽は真に子供心に帰って、子供が感じる夢や感覚の世界を描いています。「グラドス・アド・パルナムス博士」「象の子守歌」「人形へのセレナード」「雪は踊っている」「小さな羊飼い」「ゴリウォーグのケーキウォーク」これら6曲で構成されたピアノ曲集で、印象派音楽の粋を集めてような瑞々しい感覚で描かれており、やっとドビッシーの愛の遍歴が終わったということを想起させる音楽です。愛聴盤 モニック ハース(ピアノ)(ワーナーミュージック WPCS21080 )詩的な情緒に溢れたほっとするようなピアノタッチの演奏です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 イヌタデ
2007年09月29日
コメント(8)
-
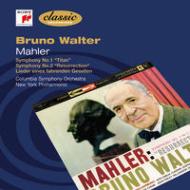
続・マーラーの失恋~さすらう若人の歌
「今日のクラシック音楽」 マーラーの失恋から生まれた歌曲集「さすらう若人の歌」マーラーは交響曲だけでなく、歌曲においても素晴らしい作品を残していますが、この「さすらう若人の歌」もその一つです。 約1年かけて書かれたこの4曲の連作歌曲はマーラーの失恋の思い出として書かれており、彼の音楽の原点とも言われている歌曲集です。詩はマーラー自身が書いておりマーラーの深い苦悩が刻みこまれていて、この恋によって受けた心痛のほどがよくわかる歌となっています。 その失恋の相手は女優のヨハンナ・リヒター。 マーラーはこの曲について語っています。 「連作歌曲を書いたが、逆境に出会った若者が世に出て行き、さびしく放浪をつづけるさすらい人を語った歌です。 これはヨハンナ・リヒターに献呈しています」と。マーラーはこのヨハンナ・リヒターと結婚まで思いつめていたと文献では語られています。 しかし、どの程度の「愛の進捗」があったのか真実は闇の中で、以前として何もわからないのが今のところ真実だそうです。 残された歌曲集の詩だけで想像すれば、とても一方通行の片想いではないと想像できます。 この恋の深い闇に包まれたマーラーとヨハンナ・リヒターだけが知っている真実が語られているように感じます。この歌曲集は当初6曲から構成されていたのですが、のちにマーラー自身によって改訂されており現在は4曲となっています。第1曲 「いとしい人の婚礼の時」から、マーラーの深い絶望感が語られています。 「悲しみの日」とか「泣く」、「逃げる」とかでその悲しみと絶望に打ちひしがれた心情を語っています。第3曲 「灼熱の燃える剣が」では、「黒い棺に横たわり、二度と目が開かなければいい」と叫んでいます。第4曲 「いとしい人の二つの青い眼」では、「彼女の二つの眼は私をさすらいの旅へと立たせた」と深い救済の願いが込められており、まさにマーラー音楽の原点かと思わせるような音楽で全曲を閉じています。この恋愛のあとマーラーはヴァイオリン奏者ナターリエ・バウアー・レヒナーと知人の家で知り合い、深い親交を結ぶ交友関係を築くのですが、彼女に対するマーラーの心は友情と信頼という関係を超えることなく終わっているようです。 それはナターリエの回想録に書き留めています。 むしろマーラーが21歳年下のアルマと結婚することを知って、深い心の傷を負ったのはナターリエの方だったようです。 マーラーとの結婚願望があったナターリエは言葉に出さずに、敬愛する人を陰から支える立場を選んでいたのでしょう。そうしてマーラーは21歳年下のアルマ・シントラーと1901年に知り合い、結婚への道を歩んで行ったのです。「さすらう若人の歌」 愛聴盤ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団 ミルドレッド・ミラー(Ms) (SONYクラシカル 5160252 1961年録音 海外盤)ワルターの音楽性は「歌う」ことにあります。 とても柔和な表情がベートーベンやブラームス、シューベルトに出ています。 ここでも夢破れた青年の表情を情感豊かに、柔和な表情でいつくしむような情緒で歌いこんでおり、ミラーの少し暗さのある表情づけが素晴らしい演奏となっています。 得意の第1、第2番のマーラーの交響曲がカップリングされており、マーラー入門にぴったりのディスクです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「その後のマーラー」1901年にマーラーとアルマは知り合います。 アルマは作曲家ツェムリンスキーの弟子でした。 当時アルマは絶世の美貌を誇り、ウイーンの芸術家の憧れであったようです。 マーラーと知り合う前のアルマはツェムリンスキーを愛していたようですが、後の彼女の恋に遍歴を見ますと芸術家に魅かれるという性癖があったようです。 アルマにとってマーラーは力強い男性・芸術家であったようです。 二人は1902年に結婚式をを挙げています。 その時アルマは妊娠2か月だったそうです。 今流の「できちゃった婚」でした。しかしアルマの生来の芸術家に魅かれるという性格は直らずに、結婚しても他の芸術家との浮名を流す女性でした。 ピアニストとの恋愛、そして建築家ワルター・グロピウス(現代建築に大きな影響を与えた人物と言われています)へと心は移っていきます。アルマのこうした自由奔放な性格がマーラーの心は結婚生活だけでなくて、「人生」そのものに懐疑的となる影響を与えたようです。妻の不倫を知ったマーラーにとって、「さすらう若人の歌」で見せた深い苦悩は結婚生活でも繰り返されたのです。 マーラーの音楽に書かれている厭世感や、「死」と隣合わせた苦悩は一層深いものになっていったことは、容易に想像されます。 交響曲第9番や未完の第10番などはその最も顕著な例かも知れません。 建築家グロピウスとのアルマの恋愛を知ったマーラー。 このときマーラーは50歳、アルマはまだ30歳を過ぎたばかりの女盛りであったことは、二人の生活に影を落とす要因にでもばったのでしょうか。こうした事実を知って第9番などを聴くと、まるでマーラーがのた打ち回っているような感じを受けます。 「悲しみ」と「苦悩」「絶望」という心情の中でフロイトに精神診断を仰いだというエピソードは、マーラーの心の苦しみを如実に表しています。マーラーの死後、1915年にアルマはグロピウスと結婚してマノンという娘が誕生します。 その娘が18歳で亡くなった時に、彼女を可愛がっていた作曲家アルバン・ベルグが嘆き悲しんで書いたのが「ヴァイオリン協奏曲」という有名なエピソードがあります。アルマには結婚という定住はなかったようです。 グロピウスと離婚したアルマは、マーラーの生前からの恋の相手であった作家と3度目の結婚をするという遍歴を重ねています。「疲れ果てた孤独な魂に 永遠の救いを求めて 今こそ故郷に帰って行くのだ 私はその時を待ち受けている」これは交響曲「大地の歌」~第6楽章「告別」で歌われていますが、まさにマーラーの心情を的確に表現した言葉でしょう。1911年、生涯を通じて女性との「愛」に苦しんだグスタフ・マーラーは51歳の命を閉じています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 秋の鰻掴み
2007年09月28日
コメント(2)
-

マーラーの失恋~さすらう若人の歌(1)
「今日のクラシック音楽」 若きマーラーの失恋~さすらう若人の歌グスタフ・マーラー(1860-1911)はボヘミア出身の指揮者・作曲家として近代音楽史上に燦然と輝く人で、11曲(大地の歌を含めて)の交響曲や「さすらう若人の歌」、「亡き子をしのぶ歌」などの歌曲集を書いて、後期ドイツロマン派の残照とも呼べる音楽を確立しており、1980年代には日本でもマーラー・ブームとでも呼べる現象を起こしており、今なおその音楽は古典派のそれと同じくらいに愛され続けている作曲家です。またウイーン宮廷歌劇場の指揮者と絶大なる権力を誇り、近代指揮者の方向を定めたとさえ言われるほどに指揮者としての名声も確立しています。一貫してマーラーの音楽は素直さや明快晴朗な響きがほとんど聴かれず、まるで屈折したプリズムのような光と影を宿す、どこか世紀末的な退廃さえ感じられます。 悲劇的情緒と心の影を醸し出し、深い苦悩を刻んだような憧れにも似た風情の音楽を数多く書き残しています。その理由はマーラーがその生涯を通じて心に落とした「愛の苦悩」ではないでしょうか。乱暴な言い方をすれば彼は生涯理想的な愛ー信じて信頼される相互愛ーに恵まれなかった人ではないかと思います。 残された彼の写真を見ても非常に神経質そうな様相を呈しています。彼のどの写真からも「ふくよかさ」「円満」と言った「正」の表情をうかがうことが出来ず、霊能者なら「何かに執りつかれている」と言うような苦悩の表情ばかりが目立ちます。それは「満たされない愛」が生涯つきまとったからだと思います。 その「負」をはねのけしてしまう資質が神さまから授からなかったのか、それとも「そうして生きよ、そうして人々に敬愛される音楽を創造せよ」と神さまから命じられたのか、少なくとも私にはマーラーの音楽を聴いて感動はすれども、心を慰められる音楽ではないと感じています。 交響曲の中にはー第1番「巨人」、第2番「復活」や第3番、第4番は例外としてー特に悲劇性が色濃く刻まれているように感じます。残された音楽だけでマーラーの心象を追うことは難しいと思います。 この項を書くにあたって図書館などで文献を調べてみました(ブログ再開後の作曲家の恋とそれにまつわる音楽はほとんどそうした文献での調べによるものですが)。そこに浮かび上がった3人の女性。1. ヨハンナ・リヒター2. ナターリエ・バウアー3. マーラーの妻 アルマ・マーラーマーラーを取り巻くこれら3人の女性が(2.のナターリエは例外として)マーラーの生涯に深い心の傷を刻みつけたのでしょう。(この項つづく)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 イヌホウズキ
2007年09月27日
コメント(2)
-
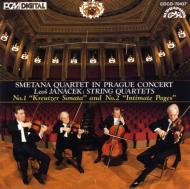
老いらくの恋~ヤナーチェック
『今日のクラシック音楽』 晩年の人妻への恋~ヤナーチェック 弦楽四重奏曲第2番「ないしょの手紙」異性を愛するようになると自分の恋心を言葉にして話したり、電話で伝えたり、メール文章や手紙で心境を吐露したくなることは誰もがすることですが、その恋心を音楽に表すのは作曲家の得意とすることです。 チェコの生んだ作曲家ドヴォルザーク、スメタナと共に名を残すレオシュ・ヤナーチェック(1854-1928)もその中の一人です。 それもはるかに年下の他人の妻への「老いらくの恋」だったのです。ヤナーチェックはオペラ、室内楽、ピアノ曲、声楽などに多数の作品を残していますが、何と言っても彼の弦楽四重奏曲は音楽史に燦然と輝く傑作で、今尚、演奏会や録音に採り上げられている人気のある室内楽作品です。2曲ある弦楽四重奏曲のうち、第2番がその「恋心」を表現した音楽史上稀有な作品です。 ヤナーチェックが晩年になって心を許し、恋した気分を4つの弦楽器に託してかいた「恋文」で、彼女の名前はカミーラ・シュテッスロヴァという、ヤナーチェックより38歳年下の骨董商の人妻でした。 彼はこのカミーラに熱烈に恋をして、彼女宛に書いて送られた手紙が700通以上あると記録に残っているそうです。まさに「老いらくの恋」だったのでしょう。ヤナーチェックは、40歳代で二人の子供に先立たれて、心の支えを失くしていたようです。 妻とは趣味も生き方も違っていたようで、夫婦の仲にすきま風が吹くばかりだったのでしょう、子供に死なれてますます夫婦仲がうまくいかなくなったときに、この38歳年下のカミラとの「恋」が心の支えであり、芸術への想像力の高まりを支えてくれたのだと思います。二人の恋愛はとても世間に戸を立てることができず、世間に知れ渡ってしまったのですが、ヤナーチェックはお構いなしだったそうです。 カミラは控えめな返信を書いていたそうです。またカミラの家庭はこの恋愛で夫婦仲が悪くなることもないようでした。自作の初演時には自分の隣に、妻のズデンカではなくてカミラを座らせたというのですから凄い人だと思います。700通以上書いた手紙にも満足せず、いやまだ恋情を吐露しきれずに、また音楽にすることで「永遠の恋心」をヤナーチェックは残したかったのでしょうか? 弦楽四重奏曲第2番は、最初は「ラヴ・レター」というタイトルを付けたそうですが、あまりにも自分の心の中を覗かれるのが嫌で「ないしょの手紙」というタイトルに変えたそうです。曲は4楽章構成で、弦楽4声での非常に引き締まった楽想で、彼の「恋」が本物であると頷ける表現と、自由・闊達に曲想が表現されている音楽です。約25分間にヤナーチェックの「恋心」「恋情」が書き込まれている曲です。ヤナーチェックは、この「ないしょの手紙」を完成した半年後の1928年の8月12日、74歳の生涯を閉じています。恋するカミラの子供が迷い子になり、その子を高齢と雨中にもかかわらず探しに行ったために、肺炎にかかったのが死因と言われています。 その間ヤナーチェックが息を引き取るまでカミラは看病を続けていたそうです。愛聴盤 スメタナ弦楽四重奏団(スプラフォン原盤 DENONレーベル COCO70437 1979年10月10日ライブ録音)このCDは何かと話題になっていますDENON CREST 1000シリーズの中の1枚で、1,000円でお手頃な価格で現在求め得る盤です(旧COCO75988)。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日のクラシック音楽」 ツリフネソウ
2007年09月26日
コメント(0)
-
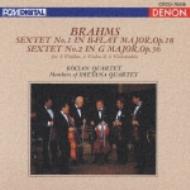
婚約破棄~ブラームス/時計草
「今日のクラシック音楽」 婚約を破棄して生まれた名曲~ブラームス9月23日の日記でブラームスとクララ・シューマンの禁断の愛について書きましたが、実はその後ブラームスには結婚を約束した女性が存在していたのです。1856年7月29日の恩師シューマンの死は、ブラームスのクララ・シューマンへの愛が変わっていきました。そしてシューマンの死後3か月で、あおれほど献身的に支えたクララとその家族の許を離れたブラームスは、やがて一人の女性との恋に身を焦がします。その女性はアガーテ・フォン・ジーボルトでした。日本に来たこともあるシーボルト一族の家系です。 1858年の夏、ブラームスは友人の家でアガーテと出会い恋に落ちています。 このあたりはまだクララへの愛が残っているように思うのですが、彼自身の心の中で友情と信頼というクララへの接し方が変わっていたのかも知れません。アガーテは聡明な女性で美しい声を持っていた女性だそうです。 そして彼女を紹介した友人はブラームスとの間をとりもつこととなって、アガーテはブラームスの歌曲を歌うなどして、二人の交際は蜜月へと導かれて、ブラームスも恋心を募らせたようです。そして二人は結婚を約束して、ブラームスは結婚指輪を贈るのです。 ところがブラームスはアガーテ宛てにに手紙で一方的な婚約の破棄を伝えています。 それは誰にも充分に理解できない破棄でした。手紙でブラームスは、「あなたを愛しています・・・・・しかし私は束縛されるわけにはいかないと」(アガーテ回想録)と書き記していたそうです。 仲をとりもった友人も憤りました。 アガーテは回想録で「いかなる犠牲を払ってもブラームスと結婚したかった」と述べています。クララへの決別と同じ理由かも知れません。家庭内に収まることがブラームスの音楽の天性が伸びなくなってしまうと思ったのでしょうか。1958年の出来事でした。1865年、婚約破棄から17年の歳月が流れて、ブラームスは「弦楽六重奏曲第2番」を完成しています。 この曲の第1楽章で第1、第2ヴァイオリンの部分にA-G-A-D-H-E(DはTの音名化です)という音が奏されています。 アガーテです。 これが3回も繰り返されています。後に人はこの曲を「アガーテ六重奏曲」と呼んだそうです。ブラームス自身がこの曲について「これで私の最後の恋愛から解放された」と述べているそうで、この曲はアガーテへの愛情告白ではなくて思い出として書き残した、というのが定説になっているようです。婚約を一方的に破棄したブラームスは形を変えたクララへの愛情(信頼と友情)を抱きながら、またクララのもとへと戻っていくのでした。それはクララの娘がブラームスに宛てた電報でこのあたりのシューマン家との交際のいきさつはわかると思います。電報を受け取ったブラームスは、約40時間を費やしてクララの亡骸へとたどり着き、埋葬直前に永遠にクララとの別れを告げたのでした。心の中でクララへの愛を断ち切れなかったのか、それとも天職を全うするために家庭・家族を不要と考えたのか、愛してくれて結婚まで約束したアガーテを断ち切ったブラームスの本心は何だったのか、芸術家の恋と結婚の難しさを考えさせられる出来事です。アガーテとの思い出が込められたと言われている、この弦楽六重奏曲はブラームスの渋い室内楽とは一線を画すような、流れるような流麗な旋律に満ちた美しい音楽です。愛聴盤 コチアン弦楽四重奏団+スメタナ四重奏団メンバー(DENON CREST1000 COCO70438 1987年録音)第1番とのカップリングで価格も1,000円という求め易い廉価盤です。 チェコを代表するコチアン四重奏団にスメタナ四重奏団のメンバーが加わり、流麗な演奏を繰り広げています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 時計草
2007年09月25日
コメント(2)
-
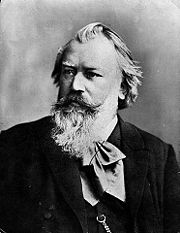
残照の音楽~ブラームスの恋と交響曲第4番
「今日のクラシック音楽」 生涯変わらぬブラームスの恋 私に誰かが「一番好きな音楽と作曲家は?」と問われると、ヨハネス・ブラームス(1833-1897)とすぐさま答えるかも知れないとても好きな音楽であり作曲家です。彼の音楽を好きになったきっかけは中学3年生の時でした。 登校前の朝食では私はいつもラジオのNHK番組ー番組名は明確に記憶していませんがーで放送されるクラシック音楽を聴いていました。 ある日、私の心に飛び込んできたとてつもない大きな旋律に、朝食を摂るのも忘れて聴いていました。こんな巨大な音楽を聴いたのはベートーベンの交響曲第9番以来でした。 ブラームスの交響曲第1番ハ短調の第1楽章の冒頭の音楽でした。 親から「遅れるよ!」と叱られながらも第1楽章だけを聴き終えて、あわてて家を飛び出して学校に向かいました。以来この第1番全曲を聴きたいという願望で月日を過ごし、やっと高校1年生の時にモノラルLP盤(エドアルト・ヴァン・ベイヌム指揮 アムステルダム・コンセルトヘボー菅)を1500円で買って聴きこみました。 そしてブラームスファンとなりました。 以来今日まで彼の音楽に傾倒したままで日を過ごしてきました。ブラームスは38歳でウイーンに定住しています。 ウイーンの秋は落ち葉が舞い落ちて美しい風情をしっとりとした趣きで人を安らいだ気持ちにさせてくれる街です。 枯葉を踏みながら自然を愛したブラームスは散歩を楽しんでいたのでしょう。そうした風景を思い起こさせる音楽が彼の曲にあります。どこかほの暗く、重厚でありながら叙情性をまき散らし、流麗に豊かに鳴り響き、まるで秋の輝きとその影を伴ったような、まるで夕陽の残照のような輝きと哀愁を感じさせる、そんな魅力に富んだ音色と響きの音楽が、私を虜にしています。ブラームスの曲の中で1曲だけ選べと言われると躊躇なく交響曲第4番を挙げます。 この曲はブラームス52歳(1885年)に完成していますが、この頃の彼には「孤独」がひしひしと忍び寄っており、ブラームス自身もそれを感じていたのでしょう。ブラームスは生涯を通じて独身を貫き自分の家族を持たなかったので、その意味でも晩年は孤独であったろうと容易に想像できます。 この頃には押しも押されぬ「世界の大作曲家」としての地位を築いていましたが、自分を支えてくれる妻や子供もなく、それに加えて彼のまわりの人たちが他界していくのを見守るブラームスには「人生の秋」「人生のたそがれ」が、影のようにまとわりついていたのでしょう。第1楽章冒頭の「ため息のモチーフ」と呼ばれるヴァイリンの旋律が如実にそれを物語っているように感じてなりません。 これこそがブラームスの「人生の秋」であり、孤独をしみじみ味わう諦観のような気がします。1853年にブラームスはシューマン夫妻の自宅を戸を初めて叩き、シューマン家との交際がはじまりました。 この時から44年間にわたるシューマンの妻・クララ・シューマンへの憧憬が始まったのかもしれません。今でもブラームス直筆の手紙が数多く残されており、クララへの愛がはっきりと書かれているそうです。 とりわけシューマンが精神に異常をきたしてライン河に身を投じた頃から(1854年)、献身的にクララを支えており、手紙の冒頭の「敬愛なるクララへ」から次第に「恋愛感情」に変わり、とうとう「愛するクララへ」となっています。シューマンが亡くなって(1856年)からは7人の子供を抱えたクララを励まし、精神的な支えにもなっていたようですが、クララからはとうとうブラームスを受け入れる言葉を聞けなかったようです。 クララの日記にはこう記されています。「子供たち、あなたがたの父シューマンははブラームスを愛し、尊敬していました。ブラームスは、悲しみを共に感じてくれる親友として、私たちの前に現れ、私の心を力のかぎり励ましてくれたのです。私は、彼の精神の新鮮さ、驚くべき才能高潔な魂を愛しています。ブラームスとの愛情は二つの魂の最も美しい調和なのです。 ‥‥愛する子供たちよ。この母の言葉を信じ、彼の友情を感謝の心で受けとめてほしいのです。 人々は、私たちの愛情を非難したり、話題にしたりしていますが、そんな嫉妬心に、決して耳を傾けたりしてはなりません。彼らには私たちを理解する心がないのですから」しかし、ブラームスはクララの許を去っていきます。 それは作曲家としての自分の天命を果たそうとする責務のような想いからなのか、シューマンが亡くなって残された家族を引き受けるという現実に直面して、天職を危うくすることに危惧を感じたのか、シューマンの娘オイゲン・シューマンがこう書いています。「ブラームスは無情にも、突然去って行きました。 果たさなくてはならない自分の“天職”と私の母に対する“愛情への献身”。 この両立は不可能であると、彼は悟っただろうと思う。 ── が、私たちのもとを離れるとき、彼は自分自身と激しく闘い、自責の念にかられたにちがいありません」と。それが1856年10月、シューマンの死後3か月経った頃でした。ブラームスが自ら「孤独への旅」を選んだのでしょう。そして1896年にブラームスに1つの電報が届きました。 クララの娘が送った電報で、「母が永眠しました」と。約1年後の1897年4月3日、ブラームスはようやく「孤独な旅」を終えてその生涯を閉じたのです。私はこの交響曲第4番に込められたブラームスのメッセージは、クララと添い遂げられなかった彼の孤独と寂しさ、人生のたそがれを歌っているような気がしてなりません。 それも年を重ねるごとに感じ始めたことなのです。愛聴盤1.クルト・ザンテルリンク指揮 ベルリン交響楽団(カプリッチオ原盤 10600 1990年録音)↓ザンテルリング重厚で、どっしりと落着いた構えで、旋律を遅めのテンポでじっくりと歌わせ、弦楽器の響きが古色ががった、いくぶんくすんだような響きで、その上にまるでほどよくブレンドされたような管楽器が柔らかくかぶさり、ブラームス特有のロマンテイックな美しさを味わえる演奏・録音です。 私の一番好きな演奏です。2.オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団(EMI レーベル 562760 1957年録音)↓クレンペラー3.ジョン・バルビローリ指揮 ウイーンフィルハーモニー(パレ原盤 EMIリマスター Diskyライセンス発売 HR708222)↓バルビローリ4.朝比奈 隆指揮 新日本フィルハーモニー(フォンテック FOCD9206/8 2001年3月19日 サントリーホール ライブ)↓朝比奈 隆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 ニラの花
2007年09月23日
コメント(12)
-

四季に聴く音楽
「今日のクラシック音楽」 それぞれの季節に聴く音楽作曲家の恋と名曲について書いていますが、今日はヨハネス・ブラームスとクララ・シューマンの恋愛について書くつもりでしたが、まだ明確な構想が出来上がっておらず、また調べたいことも残っていますので、あす以降に掲載しようと思っています。今日は四季のある日本でそれぞれの季節にふさわしい音楽ってなんだろうと考えていましたので、それについて私の好みを書いてみようと思います。1. 春春はとても輝かしい気分になれる季節です。 野原では色々な草花が花を咲かせ、花や木々の香りも匂い立つような風情があります。 萌える季節とでも言うのでしょうか、まるで大地から萌え立ってくるような気分を感じます。そんな季節に聴く音楽と言えば、私が真っ先に聴くのがベートーベンのヴァイオリン・ソナタ第5番「スプリング」です。 第1楽章の主題はまるで春の喜びを歌いあげているような気分です。 それにハイドンの弦楽四重奏曲第63番「ひばり」。 これも第1楽章の主題がまるでひばりが飛んでいくような旋律で、清新な春の訪れを思い起こさせます。サンサーンスのヴァイオリン協奏曲もいいですね。 特に第2楽章は春独特の夕暮れの甘い香りが伝わってくるような響きがとても好きです。ベートーベンやシューベルトの初期の交響曲なども春によく聴く音楽で、若い日の大作曲家の新鮮な息吹に満ちたこれらの交響曲も春に似つかわしい音楽として気に入っています。2. 夏今年の夏の平均気温は大阪で29.9度で日本一だったそうです。 今日も大阪は35度を超える猛暑日で、もうお彼岸になっているのに秋はどこやらという感じです。 夏はやはり一番音楽を聴く機会が少ない季節です。夏にはクールなモダン・ジャズが多いのですが、クラシック音楽でいうとヘンデルの「水上の音楽」などいかにも涼しげに聞こえますが、これなどはむしろ春に聴く音楽だろうと思っています。では、夏には何を聴くのと問われると、筆頭はハープでしょうね。 とても涼しげに聴こえてきます。 夏にはハープが一番似合う音楽だと思っています。3. 秋この季節はもう何を聴いてもいいと思うくらいに聴きまくります。 でも、秋の夜に音楽を楽しむならチェロでしょう。 夜の帳を降ろした頃から聴き始めますと、深い音色が心の中でしみとおってくるような気がします。 特にロマン派のチェロ音楽は秋の夜にふさわしい音楽で、重厚さと渋さを兼ね備えたチェロの響きを楽しんでいます。ピアノもいいですね。 ショパンの詩情あふれる美しい旋律、まるで泉のように豊かな旋律が湧き起こってくるようなシューベルトのソナタ。 男性的な逞しさにあふれたベートーベン。例をあげればきりがありません。秋はどんな音楽をも、まるで砂が水を吸い込むように、豊かに響いてくれます。4. 冬冬も秋と同じでどんな音楽でも合うと思いますが、寒い日などは炬燵に丸まっていることからオペラをよく聴きます。 特にワーグナーなどのドイツ・オペラは冬に限ります。それに各時代の交響曲も冬に聴く機会が多いです。 それとヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲「四季」~冬。 これは毎年この季節に聴いています。 この曲で一番好きなのがこ第4楽章の「冬」です。さて、あなたはどうでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 小紫
2007年09月22日
コメント(2)
-

ワーグナーの不倫の恋~ジーグフリート牧歌
『今日のクラシック音楽』 R.ワーグナー作曲 「ジークフリート牧歌」リヒャルト・ワーグナー(1813-1883)と言えば「楽劇」というオペラのジャンルに新しいスタイルを確立した作曲家で、楽劇「ニーベルングの指環」や「トリスタンとイゾルデ」、「ニュールンベルグの名歌手」や、楽劇を確立する前の歌劇「さまよえるオランダ人」や「ローエングリン」などの名作オペラを書いて、ワーグナー音楽を好きで愛する人たちを「ワグネリアン」と呼ぶほどの人気のある作曲家であり音楽です。現在もスイスのルッツェルン郊外にワーグナーの住んでいた家が記念館として保存されています。風光明媚なルッツェルン湖を眺めおろす素晴らしい風景を楽しめる小高い丘に建っています。 在職中にスイスへ行った時にこの「ワーグナー記念館」を訪れたことがあります。 (ワーグナー記念館)玄関を入ると素晴らしいらせん階段があります。それを見た時に思い出したのが17人のオーケストラ奏者と指揮するワーグナーが、その螺旋階段に立って「ジーグフリート牧歌」を演奏しているのを想像しました。(ワーグナーと17名の楽団員が立った階段)上記2枚の画像は「ワーグナー記念館」資料から転載しました。ワーグナーは56歳で妻コジマとの間に3番目の子供として初めて長男を授かり、「ジークフリート」と命名してその喜びを表す為に彼はコジマに一曲の音楽を贈ったのです。 その曲が「ジークフリート牧歌」で、贈られた日がコジマの誕生日でした。ワーグナーの妻コジマは、あの有名な作曲家フランツ・リストと当時の名ピアニストと言われたマリー・ダグーとの同棲中に生れた娘で、伝説的名指揮者ハンス・フォン・ビューローの妻でしたが、ワーグナーに惚れて彼の許に走ったのです。 ビューローはワーグナーの弟子で、コジマとビューローとの間に二児がいました。 ワーグナーはそれまでの借金生活が嘘のようにバイエルン国王の寵愛で年金を授けられて不自由のない生活をしていた頃の話です。ワーグナーにはバイエルン国王からミュンヘン近くに別荘を提供されるほどの寵愛を受けていました。 その別荘に落ち着いた時に、ワーグナーはビューローの家族を別荘に招きました。 ワーグナーの成功を喜んだ弟子ビューローは、別荘でのワーグナーの身の回りの世話をさせるために、妻コジマと子供二人を先に別荘に行かせたのでした。 それが間違いのもとで、ワーグナーとコジマはビューローが別荘に来るまでにただならぬ関係になってしまっていました。 ワーグナーが51歳の1864年のことでした。その翌年(1865年)にワーグナーは楽劇「トリスタンとイゾルデ」の初演に大成功を収めます。 初演の指揮は勿論ハンス・フォン・ビューローでした。 そしてビューローがこの初演に情熱を傾けていた頃に、コジマはビューローの子として3人目の女の子を産んでおり、その子に「イゾルデ」と命名しています。 しかし、実の父親はビューローでなく、ワーグナーだったそうです。 何とも皮肉な話です。楽劇「トリスタンとイゾルデ」は1859年(46歳)に完成されていますが、この時もワーグナーは不倫騒ぎを起こしています。 不遇の時代を支えた豪商ヴェーゼンドンクの妻マティルデと不倫の恋に落ちていたのです。この歪んだ恋が「トリスタンとイゾルデ」を書かせる原動力になったのではないかと穿った見方をしてみたくもなるエピソードです。長男「ジークフリート」が生まれた時にはワーグナーとコジマの生活は正式な夫婦として成立していなかったのです。話は「ジークフリート牧歌」に戻ります。1870年12月25日の朝、目覚めたコジマは部屋の外の物音に気づいて寝室を出ました。 すると寝室に通じる階段には17名の楽団員が並んでいて、ワーグナーの指揮でこの曲の演奏を始められ、これが夫ワーグナーの自分への誕生日(12月25日)の贈り物と知ったのでした。楽劇「ジークフリート」が作曲されている頃の音楽で、「愛と平和の動機」、「ワルキューレの眠りの動機」、「ブリュンヒルデの叫びの動機」、「活躍するジークフリートの動機」、「鳥の声の動機」など、実にのどかな、幸せな気分に包まれた極上のサウンドが聴く者を酔わせます。不倫の恋から盗むようにビューローからコジマを奪ったワーグナーでしたが、この恋がなければ「ジーグフリート牧歌」という名曲は生まれなかったでしょう。愛聴盤 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウイーンフィルハーモニー(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG20031 1987年ザルツブルグ・ライブ)↓カラヤンジェシー・ノーマンの「イゾルデの愛の死」がオペラ舞台で聴けないだけに貴重な演奏会記録も収録されています。 ジークフリートではウイーンフィルのビロードの肌触りのようなサ ウンドを楽しめ、「トリスタンとイゾルデ」ではこれほどの官能をこの年で、と思うほどのむせ返るような法悦を聴かせてくれる最晩年の演奏記録を味わえます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 ヒメツルソバ 撮影地 大阪府和泉市 2006年10月28日タデ科 タデ属 ヒマラヤ地方が原産地でピンク色の小さい花が、コンペイトウのようにつぶつぶ状に球形に集まって咲いています。 春・秋に開花しますが、四季を通じて咲いているようです。 明治中期に日本に渡って来たと言われています。 繁殖力が強く、カーペット状に群生して咲いています。
2007年09月21日
コメント(4)
-
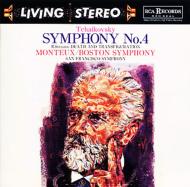
続・チャイコフスキーをめぐる二人の女性/現の証拠
「今日のクラシック音楽」 続・チャイコフスキーをめぐる二人の女性「彼女は28歳で魅力的な、世間の評判も申し分のない女性です。 暮らしは貧しく教育は普通程度。 気立てはいいのでしが、食べていくのがやっと・・・・」とメック夫人に宛てた手紙に書いていたのに、結婚後はまるで正反対のことを手紙に書いています。「私が何の仕事をしているのか、私のプランはどんなものなのか、私が何を読んでいるのか、芸術面では何を好きなのか、彼女は興味を抱いたこともありません。 4年間も私を恋し続けていたのに、彼女は私の作曲した音楽の楽譜を一つも知らないのです。・・・・・・」と綴っており、神経質で真面目なチャイコフスキーはとうとうノイローゼとなり、結婚後わずか3か月で離婚しています。 そうとう精神的に落ち込んだのでしょう。彼の弟アナトーりが転地療養を勧めてスイス・イタリアへ旅行をしました。 ロシアの重い空と違って、澄んだ空気・素晴らしい眺望の湖のスイス、明るく輝く陽光と色深い紺碧のイタリアの海がチャイコフスキーの心を徐々に癒してくれました。 そして結婚前から構想を練っていた4曲目の交響曲の筆が進んでいくのでした。 そして1878年1月にイタリアで曲を完成しています。 勿論、この第4交響曲はメック夫人に献呈されています。この第4番目の交響曲はそれまでの3曲(初期3曲)とは趣きをがらりと変えています。 この曲には大きなテーマとして「運命と人生」というような巨大な物が表現されているように感じられます。 第1楽章冒頭で奏される「主想」と呼ばれる旋律が曲全体を支配しており、全曲にわたって形を変えて現れます。 暗い重みがあり、淡い夢もある「人生」だと、メック夫人に宛てた手紙に書かれているそうです。第2楽章は、仕事で疲れ果て、夜にまるで放心したように座っている人のように、困ばいしたような悲哀の楽章であり、第3楽章は、気まぐれな、とりとめのない音楽で、第4楽章は、生きる希望のような音楽です、と大要約すれば上に書いたような趣旨の説明書を夫人に書いて送っています。何もこの通りに聴く必要はないと思いますが、不幸な結婚がチャイコフスキーの人生に影を落として、その結果生まれたのがこの交響曲第4番であることは明白だと思います。 しかしこの曲を聴かれた方にはおわかりと思いますが、彼の音楽は見事に脱皮しています。 特に交響曲で言えばこの曲をきっかけにして、続く第5番、第6番へと飛躍していったのです。もし、メック夫人に宛てた新婦の様子が最初の手紙のようであれば、どんな音楽が生まれていたであろうかと想像すると面白いですね。ところでフォン・メック夫人の13年間続いた経済援助は唐突に打ち切られてしまいました。 1890年でした。 夫人からの一方通行のような打ち切り方だったそうです。 少なくともある程度の恋愛感情を抱いていたチャイコフスキーには痛手であったと想像に難くありません。 すでに世界の大作曲家にのしあがっていましたから経済的には困らなかったと思いますが、翌1891年の春にアメリカ・ニューヨークのカーネギ・ホールから招待されて渡米した際のホテルで、一人になると涙していたそうですから、やはりメック夫人への想いがあったのでしょう。夫人にしてみればこれだけ大きな作曲家になったチャイコフスキーを、もう経済的に援助して育てるという意思がなくなったのでしょうか? これは今でも謎とされています。愛聴盤(1) ピエール・モントー指揮 ボストン交響楽団(RCA原盤 BMGファンハウス BVCC37166 1959年録音)名盤が多くある中で1枚だけ選ぶとすればこの演奏でしょうか。 灼熱するような熱いエネルギーに満ちた音楽が全編を支配しており、約50年前の古い録音ですが血がたぎるような昂奮を呼ぶ名演奏です。他にムラビンスキー/レニングラードフィルの60年ロンドン録音(グラモフォン)、カラヤン/ウイーンフィルの84年録音盤(グラモフォン)も素晴らしいチャイコフスキーの音楽を楽しめます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 現の証拠(ゲンノショウコ)風露草(ふうろそう)科 下痢止めの薬草として有名で、煎じて飲めばぴたりと効くところから「現の証拠」と名付けられたそうです。 花はピンクと白があり、西日本がピンク、東日本に白が多いそうです。
2007年09月20日
コメント(2)
-

チャイコフスキーをめぐる二人の女性
「今日のクラシック音楽」 チャイコフスキーをめぐる二人の女性チャイコフスキー(1840-1893)には同性愛者という影のようなものが終生ついてまわっていて、有名な第6交響曲「悲愴」の初演からわずか9日後に、同性愛が原因で自殺によって亡くなったと現代では定説のように言われています。 亡くなった日はたしかに1893年11月6日なのですが、その死因はコレラによるものと長い間言われていましたが、自殺の原因はあるロシアの公爵の甥と親しく同性愛として交際をしていたことから、公爵に訴えられると脅迫観念から起こったとされており、これが彼の自殺の原因と言われています。そのチャイコフスキーにも生涯に関わった女性が二人いて、それが光の明と暗のような存在を示しています。 一人はチャイコフスキーの音楽を愛し、パトロン的な経済援助を13年間も続けたフォン・メック夫人。 もう一人がアントリーナ・ミリューコバという女性です。 チャイコフスキーの弟子にイオシオフ・コチェークというヴァイオリニストがいて、彼が時々ある未亡人の依頼だと言ってヴァイオリンの小品の作曲を頼んでいました。 しかし小品にしては法外な多額の謝礼を寄こすのでチャイコフスキーは非常にこの未亡人に興味を抱き始めたのです。 その未亡人こそがフォン・メック夫人だったのです。フォン・メック夫人の夫、カール・オットーはロシアの鉄道王のような存在でロシアを縦横に走る鉄道経営で巨万の富を築いていたそうです。 この夫婦には6男6女という子宝に恵まれており、相当仲のいいカップルだったのでしょう。 しかし夫カールが50代で世を去ってのちに、メック未亡人は残された子供たちの養育と引き継いだ鉄道経営のかじ取りをしていたそうです。チャイコフスキーと最初の手紙のやり取りを始めたのが1876年の冬で、この頃には息子に鉄道経営を任せて好きな音楽を聴く余生を楽しむ夫人となっていました。 この手紙での交際は13年間も続きチャイコフスキーも経済的に相当余裕が出来たそうです。 年間の援助額が6,000ルーブル。 彼のモスクワ音楽院での初任給が800ルーブルであったことと比較すると、いかに夫人の援助がチャイコフスキーを安心して作曲に没頭できたか想像できます。しかし、この二人は終生一度も会うことなく13年間で1200通にも及ぶ手紙だけの交際に終わっています。 世にも不思議な男女の交際です。 そこへ大変な出来事が起こりました。 フォン・メック夫人との交際も不思議ですが、この話も実に摩訶不思議な物語です。 彼が教鞭をとっていたモスクワ音楽院に9歳年下のアントリーナ・ミリューコバという女性の教え子がいました。 彼女が突然にラブレターを送ってきたのです。 チャイコフスキーは彼女と一言も言葉を交わしていないので、このラブレターには驚き・狼狽さえ感じたようですが、手紙には彼女の誠実さが見られ、傷つけまいと思って返事を書いてしまったのです。 その後は続々と手紙を送ってくるようになり、「あなたなしでは生きてはおれません。 いっそうのこと自殺した方がましです」と熱烈な内容となり、結婚まで迫るようになってきました。現代のストーカーのような存在だったのでしょう。 私も一度この類の経験を学生時代に味わったことがあります。 普通なら路上ですれ違った、ただそれだけの邂逅の機会くらいに思っていなかったのに、10枚ほどのラブレターをもらい、その後夜を徹して迫られたことがあります。 惚れられる方が辛いこともあるんだと思った体験でした。話は横道にそれました。 チャイコフスキーは気が弱かったのか、結局二人はひっそりと式をあげました。 1877年9月のことでした。 彼は最初は彼女のことをそう悪くは思っていなかったようで、メック夫人への手紙に結婚のことを述べて妻となるミリューコバのことは好意的に書き添えていたそうです。ところが結婚してチャイコフスキーは愕然となり、その驚き・怒りの心情を手紙に書いています。 そしてあの名曲がこの摩訶不思議な結婚~悲劇へと導かれて生まれるのです。つづく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の風景」 お地蔵さん「大野の阿弥陀さん」として親しまれている堯王院(ぎょうおういん)は、自宅から車で約20分くらいのところにあり、聖武天皇の皇后である光明皇后の安産を祈るために行基が作ったという阿弥陀如来像を祭っています。そのため安産を祈願する女性が多く参詣し、丈夫な子どもが産まれるようにと腹帯を授かりにくる参拝者で賑わっています。 その阿弥陀如来像が鎮座する堂の前に可愛らしい石のお地蔵さんがありました。 参拝客の妊婦が掛けていったのでしょう。 安産祈願や出産のお礼を書いた白いハンカチのような布が巻かれていました。
2007年09月19日
コメント(4)
-
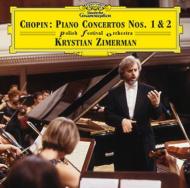
告白されなかったショパンの恋
珠玉のピアノ作品を残したフレデリック・ショパン(1810-1849)は若き命を散らして39歳で肺結核で亡くなっています。 残された作品の美しさ・素晴らしさを聴くたびに、あと20年延命であればどん作品が残されたのだろうか、と想像しながら聴いていることもあります。「ピアノの詩人」とも呼ばれるショパンは自身ピアノの名手でもあったそうで、演奏会などにひっぱりだこのようでした。 そんな彼が書いた作品は全てピアノ作品と言っても過言ではないでしょう。 3つのソナタ、24の前奏曲、ボロネーズ集、マズルカ集、ワルツ集、20曲を超える夜想曲集、練習曲集など珠玉のピアノ作品を残しています。そんな彼の作品の中で2曲の協奏曲があります。 この2曲ともが素晴らしい協奏曲なんですが、私の好みからすると第1番の方が聴く機会が多い曲です。 実際はこの第1番は2番目の協奏曲なのですが、楽譜出版の時に2作目より先に出版されたために「第1番」と呼ばれるようになったそうです。芸術家は人並み外れた「感性」を持っているようで、作品を生み出すエネルギーのような火山のマグマのようなふつふつとした情念が沸き起こっているようです。 それらの「感性」の中でも作曲家に多大な影響を与えた「女性」の存在があります。 昨日の日記にも書きましたように、ヴェルディのオペラ「椿姫」がソプラノ歌手とのパリへの逃避行で観た演劇「椿姫」に大いに感動したソプラノ歌手から囁かれて生まれています。この「ピアノ協奏曲第1番」もショパンの初恋の女性への思慕から生まれた作品です。 ショパンは相当な美男子であったようです。現在残されている彼の肖像画を見ても現代流に形容すれば「やさ男」の部類に入る美男子です。 「なよやかな茎の上に青い花をのせた昼顔のようで、そっと手を触れただけではかなく散ってしまいそうだ」と形容したのはフランツ・リストでした。 まさに言い得て妙なる表現です。 それはショパン像のみならず彼の音楽そのものを語っているように感じられます。彼はまたこういう風にも形容されています。「デリケートな肉体、洗練された貴族的な態度、音楽のような静かな声、ピアノ演奏の美しさ、更に美しい彼のピアノ作品の数々、とび色の目、ふさふさとした栗色の髪、そうした彼の魅力に年齢を問わず多くの女性が魅かれていた」と。ショパンの生涯に寄り添う3人の女性がいました。 コンスタンチィア・グラドコフスカ、マリア・ヴォジンスカ、それに最も有名なジョルジョ・サンド。このピアノ協奏曲第1番はそれらの女性の中で、ショパンの初恋の人と言われているコンスタンチア・グラドコフスカという、声楽を勉強していた女性なしに語れない曲です。ショパンはワルシャワ音楽院でピアノを学んでいた時に、グラドコフスカも声楽を学んでおり、いわば同期生だったのです。 「まばゆい程に美しく、素晴らしい声の持ち主」という「僕は悲しいことに、理想の女性を見つけた。 まだひとことも話をしたこともないが、この半年間僕の心は忠実にあの人に仕えているんだ」と手放しの惚れ込みようです。そうした「熱い想い」をとうとう打ち明けることなくショパンはポーランドを去り、その後二度と祖国の土を踏むことがなかったのです。 友人への手紙にそうしたグラドコフスカかの想い・恋心が連綿と書かれていたそうです。 まさに青年期に誰もが体験するような恋の想いではないでしょうか。そのグラドコフスカへの想いを綴った曲が2曲のピアノ協奏曲です。 自分の燃え上がる炎のような恋心を音楽にぶつけたのでしょう。 特に第2番の「アダージョ楽章」は明確に彼女への想いだというショパン自筆の手紙に書かれているそうです。「第1番」は作曲順からすると後になるのですが、この曲には「第2番」のような明確なものが残っていません。 しかし、この曲もグラドコフスカへの想いが込められていることは容易に推察できます。 音楽活動をもっと盛んにするためにショパンは祖国ポーランドを離れてパリへ旅立つことを決意して、1830年10月11日にワルシャワで「告別演奏会」を開きました。 その演奏会に花を添えたのがグラドコフスカでした。 彼女はこの演奏会でロッシーニのオペラ「湖上の美人」のカヴァティーナを歌ったそうです。 その演奏会でショパンのピアノで演奏されたのが「ピアノ協奏曲第1番ホ短調 作品11」で、これがこの曲の初演となっています。ピアノの技巧をあますところなく表現しており、そこへ濃厚なロマンの香りを乗せた甘美な旋律が聴く者をうっとりとさせる名作です。 グラドコフスカへの熱い想いが伝わってくるかのようなうっとりする名曲です。第1楽章の主題などは、こぼれ落ちそうな、したたり落ちそうな濃厚な想いが語られており、ショパンの彼女への想いがこれほどまでかと推測されるほどの、美しい旋律に彩られています。第2楽章「ロマンツェ」などはまるで夜想曲のようで、ショパン自身の言葉によれば「ロマンティックな、静かな、少し憂鬱な気分で書いており、春の美しい月の夜のような、懐かしい思い出を振り返るような感じなんだ。」と。第3楽章はロンド形式で、繊細に、愛らしく、それでいて華やかな情緒もある見事な完結楽章です。この演奏会のあとショパンはフランス・パリへと旅立って、二度と祖国ポーランドの土を踏むことなくパリで39歳の若い命を散らしています。またコンスタンチィア・グラドコフスカは、こうしたショパンの想いを知らずに、この演奏会の2年後にワルシャワの地主と結婚して5人の子供たちに恵まれたのですが、35歳で失明します。 それでも79歳まで長命で1889年に亡くなったそうです。愛聴盤クリスティアン・ティマーマン(P) ポーランド祝祭管弦楽団 (グラモフォンレーベル 459684 1998年8月録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の一花 デュランタ
2007年09月13日
コメント(14)
-
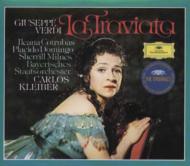
ヴェルディの恋から生まれた「椿姫」
作曲家と言っても人間。 恋もすれば借金もします。 いや、芸術家であれば尚更普通の人よりも繊細な精神をお持ちなのかも知れません。 それ故に恋に心を焦がし、その燃えさかる恋の炎が名曲を生み出したのかも知れません。ドイツの詩人ハイネは「恋に狂うって! 何を言ってるんだね。 恋そのものが狂気なんだよ」という有名な言葉を残しています。今日からしばらくの間、恋に身を、心を焦がした有名作曲家とそこから生まれた名作エピソードをお楽しみ下さい。さてそのトップ・バッターにイタリアの作曲家ジュゼッペ・ヴェルディを選んでみました。1851年の暮のこと、ヴェルディはソプラノ歌手ジュゼッピーナと手を取り合ってフランス・パリに逃げました。 その時にはヴェルディの妻マルガリータはすでに亡くなっていました。その恋の顛末は?亡くなった妻マルガレータはヴェルディの後援者の娘でした。 そして、歌手ジュゼッピーナは当時イタリアの最高のソプラノ歌手だったそうです。 ヴェルディは彼女にアビガイッレ役を歌わせるためにオペラ「ナブッコ」を書いたとも言われているくらいに、ジュゼッピーナにぞっこん惚れていました。妻が亡くなり、自由の身となったヴェルディに猛烈な恋心がわきあがりました。 二人の心に恋の炎が棲みつくのにそんなに時間がかからなかったのです。1849年にもう二人は同棲生活を始めました。 しかも亡き妻との住居のあるプッセードという町で。 前述のようにヴェルディの支援者の娘がヴェルディの妻。 その妻が亡くなったばかりなのに、もうソプラノ歌手と同棲しているのですから、世間の二人への風あたりは相当強いものでした。 ジュゼッピーナも色好くの強い女性で、指揮者や歌手との間で肉体関係が平気で子供まで産むような、当時としては破格の女性だったようです。 恋に奔放な女性! だったのでしょう。男は概してこういうタイプの女性に弱いのかも知れません。その彼女と狭いイタリアの片田舎で同棲を始めたのです。 当然支援者は娘が亡くなり、失望しているところに、婿殿が風評の悪い歌手と同棲をしていますから、面白くなく、確執が生まれてきます。いたたまれなくなったヴェルディはジュゼッピーナと1851年の暮にフランス・パリに逃げてしまいます。 そこでヴェルディは作曲、彼女は音楽教師として生計を立てていました。そのパリ滞在中に二人が観劇したのが演劇「椿姫」でした。 これはデュマ・フィスが書いた小説「椿姫」で大ベストセラーとなっていたそうです。 この小説をフィス自身が五幕の戯曲に改作して演劇としても売り出して、大成功を収めていた芝居でした。ヴェルディは当時オペラ「イル・トロヴァトーレ」の作曲に勤しんでおり、忙しく時間を割いていました。 そこへ恋人ジュゼッピーナが囁いたのです。 「椿姫」をオペラ化して欲しいと。 しかし、ヴェルディにはとてもそんな時間がありません。 恋人の督促もあり短期間で書きあげたようです。 それでも観劇から1年は経っていました。「ドミ・モンド」と呼ばれる貴族のパトロンから愛される高級娼婦の物語ですが、夜会で純真な若者と恋に落ちて、パトロンから寄与される一切のものを捨てて、パリ郊外に住居を構えるヴィオレッタとあるフレード。 しかし贅沢になれたヴィオレッタは売り食いで生計を立てています。 アルフレードの収入だけではとても食べていけないのです。そこへアルフレードの父ジェルモンが、息子が不在時に訪ねてきてヴィオレッタに別れを乞うのです。 妹たちの結婚に傷がつくから別れて欲しいと。 泣く泣くパリに帰るヴィオレッタ。 何も知らないアルフレードはヴィオレッタに復讐を誓い、パリの夜会賭博で買った大金をヴィオレッタに投げつけてしまいます。絶望のうちにヴィオレッタは肺を患って息を引き取る悲しい結末です。この薄幸の「ドミ・モンド」の日陰の自分を重ねたのでしょうか、ジュゼッピーナはヴェルディにささやき続け、「イル・トロヴァトーレ」で忙しいヴェルディにこの「椿姫」を書かせてしまいました。1853年3月6日、この「椿姫」はベネツィアで初演されていますが、ヒロイン役が大柄の歌手でとても薄幸の女性のイメージからかけ離れていたのが原因で大不評だったそうです。「第1幕への前奏曲」「乾杯の歌」 ヴィオレッタのアリア「ああ、そはかの人か~花から花へ」、ジェルモンのアリア「プロヴァンスの海と陸」、ヴィオレッタとアルフレードの二重唱「パリを離れて」などが、聴きどころの名旋律でしょう。ヴェルディがジュゼッピーナの惚れなかったなら、二人で戯曲「椿姫」を観なかったならば、この不朽の名作オペラ「椿姫」はこの世に出ることはなかったかも知れません。そして二人は同棲を始めて10年後にやっと晴れて結婚したそうです。めでたし、めでたし。私の愛聴盤(CD) カルロス・クライバー指揮バイエルン国立管弦楽団・合唱団イレアーナ・コトルバシュ(S)プラシド・ドミンゴ(T)シェリル・ミルンズ(B)(ドイツ・グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG30149 1976-77年録音)クライバーの凄まじいまでのダイナミックな表現と精緻な音楽作りは、今聴いても新たな感動を覚える素晴らしい演奏です。映像ではこれ!↓(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POBG1017 1982年制作)テレサ・ストラータス(S) プラシド・ドミンゴ(T) コーネル・マックネイル(Br) ジェームズ・レヴァイン指揮 ニューヨーク・メトロロポリタン歌劇場管弦楽団・合唱団舞台映像でなく、オペラ映画。 ゼッフィッレリの演出が秀逸な作品で、ストラータスの美貌と容姿が美しく、映像なら断然このDVDに限るとまで断言できる素晴らしいオペラ映画です。
2007年09月12日
コメント(7)
-
ブログ再開
やっと体調が元に戻りつつあります。 好きなクラシック音楽の記事を基本にしてブログの再開を始めたいと思っています。 早ければ明日からでも書いていこうと思います。これまでは名曲・珍曲・好きな曲などをランダムに選んで書いていましたが、作曲家の恋を中心に書いていきたいと思っています。 約1ケ月の間色々と考えていましたが、これまでは曲の素晴らしさ・成り立ちなどを主に書いていましたが、作曲家とて人間ですから好色な人もいます。 他人の妻を盗んだけしからぬ人もいます。 一方で告白もせずに恋が成就しかった人もいます。そうした作曲家の恋のエピソードに光をあてて、そこから生まれ出た名曲などの紹介をしていくことが出来ればと願っています。また音楽記事とは別に趣味のカメラで撮った四季の花画像も掲載していましたが、これは自宅に居る限りは新しい花画像を撮ることができません。 この花画像は相変わらず昔撮影した花の写真になりますが、どうぞご勘弁下さい。 いずれあちこちの花の名所を訪ね歩いて撮る時期が来ると思います。 その折は思いのたけをぶっつけて撮ろうと思っています。 満足できる画像であれば順次掲載していこうと思っています。どうぞ旧倍のお愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
2007年09月11日
コメント(17)
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-
-
-

- 好きなクラシック
- ベートーヴェン交響曲第6番「田園」。
- (2025-11-19 17:55:25)
-
-
-

- 吹奏楽
- ちくたくミュージッククラブ7thコ…
- (2025-11-22 23:43:42)
-







