2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年05月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
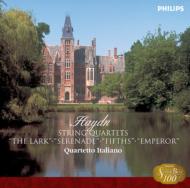
ハイドン 「ひばり」/南天の花
『今日のクラシック音楽』 ハイドン作曲 弦楽四重奏曲第63番ニ長調 「ひばり」私はヨゼフ・ハイドン(1732-1809)の音楽が大好きです。 彼の音楽はとても「端正」で、明るく、伸びやかで華麗さのない素朴な旋律、落ち着きのある音楽の中に浸っていられる数少ない作曲家の一人で、ロココ風の華麗で典雅なモーツアルトよりも好きな作曲家です。ハイドンはユニークな作曲家の一人に入るでしょう。 何がユニークかと言えば、この人ほど作品に副タイトルがついている人も珍しいのです。全104曲の交響曲の中でも思いつくままに挙げてみても「朝」「昼」「晩」、「熊」、「めんどり」、「王妃」、「哲学者」、「校長先生」、「うすのろ」、「火事」、「狩り」、「びっくり」、「V字」、「告別」、「時計」、「太鼓連打」、「ロンドン」、「軍隊」などあります。 全74曲の弦楽四重奏曲も同じで、「五度」、「日の出」、「皇帝」、「ひばり」、「鳥」、「蛙」、「騎手」、「剃刀」などがあります。ハイドン自身が命名したものは数少なくて、フィクションのようなエピソードがそのままニックネームになっている作品がほとんどで、作品の音楽とは関係のないニックネームがあります。 どうも作品を区別するために後世の人がつけたものが多いようです。ハイドンは「交響曲の父」と呼ばれるほど104曲の交響曲を書いています。 それと同じように「弦楽四重奏曲の父」と呼ばれるほど74曲もの弦楽四重奏曲を書き残しています。 イギリスの興行師ザロモンからの2度目の招聘を果たして交響曲第104番「ロンドン」を置き土産にして、交響曲の絶筆を済ませてウイーンに帰ったハイドンは、弦楽四重奏曲は相変わらず書き続けていたようです。 その中から今日は第63番ニ長調 「ひばり」作品64の5を採り上げました。この曲は、ハンガリーの貴族エスターハージ候に仕えていた1772年、ハイドン40歳の時の作品で、この曲はエスターハージ候の宮廷楽団のヴァイオリン奏者ヨハン・トストに献呈しています。 「トスト四重奏曲」と呼ばれる12曲の献呈曲の1曲です。「ひばり」と言えば、春を代表する鳥で「春うらら」の空高く舞い上がる姿を想像するほど、桜や鶯などと同じように春を連想する鳥です。 「さわやかさ」や「明るさ」をも連想させる鳥です。 「春」に時期に聴くにふさわしい音楽で晩秋のこの時期に採り上げるのはどうかと思うのですが、「室内楽の楽しみ」を満喫できる曲として選びました。この曲の第1楽章冒頭、第1ヴァイオリンでとても爽やかに、晴れやかに演奏される第1主題の旋律が、まるで空に向って高く飛び立つ「ひばり」のような、伸びやかな美しい旋律にちなんでこのニックネームが付けられています。 寒い冬に聴けば春への願望、春に聴けば春の謳歌となる、非常に美しい旋律です。 天高く舞う「ひばり」の如くです。ハイドンは「ひばり」の鳴き声を模倣して書いた曲でないとわかっていても、そう思いたくなるほど実に見事に「ひばり」が鳴いています。 第1楽章だけでなく、落ち着いた情緒の旋律が美しい第2楽章、まるで無窮動風の鳥のさえずりのような終楽章など、4つの弦がしなやかに、伸びやかに音色を奏でる、室内楽を楽しめる見事な音楽構成で書かれています。1809年の今日(5月31日)、ハイドンは77歳の生涯を閉じています。愛聴盤 イタリア弦楽四重奏団(Philips原盤 ユニヴァーサルクラシック UCCP7080 1965年録音)この団体の一番いい時期に録音された演奏です。 古い録音ですがリマスターされて良質の音に蘇っています。LP時代から聴き続けている演奏です。 流麗で明快な響き、緊密に絡み合う絶妙なアンサンブルでこの名品の魅力を生き生きと表現しています。 1000円盤で「フィリップス スーパーベスト100」シリーズの1枚としてリリースされています。 収録曲は「ひばり」、「皇帝」それに「セレナーデ」の3曲です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1809年 没 ヨゼフ・ハイドン(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 南天の花もう南天の花が開花しています。 やはり温暖化の影響なんでしょうね。 撮影地 自宅庭
2007年05月31日
コメント(8)
-
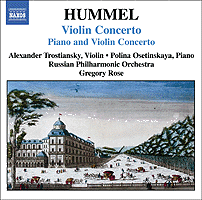
フンメル ヴァイオリン協奏曲/野あざみ
『今日のクラシック音楽』 フンメル作曲 ヴァイオリン協奏曲(未完の補筆作品)ヨハン・ネポムク・フンメル(1778年ー1837)はスロヴァキア出身のピアニストでもあり作曲家でした。作曲した作品はバレエや舞曲などの管弦楽作品、番号つきの5曲のピアノ協奏曲と番号無しが2曲、ピアノとオーストラの為の作品、ピアノとヴァイオリンのための二重協奏曲、ヴァイオリン協奏曲やトランペット協奏曲、8曲のピアノ三重奏曲や七重奏曲などの室内楽など、それに7曲のピアノソナタをはじめ非常に多くのピアノ作品など120を超える曲を書き残しているそうです。モーツアルトの弟子であり、ベートーヴェンの時代に生きた人で彼とも親交があったそうです。またメンデルスゾーンの先生でもあったそうです。私が持っているフンメル作品のディスクは2枚だけなのですが、今日はその2枚のうちの1枚から「ヴァイオリン協奏曲」を採り上げました。 この曲は未完に終わっているのですが、グレゴリーズ・ローズというここで紹介していますディスクでの指揮者が補筆完成したもので世界初録音のディスクです。曲想、楽想はモーツアルトとベートーベンのヴァイオリン協奏曲のような趣きがあり、第1楽章から実にのびやかなオーケストラの旋律にのって、これも優美にのびやかに独奏ヴァイオリンが美しい旋律が奏でられます。 この楽章は終始この気分に満ちておりしかも多少名人芸的なヴァイオリンの技巧もあり、聴いていてとても落ち着いた気分にさせてくれる楽章です。こののような楽想は続く3分足らずの短い第2楽章「アダージョ」、10分足らずの第3楽章「ロンド」にも共通の趣きで、しっかりと安定した合奏と掛け合う独奏ヴァイオリンの興趣溢れる音楽を楽しめる佳品です。毎日ではありませんが、特に晴れた日の朝、目さめのモーニング珈琲を味わいながら聴く曲の一つになっています。愛聴盤 アレクサンドロ・トロスティアンスキー(VN)、 グレゴリー・ローズ指揮 ロシアフィルハーモニー管弦楽団(Naxosレーベル 8.558595 200411年9月 モスクワ録音)フンメルの「ピアノとヴァイオリンのための協奏曲 作品17」とのカップリングですが、それについてこちらをご覧下さい。↓2005年10月12日の日記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1866年 初演 スメタナ オペラ「売られた花嫁」1927年 初演 ラヴェル ヴァイオリン・ソナタ1958年 初演 バルトーク ヴァイオリン協奏曲第1番1962年 初演 ブリテン 「戦争レクイエム」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 野あざみ 撮影地 大阪府和泉市
2007年05月30日
コメント(8)
-
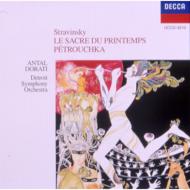
「春の祭典」/麦撫子(むぎなでしこ)
『今日のクラシック音楽』 ストラヴィンスキー作曲 バレエ音楽「春の祭典」イゴール・ストラヴィンスキー(1882-1971)は、3つのバレエ音楽で有名です。 「火の鳥」、「ペトルーシュカ」、そして「春の祭典」です。 この3つの曲が最もポピュラーな曲として彼の名を音楽史上に名を残しています。 そのストラヴィンスキーのバレエ音楽は、「ロシアバレエ団」の主催者ディアギレフと切り離して語れません。 1909年に興した「ロシアバレエ団(バレエ・リュッセ)を率いてパリで打った興行が大成功を収め、以来このバレエ団は彼の死(1929年)まで20年間世界のバレエ界を引っ張っていきました。そのディアギレフと親交を結んだストラヴィンスキーは、同時に世界の檜舞台へと駆け上がって行きました。 ストラヴィンスキーを語る上でディアギレフはなくてはならない人なのです。この二人の接触は1908年だと言われています。 ストラヴィンスキーはまだ無名の時代でした。 ディアギレフはストラヴィンスキーの「花火」を聴いて、彼の才能を高く評価して新作バレエ音楽を依頼したことが始まりでした。その曲がバレエ音楽「火の鳥」でした。 1910年6月25日にパリで初演されたバレエが大成功を収め、ストラヴィンスキーの名は一夜にして世界を席巻したのです。 ストラヴィンスキー28歳でした。この「火の鳥」の作曲の頃に、不思議な幻想にとらわれています。 幻想とは異教徒たちが原始的な儀式を行うというもので、厳粛な中に行われており、円く座った長老たちに春の太陽が降り注ぎ、中央では太陽の神への生贄となった乙女が踊り狂って死んでいく、そんな幻想でした。この幻想をスコアに表したのはそれから約3年後でした。 すでに書いていたバレエ音楽の第2作「ペトルーシュカ」で忙しい日々を送っていたからです。 1913年5月29日にパリのシャンゼリゼ劇場で、ピエール・モントーの指揮で初演されました。この初演にまつわるエピソードは、この曲を聴いている方々はおそらく知っているほど、クラシック音楽史上類を見ない騒ぎとなったのです。 ファゴットで始まったこの音楽は、パリの人たちが今でに聴いたことのないリズム(変拍子)や不協和音に驚いて、口笛を吹いたり、床を踏みつけたり、お互いに罵り合うなど未曽有の騒ぎとなり、「私は曲の数小節が始まって間もなく、嘲笑が沸き起こったので、いたたまれずに席を立った・・・・」(ストラヴィンスキー)という程の騒ぎでした。 初演の指揮者モントーの回顧談では「16番街の淫売婦!」というユニゾンでの哄笑があったと述べています。 聴衆の無理解もわからぬことではありません。 指揮者モントーがスコアを始めて見た時に、「一音も理解できなかった」と述壊しているほどです。それほどこの曲は当時の人々に衝撃的な音楽でした。 現在でこそ現代音楽の古典と呼ばれており、演奏会や録音でも定番となっているほどポピュラーな曲となっています。私がこの曲を初めて聴いたのが高校1年生(1960年)でした。 当時毎日曜日の朝10時から、日本フィルハーモニーの定期演奏会の模様をフジテレビが放映していました。 その朝の番組はイゴール・マルケビッチ指揮でした。 曲はストラヴィンスキーの「春の祭典」。 作曲家名を知っていても音楽を聴いたことのない時代でした。 ましてや彼の「春の祭典」など聴いたこともなく、テレビの前でどんな音楽かなと興味津々でした。 聴き終わって私はすぐに調べました。 どこかの会社からこの作品のLPがリリースされていないか。 ありました。 マルケヴィッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団の25cmLP盤。 1500円。 私は亡父に頼みました。 買ってもらったこのLPを35年間聴いていました。さて、この音楽なんですが、現代音楽と言っても原始的なリズム、不協和音の連続、咆哮する金管楽器、のたうちまわるようなティパニー。 この音楽の魅力は何と言っても原始的な色彩豊かな音楽でしょう。曲は2部構成で、第1部「大地礼讃」、第2部が「いけにえ」となっています。時代は古代ロシア。 春が芽生えてきたロシアの大地で、原始民族が大地に感謝をする行事を描いています。 そして選ばれた乙女が太陽の神への生贄となって踊り狂うという物語です。ロシアの原始的な主題がファゴットで奏されて曲が始まりますが、とてつもない高音域で始まり、弦楽器が強烈なリズムを刻みます。 そして不協和音の氾濫。 物凄いエネルギーのブラスの咆哮。 やはり約100年前のパリの聴衆には理解できない超進歩的な作品だったのでしょうか?1913年の今日(5月29日)、この「春の祭典」はパリでピエール・モントーの指揮で行われています。愛聴盤(1) アンタル・ドラティ指揮 デトロイト交響楽団 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD3210 1981年録音)色彩豊かにロシア情緒をうまく表現した演奏で、ドラティのバレエ音楽演奏の巧さを知る名盤。 録音も超優秀です。 「ペトルーシュカ」とのカップリング。(2) イゴール・マルケヴィッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 (EMIレーベル 5696742 1959年録音 海外盤)日記にも書いている通り、マルケビッチの演奏を長い間愛聴していた録音。私の「春の祭典」はこの演奏なしに語れません。 50年近くなる古い録音ですが、色褪せていません。(3) ロリン・マゼール指揮 クリーヴランド管弦楽団 (テラーク・レーベル CD800054 1980年録音 海外盤)マゼールのバトン・テクニックでクリーヴランドを思いのままに操る演奏。 この盤を採り上げたのはテラークの誇る超優秀録音の凄さです。(4) スヴェトラーノフ指揮 ソヴィエト国立交響楽団(ロシアレーベル SC030 1966年録音 海外盤)爆演指揮者というニックネームのあるスヴェトラーノフの古い録音ですが、まさにこれぞロシアの大地で踊るバレエと言わんばかりの、強烈なリズムで刻むロシア一色の演奏。(6) ファジル・サイ(独奏ピアノ) (テルデック原盤 ワーナー・ミュージック WPCS21228 1999年録音)ピアノ・デュオ盤は何点かリリースされていますが、独奏による演奏はこれだけ。 多重録音による演奏。 旋律、和音などとても勉強になるディスクです。 現在は1000円盤です。(7) マルケビッチ指揮 日本フィルハーモニー交響楽団 (EXTONレーベル OVBC00009 1968年収録)1968年に何度目かの来日で再び日フィルを振って「春の祭典」を披露したマルケビッチ。 とても懐かしい映像です。 日本で「春の祭典」を広めたのはマルケヴィッチだと思っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1801年 初演 ハイドン オラトリオ「四季」1860年 誕生 イサーク・アルベニス(作曲家)1912年 初演 ドビッシー 「牧神の午後への前奏曲」1913年 初演 ストラビンスキー バレエ音楽「春の祭典」1915年 誕生 カール・ミュンヒンガー(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 麦撫子(むぎなでしこ)撮影地 大阪府和泉市なでしこ科ムギセンノウ属 ヨーロッパが原産でしょうか、たくさん植わっているのを見たことがあります。葉が長いので麦に例えられて、この名前がついたと言われているそうです。1mくらいの高さになります。 5月には花が咲きます。
2007年05月29日
コメント(10)
-
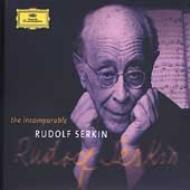
ベートーベン ピアノ・ソナタ第31番/ニラの花
『今日のクラシック音楽』 ベートーベン作曲 ピアノソナタ 第31番変イ長調 同じ曲を紹介したり、音楽記事を書かずに花画像だけの日も若干ありますが、今日のこの曲でちょうど1000件という節目を迎えました。 しかし、まだまだ紹介したい曲も数多く残っています。 頑張って更新を続けたいと願っています。ルードビッヒ・ヴァン・ベートーベン(1770-1827)は耳の障害に悩まされながらも100数十曲の音楽を書き残していますが、耳だけではなくてリュウマチや内臓疾患に悩まされ続けた作曲家だと言われています。50歳を過ぎた頃には病気も慢性化して彼の体を蝕んでおり、しかも確実に進行していたそうです。 そんな状態の51歳の頃(1821年)には「荘厳ミサ曲」の作曲をしながら、2曲のピアノ・ソナタを書いています。第31番と32番のソナタがそれです。 ベートーベンは32曲のピアノソナタを書き残していますから、この第31番が彼のソナタとしての絶筆前の曲です。しかもこれら2曲が上述のように、病気との闘いの中で書かれています。特に31番は闘病の苦しい中で書かれている曲だけに、音楽には悲哀とか悲壮感のような情緒が散りばめられており、聴く者を感動へ誘う音楽です。ある意味、病を得た人であればより鮮明にわかる情緒の音楽だと思います。ピアノから紡ぎ出される第1楽章の叙情溢れる楽想は、聴く者の胸をしめつけてくるようです。しかし、何と言っても見事な音楽を表出している終楽章は深い感動を与えてくれます。 ベートーベン自筆の言葉で書かれた「嘆きの歌」が、泣き叫ぶかのように悲痛に訴えてきます。その後に「フーガ」の楽想となってもう一度「嘆きの歌」が戻り、最後にまた「フーガ」によって曲が結ばれています。ベートーベンの音楽の根底を成している「人生観」「人生哲学」- 不幸な苦しい境遇であっても耐え忍ぶことが優れた人間であり、成長する - が感じられる楽章で、聴いていて最後には大きな勇気が与えられるように感じる曲です。私事になりますが、3度の脳梗塞を患い、言語障害と闘って治さねばならない立場になってこの曲を改めて聴きましすと、私はベートーベンがこの曲に込めた・秘めたメッセージを初めて理解できたように思います。「諦めるな!」ベートーベンが人間の可能性を信じて、勇気を自らに与えようとして書いたこの音楽が、人類への発信でもあったのかとリハビリを続ける私を励ましてくれた一曲でした。昨日は「真夏日」を思わせるような暑さでしたが、日付が変わると涼しい風が吹き渡っています。 とても涼しく感じる真夜中です。 そんな初夏の夜に、もう一度ベートーベンに感謝しながら今夜はこの曲を聴いています。愛聴盤 (1)ルドルフ・ゼルキン(ピアノ)(ドイツグラモフォン 474328 1987年 ウイーン・ライブ録音)↓ゼルキン後期の3大ソナタ第30番、31番、32番を収録しており、当時ゼルキンはすでに80歳を超えていたのですが、純粋で高雅で緊張感をも漂わせる演奏が、より一層私を勇気付けてくれました。 私の盤はこれ1枚ですが紹介のCDはロストロポービチとのブラームスのチェロソナタがもう1枚組まれています。(2) 長岡純子(ピアノ)(ソニー・クラシカル SRCR1696 1996年録音)1928年生まれですから、この録音時は68歳ということになります。 彼女の音色は透明度が高くて、粒立ちのいい美しい音色を聴かせ、しかも音楽の表情にとても温かい響きがこもっています。 ベートーベンの協奏曲、シューベルトのソナタ、ショパンの曲なども聴きたくなります。 収録されている曲はすべてベートーベンのソナタで、第23番「熱情」、それに静かな美しさを秘めた第27番です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1787年 没 レオポルド・モーツアルト(W.A.モーツアルトの父)1925年 生誕 ディートリッヒ・フィッシャー=ディースカウ(バリトン)1938年 初演 ヒンデミット 交響曲「画家マティス」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ニラの花 撮影地 大阪府和泉市ゆり科 ネギ属 アジア原産 開花時期 今までは8月頃から咲き始めましたが、温暖化で最近は早くなっています。 道端や畑の畔などにもよく見かけます。 これは畑の畔で咲いていまた。 茎のてっぺんに白い花がたくさん咲いています。葉は食べられます。 ちぎるとニラ独特の匂いがします。
2007年05月28日
コメント(14)
-
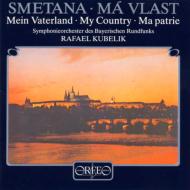
スメタナ 「わが祖国」/ジャガイモの花
『今日のクラシック音楽』 スメタナ作曲 連作交響詩「わが祖国」世界中で様々な音楽祭が催されていますが、開幕日と開幕のコンサート・プログラムが発足以来変わることのない音楽祭があります。 それはチェコの「プラハの春」と呼ばれるフェスティバルです。第2次世界大戦後すぐに催された音楽祭で、開幕日は5月12日でオープニング・プログラムはペドルジーハ・スメタナ(1824-1884)作曲の連作交響詩「わが祖国」が、初めての音楽祭以来変わることなく続けられています。チェコスロヴァキアは長い年月オーストリア帝政時代の占領統治下にあり、その圧政に国民が疲労困憊の状態でした。 ヨーロッパ全体が帝国主義国によって支配されていた国が多かったのですが、スメタナの時代になって欧州に民族主義運動が広がっており、政治・文化の両面で大きな運動の波が押し寄せており、スメタナが生まれたボヘミアでも民族主義運動が高まっていた時代でした。スメタナは熱烈な愛国者であり「民族自立」へ熱い志を持っていて、オペラ「売られた花嫁」によって見事に民族音楽への基礎を確立したあと、この連作交響詩「わが祖国」がスメタナの祖国愛の迸りから生まれていて、祖国の大自然や歴史的英雄の回顧や土地などを題材にしており、6曲の交響詩から構成されています。 これらの音楽には、チェコスロヴァキアの豊かな緑に恵まれた自然をスメタナの限りない祖国への愛情で音楽として表現されています。オーストリア圧政の時代にも、1968年の旧ソ連の軍事介入による悲劇の時代にも、チェコの人々に勇気を与え続けた音楽で、「プラハの春」音楽祭開幕をスメタナの命日にあたる5月12日として、そのオープニング・プログラムがこの「わが祖国」でチェコフィルハーモニー管弦楽団によって演奏されると決められたのでした。スメタナはベートーベンと同じく難聴で苦しんだ作曲家でした。 この「わが祖国」の第1曲「高い城」の作曲に取りかかった時にはスメタナ50歳で、もう難聴はかなりひどい状況で、第2曲「モルダウ」が作曲された頃には、完全に耳が聞こえないという何とも痛ましい病状だったそうです。作曲家・音楽家にとって痛恨の病状のなかで、スメタナは5年の歳月をかけて6曲の音楽を完成して1882年に全曲が初演されたのですが、その時には自分の書いた音楽を「音」として自分の耳で聴くことが出来ない状態だったそうです。 その頃には精神錯乱を起こすようになっており、2年後の1884年5月12日に、祖国独立のため、民族音楽のために戦い抜いて、もう成す術がなく「矢折れ、刀尽きた」とばかりに、60年の生涯を精神病院で壮絶な最後を遂げたと言われています。第1曲「高い城」ハープによって憧憬に満ちたような美しい主題が冒頭から奏でられます。 モルダウ河のほとりには中世ボヘミア王国の古城ヴィシュフラッドが現在でも建っており、そこには伝説の吟遊詩人ルミールが住んでいたとされており、英雄の歌や愛の歌を歌っていたのです。このハープによる主題はルミールの竪琴を表していて、この旋律は第1曲の主題だけでなく、全曲を通じての重要な主題となっています。この主題が変奏されてかつての栄光の祖国への回想と、ボヘミアの栄枯盛衰の歴史をつぶさに眺めてきた「高い城」によって祖国愛を語っていると思います。第2曲「モルダウ」「わが祖国」中で最も有名な曲で単独で演奏会や録音などで採り上げられています。 「モルダウ」とはチェコ中央部を流れる大河モルダウ河のことで、その河の景観を描いています。曲冒頭ではボヘミア南部の森の水源から湧き出す水を表現しているような旋律によって河の起こりを表しており、次第に水かさを増し川幅を広げてやがて大河となってボヘミアの森と野を流れプラハに至る様を、美しく、とうとうとした旋律で表現されており、全曲中最も美しい部分でこの作品の白眉となっています。そして河の周囲に住む農民たちの踊りや、静かな月光の夜の水の精や、河の急流や、高い城が描かれていき、まるで河を船で下るかのような音の絵巻物のような音楽にあふれた、メンデルスゾーンも脱帽の「音の風景画家」といった、あらゆる交響詩の中でも最高の名作かと思います。第3曲「シャルカ」チェコの伝説に「シャルカ」という伝説の女王がいたそうです。 スメタナは彼女の伝説を採り上げて、祖国の栄光の歴史を偲んでいるようです。伝説では、シャルカは恋人に裏切られ男への復讐を誓うのですが、シャルカを討つために派遣された騎士ツティラートは、彼女を捕らえますが、木に縛られて苦しむシャルカの美しさに魅かれて彼女を彼女を解放します。シャルカはツティラートとその部下に酒をふるまい酔っ払ったところで、ホルンで女性軍を呼び寄せ追討者たちを全滅させてしまいます。この曲はこういう伝説を音で描いています。第4曲「ボヘミアの牧場と森から」「モルダウ」に次いで親しまれている曲です。 輝く陽光が降り注ぐボヘミアの草原、収穫に感謝する農民の歌と踊り、森を吹き渡っていく風、小鳥たちのさえずり。 ここにはボヘミアの自然と森への感謝を込めた「自然賛歌」があります。 親しみやすい美しい旋律の曲です。第5曲「ターボル」「ターボル」とはチェコ民族主義運動の一つの象徴で、チェコの「フス戦争」時代に最も急進的で独立政権が樹立されたこともある町のことです。中世にはチェコスロヴァキアにも宗教戦争がありました。 その時代の祖国のフス教徒の英雄的な戦いを描いています。15世紀初頭、フス教徒たちが宗教改革運動がボヘミアに広がるのを機に、カトリック教と対立するのですが、逆に弾圧によってフス教徒は火炙りの刑に処されてしまいます。これによって「フス戦争」という民族独立戦争にまで発展してゆきます。この曲はフス教徒のコラールが主題で、チェコ民族主義運動への強い決意と意志の力を表現しているかのようです。第6曲「プラニーク」「プラニーク」はボヘミアにある山の名前で、プラニーク山には騎士たちが永遠の眠りについており、祖国に危機が訪れると眠りから起きて祖国を救うために現れるというボヘミア伝説を採り上げて、スメタナは祖国の自主独立を願ったのでしょう。第5曲「ターボル」で奏でられたフス教徒のコラールが、この曲で主要な旋律として再び使われています。 スメタナにはプラニーク山に眠る伝説の騎士はフス教徒であったのかも知れません。スメタナは、全曲を締めくくるこの第6曲で民族独立の賛歌を高らかに歌い上げ、第1曲「高い城」の主題が再現されてを高らかに誇るかのように「わが祖国」を閉じています。愛聴盤 (1) ラファエル・クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団( OREFEOレーベル ORFEO115841 1984年ミュンヘンライブ録音)スメタナ没後100年、クーベリック生誕70年を祝う記念演奏会ライブ。 クーベリック特有のしなやかな旋律の膨らませた方が絶妙で、スメタナへの熱い共感が伝わってくる「わが祖国」の演奏でも出色の名演。 ライブながら録音は極めて鮮明です。(2) ラフェエル・クーベリック指揮 チェコフィルハーモニー管弦楽団(NHK音源 ALTUSレーベル ALT098 1991年11月2日シンフォニーホール ライブ)1990年に祖国チェコに戻ったクーベリックがチェコフィルを振って歴史的演奏会を行った翌年に来日した演奏会の記録。 NHKでも放映されており、その時の録画も観ています。チェコフィルメンバーが終演後に涙を流している光景はとても感動的です。 チェコフィルの弦楽器の美しさが熱い演奏の中でも出色の印象を残しています。(3) ヴァツラフ・ノイマン指揮 チェコフィルハーモニー管弦楽団 (DENON CREST1000シリーズ COCO70604 1982年11月5日 東京ライブ録音)東京公演の記録で、「わが祖国」初演100年を祝っての演奏会。 民俗色豊かな色どりが素晴らしく、熱い共感にあふれた名演。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1840年 没 ニコロ・パガニーニ(ヴァイオリニスト・作曲家)1906年 初演 マーラー 交響曲第6番「悲劇的」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ジャガイモの花 撮影地 大阪府和泉市
2007年05月27日
コメント(4)
-
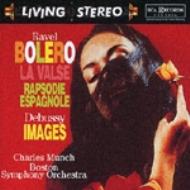
ラヴェル「ボレロ」/丸葉車輪梅
『今日のクラシック音楽』 ラヴェル作曲 「ボレロ」今日は音楽史上になかった、また後世にも書かれることのなかった、同じ主題だけが延々と演奏され続けるという画期的な音楽を採り上げました。 フランスの作曲家モーリス・ラヴェル(1875-1937)が書きました管弦楽作品の「ボレロ」です。 もともとフランスのバレエ団の舞台上演用として書かれた音楽ですが、1928年11月22日に演奏会用としてコンサートで初演されたそうです。とにかく音楽常識からしますと完全に常軌を逸脱した音楽なのです。 曲の始まりは小太鼓。 CDで聴いていても思わず音量つまみを上げてしまうほど小さな小太鼓の音が「タン・タタタタン、タン・タタタタン・・・・」と単調なリズムを刻んで始まります。 そうしているうちにフルートがどこかエキゾチックなメロデイーを吹き始めます。 続くクラリネットが後半の旋律を引き継いで吹き始め、この同じ(全く同じ)旋律を別の楽器が延々と引き継いでいくのです。その間小太鼓で、相変わらずあの始まりの単調なリズムが間断なく刻まれており、しかも執拗に繰り返される同じ旋律が延々と楽器を変えて演奏され続け、やがて音量を増していき、フルオーケストラでリズム、同一メロデイー、響きが一体となって音楽はそのままクライマックスを迎えて、まるで爆発するかのように転調した瞬間に音楽が終るという曲なのです。 音楽の終焉はまるで階段から人が転げ落ちたかのような終り方です。演奏時間 約15分の曲です。一つの旋律、主題とリズムだけが楽器を替えることだけで始まりから最後まで繰り返される音楽はこの1曲だけではないでしょうか。ラヴェルは旧ロシアの作曲家ムソルグスキーが書きましたピアノ曲「展覧会の絵」を華麗な管弦楽作品に編曲して、現代でもオーケストラ作品としては最もポピュラーな曲に仕立てあげているように、「オーケストレーションの魔術師」と呼ばれた人でした。 この「ボレロ」でも同じ主題を演奏させる楽器の音色、彩りなど計算し尽して書かれているように思えます。 ストラビンスキー(作曲家)がラヴェルを評して「スイスの時計師」と呼んだそうですが、オーケストラを知り尽くした正確無比な音楽設計を評してのことでしょう。 この「ボレロ」はそれほど人を喰ったような音楽であり、興奮させる音楽、そして最後には感動させる音楽です。ラヴェルはその後交通事故に遭い、脳が少しずつ縮小していく残酷な脳障害に冒されました。 彼の頭の中では新しい音楽が鳴り響いていても、それを楽譜にして音楽にすることができなくなっていったのです。 亡くなる直前まで脳は理性を保ち、音楽を鳴らせているかのような残酷な運命を与えられたそうです。そして、あたかもこの「ボレロ」の終結が突然転調して爆発的に曲を閉じたのと同じように、彼自身も頭の中で音楽を響かせながら悲劇的にその生涯を閉じたのです。この曲を聴くたびに、私は彼の生涯の終焉でのわずかな期間の、階段から転げ落ちたような、悲劇的な人生に思いを馳せるのです。この曲は何度聴いても小太鼓を演奏する人に同情します。終始同じリズムを15分間刻み続けるって大変なことだと思います。訂正嫌好法師さんのご指摘の通りで、この曲は主題が2つでAとBのパターンとして分けるべきでしょう。 本文中に1つの主題と書いていますのは誤りです。 訂正してお詫び申し上げます。愛聴盤 1) シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団(RCAレーベル 09026-81956-2 1956年録音 輸入盤)2) エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7011 1963年録音)上記2枚はLP時代から数え切れないほどの再発売を繰り返してきた録音盤で、今聴き直しても決して色褪せることのない、色彩豊かな演奏が刻み込まれていて、どちらもラヴェル名演集というタイトルで、ラヴェルの管弦楽名曲がカップリングされた名盤です。3) ピエール・ブーレーズ指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団 (ドイツ・グラモフォン 439859 1993年録音 海外盤)ベルリンフィルの驚異的とも言えるアンサンブルからブーレーズが透徹した光と色彩を引き出した名演奏で、録音は超がつく優秀な録音で刻み込まれた演奏です。4) アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団(EMI原盤 東芝EMI TOCE59035 1961年録音)クリュイタンスの見事な統率でパリ音楽院奏者の、フランスの洒落た詩情をぷんぷんと匂わせる香気を感じさせる響きと、高雅な気品を漂わせた、しかもラヴェルの光輝くようなガラス細工のような感じを伝える名盤。 録音は古いですが、これこそ「永遠の名盤」と呼べるディスクではないでしょうか。 リマスタリングの向上した技術でとても聴きやすい音質になっています。 カップリングは「スペイン狂詩曲」と「ラ・ヴァルス」です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』本日は該当する記事はありません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 丸葉車輪梅(マルバシャリンバイ)5月になると公園やマンションなどの植え込みに植えられている「丸葉車輪梅」が白い花を咲かせます。 小さな目立たない花ですが、梅のような姿をした可愛い花です。 撮影地 大阪府和泉市 2006年5月25日薔薇科 シャリンバイ属 開花時期 5月初め~5月下旬頃まで。葉が枝先に車輪状に集まっていて、分厚い丸い葉で背丈は50cm~70cmくらい。公園や集合住宅などに生垣として植えられているのをよく見かけます。5弁花で梅の花に似ているところからこの名前が命名されています。
2007年05月26日
コメント(6)
-
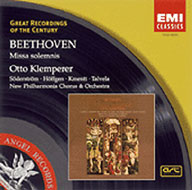
ベートーベン「荘厳ミサ」/赤花夕化粧
『今日のクラシック音楽』 ベートーベン作曲 荘厳ミサ曲 ニ長調 作品125大バッハ(1685-1750)とベートーベンの(1770-1827)の大きな違いは、バッハは世俗音楽に比べて数多く教会音楽を書き遺していることです。 バッハは教会に仕えて宗教行事に携わっていたという周囲の環境もあって、教会音楽に絶えず関わっていました。 ベートーベンは、あくまでも自由な作曲家・演奏家という「芸術家」としての職業から、貴族や一般人に聴かせる演奏会用音楽を書いていたという違いがあります。ベートーベンにはキリスト教に関わる曲は、「ミサ曲ハ長調」と今日の話題曲「荘厳ミサ」の2曲しか書いていません。 決して信仰心がなかったのではありません。 ヨーロッパの文化はキリスト教に基づいていると言っても過言ではなく、絵画・建築など目にするものだけでも相当なものがあります。 「神への畏れ」を常に心に生きる人たちの文化で、仏教が大半を占める日本とは異なった文化であり、キリスト教信仰に根ざした人たちの文化に圧倒されます(建築だけで言えばお寺などの文化も大したものだと思いますが)。 そんな環境の中で育ったベートーベンも「神への畏れ」「神への救済」「神の栄光」を常に心に根ざしていたのだと思います。この「荘厳ミサ」に対してベートーベンは言ってます。 「歌う人にも、聴く人にも、宗教的な念を起させ、またそれを持続せしめるためにも作曲したのだ」と。ピアノ三重奏曲「大公」を献呈されたベートーベンのパトロンでもあったルドルフ公へ捧げられた曲で、公が枢機卿に昇進後に、オルシュミッツ大司教に就任することとなって作曲されていますが、ベートーベン自身の周りの騒音が激しい時期と自身の病気もあって、結局大司教就任三周年記念式典で初演されています。最初にバッハとの違いを書きましたが、この宗教音楽でも大きな違いがあります。 バッハの音楽は教会で歌える音楽ですが、ベートーベンのこの「荘厳ミサ」は実に交響楽的に書かれており、彼の大作「交響曲第9番」にも匹敵するほどのシンフォニックな響きを持った壮大なミサ曲です。 一部の学者は、この音楽の壮大さと交響楽的な響きがカソリックの典礼音楽としてふさわしいものではないと、主張しているそうですが、この曲を聴くとそういう問題ではないことがわかります。 魂・心を揺さぶられ、圧倒される音楽です。曲は、I. キリエ(あわれみの賛歌) (1) 主よ、憐れみ給え (2) キリストよ、憐れみ給え (3) 主よ、憐れみ給えII. グローリア(栄光の賛歌) (1) 天のいと高きところには、神に栄光 (2) 世の罪を除きたもう主よ、我らを憐れみ給え (3) 主のみ聖なり、主のみ主なり、主のみいと高し (4) 父なる神の栄光のうちに。 アーメン (5) アーメン、アーメン、父なる神の栄光のうちにIII. クレド(信仰宣言) (1) われらは信ず (2) 聖霊によりて (3) 天に昇り父の右に坐したもう (4) アーメン、来世の生命を待ち望む。 アーメンIV. サンクトゥス(感謝の賛歌) (1) 聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主 (2) 主の大地に満つ (4) 前奏曲 (5) ベネディクトウス ほむべきかな、主の名によりて来る者V. アニュス・デイ(神の小羊) (1) 神の小羊 御身世の罪を除きたもうた主よ (2) 我らに平安を与えたまえ (3) 神の小羊、おん身世の罪を除きたもうた主よ (4) Prestoこれだけの、神への畏れ、神への感謝、来世の永遠の命を望む敬虔な信仰心に貫かれた音楽が約80分あまり続く、独唱、重唱、合唱、管弦楽で描かれた、まるで大伽藍建築を思わせるような壮大なスケールで、キリスト教信者であるか、ないかを問わず聴く者を圧倒してきます。生涯に一度は聴いておきたいベートーベンの傑作です。愛聴盤(1) オットー・クレンペラー指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団・合唱団 エリザベート・シュトレーム(S) マルガ・へフゲン(A) ヴェルデマール・クメント(T) マルッティ・タルヴェラ(Bs)(EMI原盤 東芝EMI TOCE59103 1965-67年録音)クレンペラー80歳の録音で、遅めのテンポで克明に旋律を描いて、壮大なスケールと厳しい音楽で表現した、まるで霊峰を望むかのような演奏。 もう40年前の録音ですが、今なお色褪せないクレンペラー畢生の名演盤。 今では1700円で買い求められます。(2) レナード・バーンスタイン指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 ヴィルヴァーサム・オランダ合唱団 エッダ・モーザー(S) ハンナ・シュヴァルツ (A) ルネ・コロ(T) クルト・モル(Bs)生命の燃焼を思わせるような熱情にあふれたライブ録音。 紹介ディスクは第9とカップリングされた1,500円でお買い得です。 但し、「荘厳ミサ」の録音はライブ録音特有の制限の中で収録されているためか、すごく平面的な音になっているのが惜しまれます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1830年 初演 ドリーブ バレエ音楽「コッペリア」1910年 初演 ドビッシー 前奏曲集第一巻1934年 没 グスタフ・ホルスト(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 赤花夕化粧撮影地 大阪府和泉市赤花科 マツヨイグサ属 南アメリカ原産明治時代にアメリカから渡ってきたそうです。5月から9月頃まで、ピンク色のきれいな4弁花が咲かせています。夕方に開花することから命名されたそうです。
2007年05月25日
コメント(10)
-
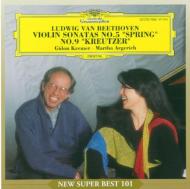
「クロイツェル・ソナタ」/テッセン(白)
いつの間にか200,000アクセスを超えていました。 ご訪問いただきました方々には感謝、感謝でいっぱいです。 200,000目をアクセスいただいた方はどなたかわからないのですが、どうもありがとうございました。 またいっそう励んで更新致しますのでよろしくお願い申しあげます。昨日から体調(高血圧)があまり良くないので、今日は昨年の同日の日記を再掲載させていただきます。 尚、若干の加筆・修正はおこなっております。 悪しからずご了承下さい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ベートーヴェン作曲 ヴァイオリンソナタ第9番イ長調 「クロイツェル」 作品47ベートーヴェン(1770-1827)はヴァイオリンソナタ第5番「春」を書いた後、6番ー8番を作品30として一括して出版したあとに、1803年5月にイ長調の第9番「クロイツェル」を書き上げています。 ベートーヴェン32歳の春でした。 交響曲では3番「英雄」が完成間近の頃にあたります。 彼はヴァイオリン・ソナタを全部で10曲書いていますから、「傑作の森」と呼ばれる中期以前の第1期にすでに9割のソナタを書き上げてしまったことになり、最後の10番の完成はほぼ10年経った1812年まで待たねばならないのです。そして1812年以降、亡くなるまでの15年間はとうとうヴァイオリンソナタを書くことがありませんでした。さて、この第9番の「クロイツェル」ですが、様々なエピソードが残されています。第一に、ベートーヴェン自身が副題をスコアに書いているのが「ヴァイオリンの助奏を伴うきわめて協奏的なピアノのためのソナタ」と指示していますが、とんでもない、この曲は「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」と呼ぶべき、きわめて二重奏的な色合いの濃い曲となっています。 これは前作の第5番「春」についても言えることですが、ヴァイオリンとピアノのパートが独立性が高く、まるで2つの楽器による二重奏といった趣きで、決してヴァイオリンパートは「助奏」ではありません。 もっとも曲を聴けばそんなことはすぐにわかるくらいにきわめて優れた二重奏曲であると理解はできますが。演奏時間は30分を超す雄大・壮大な規模で書かれており、3楽章形式です。第1楽章は、二つの楽器の対話で進む緊張感にあふれたアダージョ・ソステヌートで始まり、大規模な主部へと進んでヴァイオリンとピアノの掛け合いによる張り詰めた緊張を伴う音楽に耳を奪われます。 ベートーベンのほとんどの音楽がそうであるように、とても腰が据わった安定感のある旋律・リズム・和声で貫かれた堂々とした音楽に耳を奪われます。第2楽章は、アンダンテでしかも変奏曲風にと書かれていて、変奏曲スタイルによる緩やかなテンポの楽章で、風格ある主題が提示されたあとに4つの変奏が行われ、しかもカデンツァとコーダ付きという重厚なアンダンテ楽章です。 雄大・壮大な規模の音楽と打って変わって、ベートーベンはこれほどに優しいのかと思うぐらいに優美な旋律の楽章です。終楽章は、プレストでまるで「タランテラ舞曲」を想起させるようなリズミックな躍動感にあふれ、華麗で、力強い音楽で締めくくられています。まさにヴァイオリンソナタの音楽史上でも稀な大傑作です。ベートーヴェンは、この曲をイギリス国籍のブリッジタワーというヴァイオリニストに献呈するために書いたと言われています。 ですから初演はこのブリッジタワーとベートーヴェンによって行われたのですが、完成が遅れたために初演のステージでは、楽譜の清書が間に合わず、第2楽章はヴァイオリンは草稿のまま、ピアノはスケッチで演奏されたというエピソードが残っています。ブリッジタワーに献呈するために書かれたこの曲が、何故「クロイツェル」なのか? それは初演のあとベートーヴェンとブリッジタワーが不仲となり、献呈はフランスのヴァイオリニストのロドルフォ・クロイツェルに献呈されてこの副題がつけられたそうです。しかし、クロイツェル自身がベートーヴェンの激しい音楽を好んでいなかったので、彼によってこの曲は一度も演奏されなかったという後日談が残っています。この曲にまつわる話は、ロシアの文豪トルストイが書いた小説「クロイツェル・ソナタ」があります。 倦怠期のロシア貴族の一家庭の不倫事件を扱っており、貴族の妻が家庭に出入りするヴァイオリニストと恋に落ち、夫が嫉妬のあまり妻を殺すという物語ですが、その不倫の発端となったのがこの「クロイツェル・ソナタ」の合奏だったのです。 トルストイはこの小説の展開上、この曲を重要な予想として扱っています。またチェコの作曲家ヤナーチェックは、このトルストイの小説を読んで「トルストイのクロイツェル・ソナタに霊感をうけて」と題した弦楽四重奏曲第1番を作曲しています。この「クロイツェル」は1803年の今日(5月24日)、ブリッジタワーのヴァイオリン、ベートーヴェンのピアノでウイーンで初演されています。愛聴盤ギドン・クレーメル(VN) マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)(ドイツ・グラモフォン 447054-2 輸入盤)緊張感の漲った演奏で丁々発止と受け渡しをしながら演奏される名人芸に酔うのに格好のディスクダヴィッド・オイストラフ(VN)、レフ・オボーリン(ピアノ)(Philps原盤 ユニヴァーサル・ミュージック 1967年録音)風格がただよう、オイストラフの遅めのテンポが王者の足取りのように聴こえてきます。 しかも力強い気迫のこもった熱い演奏で、40年以上の前の録音というのを忘れてしますほどの堂々とした熱演で、これこそ名演奏と呼べる記録だと思います。現在は1000円盤で第5番「春」とのカップリングもうれしいディスクです。アルテュール・グリュミオー(Vn) クララ・ハスキル(P)(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP9521 1957年モノラル録音)私が14-5歳の頃に買って聴いた懐かしい録音で、しなやかで温かみのあるグリュミオーのヴァイオリンとハスキルの奏でるピアノは、至福の時空へ誘ってくるれような演奏です。西崎崇子(Vn) イェネ・ヤンドー(ピアノ)(Naxos 8.550283 1989年録音)可もなし不可もなしと言ってしまえばそれまでですが、西崎の実に素直な音色が美しい演奏で、こういうのを「普遍的」と呼べる演奏ではないでしょうか。 Naxos社長夫人という地位にありながら、さすが世界で最も録音の数が多いヴァイオリニストの演奏と肯ける模範的で万人に薦めたいディスクです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1803年 初演 ベートーベン ヴァイオリン・ソナタ第9番「クロイツェル」1810年 初演 ベートーベン 劇付随音楽「エグモント」1918年 初演 バルトーク オペラ「青ひげ公の城」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 テッセン(クレマティス) 白 撮影地 大阪府和泉市 2006年5月17日
2007年05月24日
コメント(18)
-
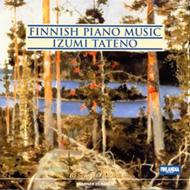
フィンランドピアノ作品集/名前不祥の花
『今日のクラシック音楽』 フィンランド・ピアノ作品集先日から比較的大曲が続いていましたので、今日は紹介のディスクから好きな曲だけ選んで聴こうと思っています。 フィンランドの作曲家だけの「ピアノ小品集」です。私が名前を知っているのはヤン・シベリウスだけで、あとの8人の作曲家は全く知りません。 ですからいつものように四方山話のような解説記事は書けません。このCDの解説にも書いていますが、フィンランドの旅情・抒情・叙情を美しく描き出したピアノ音楽ばかりで、長い曲で5分、最も短い曲で1分という小品ばかりですから、作曲家の背景がわからなくても、ただ流れ来る音楽に耳を傾けてお好きな曲を選んでお聴きになればいいと思います。9人の作曲家のピアノ作品で77分という総合計演奏時間です。 フィンランドが好きな舘野 泉さんが細やかな、美しい音色であなたをフィンランドへと誘ってくれる極上の1枚です。オリジナルでは2枚組でしたが、1枚に収録して価格も1000円という買い易い値段で発売されています。初夏の爽やかな陽光の中で、珈琲・紅茶を片手にくつろぎのピアノ音楽を楽しまれては。「FINLANDIA Finnish Piano Pieces」(Fazer F07876-6)にこのCDに収められている作品全部の楽譜もあるそうです。 ピアノを弾かれる方でご興味があれば参考にして下さい。収録作曲家と曲名ヤン・シベリウス(1865-1957)(1) 練習曲 (2) 樅の木 (3) 即興曲 (4) ロンドレット オスカル・メリカント(1868-1924)(5) 牧歌 (6) ゆるやかなワルツ (7) スケルツォ エリッキ・メラルティン(1875-1937)(8) 舟歌 (9) 蝶のワルツ (10) 高みにて セリム・パルムグレン(1878-1951)(11) とんぼ (12) プレリュード=カプリス (13) 5月の夜 (14) ヴェネツィアのゴンドラ漕ぎ (15) 海 トイヴォ・クーラ(1883-1918)(16) 羊飼いのポルカ (17) 結婚行進曲 ヘイモ・カスキ(1885-1957)(18) 前奏曲 (19) トロルのタップダンス リーヴィ・マデトヤ(1887-1957)(20) ワルツ (21) 古い記憶 (22) 伝説 イマリ・ハンニカイネン(1892-1955)(23) 夕べに(24) ワルツ エルムスト・リンコ(1889-1960)(25) アリア (26) 田園風メヌエット ピアノ 舘野 泉 (FINLANDIA原盤 ワーナー・クラシックス WPCS21138 1991年9月 12月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1814年 初演 ベートーベン オペラ「フィデリオ」1899年 初演 マーラー 交響曲第1番「巨人」1937年 誕生 ルネ・コロ(テノール)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 名前不詳の花これも近所の庭の植え込みで咲いているのですが、家の人は名前がわからないそうです。 撮影地 大阪府和泉市
2007年05月23日
コメント(10)
-
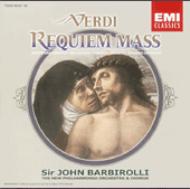
ヴェルディ 「レクイエム」/名前不詳の花
『今日のクラシック音楽』 ヴェルディ作曲 「レクイエム」最近自分が死んでしまった夢をよく見ます。 一昨夜まで四夜続けて見るという嫌なことが続いています。 まさか今は死に直面することはないと信じ切ってはいますが。 それでも急死するようなことがあればと思い、近所に住む人で、私が高校生の頃からクラシック音楽を論じ合う友人に楽天のIDとパスワードを教えて「万が一のことがあれば、所有するCDの処分と不慮の出来事を日記に書いてくれ」と頼んでおきました。 何か嫌な気分なんですが、突然このブログが休止するようなことが起これば、と思って頼んだことです。神さまから体の麻痺を守っていただいて、こうして日記を書き続けることができる幸せに感謝しながらおかしな行動ですが、あまりにも変な夢を見続けるので頼みました。 そんなことが起きないように今日は初演日でもあるので、ヴェルディの「レクイエム」を採り上げました。ジュゼッペ・ヴェルディ(1813-1901)は、「アイーダ」「椿姫」「オテロ」など「オペラの神様」と言われるイタリア・オペラの大作曲家です。 そう、あのヴェルディが書いた「レクイエム」です。「レクイエム」とは、「死者のためのミサ曲」とも呼ばれているように故人の安息を祈る、カソリック教会の儀式に演奏される音楽のことです。 「我のすべてを許し給え」と祈る言葉を根幹に永遠の命を祈る音楽です。多くの作曲家がこの「レクイエム」を書いています。 モーツアルト、ベルリオーズ、ケルビーニ、フォーレ、ヴェルディの曲を「五大レクイエム」と呼ぶ人がいるくらいに、この曲には名曲が多く残されています。それらの中で最もドラマティック(劇的)なのがこのヴェルディの曲です。 まるで彼のオペラを聴いているような感じのする曲です。 モーツアルトの「レクイエム」は絶筆となった遺作で、まるで自分の死を悼むかのような感のする曲ですが、ヴェルディのこの曲は二人の死に基づいて書かれています。ヴェルディはロッシーニ(1792-1868)をすごく尊敬していたようです。 そのロッシーニが1868年11月13日に亡くなりました。 その死を悼んでロッシーニに世話になった12人の作曲家と相談して、「レクイエム」を共同で作曲して彼の墓前に捧げようという計画でした。 ヴェルディは「リベラ・メ」(赦祷文~我を許し給え)を担当して作曲を終えたのですが、他の作曲家との足並みがそろわずに、この計画がお流れとなってしまいました。時が経って5年、今度は1873年に当時イタリアが誇る大詩人アレッサンドロ・マンツォーニが88歳の生涯を閉じました。 ヴェルディは若い頃からマンツォーニをすごく尊敬していたそうなんですが、あまりの衝撃で葬儀にも列席せずに一人静かに墓前へ参ったそうです。 その墓前でマンツォーニを悼む心から再び「レクイエム」の作曲を思い立って、固く心に誓ったそうです。こうして世紀の名曲「レクイエム」のお膳立てが揃い、ヴェルディは作曲に打ち込んでこの大曲を完成させたのでした。 このときヴェルディは63歳だったそうです。曲は、7曲から構成されており第2曲「怒りの日」は全9章からなる長大な曲で、全曲中最も劇的な楽章となっています。第1曲 「レクイエムとキリエ」(入祭文)第2曲 「ディエス・レイ<怒りの日>」(続誦) 第1章 怒りの日 第2章 不思議な響きを伝えるラッパが鳴り渡る 第3章 書き記されている書物が 第4章 憐れな私は 第5章 みいつの大王 第6章 慈悲深きイエズス 第7章 私は、自分のあやまちを嘆き 第8章 呪われし者どもを罰し 第9章 涙の日第3曲 「オッフェルトリウム<栄光の王>」(奉献誦)第4曲 「サンクトゥス<聖なるかな>」(聖誦)第5曲 「アニュス・ディ<神の子羊>」(神羊誦)第6曲 「ルックス・エテルナ<永遠の光明を>」(聖体拝領誦)第7曲 「リベラ・メ<我を許し給え>」(赦祷文)最後の「リベラ・メ」はロッシーニ追悼時に書かれた音楽をそのまま採用しているそうです。この音楽はベルリオーズの「レクイエム」とよく比べられます。 非常に劇的に書かれているからでしょうか。 しかし、ヴェルディのこの曲は最も華やかな感じのするオペラ的な音楽で塗りつぶされています。 独唱でも重唱や合唱でもオペラを聴いているような感じになるほどです。 フォーレの静かな、平安な「レクイエム」とは対極をなす音楽です。 演奏時間も、モーツアルト、フォーレ、ケルビーニなどと比べると長く、このヴェルディの曲はCDで1枚物はありません。 (例外はトスカニーニ盤です。77分という演奏時間で1枚物です)。音楽は非常に美しく書かれており、90分ほどかかる大曲ですが長さを忘れて聴き入ってしまいます。マンツォーニの一周忌にあたる1874年の今日(5月22日)、この「レクイエム」が初演されています。愛聴盤(1) サー・ジョン・バルビローリ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団・合唱団 モンセラート・カバリエ(ソプラノ) フィオレンツァ・コッソット(メゾ・ソプラ ノ)、ジョン・ヴィッカーズ(テノール)、ルッジェーロ・ライモンディ(バリトン) (EMI原盤 東芝EMI TOCE55451 1969-70年録音)バルビローリ特有の「メロウ・サウンド」が素晴らしく、最盛期の歌手たちの美しい声が花を添える名盤。(2) カラヤン指揮 ウインフィルハーモニー管弦楽団・合唱団 アンナ・トモワ=シントウ(ソプラノ)、 アグネス・ヴァルツァ(メゾ・ソプラノ) ホセ・カレーラス(テノール)、 ホセ・ファン・ダム(バス) (グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG20022 1984年録音)カラヤンの磨き抜かれた音楽性がオペラと見まがうほどの美麗な音楽に圧倒される名演。(3) イゴール・マルケヴィッチ指揮 モスクワフィルハーモニー管弦楽団 ガリーナ・ヴィネフスカヤ(ソプラノ)、二ーナ・イサコワ(メゾ・ソプラノ) ヴラディミール・イワノフスキー(テノール)、イワン・ペトロフ(バス) ソヴィエト国立アカデミー合唱団 (Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック 1961年ロシア・モノラル録音)マルケビッチの鋭利な刃物で突き刺すような表現と総ロシア勢による大地を揺るがすような演奏は実にユニークな盤。 モノラル録音が惜しまれる。(4) サー・ゲオルグ・ショルティ指揮 シカゴ交響楽団・合唱団 レオンタイン・プライス(ソプラノ)、 ジャネット・ベイカー(メゾ・ソプラノ) ヴェリアーノ・ランチェッティ(テノール)、 ホセ・ファン・ダム(バス) (RCAレーベル 82876623182 1977年録音 海外盤)ショルティのシャープな表現とシカゴ響の怒涛の演奏で目が眩みそうな豪演。 歌手陣も万全の布陣。(5) アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 ヘルヴァ・ネルリ(ソプラノ)、 フェードラ・バルビエーリ(メゾ・ソプラノ) ジュゼッペ・ディ・ステファーノ(テノール)、チェーザレ・シェピ(バス) ロバート・ショウ合唱団 (RCA原盤 BMGジャパン BVCC38106 1951年録音)私の最も好きな演奏。 録音が古くなっているが少し速めのテンポでの推進力とカンタービレの美しさには比類のない演奏で、まさに「人類の遺産」とはこういう演奏かと思われるトスカニーニ畢生の名演。 但し、紹介盤には「聖歌四編」がカップリングされていて2枚組です。私が聴いていますのは、限定盤で98年にリリースされた1000円だったCDです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1813年 誕生 リヒャルト・ワーグナー(作曲家)1813年 初演 ロッシーニ オペラ「アルジェのイタリア女」1874年 初演 ヴェルディ 「レクイエム」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 名前不詳の花この花は近所の玄関に鉢植えで置かれていました。 家の人に名前を訊いてもご存じありません。 どなたかご存じの方がおられましたら、どうか教えて下さい。 撮影地 大阪府和泉市 2007年5月21日
2007年05月22日
コメント(12)
-

オペラ「道化師」/紫かたばみ
『今日のクラシック音楽』 レオンカヴァルロ作曲 オペラ「道化師」ルッジェーロ・レオンカヴァルロ(1857-1919)の最高傑作オペラ。 と言ってもこのオペラ以降はぱっとせずにほぼこの一作のみで、オペラ史上・音楽史上に名を残しています。先日書きましたマスカーニと同じように一幕物オペラに応募したのですが、この「道化師」は二幕なので対象にならなかったのですが、演奏時間、ヴェリズモ・オペラということで、「カヴァレリア・ルスティカーナ」と共に一夜の公演として組まれることの多いオペラです。このオペラの題材は、レオンカヴァルロの父が裁判官をしている時に、実際に起こった事件を基にして書かれており、台本はレオンカヴァルロ自身が書いています。私がオペラ好きになった記念すべきオペラで、1961年イタリア歌劇団の来日公演で大阪フェスティヴァル・ホールで、マリオ・デル・モナコの「道化師」、シミオナートの「カヴァレリア・ルスティカーナ」の舞台公演を観てからでした。 その時のモナコの鬼気迫る熱演が昨日のように蘇ってきます。「カヴァレリア・ルスティカーナ」同様演奏時間は70分~75分の短いオペラ。プロローグ座員トニオ(Br)が開幕前に登場して前向上を述べます。 第1幕1860年代後半のイタリアのある村が舞台。 村人が楽しみに待っていたどさ回りの旅役者一行がやってきた。 座長のカニオ(テノール)には彼が育て上げた美人の妻ネッダ(ソプラノ)がいる。 他の男と恋愛しないかといつも気にしている嫉妬深い男。 馬車から下りようとするネッダに手を貸すトニオにさえ怒って殴るほどの嫉妬深いところがある。村人は「鐘の合唱」を歌いながら家路に着く。この村にはネッダが密かに恋するシルヴィオがいる。 そのことは誰も知らない。 ネッダは飛ぶ鳥を見て「小鳥たちは囀り合い、好きなところへと飛んで行ける」と、「鳥の歌」を歌っていると、座員のトニオがネッダに横恋慕して言い寄ってくる。 ネッダに鞭でこっぴどく叩かれてしまうトニオ。 「この恨みをきっと晴らしてやる。 高くつくぞ、ネッダ!」と吠える。 そこへネッダの恋人シルヴィオがやってきて、しばしの逢瀬を楽しみ、駆け落ちを相談する二人。 その現場をトニオが見ており、座長カニオに知らせて現場へやってくると、二人は別れるところでネッダが囁いている。 「今夜からあなたのものよ」と。 取り逃がしたカニオはネッダに男の名前を言えと迫るが、座員ぺっぺに「衣装を着けて下さい。 開幕時間がきますよ」と言われて、この場はそのまま納まる。「どんな不幸があっても、笑うんだパリアッチョ。 笑え、パリアッチョ!」とアリア「衣装を着けろ」を歌うカニオ。 第1幕はこうして幕を閉じます。間奏曲第2幕(劇中劇)待ちに待った旅芝居の幕が開くのを待ちかねている(さあ~、早く良い席を)。 ネッダが客から木戸銭を取りながらシルヴィオと今夜の駆け落ちの打ち合わせをする。そして幕が上がる。道化師(パリアッチョ)の妻コロンビーナ(ネッダ)が夫がいないことをいいことに恋人アレッキーノ(ぺっぺ)と恋を語り合っていると、召使のタデオ(トニオ)が道化師が帰ってきたことを告げる。 あわてたアレッキーノが窓から逃げ出す。 コロンビーナが「今夜からあなたのものよ」と囁く。 それを聴いた道化師カニオは芝居と現実がわからなくなる。 それでも必死に芝居を続けようとするコロンビーナ。 その対照が面白くて観客席が沸く。とうとう現実と芝居が一緒になってしまったカニオは、「もう道化師じゃない」と現実に戻り、トニオからそっと渡されたナイフで彼女を刺してしまいます。 それでも男の名前を執拗に迫るカニオ。 助けを請うために「シルヴィオ」と叫ぶと、彼は舞台に上がってカニオに刺されてしまいます。 呆然と立ち尽くす道化師カニオが「これで喜劇が終わりです」と言うと、「衣装をつけろ」の旋律が奏されて幕となります。「プロローグ」の田舎芝居を語るトニオのアリア。「鐘の合唱」「鳥の歌」(ネッダのアリア)「衣装をつけろ」「もう道化師じゃない」70分の短いオペラですが聴きどころいっぱいのオペラです。 特に「衣装をつけろ」は道化師でありながら辛いことも我慢して笑わせなければならない宿命を歌った壮絶なアリア。1961年のイタリア歌劇団東京公演では、この第1幕の幕切れで歌ったモナコの詠唱に聴衆が舞台に殺到するほどの騒ぎになった、オペラ史上未曽有のモナコの名唱でした。アメリカ1930年代にこの「道化師」を得意のレパートリーにしていたテノール歌手エンリコ・カルーソーの妻が、他の男と駆け落ちをします。 それでもその夜舞台で「道化師」を歌わねばならないカルーソー。 事情を知らない指揮者もオーケストラも鬼気せまるアリア「衣装をつけろ」に涙したという実話が残っています。愛聴盤(1) マリオ・デル・モナコ(テノール)、ガブリエルラ・トゥッチ(ソプラノ)、コーネル・マックニール(バリトン)モリナーリ・プラデルリ指揮 ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団・合唱団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCD3340 1959年録音)「道化師」のCDはこれ1枚で充分ではないかと思われる「黄金のトランペット」と形容されたドラマティック・テノールのマリオ・デル・モナコ畢生の名演。 彼は声だけでなく演技も素晴らしく、「衣装をつけろ」で泣き崩れるアリアはまさに「空前絶後」と思える迫真の演技。 もう10年以上前になりますが、私の持っているCDをテープに録音して解説も付けたのを200曲ほど友人にあげたことがあります。 それらの中で何が一番好きかと問うたところ、間髪入れずに返った答えが「マリオ・デル・モナコ」でした。 舞台でこのオペラを観ていることもありますが、私にとって「永遠のモナコ」です。1960年代はモナコに限らず、まさに伝説の名演奏家を輩出していた懐かしい時代です。(2) マリオ・デル・モナコ、 ガブリエルラ・トゥッチ、 アルド・プロッティ(バリトン) ジュゼッペ・モレルリ指揮 NHK交響楽団(NHK音源 キング・インターナショナル KIBM1015 1961年東京公演)伝説の1961年の東京公演をNHK保存の映像をDVD化したもの。(3) プラシッド・ドミンゴ、 テレサ・ストラータス、 ファン・ポンス ジョルジョ・プレートル指揮 スカラ座管弦楽団・合唱団(グラモフォン・レーベル ユニヴァーサル・クラシックス UCBG1100 1982年制作)ゼッフィレッリ演出のオペラ映画。 「カヴァレリア・ルスティカーナ」とのカップリングです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1892年 初演 レオンカヴァルロ オペラ「道化師」1895年 没 フランツ・スッペ(作曲家)1933年 誕生 モーリス・アンドレ(トランペット奏者)1937年 誕生 ハインツ・ホリガー(オーボエ奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 紫カタバミ 撮影地 大阪府和泉市
2007年05月21日
コメント(12)
-
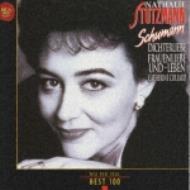
シューマン 歌曲集「女の愛と生涯」/薔薇
『今日のクラシック音楽』 シューマン作曲 連編歌曲集「女の愛と生涯」ロベルト・シューマン(1810-1856)はピアノの名手として知られており、作曲する音楽もピアノ曲の多かった人ですが、音楽史上に有名な花嫁の父(シューマンのピアノの師)との確執を経ながら5年のロマンスを実らせて、1840年にクララ・ヴィークと結婚することになりました。シューマンはその結婚前夜に花嫁クララに歌曲集「ミルテの花」を贈っています。 この歌曲集の第1曲「献呈」の詩には「君は僕の心、僕の魂、君は僕の心の至福・・・・・」と謳われています。 いかにシューマンがクララを愛し、結婚を待ち望んでいたかがこの歌曲集でもわかります。シューマンは結婚の年1840年までは多くのピアノ曲を書いていますが、この結婚した年にはなんと130曲ものリートを書いていることが彼の作品年譜からもわかります。 ピアノ曲からリート(歌曲)作曲への大きな変貌です。 この1840年には「女の愛と生涯」や「詩人の恋」などの名作歌曲集が書かれています。シューマンには一体何が起こったのでしょうか? 私見ですが、ピアノの音の世界では愛する人への心を表現しきれなくて、「詩」を選ぶことによって人の声で直接「愛」を伝えることに自身が目覚めたのではないでしょうか?そんな結婚年の幸福な心に満たされている彼の創作の中で異色の歌曲集があります。 それが連編歌曲集「女の愛と生涯」作品42です。この歌曲集はドイツの詩人シャミッソーの詩を選んで8曲からなる歌曲集となっていて、一人の女性がある男性と知り合い、恋に落ち、結婚をして、母親の喜びを知るのですが、夫と死に別れて寂しさを味わうという物語風の連作歌曲です。第1曲 「あの人に会ってからは」心惹かれる男性への憧れを歌う女心。第2曲「誰にもまさる君」恋する人に捧げるひたむきな純真な愛情を歌う。第3曲「私にはわからないは、信じられないわ」思いがけず意中の男性から恋心を打ち明けられた女心と驚きと喜び。第4曲「この指にさした指輪」結婚指輪が光る指を見て、大きく開ける人生の喜びに浸る新婦。第5曲「手伝って頂戴、妹たち」ウエデイング・ドレスを着る喜びがはちきれんばかり。 それでも妹への惜情がこみ上げてくる。第6曲「優しいきみよ、あなたの目は不思議そう」愛児を身ごもって感動に涙する妻。 いぶかしげな夫に打ち明けて、愛する人の子供を産む幸せに浸る妻。第7曲「私の心に、私の胸に抱かれた」愛児に胸に母親としての喜びを無邪気までに喜ぶ妻の表情。第8曲「今あなたは初めての悲しみを私に与え」夫の死という残酷な運命に直面してモノローグのように嘆き・深い悲しみに沈みこんでいく妻の心情。という8曲です。幸福の絶頂期であった1840年に最後は暗い、寂しい女の心を謳った曲を何故シューマンは書いたのか、想像もできず未だに謎とされています。シューマン自身は、44歳になった1854年に精神病を発病しています。 病状が重くなり絶望したシューマンはライン川に入水自殺を図り救出されますが、その2年半後(1856年)に精神病院で46歳の生涯を閉じています。 クララとの結婚生活は発病までの14年間だけでした。シューマンに先立たれたクララには「女の愛と生涯」第8曲が重く心にのしかかったことでしょう。 「あなたは静かに眠っています。 死の眠りについてしまってひどい方です。 残された私にとって、この世はうつろです。 私は激しく愛し、生きてきました。 でも、もう私は生ける屍です」これが第8曲の詩です。 まるでクララの心そのままの詩です。 この歌曲をシューマンは結婚の年に、まるで自分とクララのこれからの人生を予見していたかのように書いていたのです。いつの世にも天才が生まれ、その天才のなし得る偉業は凡人には神がかりとしか見えません。 まさにこの歌曲集「女の愛と生涯」は、神さまから天才だけが与えられた予知によって生まれたのでしょうか?クララ・シューマンは夫シューマンの死後40年の1896年の今日(5月20日)、ドイツで亡くなっています。愛聴盤 (1) ナタリー・シュトゥッマン(Ms) カトリーヌ・コラール(ピアノ) (RCA原盤 BMGビクター BVCC37244 1992年1月録音)(2) アンネ・ゾフィー・フォン・オッター(Ms) ベングト・ホルスベルグ(ピアノ)(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG3477 1993年10月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1896年 没 クララ・シューマン(ピアニスト、シューマンの妻)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 薔薇 撮影地 大阪市立長居植物園
2007年05月20日
コメント(8)
-
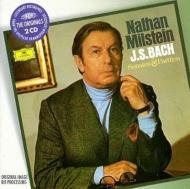
バッハ 「シャコンヌ」/ニワゼキショウ
・『今日のクラシック音楽』 J.S.バッハ作曲 「シャコンヌ」ヨハン・セバスチャン・バッハ(1765-1750)はその生涯で4つの場所で作曲を行っています。 それは大きく分けてという意味ですが、「ミュールハウゼン時代」は1703年~1708年。 「ワイマール時代」が17098年~1717年まで。 1717年~1723年が「ケーテン時代」。 1723年~1750年の「ライプチッヒ時代」。これらの土地でバッハは教会や宮廷の礼拝堂での職に就いて教会のオルガン奏者や楽長などの職を経験しています。 必定作曲される音楽はオルガン曲やカンタータなどの教会に関係する音楽が多くなっています。 例外は「ケーテン時代」で、ここの領主がカルヴィン派(プロテスタンとでこの世の富と繁栄は神の祝福であり、勤労と富の蓄積を神の栄光を讃える行為として肯定し、禁欲的によく働き、富の蓄積を促進した資本主義の形成に内面的に大きな役割を果たした教義とされて有名です)に属していたので、教会のオルガン曲や教会音楽を作曲する義務から解放されて、世俗的な音楽を書くことに専念でしたのでした。 それが無伴奏のヴァイオリン曲やチェロ曲が生まれた背景となっています。この「ケーテン時代」には、「ブランデルブルグ協奏曲」や「ヴァイオリン協奏曲」、「無伴奏チェロ組曲」、「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」、教育用の「平均律クラヴィーア曲集」、「イギリス組曲」、「フランス組曲」が生まれています。ドイツ・バロック時代の遺産とも呼ばれるこうした器楽曲の傑作がケーテンの領主に仕えたことから生まれているのです。 なかでも「無伴奏チェロ組曲」は”チェロの旧約聖書”とも呼ばれるチェロ楽器の最高の作品としても、現代のチェロ奏者にとって最高峰の極みに立つ曲とされています。一方、ヴァイオリン曲としては3曲の「無伴奏ヴァイオリン・ソナタ」、3曲の「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ」がヴァイオリン奏者の「聖書的」存在となっていることは間違いのない作品です。ヴァイオリン奏者としても研鑽を積んだバッハは、ヴァイオリン奏法を消化して先達を超える芸術作品として生み出しているのが「無伴奏」なのです。 単なる旋律楽器としてでなく、対位法的な和声の創意、まるで伴奏的な多声的な響きを創り、作曲技法に見事な昇華を成した芸術作品として創り上げています。多くのヴァイオリン奏者はこれらの作品を舞台で弾いたり、録音をしたりすることが一つの目標としていることは間違いのないことです。 あの有名なダヴィッド・オイストラフは結局一度もこれらの作品を録音に残さなかったことからしても、容易な曲でないことが計り知れることです。 ひときわ輝く演奏にするのは精神的な充実、人生体験などが要求されるのでしょう。「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 二短調 BWB1004」の第5楽章「シャコンヌ」は特に技巧を要する曲で、もともとスペイン舞曲が原型で、短い主題を何度も変装を繰り返す意味となった曲で、バッハここで30回もの変奏を試みており、非常に難しい技巧を要求される、素晴らしく美しい、威厳をもった曲に仕上がっています。 コンサートなどや録音などでも単独で採りあげられる有名なヴァイオリン曲で、約15~6分を要する大曲です。愛聴盤(1) ナタン・ミルシティン(Vn)(グラモフォン 457701 1973年録音 海外盤)ヴァイオリンの美音と言えばこの人。 美音に裏打ちされバッハ音楽の美しさをきわめて決定的名盤(2) ヘンリク・シェリング(Vn)(グラモフォン 453004 1967年録音)知性的演奏の代表盤。 厳しいバッハへの姿勢がひしひしと訴えかけてくる名盤(3) ヨゼフ・シゲティ(Vn)(ヴァンガード原盤 DENONレーベル COCQ83794 195-56年モノラル録音)厳しい姿勢のバッハ。 決して美音ではないが音楽はそれを凌駕する古典的名演奏。(4) 前橋汀子(ソニー・クラシカル SRCR2677 1988年録音)端正な造形、歌にあふれた抒情豊かな演奏に魅かれます。編曲版(1) ミハイル・プレトニフ(P)(グラモフォン 471157 2000年11月カーネギーホールライブ 海外盤)ブゾーニ編曲版。 荒々しい一気呵成に弾きこんだ演奏。 聴く人には賛否両論が出ると予想される演奏。(2) 小菅 優(P)(ソニー・クラシカル SICC545 2005年11月カーネギーホールライブ)まだ20代の小菅がニューヨークのファンに問うた畢生の名演。 遅めのテンポで曲をじっくりと弾いた素晴らしい逸材の名演。ブゾーニ編曲(3) ニコライ・デミジェンコ(P)(ハイペリオン CDA66566 2001年8月録音 海外盤)じっくりと旋律を歌わせて絶品の演奏。 現在この盤が最も普遍的なピアノ演奏かも知れない。 ブゾーニ編曲。 バッハ音楽編曲集の1曲。(4) レポルド・ストコフスキー 指揮 RCAビクター交響楽団(RCA原盤 BMGジャパン BVCC8901/2 1974年録音)ストコフスキーがオーケストラ用に編曲した版で、音楽宇宙がオリジナルから飛び出して独自のファンタジックな世界へと誘う、原曲とは全く違うバッハの世界が広がる名演。(5) 福田進一(ギター)(DENON CREST1000 COCO70812 2000年録音)アンドレ・ゼコビア編曲 ギター好きにはいいかも知れませんが、バッハの深遠な世界とは遠い次元の演奏。 1000円盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1886年 初演 サン=サーンス 交響曲第3番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 庭石菖(ニワゼキショウ)公園や空き地で今を盛りと咲いています。 薄紫色と白の2種類があるようです。 近所の公園で撮った写真です。撮影地 大阪府和泉市 2007年5月18日アヤメ科 ニワセキショウ属 開花時期 5月~6月末。北アメリカ原産で1890年年頃に渡来したそうです。 色は白か紅紫。小さい花ですがきれいです。 葉が石菖(せきしょう)というサトイモ科の植物に似ていて、また、庭によく生える ところから、庭石菖の名になったそうです。 別名 「南京文目」(なんきんあやめ)
2007年05月19日
コメント(16)
-
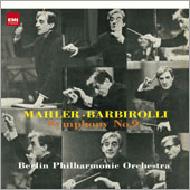
マーラー 交響曲第9番/ヒメツルソバ
『今日のクラシック音楽』 マーラー作曲 交響曲第9番ニ長調今日はグスタフ・マーラー(1860-1911)の命日。 マーラーの作品で最も好きなのは交響曲「大地の歌」。 それに「歌曲集」です。 しかしこれらの曲はすでに日記に書いていますので、今日はまだ書いていない曲で、彼の死と関係ある交響曲第9番を選びました。マーラーの作品は私にとって「負の世界」を描いたのが多くて、どうにも手放しで好きになれない作曲家の一人で、そうかと言って無視できる人、作品ばかりではありません。 どうも始末に終えない一人であることは事実です。日記を書くときは、大概3日前くらいからテーマを決めておいて、前日に草稿を完成させておくのですが、今日の記事はそういうわけにはいきません。 そう「負の世界」。つまり「死」と隣り合わせの音楽が多いからです。 音楽を聴いていても交響曲では第5番くらいまでは「肯定的」な主観のある作品なのですが、それ以後の作品は何か人生を否定的に考えた作品という先入観があります。今日の交響曲第9番も彼の死への恐れが強いでしょうか暗い曲なのですが、聴き終わると不思議な感動に誘われてしまっている音楽です。この曲は1909年~1910年に書かれており、彼の死の前年に完成しています。 この曲の前の交響曲が「大地の歌」でした。 9番目にあたるシンフォニーですが、かれはわざわざこの「大地の歌」に9番という番号を付けていません。 それは彼の先輩たち(ベートーベン、シューベルト、ブルックナー、ドヴォルザーク)の交響曲が9曲で生涯を閉じており、神経質なマーラーは自分も「大地の歌」で死ぬのではないかという観念にとらわれて、わざわざ番号を付することを嫌って単なる「大地の歌」と呼んだというのは、あまりにも有名なエピソードとして残っています。この曲を書いた1910ごろはマーラーは非常に多忙な時期でした。 1908年からニューヨーク・メトロポリタン歌劇場の指揮者を務め、同時にヨーロッパでも指揮者として君臨しており、大西洋を挟んでの指揮活動に励んでいました。 彼の一徹な性格が災いしてウイーン国立歌劇場の指揮者を辞任せざるを得ないという時期のあとでした。体力的に相当な疲れもあったのでしょう。 しかも医師から「心臓病」を宣告されており、悩んでいたのでしょう。 1907年7月には愛娘マリアを亡くす不幸もありました。 精神状態も不安定であったと言われています。自身の病気、家族の不幸が重なり、精神的な疲労が重なる中で書かれた第9番のシンフォニーは、必定「死と向かい合う」姿勢になったのだと思います。それが私のいう「負の世界」なのです。そういう背景で書かれたこの曲は1910年4月1日に完成されています。 1907年以来「死の影」とと共に生きて、それを音楽に表したのがこの第9番です。しかし曲の完成があっても、初演は彼の死後1年余り経って、直弟子ブルーノ・ワルターによって1912年6月26日にウイーンで初演されています。 マーラーは結局9番目の交響曲となった「大地の歌」を聴いたのみで、この「第9番」の演奏を聴くことなく51歳の生涯を閉じています。この曲の形式は従来の交響曲形式が逸脱した、マーラー独自の音楽観で貫かれています。 第1楽章と第4楽章には遅いテンポの曲が置かれており、ソナタ形式も自由に拡大されて書かれています。第1楽章の序奏ではホルン、ハープ、低弦楽器などでこの楽章の根幹となるリズムが刻まれてのち、ヴァイオリンで美しい旋律がおずおずとした風情で現われます。 これがこの楽章の主題の根幹を成しており、何度も新しい衣装をまとったかのように表れます。 展開部では音量も大きくなりますが、やがて主要旋律が何度も繰り返されて静かにこの楽章を終わります。 全曲中最も長い楽章で、ここだけでカラヤン指揮のベートーベンの交響曲第5番全曲がすっぽりと入ってしまいます。第2楽章はレントラー風の舞曲で、3種のレントラー主題をもったスケルツォ形式の音楽です。第3楽章は、「ブルレスケ」風のマーラー特有の歪みのある、野性的で、反抗的な、グロテスクな雰囲気の楽章です。 ユーモラスな情感も伝えてはいますが、やはりマーラー特有のゆがみのある音楽が特徴です。第4楽章は、ブルーノ・ワルターの言葉によれば「マーラーは心静かに世界に別れを告げている」音楽で、悲哀のこもった流れるような旋律で始まります。 この楽章が白眉で、透明度をいよいよ増して、彼岸のかなたへと旅立っていくような情感のこもった音楽が展開していきます。この楽章で聴き手は明確にマーラーの意図を知ることができます。 「死の世界」への旅立ちが美しく浄化された感動的な音楽が流れ、ブルーノ・ワルターの「紺碧の大空に溶け込んでゆく雲のように」、やがて静かに曲を閉じていきます。そしてここに後期ドイツ・ロマン派音楽の幕が閉じられ終焉に向かうのです。グスタフ・マーラーは1911年の今日(5月18日)、51歳の生涯を閉じています。愛聴盤 (1) サー・ジョン・バルビローリ指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団(EMI原盤 東芝EMI TOCE13423 1964年録音)ベルフィルの総意で実現した録音。 「メロウ・サウンド」と呼ばれるバルビローニ特有の温かいサウンドに包まれた稀有なマーラー演奏。 イギリスにWarm Beerという飲み方があります。陶器のビールカップを温めて、冷たいビールを注いで飲むのですが、そのビールの温かい味と同じような、ヒューマンな味の伝説的名演。(2) ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団(ソニー・クラシカル SRCR2337 1961年録音)ワルター特有の「歌」にあふれた、テンポを遅くしてじっくりと歌わせた最晩年の名演。(3) カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック 1984年ライブ録音)徹底したカラヤン美学(オーケストラを磨き上げて、その華麗な技術を塗りたくった)で貫かれたある意味では美しい演奏。(4) バーンスタイン指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団(グラモフォン 435378 1979年ライブ録音 海外盤)たった一度のバーンスタインとBPOの演奏。 凄まじい情念が噴き出した生命力豊かな、一期一会の名演。 カラヤンがバーンスタインがBPOを振るのを嫌ったというエピソードが残っているが、この演奏を聴くとベルリンの人たちはいかに大きな宝を逃したがわかる演奏。(5) ヴァーツラフ・ノイマン指揮 チェコフィルハーモニー(EXTON OVCL00268 1995年録音)ノイマンの遺言。 この曲を録音して2週間後に他界したノイマン畢生の名演。 実に丁寧に曲を掘り起こしており、曲の隅々まで照らしている名演盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1897年 初演 デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」1909年 誕生 イサーク・アルベニス(作曲家)1911年 没 グスタフ・マーラー(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ヒメツルソバ撮影地 大阪府堺市緑化センター
2007年05月18日
コメント(8)
-
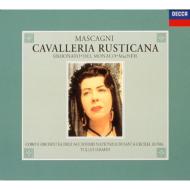
オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」/薔薇
『今日のクラシック音楽』 マスカーニ作曲 オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」イタリアの作曲家ピエトロ・マスカーニ(1863-1945)といえばこの曲、オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」です。マスカーニ25歳の時の作品で、ローマの楽譜出版社が募集したオペラ作品に応募して賞金をもらい、初演は1890年の5月17日にローマで行なわれています。 この初演は大成功をおさめ、マスカーニは一躍有名作曲家となったオペラです。このオペラは同名小説をオペラ化したもので、開放的で感情的なところのあるシチリアを舞台にした一幕オペラで、「カヴァレリア・ルスティカーナ」とは「田舎の騎士道」という意味です。 謂わば「男の道」みたいなものでしょう。 シチリア人は激情的なところがあり、すぐに感情を露にする傾向があり、「シチリアの決闘」という言葉があるほど熱しやすい気質の地方です。物語はシチリアのある村の青年トリッドゥが兵役から免除されて帰ってくると、恋人だったローラが馬車屋のアルフィオと結婚していました。 そこで彼は、村の女性サントッツアと交際をするのですが、ローラのことを諦めきれず昔のようによりを戻します。 所謂「不倫恋愛」です。 このことを知ったサントッツアは嫉妬のあまり馬車屋に告げ口をしたために、二人の男の決闘となりトリッドゥは殺されて幕となる暗い話です。このオペラは「ヴェリズモ・オペラ」と呼ばれており、それまでのヴェルディの「椿姫」に代表される上流社会を舞台にしたオペラではなく、イタリアのどこの村にでもいる青年男女を主人公にして、「夢想的」な世界でなく、「現実的」な生活の中で起こることを描写したオペラです。 「ヴェリズモ」とは『現実』という意味です。音楽はシチリアの甘く美しい旋律に溢れています。第1幕の幕が上がる前の前奏曲静かな抒情的な旋律が流れる中、トリッドゥの甘い、しかし情熱的なアリア「おー、ローラ」が歌われています。合唱曲「オレンジの花香りは平和なシチリア村の日常の風情を表しており、これから起こる悲劇など感じられないのどかな平和な村をの様子を歌った合唱がとても美しく響いています。有名なアリア「ママも知る通り」(サントッツアのアリア)で初めて悲劇的な情緒が舞台を包んできます。 ローラにトゥリッドを取られたサントッツアの嘆きが胸を打ちます。そしてサントッツアとトゥリッドの激しいやり取りが激情の渦の中に巻き込んでいきます。ここの二人の歌も激しい熱情にあふれた見事な旋律が、聴く者の心を打ってきます。「間奏曲」コンサートで単独でも採り上げられる美しい抒情にあふれた旋律で、数あるオペラ間奏曲の中でも、これほど美しい旋律が見当たらないほど、と言える見事な曲です。「母さん、あの酒は強いね」は、これからアルフィオとの決闘に出かける前にトゥリッドが母に歌う別れのアリア。 何度聴いても涙が出そうな素晴らしいアリアです。旋律は美しく哀愁もあり、70分あまり聴く者をシチリアへと誘うオペラです 1890年の今日(5月17日)、このオペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」が初演されています。愛聴盤 (1)マリオ・デル・モナコ(テノール) ジュリエッタ・シミオナート(メゾ・ソプラノ) コーネル・マックニール トリオ・セラフィン指揮ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団・合唱団(Decca レーベル ユニヴァーサル・クラシックス UCCD 3341 1960年7月ローマ録音)↓シミオナートもう45年前のステレオ録音ですが、デル・モナコの感動的な「黄金のトランペット」最盛期で、シミオナートのあたり役サントッツアは、未だにこの録音を凌駕する歌唱がないと思えるほどの激情に溢れた名唱です。 LP時代からもう数え切れないくらい聴いていますが、『母さん、あの酒は強いね』のモナコのアリアは今でも涙が溢れてくるほどの迫真の歌唱、シミオナートの「ママも知るとおり」の切ないサントッツアの心情のアリアなど、色褪せない名演奏です。(2)カラヤン指揮 ミラノスカラ座管弦楽団・合唱団 フィオレンツア・コッソット(Ms)カルロ・ベルゴンツィ(T) (グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG30148 1965年録音)マスカーニの美しい旋律を情感たっぷりに歌わせて、劇的なドラマとして仕上げており、緊迫感あふれる精巧な表現は、さすがカラヤン。 この指揮者をあまり好きでないのですが、オペラは別物。 素晴らしいオペラ指揮者です。(3)ジュリエッタ・シミオナート(Ms)フランコ・コレッリ(T) ミラノ・スカラ座管弦楽団&合唱団 ジャナンドレア・ガヴァッツェーニ(指揮) (Music & Arts OPD1448 1963年12月7日ライブ録音)シミオナートのサントッツア、コレッリのトゥリッドという黄金スターの顔合わせ。 60年代は凄かったと感じられるイタリア・オペラ黄金時代の遺産。(4)1961年にNHKの招きで来日した「イタリア歌劇団」は日本中のオペラファンを熱狂させて去って行きました。 モナコとテバルデイの「アンドレア・シェニエ」モナコの「道化師」アルド・プロッテイの「リゴレット」 テバルデイの「トスカ」 モナコの「アイーダ」 それにシミオナートのこの「カヴェレリア・ルスティカーナ」とまさにオペラファンを完全にKOした秋でした。幸運にも私は大阪公演でモナコの「道化師」 シミオナートの「カヴァレリア・・・・」をフェスティバルホールで観ることができました。 高校2年生でした。 あの夜の名舞台が昨日のように蘇ってきます。 NHK映像DVDであの夜の感動を味わっています。(NHK DVD キングインターナショナル KIBM1016 1961年 東京文化会館での公演ライブ)↓シミオナート(5)最近の映像で凄いのがあります。 ゼッフィレッリが演出したオペラ映画「カヴァレリア・ルステイカーナ」がそれです。 プラッシード・ドミンゴのトリッドゥ、オブラソッワのサントッツア、ジョルジョ・プレートルの指揮で演奏されるこの映画は、ゼッフィレッリ抜きでは話せない映画です。 シチリアの情景をたっぷりと見せて、前奏曲ではトゥリッドとローラのベッドを映し出し、朝早く自宅に帰って行くトゥリッドを「オ~、ローラ」のアリアにかぶせたり、最後の決闘場面を描いたり、オペラ音楽を忘れて映像、映画として見事な出来映えの演出です。 「道化師」とのカップリングで、ドミンゴ、ストラータスのオペラ映画「ラ・トラヴィアータ」と双肩の出来映えです。(グラモフォン・レーベル ユニヴァーサル・クラシックス UCBG1100 1982年制作)↓ドミンゴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1866年 誕生 エリック・サティ(作曲家)1890年 初演 マスカーニ オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」1906年 誕生 ジンカ・ミラノフ(ソプラノ)1918年 誕生 ビルギット・ニルソン(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 薔薇(ダブル・デライト)撮影地 大阪市立長居植物園
2007年05月17日
コメント(2)
-
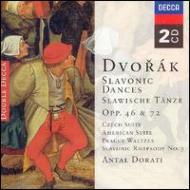
スラブ舞曲集/鈴蘭(スズラン)
『今日のクラシック音楽』 ドヴォルザーク作曲 「スラブ舞曲集」アントニン・ドヴォルザーク(1841-1904)はブラームスとの親交が深かった一人です。 もちろんブラームスの方が先輩なのですが、ドヴォルザークが無名の頃オーストリア政府の奨学金制度に応募を始めてからその応募作品に、審査員をしていたブラームスの目にとまり、その才能と可能性に注目してからだと、言われています。ドヴォルザークの民族的特質・民族色を活かした音楽に注目したのでした。 それがドヴォルザークの作曲家への道を拓く契機になったことは言うまでもありません。 そして生涯を通じての親交が続きます。そんなブラームスが、自身ピアニストとしてヴァイオリン奏者と共に東欧諸国を歩いた時の体験から作曲したのがピアノ連弾用「ハンガリー舞曲集」でした。 ご存じのようにこの曲は世界を席巻して大人気曲となり、今では全曲が管弦楽用に編曲されて、ピアノ演奏用を凌駕するまでになっています。自分の「ハンガリー舞曲集」に気を良くしたブラームスは、ドヴォルザークにもスラブ的な舞曲集の作曲を勧めました。 そこに介在したのが楽譜出版のジムロックでした。 彼はブラームスの「ハンガリー舞曲集」を出版した人でした。ブラームスとジムロックの勧めで作曲して発表したのが「スラブ舞曲第1集」でした。 当初この曲は、ブラームスと同様にピアノ連弾用として書かれていますが、ドヴォルザークは管弦楽用にも全曲編曲して、いっそうの人気曲となったようです(ちなみにブラームスは3曲しか管弦楽用に編曲していません)。ブラームスの「ハンガリー舞曲集」と同じで1曲が約3~5分という短い曲ばかりで、演奏会のアンコール・ピースとしてもよく演奏されています。「スラブ舞曲集」は、チェコやポーランド、小ロシアなど東欧の民族色豊かな音楽で、ポロネーズ、ドゥムカ、フリアント、ポルカなどの舞曲ばかりを集めたもので、スラブの土の匂いがする実に見事な、魅力的な音楽に仕上がっています。曲は第2集まであり第1集、第2集ともに8曲づつで構成されています。 ピアノ連弾用用よりも管弦楽版の方がはるかに色彩的でスラブの情感が、弦楽器や管楽器で色濃く語られており、スラブの哀愁がひしひしと伝わってくるし、また陽気な舞曲の溌剌とした気分が味わえて、私は管弦楽用を聴いています。全16曲全てが素晴らしく魅力のある音楽ですが、特に「スラブ舞曲集」の代名詞と呼んでも言いくらいの、第1集の「第3番」チェヒ舞曲に基づくポルカや、「第8番」のフリアントに始まり、フリアントに終わる音楽、第2集のドゥムカ風の抒情豊かな「第10番」などを、気に入って聴いています。1878年の今日(5月16日)、管弦楽用の第1集がプラハで初演されています。愛聴盤 アンタル・ドラテイ指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD3883 1983年録音)コダーイ、バルトークの門下生ドラテイが最晩年に録音した全曲盤。 緻密なアンサンブルと精妙を極めるバランスの良さ。 好きな指揮者の一人ですが、1988年に他界しました。このジャケットは現在発売中の2枚組ディスクで、「チェコ組曲」が収録されています。上記商品番号は7月25日に再発売される「アンタル・ドラティの芸術」の1枚です。 1200円で買いやすい価格になっています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1878年 初演 ドヴォルザーク 「スラブ舞曲 第1集」(オーケストラ版)1893年 誕生 パウル・ファン・ケンペン(指揮者)1922年 誕生 オットマール・スイトナー(指揮者)1954年 没 クレメンス・クラウス(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 鈴蘭(スズラン)
2007年05月16日
コメント(12)
-
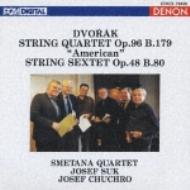
弦楽四重奏曲「アメリカ」/薔薇
『今日のクラシック音楽』 ドヴォルザーク作曲 弦楽四重奏曲第12番 「アメリカ」今日もチェコの作曲家アントニン・ドヴォルザーク(1841-1904)が、アメリカ滞在中に書いた「アメリカ三部作」(これは私が勝手に名付けています)の一つ、弦楽四重奏曲第12番ヘ長調 作品96です。アメリカに渡って約2年半ナショナル音楽院の院長としての職務を果たしているうちに郷愁に駆られたドヴォルザークは、彼の弟子の勧めでアイオワ州スピルヴィルへ避暑に出かけます。 そこはボヘミア移民の多いところでドヴォルザークにとって郷愁を癒す格好の場所でした。 ボヘミアの自然と似た風景があり、チェコ料理を楽しめ、母国語を話せる場所でした。 そのスピルヴィルで作品95の「新世界より」を仕上げたのでした。アメリカにわたって以来ドヴォルザークにとって黒人霊歌やアメリカインディアンの民謡音楽が、とても新鮮に聞こえたのでしょう。 音楽は必ずしもそういうアメリカ土着の歌を歌いげているのではないのですが、少なからず「新世界より」や「チェロ協奏曲」に色濃くその影を落としています。「ナショナル音楽院」は当時としては少し変わった学校で、経営者サーバー夫人の意図で白人、黒人の区別なく生徒を受け入れていたそうです。 それでいっそう黒人霊歌との接触があったのでしょう。 「黒人霊歌」は五音階でできており、ボヘミア音楽とどこか通じるものがあったのでしょうね。 こうしたドヴォルザークのとっての未知の音楽が、彼に創作意欲を湧き起させたのでしょう。この「弦楽四重奏曲第12番」はスピルヴィルに着いて3日後に着手されて、わずか2週間で書き上げられています。 やはりこれらの未知との遭遇が異例の速さで仕上げるエネルギーになったのでしょう。 それと故郷への郷愁も大きく影響していたのでしょう。 1893年の夏のことでした。 初演は翌1894年1月12日にボストンで初演されて、大成功のうちに終わったそうです。曲は4楽章構成で書かれており約25分ほどの演奏時間で、全楽章とも民族的な色彩・情緒・情感の色濃い音楽で、非常に親しみやすい旋律に充ち溢れた音楽です。いきなり「新大陸」に放り投げられたような感じのする、非常におおらかな気分の第1楽章や、ノスタルジックで哀愁漂う感傷的な第2楽章など「五音階」が使われており、ボヘミア音楽の「五音階」と見事に融合しており、いかにドヴォルザークがアメリカ土着の音楽に興味を持っていたを物語る音楽です。 愛聴盤 (1) スメタナ弦楽四重奏団(DENON CREST1000 COCO70436 1988年録音)練り上げられた、瑞々しい表現が素晴らしい、自国の大作曲家への共感が伝わってくるような名演です。 解散したことが惜しまれる演奏です。(2) アルバン・ベルク弦楽四重奏団 (EMI原盤 TOCE9022 1989年ウイーンライブ録音)アンサンブルの完璧さ、精緻な表現、どこを切り取っても不満のない見事な演奏。 不満があるとすれば「完璧なアンサンブル」がぬくもりを遠ざけていることでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1913年 初演 ドビッシー バレエ音楽「遊戯」1920年 初演 ストラヴィンスキー バレエ音楽「プルチネルラ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 薔薇近所の公園でバラが咲いているので、同級生の車で一緒に観に行ってついでに1枚撮ってきました。何故か今年は咲いている花はほとんど傷があって写真にできないものばかり。 かろうじてこの1枚のみ撮りました。 やはり生気がないですね。撮影地 大阪府和泉市 2007年5月14日
2007年05月15日
コメント(10)
-
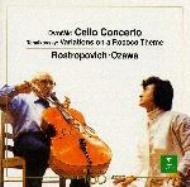
ドヴォルザーク チェロ協奏曲/ユキノシタ
『今日のクラシック音楽』 ドヴォルザーク作曲 チェロ協奏曲ロ短調 作品104アントニン・ドヴォルザーク(1841-1904)が、アメリカの「ナショナル音楽院」の院長をしていた頃に生れた交響曲第9番「新世界より」の作曲経緯は昨日の日記に書きました。 彼のアメリカ滞在中に生れた傑作は「新世界より」だけでなく、他にもまだあります。 「新世界より」とと共にドヴォルザークの最高傑作と言われている「チェロ協奏曲ロ短調 作品104」もその一つです。ニューヨークのジャネット・サーバー夫人から請われて「ナショナル音楽院」の初代院長として、1892年の秋にドヴォルザークはアメリカに赴き約2年半の滞在期間中に書いた作品で「アメリカ三部作」とも呼べる3曲があります。 一つは昨日掲載しました「新世界より」。 二つ目は「弦楽四重奏曲第12番アメリカ 作品96」。 三つ目は今日の話題曲「チェロ協奏曲ロ短調 作品104」。チェロの前身は「ヴィオラ・ダ・ガンバ」(足のヴィオラ)という楽器で、バロック期から通奏低音楽器として使われてきています。チェロはよく 女性の体形と比べられますが、良く似た小型のヴァイオリンが明るい高い澄んだ音色であるのに対して、ヴァイオリンよりも女性体形に似ているチェロはとても男性的な音を響かせます。 温かくて深く、朗々とした響きを出す楽器です。チェロを独奏楽器として位置づけたのは大バッハではないでしょうか。 パブロ・カザルスによって発見された「無伴奏チェロ組曲」によって、バッハがすでにこの楽器の性能をよく知っていたことを証明しており、「チェロの旧約聖書」と呼ばれ、のちにベートーベンが書いた「チェロ・ソナタ」が「新約聖書」と呼ばれており、チェロの市民権が確立しています。ところが協奏曲となると、ボッケリーニ、ハイドンが書いて以来本格的な協奏曲は数少ないのです。 19世紀後半になってサン=サーンス、シューマン、ラロなどの協奏曲が生まれていたのですが、このドヴォルザークの曲で影が薄くなってしまいました。ドヴォルザークは一度祖国へ帰っています。 よほど郷愁に駆られていたのでしょう。 このチェロ協奏曲も一時帰国前から書かれており、「新世界より」と比べてもよりいっそうボヘミア的郷愁を感じさせる音楽になっています。アメリカに再度帰ってきてもドヴォルザークは契約任期を務めることが出来ずに、1895年の春、永久にアメリカに別れを告げて帰国しました。 この曲は帰国後プラハで最終楽章の手直しをして完成させ、翌年1896年の春にロンドンで初演されています。この曲の魅力は第1楽章は、序奏がなくていきなり低弦とクラリネットで第1主題提示を終わって独奏チェロが奏でられると、まるで歌舞伎の千両役者の登場のような趣きがあります。 また独奏者にとっても弾きがいのある部分ではないでしょうか。 ロマンティックな情緒の第1主題の旋律からして、すでにボヘミヤ的な情感がたっぷりです。 展開部でチェロがお休みというのも面白い趣向です。 第2主題が五音階で牧歌的主題が奏でられて、この2つの主題が軸となっています。 いかにもロマン派の、国民樂派の協奏曲という貫録たっぷりの楽章です。私が一番好きなのは第2楽章です。 独奏チェロによるボヘミヤ的な哀愁が漂う旋律が素晴らしく、これほどまでにドヴォルザークの郷愁が高まっていたのかと思うくらいに、哀感漂うしみじみとした情緒がとても美しい楽章です。 とてもノスタルジアに満ちたセンティメンタルな情緒が、チェロの深みのある、甘く抒情的な音色で美しい音の世界が繰り広げられています。第3楽章は、ボヘミア的な民族舞曲風の旋律がとても印象的で、華麗なチェロの技巧が活躍する溌剌とした音楽で、この楽章を帰国後プラハで手直しをしたという経緯から、故郷に戻ってきたドヴォルザークの喜びを謳い上げているようです。ブラームスがこの曲を聴いて「私は何故こういう書き方に気がつかなかったのだろう」と絶賛した有名なエピソードが残っています。最初にドヴォルザークの最高傑作と書きましたが、おそらくチェロ協奏曲の最高傑作であることは間違いないと思います。 とても好きな曲です。愛聴盤大好きな曲ですから色々なチェリストの演奏で聴いてみたいという想いが強くて、他の協奏曲に比べてディスクの数も多くなっています。(1) ロストロポーヴィチ(チェロ) 小沢征爾指揮 ボストン交響楽団 (エラート原盤 ワーナー・ミュージック WPCS21056 1985年2月録音)朗々とした音色、スケール雄大な幅の広い表現が見事。 テンポを自在に動かし、音色を多彩に使い分けた演奏は独壇場。 最強音から最弱音までの情感豊かな表現。 絶え入るようなピアニッシモは圧巻。(2) ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ) アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 (マーキュリー原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7075 1962年7月録音)鋭利な刃物のような感じを与える音色で、朗々とした響きはロストロポーヴィチと変わらないが、非常に精緻な表現の音色で、一度聴くとたちまち人を引き付ける魔力のようなものを持った技巧の素晴らしいチェロ。(3) ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) バレンボイム指揮 シカゴ交響楽団(EMI原盤 東芝EMI TOCE59051 1970年5月録音)私が付け加える言葉がないほどに絶賛されている「世紀に一人」と言われる女性チェリスト。 激しい情熱が噴き出す物凄い演奏。 初めてLP盤で聴いた時には、言葉を失って聴いていた記憶があります。 1971年に26歳で難病の「多発性硬化症」を発病してから闘病生活をつづけ、1987年に42歳で亡くなった空前絶後と言いたくなる別格のチェリスト。(4) ピエール・フルニエ(チェロ) ジョージ・セル指揮 ベルリンフィルハーモニー (グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG5051 1962年録音) 「高貴なプリンス」と呼ばれたフルニエとセルが繰り広げる格調高い演奏。 ロストロポーヴィチやシュタルケルのような豪放さや荒々しさもない、実に品格のあるチェロで穏やかに、柔和にボヘミアの郷愁を切々と語った名演。(5) ピーター・ウィスペルウエイ(チェロ) ローレンス・ネレス指揮 オランダフィルハーモニー (CHANEL CLASSICS CCS8695 1995年12月録音 海外盤)「力強さ」と「優しさ」「柔和さ」で聴く者を柔らかく包み込んでくれるような表現のチェロの音色です。 ボヘミアの郷愁がを吹き渡るかのような音色が部屋を満たしてくれます。ロストロポービチやシュタルケルのような剛毅さでもなく、デ・ピュレのような情熱的な激しさでもなく、チェロの音色を汚れなく美しく響かせて、それでいて決してBGM的な音色にならずに、ステレオ装置の前でじっと耳を傾けて聴き入ってしまう、稀有な演奏家の一人です。(6) オーフラ・ハーノイ(チェロ) マッケラス指揮 プラハ交響楽団(RCAレーベル 09026 68186 2 1994年9月録音 海外盤)6枚のディスク中、最もテンポを自在に動かした演奏で、思い入れたっぷりな非常に個性的な演奏。 一時期よく日本で演奏会を開いていたが、最近は来日のニュースも聞かないがどうしているのだろうか。 彼女の演奏はヴァイオリンのソネンバーグのような奔放とまで言わないが、自在にテンポを動かして強弱をたっぷりと付けて「妖艶」な演奏が魅力。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1832年 初演 メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」1885年 誕生 オットー・クレンペラー(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ユキノシタ撮影地 大阪府和泉市 2006年5月
2007年05月14日
コメント(22)
-
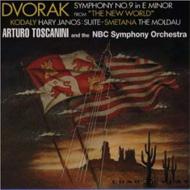
ドヴォルザーク「新世界より」/麦撫子
『今日のクラシック音楽』 ドヴォルザーク作曲 交響曲第9番「新世界より」アメリカ・ニューヨークのジャネット・サーバー夫人から、彼女が経営する「ナショナル音楽院」の院長という職への要請が、チェコのアントニン・ドヴォルザーク(1841-1901)に届いたのは1891年の春で、その頃のドヴォルザークは既に8つの交響曲、ピアノ曲、室内楽作品、オペラなどを発表しており、ヨーロッパでは大作曲家の一人でした。受託までは紆余曲折がありましたが、ドヴォルザークは1892年9月15日にニューヨークに向けて旅立ちました。 ニューヨークには9月26日に到着しました。 それから約2年半彼はアメリカに留まります。その頃のアメリカは、すでに大陸横断鉄道が完成しており、1793年に独立を果たして109年目を迎えていました。ドヴォルザークがアメリカについて驚いたのは、活気にあふれた街並みでした。 まだエンパイア・ステートビルは建っていませんが、大きな建物がブロードウエイに立ち並び、行き交う群衆の活気あふれる姿に驚いたそうです。 祖国の田舎町とは比較にならない活気ぶりでした。 もう一つは「黒人霊歌」や純朴なアメリカ民謡に大きな感動を受けたそうです。 アフリカから奴隷として売られてきた黒人たちの歌う「黒人霊歌」は、虐げられた人々の救済への祈りと願いを込めた歌ですが、ドヴォルザークはその歌にいたく感銘を受けて、自宅に黒人歌手を呼んで彼らの歌に耳を傾ける機会が非常に多かったそうです。ドヴォルザークは、それまでアメリカ人には不当に低く見られていた「黒人霊歌」の価値を高く認めた、最初の大作曲家であったそうです。 彼は美しく変化に富む黒人霊歌を「土の産物」として評価していました。「ナショナル音楽院」の忙しい職務のかたわら、1893年の約半年間新しい交響曲への構想をまとめて草稿を仕上げています。 その年(1893年)の夏に休暇を取ってニューヨークから遠く離れたアイオワ州の町へと旅立ちます。 この時にはドヴォルザークはかなりひどいホームシックに陥っており、音楽院の弟子の勧めでわざわざ遠いアイオワまで出かけたそうです。そこはスピルヴィルという小さな町ですが、そこにはボヘミアから移住してきた人々が数多く住んでいた所で、母国語を気兼ねなく話すことが出来、祖国の料理を楽しめる、祖国の雰囲気を味わえる土地でした。 アイオワの自然は祖国のそれと似ていたのかも知れません。 ボヘミア移住民と接することで彼の郷愁も少しずつ和らいでいったそうです。こうして新しい交響曲は短期間で書き上げられています。 それが交響曲第9番ホ短調「新世界より」なのです。 初演はその年(1893)の12月16日にニューヨークで行われており、大成功に終わったそうです。「新世界より」はドヴォルザーク自身が付けた副題で、当時ヨーロッパでは「新大陸」と呼んでいたアメリカを指す「新世界」ですが、音楽にはアメリカ・インディアンの民謡と思しき旋律や、黒人霊歌の旋律らしいものが使われていますが、彼が何故「新世界より」と「より」を付けたを考えると、決して「新大陸」を表現した音楽ではなくて、遠くアメリカからボヘミアを望郷の想いで書いたことは容易に想像できます。 この「新世界より」は、ドヴォルザークが故郷ボヘミアを想って書き綴った「手紙」のような音楽でしょう。 アメリカ的な匂いがすると感じれば、その「手紙」をアメリカで書いたからと思えばいいのではないでしょうか。この作品中、最も有名なのが第2楽章「ラルゴ」です。 イングリッシュ・ホルンによる郷愁を誘うような美しい旋律は一度聴けば忘れられない、ほのぼのとした哀愁を誘う旋律で、今では「家路」という名前で合唱曲にさえなっている有名な旋律です。 小学校の下校時の音楽もこの旋律を使っている学校が一体何校あるでしょう。 ほとんどの学校が使っているほど家路に着く旋律にぴったりです。1957年、私がクラシック音楽に興味を持って聴き始めた時に、小学校の恩師が貸してくれたLPがこの「新世界より」でトスカニーニ指揮 NBC交響楽団の演奏で、何度も何度も第2楽章「ラルゴ」を聴いていました。私がクラシック音楽を聴く原点の一つでもありました。 今日はこのドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」に、じっくりと耳を傾けて聴いてみようと思います。愛聴盤(1) アウトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 (RCA原盤 BMGジャパン BVCC38037 1953年2月2日録音)今聴いてもちっとも色褪せない、早めのテンポで推進力のある演奏で、トスカニーニ特有のカンタービレの美しさに酔える演奏です。 録音の古さも気にならない名演奏です。スメタナの「モルダウ」とのカップリングで1,500円です。(2) イシュトヴァン・ケルテス指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7005 1960年録音)トスカニーニの演奏をインターナショナル的なものとすれば、ケルテスはボヘミアの情感をたっぷりと焙りだして、堅固な造形をも作り出しており、しかもウイーンフィルの弦楽器やホルンなどの極上の美しい響きを醸し出した稀有の名演。 1968年にこの曲をケルテス指揮 読響の演奏会で聴いた感動は今もって忘れえない感激の一つです。 スメタナのオペラ「売られた花嫁」~序曲がカップリングされていて、1000円盤です。(3) サー・ゲオルグ・ショルティ指揮 シカゴ交響楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック 1985年録音)ショルティの鋭利な刃物で切り裂くような、精緻な音楽作りとダイナミックな表現が素晴らしい演奏で、録音も恐ろしくなるほどの超優秀録音盤です。 シューベルトの「未完成」がカップリングされて1800円です。(4) ヴァーツラフ・ノイマン指揮 チェコフィルハーモニー管弦楽団 (CANYON CLASSICS PCCL00273 1995年1月録音)ノイマン最後の「新世界より」の録音。 適度なテンポで歌われ、ボヘミア的郷愁がどの楽章にもただよう、弦楽器が豊かに響く、まるでノイマンの「遺言」のような色彩豊かな情感のこもった名演奏盤。(ジャケットはSACD盤ですが、商品番号は通常のCDです)通常のCDも3000円。 このSACDも3000円です。 カップリングはドヴォルザークの「交響的変装曲」です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1833年 初演 メンデルスゾーン 交響曲第4番「イタリア」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 麦撫子(ムギナデシコ)撮影地 大阪府和泉市 2006年5月
2007年05月13日
コメント(12)
-
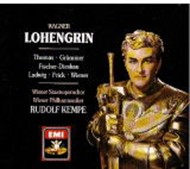
ワーグナー「ローエングリン」/躑躅(つつじ)
『今日のクラシック音楽』 ワーグナー作曲 オペラ「ローエングリン」リヒャルト・ワーグナー(1813-1883)の書き遺したロマンティック・オペラの最後の飾る作品で、このオペラ以後ワーグナーは文学と音楽と造形芸術を総合した「楽劇」の世界へと取り組んでいきます。 ワーグナー音楽としては当然のちの楽劇のような難解なところがなくて、非常に親しみやすい、美しい旋律が全曲中に散りばめれられているロマンティックなオペラです。ヨーロッパには昔から色々な伝説があります。 ワーグナーはこのオペラでもヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハの叙事詩「パルジファル」、コンラート・フォン・ヴュルツブルクの「白鳥の騎士」、バイエルン地方の吟遊詩人の叙事詩、グリム兄弟の「ドイツ伝説集」などを題材にして自ら台本を書いています。あらすじは簡単に書けばこんな風です。物語の舞台は10世紀、アントワープ近く、スヘルデ川のほとり。ドイツ国王ハインリヒ1世が、ザクセン軍を率いてブラバント公国を訪れると、ブラバント公が亡くなってから、世継ぎのゴットフリート公子が行方知れずとなっているが、それは公子の姉エルザ公女の仕業に違いないと、テルラムント伯爵から聞かされます。ハインリヒ王は、エルザ公女に真偽を問いただすが、彼女は夢に見た白鳥の騎士が自分の無実を証明してくれると弁明します。 それではとテルムラント伯爵がその白鳥の騎士と決闘をすると言い出します。 決闘による神明裁判です。エルザ公女が一心に祈り始めると、白鳥の引く小船に乗り、銀色に輝く甲冑に身を固めた見知らぬ騎士が現れ、エルザ公女の決闘の代理人を努めようとと名乗り出ます。 ただし、決して彼の名前と素性を尋ねてはならない、とエルザ公女にそれを誓わせて、決闘が始まりますが白鳥の騎士の圧勝で終わり、エルザ公女の潔白が証明されます。決闘に敗れたテルラムント伯爵は自暴自棄になりますが、妻のオルトルートは、白鳥の騎士が勝ったのは魔法によるまやかしだからといって慰めます。 夜が明けると、国王の伝令がやってきて、テルラムント伯爵に追放処分が出たことを告げます。白鳥の騎士は、ブラバント公の地位を提供されますが辞退して、「ブラバントの守護者」になり、エルザ公女と結婚することになります。 婚礼のために、エルザ公女が聖堂に向かっている途中で、オルトルートは、白鳥の騎士が名前も素性も明らかにしないのはおかしいと言い出します。 一同は、そんなオルトルートを非難しますが、エルザ公女は、名前を訊いてはならないという白鳥の騎士との約束を守れるか、不安を覚えます。そして、白鳥の騎士と二人きりになったエルザ公女は、とうとう我慢しきれなくなり、禁断の彼の名前と素性を教えて欲しいと言ってしまいます。白鳥の騎士は、自分こそ、聖杯騎士のローエングリンであると名乗りますが、聖杯城の掟により、素性を明かしたからにはローエングリンは立ち去らなければならない。白鳥の騎士は、放心状態のエルザ公女に別れの言葉を告げます。するとオルトルートが現れて勝利を叫びます。しかし、ローエングリンが祈りを捧げると、そこにいた1羽の白鳥が行方不明になっているゴットフリート公子の姿に戻ります。 ゴットフリートは、オルトルートの魔法で白鳥に姿を変えられていたのでした。 自らの魔法が破れたことを知ったオルトルートはその場に倒れ、ローエングリンは姿を消し、一同が嘆く中でエルザ公女は息を引き取ります。これは超人間的性格男性と人間女性の何とも悲しい恋愛物語です。日本にも民話「鶴の恩返し」があります。 これと似たような悲恋物語です。尚、「聖杯騎士」とは、キリストが十字架に架けられた時に、その血を受けたとされる伝説的聖杯の守護者という騎士のことです。随所に美しい音楽が散りばめられており、序曲にあたる「第1幕への前奏曲」はこの聖杯騎士ローエングリンの降臨を象徴するかのような、神々しさに溢れた旋律と情緒が素晴らしく、単独で演奏会や「ワーグナー管弦楽曲集」などのディスクに収録されている、このオペラの根幹を成す音楽となっています。また「第3幕への前奏曲」も豪華・華麗・勇壮な音楽でローエングリンとエルザの婚礼の気分を表す有名な音楽で、これも演奏会や録音などで単独に採り上げられています。最も有名なのは「婚礼の合唱」でしょう。 どの結婚式場でも鳴り渡る壮麗な結婚式の合唱で、メンデルスゾーンの「結婚行進曲」共に超有名曲のなっています。また第1幕の「エルザの夢」、第2幕「そよ風の歌」、第3幕「花の香りの歌」、「名乗りの歌」、「白鳥の歌」など聴きどころ満載のオペラです。全曲通して220分という長大なオペラですが、オペラ好きなら一度は聴いておきたいワーグナー畢生のロマンティック・オペラです。今日はドイツの名指揮者ルドルフ・ケンぺ(1910-1976)が亡くなった命日です(5月11日説もあります)。 彼が1963年にウイーンフィルと遺した名演でこの曲を聴いてみようと思っています。愛聴盤(1) ルドルフ・ケンぺ指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団 ウイーン国立歌劇場合唱団ジェス・トーマス(T)、 エリザベート・グリュンマー(S)、クリスタ・ルードヴィッヒ(Ms) ディートリッヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br)(EMIレーベル 49017 1963年録音 海外盤)リズム感が素晴らしく、非常に透明な響きでこのオペラの美しさを見事に表現しており、220分の長さを感じさせない素晴らしいロマンの世界を表現しています。東芝EMIからも日本盤プレスが発売されています。(2) ゲオルグ・ショルティ指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団 ウイーン国立歌劇場合唱団 プラシッド・ドミンゴ(T)、 ジュシー・ノーマン(S)、エヴァ・ランドヴァー(Ms)、ジークムント・ニムスゲルン(Br)(DECCAレーベル 470795 1985-6年録音 海外盤)何と言ってもドミンゴのローエングリンとノーマンのエルザがずば抜けて素晴らしく、またショルティ指揮も透明な響きの白鳥表現や、第3幕の圧倒される厚い金管群の響き、精緻に掘り下げた音楽表現と超優秀録音が素晴らしいディスクです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1832年 初演 ドニゼッティ オペラ「愛の妙薬」1842年 誕生 ジュール・マスネ(作曲家)1845年 誕生 ガブリエル・フォーレ(作曲家)1884年 没 ぺドルジーハ・スメタナ(作曲家)1976年 没 ルドルフ・ケンぺ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 躑躅(つつじ)
2007年05月12日
コメント(6)
-
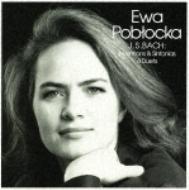
バッハ「イノヴェンションとシンフォニア」/チューリップ
『今日のクラシック音楽』 J.S.バッハ作曲 「インヴェンションとシンフォニア」ヨハン・セバスチャン・バッハ(1685-1750)は65歳の生涯で非常に数多くの鍵盤楽器作品を書き遺しています。 2つの「平均律クラヴィーア曲集」、「ゴールドベルグ変奏曲」、「イタリア協奏曲」、「フランス組曲」、「イタリア組曲」など目白押しに書かれています。この「インヴェンションとシンフォニア」は、ケーテンの宮廷楽長をしていた頃に書かれています。 バッハ32歳の時にワイマールからケーテンに移っています。 そして38歳までレポルド候の庇護の許に、満足できる作曲活動を行っていたようです。レオポルド候自身もヴァイオリンなどの演奏に優れており、何よりも音楽を愛好した人だったことが大バッハには恵まれた時期であったようです。 但し、レポルド候は教会音楽をあまり重用しない「カルヴィン派」に属するひとだたので、バッハのこの時期は「世俗音楽」の作曲に打ち込んだと言われています。さて、今日の話題曲「インヴェンション」と「シンフォニア」ですが、これはバッハの息子ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハへの教育用と書かれているのですが、ただの「練習曲」にとどまらない素晴らしい芸術性を備えた作品です。 自筆の楽譜には「2声のインヴェンションをうまく演奏できるようになれば、3声のシンフォニアに進むように」と指示されているそうです。 ですからまぎれもなく、この作品は息子への教則本というか練習曲だったのでしょう。「インヴェンション」とは「着想」という意味があり、バッハは楽譜にこう記しているそうです。 「よい着想を得るだけでなく、それを巧みに展開できるようになること。 そしてカンタービレの奏法を身につけて、作曲の予備知識を身につけること」と。つまりこの曲はピアノ演奏のための練習曲でもあり、作曲への練習曲でもあったのです。 今ではピアノを練習する人がこの作品を避けて通れない大事な曲となっているようです。 この作品は「聴く」ことよりも「弾く」ことが大事な音楽ではないでしょうか。 私のようにピアノ演奏ができない者にはもどかしさを感じさせる作品です。曲は全部で15曲あって、簡素なコラールやプレリュード、それに舞曲にいたるさまざまな曲が網羅されており、曲には色や影、多彩な彩りが施されたとても練習曲とは思えない深い芸術性を備えています。「シンフォニア」は3声で書かれており、技法も複雑で3本の旋律線が和声的な骨組を構成した、やはり15曲の曲から構成されています。愛聴盤 エヴァ・ポヴォッカ(ピアノ) (ビクター・レーベル VCC60655 2006年7月録音)曲の持つ簡素な美しさを見事に表現した、豊かな歌で奏でられた祈りにも似た情感を醸し出した演奏です。 今年1月にリリースされたディスクです。タチアナ・ニコラーエフ(ピアノ)(JVCレーベル VDC1079)バッハ鍵盤の音楽に生涯を捧げたようなニコラーエフの厳しい姿勢が全曲にうかがわれる名演。 残念ながらこのディスクを傷つけてしまって再生不能となり、しばらくこの曲を聴いていなかったのですが、彼女の弟子ポヴォォッカ ノディスクをHMVで聴いて買った次第です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1849年 没 オットー・ニコライ(作曲家)1855年 誕生 アナトリ・リャードフ(作曲家) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 チューリップ
2007年05月11日
コメント(12)
-
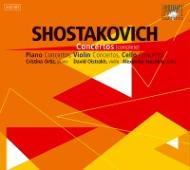
ショスタコーヴィッチ ピアノ協奏曲/小判草(コバンソウ)
『今日のクラシック音楽』 ショスタコーヴィチ作曲 ピアノ協奏曲第2番ディミトリ・ショスタコーヴィチ(1906-1975)は、生きた年齢と難しい国政の中を生き抜いた「したたかさ」で数多くの作品を書いています。 交響曲(15曲)、弦楽四重奏曲(15曲)、オペラ、映画音楽、ピアノ独奏曲、2曲のヴァイオリン協奏曲とチェロ協奏曲、それに2曲のピアノ協奏曲など、非常に多彩に音楽を書き遺しています。ショスタコーヴィチの2曲のピアノ協奏曲は、2曲とも実に簡素・簡明でなかなか洒落た音楽となっています。「ピアノ協奏曲第2番」は、1957年作曲者51歳のときの作品で、「ピアノ協奏曲第1番」(1933年)からおよそ25年経ってから書かれています。 「ピアノ協奏曲第1番」は、独奏ピアノにピアノに弦楽合奏とトランペットだけの小さな編成の曲でしたが、この「2番」は通常のオーケストラとの編成になっています。彼のピアノ協奏曲の中では、この「第2番」の方が私には聴きやすい曲です。 簡素・簡明というのは主に演奏時間からそう感じます。 約20分間の短い曲です。この曲は3楽章構成で伝統的な協奏曲形式を踏襲しており、4楽章ある「第1番」とは異なった趣があります。 音楽のテーマも非常に単純に描かれており、主題の展開や再現などは実に見通しのいい作品です。この頃には芸術面では悪名高きスターリンはすでに亡くなっており、作曲活動に何かと干渉されてきたショスタコーヴィチも、したたかにここまで生きてきて家族との幸せな時間を、まだまだ干渉のあった国政と付き合いながら作曲を楽しんでいたのではないかと思えるような作品です。ショスタコーヴィチの作品だからだと言って、難解でしかっつめらの気難しい音楽ではありません。第1楽章は、第1主題がのんびりした趣きと情緒で現われてきます。 しかし音楽はすぐに忙しい動きに早変わりして、ショスタコーヴィチらしい音楽に変っていきます。 展開部では華やかさがあり、第2主題が全管弦楽で大きく鳴らされてクライマックスを築くいていくという、協奏曲の王道を行くような音楽です。第2楽章が圧巻です。 この旋律の美しさは格別で「これがショスタコーヴィッチ?」と言いたくなるほど響きが美しいのです。 まるでショパンを想い起させるような「アンダンテ」楽章です。この「ピアノ協奏曲第2番」は1957年の今日(5月10日)、初演されています。愛聴盤 クリスティーナ・オルティス(P) パーヴォ・ヤルヴィ指揮 ボーンマス交響楽団(EMI原盤 Briliantレーベル BRL7620 1975年録音)EMIライセンスでの発売でショスタコーヴィチの全協奏曲を3枚に収録した廉価盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1919年 誕生 ペーター・マーク(指揮者)1957年 初演 ショスタコーヴィッチ ピアノ協奏曲第2番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 小判草空き地や公園の植え込み、畑の畔などに咲いている初夏の野草の一つです。 撮影地 大阪府和泉市 2006年5月稲科 コバンソウ属 ヨーロッパ原産。 名前の通りで小判のような実がなります。
2007年05月10日
コメント(4)
-
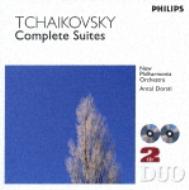
チャイコフスキー 組曲第3番/常盤露草
『今日のクラシック音楽』 チャイコフスキー作曲 組曲第3番 ト長調 チャイコフスキー(1840-1893)は管弦楽用として4つの「組曲」を、1878年~1887年の11年間で書き上げています。 これらの「組曲」は彼の交響曲の作曲と関連付けて書いたと考えられています。第4番は1877年に、第5番は1888年に完成していますから11年の感覚が空いています。 その間に書かれたのがオペラであり、「イタリア奇想曲」、「大序曲1812年」やピアノ三重奏曲「偉大な芸術家の思い出」などがあります。 そしてこれら4つの「組曲」はちょうど第4番から第5番までの間に書かれています。彼の交響曲で演奏回数の多い、コンサートでの採り上げや録音の頻度が多いのは「後期三大交響曲」と呼ばれる第4番~第6番なのですが、第4番では初めて循環主題なるものを書いています。 第1楽章と第4楽章に「運命の動機」なる主題を入れています。 循環動機・主題は曲自体を有機的に結び付けて、統一感のある作品に仕上げるのに用いられる手法ですが、チャイコフスキーはこの第4番で初めてこの手法を使っています。第4番のあとに来る第5番への模索のように思えます。 チャイコフスキーは明らかに何かを模索していたのでしょう。 これらの組曲は「管弦楽組曲」と呼んでもいいほどの、すべて管弦楽で演奏される作品ばかりです。「組曲第1番」は6楽章構成であたかも古典組曲のような作品であり、「第2番」は弟の別荘で彼ら家族と共に過ごして書かれており、「音遊び」、「ユーモラスなスケルツォ」、「子供の夢」などと楽章にサブタイトルを付けており、性格的な内容の組曲です。 第4番「モーツアルティーナ」はまるで古典への回帰を想わせる作品となっています。今日の話題曲「組曲第3番」はもっとも交響曲に近い形の4楽章構成で、作品自体も一番交響曲に近い曲です。第1楽章「エレジー」は、とても美しいチャイコフスキー節満開の感傷的で哀感ただよう悲しげな「エレジー」楽章で、その哀愁ただよう主題を変奏によって連綿と綴られています。第2楽章「憂鬱なワルツ」は、チャイコフスキーが得意で好きな「ワルツ楽章」で、郷愁を誘うような情緒の素晴らしい音楽が展開しています。第3楽章「スケルツォ」は、まるで行進曲風で、タランティラのような舞曲風でもある、明るい音楽です。第4楽章「主題と変奏」は、この曲中最も長い楽章で約20分かかります。 主題と12の変奏からなる長大な楽章です。 ヴァイオリン・ソロのカデンツァがあったり、哀愁を湛えた変奏があったり、甘く美しい変奏があったりして、最後の第12変奏は「ポロネーズ」で豪華・華麗に曲を閉じています。こういう曲を聴いていますと、やはりチャイコフスキーは第5番へのステップとして模索していたのではないかと思われます。「組曲」中、最もロシアのメランコリックな美しさを表現した約40分の大曲です。愛聴盤 アンタル・ドラティ指揮 ニューフィルハーモニア管弦楽団(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP3359 1966年録音)全4曲の組曲を収録した1,800円(2枚組)廉価盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1904年 初演 アルベニス 組曲「イベリア」1914年 誕生 カルロ・マリア・ジュリーニ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 常盤露草道端や公園や空き地などどこにでも見かける小さな白い花です。露草科 ムラサキツユクサ属 南アメリカ原産
2007年05月09日
コメント(6)
-

ツェルニー プルミエ・グラン・トリオ 変ホ長調/春女苑(ハルジョオン)
『今日が誕生日』今日で63歳になりました。 昨年も同じことを書きましたが、今度の「脳梗塞」でやはり健康でないと心も健全にならず、やりたいことも出来ないものだと痛感しています。 今はリハビリに勤しむ毎日ですが、「高血圧」という厄介な病気を抱えてしまいました。 強い薬で血圧を下げることができるのですが、脳梗塞の直後ですから服用する薬も徐々に下げていく効き目しかなくて、もう少し治療に時間がかかるようです。入院中に半身麻痺の患者さん達を見て、自分はつくづく「運」が良かったと思いました。 麻痺が残れば歩くのにも、トイレ・入浴・食事にも誰かの介護が必要になります。 言語障害だけの症状は、「神さまからの贈り物」だと感謝しています。 入院した当座はもうブログもやめやようかと思いましたが、神さまの贈り物で「入力」も今までと変わらないのだから感謝して、続けて行こうと思いました。 自分のCD棚を見ると、まだまだ書いていない音楽・作品がたくさんあります。 神さまへの感謝を込めて毎日書いていこうと思っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ツェルニー作曲 プルミエ・グラン・トリオ 変ホ長調カール・ツェルニー(1791-1857)という作曲家の名前は、ピアノを習っている方には知らぬ人はないでしょう。 ピアノ練習曲で必ずお付き合いをされていると思います。 出版された作品だけでも861曲を数えており、ピアノ独奏作品が圧倒的に多いのですが交響曲やピアノ協奏曲なども書き遺されているそうです。9歳にしてベートーベンに弟子入りして基礎勉強をしていることでも有名で、ベートーベンからは特に目をかけられておりピアノ協奏曲第5番「皇帝」のウイーン初演の独奏者に指名されています(この曲の初演はライプチッヒ)でした。そんなチェルニーの作品に室内楽もあります。 「序奏とチロルの歌による協奏的変奏曲」とか、「3つの華麗なる幻想曲」、「ピアノ三重奏曲」などで、今日の話題曲「プルミエ・グラン・トリオ 変ホ長調 作品105」もその一つです。ツェルニーは「ピアノ三重奏曲」を全部で8曲書いているそうですが、この「プルミエ・グラン・トリオ 変ホ長調」は第1番にあたるそうです。 ピアノ三重奏曲は、ピアノ、ヴァイオリン、チェロによる演奏曲ですが、この第1番だけはチェロ・パートに「またはホルン」という指定があるそうです。今日の紹介盤はそのホルン指定によるものです。 作曲当時のホルンと現代のそれとは弁の機能なども違っていますから、このディスクの奏者(ラデク・バボラーク)は自身で少し手を加えて演奏しているそうです。この曲は3楽章で構成されており、第1楽章「アレグロ」、第2楽章「アダージョ」、第3楽章「ロンド」と伝統的な形式を踏襲しています。第1楽章の音楽が始まると、まるでベートーベンの初期のピアノ・トリオのような錯覚を覚えます。 ベートーベンの死後30年も生きた人ですからロマン的な音楽かと思いきや、古典的な情緒のある音楽にまず驚きます。 ベートーベン的な音楽という表現を使いましたが、室内楽作品では最晩年の弦楽四重奏曲などは例外にして、ベートーベンのどの音楽もとても安定感のある響きで聴き手を安心させてくれます。交響曲でも劇音楽でもピアノ・ソナタやヴァイオリン・ソナタ、チェロ・ソナタ、それに協奏曲でもそうです。 雄大なスケールを持ちながら常に安定した響き・和声を伴う音楽なんですね。ツェルニーのこの曲も同じで、難しいところはなくて聴き手はただ音楽に身をゆだねているだけでいのです。 さすがにベートーベンの室内楽作品のレヴェルまでいきませんが、約35分の間幸せな気分に浸らせてくれる音楽です。 特にピアノがきらめくような輝きで非常に美しい旋律が随所に表れています。愛聴盤 (CRYSTONレーベル OVCC-00041 2006年7月録音)ラデク・バボラーク(ホルン ベルリンフィル首席奏者)ローレンツ・ナストゥリカ(Vn ミュンヘン・フィル コンサートマスター)清水和音(ピアノ)のトリオ編成による演奏でこのディスクは、ブラームスの「ホルン三重奏曲」を聴きたくて買ったのですが、このツェルニーの作品を気に入ってこればかり聴いています。昨年2006年12月リリースのディスクです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1924年 初演 オネゲル 交響的運動第1番「パシフィック231」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 春女苑(ハルジョオン) 撮影地 大阪府堺市大仙公園 2006年4月
2007年05月08日
コメント(22)
-
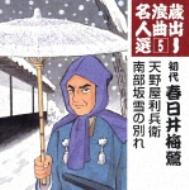
浪曲を聴く/ドウダンツツジ
昨夜は整理をしていなかったCDやDVDを棚にきちんと整理し直していると、浪曲CDが出てきました。 二代目広沢虎造の「清水次郎長外伝~森の石松」と春日井梅鶯の「南部坂雪の別れ」。 このうち「南部坂雪の別れ」を久しぶりに聴いてみました。私が小学生の頃はラジオが主流で、うちでは漫才・落語・浪曲・映画音楽・プロ野球のナイター中継・ニュースなどを家族一緒に聴いており、漫才や落語番組などは家中が笑いに包まれ、浪曲では涙しながら聴いたり、野球では手に汗握る思いで聴いていました。そんなわけで浪曲は特に好きで、隣家にはたくさんのレコードがあって「森の石松~金毘羅道中」などは全部覚えてしまって、小学校卒業の茶話会で唸ったこともありました。浪曲の魅力は物語が庶民が好む胸がすか~とするとか、お涙頂戴物語とか、義理人情物語とかのストーリーがすごくわかりやすく、そこへ浪曲師の声が「寂声」で唸る独特の語りにつきます。昨夜聴いた「南部坂雪の別れ」は忠臣蔵を台本にしており、討ち入りの夜に大石内蔵助が遥泉院に打ち明けに行くのですが、腰元におかしなのがいて胸の内を打ち明けずに、別れを言って帰るのですが、明け方に寺坂吉衛門が大願成就の知らせを持ってきます。その寺坂の討ち入りの委細を語る約10分間の長丁場は息もつけないほどの名調子での語りで、この部分にくると鳥肌立てて聴いています。子供のころには映画館で浪曲大会などが行われていましたが、今ではすっかりと影を潜めてしまいました。 寂しいですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ドウダンツツジ つつじ科 ドウダンツツジ属 開花時期 4月初め~5月初め 壷形の花が咲きます。
2007年05月07日
コメント(9)
-
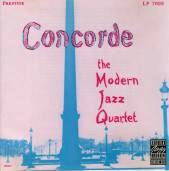
MJQ/藤の花
今日は趣を変えてモダン・ジャズからMJQを採り上げました。 このクワルテットは1952年に結成されて、その数年前からの「クール・ジャズ」と呼ばれる流れを継承するかのような爽やかな「クールネス」と、当時流行った白人ジャズの「ウエストコースト・ジャズ」のグループ・サウンドの過熱するスタイルの両面を持ち合わせて登場してきました。後年になってバッハの曲を積極的に採り上げて、MJQ独特の「クールネス」な響きで一世を風靡しました。 ヨーロッパのクラシック音楽をジャズの響きに融合させた成功例がMJQです。 フランスのジャック・ルーシェトリオとは、全く趣の違うクラシック音楽とジャズの融合であり、アメリカのジャズ音楽が底辺に脈々と流れているMJQとフランス・ジャズの洒落た音楽・響きとの違いだと思います。私がMJQに魅かれる一番の理由は、メンバーであるミルト・ジャクソンのヴァイブ(ヴィブラフォン)です。 彼のヴァイブはどの曲を聴いても、この楽団の核となっており「クールネス」と「白人ジャズ」の過熱さを楽しませてくれます。 またリーダーのジョン・ルイス(ピアノ)はバッハの音楽をジャズにアレンジして、クールなジャズ・ピアノを楽しませてくれます。お薦めは「プレステイッジ」に1955年に録音された「コンコルド」というCDです。 「ガーシュイン・メドレー」としてジョージ・ガーシュインの曲が4曲録音されているのが貴重です。このときのメンバーは、ジョン・ルイス(ピアノ)ミルト・ジャクソン(ヴァイブ)パーシー・ヒース(ベース)コニー・ケイ(ドラム)となっています。初期のアルバムですがMJQを語るには欠かせない録音です。(プレステイッジ盤 VICJ-2043)そしてMJQのお別れコンサートを収録した2枚組CDがあります。 「The Last Concert」というタイトルで、メンバーは上記のメンバーです。 これが最高のディスクとして今でも時々取り出しては聴いています。(ATLANTICレーベル AMCY1030/1 1977年ライブ録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 藤の花5月3日に春日大社で早朝撮影会があり、早くから申し込んでいたのですが、病気のために行くことができなかったのが残念です。 この写真は2005年にたぶん掲載していると思いますが、静岡県藤枝市にあります蓮華寺池公園の藤です。 大きな池を取り囲むように藤棚が30ヶ所ほどある藤の名所です。 愛機Pentaxの一眼レフではなくて、やはりPentaxのコンパクト型デジタルカメラでの撮影です。撮影地 静岡県藤枝市 2005年4月下旬
2007年05月06日
コメント(8)
-
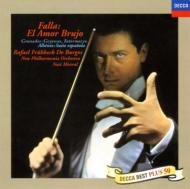
アルベニス 「スペイン組曲」/夕陽
『今日のクラシック音楽』 アルベニス作曲 「スペイン組曲」(管弦楽版)昨日、一昨日と重い曲を採り上げて自分もそれら紹介のディスクを聴いたりしてしていたので、今日は少し気分を変えて心がウキウキするような曲がないかと、昨夜10時ごろにCD棚を覗いていると、ありました恰好の音楽が、「スペイン組曲」。イサーク・アルベニス(1860-1909)はスペインの国宝とも言われている作曲家で、ピアノにかけては相当な腕前だったそうです。 嘘か本当か定かではありませんが、4歳にしてピアニストとしてその名を馳せたと伝えられているほどに、ピアニストとしては抜群の技量を発揮した人だそうです。アルベニスには有名な冒険物語が残っています。 私が初めて彼のピアノ曲を買ったLPにはそういう解説が掲載されており、アメリカ、南米まで10代のころに渡り歩いた、まるで冒険小説の主人公のように紹介されていましたが、現代ではそれがフィクションであったと結論づけられているそうです。ピアノ協奏曲やピアノ曲が多くて、12年間に250曲を超える作品を作曲したも言われています。 それらの中でも有名なのが組曲「イベリア」、「スペインの歌」、そして「スペイン組曲」などです。のちにこれらの曲はギター演奏用などにも編曲されており、原曲はスペイン情緒を色濃く残した、とてもロマンティックな作品を書き残しています。今日の話題曲「スペイン組曲」は原曲のピアノ音楽ではなくて、スペイン生まれのドイツ系スペイン人指揮者ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴスが自ら管弦楽用に編曲したものの紹介です。「スペイン組曲」は1885-86年ごろにかけて作曲されており、ブルゴスは最後の8曲目「キューバ」を省き、ピアノ曲集「スペインの歌」から「ゴルドバ」を追加して最後に置いています。 ですから通常のピアノ曲集とは異なる音楽になっています。どの曲も原曲と比べて実に色彩豊かに編曲されており、とても異国情緒満点の、部屋に居ながらにして「情熱と熱気の国 スペイン」へと運んでくれます。8曲から成る構成で(1)カスティーリャ(セギディーリャス) 情熱的なセギディーリャ舞曲の情感たっぷりの音楽です。(2)アストゥーリアス(伝説曲) スペイン北西部のアストゥーリアス地方を歌いあげており、神秘的なリズム主題がとても映えている音楽です。(3)アラゴン(幻想曲) アラゴン地方の「ホタ」で郷土舞踊音楽がカスタネットの伴奏で踊られるます。 これを幻想曲風にアルベニスは仕上げており、ブルゴスの巧みな編曲で彩り豊かな音楽となっています。(4)カディス(カシオンー歌) ブルゴスはこれを弦楽合奏用に編曲しており、スペイン風ワルツの情感が素晴らしい音楽です。(5)セビーリャ アルベニスはセビーリャの復活祭聖週間のフィエスタ(祭り)を情熱的に描いて、群衆の熱気する様を表現していますが、ブルゴスの編曲が最も生かされて情熱的で、しかも哀愁漂う情感の伝わる音楽です。(6)グラナダ アンダルシア地方の「グラナダ」を描いており、ギター奏法を模したセレナーデがとても美しく、哀愁ただよう美しい旋律がとても印象的です。(7)カタルーニャ(コランダ) アルベニスはハーデイ・ガーデイと呼ばれる特殊な弦楽器を模して作曲したそうです。原曲を上手く活かしてイタリア風タラント舞曲をうまく処理しています。(8)コルドバ がらりと音楽が変わります。 ここではアラビア風幻想曲の趣きがあり、古都コルドバの夕暮れのような詩情をただよわせ、回教寺院から鳴り響く「鐘」、哀感をそそる美しい旋律、ここにはアルベニスの夢見る「アラビアの黄昏」が見事に描かれています。愛聴盤 ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴス指揮 ニューフィルハーモニア管弦楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7126 1968年録音)もう40年前の古い録音ですが、さすがDECCA録音だけあって何の遜色もなく現代の録音と変わらぬ優秀録音盤で、1000円の廉価盤としてリリースされています。 音色がとても豊かで、豊穣・豊麗な美しい演奏、それにリズムが素晴らしい。まるで躍動するようなリズム感があって、アルベニスの情熱が乗り移ったかのようで、輝くような演奏を繰り広げています。スペイン音楽を振らせると右に出る者がいないと言われたブルゴスの不滅の名演奏です。カップリングはファリャの「恋は魔術師」。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1900年 誕生 ハンス・シュミット=イッセルシュテット(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の風景』 りんくうタウンの夕日2004年4月に初めて持ったコンパクト型デジタルカメラでの撮影です。 もう保存はしていないだろうと思っていたのですが、まだCD-RWに残っていました。撮影地 大阪府泉南市りんくうタウン 2004年6月
2007年05月05日
コメント(107)
-
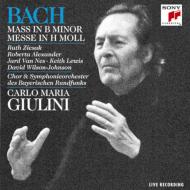
J.S.バッハ ミサ曲ロ短調/スノードロップ
『今日のクラシック音楽』 J.S.バッハ作曲 ミサ曲ロ短調 BWV232西洋文化と日本を含めて東洋文化の一番大きな違いは宗教ではないでしょうか。 なるほど宗教の建造物だけを比べてみますとそれほどの大きな違いはありません。 日本中どこに行ってもお寺があります。 西洋もどんな小さな町を訪れても教会があります。 アメリカ新大陸へ渡った移民・開拓者たちも町を作れば、必ず建てるのが教会でした。西洋クラシック音楽もキリスト教文化と切り離すことが出来ません。 それらの頂点に立っていると言っても過言でないのがヨハン・セバスチャン・バッハ(1685-1750)でしょう。 彼の音楽はキリスト教と切り離して考えることは出来ません。 特に教会音楽がそうです。 彼の作品には「ミサ曲ロ短調」、「ヨハネ受難曲」、「マタイ受難曲」などキリストを題材にした作品が多くあり、その他の音楽も彼が宮廷音楽長をしていた頃でも、教会のオルガンを弾いていた頃でもキリストとは切り離すことの出来ない作品が数多く残されています。これらの作品を演奏する人たちも敬虔なキリスト教徒です。 神への敬い、恐れ、救済を生涯祈り続ける演奏家たちによる大バッハの作品。 そこに東洋の演奏家 - キリスト教信者でない - とは一線を画すものがあるのではないかと思います。 邦人演奏家にいかにこれらの教会音楽の演奏が少ないかを見てもわかります。 私の知る限りでは鈴木秀美と小沢征爾くらいでしょうか。例えば今日の話題曲 - ミサ曲ロ短調にしても指揮者・オーケストラ・独奏者・合唱団の人たちは、大バッハの作品に触れて演奏する時に、大バッハの向こうにいる彼らの「主キリスト」と向い合いながら、神への祈りを込めて演奏していると思います。そこに西洋音楽文化と東洋のそれとの違いを感じます。 もちろん芸術作品ですからキリスト教にこだわることは必要ありません。 しかし、今日の話題作品などを聴くときには、いつもそういう違いを感じないわけにはいきません。本題に戻りますが大バッハは1865年3月21日に生れ、1750年7月28日にライプチッヒで65歳で亡くなっています。彼はキリスト教の中でも「改革派(プロテスタント)」に属する人でした。 このミサ曲は通常のミサとは形態が違っています。伝統的なカトリックのミサ曲は「キリエ(主よ憐れみたまえ)」、「グローリア(神に栄光あれ)」、「クレド(我は信仰す)」、「サンクゥス(聖なるかな)」、「アニュス・ディ(神の子羊)」というミサ通常文に従った五部構成が通常の形態です。しかしこの大バッハの「ミサ曲ロ短調」は、「キリエ」と「グローリア」をまとめて第1部、「クレド」に相当する「二ケア信教」が第2部、「サンクトゥス」が第3部「オサンナ」(サンクトゥスの後半)、「ベネディクトゥス(祝せられる)、「アニュス・ディ」(我らに平和を与え給え)が4部という構成になっています。この曲は「主よ憐れみ給え」から十字架にはり付けられて復活した、キリストを讃えて「死者の蘇り」と「来世の平和と永遠の命を待ち望む」キリスト教徒の切なる願いを歌った、合唱と独唱、大編成の管弦楽が織成す大バッハ畢生の2時間を超す大曲です。クラシック音楽を好きな方は一度は聴いておくべき音楽だと思います。愛聴盤(1) カルロ・マリア=ジュリーニ指揮 バイエルン放送交響楽団・合唱団 ルート・ツィザーク(S) ロバータ・アレクザンダー(S) ヤルト・ヴァン・ネス(A) キース・ルイス(T) ディビット・ウイルソン=ジョンソン(Br)(SONYクラシカル SICC263/4 1994年6月ミュンヘンライブ)(2) オイゲン・ヨッフム指揮 バイエルン放送交響楽団・合唱団 ロイス・マーシャル(S) ヘルタ・テッパー(S) ピーター・ピアーズ(T) キム・ボルイ(Bs) ハンス・ブラウン(Bs)(Philipsレーベル PHCP20019/20 1957年録音 廃盤)(3) グスタフ・レオンハルト指揮 ラ・プティット・バンド オランダ・コレギウム・ムジクム・バッハ合唱団 イザベル・プーナール(S) ギュメット・ロランス(Ms) ルネ・ヤーコブス(カウンター・テナー、アルト) ジョン・エルビス(T) マックス・ファン・エグモント(Bs) ハリー・ファン・デル・カンプ(Bs) (ハルモニア・ムンディ原盤 BMGジャパン BVCD38119 1985年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1759年 初演 ハイドン 交響曲第104番「ロンドン」1931年 誕生 ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指揮者)1955年 没 ジョルジュ・エネスコ(作曲家・ヴァイオリニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 スノードロップ撮影地 大阪府和泉市 2006年4月25日彼岸花科 ガランサス属 ヨーロッパ原産で球根草
2007年05月04日
コメント(12)
-
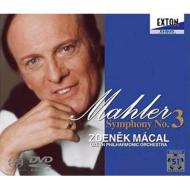
マーラー 交響曲第3番/小手毬
『今日のクラシック音楽』 マーラー作曲 交響曲第3番ニ短調グスタフ・マーラー(1860-1911)の音楽について書こうとすると、とても億劫になります。 彼の音楽 - 特に交響曲は彼自身が述べていることが多くて、それに惑わされてしまいがちになります。 その言葉も非常に哲学的な言葉が多くて、その意味を汲み取ろうとすると音楽の本質を見失うことがあります。 今までもマーラーの交響曲について書きたいという意欲がありましたが、どこから手をつけていいのかわからないという面がありましたのであまり書いていなかったのですが、昨日久しぶりにマーツァルが2005年にチェコフィルを振った昨年リリースされた新盤を聴いて、俄然書こうと意欲を燃やしたわけです。マーラーは1860年7月7日にボヘミアで生まれたユダヤ系で、宗教はユダヤ教ですが1897年にローマ・カトリックに改宗しています(このことは今日の話題曲 - 交響曲第3番ととても密接な関係にあります)。マーラーの時代 - 19世紀後半から20世紀前半にかけての時代はどういう作曲家がいたのか、ということから書いてみましょう。1860年 マーラー誕生 ブルックナー36歳1862年 ドビッシー誕生1864年 R.シュトラウス誕生1896年 マーラー36歳で交響曲第3番を書き上げた。 ブルックナー72歳で他界。1897年 ブラームス 63歳で他界1911年 マーラー 51歳で他界。 この時、バルトーク30歳、アルバン・ベルグ26歳、 ドビッシー49歳、ラヴェル36歳、シェーンベルグ37歳 ストラビンスキー29歳 プロコフィエフ20歳これがマーラーの生きた時代の背景です。マーラーを語る時にいつも出てくる場所にオーストリアのシュタインバッハという地名があります。 ここは1893-1896年までの夏の間に過ごした場所です。 この第3番は1896年に脱稿していますから、この曲もシュタインバッハで書かれています。 彼が滞在した家の写真を見ますと、アッター湖畔にあり風光明媚なところです。 きっと夏の陽光を浴びる湖や小高い緑の丘などは、作曲に専念するのに格好の場所であったろうと、この写真を見ると容易に想像できます。マーラーの音楽はよくボヘミア的な影を色濃く残している、とか後期ドイツ・ロマン派音楽とか言われています。 しかしマーラーの音楽は、ドヴォルザークやスメタナなどのボヘミア的土着性の強い、ボヘミアの郷愁を感じるほどではなく、都会的で洗練された音楽が響いてきます。この第3番はそういうボヘミア的なところがなくて、マーラー自身が「自然」と対話をしながら、やがて神への愛へと上りつめていくような、そういう言葉を残しています。マーラーはこの曲で自然について語ろうとしています。 それがシュタインバッハでの自然の風景と重なってきます。 自然との触れ合いが反映していることは容易に想像できます。しかし、ベートーベンの「田園」のように、自然の中で心に浮かぶ感情を表出しようと書いた音楽でもありません。またこの時期マーラーの弟がピストル自殺をじた時期でもあり(1895年2月)、この曲の全曲初演(1902年6月12日)までに前述のようにキリスト教への改宗もあり、この曲は決して自然賛歌という形にならず、ニーチェの「ツァラトゥストラはかく語りき」からの言葉を引用したアルト独唱を入れた第4楽章や子供に合唱を入れて「天国」への憧れの気分を入れた第5楽章、そしてフィナーレでは「神への救済を求める」ような音楽になっています。現在は楽譜から消されていますが、この曲へのマーラーへの想いが語られている各楽章のタイトルがあります。 それを最後に書いておきますが、私はこういうマーラーの複雑な思いにとらわれることなく、素直に音楽を楽しめばいいと思っています。 マーラーの交響曲は演奏時間が長いの特徴ですが、この第3番は最も長い曲でほぼ95分ー100分かかります。 第1楽章だけでベートーベンの第5番「運命」がすっぽりと入る長さです。第1楽章「牧神が目覚める。 夏がすすみくる」行進曲のリズムがこの楽章全体を支えており、まるで夏が行進してくるように音楽は進み、緑の新芽の吹き出すのを楽しむかのように自然の造形を敬い、楽しんでいるかのような音楽で、全曲中最も楽しい楽章です。第2楽章「牧場で花が私に語ること」とても優美なメヌエットで野の花たちへの感謝のような音楽が展開しています。第3楽章「森の動物たちが私に語ること」歌曲集「少年の魔法の角笛」の旋律がベースとなっており、とても美しく、ホルンの民謡調の音楽と好対照をなしている最もボへミヤ調の濃い音楽です。第4楽章「夜が私に語ること」アルト独唱がニーチェの「ツァラトゥストラはこう語りき」の一節を歌う楽章で、月の明るい夜に澄んだ夜気の瞑想的な情緒が、マーラーの宇宙観をよく表現した全曲中白眉の楽章の一つ。第5楽章「天使が私に語ること」「神の愛」を語るかのような児童合唱による天国的な美しさの音楽が聴こえてきます。 女性合唱、アルト独唱も加わり対位法的に音楽が展開していきます。第6楽章「愛が私に語ること」穏やかに歌われる主題が実に美しい旋律でやがて大伽藍建築のような壮絶なクライマックスへと導かれて全曲が閉じられます。一度は聴いておきたいマーラー畢生の大作で、全曲はとても聴きやすい後期ロマン派の音楽で、アルト独唱、児童合唱、女性合唱を交えた大管弦楽による「自然賛歌」を歌いあげた音楽です。愛聴盤 (1)ズデニック・マーツァル指揮 チェコフィルハーモニー管弦楽団(EXTONレーベル OVCL00219 2005年5月録音)何よりも録音の優秀なのが目を見張るばかりで、居ながらにしてコンサートホールで聴くような超優秀録音。 マーツアルの演奏は色彩豊かでどの楽章も光り輝くようで、従来のマーラー演奏とは一線を画す彩りを伝える名演。(2)エリアフ・インバル指揮 フランクフルト放送交響楽団 (DENON CREST1000 COCO70473 1985年4月録音)インバルの演奏はテンポが妥当で、それでゆったりとしたキメ細かな演奏を繰り広げており、そんなに数多くは聴いていない曲ですが、普遍的な演奏で録音も優秀。 紹介盤としては持っていませんが、Briliantレーベルで廉価で全集が出たライセンス盤で聴いています。(3)ガリー・ベルティーニ指揮 ケルン放送交響楽団(ハルモニア・ムンディ EMIレーベル 7475688 1985年4月録音 輸入盤)少し遅めのテンポでマーラーの音楽世界を深い響きで表現した、指揮者ベルテーニがマーラーに寄せる共感がひしひしと伝わってくる畢生の名演盤。 ベスト盤という言葉を極力使いわないようにしていますが、この曲に関する限り私が最も好きな名演奏。 録音は少しくすんだ感のある音づくりですが、それがこの曲のイメージにピッタリで、フィナーレ楽章の盛り上がりは筆舌に尽くしがたい演奏。 ただこのディスクを単売で見つけることは難しく、現在はベルティーニ追悼としてマーラー交響曲全集となっています。 単売での再発売が望まれる世紀の名盤だと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1856年 没 アドルフ・アダン(作曲家)1917年 初演 ブロッホ ヘブライ狂詩曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 小手毬
2007年05月03日
コメント(8)
-

メトネル ピアノ協奏曲第2番/花水木
『今日のクラシック音楽』 メトネル作曲 ピアノ協奏曲第2番ハ短調ニコライ・メトネル(1880-1951)は、モスクワで生まれたドイツ系ロシア人で、12歳でモスクワ音楽院に入学した神童。ピアノを専攻して首席で卒業という天才型のピアニストだったそうです。 ピアニストとして将来を大いに嘱望されて、ラフマニノフとは生涯を通じての親友だったそうです。 やがてメトネルは作曲を独学で勉強してピアノ協奏曲やピアノ独奏曲などを書き残しています。ところがラフマニノフと同じで、ロシア革命の混乱を避けて1921年にロシアを離れています。そして1927年に一度祖国に戻り、ピアノ協奏曲第2番を初演していますが、その後またロシアを離れて、以降二度と祖国に戻ることがなかったそうです。メトネルの妻アンナは彼の長兄の妻で、さまざまな障害を乗り越えて1919年に結婚しているそうです。 初めての出会いから23年の月日を経ての結婚だったそうです。盤年には心臓病を病んで、1951年11月13日に71歳の生涯をイギリスで閉じています。 そしてロンドン郊外のヘンドン墓地に眠っているそうです。メトネルの音楽の特徴は「ピアノ」につきます。 生涯にわたって書き続けた独奏ピアノ曲は彼が創作した「おとぎ話」に代表されています。 ほとんどの独奏曲は標題音楽であるというのが特徴です。 他にも3曲のピアノ協奏曲などや室内楽作品を書き残しています。メトネルの音楽は、「ロマン派」に属するピアノ音楽で、わかりやすく例えますとラフマニノフとショパンを足して2で割ったような音楽です。 ピアノ独奏曲にはほとんどタイトルがつけられた表題音楽ですから、聴き手を自由に瞑想、空想の世界に誘ってくれる音楽です。今日の話題曲、「ピアノ協奏曲第2番ハ短調 作品50」もロマン派音楽として位置づけができる曲で、ロシアの哀愁が見事に表現された美しい協奏曲です。 第2楽章のロマンの香りがしたたり落ちそうな美しい旋律は、この協奏曲の白眉でしょう。こういうマイナーな曲を廉価で提供しているNaxosのディスクがあります。 演奏は、コンスタンティン・シチェルバコフ(ピアノ)、イゴール・ゴロフスチン指揮 モスクワ交響楽団です。 (Naxosレーベル 8.553390 1996年6月録音)またメトネルのピアノ独奏曲ならDENON CREST1000で1000円の廉価盤でイリーナ・メジューエワが演奏したディスクがお薦めです。 女性ながら打鍵の強いピアニストで透明度の高いピアノの音色が魅力的な、メトネルの音楽を熱心に紹介している女性ピアニストです。 「おとぎ話」や「忘れられた調べ」などメトネルの代表作を網羅したディスクです。 (DENON CREST1000 COCO70756 1998年10月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1660年 誕生 アレッサンドロ・スカルラッティ(作曲家)1864年 没 ジャコモ・マイアベーア(作曲家)1885年 初演 ブルックナー 「テ・デウム」1936年 初演 プロコフィエフ 交響的物語「ピーターと狼」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 花水木これも昨年の画像で開花前の花びらをとらえたものです。 撮影地 大阪市立長居植物園 2006年4月
2007年05月02日
コメント(8)
-
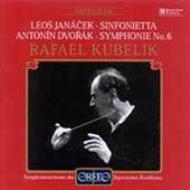
交響曲第6番/マニラの熱い夜/コデマリ
『今日のクラシック音楽』 ドヴォルザーク作曲 交響曲第6番ニ長調アントニーン・ドヴォルザーク(1841-1904)という作曲家の頭はどういう構造をしているのだろう、と思うことがあります。 チェコのスメタナ(1824-1884)亡き後、チェコ国民楽派の第一人者として揺ぎない地位を確立して、交響曲、室内楽、管弦楽曲などに優れた作品を数多く残していますが、彼の音楽に共通しているのは「スラブ的・ボヘミア的哀愁」に彩られた美しい旋律であると言えるでしょう。ドヴォルザークの音楽はとどめもないくらいに、美しい旋律が次々と現れては消え、消えては新たな魅力的な旋律が現れて消える、「方丈記」ではないですが、まるで河のように美しい音楽が滔々と流れています。9曲の交響曲、「スラブ舞曲」や交響詩、チェロ協奏曲やピアノ協奏曲、弦楽四重奏曲「アメリカ」、ピアノ三重奏曲「ドゥムキー」、五重奏曲などの室内楽作品、どれをとっても美しい旋律に満ち溢れており、しかもそれぞれがとても親しみやすい音楽であることが特徴で、スラブ的・ボヘミア的哀愁を伴った哀感に溢れています。そんな中でも交響曲第6番ニ長調 作品60は、そのドヴォルザークの音楽の特徴を最も表したもので、全曲がボヘミア的な郷愁美にあふれています。耳に馴染み易い旋律が次々と出てきて、メロディー・メーカー・ドヴォルザークの面目躍如みたいな楽しい曲です。 ボヘミアの民族感情がほとばしり出るようだし、終始明るく陽気で、大衆に受け入れられ易い曲のような旋律の美しい音楽で、この第6番の交響曲ももっと聴かれても良い曲ではないか、と思います。ところでこの曲、ドヴォルザーク生前の交響曲番号でいうと第1番になっています。 1882年にジムロック社より出版された最初の交響曲ということになっているそうです。 しかし彼が書いた最初の交響曲でもないようです。 まだ充分に調べておりませんので、いづれ調べてみるつもりです。今日はドヴォルザークの命日です。 最も彼らしいこの交響曲第6番を聴いてみようと思います。愛聴盤 ラファエル・クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団(ORFEOレーベル ORFEO552011 1981年10月12日録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『マニラの熱い夜』最近アメリカで盛んに銃による襲撃事件が起きているし、日本でも立てこもり事件があったためか、30年前に起こったマニラでの事件が思い出されます。当時フィリピン・マニラ近郊に合弁会社を設立して工場の稼働が動き出した頃でした。 日本から駐在として派遣されて間もない頃の事件です。当夜は日本の銀行の駐在員と夕食を共にして、二次会に悪名高いマビニ通りへ二人で飲みに行きました。 痛飲して店を出たのが12時を過ぎており、彼とは店の前で別れました。いつもなら馴染みのタクシーが店の前で待っているんですが、その夜は1台もなくて流しのタクシーを拾って、そこから30分ほどのマカティ市にある自宅に帰るところでした。 車が走り出してすぐにうとうとと眠ってしまい、目が覚めると外の景色が違うことに気が付きました。運転手に「道が違うぞ! Bell Airに行くんだぞ!」と注意すると、近道を走っているんです、という答え。 時計を見ると12時20分。 「そうか」と思いまたうとうとする始末。目が覚めるとマカティの近代的な建物が無くて、スラムのようなところを走っており、細い道に車が入り込んだ。 両側には胡散臭い男連中が長椅子に座って、タクシーが通るのを見送っている。そこで初めて「やられるな!」と感じて、脇に置いてある書類カバンに潜めてあるコルト45のグリップを握っていました。 汗がどお~と体内から噴き出してくる。そこからものの2分も進むと3人の男が棍棒のような物を持って突っ立っている。 運転手が「旦那着きましたぜ」と私の方を振り返ったので、その額にコルト45をピタッと付けて、「ペニンスラ・ホテルへ戻れ!」と出来るだけ渋い声を出して、住友銀行の金文字の手帳を見せて、「俺は国際警察の者だ! お前を吹き飛ばすくらい何でもないぞ! 戻れ!」と怒鳴った。運転手はびっくりして住友銀行の金文字手帳をほんとに国際警察と思ったのか、車をバックさせて大通りへと出た。 3人の男は茫然と見送るしかありません。ペニンスラ・ホテルへ戻る間、私はコルト45を運転手の項にぴたりと付けて運転をさせていました。 彼は「自分には子供が3人いて警察に捕まると彼らが生きていけないから勘弁してください」と半泣きになっていました。私は面倒な警察沙汰にしたくないので、とにかくペニンスラ・ホテルへと急がせて、やっと着いて車から降りると、散々彼を脅してから車を降りて、彼を逃がしてやりました。 タクシーが見えなくなると、足がブルブルと震え出してその場にへたり込んでしまいました。銃は半ば必需品でした。 それほどマニラの街は白昼でも怖いところでした。そんな思い出を振り返っていました。6月の蒸し暑い夜の出来事でした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1786年 初演 モーツアルト オペラ「フィガロの結婚」1886年 初演 フランク 交響的変奏曲1898年 初演 デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」1904年 没 アントニーン・ドヴォルザーク(作曲家)1978年 没 アラム・ハチャトリアン(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 コデマリ今はどこの庭、公園でも満開の花を咲かせています。 撮影地 堺市大仙公園 2006年4月21日ばら科 シモツケ属 開花時期 4月中旬~5月中旬 中国から渡ってきたそうです。 小さな花が丸く集まり、手毬のように咲くことから「小さな手毬」で「小手毬」になったそうです。
2007年05月01日
コメント(12)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 人気歌手ランキング
- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…
- (2025-11-15 04:58:28)
-
-
-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…
- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…
- (2024-08-17 21:14:58)
-
-
-

- 洋楽
- ジョ・ジョ・ガン 『ジャンピング・…
- (2025-11-25 04:17:42)
-







