2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年11月の記事
全26件 (26件中 1-26件目)
1
-

ブラームス クラリネット五重奏曲
「室内楽の楽しみ」 ブラームス クラリネット五重奏曲モーツアルトの「クラリネット五重奏曲」について書けば、この曲についても書かねば片手落ちになります。 音楽史上に燦然と輝くように聳え立つクラリネットの室内楽の名曲、ブラームスの「クラリネット五重奏曲 ロ短調」です。この曲については昨年にも書いていますので、以下の文章はその時の日記をそのまま転載しています。 読み返しましてもここに加筆・追加することは何もありません。(追記あり)有名作曲家とクラリネット奏者との邂逅の機会が,そのクラリネットの名曲を生んでいるという出来事があります。 モーツアルトには、あの「クラリネット協奏曲」や「クラリネット五重奏曲」がシュタットラーという奏者との出逢い、ウエーバーはやはり2曲の「クラリネット協奏曲」や「クラリネット五重奏曲」を書いています。この曲もヨハネス・ブラームス(1833-1897)がマイニンゲンの宮廷オーケストラの首席クラリネット奏者リヒャルト・ミュールフェルトに出逢い、その音色に魅せられて書いたという有名なエピソードのある曲です。ブラームスにはベートーベンという偉大な先人が残した曲のために、作曲には非常に慎重になったようです。 ベートーベンの9曲の交響曲が彼の前に聳え立つように遺されていたために、ブラームスは第1番のシンフォニーを完成させるのに20年の歳月を費やしています。 ベートーベンと並び賞される、あるいは超える曲を書くのに苦労したのでしょう。室内楽曲でもやはりベートーベンの偉大な作品群の前に筆が鈍ったのでしょうか「弦楽四重奏曲第1番」を書いたのは40歳になってから、「弦楽五重奏曲」にいたっては57歳になってようやく作曲しています。音楽評論家の故門馬直美氏の畢生の大作「ブラームス」(春秋社刊)を読みますと、この「弦楽五重奏曲」を完成した57歳の頃(1890年)にはもう作曲意欲を喪失している 頃だったそうで、非常に寡作になって いた頃でした。そんな彼に創作意欲を奮い立たせたのが前述のクラリネット奏者ミュールフェルトでした。彼の美しい音色に魅かれてブラームスはクラリネットのための曲を書き始めました。 そして現代ではモーツアルトのそれと2大名曲として輝くほどの名作を書き残してくれました。ブラームスはクラリネットと曲としてこの五重奏曲以外にも2曲のクラリネット・ソナタを書いていますが、その方は別の機会に書いてみようと思っています。この曲が書かれたのは、すでにブラームスに「人生の秋」が訪れていた頃ですから、非常に美しい旋律の中に、「諦観」めいた哀愁漂う曲となっていて、第2楽章などはジプシー風の音の響きが東洋的な渋みのある 雰囲気を漂わせています。 クラリネットと弦楽の絡むブラームス独特の寂しさを漂わせており、全曲にわたって人生の落日を思わせるかのような美しい曲です。 彼の交響曲第4番と同じように「人生のたそがれ」「人生の秋」を感じさせるクラリネットの名曲中の名曲です。 (追記)50歳を超えたブラームスには創作意欲が衰えたのか書き上げる作品は少なくなります。 そんな時に出会ったのがマイニンゲンのオーケストラ・クラリネット奏者ミュールフェルトでした。 ドイツ菅と言われるクラリネットの甘く美しい音色に魅力を感じて、創作意欲を湧き立たせたといわれています。その最初の曲がクラリネット三重奏曲でした。 その後2つのクラリネット・ソナタを経て不朽の名作クラリネット五重奏曲となって書かれています。モーツアルトのそれを「天国的な美しさ」とすれば、ブラームスの五重奏曲は「哲学的な想いに沈んだ美しさ」と例えられると思います。 音楽は静寂に包まれ、東洋的な「わび」と「さび」の影さえ感じられる第2楽章の美しさは言葉に例えようのないものです。陰影の深さ、柔和な風情、厳しい孤独を感じさせる音色、その中に表れる夢想の情緒、最弱音で消えていく終楽章の終結は交響曲第4番よりもさらに「人生の秋」を濃厚に落としています。 ブラーマス畢生の名作と呼んでも大げさではないでしょう。愛聴盤 アルフレート・プリンツ(クラリネット) ウイーン室内合奏団員 (DENON CREST1000 COCO70673 1980年4月ウイーン録音)プリンツのクラリネットに魅せられる演奏です。 最高音から低い音までピッチはびくとも揺れることのない一貫した音色を保ち、ゲルハルト・ヘッツェル(Vn)などのウイーンフィルの弦楽奏者による、柔らかいウイーンの響きともいえるアンサンブルが聴く者をひきつけます。 カップリングは、同じくブラームスのクラリネット三重奏曲です。 私が聴いています盤はモーツアルトのクラリネット五重奏曲とのカップリングです。
2007年11月30日
コメント(6)
-
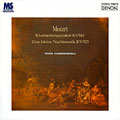
モーツアルト クラリネット五重奏曲
「室内楽の楽しみ」 モーツアルト クラリネット五重奏曲今日から室内楽シリーズとして古今東西の室内楽の名曲を私の独断と偏見で選んだ音楽について書いてみたいと思います。私が室内楽に魅かれたのは故大木正興氏(音楽評論家)が、雑誌「レコード芸術」紙に載せた文章を読んでからでした。 1959年だっと思います。 中学生の頃でした。 「クラシック音楽の醍醐味を味わうには室内楽ジャンルを聴くのが一番だと思う」という氏の言葉に強く魅かれました。 それ以降NHKクラシック番組(クラシック音楽)の「室内楽の楽しみ」を心待ちにして聴くようになりました。室内楽の編成は最低で二人。 例えばヴァイオリン・ソナタであればヴィオリンとピアノという具合です。 それまで聴いていた交響曲や管弦楽曲、協奏曲などと全く違う趣きの音楽で、しっとりとした静けさと楽器の深い音の響きにすっかり魅了されてしまいました。室内楽を聴くには四季も影響します。 なるべく避けたいのは夏です。 うだるような暑さの中では、汗を額から垂れ流しながら聴くには辛い音楽のように思えます。一番いい時期はやはり秋、それも晩秋が最適かと思います。その「室内楽の楽しみ」の初日として選んだ曲がW.A.モーツアルト(1756-1971)が死の2年前に書いた「クラリネット五重奏曲イ長調」です。クラリネットは現代ではごく普通に普及されている楽器ですが、モーツアルトの時代は新しい木管楽器としてオーケストラに現れた楽器で、特に彼がウイーンに出た頃(1781年)に知り合ったクラリネット奏者アントン・シュタートラーの強い影響があって、クラリネット協奏曲なども書いています。この曲を書いた1789年はモーツアルトは極貧の状態で、さすがのピアノの名手でも予約演奏会では聴衆は集まらず、悪妻と言われているコンスタンチェは妊娠中で治療に出かけて彼の許におらず、経済的な負担がモーツアルトにのしかっていました。 死んだ年の冬などはストーブ用の薪を買うこともなく、寒さをしのぐために妻と家の中でダンスをしていたくらいの極貧状況でした。しかし、この曲を聴くと途端に幸せな気分になれるほど、天国的に明るく爽やかで、甘く美しく、平和な気分に包まれた音楽が全編を支配しており、あの伝えられるドン底のような生活の中でどうしてこれほど天真爛漫的な明るい音楽が書けるのか、と首をかしげたくなるほどの平和な、そしてロココの典雅な風情が伝わってくる美しい音楽にあふれています。悲しいこと、辛いことがあればこの曲を聴くと、不思議に平和な気分にさせてくれる稀有な音楽です。楽器編成は弦楽四重奏にクラリネットが加わったものです。愛聴盤 アルフレート・プリンツ(Cl) ウイーン室内合奏団(DENON CREST 1000 COCO70762 1975年録音)ウイーンフィルのクラリネット奏者プリンツとウイーン室内合奏団が残した名演。 私の盤はブラームスのクラリネット五重奏曲とのカップリングですが、紹介の再発売された盤はモーツアルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」とのカップリングです。
2007年11月28日
コメント(4)
-

奈良公園の紅葉~その3(完)
「閑話休題」 奈良公園の紅葉~その3(完)昨日は奈良公園で「鹿寄せ」行事が行われたそうです。 飛火野地区で午前9時にホルンを吹くと約90頭ほどの鹿がその音色に引き寄せられて、ホルン奏者のまわりに集まり大好物のどんぐりを貰っている光景が、のんびりとしたいかにも奈良文化のおおらかさを伝える行事がニュース番組で紹介されていました。奈良公園の紅葉画像も今回で終了です。 今日は手向山八幡宮周辺の様子です。 公園管理事務所が教えてくれた通りの見事な紅葉を楽しめました。今週末は晴天のようですから京都・嵯峨野天竜寺から竹藪を抜けて、大河内山荘~常寂光寺~二尊院~祇王寺~愛宕付近まで紅葉を追っかけて撮影に行こうと思っています。撮影地 奈良公園・手向山八幡宮 2007年11月24日
2007年11月27日
コメント(12)
-

奈良公園の紅葉~その2
「閑話休題」 奈良公園の紅葉~その2昨日は朝から長居植物園に秋薔薇を撮りに行こうと思っていましたが、奈良で張り切り過ぎて疲れましたので、終日自宅で過ごしていました。昨日に引き続き奈良公園の紅葉画像です。撮影地 奈良公園浮雲園 2007年11月24日
2007年11月26日
コメント(12)
-

奈良公園の紅葉~その1
「1032525」さん、ご教示ありがとうございました。 教えていただいた通りにしますと元に戻りました。本当にありがとうございました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「閑話休題」 奈良公園の紅葉昨日は奈良公園にカメラを持って紅葉探しに出かけました。 私が一番苦手な紅葉の写真。 それは私が強度の赤緑色弱で、微妙な色のグラデーションや薄い赤などを、目が感知してくれないからです。誰か正常な目を持った人が同行してくれないと、とんでもない写真撮って帰ることがよくありました。今回は前田美帆さんという友達に同行をお願いして、朝早く7時半に難波の新歌舞伎座で待ち合わせて近鉄難波から奈良へと向かいました。電車に乗るまで雑用が多くて奈良駅に着いたのが10時でした。駅からまっすぐに延びる歩道を両側に広がる広大な公園を歩き、東大寺南門を左に見ながら紅葉スポットを捜し歩きました。確かに公園管理事務所のスタッフが教えてくれた通り、ナンキンハゼのほとんどが落葉して実が付き始めていました。 しかし、イチョウカエデは美しく色づいていました。東大寺二月堂・三月堂から奥山へ向かう道を選んで歩きますと、ところどころに見事な紅葉があり、のんびりと草を食む野生の鹿たちの群れが感興をいっそう高めてくれます。気温16度。 陽射は小春日和のようで家族連れや友人グループ、若いカップル、春日大社を訪れるのでしょう、七五三の姿の可愛い子どもたちが目を楽しませてくれました。撮影地 奈良公園・浮雲園地 2007年11月24日
2007年11月25日
コメント(6)
-

バッハ 「ブランデンブルグ協奏曲」
『今日のクラシック音楽』 J.S.バッハ作曲 「ブランデンブルグ協奏曲」ヨハン・セバスチャン・バッハ(1685-1750)は、65歳の人生で教会音楽と呼ばれる「宗教」の行事に使われる音楽と、「世俗曲」と呼ばれる教会で演奏されるものと関係がない2つの音楽ジャンルの作品を書いています。 前者が「カンタータ」や「ミサ曲」、「オルガン曲」などで、後者には「管弦楽組曲」、「ヴァイオリン協奏曲」、「無伴奏チェロ組曲」、「無伴奏ヴァイオリンソナタ」、「平均律クラヴィーア曲集」、それに「ブランデンブルグ協奏曲」などがあります。バッハには「ワイマール時代」とか「ケーテン時代」とか「ライプチッヒ時代」とか呼ばれている時期があります。 それは彼がいち時期を過ごした場所を示す時代を表しています。 それぞれの時代にその場所の王侯・貴族に遣えて「音楽長」なる職務を与えられていたことを表す言葉です。「ワイマール」では9年半の間、「宮廷オルガニスト」「宮廷楽員」としてつかえて、最後には「楽士長」となっています。 その「ワイマール」の後バッハは紆余曲折を経て、ケーテン公レオポルドに熱心に請われて公の宮廷楽団の楽長のポストに就いて約5年半を「ケーテン」で過ごしました。 1717から1723年のバッハ32歳から38歳の時期です。 ケーテン公は非常に音楽の好きな人だったそうで、バッハを手厚く扱っていたためにバッハ自身も自分の書きたい曲を思う存分に書いていたそうです。上記の「世俗曲」はほとんど「ケーテン時代」に書かれたと言われており、バッハ65歳の生涯で「最も幸せな時代」であったと言われています。その「ケーテン時代」に書かれた作品の中に「ブランデンブルグ協奏曲」(全6曲)があります。 イタリアのヴィヴァルディ(1678-1741)に代表されるイタリア・バロック音楽に「合奏協奏曲」(独奏楽器群と合奏楽器群の競演)という音楽スタイルがあり、ラテン特有の華麗な音楽に人気がありました。 バッハはその「合奏協奏曲」スタイルに、よりがっしりとした骨組みを作ってドイツ精神のようなものを吹き込んだ作品に書き上げています。使用される独奏楽器群は6曲それぞれに異なっており、曲自体に様々な彩りを与えています。 各曲の独奏楽器群は、「第1番」 ホルン2本と3本のオーボエ「第2番」 トランペットとリコーダー、オーボエ、ヴァイオリン「第3番」 独奏と合奏の区別無く、弦楽器のみ「第4番」 2本のリコーダーとヴァイオリン「第5番」 フルートとヴァイオリン、チェンバロ「第6番」 独奏と合奏の区別なく、弦楽器での演奏となっており、ヴィヴァルディ・スタイルを踏襲しているのは「第2番」「第4番」「第5番」と言われています。 他の3曲はバッハ独自のスタイルとなっているそうです。音楽は華麗さとドイツ音楽の重厚な構成による骨太の音楽となっていて、それぞれの曲の多彩な曲趣を味わえる作品です。この曲は、「ケーテン時代」に書いて宮廷演奏会で演奏されていた作品から6曲を選び出して、1721年にルードヴィッヒ・ブランデンブルグ辺境伯に献呈されています。 この曲の名前はこのルードヴィッヒ伯爵に献呈されたことに由来しているそうです。私がこの「ブランデンブルグ協奏曲」を初めて聴きましたのが高校1年生の時で、今では何故この曲を選んだのか理由は定かではありませんが、カール・ミュンヒンガー指揮 シュトットガルト室内管弦楽団の録音したLP盤から第2番のみをプレスしたEP盤を買って聴きました。 トランペットの華やかな音色に魅されて毎日この「第2番」を聴いて楽しんでいました。愛聴盤(1) ルドルフ・パウムガルトナー指揮 ルツェルン弦楽合奏団 (DENONレーベル COCO78379-80 1978年録音)ヨゼフ・スークのヴァイオリン、オーレル・ニコレのフルート、ギィ・トゥーヴロンのトランペット、クリスティアーヌ・ジャコテ(チェンバロ)などをソリストに迎えた、少しの遅めのテンポでゆったりとした素朴なドイツ・バロック音楽といった感のある、聴くほどに味のある演奏です。 日本プレス盤はしばらく廃盤になっていましたが、今は復刻されています。 2枚組1,500円という廉価盤でCreast1000シリーズで蘇っています。愛聴盤(2) ジャン=フランソァ・パイヤール指揮 パイヤール室内管弦楽団(DENONレーベル COCO70618 1973年録音)以前2枚のCDでリリースされていたのを聴いています。パウムガルトナー盤のような重厚さはありませんが、フランス・サロン音楽風のバッハでランパルのフルート、モーリス・アンドレのトランペット、ジャリのヴァイオリンなどの独奏者を迎えての名人芸を楽しめるディスクで、現在はDENON CREST1000シリーズで1000円盤として再発売されています。第1番を除いて5曲収録されています。
2007年11月23日
コメント(4)
-

近畿の紅葉はまだ早い?
20日に張り切って湖北有数の紅葉の名所金剛輪寺に行きましたが、まだ紅葉には早過ぎて部分的に色が染まっているだけでした。それに葉の傷みもひどく写真にするにはちょっと辛いところがありました。それで日帰りで帰ってきました。 20日の記事に期待していただいた方々には悪いのですが、おみやげとなる写真は何にもありません。 今年の紅葉は報道で言われているように今月末にならないとダメなようですね。金剛輪寺は天台宗のお寺で湖東三山の一つで、聖武天皇の祈祷寺として724年に行基が開山したお寺だそうです。 本堂は威風堂々とした建物で国宝に指定されています。急な坂道を登った先にあるのですが、お年寄りや体に自信のないお方にはお参りはきついかもしれません。写真で見る本堂付近や三重塔付近の紅葉は「血染めの紅葉」として有名ですので行きましたが、まだその時期ではなかったようです。近畿ではまだ紅葉は早いのでしょうか? 奈良公園はすでに見頃を迎えたとの情報もあったので、今日公園管理事務所に電話で問い合わせますと春日大社周辺、手向山八幡宮、東大寺周辺などは見頃だそうです。 24日(土)にでもカメラを持って行ってみようかと思っています。この日はちょうどお昼時に訪れたのですが、常識のなさに驚いた光景を観ることになり失望しました。 本堂左上に重要文化財の三重塔が建立されています。 その塔の軒下に大勢の訪問者(全部熟年・老人男女)が弁当を広げて食べているのです。 これには唖然としました。 まだ11時30分です。 この重要文化財に腰かけて30人くらいが居たでしょうか。 坂道を降りて駐車場には休憩所も設けられています。 そこで食事ができます。 時間がなければバスの中でも食事ができます。 何故この塔に腰かけて食事をするのか? これでは若い人たちに苦言を呈することが出来ません。 傷をつけたり、破損させたりすればどうするつもりだったのでしょう。 シンガポールの公共道徳の高さと比べると、日本人のマナーの貧困さを見せつけられたような気分になりました。
2007年11月22日
コメント(6)
-

2日間旅に出ます
今日から琵琶湖沿岸北部の古刹を訪ねて紅葉を愛でる旅にでます。 帰宅は明後日21日の予定です。 おみやげにいい写真が撮れているといいのですが。 いいのがあれば掲載します。まだ紅葉の見ごろには少し早いかなという感がありますが、日程の都合でこうなりました。24日(土)には奈良公園に紅葉を探して徘徊します。 新しいPentax K10Dの威力は如何に? 乞うご期待を! と言いたいのですが半年以上カメラを触っていませんので、どんな写真が出来上がるやら、観てのお楽しみです。いざ~、出陣!
2007年11月20日
コメント(10)
-

カリンニコフ 交響曲第1番
『今日のクラシック音楽』 カリンニコフ作曲 交響曲第1番 ト短調今日の話題は、「ロシアにこんな作曲家、音楽があったの?」というような曲です。ワシリー・カリンニコフ(1884-1901)が書きました交響曲第1番がそれです。この曲については2005年にブログで紹介したことがありますが、昨日久しぶりにCDプレーヤーに載せて聴いてみました。 やはり美しい曲です。 心が温まるような感じを受ける旋律で、どこかのどかで、どこか哀愁のあるロシア的旋律の美しさの極みのような音楽です。 それで以前に書いたブログを紐解いてみました。 やはり付け加えることは何もありません。 この曲の良さについてはその時のブログの文章のまま掲載しておきます。カリンニコフは、私もその存在さえ知らずにいたのですが、2年前にHMV阿倍野店のクラシック音楽担当者から教えてもらって初めて名前を知りました。演奏会でも録音でほとんど採り上げられない、マイナーな作曲家ですが、その音楽は極上の叙情的な美しさに彩られており、もっとレコード会社も指揮者/オーケストラも採り上げるべき音楽だと思います。カリンニコフは貧乏で、モスクワ音楽院の学費の支払いも滞るほどだったそうです。劇場オーケストラのアルバイト楽員をしながら糊口をしのいでいた作曲家だったそうです。ようやく音楽院を卒業して、チャイコフスキーの世話によって指揮者の職を辛うじて得たりしていましたが、もともと病弱だったようで結核を患って保養地送りとなってしまいます。その療養期間中に書いたのがこの交響曲第1番でした。ラフマニノフにもピアノ連弾用の楽譜出版の手助けをしてもらったりしていましたが、誕生日まであと2日で、35歳になろうという1901年に34歳で短い生涯を閉じています。作品も少ないのですが2曲の交響曲を聴く限り、惜しい人材を亡くした感があります。交響曲第1番は彼の友人に捧げられていますが、音楽は非常に美しい、それも親しみやすい旋律で書かれており、どの楽章(4楽章構成)もロシア的、スラブ的な魅力のある旋律で、美しく、繊細です。 ドヴォルザークの民族音楽的な交響曲に匹敵するほどの親しみやすさがあり、ロシアの大草原の風が吹き渡るかのような爽やかさのある音楽です。もっと多くの人々に聴かれるべき、素晴らしい国民楽派的な曲です。愛聴盤 テオドレ・クチャル指揮 ウクライナ国立交響楽団(Naxosレーベル 8.553417 1994年11月録音)カップリングは同じくカリンニコフの交響曲第2番です。 Naxosからリりースされて大ベストセラーになり、これをHMVで教えてもらって購入した盤です。
2007年11月19日
コメント(8)
-
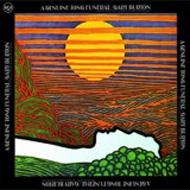
「葬送」~ゲイリー・バートン
『今日の音楽』 「葬送」~ゲイリー・バートン今日はクラシック音楽ではなくてモダン・ジャズの話題。 クラシック音楽と同様に、私にはモダンジャズはとても好きな音楽ジャンルです。年間を通しても聴く機会の多いジャンルです。そんなジャズ鑑賞歴の中でも、とても気に入っている盤を今日は書いてみようと思います。「A GENUIN TONG FUNERAL/GARY BARTON」という1枚です。ゲイリー・バートンはとても刺激的なヴィブラフォン奏者で、30年前に「ピークス」というLP盤を買って聴いて以来、MJQのミルト・ジャクソンと共に一番気に入っているバイブ奏者です。その彼がジャスピアニストであり、作曲家でもある女流のカーラ・ブレイとコラボレーションプレイを行なった、とても刺激的な1枚の録音盤が今日の話題にした1枚です。「葬送」とはカーラ・ブレイが作曲した意欲的な試みのジャズで、「死」と「葬送」をテーマにした音楽です。東洋のドラマティックな葬送からヒントを得て、ちょっと異様な雰囲気のジャズ音楽が生まれています。ここに流れている音楽は、あくまでもアメリカジャズが基調になっていますが、東洋的な、日本的な旋律が随所に現れてきて、東洋の「生と死」の輪廻のような思想が描かれているような感さえ受ける音楽です。ファンキーなモダンジャズとは一線を画した作風で、あたかも「ニュージャズ」といった雰囲気で、「葬送」を新しいサウンドで華麗に色彩豊かに表現しているドラマティックでカラフルな作品として、音楽が浮き彫りにされている名作の部類にはいる曲ではないでしょうか。ゲイリー・バートンクワルテットが中心となっていることは言うまでもなく、縦横無尽にバートンのバイブが澄んだ響きで活躍しており、カーラ・ブレイの華麗なピアノが演奏の素晴らしさを守り立てています。それにラリー・コエルのギターも美しく、瞑想的なテナー・サックスが東洋的な旋律を奏でているのも魅力です。静かに始まる葬送の音楽が、やがて各プレーやーの咆哮に似た賑やかなジャズとなり、やがて活気に満ちたジャムセッションとなり、葬儀が終われば生ある者が、普段と変わらぬ喧騒の日常生活に戻っていくような、そんな様を描いているような、画期的なモダンジャズの実験的な音楽です。ご興味ある方は一聴をお薦め致します。(RCA原盤 BMGファンハウス BMCJ38092 1967年録音)ゲイーリー・バートン(Vib) ラリー・コリエル(g)、ステイーウ・スワロー(b)、カーラ・ブレイ(ピアノ・オルガン、指揮)、他
2007年11月18日
コメント(0)
-
作曲家も驚き~俗称の多いこと
「今日のクラシック音楽」 勝手につけられた俗称(副題)クラシック音楽の曲名に副題(俗称)がつくと何となく聴いてみようかな、どんな曲かなという期待が湧くものです。 例えば、ベートーベンの交響曲第3番「英雄」とか第6番「田園」、ドヴォルザークの第9番「新世界より」やチャイコフスキーの第6番「悲愴」などがその典型的な例でしょう。 これらの曲は作曲家自ら楽譜に書いた副題ですが、作曲家本人が付けたわけでもないのに後世の人が面白おかしく付けているのもあります。 そのおかげで有名になっている曲もあります。ベートーベンのピアノ・ソナタ第14番がその典型です。 今では第何番という正式な呼び方を知らなくても「月光ソナタ」と言えば、「あ~、あれね」となります。 この曲とてベートーベンが作曲時に付けた名前でもありません。 スイスの詩人がこの曲の第1楽章を表して「スイスのルツェルン湖の月光の波に揺らぐ小舟のようだ」と形容したのが始まりだそうです。ベートーベンはただ単なる「幻想風ソナタ」としただけの曲が、現在では「月光ソナタ」として世界中に広まっています。副題(俗称)が多いのはハイドン。 この人の曲、特に交響曲に色々な副題がつけられています。 「朝」「昼」「晩」「火事」「校長先生」「めんどり」「熊」「哲学者」「ホルン信号」「王妃」「告別」「時計」「太鼓連打「驚愕」「軍隊」「ロンドン」「奇跡」など実に多数の副題が付けられており、聴く方にも食指が伸びそうなものばかりです。これらにはエピソードがあるのですが、その挿話も真実なものもあれば、後世の人たちが勝手にでっち上げた物がほとんどです。例えば第45番「告別」は事実に基づいているそうです。 ハンガリーの貴族の宮廷音楽長として仕えていたハイドンは、主が夏の間避暑に出かけるのに楽団員全員とその家族も連れて行くのが習慣でした。 ところがその年は宮殿を改修中で楽団員の家族まで収容できないので、単身赴任となり、楽団員とその家族は嘆きました。 そこでハイドンが書いたのが第45番「告別」でした。第1楽章では楽団員全員がそろっていますが、終楽章では演奏が終わった楽員がローソクを消して一人、一人退場していき、最後はヴァイオリン二人だけが残るという曲です。 これを貴族の前で演奏しますと、彼はハイドンや楽団員の気持ち理解して従来通り家族同伴で避暑地に向かったそうです。 これが「告別」の由来だそうです。もう一つ、ハイドンの「奇跡」(第96番)。 これはハイドンがザロモンという興行師によってロンドンへ演奏旅行した際に書いた「ザロモン・セット」の一曲ですが、その演奏会でハイドンが指揮をとることになっていました。当時彼はロンドンでも非常に人気があり、少しでも近くで彼を観ようと聴衆は前の席が空いているのでそこへ移動しました。 真ん中あたりに空席が目立ってしまいました。 演奏が始まるとその真ん中あたりの天井に吊下げてあっシャンデリアが客席に落ちました。 幸いなことにそのあたりの客席は聴衆が前に移動していたので、怪我をした人は誰もいなかったそうです。 それで聴衆は「奇跡だ!」と叫んだので、このときの演奏曲第96番が「奇跡」呼ばれるようになったそうです。 これは勿論作り話ですが。私が若いころ大阪フェスティバル・ホールでこの「奇跡」の演奏を聴いたことがありますが、演奏が始まると思わず天井を眺めていました。
2007年11月17日
コメント(8)
-
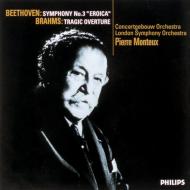
作曲家お気に入りの旋律
「今日のクラシック音楽」 作曲家お気に入りの旋律同じ作曲家が違う曲に同じ旋律かそれに酷似した旋律を使っている場合がよくあります。 「あれ、これ、聴いたことがあるぞ!」というような経験はありませんか? クラシック音楽の場合よくあります。 レコードやCDを買って聴いてみると以前聴いた旋律が出てきたりして、慌てて解説書を読むとそのいきさつを説明していることがよくあります。例えばベートーベンの交響曲第3番「英雄(エロイカ)」の終楽章。 ここは変奏曲なのですが、冒頭の序奏のあと表れる有名な旋律。 これは1801年完成のバレエ音楽「プロメテウスの創造物」に使われている旋律を使っています。 ベートーベンはよほどこの旋律がお気に入りなのか、更にピアノ曲「プロメテウスの創造物による15の変奏曲」にも使い、最後に「英雄」交響曲に使っています。 あまりにも「英雄」交響曲が有名なので、ピアノ曲は「エロイカの主題による変奏曲」なんて後から命名されています。またベートーベンの室内楽で有名な曲「七重奏曲」があります。 ファゴット・クラリネット・ホルン・ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバスで演奏される柔和で壮大で実にベートーベンらしい美しく力強い曲ですが、その中心主題が、今年初めにフリードリッヒ・グルダの演奏によるベートーベンピアノ・ソナタ全集を購入して聴いていると「第18番変ホ長調」(1804年)の「メヌエット」楽章で使われている旋律にとてもよく似ているのです。 もう一度「七重奏曲」を聴いてみると、なるほど全く同じ旋律ではありませんが酷似していました。また超有名曲、ベートーベンの代名詞のような交響曲第5番「運命」の冒頭主題。 これがピアノ・ソナタ第23番「熱情」に何度も動機の形で出てきています。 まるでこの「運命の動機」で作られたソナタのような感じもします。シューベルトもそうですね。 有名なピアノ五重奏曲「ます」の第4楽章で彼の歌曲「ます」からの旋律を使っていますし、弦楽四重奏曲第13番「ロザムンデ」は彼の劇音楽「ロザムンデ」で使われた美しい旋律の「間奏曲」を第2楽章で使っています。 故に「ロザムンデ」と呼ばれる名前が付いています。この「間奏曲」をシューベルトはよほど気に入ったのかー実に美しさにあふれた旋律ですー、ピアノ曲「即興曲第3番変ロ長調」でも転用しています。同じことが彼の弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」も第2楽章で歌曲「死と乙女」からの旋律を用いて変奏曲としています。 それ故に「死と乙女」と呼ばれる曲になっています。 これも非常に美しく哀愁あふれる旋律です。作曲家によってやはりお気に入りの旋律があって、それを変奏の形にして曲想や楽器を変えて作曲したくなるのでしょうね。愛聴盤1. 「英雄」交響曲 ピエール・モントー指揮 アムステルダム・コンセルトヘボー(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP3379 1962年録音)2. 「七重奏曲」 ベルリン・ゾリスデン(テルデック原盤 ワーナー・クラシック WPCS21063 1990年録音)3. 「エロイカ変奏曲」 クラウディオ・アラウ(P)(philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP9332 1968年録音)4. ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 バックハウス(P) (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD9155 1959-61年録音)以上3点は現在1000円盤です。5. 弦楽四重奏曲第13番「ロザムンデ」 アルバン・ベルク四重奏団(EMI原盤 東芝EMI TOCE59220 1985年録音)6. 弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」 ボロディン四重奏団(ワーナークラシックス原盤 elatusuレーベル 0927.49002 1995年録音 海外盤)
2007年11月16日
コメント(6)
-
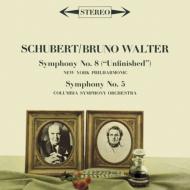
何で変わるの「未完成」の番号?
「今日のクラシック音楽」 交響曲の番号が変わっている!~「未完成」交響曲私がクラシック音楽を好きになった頃は、シューベルトの「未完成」交響曲はベートーベンの第5番「運命」、ドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」、それにチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」がクラシック・チャートのアイドル的存在でした。その頃のシューベルトの「未完成」は交響曲第8番として定着していました。 彼は9曲の交響曲を書き残しています。 ところが最近この曲は交響曲第7番ロ短調「未完成」となって売り出されています。私の所有する数枚のCDも8番もあれば7番もあります。 何故こういう紛らわしいことになっているのでしょうか? 調べてみると結果はこうでした。1.第1番~第6番は作曲年が明確に残っていて整理されています。シューベルトの死亡前。2.残りの3曲はすべて彼の死後に発見されています。3.1838年シューマンが第9番発見。1839年メンデルスゾーンにより初演 これが第7番とされた。4.1865年「未完成」発見される。5.その後ピアノ譜による「ホ長調」交響曲発見される。初演は1934年、第9番とされた。ところが実際の作曲年はこうなっていると判明。1.「ホ長調」1821年、第7番とされた2.「未完成」1822年、第8番とされた。3.第9番 1828年、第9番とされた。これで第8番「未完成」として定着しました。ところが1978年、「国際シューベルト協会」がピアノ譜だけの「ホ長調」交響曲第7番をリストから除外しました。理由は、ピアノ譜だけ残っていて1934年の初演は名指揮者ワインガルトナーによるオーケストラ版にしただけ、ということでこの第7番をはずしました。 それで第8番「未完成」、と第9番が繰り上げられたのです。それでもレコード会社は現在でもこの未完成を第8番の表記や第8番(第7番)という表記にしていたり、「ザ・グレート」と呼ばれる第9番をそのままの表記にしています。要するに「国際シューベルト協会」は、シューベルトは8曲の交響曲を書き残したと認定しています。 私の持っているサー・コリン・デービス指揮 シュターツカペレ・ドレスデン盤(RCA)は8曲収録盤ですが、「未完成」を第8番、「ザ・グレート」を第9番としています。これが「未完成」が2つの番号を持つ理由です。 私は今でも第8番「未完成」の方がしっくりと来ますが、皆さんはどうでしょうか?愛聴盤1. ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団(SONY原盤 ソニーミュージック SICC667 1958年録音)2. カルロ・マリア・ジュリーに指揮 バイエルン放送交響楽団 (SONY原盤 ソニーミュージック SICC168 1993年録音)3. サー・コリン・ディビス指揮 シュターツカペレ・ドレスデン(RCAレーベル 82876603922 1994-96年録音)シューベルト交響曲全集です。
2007年11月15日
コメント(8)
-
心の荒廃/不可解なコメント
「閑話休題」 心の荒廃私の子供時代は遊ぶ道具は現代に比べてほとんどありませんでした。 それで仲間たちと遊びの方法を自分たちで見つけて遊ぶ時代でした。 まだ畑・田圃がたくさんあって、小川が流れており灌漑用の溝には雨が少し強く降れば鯉や鮒が泳ぎ、森や林の中に木の枝や葉っぱで「住家」を作ったり、冬の寒い日には「馬乗り」や小学校のグラウンドでドッジボールをしたり、布製のグローブで三角ベースで野球をする毎日でした。 与えられる遊び道具や選択できる遊戯具のない時代でした。そんな時代に「道徳」という学校の授業がありました。人としてやってはいけないことを先生から教えられる時代でした。学校で悪いことをすれば先生に殴られ、悔しいから家でそのことを親に言うと今度は親から殴られました。悪いことをした罰だと言って。 そんな時代が懐かくなる事件ばかりが目立つ今の世の中に変わってしまいました。「心の荒廃」としか言いようのない事件が多過ぎます。 子が家に放火して親や兄弟を死なせたり、まだ小学生の我が子を手にかけて殺したり、夫や妻や、子が親や祖父・祖母を殺したり、最近の新聞・TVにはこういう事件が毎日のように報道されています。いつか書こうと思っていましたが、あまりにひど過ぎて原稿を書いても、こちらの心がやり切れなくて何度も削除する繰り返しでした。しかし病院職員による全盲男性の公園に置き去り事件報道を知って、ただただ唖然としました。 病人を世話して病気を治す仕事の病院職員にこの置き去り事件は、まさに「心の荒廃」そのものではないでしょうか? いくらその入院男性患者がひどい不始末を繰り返したとは言え、「捨て犬・捨て猫」ではありません。 人間であり病気の再発の可能性のある患者です。 もっと病院内で話し合いや協議が出来なかったのかと思います。日本人の「心の荒廃」がここまで来たのかという思いです。 やはり「道徳教育」という抜本的な改善を考えなければ、このままでは日本に「心の荒廃」がはびこり、同じような事件が起こってそれを傍観する側にも慣らされる、という悪循環によりますますこの国に「心の荒廃」が進むような気がしてなりません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「不可解な美帆さんのコメント」昨日の「ふくまる旅館」の記事に不可解なコメントが掲載されていました。 私の友人で美帆さんが書いてくれたコメントですが、コメンターの名前が2つとも私のハンドルネームになっていたのに驚きました。 このハンドルネームは私しか使えないはずなんです。それがどうして美帆さんが使えるのか不思議です。確かに彼女の不定期な記事を私のページに掲載することは承諾・同意していますが、それは基本の文章を私のメール・アドレスに送ってもらって、それを私がコピーして掲載するようになっていましだ。直接彼女が記事を書けないはずなのに、昨日はコメントに私の名前を使用していたことになります。不思議です? なぜこういうことが起こるのか?美帆さん、教えてください。
2007年11月14日
コメント(2)
-

TVドラマ「ふくまる旅館」
「閑話休題」 TVドラマ「ふくまる旅館」が訴えるもの最近は新聞を広げると殺人・放火・死体遺棄が連日のように報じられており、マスコミも被害者家族や加害者家族の人間模様を暴き立てるかのように彼らの自宅の前にカメラの方列を組んでいる。一方では食品会社の製造・賞味期限の食材の偽装発覚。 また国家公務員・地方公務員による不正発覚事件と、明るい話題がほとんどない今の日本。 家庭での唯一団欒時間では低級なスタジオトーク(若いタレントや漫才師による意味不明の日本語が飛び交う低俗番組)が多いですね)。そんな時代の風潮に逆行するかのような、観ている者をほのぼのと包んでくれる貴重な1時間番組があります。 TBS系列の月曜日8時からの放送「浅草 ふくまる旅館」。東京・浅草で60年以上続く老舗旅館「ふくまる旅館」が舞台のドラマ。主人公の福丸大吉(西田敏行)は三代目主人としてふくまる旅館を継いで30年になる男やもめ。大吉は義理と人情に篤い人柄ですが、ふくまる旅館は近年、近辺のホテルなどに客を取られ、経営が芳しくない状態が続き、旅館を切り盛りする大吉の義姉・福丸はな(木野花)はインターネットでの客の呼び込みに必死です。毎回、旅館周辺で巻き起こる身近な問題に、大吉が首を突っ込み、奔走すします。物語は、旅館の客と従業員との触れ合いを描いた、笑いあり、涙ありの人情コメディーです。ふくまる旅館のモットーは「お客は家族、従業員も家族」。このドラマは、台東区をはじめ、浅草寺、浅草花屋敷や浅草観光連盟も製作に協力しており、下町情緒が堪能できる内容となっています。この作品で「男はつらいよ」を彷彿とさせる"人情"路線をとっています。「男はつらいよ」とは違った味なんですが、どこか似ているドラマです。 福丸大吉は大のおせっかい焼き。 飛び込んでお客の悩みをおせっかいのように仲介して丸く収めるお話。毎回観るたびに心が洗われるような想いになるドラマ。 騒動はあっても観終わった後に嫌なものがのこりません。 鑑賞後はとてもさわやか。「男はつらいよ」と同じパターンで他人の悪口や他人を傷つけない人たちの集まり、日本人がいつか忘れてきた「温かさ」が蘇ってくるドラマです。鑑賞後は胸がす~として下町人情の幸せにひたれる稀有な番組です。お薦め番組です。
2007年11月13日
コメント(8)
-

秋の風物詩~吊るし柿
『閑話休題』 吊るし柿 大阪府和泉市と和歌山県の県境にある和歌山・かつらぎ町の「吊るし柿」が盛況を迎えたと産経新聞が報じています。 この月はかつらぎ町の柿畑が実りを迎え、各農家が軒先や途中のやぐらを組んだところに、所せましと柿を縦に連ねて干しています。長いヤグラに吊るされ燦燦と秋の陽射しを浴びて、谷間から吹き渡る秋風を受けて甘い干し柿になっていくそうです。主に関西方面へと出荷されて正月の飾りに使われるそうです。 ハイキングに訪れた人たちにも販売してくれます。まさに「秋の風物詩~吊るし柿」です。下の写真は昨年撮ったものです。 今週末にでも出かけてみようと思っています。撮影地 和歌山県かつらぎ町 2006年11月10日
2007年11月12日
コメント(4)
-
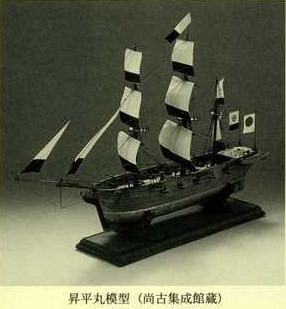
日本国旗の制定はいつ?
「閑話休題」 国旗はいつ制定されたのか1998年10月に中央公論社より「日本の近代」という歴史通史が刊行されました。 月1冊の販売で全16巻激動の幕末(ここではペリー来航から始めています)~現代までの歴史を著述したシリーズ本です。 全巻揃えていたのですが、未読のままになっていたので第1巻「開国・維新」(1853-1871)を先月から読み始めてようやく読み終えました。自分では幕末から明治に至る歴史をある程度把握しているつもりでしたが、改めてその歴史を紐解いてみますとまだまだ知らないことが圧倒的に多く、一つ一つの出来事・歴史に非常に興味を抱きました。その幕末の中で最も興味を持ったのが日本の国旗のルーツです。1854年、「黒船来航」の翌年には鹿児島(薩摩藩)桜島で早くも西洋式軍艦「昇平丸」(長さ27メートル)が12月に完成して徳川幕府に献上されています。 その軍艦に目印となる旗を掲げています。 その旗は2つあって、一つは鹿児島・島津藩の紋所「丸に十字」の十文字章の旗。 もう一つは日本国総船印として「日の丸」です。 政府(幕府)として正式な文書としての「日の丸」制定がないのですが、この島津家(島津斉彬)が掲げた「日の丸」が日本国旗となったようです。この「日の丸」の起源は定かではないようで、12世紀に武家が現れ、源平合戦には軍扇にシンボルとして描かれているそうです。 そして16世紀後半の豊臣秀吉とその後の徳川家康が貿易船に国を表す旗として用いられていたそうです。 その後長い鎖国時代があり、交易もなくなったことからこうした国を表す旗の必要性がなくなったのですが、黒船来航により一気に開国に傾いた幕府は島津斉彬の提言を受けて、再び国を表す旗として「日の丸」を用いたのでした。幕府の使節を乗せた「咸臨丸」にも日章旗がはためいています。高校生時代にかなり突っ込んだ日本史授業で習ったはずなんですが、もうすっかり忘れています。まるで忘却のかなたのようでした。1870年に明治政府によって日本船の目印と制定されましたが、まだ日本の国旗としての明確化はなく、戦後の「日章旗掲揚問題」として120年の時代が過ぎて、1999年(平成11年)にやっと議会で「国旗国歌法案」が可決されてこの「日の丸」(日章旗)が日本国の国旗として定められるに至っています。しかし、何故日章旗が日本の国旗なのかと日教組から強いクレームがあって、学校での国旗掲揚について教職員に自殺者が出た程の社会的問題となっているのは周知の事実です。私見を言わせてもらえば、いくら歴史を紐解いてもこの「日の丸」が日本国を象徴する確固たる物証がないのであれば、すでに内外にこの旗を日本の国旗として認知されているのだからそれでいいのでは、と思います。
2007年11月11日
コメント(2)
-
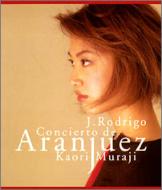
ロドリーゴ アランフェス協奏曲
『今日のクラシック音楽』 ロドリーゴ作曲 「アランフェス協奏曲」昨年もこの記事を書いていますが、加筆して掲載しておきます。アメリカの作家アーネスト・ヘミングウエーは、1930年代の「スペイン革命」に参加して、スペインに長く滞在しており、パエリアに代表されるスペイン料理やビーノ(地酒ワイン)、それに美しいセニョリータの笑顔、人の心に情熱をかきたたせるフラメンコダンスとスパニッシュギターの音色や、生と死の境に立つ闘牛をこよなく愛した作家で、長編小説「誰がために鐘は鳴る」「日はまた昇る」、ノンフィクション「午後に死す」などを書き残しています。その同じ時代に、盲目のスペイン生まれのホアキン・ロドリーゴ(1901-1999)がいました。 3歳で目の障害を患って以後盲目に近い状態が、亡くなるまで続きました。「アランフェス」は首都マドリードから南へ50kmほど離れたところにあり、スペイン黄金時代に200年かけて建てられた壮麗な離宮やスペイン随一と言われる美しい庭園があります。 私は若い頃に欧州出張の際にこのアランフェスを訪れたことがありますが、乾燥地帯の多いスペインには珍しく、豊かな水と深い緑の森に囲まれた小さい、しかし、美しい町を見て感動した思い出があります。その「アランフェス」にトルコ人で生涯ロドリーゴを支えていた夫人と、彼は訪れています。 そして頬を撫でる風、木々を吹きそよぐ微風、鳥たちのさえずりや鳴き声、川のせせらぎの音などを、目にすることが出来なくてもその空気に触れた感じを音楽で表現したのです。 そこに立ったときにこの「アランフェス協奏曲」の構想を練っていたと語っていたそうです。瓢箪のような形をした6本の弦で出来たギター。 軽くて弦を弾けば音が出る。 この楽器はスペインの情熱的な音楽にうまく溶け合っています。 時には哀愁を、時には土着の情熱を醸し出す楽器ギター。 スペインの作曲家がこれまでに巧みにこの楽器を用いた音楽を書いています。ロドリーゴは「アランフェス」で練った構想をギター協奏曲として完成しました。 スペインのかつての隆盛を偲ばせる「アランフェス」の情景を見事に描きだした第2楽章の哀愁のこもった旋律は、単独で演奏されてポピュラー音楽ジャンルでももてはやされている美しい音楽となっており、アランフェスの代名詞のようになっています。曲は3つの楽章から成り、第1楽章冒頭のギターがかき鳴らす舞曲風の陽気で明るい序奏からもう私たちはスペイン情緒に包まれています。第2楽章は、オーボエのソロと哀切の旋律を奏でるギター、それをバックアップするオーケストラの豊穣で寂しげな音楽は、後に「恋のアランフェス」と呼ばれるほど有名な、筆舌に尽くし難い美しい旋律が私たちを魅了してやみません。「秋の夜長」をこの「アランフェス協奏曲」で、ハープに似た柔らかな音と表情豊かな「ギターの音色」で、過ごされるのはいかがでしょうか。 そして、最も大切な人の傍で。1940年の今日(11月9日)、この「アランフェス」協奏曲がスペイン・バルセロナで初演されています。愛聴盤 1. 村治香織(ギター) 山下一史指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団(ビクター レーベル VICC-60154 1999年12月 東京録音)イエペスや、ぺぺ・ロメロ、ジュリアン・ブリームなどの素晴らしいギター演奏もありますが、あえて若い村治香織の演奏を採り上げました。 超優秀録音の美しい仕上がりの録音です。↓村冶香織(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD9444 2007年7月録音)村治香織の7年ぶりの「アランフェス」2度目の録音。 先月リリースされたばかりの新録音。私は未聴です。2. ナルシソ・イエペス(G) アンドレ・ナヴァロ指揮 フィルハーモニア管(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCG5034 1979年録音)↓イエペソ3.ぺぺ・ロメロ(G) ネヴィル・マリナー指揮 イギリス室内管弦楽団 (Philps原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7045 1978年録音)↓ロメロイエペス、ロメロの演奏を聴きますとさすがにスペインの土の香りが匂ってきそうな、土着の音楽性と現代的な野生の味のするオーケストラ演奏など、私にはどうしてもこの2点で挙げざるを得ない不朽の名演盤で、価格もどちらも1000円盤としての再発売ですから、初めてお聴きになる方にはこれら2点を薦めています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1881年 初演 ブラームス ピアノ協奏曲第2番1929年 誕生 ピエロ・カップッチッリ(バリトン)1940年 初演 ロドリーゴ ギター協奏曲「アランフェス」
2007年11月09日
コメント(8)
-
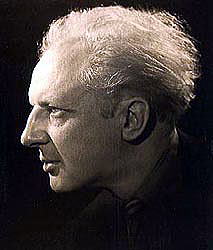
オーケストラの魔術師~ストコフスキー
「今日のクラシック音楽」 編曲の魔術~ストコフスキー若いクラシック音楽ファンには馴染みが少ないかも知れません。 指揮者レオポルド・ストコフスキー(1882-1977)。 オルガン奏者から指揮者に転じて「モンスター」とまであだ名された長寿の人。 94歳まで指揮台に立っていた伝説の指揮者。 アメリカのフィラデルフィア・オーケストラを田舎楽団からボストン響、ニューヨーク・フィルに並ぶまで育て上げた大指揮者。 指揮棒を持たずに両手で微妙なシグナルを送りながらオーケストラを統率して、豪華・華麗な・色彩豊かなサウンドを引き出して聴衆を魅了した指揮者。 従来のオーケストラ楽器配置を現在の形式に変えた指揮者。 それまではヴァイオリンを指揮者をはさんで左右に配置、チェロやコントラバスを中央に配置た形を採っていたのを、左側に第1、第2ヴァイオリンを置き、左側にヴィオラ、チェロ、その後ろにコントラバスという現代の楽器配置にした指揮者。それは常に「サウンド」を意識した指揮者だったから。 晩年になって単身来日した演奏会では、何とホルンをオーケストラの一番前に配置して演奏を行ったこともあります。マスメディアへの進出にも積極的でした。 映画「オーケストラの少女」への出演やアニメ「ファンタジア」への出演などを通じて、彼は常に大衆を意識した指揮者でした。 どこかカラヤンの映像出演にも通じるものがあり、音楽を映像を通じて普及しようたしたカラヤンのさきがけのような指揮者。批評家からは「低俗」「二流」などと酷評を受けたにもかかわらず、己の信ずる「サウンド」を追い求めた指揮者。 そんなストコフスキーが残した名盤にリムスキー=コルサコフの交響組曲「シェラザード」があります。 おそらくLP時代には3度吹きこんでいたと思います。これこそ豪華華麗・色彩美の極致のようなサウンドで、東洋絵巻物を楽しませてくれた遺産のような演奏でした。もう一つ、ストコフスキーの得意なのが編曲でした。 ムソルグスキーのピアノ組曲「展覧会の絵」を自身でオーケストラに編曲して録音や演奏会で披露しています。 あのラヴェルの編曲版よりももっと華麗に鳴り響く「展覧会の絵」が登場したのです。 現在でも多くの指揮者が彼の編曲版を採り上げて録音しています。しかし、何と言ってもストコフスキーの編曲を語る上で忘れてはならないのが、大バッハの音楽をストコフスキー自ら編曲した一連の作品集でしょう。 無伴奏ヴァイオリン・ソナタやパルティータからオーケストラ演奏に編曲したり、オルガンの名曲「トッカータとフーガ ニ短調」をオーケストラで鳴らしたり、カンタータを豪華・華麗なオーケストレーションに変えてしまったり、まさに「オーケストラの魔術師」・「編曲の魔術師」と呼ばれるにふさわしい偉業を成し遂げています。たとえば大バッハの作品「シャコンヌ」。 原曲は無伴奏のヴァイオリン1本で弾く力強い旋律、緊張感をはらんだヴァイオリンの名作ですが、これをストコフスキーは大オーケストラ演奏へと編曲しています。 弦が荘重に旋律を奏し、分厚いふくらみを見せる旋律線。 そこへ金管楽器がかぶさり、クライマックスではティンパニーまで鳴り響く荘重・華麗・美麗なるサウンドが、原曲のイメージを残しながら壮麗に響き渡る様はまさに圧巻です。「小フーガ」として名高いオルガン曲も管楽器によって華やかな音楽世界が現出して、原曲のオルガンでは出せない寂しげなサウンドが、ティンパニーの激しい打音によって華麗なるバッハの音楽世界が現れるのに驚かされます。この編曲演奏にはバッハへの尊敬の念とたどり着いた可能性が一つとなって感動的な音楽体験を味わうことができます。 決してバッハの原曲を損なうことなく、時には荘重に時には華麗な色彩で。愛聴盤(1)マティアス・バーメルト指揮 BBCフィルハーモニー(CHANDOS レーベル OCHAN10282 海外盤)収録曲幻想曲とフーガ ト短調BWV542「アリオーソ」~チェンバロ協奏曲第5番より「目を覚ませと呼ぶ声が聞こえ」~シュープラー・コラール集よりコラール「われらが神は堅き砦」「シャコンヌ」~無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番より「アンダンテ・ソステヌート」~無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番より「前奏曲」~無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番ホ長調よりコラール「深き淵より、われ汝に呼ばわる」カンタータ第147番~コラール「主よ人の望みの喜びよ」コラール第72番「わが分かるる時きたならば」~マタイ受難曲より「サラバンド」~無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第1番ロ短調よりコラール深き苦しみの淵より」「フーガ」~前奏曲とフーガ第2番(平均律クラヴィーア曲集第1巻)より (2)レオポルド・ストコフスキー指揮 チェコフィルハーモニー (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック 1972年チェコ・ライブ録音)収録曲トッカータとフーガ ニ短調 BWV565、前奏曲 変ホ短調 BWV853、「シュメッリ歌曲集」〈ゲッセマネのわが主イエスよ〉 コラール「われらは唯一の神を信ず》」、カンタータ 第4番 ~コラール〈キリストは死のとりことなれり〉より、パッサカリアとフーガ ハ短調 BWV582
2007年11月08日
コメント(3)
-
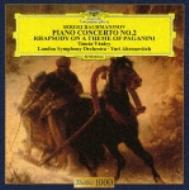
ラフマノノフ パガニーニの主題による狂詩曲/もったいない!
「今日のクラシック音樂」 ラフマニノフ 「パガニーニの主題による狂詩曲」旧ロシア帝国で貴族の家に生まれたセルゲイ・ラフマニノフ(1873-1943)は、1917年のロシア革命によりアメリカに亡命しました。 それ以後彼は欧米を中心に作曲活動やピアノの名手でもあったことから、ピアノ演奏会でその活動を行なっています。欧米での作曲活動の成果の一つが「パガニーニの主題による狂詩曲」です。 スイスで1934年に作曲されたこの曲は、あの有名なニコロ・パガニーニの「24の奇想曲」の第24番の主題を用いて書かれた、実にロマンティックな香りに包まれた約25分の変奏曲です。 タイトルは「狂詩曲」とありますが、実際は「変奏曲」の形を取っています。 しかもその内容はオーケストラとの共演ですから、まるでピアノ協奏曲のような様相を呈しています。音楽はラフマニノフ特有の美しさにあふれ、ピアノ華麗な音色が美しい一曲です。 中でも第18変奏は、昔からクラシック音楽番組のテーマメロディーとなったり、コマーシャルなどに使われたり、その旋律の甘く美しさは例えようもありません。この「パガニーニの主題による変奏曲」は、1934年の今日(11月7日)、アメリカ・ヴァルティモアでラフマニノフ自身のピアノ、ストコフスキー指揮フィラデルフィア管弦楽団によって初演されています。愛聴盤 タマーシャ・ヴァーシャリー(P) ユーリ・アーノロヴィッチ指揮 ロンドン交響楽団(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG5058 1976年録音)LP発売以来、事あるごとに再発売されてきた盤。 現在は1,000円盤としてリリースされています。 名曲ピアノ協奏曲第2番との併録です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「閑話休題」 もったいない!また美帆さんネタですが、彼女と食事をするといつも言われることが一つあります。それは「もったいない」です。外食で料理を注文すると彼女は皿、お椀の中にあるおかずを全て平らげてしまいます。ご飯も一粒もの残さずに平らげます。 これはどこのどんなレストランのどのメニューでも同じです。ご飯なら、お米を作った人に失礼だ。おかずなら作った人に失礼だ、と言って平らげてしまします。 味はまずくてもおいしくても同じ姿勢を崩しません。子供のころはお皿・お茶碗に少しでも残すと、おばあちゃんから「もったいない」と叱られて育ったそうです。 自宅は農家。米・野菜を育て上げる苦労を知っているからだと、彼女は言います。「いただける」感謝と「ありがたさ」を込めて「もったいない」という心になるそうです。彼女と食事をするたびに自分の皿と彼女のそれと比べてしまい、私もきれいに食べきる習慣がつきました。 これは自宅でも食事するときも同じです。 お茶碗に米粒が残っていないか、お皿におかずが残っていないか、無意識に調べています。「美帆シンドローム」かな?たくさん注文してもきれいに食べてしまいましょう
2007年11月07日
コメント(8)
-
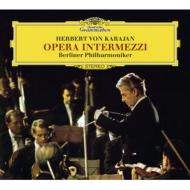
オペラ間奏曲集~カラヤン
「今日のクラシック音楽」 オペラ間奏曲の楽しみ私の友人でオペラを全く聴かない「クラシック音楽大好き人間」がいる。 交響曲や管弦楽曲、器楽曲、室内楽曲にはとても造詣が深く知識も豊富なんですが、ことオペラになると知識がない。 どうも人間が発するあの独特の歌い方についていけないのと、全曲があまりに長過ぎるというのが、オペラを聴かない理由だそうです。確かにオペラは長い。 短いオペラでも80分(CD1枚分)はかかります。 レオンカヴァルロの「道化師」やマスカーニの「カヴァレリア・ルスティカーナ」などはその部類に入ります。ところがほとんどのオペラは2時間はかかります。 ワーグナーの楽劇などは4時間近くかかります。オペラは、イタリア物のように「声の競演」「歌の競演」などと言っても第1幕から終幕までそればかりかと言うと、決してそうではありません。 やはり退屈な時間も生じることがあります。ならばCDなどではハイライト盤があります。4時間近くかかるオペラをいいとこだけ切り取って編集したCDで、大概は1枚物です。 これならアリアや合唱曲、序曲・前奏曲・間奏曲などが入っていて、そのオペラのエッセンスみたいなものです。確かにその当該オペラの「おいしい」歌や部分だけを楽しめる趣向のCDですが、オペラ全体の劇としての緊張感や物語としての面白さには欠けてしまいます。 しかしどうしても全幕を聴くのは億劫だという人には、このハイライト盤はとても重宝すると思います。それよりもまだ短く凄いのがあります。 ヘルベルト・フォン・カラヤンが1950年代にフィルハーモニア管弦楽団と録音した「オペラ間奏曲集」。 序曲集というレコードは昔から色々な指揮者によって録音されています。 「ロッシーニ序曲集」「モーツアルト序曲集」や「オペレッタ序曲集」などがそれです。しかしオペラの間奏曲ばかり集めて録音したのはカラヤンだけではないでしょうか。 「間奏曲」は幕間に演奏される短い小品ですが、ここに紹介します盤に収録されています間奏曲は、どれもこれもまるで独立した曲の様に素晴らしく美しい旋律に彩られた珠玉の小品ばかりです。勿論、この小品一曲でそのオペラを想像したり、物語っているとはとても言えませんが、これらを聴きながらオペラの場面を想像して楽しめる趣向のアルバムです。 まだオペラを聴いたことがない人には、旋律だけを楽しんでもらえるように選りすぐりの美しいメロディーに満ちたアルバムです。カラヤンは50年代からこういう大衆向けとでも言えるような音楽を提供することを考えていたのですね。 そしてこういう誰の心にも入り込むようなクラシック音楽を広めていたのだと思うと、一指揮者にとどまらず、クラシック音楽普及への情熱が沸々と湧き上がっていたのだ、ということがよくわかります。今日紹介する盤は1967年ベルリンフィルとの録音で、選曲もこれ以上ないと思われる間奏曲ばかりです。 特筆すべきはカラヤンのこういう小品の表現の素晴らしさで、どの曲も美しさに満ちたこぼれんばかりの美麗に包まれた演奏です。 間奏曲集ならこれ1枚で充分と思えるほどの華麗・美麗・流麗な演奏です。私は基本的にはカラヤンの美麗さを好みません。 特にベートーベンやモーツアルト、シューベルト、シューマンの交響曲などは、燕尾服を着た作曲者がベンツで疾走するかのような感じを受けるのですが、こういう小品を振ると右にでる指揮者がいないと思わせる美しさにあふれた演奏を繰り広げています。LP時代から何度も装いを新たにして再発売を繰り返してきていますが、ユニヴァーサルからまた12月に再発売される予定です。紹介の商品番号はその12月再発売のものです。珈琲を味わいながら秋の午後に、こうした名旋律をたっぷりと聴くのもおつなものです。愛聴盤 カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG4277 1967年録音)40年前の古い録音ですが再発売のたびにリマスターされて音質も向上して鑑賞には何ら支障のない録音状態で聴くことができます。 1200円で発売されます。収録曲1 歌劇「椿姫」第3幕への間奏曲2 歌劇「カウ゛ァレリア・ルスティカーナ」間奏曲3 歌劇「修道女アンジェリカ」間奏曲4 歌劇「道化師」間奏曲5 歌劇「ホヴァンシチナ」第4幕間奏曲6 歌劇「マノン・レスコー」第3幕間奏曲7 歌劇「ノートル・ダム」間奏曲8 歌劇「タイース」~タイースの瞑想曲9 歌劇「フェドーラ」第2幕間奏曲10 歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」第2幕間奏曲11 歌劇「マドンナの宝石」第3幕間奏曲12 歌劇「友人フリッツ」間奏曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1854年 誕生 ジョン・フィリップ・スーザ(作曲家)1860年 誕生 イグナッツ・ヤン・パデレフスキー(ピアニスト・作曲家)1893年 没 ピョートル・チャイコフスキー(作曲家)1913年 初演 サン=サーンス 「序奏とロンド・カプリチオーソ」1968年 没 シャルル・ミュンシュ(指揮者)1986年 没 エリザベート・グリュンマー(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 風船唐綿
2007年11月06日
コメント(4)
-

バーバー 弦楽のためのアダージョ/薔薇
『今日のクラシック音楽』 バーバー作曲 「弦楽のためのアダージョ」アメリカを代表する作曲家としてサミュエル・バーバー(1910~1981)がいます。 彼の音楽は「豊麗」という比喩が一番似合うように思えます。 彼は、1935年ピュリッツァー奨学金とアメリカ・ローマ大賞を受賞してイタリアに留学。 その際に作曲されたのが「交響曲第1番」と「弦楽四重奏曲」。 そしてこの「弦楽四重奏曲」第2楽章を弦楽に編曲したものが「弦楽のためのアダージョ」です。ほぼ同世代のコープランドなどが実験的試みやモダニズムに興味を持ったのに対して、バーバーは伝統を基幹とした姿勢を貫いて新ロマン主義音楽を標榜しています。 とりわけ旋律線の美しさは秀逸で、「バーバーのアダージョ」と呼ばれるこの作品も、清冽な叙情と情熱が全篇に湛えられています。第1ヴァイオリンの奏する、静かな瞑想的な気分の主題で始まり、ヴィオラ、チェロ等が対位的に現れてきて、段々と音楽が高潮していって最高の頂点にまで至ると、もう一度静かな、穏やかな気分に戻り、第1ヴァイオリンとヴィオラのユニゾンで主題が奏されて静かに終わる曲です。 演奏時間は8分ほどの短い曲ですが、とてもロマンに溢れた音楽です。1938年の今日(11月5日)、トスカニーニの指揮、NBC交響楽団によって初演が行われています。愛聴盤 レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨークフィルハーモニー交響楽団(SONY原盤 Sony Masterworks 5162352 USA輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』1846年 初演 シューマン 交響曲第2番1859年 誕生 ワルター・ギーゼキング(ピアニスト)1882年 初演 スメタナ 連作交響詩「わが祖国」1938年 初演 バーバー 「弦楽のためのアダージョ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 薔薇(ばら)
2007年11月05日
コメント(4)
-
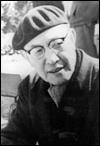
内田吐夢監督~映画「人生劇場 飛車角と吉良常」/ホトギス
「閑話休題」 内田吐夢の映像の素晴らしさ~「人生劇場 飛車角と吉良常」 戦後東映映画で監督として活躍した内田吐夢。 戦前から男っぽい映画を手掛けてきた職人肌の監督。 昭和20年に満州に渡りそこで映画製作を夢見たが、日本の敗戦により挫折。 それでも何故か帰国の途につかず、その理由は今でも謎とされている。彼が帰国したのは昭和28年になってからで、帰国後に撮ったのが片岡千恵蔵主演の「血槍富士」。 彼が撮った映画は骨太で男っぽい主人公という図式があちました。東映で花咲いたのが「大菩薩峠 3部作」(片岡千恵蔵・中村錦之助主演)。 中里介山の未完の時代劇小説を完全映像化した最初の監督。 それが1957年(第一部)でこの映画が封切りされたときは、私は中学1年生で叔父に連れられて映画館の客席で観ました。剣鬼・机 龍之介の数奇な運命と「因果応報」的な仏教的教えに導かれた原作を見事な映像美で描いた秀逸な時代劇映画でした。そして内田吐夢の名を決定的にしたのが村上 勉の小説「飢餓海峡」を映像にした映画「飢餓海峡」でした。 部落民差別から逃れるために殺人を犯し、「洞爺丸」沈没事故で自分を抹殺してまでのし上がった犯人を、伴 淳三郎・高倉 健の刑事が追い詰める執念の刑事サスペンスで、津軽海峡の荒海を見ながら犯人を追う伴 淳三郎の凄まじい執念を荒波で表現したシーンは名場面とも評された映画でした。その後中村錦之助他東映のオールスターを使って製作された「宮本武蔵 5部作」は人間武蔵の心の奥深くまでえぐり出した、同名映画の決定的名画として世に残しています。 1960年代でした。その内田吐夢が監督として初めてメガホンを持った「やくざ映画」が、尾崎士朗原作の「人生劇場 飛車角と吉良常」でした。 戦前にも「人生劇場」を撮っていたそうですが、主人公青成瓢吉を軸とした映画だったそうで、「やくざ映画」ではなかったそうです。私の学生時代は日本映画は「任侠路線」と呼ばれ、東映も日活・大映も「やくざ映画」全盛の時代でよく見ました。高倉 健の「唐獅子牡丹」、鶴田浩二の「博徒シリーズ」、藤 純子の「緋牡丹博徒」などが全盛の頃でした。東映が作る映画はすべて「やくざ映画」という特殊な時代で、その頃に後藤浩二というプロデューサーと言うか企画担当の重役がいて、この人が「やくざ映画」誕生の人物と呼ばれています。その「やくざ映画」全盛のきっかけになったのが、やはり「人生劇場 飛車角」でした。私はこの尾崎士朗の小説を全て読みましたが、やくざが登場するのは「残侠編」で主人公の文士青成瓢吉はこの編だけは蚊帳の外的な物語でした。東映はこの「残侠編」だけを採り上げて「やくざ映画」として撮っています。鶴田浩二の飛車角でこの映画が東映「やくざ映画」のさきがけとなったと言われています。この内田吐夢作品も「残狭編」だけを採り上げています。 それまでの東映得意の「殴り込み」シーンだけのやくざ映画と違って、大正ロマンを思わせる原作者尾崎士郎の文学の世界~男と女の情念の深さ、不条理の世界に生きる博徒が彼等独特の「決まり」に縛られて、その縛られた不条理の世界で命のやり取りをする特殊な世界を描き、カメラの秀逸な画面構成で観る者を圧倒する絵となっています。八年ぶりに故郷に戻った吉良常(辰巳柳太郎)は、ある日、警察に追われて逃げ込んできた飛車角(鶴田浩二)をかくまった事から知り合いになる。娼婦おとよ(藤純子)と共に逃げた事から、小金一家に匿まわれ、飛車角は宮川(高倉健)たちと大横田に殴り込みをかけたのだ。しかも、飛車角を裏切った奈良平を斬った飛車角は吉良常に説得され、自首を決意した。それから数年の月日が流れ、偶然にも宮川は、おとよの働く店の常連となっていた。二人は、皮肉な運命の悪戯を呪い、それでも、おとよに惚れた宮川は、おとよと逃げる決意をしていた。やがて特赦で出所した飛車角は、おとよと宮川の事を知り、自ら身を引く決心をするのだが…。その影では、飛車角の命を狙う大横田の子分たちが、吉良港に集結をしていた。単身、敵地へ殴り込みをかける宮川と、後を追う飛車角。二人の男は避ける事が出来ない運命に向かっていく。この映画が製作されたのが1968年。 その年のキネマ旬報の日本映画ベストテン9位に入ったのも肯けます。やくざ映画としては初めての快挙だそうです。 ゴミのように扱われていたこの種の映画としては、初めて市民権を得たと言ってもよいでしょう。飛車角が殺人を犯し警察に自主する前に愛人おとよと顔を合わせることなく去ろうとする小川の橋に立ち、世話になった一家の若頭と別れを告げている雨の場面。 飛車角が橋に立っているのも知らず、その堤を人力車で通るおとよ。雨に煙る情景。 声をかけようともせずに惜情の念をこらえる飛車角。 不条理の世界に生きる男と女の情愛がこぬか雨降る情景を演出した内田のこだわり。それを見事にカメラにとらえた中沢カメラマンの手腕。出所して吉良常と共に三州吉良に来た飛車角の座敷に、それとも知らず入ってくる芸者おとよ。吉良常、飛車角、おとよの驚愕の表情を天井斜め上から見据えた構図。三者三様の心の動きを見事にとらえた秀逸の名場面。やくざの義理・人情のために切り込む飛車角の「殴りこみ」シーンは暗転となったようにカラーから白黒に変わり、この決闘シーンのモノクロ調に変えた内田の計算と凄惨な切り込みを見事なカメラワークでとらえた中沢。 この映画の企画者後藤が従来の娯楽一辺倒の「殴りこみ」シーンを要求したが、内田吐夢はがんとして聞かずに自説を押し通し、フラッシュを観た後藤を唸らせたと言われる名シーン。そしてこの映画の最も秀逸なのは白黒の切り込みシーンが終わると藤 純子演ずるおとよが、大地に横たわりながら飛車角(鶴田浩二)の足にすがりつくのですが、パッとカラーに変わりおとよの乱れた緋文字の着物姿が、またもや不条理な男と女の情愛を切なげに表現しており、余韻を残して映画が終わります。またもう一つ特筆すべきは吉良常役の辰巳柳太郎の演技の素晴らしさです。小説で読んだ吉良常そのものが出て来たような感さえある名演技。 漂漂とした面白しさと無職渡世の厳しさを見事に使い分けた演技は秀逸で、この映画は辰巳で持っていると言っても過言ではないでしょう。何年か振りで観たこの映画。 やはりいい映画は何度観てもいいものですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 ホトトギス
2007年11月04日
コメント(0)
-

ボウリングゲームを楽しむ
「閑話休題」 ボウリングゲームを楽しむ今日は友人の美帆さんと夕方ボウリングゲームを楽しんできました。 もう10何年来やっていないので、という言い訳は通用しない私です。 何年やっていなくても下手は下手。 ガーターはやるし、折角残したピンを全て倒す位置にあってもボールはピンにかすりもせずに空を切って流れていくし、ごくごく稀にストライクを取っても次はガーターとまったくふるいません。2ゲームやってスコアは173ですから話になりません。美帆さんはボーリングのインストラクターのライセンスを持つ人。 その人に足の位置、手の振り方を教えてもらっても、さっぱり効果なし。彼女も3年ボールを投げていないのと「マイ・ボール」でなくて「ハウス・ボール」のせいか投げにくそう。 トータルで258でした。駅近くのスーパーに駐輪していた自転車で帰宅しましたが、左足膝に痛みがあり、たった2ゲームでこの体たらくです。 やはり年はとりたくないものです。彼女の話によると、ボウリングは古代エジプトが発祥の地と聞きました。現在のような9ピンでなく、三角形でもなくダイアモンド型の10ピンだったそうです。 調べてみると1920年代にロンドン大学の考古学者、フリンダ-ス・ペトリー教授が、エジプトで5200B.C.の古墳の中から、テンピンボウリングによく似たピンとボールを発見したそうです。 そして16世紀のはじめにマルティン・ルターによって、ボウリングのルールが作られ、ピンは9本に統一されたそうです。 1626年には、オランダ人のアメリカ大陸移住にともない、ニューヨーク市のマンハッタンに上陸して、これが、アメリカでの最初のボウリングとなったようです。 以降アメリカで大発展を遂げてきたゲームらしい。美帆さんに会うといつも新鮮な話題に驚かされます。 実に知識の深い女性で人間的に尊敬できる人で、会うたびに尊敬の念を改めています。美帆さん、今日もありがとう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 鬼野芥子
2007年11月03日
コメント(8)
-

カレー料理の楽しみ
「閑話休題」 カレー料理の楽しさカレー は、さまざまな香辛料から出来たカレー粉で野菜や肉を煮込んだ料理のことを指しています。 これが所謂カレーソースです。 このカレー料理はインドや周辺のアジア諸国を中心に作られていたのですが、これらの国は亜熱帯に属する地域です。 現在は世界中で広まった料理となっています。日本でカレーと言う料理はカレー味で煮込んだソースを白米の飯にかける料理、つまりこれがカレーライスです。インドなどの市場の屋台で売られているカレー粉は香辛料を混合した粉末前の個々の香辛料です。 主としてターメリック、サフラン、パプリカなどで色をつけ、クミン、ナツメグ、オールスパイス、キャラウェイ、ガーリック、クローブ、コリアンダー、フェンネル、シナモン、などで香りをつけて、トウガラシ、コショウ、ジンジャーなどで辛さをつけています。インドの人たちは家庭でこうした香辛料を混ぜ合わせて「インド料理」を作っています。 しかしカレー粉なる物は存在していません。 カレー粉なる食材はイギリスで開発されたものです。インドでは、クローブやシナモン、ナツメグなど多種のスパイスを使った香辛料の混ぜ合わせたのをマサラと呼んでいます。マサラはあらゆる料理の調味料として使われていて、出来合いのカレー粉とは違って料理ごとに種類や調合が異なり、ひとくちにマサラと言っても無数のバリエーションがあります。日本のスーパーなどで売られているガラムマサラはその代表的な例でしょう。インドでは香辛料を混合したマサラを幅広い料理に使います。 人はカレーと同義の意味でインドで使われていると思いがちですが、それは誤った認識と言えます。インド人は、身の回りにあるスパイスを毎日の料理に使っているに過ぎず、彼ら自身は「カレー」なるものを作っているつもりは全くありません。 20年前に初めてインドの地に降り立ってインド料理を食した私は、それまで持っていた「カレー」なる言葉の違いを認識しました。インド固有の言葉に「カレー」という言葉はありません。「カレー」の語源としては、タミル語(南インド)でソースを意味する「カリ」あるいはカンナダ語(南インド)の「カリル」が語源で、ポルトガル人が習得して使用したと言われいます。しかし、タミル語とカンナダ語にはソースを意味する「カリ(カリル)」はなくて、「野菜や肉」を意味する「カリ」があり、ポルトガル人がインドのスパイスで煮込まれた料理のことを「カリ」と思い込んでヨーロッパへ持ち帰り、それが英語の curry となり、マサラを使った多くの料理がその名で呼ばれるようになったとされている、と私のインドの知人が言ってました。 日本人が抱くカレーなるものは、イギリスを経由した欧風料理のバリエーションとしてのそれであり、インド固有の料理ではありません。 (上記説明はインターネットからの拠出と私の体験によるものです)ただ我が日本はバリエーションを創ることには他の国に負けない国民性があり、輸入・移入された西洋料理を含めて実にうまく自分たちの口に合うようにアレンジできる稀有な国民です。 その例がカレー・ライスでしょう。 インド料理では日本のカレーのようにどろっとした作り方ではなく、スープのように見えるメニューがほとんどです。 ところが日本のカレーライスはどろったしたソースがほとんどなのが特徴的な違いです。また現代日本人はこの「カレー」なるものを使って、実に多種多様のメニューを編み出しています。 「カレーうどん」「カレーパン」「カレーラーメン」「カレースパゲティ」「ドライカレー」など様々なメニューを生み出しています。 最近ではスーパーに「カレースープ」なる食材も並んでいます。私が台所に立ってカレーを作るとなると、朝から始めます。 基本となるカレー・ルーを入れる前のスープが料理の全てを決めるので、午前中だけでこのスープ作りにかかります。台所に小説を持ちこんでガスレンジの前に椅子を置いて、読書を楽しみながらスープを作ります。 カレールーを入れた後はまるでカレーレストランのような匂いが家じゅうに立ちこめて、この匂いが食欲をそそります。 出来たカレーに家族が「おいしい」と言ってくれるのを期待して食卓に出しますが、あまりこの言葉を聞きません。 美味しいと思うのですが。私のカレーライスのレシピ1.一羽分の鶏ガラを湯がく2.沸騰したら鶏ガラを出して湯を捨てる(鶏の血を取るため)3.もう一度湯(2リットル)を沸かして取り出した鶏ガラと生姜・ニンニク(ひとかけら)を湯がく4.この湯がきは3時間(沸騰してから弱火)。 丁寧にアクを取り出す。鶏ガラを捨てる。5.細かく切ったホウレンソウ(一把)と玉ねぎみじん切りを色がつくまで弱火で炒める。6.5を4の湯と煮込む(4時間弱火で)7.カレールー(市販品)を混ぜて出来上がり。8.食べる前にプレーン・ヨーグルト(小)一個を入れる。これを一晩寝かせると、いっそうコクの深い味になります。
2007年11月02日
コメント(4)
-

楽しきやカレー料理
「閑話休題」 楽しいカレー料理 カレー・ライスという言葉・料理がすでに日本に定着して久しくなっています。 日本独特のレシピによる「食文化」の一端を担う料理となっているカレー・ライス。 江戸時代まではこの料理はまだ日本人の目の前に表れてこなかった料理。 歴史はまだ100年を少し超えたばかりの料理。 スーパーに行けばカレー・ライスのコーナーに溢れんばかりにさまざまなルーが置かれている日本独特の「食文化」の一つ。 一つの頂点を極めたかと思うほどの成長ぶり、人気を誇るカレー・ライス。 この「カレー食文化」にも日本人の器用さをかい間見ることができます。日本人がはじめてカレーに出会ったのは、文献に表れているのは、徳川幕府末期、尊皇攘夷運動が渦巻く1863年、幕府の遣欧使節一行34がヨーロッパに出帆。航路途中、乗り合わせたインド人達が食事するのを見ました。随行した三宅秀清の日誌に『飯の上へ唐辛子細味に致し、芋のドロドロのような物をかけ、これを手にて掻きまわして手づかみで食す。至って汚き人物の物なり」という記述が残っているそうです。どうやらこれがカレーだったようです。その後開国、幕末維新を経て徳川封建体制が崩壊して、文明開化の時代がやってくるのですが、このときに西洋人が持ち込んだカレー料理がやがて日本独特のカレー・ライスとして定着していき130年を過ぎた現代の「カレー料理文化」として定着したようです。西洋から輸入された「カレー料理」は欧米の土着の「食文化」ではなくて、1500年初期に行われたフェルディナンド・マゼランによる世界一周航路に代表されるキリスト教布教という、ヨーロッパの「初期帝国主義」の発展の賜物で、こうしたヨーロッパ人たちの未知の世界に乗り出した集団が持ち帰った「香辛料」が、ヨーロッパの「食文化」に革命的な異変を起こしてその歴史をも変えたのでした。 鎖国による国際社会と遮断していた為に300年の月日を経て日本にこの香辛料をベースにした「カレー粉」が明治時代初期に日本にもたらされたのです。次回は「カレー・ライス」の起源となったインドのカレー・料理と比較しながら日本独特のカレー・ライスの楽しみを、私のカレー・ライス・レシピを交えて書こうと思っています。あ、それから美帆さん、これを読んでくれていますか? あなたのレシピも知りたいですね。
2007年11月01日
コメント(4)
全26件 (26件中 1-26件目)
1
-
-

- プログレッシヴ・ロック
- Yes【イエス】ロンリーハート~ビッ…
- (2025-11-25 21:23:42)
-
-
-

- LIVEに行って来ました♪
- サーカスパフォーマーまおのライブ
- (2025-11-23 13:17:54)
-
-
-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 【輸入盤】ミニ・アルバム:ラッシュ…
- (2025-11-25 00:00:11)
-







