2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年06月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
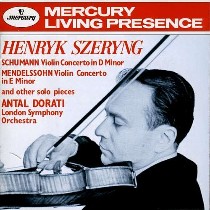
シューマン ヴァイオリン協奏曲/紅葉葵(もみじあおい)
『今日のクラシック音楽』 シューマン作曲 ヴァイオリン協奏曲 ニ短調ロベルト・シューマン(1810-1856)が書き残したヴァイオリン協奏曲は1曲で、しかも数多くのエピソードが残されています。作曲時期は1853年9月20日~10月1日という短い期間に書かれています。この1853年はすでにシューマンに精神の破綻が現われていた時期と言われています。この曲を書き終わって半年後に精神錯乱を起こしています。シューマンは当時デュッセルドルフの音楽監督で指揮活動も行なっていましたので、当時まだ若手ではありましたがヴァイオリンの名手ヨーゼフ・ヨアヒムに初演を依頼して、シューマン自身の指揮で初演を願っていたのでしょう、スコアをヨアヒムに送っています。しかし、ヨアヒムはこの曲を初演するどころかそのまま楽譜を握っていて、公開することもなかったのです。これはシューマンの妻クララ・シューマンが演奏されることを拒んでいたという説もありますが、ヨアヒム自身がこの曲に対して弾きたいという想いに至らなかったのでしょう。しかも、この楽譜はヨアヒムの遺品と共に84年間も眠り続けていたのです。ヨアヒムは自分の遺書にも、この曲はシューマン没100年後に上演を許可するという指定まで書いていたのです。 1937年にこの楽譜が発見されているそうです。そうして、ヴァイオリン奏者のユーディ・メニューイン、ゲオルグ・クーレンカンプ、イギリスのハンガリー系女性奏者イェリー・ダラーニ(ヨアヒムの縁筋にあたるそうです)の3人が初演を申し出たのですが(1937年)、当時のドイツ・ナチ政府は自国の音楽を国外で初演することを禁じていましたので、結局1937年11月26日にカール・ベーム指揮ベルリンフィル、ヴァイオリンがクーレンカンプで初演されています。ちなみにメニューインとダラーニはベルリンでの初演後の1938年にそれぞれアメリカとイギリスで初演しています。この曲を聴いていますとヨアヒムが封印したという、クララが初演することを拒んだという説は何となく理解できます。第1楽章では、始まりからただならぬ空気の支配する重厚な響きのオーケストラから主題提示が始まり、これこそロマン派の書いた美しい、高貴に満ちた旋律が精神の高揚を促すかのように聴く人を圧倒するかの如きで、つづく独奏ヴァイオリンの気品あふれる、高貴な歌謡性が歌われるのですが、私にはこの曲はこの第1楽章までは聴き惚れますが、続く2つの楽章はなんだか極上のソースを使っているのに、牛肉の質、焼き方の問題で味気ないフランス料理のステーキを食べさせられた感のある曲・音楽になっています。ですからこの曲を聴く時は第1楽章のみと限定しています。当然、こういう私の感じ方に異論を挟む方もおられると思いますが、私にはどうしてもそういう感じにしか受け取れない曲で、ヨアヒムがクララが上演を拒んだという理由が何となくわかります。すでに精神的に破滅の道を歩んでいたシューマンのこの曲には、そういう「病い」のようなものが現われているのかもしれません。事実この曲を完成した後すぐ1853年10月のデュッセルドルフ市の演奏会を最後に、シューマンはこの市のオーケストラの指揮を解任されています。しかし、第1楽章の高貴な精神性は実に見事なもので、好きな協奏曲の一つです。愛聴盤 ヘンリク・シェリング(Vn)、アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団(マーキュリー原盤 フィリップス PHCP-10211 1964年7月ロンドン録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1874年 誕生 ガブリエル・ピエルネ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 紅葉葵撮影地 大阪府和泉市 葵科 フヨウ(ハイビスカス)属 開花時期は7月中旬~8月中旬。 鮮やかな赤い、夏らしい花です。葉っぱはムクゲや芙蓉、ハイビスカスと異なっていて、その基部がひっついた状態で3つもしくは5つに裂けたような形をしています。
2007年06月30日
コメント(4)
-
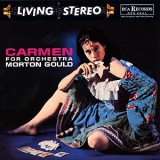
ビゼー 「カルメン」組曲/ノカンゾウ
『今日のクラシック音楽』 オペラ「カルメン」(オーケストラ版)今日はいやな梅雨日和を払拭してくれる音楽を聴きたいと思い、ビゼーの「カルメン」組曲を選びました。最近では珍しく朝寝をした日曜日でした。 ビゼー作曲のオペラ「カルメン」! でもこのCDは歌手がいないのです。 そう歌手の歌う「アリア」もすべてオーケストラだけで演奏された録音盤です。アメリカの偉大な音楽家の一人、モートン・グールド(1913-1996)が有名な「カルメン」組曲でなくて、「アリア」を自分で編曲して自分の作ったオーケストラで演奏している盤です。オリジナルの「カルメン」は第1、第2組曲となっていますが、グールドはそこへ歌手が歌う「アリア」も含めて編曲しています。 合唱もそれと同じです。 全曲を舞台で完全版で演奏すれば3時間近くかかるこの人気オペラのエッセンスを約45分間に圧縮して、このオペラの旋律・和声・リズムの素晴らしさを際立たせています。 オペラでの管弦楽部分にはほとんど手を入れず、歌手や合唱部分のみを新たに楽器を加えて演奏しているのですが、これを聴くと、なるほどこのオペラは確かに世界中の歌劇場で今でも上演されるだけのことはあるな、と改めて感じさせられます。カルメンの歌う「ハバネラ」は、女性歌手とは違ったコケティッシュな雰囲気と情緒が彩り豊かに奏でられ、カルメンに恋するドン・ホセの「花の歌」がテノールのオリジナルよりも、切実にオーケストラで響いており、「セギディーリャ」や「ジプシーの踊り」ではオーケストラの色彩豊かな響きが聴く者の心を煽ってきたり、エスカミリオの「闘牛士の歌」が金管の太い響きで鳴らされて、闘牛への興奮をかきたたせてくれます。そういう意味では、まさにオペラのエッセンスを味わう45分間です。グールドが編曲した音楽は、ビゼーの書いたこのオペラでの旋律・和声・リズムが、他のオペラと比べて出色の音楽であることを再認識させられます。 日曜日の午後にでも気楽に音楽を楽しもうという人には、ぴったりのオペラ音楽です。曲目は下記のとおりです。1.前奏曲 2.プロローグ 3.街の子供たち 4.タバコ工場の女たち 5.ハバネラ 6.母の便りを聞かせて 7.セギディーリヤ 8.第2幕への間奏曲 9.ジプシーの踊り 10.闘牛士の歌 11.タンプリンの歌 12.花の歌 13.第3幕への間奏曲 14.蜜入者の行進 15.カルメンのアリア(占いの場) 16.ミカエラのアリア 17.第4幕への前奏曲 18.行進曲と合唱 19.ドン・ホセとカルメンの二重唱 20.フィナーレこの盤です。 モートン・グールドと彼のオーケストラ↓ (RCA原盤 BMGジャパン BVCC37182 1960年録音)モートン・グールドはRCAレーベルで活躍したセミ・クラシックの王様と呼ばれた作曲家、指揮者、ピアニスト、編曲者で、現代のアンドレ・プレヴィンのような存在でした。 グールドとアーサー・フィードラーが軽妙にクラシック音楽を演奏した盤がRCAからリリースされていた頃は、私が中学・高校のころで、RCAにコープランドやグローフェのアメリカ音楽を録音したり、ウインナ・ワルツなどクラシック音楽の演奏会アンコール・ピースのような管弦楽小曲なども人気の高いLP盤でした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1903年 没 滝 廉太郎(作曲家)1908年 誕生 ルロイ・アンダーソン(作曲家)1914年 誕生 ラファエル・クーベリック(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ノカンゾウ撮影地 大阪府和泉市ゆり科 ワスレグサ属 (ヘメロカリス属) 6~8月頃、オレンジ色の赤っぽい花が咲きます。
2007年06月29日
コメント(12)
-

バックハウス/朝顔
『今日のクラシック音楽』 ヴィルヘルム・バックハウス(ピアニスト)私がクラシック音楽に親しんだ48年前から指揮者のトスカニーニやフルトヴェングラーと同じように名前だけ聞いていた演奏家にピアニストのヴィルヘルム・バックハウスがいました。 とにかく凄いピアニストということだけを知っていた頃です。そのバックハウスの録音したLP盤を買って、初めて彼の演奏を聴いたのが1962年で高校2年生でした。 DECCAへの録音でLONDONレーベルとしてリリースされていて、それが再発売のモノラル25cmLP盤でした。 曲はベートーベンの「熱情ソナタ」と「月光ソナタ」でした。当時の印象はピアノという楽器はこんなにも多彩な音色を奏でるものなのか、ベートーベンのピアノソナタってこんなに激しい音楽なんだ(熱情)というくらいでした。当時は管弦楽で演奏する交響曲やオーケストラ音楽、それにイタリア歌劇団の公演による刺激(モナコ、テバルディ)によるオペラなどを聴きまくっていた頃で、ヴァイオリンやピアノ曲、室内楽などは数えるほどしか聴いていなかったように思います。そのうちに色々な音楽を積極的に聴くようになり、ピアノ音楽にも交響曲やオペラと同じように興味と共感を抱くようになってきました。それが1967-68年という頃で、一番真摯に音楽を聴いていた時代かなと思います。そしてバックハウスとの再会がありました。 ベートーベン、ブラームスの協奏曲やソナタを聴きながら、何となく他のピアニスト(例えばルービンシュタインやホロビッツ)と違う人だと感じるようになり、しっかりと聴き込み始めました。バックハウスが録音で採り上げた曲は、ベートーベンやブラームス、シューマンやシューベルト、それに古典派のモーツアルトが多く、謂わばドイツ音楽の主流のような作曲家、曲を演奏していました。一言でバックハウスを形容するならば「武骨」という言葉を連想します。 おそらく完璧な技巧に裏打ちされた素朴な感じで、曲にストレートに迫るタイプの演奏家であったように思います。 曲の精神性を厳しいという表現がぴったりの男性的な音楽を創るピアニストだと思います。しかし、こういうことはずーとあとになって、やっと理解できるようになりました。 しかし、そのときはバックハウスはもう天に召されたあとでした。 幸いにも彼は数多くの録音をDECCAに残してくれています。 今はベームやイッセルシュテット、シューリヒトなどの指揮者との共演も残されており、ベートーベンのソナタ全集や大バッハの曲も録音されています。 それらを聴くたびに、彼は基本をしっかりと身につけた、大きなピアノ音楽を演奏するピアニストであったのかと、今更ながらに感動させられています。愛聴盤 「バックハウス 最後の演奏会」 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCD9185 1969年6月26日、28日録音)「最後の演奏会」全記録CD1(1969年6月26日の演奏会)ベートーヴェン1.ピアノ・ソナタ第21番ハ長調作品53《ワルトシュタイン》シューベルト2.楽興の時D.780(作品94)モーツァルト3.ピアノ・ソナタ第11番イ長調K.331《トルコ行進曲付き》シューベルト4.即興曲変イ長調D.935の2(作品142の2)CD2(1969年6月28日の演奏会)ベートーヴェン5.ピアノ・ソナタ第18番変ホ長調作品31の3から(第4楽章を除く)シューマン6.幻想小曲集作品12から 第1曲《夕べに》/第3曲《なぜに?》シューベルト7.即興曲変イ長調D.935の2(作品142の2)この録音はオーストリア高地のオシアッハ湖畔の教会で行われた1969年6月26日と28日の2日間の演奏会の全記録です。 85歳の高齢となったバックハウスのこのときの演奏にはミス・タッチがみられるところもあり、またDECCAにしては貧弱な録音ですが、温かさと音楽の豊かさが伝わってくる演奏です。 若い頃のもっと素晴らしい演奏・録音盤がありますが、バックハウスはこの2日間のコンサートを終えてわずか1週間後にこの世を去っています。まさにバックハウスの「白鳥の歌」となったこの盤を敢えて掲載致します。 2枚組で2,000円です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 雨と朝顔撮影地 大阪府和泉市 昼顔科 サツマイモ属 開花時期 7月初め~10月初め頃 中国原産で平安時代に日本に渡来したそうです。 朝開花して午前中はきれいに咲いています。 夏から秋まで長い間咲き続けています。 最近店などで売られている鉢植えは、「行灯づくり」(竹やプラスチック製の輪がついた支柱につるをからませて花を咲かせる方法)が多いようです。 「朝顔」とは 「朝の美女」の意味だそうです。
2007年06月28日
コメント(4)
-
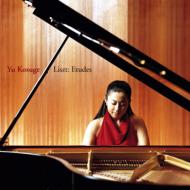
リスト 超絶技巧練習曲/水カンナ
『今日のクラシック音楽』 リスト作曲 「超絶技巧練習曲」フランツ・リスト(1811-1886)はその生涯で約600曲のピアノ音楽を書き残したと言われています。彼自身が非常にピアノ演奏が巧く、演奏会でもヨーロッパ各地を巡ってその卓越した技巧を披露していました。リストは自作のピアノ音楽にとどまらず、大作曲家が発表した作品の編曲も行なっています。例えばベートーベンの9曲の交響曲を演奏会で弾けるようにピアノ版への編曲を行なっています。こういう楽器演奏に長じた技巧の持ち主は自己の演奏技巧を披露するために演奏する上で非常に難しい曲を書くようになるんですね。 その例としてパガニーニやサラサーテ、現代ではクライスラーなどのヴァイオリンが挙げられます。リストもそうした技巧派演奏家の常として、ピアノ音楽として発表したのがこの「超絶技巧練習曲」(全12曲)です。この曲の下地はすでに15歳の時に始まっていたそうです。つまり1826年、リスト15歳で12曲の練習曲を書いており、その後1837年、26歳の時にそれら12曲を書き直しているそうです。最終的に完成して出版されたのが1851年、リスト40歳の時ですから、15年間もの間この曲は推敲に推敲を重ねてきて完成された曲ということになります。その15年間で作曲の技法などの技術向上もあり、何度も書き直しをしていたのでしょう。またこの15年間で彼自身の生活環境も変わっていった事実も、曲への影響もあるかもしれません。彼自身、コンサート・ピアニストとしてのヨーロッパ各地への演奏会ツアーの生活の傍ら、ピアノ曲の作曲をおこなっていたのが、ドイツ・ワイマールに定住してワイマール宮廷楽団長として迎えられ、オーケストラ作品などの作曲が落ち着いた環境で出来るようになったという、生活環境の変化も影響して、この12曲のピアノ曲をじっくりと書き直していったのかも知れません。曲の名前の通り、非常に高度な技巧が要求されるピアノ曲ですが、目も覚めるような素晴らしいピアノ演奏技巧の楽しめる曲です。第1番 「前奏曲」華麗で技巧的な曲です第2番 イ短調 スタッカートの目立つ奇想曲風な音楽です第3番 「風景」 牧歌的な、詩情豊かな音楽です第4番 「マゼッパ」 彼の交響詩「マゼッパ」主題による変奏曲第5番 「鬼火」 何やら空想的な趣のある超絶技巧の難曲です。第6番 「幻影」 段々と華やかさ、テンポが速くなっていく曲です。第7番 「英雄」 行進曲のような曲想の音楽です。第8番 「狩」 荒々しさや不気味さが混じった音楽です。第9番 「回想」 メランコリックな楽想です。第10番 ヘ短調 2つの主題によって劇的に進行していきます。第11番 「夕べの調べ」 抒情的な、美しい曲で、教会の鐘の音を表現しています。第12番 「雪嵐」 幻想的な吹雪の様子を描いた音楽です。愛聴盤 小菅 優(ピアノ)(SONY CLASSICAL CD87315 2002年8月録音 輸入盤)(追記)長い間ラザール・ベルマンのピアノ演奏でこの曲を聴いていましたが、わずか20歳でドイツ・ソニーと契約してデビュー録音がこの「超絶技巧練習曲」とは。小菅 優はピアノを豊かに鳴らし、とてもスケールの大きな音楽を紡ぎ出しています。豊穣で流麗なメロディー、弱音から強靭な音まで崩れることなく多彩な音色で、この難曲を弾きこなしているのに驚きます。 素晴らしい、今年25歳の逸材でこれからの録音が楽しみです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1870年 初演 ワーグナー 楽劇「ワルキューレ」1933年 誕生 クラウディオ・アバド(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 水カンナ水中に植わっている花でなかなかお目にかかれない花の一つです。 この画像は蓮の大きな葉に花びらを落としながら散っていこうとする花です。 撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2006年6月30日くずうこん科 タリア属 水中に生えており、夏になると紫色の花が咲きます。 ほとんど見かけることのない花です。 葉がカンナに似ているところから命名されているようです。
2007年06月26日
コメント(12)
-

ブリッジ ピアノ曲集
『今日のクラシック音楽』 ブリッジ作曲 ピアノ曲集イギリスの作曲家フランク・ブリッジ(1879-1941)は、ベンジャミン・ブリテン(1913-1976)に音楽理論と作曲を教えた人として知られています。 ブリッジ自身は小規模のオーケストラ曲や室内楽作品を書き残しています。 彼の音楽は哀愁に溢れた作品が多く、心の内面を写すかのような音楽が特徴です。しかし、今日採り上げましたピアノ曲集はとても多面的なものを表現しています。 ラヴェルのピアノ音楽のようなガラスのような硬質性と、ドビッシーの印象派風の作品もあれば、フランス・サロン風の趣きのある作品も聴かれます。キラキラと輝くような粒立ちの音で始まる「おとぎ話」組曲の「お姫様」が、このディスクの第1曲なのですが、親しみのある、平明な美しい旋律が聴き手を彼のピアノ音楽の世界に引きずり込むような魅力を持ったピアノ音楽、この第1曲で私は完全に彼の世界に誘い込まれました。「秋に」という2曲の風景ではロマンティックな情緒がたっぷりと盛り込まれていて、ブリッジ特有の哀愁を帯びた旋律が聴く者を酔わせてくれます。「田園的小曲集」では、のびやかな幻想的な旋律がイギリスのなだらかな丘陵を想い起こさせてくれました。 かつて訪れたことのあるイギリスの丘陵を吹き渡る風が私の部屋にまで届くような、そんな感じで聴いていました。全般に親しみやすい、美しくロマンティックで、印象派風のパステル画の色彩といった曲もある、ピアノ音楽が好きな方には「必聴」としてお薦めしたい、Naxosレーベル今月リリースされたばかりの新譜ディスクです。ブルックナーやマーラーの長大・重厚な曲やオペラなどを聴いたあとに、聴きますといっそう心和やかにさせてくれる音楽ばかりです。第1集とタイトルされていますから、第2集もリリースされるのでしょうね。 今からそれが楽しみです。このCDです。 ブリッジ ピアノ曲集 第1集 アシュレー・ウェイス(ピアノ)↓(Naxosレーベル 8.557842 2005年4月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1824年 誕生 カール・ライネッケ(作曲家)1892年 誕生 ミエチスラフ・ホルショフスキー(ピアニスト)1926年 初演 ヴェーヴェルン 「管弦楽のための5つの小品」1943年 誕生 ジェイムズ・レヴァイン(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 花蓮今日23日から大阪市立長居植物園では早朝開園を行います。 花蓮の開花に合わせて朝7時30分からの開園です。 花蓮は早朝に花を開くので開花に合わせて開園という恒例の行事です。私も体調が良ければ撮影に行こうかと思っています。 この画像は2年前に長居植物園で撮影したもので、すでにこのブログに掲載しております。 撮影地 大阪市立長居植物園 2005年6月30日
2007年06月23日
コメント(16)
-
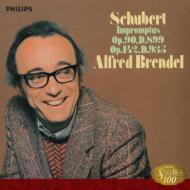
シューベルト 「即興曲」/露草
『今日のクラシック音楽』 シューベルト作曲 「即興曲集」フランツ・シューベルト(1797-1828)はその生涯に1200曲以上にものぼる作品を書いているそうです。 それらの中でも歌曲は600曲を超すと言われていますから、まさに「歌曲王」と呼ぶにふさわしい作曲家でした。 しかも彼は31歳という若さで亡くなっています。 シューベルトの作曲家としての実動期間は15年間と言われていますから、1200曲もの作品を書いたという多作ぶりに驚きます。9曲の交響曲、15曲の弦楽四重奏曲、20曲以上のピアノ・ソナタ、それに「三大歌曲集」と呼ばれている「美しき水車小屋の娘」「冬の旅」「白鳥の歌」などの歌曲をはじめ、実に多彩な作品を書き残しています。シューベルトの音楽は「叙情性」という言葉がぴったりな作品ばかりです。 まるで泉がこんこんと湧き出るかのように音楽が生まれてきたのでしょう。そうした作品の中でもピアノ音樂は、シューベルトを語る上でとても大切なジャンルです。 私はピアノ・ソナタ全てを聴いていませんが、ソナタに限って言えばあまり好きな作品がありません。 最後の3大ソナタや第18番「幻想」くらいでしょうか、シューベルトらしい音楽性が見事に表現されているのは。シューベルトは100曲以上のピアノ曲を書いているそうですが、それらの作品の中でも特に私が好きなのは2集にまたがる「即興曲集」・それに「楽興の時」です。シューベルトの「即興曲集」は作品90と作品142の二つを指していて、ともに短い4曲ずつの音楽が書かれています。しかし、この2つの作品を全曲演奏すれば1時間ほどはかかります。彼が世を去る1年前の1827年に書かれています。即興曲とは、作曲家があまり形式にとらわれないで自由にインスピレーションを羽ばたかせて、奔放に書いている作品です。シューベルトのこの作品もそういう感じで書かれていて、自由に空想の空間をさまよい歩くシューベルトの心情がどの曲にも如実に表れています。まさに泉が限りなく湧き出るような、叙情性豊かな音楽が流れています。「即興曲」という名前は作品90の第1集は楽譜出版社が名づけており、第2集はシューベルト自身が付けているそうです。愛聴盤(1) アルフレート・ブレンデル(ピアノ)(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7042 1972年録音)現在は1000円で発売されています。(2) 内田光子(ピアノ)(Philips レーベル 456245 1996年9月録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1910年 誕生 ピーター・ピアーズ(テノール)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 露草もう道端で見かけるようになりました。 小さな可愛い花ですが、もっと紫色の濃い花なのですが、この被写体は少し薄いようです。撮影地 大阪府和泉市
2007年06月22日
コメント(12)
-

R.シュトラウス 「死と変容」/のうぜんかづら
『今日のクラシック音楽』 R.シュトラウス作曲 交響詩「死と変容」リヒャルト・シュトラウス(1864-1949)は後期ドイツ・ロマン派の最後の作曲家と呼ばれています。 彼の音楽は、特にオーケストレーションにおいて、豊穣な響き、官能的とも言える旋律のふくらみ、管楽器と弦楽器の程よいバランス、艶やかな響きなどが特徴です。彼は交響詩作曲家ととして「ドン・ファン」以来次々と交響詩を書いています。 その題材は文学からインスピレーションを得たのが多いのです。 「ツァラトゥストラ・・・」「マクベス」「ドン・ファン」などがその例です。 またドイツの伝説や民話を題材にしているのもあります。 「ティル・オイレンシュピーゲル・・・・」がその例です。 こうした具体的な題材を基にして、それを豊穣な音楽に表現することに集中していたのでしょう。 彼は第二次世界大戦をはさんで85歳までの長寿を全うしていますが、彼の重要な作曲ジャンルである交響詩の世界とは39歳で筆を折っています。 自分の歩いた道を音楽で表した交響詩「英雄の生涯」が最後の交響詩となっています。 1888年の「ドン・ファン」に始まり、1898年 の「英雄の生涯」までわずか11年間が彼の交響詩の世界となってしまったのです。それ以降シュトラウスはオペラの世界に踏み入って、より具体的に歌によって文学的世界を表現していきました。 「ばらの騎士」「サロメ」「アラベラ」「影のない女」など素晴らしいオペラを生み出していったのです。さて今日の話題曲、交響詩「死と変容」は「ドン・ファン」「マクベス」に続く第3作目の作品です。この交響詩の内容は、彼の友人リッターの詩を題材にしています。 ただ音楽の方が先だったという通説になっています。 それをシュトラウスはスコアに貼り付けたのでした。 だから私はシュトラウスが自らの詩想で書いた最初の交響詩がこの「死と変容」だと思って聴いています。シュトラウスは生来丈夫な体でなくて脆弱で、この曲の作曲の前にも何度も床についています。 リッターの詩は「部屋に重病人が横たわっている。 彼の死の直前に、子供の頃の楽しい思い出にふけっているが、それは長続きせずに間もなく死の鉄鎚が振り下ろされて命を閉じる。 しかし、魂だけは憧れていた天上に救われる」という内容です。 音楽はまるでこの詩を予言するかのような内容になっているのが不思議です。音楽は、ソナタ形式を踏まえて書かれています。 序奏から始まり、ものうげなリズムが支える中、弱奏で「死の動機」が演奏されます。 やがてオーボエが優美な旋律を奏でます。 まるで少年時代を思い出しているかのようです。 そして音楽は暗く沈んだようになっていきます。突然ティンパニーの強打によって音楽は主部に入ります。 「死の動機」と「生の動機」が対照的に現れます。 そこへ管楽器で「愛の動機」がからんできて第1主題を形成します。第2主題部は、少年時代を回想するかのようにフルートでの「回想の動機」、それに木管とハープによる「青年時代の動機」が中心になって展開していきます。展開部ではこれまでの動機が出てきて、展開していきます。 そして「変容の動機」も現れます。再現部では、この曲冒頭のリズムがティパニーによって刻まれて、「生の動機」「愛の動機」「死の動機」などが流れていきます。 そして天上から陽が射しこむかのように、ホルンと木管によって荘厳に「変容の動機」が奏されて、コーダへと流れていきます。そして明快に「変容の動機」が姿を現して、やがてタムタムの弱音で病人が天上へと召されたことを示しながら、静かに曲を閉じていきます。シュトラウスの豊穣なる響き、艶やかな響き、ふっくらとした魅力的で美しい旋律。 シュトラウス音楽の美しさに溢れた名作です。 演奏時間約25分の、シュトラウス自身の病床での体験による音楽と言われています。1890年の今日(6月21日)、この「死と変容」がシュトラウス自身の指揮で初演されています。愛聴盤(1) ルドルフ・ケンぺ指揮 シュターツカペレ・ドレスデン(EMI原盤 東芝EMI TOCE13467 1972年録音)深い響きでシュトラウスの音楽を克明に刻んだ、ドレスデンの響きが絶品の味を伝える名盤。「ドン・ファン」「ティル・・・・」「ツァラトゥストラ・・・」とのカップリング。価格も廉価となっています(1300円)。(2) アンドレ・プレヴィン指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団(テラーク原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCT4014 1987年11月録音)プレヴィンとウイーンフィルが織りなす、しなやかな弦楽器、ホルンなどのブレンドの良さを伝えるシュトラウスの世界に酔える演奏。 「ツァトゥストラ・・・」とのカップリング。 録音はすこぶる付きの優秀録音。この演奏、優秀録音盤が1500円です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1868年 初演 R.ワーグナー オペラ「ニュールンベルグの名歌手」1890年 初演 R.シュトラウス 交響詩「死と変容」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 ノウゼンカヅラ初夏を彩る花の一つです。撮影地 大阪府和泉市のうぜんかずら科 ノウゼンカズラ属 開花時期 6月~9月中国原産 日本には平安時代の9世紀頃に渡ってきたそうです。 オレンジ色の派手な色の花で、つるがどんどん伸びていきます。
2007年06月21日
コメント(7)
-
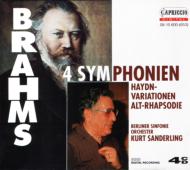
ブラームス 交響曲第2番/悪茄子(ワルナスビ)
『今日のクラシック音楽』 ブラームス 作曲 交響曲第2番ニ長調 作品73ヨハネス・ブラームス(1883-1897)が最初の交響曲第1番の作曲に20年という歳月をかけて書いていたことは有名な話です。 ベートーベンの交響曲が壁になtっており、それらを超越する作品を書くためにこれだけの年月を費やしたと言われています。 古典的形式美とロマンの香りを漂わせる畢生の名曲として完成、現代では指揮者、オーケストラの重要なレパートリーとなっています。 また録音では夥しい数のディスクが発売されています。その第1番のあとに書かれた交響曲第2番は約4か月で完成しています。 おそらく大好評だった第1番で交響曲作曲家として絶大な自信を得た結果であろうと推測されます。 あるいは20年の間に交響曲作曲のとしてのノウハウを得ていたのかも知れません。 ブラームスとしては早書きとして特筆すべきことだと思います。この交響曲第2番は2つの地で書かれています。 1877年の夏、南オーストリアの避暑地ベルハッチャで書きだされています。 ベルハッチャは写真で観ると南オーストリアの山々に囲まれたヴェルター湖畔にある美しい、風光明媚な避暑地です。 ブラームスの友人宛に送った手紙に書かれたベルハッチャの美しさに心を奪われたことが書かれているそうです。 そして二度にわたり夏にはここで過ごすブラームスは、よほどこの地を好んでいたのでしょう。曲はドイツのバーデン・バーデン近郊のリヒテンタールで9月から10月にかけて完成しており、初演は1877年12月30日にハンス・リヒター指揮 ウイーンフィルハーモニーによって行われています。 この初演は大成功だったそうです。 第3楽章が終わると熱狂した聴衆がアンコールを要求して再度演奏されてから終楽章へと移ったという有名なエピソードが残されています。ブラームスは、作曲時の風景や環境・雰囲気を作品に反映させる作曲家であったと言われていますが、この第2番もブラームス好みの風光明媚で明るいペルハッチャで作曲が大いに影響しているのでしょう。 第1番の劇性の強い曲とは対照的な作品に仕上がっています。 別名「ブラームスの田園」と呼ばれることもあるこの曲は、とてものどかで、柔和で温和、人間的な深みを増しており、喜びにあふれています。 しかしこの音楽を聴いて何を空想するかは聴き手に委ねられますが、この作品は表題音楽ではなくて、やはり絶対音楽として書かれています。 第1番のような規模の大きさでもなく、暗から明への解放、苦悩から歓喜へという推移もみられないし、調性も短調ではなく全楽章が長調で書かれています。 木管をふくらみのある音にしてみたり、トロンボーンやテューバを弱く吹かせたり、柔らかい音色を出すことに苦心しています。終楽章のコーダは、まさに喜びの爆発とでも言えそうな音楽で閉じています。古典的形式美という造形を踏まえながら、音楽はロマンの香りをまき散らしたような美しい交響曲です。愛聴盤 (1) クルト・ザンテルリンク指揮 ベルリン交響楽団(カプリッチオ・レーベル 10600 1990年録音 海外盤)DENON盤よりテンポが遅いのですがまったく弛緩することなく重厚に、精緻に描いたブラームスの世界。 今のところ一番好きな演奏です。 4枚組全集です。(2) クルト・ザンテルリンク指揮 シュターツカペレ・ドレスデン (DENON CREST1000 COCO70491 1972年録音)最も普遍的なドイツ的演奏。 この曲のスタンダードとも呼べそうなディスク。これからこの曲を聴こうとする方には、この盤がお薦めです。 価格も1000円です。ブラームス好きな私は上記2つのディスクにとどまらず下記の盤でも楽しんでいます。 朝比奈 隆指揮 新日本フィルハーモニー (2000年ライブ)カール・ベーム指揮 ウイーンフィル (1977年東京ライブ)オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団バーンスタイン指揮 ウイーンフィルハーモージュリーニ指揮 ロス・アンジェルスフィルハーモニーヨゼフ・カイルベルト指揮 バイエルン放送交響楽団サー・エドリアン・ボールト指揮 ロンドンフィルハーモニーオットマール・スイトナー指揮 ベルリン国立歌劇場管弦楽団オイゲン・ヨッフム指揮 ウイーンフィルハーモニー (1981年9月20日ウイーンライブ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 悪茄子(わるなすび) 撮影地 大阪市立長居植物園なす科 ナス属 開花時期 6月~8月 ナスの花に似た白やピンクの花が咲きます。 茎と葉にとげがあり始末が悪く繁殖力があり強いので”悪”と名づけられているそうです。雑草には「鬼」とか「悪」という名前がおおいですね。 可愛いのかわいそうですね。
2007年06月20日
コメント(10)
-
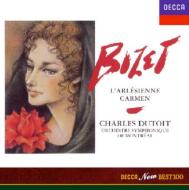
ビゼー 組曲「アルルの女」/西洋ノコギリソウ
『今日のクラシック音楽』 ビゼー作曲 組曲「アルルの女」フランスの作家にアルフォンス・ドーデ(1840-1897)という文豪がいました。 最も有名なのが「風車小屋だより」という短編小説集です。 フランスのアルル地方とその周辺を舞台にした短編小説集です。 学生時代に二度読んだ経験があります(その後は読んでいません)。 その短編集の短い物語の中から作者自身が選んで書いた戯曲があります。 それが「アルルの女」です。 選んだ短編を自ら脚色して戯曲として書きあげています。 この戯曲を読んだことはありませんが、3幕4場の舞台で構成された演劇だそうです。 変わっているのは題名が「アルルの女」なのに舞台に表れないし、その女の名前も出てこないという劇だそうです。アルルの旧家の長男が、アルルの町の闘牛場で一人の女と知り合って激しい恋に落ちて、彼女と結婚できなければ死ぬとまで言いきって両親の承諾を得ます。 ところがその女には情夫がいることがわかり、やむなく結婚を諦めて幼馴染と結婚することになるのですが、町の祭日にその女が情夫と駆け落ちすることを知り、彼は嫉妬に狂ってしまい飛び降り自殺を図って命を絶つという物語だそうです。その戯曲の音楽を委嘱されたのがビゼー(1838-1875)でした。 ビゼー34歳の1874年でした。 そして完成させたのが混声合唱を含めた全27曲の音楽です。 戯曲の上演は失敗だったと伝えられています。 以降何回か上演されましたが、あまりに暗い結末が原因で戯曲の上演は打ち切られたそうです。ビゼーはこの劇付随音楽に自信を持っていたのか、全27曲から4曲を選んで演奏会用組曲として発表しています。 それが「アルルの女」第1組曲です。「前奏曲」、「メヌエット」、「アダージェット」、「カリヨン(鐘)」の4曲から構成されており、南欧情緒満点の美しい音楽に充ち溢れた管弦楽作品となっています。 ビゼーの死後親友ギローが新たに全曲から4曲を選んで別の組曲を作り上げています。 それが第2組曲となっており、特にフルート独奏が美しい「メヌエット」は単独でも演奏される素晴らしい曲となっています。クラシック音楽に親しみ始めたころは、この組曲「アルルの女」が大好きで毎日のように聴いていました。 そしていつかはフランス・プロヴァンス地方へ行ってみたいと夢を見続けていました。 在職中は何度もヨーロッパへ行きましたが、とうとうこのプロヴァンスへは足を延ばすことができなかったのが残念です。 いつかは訪れたい場所です。愛聴盤(1) シャルル・デュトワ指揮 モントリオール交響楽団 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD5030 1986年10月録音)少し速めのテンポでくっきりと各曲を丁寧に浮き上がらせていく演奏で、非常に表情豊かで、「間奏曲」「メヌエット」などの牧歌的な表情も情感豊かに仕上げています。(2) チョン・ミュン=フン指揮 パリ・バスティーユ・オペラ座管弦楽団 (グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG5020 1991年録音)デュトワとは対照的な情熱のこもった熱い演奏で、ラテンの血をたぎらすような熱演となっています。両盤とも「カルメン」組曲とのカップリングです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1863年 初演 J.シュトラウス ワルツ「ウイーンの森の物語」1899年 初演 エルガー 「エニグマ変奏曲」1915年 没 セルゲイ・タニェエフ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 西洋ノコギリソウ 撮影地 大阪府和泉市菊科 ノコギリソウ属 葉が櫛の歯状にまるで鋸のようにギザギザに切れ込んでいるところから命名されています。白かピンク色の花が咲きます。
2007年06月19日
コメント(8)
-
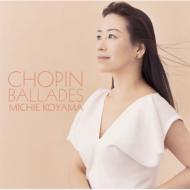
小山実稚恵「バラード」/ハイビスカス(黄色)
『今日のクラシック音楽』 小山実稚恵が弾くショパンの「バラード」今日はオペラ「魔弾の射手」ともう一つ紹介しておきます。 小山実稚恵が弾くショパンの「バラード」。「バラード」とは、もとは「舞踊歌」のことで、18世紀ごろに叙事詩のような性格をもった声楽曲となり、やがて器楽曲になっていったものでショパンがそれを芸術的に高めたものでした。バラードの意味からすると物語性があるような感じがするのですが、ショパンは標題音楽とせずに絶対音楽として書いているようです。 この作品を書いたのはポーランドの詩人ミツケヴィッチが書いた14編の「バラードとロマンス」の第1集を読んでインスピレーションを得たと言われていますが、聴く側はそういうエピソードにとらわれず自由に空想を楽しみ、音楽から生まれる空想に浸れば良いと思っています。 またエピソードにとらわれようにも、ミツケヴィッチの詩を探すのが大変です。 勿論、私も読んだことがありません。第2番では主要主題がポーランドの「伝承歌謡」から得た旋律と言われていますが、ミツケヴィッチにしろ「伝承歌謡」にしろ祖国ポーランドへの郷愁が書かせたのかなと思っています。ショパンは全4曲を書いています。 いずれもスケールの大きい曲ばかりで、音楽は実に自由な形式で書かれています。 そして大きな特徴は6拍子で書かれていることです。 第2番~第4番まではすべて8分の6拍子で書かれていて、第1番のみ4分の6拍子で書かれています(但し、序奏は4分の4拍子です)。これは「語る」ことに徹しているのだろうと思います。 ミツケヴィッチの詩から得たインスピレーションで書いた音楽を、「語り」として音楽で表そうとしたのかな、と想像しています。 音楽はまさにその通りで、全4曲ともいつくしみながらショパンが語っているかのように書き綴られています。 前述の祖国ポーランドへの郷愁が「マズルカ」を書かせています。 あの3拍子の音楽の延長線上にあるのが6拍子です。 そんな他愛もない屁理屈を付けて聴いています。もう一つの特徴は音楽がとても男性的に表現されていることです。 彼の「スケルツオ」もそうですが、他の彼のピアノ曲に比べてとても男性的な表現になっているのが特徴です。小山実稚恵のこの「バラード」は2005年10月に新譜としてリリースされたディスクで、ここに紹介するまでもなくいまや国際的ピアニストとして円熟の境地に入っている女性。 特に女性ファンが多いピアニストです。 ショパン・コンクール、チャイコフスキー・コンクールで入賞という快挙を成し遂げて以来、ショパンは小山実稚恵の代名詞のようでした。 その後ロシアン・アルバムなどレパートリーを広げていき、またショパンに戻っての録音。この4曲を実に深い音色で弾いています。 第1番からもう小山ワールドへ引き込まれてしまいます。 まさに「物語風」にしかもしっとりとした情緒で弾いています。 特に弱音の美しさは特筆すべき美しさにあふれています。 全4曲を聴いて「あ~、ショパンのバラードというのはこういう音楽だったのか」と改めてその美しさを再認識しました。 今まではプレトニョフのニューヨーク・ライブを聴いて、「もうこれでバラードは、他のディスクはいらない」と感じていたのに、今年になって衝動買いで手にした盤ですが、完全に打ちのめされた感があります。音は透明で、もちろん粒立ちの良さは抜群、ぺダリングの活用による絶妙なる音色。 そして「バラード」の空想を豊かに響かせる業は凄い! これからショパンのバラードを最新の優秀録音で聴きたい方に真っ先にお薦めのディスクです。(ソニークラシカル SICC10028 2005年3月ー4月録音)今日はウエーバーのオペラ「魔弾の射手」ともう1枚のハイビスカスを掲載しています。 そちらの方もどうぞご覧下さい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 ハイビスカス撮影地 大阪市立長居植物園
2007年06月18日
コメント(12)
-

オペラ「魔弾の射手」/ハイビスカス
『今日のクラシック音楽』 ウエーバー作曲 オペラ「魔弾の射手」日本ではほとんど上演される機会のないオペラ「魔弾の射手」は、カール・マリア・フォン・ウエーバー(1786-1826)が書き残したドイツの「ジンク・シュピーゲル(歌芝居)」を確立したオペラとして、音楽史上に燦然と輝いています。ウエーバーはベートーベン(1770-1827)から遅れること16年、この世に生を受けており、ベートーベンが亡くなる前年にわずか39歳という若さでこの世を去っています。 ウエーバーの活躍した時期がベートーベンの時代とほぼ同時期ということなります。「魔弾の射手」が書かれた頃は、モーツアルトやベートーベンによって切り開かれてきたドイツ国民オペラがイタリアオペラの人気によって低迷していた頃でした。ところでドイツやオーストリア、フランス、イタリアを訪ねると驚くことが一つあります。 それは小さな町にも市立オペラハウスがあって、そこでオペラの上演が盛んに行われており、有名なコンサート指揮者は必ずと言っていいほど、こういう小さなオペラハウスで研鑽を積んで檜舞台に上がることを繰り返してきています。この点、オペラファンでもある私にはとても羨ましい環境であり、ヨーロッパにおけるクラシック音楽の歴史の深さを思い知らされます。 日本では専門のオペラハウスは幾つあるでしょう。 大阪ではまだありません。話は横道にそれましたが、ウエーバーの時代はイタリア・オペラに席捲されていた時代で、ドイツ国民には自国の国民オペラが現れることを待ち望んでいたそうです。ウエーバーは作曲家でもあり、指揮者でもありました。 ドイツ屈指のオペラハウス「ドレスデン国立歌劇場」の指揮者として活躍しています。 彼の年譜を読むと1817年にドレスデンに着任しており、その後生涯最後の10年間をドレスデンで過ごしています。この「魔弾の射手」はドレスデンに着いてからすぐに書き始められたそうです。 そして3年の歳月を経て、1821年6月18日にこのオペラハウスで初演されています。物語はチェコのボヘミア地方(当時のドイツ領)に伝わる魔弾伝説を台本にして書かれています。狩人マックスは、恋人のアガーテと結ばれたいがために、悪魔に魂を売って命中率100%の弾を得ます。 そして射撃競技に出場するのですが、この魂を売ることをそそのかしたカスパールに命中して殺してしまいます。 マックスはそこで初めて己の非を後悔して、森に棲む隠者のとりなしで晴れてアガーテと結ばれるという筋書きです。この「魔弾の射手」は熱狂的にドイツ国民に迎えられたそうです。 それは上述のようにイタリア・オペラ一色であったドイツに待望のドイツ国民オペラが誕生したからです。 台本はドイツ語、芝居形式、音楽はドイツにつたわる民謡が多く使われており、まさに「ドイツ精神」に満ちたオペラだったからです。実際にこのオペラを聴いてみると、実にわかりやすい音楽、ドイツに根ざした旋律(民謡)などに彩られていて、しかも「歌芝居」の形式で台詞のやり取りが歌の合間にあり、心を昂揚させるような音楽に溢れたオペラです。序曲はコンサートプログラムを飾り、合唱曲の定番のような「狩人の合唱」に代表される親しみやすい音楽で書かれています。 このオペラは日本では極端に上演機会がありませんが、ヨーロッパでは数多くシーズンには上演されている、「ドイツ・オペラ」の遺産のようなオペラとなっています。この「魔弾の射手」によってドイツ国民オペラが確立され、続いてロンドンのコヴェントガーデン王立歌劇場から委嘱されたオペラ「オベロン」もロンドン初演で大成功を収めたのですが、持病の結核が悪化して、ウエーバーは1826年6月5日にロンドンで亡くなり、真の国民オペラの発展はリヒャルト・ワーグナーの出現による大規模な歌劇・楽劇まで待たなければならなかったのです。「もし」という仮定で考えれば、ウエーバーがもっと長生きをしてくれておれば、きっとドイツ・オペラの歴史は変わっていたことは間違いないと思います。1821年の今日(6月18日)、ウエーバーの指揮でベルリンで「魔弾の射手」が初演されています。愛聴盤 ヨゼフ・カイルベルト指揮 ベルリンフィルハーモニー・合唱団 ヘルマン・プライ(BR)、ルドルフ・ショック(T)、エリザベート・グリュンマー(S)他(EMI原盤 東芝EMI TOCE9125 1958年録音 旧TOCE6337/38の廉価再発売)LP時代から愛聴してきたカイルベルトの見事な演奏。 骨太で重厚、スケールの大きな表現はこの指揮者の真骨頂で真にドイツ的厚みのある演奏です。 それでいてロマンティックな表現が随所に聴かれる演奏です。 ステレオ録音とはいえ音質の悪いLP盤から、リマスターされたCDでは各段に音質が向上されていて、不滅の名盤として遺しておきたい演奏です。 グリュンマーのアガーテが素晴らしい美声を聴かせてくれます。ラファエル・クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団・合唱団 ヒルデガルデ・ベーレンス(S)、ルネ・コロ(T)、クルト・モル(Br)他カイルベルトの重厚さとは違いますが、クーベリック特有のしなやかさがあり、繊細に表現されたロマンティックな音楽が魅力の演奏です。 ルネ・コロ、ベーレンス、クルト・モルの歌唱は聴く者を酔わせる美声と表現で、これも素晴らしいドイツ・オペラを楽しめます。(DECCA原盤 LONDONレーベル ユニヴァーサル・ミュージック POCL3820/1 1979年録音)オペラ全曲を聴くのを躊躇う方にはウエーバーのオペラ序曲を1枚のCDに収めた素晴らしい演奏があります。 帝王カラヤンの「ウエーバー序曲集」で、「魔弾の射手」「オベロン」「オイリアンテ」「アブ・ハッサン」など5曲に「舞踏への勧誘」がカップリングされています。 こういう曲を指揮するとカラヤンの美点が光り輝くように聴こえてくるのが不思議です。 流麗・美麗の極みのような、手軽にウエーバー音楽を楽しめます。(ドイツ・グラモフォン 419070 1972-73年録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1778年 初演 モーツアルト 交響曲第31番「パリ」1821年 初演 ウエーバー オペラ「魔弾の射手」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ハイビスカス長居植物園の花壇では年中この花が咲いているような感じがします。撮影地 大阪市立長居植物園
2007年06月18日
コメント(4)
-
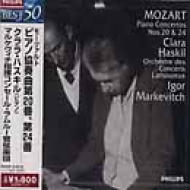
モーツアルト ピアノ協奏曲第24番 ハ短調/初夏の花
『今日のクラシック音楽』 モーツアルト作曲 ピアノ協奏曲第24番ハ短調昨日に続いてモーツアルトの短調の曲です。 ピアノ協奏曲第24番ハ短調 K.491モーツアルトの作品の中でもピアノ作品は重要な曲のようです。 ピアノ・ソナタは全部で17曲。 協奏曲は27曲。 その他に「幻想曲」や「変奏曲」、「ロンド」、2台のための協奏曲やソナタ、3台のための協奏曲など数多くのピアノ作品を書き残しています。 モーツアルト自身がピアノの名手であったこと、お金のために書かねばならなかった事情もあったようです。 特に、1781年25歳でウイーンに出た翌年にコンスタンチェと結婚してから、その傾向が顕著だったようです。 生活のために協奏曲を書いて自ら演奏することを余儀なくされたのでしょう。モーツアルトは音楽史上では古典派に属する作曲家です。 その点では先輩のハイドンと同じです。 古典派の作曲家は、貴族などのパトロンに快く受け入れてもらう音楽として誰にでもわかりやすい一般的な美しさを表出する、形にはまった個人的な感情を表すことを差し控えた音楽が多い中で、モーツアルトの音楽は理にかなった形式美の内にもハッとする美しさを湛えたものがあります。その「美しさ」は短調で書かれた作品に特に顕著です。 モーツアルトが短調で描いた音楽は彼自身の「感情」-悲痛な想いが「アレグロ」で書かれているため、劇的ともいえる緊張感をはらんでいるのが特色です。例えば第25番のト短調の第1楽章がその最も顕著な例でしょう。 また昨日採り上げましたピアノ・ソナタ第8番の第1楽章「アレグロ・マエストーソ」などもあげられます。 劇的とは言えませんが、同じく「アレグロ」で訴える悲しみの感情として有名な交響曲第40番の有名な第1楽章の主題があります。こうしたモーツアルトの特徴ー個人の感情を表出することーがその他の古典派作曲家の音楽と違うところです。モーツアルトの短調の作品の特徴はそれだけにとどまらず、彼自身の感情の表出によって「ロマン的な音楽」になっていることです。 また交響曲第40番に例をとりますと、あの有名な第1楽章の悲しいアレグロの旋律はメランコリックなロマンに溢れています。 古典の形式美を保ちながら内側に秘めた烈しい悲しみの心と言える、ハッとするような深い人間感情をロマンティックな美しさで表現しています。 ロマンティックな美しさはすでに昨日採り上げましたピアノ・ソナタ第8番イ短調に表れており、1788年の交響曲第40番ト短調、絶筆となった「レクイエム」でロマンの香りをいっそう色濃く残しています。 言い変えれば、モーツアルトはロマン派が描いたように明確に自分の心を表現したのでしょう。 お金のために書いた音楽ではなく自己の主張を明言したのです。 しかし、その時には自分の葬儀を出すお金もわずかに残っているだけであったことを思うと、モーツアルトの悲しみがいっそう伝わってくるような気がします。交響曲第40番ト短調が生まれる2年前の1786年の3月にピアノ協奏曲第24番ハ短調 K.491が生まれています。当時の古典派の協奏曲とはがらりと違う内容のピアノ協奏曲第20番ニ短調で、暗い劇的な内容とシンフォニックな構成えでモーツアルト流を明確に表現しており、この第24番では「モーツアルトのロマンティック」とベートーベンのような要素ー管楽器の巧みな使い方ーで、ほの暗い情緒を際立たせています。 終楽章が「ロンド」形式でなく「変奏曲」にしているのも特徴です。第1楽章第1主題から短調の和音が重苦しく響いています。 協奏的なソナタ形式に暗い、悲劇的・悲痛な情熱が醸し出されています。 第20番ニ短調よりもいっそう悲劇的な色を濃く残しています。第2楽章ピアノ独奏から開始される伸びやかな旋律は、詩的で瞑想的な情緒が美しい楽章です。 愛らしく美しい主旋律に込められたモーツアルトの嘆きが心に沁み入ってくるような、決して嘆き節ではないひっそりと悲しむモーツアルトの心がを打ちます。第3楽章変奏曲で、主題は短いのですが哀愁を湛えた美しい旋律です。 様々な音型での変奏が繰り広げられています。 唯一明るさを感じる楽章ですが、そこはかとなく悲しみを伝えるモーツアルトの天才ぶりに驚かされます。こうした短調の曲を書き終えた後にあのオペラ「魔笛」の明るさを書いているモーツアルトの天才ぶりに改めて頭が下がる思いで、なぜそれほどまでに若い命を散らしたのか、残念でなりません。モーツアルトの短調の作品にはとても魅力のある美しい音楽をたたえています。 まだまだ彼の短調作品を書きたいのですがそれは後日にさせていただき、ひとまずこれで終わらせていただきます。愛聴盤(1) クララ・ハスキル(ピアノ) イーゴリ・マルケヴィッチ指揮 ラムルー管弦楽団(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック PHCP21013 1960年録音)1枚だけとなれば躊躇なくこのハスキル盤を選ぶでしょう。 ピアノから立ち上る高雅な憂いの表情、温かく優しいカンタービレ。 ハスキルの至芸です。(2) ロベール・カサドシュ(ピアノ) ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団(ソニークラシカル SICC482 1961年録音)LP時代から聴き親しんだカサドジュの名盤で現在は3枚組で「モーツアルト協奏曲選集」として3枚組3,000円でリリースされています。(3) 内田光子(ピアノ) ジェフリー・テイト指揮 イギリス室内管弦楽団(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7004 1988年録音)現在は「フィリップス スーパーベスト100」の1枚として1000円で発売されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1818年 誕生 シャルル・グノー(作曲家)1882年 誕生 イーゴル・ストラヴィンスキー(作曲家)1944年 初演 プロコフィエフ ヴァイオリン・ソナタ第2番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 初夏の花 (1)花菖蒲花菖蒲は構図としてはとても撮りにくい花の一つです。 菖蒲苑やアヤメ園などのように群生で咲いているのはそれなりに撮り方がありますが、鉢植えや畑の花菖蒲には構図に困ります。この花はは畑の隅に咲いていた花です。 撮影地 大阪府和泉市(2) 紫陽花今月が見ごろのところが多いです。 関西でも紫陽花の名所が多いです。 京都のお寺・神社の庭など、植物園や記念公園の紫陽花園などたくさんあります。 雨に似合う花です。額紫陽花 紅額女人鎌倉 紫陽花はいずれも大阪市立長居植物園です。
2007年06月17日
コメント(10)
-

モーツアルト ピアノソナタ第8番イ短調/からす麦
『今日のクラシック音楽』 モーツアルト作曲 ピアノ・ソナタ第8番イ短調 モーツアルトには数は少ないが短調で書かれた作品が残されており、それらのどれもが素晴らしい旋律・リズム・和声で描かれていて、聴く者の胸をえぐるような作品ばかりです。 最も有名なのが交響曲第40番ト短調。 あの第1楽章の冒頭の主題を聴いて心が動かない人はいないだろうと、思うほどに悲しみ・悲哀・哀愁が伝わってくる、どこかロマンティックな香りのする名旋律が胸を締め付けます。他に短調の曲は、交響曲第25番ト短調、弦楽五重奏曲ト短調、ヴァイオリン・ソナタ第28番ホ短調、ピアノ・ソナタ第8番イ短調、ピアノ・ソナタ第14番ハ短調、それにピアノ協奏曲第20番ニ短調、第24番ハ短調があります。 もっと他にもあるかも知れませんが、今、頭に浮かぶ曲はそれくらいでしょうか。今日はそれらの中からピアノ・ソナタ第8番イ短調 K.310を採り上げました。モーツアルトの短調の作品で顕著な特徴は、悲痛な感情を「アレグロ」で表現していることです。 第25番・第40番の交響曲でも「アレグロ」によって悲しみを表現しています。 その悲しみが後のロマン派の短調のように、のたうちまわって悲しみを伝えていません。 チャイコフスキーのようにロシアの大地の憂愁を伝えるような表現でもなく、快速で悲しみを伝えてくる独特の表現で心の内を覗かせています。 それによっていっそうモーツアルトの深い悲しみ・哀しみを感じるのです。単一楽器ピアノで表現される悲しみは管弦楽などによる表現とは異なりますが、旋律がそのまま聴く人の心に迫ってきます。 この第8番のソナタでも第1楽章の「アレグロ・マエストーソ」では、快速に表現されるモーツアルトの悲しみが伝わってきます。この第8番の作曲は1878年モーツアルト22歳の6月と伝えられています。 彼がフランス・パリに樂旅で訪れていた時でした。 その時には母親マリア・アンナが同行しており、彼女はその折に急病で生涯を閉じています。 モーツアルトは父親宛てに母の死を知らせるのにこういう手紙を書いています。「とても不快な、悲しいお知らせをしなければなりません。 お母さんのかげんが大変悪いのです・・・・・」と亡くなった事実を書かずにぼかして書いています。 この手紙の最後には「それではご機嫌よろしゅう。 神さまのお心におまかせ下さい。 そうすると慰めが得られます。 愛する母さんは神さまの御手の中にあります」と。 父と姉の心を気遣うモーツアルトのやさしい心が切々と胸を打つ言葉で綴られています。そして、その手紙の6日後にようやく事実を知らせています。 「僕のこの小さな嘘をお許し下さい。 あなた方のことを思うと、恐ろしい知らせを書けなかったのです・・・・」と。こうした母の急死に直面して書かれたのが、この第8番のソナタでした。 通説では母の死の直前に完成したと言われていますが、いずれにしても危篤の床に伏せる母を看取りながら、やがて永遠の別れを告げる時期を知ったモーツアルトの心情が、この作品にそのまま投影されているように思われてなりません。 独特の張りつめた緊張感と暗い情感・色合いが、完成度の高い「悲愴美」を醸し出しています。世に天才の早死という言葉がありますが、モーツアルトやシューベルト、メンデルスゾーンのように30歳代で亡くなった作曲家もいれば、再現芸術家にもいます。 飛行機事故で30歳で亡くなったヴァイオリンのジャネット・ヌヴー、 交通事故死で36歳の命を散らしたホルンのデニス・ブレイン、水泳事故で44歳で亡くなった指揮者イシュトバン・ケルテス、そして白血病で33歳の若さで亡くなったピアニスト、ディヌ・リパッティ。リパッティは1950年9月16日にブザンソン音楽祭でリサイタルを開いています。 このときはドクター・ストップがかかっていたにも拘わらず「演奏会の約束は守らなければ」と言ってステージに上がり、最後のプログラムであったショパンのワルツを全曲を弾くことが出来ずにリサイタルを閉じており、これがリパッティ最後の演奏会となってしまいました。 そしてその2週間後にリパッティは33歳の若さで神さまに召されたのでした。その当夜のプログラムの中で、このモーツアルトの第8番のソナタが演奏されています。 私はこのディスクを聴くたびにモーツアルトの溢れんばかりの惜情と、死期の近いのを悟ったリパッティの心情に胸を抉られるような気持で聴いています。愛聴盤 (1) 「リパッティ 最後のリサイタル」(EMI原盤 東芝EMI TOCE3159 1950年9月16日ブザンソン・ライブ)音の状態は良くありませんが純粋無垢な、透明感のある響き。 まるで鍵盤を蝶々が舞っているような感じのリパッティの「白鳥の歌」。(2) イングリッド・へブラー(ピアノ) (DENON CREST1000 COCO70445 1986年録音)指揮者ワルターの演奏のようにとても温かい響き、音色でモーツアルトの哀しみを描いています。 クレスト1000シリーズで1000円盤です。(3) 内田光子(ピアノ) (Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7006 1983年録音)へブラーに比べると少しメタリックな響きですが、粒立ちのよい透明な音色が魅力の演奏で、現在は「フィリップス スーパーベスト100」の中の1枚で1000円盤です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1909年 誕生 ウイリー・ボスコフスキー(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 からす麦道端や空き地・公園・畑などどこにでも見かける「からす麦」です。 今を盛りと時には群生で植わっていることもあります。 撮影地 大阪府和泉市
2007年06月16日
コメント(6)
-
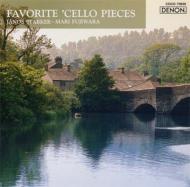
チェロ名曲集/クレマティス(テッセン)
『今日のクラシック音楽』 チェロ名曲集チェロは、最初はヴィオラ・ダ・ガンバという名前でバロックに時代に通奏低音楽器として使われていましたが、徐々に市民権を得るようになりバロック時代でも、チェロ協奏曲としてデビューしました。 その頃の有名曲ではボッケリーニの協奏曲、そして古典派時代にはハイドンの協奏曲などで脚光を浴びるようになりました。ベートーベンはチェロ協奏曲を書いていませんが、5つのチェロ・ソナタによってこの楽器の地位を確立しています。 そして1889年パブロ・カザルス(チェロ奏者・指揮者)によってあの大バッハの無伴奏チェロ組曲が発見されて、バッハがベートーベンの前に偉大なチェロ作品を書き残していることがわかりました。チェロは、女性を想像させるような体形でありながら、そのしとやかな弧線から逞しいタッチで、時には豪快に、時には優美な音楽を奏でる楽器として親しまれています。チェロが朗々と旋律を歌う美しさ、音を出した途端に惹きつけられる色彩豊かな音色、まるで人間の古老の持つ、酸いも甘いも渋さも兼ね備えたような色合い、明るい輝きもあれば、ほの暗い憂愁の美しさもたたえた彩り、聴く者の心を落ち着かせる不思議な楽器・チェロ。そのチェロに魅せられて数多くの作曲家が小品として残した作品が数多くあります。 またオリジナルがピアノ曲やヴァイオリン曲、フルート曲でも後世の人がチェロ演奏用に編曲したものもあります。私はブログの原稿を書き終えてコーヒーブレイクなどの時間に取出して聴くディスクがあります。DENONからリリースされた「チェロ名曲集」で、藤原真理とヤーノシュ・シュタルケルの演奏でショーピース(小品)ばかりを集めたディスクです。 全曲を聴くことはまづありませんが、好きな曲を選んで2~3曲聴いています。 特に夜の帳が降りた頃に聴きますと、朗々たるチェロの響きが疲れた頭を癒してくれるような感じを受けます。このディスクは発売当時から数えると何度再発売されたかわからないほど、繰り返しリリースされているようです。 現在はCREST1000シリーズの340枚の中の1枚として1000円盤として発売されています。このCDです。 (DENON CREST1000 COCO70736)藤原真理とシュタルケルの演奏によるオムニバス形式のディスクで、ピアノ伴奏は岩崎 淑、練木繁夫などが受け持っています。収録曲は下記です。(1)エルガー:愛の挨拶(2)ヘンデル:シチリアーノ(3)サン=サーンス:白鳥(4)ブロッホ:祈り(5)ポッパー:タランテラ(6)ウェーバー:アダージョとロンド(7)パガニーニ:モーゼ幻想曲(8)シューマン:トロイメライ(9)カザルス:鳥の歌(10)フォーレ:シチリアーノ(11)フォーレ:夢のあとに(12)フォーレ: エレジー(13)ポッパー:ハンガリー狂詩曲(14)ファリャ:火祭りの踊り(15)グラナドス:「ゴイェスカス」間奏曲尚、このDENONのCREST1000シリーズは、オペラ全曲盤を除いて交響曲、管弦楽曲、協奏曲、器楽曲、声楽曲、宗教音楽、バロック音楽などが素晴らしい演奏家たちによって録音されたものを厳選して340枚のCDとして発売されています。 これからクラシック音楽を聴こうという人には1000円という価格の魅力・PCMデジタル録音の優秀さなどから、お薦めのシリーズです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1843年 誕生 エドヴァルド・グリーグ(作曲家)1962年 没 アルフレッド・コルトー(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 クレマティス(テッセン)自宅前のおうちの庭に咲いている鉢植えのクレマティスを撮らせてもらいました。 撮影地 大阪府和泉市
2007年06月15日
コメント(8)
-
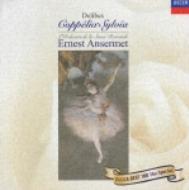
ドリーブ「シルヴィア」/姫女苑(ヒメジョオン)
『今日のクラシック音楽』 ドリーブ作曲 バレエ音楽「シルヴィア」フランスの作曲家リオ・ドリーブ(1836-1891)は「バレエ音楽の父」とも呼ばれている人で、それまでのバレエ音楽はダンサーのステップに対して拍子を取るだけあったのを、もっと劇的に登場人物の性格などを表現する音楽として世に送り出しています。 彼の代表作としては「コッぺりア」とこの「シルヴィア」が挙げられます。 また超絶技巧の難曲として有名なオペラ「ラクメ」も書いています。前作「コッぺリア」は人形が主人公の物語でしたが、「シルヴィア」は古代の神を中心に神話のような物語が進みます。 羊使いのアミンタと妖精シルヴィアの物語です。 女神ディアーヌに仕える妖精シルヴィアは、愛の神「エロス」の矢に射られて羊飼いアミンタに恋心を抱きます。 ところが狩人オリオンにシルヴィアが誘拐されてしまいます。 危うくオリオンの自由にされかけた時に、エロスが現れシルヴィアを助けて、彼女とアマンタが結べばれて大円団となるという、いかにも単純な物語です。ロマンティック・オペラとも呼ばれるこのバレエの音楽は、実に精妙に音楽で描かれていて、楽しく、優美な旋律が古代神話の世界へと導いてくれます。演奏会ではバレエならともかく、オーケストラ演奏会では全曲演奏という機会は滅多になく、4曲からなる組曲が最もポピュラーな選曲として選ばれています。第1曲 前奏曲と狩りの女神たち第2曲 間奏曲と緩やかなワルツ第3曲 ピッチカート第4曲 バッカスの行列このうち第4曲「バッカスの行列」は単独でも演奏会で採りあげられる機会の多い曲です。あのチャイコフスキーが「もし私がもっと早くこの作品を知っていたなら、白鳥の湖を書かなかっただろう」と言わしめたそうです。1876年の今日(6月14日)、このバレエ音楽「シルヴィア」がフランス・パリで初演されています。愛聴盤(1) エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7038 1957年録音)LP時代から聴いているディスクです。 ハイライト盤で「コッペリア」ハイライトとのカップリングです。(2) リチャード・ボニング指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD3835 1972年録音)バレエ音楽を演奏させると、冴えわたるボニングの全曲盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1671年 誕生 トマーゾ・アルビノーニ(作曲家)1876年 初演 ドリーブ バレエ音楽「シルヴィア」1910年 誕生 ルドルフ・ケンぺ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 姫女苑(ヒメジョオン)菊科の花。ムカシヨモギ属 開花時期 6月~8月 北アメリカ原産の帰化植物 道端・公園・空き地・畑などでよく見かける花です。 撮影地 大阪府和泉市
2007年06月14日
コメント(4)
-
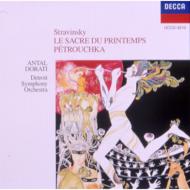
「ペトルーシュカ」/トマトの花
『今日のクラシック音楽』ストラヴィンスキー作曲 バレエ音楽「ペトルーシュカ」「ペトルーシュカ」は、ストラヴィンスキーの三大バレエ音楽の一つに数えられています。 現代音楽でありながらチャイコフスキーの3大バレエ音楽と並び称せられる、古典バレエの地位を築いている親しみやすい現代音楽です。ディアギオレフ・バレエ団の委嘱作品で1911年に完成しています。 その後作曲者によって改編されています(1947年版)。 現代でこそ古典のような扱いですが、初演当時は斬新なリズム・和声などが音楽のグロテスクな面を採り上げられて賛否両論だったそうです。 ウイーンフィルはバレエ団がウイーンに訪れた際に「いかがわしい音楽」と批評したそうです。物語はわら人形ペトルーシュカが魔法をかけられて人間の恋情を持ち、やはり人形のバレリーナに恋をするのですが、やはり人形のムーア人に殺されてしますという悲劇です。第1部 謝肉祭の市導入 - 群集人形使いの見世物小屋ロシアの踊り第2部 ペトルーシュカの部屋 ペトルーシュカの部屋第3部 ムーア人の部屋ムーア人の部屋バレリーナの踊りワルツ(バレリーナとムーア人の踊り)第4部 謝肉祭の市(夕景)乳母の踊り熊を連れた農夫の踊り行商人と二人のジプシー娘馭者と馬丁たちの踊り仮装した人々格闘(ペトルーシュカとムーア人の喧嘩)終景:ペトルーシュカの死警官と人形使いペトルーシュカの亡霊という場面構成でバレエが披露されます。宗教上の長い断食期間に先立って行われる、「シロヴェティデ」と呼ばれる数日間の市場から舞台が始まります。 しばらく破目を外すことのできない日々を前に、人々は大いに浮かれています。オーケストレーションと頻繁なリズムの変更が、祭日の喧騒とざわめきを描写しています。 手回しオルガン奏者と踊り子が群衆を楽しませており、ドラムは老魔術師のお出ましを告げ、魔術師が観衆に魔法をかけます。突然に幕が開いて小劇場が現われ、魔術師が動かない、命のない3つの「わら人形」ーペトルーシュカ、バレリーナ、荒くれ者のムーア人ーを取り出します。 そして魔術師は横笛を吹いて魔法をかけて人形たちに生命を吹き込みます。 命を与えられた人形たちは、小さな舞台から飛び出して、ぎょっとしている市場の通行人の中で踊り出します。 今や生きた人形たちは、激しいロシア舞曲を踊り出します。ペトルーシュカの部屋に転換して、一面暗い色をした壁は、黒い星印や半月、老魔術師の肖像が飾られています。 ペトルーシュカは、自分の小部屋に音を立ててぶつかり、魔術師に蹴飛ばされて暗い部屋の中に入ります。ペトルーシュカは見世物小屋の幕の陰で気の滅入るような生活を送りながら、バレリーナ人形に思いを寄せます。 むっつりとした表情の魔術師の肖像画が、ペトルーシュカはただの人形で、人間と同じでないのだから、従順であるべきだとでも言いたげに、ぼんやりと浮き上がって見えてきます。 だがペトルーシュカは腹を立て、魔術師のにらみ顔に拳を食らわします。ペトルーシュカは人形ですが、人間的な感情があり、老魔術師に対しては囚人のような気持ちを、美人のバレリーナには恋心を抱いています。 ペトルーシュカは自分の小部屋から逃げ出そうとするのですが果たせません。バレリーナが入って来たので、ペトルーシュカは思いを告げようとしますが、バレリーナはペトルーシュカの哀れっぽい口説き文句をはねつけます。 そしてバレリーナはムーア人といちゃつき始め、哀れなペトルーシュカの感じやすい心を傷つけます。ムーア人が快適な暮らしを送っていると容易に察せられるムーア人の部屋。 ムーア人は寝そべるためのソファを持ち、そこでココナッツを玩んでいます。 ムーア人の部屋は広くて、明るく愉快で豪奢な気分を盛り立てています。 すると、ムーア人のスマートな見た目に惹かれたバレリーナが登場し、魔術師によってムーア人の部屋の中に入れられます。 バレリーナが小粋な節を奏でると、ムーア人が踊り出します。するとペトルーシュカは、小部屋を破り、ムーア人の部屋に向かって行きます。 魔術師はペトルーシュカに、バレリーナの誘惑を邪魔させます。 ペトルーシュカはムーア人に体当たりしますがかないません。 そしてペトルーシュカは命からがらその部屋から逃げ出して行きます。再び市場の場面。 オーケストラは色彩豊かな舞曲を導き出します。 中でも最も有名なのは「乳母たちの舞曲」です。 そして熊と熊使い、遊び人の承認とジプシー娘たち、馭者と馬丁たち、そして仮装した人々が交互に現われます。お祭り騒ぎが頂点に達すると、人形劇場から叫び声が上がり、突然ペトルーシュカが、刃物を手にしたムーア人に追い立てられて、舞台を走りぬけます。 ムーア人がペトルーシュカに追いついて殺してしまいます。魔術師はぐにゃぐにゃしたペトルーシュカのむくろを担ぎながら去ろうとすると、ペトルーシュカの死霊が人形劇場の屋根の上に現われ、ペトルーシュカの怒りに満ちた抗議となりますが、老魔術師は、ペトルーシュカの亡霊を目の当たりにして、恐れをなす。 魔術師は慌てて逃げ出し、場内は静まり返り、聴衆に謎を残したまま閉幕となります。音楽はロシアの民族色豊かな旋律で彩られて、以上のような物語を鮮明に描いており、親しみやすい現代音楽によるバレエの傑作です。1911年の今日(6月13日)、この「ペトルーシュカ」はフランス・パリで初演されています。愛聴盤(1) アンタル・ドラティ指揮 デトロイト交響楽団 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD3210 1980年録音)舞台を彷彿させる語り口の巧さが光る、ドラティ得意のバレエ音楽で、ストラヴィンスキーの「春の祭典」とカップリングされています。(2) キリル・コンドラシン指揮 アムステルダム・コンセルトヘボー管弦楽団 (Philipsレーベル PHCP9241 1973年アムステルダム・ライブ録音 廃盤)まるでロシアの重戦車が地響きをたてて行進するような響きで、これがコンセルトヘボーなのかと思うほどロシア色濃厚な演奏で、このディスクを聴くたびにコンドラシンの急逝が惜しまれてなりません。 カップリングのボロディンの交響曲第2番も録音史上に残る名演だと思います。 現在はユニヴァーサル・ミュージックが版権を持っていると思いますが、再発売を強く望まれる名盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1855年 初演 ヴェルディ オペラ「シチリア島の夕べの祈り」1911年 初演 ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」2006年 没 岩城宏之(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 トマトの花これも小さな花ですが、マクロレンズを使って撮りました。 撮影地 大阪府和泉市
2007年06月13日
コメント(6)
-
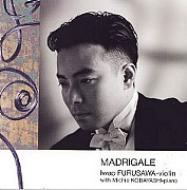
シモネッティ 「マドリガル」/セダム
『今日のクラシック音楽』 シモネッティ作曲 「マドリガル」今日はマーラー作曲の交響曲第9番の初演日なのですが、この曲については先月18日にマーラーの命日にすでに採り上げていますので、今日は小品一曲を採り上げてみました。イタリア(のちにイギリスに帰化しています)のヴァイオリン奏者であり作曲家でもある、アキルレ・シモネッティ(1859-1928)が作曲しました「マドリガル」です。マドリガルとは、中世のイタリアで流行しました多声の声楽曲のことなんですが、この曲はそういうことに関係なく書かれています。 おそらく中世の精神か中世への郷愁で書かれた曲かも知れません。 音楽は流麗なイタリア歌曲か、あるいはセレナーデを想わせるような旋律で、寄り添う若いカップルの甘い囁きが聞こえてくるような、実に美しい音楽です。偶然手にしたCDに収録されていて、帯に書かれた解説を読んで購入したように記憶しています。 日本列島を寒気が通過したためか気温が高いのですが、空気が冷えているのか爽やかな日々の続く毎日です。 こんな初夏の夜に聴いてみるのに打ってつけの、美しい旋律に彩られた音楽です。アキルレ・シモネッティは1859年の今日(6月12日)、イタリアで生まれています。愛聴盤 古澤 巌(ヴァイオリン) 小林道夫(ピアノ) (エピックソニー・レーベル ESCK8002 1988年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1859年 誕生 アキレル・シモネッティ(ヴァイオリニスト・作曲家)1912年 初演 マーラー 交響曲第9番1984年 没 ヤーノシュ・フェレンチーク(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 セダム 約600種類あると言われています多肉科植物で、黄色の花もあるそうです。 肉眼で見るとそれほど可愛い花ではありませんが、マクロレンズで覗いてみますとなかなか可愛い表情をしています。 ベンケイソウ科の花です。 撮影地 大阪府和泉市
2007年06月12日
コメント(10)
-
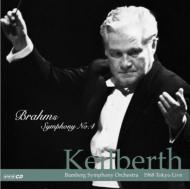
「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」/蔓花茄子
『今日のクラシック音楽』 R.シュトラウス作曲 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」私がリヒャルト・シュトラウスという作曲家を知ったのは1962年、高校2年生の頃でした。 そのときはあの有名な「ワルツ王」と呼ばれたヨハン・シュトラウス一家の人で、同じようにワルツを作曲している人かと思ったものでした。何故か理由を覚えていないのですが、この人の書いた交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」(以下テイルと略します)という曲があることを知って聴きたくなり、カール・ベーム指揮のドレスデン国立歌劇場管弦楽団のモノラル録音の45回転EP盤を買って聴いたのが、最初のリヒャルト・シュトラウス体験でした。 この体験を何故自分から望んだのか今もって不明です。曲を聴いてこの人のオーケストレーションをいっぺんに好きになりました。それまで聴いていたハイドン、モーツアルト、ベートーベンやブラームス、チャイコフスキーなどの曲とは次元が違う音楽で、華麗で精緻な音の響きに魅了されました。それからはこのR.シュトラウスの曲のLP盤がリリースされる度に指をくわえて我慢の子でした。その頃はちょうどイタリア歌劇団が来日して、イタリアオペラにも夢中になっていた時代で、とても両親から何枚ものLP盤を買ってもらうことができなかったので、「レコード藝術」や朝日新聞などで紹介されるシュトラウス音楽の記事を読んでいるに過ぎない時が過ぎていきました。そして大学生になってから友人がオープンリールのテープレコーダーで、「ツァラトゥストラはかく語りき」を聴かせてくれて、すっかりシュトラウス音楽の魅力にとりつかれてしまいました。そんな折のこと、名指揮者ヨゼフ・カイルベルトが手兵のバンベルグ交響楽団を率いて来日、東京で勉強していました私は上野の東京文化会館に足を運びました。 1968年5月20日のことでした。プログラムはこの交響詩「ティル・・・」、ハイドンの「時計」交響曲、ブラームスの第4番の交響曲でした。 ブラームスも目当ての曲でしたが、何と言っても「ティル」でした。 これが生演奏でしかもドイツの名門オケとカイルベルトですから、当日までに興奮気味の日が続いていたのを今でも覚えています。今でこそR.シュトラウスを演奏するコンサートがあっても、皆さんはさほど興奮もしないと思います。 日本のオケもうまくなり、これを演奏することは難しくない時代になっていますし、レコード・CDは夥しい数の演奏がリリースされています。しかし、1968年はまだこの曲はマイナーだったのか、曲の終わり部分であたかも終わったかのように音楽が途切れる部分があります。そこで聴衆の半分くらいが拍手をするというような時代でした。 オイゲン・ヨッフムが初めてアムステルダム・コンセルトへボーを率いての来日公演でも、この曲を演奏したのですが、彼が客席を振り向いて「シー」という仕草をやったという嘘のような、本当の話があるくらいに、この曲はまだまだマイナーでした。話は逸れましたが、この演奏には心も体も震えるほどの感動を味わいました。R.シュトラウスの見事な、美しく、精緻なオーケストレーションに客席で、音楽に酔っているのかのような至福の時を過ごしていました。この音楽の物語は1300年代のドイツの民話で、いたずら好きなティルが様々な悪いことをやって、最後には捕まって死刑になるのですが、その物語をわずか15分間くらいの音楽で描写した交響詩です。 そのいたずら振りを彼特有の華麗で、豊穣な響きに満ちたオーケストレーションで描いています。「ロンド形式による昔の無頼の物語」とサブタイトルされているように、14世紀の北ドイツの伝説の奇人ティル・オイレンシュピーゲルの冒険談を題材に、シュトラウスの管弦楽法が巧妙に生かされた傑作です。オーケストラの各楽器が豊穣に響き渡る様が聴きもので、シュトラウス流のユーモアとウィットに溢れた音楽です。曲は、弦楽器による親しみやすい短い前奏で始まります。これは昔話の「むかしむかし・・・」を表すテーマでしょう。続いてホルンによるティル・オイレンシュピーゲルの第1のテーマが出てきます。続いてクラリネットでティルの笑いを表すテーマが示されます。 悪戯は、まず市場に現れたティルは牛馬を解き放し、市場は大騒ぎになり、ティルは空を飛ぶ靴で逃げてしまいます。続いてティルは僧侶に変装し、でたらめなお説教で人々を煙に巻きます。 独奏ヴァイオリンが退屈したティルのあくびを表現しますが、ふと彼の心に破滅への予感がよぎります。これは金管群によって表現されています。続いてティルは騎士に変装し、美しい淑女を口説きますが彼女にあっさりと振られます。怒ったティルは全人類への復讐を誓います。これは金管の鋭い上昇音型で表現されています。最初の標的をファゴットでユーモラスに表現された俗物学者に定めたティルは、彼らに論争をふっかけます。しかし次第に旗色が悪くなり、論戦に敗れたティルは悔しまぎれに小唄を歌います。再びホルンによるティルのテーマが現れ、次第に勢いを増していき、好き放題にいたずらを繰り返すティルの様子が描かれていきますが、突如小太鼓が鳴り響き、ティルは逮捕されます。そして金管によるいかめしい裁判のテーマが奏されます。ティルは裁判を嘲笑っていますが、やがて彼は死の予感におびえて金切り声を上げます。ついに死刑の判決が下り、ティルは絞首台に昇らされ敢えない最期を遂げます。冒頭の「むかしむかし・・・」のテーマが回帰し、ティルは死んでも彼の残した愉快ないたずらは不滅であることを示すティルの笑いの動機で曲が締めくくられます。R.シュトラウスの音楽は管楽器、特に金管楽器が重要な役割を持たされていて、その響きやハーモニーがことのほか美しいという特徴がありますが、この曲も同じです。金管楽器や打楽器が非常に効果的に用いられていて、情景が膨らむかのように描き出されています。この音楽はディズニーの「ファンタジア」のようなアニメにして、音楽とアニメを一緒に味わえたら最高に面白いだろうと常々思っています。1864年の今日(6月11日)、そのリヒャルト・シュトラウスが生まれています。愛聴盤 (1)ヨゼフ・カイルベルト指揮 バンベルグ交響楽団(キングレコード KICC 422 1968年5月20日 東京文化会館ライブ録音)このCDは上述しました、私が客席で聴きました演奏会の録音で音源はNHKです。 当時FMでも放送されて大変話題になった演奏会です。ハイドンのみ収録されておらず、アンコール曲のワーグナーの「ニュルンベルグのマイスタージンガー」前奏曲も収録されています。(2) ルドルフ・ケンペ指揮 シュターツカペレ・ドレスデン (EMI原盤 東芝EMI TOCE13467 1970年録音)「ドン・ファン」、「ツラトゥストラ」、がカップリングされた遅めのテンポで旋律をたっぷりと歌わせるケンペの指揮が魅力のディスク。1300円盤(3) アンタル・ドラティ指揮 デトロイト交響楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD3882 1980年録音)これも「ドン・ファン」「ツラトゥストラ」とのカップリング。 雄大なスケールでシュトラウスの豊穣な響きをDECCA特有の優秀録音で描いた普遍的な名演。 来月25日に「アンタル・ドラティの芸術」の1枚として再リリースされます。 1200円盤。(4) カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団 (ドイツ・グラモフォン 4158532 1973年録音 海外盤)カラヤンの豊麗な演奏が最も合っていると思われる、響きの素晴らしい演奏。 これも「ドン・ファン」「ツラトゥストラ」とのカップリング。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1864年 誕生 R.シュトラウス(作曲家)1940年 初演 バルトーク 弦楽のためのディベルティメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 蔓花茄子(ツルハナナス)この花は園芸種として家の庭に植えられているのを撮らせてもらいました。 山野に咲くのは「山保呂志」と呼ばれています。撮影地 大阪府和泉市 茄子科の花で6月頃から秋までの長い間咲く花です。 清楚な感じの日本的な感じのする花です。
2007年06月11日
コメント(8)
-
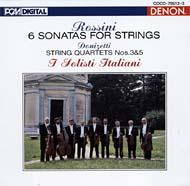
ロッシーニ 「弦楽のためのソナタ」/時計草
『今日のクラシック音楽』 ロッシーニ作曲 弦楽のためのソナタジョアッキーノ・ロッシーニ(1792-1868)といえばオペラ。 彼の書き残した傑作オペラの数々がすぐに思い浮かびます。 「セビリアの理髪師」「ウイリアム・テル」「アルジェのイタリア女」「シンデレラ」等々。両親は音楽で生計を立てていましたが、ジプシーのように色々な土地を転々とした生活だったそうで、息子ロッシーニは充分な音楽教育を受けていなかったそうです。 彼自身はチェンバロを演奏したり、教会で歌ったり、合唱の指揮を行なったりして生計を助けていたそうです。「弦楽のためのソナタ」が作曲されたのは、彼が12歳の時です。 このソナタは事実上ロッシーニの最初のまとまった曲で、オペラはそれから5年近く経って書き始めたそうです。 W.A.モーツアルトが、父レオポルドによって幼いころから音楽の英才教育を受けて、「神童」と呼ばれていたの対して、ろくな教育も受けていないロッシーニが12歳で書いたこの曲は、とても12歳の子供が書いたとは思えない美しいソナタ集です。CD解説によりますと、この作品の自筆譜はアメリカ合衆国国会図書館(ワシントン)に所蔵されており、そこには自筆で「まだまったくの子供で、ただの一度の伴奏法のレッスンを受けたことがない頃に作曲された」と記されているそうです。 いやはや、この記述を知って作品を聴けば、ロッシーニの天才的な音楽才能をまさに驚きでもって頷かざるを得ない、美しい弦の響きが心を打つ作品です。弦楽4部編成の曲で(ヴィオラ部がありません)、 ソナタは1番から6番まで6曲書かれています。 少年ロッシーニの瑞々しい才気と明るさと美しい旋律に溢れた名品です。 特に素晴らしいのは第1番と第5番で、 今までに一番好んで聴いてきた作品です。 流麗・豊麗な旋律がどの作品にも溢れており、しかもイタリア的な伸びやかさがあって、ロッシーニのオペラ音楽とは一味違う弦楽の響きです。朝のクラシック音楽として、或いは午後のテイータイム音楽として、はたまた夜のおやすみ前のセレナードとして聴くのもいい、一日中どの時間帯にでもぴったりと合う普遍的な美しさの曲です。愛聴盤 イタリア合奏団 (DENON レーベル COCO70512 1987年 イタリア録音)レナート・ファザーノ主宰の「ローマ合奏団」が解散後に同メンバー有志で出来た「イタリア合奏団」の演奏はファザーノ時代の、豊穣で美しい響きと、まさに「磨き上げられた」カンタービレの美しさを継承しており、学生の頃に聴いていたあの「ローマ合奏団」が帰ってきたかに思える旋律の美しさを堪能できる演奏で、DENONチームがイタリアで行なったPCM録音の超優秀さと兼ね合せ、しかも発売当時2枚組み\6,000だったのが、CREST1000シリーズで\1,500という廉価盤になっているのが魅力です。↓イタリア合奏団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1865年 初演 ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」1899年 没 エルネスト・ショーソン(作曲家)1934年 没 フレデリック・ディーリアス(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 時計草ユニークな形の花です。 まるで文字盤を示すような花びらが特徴です。撮影地 大阪府和泉市時計草科 トケイソウ属 開花時期 6月初め~8月初めごろブラジル原産で18世紀半ばに日本に伝わっているそうです。 壁掛けの時計盤のような咲きかたをすることから命名されています。
2007年06月10日
コメント(8)
-
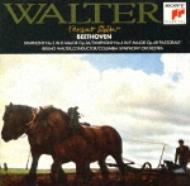
ベートーベン「田園」/アガパンサス
毎日リンクしていただいている方々のページを訪問させていただいておりましたが、ここのところ体調が良くありませんので、体調が良くなるまでは日記の更新とコメントをいただきました方々への返信だけにさせていただきます。 悪しからずご了承下さい。 体調良くなれば以前のように訪問させていただきます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ベートーベン作曲 交響曲第6番へ長調 「田園」クラシック音楽を長年聴き続けていますと「超有名曲」と呼ばれている作品が、だんだんと遠くに押しやって未知の音楽に触れたいと願うようになっていきます。 私の場合もそうで、交響曲ではベートーベンの「英雄」・「運命」・「田園」・「合唱付き」など、シューベルトでは「未完成」、チャイコフスキーでは「悲愴」、ドヴォルザークでは「新世界より」、モーツアルトの後期3大交響曲などが挙げられます。今日は今までに採り上げていなかったベートーベン(1770-1827)の交響曲第6番ヘ長調 作品68 「田園」を採り上げてみました。 この作品を最後に聴いたのがいつだったか忘れてしまうほどに記憶が薄れてしまっています。ベートーベンは散歩が好きで、ウイーン郊外の田舎を歩き、自然を楽しむ作曲家であったようです。 彼の日課は空が明けてくると起きて午後2時まで作曲に没頭して、そのあとに散歩を楽しんでいたようです。 ご承知のようにベートーベンは作曲家にとって致命症の「難聴」という厄介な病気を背負っており、26歳(1796年)頃から「難聴」が始まったと言われています。 この「田園」は有名な第5番「運命」と共に同時期の1807年~1808年にかけて作曲されており、初演は1808年12月22日に「運命」と共にウイーンで初演されています。 ベートーベン35~6歳の作品で、その時にはかなり「難聴」が進んでいた頃です。そんなベートーベンが耳の患いという病気を忘れさせてくれたのが、ウイーン郊外の田舎の風情と自然の美しさであったのかも知れません。 彼の遺書で有名なハイリゲンシュタットで書かれており、この曲には自然の美しさが滔々と語られており、ベートーベンの自然への愛、ひいてはその自然を創り給うた「神」への感謝を込めた音楽となっています。曲はベートーベンの交響曲では唯一5つの楽章で構成されています。 また第5番と同じく終楽章へは切れ目なく演奏されるのが特徴の一つです。 またこれまでのベートーベンの交響曲に比べて違う点は、それまでの「絶対音楽」でなくて、「表題音楽」として書かれています。 各楽章には表題がベートーベン自身によって書かれています。第1楽章「田舎に到着して晴れ晴れとした気分がよみがえる」晴朗で親しみやすいメロディーが、田舎での楽しい生活が描かれています。第2楽章「小川のほとりの情景」流麗なメロディーで小川のほとりの情景が表現されており、曲の終結部で、ナイチンゲールやカッコウの鳴き声が描写されています。第3楽章「農民達の楽しい集い」刈り入れが終わったあとの収穫を祝う、楽しく素朴な農民の踊りを表したスケルツォで描かれています。 第4楽章「雷雨、嵐」この楽章のみティンパニ、トロンボーン、ピッコロが加わり、すさまじい雷雨の様子を描写しています。 ロッシーニの序曲「ウイリアム・テル」の中の「嵐の場面」と比較されるほどに「嵐」を描写した素晴らしい音楽です。第5楽章「牧人の歌?嵐の後の喜ばしく感謝に満ちた気分」雨が上がり、陽が差し、感謝の歌が歌い上げられています。 終楽章にはAllegroのテンポを取るベートーヴェンですが、この曲ではAllegrettoという中庸のテンポを採用しており、穏やかな印象を与えて感動的に曲が閉じられています。散歩好きなベートーベンに面白いエピソードがあります。 ひと晩留置場に留め置かれたのです。 その日の午後の散歩では薄汚れた上着を羽織って、散歩には常に着用する帽子をかぶらずに出かけました。 この「田園」の初演17年後の夏のことです。 彼は散歩でも新しい楽想、曲想が湧いてくると大きな声でそれを唸る習慣がありました。 その日もそうした習慣に身を置いていたのでしょう、気がつくと日はとっぷりと暮れていました。 しかも自分の居場所もわからなくなっていました。とある1軒の家に灯がともっていたので、そこで場所を訊こうと窓から家の中を覗いていますと、警官に不審者として捕えられてしまい、自分は「ベートーベンだ!」と主張しても警官は「ベートーベンがそんな薄汚い乞食のような格好をしているものか」と相手にされずに留置場に1晩留め置かれてしまいました。知人の証言でやっとベートーベンとわかりあくる朝釈放されたそうです。この曲を聴くといつもこの愉快なエピソードを思い出しています。愛聴盤(1) ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団 (ソニークラシカル SRCR9966 1959年1月録音)ワルターの歌心にあふれた旋律の美しさが際立つ演奏。カップリングはベートーベンの第2番(2) カール・ベーム指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団 (ALTUS レーベル ALT0026 1977年3月東京ライブ録音)ドイツ音楽の造形美がウイーンフィルという名器によって奏でられている演奏。カップリングは「運命」(3) エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮 レニングラードフィルハーモニー (ALTUSレーベル ALT063 1979年5月東京ライブ)贅肉を削ぎ落としたようなスリムな表現がこの曲の持つ「静」の世界を描き出したムラヴィンスキーの名演。 カップリングはワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」から「前奏曲と愛の死」、「ワルキューレ」から「ワルキューレの騎行」(4) ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 ウイーンフィルハーモニー (DECCA原盤 UCCD7012 1967年録音 ユニヴァーサル・ミュージック)ウイーンフィルの美質を最大限に引き出した柔らかい音が魅力の演奏。 カップリングは「運命」。 ウイーンフィル初めてのステレオ録音。 価格は1,000円。(5) ベルナルト・ハインティンク指揮 アムステルダム・コンセルトヘボー管弦楽団 (Phlips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7015 1986年4月録音)最も普遍的な名演奏と呼べるテンポも中庸で、美しい旋律がコンセルトヘボー菅の魅力的な弦楽器によって奏でらています。 1,000円盤。 カップリングは「運命」。 初めて「運命」「田園」を聴く人にお薦めのディスク。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1860年 初演 シューマン チェロ協奏曲1865年 誕生 カール・ニールセン(作曲家)1902年 初演 マーラー 交響曲第3番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 アガパンサス昨日の画像は蕾ばかりの開花前でしたが、今日は開花したアガパンサスの画像です。撮影地 大阪府和泉市
2007年06月09日
コメント(6)
-

クーラウ フルートソナタ/アガパンサス
『今日のクラシック音楽』 クーラウ作曲 フルートとピアノのためのソナタ 作品83このCDをいつ購入したのか理由と共に全く覚えていないのですが、多分HMVで見つけて衝動買いをしたのだと思います。 しかし、これがなかなか素晴らしい作品で時折取り出しては聴いています。それはともかくとして、このフレデリック・クーラウ(1786-1832)なる作曲家の名前は、ピアノの練習をする人たちがほとんどが学ぶ「ソナチネ・アルバム」に収録されていることくらい知っいた程度の作曲家なのですが、時代はほぼベートーベンやシューベルトと重なる時期に音楽を書いていたことになります。 ベートーベンが亡くなったのが1827年で、シューベルトが1828年。ほぼ同時期に作曲を行なっていたことになります。クーラウが書き残した曲も幅広く、ピアノ協奏曲やピアノ三重奏曲、弦楽四重奏曲、それにオペラも書いているようです。ところで今日の話題曲の「フルートとピアノのためのソナタ作品83」ですが、このCDによると83という作品番号で3曲収録されています。ト長調とハ長調の2曲とト短調の1曲。音楽はモーツアルトのフルート音楽のようなロココ風の古典・典雅な調べではなくて、またシューベルトのようなロマンティックな音楽でもない、その中間のような「サロン風」の洒落たフルート音楽を楽しめます。2曲の長調は晴朗、明快、快活な旋律に彩られていて、ピアノとの均整のとれた美しい和音が耳に心地よく響いてきます。一方のト短調はこの時期のこの調性の特徴のようで、憂いの含んだ実に美しい、少し暗い音楽を楽しめます。それにしても、このクーラウの曲を聴きながらベートーベンは何故フルート・ソナタを書かなかったのだろうかと、珈琲カップの珈琲を見つめながら考えていました。このCDです。 ↓ウーヴェ・グロット(フルート) マッテオ・ナポリ(ピアノ)(NAXOS レーベル 8.555346 2000年6月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1810年 誕生 ロベルト・シューマン(作曲家)1912年 初演 ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」1937年 初演 オルフ 「カルミナ・ブラーナ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 アガパンサス夏を彩る花の一つです。 うちの町内でもこの花はすでに蕾をつけています。 撮影地 大阪府和泉市百合科 アガパンサス属 開花時期 6月中旬~8月初め南アフリカ原産 明治時代に日本に持ち込まれたそうです。 紫色の小花をたくさん咲かせます。葉が君子蘭に似ています。 別名「紫君子蘭」
2007年06月08日
コメント(2)
-

トゥリーナのピアノ音楽/紫陽花(伊豆の華)
体調不良のためしばらく休んでいました。 久し振りの更新です。 6月1日のゴべールのフルート音楽の記事にコメントをいただきました方々には、誠に申し訳なく思っています。 一つも返信を書かずにいます。 体調よくなれば従来のように返信させていただきますので、お許し下さい。ブログを書いていてこれで絶筆となったら(予めわかっていれば)、どんな曲を選ぶだろうかと時々思うことがあります。 結果はこれを書きたいという曲が出てこないのです。 やはりその日の記念に関係する曲を選ぶのかなと思っていますが、皆さんはどうでしょうか、どんな曲を選ぶのでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 トゥリーナのピアノ音楽私は機会あるごとに日記に書いていますように民族音楽というジャンルが大好き人間でファンです。 理由の第一は、絶対音楽に比べて非常に理解しやすいからです。 旋律は親しみやすく、平明でしかも美しい彩りを施された音楽だからです。 ロシア音楽、ハンガリー音楽、ジプシー音楽、スラブ音楽、スペイン音楽や中南米音楽など、非常に聴きやすく直截的に心の琴線に触れてきます。そんな中でもスペイン音楽は最も親しみやすく、平明な音楽として大好きなジャンルです。 今日はその好きなスペイン音楽からピアノ曲を採り上げてみました。 作曲家はホアキン・トゥリーナ。ホアキン・トゥリーナ(1882-1949)はファリャと同じくスペインのセビリアで生まれた作曲家です。 室内楽作品やギターやピアノのような器楽曲や管弦楽曲などを書き残しています。スペインの他の作曲家、例えばファリャと同じようにフランス・パリに滞在してダンディに音楽を師事しています。 当時のパリにはスペインからはアルベニスなどもおり、交流があり、ラヴェルやドビッシーなどとも交友があったそうです。トゥリーナの書いた音楽はスペインのアンダルシア地方の民族音楽に非常に影響を受けていると言われています。 その作品にはこうしたローカル色豊かな色彩が色濃く施されており、今日の話題のピアノ音楽でもそうした影響が濃厚に刻まれており、とてもスペイン風のロマンティックな情緒と、熱いスペイン民族の血のたぎりのような熱気がムンムンするような雰囲気とが交錯しています。Naxosからトゥリーナのピアノ作品集が2枚リリースされていますが、私が聴いていますのは録音年の新しい第2集です。 このディスクには、「スペインの主題によるロマンティックなソナタ」「幻想的ソナタ」「ソナタ形式の行進」「管弦楽のない協奏曲」が収録されていて、どの曲も前述のようにスペイン色濃厚な彩りが添えられており、甘いロマンの香りと熱気に溢れたピアノ音楽が展開しています。このCDです。 「トゥリーナ・ピアノ作品集 第2集」 ホルディ・マソ(P)↓(Naxosレーベル 8.557438 2004年7月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1897年 誕生 ジョージ・セル(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 紫陽花(伊豆の華)大阪市の長居植物園に紫陽花園があり、毎年写真を撮りに出かけています。ここの紫陽花園は花の種類としては決して多くはないのですが、花のすぐ近くで撮れる利点があってマクロレンズの使用が可能ということもあり、自宅からJR普通電車で30分という便利さも手伝って、今年で4年目の撮影となるほどに楽しみにしています。 この紫陽花園で咲く私の最も好きな種類の「伊豆の華」を今日は掲載しました。(伊豆の華) 撮影地 大阪市立長居植物園 2006年6月24日
2007年06月07日
コメント(16)
-

ゴべールのフルート音楽/毒だみ
『今日のクラシック音楽』 ゴベールのフルート音楽最近はNaxosのカタログを読むのが楽しみになっています。 新譜についてはNaxos JapanかHMVのホームページでチェックしています。今日は昨年5月に購入しましたフルート音楽を採り上げました。フランスの作曲家で自身が卓越した技巧を誇ったフィリップ・ゴベール(1879‐1941)が書き残したオリジナルのフルート音楽と有名曲のフルート演奏を編曲した音楽を収録したディスクです。ゴベールはパリ音楽院で指揮とフルートを教えていたそうで、先ごろ東京都交響楽団を振って引退公演を東京でおこなったジャン・フルネもゴベールに指揮とフルートを師事したそうです。さてこのディスクは「ゴベール・フルート作品全集 第3集」というタイトルで、ゴベール自身が書いたオリジナル曲が12曲、編曲集が12曲が収録されています。 フルート独奏がボストン交響楽団フルート奏者のフェンウイック・スミス、ピアノ伴奏がサリー・ピンカスというアメリカ人奏者というのも意外です。 このCDの最初の曲「二つのスケッチ」の”平原の夕暮れ”が始まると、「あれ、ドビッシーの牧神の午後への前奏曲?」と思ってしまうほどそっくりなんです。 どうしてこういう音楽の始まり方をしているのかはわかりませんが、ほんとにそっくりなので驚いてしまいますが、すぐにゴベールのオリジナルに展開していきます。フランス音楽らしい洗練された美しさがどの曲にも溢れていてとても優美なフルートの世界に浸ることができます。 私が特に気に入ったのは上述の「2つのスケッチ」、「シシリエンヌ」、それに2つの「ロマンス」。 ゴベールはフルート奏者としても卓越した技量を持った演奏家でもあったそうですが、これらの曲はフルートの魅力を充分に知っていて、その魅力を存分に聴かせるという音楽ばかりです。 キラキラする輝きがあるかと思えば影のある低い音の美しさも伝えており、聴いていて間然とすることがありません。 曲はどれも短い小品ばかりで、長い曲でも7分強ですから、彼のオリジナルをその時の気分に合わせて聴いています。編曲の方はバッハ、モーツアルト、ベートーベン、シューベルト、シューマンやショパンから選んだ超有名曲ばかりで、これもその時の気分に合わせて聴いています。 「トロイメライ」などはオリジナルが美しい旋律ですから、こうしてフルートに編曲されたのを聴いてもシューマンがフルート用に作曲したように聴こえてくるのが不思議です。2006年5月にリリースされた新録音で、これらの曲を聴いていますと前作第1集、第2集も聴いてみたくなります。またNaxosがいいディスクをリリースしてくれたと喜んで聴いています。↓「ゴベール・フルート作品全集 第3集」(Naxosレーベル 8.557307 2003年4月-2004年4月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1804年 誕生 ミハイル・グリンカ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 毒だみ道端や空き地・畑の畔・公園の植え込みなど、どこにでも見かける小さな花です。 こうしてマクロレンズで覗いてみると、なかなか可愛い表情をしています。 撮影地 大阪府和泉市どくだみ科 ドクダミ属 開花時期 5月中旬~6月末頃 葉や茎は漢方薬となっていて「どくだみ茶」というのがあります。
2007年06月01日
コメント(14)
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
-

- 人気歌手ランキング
- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…
- (2025-11-15 04:58:28)
-
-
-

- 70年代サブカルチャー URC, ELEC, …
- まんだらけの優待のまんだらけZEM…
- (2023-06-24 23:18:46)
-
-
-
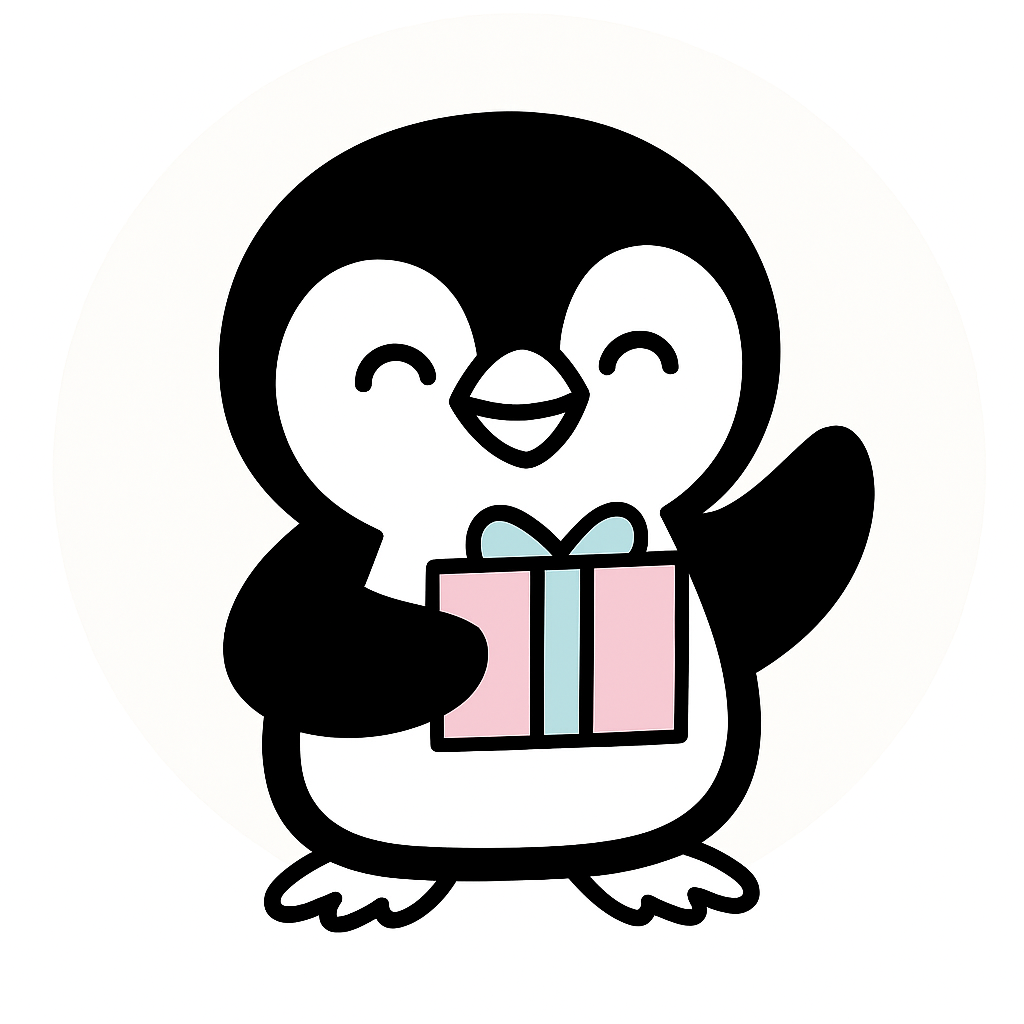
- やっぱりジャニーズ
- 楽天予約 SixTONES Best Album「MILE…
- (2025-11-20 16:44:46)
-







