2009年08月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
歴史的大敗
いやあ、歴史的な大敗でしたね! 大物というか、いつもなら絶対勝てる人が次々とあえなく破れ去っていって、結果は目を覆うばかり。歴史的に見てもこんなに負けたのは初めてなんでしょ? もう随分前から「今回は厳しい」と言われてきたのに、その対策をしてこなかったのが響いたんじゃないかな。もちろん上層部や本人たちは「対策は十分したつもり」と言うでしょうけど、それが十分じゃなかったことはこの結果がはっきりと示しています。 もちろん、これですべてが終わったわけではありません。次は立場逆転、今度はチャレンジャーとして、再び頑張ってもらいたい。そして・・・ ・・・金メダルを沢山とって欲しい! え? 何の話かって? そりゃ、世界柔道で男子が大負けしたって話ですよ。内柴も負け、棟田も負け、穴井も負け・・・。世界大会で金メダルが一つも取れなかったのは、史上初なんですよ! ったく! ちなみに、女子選手も含め、負けた選手全員に共通するのは、「寝技をやらない選手」であるということ。試合運びの中で畳の上に倒れた場合でも、相手をほっぽらかしたままさっさと立ちあがっちゃって、寝技に入るそぶりすら見せない選手がこぞって負けています。逆に勝った上野選手を御覧なさい、寝技をやるべき時には必ずやっている。また以前は立ち技ばっかりだった福見選手も、今回は寝技も視野に入れていた。だから勝ったんですよ。 だから、日本柔道も立ち技や足技で相手を投げ飛ばすことばっかり考えているようじゃダメ、ダメ。外国人選手はなかなか組ませないし、手足が長くて背負い難いんですから。それに立ち技勝負だと偶然負けることもある(穴井選手の場合のように!)けど、寝技勝負は、必ず強い方が勝つ。だからこそ、男子柔道は今後、寝技・絞め技に重点を置いて技を磨くべきなんですよ。篠原さん、聞こえてる? というわけで、今回の歴史的大敗を受け、日本柔道、特に男子柔道は、寝技・絞め技に活路を見出すこと! これが教授の処方です。 じゃ、自民党の方の処方はどうなのかって? もう、ここまで負けちゃあ仕方がない。自民党員は全員脱党して、民主党に入党しなさい! それで君らは明日からも与党だ!
August 31, 2009
コメント(4)
-

それでいいんか、ディーン・クーンツ
先日来、暇を見てちょこちょこ読んでいたディーン・クーンツの『Forever Odd』というサスペンス(?)を読了しました。で、最後まで読んで、ちょっとビックリ・・・。 ま、さすがはアメリカのベストセラー作家の手になる作品ですから、スラスラ読ませることは読ませるわけ。文章自体もまあ、月並みかも知れないけど、なるほどと思わせるような感じで、例えば "Holding my breath, I lay listening to the silence, and felt the silence listening to me." 「息を顰め、ベッドに横たわったままじっと暗闇に耳を澄ますと、暗闇もまた息を顰めて、僕の様子を伺っているのが感じられた」 といった感じの文がバンバン出てくる。要するに、調子がいいわけですよ。 で、内容はと言いますと(オチまで言いますから、要注意!)、オッド・トーマス君という主人公がおりまして、彼は未練があってこの世に留まっている死者の霊魂が見える、という特殊な能力の持ち主なんですな。で、ある時、彼は彼の親友のダニーの義父という人の霊の訪れを受けるわけ。しかもその様子から、彼が何者かに惨殺されたことが分る。 で、知人の警部に連絡しつつ、自分も現場に行ってみると、案の定、彼は殺されていたばかりか、親友のダニーまで誘拐されていることを発見するんですな。 ところで、その誘拐されたダニーなんですが、彼は全身の骨が非常に脆いという特殊な病気にかかっておりまして、ちょっとしたことでもすぐ骨折してしまうんです。そんな彼が何者かに誘拐されたとなると、彼の身にひどいことが降りかかるであろうことは目に見えている。親友の危機に、オッドは動揺します。 と、そんなオッドのもとに見知らぬ女からの電話が掛かってくる。どうやらこの殺人・誘拐の首謀者らしく、ダニーを助けたくば、一人で追ってこいというチャレンジをしてくるわけ。 実はオッドには、霊魂を見る能力だけでなく、自分と深い関わりのある人物の居場所が分るという能力もありまして、この謎の女は、ダニーを誘拐することによって、オッドの能力を試しているらしいんですな。かくして、親友・ダニーを奪還すべく、オッドは誘拐者たちの後を一人追うんです。そして、とある古いカジノ、地震と火事による被害により今は廃墟となっているカジノに立てこもっている謎の女の一味を見つけ、彼らに囚われているダニーを助けるべく、オッドの孤軍奮闘が始まる、と。 ところで、ここでオッソロシイのが、敵の首謀者たる謎の女・ダチューラなんですな。 この女、実は心霊マニアでありまして、心霊に関することになると異常なまでの興味・関心を示し、心霊スポットへ行っちゃあエクスタシーに到達するという変な奴なわけ。ただ、それほどのマニアにして、彼女はまだ霊魂を実際に見たことがない。それで霊魂を目に見える形で呼び出せるほどの霊能者を探していたわけですよ。で、あるきっかけでダニーと知り合い、彼からオッドのことを聞いたダチューラは、オッドを利用すれば霊魂が見られるようになるのではないかと考え、ダニーを使って彼をおびき寄せたようとした、と。 何せ、ダチューラは狂気の人ですから、自分の目的を果たすためなら何でもやりかねません。しかも彼女は、自分の狂気オーラで虜にした手下が二人いて、この屈強の男たちもダチューラの命令なら何でも従うという状態にある。さて、この状況下で、しかも病気のために身体が極端に虚弱なダニーを、オッドは助けられるのか?! とまあ、そんな話です。 で、この辺までの筋書きからすると、面白くなくはないんです。しかも、ダチューラという女の狂気の描き方なんてのはなかなか良くて、マニアックな人間の恐ろしさというものがよく描けている。ですから、途中三分の二くらいまで読み進んだところまでは、「ひゃー、この先どうなるの、どうなるの!」と思いながら楽しく読めるんです。 が・・・。 この先がね、悪い意味で驚くような展開を示すんだな~。(再度、ネタバレ注意!) だって、一度は何とか逃れたものの、再びオッドがダチューラに捕まり、もうダメだ! 絶対絶命! となった瞬間、どうなると思います? たまたまそこにピューマ(アメリカ・ライオン)が通りかかって、ダチューラが食われてしまう、ってんですよ! ありえねえ・・・。半端ないくらい、ありえねえ・・・。 いや~、ビックリした。ビックリするでしょ? いくらなんでも、脈絡なく登場したピューマに食われるって・・・。 実はワタクシ、この辺まで読み進めながら、もっと複雑な展開をするのだとばかり思っていたんです。 例えば、実はこの事件の本当の首謀者は、ダチューラではなく、ダニーだった、とか・・・。つまり、ダニー自身が自分の誘拐を演出しつつ、ダチューラを使って義父を殺し、親友であるはずだったオッドまで殺す計画を立てていた、なーんてね。そこに身体の弱いダニーの、オッドに対する積年の嫉妬とか、そういうものが絡んでいた・・・。 ところが実際には、そんな複雑な人間感情なんてありもせず、たまたま通りかかったピューマがすべての事件を解決してしまうってんですから、もうガックリよ・・・。 っつーことで、初めて読んだディーン・クーンツの作品ですが、あまりの唐突なオチに言葉を失ったワタクシなのでございます。読後、一応この作品のレビューを見ましたけど、あまり好意的なのはありませんでしたね。そりゃ、そうでしょうな。 かくして、クーンツの『Forever Odd』、教授のおすすめ! というレベルには到達しなかったのでありまーす。残念でした~! ちなみにこの作品の前の作品、つまりオッド・トーマスが初めて登場する『オッド・トーマスの霊感』とかいう作品には邦訳もあって、それなりに評判がいいようですから、興味のある方はそちらを読まれるといいのではないでしょうか。こちらは、オッドと彼のガールフレンドたるストーミーとの悲恋の物語(『Forever Odd』にもチラホラと言及される)が扱われるようですから、「泣ける恋愛サスペンス」として面白いのかもしれません。これこれ! ↓オッド・トーマスの霊感
August 30, 2009
コメント(6)
-
上野順恵を称える
世界陸上の次は世界柔道と、深夜のスポーツ観戦が続いておりますが、昨夜の女子柔道63キロ級・上野順恵選手は強かったねえ! 全戦一本勝ち、それも圧倒的な強さで優勝、素晴らしい! 63キロ級というと、何しろオリンピック2連覇の谷本歩実選手がいる階級なので、これまでその陰に隠れてどうしても表舞台に出られなかった上野選手ですが、今回はその憂さを一気に晴らすような勝ち方でした。彼女、完全に一皮剥けた感じがします。 大体、上野選手は谷本選手にも勝つんだよね。だけど、谷本選手というのはどこか華があるし、柔道連盟を含む世間の覚えがめでたいもので、それを押しのけて日本代表に選ばれるというのは至難の業。世間は谷選手や中村美里選手や谷本選手が勝つドラマが見たいんですから。しかし今回の世界大会での勝利によって、福見選手と上野選手が、谷・谷本両選手を押しのけ、ドラマの主役になる可能性大だなあ。今後の女子柔道は、福見・中村・上野のラインで行くんじゃないの? もっとも、そうなると今度は福見選手と階級の重なる山岸絵美選手の代表入りが難しくなるなあ。私が強く推す山岸も強いんだけどなあ。 それはともかく、今回の上野選手は強かった。必殺の大外刈りも良かったけれど、ここ最近、彼女は寝技に格段の進歩を見せているので、国際試合では今後ますます活躍が期待されるでしょうな。今回の決勝戦にしても、袈裟固めを決めた上野選手、相手選手を押さえ込みながら笑ってたもんね。 谷本選手の陰に不遇をかこちつつ、腐らずに努力して今回の大勝利を手に入れた上野順恵選手、あんたはエライ! この調子で頑張って、次のオリンピックで金メダル獲ってよ! それからも一つ、今回の世界柔道を見ていて思うのは、開催地オランダの観客の見巧者ぶり。さすがオランダは柔道の盛んな国だけあって、観客も柔道を良く知ってますな。だから試合中でもどちらかの選手が消極的だったり、「掛け逃げ」をすると、とたんにブーイングですわ。 それから一方の選手が相手を寝技で攻め立て、いい形になりかけた時に審判が「待て」をかけたりすると、これまた大ブーイング。ある意味、審判よりよっぽど柔道のことがよく分ってますよ。ああいう「よくわかった」観客に見守られて柔道をするのって、気持ちがいいだろうな。審判以上に公平な判断をしてくれるんだもん。 というわけで、今回の世界柔道に関しては、上野選手をはじめとする参加選手の皆さんだけでなく、観戦に詰めかけたオランダの柔道ファンに対しても、私は大きな拍手を送りたいと思うのであります。
August 29, 2009
コメント(0)
-
宿題のあり方
今日は10月から始まる教育実習に関し、勤務先大学の実習生を受け入れて下さる実習校に事前のご挨拶をすべく、愛知県は犬山市と小牧市の小学校に出張して参りました。 この事前挨拶、いつもですと割と形式的に終わることが多く、それこそ5分、10分で引き上げることもよくあるのですが、今回は割と時間が掛かりましてね。というのも、今日び教育の現場は「新型インフルエンザ」に恐々としているようで、その対策をどうすべきか、大学としてはどういうつもりなのか、細かく聞かれてしまったからです。 というのも、少子化の折、一学級の人数も少なくなっていて、例えばひとクラス3人の児童がインフルエンザに罹ったら、もうそれで「クラスの一割」に達してしまって、即、学級閉鎖なんてところもざらにある。それで所定の教育実習のスケジュールがこなせなくなった場合、単位を出していいのかどうか。それとも実習期間を延長すべきなのか。逆に実習生がインフルエンザに罹った場合はどうするのか。ま、そんなことを延々尋ねられて往生しましたわ。 仕方がない、即答できない部分についてはその場で大学と連絡をとったりして、それでもどうにか質問攻めを切り抜け、実習校回りの責務をこなしたワタクシ。あーあ、疲れちゃった。 というわけで、その疲れをアートで癒すべく、今日は出張先にほど近いところにあった「メナード美術館」というところに行ってきました。 その名の通り、化粧品会社のメナードの創立者が作ったこの美術館、小ぶりながら収蔵されている作品は割と粒ぞろいで、日本の画家ですと安井曽太郎、岡鹿之助、東山魁夷、前田青邨、坂本繁二郎、小絲源太郎、岸田劉生、杉本健吉、熊谷守一、島田章三などの作品が、また外国の画家ですとアンリ・ルソー、クロード・モネ、ポール・セザンヌ、ワシリー・カンディンスキー、アンリ・マティス、ジョルジュ・ルオー、フェルナン・レジェ、パブロ・ピカソ、ジョルジュ・ブラック、マルク・シャガール、ジョアン・ミロ、アンドリュー・ワイエスなどが展示されている。今日の展示では、アンドリュー・ワイエスの作品と熊谷守一の作品でいいのがあったなあ。 というわけで、これらのアートを鑑賞し、実習校回りの疲れは大体とれたのですが・・・、実はこの美術館でもまたひとつ、ちょっとしたストレスに晒されまして・・・。 いや、多分「夏休みの宿題」か何かなんでしょうけど、中学生の男女が三々五々、この美術館を訪れておりまして。しかしながら、彼らはどうもこれらアートの何たるかにはまるで興味がないらしく、部屋の中ほどに置いてある長椅子を占領してぺちゃくちゃとおしゃべりに興じていたり、部屋から部屋へと友達を探して渡り歩いている奴がいたり、とにかくせわしないこと限りなし。おかげでワタクシ、本当ならもう少しここでのんびり過ごしたかったのですが、さすがにこいつらと一緒では嫌だなと思って、一通り見ただけで出てきてしまったんです。 で、思うのですが、日本の中学生だの高校生なんてのには、こういうものを見せても意味がないのではないかと。そのことは、例えば「修学旅行」と称して彼らに奈良や京都の神社仏閣を見学させることの無意味さにも通じますが。だから「夏休み中に、どこそこ美術館へ行って展示を見て、感想を書いてこい」的な宿題は、出さないで欲しいんですよね。 やっぱりね、こういうものは見たい人、見る必要がある人、見る準備がある人だけが見ればいいので、動機のないガキに見せても猫に小判、豚に真珠でございますよ。むしろ、美術館・寺院などは原則成人のみに公開し、未成年への公開は親の同伴か、あるいは学校長等の紹介状を要す、としたらどうでしょう。大体中学・高校なんて年頃の連中は「見ろ」と言えば見ないし、「見るな」と言えば見るものですし。 ということで、「釈迦楽党」のマニフェストに、「大人のものは、子供には見せません」という一項を盛り込みます。さあ、あなたの清き一票を!
August 28, 2009
コメント(2)
-
思うようにいかない日
イギリスの児童文学の傑作、と言っていいのだと思いますが、『メアリー・ポピンズ』というのがあります。まあ、不思議なナニー(=子守&家政婦)の話なんですが、ある時、彼女が面倒を見ている子供の一人が朝から何をやってもうまくいかなくてむしゃくしゃしていると、メアリーは「あなたは今朝はベッドの反対側から起きたでしょう、だから何もかもうまくいかないんです」と言うんです。 で、子供が「僕のベッドは壁際に寄せてあるから、反対側からは起きられないよ」と言うと、「いいえ、あなたは反対側から起きたんです」と決めつけるわけ。 私は、このメアリーの言い方は真実をついていると思うんですよね。 で、今朝、どうやらワタクシも、ベッドの反対側から起きてしまったらしいんです。もう、今日は朝から何をやってもうまくいかない。 銀行に行けば、私の望む手続きは本店でないとできないと言われる。郵便局でもタライ回しにされた挙句、結局今日は予定のことができなかった。髪の毛を切ろうと床屋に行くと、一番下手な人が客待ちしてる。メールを書こうとしたら、急に漢字変換しなくなり、全部ひらがなか、全部カタカナになってしまう。そのうち、パソコン自体がロックされ、パスワードが思い出せない(そもそもそんな設定したことがない)・・・。 あー! もうっ!! まったく、今日は何もかもうまくいかず、イライラしっぱなしですわ。 こういう時は、もうなにもかもほったらかして不貞寝でもしたいところですが、そうもいかず。ヤレヤレ・・・。 ところで、選挙が近くなってきましたが、最近の日本の選挙はますますアメリカ化しているというのか、政党同士がライバル政党を批判したパンフレットなんかを配るようになりましたね。 で、今日、そんなパンフが入っていたので、見るともなしに見ていると、自民党が民主党の政策を目いっぱい批判している。「民主党に騙されるな」というような文字が躍っているのですから、なかなか穏やかではありません。 で、どう騙されちゃいけないのかと思って読むと、その中の一項に教育関係のことがあって、「自民党が苦労して作った教員免許更新制度を、民主党は反古にしようとしている」なんて書いてある。 あ、そうなんだ。民主党は教員免許更新制度を見直しすると言ってるんだ。 じゃ、民主党に入れようかな。 今年から始まった教員免許更新制度、うちの大学も担当しているので、先日ワタクシの同僚が講習を担当したんですけど、あとで聞いてみたらものすごくやりにくい講習だった、というんです。 そりゃそうでしょう。中学・高校の現場で二十年も三十年も教えている大ベテランの先生方をですよ、現場の経験もない大学の先生が、どう「指導」し、どう「成績をつけ」ればいいというのでしょうか。場合によっては大学院出たての若造が、40代、50代の働き盛りの先生方に「教え方の指導」をするんですからね。 で、講習に来られている先生方も、当然面白くないわけですよ。だから、中にはその「面白くない」という気分を、態度に表わす先生方もいる。と、そうなれば教える側の大学教員もものすごくやりにくいわけ。 でも、この教員免許更新制度とやら、ちょっと考えればこういう事態になる、ということくらい、誰でも分かるだろうと思うんですよね。だったら、教える側、教わる側ともにやりにくい制度をどうして作るのか。 最近何だかたるんでいる中・高の先生が多くて、事件なんか起こす人もいるから、適当なインターバルでカツを入れ直すようにしちまえ、という安易な発想。それだけだと思うんですよね。 ま、現政権政党なんてこの程度のもんなんですから、この際、あんたらこそ国民にカツ入れてもらった方がいいんじゃないの? ということで、自民党の「民主党に騙されるな」のパンフレットを見ながら、逆の反応を示したくなってきたワタクシなのでありました、とさ。ま、投票までにもう少し考えますけどね!
August 27, 2009
コメント(2)
-
卒業生たちからの便り
マイケル・ジャクソンの死因がプロポフォールの致死量を超える使用、ということにほぼ断定されたようですが、薬好きの私、「プロポフォール」という薬品名に聞き覚えがあったので調べてみたら、私も使ったことがありました。数年前、全身麻酔をかけて親知らずを全部一遍に抜いた時、使用したのがこれだったんです。ま、もちろんこの薬の投与で私は完全に意識を失っていたわけですけど、そんな強い麻酔薬を睡眠剤代わりに使っていたとは。そりゃ、体に悪いわ・・・。 さて、このところ卒業生たちからの残暑見舞いの便りが立て続けに届いています。 一人は一流のパティシエになるべく、フランスに修行に出ているNさん。フランスに行ってからもう3年目くらいかな? 当初は南仏でも有名な菓子店で修行をしていたのですが、今年リヨンのお店に移ってからは、お菓子修行と同時に学校(大学?)にも通うようになったようで、朝仕事、昼学校、夜また仕事、というハードなスケジュールで頑張っているとのこと。いやあ、彼女、頑張るなあ。もうフランス語もぺらぺらじゃないでしょうかね。日本人の繊細なお菓子作りの腕をもってすれば、このままフランスで一流パティシエとして名を挙げることもできるんじゃないかと思います。素晴らしい! 二人目は、今年ご主人の仕事の関係で名古屋を離れ、北海道は旭川へ引っ越されたHさん。夏の北海道を堪能されたそうですが、日本でももっとも冬の厳しいことで知られる旭川はすでに秋に入ったようで、この先10月から冬になり、そして厳寒期にはバナナで釘が打てるとのこと。本当にそれができるか試してみたい、などと頼りに書いてありましたが、さてさて、温暖な名古屋から移って初めての冬、Hさん、風邪ひかないでよ! 三人目は、子育て真っ最中のYさん。最近、同窓のAさんがご主人の都合でアメリカはアラバマ州へ引っ越されることになり、それを機に仲良しの数人で集まってミニ同窓会をしたとのこと。で、その場で同窓生の皆がそれぞれ頑張っているのに刺激を受け、Yさんも「子育てを理由に何もしないのはよくない」と思うところがあったらしく、子供に英語を教えるための講習を受けることにしたとのこと。文面には、自分なりに新しい第一歩を踏み出したことに対する溌剌とした思いが溢れていて、なかなか微笑ましい。Yさん、一旦やり始めたら、時間はかかってもやり遂げるんだゾ! ということで、三者三様の便りを読み、卒業生って可愛いなと改めて思いつつ、そういう報告を受けた私自身も頑張らねばと思う今日この頃なのでありました、とさ。
August 26, 2009
コメント(0)
-
外人さん向けのお土産に悩む
今日のひと言: セミって、死ぬ前の最後の1週間だけセミの格好をしているので、それまでの7年間は土の中で別な形をしてるんですよね・・・。それもある意味、不思議ですけど、もし人間もそうだったら、と考えるとちょっと怖くないっすか・・・。死ぬ前の1週間、別な形になったら! (ホラーだよ・・・。) さて、今日も今日とて渡米準備のため、名古屋・栄のシティバンクで色々手続きをしたりしてたんですが、せっかく栄まで出るならばちょっとおいしいランチでも食ってやるかということで、家内を連れて「TOPE」に向かいました。 この「トペ」というお店、以前にも一度このブログで取り上げましたが、栄の穴場ですよ。今日、我々はスペシャル・パスタランチを注文しましたが、まず冷製のマッシュルームのスープ(絶品!)が出て、次に5品の前菜(玉ねぎのキッシュ、鯛のエスカベッシュ、フリッタータ、タコのマリネ、パテ)が来る。この前菜がどれもおいしくて。そしてメインのパスタがまた手が込んでいて、私は「大根と秋刀魚のペペロンチーノ」、家内が「パンチェッタと夏野菜のクリームスパ」でしたが、どちらもおいしかった。そして最後はデザート(ティラミスとジェラート)とコーヒーで、これで1580円ですからね! サーブしてくれるちょっと年配の男性の接客態度も素晴しく、言うことなし。名古屋にお住まいの方、あまり大きな声で言いたくはありませんが、ここ、おすすめですよ! そして、シティバンクでの用事が済んだ後、ロスに住む友人たちへのお土産を買うため、三越やら何やらを経巡っていたのですが、この土産物選びにはいつもながら難渋しまして。難しいですよね、お土産を買うのって。そりゃ、値段の高いものを自由に買えるのならいいですが、そこはやはり予算の問題もあるので、「このくらいの値段のもので」という条件がかかってくる。でまた渡す相手が外国人ですから、外国人受けしそうなものがいいかなあ、という思いもある。 となると何? 漆器とか? 陶器? 江戸切子? 千代紙? 絞り染め? はたまた七宝? 真珠? あるいはソニーの電化製品? というわけで散々歩き回ったものの、大した獲物は得られず・・・。 どうでしょう、海外へお土産を持っていった経験のある方で、「あれはウケた」というようなものがある方、悩めるワタクシにご教示下さい。よろしくお願いいたします。
August 25, 2009
コメント(4)
-
国際免許を取る
今日のひと言:みかんジュースの「プラッシー」を見て、懐かしさに興奮するのは、多分40代半ばの人間だ。(今日飲んじゃった! なぜかお米屋さんで売ってるんだよね!) 9月をロスで過ごすため、今日は国際免許を取りに行ってきました。NYと違って、ロスはクルマがなければどうにもならない街なのでね。その点、名古屋と似ているなあと思ったら、両者は姉妹都市なのですな。 で、平針というところにある愛知県の運転免許試験場に行ってきたわけですが、うーん、運転免許試験場って、なんだか雰囲気がスゴイね。 クルマの免許に関することであれば、取得や更新、紛失手続きや返納、はたまた国際免許の取得などなど、すべてここが窓口になるのでしょうが、それだけに色々な人がここにやってくる。そのバラエティーが異様なわけですよ。 茶髪の兄ちゃん・姉ちゃんがいる。ブラジル人がいる。サラリーマンがいる。主婦がいる。お水系の姐さんがいる。堅気じゃなさそうな危ない人がいる。おじいさんがいる。長椅子に座って得体の知れないことをぶつぶつ呟いているおばあさんがいる。そしてワタクシのようなジェントルマンもいる。これほどバラエティーのある集団が一堂に会す場所って、他にもありそうで、案外ないんじゃないかな・・・。 っつーわけで、世の中には色々な人がいるなあと、実感したワタクシだったのでありました、とさ。 それにしても、ここで私は世間に対して一つ提案したいのですが、「証明書写真」のサイズをすべて統一してはいかがでしょうかね? 例えば私、先日パスポートを新たに取得するのにパスポート用の写真を撮ったわけですが、その時に余った写真を今回の国際免許にも使いまわそうと思ったら、サイズが違って使えないんですよね。だから今日は今日で別に写真を撮らなければならなかったんですけど、これは明らかに無駄ですわ。 ということで、「証明書(含む履歴書・運転免許証)用の写真はすべてこのサイズ」というのを全国的に、あるいは万国的に制定せよ、ということを私はこの場から発信したい。いささか非力な意見発信の場ではありますが、賛同される方、リレー方式でこのアイディアを世界へ向けて広めて参ろうではありませぬか!
August 24, 2009
コメント(4)
-
名古屋に戻る
さあて、今日はこれから名古屋に戻らなくては。 二週間弱の帰省でしたが、毎日、それなりにイベントがあって、のんびり家で過ごしたのなんてほとんどありませんでした。やはり普段、東京から離れて住んでいるので、たまに帰ると、やっておきたいこと、やっておかなければならないことがたまっていまして、それを一気に全部片付けようとするものだから、これで結構忙しいんです。 しかし、「今日は帰る日」となると、何となく心残りがあって、なかなか落ち着いて過ごせませんね。今日も何をするわけではないのですが、荷物をまとめたり、部屋の掃除をしたりして、なんだかそわそわとしていました。 その昔、まだ独り身で、名古屋の大学に赴任したばかりの頃、実家から一人名古屋に向かうのは寂しかったですが、それは「自分が寂しい」という意味だったんですね。当時はまだ両親もそれなりに若くて元気でしたですから、別に心配もしていなかった。 ところが最近、だいぶ齢をとってきた両親を残して名古屋に向かうとなると、「自分が寂しい」というよりは、「自分が名古屋に行ってしまえば、父も母も寂しいと思うだろうなあ」という気がして、それで後ろ髪を引かれます。私のように気の利かない、頼りない息子でも、若い者が近くにいれば、親としては何かと心強いでしょうからね。 まあ、そんなことを言っても仕方がないんですが。 とりあえず、今はまだ両親ともしっかりしているので、この状態が少しでも長く続いてくれと祈るばかりでございますよ。 ということで、これから母の手料理をごちそうになってから、ETC割引の恩恵を受けつつ、一足先に名古屋に戻ってしばらく自分の実家に帰省していた家内の待つ自宅に戻ります。明日からはまた名古屋発の「お気楽日記」、ご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
August 23, 2009
コメント(0)
-
コストコでお買い物
明日は名古屋に戻る日。自由に使える日は今日が最後ということで、今日は会員制スーパー、コストコにお買い物に行って来ました。 で、どうせ行くなら賑やかな方がいいだろうと思い、先日婚約した親友のTとそのフィアンセも誘ってあげることに。コストコは会員制ですが、会員一人につき二人まで非会員を連れていくことができるのです。 で、コストコには初めて行くというTとフィアンセ、お店に到着するやまずそのカートのでかさに一驚。確かに、日本のスーパーにおいてあるショッピング・カートの4倍くらいの大きさがありますからね。 そして店に置いてある商品が、このショッピング・カートに見合うようにすべて超ビッグサイズであることにもビックリしてました。何しろ、袋入りのポテトチップからして大型の枕くらいの大きさはありますし。牛肉の塊なんて、丸まって昼寝している猫くらいの大きさですよ。とまあ、そんな調子ですから、特にフィアンセのKさんはショッピング好きということもあって、コストコでの買い物を存分に楽しんでいた様子。やあ、こんなに喜んでくれるなら、連れてきた甲斐があったなあ。 で、私も私で「ダウニー入りタイド(=洗濯洗剤)の超デカボトル」「オランダ直輸入ビール24缶入り1ケース」「超デカ缶入り紅茶(リーフ)」「ティムタム4本セット」・・・と、買う予定の品を次々にカートに放り込みます。36個入りのコーンブレッドはTのところと分け合って・・・。 ってな具合で、ワタクシのところとTのところ、合わせてアルファロメオのトランクがほぼ満杯になるほどの買い物をし、合計2万円ほど。高いようですが、同じだけの量を日本のスーパーで買ったら、おそらく3万円を軽く超すのではないかと。そういう意味ではさすがにコストコ、抜群の経済性があります。 で、買い物の後はおやつタイム、というわけで、コストコ名物のホットドッグをフードコートで食べましたけど、これ、たった250円でコーラ付き、しかもコーラは何杯でもお代わり自由ですから安いですよね。しかも、これがうまいんだ! かくしてお腹もいっぱい、買い物もいっぱいになった我らは、意気揚揚と引き揚げてきたという次第。TもKさんも「絶対会員になる!」と言っていましたので、今回のコストコ・ショッピングはまずまず大成功というところでございましょう。 さてさて、これで今回の夏休み帰省のイベントは終了~! 明日はまた名古屋に戻ります。帰れば帰ったで、9月の渡米に備え、準備に大わらわとなることでしょう。楽しいような、面倒臭いような・・・。 ということで、明日からはまた名古屋からの「お気楽日記」、よろしゅうおたの申します。
August 22, 2009
コメント(2)
-

明野村ひまわりドライブ
実家で過ごす夏休みも残り少なくなってきたこともあり、今日は両親を連れてドライブに行って来ました。今日は箱根ではなく、小淵沢方面。 で、まず向かったのは長坂インターを降りて10分ほど走ったところにある蕎麦の店「いち」。このブログにもよく登場しますが、お気に入りの蕎麦屋さんなんです。場所がものすごく分かり難いところにあるにも関わらず、駐車場には他府県ナンバーの車がズラリ。人に遠路はるばるやってきてでも食べたい、と思わせるだけあって、実に美味。今日もおいしくいただきました。 さて、いちの後はお決まりのコースで、まずは「とりはた」でジャムを買い、続いて「月の手工房」にお邪魔して陶器とガラス細工を見ます。今日は奥様(あいざわ ゆみさん)が作られる繊細なガラスのオブジェを使ったネックレスを、来月二十歳になる二番目の姪っこのために購入しちゃいました。 しかし、今日はここからお決まりのコースを外れ、小淵沢のちょっと東南の方角にある「明野村」というところに向かうことに。ここ、日照時間が日本一長いということで、20万本のひまわりを植えた畑があり、この時期、満開を迎えているとのことで、この一面のひまわりを見てやろうと、まあ、そういう次第なのです。 で、到着したひまわり畑の様子をご覧ください。 ま、こんな調子でひまわりの海でございます。 で、ここでひまわりを担当した後、その向いにある施設、「山梨県立フラワーセンター ハイジの村」を覗いて行きました。 上の写真のように、ここはスイスの小村(デルフリ村?)を模した施設で、結婚式もできる教会やらレストランやら、土産物屋などが立ち並んでいるわけ。で、その先にはきれいに整備された花壇やら、「バラの回廊」などがあるんです。ま、その内容は・・・、やや子供騙しかなと思わないでもありませんが、それでも熱烈なる「ハイジ・ファン」のワタクシとしては結構、楽しかったかな・・・。園内には汽車を模したバスみたいなのも走ってますから、小さな子供には確実に受けると思います。 というわけで、今日は八ヶ岳南麓の空気をちょっと吸い、しばしハイジの世界に遊んで、過ぎゆく夏を惜しんできた釈迦楽家一同なのでありました、とさ。それにしても、東京に戻ってきたら暑いのなんの。やっぱり山の上は涼しいですね!
August 21, 2009
コメント(0)
-
恩師の家に遊びに行く
今日は、これも帰省中のお決まりのイベントですが、大学時代の恩師S先生の家に遊びに行きました。 大正生まれのS先生は、おん歳84か85だと思いますが、話を始めるとまるで以前と変わらず、自分が大学時代に戻ったような気がします。 とりわけ今日は、先日私が出版した本をお見せしたり、数日前に渋谷のデパートの古書市でゲットした先生のご著書をお見せしたりといった具合で、話の芽が沢山ありまして。で、ついでに、これも先日読了した安原顯氏の『「編集者」という仕事』という本の中にS先生のお名前が出てくることに触れ、S先生が安原氏のことを直接知っていたかどうか、もしご存じならば、先生の安原氏に対するイメージはどんなものか、を教えていただこうと、そちらの方面に話を持っていったんです。 そしたら、確かに安原さんと一緒に仕事をした記憶がある、とのことでした。で、その際、決して「嫌な奴だ」といった印象は一切感じられず、むしろ仕事熱心な人だなあと思われた、とのこと。S先生も安原氏に対して、特に悪いイメージは持ってない、ということなんですな。なるほど、なるほど。 ま、そんな話を先生と私でしていたら、それを聞いていらしたS先生の奥様が、「安原さんは、この家にも何度かいらっしゃいましたよ、自転車に乗って・・・」と教えて下さったんです。S先生のお宅は調布市深大寺にあるのですが、そういえば安原氏の自宅とはさほど離れていないかも。へーえ、そうだったんだ。自転車で、ねえ・・・。 というわけで、お尋ねしようと思っていたことが聞けて大満足。 で、安原氏との仕事の内容がアメリカ小説の翻訳のことだったため、そこから話は「翻訳」をめぐって色々と展開しまして。 ま、S先生がお若かったころ、つまり1970年代のことですが、この頃、大学の英文科とかの先生の仕事のかなり大きな部分は、英米の小説の翻訳の仕事に割かれていたわけですね。 で、そんな風ですから、ある程度名のある先生であれば、出版社から翻訳の依頼が結構な頻度で来る。そうなると、名のある先生は忙しくなり過ぎますから、自分より年少の同僚、すなわち同じ大学の助手とか助教授あたりに、「お前、下訳をやれ」と命じるわけですね。で、そうやって「下訳」をやっているうちに段々翻訳のなんたるかが大体わかってくると、今度はそういう若手が自分の名前で翻訳が出せるようになる。 ま、そうやって翻訳の仕事が大学の先生の仕事として、受け継がれていくというか、そういう感じになっていたわけですね。 ・・・という昔話を伺っていると、時代は変わったなあ、という気がしてきます。今、大学の同じ学科の中で、先生同士のこうした関係って存在しないですもんね。今や「隣は何をする人ぞ」状態で、若手が先輩教授から「俺の仕事の下働きをしろ」みたいなこと、言われないですから。もちろん、そのことにはいい点もありますが、良かれ悪しかれ、大学の中から「徒弟制度」が無くなったことは事実。 だけど、私なんかは、年齢の割に考え方が古いので、こういう徒弟制度にちょっと憧れはありますね。それとも、あれかな、そういうものが残っている大学もあるのかな・・・? いずれにせよ、たとえばその昔、冨山房なんて出版社から「フォークナー全集」が出たときみたいに、名のある先生方とその徒弟たちとが最大限の努力を注ぎ込んで、フォークナーの全作品を訳出しようとした時のような企画というか、そういう集中的な熱意のようなものが「大学英文科」業界にあるかっつーと、ないですもんね。 ま、「今、フォークナーみたいな作家がいないんだもん」と言われてしまえば、それまでですが。 というわけで、恩師S先生と翻訳をめぐる様々な話をしながら、そんなことを考えたり感じたりしていた今日の私なのでございます。 でも、S先生と清談をしたことで、なんか元気が出てきたなあ。実際に先生の仕事の下働きを命じられたわけではないけれど、S先生から元気をもらったことで、私にとっての「徒弟制度」がまだここにあるんだ、と思うことにしましょうかね。
August 20, 2009
コメント(2)
-
パソコンと苦闘半日
今日のひと言: 今更ですが、「パラパラ」って、一種のラジオ体操だよね! 我が姪っこは私の実家に下宿しておるのですが、その姪っこのパソコンがぶっ壊れまして。完全にぶっ壊れたというか、作業中に頻繁にダウンするようになってしまって、色々と支障が出るようになったと。 で、思い切りのいい彼女は、出荷状態に戻しちまえと、XPの再インストールを試みたんですな。私だったら、絶対にそんなことしないけど・・・。 で、再インストールをした後、ネットにつなげようとしたところ、どうもつながらないらしく、困り果てている様子。となれば、ここはひとつ、叔父さんがいいところを見せてやりたくなるじゃないですか。 というわけで、今度は私がパソコンのネット接続を試み始めたのですが、確かにうまくいかない。何で? そのうち、何となく原因がわかったのですが、「ネット接続」を開いても「ローカルエリア接続」というアイコンが出てこないことがどうやら諸悪の根源らしいんです。 じゃ、どうすればいいのかと思って、私のパソコンからネット検索をしたところ、「OSを再インストールしたら、ローカルエリア接続のアイコンが消えちゃった。どうすればいいの?」という質問が沢山あることが判明。どうも、こういう現象はよくあるパターンなんでしょうね。 で、そういう問いに対する答えはというと、これがまた不思議なものが多くて、「○○というプログラムをネットからダウンロードすればすぐ解決」なんて書いてある。 ・・・あのね、ダウンロードすればいいったって、そもそもネットにつなげないんだから、それ、答えになってないじゃないですかっ! というわけで、孤軍奮闘すること半日、結局、「私にはどうにもできん」という結論に達したのでありました。嗚呼、情けなや。頼りにならぬ叔父を許されよ、姪殿。 読者諸賢の中に詳しい方がいらっしゃいましたら、「ローカルエリア接続」を復活させる方法を伝授して下さーい。よろしくお願いいたします。
August 19, 2009
コメント(2)
-
東急東横店の古本市に行く
今日のひと言: 世に教訓を含んだ昔話の類は多いが、私の経験上、この種の昔話で一番優れている(=実社会で役立つ)のは、「北風と太陽」だと思う。 さて、今日は渋谷の東急東横店8階催事場で行われている夏の古本市に行って来ました。ま、休みの間に一回くらい、この種の古書市に行っておかないと、何となく気分が出ないものですから。 で、まず会場に入りしな、いきなり目についたのが須山静夫先生の名著『神の残した黒い穴:現代アメリカ南部の小説』(花曜社・1900円)の帯付き・愛読者カード付き・ビニールカバー付きの美本。お値段は1050円也。ああ、これが今日の古本の神様のしょっぱなの試みだな、と思ったワタクシ、すでにこの本を持っているにもかかわらず、ズバッと買い物かごの中に入れてしまいました。 すでに何回か書いたことではありますが、この種の古本市には「古本の神様」というのがいましてね、古本を買いに来る人を一人ずつ眺めている。で、神様はそういう人たちを試すわけ。つまり、その人が買うか買わないか、ちょっと微妙な本を一冊、最初の5分間のうちに提示するんですな。 で、その人がその本を買えば、古本の神様は「よし」と頷いて、そこから先、その人がいい本に出会えるよう、ツキをくれるんです。だけど、逆に神様がそっと指し示した本を無視した場合、神様はつむじを曲げて、いい本をその人の前から隠してしまう。だから、こういう古本市に来たら、最初の5分間のうちに少なくとも1冊、買い物かごに入れないとダメなんです。 かくして、神様の試みにパスしたはずの私。今日はいい収穫があるはず・・・。 ・・・だったんですが、そうでもなかったかな? それでも寺島靖国氏の『Jazz 晴れ、時々快晴』(山海堂・1680円)の美本を500円で、また絶版になった旺文社文庫の一冊、岩浪洋三氏の『ニューヨーク Jazzガイド』(380円)を200円でゲットするなど、ジャズ関係の本を何冊か買ってまずまずご満悦。ただ、コレクションしている池田満寿夫の本とか、ヘンリー・ミラー関係の本、それに折口信夫関係の本や歌舞伎関係の本などでめぼしいものが見つからなかったのがちょっと残念なところでしたかね。あと、洋書もまったくなかったな・・・。京王百貨店の古書市にはいつも洋書が出るんですが。 でも、ま、いいんです。古本というのは釣りと似ておりまして、釣れる釣れないも大事ですが、そもそも釣りに行くことそれ自体が面白い。それと同じで、日本各地の古本屋さんが一堂に会するこういうデパートの古本市に行って、古本がずらりと並んでいるところを一軒一軒見て回ること自体、我々古本ファンにとってはたまらなく面白いわけですよ。だから、収穫のあるなしはあまり関係ないんですな。 というわけで、今日は古本の山に埋もれた半日を過ごして、心地よく遊び疲れた私だったのでありました、とさ。
August 18, 2009
コメント(0)
-
7秒ルール
今日のひと言: らりピーさんの復帰作は『極妻』シリーズで決まり! 「おまえさんら、このおとしまえ、どうつけてくれマンモス!」 さて、今日も今日とてあれこれ読書に打ち込んでいたワタクシ、とりあえず玉村豊男著『種まく人』(新潮文庫)を読み終わり、前に買って、少し読み始めたまま放置してあったディーン・クーンツの『Forever Odd』に取り掛かりました。これ、この世に何らかの未練があって成仏できない死者が見えてしまう超能力を持った青年が、とある殺人・誘拐事件の捜査に関わることになる、という話なのですが、半分くらい読んだところでは面白いですよ。特に主人公の青年オッド君の知り合いというか友人の太っちょコックさん、オジー氏がなかなかの傑物でね。 ところで、急に話が変わりますが、「7秒ルール」ってご存知? 新たに知識を獲得しようという場合、それを完全に脳裏に刻み込むためには7秒の時間がかかる、というものなんですが。 このルール、私も最近、ある人から教わったのですが、記憶を研究している学者さんたちが言いだしたことが一般にも広まって、アメリカでは20年くらい前からよく言われていることらしく、本当に本当のことなのかは分かりませんが、「後ろ向きに歩くとしゃっくりが止まる」とか、そういう程度の科学的(?)な知識として広まっていることなのだとか。 でね、私も英語の小説なんぞ読んでいると、「あれ、この単語、何ていう意味だったっけ? 前にも辞書を引いたんだけど、また忘れちゃった!」なんてことがよくある。つまり、その単語は、一度辞書を引いて調べたにもかかわらず、ちゃんと脳裏に刻まれていなかった、ということですね。 で、それはひょっとして、「7秒ルール」を守らなかったからではないか、と。 そう思って、今日は『Forever Odd』を読みながら、未知の英単語に出会って辞書を引くたびに、その英単語とその意味を7秒間、頭の中で反復して覚えることをやってみたわけ。 するとね、「7秒間」というのが、かなり長い時間である、ということが分かりますね。 ということはつまり、今までは、未知の英単語を辞書で引いて、「あ、そういう意味ね」と分かった次の瞬間には、もうどんどん次の文章を読み始めてしまっていたんですな。 というわけで、私のように段々自分の記憶力に自信が持てなくなってきた年代の人間にとって、この「7秒ルール」というのは、それが本当に科学的な根拠のあることかどうかは別として、心しておいて損はないことなんじゃないかなと、まあ、そんな風に思ったわけでございます。 読者諸賢よ、せまい日本、そんなに急いでどこへ行く。これからは、自らの灰色の脳細胞に、7秒くらいの猶予は与えてあげようじゃありませぬか!
August 17, 2009
コメント(2)
-
穐吉敏子著『ジャズと生きる』を読む
日本が生んだ世界的ジャズ・ピアニスト、穐吉(あきよし)敏子さんの自伝、『ジャズと生きる』(岩波新書)を読了しました。日本人でジャズをやるということがどういうことなのか、ちょっと知りたくて読み始めたのですけど、穐吉さんのみならず、アメリカという国について、なかなか示唆に富む本でした。 穐吉さんは戦前の満州で生まれ育った方なんですが、やがて戦争が始まり、戦争が終わり、混乱の中で帰国される。で、満州でビジネスをされていたご両親も戦後の混乱の中で職が定まらない中、ピアノが弾けた十代の穐吉さんは、たまたま目にした人材募集のビラによってダンスホールみたいなところのピアニストの職を得る。で、そこでだんだん頭角を現していくんですね。 その辺の話はまるで藁しべ長者みたいで、小さな地方バンドから始まって、やがてそこに飽き足らなくなり、もっと大きなバンド、もっと有名なバンド、さらには東京のバンドへと、どんどん出世移籍していくわけ。もう、向かうところ敵なしと言う感じですが、当時の日本人バンドマンたちも偉いもので、「もっといいバンドに移籍したい」という若い穐吉さんのある意味身勝手な要求に応え、彼女の希望をかなえるためにバンドリーダーがもっといいバンドのリーダーに紹介状なんか書いてあげるんですな。というわけでやがて穐吉さんは、日本の頂点に立ってしまう。なにせ日本にいるうちからアメリカのレコード会社に目をつけられ、一足先にレコード・デビューまでしてしまったというのですから、大したものです。 となれば、次の夢はジャズの本場・アメリカへと向かうのは当然のことでしょう。で、ここでも穐吉さんは幸運に恵まれていて、知人のつてでニューヨークのバークリー音楽院への留学がかなうことになる。 で、当時のプロペラ機でやっとこさっとこロスまで着いて、とりあえずその日はそこに泊まることにして、ロスのジャズ・クラブを覗いたところ、誰が知らせたのか、かの名ピアニスト、ハンプトン・ホーズから彼女宛てに電話がかかってきた、と。ホーズはかつて横浜の軍楽隊に所属していた時に穐吉さんのことを知り、その彼女がアメリカに来ることを聞いて、電話をかけてきてくれたんですな。 で、彼に誘われるまま、別なジャズ・クラブに行ってみたら、そこにマイルス・デイヴィスが居た、と。で、そのマイルスから「一緒にプレイするか?」と聞かれたというのですから、アメリカではまだ無名の日本人ジャズ・ピアニストとしては、目の回るような瞬間だったことでしょう。もっとも、その時は彼女も気おくれがして、せっかくのマイルスの誘いを断ってしまったそうですが。 ま、この辺の記述を読むと、おお、アメリカっていいなあ、と思いますね。無名だろうと何だろうと、まず人間として認め、もし実力があればジャズ・メンとしても認めようとする気風がある。 というわけで、周囲の人の好意も手伝って、いわばトントン拍子に本場アメリカのジャズ・シーンに飛び込んだ穐吉さんですが、実はここからが穐吉さんの苦闘が始まるんですな。 先ほど、実力さえあればバックグラウンドを問わず認めてもらえるのがアメリカだ、というようなことを書き、確かにそういう一面はあるのですが、やはりそんないい話ばかりではないのもまた、アメリカという国なんです。 最初のうちはまるで自分の娘であるかのように扱ってくれたマネージャーから、次第にひどい扱いを受けるようになってしまったり、穐吉さんが女であることから、バンド仲間から色目を使われたり、とにかく彼女は人間関係の上で様々な嫌な思いをすることになるんですね。で、人間関係だけでなく仕事の方もまったくうだつが上がらず、渡米して10年間というもの必死で努力したにも関わらず、まったく注目を浴びることができず、アメリカで名前を挙げるには、実力だけでは足りないということをいやというほど思い知らされることになるんです。そしてさらに最初の結婚に失敗したり、娘さんとの関係が悪化したりと、私生活もボロボロ。 穐吉敏子ほどの人ですら、日本人がアメリカでジャズをやるとなると、こういう困難が待ち構えていると。どうも、そういうことらしい。 しかし、それでも彼女は堅忍不抜の思いで歯を食いしばり、ジャズを続けるわけ。そして渡米してから35年くらいして、ようやく本場アメリカでの地位も確立し、何とか自分の思うような活動ができるようになってきたと。この本は、そんな穐吉さんの苦闘の歴史を振り返ったものなんです。 やっぱり、アメリカって国は甘い顔をしているようでいて、甘くないね。そのことが、この本を読んでいると、よーく分かる。 ま、穐吉さんという人は、さほどの文才はありません。ので、これほどのドラマを含んだ人生を語っている割に、そのドラマ性がページから立ち上ってくるというようなものではない。そういう意味での味わいというのを期待してはいけません。しかし、その淡々とした語り口を反芻しながら読み進めると、こりゃすごいわ、ということが分かる。そういう本ですね。それにこの本には色々と有名なジャズ・メンたちが登場しますから、ジャズ・ファンからすると、その点でも面白く読めます。たとえばピアノの巨匠、オスカー・ピーターソンの人柄とか、MJQのジョン・ルイスの志の高さとか、この本から知りえることも多いと思います。 ということで、日本が誇る世界的ジャズ・ピアニスト、穐吉敏子の自伝、教授のおすすめ!です。これこれ! ↓ジャズと生きる ただ・・・だからと言って、私が穐吉敏子のジャズをジャズとして認めているかと言うと、実はそうでもないんだなー。ま、その辺のごたくは、また後日。
August 16, 2009
コメント(0)
-
ポワロで一家団欒
今日のひと言:一度見てしまったら、デビッド・スーシェ以外のポワロ俳優は考えられない。 実家が入っているケーブルテレビ局では洋モノのドラマばかりやるチャンネルがあるのですが、夕方は『名探偵ポワロ』(再放送)を放映するもので、何となく釈迦楽家一同揃って見てしまいます。それにしてもこうして家族全員揃ってテレビを見るのって、なんだか久しぶりだなあ・・・。昭和の時代の「お茶の間」が復活したようです。 ところでその『名探偵ポワロ』、有名なテレビ・シリーズですからご覧になった方も多いと思いますが、デビッド・スーシェ演じるポワロに相棒のヘイスティングズ大尉、それにジャップ警部やミス・レモンといったお馴染みの登場人物たちが活躍するこのシリーズ、なかなかよく出来ていて、つい見てしまうもんですなあ。もちろん中には既に見たものもありますが、そこはそれ「年の功」といいますか、内容をすっかり忘れていて、犯人が誰だったかさっぱり思い出せないので、何度見ても面白いという・・・。 それにしてもポワロ演じるデビッド・スーシェ、そして吹き替えを担当している熊倉一雄は見事の一語に尽きますね。もう今やポワロと言ったらこの組み合わせしか考えられない。アガサ・クリスティーの原作を読むと、ポワロは「小男」と表現されているので、私としてはもう少し貧相な男のイメージがあって、最初にテレビ版を見た時、デビッド・スーシェのように恰幅のよい俳優はどうかと思いましたが、どうしてどうして、彼は完璧にポワロになりきっています。 でまたそのポワロがね、とてもステキなんだ、これが。彼のように、自分の趣味を自己の生活の全ての方面に完全に行き渡らせた生き方というのは、ある意味、私の理想でもある。ワタクシのように大雑把な人間にはやろうと思ってもできないことかも知れませんが、それだけ一層憧れますねえ。そう言えば子どもの頃、シャーロック・ホームズのライフスタイルに憧れたことがありますが、どうもイギリスの探偵というのは、私の琴線に触れてくるものがあるようです。 というわけで、このところ暇にまかせて暢気に『ポワロ』なんか見ているわけですけれど、夏休みの夕刻、家族一同誰一人欠けることなく何度目の『ポワロ』を見ていられるのって、これ以上ない幸せなんだろうなって、時々ふと思います。テレビ画面の向こうはイギリスの1930年代ですけど、こちら側は「三丁目の夕日」みたいですね。
August 15, 2009
コメント(0)
-
親友の婚約者に会う
今日のひと言: お盆こそ、都心で遊ぶに限る。(空いてるよ~!) 今日は先日婚約した親友のTと、その婚約者に会ってきました! なにせTと私は三十数年来の友達でありますからして、今後もその友誼は続くでしょうから、私としても今後、その婚約者さんと何かと言えば会うことになるに違いない。その意味で、その方が付き合い易い人かどうかは私にとっても大問題なのでありまーす。 で・・・。 実際に会ってみたら、面食いのTらしく、女優の高木美保さんをもう少し穏やかにしたような別嬪さんでございました。やっぱりね。 しかも、上辺だけでなく、中身の人間もとても別嬪さんでした。何しろバイク好きのTがハーレー・ダビッドソンの魅力について延々15分にわたって熱弁を振るうのを、隣りでニコニコしながら、時には軽く頷きながら、黙って聞いているんですもん。 で、私が「こういう退屈な話、もう何度も聞かされたでしょ?」と尋ねると、莞爾として微笑みながら「ええ、何度も」なんて言うんだもんね。いい人に決まってるじゃん? これならTが一発で持ってかれたのも無理はないな。 で、そんな風におしとやかなようでいて、案外、スポーツウーマンだそうですからこれまた頼もしい。 というわけで、私としてはTの婚約者さんに大きな○を進呈することに決めたのでございます。よかったね、T、いい人見つけて。 さて、そんなこんなで新しい仲間と会った後は、今度は釈迦楽家恒例の行事であります。そう、我が家では毎年夏にバーべQ大会をやるんですねえ。今年は特にカルビの焼き具合にコツを見出したようで、炭火で焙ったカルビを堪能しました。そして、バーべQの締めとしてどうなのかというところはありますが、先日知人から頂いた最高級ベルーガ・キャビアでフィニッシュ。いやあ、やっぱりベルーガは旨いねえ。 とまあ、今日は盛り沢山な一日となったのであります。え? 仕事? ・・・知りまっしぇーーん!
August 14, 2009
コメント(2)
-

村松友視著『ヤスケンの海』を読む
今日のひと言:自分が絶対になりそうもないもの、スニーカーのコレクター。 さて、今日も今日とて仕事をサボりにサボりまくった私は、最近気になるヤスケンこと安原顯氏のことをもっとよく知ろうと、中央公論社で彼の同僚であった村松友視氏の手になる評伝『ヤスケンの海』(幻冬舎文庫)を一気に読了してしまいました。 先に「ほぼ日刊イトイ新聞」の伊丹十三特集で、伊丹さんのことを語っていた村松さんの語り口のうまさに感銘を受け、この本にもかなり期待したんですけど、うーん、ま、こちらは普通でしたね。おそらく村松さんが中央公論社を辞めてから、特に連絡を取り合わない時期があったため、ある時期以降のヤスケンさんについて、村松さんが個人的に知る部分が少なかったのでしょう。伝記ってのは、難しいですからね。 でも、たとえばヤスケン氏と大江健三郎氏の間のトラブルの詳細について、この本によって詳しいことが分かって面白かった。 このトラブルというのは、要するにヤスケンさんが中央公論社の編集者だった時、別な雑誌で大江健三郎氏の偽善性についてコテンパンに批判したんですな。するとそれを知った大江氏が「こういう編集者がいる出版社とは縁を切る」と言って、一方的に絶縁状を中央公論社の社長とヤスケン氏宛てで送ってきた、ということなんです。 こういうことをすれば、中央公論社内でのヤスケンさんの立場は当然のことながらまずいことになるわけで、ヤスケンさんとしてはこういう大江氏のやり方に対してさらに腹を立てるわけ。弱い者の立場に立つ、というようなスタンスを普段は取っているくせに、いざ自分が批判されるとなると、一介の編集者の首を危うくすることも厭わないのは何事だ、というわけ。これこそ言論の自由を圧迫する行為ではないかと。 ま、この一件だけを見ると、確かにヤスケンさんの言っていることの方が一理ありますなあ。大江さんはいかにも大人げない。実際、大江さんを怒らせたヤスケンさんの批判も、当たっているところがあるんだ、これが。 ということでこの本、ところヤスケン贔屓になりつつあるワタクシとしては、ヤスケン氏をさらに見直す材料を色々与えてくれたところはありますね。特にヤスケン氏が意外に愛妻家であった、なんてことはこの本を読んで初めて知りましたが、その辺のこともとてもいい。私は基本的に、愛妻家には好感を持つんです。 それから肺癌にかかって余命1か月と診断されてからの彼の身の振り方もとてもいいなあ。 というわけで、評伝としてとても優れた本とは思いませんが、安原顯という人のことを知る手がかりになる本ではありますから、そういう意味で興味のある方にはおすすめ! と言っておきましょう。これこれ! ↓ヤスケンの海
August 13, 2009
コメント(0)
-
ヤスケンのジャズ談義
今日のひと言: レギンス姿の女性を「カッコイイ!」と思っている男は、多分、居ない。 さて、先日、本を一冊刊行したことですっかり一仕事終えた気分のワタクシ。実家に居る気安さもあって、ここ数日まったく勉強をしておりませーん。でまた、今日は注文しておいた本が数冊まとめて届いたこともあって、それらをとっかえひっかえ読んではグズグズとりラックスしていたのでございます。 で、その中の一冊、寺島靖国氏と安原顯氏によるジャズをめぐる対談集『JAZZジャイアンツ 名盤はこれだ!』(講談社+α新書、アマゾンの古本で1円でゲットしたもの)を半分ほど読んだのですけど、最近、段々安原顯氏を見直すようになっているワタクシとしては、かなり面白く読みました。 これは寺島氏と安原氏の対談ですから、二人が色々なジャズ・プレーヤーやその作品について「これは好き」とか「あれはダメ」とか言いあうわけですけど、そういう場合、ワタクシは大抵、安原氏と気が合うんですよね。たとえばチェット・ベイカーのボーカルについて、寺島氏は嫌いといい、安原氏は最高と言う。私自身は安原氏に与します。またキース・ジャレットの『ケルン・コンサート』について、寺島氏は嫌いじゃないようですが、安原氏は「あたしはダメ」と言う。この点でも私は安原氏と気が合う。 またマイルス・デイヴィスが70年代に電子楽器を取り入れ、ロック音楽に歩み寄ったようなサウンドを作り始めたことについて、寺島氏は「大衆に迎合した」として批判的に見ているようですが、安原氏はそうではないんですね。氏曰く、「マイルスがそういう音楽をやり始めた時、ファンや批評家からさんざん酷評された。それにも拘わらず彼はその路線を突っ走ったのだから、大衆に迎合したとは言えないのではないか」と。 ほら。安原氏の言い分の方が説得力がありませぬか? で、これに続けて安原氏はマイルスの天才性をピカソのそれにたとえ、「いいか悪いかといったら、エレキ時代のマイルスより昔のマイルスの方がいいに決まっている。それはキュービスム以降のピカソと青の時代のピカソのどちらがいいかと言えば、青の時代の方がいいのと同じ。それでも二人とも、同じことを繰り返すよりは、自己変革を続けることの方を選んだ」と見る。なるほど、と思います。 とまあ、そんな具合で、二人の対談を読んでいると、安原氏の言い分の方により説得される私がいるわけですよ。 というわけで、安原さんの『「編集者」という仕事』を読んで以来、なんかこの人にますます興味が湧いてきたのであります。私の恩師は、生前、何度か安原さんと仕事をしているようですが、彼がどんな人だったのか、恩師から聞いておきたかったなあ。 さて、そんなこんなのグダグダ・リラックス状態はまだしばらく続きそうです。ま、「充電中」ということにして、しばらく自分に甘えますかね。
August 12, 2009
コメント(0)
-
裏原キャットストリートに出没
今日は「帽子が買いたい」という姉につき合って、家内も連れて3人で都内に出ました。 で、まずは明治神宮前で降りていわゆる「裏原」ってんですか? そこの「キャットストリート」なる通りを渋谷に向かって歩き始めます。そこにある「LoRo」という帽子屋さんに行きたいというのでね。 ところが驚いたことに、この辺って、お店のオープンが遅いんですね! たいていは11時半のオープンらしい。11時だと、まだお店が開いてないよ!今日のひと言:「裏原の朝は遅い・・・。」 でも、このキャットストリート、細い路地みたいなところまで色々とお店が並んでいて、面白そうなところですね。こういう通りは、名古屋にはないんだなあ・・・。 が! なんとなんと、今日一番の目的地である「LoRo」に着いたと思ったら、今日は定休日じゃん! あーれーーーー・・・。 茫然自失する我ら3人。 しかしせっかくここまで来たのだからと気を取り直し、近くにあった「Cocotiビル」というセレクトショップが集まったお店を冷やかすことに。すると、一階を占める「トゥモローランド」をはじめ、結構、面白い店がありましてね。ま、そこそこ楽しむことができました。 で、いい時間になったので、このビルの3階にある「Chef's V」というレストランに何の気もなしに入ってランチをしたのですが、これが大正解。このお店、野菜料理を売りにしているのですが、確かに前菜で出てきた「野菜のテリーヌ」(各種野菜をゼリーで固め、オリーブオイルと岩塩で食べさせるもの)がおいしくて。メインの「鰆のポワレ・ピーナツバターソース」も絶妙のお味。これに食後の紅茶(これも濃くておいしかった)を付けて1,300円は安い! レストランの雰囲気もとてもよく、充実のランチでございました。 で、すっかり満足した我らは、渋谷駅から新宿へ向かい、家内お気に入りの「バーニーズ・ニューヨーク」へ。色々見て回った結果、家内としてはとあるスカートが欲しかったようですが、ちょっとお値段が張ったので今回は諦め、代わりに帽子を一つ購入。本当は姉が帽子を買いに来たのですが、逆になってしまいましたネ。 そして次に、今度はワタクシのリクエストで、新宿の有名なジャズ喫茶「DUG」でアーモンド・オレなどを賞味(おすすめ!)し、しばしまったりした後、小田急デパートの地下で舟橋屋の葛餅をお土産に買って帰宅の途についた、と。 というわけで、今日は都内ショッピング・ツアーとあいなったわけですが、予期したほどには収穫がなかったとはいえ、すっかり田舎のネズミと化した私には十分物珍しい経験となったのでした。たまにはこういうのも頭の活性化になりますからね! さて、明日は明日でスケジュール目白押し! どうなりますことやら・・・。
August 11, 2009
コメント(2)
-
東京へ戻る
今日のひと言:小学生ぐらいの男の子の兄弟を見ると、全部「まえだ・まえだ」に見える。 さて、今日は東京の実家に戻る日。ということで、数日前からの計画で冷蔵庫はほぼカラッポにしてあるので、お昼は道すがら食べようということになり、名古屋郊外・日進市竹の山にあるサンドイッチの店「クラブハウス」に向かいました。ここへ来るのは初めて。 で、このお店はさすがに専門店だけあって何十種類もあるサンドイッチ・メニューの中から選ぶことができるのですが、今日私が選んだのは王道ともいうべきコールドビーフのクラブハウス・サンド。で、家内は季節限定メニューの「アスパラガス・フライのサンドイッチ」を注文しました。どちらも単品では900円位でしたかね。 で、運ばれてきたのは3枚のパンを使い、具がぎっしり詰まったクラブハウス・サンドでボリュームたっぷり。で、私のもおいしかったですけど、家内が頼んだアスパラガス・フライのサンドイッチがかなりおいしかった。アスパラガスの歯ざわりといい、味の濃さといい、またチーズやら野菜やら他の具材との相性といい、なかなかのものでしたね。この他にも食べてみたいサンドイッチがずらりとメニューに並んでいましたので、また来てもいいかな。ただ、サンドイッチにコーヒーをつけたり、セットメニューにすると、一人前1,300円以上になってしまうので、ランチとしてはちょっと高めですかね・・・。 ま、そんなこんなでお腹一杯になりながら東名に飛び乗り、あとは東京まで一直線。渋滞を心配しましたけど、拍子ぬけするくらいまったく渋滞がなく、むしろ走り易かったです。 で、実家には既に仙台に住む姉一家も到着済みだったので、久しぶりに釈迦楽家大集合。賑やかな夕食、そしてその後の団欒となりました。釈迦楽家・名古屋支部は私と家内の二人所帯なので、たまにこういう賑やかさがあると、楽しくていいもんです。 というわけで東京での夏休みがスタート! 明日は早速渋谷・新宿あたりに出かけることが計画されているらしいので、のんびりもしていられないようです。ということで、今日はもう休みます。皆様、お休みなさーい!
August 10, 2009
コメント(4)
-
ついに来たか、新書・古書併売時代
小耳に挟んだところによると、大手新刊書店が次々と古書市場に進出しようとしているとのこと。 つまり、新刊書店に古書買い取りコーナーを設置し、そこで読み終わった古本をお客さんに売ってもらって、そのお金でまた新刊本を買ってもらうというようなシステムを導入する新刊書店が生まれているんですって。で、そこでお客さんから買い取った古本は、店内の古書コーナーで販売すると。となると客側からすれば、一つの店内で新しい本を買うか、それとも古本で済ますかの選択をすることができるわけです。 いや~、ついにそういう時代が来ましたか。新刊と古書の併売時代が。 アメリカのポートランドに「パウウェル」という巨大書店がありまして、ここは新刊と古書を区別なく書架に並べて売っていて、ワタクシなどの古本好きからすると夢のような書店なわけですが、いよいよ日本にもそういう書店が生まれるのかも知れません。 大体、書店というのは本来、こうでなければならないのではないでしょうか? 人に読まれるべき本は新刊でなければならない、なんてことはないのだから、新刊書は出版社から仕入れるとして、それとは別に古本の良書もどこかから仕入れ、両方とも同じように店頭に並べて売る。当たり前のことではありませぬか。 それに、例えば自動車の販売店だって昔からそういうことをやってますよ。自動車を買う場合、今まで乗っていたクルマを下取りに出して、新車を買うわけでしょ? だったら本だって、古い本を下取りに出して、そのお金を新刊書を買うお代の足しにすればいい。同じ事ですわ。 で、さらに嬉しいのは、新刊・古書併売を始めようともくろんでいる書店の中に、名古屋の有名な書店グループ・三洋堂も含まれているところ。わーい、三洋堂で古本が買える時代が来るかもしれないぞ! ということで、本の流通に新しい風が吹きそうな気配を感じ、大いに歓迎している私なのでございます。 さて、ところでワタクシ、明日は東京の実家に戻ります。月曜日、しかも上りですから、さほど渋滞はしないのではないかと期待しているのですが、どうなりますことやら。では、明日からは東京からのお気楽日記、乞うご期待でございます。
August 9, 2009
コメント(0)
-
ビアホール浩養園でまったり!
今日の名古屋は厳しい陽射しが照りつける夏らしい暑い暑い一日でしたが、そんな日にふさわしい過ごし方をしてきましたよ。同僚の「叔父貴」ことO教授と「兄貴」ことK教授、そして名誉教授のH先生と4人で、ビアホールに行って生ビールを飲み、かつ、バーべQをむさぼり食ってきたのでございます。 我ら仲良し4人組が向かったのは、名古屋で有名なサッポロビールのビアホール「浩養園」。ここ、もともとサッポロビールの工場の跡地をビアホールに作り替えたところで、室内・室外合わせるとものすごい収容人数がある大きなビアホールなんです。 で、ビールに合わせる料理は色々ありますが、何といっても有名なのがラム肉を使ったバーべQ。これがね、ラム肉の臭みなんてまるで感じさせない、非常においしいバーべQでありまして、浩養園に来たからにはコイツを食べないでどうする、というようなものなんです。 ということで、前期の授業をすべて終え、ようやく夏休みを楽しむ態勢に入った我らは、その解放感に浸りつつ、サッポロビールの生ビールをグビーっとやりながら、絶妙の味のラム肉バーべQを死ぬほど楽しんだのでございます。もうこれ以上食べられないというところまで食べて飲んで、お会計は一人3千両也。十分にリーズナブルではございませんか。また、たまたま我々の隣の席にはタニマチに率いられた十人ほどの浴衣姿のお相撲さんたちが居て、気持ちいいほどの食べっぷりで飲みかつ食べていたのも雰囲気を盛り上げてくれました。 で、食後は隣にあるイオン・ショッピングモール内の「コメダ珈琲店」に場所を移し、別腹とばかり名物「シロノワール」を分けて食べつつ、雑談の続き。定年で大学を離れて久しいH名誉教授にも現在の大学の状況などをお知らせしつつ、ますます悪化する一方の大学のあり方やら、ますます落ちる一方の学生たちの学力のことやらへの愚痴を言い合ったり、それに対比する形で、大学生え抜きのH先生の大学生時代の話を伺って、昔の大学生はものすごく勉強したんだなあ、なんてことを教わったり。はたまた個々の先生方の愉快な海外体験の話なども出て、話題は尽きることがありません。 そんなこんなでお昼から3時半くらいまでのんびり過ごして、今日の会はお開きということに。散会に際してO叔父貴の発した「今日は久しぶりにのんびりしたな~」という一言に、この会を企画した私もすっかり嬉しくなりました。 ということで、暑さの真っただ中での生ビール&バーべQ&おしゃべりに、至福のひと時を過ごしていた今日の私だったのでありました、とさ。
August 8, 2009
コメント(0)
-
卒論マニュアル本、完成!
昨年の夏休みに勝手に企画し、以後、仕事の合間に書き進めてきた卒論執筆マニュアル本が完成しました~! とりあえず今年前半の主たる仕事が終わった、って感じです。 卒論・レポートの書き方ってのは世に色々出回っておりますが、どうもこう味気ないと言いますか、瑣末過ぎたり、逆に大味過ぎたり、少なくともうちの学科の学生に読ませて役に立つものが見当たらないような気がしていたんですよね。大体、類書の多くは読者対象が絞り込まれておらず、理系・文系の区別さえつけていないため、そのどちらにも役に立たないモノが多い。 そこで、もう、私の専門に引きつけてしまって、「アメリカ文化を研究対象として卒論を書く学生向け」の卒論執筆マニュアルにしちゃった。それが今回の私の本の狙いでございます。ですから、読者対象どんぴしゃりの学生にとっては、かなり役立つ本になっているのではないかと。 でも、「アメリカ」という部分を「イギリス」とか「フランス」とか「ドイツ」に置き換えてもいいくらいの応用性はあります。要するに外国文化研究をする学部学生なら、読んで損はないようにはなっているかな。 で、それにプラスして、アメリカ文化の面白さについて多くのページを割き、単なるマニュアルというよりは、「アメリカ文化入門」的な側面も持たせていますので、とりあえず一般の人でも読んで面白いものにはなっていると思うのですが・・・。 しかし、問題は「販路」なんですね~・・・。設立間もない大学出版会ゆえ、取次との契約がまだできていない。ということは、全国の書店に並ぶようなシステムがまだ構築されてないわけ。というわけで、一般の方がすぐに購入できるものではないんですなあ。我ながら、結構面白い本だと思うのに。 でもね、そんなマイナーな本ではあっても、自分の本が完成すると嬉しいものなんですよ。著者取り分として受け取った十数冊の新著を眺めては、にんまりとしている次第。 というわけで、このブログを読んでいる我がゼミ生OB・OGたちよ。良かったら、買ってね! 直接メールしてくれれば、買い方を教えるからさ!
August 7, 2009
コメント(0)
-
恒例! 誤字大賞発表!
はあ~・・・。ようやく期末試験の採点が終わった~。長く辛い、単調な作業だったのぅ。 ということで、採点終了後のお楽しみとなりました、学生たちの解答に見られた「誤字」の発表でーす! 今回も色々ありましたぞ・・・。「音は合ってるけど」編:辺事: 大学生なんだから「返事」くらい正しく書いてくれよ・・・。許住区: ここに住んでもいいよ、ということかな? 正しくは「居住区」。捕強: 良いキャッチャーでも加入させましたかね? 正しくは「補強」。家夫長制度: 夫じゃなくて、オヤジの方ですね。正しくは「家父長制度」。心みる: それを言うなら「試みる」ですな。「音からして違うだろ」編:錠: これじゃ「じょう」じゃないか! 「gun」の訳だから「銃」にしてくれ。ベット: 英語で書けば「bed」だからなあ。「ベッド」だろ? でもこう書く学生の多いこと・・・。「字は似ているけど」編:往民表: これじゃ「おうみんひょう」だよ。正しくは「住民票」。「ある意味、合ってる」編:偽手: なるほど、一理ありますね。でも正しくは「義手」。避任: 責任とって! 正しくは「避妊」。囚容所: 「囚人」を「容れる」「所」か。なるほど。だけど、そういうのは普通「刑務所」って言うんだぜ。「そうは言わないだろう」編:義腕: 「ぎわん」って・・・。「義手」だよね。生産: 赤ちゃんを産むのを「生産」とは味気ない。「出産」だね。警察員: 銀行員みたいじゃないか! 普通「警察官」だろ・・・。押しがけ: 故障したクルマを押すのじゃあるまいし! 正しくは「先駆け」。長い昼休み過ぎた: これ、日本語か? 「昼休みを長くとり過ぎた」だろ?そして、2009年前期の誤字大賞は・・・「面訴書」でーす。これ、そのまま読むと「めんそしょ」だけど、「driver’s license」の訳なので、「免許証」のつもりなんでしょうなあ。しかし、大学生にもなって「免許証」ってどう書くか、知らなかったのかい? ホントに?? いやあ。学生の日本語力の欠如たるや目を覆うばかりですけど、それだけでなく、字そのものにまるで教養がない、というか、幼稚な字ばっかりでねえ。まあ、これが最高学府に通う人間の字か? と思うようなのが多いんですわ。ほんと、目を疑いますよ、小学生でももう少しまともな字を書くだろうと思うような答案に出会うと。そういう点では江戸時代とかの「寺子屋」の方が、現代の小学校よりよっぽどまともな教育してたんじゃないかと思いますねえ。情けなや、情けなや・・・。 さて、明日はいよいよ私の新しい本が出版される日! 大学に成績を届けに行きがてら、受け取ってくることにいたします。わーお、楽しみ~!
August 6, 2009
コメント(6)
-
採点やら何やら
お盆前に期末試験の採点を終えてしまおうと、昨日あたりからこの嫌な仕事に取り掛かりました。 しかし、定期試験の採点ほどつまらないものはないですな・・・。私はこの仕事が大嫌いでございまして。少なくとも私にとって何のプラスにもならない単調な仕事ですからねえ。○が多けりゃ退屈だし、×が多いと「自分の教え方が下手だったか・・・」と落ち込むし、中途半端に×があると計算が難しいし。 で、10分採点しては「限界だ・・・」とつぶやいて冷蔵庫を開けて麦茶を飲み、また10分採点しては「ノリぴーは見つかったのか?」とテレビをつけに行く。こんな調子ですから捗らない、捗らない。 ってなわけで、何か気晴らしになることをしないと頭がおかしくなりそうなため、今日のお昼は外に食べに行くことに。と言っても、別にごちそうを食べようってんではなく、モスバーガーでもどうかな、と。 で、家内と家の近くのモスに赴いて、今宣伝中の「カレーチキン・バーガー」ってんですか? そいつを食べたわけですよ。すると・・・ うまーい! カレーソースが夏らしさを演出して、なかなかおいしいでないの。さすがモス、たまに食べるとうまいねえ。 そしてデザートには定番の「モスシェイク・抹茶」。これ、毎年少しずつ変更が加えられるようですが、今年のは抹茶白玉にあずき、そして崩した抹茶ゼリー(プリン?)などが入っていて美味。おいしかった~! でも次は苺味の「リカちゃん・シェイク」を注文しようかな。 というわけですっかり満足して帰宅し、採点の続き。 で、すぐ飽きると。 仕方がないので、おもむろに部屋の片づけをはじめ、懸案だったステレオ・セットの移動をしちゃいました。今まで机の斜め前にあってどうも音の抜けが悪かったんですけど、今度は自分の机の真後ろにある棚から音が降ってくるようにしてみたわけ。そしたら、うーん、やっぱりこっちの方が音がいいなあ。快適、快適。 で、満足して採点の続き。 で、すぐ飽きると。 ということで、採点している合間に気晴らしをしているんだか、気晴らしの合間に採点をしているんだか、よくわからないまま、さっぱり仕事が進行しない今日のワタクシなのでありました。わーん、誰か採点代わって~!
August 5, 2009
コメント(2)
-
紀要論文のダウンロード数
しっかし、世の中、結婚の対象にしちゃいけない男ってのはいるねえ。でまた、どうしてそういう男にひっかかる女ってのがいるかねえ。パッと見、かっこいいとかってのはあるかも知れないけどさ。一目見て、「あ、こいつはたった一人の女も幸せに出来ない奴だ」ってのは、すぐ分かるような気がするけどねえ・・・。 ま、今のはまったくの独り言。 さて、今日は所用があって大学に行ったのですが、行けばやたらに仕事がおっかぶさって来るのが大学というところでございまして。それこそ早回しの喜劇映画みたいに、数時間というもの、一瞬も手足を止めることなく働き詰めに働きました。もうね、もしも家内が大学で働いているワタクシの姿を見たら、きっと泣くよ。自分の夫はこんなに働いているのか、と。 それでも、今日は一つだけいいニュースがありまして。図書館から連絡があって、私の紀要論文のダウンロード数を知らせてくれたんです。 「紀要」ってのは、要するにそれぞれの大学が発行する論文集でございまして、その大学に専属で勤めている大学の先生は、なるべく毎年、これに寄稿することが望ましいとされている。学術論文の発表場所として、最もポピュラーな場と考えて良いでしょう。 ところが、数年前くらいからでしょうか、この紀要の「電子媒体化」というのが進んでおりまして。つまり、今までは紀要といえば紙の冊子であり、もしこれを読もうと思ったら図書館に行かなければならなかったわけですけど、これが順次電子媒体化されたことによって、インターネット上でアクセスし、ダウンロードできるようになってきたんですね。うちの大学なんて、もう今年から紙媒体の冊子の紀要は一切発行せず、ネット上に公開されるPDF版のみになるそうですが、おそらく日本中、どこの大学でもこの種のペーパーレス化は進んでいることと思います。 ま、せっかく紀要論文を書いても、冊子状の論文集になったものをもらえなくなると、なんだか「論文を書いた」という実感が湧かなくて、私なんかは寂しいなと思う方なんですけど、とにかく紀要をペーパーレスにすると、スペース不足に悩む日本中の大学図書館が狂喜するんですよね。ということで、これも時代の流れなのだろうと思います。 で、そんな紀要ペーパーレス化の副産物として出てきたのが、「ダウンロード件数の報告」というサービスでありまして、一カ月間に自分の書いた紀要論文が何回ダウンロードされたか、を教えてくれるというわけ。 で、この有難いサービスが始まって、その記念すべき第一回目が今日だったのですが・・・ おお! これは意外! 私の書いた紀要論文なんぞ、ダウンロードして読もうとする奇特な人なんか一人もいないだろうと思いきや、これが結構居るんだ。7月ひと月だけ見てもこんなにいるのなら、1年通して見たらそれこそ結構な数じゃん。 あーん。嬉しいよーん。 だって、自分の研究が他の研究者から参考にされたり、引用されたりすることほど、研究者冥利に尽きることなんかないですよ。他人から利用されなかったら、それは単なる独り言なんだもん。研究としての価値がないっつーことでしょ? 今までのように紙媒体の紀要しかなかったとしたら、自分の紀要論文がどのくらい他の研究者に読まれたかなんてまったく分らないわけですけど、電子媒体化されたことで、それが分るようになった。これは、スゴイことですな。 ということで、私の研究も、まんざら独りよがりの独り言でもなかった、ということが分って、ちょっと気分のいい今日の私だったのでした、とさ。ひゃっほう!
August 4, 2009
コメント(0)
-
ヤスケンを見直す
巽孝之さんの『思い出のブックカフェ』を読んでいたら、高山宏さんとの対談の中で編集者の安原顯氏の話が出てきて、それによると、彼が書いた『「編集者」の仕事』という本は、「名著というよりキャノンですよ(巽談:300頁)」とのこと。 ということで、ちょっと興味を持ったワタクシは、この本を買って、今、読んでいるところなんですが・・・、 結論を申しますと、面白い。相当面白いですね。 ま、安原顯、いや、通称(自称?)「スーパー・エディター」のヤスケンさんですが、彼はその昔、竹内書店というところに在籍していた時に伝説のPR誌『パイデイア』の編集をされ、その後中央公論社に移って文芸雑誌『海』の編集を担当、その後同社の、これまた伝説の女性誌『マリ・クレール』を編集して一時代を築いた人。特に最後の『マリ・クレール』では、売れない女性誌の編集を引き受けるや、それまでの女性誌の概念を一変させるような洒落た文化雑誌に仕立て直しつつ、当時の「ニューアカ・ブーム」と並行して、「文化」なるものが売れることを証明してみせた。その点で、確かに1970年代から80年代にかけ、一つの文化運動を陰からリードした人物、と言えそうです。 しかし、その反面、この人は毀誉褒貶の激しい人でもあって、悪く言う人はとことん悪く言う。で、ヤスケンさんのことを悪く言う人の話に耳を傾けると、「もし本当にそういうことを言ったりやったりしたのであれば、こいつは人間として許せん」という風に思えてくる。 ということで、私もこの人について、従来あまりいい印象を持っていなかったのですが、とりあえずそういう偏見は横に置いておいて、『「編集者」の仕事』という本だけに限って言えば、非常に説得力があります。というのは、この中で彼が述べていることはすべて体験談ですからね。 例えば、この本の中でヤスケン氏は色々な人のことを云々するのですが、「こういう場で、あいつがこれこれこういうことを言った。それは許せん!」と彼が言う場合、もっともな話だな、と思いますし、逆に「この人は、こういうことをやる人であって、実に感心した」と彼が言う場合も、やっぱり共感できる。つまり、感性の点でおかしなところがないんですね。 で、そういう風に色々な人のことを褒めたり、貶したりしながら、首尾一貫して編集者の世界の腐敗ぶり、堕落ぶりを罵り、それを反面教師として、編集者たるものこうあるべし、というところを示している。で、その書き方・語り口もなかなか上手なもので、読ませるわけですよ。 でまた、この本では、特にヤスケンさん自身が編集に携わった雑誌の、各号の目次を延々と載せることにも力を注いでいるのですが、その心は、「目次を見れば、それぞれの雑誌のその号の企画が分るだろ。それを見て、ははん、と納得できなければ、そもそも編集者の素質がないから、そんなものになろうなどと考えるな!」ということなんですな。その辺の突き離し方も、なかなかいいじゃないですか。理に適っているじゃないですか。 ということで、この本、ワタクシとしてはとても面白く読んでいるのですが、さてさて、そうなってくると、人というのはますます分らないということになりますね。これだけいい本が書ける人物でありながら、彼のことを蛇蝎のごとく嫌う人が沢山いる、というのはどういうことなのか。一体、ヤスケンという人物は、いい人なのか、悪い人なのか。唾棄すべき人間なのか、唾棄すべきだけど有能な人間なのか、はたまた有能であり、かつ、実はいい奴なのか。 ま、本人が既に鬼籍に入っていますから、もうどうでも分らないわけですけどね。 でも、今回初めて、あの悪名高い人物の本を読んでみて、なるほどとにかくこの人も一人物であったのだなあ、という感を受けたワタクシなのでありました。 いずれにせよ、この本の中には色々な「文化人」が登場しまして、その人たちのことをヤスケンがくそみそに貶したり、たまーに褒めたりしますから、そういうミーハーな興味からだけでも、一読の価値はあると思いますよ。かくして、この本、教授のおすすめ!です。
August 3, 2009
コメント(0)
-
ラーメン慕情
たまに襲ってくる「ラーメン食べたい衝動」に駆られ、今日の昼はラーメンを食べに行く!というところまでは決まったものの、さて、どこへ行けばいいのやら。ということで、ネットで色々探してみた結果、「ラ王への道 愛知県人のための情報サイト」なるものを見つけてしまいました。これこれ! ↓ラ王への道 で、こいつを使って家の近くのラーメン屋さんを探してみたのですが、これがなかなか。というのは、世はとんこつラーメン全盛と言いますか、この手のお店が多くて、私が望むごく普通のしょうゆラーメンのお店が全体的に少ないからです。それでも「こころ家」というお店が良さそうかなと思い、結局ここへ行くことに。 実際に行ってみると、ま、こじんまりとしながらもキレイ目なお店で、メニューもシンプル。私は「中華そば」のたまりしょうゆ味を選び、これに味付卵をトッピング、家内はふつうのしょうゆ味の中華そばで同じく味付卵付きを注文。これに焼き餃子とごはんをプラスしました。 ほどなく出てきたのは、なるほどいかにも「これがラーメンってものでしょ?」という王道版。大きめのチャーシュー(これはおいしかった)にメンマに鳴門、大きな焼のりが一枚突き刺さっていて、これに味付卵が一個丸ごと入っているという風情です。 で、私が注文した「たまりしょうゆ」の方は、ふつうのしょうゆよりも色も濃く、味も濃い目。最初に一口スープを飲んだ時は、やや魚介系の出汁の味が濃すぎるかなと思いましたが、それも次第に慣れてきて、ペロッと食べてしまいました。ま、食べ終わってから「やっぱり大盛りにすれば良かったかな」と、ちょっと思いましたけどね。一方、餃子の方はと言いますと、うーん、ごく普通、ですね。可もなく、不可もなし。 というわけで、全体的に判断しておいしかったですし、何の不満もないのですが、強いて言えば、「次も絶対、ここに来よう!」というほどのインパクトがちょっと足りなかったかな、と。ヤミツキになる要素がなかった、と言いましょうか。 いや、世の中は依然としてラーメン・ブームですけど、身近なところに「これ!」という贔屓のラーメン屋を見つけるのって、結構、難しいなと思うのであります。 そう言えば先程のラーメン情報サイトですけど、これを見ると、運営者が食べ歩いたラーメン屋さんのうち、そうですね、4分の1から5分の1位は、すでに閉店しているんですよね。つまりこのラーメン・ブームの中でさえ、(あるいはその渦中にあるからこそ?)、長く固定客を惹きつけ続けるラーメン屋さんって、ありそうでないのかな、と。 出版業界も新刊本がどんどん出る割に、出版不況と言われて久しいですが、ラーメン屋さんも同じで、気負って店を出してみても、実際にはなかなか当たらない、ということなんでしょうか。 しかし、私の子供の頃、別にラーメン・ブームでも何でもない時代、家の近くの何の変哲もない町の中華料理屋さんで食べたごく普通のラーメン、それこそ一杯280円とかそんな値段のラーメンは旨かったなあ。私が今も食べたいと望むのは、そういうごく普通のラーメンなんですけどね。 そう、それとね、私が子供の頃に住んでいた横浜とか相模原とか、その辺では、どの中華料理屋さんにも大抵「サンマー麺」というのがありまして。モヤシと野菜を炒めたものを片栗粉でとろみをつけ、それをラーメン(だったかタンメンだったか)にドロっとかけたもので、これはこれでなかなかおいしいものなんですが、どうもあれは神奈川県の隠れた名産なのか、それ以外の地域であまり見かけたことがありません。博多のとんこつとか、そういうのは既に有名になりすぎたのですから、これからはサンマー麺的なちょいとマイナーなご当地麺を発掘してみたらどうなのかしら。 かくして愛知県における私の「ラ王への道」は、まだまだ道のり遠いのでありました、とさ。
August 2, 2009
コメント(4)
-
悩ましき仕事のオファー
もうすぐ出版される私の本の「表紙見本」が出来たということで、出版社の方ととある喫茶店で落ち合い、色の出方などの細かいチェックをしたのですけど、その時、別件で仕事のオファーをいただいてしまいました。 実はその出版社、高校向けの参考書とか問題集なんかも作っているのですが、その売れ筋の問題集の全面改定を計画していらっしゃるようで、その改定を私に引き受けてくれないか、ということなのです。 うーん・・・。そう来ましたか・・・。 実は今回の「卒論執筆マニュアル」を完成させた後は、本来の仕事である文学論の執筆に全力を注ぐため、シンポジウムの企画だろうと、学会発表だろうと、共著のお誘いだろうと、外部からのお誘いは、しばらくの間、一切断ろうと思っていたのですが・・・。 ちなみにくだんの問題集というのは、生徒個人が買うものというよりは、学校単位でガバっと買って、教科書の補助教材として使うもので、そのため売れる部数はものすごいものらしく、「陰のベストセラー」となっているのだとか。何しろ北は北海道から南は沖縄まで、全国4000の高校にサンプルを送り、採用率も上々。もし採用されれば、一校で何百部も捌けますからね。 で、実際に私もその場でサンプルを見せてもらったのですが、レベルが9段階ほどあり、一番上のレベルのものは、いわゆる大学受験対策の問題集ですが、一番下のレベルのものとなると、ほとんど中学英語そのもののような内容でございまして、とにかく絵が一杯。バナナの絵が描いてあって、その隣に「banana」なんて書いてある。そういうレベルのものです。 で、この一番下のレベルのものは一体誰が使うのだろうと思って聞いてみると、これが案外、日本中で売れるのだそうですね。で、これに関して聞いた話が面白かった。 今回見せていただいたのは「英語」の参考書・問題集ですが、同じシリーズの「数学」の一番下のレベルでは、まず最初に「3ケタの足し算」が出てくる、というのです。つまり、3ケタの足し算ができない高校生ってのが日本中に沢山いる、ということなんですな。しかし、だからと言って彼らに小学校の教科書を使って教えられるかというと、彼らにもプライドはありますからそんなことはできない。 だからこそ、そういう高校生たちのために、この種の参考書・問題集が必要だ、というわけ。つまり、表紙は立派に「高校生対象」になっているけど、中身は小学校・中学校レベルの内容になっている「補助教材」が、何としても必要なんですな。で、同じことが「英語」にも当てはまる、と。 「高校生向け」とうたっていながら、中身は小学校・中学校レベルの内容の参考書・問題集が日本中でバカ売れ。これが日本の教育界の、まさに「実態」だと。 一般に、本屋さんなんかで売っている高校生向けの参考書・問題集というと、代ゼミ・駿台・河合塾・Z会などの予備校系出版物だったり、旺文社やら学研やら文英堂などの出版社のものが思い浮かびますが、そういうところが出している参考書・問題集を使いこなせるのなんて、日本全国の高校生の上半分くらいなもので、下半分の学力は、本屋さんなどではあまり扱っていない「補助教材」系出版社の出版物が支えていると。どうも、そういうことらしい。 とまあ、そういう社会勉強をさせていただいた上で、さて、ワタクシ自身がその補助教材の世界に手を染めるのか? ということなんですが、そこが問題だよな~。ま、もちろん手を染めると言っても、ワタクシが担当できそうなのは一番上のレベル、つまり大学受験問題集だけでしょうけどね。 ということで、高校教育のアンダーグラウンドに君臨して大金を手にいれるか、それとも研究者としてその道には近づかない方がいいのか。ちょっとばかり悩ましい選択に直面しているワタクシなのでありました、とさ。あーん、どっちが、ええんや~!?
August 1, 2009
コメント(2)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 楽天レビュー、信じていい?私がレビ…
- (2025-11-26 22:00:05)
-
-
-
- ひとりごと
- 今日の気になるもの 11/26
- (2025-11-26 22:03:37)
-
-
-
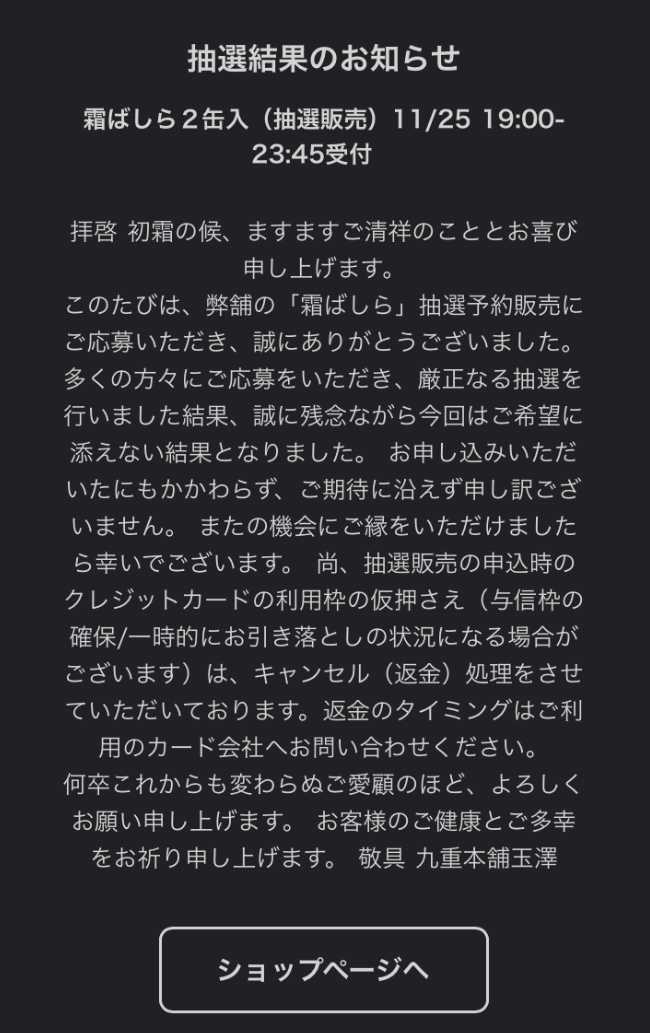
- 株式投資日記
- またまた上がってきた日経平均株価
- (2025-11-27 07:00:05)
-







