2012年08月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
説教要約 792
「初めに情報ありきか物理法則ありきか」 甲斐慎一郎 ヨハネの福音書、1章1~5節 一、初めに物理法則ありき 「車いすの天才科学者」として有名な英ケンブリッジ大のスティーブン・ホーキング博士は、「二〇一〇年九月に『ホーキング、宇宙と人間を語る』を出版し、たちまちベストセラーになりました。日本の新聞にも、ホーキングが『宇宙は神によって創られたのではなく、物理法則によって自然に作られるのだ』と書いていることに対して、欧米ではキリスト教関係者から強い反発を受けているというニュースが流れました」(『ホーキング、宇宙と人間を語る』258、259頁、エクスナレッジ、2011年)。 ホーキング博士は、次のように述べています。 「この世界には完全なる法則の集合があり、現在の宇宙の状態を知ることができれば、今後宇宙がどのように発展するのかを予言することができる、という考え方です。このような法則はどの場所でもどの時刻でも成り立つべきで、そうでなかったらそれは法則ではありません。例外や奇跡もありません。神でも悪魔でも宇宙の発展に干渉することはできないのです」(『ホーキング、宇宙と人間を語る』239頁、エクスナレッジ、2011年)。 ホーキング博士は、この本の出版に関して次のような謝辞を述べています。 「宇宙は偉大な設計図によって創造されました。そして本も、その設計図に従って書かれるのです。しかし、宇宙は無から生まれましたが、本は無から自発的に現れることはあり得ません。宇宙が創られるために創造主は必要ではありませんでしたが、本が出版されるためには制作者が必要です。その役割は著者だけが果たすのではありません。編集者、デザインをした人、校正をした人、図版の制作者、絵を書いた人、個人秘書、コンピューター補佐役の名前を挙げて感謝しています」(『ホーキング、宇宙と人間を語る』255~257頁、エクスナレッジ、2011年)。 二、初めに情報ありき 現代は、ITの時代です。ITとは「Information Technology」すなわち「情報技術」ということです。情報がなければ、何も考えられず、また何も動きません。21世紀になって、人類は「情報」ほど大切なものはないことがわかったのです。ところが聖書は、初めから「情報」が何よりも大切であることを教えています。 ヨハネは、「初めにことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。この方は、初めに神とともにおられた。すべてのものは、この方によって造られた」と記しています(1~3節)。「ことば」は心の表現、言い換えれば、人格を持つ者の表現です(マタイ12章34節)。 情報学者のヴェルナー・ギット博士は、この「初めにことばありき」というヨハネのことばを用いて「初めに情報ありき」という本を出版しています。すなわち「ことば」は、情報にほかなりません。 聖書は、「家はそれぞれだれかが建てるのですが、すべてのものを造られた方は、神です」と記しています(ヘブル3章4節)。 ケン・ハム氏は、「背後に知性の存在を指し示すものの例として、建物、ラシュモア山の彫刻、車を挙げ、これらは決して自然にはできません。知性のある誰かが計画して作ったから存在するのです」と述べています。 「ヒトの遺伝情報を読んでいで、不思議な気侍ちにさせられることが少なくありません。これだけ精巧な生命の設計図を、いったいだれがどのようにして書いたのか。もし何の目的もなく自然にできあがったのだとしたら、これだけ意味のある情報にはなりえない。まさに奇跡というしかなく、人間業をはるかに超えている。そうなると、どうしても人間を超えた存在を想定しないわけにはいかない。そういう存在を私は『偉大なる何者か』という意味で十年くらい前からサムシング・グレートと呼んできました」(村上和雄『生命の暗号』198頁、サンマーク出版、1997年)。 情報学者のヴェルナー・ギット博士は、宇宙には「情報」と「エネルギー」と「物質」があり、情報がエネルギー(物理法則)を造り出し、エネルギーが物質を形造ると述べています。情報がなければ、エネルギー(物理法則)はなく、エネルギーがなければ、物質は存在しません。 「初めに情報ありき」と「初めに物理法則ありき」のどちらが正しいでしょうか。私たちは、どちらを信じるでしょうか。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2012.08.28
コメント(0)
-
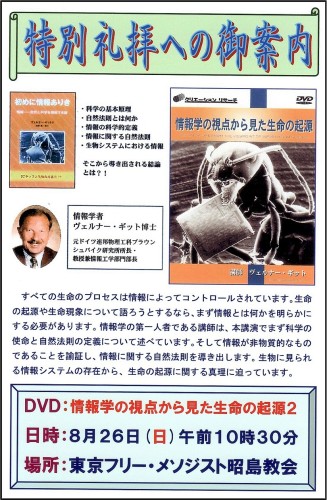
説教要約 791
「全能の神に拠り頼む訓練(3)」 甲斐慎一郎 列王記、第一、19章 「旧約と新約の間には根本的な相違があります。新約における宗教は、各個人の選択によるものであり、その信奉心は聖霊の導きによるものです。これに対して旧約における宗教は、律法から出ています。......唯一の神の権威を根本の主意とする旧約においては、偶像を礼拝することは、犯罪であるだけでなく、イスラエルの王である天の神に対する反逆であり、国民はそのために大きな刑罰を受けるのです」(A・イーダーシャイム)。 一、民が主の契約を捨てたことを知って絶望し、逃走して死を願ったエリヤ(1~4節) イズレエルにある避暑の宮殿にいたイゼベルは、アハブからエリヤがしたすべてのことと、バアルの預言者たちを剣で皆殺しにしたこととを残らず聞くと、烈火のごとく怒り、使者を遣わして二十四時間以内に必ずエリヤを殺すと脅しました(1、2節)。 するとエリヤは、そこを立ち去り、荒野へはいって行き、深い絶望に襲われて自分の死を願いました(3、4節)。全力を尽くして主に仕え、精一杯の働きをし、心を注ぎ出して祈り、その結果、驚くべき神のみわざが現されたにもかかわらず、翌日に民は主に背いたのですから、彼の心中の苦しみを推し量ることができる人はだれもいないでしょう。 カルメル山の出来事の翌日、イスラエルが再び契約を破ったことを知った時(1節)、エリヤは絶望して逃走しました。しかし彼が逃走したのは、決してイゼベルを恐れたためではありません。深い失望と落胆のためです。それとともにカルメル山からイズレエルまでアハブの前を走ったので、その激しい疲労のために失望の色を濃くしたのでしょう。 二、主の取扱いを受けて立ち直り、主から重大な任務を命じられたエリヤ(5~18節) 主は、心身ともに疲労困憊していたエリヤに対して、まず十分な睡眠と食物を与えられました(5~7節)。こうして彼は、肉体的な疲労が取れ、元気を回復しました(8節)。 次に主は、エリヤに悩みを打ち明けさせるとともに(9、10節)、風と地震と火のあとに彼に現れて、かすかな細い声で語られました(11、12節)。彼は、この神の顕現と御声によって心に大きな変化を受け、慰めと希望が与えられたのではないでしょうか。 「神の答えは、あなたは神の性格と御旨と行為を見て、敬虔にひざまずいて主をあがめなさい。......またあなたは自分の務めを果たし、その結果は神に任せなさい。神は後にこれらのことを明らかにされるからです、ということです」(A・イーダーシャイム)。 主は、エリヤにハザエルとエフーとエリシャに油をそそいで、それぞれアラムの王、イスラエルの王、エリヤに代わる預言者とするように仰せられました(15、16節)。これは、主の契約を破ったイスラエル人はアラムの王ハザエルに殺され、アハブの家はイスラエルの王エフーに滅ぼされ、エリシャはエリヤの任務を受け継ぐことを意味しています。こうしてエリヤは、主から重大な任務を命じられて、前進して行かなければならないのです。 また主は、エリヤだけが主に熱心に仕えているのではなく、「恵みの選びによって残された者」(ローマ11章5節)が七千人もいることを告げて、彼を慰められたのです(18節)。 三、エリシャを見つけ、彼を後継の預言者として認めて任命したエリヤ(19~21節) エリヤは、エリシャを見つけると、自分の外套を彼に掛けました(19節)。これは、後継の預言者として彼を認め、彼を任命したことを教えています。 エリシャは、すべてを捨ててエリヤに従っただけでなく(20節)、家族の者たちと別れるために一くびきの牛の肉を調理し、彼らに与えて、それを食べさせました(21節)。 神にすべてをささげて、主に仕えようとする者は、いままで与えられていたすべてのものを捨てることだけで決して満足してはなりません。それとともに以前に持っていたもの、また行っていたことを新しい務めのために聖別しなければならないのです。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2012.08.20
コメント(0)
-
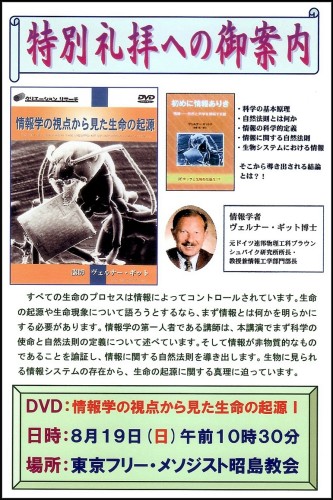
説教要約 790
「全能の神に拠り頼む訓練(2)」 甲斐慎一郎 列王記第一、18章 雨が降らくなってから三年半の歳月が流れました(ヤコブ5章17節)。エリヤがききんを預言したことによって、それが効を奏するとすれば、すでにあるはずです。しかしアハブもイスラエルの民も、このようなことがあっても悔い改めようとはしませんでした。 一、アハブに会いに行くためオバデヤに会い、彼に取り次ぎを命じたエリヤ(1~15節) 「そのころ、サマリヤではききんがひど」く(2節)、しかも夏でしたので、イゼベルはサマリヤの宮殿を出て、イズレエルにある避暑の宮殿にいました(45、46節、21章1、2節参照)。神の摂理によってイゼベルがサマリヤにいなかったので、アハブは、オバデヤを呼び寄せ、草を見つけるために、ふたりで国を二分して巡り歩くことができただけでなく(3~6節)、その後、エリヤの挑戦に応じて自らカルメル山に行くのです(20節)。 主はエリヤにアハブに会いに行くように命じられました(1節)。エリヤはアハブに会いに行くためにオバデヤに会い、王に取り次ぐよう彼に命じました(7、8節)。 二、アハブに偶像の預言者を集めさせ、彼らに信仰の戦いを挑んだエリヤ(16~29節) エリヤは、アハブに偶像の預言者をカルメル山に集めさせ、大胆にもひとりで四百五十人のバアルの預言者に立ち向かい、主が神であるのか、それともバアルが神であるのかという信仰の戦いを挑みました。そのために祭壇を築き、たきぎの上に雄牛を載せ、「火をもって答える神、その方が神である」と民に信仰の決断を迫りました(20~24節)。 バアルは火の神でしたが、バアルの預言者たちが声をからして朝から昼まで叫んでも、剣や槍で自分たちの身を傷つけても火を呼び下すことはできませんでした(26~29節)。 この日、カルメル山の上で起こった事件は、イスラエルの歴史の中で特別な出来事です。聖書は山上の光景を三つ教えています。 「第一はシナイ山上においてモーセを通して契約を結んだ時、第二はカルメル山上においてエリヤを通して契約を確認した時、第三は変貌山上においてモーセとエリヤがキリストについて荘重なあかしをし、そして契約は、このキリストによって完了し、変貌し、一新された時です」(A・イーダーシャイム)。 三、天から火を呼び下し、主が神であることを民に明らかに示したエリヤ(30~40節) エリヤは、壊れていた主の祭壇を建て直し、たきぎの上に雄牛を載せただけでなく、その上に三度も水を注がせました(30~35節)。晩のささげ物をささげるころになると、主に祈りました(36節)。この時、エリヤではなく生ける神ご自身が手を伸ばし、奇蹟を行われました。この御手を動かしたのは祈りでした。その祈りは主こそ神であることを沈着冷静にとらえつつ、火のように激しい熱心さでみわざを行ってくださることを求めています。 民はひれ伏して、「主こそ神です」と言いました(39節)。こうしてイスラエルは悔い改めて神に立ち返りました。アハブは、事の一部始終をしばし茫然として眺めていましたが、やがてこうべを垂れ、しばらくの間、主に対して悔い改めの心を表したのです。 四、祈りによって大雨を降らせ、アハブの前を走って帰途についたエリヤ(41~46節) しかしエリヤの奉仕は、これで終わったのではありません。彼は、苦しみ悶えて七度も祈り、主が彼の祈りに答えてくださったので、三年半ぶりに雨が降りました(41~45節)。 「エリヤは、悔い改めた王の前を走ることを恥とせず、かえってそのことをイズレエルに伝える先駆者になろうとしています。イズレエルの入口まで新しい知らせを伝えに行きました。その門まで神の警戒の声のように先駆をなしました。しかしアハブは門をはいるならば、再び誘惑者(イゼベル)に会おうとしています。両者(アハブとイゼベル)は、この門のそばで相離れなければなりません。以後イスラエルの王は、主につくか、またはイゼベルの神につくかを決断しなければならないのです」(A・イーダーシャイム)。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2012.08.14
コメント(0)
-
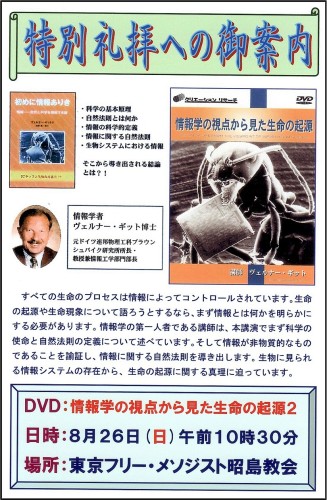
説教要約 789
「全能の神に拠り頼む訓練(1)」 甲斐慎一郎 列王記、第一、17章 イスラエルの背教は、アハブの治世にその頂点に達しました。しかし主は、この堕落を食い止めるために旧約時代において最大の預言者であるエリヤを遣わされました。 一、アハブの前に立ち、二、三年の間は露も雨も降らないことを預言したエリヤ(1節) エリヤは、「毛衣を着て、腰に皮帯を締めた人でした」(第二列王1章8節)。彼は、服装だけでなく、その使命においても旧約におけるバプテスマのヨハネであるということができます(マタイ3章4節、17章11、12節)。アハブの前に忽然と現れ、「ここ二、三年の間は露も雨も降らないであろう」と預言すると、王の前から忽然と姿を消しました(1節)。 エリヤは、アハブの預言者と祭司は主を知らず、主に対して全く無力であることを教えるためにこのような奇怪な行動をとったのでしょう。そして、神のことばは必ず成就することを心から信じて、「雨が降らないように祈」ったのです(ヤコブ5章17節)。 二、ケリテ川のほとりに行って住み、主の命を受けた烏に養われたエリヤ(2~7節) エリヤは、主のことばに従ってケリテ川のほとりに行って住み、主の命を受けた烏に養われました(3~6節)。それにしても烏がパンと肉を運ぶとは何とも心もとない話です。 エリヤは、ミデヤンの荒野において神の教育を受けたモーセのように、いや主イエス・キリストのように、ただ神とともにあってイスラエルのために祈り、また将来のために準備しなければなりませんでした。このようにしてイスラエルを滅亡から救うために、自然の世界を支配しておられる全能の神に拠り頼む訓練を受けたのです。 三、ツァレファテに行って住み、主の命を受けたやもめに養われたエリヤ(8~16節) しばらくすると、ケリテ川がかれたので、エリヤは、主のことばに従ってシドンのツァレファテに行って住み、主の命を受けたひとりのやもめに養われました(7~16節)。 「イエスがこの出来事を引用された箇所は(ルカ4章25、26節)、三つのことを教えています。第一は、エリヤをもてなすことはツァレファテのやもめに与えられた特権であること、第二は、この特権は彼女に真の霊的祝福となること、第三は、神はユダヤ人だけの神ではなく、異邦人にとっても神であること(ローマ3章29節)です」(A・イーダーシャイム)。 エリヤは、よりによって自分のいのちを狙うイゼベルの生まれたシドンに行き、イスラエルではなく異邦人の町であるツァレファテに住み、しかも最後の食事をして死のうとしているような貧しいやもめに養われました。このようにしてイスラエルを滅亡から救うために、人間の世界を支配しておられる全能の神に拠り頼む訓練を受けたのです。 四、重い病気のために息を引き取ったやもめの息子を生き返らせたエリヤ(17~24節) ところが、やもめの息子が重い病気になり、息を引き取りました(17節)。これは、やもめはもちろんのこと、エリヤにとっても大きな信仰の試練でした(18節)。しかしエリヤの望みえない時に望みを抱く信仰と執拗な祈りによって、その子は生き返りました(19~23節)。やもめは生き返った息子を腕に抱き、エリヤに「今、私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主のことばが真実であることを知りました」と言いました(24節)。 「これは、このやもめが最初にエリヤを迎えた時、すでに学んだことであり、また日々の食事の際に目撃したことでした。そして神は、ことばに表せない彼女の思いと祈りに答えて、神が人をお取り扱いになる最も高尚な意味は、さばきではなくあわれみであり、刑罰と復讐ではなく愛と赦しであることを示された時、彼女は、このことを知ることができました」(A・イーダーシャイム)。 このようにして彼は、イスラエルを滅亡から救うために、人間のいのち--肉体的、精神的そして霊的ないのち--を支配しておられる全能の神に拠り頼む訓練を受けたのです。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2012.08.07
コメント(0)
-
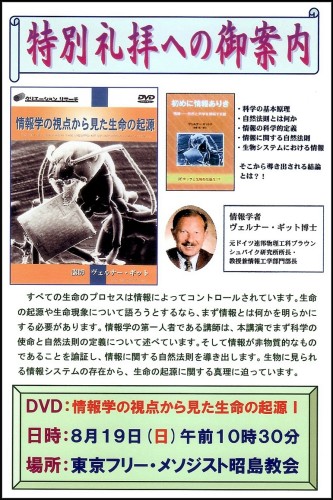
説教要約 788
「救いの達成に努めなさい」 甲斐慎一郎 ピリピ人への手紙、2章12~16節 「恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行わせてくださるのです」(12、13節)。 真の救いには、常に「恐れおののいて自分の救いの達成に努める」という人のなすべき分と、「神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行わせてくださる」という神のなさる分との両面があります。 しかし聖書が初めから終わりまで私たちに勧めていることは「怠ることなく常に目を覚まして励み」、しかも「思い煩うことなく重荷を主に委ねて安息する」ことです。 この「励みつつ安息する」または「安息しつつ励む」ということを可能にする秘訣は、人のなすべき分と神のなさる分とをきちんとわきまえて、前者にのみ心を配り、後者は神に任せることです。しかしこれを反対にするなら、思い煩って焦り、心の安息と気力を失い、怠慢になるのです。 一、神の前になすべきこと 神の前において人間のなすべき分は何でしょうか。このように言われると人はすぐ「あれもしなければ、これもしなければ、あれもしていない、これもしていない」と考えてしまいます。しかし神の前において私たちの果たすべきことは決して多くありません。 聖書全体から学んでみると、第一は、神のことばによって示された罪を悔い改めて神に立ち返る「悔い改め」です。第二は、神のことばを信じて立ち上がる「信仰」です。第三は、神のことばに従う「服従」です。第四は、神のことばに従って神にすべてをささげ、お任せする「献身」です。ほかのことはみな、この四つのことについてくるものであり、私たちがこの四つのことをする時、神は私たちにほかのことをも行わせてくださるのです。 ですから私たちは、この四つのことを果たすことを忘れて、「あれもできていない、これもできていない」と言って、嘆いたり思い煩ったりしてはなりません。この四つのことを果たし、後のことは神に任せて、神が行わせてくださることをしていればよいのです。 二、自分のなすべきこと 人間は、たとえどんなに良いことをしようとも、反対にどんなに悪いことをしようとも、神の前に出られるのは、キリストの十字架のゆえに先の四つの条件を果たす時だけです。これ以外に人間は神の前に立つことはできません。しかし「それでは、さんざん悪いことをして、最後に悔い改めればよいだろう」というのは、その動機と方法において間違っていることは明らかです。 それで自分自身に対して心がけなければならない最も大切なことは、動機の純粋さと方法や手段の正しさです。これこそ人のなすべきことであり、結果は神がよいようにしてくださるのです。 結果は神のなさる分であり(箴言16章33節、21章31節)、人の力ではどうすることもできないことですから、私たちとしては、純粋な動機と正しい方法で物事を行い、結果は神に任せることが必要です。しかし良い結果のみを夢みて、動機の純粋さも方法の正しさも心がけなければ、結果が良くても悪くても、それは私たちをつまずかせ、神のみこころをそこなうことになるのです。 三、ほかの人になすべきこと 私たちは、人に対しても純粋な愛の動機と正しい方法(忍耐と謙遜と知恵)をもって接することが人のなすべき分です。その結果、ほかの人々がどのような態度をとろうが、私たちは、思い煩うことなく、神に委ねて、心を安んじていればよいのです。そして純粋な動機と正しい方法で物事を行う秘訣は、先の四つの条件を果たすことです。 このようにする時、「すべてのことを、つぶやかず、疑わずに行い......非難されるところのない純真な者......傷のない神の子どもとなり......彼らの間で世の光として輝く」ことができるのです(14~16節)。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2012.08.01
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1










