2012年02月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
説教要約 766
「山の霊的な教え」 甲斐慎一郎 詩篇24篇1~6節 聖書は神の霊感によって記された神のことばですが、その文体や用語法は様々です。特に霊の真理を教えるための比喩的な用語法は実に多種多様です。同じことばであっても、いくつもの意味をもっています。 「山」ということばも、その一つであり、旧約聖書の中では、次に記すような九つの意味があります。キリスト教と異教とを問わず、「山」と「宗教」とは、切っても切れない関係にあるようです(第一列王20章23節)。九つの中で特に重要な三つを選んで、「山」の霊的な教えについて学んでみましょう。 1.「私は山に向かって目を上げる」(詩篇121篇1節) これは神の被造物としての山を教えており、私たちは山を見る時、それを造られた偉大な神を思うのです。 2.「山々よ。......地の変わることのない基よ」(ミカ6章2節) 山は、堅固で、不動のものの象徴です(イザヤ54章10節)。 3.「山々、丘々は義によって、民に平和をもたらしますように」(詩篇72篇3節) ここでいう山とは、国のことを指しています。 4.「ろばのあご骨で、山と積み上げた」(士師15章16節)、「山なすしかばね」(ナホム3章3節) 蓄積されたり、積み上げられたりして、多くなったり、大きくなったりしたものを山と呼んでいます。 5.「すべての山や丘は低くなる」(イザヤ40章4節) ここでは高慢な心を山にたとえています。 6.「山に逃げなさい」(創世記19章17節) 山は、安全な隠れ家や避難場所を意味しています。 この六つのほかに、さらに三つの意味があります。 一、「だれが、主の山に登りえようか」(詩篇24篇3節) 山は高い所です。ですから山とは、霊的には「信仰の高嶺」を意味しています。しかしここでいう山とは、単なる「信仰の高嶺」のことではなく、「聖なる所」(詩篇24篇3節)であり、「幕屋」(同15篇1節)です。すなわち「聖なる神の臨在される所」です。私たちが信仰をもって聖なる神に近づくなら、「主から祝福を受け、その救いの神から義を受け」て、「手がきよく、心がきよらかな者」(同24篇5、4節)とされるのです。 二、「主があの日に約束されたこの山地を私に与えてください」(ヨシュア14章12節) ここでいう「山地」は、直接的には文字通りの山ですが、私たちにとっては、「主があの日に約束された」とあるので、私たち人間が自分勝手に決めたものではなく、神のみこころにかなったものであり、それは、「キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目ざして一心に走」ることを表しています(ピリピ3章14節)。 私たちは、このような「山」に向かって走っているでしょうか。もし私たちがこのような「山」を持たなければ、目先の困難や罪に負けてしまい、この世の流れに流されて、惰性的に生きることになるでしょう。 三、「大いなる山よ。おまえは何者だ。......平地となれ」(ゼカリヤ4章7節) ここでいう「山」は、霊的には「神の国に敵対するサタンの国」を指していますが、一般的には「困難や敵の妨害」のことを意味しています。神のみこころの道を歩んでも、行く手に幾多の困難が立ちはだかりますが、信仰をもって困難の山に立ち向かうなら、神は、次のような救いを与えてくださるのです。1.困難が取り除かれて平地となる2.困難の山を乗り越えることができる3.困難の中を苦難のトンネルによって通過する 私たちは、聖なる神の臨在される「主の山に登」って、「手がきよく、心がきよらかな者」とされ、「神の栄冠を得るために、目標を目ざして一心に走」るなら、「大いなる山」は「平地とな」るのです。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2012.02.28
コメント(0)
-
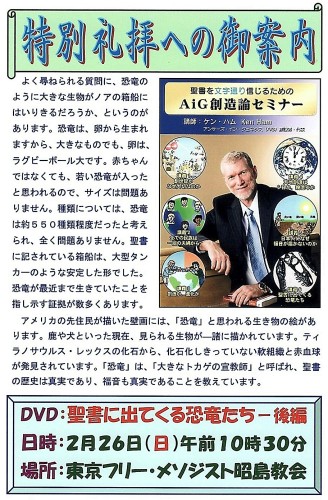
説教要約 765
「聖書に出てくる恐竜たち-後編」 AIG代表 ケン・ハム 創世記1章 五、恐竜は箱船に入ったか? よく尋ねられる質問 1.恐竜のように大きな生物が箱船に入りきるだろうか? 恐竜は卵から産まれるので、大きなものでも、卵はラグビーボール大である。赤ちゃんではなくても、若い恐竜が入ったと思われるので、サイズは問題ない。 2.恐竜はたくさんの「種」があるが、全てが入るだろうか? 聖書の分類区分の「種類」で考えると、恐竜は約550種類程度だったと考えられ、まったく問題ない。 3.箱船に本当に全ての生物が入ったのか? 聖書に記されている箱船のサイズを知ろう。おとぎ話のようなひっくり返りそうな形ではなく、大型タンカーのような安定した形であった。 六。箱船はキリストの型 1.ノアとその家族、そして動物たちが箱船に乗り込んでから7日間、扉は、聞いていた (創世記7章4、10節)。「義の伝道者」であったノア(第二ペテロ2章5節)は、扉の入り口に立って、人人に向かって主のさばきの警告を発し、箱船に入るように招いていたことだろう。現代においては、やがて来る火のさばきを免れるよう、主イエス・キリストの門が開かれている(第二ペテロ3章6、7節)。「わたしは門です。だれでも、わたしを通ってはいるなら、救われます」(ヨハネ10章9節)。 七、聖書に出てくる恐竜:「ベヘモス」ヨブ記40章15~24節 1.新改訳聖書と口語訳聖書では「河馬(かば)」と訳されているが、ヘブル語では「ベヘモス」と呼ばれる生き物である。「杉の木のような尾」「青銅の管のような骨]「鉄の棒のような肋骨」は、カバやゾウには当てはまらないが、ブラキオサウルスのような竜脚類の恐竜であれば、ぴったりくる。 八、恐竜が最近まで生きていたことを指し示す証拠の数々 1.アメリカの先住民が描いた壁画には、「恐竜」と思われる生き物の絵がある。鹿や犬といった現在、見られる生物が-諸に描かれている。 2.ティラノサウルス・レックスの化石から、化石化しきっていない軟組織と赤血球が発見された。 九、結論 「恐竜」は、「大きなトカゲの宣教師」である。聖書の歴史は真実である。そして福音も真実である。 甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2012.02.20
コメント(0)
-
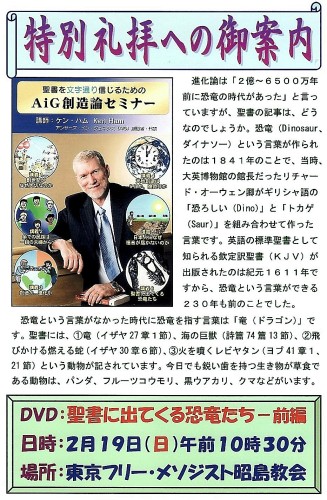
説教要約 764
「聖書に出てくる恐竜たち-前編」 AIG代表 ケン・ハム 創世記1章 進化論では「2億年~6500万年前に恐竜の時代があった」と言っているが、聖書は、恐竜についてどのように記しているのであろうか。 一、聖書の歴史観:「恐竜が通った7つの時代」 1.「創造された」時代 恐竜は、厳密には陸の生き物を言う。つまり恐竜は、創造の6日間の6日目に人間よ り前に創造された。海竜や翼竜は、5日目に創造された(創世記1章)。 2.「恐くない」時代 創造当初は、人も動物もみな菜食だった(創世記1章29~30節)。肉食が正式に許可されたのはノアの洪水の後のことである(創世記9章3節)。 3.「堕落」の時代 アダムが創造主からの唯一の命令に背いて罪を犯したとき、この世界がのろわれ、死が入ってしまった(創世記3章)。動物の間に肉食するものが現われ、互いを恐れるようになった。恐竜の化石を調べると、骨に噛まれた跡の歯形が残っていたりして、洪水前から肉食が始まっていたことを示す証拠がある。 4.「大洪水」の時代 大洪水のさばきを逃れるため、ノアは創造主に命じられたとおり箱船を作った。創造主は「各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地をはうものすべてのうち、それそれ二匹ずつ」をノアのもとに連れてきて、箱船に入れた(創世記6章)。 5.「消えていった」時代 今日知る限りにおいて生きている恐竜は見つかっていない。今日、色々な動物の絶滅が危惧されているように、恐竜も環境の変化・天災・人間による狩猟によって徐々に減少していったと思われる。 6.「発掘」された時代 恐竜の化石が世界各地で見つかっている。進化論で恐竜時代のものとされていた「ウオレミ松」や「シーラカンス」は、「生きた化石」として見つかり、今日も生きている。 7.「作り話」にされた時代 巨大な恐竜の化石は、特に子どもたちの心をとらえるが、常に、「何千万年前」と説明されて、進化論の広告塔にされている。私たちは、恐竜の本当の歴史を伝える必要がある。 二、聖書に「恐竜」という言葉が出てこない理由 恐竜(Dinosaurダイナソー)という言葉が作られたのは1841年のこと。当時大英博物館の館長だったリチャード・オーウェン卿が、ギリシャ語の「恐ろしい(Dino)」と「トカゲ(Saur)」を組み合わせて作った言葉。英語の標準聖書として知られる欽定訳聖書(KJV)が出版されたのは1611年のことで、恐竜という言葉ができる230年も前のことだった。 三、ドラゴン伝説 1.「恐竜」という言葉が作られていなかった時代に、そのような生き物を指す別の言葉があったはずである。それは、「竜(ドラゴン)」という言葉だと考えられる。世界各地に残されているドラゴン伝説は、実際の生き物(すなわち現代では「恐竜」と呼ばれる生き物)に関するものではないだろうか。例:ウェールズの国旗、「聖ジョージとドラゴン退治」の物語。 2.聖書にも、竜やその他、恐竜・海竜・翼竜を指すような生き物の描写がある。 (1)竜(イザヤ27章1節)、海の巨獣(詩篇74篇13節)。 (2)飛びかける燃える蛇(イザヤ30章6節)。 (3)火を噴くレビヤタン(ヨブ記41章、1、21節)。 (4)火を噴く(?)生き物の例:bombardier beetle(爆弾甲虫) (5)日本のミイデラゴミムシ(俗に言うヘッピリムシ)の仲間。お 尻から100℃の高温ガスを爆発的に噴出して敵を追い払う。 四、恐竜が草食? 1.恐竜のように鋭い歯を持っている動物が草食であったはずがないという考えに対して、今日にも鋭い歯を持つ生き物が草食であるケースはいくつもある。 (例)パンダ、フルーツコウモリ、黒ウアカリ、クマ 今とは違い、罪が入る以前の時代には、すべての動物が草食であった(創世記1章29~30節)。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2012.02.13
コメント(0)
-
説教要約 763
「集注の霊的な教え」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第二、10章1~6節 「私たちは、さまざまの思弁と、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべてのはかりごと(文語訳、思い)をとりこにしてキリストに服従させ」(5節)。 パウロは、主の尊い血によって贖われ、罪から救われたキリスト者は、「代価を払って買い取られたのです。ですから自分のからだをもって、神の栄光を現しなさい」と勧めています(第一コリント6章20節)。しかし神の栄光を現すためには、私たちの心とすべての思いをとりこにしてキリストに服従させなければなりません。 「集注」ということばがあります。国語の辞書には、「注意力を分散させず、ただ一つの事に集めること」と記されています。 それでこの「すべての思い(文語訳)をとりこにしてキリストに服従させ」る(5節)ということを、私たちがキリストに心を集め注ぐという意味における「心の集注」という観点から学んでみましょう。 一、散漫な心について まず神に集注することができない心は、散漫な心や分散する心です。これを霊的に聖書のことばで表現すれば、「心定まらず、その霊が神に忠実でない」(詩篇78篇8節)ということです。このような定まらない心は、「よみのようにのどを広げ、死のように足ることを知らない」(ハバクク2章5節)貪欲が、その原因ではないでしょうか。 このような定まらない心の人は、世の中においては、優柔不断や意志薄弱で、付和雷同する弱い人間と見られていますが、聖書においては、そのような生易しいものではありません。それは、「心の定まらない者たちを誘惑し」(第二ペテロ2章14節)とあるように罪の誘惑を受け、また「心の定まらない人たちは、聖書......を曲解し、自分自身に滅びを招いています」(同3章16節)とあるように、まちがった教えや異端に誘われて、滅びに向かう者なのです。 二、二心について 次に神に集注することができない心は、二心です。ヤコブが「二心の人たち。心を情くしなさい」(4章8節)と言っているように、二心とは、真の神に従うか、バアル(偶像)に従うか「どっちつかずによろめいている」(第一列王18章21節)不純な心です。 このような心は、西洋の諺に、「二兎を追う者は一兎をも得ず」とあるように、無益なことであるだけでなく、キリストが「あなたがたは、神にも仕え、また富にも仕えるということはできません」(マタイ6章24節)と言われたように不可能なことです。 このような二心のある人は、「その歩む道のすべてに安定を欠」き(ヤコブ1章8節)、また「何を食べようか、何を飲もうか......何を着ようか」(マタイ6章25節)と言って思い煩うだけでなく、神を軽んじ、神を憎むこになるのです(同6章24節)。 三、集注する心について B・F・バックストンは、聖書には「一つの事」ということばが四回記されていると述べています。 1.一つの欠乏--「あなたには欠けたことが一つあります」(マルコ10章21節)。 2.一つの必要--「どうしても必要なことは......一つだけです」(ルカ10章42節)。 3.一つの願望--「私は一つのことを主に願った」(詩篇27篇4節)。 4.一つの目標--「私は......ただ、この一事に励んでいます」(ピリピ3章13節)。 このようなことから神に集注する心とは、「神よわが心さだまれり」(詩篇57篇7節、文語訳)とあるように最も大切な一つのことに心を定めることです。それは「神の国とその義とをまず第一に求め」る(マタイ6章33節)ことであり、このように神に集注した心にこそ、真の聖さと平安と力があるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2012.02.06
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-
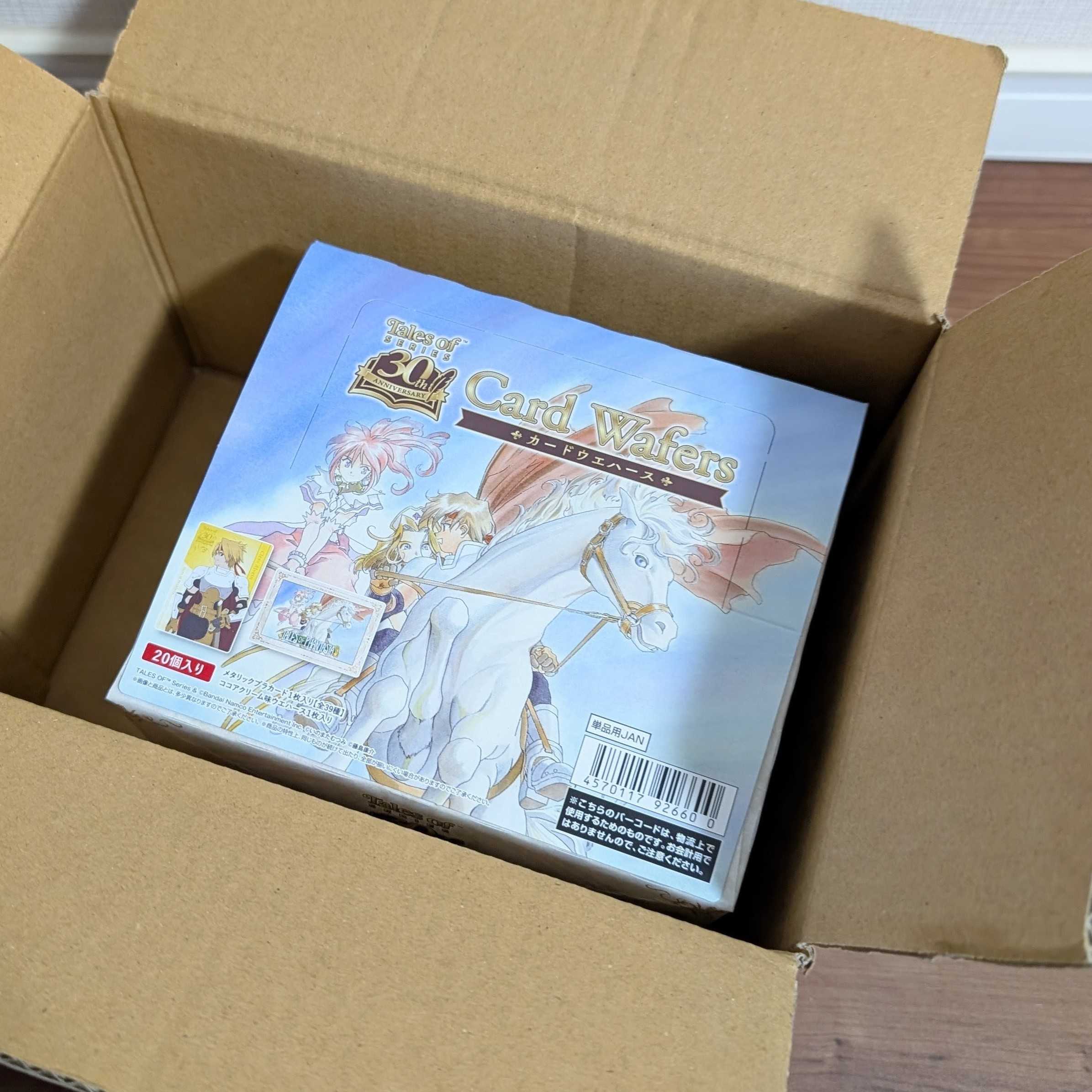
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 【楽天】人生初!胸アツ買いのテイル…
- (2025-11-25 21:50:38)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- お買い物マラソンで損したくないあな…
- (2025-11-25 20:30:05)
-
-
-

- つぶやき
- 里芋と厚揚げのひき肉餡掛け、アンチ…
- (2025-11-26 00:00:13)
-







