2012年07月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
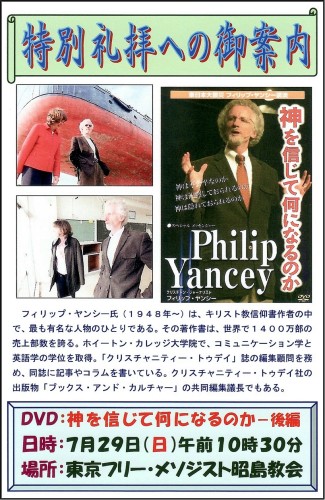
説教要約 787
「救いを受ける条件」 甲斐慎一郎 使徒の働き、26章14~18節 「彼らの目を開いて、暗やみから光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、わたしを信じる信仰によって、彼らに罪の赦しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである」(18節)。 イエス・キリストが宣教を開始して最初に語られた言葉は、「時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい」であり(マルコ1章15節)、パウロも、その伝道の生涯において、はっきりと主張したことは、「神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰」でした(使徒20章21節)。 冒頭に掲げたみことばは、パウロがダマスコの途上において回心し、その後、召命を受けた時、主イエスがパウロに語られたものですが、ここにも救われるための条件が明白に記されています。 一、認罪について 認罪とは、文字通り「罪を認めること」であり、これには三つの段階があります。 1.人に対する罪 まず私たちが罪と言われて、すぐに思い当たるのは、人に対する罪です。人を傷つけたり、人に害を与えたりしたことによって、自分の悪いところに気がつくことは、認罪の最初の段階です。 2.自分自身の罪 次に私たちは、たとえ誰をも傷つけず、また誰にも害を与えなくても、自分の中に悪い思いや罪深い心があることに気がつかなければなりません(マタイ5章22、28節)。これが認罪の第二段階です。 3.神に対する罪 ダビデが「私はあなたに、ただあなたに、罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました」(詩篇51篇4節)と告白しているように、罪は、究極的には神に対して犯したものであり、この神に罪を犯したという自覚こそ、聖霊による真の認罪です。そして、「神のほかに、だれが罪を赦すことができよう」(ルカ5章21節)とあるように、この真の認罪と神への悔い改めと十字架の贖いを信じる信仰によってのみ神から罪の赦しを受けることができるのです。 二、悔い改めについて これには二つの面があります。 1.神に対する心の悔い改め (1)悪い結果を悲しむことではなく、その原因である罪そのものを悲しむことです。 (2)後ろを振り向いて悔やむ後悔ではなく、前向きに神と真理の方へ転回することです。 (3)神と罪との両者に着いたり、中立になったりすることではなく、神のみに着くことです。 2.自分と他人に対する実際的な悔い改め (1)偶像や異教的なものをはじめ、私たちを罪に誘惑するすべてのいかがわしいものを捨て去ることです(使徒19章19節)。 (2)人と和解することです。このためには人に恨まれていたならば謝罪が必要であり(マタイ5章23~25節)、人を恨んでいたならば赦しが必要です(マタイ18章21~35節)。 (3)だまし取ったり盗んだりしていたならば弁償することです(ルカ19章8節)。 三、信仰について 真の信仰は、次のような三つのものから成り立っています。 1.心に信じることです(ローマ10章9、10節)。私たちはキリストが私たちの罪のために死んでくださったことを信じて、キリストを自分の救い主として心に受け入れなければなりません。 2.口で告白することです(ローマ10章9、10節)。次に私たちはキリストを信じたことを人々に告白しなければなりません(具体的には洗礼を受けることです)。そうする時、救われたという確信が与えられます。 3.信じた通りに歩み出すことです(コロサイ2章6節)。信仰は敢行(悪条件や困難を押し切って踏み出すこと)であり、信じた通りに歩み出す時、信仰は実を結び、不動のものとなっていくのです。 このように私たちが罪を認めて、悔い改め、主の十字架の贖いを信じる時、罪が赦されて、新しく生まれ変わり、神の子どもとされて、天の御国を受け継ぐ者とされるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2012.07.24
コメント(0)
-
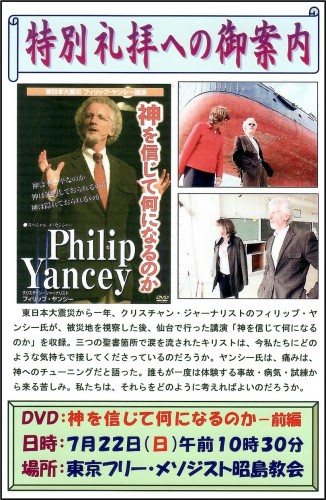
説教要約 786
「罪を赦す権威」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、5章17~26節 「神をけがすことを言うこの人は、いったい何者だ。神のほかに、だれが罪を赦すことができよう」(21節)。 これは、中風をわずらっている人を床のまま運んで来た人たちの信仰を見たキリストが「友よ。あなたの罪は赦されました」と言われた時、その場に座っていた律法学者とパリサイ人が心の中で言った言葉です。この言葉から、人間にとって最大の問題である罪について三つのことを学んでみましょう。 一、人が罪を犯す相手は究極的には神であることについて もし私たちが人々に、「人間は、なぜ罪を犯してはならないのか」と聞くなら、恐らく次のような答えが返ってくるでしょう。1.それは人間として恥ずべきことだから。2.それは人に迷惑をかけることだから。3.それは人に悪い影響を及ぼすから。4.それは家庭や社会の秩序を乱すから。 もしこのようなことが根本的な理由なら、恥ずべきことと思わず、人に迷惑をかけず、悪い影響も及ぼさず、家庭や社会の秩序を乱さなければ罪ではなく、何をしてもよいことになってしまうでしょう。しかし決してそうではありません。 これらの理由はみな、人間の都合に過ぎません。しかし罪は、人間の都合によってではなく、「律法を定め、さばきを行う」(ヤコブ4章12節)ただひとりの神の前に、どのような姿であるかによって決まるのです。 「神のほかに、だれが罪を赦すことができよう」という言葉は、裏を返せば、罪を犯す相手は神のみであることを教えています。ダビデは「私はあなたに、ただあなたに、罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました」と告白しています(詩篇51篇4節)。 二、人の罪を覚えてさばかれるのは神であることについて 人が制定した法律には、時効というものがあります。これは、あまり長い年月が経過すると、正確な事実関係を調査することが困難になるからであり、もし時効がなければ、事件が解決するまで永久に調査しなければならず、そのようなことは実際的には不可能であるために設けられたもので、有限な人間にとっては、やむを得ない措置です。 この時効という考え方があるために、私たちは、「罪などというものは、時間の経過とともに軽くなり、ついには消滅してしまうものである」と思っていないでしょうか。 しかし時間に拘束されない無限の神が定められた律法には、時効などというものはありません。すなわち常に現在しかない永遠の神の前には、過去の罪などというものはなく、どんなに古い罪でも、今犯したかのように、はっきりと覚えられているだけでなく、その罪は、私たちが悔い改め、キリストの贖いを信じて赦されない限り、積もり積もって、終わりの日に必ずさばかれるのです。 三、人の罪を赦す権威を持つのは神のみであることについて ひとりの人が、他の人を巻き込んで王に反逆し、陰謀を企てたが、それが発覚して捕らえられた場合、この首謀者は、同じ仲間に謝罪し、赦しを得るなら、その反逆罪は赦されるでしょうか。決してそんなことはありません。仲間の人は、巻き添えを食った犠牲者また被害者に過ぎず、この首謀者の罪を赦す権威を持つのは王のみです。 このように罪は、王である神への反逆であり、私たちは、その首謀者です。人に対する罪は、私たちの反逆のために他の人を巻き添えにした悲劇であるということができます。ですから私たちの罪を赦す権威を持つのは、ただ王である神のみなのです。 そして神は、その計り知れない恵みによって、心から罪を悔い改め、キリストの贖いを信じる者の罪を赦してくださるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2012.07.18
コメント(0)
-
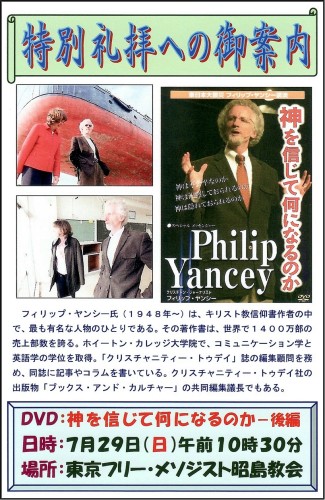
説教要約 785
「キリスト教の神髄」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、6章19~34節 マタイの福音書の五章から七章に書かれているキリストの教えは、「山上の説教」と呼ばれ、聖書の中で最も有名なことばが数多く記されています。 たとえば、「あなたの右の頬を打つような者には、左の頬を向けなさい」とか、「自分の敵を愛し......なさい」というようなことばはあまりにも有名です(5章39、44節)。 しかし私たちが、このような聖書の教えを真の神を信じる信仰を持たずに、ただ外側の行為だけを模倣しようとするなら、必ず行き詰まり、失望落胆して、果ては「キリスト教は、実行不可能なきれい事を教えているに過ぎない」と言って、聖書の教えやキリスト教を敬遠したり、非難したりするようになってしまうでしょう。 このような間違いは、どこから来るのでしょうか。それは、聖書が教えている最も大切で中心的な事柄を見失っているからです。そこで「キリスト教の神髄」とも言うべきことをこの箇所から学んでみましょう。 一、第一は、人に依存することではなく、神に拠り頼むことです キリストは、「あなたがたのうちだれが、心配したからといって、自分のいのちを少しでも延ばすことができますか」と言われました(27節)。私たちは、人のいのちに関すること、また明日や未来のこと、そして死や罪の問題などは、人間の力ではどうすることもできないことを認めなければなりません。 キリスト教は、人間の力の限界を認めず、それを過信して、人に依存する宗教ではありません。謙虚に人間の力の限界を認め、生殺与奪の権を握っておられる偉大な神の力を信じ、すべてをゆだねて神に拠り頼む宗教です。 二、第二は、物質的な御利益の追及ではなく、内的な救いを求めることです キリストは、「神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます」と言われました(33節)。 キリスト教は、この世における物質的な祝福や恩恵を得るために打算的に神を信じる御利益宗教ではありません。神とその救いを求めることによって、心が変えられて、神を喜ばせることを目的とする内的な宗教です。 私たちが神とその救いをまず第一に求めるなら、神は、それに加えて、必要なものはすべて与えてくださいます。ですから私たちは、「何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配する」必要は全くないのです(31節)。 三、第三は、外側の行為の模倣ではなく、心の生まれ変わりです キリストは、「もしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし、目が悪ければ、あなたの全身が暗いでしょう」と言われました(22、23節)。ここで言う「目」とは、意図や動機また心や霊性を指しており、「全身」とは、行為や行動また品性や人格など私たちの全存在を意味しています。 キリスト教は、キリストとその弟子たちの模範的な行為や高潔な人格を学んで、それを自力で模倣する宗教ではありません。心の中に罪を持っている私たちは、このような外側の行為を模倣することは不可能です。 キリストは「あなたがたは新しく生まれなければならない」(ヨハネ3章7節)と言われました。私たちは、罪を認めて、悔い改め、キリストは十字架の上で、私たちの罪をその身に負ってくださったことを信じるなら、新しく生まれ変わることができます。 このように新しく生まれ変わることによってのみ、良いことを行い、立派な人格が形造られるだけでなく、いままで罪のために妨げられていた神からの賜物や才能また様々な能力が十分に発揮されて、神に喜ばれる人に変えられていくのです。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2012.07.08
コメント(0)
-
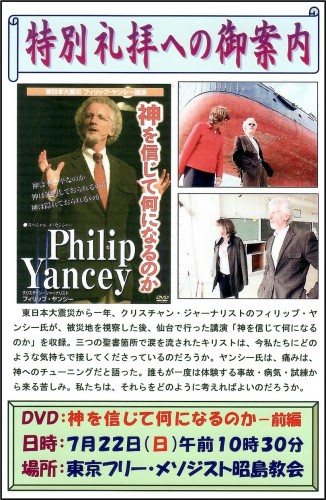
説教要約 784
「神を信じなさい」 甲斐慎一郎 使徒の働き、17章16~34節 この箇所にはパウロのアテネにおける伝道が記されています。エルサレムを宗教の都、ローマを政治の都と呼ぶならば、アテネは学問の都です。このアテネにおけるパウロの説教は、学問の都にふさわしく、極めて論理的であり、巧みな導入の序論から始まり、核心を突いた説得力のある本論へ話を進め、そして決断を促す結論に至るまで、実に見事であり、模範的な説教の良い実例です。 一、パウロの説教のきっかけ(16~21節) 一足先にアテネに来て、アテネでシラスとテモテを待っていたパウロは、「町が偶像でいっぱいなのを見て、心に憤りを感じ」ました(16節)。「アテネの町の人の数よりも、その町の神々の数のほうが多かった」と記録している人がいるほどです。日本語に「八百万の神々」という言葉がありますが、現在の日本と非常によく似ています。この彼の憤りは罪に対する義憤ですが、それはすぐに人々に福音を語る情熱に変わっていきました。 そこでパウロは、会堂ではユダヤ人や神を敬う人たちと、広場ではエピクロス派とストア派の哲学者たちと論じました(17、18節)。エピクロス派の創始者は、エピクロスで、最高善は快楽であると教えました。しかしその快楽は、刹那的な享楽ではなく、全生涯にわたる幸福を追求するように説きました。これに対してストア派の創始者は、ゼノンで、最高善は徳であると教えました。すべてのものが神であるという「汎神論」的思想をもち、自然に従うことが幸福であると説きました。 彼らはパウロをアレオパゴス(裁判をするためにアテネにあった評議所)に連れて行き、パウロが語っている新しい教えを聞きたいと言い出しました(17~20節)。パウロにとっては、彼らに福音を語る絶好の機会でした。 二、パウロの説教の内容(22~31節) アテネの人たちは、多くの偶像を拝んでいましたが、それでも、拝み忘れていた神々があることを恐れて、「知られない神に」と刻んだ祭壇まで造って拝んでいました。パウロは、偶像を見て心に憤りを感じましたが、その憤りをそのまま言葉に出すような知恵のないことはしませんでした。 かえって、「あらゆる点から見て、私はあなたがたを宗教心にあつい方々だと見ております」と言って、彼らの宗教心に訴え、「あなたがたが知らずに拝んでいるものを教えましょう」と偶像さえも真の神を教える材料として巧みに用いたのです(22、23節)。 パウロは、真の神はどのような方であるかということを偶像と対比させながら、次のように分かりやすく述べています。 1.真の神は、すべてのものをお造りになった方です(24節) 人間が造ったのが偶像であるのに対して、人間をはじめすべてのものをお造りになったのが真の神です。 2.真の神は、すべてのものをお与えになった方です(25節) 人から与えられるのが偶像であるのに対して、人にすべてのものをお与えになるのが真の神です。 3.真の神は、すべての人をおさばきになる方です(31節) 人に品定めをされて、さばかれるのが偶像であるのに対して、すべての人をおさばきになるのが真の神です。 人は、このような「神の中に生き、動き、また存在している」(28節)にもかかわらず、そのことを知らずに、偶像を拝み、罪を犯して来ました。そこで神は、「すべての人に悔い改めを命じておられ」るのです(30節)。 三、パウロの説教の結果(32~34節) パウロの説教を聞いた人々は、どのような反応を示したでしょうか。聖書は次のような三種類の人たちがいたことを教えています。 1.ある者たちは、死者の復活のことを聞いてあざ笑った(32節)。 2.ほかの者たちは、「このことについては、またいつか聞くことにしよう」と言った(32節)。 3.信仰にはいった人たちがいた(34節)。 この反応は、いつの時代のどの国の人々も同じです。私たちは、どうでしょうか。甲斐慎一郎の著書→説教集東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2012.07.03
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1










