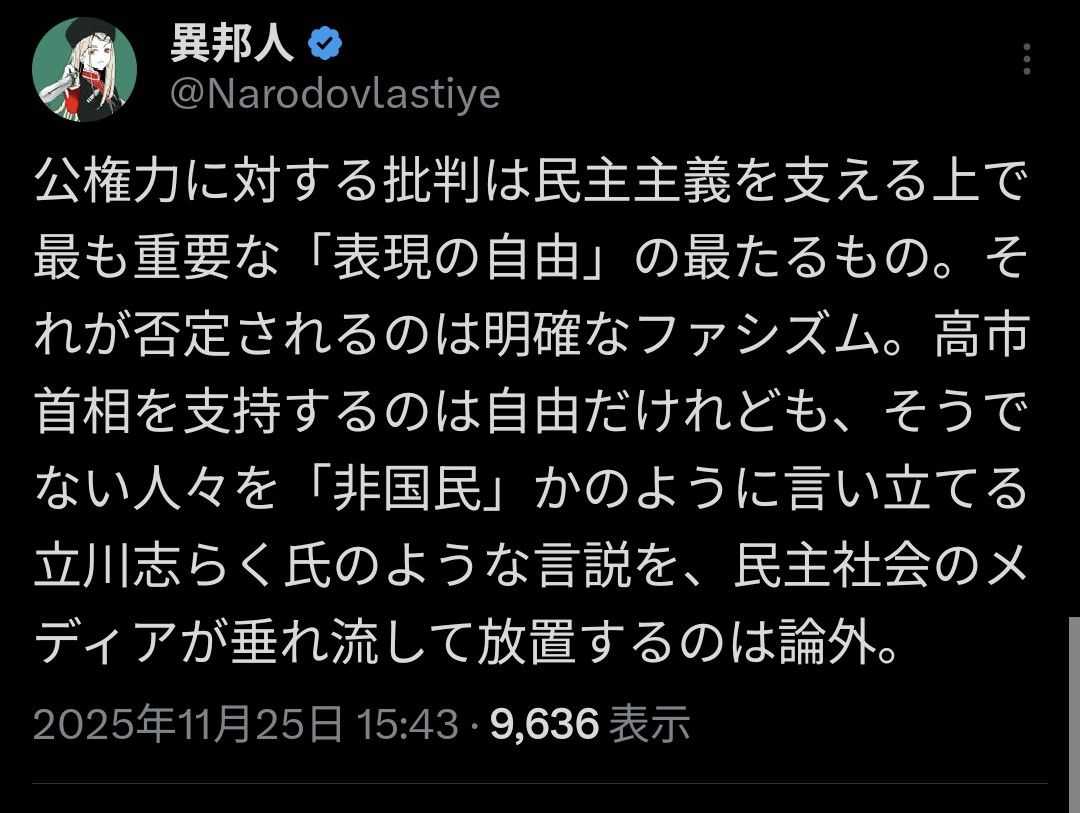2019年04月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
説教要約 1149
「神の道と人の道」 2019年4月28日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2014年7月11日放映「覚えることと忘れること」 「神の道と人の道」 甲斐慎一郎 イザヤ書、55章1~9節 「わたしの思いは、あなたがたの思いと異なり、わたしの道は、あなたがたの道と異なるからだ。――主の御告げ。――天が地よりも高いように、わたしの道は、あなたがたの道よりも高く、わたしの思いは、あなたがたの思いよりも高い」(8、9節)。 「道」という言葉には辞書を引くと十種類ほどの意味があります。①道路、②途中、③専門、④方法、⑤道徳、⑥教え、⑦道程、⑧歩み、⑨筋道、⑩分別 しかしここでは、単なる道ではなく、「人が生きる」ということに関連づけて、「人が生きる方法」、「人が生きる道徳」、「人が生きる教え」、「人が生きる道程」「人が生きる歩み」、「人が生きる筋道」、「人が生きる分別」という意味を加えるので、「神の道と人の道」というのは、ともに記されている「思い」という言葉から、神の道は、「人が生きるために必要な、神が思い、また考える道」、人の道は、「人が生きるために必要な、人が思い、また考える道」ということで学んでみましょう。 一、三種類の道 私たちの生涯には、様々な方面において大切な道というものが数多くありますが、人間の三つの要素である「からだ」と「たましい(心)」と「霊」に関して述べるなら、代表的なものは、次のような三つの道です。 1.生活の道(からだに関して) これは、衣食住を支える生計の道、また健康を保ち、生命を維持する生きていくための道のことです。 2.人生の道(心に関して) これは、ただ生活のために生きるのではなく、一生をどのように生きるのが私たち人間の責務であるのかという人として歩むべき道のことです。 3.救いの道(霊に関して) これは、この世の人生だけでなく、次に来る世(来世)をも含めた永遠の世界において、「御前で聖く、傷のない者」(エペソ1章4節)となり、聖なる神の前に立つことができるという天の御国に至る道のことです。 二、人の道 この三つの道に関して、人が思い、また考えることは、どのようなことでしょうか。 それは、まず生活の道が第一であり、それが人間の一生のほとんどを占めています。人生の道は二の次であり、これは、苦しみに会った時や、生涯の晩年に少し考える程度ではないでしょうか。最も後回しにするのは、救いの道であり、これは、死に直面した時や、何か特別なことがあって自分の罪深さを意識した時に求めることがありますが、自分で自分を救おうとする、むなしい努力をするだけで終わってしまうのではないでしょうか。 バビロンに捕囚になっていたイスラエル人は、神の宮が廃墟となっているのに、「自分の家のために走り回ってい」ましたが(ハガイ1章9節)、これこそ、大切な人生のことも、尊い「たましい」や「霊」の救いのことも考えず、ただ生活を支えることを第一として生きている罪深い生き方です。 三、神の道 これに対して、神が思い、また考える道は、どのようなものでしょうか。 それは、救いの道を第一とすることです。その救いは、神の招きに応じて(1節)、主を求め(6節)、その無代価の恵みにあずかり(1節)、罪を悔い改め、主に立ち返って、豊かに赦される(7節)という人の思いもよらない驚くべき救いです。 そしてこの救いを受けた人のみ、「地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神のみこころのために過ごすようになる」(第一ペテロ4章2節)という人生の道が分かってくるのです。 生活の道は、神のみこころにかなった人生を送るために必要な手段として、「神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます」(マタイ6章33節)という神の約束を信じて歩むことができるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集
2019.04.27
コメント(0)
-
説教要約 1148
「私たちの人生と復活」 2019年4月21日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2014年5月14日放映「イエスを仰ぎ見なさい(1)」「私たちの人生と復活」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第二、1章8~11節 キリストの復活は、キリスト教の福音において最も大切で中心的なものです。しかし世の中においても、一般的な意味における復活や復興ということは、非常に重要なことではないでしょうか。それでキリストの復活および一般的な意味における復活を問わず、復活について考えてみましょう。 一、復活――それは人間本来の願望です キリストの復活は後に述べるとして、私たちは、一般的な意味における復活というものを切に求めているのではないでしょうか。 からだが常に健康で、若々しく、生き生きとしていることを願わない人がいるでしょうか。不老不死は人間の悲願です。科学、特に医学は、このために少しでも貢献しようとしているのであり、体育やスポーツも同じではないでしょうか。 また精神的にも生きる喜びや希望に満ちていることを願わない人がいるでしょうか。文明の発達や文化の向上は、このような心の願いの当然の結果であるということができます。 そして霊的な面において、清く正しく生きることが人の道であり、もしそこから逸脱していれば、更生しようとするのが人のあるべき姿ではないでしょうか。道徳や倫理また宗教は、このことを私たちに教えています。 このように人間は、肉体的にも精神的にもそして霊的にも、復活や復興また更生を切に求めているのです。 二、復活――それは正真正銘の事実です キリストが復活したというと、多くの人々は、「死んだ人間が生き返るはずがない」と一笑に付してしまいます。しかしルカの福音書の24章には、キリストの復活が事実であることを証明する根拠が3つ記されています。 1.第一は、死体のない墓です この箇所には、3回も墓の中には主イエスのからだが見当たらなかったことが記されています(3、23、24節)。 2.第二は、キリストの顕現です この箇所には、エマオという村へ行く途中のふたりの弟子たち(15節)とシモン・ペテロ(34節)と11使徒(36節)にキリストが現れたことが記されています。彼らは、よみがえられたキリストを目撃した証人なのです(48節)。 3.第三は、聖書の証言です この箇所には、3回も聖書という言葉が記されており(27、32、45節)、キリストは聖書の預言の通りに死んで復活されたことを私たちに教えています。 三、復活――それは起死回生の秘訣です パウロは、アジヤで非常に大きな苦しみに遭った時、「非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ほんとうに、自分の心の中で死を覚悟しました。これは、もはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼む者となるためでした」と告白しています(第二コリント1章8、9節)。これは復活を信じる信仰です。 私たちのからだは、疲れたり、病気になったりすることがあります。しかし再び元気になったり、病気が治ったりすればよいのです。また様々な問題のために失望したり、落胆したり、挫折したりすることもあるでしょう。しかし再び立ち上がればよいのです。さらに信仰が死んだような状態になることがあるかも知れません。しかし再び生きた信仰を持てばよいのではないでしょうか。 キリストは、十字架の上で死なれましたが、よみがえられた方です。聖書は、「もし私たちが、キリストにつぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです」と教えています(ローマ6章5節)。 キリストの死と復活を信じる人は、たとえ倒れても、打ちのめされても、また死んだようになっても、再び起き上がり、生き返ることができます。キリストの死と復活を信じる信仰は、私たちに起死回生の力を与え、私たちが苦しみに満ちた人生を歩んでいくために不可欠なものなのです。甲斐慎一郎の著書→説教集
2019.04.20
コメント(0)
-
説教要約 1147
「罪を憎んで人を憎まず」 2019年4月14日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2014年5月6日放映「三つのさばき」「罪を憎んで人を憎まず」 甲斐慎一郎 テモテへの手紙第一、2章4節 「神は、すべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます」(第一テモテ2章4節)。 一、罪を憎んで人を憎まず――人の善悪を判断する時、感情移入をしないで、法律だけで人の善悪を判断することである 「罪を憎んで人を憎まず」という言葉には、様々な解釈がありますが、共通している解釈は「実現不可能な理想論」ということです。なぜなら「罪は憎むが、人は憎まない」ということは「罪」と「人」を分離しなければ到底不可能なことだからです。現実の問題として「罪」と「人」を分離することなど、絶対にできないことで、もし分離すれば、人間ではなくなってしまうからです。 法曹界の人(裁判官、検事、弁護士)が、「これは法の精神を教えるもので、人を裁く時、感情移入をしないで――容疑者に同情したり、容疑者を軽蔑したりしないで――ただ法律の文言だけで人を裁くことである」と説明していました。これは一般の人にも当てはまることで、人の善悪を判断する時、感情移入(同情や軽蔑)をしないで、法律や道徳の教えだけで人の善悪を判断することです。 二、罪を憎んで人を憎まず――法律と神の教えに従って、人の罪も自分の罪も許さない人こそ、正しく、きよい人である キリスト者を含めた世の人の中に、悪人の罪を赦すことは美徳であると考えている人がいますが、それは誤りです。聖書の教えによれば、「罪の赦し」は「義と認められる」ことと同じで(使徒13章38、39節)、「罪を犯さなかった者とみなす」という意味です。もし警察官や法曹界の人(裁判官、検事、弁護士)が容疑者の罪を許し、罪を犯さなかった者とみなすなら、社会は無法地帯となります。国民も法律を守って、人の罪も自分の罪も許さない人こそ善良な市民です。罪を憎む人は義人で、罪を愛する人は悪人です。「罪を憎んで」というのは、このような意味なのです。 三、罪を憎んで人を憎まず――人を罪に定める権威も罪を赦す権威も人にはないので、人も自分も神のさばきにゆだねることである それでは、警察官や法曹界の人(裁判官、検事、弁護士)、また善良な市民は、「罪を憎む」ことはよいとしても「人を憎んで」よいのでしょうか。決してそうではありません。 「罪」と「人」を分離することなどできませんから、罪を憎むことは、同時に人を憎むことでもあり、「罪を憎んで人を憎まず」というのは、「実現不可能な理想論」です。それでは、どうすればよいのでしょうか。そもそも「人を憎む」のは、「人の中に罪がある」からで、もし「人の中から罪が取り除かれる」なら、「人を憎む」ことはなくなるわけです。 しかし現実の問題として「人の中から罪を取り除く」ことなど、できるのでしょうか。「それは人にはできないことです。しかし、神にはどんなことでもできます」(マタイ19章26節)。神は、イエス・キリストをこの世に遣わし、キリストの十字架による罪の贖いによって「罪の行いを赦し」、「うちに住む罪をきよめ」てくださいます。私たちは、心から罪を悔い改めて、キリストが私たちの罪を贖ってくださることを信じるなら、義と認められ(罪が赦され)、さらに「イエスの血はすべての罪から私たちをきよめます」(第一ヨハネ1章7節)と信じるなら、聖霊によって「うちに住む罪」がきよめられます。 このように私たちの罪が取り除かれて、きよめられるなら、ほかの人が私たちに罪を犯した時、それは神に対して犯したもので、しかも「律法を定め、さばきを行う方は、ただひとりであり、その方は、救うことも滅ぼすこともできます」から(ヤコブ4章12節)、私たちには「人を罪に定める権威」も「人の罪を赦す権威」もなく、それは神のみ持っておられるので、私たちはその人を神のさばきにゆだねることができます。これが私たちにとって、その人の罪を赦すことになるのです。このようにして私たちは、「罪を憎んで、人を憎まず」ということができるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集
2019.04.13
コメント(0)
-
説教要約 1146
「神の報いと人の報い」 2019年4月7日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2014年4月1日放映「三つの現実」 「神の報いと人の報い」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、6章1~18節 「マタイの福音書」の六章1~18節には、「報い」ということに関して3回ずつ2つの言葉が記されています。 「彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです」(2、5、16節)。 「そうすれば、隠れた所で見ておられるあなたの父が、あなたに報いてくださいます」(4、6、18節)。 この前半の言葉には人からの称賛、すなわち人の報いについて、後半の言葉には神からの応答、すなわち神の報いについて記されています。しかし、ここでは人の報いは、「人が求める報い」、また神の報いは、「神が与えてくださる報い」として考え、特に両者は、どのような違いがあるのかということについて聖書全体から学んでみましょう。 一、人の報いについて 人が求める報いは、どのようなものでしょうか。 1.その期間――目先の報いを求める 私たちは、自分が何か良いことをした時は、直ちに良い報いを受けることを期待し、また他の人が私たちに何か悪いことをした時は、直ちにその人に悪い報いが来ることを願う心があるのではないでしょうか。 このように人は、自分に都合の良いことに関しては、できるだけ早く、できれば今すぐにでも報いが来ることを求めているのではないでしょうか。 2.その範囲――部分的な報いを求める 私たちは、自分のことに関しては、今までしてきた悪いことを棚上げして、一部の小さな善行に対して良い報いを期待し、また他の人のことに関しては、その人が今までしてきた多くの良いことに目をつぶって、その人の一部の悪行に対して悪い報いが来ることを願う心があるのではないでしょうか。 このように人は、自分に都合の良いことに関しては、すべての行為に対する報いではなく、部分的な善行や悪行に対して報いが来ることを求めているのではないでしょうか。 3.その性質――不当な報いを求める 良いことをすれば良い報いがあり、悪いことをすれば悪い報いがあるのが正当な報いです。私たちは、良いことをしている時は、良い報いを期待するのは当然のこととしても、悪いことをしている時も良い報いを期待する厚かましい心があるのではないでしょうか。 このように人は、良いことをしている時は、正当な報いを求めながら、悪いことをしている時は、不当な報いを求めているのではないでしょうか。 二、神の報いについて 神が与えてくださる報いは、どのようなものでしょうか。 1.その期間――永遠の報いを与える 神は、私たちが悪いことをした時は、私たちに悔い改めの機会を与えるために、また良いことをした時は、私たちが小成に安んじたり、高ぶったりしないように、良い報いも悪い報いも延ばすことがあります。 このように神は、私たちの善悪に対して近視眼的にではなく、長い目をもって、永遠の角度から報いを与えてくださるのです。 2.その範囲――総合的な報いを与える 神は、報いに関しては、私たちの一つの善行のために今までの多くの悪いことを見過ごしたり、また一つの悪行のために、今までの多くの良いことを忘れたりするような方ではありません(ヘブル6章10節)。神は、「善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて」(第二コリント5章10節)総合的な報いを与えられるのです。 3.その性質――正当な報いを与える 「患難と苦悩とは、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、悪を行うすべての者の上に下り、栄光と誉れと平和は、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、善を行うすべての者の上にあります」。「神にはえこひいきなどはな」く、どこまでも正当な報いを与えられる方なのです(ローマ2章9~11節)。甲斐慎一郎の著書→説教集
2019.04.06
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1