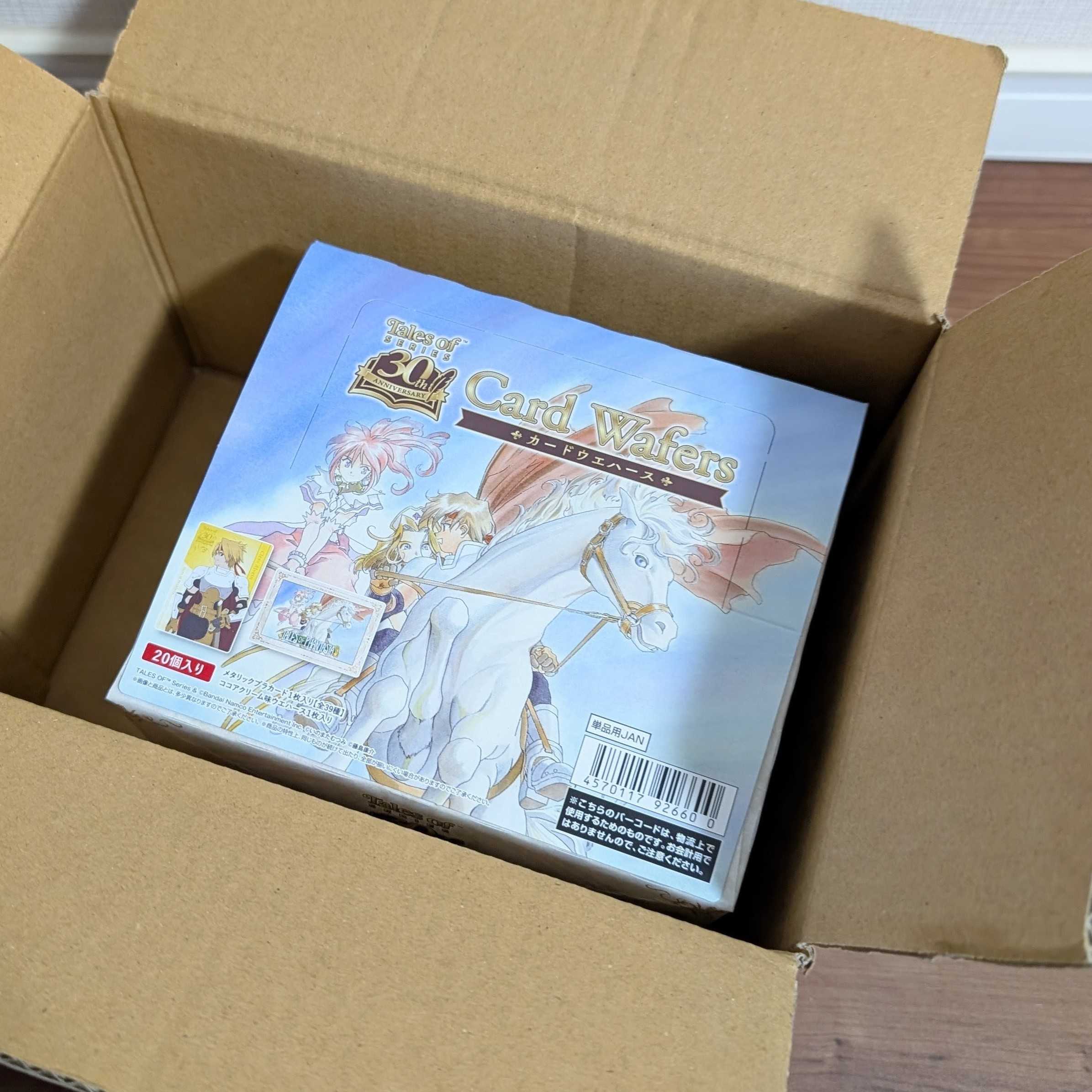2019年09月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
説教要約 1168
「根拠に基づいて神と福音を信じる」 2019年9月29日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2015年7月7日放映「神の啓示と人の探求」 「根拠に基づいて神と福音を信じる」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第一、15章2節 「あなたがたがよく考えもしないで(直訳、根拠なしに)信じたのでないなら……この福音によって救われるのです」(2節)。 一、真の信仰の三要素 H・オートン・ワイレーは、真の信仰は、「知性的に承認し、意志的に承諾し、信頼し、拠り頼む」ことであると述べています。 この言葉の中で大切なことは、第一の神を知性的に承認することであり、これがなければ、第二の意志的に承諾し、第三の信頼し、拠り頼むことはできません。神を知性的に承認することにおいて大切なことは、「根拠」や「証拠」です。根拠や証拠がなければ、知性的に承認することはできないからです。 二、論理的思考によって真理を発見する 「感情論」が「理性を忘れて感情に走った議論」で「自分だけの主観的な考えや思考」であるのに対して、「論理的思考は、根拠や証拠、すなわち客観的な事実や真理に基づいた考えや思考のことで、自然の法則・原理・原則を学び、その法則や法に従って物事を考え、その法や法則を駆使して証拠を見出し、真理や真相を発見するのです。現代科学は、目に見えないもの、すなわち五感で知ることができない実在の質や量を扱い、論理的思考で真理や真相を発見しているので、「神を知る方法」と同じです。 三、原語のギリシャ語の意味 冒頭の聖句は、原語のギリシャ語は、日本語において色々な言葉に訳されています。(1)理由なしに、根拠なしに (2)むだに、無益に、いたずらに、だてに これは、神への信仰と福音に関する言葉なので、「根拠なしに」が最善の訳です。なぜなら神への信仰と福音は、聖書が教えているように根拠に基づいて信じなければならないからで、決して「むだに、無益に、いたずらに、だてに」信じてはならないからです。 四、キリスト教は証しの宗教 旧新約聖書は、「証」という語を含む次のような五つのことを教えています。 ▼証明――事実の真偽を明らかにすること▼証拠――事実を証明する根拠のことで、これは「物の証し(物証)」 です。▼証人――事実を証言する人のことで、これは「人間の証し」です。▼証言――事実を証明する言葉のことで、これは「言葉の証し」です。▼心証――裁判官が心に得た確信のことで、これは「心の証し」です。 神は、ご自身を人間にあかししておられますが、これには五つの段階があります。 1.第一段階――自然界によるあかし 「ご自身のことをあかししないでおられたのではありません。すなわち、恵みをもって、天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとで、あなたがたの心を満たしてくださったのです」(使徒14章17節)。これは、神が創造された被造物による「物的証拠」です(ローマ1章19、20節)。 2.第二段階――預言者の声によるあかし 「この人はあかしのために来た。光についてあかしするためで」す(ヨハネ1章7節)。これは預言者の声による「証言」です。 3.第三段階――聖書の言葉によるあかし 「あなたがたは……聖書を調べています。その聖書が、わたしについて証言(あかし)しているのです」(ヨハネ5章39節)。これは、聖書の言葉による「証言」です。 4.第四段階――キリストによるあかし 「わたしが行っているわざそのものが、わたしについて、父がわたしを遣わしたことを証言(あかし)しているのです」(ヨハネ5章36節)。これは、キリストとそのわざによる「証人」と「証言」です。 5.第五段階――御霊によるあかし 「私たちが神の子どもであることは、御霊ご自身が、私たちの霊とともに、あかししてくださいます」(ローマ8章16節)。これは「御霊のあかし」による「心証」です。 このように神は、確かな証拠と証人と証言と心証によってご自身が存在し、生きていることを証明しておられるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「聖書の中心的な教え」
2019.09.27
コメント(0)
-
説教要約 1167
「不思議の霊的な教え」 2019年9月22日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2015年5月19日放映「目に見える救いと目に見えない救い」「不思議の霊的な教え」 甲斐慎一郎 詩篇139篇1~24節 「そのような知識は私にとって、あまりにも不思議、あまりにも高くて、及びもつきません」(6節)。 「私は感謝します。あなたは私に、奇しいことをなさって恐ろしいほどです」(14節)。 この詩篇においてダビデは、神の全知の不思議さと神の全能の奇しさに驚嘆しています。良いことについても悪いことについても、すぐ慣れて無感覚になりやすい人間にとって、不思議なものには不思議に思い、驚嘆すべきことには素直に驚き、すばらしいことには心から感動する気持ちが必要ではないでしょうか。 そこで不思議という観点から、聖書が教えている大切な真理と教訓を学んでみましょう。 一、不思議の意味について まず不思議ということの意味について考えてみましょう。 1.それは、知識の面からみるなら、文字通り不可思議ということ、すなわち人間の知識や理解を越えているということです。 2.それは、感情の面からみるなら、その不思議さのゆえに驚嘆したり感動したりして、眠っている感情が呼び覚まされることです。 3.それは、意志の面からみるなら、人間の意志や力の及ばないこと、すなわち人間の意志や力を越えているということです。 ですから私たちが不思議な宇宙や自然を見ても、何も不思議に思わなかったならば、私たちは、人間の知識と力の限界を認めない高慢な人であり、また木石のように無感覚で、冷たい心の持ち主なのです。 二、不思議の対象について それでは私たちは、不思議なものには何でも不思議に思い、驚嘆すればよいのでしょうか。決してそうではありません。 1.不思議なもの自体を恐れて礼拝する これは、すべてのものが神であるという「汎神論」や「偶像崇拝」であり、まちがっています。 2.不思議なものの背後にある未知のものを恐れる これは占いや呪い、また偶像崇拝であり、決して正しいことではありません。 3.不思議な宇宙や自然の背後におられるる唯一の真の神を認めて礼拝する これこそ聖書が教えている正しいことです。 三、不思議の霊的な教えについて 聖書は私たちに次のような三つの不思議なものについて教えています。 1.神の不思議さ 神は、人間の知識と理解そして人間の意志と力を越えた全知、全能、永遠、偏在の驚くべき方です。この世界に神ほど不思議な方はおられません。 2.人間の不思議さ 三つの不思議があります。 (1)人間の存在の不思惑さ 人間のからだは最も精密で精巧にできた機械以上のものであり、さらに驚くべきことには人間は、このからだに精神と霊を宿した不思議な存在なのです。 (2)人間の反逆の不思議さ しかしもっと驚くべきことは、このような神の傑作品である人間が、人知を超越した不思議な宇宙と自然に囲まれながら、神に背いて、罪に陥っていることです。 (3)人間の救いの不思議さ さらに最も驚くべきことは、神に背いていた人間がキリストとその十字架の贖いを信じる信仰によって罪から救われて新しく造り変えられるということです。 3.キリストの不思議さ キリストは、その名が「不思議」(イザヤ9章6節)であるだけでなく、永遠の神が有限な人となられたという不思議な方です。そしてキリストは、その生涯において数々の不思議なわざを行われ、最後は人類の罪を負って十字架につけられるという不思議な死を遂げられました(第一ペテロ2章24節)。しかしこのキリストの不思議な死によって、そのことを信じる者は罪から救われて、新しく造り変えられるのです(第二コリント5章17節)。 甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「使徒パウロの生涯」
2019.09.21
コメント(0)
-
説教要約 1166
「沈黙の霊的な教え」 2019年9月15日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2015年5月12日放映「目に見える罪と目に見えない罪」 「沈黙の霊的な教え」 甲斐慎一郎 詩篇50篇1~23節 外国の諺に、「沈黙は金、雄弁は銀」というのがあり、聖書には「愚か者でも、黙っていれば、知恵のある者と思われ、その唇を閉じていれば、悟りのある者と思われる」という言葉が記されています(箴言17章28節)。 この詩篇には、神に関して対照的な言葉が記されています。 「われらの神は来て、黙ってはおられない」(3節)。 「こういうことをおまえはしてきたが、わたしは黙っていた」(21節)。 聖書が教えている真の神は、私たちに語りかけられる神ですが、またある時は、何も語らずに黙っておられる神でもあります。それで沈黙について聖書から学んでみましょう。 一、人の沈黙について 人が沈黙するのは、およそ次のような場合ではないでしょうか。 1.一般的な場合――次の8つがあります。①試す時(創世記24章21節)②かかわりあわない時(ヨブ13章13節)③忍耐する時(詩篇39篇2、9節)④観念する時(イザヤ47章5節)⑤恥じる時(エレミヤ14章3、4節)⑥途方に暮れる時(ダニエル10章15節)⑦驚嘆する時(ルカ20章26節)⑧承認する時(使徒11章18節) 2.悪い場合――次の4つがあります。①怠慢の時(第二列王記7章9節)②弁解の余地がない時(マタイ22章12節)③隠す時(マルコ9章34節)④頑固な時(ルカ14章3、4節) 3.良い場合――次の5つがあります。①信頼する時(出エジプト14章14節)②待ち望む時(詩篇62篇1節)③自制する時(イザヤ42章14節)④服従する時(イザヤ53章7節)⑤悔い改める時(哀歌2章10節) 同じ沈黙であっても、このような多くの意味があることから、沈黙というのは決して何もないということではなく、それも私たちに何かを語りかけ、ある場合には、ことばで語る以上に雄弁であることが分かるでしょう。 二、神の沈黙について それでは神の沈黙というのは、どのようなことを意味しているのでしょうか。 1.それは、神の怒りであり刑罰です 良心の光に背いてバプテスマのヨハネを殺させたヘロデは(マタイ14章10節)、その後、十字架につけられるキリストに色々と質問しましたが、キリストは、彼に何もお答えになりませんでした(ルカ23章9節)。またパウロは、ローマ人への手紙において「神は、彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され」(1章24節)と述べていますが、このような神の沈黙や放任は、恐ろしい神の怒りや刑罰を表しているのです。 2.それは、神の愛であり忍耐です ゼパニヤ書には、「彼なんじのために喜び楽しみ愛の余り黙し」(三章17節、文語訳)と記されています。またペテロは、その手紙において「主は……あなたがたに対して忍耐深くあられるのであって、ひとりでも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです」(Ⅱペテロ三章9節)と述べていますが、このような神の沈黙や忍耐は、神の愛を表しているのです。 3.それは、神の試験であり試練です 聖書は、ヒゼキヤ王について「バビロンのつかさたちが……説明を求めたとき、神は彼を試みて、その心にあることをことごとく知るために彼を捨て置かれた」(第二歴代32章31節)と記していますが、このような神の沈黙や不干渉は、神に従うかどうかを試す神の試験や試練を表しているのです。 人の沈黙は、ある時は、ことばで語る以上の雄弁であるように、神の沈黙も、ことばに優るとも劣らない語りかけであることを知らなければなりません。ですから私たちは、神の語りかけのみならず、神の沈黙の中にも神のみこころを知って、いよいよ神を恐れて、敬虔に歩まなければならないのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「聖書の中心的な教え」
2019.09.14
コメント(0)
-
説教要約 1165
「永遠の霊的な教え」 2019年9月8日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2015年5月5日放映「目に見える神と目に見えない神」 「永遠の霊的な教え」 甲斐慎一郎 詩篇90篇1~17節 ある人は、「過去のない人は、動物に近い。そうして未来のない人は、まさしく動物である」と言いましたが、「伝道者の書」の著者のソロモンは、神の霊感を受けて、次のように述べています。 「神はまた、人の心に永遠への思いを与えられた」(伝道者3章11節、新改訳二版)。 このみことばは私たちに、人間だけが「永遠」とか「永遠の世界」、そして「永達なる神」を思うことができるということを教えています。そこでこの詩篇九〇篇から永遠について考えてみましょう。 一、神について(1、2節) モーセは、「まことに、とこしえからとこしえまであなたは神です」(2節)と記していますが、永遠とは、どういうことなのでしょうか。 このことに関しては、R・A・トーレーの次のような定義が最もよいのではないでしょうか。1.始めがなく終わりがない(無始無終)2.常に同一で全く変わらない(不変性)3.何にも依存せず独立している(自存性) 神はモーセに対してご自身を啓示された時、「我は有りて在る者なり」(出エジプト3章14節、文語訳)と言われましたが、これこそ「無始無終」にして「絶対不変」なる「自存者」を表しています。 この定義に従えば、永遠なるものは神以外には存在しないことがわかるでしょう。ですから神は信じるが、永遠は信じないとか、永遠は信じるが、神は信じないということは、あり得ないのであり、神を信じるということは、必然的に永遠を信じるということを含んでいるのです。 聖書は私たちに、「永遠の罪」、「永遠のさばき」、「永遠の刑罰」、「永遠の火」、「永遠の国」、「永遠の栄光」、「永遠の支配」、「永遠の贖い」、そして「永遠のいのち」について大胆に教えているのです。 二、人間について(3~11節) この箇所には、「人のいのちのはかなさ」(3~6節)と「人の心の罪深さ」(7~9節)と「人生のむなしさ」(10、11節)が記されています。もし私たちが永遠なる神と永遠の世界を信じなければ、いのちのはかなさと心の罪深さと人生のむなしさは、避けることができないことがわかるでしょう。なぜなら永遠を信じないことは、必然的に次のような人生にならざるを得ないからです。 1.刹那の人生 「あすは死ぬのだ。さあ、飲み食いしようではないか」という刹那的な人生です(第一コリント15章32節)。 2.流転の人生 「移ろう草のよう」(5節)に、人生の土台も善悪の規準も定まらず、世と時の流れに流されている放浪の人生です。 3.盲目の人生 人生の目的も目標もわからず、どこに行く着くかを知らないで、さ迷い、「やみの中を歩む」(ヨハネ8章12節)人生です。 三、救いについて(12~17節) このように、はかなく、罪深く、むなしい人生から救われるためには、永遠なる神を私たちの住まいとするほかにはないことがわかるでしょう。それは、永遠なる神を私たちの心の中に迎え、その永遠の神のいのちに与かることです。まさに使徒ヨハネが「御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである」と述べている通りです(ヨハネ3章16節)。 聖書が教えている救いは、この世において、すでに「永遠のいのち」が与えられて、「永遠の世界」に生きることです。それは、具体的には永遠の観点から物事を見、また考え、そして判断して、永遠に有益なことだけをすることです。それは、主イエス・キリストが言われたように「なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠のいのちに至る食物のために働」くことを意味しているのです(ヨハネ6章27節)。 甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「神のご計画の全体」
2019.09.07
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1