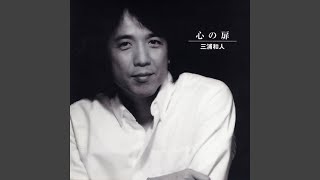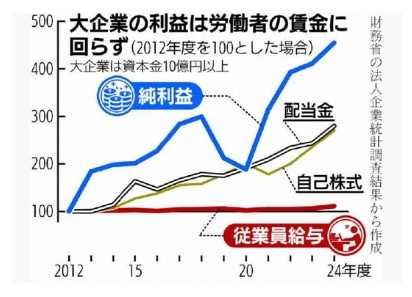2007年09月の記事
全100件 (100件中 1-50件目)
-
落書き日記 肌 寒 い 雨 の 日 9/30
☆彡 肌 寒 い 雨 の 日 ☆彡朝から雨の日で肌寒い一日であった。半袖から長袖のシャツに着替えた。彼岸があけても暑かったけどやっと秋の気分!!百日紅(サルスベリ)の花も色あせた。この花はたしか7月20日頃咲いたから・・・約100日で花としての命はおわる。明日からはもう10月で神無月となる。
2007年09月30日
-
清 く 正 し く 美 し く 生 き た い 男
清 く 正 し く 美 し く 生 き た い 男 生きることは芸術である 生まれてからいろんな人の力や助けを 借りて人は歩んできたのである 父や母はもちろん物心がついてからは 兄弟・親族・教師・友人その他いろんな 多くの人のお世話になった されども人は案外それらの人たちのことを 忘れて自己本位でもって生きている 清い心や正しい心や美しい心で接しているか!! 万人がそういうことで生活しているわけではない いろんな人がいるからいろんな人に対する 接し方があってしかるべきだろう 清く正しく・美しく生きることはむずかしい!! 感情があるだけに一日中そう生きたくとも 生きられない現実があるのが常の世界である しかし人類は自己の肉体や精神の葛藤を 克服し自らのおかれた環境やくらしのなかで 清く・正しく・美しく・生きなければならない 苦難や苦痛や困難のなかでも自己が納得する 清く・正しく・美しく生きることを最大の 生活目標とし人生を歩まなければならない いろんな生き方があるなかにおいて常に 脳裏の片隅に清く・正しく・美しくの言葉を 掲げておかなければならない 一つの人生という人間の芸術品を 清く・正しく・美しくをもって創りあげねばならない 清く・正しく・美しい芸術品を完成しようと 努力することによって肉体も精神も磨かれ 新しく生まれ変わることができるのだ 人間としてどのように生きるかそれは自由である 人それぞれの生き方でいいのだが・・・ 清く・正しく・美しく生きよう!! そういう思いだけはいつも忘れずに 人生の旅を続けるべきである
2007年09月30日
-
足 跡 を つ け た 男
足 跡 を つ け た 男 白い山があった 白い海があった 白い空があった 白い風が吹いていた 白い雨が降っていた 白い雪が舞っていた 白い家があった 白い庭があった 白い机があった 白い肉体があった 白い言葉があった 白い笑いがあった いろんなあしあとを私は いろんな色でそめてきた 万華鏡の中をのぞけば いろんなあしあとが輝いて 私を笑っていた
2007年09月30日
-
透 明 な る 愛 に あ り が と う を い う 女
透明なる愛にありがとうをいう女 目の前に見えないものがある 生まれ落ちたるその時より われわれはその恩恵に浴してきた いつも人生とともにあった 真空の世界でないかぎり かすかなすき間から忍びこみ 部屋のなかに満ちる なんという絶対の愛があるというのか この命に光をあたえ人を人として 活かしつづける永遠の愛 無尽蔵に大地をうるおし 悲しみもせず笑いもせず 姿もみせずあたえ続ける平和な愛よ 雨の日も風の日も泣きもせずわめきもせず 喜びだけをあたえつづける無償の愛よ 空気その愛!! 透明なるその愛!! 永遠の愛よ!! 空気よありがとう!!
2007年09月30日
-
凡 な る 男
凡 な る 男 君はねごとをいう 大きなねごとだね 君はあくびをする 大きなあくびだね つかれたんだね 君はため息をつく 大きなため息だね みんな大きいから いいんだよ
2007年09月29日
-
清 く 正 し く 美 し く 9/29 22回
☆彡 清 く 正 し く 美 し く ☆彡清く正しく美しくというのは宝塚歌劇団の創設者の言葉で、これは宝塚塚歌劇団に入団したら必ずこのような心構えで生活するようにとの目標とする教えである。タカラジェンヌとして生きる心構えとなっているすばらしい言葉であると思う。僕は、清く・正しく・美しくの言葉が好きになった。なぜなら今の日本人にとってこの言葉が必要だと思うのです。大人も子供も清く正しく美しく生きる!!そんな心構えで過すように努めれば人間として成長できるのでは・・・そのように思っています。清らかな心・正しい心・美しい心・この言葉はいろんなことに使えるのです。清らかな言葉・正しい言葉・美しい言葉・清らかな生活・正しい生活・美しい生活・清らかな姿勢・正しい姿勢・美しい姿勢・清らかな行動・正しい行動・美しい行動など人間が生きる上での目標となる言葉だ。この言葉をこれから生きていく上での好きな言葉にいれたいと思う。
2007年09月29日
-
俳 句 「 秋 の 燈 」 9/28
俳句1万句の旅☆彡 秋の燈やブログに絵文字ひとつあり ☆彡 季語:秋の燈(あきのひ)春の燈の明るい感じに対して、秋の燈は大気が澄んでいるので清明の感じが強い。
2007年09月28日
-
愛 よ お ま え は の 男
愛 よ お ま え は の 男 愛は誰のためにあり誰を愛すればいいのか!! 真実の愛は生きていなければ達成できないのか!! 愛よ!! おまえは命より大切なものなのか!! 愛よ!! おまえは・・・・・ ヘッセはいったー 愛は、わたしたちを幸福にするためにあるのではなく、 わたしたちが悩みと忍耐においてどれほど強く なれることができるかを示すためにあるものです。 愛よ!! おまえは・・・・・ ゲラーはいったー 愛よ!! おまえこそはまことの命の魂、 やすみなき幸 愛よ!! おまえは・・・・・ リルケはいったー 愛せられるだけの人間ではつまらない 生き方をしているのであり、また危険でもある できることなら、みずからを克服して 愛する人間となりたいものである
2007年09月27日
-
風鈴文楽短歌集 9/27 あ
風鈴文楽短歌集浜辺にて流浪の旅を想うかな秋の夕日に一握の砂こぼしつつ
2007年09月27日
-
旅 立 ち の 男
旅 立 ち の 男 星まだ残る早い朝に君は何処へ行くのか 星が消える前にひとり若武者のごとく 熱き想いを胸に秘め旅立つというのか カバンひとつもちて朝の駅に立つのか 誰もいない冷たい駅で生まれ育った町に 別れの言葉を投げかけて・・・ 1番列車が駅に着いたらうるむ瞳で 故郷にむかってさようならをいうのか 窓に映る父も母も恋人も指で消して 遠い夢の道へ行こうとするのか かすむような小さな町が動いて 列車の音が聞こえると心の奥で 人生のメロディーが聞こえた 自分の本当の夢はなんだろうか これからの人生に何があるのか 愛をすてて一人旅立つ朝の町が 明るくなって窓から昇る朝日が見えた 列車にゆれる希望の光が一つ 未来にむかって進んでゆく 男だったら誰にも負けはしない つらくとも強い心で頑張るだけと 大きな夢を描いてるのだった
2007年09月27日
-
俳 句 「 立 待 月 」 9/27
俳句1万句の旅☆彡 密やかに立待ち月に雲の影 ☆彡 季語:立待月(たちまちづき)陰暦8月17日の夜の月。月の出は満月を過ぎれば遅くなる。緑や庭に立って待っているうちに出てくるの意。
2007年09月27日
-
俳 句 「 満 月 」 9/26
俳句1万句の旅☆彡 満月や天上にある千の風 ☆彡 季語:満月(まんげつ)欠けた部分がなく、円形に輝く月をいう。望月・十五夜の月。
2007年09月26日
-
俳 句 「 美 術 の 秋 」 9/26
俳句1万句の旅☆彡 裸婦像に見入る人あり美術展 ☆彡 季語:美術展(びじゅつてん)美術展はどこかで一年中行われているが、特に9月に入ると院展、仁科展、日展等美術展覧会がはじまる。9・10月に多く開催されるので美術の秋といわれる。
2007年09月26日
-
俳 句 「 秋 遍 路 」 9/26
俳句1万句の旅☆彡 笠とりて美人といわれ秋遍路 ☆彡 季語:秋遍路(あきへんろ)四国の遍路の季節は春であるが、時候の良い秋にも遍路の姿がみられる。
2007年09月26日
-
落書き日記 和 歌 山 の 蜜 柑 と 柿 9/26
☆彡 和 歌 山 の 蜜 柑 と 柿 ☆彡今日駅から帰る途中に、蜜柑と柿を売る店があった。ダンボールに入っているうすく黄色がかった緑の蜜柑””そして、うす赤くなった柿もいっぱい入っている。張り紙には・・・和 歌 山 ・ 有 田 の み か ん !!和 歌 山 の お い し い 柿 !!と大きく書かれている。昨日のテレビで有田の極わせみかんが出荷されたといっていたので、多分売られているのは極わせみかん!!柿は多分、九度山産の富有柿ではないだろうか・・・蜜柑や柿の横では70歳は過ぎたであろうオジイさんが淋しそうに売り場を見守っていた。買って帰ろうかなあ~と思ったが手には大きなカバンを提げていたから荷物になると思い買うのをやめた。和歌山は、蜜柑と柿と桃と梅で有名です。これから10月になると山一面が蜜柑で黄色くなります。列車で有田付近に近づくと山が蜜柑で真っ黄色になります。まあ~紀伊國屋文左衛門が江戸に蜜柑を運んで売ったというくらいですから江戸時代から蜜柑が採れたのでしょう。また九度山では、柿で斜面が真っ赤にそまります。車で行くと柿・柿・柿・・・行けども行けども柿ばかり!!はじめてドライブで行くと突然柿の村があらわれて、びっくりしてしまいますよ。ほんとに柿ばかりで何もない村で・・・(@_@;)なんといっても和歌山の蜜柑と柿はとてもうまい””これだけは自慢できる和歌山の果物ですね””今年はじめての蜜柑と柿の味見をしなければ。。。
2007年09月26日
-
落書き日記 夜 露 が 降 り た 日 9/26
☆彡 夜 露 が 降 り た 日 ☆彡今日の朝は、半袖ではひんやりとするぐらいだった。ミーティングでも涼しくなっていい気候だねぇーという人がいた。なるほどぅ。。今日は彼岸明けだしこれから過しやすくなると思っていると今朝は夜露がおりたよっていう人がいた。よく聞くと今朝は、車の窓が白くなったというのである。今年になってはじめてやわ””そういった。今日はひょっとしたら日本晴れかも知れんよぅきっとえぇ~天気と違うかなあ~なんていう人も・・・そうしたらモミジもこれから色づくなあ~といって・・・朝晩の寒暖の差がないとモミジもきれいにはならん””そういう人がいたかと思うと阪神タイガースは5連敗””自力優勝ができへんなあ~という人がいて・・・(T_T)そして最後に昨日の晩は満月の十五夜やったという人がいたから僕が少しの月の知識・和の知識をもって満月は27日で今夜は十六夜ですよというと、いざよいって十六の夜と書くんやったかなあ~というんで僕はそうやっといったら次の夜は十七夜というん?なんて聞いてきたから僕はまあ~そういえばそうやけど・・・明日は立待月・その次は居待月・臥待月・更待月とというんやでぇ~なんていうとそれって太陽暦とかいうん?なんていうもんやから僕は陰暦いうて月による暦でいま使っているのは陽暦といって太陽による暦なんやで~なんていうと文楽さんは詳しいなあ~なんていった。(*_*;ほんと情けないほど和の文化を知らない人たち・・・もっと月見のことも勉強しないと子供に笑われるよ””そんなことを思った一日でした。今日は仕事中ずっと一度もクーラはかけなかった。電車でもカーデガンや長袖の人もいていよいよ暑さも遠のいたかなあ~なんて思った。
2007年09月26日
-
千 鳥 足 の 男
千 鳥 足 の 男 今日も一生懸命働いて疲れて帰る街角の 赤ちょうちんに誘われてたどりつきたる 止まり木はいつも居酒屋片隅に好きな 日本酒をおいて飲む 何が悲しくて何が嬉しくてたった一人で酒を飲む 誰がどういおうとも俺には俺の人生がある 心より愛する人もなく悲しい運命(さだめ)に 流されてどうしょうもない人生を送ってる 朝が来ても昼が来ても夜が来てもどこに 幸せあるのかと馬鹿な男の生きざまに ほろ酔い気分の酒をつぐ 働けど働けど学問のないこの俺は いつも劣等感にさいなまれキレイな 文字を書きたくて立派な社会人に なりたくて今日まで身を粉にして働いた どうにもならない人生に布団のなかでは 人の世の不運をなげき涙にくれた 誰をうらんでも生まれ落ちたるその日から はぐれ迷子の俺だもの明日なき命あるだけで 幸せだよと空しい日々を生きてきた いつも強くなりたいと幸せになりたいと 思えど願いは叶えられずにあきらめた こうとしか生きられない俺がいる こうとしか生きていけない人生を悲観して 死んでしまおうなんて思ったことも・・・ 働いて働いて働き尽くせば肉体もいつかは 滅びる運命と働き続けてきたけれど・・・ 今も元気で働いて小さな命を捨てないで 明日なき日々を生きている 自分だけの人生を迷惑かけずに生きようと 慰め言葉いいながらほろ酔い気分の酒をつぐ 明日は明日の風がふく 命があれば生きなくちゃ こんな俺でも人間だよとチビリチビリと酒を飲み ほんのり赤くなったなら酒に飲まれちゃいけないと そろそろお開きしょうかと最後の一杯飲みほせば この世はバラ色 夢の心地となりぬるを・・・ ああこんな男で悪かった 男なんて人生に負けてもともと行き先は 風に吹かれる野良犬か 誰も助けてくれないと汚れた財布広げては 飲んだ酒代さらりとはらいそれじゃ帰ると さよならしては明日も来るよとつぶやきながら 店を出たれば満月が俺をてらして笑ってた
2007年09月25日
-
俳 句 「 月 」 9/25
俳句1万句の旅☆彡 月光をあびて童と遊びけり ☆彡 季語:月(つき)
2007年09月25日
-
俳 句 「 名 月 」 9/24
俳句1万句の旅☆彡 名月を見たくてしばし縁側に ☆彡 季語:名月(めいげつ)陰暦8月15日の中秋の満月である。1年中で、この夜月が澄んで美しい。
2007年09月24日
-
俳 句 「 無 月 」 9/24
俳句1万句の旅☆彡 無月にて舞妓かなしや京の夜 ☆彡 季語:無月(むげつ)十五夜に雨、雲のため名月を見ることができないこと。雨で見えない場合は、「雨月」という別の季題がある。
2007年09月24日
-
俳 句 「 月 見 」 9/24
俳句1万句の旅☆彡 乾杯の影うるわしき月見かな ☆彡 季語:月見(つきみ)秋の月を鑑賞することだが、名月と十三夜の月見をいう。
2007年09月24日
-
月 の こ と 9/24
☆彡 月 の こ と ☆彡今日は旧暦の待つ宵です。古来より日本人は月に特別な愛着を感じてきた。平安時代の歌人・大江千里は、次の和歌で、もののあわれをうたった。 ☆彡 月見れば千々にものこそかなしけれ わが身ひとつの秋にはあらねど ☆彡● 月をながめていると、あれやこれや、限りなく ものごとが身にしみて悲しい。 なにもわたしひとりための秋というわけでは ないけれど。そして江戸時代には、俳人・与謝野蕪村が雄大なスケールの情景を次の俳句に詠んだ。 ☆彡 菜の花や月は東に日は西に ☆彡そして日本には有名な日本最古の物語である「竹取物語」がある。この物語はいまも世代をこえて読まれている。そして平成時代になって・・・2007年9月14日。月周回衛星「かぐや」が打ち上げられ、約38万キロかなたの月へむかった。かぐやは縦横2メートル、高さ約5メートル。この大きさを想像してみれば・・・月からかぐや姫を迎えに来た、牛車(ぎゅうしゃ)ほどの大きさかも知れない。かぐやは、日本の科学衛星技術の集大成””月の重力を測定する子衛星や磁場、エックス線、プラズマなどを観測するさまざまな最新の装置や、月面の立体画像を精密にとらえるカメラを積んでいる。かぐや姫は、中秋の名月の旧暦8月15日に月へ帰っていった。中秋の名月は9月25日(月)。日本が打ち上げたかぐやは、10月下旬、月の上空100キロを周回する観測軌道に入る。かぐやはいま、月への途上にある。
2007年09月24日
-
俳 句 「 待 宵 」 9/24
俳句1万句の旅☆彡 待つ宵の祇園にともる明かりかな ☆彡 季語:待宵(まつよい)陰暦8月14日の夜。明日の名月を待つ宵のことであり、またその夜の月のこともいう。
2007年09月24日
-
高 瀬 川 で 舞 妓 さ ん が お も て な し 9/23
☆彡 高瀬川で舞妓さんがおもてなし ☆彡 (2007年9月23日)江戸時代に京都の物資輸送の幹線として栄えた高瀬川の歴史に触れる「高瀬川船まつり」が、2007年9月23日、京都市中央区一之船入町で行われ、観光客らが舞妓さんが接待する茶席や、一般開放された高瀬舟に試乗するなどして楽しんだ。地元町内会などで組織する銅駝(どうだ)高瀬川保勝会(増井孝信会長)が、1984(昭59)年に高瀬船を復元したのを契機に、1990年から毎年開催している。この日は夏の暑さが残る中、家族連れや外国人観光客でにぎわい、茶席や船への試乗を楽しんでいた。また、高瀬川の歴史を紹介する展示やクイズラリー、宝物探しなどのイベントも行われた。
2007年09月23日
-
お も し ろ い 日 本 語 9/23 第21回
☆彡 お も し ろ い 日 本 語 ☆彡日本語というのは一言でいうとおもしろい。漢字・ひらがな・カタカナがあるというユニークさがなんといってもすばらしい””外国語などはカタカナで表記するし、また植物・動物などは、日本語表記とカタカナ表記の二つがあるし、植物の病気はひらがなで表記するし・・・こういう使い分けというのは日本語のユニークさといえるものです。また4字熟語というのもあるし、短歌や俳句という独自の詩形でもって表す文化もあるし、日本語と英語をミックスした文章もあるし、それは歌の世界に浸透している(歌詞)それから僕はもうひとつ・・・対比した言葉、コンビとなる言葉がある。これはおもしろいと思うのです。きってもきれない仲良し言葉。たとえば・・・花と蝶・月と星・男と女・犬と猫・白と黒ほかにもたくさんあると思いますが・・・思いつくのはこんな用語です。これはきってもきれないコンビ言葉でしょう(笑)こんなのも日本語のおもしろさです。日本語はとてもおもしろいです。
2007年09月23日
-
#27 ま だ ま だ 蝶 は 飛 ぶ 9/23
蝶の日記☆彡 ま だ ま だ 蝶 は 飛 ぶ ☆彡今日2007年9月23日は彼岸の中日である。暑さ寒さも彼岸までといいますが・・・昼に少し散歩したが、昨日より暑さはましであった。公園では今日も蝶はいました。小さい灰色の蝶なんですが蝶の名は知らない。まだまだ蝶は飛んでいます。花の数は春にくらべて少ないのに・・・花をさがし密を求めて飛んでいました。しかし春に比べると秋の蝶は少しかわいそう~それは蜜が少ない花ばかりのようで。・。・。・蝶には花がつきものですからねぇー花が少ないから花はどこにあるの?そんな気持ちで探しまわっている蝶がいた。ああ~いつまで蝶は見れるのかなあ~
2007年09月23日
-
風鈴文楽短歌集 9/23 あ
風鈴文楽短歌集この道に花は咲くかとわれ問わばいつかは咲くよ蝶もきたるや
2007年09月23日
-
落書き日記 シ ン プ ル に 生 き る 9/23
☆彡 シ ン プ ル に 生 き る ☆彡人間は欲望の生き物である。欲望があるから生きられるのであるが・・・文明が発達すると何もかもが複雑になる。街は人があふれ、喧騒になりすぎて安らぐような過しやすいスペースは少なくなってきている。田舎のくらしがいいのかと問われたら・・・田舎が最高であると僕は言わない””田舎の生活を都会で味わうにはどうすればいいのか?都会というモザイクのようで迷路のようでゴミゴミしている狭い空間でどのように過せばいいのか。・。・都会での過し方はシンプルに過すことが快適なくらしの秘訣といっていいと思う。シンプルということは何もないというゼロの感覚ではなく普通のくらしをすればいい””そういうくらしをすればいいのである。それはは自然を愛でる。自然に感謝するということである。そしてその要諦には空気と水に感謝すること。空気を吸って水を飲めることのありがたさ””これを思って暮らせばシンプルになるのである。極限すれば毎日空気を吸えるだけで・・・毎日おいしい水を飲めるだけで幸せである。空気と水だけで生きられるわけではないが・・・「空気と水だけあれば幸せである」という感覚がシンプルな心””シンプルなくらしの原点なのである。田舎くらしには娯楽的なものはほとんどなく・・・あるのは、澄みわたる空気と水に囲まれた自然の風景のみである。都会生活におけるシンプルな暮らし方には・・・「空気と水があればそれだけで幸せである」という感覚が必要なのである。それを思うならば、いかに自分の身のまわりには、たくさんの不必要な荷物があることがわかるだろう。「空気と水があれば何もいらない」というシンプルなくらしの極限的な言葉を考えて、何を捨て何を残しこれからの都会生活を過していくか・・・これからの快適な都会生活は、シンプルから生まれるといっていいだろう・・・空気と水とそれ以外に幸せなものは・・・シンプルな心であろうか。・。・。・
2007年09月23日
-
神 の 日 本 語 9/23 第20回
☆彡 神 の 日 本 語 ☆彡ひとりごとなんですが・・・日本語というのは面白くて意味深いものである。僕は前からそのように思っているのです。最近「神の日本語」というのに興味がある。なんだってぇーなんていうかも知れないが簡単にいえば神のつく用語ということですぅ。精神・神経という用語を不思議に思うのです。神の精と書いて精神という・・・神の径と書いて神経という・・・誰がこういう用語・熟語を作ったのか!!僕はすばらしい用語だと思うのです。神様が住んでいる心という見えないもの。神様が通る径(みち)という見えないもの。人間の心の中には神様が住み、神様が全身にはりめぐらした神経というものがある。この二つだけに神の字がつくのはなぜなのか?精神と肉体という切っても切れないものに神がついているというのが不思議なのである。
2007年09月23日
-
ム ー ン ラ イ ト ・ セ レ モ ニ ー 9/23
☆彡 ム ー ン ラ イ ト ・ セ レ モ ニ ー ☆彡今日2007年9月23日は秋分の日である。9月20日の彼岸の入りから彼岸の中日となった。この日より夜が長くなるのである。夜が長くなるというのは個人的に部屋のなかで過すことが多くなるということになるのである。日没が早まるとそれだけ早く家に帰ろうと普通の人はそう思うものである。そして家に帰れば秋の夜長を楽しむことになるというわけであるが・・・秋の夜長を楽しむ一つに月見を入れてみよう!!色々と月見の場所はあるのであるが・・・月の見れる最高の場所をさがすのも楽しい!!車で月を見に行くのだっていいだろう。双眼鏡をもってカメラをもって今月今夜の月をながめて宇宙の広さ・不思議さに酔う””お酒を飲みながら月をながめる。月見団子を食べながら・・・おでんを食べながら・・・インスタントラーメンを食べながら・・・何を食べながら月を見るのか。何を飲みながら月を見るのか。( ^^) _旦~~月光にさらされて月を見るのもいいだろう。かぐや姫のことを想うこともいいだろう。かぐや姫のかぐやとは輝かしいとか、光輝くという意味であるそうだ。 家具屋のお姫様ではない(笑)かぐや姫伝説は、宇宙人だった話かも・・・かぐや姫は、宇宙人であった?さて9月23日が彼岸の中日ですが旧暦でいうと8月13日である。9月24日からは旧暦の月見の世界へのスタートとなるのである。ムーンライト・セレモニーのはじまりー☆彡。ムーンライト・セレモニーという名前は、僕がつけた造語ではありますが。・。・この時期にふさわしい言葉だと思っている。それではムーンライトの世界・旧暦の月の世界へご案内するための日本の風習を書きます。月見を楽しむために旧暦の世界へ。・。・。月を見れるかどうか晴れるといいんですがねぇ~☆彡 ム ー ン ラ イ ト ・ セ レ モ ニ ー ☆彡9月24日(月)→ 待宵9月25日(火)→ 中秋の名月(十五夜)9月26日(水)→ 十六夜9月27日(木)→ 立待月(満月)9月28日(金)→ 居待月9月29日(土)→ 臥待月9月30日(日)→ 更待月10月23日(火)→十三夜(後の月)十三夜は後の月、二夜の月、豆名月・ 栗名月といい、豆・栗を供えた。
2007年09月23日
-
月 見 を 楽 し む 9/22
☆彡 月 見 を 楽 し む ☆彡月を見るというのは楽しくて心が洗われるものです。9月の満月を僕はどこで見るのだろうか?露天風呂か公園か庭かどこで月の明かりに晒されて月を鑑賞するだろうか?露天風呂の湯のなかに半身をしずめて月を見る””湯船で月を見ることは至福のひと時ではないだろうか。月は約45度くらいの角度でみるのがいい。7時~8時ごろが一番いい時間帯ではないだろうか。・。真上だと首が痛くなってゆっくりとは見れない””月見はできれば双眼鏡で見るのがいいらしい。太陽は双眼鏡では見ることはできないが・・・月はやわらかい光だから双眼鏡で見れる。昔の人は月の満ち欠けはどうしてできるのか?地球が動いていることさえもわからなかった。月の明かりが太陽の反射光であることもわからなかった。現代人はどうだろうか・・・宇宙・地球・月・星に興味のある人なら月の満ち欠けがどうしてできるかということは知っている。・。地球が動いていることも知っている。だから月を見るのも昔の古代人が眺めた月への思いとは現代人とはだいぶかけはなれているだろう。月を見て何を思い何を感じるだろうかなあ~月を見ることは楽しくてロマンチックなのである。月見を大いに楽しみましょうー☆
2007年09月22日
-
俳 句 「 秋 の 蝶 」 9/21
俳句1万句の旅☆彡 飛びゆきぬ一つのあわれ秋の蝶 ☆彡 季語:秋の蝶(あきのちょう)秋に発生した蝶をいう。春の蝶のはなやかさはない。
2007年09月22日
-
俳 句 「 鬼 や ん ま 」 9/21
俳句1万句の旅☆彡 鬼やんま夕暮れの池ひとりじめ ☆彡 季語:鬼やんま(おにやんま)非常に種類が多い。蜻蛉は皆肉食で飛びながら蚊、蝿、うんか等を捕食し、幼虫はヤゴといって水中に住む。
2007年09月21日
-
彼 岸 の 入 り 9/20
☆彡 彼 岸 の 入 り ☆彡今日は彼岸の入りです。このところ真夏のような暑さでうんざりしています。この暑さで秋の蝶も生まれているようです。今日はめずらしく紋白蝶を2匹も見ました。そして17時半ごろ大根を切ったような月がほの白く天空にかがやいていました。上弦の月、右半分の大根の月でした。白い月を大根の月と表現したのは作家の故・向田邦子さんでしたが・・・本当に大根を半切りにした感じの月でした。月の白っぽい部分はクレーターの多い高地で、黒っぽく見える部分は「海」と呼ばれる低地だそうです。もう彼岸花も咲いていることでしょう。暑さ寒さも彼岸までというように彼岸を境に暑さもやわらぎ過しやすくなるかと思います。
2007年09月20日
-
俳 句 「 竹 伐 る 」 9/20
俳句1万句の旅☆彡 笹ゆれて竹きる音か裏の山 ☆彡 季語:竹伐る(たけきる)竹は9月に伐るのが良いとされている。
2007年09月20日
-
風鈴文楽独言集 9.19
テレビは魔物である。テレビは常識と非常識を併せもっている。常識や非常識は言葉と映像から生まれる。テレビの怖さは言葉と映像にある。
2007年09月19日
-
俳 句 「 秋 彼 岸 」 9/19
俳句1万句の旅☆彡 おはぎ買う秋の彼岸のよき日かな ☆彡 季語:秋彼岸(あきひがん)秋分の日の前後1週間をいう。春の彼岸と同じく彼岸会が行われ、参詣と墓詣の人でにぎわう。
2007年09月19日
-
俳 句 「 秋 の 朝 」 9/19
俳句1万句の旅☆彡 秋朝や電車の中のひと眠り ☆彡 季語:秋の朝(あきのあさ)立秋を過ぎると、朝夕どことなくさわやかにになる。その頃の朝をいう。
2007年09月19日
-
俳 句 「秋 の 海 」 9/18
俳句1万句の旅☆彡 人もなく風ふくばかり秋の海 ☆彡 季語:秋の海(あきのうみ)秋天の下にひろがる爽やかに澄んだ海。浜辺も寄せ来る波も、夏に比べて清楚な感じがする。
2007年09月18日
-
落書き日記 残 暑 き び し い 日 9/18
☆彡 残 暑 き び し い 日 ☆彡今日も残暑がきびしい一日だった。昼に行きつけの喫茶店に行った。いや~暑いねぇーマスター~ほんとやいつまで暑いんやろかなあー残暑じゃなく猛暑やなあー (=_=)いつものアイスコーヒーにしてくれる””あいょっ 文楽さん少し痩せたかな?いや頬が少しやせてすっきりした感じやよぅ。・。そうかいねぇー夏やせかもなあ~こう暑くては夏やせもするでねぇ~マスター””マスター毎日何時ごろ寝とるんですかぁーああ~だいたい12:00頃やなあ~それでさあ~ ニュースなんか見るん?ニュースはNHKばかり、たまに報道ステーションやねっそれはそうと23:00に筑紫さんのニュースやってるけど筑紫さんは最近TVにでてこないけどどうなってるの?筑紫さんはガンで闘病生活をおくってるよ””ええっ ガンなんですか~(@_@;)それからなあ~鳥越さん知ってるやろ・・・記者の。・。あの人もガンになって・・・CMにはでてるけれどな・・・みんなガンやなあ~お気の毒なことですわ””ええっそうだったんですかあ~ ほんとぅ 「。。。。。」マスターなあ~実は僕もガンなんですよっ文楽さんご冗談を・・・ あははっ(^◇^)いやあ~マスター本当に「ガン」なんです。””ええっ またあー文楽さんそんなバカなあっ!!いやねぇ~マスター僕は職場のガンですわ””ガンじゃなく「バイキン」かもしれへんなあ~(笑)あははっはっ よくいうよ文楽さん!!文楽さん! さっきから水ばかり飲んでるけどカライもん食べたなあ~?昼の食事は焼きそばでからかったわ””そうやろなあ~水のよく飲む人は糖尿病やいうんやで・・・まあ~文楽さんはそんなことないやろうけども。・。・マスターナイナイそれはナイよぅ”” 僕は職場の「ガン」やから・・・・・うっあははっは あははっは。・。 (●^o^●)マスターも僕も大笑いでした。
2007年09月18日
-
名 月 考 9/17
☆彡 名 月 考 ☆彡都会にいる人は月を見ることは少ない。ただ9月・10月となると月のことを考える。一部かも知れないがお月見のことを考える。旧暦では7月から9月までが秋であった。旧暦8月を「中秋」と呼んでいた。古くから「月」といえば、秋の月をさし風雅の対象として愛でるだけでなく、信仰の対象でもあった。俳人や歌人たちがもっとも多く詠んだのも月であった。「竹取物語」「源氏物語」に登場する月も有名である。月面の陰影は日本では兎の餅つき、中国では水桶で水を汲む人を連想する。伝説では、月には桂の木を伐る男、また不老長寿の薬を盗みだして月に逃れた女性がいるといわれる。名月といえば中秋の名月、旧暦8月15日の満月を指す。「竹取物語」でかぐや姫が月に帰るのは中秋の名月のときである。芋名月ともいわれるのは、この頃に芋がとれるのでその収穫感謝の意をこめ月に芋・団子・枝豆・果物などを供えた。京都などでは、月見の鑑賞会いわゆる観月会もおこなわれるようです。有名な観月会としては紫式部ゆかりの石山寺(大津市)や京都嵯峨の大覚寺、東京向島の百花園がある。日本の風習であるお月見を都会でもできるような環境がほしいところです。高層ビルの屋上庭園なら十五夜が見られる。
2007年09月17日
-
俳 句 「 秋 日 傘 」 9/17
俳句1万句の旅☆彡 いずこへや角をまがりて秋日傘 ☆彡 季語:秋日傘(あきひがさ)秋に入って暑い日にさす日傘をいう。真夏にさす日傘とは気分的に異なる。
2007年09月17日
-
俳 句 「 衣 被 」 9/17
俳句1万句の旅☆彡 鍋にあるひとつ食べたり衣被 ☆彡 季語:衣被(きぬかつぎ)里芋の小ぶりのものを、皮をむかずに茹でて塩をふりかけて食べる。名月の供え物としてなくてはならぬもの。
2007年09月17日
-
お は ぎ 9/17
☆彡 お は ぎ ☆彡「萩の餅」ともいい、もち米とうるち米を半々にして蒸し、すり鉢などで粗くつぶし、小豆餡、胡麻餡、きな粉などをまぶした餅のことである。春秋の彼岸に家庭でつくり、仏前に供え、近隣親戚に配る。秋の彼岸のものを「おはぎ」、春は牡丹にたとえて「ぼたん餅・ぼた餅」と呼びます。
2007年09月17日
-
俳 句 「 秋 扇 」 9/17
俳句1万句の旅☆彡 風ひとつ眠気さませし秋扇 ☆彡 季語:秋扇(あきおうぎ・しゅうせん)秋になってもまだ使用している扇。または不要になって、机上等手近なところに忘れられている扇をいう。
2007年09月17日
-
俳 句 「 秋 簾 」 9/17
俳句1万句の旅☆彡 古びたる秋のすだれに雨しずく ☆彡 季語:秋簾(あきすだれ)秋のうち、まだ掛けている簾のこと。秋の日ざしをよけて、よごれたまま吊りっぱなしの簾をよく見かける。
2007年09月17日
-
俳 句 「 枝 豆 」 9/17
俳句1万句の旅☆彡 枝豆の皮いっぱいの皿ひとつ ☆彡 季語:枝豆(えだまめ)大豆のまだ十分熟さぬ青いのを採って、莢(さや)ごと塩ゆでして食べる。名月に供えるので「月見豆」ともいう。
2007年09月17日
-
俳 句 「 敬 老 の 日 」 9/17
俳句1万句の旅☆彡 母という大きな海や敬老の日 ☆彡 季語:敬老の日(けいろうのひ)9月15日。昭和41年に国民の祝日となった。老人のための慰安会、老人ホームの慰問等が催される。
2007年09月17日
-
敬 老 の 日 9/17
☆彡 敬 老 の 日 ☆彡2007年9月17日は敬老の日です。敬老の日は、聖徳太子が四天王寺(大阪市)に身寄りのない病人や高齢者を収容する救護施設である悲田院(ひでんいん)を設立した日にちなむともいわれている。9月15日が祝日の「老人の日」となったのは1964年、1966年に「敬老の日」と改められ、2001年より、9月第3日曜日となった。
2007年09月17日
-
風鈴文楽短歌集 9/17 あ
風鈴文楽短歌集 学校へ微笑み歩ゆむ少女らにぽつんと離れひとりの少女
2007年09月17日
全100件 (100件中 1-50件目)