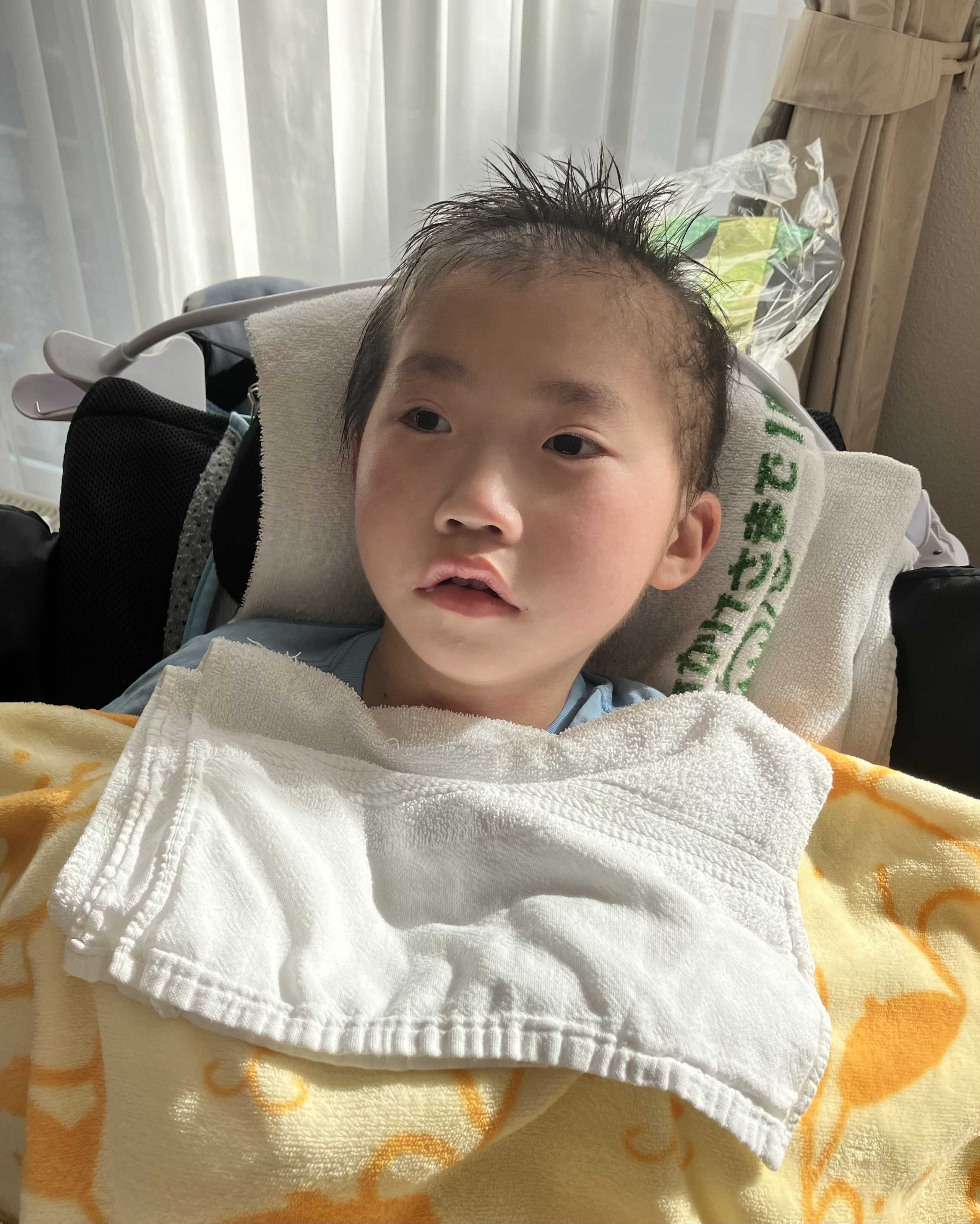2017年12月の記事
全34件 (34件中 1-34件目)
1
-
不安・恐怖と依存症の関係性
今日は恐怖などの感情と依存症について投稿してみたいと思います。人間の先祖は他の肉食獣と闘って生き伸びていかなくてはなりませんでした。 絶えず周囲をうかがい、慎重に生きていたのです。 危険を素早くキャッチして戦うか逃げるかの決断をしなければなりませんでした。そうしないと簡単に肉食獣の餌食になってしまいます。 脳ではいち早く五感、扁桃体、海馬、大脳新皮質の神経細胞のネットワークが強化されました。その結果 絶えず不安や恐怖にさらされながら生きていたのです。 神経伝達物質としては、アセチルコリン、ヒスタミン、ギャバ、ノルアドレナリン、等が多量に分泌されていました。 その後人類の進化に伴い、側坐核、腹側被蓋野から大脳新皮質につながる快楽神経というものが生まれました。いわゆるA10(エーテン神経)といわれるものです。 人間は葛藤や苦しみばかりでは生き延びることはできなかったのだと思われます。人間の身体が不安や恐怖を和らげる神経回路も必要としたのです。 この神経が活性化されると神経伝達物質として、ドーパミン、セロトニン、脳内モルヒネ等が放出されます。ギャンブル、アルコール、セックス、覚せい剤などはこの神経回路をさらに活性化させるものです。 現代人は基本的にこの二つの神経回路を備えています。 神経症やうつになると不安や恐怖に反応する神経伝達経路が強化されてしまいます。 一方快楽神経系であるエーテン神経はどうなのか。実は神経症などに陥った場合、エネルギーのある人は、この神経系も活性化されているのです。 神経症になり、不安、恐怖、不安感に押しつぶされそうになると、何とかその苦しみから逃れたくなります。手っ取り早い手段としてエーテン神経を賦活させて苦しみを和らげようとするのです。これは意識的ではなく無意識的に行われています。 そうして苦しみ一辺倒の精神状態を緩和してバランスを保とうとしているのです。人間の身体は実によくできているものと感心します。 美味しいものを食べる、お酒を飲む、身体が心地よいと感じる楽しいことをする。 具体的には、趣味三昧、旅行三昧、カード利用による買い物三昧、グルメ三昧、ネットゲーム三昧、ギャンブル三昧、アルコール三昧、セックス三昧、覚せい剤などに頼るなどです。しかしこれらは、一旦はまり込むとエーテン神経の中にしっかりとその快楽が刻み込まれてしまいます。一旦絶大なその効果を自覚すると、すぐに常習性が出てきます。依存症の始まりです。これらにどっぷりと漬かって、普段の生活に重大な影響を及ぼしている人を見ると、これらのどれか一つに特化しておられる人が多いようです。多くても2つか3つまでです。 一旦依存症に陥ると、自分の健康的、経済的、精神的、社会的立場はいとも簡単に破滅的状況に追いやられる傾向があります。 さらに周囲の人に多大な迷惑をかけることになります。 一旦依存症に陥ると、それから手を切るのは大変なことです。効き目が薄くなって使用量が増えてくると同時に、中止しようと思っても今度はイライラ感などの禁断症状が続いて抜け出すことができなくなるのです。 依存症に縁がない人でも、深刻な不安や恐怖などを抱えると、絶えず依存症の誘惑に取り囲まれているということは自覚しておく必要があります。 最初はごく小さな不安、恐怖、不快感、違和感の取り扱いを誤って、精神交互作用によって増悪させて、その苦しみから逃れるために、気が付いたらとんでもない依存症に陥っていたという事態に陥りやすいということです。 神経症に陥りやすい人は、そのことに十分に注意を払っておく必要があるのです。 依存症に陥らないためには、普段から森田理論学習によって、精神交互作用、不安と欲望の関係、不安の役割、欲望の制御、不安と欲望の調和などの学習をして、不安や恐怖の取り扱いを誤らないようにすることが大切になるのです。
2017.12.31
コメント(0)
-
他人に責任転嫁する人の問題点
森田先生のお話です。死刑囚の者が懺悔するときに、申し合わせたように必ず、自分は、これまでかくかくの悪いことをしてきたが、世の中の人はこれを戒めにして、悪いことをしてはならないという。すなわち、自分ではできなかったが、人は都合よくするようにという。これは懺悔に似て、実は本当の懺悔ではないのであります。自分は悪いことをした。自分は悪人である。善人になることができない。人に善を勧めるなど、およびもつかぬ事であるとかいうことを自覚すれば、単にそれだけで懺悔になる。自分の因果・応報を見本にして、世の中の人に善をさせて、それでいくらか自分の罪を軽減して、安らかに往生しようというのが余計なことである。またある時、森田先生のところに入院していた女性の患者さんが、森田先生のところへ手紙をよこしたことがあった。その内容は、何かにつけて主人から虐待を受けているので、どうか主人に教訓して、改心させてもらいたいという依頼の手紙だった。弟子の古閑先生は、その人は入院してあれほどよくなったのに、主人がそれほどまでにいじめるのはひどいと思ったといわれた。森田先生は、それは古閑先生の判断の仕方が悪いと言われた。森田先生は、古閑先生は言葉の見かけに、騙されていると言われた。なるほど、その奥さんの言うことをうのみにすれば、全く理由もないのに、非常識の乱暴をするその主人はほとんど精神異常とみなければならない。でも少し考えてみると、奥さんは、一方的にご主人の悪い事ばかりを誇張している。自分の欠点・短所は少しもかえりみていない。また自分がどんな事をした時に、主人が悪口を吐いたかという事はほとんど書いてないのであります。すなわち、この奥さんは、少しも自己反省の力がなくて、いたずらに相手のみを嫉視・憤慨するもので、ヒステリー性・低能性のものと鑑定しなければならない。少しも自分の悪いところや欠点を内省・自覚することなく、周囲を悪意にばかり解するときには、相当に見識があり、経験のある眼を持った人でなければ、その文章に欺かるる事はやむをえないのであります。死刑囚者、その他の悪人が懺悔するように、奥さんは自分の恥ずかしいことも、すべてその不運の一生を赤裸々に、世の人に発表するのは、懺悔に似て、実は懺悔と大いにその趣を異にしている。すなわち、本人は、自分がその悪を自覚して、これを悔いあらためて、天国に生まれるとするのではなく、これと反対に、周囲の境遇を恨み、世の人を呪い、自分の悪を弁護し、強い自信を持って自分の善意を主張するものであって、宗教家が神に準ずると同様に、いわゆる主義に殉じ、すなわち死んでも我意・我執を張り通そうとするものである。(森田全集第5巻 180、 181ページより要旨引用)少し難しいところもあるので、私なりに分かりやすく解説してみたい。私たちは、他人に暴言を吐いたり、危害を加えたときに、自分のことは棚に上げて、相手のせいにすることがあります。自分は何も悪くない。その原因を作ったのは相手の方だと言って、他人を攻撃し、他人に責任転嫁をする。そしていろいろと弁解したり、自己擁護ばかりしている。森田先生はそういう態度は、出発点からして間違っていると言われているのです。ここは「かくあるべし」の弊害、思想の矛盾について説明されていると思います。ここは森田理論の根幹にかかわる部分なので、よく理解してほしいところだ。死刑囚の話は、もっともの様に見えるが、実は重い罪を犯した自分を上から下目線で眺めている。つまり自分の立ち位置というものが、事実、現実、現状にはないのだ。ではその人の立ち位置はどこにあるのか。現実とは程遠いい雲の上のようなところにあるのだ。そこから重い罪を犯した自分自身を見下ろしている。見下しているといったほうが分かりやすい。そのような態度は、罪を犯した自分を他人事のように眺めてしまう。罪を反省して、懺悔するという気持ちにはならないのだ。ともすれば、自分のような過酷な境遇に育ったものは、重い罪を犯したとしても仕方のないことなのだ、許されるのだと弁解したりする。そして私のような者を、見本にして私のような不幸な人生を送らないようにしてもらいたいなどという。これは本当は自分にはあまり落ち度がなかったかという自己擁護以外の何物でもない。事実を軽視するとこのような状態になるのである。主人に虐待されているという女性の場合もそうである。その人は雲の上のようなところに立ち位置をとっている。決して地上にいる自分に寄り添っているわけではない。かわいそうでみじめな自分を上から下目線で眺めているのである。他人事のようである。そして主人のこのような理不尽な仕打ちは決して許すことはできないと考えている。なんとか仕返しをしてやりたい。でも、自分の力ではどうすることもできない。そこで、昔世話になった森田先生に助け舟を出してもらおうと手紙を書いたのである。森田先生のすごいところは、その女性が現実にしっかりと根を張らずに、雲の上のようなところに立ち位置をとっていることをすぐに見抜いていることである。現実に立ち位置をとっているとすれば、自分がどういう言動をとったときに、主人が理不尽な対応をとったのか、具体的、赤裸々に手紙に書くはずである。そうなれば客観的な立場から、自己内省力も湧いてくる。自分の言動を振り返ってみることができる。私の態度で改善するところがあればぜひ教えてほしいということになる。事実を出発点にすれば、問題がどこにあって、どう改善していけば、夫婦の人間関係が良くなるかという方向性が見えてくるはずだ。上から下目線で主人のいうことなすことを批判したり、否定するばかりでは、結局は家庭内別居、離婚は避けられないものと思われる。
2017.12.30
コメント(2)
-
相手の気づき、発見の楽しみを奪ってはならない
おじいちゃんやおばあちゃんの認知症が進んでくると、自分が財布をどこに置いたのかを忘れてしまう。自分がどこに置いたのかを忘れたのではなく、自分の息子や嫁が自分の財布を盗んだと思い込んでしまう。そのことを家族や近所の人に、息子や嫁が泥棒をしていると言いふらす。息子や嫁は腹が立って仕方がない。嫁の場合、夫が自分の味方になってくれないと居場所がなくなる。こういう出来事が発生すると、息子や嫁は必死になって財布を探す。だいたい置き忘れているだけだから、居間や寝室などからすぐ見つかる。なかなか見つからない場合でも、引き出しの中やたんすの中に置いているケースが多い。見つけると、 「ここに置いているじゃないか。人を泥棒扱いするのもいい加減にしろ」と言って認知症のおじいちゃんやおばあちゃんを叱りつける。自分たちを犯人扱いにした認知症のおじいちゃんおばあちゃんが許せないのである。憤懣やるかたない不快感を払拭するためには、そうする気持ちもわからないではない。でも、そんなことをすると認知症のおじいちゃんおばあちゃんは立場がなくなる。ますますおじいちゃんやおばあちゃんとの人間関係は悪化してくる。認知症の対応マニュアルを見ると、そのような対応は最悪であると説明されている。ではどうすればよいのか。たとえば、本人より先にタンスの引き出しから財布を見つけた場合、見て見ぬふりをして、 「おじいちゃん(あるいはおばあちゃん)、私は居間の方を探すから、タンスの方を探してもらえますか」と声をかける。そして運良く認知症のおじいちゃんおばあちゃんが探し出すと、 「あっ 、そんなところにあったんだ。見つかってよかったね」と言って一緒に喜んであげる。そうすると自分たちが財布を盗んだ犯人と間違われることもなく、認知症のおじいちゃんやおばあちゃんも傷つくことがない。実はこれは、集談会の体験交流でも応用ができることである。というよりも、こういう姿勢で体験交流に臨む必要がある。例えば、対人恐怖症の人で、会社の中での人間関係で悩んでいる人がいるとする。まず最初は、具体的にどのような人間関係で悩んでおられるのかを聞いていく。傾聴、共感と受容の態度で聴いていく。問題はその後である。普通は森田理論では、その症状は横に置いて、もっと仕事のほうに集中した方がいいなどとアドバイスをする場合がある。これが森田だというような話である。これ自体は森田理論に照らし合わせて見ても間違いのないことである。しかしこれは、認知症のおじいちゃんおばあちゃんに、 「あなたは記憶障害を起こして、財布がないといって大騒ぎをしている 」その事実を指摘して、あなたの態度を改めなさい、と言っているのとほとんどかわりがない。本人にしてみれば、どうしてこのような窮地に立たされているのか皆目見当がつかないのである。それを指摘してみたところで、認知症やお互いの人間関係が改善される事はほとんど期待できない。対人恐怖症の人の場合、人の思惑ばかりに注意や意識を集中していて、神経症の深みにはまってしまった。それよりは不安、恐怖、不快感、違和感などはそのままにして、目の前の家事、仕事、勉強に取り組んだ方がいい。それが森田理論の目指す道だ。そんな話をしてあげたくなる。でも、森田理論を頼って初めて集談会に参加したような人に、最初からそのような話をしても効果が上がったためしがない。それよりは次回も参加してもらえるような話をしたほうがよい。だから、アドバイスしたいのはやまやまだができるだけ相手の話を聞くことばかりにする。あるいは会の説明や発見誌はどうすれば送られてくるのかなどの話をしてあげる。とにかく、ここは自分の話をよく聞いて居心地のよいところだなという感じを持ってもらうことだ。集談会に参加している人たちも、かっては神経症で悩んでいた仲間であることを伝える。しかし、アドバイスを封印することは大変難しいハードルである。でも諦めてはいけないと思う。短絡的に「森田理論によるとこうすればいいのです」などと簡単に答えを先に言ってはならない。その道筋を相手にすぐに喋ってしまえば、相手が自分で答えを見つけるという楽しみを結果的には奪ってしまっているのである。そのようなアドバイスをしても相手には届かず、自己満足に終わってしまう。仮にアドバイスを求められた場合でも、最小限の話をする程度でよいのかもしれない。そういう気持ちを持って対応することが大切なのだ。そして何回か参加して、本格的に森田理論を学習し始めたときがアドバイスの好機が訪れた時である。その時は、森田理論を整然と分かりやすく説明してあげなければならないと思う。現状を見ていると、信頼関係を構築するべき時に、過剰に森田理論の説明をしている。また信頼関係ができ、詳しく理路整然と森田理論の説明をしなければならないのに、尻切れトンボの説明しかできていないようだ。順序は全く逆になっているのではなかろうか。森田理論に「砕啄同時」という言葉があるが、相手のことをよく観察して、機が熟すまでじっと待ってあげるという態度が大切である。
2017.12.29
コメント(0)
-
☆自動車のタイヤと森田理論
自動車はハンドル操作によって2つの前輪が左右に動きます。つまり、前輪は人間の意思の自由があるということです。後ろ側にある2つの後輪は人間の意思の自由は働きません。前輪が動く方向に従って動くだけです。これを森田理論に応用して考えてみたいと思います。自動車の前輪にあたるものは、まず行動・実践です。そして森田理論の学習をすることです。この2つは人間の意思の自由が働きます。自動車の後輪にあたるものは、 1つには、不安、恐怖、不快感、違和感などです。もう一つは、自分の望んでいる思いとは異なる目の前の事実、現実です。この2つは人間の意思の自由はありません。自然現象と同じですから、どんなに理不尽なのであっても、基本的にはそれに従うことしかできません。神経症で苦しんでいる人の場合は、ハンドルを前輪駆動から、後輪駆動に切り替えているようなものです。あるいはハンドル操作を後輪に直結しているようなものです。実際にはどう考えてもそのようなことで、自動車が正常に動くはずがありません。しかし観念の世界では実際に起こっていることなのです。これでは行動・実践がおろそかになり、森田理論学習の理解も不十分になります。それに引き換え、不安、恐怖、不快感、違和感などに対しては積極的に無きものにしようとしている。あるいは逃げまくっている。さらに強力な「かくあるべし」を持って事実や現実を否定している。自己否定や他人否定で苦しんでいる。自動車の前輪のタイヤがパンクした時、JAFに依頼すれば、パンクした前輪のタイヤを外します。そこに応急的に予備のタイヤをつけかえる事はしません。そのタイヤは今まで付いていたタイヤとは比べ物にならないほど幅の狭いものです。そこで、後輪のタイヤを外してパンクした前輪に取り付けます。予備のタイヤは外した後輪の代用として取り付けます。前輪駆動の自動車では、前輪に重量の大半がかかっているので、その方が安定性がよいわけです。それほど前輪の働きというのは重要なのです。森田理論学習を続けている人も、このことをよく振り返ってみることが必要です。行動・実践と森田理論学習は人間の意思の自由が効きます。生の欲望に沿った行動・実践はできているだろうか。基礎的な森田理論学習、応用編として「森田理論全体像」から森田理論を深めていけているだろうか。もし不十分でしたら、エネルギーはまさにここに投入すべきではないでしょうか。その2つで日常生活を牽引していくことが理にかなっています。不安、恐怖、不快感、違和感などは基本的に受け入れていくしかありません。理不尽な事実や現実も受け入れていくしかありません。いつも事実や現実を正しく認識して、そこから出発するという生活態度を養成していくことが大切です。神経症の克服は、自動車の前輪と後輪に見立てて考えてみると、とても分かりやすくなると思います。
2017.12.28
コメント(0)
-
会社での人間関係の悩みについて
会社の中で、人間関係の悩みを抱えている人が多い。何かにつけて自分のこと無視される。からかわれる。軽蔑されていると思っている人。仕事のスピードについていけない。能力的に自分はだめな人間だと思われているのではないか。いつもノルマは達成できないので、グループのお荷物扱いされている。ミスや失敗をすると、上司や同僚から激しく叱責される。こういう予期不安でいつも針のむしろに座らされているような気持ちを持っている。会社の中での言動はいつもビクビクハラハラしている。こういう人の特徴は、自分で自分が好きになれない。専守防衛で、注意や意識が自分にばかり向いている。まったく自己主張ができない。心の中では相手と違う気持ちを持っていても、言いたいことを我慢している。耐えてばかりいるので、ストレスが溜まりっぱなしである。アルコールやギャンブル、ネットゲームや風俗、買い物やヤケ食いで憂さをはらしている。そんな自分を見て、会社の仲間たちはますますけむたがっているようだ。女子社員にさえ、 「本当に大学を出ているんですか」とか「転職をされた方がいいんではないですか」などとあからさまに言われる。いつも退職のことを考えている。でも生活のことを考えると、やめるにやめられない状況だ。薬物療法を受けているが、胃がキリキリと痛む。夜中に眠れない。死ぬことを考えることもある。こういう状態は、注意や意識が会社の人間関係にばかり向いている。本来は注意や意識の大半は仕事に向いている必要がある。仕事をする上において良好な人間関係を築くことは大切ではあるが、それが最大の目的ではないはずだ。最初は仕事について自立することが目的だったのだが、そのうち対人関係を上手にこなすことに目的はすり替わってしまった。いまや「自分は月給取りという鳥である」という考え方には立てそうにもない。精神交互作用でアリ地獄の底に落ちたようなものだ。もがけばもがくほど深めに落ちていってしまう。このことをまず自覚することが必要だと思う。次にすることは精神科の医師の療法を受けることである。さらに臨床心理士によるカウンセリングを受ける。そして生活の発見からの集談会に参加する。集談会にはこうした悩みを持った人たちがたくさんいる。これは岡田尊司氏が言われているところの、「心の安全基地づくり」にあたる。グチや悩みを吐き出したりできるグループを見つけ出すことがとても大事なのである。それが配偶者であればよいのだが、そのような関係ではないことも多い。その点集談会はうってつけである。その他、祖父母、いとこ、同級生、以前勤めていた会社の同僚、昔の仲間などもその候補である。会社の人間関係だけで凝り固まり、四面楚歌状態で孤立することは避けなければならない。次に、仕事以外で自分の好きなことや、自分の得意なことに取り組んでみることである。旅行、観劇、スポーツ観戦などを思い浮かべる人も多いようだが、自分の頭や手足を動かすようなものがよい。花を育てたり、家庭菜園を始めるようなものだ。そうすることで、仲間づくりにもつながればもっとよい。趣味や夢や目標を持つことで、会社での人間関係一辺倒を避けることができる。人間関係にとらわれていると、仕事が上の空になっている。ますます仕事が停滞し、ミスや失敗を繰り返すという悪循環になっている。そういう人は、仕事をしている中で、どんな小さなことであっても気づいたことをすぐにメモする習慣を作った方がよい。むしろ小さければ小さいほどよい。できてもできなくても、ストックを沢山貯めることだ。それを1つずつ片付けて線を引いて消していく。できれば他人の役に立つことなども積極的にメモするようにするといい。簡単な物や納期の急ぐものから片付けていく。注意することは、完全主義に陥ることなく、 6割から7割程度を目指すことだ。会社での対人関係で悩んでいる人は私生活が乱れていることが多い。毎日規則正しい生活を続けることが大切である。森田理論では、外相を整えることを大切にする。形が整っていれば心はおのずから整ってくるのである。当面、会社の人間関係では朝夕の挨拶はきちんとする。仕事の上で必要な話だけはきちんとする。それ以上の付き合いはしなくても構わないと思う。最後にもう一度繰り返すと、会社勤めは生活費を稼ぐことが一番の目的です。人間関係をよくすることはその手段に過ぎない。そこに振り回されてはならないのだ。会社の人間関係で破綻していると思っている人は、当面は「月給鳥という鳥」になって安易に辞職しないことをお勧めしたい。
2017.12.27
コメント(2)
-
対人恐怖症の人へ
今月号の生活の発見誌に高良武久先生の対人恐怖症の記事があった。要旨を簡単に整理して私の感想を述べてみたい。まず、対人恐怖症の克服にあたっては、神経症のカラクリをよく自覚することが大切であると言われる。神経症は器質的なものから来るのではなく、精神的なカラクリから起こってくるものだという事を学習する必要がある。学習単元で言えば、神経症とは何か、神経症の成り立ちの学習である。神経症の治療で最も大切なのは、 「あるがまま」ということだといわれています。「あるがまま」の要点は2つあります。・人前に出て臆する気持ち、あるいは怖いような気持ちが起これば起こるままにまかせ、それに反発しないで「あるがまま」に受け入れるということです。・それらの気持ちを持ったまま、当面の目的に没入していくのであります。行動のほうを変えていくということです。飛び込み台から飛び込む3つのタイプ分けはとても分かりやすい。恐ろしいから飛び込まないというのは気分本位の態度です。先に怖ろしい気持ちをなくしてからと飛び込もうとする態度は神経症の発症につながります。怖ろしい気持ちを持ちながらも、飛び込む態度を恐怖突入といいます。森田理論学習ではこれをお勧めしています。これが事実本位・物事本位の生活態度となります。次に、神経症の人の特徴と改善点について次のように述べておられます。・対人恐怖症の人は、人と会って話をする時、自分のことばかりに注意を向けています。自己中心的というか、自己防衛に専念しています。そのような自己内省一辺倒の態度から、外界に視線を向けて、目的本位、物事本位の生活態度に変更していくことが大切です。自己内省はよい面もありますが、それと「生の欲望の発揮」とのバランスをとることのほうがもっと大切です。我々の場合、バランスをとろうと思えば、「生の欲望の発揮」に重点的にエネルギーを投入することです。その際、不安、恐怖、不快感、違和感は、この際つつきまわさずにそっとしておくことです。・神経症の人は物事がうまくいかないと、俺はもうダメだと劣等感を起こしやすい傾向があります。普通の人は、物事がうまくいかないと、 「どこがうまくいかなかったのか、どの点が悪かったのか、どうすればうまくいくのか」と考えます。神経症の人は、物事がうまくいかなかった原因を、全て自分のせいであるという風に考えやすいのです。これは森田理論で言うところの、「認識の誤り」にあたります。認知療法でいう「認知の誤り」です。その特徴は次のようなものです。1、考えることが無茶で大げさであり、論理的に破たんしている。2、マイナス思考、ネガティブ思考一辺倒である。そして、自己嫌悪、自己否定に陥っている。3、事実を無視して、実態から遊離して、勝手に先入観、決めつけをしている。4、完全主義、完璧主義、「かくあるべし」思考に陥っている。私は「認知の誤り」の学習は一単元として独立させて、自覚を深めるとともに改善策を学習しておく必要があると考えています。・神経症の人は、形が崩れています。形を正していくようにすれば、その形に伴って、心の内容も良くなります。だんだん寒くなってくると、寝床から起き上がるのが辛くなります。誰でも起きるより寝ていた方が楽です。それで中には、 「起きる気持ちが起きてきてから起きよう」と言うような人もいます。起き上がる気が起こってくるまでに、なかなか時間がかかります。パッとはね起きれば、それで気分が変わるのであります。そのようなわけで、神経症の人は生活のリズムが崩れています。日常生活を規則正しく人間本来の姿に戻していく必要があります。
2017.12.26
コメント(0)
-
本能的な欲望を野放しにしない
先日薬局の前を通りかかると、次のような文言が書いてあった。少肉多菜、少塩多酢、少糖多果、少食多嚼、少車多歩、少衣多浴、少煩多眠、少念多笑、少欲多施、少言多行である。すべて「少」「多」という字がついている。「少」は抑制すること。「多」積極的に推し進めていくこと。肉食、塩辛いもの、甘いもの、飽食、乗り物に乗る、たくさん着こむこと、ストレスを抱え込むこと、しかめっ面をすること、欲望を野放しにすること、理屈ばかりいうことは行き過ぎになりやすいので普段から抑え気味にする。反対に野菜食、酢の物、果物、粗食、歩くこと、日光をよく浴びること、よく眠ること、笑うこと、人のために役立つことをすること、実行・実践を心がけることは積極的に取り組んでいくようにする。本来はこれらがバランスがとれていれば問題は起きないのである。しかし、人間には好き嫌い、本能的欲望、楽をして人よりよい思いをしたいなどの気持ちがあるために、なかなかバランスが取れないのである。バランスをとることを無視するから、生活習慣病にかかったり、精神的に不安定になるのである。私は、「少欲知足」という言葉が好きである。欲望は放っておくと際限なく膨らんでいく。野放しにしておくと、やがて欲望は暴走を始めて制御不能となる。欲望が起きると多かれ少なかれ不安が発生する。その不安を活用して欲望を抑制する。つまり、欲望と不安のバランスを上手にとりながら生活していくということである。これは森田理論で言えば、精神拮抗作用、調和という考え方につながる。余談だが、京都龍安寺のつくばいは、口という字を真ん中に大きくとって、その上下左右に「吾唯足知」と書いてある。4文字すべてに口という字があるので、それを利用しているのだ。この内容も、欲望は無制限に野放しにしてはならない。欲望と不安のバランスとるという事は大切であるということだ。欲望は生きる上において、とても大切なものではあるが、行き過ぎると、その弊害が大きくなる。欲望と不安の関係は、私がいつも投稿しているように、、サーカスの綱渡りのように微調整を繰り返してバランスをとる必要があるのだ。生きるという事は、バランスを取りながら注意深く前を向いて前進していくことである。一旦バランスを壊してしまうと、自他ともに破滅の方向に向かう。そのことは肝に銘じておくことだ。本能的な欲望を抑制するともう一ついいことがある。鋭い感性が常に刺激を受けて、維持されやすいということである。逆に言うと贅沢三昧の生活を続けていると感性がどんどん鈍化してくるということだ。例えば、自分は霜降り肉が好きだからといって毎日食べていると、最初に食べた時の感動は味わえなくなってくる。マグロの大トロが好きだと言って、毎日口にしていると、最初に味わった感動は薄れていく。我々森田理論学習しているものにとっては、日々小さな気づきや感動が泉のようにこんこんと湧き出てくることはとても大切なことである。そこにある気づき、興味、関心、発見が宝の山となるのである。それによって感情が高まっていく。感情が高まっていけば、工夫やアイディアが浮かんでくる。つまり、やる気や意欲が出てくるのである。そういう積極的な生きる元気の素をいかにたくさん作り出すか。人生は活性化していくのは、主にこの点にかかっているのである。そういう意味からいっても、本能的な欲望は野放しにしてはならない。普通人間は放っておくと欲望が欲望を産んで収拾がつかなくなる傾向が強い。森田理論を学んだ人は、ぜひとも欲望と不安のバランスをとる事を信条にしてほしいものだ。
2017.12.25
コメント(0)
-
「自分の意思を相手に伝える」ということ
対人恐怖症の人は、人からの依頼事項を断ることをためらうことが多い。それは根本的なところで人を信頼することができないことからきている。他人の依頼事項を断ると、あからさまに相手が嫌な顔をする。あるいは、面と向かって自分のこと非難する。すると、自分は孤立して仲間はずれにされるのではないかということを恐れているのだ。そういう不快な場面が予想されるので、はっきりと自分の意思を伝えることができない。相手の理不尽な要求でも、自分の意志を捻じ曲げて耐えているのだ。これは一見すると、八方美人に見える。反対にそういう人は、相手に自分の意思を伝えて、何かをお願いするということができない。例えば集談会でも、世話役候補の人に「世話役になってください」と依頼することができない。ダメでもともとという考えが持てない。特に対人恐怖の人は、一大決心がいるのである。世話役をすることが相手の神経症の克服にとって重大な意味を持っていることは分かっている。しかしなんだかんだと理由をつけられて断られることが恐ろしいのである。予期不安でがんじがらめに支配されているのだ。注意や意識が外に向かわずに、内へ内へと向いている。常に否定的。ネガティブに考えるのだ。自分の事を悪く思われても、それは相手の自由なのだ。自分の依頼事項を相手が断っても、それは相手の自由なのだ。そういう風には体質的に考えられない。相手が自分の人格を否定していると受け取るのだ。あるいは自分の人間性に問題があると考える。本来はうまくいかなかった理由を考えればよいのだが、そんな余裕は持ち合わせていない。あまりにも飛躍しているのは頭の中ではわかっているが、行動としてはとても怖くてできないのだ。最近、私はこんな経験をした。マンション管理人の仕事をしている棟で、居住者のある女性の人から宗教の勧誘を受けた。私はそのつもりはないのだが、私のところにやって来て、お祈りをさせてくださいという。3分ぐらい目を閉じてください。今からお祈りをします。きっといいことがありますなどという。そんなことが2回あった。すると、次には本部の道場に行ってくださいという。詳しい内容説明は何もない。私はいいカモとみたのか、本部まで送り迎えをしてあげるという。都合がいい日を選んで電話をして下さいということだった。私は即座に断りたかったが、そこで働かせてもらっているという手前もあって即答できなかった。それから数日間、どうすれば当たり障りのない断り方ができるのか悩み必死で考えた。お布施はいらないのか。信者として勧誘されることはないのか。いつでも中止することができるのか。などなど。でも、これらはいくら考えても断るための口実である。相手に言い訳を与えるようなものだ。そんな折、名案が思い浮かばないので、会社の営業マンに相談してみた。するとよいヒントもらった。会社からは、仕事以外のことで、個人的に特定の居住者と接触を持つことは禁じている。政治活動、宗教の勧誘、物品販売、カラオケや飲食などの関わりは、過去に重大なトラブルに発展したことがあります。会社は、居住者との付き合い方は挨拶程度にとどめておくように決めています。特定の居住者と親しく世間話を5分以上にわたって続けてはいけません。管理会社に雇われている管理人は全員そういう誓約書にサインしています。そういうわけで、ご期待にお応えすることができませんと伝えたらどうかと言われた。それにヒントを得て、早速その居住者が受付を通りかかった時にお断りの話をした。相手は予想外の事を言われたので、一瞬驚いた様子であった。そして「勤務が終わった後も、会社に拘束されているのか」などといわれる。でも最終的には「わかりました」とぶっきらぼうに言って立ち去られました。相手に不快な感情が渦巻いているのが分かったが、この1件はこれで落着した。それ以来お祈りの話はされなくなった。これをいつまでも先延ばしにして、うやむやにしていたとすれば、後々までイライラ感が続いていたことであろう。思い切って断ることができてほっとしている。今まで夜寝不足になるほど悩んでいたのはなんだったのだろう。自分でどうしたらよいのか分からないときは、信頼できる人に相談することが一番だと感じた。自分一人の判断は間違いが多いという認識は持っておいたほうがよさそうだ。特に対人関係の面では、集談会の仲間は、適切なアドバイスをしてもらえることが多い。信頼できる人のアドバイスを参考にして、自分の意思をはっきりと相手に伝える事は大切だなと感じた。そうしないと、相手の思うつぼで、自分の意志に反した行動をとると苦しみはずっと続くことになる。
2017.12.24
コメント(0)
-
部分的弱点の絶対視について
森田先生のお話です。最近、朝日新聞に、五重奏ということが出ていた。それは本を読みながら、会話をし、字を書き、計算をするとか、同時に5種類のことをするということです。聖徳太子は1度に8人の訴えを聴かれたとのこと、すなわち八重奏である。私どもも平常、2つや3つの仕事は同時にやっている。たとえば、病院などでも、患者の家人に面接しながら机上の雑誌を読み、一方には看護婦に用事を命令するとか言うようなものである。 三重奏である。我々の日常は、だれでも、同時にいくつもの方面のことを考えているのは普通のことである。強迫観念でも、苦しみながら何でもできるものである。神経質の人の考え方の特徴として、それを自分で出来ないことと、理論的に独断してしまうのである。(森田全集第五巻 99ページより引用)観念的に考えると、物事は集中して行わないと間違いだらけになると考えやすい。プロ野球でも、いくら大観衆がいてもピッチャーはバッターを牛耳ること一点に注意を集中しているではないか。それが逆に、自分の投球動作が気になる。監督やコーチのしぐさが気になる。あるいは、自分のピッチングの組み立てを解説者がどう話しているだろうかと気になる。そんなことにとらわれていては、相手打者に対する強い闘争心が分散されて、力が入らなくなり、微妙なコントロールに狂いが出てくるのではないか。バッターだってそうだ。自分のバッティングフォームが気になる。あるいは自分の名前を連呼されて大声援を受けて、そちらのほうに気をとられていては、バッティングに集中できない。大声援が耳に入らないぐらいに、バッティングに集中していないと、 140キロを超えるような速球やキレのある変化球には、とてもではないが対応できないはずだ。森田理論では、こういう態度のことを「部分的弱点を絶対視」、あるいは「防衛単純化」とも言います。これらは認識の誤りであるといいます。「部分的弱点の絶対視」とは、神経症に悩んでいる時、自分の苦しい症状一点に注意を集中させて、これさえなければ、私の人生はうまく回転していくはずだと思っていることです。そして、何とかその苦しみから逃れようと格闘を続けているのです。しかしその多くの努力は不毛に終わります。努力すればするほど苦しみの加速度は増してゆきます。そして蟻地獄の底に落ち込んでいくのです。森田理論学習では、症状のみに注意が向いて、主観の世界にどっぷりと使っていた状態から、注意の外向化を目指してゆきます。そして活動的で前向きな生活態度に転換を図ってゆきます。この態度を森田理論では「無所住心」といいます。周囲のこと全てに気が付いて、しかも何事にも心が固着しないで、水が流れるごとく 、心が自由自在に流転してゆく有り様であります。谷川を勢い良く流れる小川を連想されるとよいと思います。鴨長明が方丈記の中で、「行く川のながれは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ 消えかつ結びて久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し」といっています。森田理論そのものの考え方を示しています。不安一点に注意を集中させ、精神交互作用で神経症に陥らないためには、この言葉を机の前に貼って戒めとしておきたいものです。「防衛単純化」は、不安の要因は無数にあります。それらのすべてに対処することは非常に困難であるように思われます。そこで、その中から最も自分が気になっていると思われる不安、恐怖、違和感に対して焦点を絞っていく態度です。これさえなければ、十分に自分の能力を発揮できると感じて、この障害と思われることに専念していく態度のことです。少し考えただけでも、容易に神経症の蟻地獄に陥ってしまいます。私たちの日常生活を見ていると、たくさんの不安や違和感に取り囲まれています。それらに一時的にはとらわれたとしても、どうすることも出来ない不安や違和感は、それらを抱えたまま次の仕事や家事、課題や問題点に取り組んでいくという態度が大切なのではないでしょうか。
2017.12.23
コメント(0)
-
☆書痙の人に対するアドバイス
森田先生が昭和6年10月13日京都の東福寺で座談会を開かれた。その時、書痙の人が森田先生に質問をしている。書痙で27年間苦しみ、この夏、宇佐先生のところに2か月入院し、先生はこれでよいと言われましたが、私は完全癖でまだ不十分だと思っています。ゆっくり活字を書くような気持ちで書けば書けるが、急ぐときには十分にはいかない。また別な人で、書痙をまずよかろうというところまで治してもらいました。しかし、退院して生活に追われると、また気がイライラして震えて困っています。そのため、今は針や灸をやっていますが、なんとか治す方法はないでしょうか。これに対して森田先生曰く。もっとよくなりたいというのはごもっとものことです。書痙はとにかく書けるようになった。それでよくなったといえる。事実唯真というが、以前よりよくなったとただ思えばよい。もっと上手になりたいと思うのもよい。ただ、自分はどこまでも欲張るものであるということを認めるとともに、以前よりはよくなったという事実を認めなければならない。十中1つでも治ったと思えば全部治る。ひとつ治らないといって苦にすれば、また十になる。十中1つよくなったという事実を認めればよい。1つ治ったことを忘れ、悔しいと思えば、また元に戻る。書痙の人はみんな普通の人より上手に書けないから、以前より治ったという事実を認めないのである。よいとか悪いとかを離れて事実を認めるのです。例えば、入院中に、体重が300匁増えたら、それを認めたらよい。体重は増えたが、煩悶はとれないといった風に、よいとか悪いとか気分本位をやめてもらいたい。また、あなたが字がうまく書けない。もっとよく描けるようになりたい。その事実を認めればよい。(森田全集第5巻 152ページから155ページより引用)森田先生はこの2人の書痙の症状の人に、何を言いたかったのか、私なりに考えてみた。この2人の書痙の人は、入院森田療法によってある程度改善しているのである。まず、その事実を認めなさいと言われている。そのことの認識が希薄である。さらに、もっと上手く書けるようになりたいという強い欲望がある。同時に、その強い欲望も認める必要がある。ただそれだけでよい。お二人の話を聞いていると、書痙を完全に治さなければという「かくあるべし」が非常に強い。理想の立場に自分の身を置いて、 十のうち、二から三程度にしか治っていない自分を否定しているのである。そうなると理想と現実のギャップがやたら気になって、神経症的な葛藤や苦しみで悩むようなことにある。本来は書痙で全く字が書けなかった状態から、ぎこちないながらもなんとか字をかけるようになったことを喜ぶべきだ。さらにもっと上手くなりたいという欲望を認めて、それに沿って努力していけばよい。決して上から下目線で現実の自分の至らなさを否定してはならないのである。これが森田先生が言われている、「十中1つでも治ったと思えば全部治る。ひとつ治らないといって苦にすれば、また十になる。十中1つよくなったという事実を認めればよい」という事だと思う。神経症の治癒という面から見れば、 「かくあるべし」的思考を、事実本位・物事本位に修正していくことが大事なのである。自分の立ち位置を変更することだと思う。あるいは、目の付け所を変えていくことだ。そのうえで、目標達成のために努力するようになれればよい。お二人の態度では、書痙は治ったとしても、根本的に神経症体質は治らないということだと思う。
2017.12.22
コメント(0)
-
夫婦の人間関係
形外会で次のようなやりとりがあった。篠崎氏が、「私は神経症が治らないときは、家の人に乱暴な事は言わなかったが、神経症が治ってからは、ちょっとのことで、弟と言い争って乱暴な口をきくようになった。これはどういうことでしょうか」と質問した。これに答えて森田先生曰く「根治法」の中に、陸軍中尉は、退院してから、以前と違って、よく部下を思うがままにしかり、また可愛がるようになったと言っているのと同じである。いたずらに自分を善人ぶらずつくろうわず、自分のありのままをさらけ出すからである。兄弟・朋友でも、いたずらに道学者流に礼儀正しく、常に慇懃であると言うことが、必ずしも親密であり、愛情があるということはできない。われわれはお互いに少々無理なことを言っても許され、自分の欠点をも知ってくれるのでなければ、本当の平和は得られないのである。これに対して篠崎氏は、 「そう言われれば、私と弟は現在、喧嘩はするが、以前よりもかえって仲がよくなっています」と答えている。(森田全集第5巻 145ページより引用)私はこの話を聞いて、あの夫婦のことを思い出した。老人ホームの慰問に行く時、この夫婦の車に同乗させてもらうことが多い。車内でこの夫婦はよく口喧嘩をする。しないことのほうが珍しい。例えば、助手席に乗っている奥さんが主人に向かって「右から車が来たよ」「交差点に人がいる」などと伝える。すると主人は、すぐに頭に血が上って「そんなことはいちいち言わなくても分かっている。黙っててくれ」と反発する。一瞬険悪になり大きな喧嘩に発展するかと見ているが、すぐに収まる。拍子抜けをする。私の家のようにお互いに小さな対立を根に持って、しばらく口を聞かないということがない。2人のやりとりを見ていると、コミュニケーションの一環として口喧嘩を楽しんでいるように見える。この夫婦は自由業なのでずっと夫婦で仕事をしてきた。一心同体で四六時中いつも身近に接触しているのである。私から見ると、お互いに顔も見たくないということもあるのではないかと思うのだが、全くそんなことはない。ただいつも意見の衝突はあったそうだ。その時、 2人とも耐えたり我慢するというやり方ではない。言いたいことを言い合う。あるいは一方が他方を支配するというやり方でもない。お互いに平等な力関係で調和がとれているようなのだ。この夫婦のやり方は、基本的には自分の感情や気持ちをそのまま相手に伝えるというやり方である。相手が反発すれば、いったんは引き下がる。そしてまた別の提案をする。つまり双方の意見の違いを見つけ出して妥協点を探るようなやり方である。奥さんに聞くと、「うちのお父さんは手先が器用で何でも手作りする。好奇心が旺盛で、思いついたことは何でも手を出す」などと主人を認めて評価をしている。何かにつけて夫自慢をしているのである。ご主人は、「うちの母さんには若い頃から苦労をかけさせた。今は旅行が趣味なので、できるだけ行きたいところに行かせている」などと思いやりのあることを言う。普段の口喧嘩を見ていると考えられない。その奥さんは、現在友達と連れ立って日本全国あらゆるところに旅行に出かけている。いわば旅行三昧の最中である。私はこれは森田理論学習で言うところの、「不即不離」の人間関係をそのまま具体化している夫婦ではないかと考えている。形外会で森田先生が言われているように、 「かくあるべし」で自分を善人ぶらず、自分のありのままをさらけ出すことができれば、人間関係ではとても楽な生き方につながると思う。
2017.12.21
コメント(0)
-
認知症にならないために
認知症やアルツハイマー病になっても、快楽や怒り、腹立たしい感情はなくなりません。これは古い脳といわれる大脳辺縁系がいつまでも機能している証拠です。扁桃体や快楽神経のA10神経は働いているのです。これは動物にもあります。でも人間と動物が一緒なのはそこまでです。人間は動物と違って記憶できるという能力が備わっています。記憶する能力があるということは、現在の感情を過去の経験、学習したことと照合することができるということです。記憶力は脳を鍛えないと衰えてきます。40代から記憶力は徐々に減退してきます。これは脳でいうと海馬や大脳新皮質などが関係しています。アルツハイマー病ではこの海馬が萎縮しているそうです。子どもの頃の重要な記憶は海馬で処理されて大脳新皮質に送られて収納されています。ところが歳をとると海馬の機能が弱まり、しだいに機能しなくなるのです。病気が進行すると、2時間前に食事をしたことさえ分からなくなるのです。あるいはさっき風呂に入ったことを記憶することができなくなるのです。これが昔のことは鮮明に記憶しているのに、ついさっきのことは思い出せない原因です。この原因として、脳に異常タンパク質が蓄積されることや神経細胞の減少、さらに神経伝達物質のアセチルコリンが減少していることが分かっています。アルツハイマーになると初期は健忘症、中期になると夜間せん妄、徘徊、幻覚妄想等の精神症状が起こります。後期になると重度の認知症になります。怒りなどの感情の抑制という面から言えば、眼窩前頭葉皮質の働きが重要になります。この部分が機能しなくなると、すぐに怒りを爆発させたり、暴力をふるったりするようになります。記憶力の低下により叱られた出来事の原因を忘れ、大脳辺縁系には叱られたイヤな気分だけが残るのです。つまり眼窩前頭葉皮質の機能低下により、溜まりに溜まった不快な感情の抑制力が効かないという現象が起きているのです。老人が2日か3日か寝込むとそのまま寝たきりになることがあります。ここで問題なのは、海馬など脳の働きも使わないと急速に廃用性萎縮を起こします。感情を正常に機能させるためには、海馬、眼窩前頭葉皮質を普段から鍛えていくことが大切です。東北大学の川島隆太教授は単純計算や音読で眼窩前頭葉皮質を鍛えることができるといわれています。手先を使う楽器の演奏や編み物もよいそうです。その他、海馬を鍛えるには、時間を忘れるぐらい1つの事に集中する。異性と積極的に話をする。これは性ホルモンの増加が海馬によい影響を与えるそうです。またプチダイエットをおこなうと海馬に新しい細胞が増えることが分かっているそうです。いずれにしても好奇心を持って、積極的に手足を動かすという生活を維持することが大切だということです。人生90年といっても、最後の7年とか8年が認知症や植物人間状態になっては悔いが残ると思います。認知症は徐々に進行し、気が付いたときでは遅いのです。また認知症は今までみてきたように心がけ次第で予防することができます。普段から森田的生活を心がけていると、脳は益々活性化されると思っていますが、いかがでしょうか。
2017.12.20
コメント(0)
-
懇親会の効用について
第9回形外会が終わった後、食事会があり、その後余興が行われている。時間は午後6時から3時間にわたっている。その日はゲームが行われた。まず「職業当て」と称し、 1組2人の背中に、芸者・医者・女中などと書いた紙片をつけ、互いにこれを見せ合いたる後、決して言葉を用いず、身振りのみで、これを相手に知らせる。つまりジェスチャーで、一方が相手の背中に書いてある職業を演じる。その動作を見て自分は背中に貼られた職業を当てるゲームである。とんでもない動作をする人もいてすぐに笑いの渦になる。次に「トエンティー・クェッション」と称し、相手が例えば電灯・鯉など、ある一つの物の名を考えているのに対し、20以下の問答にてこれを言い当てるものである。その問う方の人は、例えば人工物か、鉱物質か、この室内にあるかなどと問い、答え方はイエスとノーとのほかは答えてはならぬという規則である。(森田全集第5巻 94ページより引用)実は形外会の後には、このような懇親会がたびたび開かれている。落語を聞いたり、寸劇を演じる。踊りを踊る。歌を歌うなどである。美味しいもの食べて、その後に工夫をこなして演芸大会のようなものされているのである。森田先生はウグイスの綱渡りという宴会芸を披露された。また民謡を歌ったり、踊ったりされている。森田全集の中には確か11回にわたって、その模様が収録されている。その中でも「三方一両損」という寸劇はいたく感心した。こういうことを集談会や支部研修会の懇親会の後に取り入れるというのはどうでしょうか。すぐに場が和み、お互いに親しみが増すのではないでしょうか。集談会は、森田理論学習をするだけではなく、人間関係の幅を広げるという重要な側面もあります。苦しい時は、あの人に話を聞いてもらおう。集談会に参加すれば、あの人に会える。と思うだけで、生きていく力は湧いてくるものです。この側面を見逃してはなりません。そういうものは、理論学習をするだけでは得られるものではありません。懇親会や懇親会の後の演芸大会から容易に得ることができるのです。そのためには、新年会や忘年会、一泊学習会の懇親会を盛り上げることを考えることです。難しく考えることありません。みんなが楽しく愉快に過ごすためにはどんなことをしようかと考えるだけでよいのです。てっとり早いところではカラオケがあります。 1曲ぐらいはなんとか歌える歌を普段から準備しておくようにしたいものです。私はかって、 3メーター位前方に箱をを置いて、テニスボールを投げ入れるというゲームをしました。なかなかボールが入りません。みんな子供のように大はしゃぎしていました。その他にも2 、 3のゲームを用意しました。室内でやるゲームを紹介した本にいろいろと載っています。せっかく人が集まっているのですから、楽しく愉快に学習をしてゆきたいものです。こういう取り組みの中から、弾みがついて、私の勧めている「一人一芸」は生まれてくるのです。
2017.12.19
コメント(2)
-
悲しい感情の取り扱い方
第7回形外会(昭和5年11月9日)で香取会長は、森田先生ご令息の死去に対する哀悼の辞を述べられた。私も告別式の時は、先生の側におりましたが、納棺の時は先生も非常に悲しまれ、腸を立つように慟哭されました。出棺の時も、先生は門前で霊柩車を見送られましたが、のち二階に帰られた時は、はや風光せい月といった風に、他の事の話もされて、全く別人のごとき態度になられたのを見て、私も非常に感銘したのであります。こんなときに、先生がどうしてこのように急変されるのか、その心境を説明していただけるならば、甚だ幸いかと思います。これに答えて、森田先生は次のように話された。死んだ人の家に悔やみに行く人が、よく「死んだ人は、どうせ帰らないから諦めるよりほかに仕方がない」と言って慰めようとする人がある。大きなお世話である。そんなことを知らぬ人があろうか。しかし感情は、そのように簡単ではない。当然に死ぬべき病気でも、親の心は最後まで、これを死ぬとは思わず、奇跡的にも助かると思い、また死んでも帰ってくるような気がし、灰になっても、まだなくなったように思わない。否、そう思うのはあまりに恐ろしくて、ハッキリと理知で、そう認定することを避けて、我と我心をぼかしておくと言う風であります。「死んだ」ということも意味を明瞭にすることが恐ろしい。これは理知ではなくて、そのままの感情そのものである。こんな風であるから、その直情のままに、悲痛に迫っても、小児のように慟哭する。純なる感情であるから、日を経るままに、次第にその悲しみも薄くなり、忘れられるようになる。小児の感情が早く変化しやすいのもこのためである。普通、親族が亡くなって、喪主を務める場合、悲しみのあまり慟哭されるということはほとんど目にすることはない。淡々と喪主挨拶をされる場合が多い。割と落ち着いて対応されているようにお見受けする。しかし葬儀が終わった後、数日たってひどく持ち込まれているという話はよく聞く。なかには妻が亡くなった後、しばらくして後を追うように、気丈夫そうに見えたご主人も亡くなられたというケースもある。森田先生の場合は、告別式の場や出棺の時に人目もはばからず慟哭されたということである。そういう時は故人との思い出が走馬灯のように頭の中を駆けめぐり、悲しみに打ちひしがれるのが普通である。森田先生はその悲しいという感情を押さえつけようとしないで、そのまま味わい表出されている。しかし二階に場所を移動された後は、別人のような態度になられたのに香取会長は驚いたのである。香取会長は二度森田先生の行動に驚かれたのであった。私はここに森田先生の悲しみという感情に対する取り扱い方の真髄を見るのである。悲しいという感情はどうすることもできない。告別式ではその悲しい感情に人目をはばからず思いっきりひたりきる方がよいようである。これは怒りの感情と違って、人に迷惑をかける感情ではない。まず悲しみという感情は一山登るまで一切手を付けずとことんまでひたりきることが大切である。その悲しいという感情は人前で慟哭するという行動として表出してもいよいのである。1番問題なのは、そんなことをするとみっともない。大人げないことだと言って感情を抑えてしまうことである。実際は悲しいのに、悲しくないフリをするということは、悲しい感情を先送りすることになる。するとその悲しい感情はいつまでたっても自分の側から離れようとしなくなるのである。そしてその悲しい感情は、精神交互作用によってどんどん増悪していくのである。こういう対応は、悲しいという感情の取り扱い方を取り違えているのだと思う。森田ではどんな感情であっても邪魔者扱いをしてはならない。楽しい感情、嬉しい感情、怒りの感情、悲しみの感情、嫉妬する感情などなど、沸き起こってきた感情は行き着くところまでひたりきることが大切である。途中で、不快な感情を取り除こうとやりくりをしたり、手っ取り早く不快な感情から逃げるという事は最もまずいやり方である。感情は行き着くところまで行かせて味わい尽くす。その先は、他人様に迷惑をかけるような感情の場合は、表出することを避けて我慢する。そうすれば感情の法則1が教えてくれているように、後は流れに身を任せて、その感情は変化するのだ。じたばたしないで、台風が通り過ぎるのを待っていればよいのである。最初からうまくいくとは限らないが、そういう体験を積み上げることが、その後につながっていく。
2017.12.18
コメント(0)
-
「周囲の状況に合わせる」ということを考える
森田先生は、富士山の頂上で3時間も、浴衣1枚で寒さに震えて、激しく頭痛がしたことがあるけれども、風邪はひかなかったと言われている。風邪をひくのも魔がさすのも、必ず常に気の緩んだ時で、周囲の事情と、これに対する自分の反応が適応性を失ったときに起こるものである。周囲と自分との釣り合いが取れていれば、必ずそんなしくじりは起こらない。暖かいところではゆったりし、寒いところでは気が引き締まっておればよいけれども、暖かい所から急に寒いところへ入り、また寒いところから暖かいところに入る時に、これに対する心の変化に適応せず、気が緩んだところで風邪をひくのである。特にうたた寝のような事はよくない。しかし精神が自然になれば、うたた寝でも風邪をひかないようになる。武士が轡の音にも目を覚ますと言うのは、心は常に緊張しているのであって、こんなときには決して風邪も引かなければ、魔がさすこともないのである。(森田全集第5巻 59ページより引用)森田全集第5巻の中には、風邪をひくという話は何箇所か出てくる。この話は、風邪をひく、ひかないの話をされているが、実は「周囲の変化や動きに合わせて実践・行動・生活することの重要性」を説明されているのである。周囲の状況に自分の気持ちや身体を合わせていかないと、すぐに風邪をひいてしまう。私は10年以上前には毎年大風邪をひいていたが、森田でこのことを知ってから実践や行動をしているせいか、ここのところ風邪をひいたことがない。さて、周囲の状況や変化を無視する人はどういう人であるか。事実、現状を無視して、自分の「かくあるべし」を前面に押し出す傾向のある人だと思う。私たちは、ともすると、自分の頭で考えたことを優先して意地を張って押し通そうとする。これは、「かくあるべし」 を前面に押し出した生き方である。そうなると、周囲の状況は刻々と変化し動いているにも関わらず、その変化に対応するという意識が希薄になる。それがまずいいのである。自分の我と事実の間にギャップが生まれて、やることなすことが適応性を失っていく。それが神経症の発症の原因ともなるし、体調を壊すもとにもなる。我を通すのではなく、その時々の変化に対応して、適応することを優先するようにすればよいのだ。つまり事実本位・物事本位の生き方を理解して身に着けるとよいと思う。しかし、ここで対人恐怖症の人は1つ疑問が出てくる。自分は言いたいことも我慢して周囲の状況にいつも合わせようとしている。そのおかげでなんとか相手と破滅的ないざこざを起こさないで平穏を保っている。しかし、その方向は自己主張を封印しているので、とても辛いし苦しいばかりである。針のむしろに座らされているような状態だ。どこでもかしこでも、人に合わせるということは、大きな問題を起こさないかもしれないが、自分の意志を軽視しているので、抑うつ感が強まり苦しいばかりではないのか。この問題に対してどう考えるのか。確かに対人恐怖症の人は、専守防衛で、他人から支配されている人間である。他人の言動に右往左往して、いつも人の思惑に振り回されている。本来の人間関係のあり方としては、他人の言い分もよく聞き、自分の言いたいことも言い合う対等な人間関係が望ましい。対人恐怖症の人は、対等な人間関係を築けていない。相手に一方的に支配される人間関係になっている。これはいかにもバランスが悪い。ここが問題だ。このバランスが崩れているという問題は、何もしないで放置していてはならないと思う。対人恐怖症の人は、一方的に相手に従属するのではなく、自己表現の技術を身に着けて対応していくという面も大切である。将棋でも、専守防衛ばかりではそもそも勝負にはならない。まともな人間関係は、相手の言い分も聞くことも大切であるが、自分の言いたいことも言い、双方のバランスを維持していくことが重要である。対人恐怖症の人は、愛着障害もあってなかなか自己主張できないという問題もあるが、それでもその方向を目指さない限り、ストレスや苦しみはずっと続く。自分の気持ちや意思を相手に伝えるという努力を無視してはならないと思う。この点に関しては、森田理論学習の中の、次の2点はぜひとも身につけて、日々の生活の中で実践してほしいものだ。まず「純な心」の応用である。最初に感じた直観を相手に向かって表現していくことである。素直な感情のことだ。「純な心」の次に生まれてくる感情は「かくあるべし」を含んでいるので、相手と対立することが多い。初一念の後には、すぐに初二念や初三念といわれる「かくあるべし」を含んだ感情が沸き起こってくることを我々はすでに学習してきた。これらは当面無視して、初一念を思い出して、それを前面に押し出して、自分の思いを相手に伝えることだ。これは慣れてくればそんなに難しいことではない。ここに焦点を当てることだ。次に「私メッセージ」の応用である。「あなた」を主語にした会話は、「かくあるべし」を押し付けることになることが多い。「私はこう思う、私はこう感じた、私はこうしてくれたらうれしく思う」などの「私メッセージ」からの発言は、相手に「かくあるべし」押し付けることがない。それを受けて相手がどのような言動を選ぶかは、相手に任せているのだ。これも意識的に取り組んでいけば、必ず自分のものにできるはずだ。自己表現、自己主張の仕方はこれ以外にもいろいろと手法はある。それはそれで取り組んでみてほしい。ただその前に、森田理論学習をしている人は、とりあえずこの2点はぜひとも身に着けてほしいものである。
2017.12.17
コメント(0)
-
年賀状の作成について
年賀状の作成の時期がきた。挨拶がわりに、 「年賀状書いてますか」というのが風物詩である。一般的には、気が重いなと思っている人が多いようだ。特に出す枚数が多い人によく見られる。森田では、イヤイヤ取り掛かっればそのうち弾みがついてくるという。とにかく早く取り掛かっれば、精神的苦痛は少なくなると思う。たまに、年賀状作りがとても楽しみだという人もいる。聞いてみると、そういう人は 11月に入るとさっそく準備しているようだ。そういう人は絵手紙を書いたり、版画づくりから始める。あるいは毛筆で1枚1枚丁寧に書くので早くから始めないと間に合わなくなるという人もいる。心のこもった年賀状を受け取ると、とても嬉しいものである。草木染で自作の作品を描いたもの、達筆な字で書かれたもの、絵手紙に一言添えてあるものなど手作りの作品はとても好感が持てる。そういう人は毎年丁寧な年賀状作りに力を入れておられる。そういう年賀状をいただくと、そういう年賀状が少ないだけに、とても目立つのである。その人に対する印象が、好印象となってとても好感が持てる。人間的な優しさも感じることができる。今年も何かいいことが起きるかもという期待を持たせる。毎年2枚か3枚はある。なかには出してない人が聞きつけて、その作品を催促されることもあるという人もいる。これこそ年賀状作りに森田理論を応用している例だと思う。なかには市販の年賀状や印刷屋に頼んだ年賀状にそのまま宛名書きを印刷して出している人もいる。こういう人は、時間がなくて慌てて作ったのか、あるいは強いて出したいとは思わないが、相手からくるので、義理で出しているのだという気持ちが透けて見える。義理でいただく年賀状は多いが全く嬉しくない。出すだけ時間の無駄ではないかと思う。かえって相手に対する不信感すら覚える。むしろ出さないほうが悪い印象を与えないので、そのほうがよいということが分かっていないようだ。せめて一言、近況報告や相手のことを思いやる言葉を添えるのが常識のある人間のやることだ。一言書き添えるのは、「おはようございます」「おつかれさまです」という挨拶のようなものだ。こちらが挨拶をしたのに、無視されることほど不愉快な気持ちになることはない。さて、そのためには、 12月も押し詰まってから取り掛かるのでは遅いと思う。11月に入ると大まかな計画を立てて、早くから少しずつでも取り掛かることが大切だと思う。11月中に裏面は自分の撮った写真などを貼り付けて、一応は完成させておくのがよいようだ。喪中はがきが来るので、一旦目につくところにそのまま放置しておく。私は今年は老人ホームの慰問活動で撮った獅子舞を踊っている写真にした。12月10日過ぎから毎日5枚から10枚ぐらいずつ宛名書きを始める。そのとき、あらかじめ、昨年頂いた人のリストを作る。その際昨年喪中はがきの来た人が漏れないように気を配る。発見会関係、会社関係、OB会、友人、親戚や近所の人、資格試験の時の仲間、同窓会関係、趣味の関係などジャンル分けをしている。そして喪中ハガキが来た人に誤って出さないように先に印をつける。これが来年役立つ。それが完成すると、出す人を思い浮かべながら、余白に一言付け加えるのである。相手との思い出について書くことが多いが、ない場合は自分の日頃の生活状態を伝えるようにしている。そうすれば、特に年賀状作りのための時間を作る必要がなくなる。億劫でなくなる。さらに弾みがついてやる気が高まってくる。20日もあれば、自然に終わっており、後は年末に投函するだけとなる。出した人が懐かしさのあまり電話をいただくことがある。そんな年賀状を作りたいものだ。年賀状はとりかかるまでは、億劫で面倒だと思いがちである。でもそれを突破して、ものそのものになりきれば急に楽しい年末の活動に早変わりする。森田でよく言われるように、苦楽はコインの裏表なのだ。たかが年賀状、されど年賀状である。生活の発見誌でも、今年もらったうれしい年賀状というコーナーを作ってみてはどうだろうか。よく公民館や郵便局などで絵手紙年賀状の展示をしている。見事な作品がそろっている。現物展示は、来年の年賀状作りの励みになるかと思うのである。
2017.12.16
コメント(0)
-
指揮者小澤征爾氏の転機となった事件
世界的指揮者の小澤征爾さんは20代の頃ブザンソンの指揮者コンクールで1位になっている。また世界的名指揮者のバーンスタイン、カラヤン、ミュンシュに師事している。その人達から絶大な信頼を得て、海外では若き指揮者として評価が高かった。その小沢征爾さんが意気揚々と日本に凱旋し、 NHK交響楽団を指揮する機会があった。ところが、 NHK交響楽団員は指揮者小澤征爾さんを認めていなかった。実は当時のNHK交響楽団は、海野義雄氏がコンサートマスターを務め、東京芸大の出身者で固められていた。ところが、小澤征爾さんは桐朋学園の出身であり、 NHK交響楽団員にはランクが下と見られていたのだ。指揮を間違えるとか遅刻癖があるとか色々難癖をつけられて拒否されていた。でも大きな原因は、小生意気で学歴で劣る指揮者と共演はできないという気持ちが強かったようだ。ある日のコンサート当日、 NHK交響楽団員の全員が申し合わせて公演にやってこなかった。大人げない行動だが、これは事実だった。普通は突然このような理不尽な仕打ちを受けると怒り心頭となる。だれでもそうだ。その不快な気分を払拭するために、感情を爆発させるのが普通ではないだろうか。「いくら若いとは言え、世界で活躍している小澤だ。馬鹿にするのもいい加減にしろ」と。しかし小澤征爾さんは、感情を爆発させるような事はされなかった。ここがすごいことだ。逆に理不尽な行動をとった人たちに対して、いつかは見返してやりたいとめらめらと闘争意識に火がついたという。自分の居場所は日本にはない。それなら海外で努力精進して、世界で一流と認められるような指揮者になろう。そして名オーケストラを引き連れて日本に凱旋したいと強く思われた。当時日本人が世界で活躍するという前例のなかった時代である。野球界では野茂英雄氏がその扉を開いていったが、それよりもずっと前の時代であった。一人で飛び込んでいかれたのだ。小澤征爾さんは、世界で著名なベルリンフィルやボストン交響楽団など世界を代表する楽団で研鑽を積んでゆかれた。そしてクラッシックの本場のヨーロッパやアメリカで世界的な指揮者としてその地位を不動のものとされた。その後世界の三大交響楽団の一つと言われているボストン交響楽団を率いて日本で凱旋公演を行うことができた。賞賛の嵐であったという。その当時を振り返って小澤征爾さんは次のように言われている。もし、 NHK交響楽団が自分を暖かく受け入れてくれるようなことがあったら、私は日本に留まっていただろう。そうすれば、世界の小澤征爾と言われるような世界的な指揮者にはなる事は出来なかったであろう。その当時は腹が立って仕方がなかったが、今現在はNHK交響楽団に受け入れられなかったからこそ今の自分がある。逆境こそ私の出発点であった。だから拒否されたが、今となっては感謝しかない。この話は、流罪や迫害に合いながらも、北陸や関東で布教活動を続けられ多くの門弟を育てられた親鸞聖人を思い出す。一時の感情に翻弄されることなく、自分一人の力で運命を切り開いてゆかれた姿に共感を覚える。運命は耐え忍んでいてはつぶされてしまう。森田先生が言われるように、運命は切り開いていくしかない。正岡子規、後藤新平、エジソン、野口英世などもそうだった。ここが森田理論に通じるところである。
2017.12.15
コメント(0)
-
「書く森田療法」について
先日、森田療法学会での「踊る森田療法」「歌う森田療法」について紹介したが、もう一つ「書く森田療法」というのもあった。これは書道を取り入れた森田療法だ。自分の思い思いの字を選んで毛筆で書くのだ。一文字、あるいは2文字というのが多かった。これは1人で作品を作る場合と、4人ぐらいのグループで1つの作品を完成させる場合があった。やり始めると、みんなできるだけ素晴らしい作品にしようと一生懸命になる。そこで出来た作品はしばらく展示しておくということだった。それは不満足な作品であっても、それを受け入れるという体験になるということだった。この話を聞いた人からは、その際墨汁を使っているということだったが、墨をするということから始めたほうがよいのではという意見が出た。私は書くといえば、川柳やユーモア小話つくりを思い出す。これらもお金もかからず、いつでも手軽に楽しめる。その作品を皆の前で公開してあげれば、人からも喜ばれる。「おばあちゃん 試合のある日は カープ女子」「新年会 一人一芸 花盛り」「不眠症 集談会では 大いびき」「馬になれ 孫が飛び乗り ムチを打つ」来年の生活の発見誌1月号に掲載されるかどうか今からとても楽しみだ。私は1年を通じて川柳を作り続けているので、常に注意や意識は外向きになっている。こういうのを物事本位というのである。森田理論の目指すべき方向と一致している。このブログは初めて丸5年になる。文章を書くという事は、まず本を読んでネタを探す。心にひっかかるところがないと文章は書けない。疑問や興味や関心を持つことがとても大切である。次に森田理論に照らし合わせて、頭の中でいろいろと構想を練り、音声入力でどんどん入力していく。さらにそれを手直ししていく。そして投稿原稿として予約している。楽天のブログには予約機能があるので、旅行に出かけるときなどはとても楽である。今日現在は20日先の原稿づくりをしているのである。この作業を毎日繰り返していて思ったのだが、5年も経つと森田理論の理解は確実に深まっていった。また正式に文章の書き方を学んでいるわけではないが、ある程度の文章力がついた。また頭を使うのでボケ防止にもなっているのではないかと思う。それどころか益々さえてくる。これもアクセスしてくれる人がたくさんおられるから、弾みがついてきたのである。始めた当初は1日で10名から20名程度だった。現在は1日で1000名を超える日も珍しくない。最大4000名以上のアクセスがあったが、生活の発見会以外の人も森田に関心のある人がおられるということが分かった。始めた当初は5年で10万人ぐらいのアクセスがあればと思っていたが、実際には70万人を超えた。これはうれしい想定外だった。今では、5年を過ぎてももっともっと続けて、森田理論の普及に力を注ぎたいと考えるようになった。これが自分に与えられた天職ではないのかと思うようになった。私の参加している集談会では、水彩画の先生をしている方に指導してもらい、水彩画体験をしたことがある。その先生は、絵は上手い人と下手な人がいるので、今日は自分の利き腕とは違う手で描いてくださいと言われた。私は持参していた録音機と小型スピーカーを描いた。左手で描いたので少しぎこちないものになったが、味わい深いと思っていまも部屋に展示している。つい1年位前になるが、全員で向かい合わせになって似顔絵作りをしたこともある。本職の人が描くような作品にはならないが、とても個性的な作品が出来上がった。みんなの前で発表しあって大いに楽しんだことがある。森田先生の所では、夜は版画づくりのようなことをされていたという。例えば「事実唯真」と言うようなもの彫刻刀で彫っていた。これも興味を引く。そのほか集談会で取り組んだ「折り紙体験」も面白かった。その時は鶴を折った。こういう体験を集談会で短時間でもいろいろ取り入れていると、弾みがついてくる人がでる。ある人が小型ドローンの操縦実演をされたが、私はそれを見てすぐにやり始めた。模型ヘリコプターよりも簡単に操縦できた。こんなことがより多く頭の中に浮かんでくるようになれば、もう神経症で振り回されて生活が滞ってしまうことはなくなると思う。
2017.12.14
コメント(0)
-
☆変化に合わせる生き方
孔子の言葉に、「君子は、和して同せず、小人は同して和せず」という言葉がある。偉い人は人の意見を尊重して、いたずらにこれを排斥せず、しかも自分の意見は持っている。普通の人は、人が何か言えば直ちにそうかと思いながらも、いちどは争ってみる。偉い人は衆議に服従するけれども、自分の見識は動かない。この言葉のポイントは、偉い人は周囲の状況に合わせることができるということだと思う。いくら見解の相違があろうとも、最後には周囲の状況に同調するということだ。自分が周囲から浮き上がってまで、自分の意見をどこまでも主張して押し通そうという態度ではないということだ。ここで1つ疑問がある。自分が考えに考え抜いて、これだという確信を持った考え方なら、他人といくら見解の相違があるとそれを押し通すべきなのではないかということだ。それが自分の存在意義、存在価値を高めることにつながるのではないかということだ。普通一般的には、この考え方に同調する人は多いと思う。私は森田先生がこの話を持ち出して私たちに何を伝えたいのだろうかと考えてみた。森田先生は、周囲の人たちをよく観察して、その流れに乗って生活しなさいという事伝えたいのだと思う。谷川流れる水のように、流れに沿って生きていくということだ。言葉を変えれば、変化に対応した生き方を勧めておられるのだ。事実に従うといってもよい。私たちが生きている間は、不安や恐怖が絶えず襲ってくる。それらにいちいち立ち止まってとらわれていては生活が滞ってしまう。それらをいちいち解決してから次に進むという態度ではなく、未解決のままでも生活を維持していく態度が大切なのである。この生き方を上手に説明した文章がある。サーフィンの話である。サーファーは波という、動いているものに乗っかっているのです。常に波の様子を読まなくてはなりません。波はその日の天候によって変化し、動き、下手をするとサーファーを飲み込みます。サーファーにとっては一瞬一瞬は緊張の連続です。波を読み、波の上でバランスを取り、波に乗れれば、素晴らしいスピード感が体験できます。自分だけの力ではなく、勢い良く打ち寄せる波の力を自分のものにして、岸まで疾走することができるのです私たちの生活もそうです。時間は波のように変化して動いています。私たちはその波に乗らないことには生きていけないのです。人生の波に乗るとは、結局、毎瞬毎瞬、緊張感を持ち、周囲をよく観察し、そのとき、そのときで適切な判断がと れるように努め、自分の生を前に進めていくことです。流れに乗るということです。流れに乗るとき、人は注意を一点に集中したままではいられません。四方八方に目を向け、状況を考え、自分の姿勢を判断し、バランスをとっていくのです。いわゆる「無所住心」の状態です。そんなふうに現実の流れ、時間の流れに乗っている時、もはや神経症の悩み、つまり主観にとらわれた状態でいられるはずもありません。むしろ、目の前に広がる新しい景色に目を奪われ、自分が全く予想もしなかった展開に驚きながら、更に興味や意欲が湧き出してくるのです。そんなふうに人の心というものは必ず変化していくものなのです。永遠に神経症の悩みの中にとどまっている事などはありえません。自然界で静止しているものなどはありません。全てが流れ、動いて変化していくとしたら、その変化についていくことが安定であるわけです。森田先生は「不安定即安定」と言いました。不安定な人生にあるがままに服従するとも言っています。不安定なまま時間の流れ、環境の変化についていこうとするのが流れに乗るということです。(流れと動きの森田療法 岩田真理 白揚社 64ページより引用)
2017.12.13
コメント(0)
-
自助組織のルーツを探る
自助組織である生活の発見会のルーツを探ってみた。1929年(昭和4年)森田正馬先生のもとで、形外会が始まった。これは森田先生のところで入院治療を受けた人が、月に1回森田先生の家に集まっての懇話会であった。ここでは、神経症のことにこだわらず、人生や日常生活の問題なども話された。この会合は、昭和12年4月まで7年4か月、合計66回開催されている。その内容は森田正馬全集第5巻にすべて収録されている。今読んでもとても参考になる。その後森田先生は昭和13年4月に64歳の若さでご逝去された。形外会の参加者の中に水谷啓二氏がいた。水谷啓二氏は昭和7年から昭和13年まで森田先生のところに居住しながら熱心に森田療法を学ばれた。その後森田関係の図書の執筆活動を続けられていたが、それに飽きたらず、新しい活動を始められた。水谷啓二氏は昭和31年、自宅を開放して、形外会方式での相談会として「啓心会」を始められた。翌昭和32年には、機関紙「生活の発見」誌の発行を開始した。この名付け親は社会運動家永杉喜輔であった。そして昭和34年からは、啓心寮と精神科医の協力のもとに啓心会診療所を始められた。森田先生の入院森田療法とほぼ同様の活動内容である。森田療法で神経症者を救うために、全身全霊を持って打ち込んでいかれた。しかし残念なことに、昭和45年3月58歳という若さで亡くなられた。その後、「生活の発見」誌の同人であった長谷川洋三氏が中心となって再建に立ち上がった。ここでは、生活の発見会を医療の場から切り離し、会員相互の支え合いと森田理論学習の全国展開が決定された。この方針の決定が大きな転換点となった。自助組織としての生活の発見会の誕生は極めて歴史的意義がある。その後、組織は急速に全国に拡大し、 1993年には会員は最大となり6,000人を超えた。発見会活動はどの県でも活発であり、集談会は全国で約120カ所以上であった。生活の発見会は1998年、保健衛生の分野で優れた業績をあげた団体に贈られる「保健文化賞」を受賞している。その後、活動は停滞しているが、それでも会員2000名を超えるようなNPO法人はほとんど存在しない。余談だが、その後の森田療法は、元メンタルヘルス岡本記念財団理事長のご尽力により、中国をはじめとする海外において目覚ましい拡大を遂げている。現在、神経症の治療としては、薬物療法、カウンセリング、認知行動療法を始めとする精神療法が主流である。森田療法はそれらに比べると後塵を拝している、しかし森田療法にはそれらにはない優れた面がある。それは、神経症の治療にとどまらず、神経質性格を持った人がいかに生きていくべきかという生き方モデルを提示している点である。だから生涯学習として森田理論学習を続けている人が多いのである。今後森田療法は、生き方モデルとしての側面を大いに磨き、人のため世のために貢献していくべきだと考える。現在は生まれ変わるための過渡期に当たると考えている。苦しい時期であるが、森田理論は必ず評価される時代が来ると信じている。
2017.12.12
コメント(0)
-
会社で孤立している人へ その2
昨日の続きです。相談者にそのことを理解してもらうことが先である。そこまでくれば、あとは森田療法によっていかにしてして対人恐怖症をいかに克服していくかという話をすることになる。傾聴、共感、受容は大切であるが、信頼関係ができたあとは、適切な助言に進まないと相手に不安や不満が残る。まず、どんな不安や恐怖も時間が経てば、それが薄まったり、消えてなくなってしまうということを理解してもらう。これはどんな人でも経験されていることだ。学生時代に友達とけんかなどをした経験があっても、いまだに腹が立って感情が高ぶっているといることは、まずありえない。時間が怒りを自然に解決しているのだ。また、場所や環境を変えるだけでも不安は変化して、消長してしまうことも理解してもらう。いわば感情の法則の理解を深めるということだ。次に新しい行動を起こすと、以前の不安や恐怖は次第に収まってくる。新しい行動をとると、新しい感情が発生するという事を理解してもらう。これは意外と見落としがちであるが、不安や恐怖の解消に一役買っている。対人恐怖症の不安に取りつかれているときは、不安を1つに絞って格闘しています。新しい感情が生まれると、以前の不安にばかり関わってはおられなくなります。たとえば仕事中に何か問題が発生した場合、神経症の悩みは横において、問題解決に注意や意識を集中することになる。これを意識して行うことができるようになればいいのだ。不安が2つになれば、以前の不安の悩みは、極端に言えば2分の1になります。行動に弾みがついてくれば、以前の不安は変化してくるということが体験的に分かるようになります。注意と意識を対人不安だけに向けるのではなく、目の前の仕事や日常茶飯事、興味や関心に向けるようにするとよいのです。この時、対人恐怖症の人は、特に人の役に立つ行動が有効になる。意識や注意が自己内省的、自己中心的に働く傾向が強いので、それを打破することにつながる。自分のできるちょっとしたことで、人の役に立つことを見つける習慣を作ることだ。この事を森田療法では、「生の欲望の発揮」と言っています。その基本は、規則正しい生活をする。日常茶飯事を丁寧に行うということです。興味や関心があれば、好奇心を生かしていろんなことに手を出してみるということです。そういう習慣が身についてくると、次第に活動的になり、日常生活が好循環してきます。それに伴ってもともとあった不安は次第に小さくなってきます。この体験の後で、不安や恐怖がどのように変化してきたかを振り返ってみてください。きっと、元の対人不安や恐怖はなくなることはないにしても、ずいぶん変化していることでしょう。不安や恐怖をすべてなくすることを目指すことは不可能だということも理解する必要があります。それはあなたに、人と仲良くしたい、人によく思われたいという強い欲求があるからです。そのような強い欲望のある人は、強い対人不安が生まれるのは当然のことです。不安と欲望はコインの裏と表のような関係にあります。欲望の強い人は不安も強くなるのです。それは避けることのできないものなのです。肝心なことは、不安に振り回されるのではなく、「生の欲望の発揮」に注意や意識を向けることが大切なのです。サーカスの綱渡りのように、欲望と不安のバランスをとりながら、生活を前に進めていくことが大切なのです。人と仲良くしたい、人からよく思われるたいという欲望の達成のためには、人に役立つことをどう手がけいくかということを常日頃から実践することが大事なのです。
2017.12.11
コメント(0)
-
会社で孤立している人へ その1
会社で小さなミスが相次ぎ、女子社員にも同僚にも上司にも馬鹿にされているようで、会社に出勤するのが苦しいという人がおられます。なんとかこの苦しい状態を解消したいとインターネットで探して集談会に参加した。話を聞いてみると、できるだけ言いたいことを我慢しているが、時々我慢しきれずに爆発することがある。会社では、できるだけ話をしないようにして人を避けている。最近は昼ご飯も1人で食べることが多い。ストレスを発散するために、仕事が終わるとパチンコやネットゲームにはまっている。精神科にかかり、抗不安薬を処方してもらっている。その他、認知行動療法などを受けたが改善にはつながらなかった。こういう方が集談会来られたどのように対応していけばよいのだろう。まずはその人の話を共感的によく聴いてみることが前提だ。その人は対人恐怖症を改善するために精神科にも通い、認知行動療法などの心理療法を受けられている。それ以外にも対人恐怖症の改善のための自助努力をされているかもしれない。でもそれらの涙ぐましい努力は、ことごとく自分の期待する成果には結びつかなかったという事を「自覚」してもらうことが必要だと思う。不安を直接取り除くという対症療法は、ことごとく失敗したという事実をはっきりと認識できれば森田療法に取り組む前提条件が整う。まだ不安を直接取り除くことに期待をかけているのならば、それらを先に試してみる方がよいと思う。でもやはり対人恐怖症の改善には結びつかなかったという絶望の体験が必要なのである。いろいろ試してみれば、直接不安を取り除くという方法ではうまくいかないという諦めがつく。背水の陣で森田療法に取り組めるのである。他の療法と二股かけているようでは、森田療法は即効薬ではないので途中で脱落してしまうことのほうが多い。森田療法の最大の特徴は、直接不安を取り除くという療法ではないということである。こういう方法をとる心理療法は、基本的には存在しない。森田療法では不安は不問にする。不安と正面から向き合って取り去る療法ではない。別の言葉で言えば不安をかわす。不安をすみやかに流してしまう療法なのである。そういう療法であるが故に、回り道をとる。急がば回れ的な療法なのだ。だから、人によっては症状と正面に向き合わない中途半端な療法に見えるのだ。これは大いなる誤解なのだが。でも、よく思い出してほしい。対人恐怖症を直そうとして注意や意識をそのことにばかり集中してどういう結果が待っていたのか。注意と感覚の悪循環によって、症状が治るどころかますます悪化して、会社の中で孤立を深めていったのではないか。さらに不安と行動の悪循環で仕事が手につかなくなり、さらにミスを連発し、その結果女子社員、同僚、上司から軽蔑され続けたのではないのか。地図上で直線で100キロ先に宝物があるとする。でもその直線上に5,000メートル級の山脈が横たわっているようなものだ。さてあなたならどうするか。他の療法は、なんとしてもその山を乗り越えて、短い距離で直接的に手っ取り早く目的を達成しようとする。つまり不安に直接働きかけて、不安を取り去るという対症療法なのだ。森田理論は、そんなことは勧めない。たとえ目的は達成できたとしても大きな痛手を受けると教える。つまり、再発しやすくなるとみているのである。またこれでは生きづらさは全く解消できない。森田理論は、目的地に到達するまで500キロかかろうが、 1000キロかかろうが比較的平坦な道を迂回する方法をとるのだ。そのほうが安全で確実だからだ。つまり人生観までを視野に入れた療法なのである。不安を取り去るのではなく、不安を放っておいて、目の前の関心や仕事などに手を出していく療法なのである。そして不安の持っている重要な役割に気づくようになる。不安を敵視する態度が改められて、不安を欲望の相棒と見れるようになる。不安と欲望のバランスを意識して生活に取り組むことができるようになるのである。
2017.12.10
コメント(0)
-
事実本位の生活態度を養成するために
私のいう「森田理論全体像」の4番目の柱は、「事実本位・物事本位の態度を養成する」ということです。これについてはすでに何度も説明している。詳しく知りたい人はキーワード検索で見てほしい。その中身として、事実をよく観察する。事実は隠しだてをしないで具体的に話す。事実は裏表があるので、両面観で見るようにする。「かくあるべし」を少なくするために、「純な心」や「私メッセージ」「winwinの人間関係作り」を活用する。他人と比較して違いを確認することはよいが価値判断をしないこと。それぞれの存在価値を認めて高めていくこと。他人への共感、受容力をつけることなどを提案してきた。確かにそのような方向に切り替えないと、いつまでも「かくあるべし」という理想と現実のギャップに葛藤して苦しみ続ける。そのためには、さらに掘り下げて、「事実本位・物事本位の態度を養成する」という単元を学習する必要がある。その方向に向かうための、基本的な考え方をしっかりと持つことだ。1、完全主義、完璧主義をやめて、60%主義、ほどほど主義、中庸、バランス、調和の考えたかを理解して生活に活かす。なぜ完全主義、完璧主義はいけないのかということをしっかりと自覚すること。完全、完璧を目指すことは構わないが、そのことに固執しすぎると、逆に現実、現状、事実を否定することがダメなのである。2、他人へのコントロール欲求、つまり他人を自分の思い通りに操作したいという態度を改める。かけがえのない存在価値を持った人間として評価して、互いに尊重しながら生きていく。アドラーのいうタテの人間関係から、ヨコの人間関係を重視する生き方に変えていくこと。これは人間が自然に対する姿勢にしても同様である。自然をコントロールしすぎてはならない。最近の異常気象は地球の温暖化、無制限なCO2の排出の結果である。人間の欲望の暴走が異常気象の原因である。無制限な欲望の暴走は、人類の滅亡に結びつくことを認識すべきである。アメリカのトランプ大統領はパリ協定からの離脱を表明したが、将来の人類の目指すべき方向性からは逸脱していると思わざるを得ない。3、自分もかけがえのない存在価値を持った人間として再評価していく。森田でいう唯我独尊の立場を明確にする。自分の身体はすべて自分のものという考え方が主流である。私はこれに対して、自分の身体は神様からの預かりものであるという考えに立っている。いわばリース物件である。持てる特性や能力を思う存分に花開かせてあげないと次にはつながらないと考えている。4、結果よりもプロセスに重点を置いていく生き方。努力する過程が幸福であるという考え方に立つこと。森田でいう「努力即幸福」という考え方をしっかりと理解する。自分の取り組んでいることに、今一歩真剣になって、興味、気づき、発見という宝物を見つけるように努力する。それ以上に味わい深い人生を送る方法はないと考えている。以上の4つを「事実本位・物事本位の態度を養成する」というベースの考え方として、学習していくことを提案したい。
2017.12.09
コメント(0)
-
森田理論全体像の資料の件
たくさんの人から資料の依頼がありました。ありがとうございました。急いでメール送信をしておりますが、土、日ですべてメール送信しますので、すぐに届かない方は今しばらくお待ちください。尚代金はいくらかといわれる方がおられましたが、メール送信ですので無料です。尚今回お送りするのは、テキスト「新版 これで納得! 実践的森田理論学習」の中の第5章から第10章の部分です。図解はエクセル。他はワードで作成しています。A4で約40ページです。森田理論全体像の図解第5章 森田理論全体像とその説明第6章 生の欲望の発揮第7章 欲望と不安の関係第8章 「かくあるべし」の発生と苦悩の始まり第9章 事実本位・物事本位の生活態度を養う第10章 森田理論のキーワードなおこのテキストは研修会や依頼された方に、200部程度は配布しておりますので、すでにお持ちの方はダブることになりますので、ご了解願います。
2017.12.08
コメント(0)
-
「森田理論全体像」の学習の必要性
私は、森田理論の習得期間を、おおむね3年と見ている。短期集中型をオススメしているのである。これが5年も10年もかかると、途中で投げ出してしまう可能性が高くなると思う。1年目は基礎的な学習である。神経症の成り立ち、神経質性格の特徴、感情の法則、行動の原則、認識の誤りなどの学習である。学習の後で、体験発表などで自分の経験と突き合わせていく作業が必要となる。合わせて、自分の生活の中で活用できることは、早く取り入れるようにする。全部でなくても1つでも2つでも構わない。2年目に入ると応用編の学習に入る 。ここでは、「森田理論の全体像」の理解の学習から入る。これはいわば、詳細な地図を携えて森田理論学習に取り組むようなものである。森田理論を俯瞰してみると次の4つの大きな柱がある。1 、生の欲望の発揮2 .不安と欲望の関係・精神交互作用による症状の固着3 . 「かくあるべし」の発生と苦悩の始まり4 .事実本位・物事本位の生活態度の養成内容をくわしく知りたい人は、ホームページ「森田理論学習のすすめ相談室」(morita1.webnode.jp)からメールしてくだされば、折り返し資料をメールいたします。ここには見やすい図解がついている。これを見ていると、治るとはどうすればよいのかはっきり分かります。また自分の学習や実践の努力目標が見えてきます。3年目に入ると、今までの学習の上に立って、本格的に実践・体験学習に入る。生活の中に活用していかないと、森田理論は宝の持ち腐れとなる。やみくもに取り組むよりも、自分に合わせて焦点を絞った方がよいと思う。この学習ステップで「かなめ」となるのは、 2年目の「森田理論の全体像」の学習であると思っている。森田理論学習では、一般にはなじみのないキーワードは頻繁に使われている。これらは単独で理解することは構わないが、森田全体像の中で理解することが極めて効果的である。この学習によって、森田理論の全体の中で、どの部分の学習をしているのか、あらかじめよく分かるようになる。全体の森田理論の枠組みを意識しつつ、学習しないと、学習のための学習で終わってしまう可能性が高くなる。ですから、森田理論全体像を図示したものを手元に置いて学習することが大切になる。私は机の前に図解したものを張り付けている。これをいつも眺めて学習場所を確認している。1 、「生の欲望の発揮」に該当する森田のキーワードは次のようなものがある。生の欲望、なりきる、感じを高める、無所住心、不即不離、変化に対応する、物の性を尽くす、運命を切り開く、唯我独尊、努力即幸福2 .「不安と欲望の関係・精神交互作用による症状の固着」に該当するキーワードは次のようなものがある。とらわれ、はからい、精神拮抗作用、調和・バランス、精神交互作用、手段の自己目的化などがある。3 . 「かくあるべし」の発生と苦悩の始まりに対応するキーワードかくあるべし 、思想の矛盾、理想主義、完璧主義、コントロール欲求などがある。4 .「事実本位・物事本位の生活態度の養成」に対応するキーワード純な心、あるがまま、自然に服従、事実唯真、事実本位、物事本位等があります。 「森田理論の全体像」の学習では、4つの大きな柱の相互の関連性の学習が欠かせない。それが理解できたら、その4本の柱をもっと深く掘り下げて学習していく。そして、今あげた森田のキーワードで補強していくという順序になります。家の骨組みがしっかりと出来上がった後で、壁を塗って総仕上げをするようなものである。このブログを見ている人は、是非森田理論を自分のものにしてほしいと思っている。そうすれば人生90年といわれているこれから先の人生が味わい深いものになるはずだ。
2017.12.08
コメント(0)
-
認知症と神経症
先日出席した森田療法学会で面白い話を聞いた。認知症を自覚している人は、自ら病院を訪れて認知症を直そうとする。物忘れが激しくなった、薬を下さいという。認知症がさらに進行すると、被害妄想もでてくるという。探し物をしても見つからない。私物を盗られたのではないかなどという。通帳や印鑑などの大切なものをカバンの中に入れて持ち歩くような人も出てくる。しかし、認知症がさらに進むと、物忘れに対する訴えはしなくなる。診察すると、 「記憶力は人並みだと思います」「自分が忘れっぽいと思ったことは1度もありません」などという。被害妄想も全く出てこなくなる。こうなると、治療の施しようがなく手遅れであるという。私はこの話を聞いて、神経症が治ったという人のことを考えてみた。神経症で苦しんでいるときは、何かに追い詰められたようで、とても苦しい。不安や恐怖で押しつぶされそうになる。しかし森田療法に学び、不安を抱えたまま生活を進めていくと、精神交互作用は打破され、いったんは治ったかのように見える。溌溂として、肩で風を切るような自信に満ち溢れている。私生活でも、会社の中での行動もそうだ。集談会では、自分の神経症の克服体験を得意げになって話す。上から下目線で神経症で苦しんでいる人たちを見て、自分のやり方を押し付けるようになる。そういうタイプの人は集談会に参加した人はすぐに見抜いているのである。「かくあるべし」が強く出てきて、集談会の中で浮き上がってしまい、参加者から煙たがられるにもかかわらず、本人は全く気づいていない。影では、あの人は神経症が治る前の方が付き合いやすかったと言われるようになる。悩みを抱えて、四苦八苦しながら生活をしていた頃の方が、魅力がある人間として認知されているということである。神経症で悩んでいた頃の方が仲間として迎えられていたということである。本人にはその自覚がないので始末が悪いのだ。これを認知症の段階で言うと、治療の施しようがなくなった最終段階に入っているのではないかと思う。普通は神経症を克服しても、不安や恐怖を感じやすいという神経質性格は変わらない。不安や恐怖に対しての受け取り方や対応方法が変わってきたということである。だから普段の生活はビクビクハラハラしながら薄氷を踏む思いで生活していることには変わりない。また精神交互作用が打破されても、 「かくあるべし」から対象を見てしまうという思想の矛盾は残る。不安や恐怖にとりつかれて神経症に陥る場合よりも、思想の矛盾で葛藤や悩みを抱えて神経症になる場合のほうが症状としては深刻である。その点を見落としてしまえば、神経症の陶冶とは程遠い。この2つを視野に入れて、生涯学習として実践を積み重ねていく気持ちを持っていれば、軽々しく神経症が治ったといって有頂天になることはないと思う。相手の立場に立って見れるようになる。
2017.12.07
コメント(2)
-
事実を4つに分けて考える
先日の森田療法学会で岩木久満子先生の外来森田療法の話があった。その中で、事実をどう捉えるかという話があった。事実には次の4つがある。・身体の事実・ ・ ・自分の容姿、病気になったという事実・心の事実・ ・ ・不安や恐怖がわき起こってきたという事実・人生の事実、世の中の事実・ ・ ・自分の生まれ育った境遇や自然災害などを受けるという事実・己のあり方の事実・ ・ ・不安にとらわれたり、 「かくあるべし」を自分や他人に押しつけているという事実。早口で説明されたので、内容説明は若干間違っているかもしれないが、事実というものを4つに分けて考えられているということに共感した。私たちは、森田理論学習の中で 「かくあるべし」を少なくして、事実本位・物事本位に生きていく生き方を学んでいる。しかし十把一絡げで事実というものをとらえていると、事実というものが漠然としたものになる。このように事実を分けて、今の事実はどれに当たるのだろうかと考えながら、学習していく方が効率的である。一般的に森田理論では、心の事実についてのみ語られていることが多い。不安、恐怖、不快感、違和感などである。感情の事実に偏っていると、他の事実については考えが及ばなくなってくる可能性がある。そうなれば、事実を正しくとらえて、対処しているとは言えないのではないかと思う。私は、 「森田理論全体像」の中で、事実を4つに分けて考えると、より正確に分析できると述べている。・自然に湧き上がってきた。不安や恐怖などの感情の事実・自分の素質、容姿、性格、能力、弱みや欠点、ミスや失敗などの事実・他人の自分への理不尽な仕打ち、他人の素質、容姿、性格、能力、弱みや欠点、ミスや失敗などの事実・自然災害、経済危機、紛争など世の中の理不尽な出来事。不安、恐怖、不快感、違和感にとらわれて、精神交互作用によって神経症として固着するということを森田理論学習で学んでいる。しかし、事実にはそれ以外にもたくさん考慮しなければならない事実がある。それらにとらわれて、 「かくあるべし」で事実を否定してはならないのである。嫌な事実に直面した場合は、この4つのうちのどれに該当するのだろうかと考えて、如何にすれば事実に服従できるのかと考えていくことが肝心である。森田理論では現実、現状、事実にしっかりと根を張り、そこから目線を少し上にあげて前進していく生活態度を養成することを目指している。そのためには、事実をより正確につかむということが大前提となる。そのために岩木先生の言われたことや、私の分析した事実についての分析を参考にしてほしい。
2017.12.06
コメント(0)
-
歌う森田療法について
パニック発作に森田療法を応用していたお医者さんの話である。パニック発作に対して、森田療法の「不問」だけで対処すると、患者は「不満や不安」で治療から脱落してしまうことを少なからず経験してきた。これは我々も思い当たることがあるので、思わず苦笑してしまった。パニック発作の急性期にはベンゾジアゼピン系薬が有効である。即効性があり、使い勝手が良い。有効であるが故に、これを使いすぎると薬物依存になることも経験してきた。SSRIは長期的には有効であるが、即効性がないのが欠点だ。ところでパニック発作に陥ると、脈拍や呼吸が速くなる。脈拍や呼吸は早いと不安になるし、不安になるとますます脈拍や呼吸が増えるという悪循環に陥る。この場合、脈拍は変えられないが、呼吸は不随意でも随意でも行うことができる。呼吸をゆっくりすることで落ち着く。特に呼気をゆっくり吐くことが重要である。リラクゼーションに有効な深呼吸、ヨガ、太極拳、 禅 、瞑想、自律訓練法などに共通する。しかし、これらは習得するのにトレーニングが必要であり、時間がかかる。1番お手軽な呼気をゆっくりする方法は「歌を唄う」ことである。(第35回森田療法学会 一般演題5-2から要旨引用)この話をもとにして話をしてみたい。まず歌を歌う前に、声を出すということは大切だと思う。集談会のような場に参加して、自分の抱えている苦しみを人に向かって話すということである。話すということは、ダムに溜まり過ぎた水を放水するようなものである。放水しないで貯めてばかりいると、いつかは溢れ出す。また、ダムの強度がその水圧に耐えられないと、決壊して大災害を引き起こす。災害を起こさないためには、小出しに自分の悩みなどを誰かに話すという作業が必要なのである。そう言う意味では、守秘義務が徹底されている集談会は大変貴重な場である。普段はなかなか愚痴などを思う存分口に出す事は出来ない。しかし集談会では、自分をさらけ出してもほとんどの場合は相手がよく聞いてくれる。集談会は傾聴、受容と共感が建前になっているので安心して自分の葛藤や悩みを話すことができる。私が参加していた集談会では、以前集談会の最後には、ギターの上手な人の伴奏に合わせて、「仲間たち」というフォークソングを歌っていた。「君の行く道は、果てしなく遠い・・・」と言う歌である。最後に合唱で締めると和やかな雰囲気になる。 。この歌を歌うと、われわれは共に神経質で悩む同士なのだなという気持ちが湧いてきた。また、毎年1回、カラオケを使って新年会や忘年会があった。その時は、音痴である私も1曲の歌を決めて1ヶ月ぐらい前から練習をしていた。練習で歌った歌を録音してそれを聞いてみた。これも大事なことだった。とにかく最初から上手に歌おうという気持ちはない。みんなと一緒に楽しめればいいと思っていた。それだからこそ、 神経質性格を活かして、周到な準備ができるのだと思う。最悪なのは、カラオケに行って本を開いて、どの歌が歌えるだろうかと探すことである。私などのような音痴な人はその時点で負けであると思う。カラオケは苦痛以外の何物でもなくなり、人生の楽しみを一つ失うことになる。最近、あることに気がついた。嬉しい発見だった。歌手が歌っている歌声を何回も繰り返して聴いていると、歌うスピードがわかる。さらに、盛り上げるところと、おとなしめに歌うところがわかる。またのばすところと、短く切るところもわかる。それを紙に詳細に書いていった。それを見ながら真似をして歌ってみると、なんとか形になることがわかった。だいたい5人ぐらいでカラオケに行くと、よく歌っても一人3曲ぐらいである。だから、普段から何曲も用意する必要はない。これだと思う曲を2曲から3曲用意して繰り返して練習すればいいのである。あとはカラオケでは上手な人の歌声を聴いていればよい。とにかく、カラオケでは思い切って楽しむことに徹することである。そのためには後ろ盾となる何とか歌える曲を、2曲か3曲は日ごろから用意して持つことである。
2017.12.05
コメント(0)
-
森田療法学会参加のおすすめ
私は第35回森田療法学会に生活の発見会の会員として参加することができた。11月11日、12日熊本大学で行われた。森田理論学習を続けている人が、日本森田療法学会に参加することの意義について考えてみたい。•この学会には当然のことながら、森田療法を牽引している著名な学者、医師、臨床心理士、生活の発見会の会員などが多数参加している。そういう人たちの研究成果の発表の場なのである。私たちの生活の発見会は、自助グループとして参加している。自助グループが積極的に毎回発表者を送り込み、参加が許されている学会はあまりないだろう。それは神経症の治療成果を上げているので、学会がその存在を認知しているからである。ともあれ日本を代表して森田療法に関わっている人たちなので、その人たちのお話を聞くことは大変意義がある。また日ごろ森田理論の疑問点などがあれば、専門家に気軽に質問することができる。•最先端の森田療法の治療例を間近に聞くことができる。また医師や臨床心理士がどのような手法や気持ちで神経症治療に当たっているのかよくわかる。一応外来森田療法の指針があるが、その手法はそれぞれの専門家の思いが反映されている。森田療法自体は基本的には薬物を使わない、いわば儲からない心理療法なので森田療法に携わっておられる専門家には頭が下がる。•今回の学会は熊本で行われた。今年の大会テーマは、 「森田療法と五高」だった。第五高等学校が森田先生の母校と言うこともあり、高校時代の森田先生の下宿先、エピソードなどが余すところなく紹介された。人間森田正馬を深めることができた。普段の森田理論学習ではほとんど聞くことができない貴重な内容となった。•学会前には、詳しい演題内容を記載した冊子が渡される。これをあらかじめ、よく見て自分の関心のある演題に印を付けておく。そうしないと同時進行的に最大4カ所の会場で学術発表が行われているので、どの演題を聴講しようかと迷うことになる。 4カ所の会場で行われているので、自分の関心のあるテーマの会場に足を運べばよいのである。•今回、私は一般演題として発表する時間をいただいた。ただし、時間は10分間である。このブログで紹介している「森田理論全体像」のさわりの部分だけを発表した。物足りないものであったが、発表者が多いので仕方がない。その後質疑応答があった。その中で印象に残っているのは、「思想の矛盾は放っておけばよいのでは」という意見だった。臨床現場では、神経症で日常生活などか滞っている人や葛藤や悩みの深刻な人を対象として治療している。神経質者がどのような生き方を目指してゆけばよいのかという面(北西先生が言われる生き方モデル)については、積極的には意識が向かないのだと感じた。逆に言えば、神経質性格者の「生き方モデル」に焦点を当てて取り組んでいるのは、自助組織の生活の発見会が一番だなと感じた。それだけ自助グループ生活の発見会の存在は、社会教育の面から見ても貴重な存在なのである。学校教育面でも、今や人類の存続のためには「森田人間学」という分野を取り入れる時期に入っている。•ともあれ、この学会は生活の発見会の会員も参加を許されている。そのために我々の学習仲間も多数参加されている。来年は9月初旬に東京で開催される。私は東京は無理だが、今後あまり遠くない所で開催される森田療法学会には参加してみたいと思った。生活の発見誌に案内が載るので、皆さんも1度は参加されることを強くお勧めしたい。
2017.12.04
コメント(0)
-

アメリカCNNが選んだ日本の最も美しい場所31選
この中で私の訪れたことのある場所は次のところです。・足立美術館(島根県) 確かに見ごたえあり。できれば隣にある「安来節演芸館」にも行くとよい。・金閣寺(京都) 紅葉の季節がよい。できれば嵐山の紅葉の盛りに行くとよい。・嵯峨野(京都) きれいだが人が多すぎる。・那智の滝(和歌山県) さらに串本の海金剛は絶対に見ておくべきだ。・屈斜路湖(北海道) 摩周湖のほうが神秘的だ。・洞爺湖 登別温泉とクマ牧場もおすすめ。・姫路城(兵庫) 改修工事が終わった。近くの庭園も見ごたえあり。・白馬村(長野県) 冬の季節がよい。スキーや温泉を兼ねて。・仁井の棚田(広島県安芸太田町) 田植えが済んだ後がよい。人間の英知を感じる。・小樽雪あかりの路(北海道小樽市)・鳥取砂丘(鳥取県)・ラベンダー畑(北海道富良野)・厳島神社(広島県廿日市市) ロープウェイで弥山(みせん)山頂からの瀬戸内海の眺めが最高。・宇佐神社(大分県)・別府ロープウェイ(大分県) 温泉、地獄池巡り、高崎山のサル、水族館などが見どころ。・大山(鳥取県) 境港方面からの眺めが雄大でよい。・元乃隅稲成神社(山口) 稲荷ではなく稲成と書く。断崖にある神社。赤い鳥居が123基ある。31か所中17か所は訪れていた。まだ訪れてはいないが、ぜひ行ってみたいところ・河内藤園(福岡県) 藤の木のトンネルが見ごたえあり。どうして選ばれていないのか納得がいかないところ・和歌山県串本の海金剛 思わず後ずさりするような場所です。自然の驚異と力強さを感じます。・長崎の九十九島 海に浮かぶ小島の絶景に見とれてしまいます。・青森の奥入瀬から十和田湖周辺 魂が癒される場所です。・山口県岩国の錦帯橋と近くの公園 桜や菖蒲の時期が最高です。・奥日光の白樺林と小川のせせらぎ・鹿児島県最南端の島、与論島 昔はサンゴ礁がとてもきれいでした。次の写真は、果物と花街道で売り出している広島県世羅大地のチューリップ畑です。
2017.12.03
コメント(0)
-
感情の法則3について考える
今日は感情の法則の3について考えてみたい。「感情は同一の感覚に慣れるに従って、にぶくなり不感となるものである」私たちは生活の中で様々なことを感じています。・部屋の中がホコリだらけになっている。・車のボディーが水垢で汚れている。・そろそろチューリップの球根を植える時期だ。・そろそろ年賀状を予約しなければ。・パソコンの不具合を直さなければ。・最近お腹の調子がよくない。などなど、毎日いろんな気づきが次から次へと浮かんでくる。これらの気づきの発生は森田理論の立場から言うと、お金と同じようなものだ。あるいは宝の山であるとも言える。大切に扱わないといけない。神経質者の場合は特にそうだ。しかし神経質者の場合でも、これらを丁寧に扱う人と、いい加減に扱う人に分かれる。丁寧に扱う人は気づき、興味、関心、アイディアなどを忘れてしまわないようにすぐにメモする。そういうストックをたくさん持っている。いい加減に扱う人はメモなどはしない。そのうち気づきやアイディアなどは忘却の彼方へと忘れ去ってしまうのである。そして暇を持て余すようになる。退屈で毎日がつまらないなどと思うようになったら、要注意である。また最初に感じた気づきやアイディアを軽く取り扱っていると、次第に鈍くなり不感となるのである。例えば部屋の中が乱雑でホコリだらけだと思っていても、その中で生活していると感覚が麻痺してしまう。不潔極まる状況であっても、一向に気にならなくなるのである。他人が自分の部屋を訪れたとき、 「うわー、ゴミ屋敷の1歩手前だ」と思うような感覚が、もはやその人には湧き起こらなくなっているのです。これは鍋の中に飛び込んだカエルが、次第に体が暖まってきて温泉気分でいるうちに、その熱さに麻痺して、最後に茹で上がって命を落としてしまうようなものです。このように、最初に沸き起こってきた感情をいい加減に扱っていると、次第に豊かな感情が起こらなくなってくる。頭脳でも足の筋肉でも、普段から使っていないと廃用性萎縮を起こしてくる。その結果、認知症になったり寝たきりになったりすることもある。豊かな感情もいい加減な扱いをしていると、感情自体がどんどん廃用性萎縮を起こしてくるのである。廃用性萎縮を起こすと、気づきや発見、興味や関心などが少なくなってきます。豊かな感情がなくなり、人間らしさが失われてくるのです。これは森田理論の立場から見ると、とても由々しき問題です。人間は気づきや発見を通して、意欲ややる気が高まるようになっているのです。そういうエネルギー源がなくなれば、意欲ややる気はもはや湧き起こりようがないのです。好奇心や意欲のない人間は、生きる屍のようなものです。人間は「努力即幸福」と言って、自分の気づきや発見をもとにして、対象に働きかけていく永遠の過程こそが幸福の源となっているのです。でも人間には新しいことに取り組む時に、面倒だ、しんどそうだ、どうもやる気が出てこないなどと思いがちです。そういう安易な気分本位の生活に甘んじていると、人生の楽しみを自ら放棄しているようなものです。改めて言いますと、最初に沸き起こってきた気づきの感情は宝の山です。まずこれをしっかりとキャッチする必要があります。別に難しいことではありません。忘れないようにメモしておけばいいのです。メモ帳や手帳、スマホのメモ帳、カレンダー機能を活用すればよいのです。そしてやりやすい事、納期の急ぐことから手をつけていけばいいのです。行動していけば、また新たな気づきや発見があります。精神が次から次へと活性化してきます。最初の気づきを宝の山として捉え、その気づきを風化させないという姿勢がとても大事になってきます。
2017.12.03
コメント(0)
-

山口下関から美しい風景をお届けします
海に浮かぶ角島大橋とアメリカCNNが「日本の最も美しい場所31選」に選んだ元乃隅稲成神社です。
2017.12.02
コメント(0)
-
土曜日、日曜日の過ごし方について
土曜日や日曜日は休日という方も多いと思いますが、生活面では注意が必要です。会社や学校でため込んだストレスを休日に一気に解消しようとするのです。パジャマのまま過ごす。昼近くまで寝ている。外出もしないでパソコンゲームに没頭する。テレビを見続けたり、音楽を聴きながらスナック菓子を食べる。規則正しい生活が土曜、日曜でいとも簡単に崩れてしまうのです。精神的には、金曜日まで緊張していた状態から、急に弛緩状態に変わります。糸の切れた風船のような状態になります。森田先生はそんな生活をしていると、風邪をひきやすくなるといわれています。寒い冬の日に外出すると寒さのために心身共に緊張しています。家に帰るとほっとして緊張感から解放されて、こたつに潜り込んでうたた寝のようなことをするとよくない。これで一挙に心身共に弛緩状態になる。その精神状態に体のほうがついてゆけない。体調の変化を起こし風邪をひきやすくなるのである。精神は緊張から弛緩状態に移行させるときは、ソフトランディングを心がける必要があるのである。土日もあまりにも弛緩状態に浸りまくるのは、心身の活動にとって問題があるのである。また月曜日から金曜日までは、会社に出社していたので、曲がりなりにも生活のリズムがありました。そのリズムがこの土曜日、日曜日で一挙に崩れてしまうのです。リズムというのは海の波と一緒です。波は持ち上れば、必ず谷底に沈んでゆきます。それを絶えず繰り返しています。それでバランスがとれているのです。土日にそのリズムを破壊してしまうと後が大変です。また、月曜日になって一から生活のリズムづくりをすることになります。これが大変な作業となります。土日は普段の生活のように大きなリズムを作る必要はないかもしれませんが、ある程度のリズム感のある生活を心がけることが大切です。土日といえども基本的な生活スタイルは崩さないようにしたいものです。集談会で「くつがそろえば心がそろう」ということを聞きました。形を重視することが大切です。定時には起床する。歯磨きをする。洗面を済ませる。着替えをする。朝食をとる。新聞をよむ。等いつも毎朝やっていることは、いつもどおりすませる。これはウォーミングアップのようなものです。ウォーミングアップが済めばいよいよ活動開始という態勢になります。その際役に立つのは、普段から土曜、日曜日になすべきことのストックをたくさん持っておくことです。当日になって、さあ何をやろうかと考えるようでは遅すぎます。そのために気のついたことは常にメモする習慣をつけておきたいものです。私は100均で買った小さなメモ用紙にストラップつきの小さなボールペンをつけてメモしています。また携帯のメモ機能やカレンダー機能を大いに活用しています。書いたらときどき取り出して眺めるといいでしょう。準備が済んでいると、体が動きやすくなります。すぐに処理できることからどんどん片付けてゆきましょう。いろんなことが片付くとうれしくなってきます。その途中で小さな気づきや発見もあります。新たな関心や興味も湧いてきます。たまには普段できないことに挑戦するのもいいでしょう。美味しいものを食べに行くのもいいでしょう。映画を見に行くのもいいでしょう。釣りに行く。コンサートに行く。図書館や本屋さんに行ってみる。あるいは卓球やバトミントンなどのスポーツに挑戦してみる。一日が終わり、日記を書くころには思い出せないほどのたくさんのことに手を出していたことに気が付きます。一日何もしないでゴロゴロと寝っ転がっていると後悔の念が湧いてきます。自己嫌悪に陥ってしまいます。土日は普段の気にかかっていること、やりたいことを片付ける絶好の機会であると認識することが大切です。
2017.12.02
コメント(0)
-
☆「人生のフォアボール」をねらう
元ヤクルトの古田敦也さんは、人生でスランプに陥った時は「人生のフォアボール」を狙えといわれます。古田さんは野球でスランプに陥った時は、ヒットを打つなどということは考えないようにしてバッターボックスに入るそうです。それは不調のときボール球に手を出してしまう。また不思議なもので、調子の悪い時に限って打ちたくなるからです。だから「ボール球は絶対に振らない」「きわどい球は全部ファールでよい」「結果がでないときは打席に入ってもフォアボールしか狙いません」といいます。普通の野球選手は全打席ヒットを打ちたいのではないでしょうか。全打席そのように向かっていくのかと思っていました。古田さんは不調のときの自分をよく自覚しておられたのではないかと思います。自覚できれば自分の努力目標が決まります。それがフォアボールねらいだったのです。自分の現状に合わせた対策をとられていたのです。もし自覚できなかったら、自分を叱咤激励して、追い込んでいったのではないでしょうか。その結果ますますスランプに落ち込んで悪循環のスパイラルにはまってしまうのではないでしょうか。神経症で苦しいときは、何とかその苦しみから逃れてすっきりしたい。楽になりたいと思います。でも森田理論を少しでもかじった人は、はからいを始めれば、神経症は治るどころか益々増悪していくことは頭では理解できています。でもどうしてもとらわれから抜け出ることができないというジレンマで苦しんでいます。頭では理解できても、体がついてこない状態です。そんな時は、苦しくてやりきれないなと思いながら、何とか最低限の生活だけを維持していくという気持ちでよいのではないでしょうか。それが、古田さんの言われる「人生のフォアボール」を狙うということだと思います。森田理論学習で、症状で苦しいときは「超低空飛行」ということを学びました。墜落しない程度でよいので、何とか生活を維持することがとても大事だということです。そうしていればいつのまにか変化が起きるのだと思います。人生は波のようなものです。一般的には沈みっぱなしということは考えにくいと思います。また反対に、今やることなすことがうまくいっていても、必ず下り坂はやってきます。落ち込んでいるときは、変な悪あがきはやめて、台風が来た時のように活動をできる限り抑えて通り過ぎるのを待つという戦略も考えておきたいものです。台風一過必ず青空が戻ってくることを信じて。
2017.12.01
コメント(0)
全34件 (34件中 1-34件目)
1