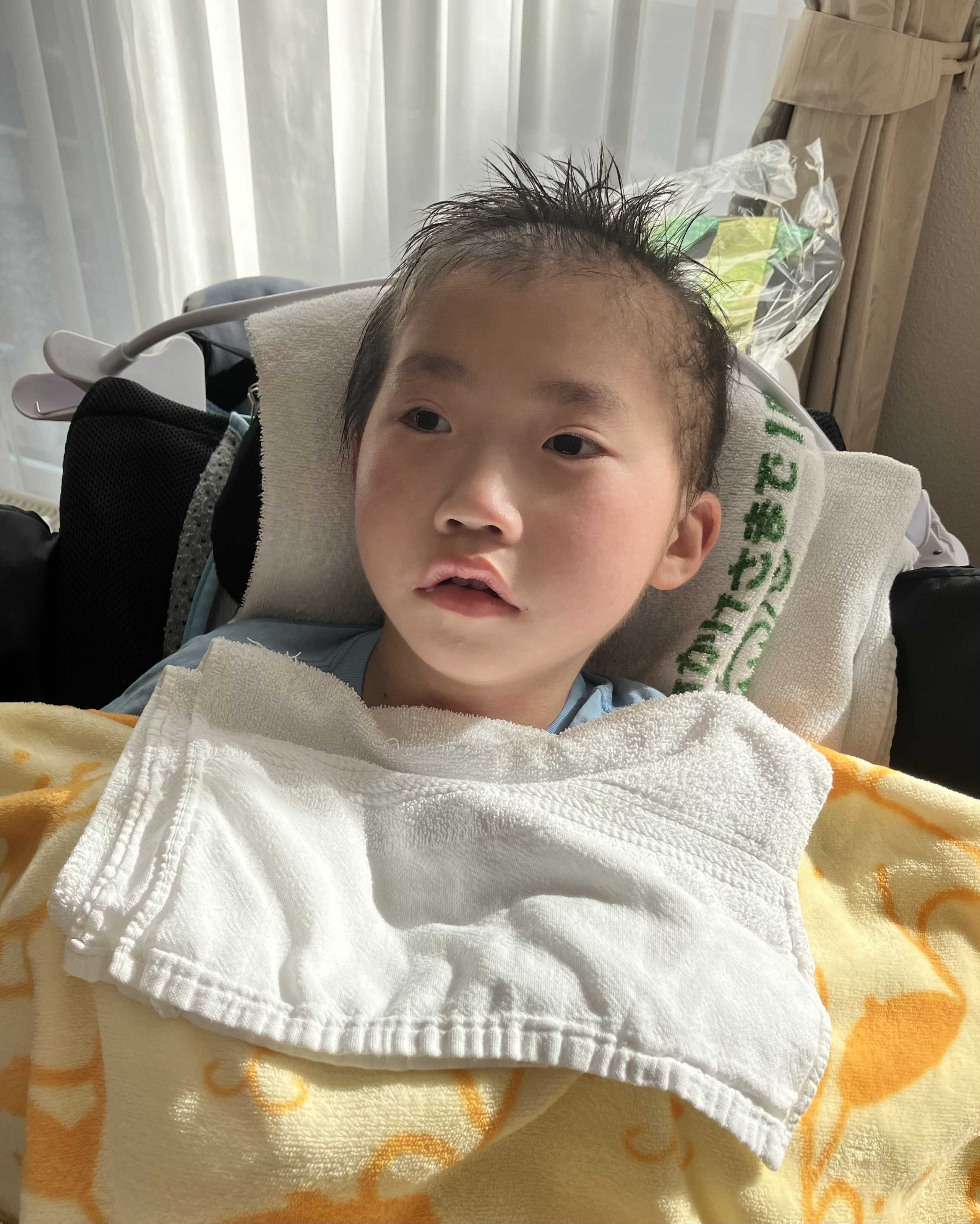2017年08月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
心機一転について
森田先生の言葉です。心機一転の普通の場合は、心の内向的が外向的に一転することかと思う。例えば自分が、いままで、足元ばかりを見、自分の勇気の有無ばかりを考えて、どうしても渡ることのできなかった丸木橋を、思いっきり捨て身になった拍子に、前の方ばかりを見つめて、すらすらと渡り得たときのようなものである。(森田全集第5巻 229ページより引用)これは私も経験がある。小さい時に川をせき止めたところに丸木橋があった。私は川に落ちるのが恐ろしくて、どうしても渡ることができなかった。友達は難なく渡ることができていた。一回渡ることができた人は、何度も行ったり来たりできるようになった。最初は友達は恐ろしくないのだろうかと思った。実際には、友達も恐ろしいと言っていた。それでも友達は落ちるかもしれないというスリルがあるのが面白いのだとも言っていた。またできるようになったことで、ますます自信がついたようだ。いったん渡り始めると、途中もたもたしないで、両手を広げてバランスをとりながらスタスタと歩いて行った。それをまねているうちに私もなんとか渡ることができるようになった。その時の心境を思い出してみると、落ちたらどうしようという恐怖心はあるが、むしろ恐怖心によって適度な緊張感が生まれていたようだ。緊張感があると真剣になる。それ以上に大事な事は、渡りきりたいという目標を強く持っていたことだ。失敗したらどうしようなどという気持ちよりも、友達ができるのだから自分もできるようになりたいという強い目標を持てた。自分の心が内向きになることが全くなく、渡りきるという目標に向かって外向きになっていたということだと思う。欲望が強くなっていった。神経症で苦しんでいる人は、気持ちの方向が自分の身体や心に内向化している。森田先生は心の内向化が神経症を発症の原因となっている。神経症が治るにあたっては、普段の生活において、内向化しやすい性格傾向を、外向的な方向に転換していく必要がある。その精神的なからくりを、ある経験を体験することによってたちどころにのうちに会得するのが心機一転と言われているのだと思う。心機一転の話は、薪割りの話、ボール投げの話でも同じことだ。薪割りでは、精神状態が薪を割っている自分の仕草やその姿を見ている周囲の人の思惑を気にしていると、なかなか正確に薪に当たらない。それらをすっかり横に置いて、薪の一点に神経を集中させた方がうまくいく。ある入院先の人が、そのことに気づき、急いで部屋に戻って、その時の心境を日記に書きとめたという。その人は、自分が長く神経症で悩んできたのは、心の使い方が間違っていたことに気が付いたのである。このように心機一転によって神経症克服のヒントが得られたという事は、大変羨ましい限りである。キャッチボールをする場合でも、心の使い手としては相手のグローブや体に向かって集中していないといけない。投げる時の動作やうまく投げられるだろうかという不安な心に向かって言っては、決してコントロールよく投げることはできなくなってしまう。私はキャッチボールからヒントを得て、心の使い方としては、内向的な方面ばかりではなく、それ以上に外向的な方面に移動していかないとうまくはいかないと気がついた。神経症の克服にはそれを応用すればよいのだと気付いたとすると、これも立派な心機一転となる。対人恐怖症や強迫神経症の場合は、心機一転というのはなかなか難しいように思う。私のような場合は、玉ねぎの薄皮をはぐように時間をかけて少しずつ改善して行く方法が性に合っていると思う。1年経って何か少しでも変わっている。少しずつ症状に振り回されるといった生活が改善できている。そういう経験を積み重ねることで、少しずつではあるが着実に神経症からの回復に向かって動き出していくのだと思う。神経症を長くかけて克服した人は再発とは無縁である。
2017.08.31
コメント(0)
-
「お使い根性」の仕事について
森田先生は修養のためにする仕事はデタラメになると言われている。たとえば障子の埃をはたきで叩く例で説明されている。入院生が埃があるなしにかかわらず、パタパタとはたく。その音は単調で一本調子であるから、隣の部屋で聞いていて、すぐにそれが、掃除の気持ちになっていないということがわかる。このような人は、またいつでも、障子を閉めきっておいてはたきをかける。「その埃は何処へ行くか」ということには気がつかない。すなわち、その埃は、そのほとんどは撒き散らされて床の置物や器具の上に置き換えられる。その結果、障子の桟の上に、埃を置いたよりもかえって始末が悪いということがわからないのである。汚いから清潔にする、埃がいやらしいからはたきだすというふうではなく、人から指示されたから仕方なしにするということでは、かえってその後始末をすることが大変なことになる場合がある。 (森田全集第5巻 583ページより要旨引用)これは森田先生がよく言われている、お使い根性の仕事ぶりの例だと思う。しかし考えてみると、他人から指示や命令されて手をつけることはどうしてもやる気や意欲が湧いてこない。いやいや、仕方なしにやらされているという気持ちがあるので身が入らないのである。自分が今からやろうと思っている事でも、親から指摘されると、急にやる気をなくして反発することもある。例えば、冬にこたつでうたた寝をしている時、母親に 「早く風呂に入りなさい」などと急かされると、そろそろ風呂に入ろうかと思っていたにもかかわらず、その言葉に反発してすねてしまい、実行しないということもある。その半面、自分が自らやろうと決めた事は、他人から見ると、とてもきつそうに見えるような事でも本人にとっては、面白くて仕方がないのである。例えば世界の最高峰の山々に登山をする人、あるいは太平洋をヨットで単独航行を試みる人などである。私達も夏の炎天下の下、魚釣りをしたり、トライアスロンを楽しんだりしている人を見ると、あんなに苦しそうなことをよくできるものだと思ってしまう。ところがやっている本人たちは、苦しみながらも、それ以上の充実感を味わうことができると思っているのである。森田先生のいわれるお使い根性と無謀とも思えるような挑戦はどこが違うのであろうか。趣味や目標に向かって挑戦するというのは、例えばテレビなどで他人がやっているのを見て、自分も挑戦してみたいという感情がわき起こってきたのだ。そして実際に思い切って自分でも挑戦でしてみることになる。やる気や意欲がみなぎっている状態である。ときには失敗することもあるが、自分でも出来るようになると喜びの感情が湧いてくる。さらに、自分でもやればできるという自信になる。次第に弾みがついて、どんどん高みを目指していく。行動は生産的、積極的、創造的に発展していく。ところが森田先生の言われるお使い根性と言うのは、そのような感情がない状態で、他人からの指示や命令によって行動すること求められているのである。自分でやってみたいという感情が湧き起こらないで、いきなり行動を求められるという事はとても苦痛なことだということだ。森田ではそのものをよく見つめなさいという。つまり、観察していると、何らかの感情がわき起こってくる。観察しているうちに、気づきや発見が出てくるとしめたものだ。人間はその感情に基づいて、意欲ややる気が高まってくるように出来ているのである。いやいや、仕方なしにやり始めた仕事であっても、今1歩踏み込んで行動していると、新たな感情がわき起こってくる可能性が高くなる。だから森田理論では、目の前の仕事や家事などはお使い根性ではなく、 「ものそのものになりきる」ということをお勧めしているのである。
2017.08.30
コメント(0)
-
☆「とらわれ」から離れる2つの方法
森田先生は、 「神経症から解放されるための最も大事な条件は、とらわれから離れることである」と言われている。そのためにはどうすればよいのか。 1つには、常に目的物から目を離さないことである。もう一つは、自分の心がとらわれから離れられないときには、そのままにとらわれていることも、同時にとらわれから離れるところの1つの方法である。 (森田全集第5巻 244 ページ)この言葉は、もう少し説明しないとわかりにくい部分だと思う。まず、とらわれたときは、その不快感や恐怖などに対して、やりくりをしたり、逃げ出してはならない。不快感や恐怖をそのまま味わいつくすという態度になればよいのだ。苦しければ苦しいままに、恥ずかしければ恥ずかしいままに、イライラすればイライラするままに、沸き起こってきた感情をそのまま素直に感じていればよい。単純で簡単なことのように思えるが、これを実践すること大変に難しい。一般的には不十分な人が多い。仮に実践することができれば、神経症のアリ地獄の底に陥ることはない。普通の人は、不安や恐怖、不快感や違和感などに対して、その感情を十分に味わう前に、すぐにその感情と対決して取り除こうとしている。あるいは、目をそむけてその場からすぐに逃げようと考える。そうすれば、我々にもともと備わっていた自己内省力がマイナスに働いてくる。注意や意識が身体の震えなどのちょっとした心身の変化に向けられくる。また、自分の性格やふがいなさに向けられていく。森田理論では、注意や意識をとらわれに向けると、注意と感覚の相互作用が始まる。 一旦始まった相互作用は、坂道を転げ落ちる雪だるまのように加速がついてどんどん増悪していく。だから一旦始まった。不快感や恐怖などに対しては、とことんまで味わい尽くしてやろうという姿勢をとることが大変重要なのである。最悪なパターンは、十分に味わう過程を無視して、すぐに対策を立ててしまうことである。これが森田先生が言われている、 「とらわれたときはそのままにとらわれていること」という意味だと思う。しかし、とらわれた時にとらわれたままにしておくだけでは、神経症からの解放という意味では不十分である。一方で森田先生は、とらわれたときは決して目的物を見失ってはならないと言われている。これは、目の前にある仕事や家事や育児を簡単に放棄してはならないという事である。あるいは、問題点や課題、夢や目標を見失ってはならないという事である。森田理論ではこれらのことを幅広く、生の欲望の発揮といっている。私たちは、不安、恐怖、不快感、違和感などに襲われると、そちらのほうにばかり注意を集中させて、目的物はすぐに蚊帳の外になってしまう。しまいにはすっかり忘れてしまって、自分の気になる症状の解決に向かって全エネルギーを集中させてしまう。つまり不安と欲望のバランスが崩れ去っているのだ。症状に陥った時は、森田先生の言われていることとは反対のことばかり行っている。とらわれた時に、そのとらわれをなくそうとしたり逃げたりしている。そして目の前の仕事や日常茶飯事は無視している。こんなに苦しいのだから、他人は私に同情して、大目に見てくれるべきだと思っている。東京から新幹線に乗って大阪へ向かうはずのところを、列車を間違えて、仙台方面に向かっているようなものだ。いつまでたっても神経症から解放されるときはやってこないだろう。神経症から解放されるということは、このように口で言ってしまえば簡単なことだ。しかし実行は難しいことを肝に銘じて、森田理論の学習と実行で、ぜひ自分のものにしてもらいたいものである。
2017.08.29
コメント(2)
-
雷恐怖症の人の話から
私は具体的な話やエピソードの中から、森田理論を膨らませていくことが楽しみである。今月号の生活の発見誌に、ある雷恐怖の男の話があった。大変興味深く読ませていただいた。この人は雷に異常なほどの恐怖心を持っており、山で木を切っているときに雷が鳴れば大変驚愕して、仕事道具のおのやのこぎりを放り出して家まで逃げかえるほどであった。家にいる時に雷が鳴ると怯えて押し入れの中に入り、小さく縮こまって雷が治まるまで押し入れから出られないような有様で、妻もそういう夫を見てあきれるばかりであった。この男性は、自分でもこのような状態を非常に情けなく思って、何とかしてこの雷恐怖を治そうとして村の禅寺に行って座禅を組んだり、それに関する本を探し回った。そんな中で森田療法と巡り会うことができた。しかし、本を読んだだけでは、雷が恐ろしいという恐怖感は相変わらずで、改善の方法が見つからなかった。その後は森田先生の手紙相談を受けていた。しかしその後、この方に転機が訪れた。あることをきっかけにして雷恐怖を乗り越えたのである。8月末の夜のことである。夜半には強烈な稲妻の閃光とゴロゴロと天地を揺るがすような大きな音とともに激しい雨が降り出した。そして時折どこかに落雷したようなドカーンという凄まじい音が聞こえてくる。この男性は全く生きた心地がしなくなり、いっそう身を縮めて「くわばら、くわばら」と念仏を唱えるようにつぶやき、脂汗を垂らしながらひたすら雷が過ぎ去るのを待っていた。そういう状況で布団をかぶりながらも、ふと気がつくと、妻が「うーん、うーん」という苦しそうな声を上げている。何だか様子がおかしい。慌てて「どうしたんだ」と声をかけても返事はなく、苦しそうに喚いているだけである。額を手で触るとものすごく熱く、高熱が出ているようである。 「これは放っておけない、一刻も早く医者に見せなければ」と瞬間的に思った。森田でいう初一念である。この男性は、雷恐怖なので外に出ることができない。頭が真っ白になった。その時森田先生の「必要ならどんなに雷が恐ろしくてもやらなければならない」という手紙相談の言葉を思い出した。ここで医者を呼びに行かないで、妻に万が一のことがあれば、一生後悔することになるし、何よりも大事な妻を失うことになりかねない。この男性は雷が鳴る真っ暗などしゃ降りの雨の中を、カッパを着て、懐中電灯だけを持って飛び出した。往診した医者は、 「もう少し遅かったら危なかった」と言い残して帰っていった。すんでの所で妻の命が助かったのである。この体験を森田先生に伝えた。森田先生から次のような返事が来た。「貴重な体験をした。何よりも奥さんが助かってよかった。あなたは座禅をしているようだが、このような場合、禅では次に同じようなことが起こったときには恐ろしくないよ、と教えるが、自分の療法では次に同じことが起きたらやっぱり恐ろしいよ、と教える、その違いを考えてみるように」ということであった。この男性は世間で一般的に言われている禅は心の安らぎを求めることもありそうだが、森田は心の安らぎなどは微塵も求めず、必要なことに焦点を合わせて実行していくことの大切さを説いているのだと思った。(生活の発見誌8月号、 16頁より引用、生活の発見誌は会員になると送られてきます)この文章を読んで、私が感じたこと書いてみたい。この男性は、書籍によって森田理論を学習し、森田先生の通信療法を受けていた。それでも、自分の雷恐怖症は治すことができなかった。それがだだ一度の心機一転の体験によって雷恐怖症を治すことができた。切羽詰まった状況に追い込まれ、背水の陣で事に臨んだのである。この体験がよかったのだ。不安神経症等の場合は、こういう話をよく聞く。乗り物恐怖の人が、止むに已まれぬ事情により、思い切って飛行機に乗ってみた。その体験が心機一転になり、乗り物恐怖症を乗り越えるきっかけとなったと言うような話である。森田理論でも、数は多くはないが、この心機一転の体験により症状を乗り越えたという人は存在する。私の身近なところでは、胃腸神経症を乗り越えられたメンタルヘルス岡本記念財団の元理事長の岡本常男氏などはまさしくそうであった。心機一転は野球で言えば逆転サヨナラホームランのようなものである。私は対人恐怖症なのでこういう経験はない。私の場合はそういうタイプの治り方ではうまくいかないと思う。野球で言えば、きちんとバントをする。フォアボールを選ぶ。大きいのを狙わずに小さなヒットを積み重ねるようなタイプだと思う。その積み重ねが、イチロー選手のような偉大な記録を作り上げるのだと思う。私のようなタイプの人は、正統派の森田理論学習を続けて、生活面では森田の基本を忠実に守り、ある程度の時間をかけて、神経症克服し、人生観を確立していくものだと思っている。拙速に結果を求めてはかえって失敗する。年の初めに、過去を振り返って眺めたときに、その変身ぶりに感慨深さを覚えるというようなタイプではないかと思う。神経症の治り方には、心機一転もあれば、玉ねぎの薄皮をはがすように徐々に治っていく道もあるのである。
2017.08.28
コメント(0)
-
☆人間関係にも「車間距離」をもて!
精神科医の阿部亨先生は、人間関係には「車間距離」が必要だと言われている。車の運転をしている時、前の車にぴったりと引っ付いていると、とっさの時に間に合わなくて、追突事故を起こしやすい。また高速道路などでは、車間距離を取らないと、精神的に大きな緊張状態を強いられる。一旦事故が起きると、大惨事になりやすい。このことを人間関係にも応用する必要がある、と言われている。つまり、 2人の人間がぴったりと寄り添い、一心同体というような状態になるととても危なっかしい。普通人間は、おしどり夫婦とか、無二の親友とかいう一心同体の人間関係に多くの人が憧れている。しかし、これは頭で考えた理想の人間関係であり、現実的ではない。常にお互いの主義主張が正面からぶつかり合い、対立関係に陥ることが日常茶飯事である。真剣にそのことに向き合って、調整したり、妥協したりしながら、お互いwin winの関係をつくりあげるように努力することが、好むと好まざるとにかかわらず我々人間に突き付けられている。雨降って地固まるという話があるが、人間関係もそういう方向で日々努力したいものである。一心同体と言われるような人間関係を見ていると、どちらかが主導権を握り、他の人がその人に追随している。つまり、親分と子分のような人間関係、あるいは共依存のような人間関係を第三者から見て、一心同体で羨ましい人間関係を築いているように見えるだけのことである。こういう主従関係はいずれ行き詰まる。 引っ付きすぎず、離れ過ぎない人間関係のことを森田理論では「不即不離」と言っている。その場の状況に応じて、ある時は親密になって一緒に行動したり、食事をしたりするが、次の瞬間には、一旦離れて、それぞれが自分の好きなことをやっている。必要に応じて密着したり離れたりしているのである。いったん離れていても、いつも見守ったり、気にしてくれており、何かあるとすぐに駆けつけて助けてくれるような人間関係である。これは相手を束縛しない自由で臨機応変な人間関係であり、自然で疲れることはない。次に阿部先生は、もう一つ人間関係で大事な事は、「秘密の部分」を持てということだった。これはどういう事かと言うと、思いついた事、考えたことなどをすべて口に出して話してはいけないということだ。自分の口にする言葉が相手にどんな悪い感情をもたらすかを考えないで、頭に浮かんだことをそのまま口に出す人がいる。そういう人に限って自分を正直者であると思っている。また、「人間は正直でなければならない」などという強い「かくあるべし」を持っている。例えば、 「あなたは顔色が悪いですね。肝臓ガンにでもかかっているのではないですか」などと言えば、相手はすぐに傷つく。阿部先生が「秘密の部分」と言われるのは、他人に配慮した話をしなさいということだと思う。まともに成長した大人は、自然に他人に配慮した言動を心がけている。これは精神拮抗作用といって、普通の人間にはある考えが沸き起こると、それを打ち消す考え方も同時に沸き起こるようになっている。そのバランスをとりながら他人と接していくことが大切だということだ。神経質者の場合、問題になるのは、自己主張の部分とと他人への配慮へのバランスが崩れていることである。神経質者の場合は、他人への配慮はしないで、四六時中自分への配慮ばかりしている。自分の容姿や性格、言動などが、他人にどのように受け止められているのか、注意や意識をそこに集中しているのである。これはバランス以前の問題である。つまり注意や意識が自己主張や他人への配慮のどちらにも向かっていない。本来、注意や意識の向かう先は、 1つには自分の考え方や意思、希望などを相手に伝える努力をする方向にある。次に、それに対して相手の反応が返ってくる。双方に隔たりがあればそれを埋め合わせる努力をする方向である。本来はその2つの目的を達成するために、自分の持てるエネルギーを投入すべきである。自分を守るためにだけ、自分の持てる大半のエネルギーを投入しているとすれば、心身の消耗を招き、多くは無駄な結果となるだけである。 (森田療法ビデオ全集 第4巻 悩める人への生きるヒント 阿部亨 参照)
2017.08.27
コメント(0)
-
良好な人間関係を築くコツ
私は老人ホームの慰問活動や祭りなどのイベント活動を行っている。私の披露する演目は、楽器演奏、獅子舞、どじょうすくい、浪曲奇術などである。慰問依頼の受付と日程調整、出し物の構成や出演者交渉を一手に担っておられる人がいる。その方は、 80代のおばあさんである。自分では三味線教室の師匠をされている。1回見ただけでは60代ぐらいにしか見えない。多分この方は痴呆症になることもなく、 100歳以上まで長生きをされるだろうと思う。とても好奇心が旺盛で、しかも人と交流することがとても好きな人だ。特に若い人と話をすることが大好きなようだ。リズム感がよく、カラオケが好きで、踊りも上手だ。私はその人と話をしていると、いつも人間関係のあり方について考えさせられる。その人の他人との交流を見ていると、とにかく相手の優れたところに常に注意を向けて観察している。見つけ出すとすぐに口に出して褒めている。「すごいね、えらいね」が口癖である。これは誰でも簡単にできそうであるが、実際に実行している人は少ない。相手はそんなに褒められるようなものではない、と思いながらも悪い気はしない。しかも、人が集まっている場で褒めてくれるので気分がよくなる。その反対に、人の悪口や人の批判をしているのを聞いたことがない。人間だから多分気に入らないことや腹が立つことは頻繁にあると思う。特にこの方は他人と接触する機会が多いので、その頻度が高いと推測される。それらは心の中に留めておくだけで、言動として表面化することはない。多くの人と温かい人間関係を保ち、お互いにざっくばらんな信頼関係が成り立っている。だから少々強引な依頼事項もたまにはあるが、それが嫌味にはならない。誘ってみてうまくいけば儲けもの、ダメなのが当たり前というスタンスで、とりあえず軽い気持ちで、当たって砕けろという態度である。また依頼されたことを断っても、 「わかった。じゃあ、またね」とすぐに引き下がられるので、とても気が楽である。そのような人間関係の中にいると、なんとか依頼されたことに対してできるだけ協力したいという気持ちにもなる。日程的にどうしても無理な場合を除いて基本的には協力するようにしている。かたや対人恐怖症で人間関係がうまく行かないと言っている人は、観察していると、これと反対のことばかり行っている。他人の欠点や弱点、ミスや失敗を必要以上に大きく取り上げて、相手を批判したり否定して罵倒している。いったん相手を避けるようになると、相手のいやなところをどんどん拡大解釈して、まったく寄り付かなくなる。先入観や決めつけが多く、結局は自分で自分の首を絞めているようになる。それを基にして人格否定まで行うのだから、相手にとってはとても苦痛である。最後には人が寄り付かなくなってくると思う。その反対に、相手の存在自体、優れた点や能力、努力している姿については何ら関心を払わない。その程度のものでは評価や賞賛には値しないと思っているかのようだ。ことさら取り上げて言動として表面化させるのは馬鹿馬鹿しいという態度である。つまりやることなすことが、そのおばあさんとは反対のことばかり行っているのである。このような事ばかり行っていて、良好な人間関係を築きたいと思うのはちょっと無理があるのではなかろうか。もし、対人関係でいつもトラブルを抱えて悩んでいる人がいるとすると、自分はどちらのタイプに属するのか調べてみた方がよいと思う。良好な人間関係を築いていきたいと思うならば、このおばあさんのやり方を真似することが大事なのではなかろうか。意識や注意を向ける方向を変えて、実践してみるだけでよいのだ。その結果大きな果実をもたらすに違いない。多くの人間は「かくあるべし」を持っているので、どうしても欠点や弱点などを見つけると、それらをなくしたり、人並みのレベルにまで改善しようとする。そんなことにエネルギーを投入するよりも、自分の元々持っている存在価値や能力を活用して、さらに前進させていく方向に舵を切り替える方がよいと思う。
2017.08.26
コメント(2)
-
カラ元気をつけてやることとやむをえずにやることの違い
森田先生は目の前の仕事に取り組む場合に、ふたつの違ったタイプの人がいるという。1つは、能動的に、自分から勇気をつけてやる人である。これはいわば、カラ元気の付け焼き刃であるから、することなすことが不自然になる。この場合は、自分の本心としては、できることなら仕事などやりたくない。経済的に恵まれた状態なら、仕事はしなくてもいいのに、自分や家族の生活の維持のために、やむなく取り組まざるを得ない。仕事は必要悪という考え方が根底にある。自分のイヤだという気持ちに反して、無理矢理、気持ちを切り替えなければならない。森田先生はこれは全く駄目というわけではないといわれている。神経症の蟻地獄に陥っている場合は、最初はそのやり方でもかまわない。ただ神経症の治療の段階でいえば、これは軽快にあたるだけだといわれている。そのやり方は徐々にステップアップしてゆかないと、完治には至らない。もう一つは、受動的に、やむをえずにやるというタイプの人である。これは背水の陣をひいて取り組むことである。この場合は、自分は弱いものと覚悟して、自然であるから、談判でも擬勢がなくて、勝たなくても、少なくとも負けることはない。この場合には、勝てば喜び、負けても当然のこととして、がっかりするような事はないといわれる。能動的に空元気の付け焼き刃で仕事を始めるのと、受動的にやむをえずに仕事を始めるのはどこに違いがあるのだろうか。私が思うには、カラ元気をつけて仕事をする場合は、イヤだという感情を否定していると思う。その感情を認めることをしないで、すぐに否定して排除しようとしているように見える。不快な感情への向き合い方としては、大いに問題がありそうである。一方、受動的にやむをえずにやるというのは、 「仕事に行くのはおっくうだ、嫌だなぁ」という自分の心に沸き起こってきた不快な感情を否定していない。あるがままに認めている。その不快感に抵抗しないで十分に味わっている。大した違いはないのではと思われる方がおられるかもしれない。しかし、ここは森田理論の核心部分にかかわる極めて重要なところだと思う。不快感に対して、とことん味わい尽くす。安易に否定したり排除しない。これは神経症の完治を目指すに当たっては、ぜひとも身につけたい重要な考え方なのだと思う。この話は森田全集第5巻の283ページで説明されていることである。この部分をさらっと読んでいるだけでは、森田先生が我々に何を伝えようとされているのかよくわからない。森田先生は、いろんな具体例や多方面の視点から森田理論の真髄を伝えようとされているのである。この部分は私たちに森田理論の中のどこの部分を理解させようとしているのか。そうした視点がないと皆目見当がつかないことになる。宝をみすみす見逃してしまうことになる。余談だが、私は、森田理論全体像を作り上げて、森田理論を俯瞰することができるようになった。いわば地図を広げて、森田理論全体の地形を判断することができるようになった。この地図をもとにして森田先生のお話を聞くと、話の内容と森田理論の焦点がぴったりと合うようになった。すんなりと森田先生の様々なお話がより深く理解できるようになった。森田理論を学習する人たちには、基礎編の学習が終了した後は、ぜひこの森田理論全体像を学習して、森田理論の枠組み、スキームを理解して欲しいと思う。内容はこのブログでも何回も取り上げてきた。私は森田理論がよくわかるようになったと感じるのは、この森田理論全体像を試行錯誤の末に作り上げた時からであった。あれから約10年経つ。その思いはますます強くなっていくばかりである。それまでの20年は正直言って森田理論を学習すればするほど、出口が見えない迷路に入ったようなものであった。今では森田理論全体像という地図を頼りにして、 迷路から脱出して、曲がりなりにも人生を楽しむことができるようになったと感じている。
2017.08.25
コメント(0)
-
「自己一致」について考える
2017年8月号の生活の発見誌に興味深い記事があった。あるがままを実現するために重要なことは「自己一致」ということです。「自己一致」とは、自己概念(そうであるべき自分)と現実経験(あるがままの自分)が一致している状態のことを言う。最近よく言われる傾聴でも、傾聴する側の基本的態度である三原則の1つで、 「自己一致」できていない人が傾聴しようとすると、 「あるがまま」を押しつけて、新たな「かくあるべし」を生むので注意が必要です。これは私たちは森田理論の学習の中の「思想の矛盾」のところで学んでいます。「自己一致」という言葉に刺激されて、私なりの解説をしてみたい。症状で苦しんでいる人は、ほとんどの人が自己が2つに分離している状態です。これは自分という1人の人間の中に、別の人格を持った2人の人間が住みついているようなものです。1人は現実の世界で悩んだり苦労したり、時にはどうしようもなくてのたうちまわっている人間です。そのために時には自暴自棄になることもあります。もう1人の自分は、地上からはほど遠く、雲の上から、そんな自分を軽蔑して見下ろしているような人間です。そんな自分を見て拒否したり、非難したり、無視したり、否定したりしている人間です。その2人の人間のうち、どちらの力が勝っているかということが、その後の展開を大きく左右します。現実に重心を置いた人間は、理想の自分がちょっかいを出してきても、おいそれとそれに従う事はありません。むしろ現実の世界に、しっかりと足をついて、そこを出発点にして上に這い上がろうとする人です。自分の容姿、性格、能力、境遇等、できることとできないことを見極めて、自分にもともと備わっている存在価値を存分に発揮しようとする人です。そういう人は「自己一致」しているので、葛藤や苦悩を抱えることがない。反対に、理想の自分に重心を置いている人は、けなげにも現実世界で必死になって生きている自分に対して、けんもほろろに扱います。そして、罵倒してしまうのです。また強引に、現実世界を捨てて、理想の世界に無理矢理自分を引っ張り上げようとするのです。まだ利用価値や存在価値が残っているのにそれを捨てて、別の新しい自分に取り替えようとしているのです。つまりポイ捨て、使い捨ての思想にはまっているのです。自分で自分を否定することほど悲しい事はありません。どんなに未熟でお粗末な自分であっても、自分は自分の最大の味方であることが大切です。森田理論では、思想の矛盾を解決するためには、雲の上にいる自分が雲の上から地上に降りてきて、現実の自分に寄り添うことが重要であると言います。これが森田理論で目指している究極の生き方です。しかし、この「自己一致」というのは、口で言うのは簡単ですが、すぐに身に付ける事は大変難しい。しかし森田理論を学習していけば、その方向に近づく事は出来る。私はその学習期間を3年と見ている。というのは、事実や現実、現状にしっかりと足をついた生き方は、森田理論の中ですでに理論化されているからだ。そのステップやそれに至る方法は、このブログの中でたびたび取り上げているとおりである。「かくあるべし」は体に纏わりついたコールタールのようなものであって、なかなか取り除く事は困難である。しかし「かくあるべし」を少なくして、 2つに分離した自分を1つに統合していくということを目指さない限り、自分の人生は苦渋に満ちた情けない終末を迎えるであろうことは間違いなさそうである。
2017.08.23
コメント(0)
-
お悔やみの言葉について
森田先生は、友達や親戚の不幸のお悔やみに行った時は、決して余計なことを言わない方がよいと言われている。自分で経験もないものが、当て推量に、いろいろなことを言うのは大間違いの元である。例えば、早く悲しみを忘れる方法とか、人間は誰でも死んでいくものだから気にしないほうがいいとかくどくどとお悔やみを述べる事はやめた方がいい。 「死んだ人はもう帰ってこないから、早くも諦めた方がいい」などは余計なことだ。お悔やみに行った時は、お辞儀の仕方も、投げかける言葉も簡単なほどよい。常に相手の人の時と場合に気をつけて、同情し、共感するように心がけ、決して余計なこと言わないのがいいのである。形外会に参加されていた馬場さんという女性の方が次のように話されている。昨年、主人が急に亡くなった時、他の人たちから、様々に慰められた時、私は「諦められるものではないですが、諦められないままに、時が解決してくれるのです」と言いました。以前ならば、この人達の言うように、どうしたら、諦められるか、どうすればこの悲しみを忘れることができるかと、様々に苦しんだことでしょうが、森田先生のおかげで、そんな考えはなくなり、大変楽で、悲しみや苦痛もひどくはありませんでした。お悔やみに来られた人が、おとなしく挨拶してくれれば、私も「ありがとうございます」と言って済ますことができます。しかし、あまりにもくどくて、しつこくお悔やみを述べられると閉口してしまいました。森田先生は先に子供さんや奥さんを亡くされたが、お悔やみも、簡単ならば、 「ありがとう」ですむが、しつこく言われるときには、私は黙って返事をしない。これによって相手に反省させるつもりである。それでも反省しない相手には反発することになる。(森田全集第5巻 285頁参照)確かに葬儀に参列すると、葬儀前の慌ただしい時間にやってきて、喪主に対して長々と話をしている人がいる。そういう人は、自分がいかに相手の身になって同情しているのかをアピールしているようである。小さな親切、大きなおせっかいと言うような状態だ。親切の押し売りをしているようにも見える。また、相手から聞かれてもいないのに、葬儀の段取りなどを説明している。いかにも自分が親身になって相手のことを思いやっているのかを押し付けているように見える。こういう人は、自己中心的で、時間や場所をわきまえるという気持ちがさらさらないようである。喪主の人が親しい人であればあるほど、お悔やみの前に様々に投げかける言葉を考える。できるだけ相手の心に響くような哀悼の気持ちがこもった言葉を用意するのである。しかし実際には、相手も放心状態でそれどころではないのだ。なかには参列してくれたこと自体を忘れていることもある。 「この度は大変ご愁傷様でした。心からお悔やみ申し上げます」というような簡単な挨拶で引き下がった方がよい。お悔やみに来ましたよと、顔を見せるくらいでよいのかもしれない。葬儀に参列し、香典を渡すことに意味がある。これが本当の思いやりというものである。当たり前の礼儀作法であると思う。これは葬儀だけに限らないと思う。集談会でも相手から聞かれてもいないのに、親切心でいろいろとアドバイスをすることがある。こちらから話をするのではなく、相手から話をしてもらうことに力点をおいたほうがよいようである。
2017.08.22
コメント(0)
-
存在価値について
人間の「存在価値」について考えてみたい。その前に存在価値以外の価値についてみてみよう。「貨幣価値」というのは、物の価格を他の物や以前と比べて、お金の価値が上がったか下がったかを比較している。例えばマンションを買って、10年後にそのマンションの販売価値が上がっていれば、そのマンションの貨幣価値は上昇している。値下がりしていれば、貨幣価値は下落しているとみる。「歴史的価値」というのは、今日の文明や文化の発達を考えるにあたって、見逃すことのできない遺産や出来事である。象徴的な遺産や出来事をいう。「なんでも鑑定団」でいう「希少価値」というものは、極めて珍しいもので、欲しい人がたくさんいるものである。それらは高値で取引されるものである。「経済的価値」というものは、利潤を沢山生むことができるものである。例えばIPS細胞などは今後の経済的価値は高まるであろう。あるいは、ガソリンを使わない電気自動車なども経済的価値が高まるものと思われる。「利用価値」があるというのは、そのものが使用用途がある、人間の役に立つということである。「潜在価値」というのは、その中に他では代替できない貴重なものがある。秘めた力があるということである。潜在能力といってもよい価値である。今は顕在化していないがいずれ役に立つに違いない価値の事です。こうしてみると価値の特徴が浮かび上がってくる。まず、価値というものは、その物だけを見ていては判断できない。つまり2つを相対的に比較してみた結果、始めて価値があるとかないとかいっているのである。比較した結果、優れたところがある。値打ちがある。役に立つ。使い物になる。利点がある。珍しいものである。価格が高いものを価値が高いと言っているのである。そうでない片方のものは、相対的に価値がないと言っているのだ。2番目の特徴としては、時代と状況によって価値は高くなったり、低くなったりすることがある。一定で永遠に普遍的な高い価値が続くというのは現実ではあり得ない。例えば野球ではホームランの数や盗塁数、打点等は減ることはない。ところが打率は打てなくなってくるとすぐに低下してくる。反対にヒットを量産するようになると打率がアップしてくる。物の価値は打率のようなものである。このように価値は変化流動性があるのである。その点をふまえて、人間の「存在価値」を見てみよう。生きとし生けるものはすべて存在価値がある。特に、私たち神経質者は他の性格には見られない優れた特徴がある。主だったものをあげてみよう。よく気がつく。感受性が豊かである。好奇心がいっぱいである。生の欲望が旺盛である。真面目でよく努力する。粘り強い。責任感が強い。自己内省力があり人に迷惑をかけない。分析力がある。堅実で計画的。しっかりとした人生観を持っている。これらは森田理論学習の「神経質の性格特徴」を学習した人は、十分に自覚されていることと思う。大事なことは、それらを自覚して磨きをかける以外に自分を活かす道なし。そのように覚悟を決めることだ。それが神経質性格を持って生まれた我々の進むべき道だと思う。次に、それらを実際の生活の場面に当てはめて活用していくことが大切である。いいなと思っても活用していかないと絵にかいた餅である。そうしないと、感受性の鋭さ、生の欲望の強さ、自己内省がマイナスに作用して、自己嫌悪、自己否定、他人攻撃に陥ってしまう。そして神経症で苦しむようになってしまう。2歩前進1歩後退の連続であってもかまわない。楽しみ、便利さばかりを追い求めて、面倒なこと、努力して苦労することを放棄する道に進むことは避けなければならない。人の役に立たない人。消費一辺倒で、精神的、経済的に他人に依存するばかりの人は、「人間としての存在価値」がどんどん下がり、みじめで、人からも見向きもされないようになる可能性が高くなる。幾多の生存競争を潜り抜けて、この世に生を受けてきた人すべてに「存在価値」はある。その「存在価値」を多少なりとも磨きをかけて、自分の器を大きくしてきた人は、この世に生まれてきた意味があったということではなかろうか。
2017.08.21
コメント(0)
-
森田理論でいう「心の流転」ということ
森田先生のお話です。今日の皆さんの話を聞くと、思いっきり往生するとか、絶体絶命でよくなるというところまではでたが、まだ流転というところまではいかなかった。絶体絶命だけではただ行き詰まるだけでまだ治らぬ。そこから、心の流転が始まった時に、はじめて治る。そこに微妙な心の流転がある。これは絶体絶命になったときに、初めて起こるものです。切羽詰まれば、必ず、それから、思想は様々に変化するようになる。変化すれば、執着を離れるようになり、強迫観念が治る。 (森田全集第5巻 422ページより引用)森田理論学習では、神経症は症状と格闘することをやめた時に初めて克服することができるといわれている。それが、ここで言われている絶体絶命ということであろう。それを体得するだけでも大変なことだが、森田先生はそれだけではただ行き詰まるだけで神経症は治らない。心の流転が出てこないと治らない。心の流転があって、はじめて治ると言われている。今日はこの「心の流転」について考えてみたい。往生するとか、絶体絶命と言うのは、不安や恐怖に闘いを挑まない態度のことをいう。このことを、まずは頭の中で理解するということである。頭の中で理解したということと、生活の中で体験として身に付けた(体得)という事は違う。例えば、不眠障害の人が夜眠れないときに、苦し紛れにあちらこちらに体を動かすのではなく、苦しいままに体を動かさずにじっとしていれば眠れるようになると言われ、その通りにしているとよく眠ることができた。次の日に、苦しいままに体を動かさずにしていれば眠れるはずだと、自分に言い聞かせるようなことがあると、それが「かくあるべし」になって眠れなくなる。元の木阿弥になってしまう。往生する、絶体絶命というのも、それ自体は森田理論に照らし合わせて間違えはないのだが、それを言葉で理解して症状を克服しようと思っている段階では治る方向とは少しずれている。往生する、絶体絶命というのは、そうならなければならないという「かくあるべし」ではなく、普段の生活の中で自然に実行できるようになることが大切なのである。とは言え、神経症の蟻地獄にすでに落ちている人にとっては、そんなことを言われてもチンプンカンプンのことだ。最初のうちは、往生する、絶体絶命というのは、そんなものかなという程度に受け取られたらよいと思う。ではそんな時には何をすればいいのか。目の前の仕事や家事、育児などに精を出すことだ。日常茶飯事に丁寧にに取り組んでいると、気づきや発見がある。あるいは疑問がわいてくる。つまり、必要に迫られて行動を実践することによって、新しい感情が生まれてくるのだ。これがとても大事なところだ。新しい感情が生まれてくると、今までとららわれていた感情にいつまでも関わっておられなくなる。新しい感情に基づいて新たな行動実践が始まると、心の中はどんどん変化してくる。後で気が付いたら、症状のことは全く気にしていなかったという状態が訪れる。つまり、森田先生が言われている「心の流転」が自然に起きることになる。第一段階の神経症が治るという事は、森田理論学習によって不安や恐怖、違和感、不快感の正体を知る。あるいは欲望と不安の関係について理解を深める。そして次の段階では、それらの知識は一旦横に置いて、自らは目の前の自分に与えられた仕事や課題、日常茶飯事に丁寧に取り組んでいくということに尽きるのである。この二つが相まって、アリ地獄の底から抜け出し、第一段階の神経症の克服に結びつくのである。ちなみに、第2段階の神経症の克服は、「かくあるべし」を少なくしていくこと。森田理論でいう「思想の矛盾」の打破である。ここまで来ると、生きていくことはつらいことばかりではなく、味わい深いものだとしみじみと感じることができるようになると思う。
2017.08.20
コメント(0)
-
「日本理化学工業」という会社について
日本理化学工業という会社がある。この会社はチョークを作っている会社である。この会社の特徴は、従業員のほとんどが知的障害者であるということである。この会社の社長さんは、 「この人たちに幸せを提供できるのは、福祉施設ではなく企業である」という考え方を持っておられる。先日テレビで仕事ぶりを紹介されていた。これによると、知的障害者の人はとても人懐っこい。社長さんが従業員達に、 「今日もよく頑張ったね、ありがとう」と声をかけると、知的障害者の人たちは、心から嬉しそうな顔をするという。また同じ単純作業を2時間程度は、苦もなく繰り返すことができる。ただ喋り方はたどたどしく、動作は普通の人のように俊敏にはできない。言われたこともすぐに理解できないこともある。そのためか整理整頓は、言葉ではなく絵や色分けで表示されていた。言葉の意味の理解ができなくても、絵や色分けされた収納で支障なく仕事ができていた。何よりも知的障害者の人が自立できていたことが素晴らしい。本来は福祉施設で生活するしかないような人が、働いて得た給料で自分の生活を成り立たせるていることに感動した。自立した生活を送っておられるのだ。この会社の社長さん曰く。「人間の究極の幸せは4つあります。 1つ目は、人に愛されること。 2つ目は、人に褒められること。 3つ目は、人の役に立つこと。 4つ目は、人に必要とされること。だから障害者の方達は、施設で大事に保護されるより、企業で働きたいと考えるのです」人は仕事をして褒められ、人の役に立ち、必要とされるから幸せを感じることができる。仲間に必要とされれば、周囲の愛し愛される関係も気づくことができる。だから、障害者達はあんなに必死になって働こうとするのだ。この社長さんの言葉と森田理論の接点について考えてみた。まず人間は毎日の仕事や家事などを持っているということがとても大切だということだ。お金さえあれば仕事をしなくてもいい。お金さえあれば家事や育児を外注してもいいなどという考え方は、本来の人間の生き方に反する。本来の人間の生き方に反することをしていると、身体の健康のみならず、精神的にもおかしくなってくる。仕事や家事は煩わしいものではありますが、それらを放棄して、他人に依存してしまうということは、何としても避けなければなりません。森田理論では自分の気になる症状1点のみに注意や意識を向けるのではなく、目の前にある仕事や日常茶飯事に目を向けて、丁寧に取り組む事を勧めています。マズローの人間の欲求の5段階説によると、人に愛される事は3番目の欲求、人に褒められる事は4番目の欲求と言われています。人間は生理的な欲求、完全への欲求が満たされると3番目、4番目の欲求を満たす方向に向かうと言われています。対人恐怖症の人は、人に愛されたいという欲求は非常に強いのですが、その半面、人に受け入れられなかった場合のことを考えて、取り越し苦労ばかりしているという面があります。特に仕事の面では、お互いの意見が衝突する場合が多く、仕事すること自体がつらいといって、逃げるようになります。それでは対人恐怖症の人が、人から愛されるためにするべき事は何か。それは人に役に立つこと見つけて実践していることだと思います。大きな事を1つするよりも、普段から小さな事を数多くのすることが、神経質性格の持ち主には性があっているように思います。仕事や日常生活の中で、周りの人にやってあげたらよいなと思うのは数多くあります。それは神経質性格の持ち主だからこそ気づくことができることです。例えば、バスに乗るときは事前に小銭があるかどうかを確かめておく。このような些細な積み重ねが、大切なのです。常日頃、人に役に立つことを見つけて実践していると、症状自体からも離れることができ、人にも喜んでもらえ、人間関係が改善し、ひいては自分の存在意義を確認することにもなるのです。
2017.08.19
コメント(2)
-
「意識の目的性」について
森田先生の「意識の目的性」について説明してみたい。我々の意識は、常に自分の行為の目的の尖端にのみ集中されて、これを実行する態度や、過程については、ほとんど気がついていないものである。我々はお茶漬けを食べるときには、箸と茶碗の持ち方、特に左の手の左腕の回転具合は、極めて微細な働きであるけれども、この方にはほとんど気がつかないで、意識はご飯をこぼさないようにとの目的ばかりに向いている。また球を投げるときに、球の方ばかりに注意を集中していさえすれば、適切に球を受けることができるけれども、意識がひとたび、自分の手つきや腰の曲げ方のほうに向かうようになれば、すぐに球を受けることができなくなる。小指を怪我したときなどでも、球が受けられなくなるのは、意識がその目的物を離れて、手元のほうに向かうようになるからである。薪割りの時に、打とうする1点のみを見つめていれば、百発百中であると言うのも、この理由に基づくものである。(森田全集第5巻 644ページより引用)神経症に陥った時は、自分の気になる症状に注意や意識を集中させている。気になるというのは自然現象であるので、どうすることもできない。しかし、われわれは意志の力でどうすることもできないものにとらわれて、戦いを挑んでいる。ドンキホーテが水車に向かって戦いを挑んでいったようなものである。森田先生がここで言いたい事は、意識が過度に自己内省的に働くようになると、注意や意識が本来向かうべき方向に向かわなくなる。するとやることなすことがうまくできなくなってしまう。ちゃらんぽらんになり、目的は果たせなくなる。これはゴルフのパターなどでよく見られる。練習の時は何度も成功しているのに、いざ本番になると緊張して手の動きが固まってしまい、肝心なところで入らなくなる。そして肝心な勝負に負けてしまう。この時は、意識が自己内省的に働いている。「どうしても沈めなければならない。ギャラリーの前で恥をかきたくない。これを逃すと優勝はできない」等々。目的物から注意や意識が離れていってしまうので、その分、球への集中力がなくなるのである。これはエネルギーの配分の間違いを起こしているのである。我々の意識は、第一に目的物に照準を定める必要がある。それは我々の欲望と言ってもよいものである。森田理論では欲望が存在すると必ず不安が出てくる。欲望と不安はコインの裏と表の関係にあるという。欲望や不安に対する我々の態度はどうあるべきなのか。まず欲望は決して見失ってはならない。いつも欲望の先を見つめていなければならない。生の欲望の発揮は人間の生きる意欲の源である。ではそれに付随して出てくる不安に対してはどうすればよいのか。これについては森田理論学習で、不安の役割、欲望と不安の関係、不安への対応方法について事前によく学習しておく必要がある。これらがよく理解できていると、不安にとらわれて、手段の自己目的化などが起きないようになる。むしろ不安を生かして、予想される困難をあらかじめ想定して対応できるようになる。また、緊張感があるために、本番では集中できて、予想以上の成果をあげることもできる。不安を排除するのではなく、不安と友達になれるようになる。神経症で悩んでいる時は、不安を目の敵にして戦っているのだが、神経症を克服してくると不安というのは唯一の無二の親友のようなものになれるのである。
2017.08.18
コメント(0)
-
事実に従う態度を養成する
森田先生は次のように言われている。何かにつけて、思想に馳せ、空想に耽りやすい青年の特徴として、一つ一つの事実を具体的に見ないで直ちにこれを抽象的に思想しようとする。事実をありのままに見ないで、直ちに人生は面白くないとか、時代はままにならぬとか、大げさにいいたがる。ただ素直に、おとなしく、一つ一つの事実について、いえばよいけれども、僭越に不従順に、大げさな言葉を弄するのがいけないのである。 (森田全集第5巻187頁より引用)森田理論を学習していると、どんなに理不尽な出来事があろうとも、それに反発はしないで、事実そのものを土台にして生きていくことが1番安楽な生き方であるということがわかる。しかし頭で理解できても、実際に実行することはなかなか難しい。普段の生活態度としては、事実からかけ離れ、先入観や決めつけで、悲観的でネガティブになりやすい。どうすれば、 「自然に服従し、境遇に従順な生き方」ができるのであろうか。われわれは言葉を使って過去のことや未来のこと、論理的、抽象的なことも様々に考えることができる。人間はそのような生き物であるという事を把握して、事実本位の態度を貫くことが重要である。さて我々は事実をありのままに正確に捉えようとしているのであろうか。ここが出発点であると思う。多くの人は事実をより深く知ろうとはしないし、たとえ見たとしても、見た瞬間に頭で解釈してしまうのである。初めて体験することが驚きや感動があるが、すでに体験した事は人の話を聞いただけで、推測してしまうのだ。大人になると、日常生活の中で経験したことが大半を占めるようになり、わざわざ事実を確かめなくても、わかったものとして、次に進もうとするのである。これが問題である。実際に事実を確認しない。観察をしない。現地に行かない。過去のデータに基づいて間違いないとすぐに断定してしまうのである。本来事実とは、人間による観念化、解釈や評価、あるいは感想など、人による処理がなされていないそのままの状態をいうのである。事実をありのままに見ることが出来ないと言う事は、事実と観念や解釈という人によって処理されたものとの区別がつかないということでもある。これが神経症の発症に大きくかかわってくる。いわゆる思想の矛盾にかかわる部分である。私は事実というのは、簡単にわかったつもりになってはならないと思っている。もっともっと事実を観察するために時間を割こう。また中途半端な事実にすがって、軽率な言動に走ってはならないと思っている。今までは事実を把握する時間があまりにも短かすぎる。だから、事実を誤認してしまうのである。もっと、もっと事実を観察して、本当の事実をつかもうとする努力が必要である。解釈や処理を考える前に、必ず間違いのない事実なのかどうかを確かめようとする態度を習慣化する必要がある。これが我々の森田理論の学習会で習得を目指していることである。今までは事実をつかみ取ろうとする時間を1とすると、解釈や処理を考える時間が9であった。これからは事実をつかみ取ろうとする時間を半分のせめて5ぐらいに拡大する必要がある。そして、解釈や処理を考える時間はそのあとに回しても遅くはない。そのような態度を養成することによって、先入観や決めつけが少なくなってくるものと思われる。そのようなことのできる人は、人間関係もうまくいくようになるし、葛藤や苦悩が少なくなってくる。
2017.08.17
コメント(0)
-
☆カツオの一本釣り漁師から学ぶこと
高知県にカツオの一本釣り漁師の明神学武さんという方がおられる。この人は第83佐賀明神丸で、ここ10年間で4度水揚げ日本一の快挙をあげられている。漁労長としての明神さん肩には、乗組員23名から27名の生活がかかっている。明神さんにはピンポイントでカツオの群れを探し出す能力を身につけられた。他の船と同じようなことをやっていては、水揚げ日本一は達成できないという。どうやってカツオの群れを見つけ出しているのか、とても興味がある。一般的にはカツオは黒潮に乗って、早春から春先、梅雨の時期から夏にかけて、沖縄方面から東北沖まで回遊している。そして8月を過ぎるとまた南の方へ戻っていく。カツオはイワシの群れを追って常に移動しているのだ。そのイワシの群れの周りには海鳥が集まっているという。そのため、漁船には海鳥を見つけるための海鳥探知器が設置されている。その他魚群探知器はもちろんのこと、 GPS航行装置によって40キロから60キロ周辺を観察している。刻々と変化するその日の気象状況、海水温、黒潮の流れの蛇行などを正確に把握して、カツオの集まっている場所を経験と勘で予想している。その他最近カツオがたくさん取れたところ、あるいは他の漁船がたくさん集まっているところもデーターとして分析もしている。ただ、それらのデータは参考にするだけで、今日の漁場を決定する際の決め手ではないと言う。膨大な多方面のデーターをよく観察して、自分なりに分析して、果敢にチャレンジされているのだ。次にカツオの生態についてとてもよく熟知されている。カツオの群れを見つけると、海水を散水する。そしてキビナゴや背黒イワシを深いところに沈める。すると小型のカツオから反応して、そのうち大きなカツオが反応して上に上がってくる。群れ全体を海面に持ってこさせる。泳げる活気のあるエサをまいて引きつける。カツオの群れは先頭を走っているカツオに付いていくという習性がある。先頭を走るカツオの動きを推測しながら生きているエサをまいて、カツオの群れを船の近くに連れてくる。海面に上がったカツオの群れは散水効果と活魚を見て、大量の餌にありついたと考える。その中に一本釣り用の疑似エサを投げ入れる。カツオは目で餌を確認できます。群れの中には釣り糸などが見えるカツオもおり、釣り糸や釣り針がわかるとすぐに逃げてしまいます。頭のよい魚なのだ。カツオの1本釣りは漁労長が指揮をとり、まだ未熟者の若者が餌配りを行い、船の先端部分と後ろ側には経験の豊富な熟練者が陣取りドンドンと釣り上げる。これが20分から長いときは2時間も続く。重いカツオは10キロ以上にもなる。大変な重労働で1人前になるには3年くらいはかかるという。また1年のうち2月から11月まで、夏季休暇を除いては約10ヶ月海の上で生活する。団体生活であるので、良好な人間関係作りと一糸乱れぬチームワークが重要になる。明神さんは、まだ若い方ではあるが、性格的には、釣りバカ日誌の浜ちゃんのような人で、人を叱りつけるようなことがない。雑談の場では、人の話をニコニコしながら黙って聞いているような人である。しかし、一旦カツオの話になると真剣そのものである。みんなの生活が自分の判断で左右されてしまうので、真剣にならざるを得ない。また収穫が上がらないと、みんなの士気が落ち込んで、人間関係にも影響してくる。大変なプレッシャーである。明神さんは、最新の設備を利用してカツオの動向を観察されている。またカツオの習性を常に研究されており、研究熱心である。また他の漁船の水揚げ高も気にしながらライバル意識を燃やしている。そして漁労長として、乗組員の全員の雇用を守るという責任感も強い。明神さんを見ているとカツオの一本釣り漁が、天職の様に思えてならない。多分一般の会社の社長として指揮を執っても、うまく切り盛りされることだろう。
2017.08.16
コメント(0)
-
強迫観念の治し方
森田先生は強迫観念の治し方について分かりやすく説明されている。強迫観念とは、身体の病根や死を直接に恐怖するのではなく、自分で「つまらぬ事を気にし余計なことを心配する」のを、自ら、あるいは自分の気質の病的異常かと思い違えて、これを排除し、気にすることの苦痛を逃れるとするためにかえってますますそれに執着を深くして逃れることのできなくなる苦悩が、すなわちそれであります。すなわち、これは誰にでも普通に起こる感じや取り越し苦労を強いて感じまい思うまいとする不可能の努力を重ねるものですから、ますます苦しくなるのは当然のことでも、ただ苦しいものはそのまま苦しみ、恐ろしいものはそのまま恐れると言う風であれば、何も強迫観念にはならないで、心の自然の絶えざる変化のうちにおのずから気が紛れて忘れるようになるべきはずであります。発作性神経症でも同様です。苦しいことは苦しい、恐ろしい事は恐ろしい、ただ一途にそのことになりきりさえすればよろしいのです。いたずらに発作を起こさないようにさまざまの工夫や、心の態度をとり、あるいはスースーハーハーやって気を楽にしたり、心を紛らせたりしようとすれば、するほど、その執着が深くなるのであります。(森田全集第4巻 白揚社 562ページより引用)結局、あなた方はいろいろに心に思い出すことは、いかに苦しくともそのままにして、自分のなすべき義務をなし、またしたいことを思い切りやっていくよりほかありません。もし、あなたがたが断然そうすることができれば、あなたがたの強迫観念も、霧の晴れるように、自分でも知らぬ間に心が朗らかになるのです。その他に、あなた方はいかなる方法や治療法を焦っても、かえってますます悪くなるばかりで、決してよくなることはありません。 (同書 566ページより引用)気になることは大いに気にして、イヤなことは大いに気にしてもよい。決してその感情をなくそうとやりくりしてはならない。また安易に逃げ出すことを考えてはならない。できるだけその感じを十分に味わうようにすること。不快な感情は味わうだけにするのだ。味わい方は、抹茶や地ビール、日本酒を味わうように、ゆっくりと堪能するまで味わうことだ。神経質者の場合は、美味しい料理を堪能することなく、ただ食べているだけという人が多い。それなのに、料理評論家のように辛辣な論評を加えようとしているように思える。逃げだすことはやりくりするよりも始末が悪い。注意や意識が内省的に傾き、自分を攻撃するようになるからである。自分自身を否定することが一番不幸である。自分がどんなに問題を抱えていても、自分は自分にとって最大の味方でなければならない。でもそれだけでは感情は流れない。目の前にある仕事や家事に手を付ける。最初はイヤイヤ仕方なしでもよい。そのうちにきっと弾みがついてくるはずだ。さらに好奇心を活かして、自分の興味のあることには積極的に手を出してみる。こういう気持ちで生活できるようになると、精神的な病気にかかることなく健康に暮らしていくことができる。さて、森田全集第4巻は外来指導、日記指導、通信療法の記録である。森田全集第5巻と同様、実際森田先生の個人相談の記録であるのでとても役に立つ。現在森田療法家には日記指導を取り入れておられる人もいる。顕著な効果をあげる場合があると聞いている。あるいは精神科医によるスカイプを利用した面談も可能となっている。集談会でもできないことはないが、基本的に余暇を利用したボランティア活動なので、個別集談会では難しい。もし4巻を読みたい人のためにワンポイントがある。5巻の読み方と同じことだ。この本は、 「現代に生きる森田正馬のことば」 (白揚社 生活の発見会編)に多数取り上げられているので、その部分をあらかじめマーカーなどで印を付けたり、ポイントの項目を記入しておくととても読みやすくなる。
2017.08.15
コメント(0)
-
循環論理とは何か
森田先生は「循環論理」について説明されている。神経質の患者で、自己内省の浅薄な人が、診察を受けに来ることがある。「どこが悪いか」と問えば、 「神経衰弱だ」という。「それではわからない。まず症状を言うように」と言えば、 「ものが気になる、いろいろのことが苦しい」と答える。「ともかくも、何が一番苦しくて、第一に治したいと思う事は」と反問すれば、 「神経衰弱を治してもらいたい」という。この場合、 「気になる」と「神経衰弱」とが循環するのである。この時に、何が気になり、それをどのように改良したいかという事を、具体的に実際に追求していけば、初めて循環がなくなって、ともかくも、ある一定の方向に、進路が見出されるようになる。赤面恐怖症の人の例で見れば、 「人前で恥ずかしい」と言うことと、 「大胆になりたい」ということが循環する。これは「苦しい」と「楽になりたい」ということが循環しているのである。これは、ある事実と、これを否定したいということの間に、循環する不可能の努力である。循環論理の人は、杭につながれたロバが、その不快感から逃れようとして、ぐるぐる回れば回るほど、ますます紐が体に巻き付いて動けなくなるのと同様です。これらは物事を、抽象的に漠然と考えて、事実を具体的に観察しないという思想の迷妄から起こるものである。(森田全集第5巻 517頁より引用)「循環論理」に陥った人は、ただ目の前の苦痛を取り除いて、楽になりたいのである。注意や意識が不快な気分にばかり向いている。これを続けていけば精神交互作用で蟻地獄の底に落ちてしまう。森田先生はこの悪循環を断ち切るため、苦しい状況を具体的に打ち明けることが必要であると言われている。抽象的に漠然と自分の不快な気分を打ち明けるだけでは、症状の発生原因が分からないので対応のしようがない。実際の出来事と、その時に感じた感情の事実を具体的で詳細に話すことが必要なのである。集談会でも自己紹介や体験交流の時に、そうした心がけが必要になってくる。「私は対人恐怖症です」と言うだけでは、他の出席者にとっては、どのような症状で悩んでおられるのかさっぱりわからない。集談会に来られるからには、対人恐怖症を治したいという強い意思はあるのだが、その思いは他の人に伝わる事はなく、自分の中で空回りしている。そんな時は具体的な例を挙げて、ていねいに説明する必要がある。そうするとみんなが真剣に話を聞いてくれるし、容易にアドバイスもしてくれる。そのためには集談会の開催日前には、自己紹介で話す内容を準備をすることが必要である。また体験交流で自分の話す内容についてはあらかじめ準備をしておく必要がある。私はこの2つについては、発表項目のリストを作っている。自己紹介では初回の方がお見えになったときは、自分の悩んできた症状について詳しく話している。初回者の人がおられないときは、ここ一か月間の生活について重点的に話している。また体験交流では、今、悩んでいること、生活上困っていること、森田を生活に応用して気の付いた事、森田の学習で気のついたこと、今月の発見誌を見て感動したこと、森田理論で疑問に思っている事、最近失敗したこと、うまくいったことなどである。その時、ここ1カ月間の日記を見ていると話したいと思うことがいくつか出てくる。その中から1つに絞って準備をして集談会に臨んでいるのである。そうなると集談会に参加することが楽しみになる。
2017.08.14
コメント(0)
-
森田正馬全集第5巻の利用の仕方
森田理論を学習するために「森田正馬全集第五巻」 (白揚社)をぜひお勧めしたい。この本は生活の発見会でいうところの集談会の記録のようなものである。その名前を形外会といった。入院生や元入院生を自宅に呼んで主に森田先生が話をされている。形外会は昭和4年12月1日から始まり、森田先生が亡くなられる1年前の昭和12年4月25日まで計66回開催されている。ほぼ1ヶ月に1回行われていたが、森田先生の健康上の理由などにより飛び飛びになることもあった。テープレコーダーもない時期になぜこのような記録が残されていたのか。この第5巻の責任編集者である青木薫久先生に聞いたところ、これはある人が速記をして、それを見て後に森田先生が加筆、訂正されたものであるという。すごく手間暇がかかっている貴重な本なのである。どうしてこの本を推薦するかというと、決して森田理論を小難しく説明されている訳ではない。身近な生活の場面をとらえて、森田理論からわかりやすく解説を加えられている本なのである。具体例や身近な生活の話から始まっているので、とても読みやすい。しかも、他の本を読まなくても森田理論のほぼ全貌が説明されているのである。参考になる話が次から次へと出てくる。これらを自分の生活に応用していくと、神経症は治るだけではなく、神経質性格者としてのこれから先の人生の方針が明確になる。欠点としては、この本には分厚い表紙が付いており、持ち運びに大変不便である。ページ数は実に774ページにものぼる。そこで私は、表紙を取り去り、この本を3分割にした。約250ページぐらいにした。真ん中に穴をあけて紐を通した。そうすると、持ち運びが容易になり、本を読む回数が格段に増えた。次にこの本は少々高い。確か8000円を超えていたと思う。 Amazon.comや古本屋でたまに安く売られていることがあるが、その本の価値を知っている人がすぐに買うので安く買うことが困難である。ちなみに私は古本屋で半額で売られていたので、すぐに買って集談会で欲しがっていた人に原価で分けてあげた。この本は白揚社では絶版にすることはないという。他の全集は単行本などとして出版されているものもあるが、第5巻はこれだけだ。次に、この本の読み方であるが、あまりにも膨大で、購入したのはよいが、ほとんど読んでいないという人もいる。そういう人にオススメしたいことがある。生活の発見会が出している、 「現代に生きる森田正馬の言葉」という本がある。この本には1と2がある。この本の内容は「森田正馬全集第5巻」からの抜粋が多い。抜粋したページ箇所が載っている。この本を持っていなければ、集談会で聞いて誰かに貸してもらうとよい。この本をみて、 「森田正馬全集第5巻」の該当箇所にマーカーで印をつけていくのである。ついでに記載ページも書いておくと後で役立つ。あと、内容のポイントを書いておく。その数が相当数あるので、あらかじめ重要なポイントがおおむね分かった上で読むことができるようになる。このような準備をしておくと、俄然読んでみたいという意欲が高まってくる。それなら分厚い全集を読まないで、その本だけを読めば森田理論が身に付くのではないかという人がいるが、私はそれは少し問題だと思っている。変な話だが、プロ野球観戦を球場に足を運んでみるのと、テレビで観戦する程度の違いがあると思う。それはどういう話の成り行きでこういう話を森田先生が出しているのかということが全集を見るとよく分かるのである。だから、 「現代に生きる森田正馬の言葉」という本は、この全集を読むための羅針盤のようなものである、と思っていたほうがよいと思う。次に生活の発見誌には、この全集第5巻からの引用がとても多い。引用があったときは、全集第5巻を開いて前後の部分を読んでいくとよいと思う。私はこの本を読むときは、このブログで説明している「森田理論全体像」のどの部分の説明なのかを念頭におきながら読むことにしている。森田理論を闇雲に学習するのではなく、森田理論の全体のスキームを分かった上で学習することが重要であると思っている。また、森田先生の話は前に言われたことと、今の話は矛盾するのではないか、と思うようなことがある。そんな時は、今話されていることで森田先生が我々に何を伝えようとしているのかという風に考えると、頭が混乱することがない。さらに森田理論の核心部分に触れることができるように思う。つまり読みっぱなしにするのではなく、自分の場合に当てはめて森田先生と対話するような気持ちで読むことが必要なのだ。最後にこの本を読んで、それぞれの感じたことを集談会の場で話し合うことでさらに効果的になる。全集第5巻の読書会なるものは、そのような学習を積み重ねているのである。
2017.08.13
コメント(0)
-
不安や恐怖は仲間の力を借りて乗り越えよう
森田先生は実践や行動をするときに、不安や恐怖をなくして、おもむろに実践や行動するという態度を諫めておられる。また、実際に行動する前に、意欲ややる気を高めて、勢いをつけて取り組むこともだめだといわれている。決心とか自信とかいうものを、思いっきり投げ出してしまって、ただ自分の机の上に、原稿用紙とペンと参考書などを並べて、静かに退屈しながら、それと、にらめっこをしていればよい。その時間は1日に、 10分なり、 30分なり短い時間で、何回でもよいから、なるべく度々 、机の上に座ればよい。そして、あるいは三行でも、落書きし、また参考書を手当たり次第、開いたところでたらめに読んでいればよい。このありさまを1週間なり、 3週間なり、忍耐して続ければよい。その全体の意味から言えば、できても、出来なくとも、いやでも応でも、しなければならぬ事は、ともかくもするということに帰着する。その時に、勇気とか自信とか言うものの、付け焼き刃をしてはいけない、ということである。今、私の言う通りにすれば、たちのよい人は、 2日目から、早くも書く気になる。遅い人でも、 1週間もすれば、自然に調子に乗ってくる。ただ、そのはじめの皮切りの間が、少々苦しいと言うまでのことである。 (森田全集第5巻 267頁より引用)私は大学を卒業して初めての仕事は訪問販売の飛び込み営業の仕事でした。しかし、対人恐怖症の私にとって、それは精神的にとてもきつい仕事でした。最初は同期入社した仲間たちに負けたくないという気持ちが多少ありました。しかし冷たく断られてばかりいると、しだいに訪問する意欲がなくなりました。森田先生に言わせると、そこで仕事をさぼってはいけない。いやいや、仕方なしに、断られ続けても仕事から逃げてはならないということだと思う。仕事から逃げると、一時的には精神的に楽になるが、そのうち何もすることがなくなって虚しくなる。大学まで出たのにどうして訪問営業の仕事で苦しまなければならないのだろうと思う。さらに、営業成績が上がらず上司や同僚から軽蔑したような目で見られる。しだいに針のむしろに座らされているような気分になる。同期入社をした人たちは、今や続々と定年退職を迎えている。OB会のお誘いをみると、その人たちが定年まで仕事を継続してこられたことに対して、大変な驚きと尊敬の念でいっぱいになる。森田理論学習を積み重ねた今だったら、仕事から逃げないで、頑張ることができたであろうか。これについては残念ながら未だ自信がない。冷たい断りの嵐の中で、その辛い気持ちを抱えたまま、次の訪問先に向かうことができたであろうか。頭ではわかるが、たぶん今でも体がついていかないのではないかと思う。そういう気持ちがいつもあるので、たまに訪問営業の辛い時が夢にまで出てくる。神経症で悩んでいる人は、逃げてはいけないのはよくわかっているのだが、それができないから神経症に陥ったのだ。不安や恐怖を持ったまま、目の前の仕事にイヤイヤ仕方なしにでも取り組みなさいといわれてもどうしても体のほうがついていかない。森田理論はそれができないから症状に陥ったのに、強いてそれをやれと、どうして無茶なことを言うのかと反発される人も多いと思う。私の場合、振り返ってみると、そういう冷たい断りの嵐の中でも逃げずに訪問営業に取り組むことができた時期がある。それは2人1組で訪問営業活動をやっていた時である。その時は先輩や同僚がいるので、おいそれと逃げ出すことはできない。それが歯止めとなって、冷たい断りを受けてもある程度水に流して、次の訪問先に向かうことができた。冷たい断り文句を二人で分散できていたような感じだった。訪問先から受けるダメージも軽く感じた。ここで教訓として得たことは、私のような場合は、自分ひとりで不安や恐怖を抱えたまま、目の前の仕事に取り組んでいくということは大変難しいことだ。のべつ幕なしに不安や恐怖を抱えたまま、イヤイヤ仕方なしにでも仕事をしなさいというよりも、このように視点を少し変えれば目的が果たせる場合があるのだ。自分をサポートしてくれる仲間がいれば、すぐに逃げ出さないで、目的を達成できていたのだ。さぼらないので1日中仕事をするので、一人で営業活動をするよりも、成績は良かった。だいたい営業マンは上司の目がないので、使命感が強くない限り、容易にさぼり癖がついてしまう。そういう場合は、ここに症状の克服の何かのヒントがあるのではないかと思った。考えてみれば、倉田百三氏が普通の人では考えなれない強迫観念で悩まれたとき、森田先生が症状で苦しくても休まないで筆を執りなさいとアドバイスし続けた。倉田氏は、そういうサポートを得て、森田先生に素直に従って強迫観念を乗り越えていかれた。森田先生の日記指導と面談による親身なサポートがなかったとしたら完治は望めなかったと思う。神経症を乗り越えるというのは、森田理論もさることながら、「森田正馬」という人の存在が大きくかかわっていたということだと思う。だから神経症で悩んでおられる方は、森田理論を学んで自分一人で乗り越えようとするよりも、人の力を借りて乗り越えようと柔軟に考えられたほうがより現実的であると思う。そういう意味では、困難に陥ったとき、集談会の仲間や尊敬する先輩をイメージすることができることは大きな意味がある。不安や恐怖で押しつぶされそうになったとき、何かあったら多くの仲間たちやあの先輩が話を聞いて相談に乗ってくれる。さらに症状の真っただ中の仲間たちも不安や恐怖にさらされながらも頑張っているのだと思えれば不安や恐怖には確かに耐えやすくなる。そのためには、1回や2回の参加だけではそんな人には巡り合うことはないだろう。最低でも1年ぐらいは参加していると、自然にそういう先輩や仲間を見つけることができる。森田理論の理解は、そういう状態が土台としてできた後に、少しずつ身に着けてゆけばよいと思う。
2017.08.12
コメント(0)
-
ブログにアップしている写真について
現在ブログにアップしている場所はどこですかという質問がありました。ご存知の方もおられると思いますが、和歌山県串本町にある「海金剛」です。日本の自然100選に選ばれているところです。インターネットではもっとよい写真がアップされているのでご覧ください。自然の美しさと圧倒的なスケールで思わずあとずさりしそうになる場所です。これぞ自然という感じです。このほか私の訪れたところで、度肝を抜かされたところは、鹿児島県与論島のシュノーケリングで見たサンゴ礁、北海道の摩周湖、知床半島のオシンコシンの露天風呂、礼文島の西海岸、長崎の九十九島、奥日光の白樺林などです。なにしろ大学では旅行研究会に入っていたため、日本全国あらゆるところに足を運んでいます。
2017.08.11
コメント(0)
-
興味のあることの棚卸
神経質者の性格特徴の1つに、普通の人と比べて好奇心が強いと言われています。森田理論でいうと「生の欲望」が強いということです。集談会で時々自分は意欲ややる気がない、つまり生の欲望があまり強くないという人がいます。それは注意や意識が自分の症状一点に向けられているために、「生の欲望」に向かうべきエネルギーが少なくなっている状態だと思われます。症状に向けられていたエネルギーが減少してくると、あり余ったエネルギーは、神経質性格者であれば、「生の欲望の発揮」に向かうのが自然だと思われます。その特徴を生かして生活するということは、神経質者の場合はとても意味があることだと思われます。私の場合は、森田先生の普段の生活を見ていて、「一人一芸」を身につけることから始めました。生活の発見会の一泊学習会に参加した時、夜の懇親会で余興が予定されていました。なんでもよかったのですが、当時勤めていた会社の近くにアルトサックスの教室がありました。早速、そこに入会して、 1カ月間でなんとか「ロンドンデリィ」という曲を吹けるようになりました。さっそく披露しましたが、本番では失敗してうまくいきませんでした。でもそこからずっと毎日のように練習をしています。コツコツ続けてもう10年以上になります。そのうち、今所属しているチンドン屋のグループを見つけました。その人達に演奏を教えてもらっているうちに、今では100曲以上の曲を演奏できるようになりました。今では500人以上の観客がいる場で、緊張しながらでも、何とかこなせるようになりました。私は対人恐怖症で、本番前は胃が痛くなるほど緊張するのですが、反面、良い演奏をしてみんなから拍手喝采を浴びたいという欲望が非常に強いことがわかりました。私はそれから自分の興味のあること、やってみたいことなどを整理してみました。それを大分類してみると、コンサート情報、サックス関連、習い事情報、健康情報、花見情報、旅行情報、瀬戸内海島めぐり、釣り情報、スポーツ情報、イベント情報、生活の発見会情報、映画、ビデオ、テレビ番組、書籍情報、公共施設利用情報、株式情報、 fp情報などがありました。これらをさらに小分類して、具体的に 50項目以上書き出しました。そして、それらの情報の収集方法を調べました。私は人の思惑が気になって仕方がないという特徴があります。それらを抱えたまま、自分の好きな事には何でもかんでも足を運んで見に行ったり、自分でも試してみるようにしました。会社での人間関係は依然として苦しいことが多かったように思いますが、その分仕事以外で発散できました。気がつけばいつもやめようやめようと思っていた仕事を定年まで続けることができました。それ以上に仕事以外の知り合いがたくさんできて、今でも交流が続いています。様々なことに取り組んだので途中でやめたものもたくさんあります。その中で、いまも続いているのは、生活の発見会活動、コンサート、サックス演奏、老人ホームの慰問活動、獅子舞、浪曲奇術、どじょうすくい、しばてんおどり、ブログの投稿、健康麻雀、趣味の花つくり、バス旅行、プロ野球観戦、図書館巡り、自然公園巡り、株式投資の研究、 financial planの勉強などです。過去に作った資料の一部をご紹介します。大分類にあたるものです。 私は森田先生の好奇心旺盛なところをまねてみようと思い、趣味ややってみたいことの棚卸をしてみました。 すると、たくさん出てきました。私もとても好奇心旺盛だなと思いました。 コンサート情報 市の情報誌による検索、区民文化センター行事 クラッシック観賞、警察、消防、自衛隊の音楽隊の観賞、アマチュアオーケストラ サックスの情報 チンドン屋の情報 練習場所 楽器情報 グループ情報 習い事情報 ブログ、デジカメ画像処理、DVD加工、パソコン活用情報 川柳、ユーモア小話の作り方 安来節、どじょうすくい 獅子舞い 浪曲奇術 しばてん踊り 蕎麦打ち、加工食品、燻製作り、男の料理教室、魚のさばき方 第9合唱団員参加、健康麻雀、自家用野菜作り、大菊仕立て 健康情報 ヨガ、水泳、卓球、ハイキング、魚釣り 花盆栽情報 季節の花見情報 盆栽展 ラン展 菊花展 五月展 花ごよみ作成 公園、植物園情報 旅行情報 工場見学、ビール工場見学、博物館、美術館、温泉情報、グルメ イベント情報 祭り、プロ野球、サッカー、イベント情報、写真展、公開講演情報 映画、テレビ、ビデオ、書籍情報、落語情報 公共施設利用情報 みなさんも趣味などの棚卸をして、常にアンテナを四方八方に張って、有用な情報の取得に力を入れてみてはどうでしょうか。生活がすぐに活性化すると思います。
2017.08.11
コメント(0)
-
鋸の目立てについて
森田先生の話です。今日、患者が、鋸で木を切っているところを見たが、ここの患者は、鋸の種類を選ばないうえに、いくら鋸が切れなくとも、平気でひいている。鋸の切れ味などはまったく無頓着である。職人は、道具は大事にして、常にこれを研いでいる。素人は、その研ぐ時間で、少しでも木をひいた方が、その時間に、余計に能率が上がると思っている。それは大きな間違いである。先日も材木屋で、木挽をみたが、鋸の目立てを、 1日に3回ばかりもやり、 一回に40分くらいもかかるということである。素人が考えて、無駄な時間が、実は最も大切な時間である。(森田全集第5巻 251頁より引用)鋸の切れが悪くなれば、普通は木を切るのを中断して、目立てを行う。職人さんは、木を切っているよりも、鋸の目立てに費やす時間の方がはるかに長いという。神経症で苦しんでいる人も、鋸の切れが少々悪いということには気がついていると思う。しかし、木を切るのを中断して、目立てを行うという方向にはいかない。切れが悪くてもイライラしながら無理やり木を切ろうとする。自分は大工で生計を立てているわけではないので、時間がかかってでも、言われたことさえすればよい。ましてや自分が進んでやり始めたことではなく、他人から言われてとりかかった仕事の場合には、早く終わらせてその仕事から逃げたいという気持ちが強いので、鋸の目立てには注意が向かない。なかには、この鋸はもうダメになってしまったから、新しい鋸を買ってくるしかないと考えてしまう。そして切れなくなった鋸が数多く放置され錆びてくる。最後にはまとめて処分してしまう。鋸にとってみれば、目立てをしてくれれば、新品と同じように切れ味が鋭くなるのに、どうしてそんなに簡単に見捨ててしまうのかという気持ちであろう。そういう人はものだけではなく、自分や他人も役に立たなければ拒否したり、否定するという考え方だ。うまくいかない現実に対してイライラしたり投げやりになってしまう前に、それらを改善する事は考えられないのか。森田理論では、その原因を見極めて、問題点を解消しようとする態度をとても重要視している。そのためには、不具合や問題点はそのまま放置すれば心身共に苦境に陥るが、それらに対して改善や問題解決の方向に舵を切っていくことがとても大切となる。エジソンは汽車の機関士をしていた時、いつも寝坊をして仕事に間に合わなかった。そこで投げやりになるのではなく、時間になったら起こしてくれる目覚まし時計を発明したという。これは自分だけではなく、多くの人にも役立つ発明品となった。神経症で苦しむ人は、注意や意識の大半を自分の症状一点に集中させている。そのために、目の前に与えられた仕事を機械的にこなすのが精一杯である。これでは、不具合や問題点に気づいたり、発見するということが殆どできない状態である。神経症から回復したいと思うなら、症状と格闘することやめて、目の前の仕事や家事などに今までよりも少しだけ身を入れて取り組むことである。そしてその中で気づきや発見、楽しみや面白みが出てくるという状態を作り出すことがとても大切なのである。そうして頭の中で症状1点に集中していた注意や意識が、少しずつ低下してくるということが、神経症が回復してくるプロセスなのである。
2017.08.10
コメント(2)
-
「自己を赤裸々に打ち出す」ということ
森田先生は周囲の人々に対して自己を「赤裸々に打ち出す」ことが大切であると言われている。自分の気にくわない容姿や性格、恵まれない境遇や自分の能力、弱点や欠点、ミスや失敗などを隠したりしないで、事実をそのまま他人の前に公開していくという態度である。神経質者の場合は、そんなことをすると、自分がますます惨めになり、ピエロを演じているような気分になると思っている人がいる。自分の周りに人が寄り付かなくなり、完全に孤立してしまう。そうなれば社会的には死んだも同然である。命に代えても絶対に人の目に付かないようにごまかしたり隠したりしなければならない。できれば、装飾して少しでも誤魔化してよく見せたい。 人並み以下に見られる事は、自分自身が許せないのだ。こういう人は確固たる「かくあるべし」を持っている人だ。頭の中で考える理想の自己像を持っている。「かくあるべし」を持っている人は、自分という1人の人間の中に、 2人の人間が住みついている。1人の人間は雲の上のようなところにいて、地上で様々な問題に直面して右往左往している現実の自分を見て、いつも批判をしている。存在を認めるということはなく、いつも自分の存在を否定しているのである。自分という1人の人間の中で、 2人の自分がいがみ合って喧嘩をしているような状態である。そんな状態で生活していると、本来は仕事、家事、育児などの日常茶飯事や、自分のやりたいことなどに向かうべきエネルギーを喧嘩の仲裁に投入せざるをえなくなる。自分も苦しいが、周囲の人も腫れ物を扱うかのごとき対応になる。これを打ち破る方法は、事実を素直に認めて、出来る限りその事実を他人に包み隠さず公開していくことである。中学時代テストの答案が返されると、普通の人はすぐに机の中に入れて、人の目に触れさせないようにする。まして、その点数が平均点をはるかに下回る場合、急いで隠さないといけないと考えてしまう。同級生に勉強のできない馬鹿な奴だ見られたくないのである。能力がない人間は人生の落伍者とみなされることがたまらないのである。しかし自分ではうまく隠したと思っても、他の人から見ると、すぐに隠すということは、あまり良い点数ではなかったのではないかと思われてしまう。そんな時、平均点を大きく下回る点数の人が、その答案用紙をみんなに見せている。そのような同級生は、あらゆる面において自分を飾りたてたりすることがない。正味の自分を事実のままにさらけ出すことができるのである。自分の欠点や弱み、家庭内の出来事、失敗などを、まるで手柄のように面白おかしく脚色して笑いを振り撒いているのである。彼の周りには笑いが絶えない。彼も相手も構えるということがないので、いつもリラックスして付き合うことができる。反対に、我々のように容姿や性格、生まれ持った環境、自分の潜在的な能力、弱点や欠点、ミスや失敗などを人目にに付かないように、隠すことに汲々としていると、周囲の人もそれを察知して人が寄り付かなくなる。自分の都合の悪い事を、どんな手段を使ってでも隠そうとしている人を見ると嫌悪感を催す。それは悪事を働いた政治家が、都合の悪い事実を隠そうとすればするほど、一般国民から見ると嫌悪感を催すのと同じことだ。次のの選挙では、そういう人には投票したくない。また、その人が所属している政党は絶対に支持したくない。これと同じようなことが、我々神経質者にも起こりうるのである。集談会で出会った人の中に、人前で自分が隠したいことを話すという事は、自分に対する自覚を深めることになり、自分のダメな事実に服従し、より自分のあるがままの姿になっていくことではないかと思いますと言われていた。自分のミスや失敗を面白く分かりやすく人に説明することは、工夫や準備もいるし、勇気もいる。そういうことに気が向いていく人は、神経症とは無縁の人だと思う。
2017.08.09
コメント(0)
-
☆「かくあるべし」と「夢や目標」の違いについて
「かくあるべし」と「夢や目標」には共通点がある。それは両方とも、意識や注意が今現在ではなく、遥か彼方にあるということだ。そのためか、この2つを混同して考えることがある。共通点はあるが、この2つは似ても似つかない違いがある。今日はこれについて考えてみたい。「かくあるべし」は自分の頭の中で考えた理想を意識している。こうでなくてはならない、こうであってはならないなどは、すべて現実の事実を無視して、現実を自分の頭で考える理想に近づけようとする態度である。「かくあるべし」は、自分の立っている位置が、現実とはほど遠く、雲の上のようなところに立っているのである。その地点から、事実、現実、現状を見降ろしていると、理想とはほど遠く、我慢がならなくなる。自分の容姿や性格、能力や境遇、欠点や弱点、ミスや失敗などを素直に認めて受け入れることができないのだ。そこで事実を修正、改造しようとする。また、その事実をねじまげたり隠そうとする。そこにエネルギーの大半をつぎ込んでいるので、本来やるべき仕事や日常茶飯事がおろそかになる。しだいに観念と実生活の悪循環が始まるようになるのだ。そういう人は、他人を見る場合も、自分以上に「かくあるべし」という物差しで善悪の判定をするのである。自分の頭で考えた理想に他人を合わせようとするのである。自分のやることなすことを否定してくるので他人にとっては面白くない話である。自分の存在や問題点などの事実を否定された人は当然反発してくる。そのうち「かくあるべし」を正面に押し出して、人と付き合っている人は敬遠されるようになる。その結果、ますます対立を深め、さらに「かくあるべし」を強引に押しつけてしまうということになりがちである。森田理論学習では、 「かくあるべし」を少なくしていくことが実践目標となる。そのためには、どんなに気に食わない事実、現実、現状であっても、まずはそれらを素直に認めていきましょうということになる。その方法はこのブログで述べてきているとおりである。次に「夢や目標」も遥か彼方に視線を向けている。視線は今現在自分の立っているところから、遥か上にある「夢や目標」を見上げているといえる。「かくあるべし」と違うのは、 「夢や目標」の達成に向かって、努力精進してゆきたいという気持ちを持っていることである。つまり現在の自分の立ち位置が、事実、現実、現状にあるといえる。事実を認めているのだ。ここが決定的な違いである。そして今の自分には、 「夢や目標」との間に大きな乖離があるというこを素直に認めている。次に「夢や目標」の達成に向かって問題点や壁を乗り越えて、階段を一歩一歩登ってみたいという気持ちを持っている。次第にやる気や意欲が高まり、生きがいを持てるということにもなる。これは森田理論で言えば、生の欲望の発揮に邁進している状態である。「かくあるべし」と「夢や目標」というのは、同じように事実、現実、現状とはかけ離れたところに注意や意識があるのだが、その中身を見るとまるっきり違う。その大きな違いは、自分の立ち位置である。現実に身を置いて、下から上目線で見上げているのか。あるいは雲の上のようなところに身を置いて、上から下目線で現実を見ているのかの違いである。森田理論を学習していると、上から下目線が少なくなり、下から上目線でものを見るように自分自身が変化してきたと感じられるようになる。「かくあるべし」が少なくなると、葛藤や苦悩で苦しむことが少なくなるので、とても生きやすくなるのである。
2017.08.08
コメント(0)
-
森田先生の真意を考えることの大切さ
形外会の記録にこんな話がある。松本さんが森田先生に質問した。森田先生が「絶えずハラハラしているようであれば、神経症がよくなる」と言われた事は、自分は1人で自分の部屋にいるときには、その必要はないのではないか。松本さんは、仕事をしているような時はハラハラしていてもよいが、家にいるときはリラックスして精神が弛緩状態になっても構わないのではないか、といわれているのだ。これに答えて森田先生は次のように言われている。松本君の質問の仕方は、自分をハラハラさせなければならない、自分をかくあらなければならぬと、人為的に作為しようとするものである。ハラハラというのは、あれもしなければならない、これもしたいという欲望の高まることであって、これがために自分の異常に対して、ひとつひとつこだわっていられなくなり、そこに欲望と恐怖との調和ができて、神経質の症状がなくなるのである。ちょっと考えると、忙しくて気が紛れる、という風に解釈されるようであるけれども、決してそれだけでは無い。ここの療法で、その症状だけは、単に苦痛もしくは恐怖そのものになりきることによって、治すことができるけれども、これが根治するのに、さらに欲望と恐怖との調和を体得することが必要であります。 (森田全集第五巻 112ページより引用)このやり取りを私なりに考えてみた。松本さんは、神経症を治すためには仕事を見つけて、いつも精神状態を緊張させておくということは大切だということはわかりました。だから糸車を回しつづけるハツカネズミのように、日中は動き回ればいいですね。でも日中動き回っていると、夕方には心身ともに疲れてきます。そんな時は緊張状態から解放してあげて、心身を休ませてあげる必要があるのではないですか。それだけ聞けばもっともな理屈のように思えてくる。しかしこのような論法で森田理論に議論を吹っかけていけば、なかなか話が噛み合っていかない。議論を噛み合わせようとすると、どうすればいいのだろうか。それは森田先生が形外会に集まった人に対して何を伝えようとしているのかを考えることだと思う。森田先生は、神経症を治すためには、神経を四方八方に張り巡らせて、 「無所住心」の生活態度の養成が極めて大切であると言われている。神経症に陥った人は、自分の気になる症状、一点に神経を集中させている。一点に集中された注意や意識が、周囲にまんべんなく分散されるようになると、症状だけに関わっておられなくなる。すると、精神交互作用が働かなくなってくる。神経症がアリ地獄のそこに落ち込んで、固着してしまうということを防ぐことができる。観念上の悪循環、行動の悪循環を断ち切ることができるのである。反対に、生活のほうは張り合いが出てきて、観念上の悪循環がなくなり、行動の良循環が始まるのである。松本さんは、頭の中で、 1日中緊張状態で生活していると心身ともにおかしくなってしまうのではないか、と考えられたのであろう。森田理論を学習していると、言葉尻にとらわれて、ああでもない、こうでもないと議論する方向に向かうことがある。こういう時は、森田先生が手を変え品を変えて何を我々に伝えたいのだろう、という原点に戻って考えてみる必要があると思う。我々は森田理論から神経症からの解放、神経質性格者としての生き方を学びたいのであって、森田先生の言われていることが、正しいとか間違っているとかの判定をしているわけではない。
2017.08.07
コメント(0)
-
陶芸家河井寛次郎氏の言葉
陶芸家、木彫家、詩人の河井寛次郎さんは優れた言葉を残されている。その優れた作品は島根県安来市の足立美術館に展示されている。その一端を紹介します。仕事が仕事をしてゐます仕事は毎日元気です出来ない事のない仕事どんな事でも仕事はしますいやな事でも進んでします進む事しか知らない仕事びつくりする程力出す知らない事のない仕事聞けば何でも教へます頼めば何でもはたします仕事の一番すきなのは苦しむ事がすきなのだ苦しい事は仕事にまかせさあさ我等は楽しみませう仕事が仕事をしてゐる仕事暮らしが仕事 仕事が暮らしこの詩を理解するには「仕事」を、例えば「森田先生」に置き換えてみてください。この詩は全く趣を変えて、私たちに何かを訴えかけてきます。何事にも情熱を持って取り組んでおられる森田先生の姿がありありと目の前に浮かんでくるようです。手考足思(しゅこうそくい)という詩も味わいがあります。私は木の中にいる石の中にいる、鉄や真鋳の中にある人の中にもある。一度も見た事のない私が沢山いる。終始こんな私は出してくれとせがむ。私はそれを掘り出したい。出してやりたい。私は今、自分で作ろうが人が作ろうがそんな事はどうでもよい。新しかろうが古かろうが西で出来たものでも東でできたものでもそんな事はどうでもよい。すきなものの中には必ず私はいる。この文章は森田理論でいう「物の性を尽くす」を頭の片隅において読んでみることをお勧めする。その際「私」を「潜在能力」あるいは「存在価値」と置き換えて読んでみたらどうだろうか。すべての人間は自分の潜在能力や存在価値を、何とかこの世で生きている間に花開かせたい。自分だけではない。他人、物、時間、お金もその持っている潜在能力、存在価値を存分に発揮してその使命を果たしたいと願っているのだ。それらにたいしての絶対的な信頼感や包容力がないと、できることではない。
2017.08.06
コメント(0)
-
欲望の暴走について
アフリカでは原始的な焼き畑農業で生計を立てている部族がいるようです。焼き畑農業は、集落のまわり森を10等分に分けて、それを順番に焼き払って耕作するそうです。食料の量は、部族の人間が1年間に食べられる分しか作らないそうです。もっとたくさんの食糧を得ようと、いつもより多く森を焼き払えば、短期的には多くの食料を確保できます。しかしそんなことをすれば多くの畑がやせて、作物が育たなくなり、飢饉を招きかねません。だから原住民たちは、今はひもじい思いをしても、多くの森をいっぺんに焼き払うということはしないのです。そして子孫代々まで食料の安定供給を目指しているのです。普通人間には欲望や本能があります。でもそれらが行き過ぎると問題が生じます。人と争いを起こす。環境破壊を起こす。挙句の果てには自分たちの首を絞めるようなことになる。アフリカで、焼き畑農業で生活している人はそのことがよく分かっています。自然に本能や欲望の歯止めがかかっている。自動車でいえばアクセルとブレーキが正常に作動している。たくさんのジャングルを焼き払えば一時は収量も上がり自分たちの生活が豊かになることはよく知っている。でもそれでは、これから将来、子どもや孫の時代の生活は保障されない。だからけっして無理はしない。将来のことを考えて果てしのない欲望は制御しているのです。それをよく理解しているだけではなく、実際に行動として実践できていることが素晴らしい。翻って現代人はどうか。快適、便利、快楽、飽食の欲望が暴走してもう制御不能である。車のブレーキが故障して制御できない。それなのにアクセルを踏み込んでいる状態である。さらに下り坂に差し掛かっている。この先どんどん勢いを増してスピードが上がる。将来は暗澹たる閉塞の時代が予想される。欲望の暴走が今や地球を破壊しようとしている。こういう状態は一つの欲望の充足が、次々と新たな欲望を作り出して、それ自体が目的となってしまっている。アフリカの人たちのような欲望と不安の調和がとれた考えはどだい無理な状況にある。それが分かるのは人類が破滅する時かもしれない。その時になって初めて、欲望の暴走は間違いだった。少々不満や生きづらさがあっても、欲望を制御しながら生活することが大切だったのだと気が付くのだ。破滅というのは、ある超えてはならない一定の限界点を超えた時、急速に終焉に向かって突き進む。その時の手立てはすべて無駄である。水の泡なのに、欲望の暴走をだれも止めることができない。今我々の出来ることは、欲望の暴走がとんでもない段階に差し掛かっているということを自覚することである。そしてとりあえず、欲望には近づかないことである。できるだけ我慢することだ。近づいてしまうとバランス感覚がマヒしているのだから、どうしてもなし崩し的に欲望に負けてしまう。物欲、所有欲に対しては、今持っているものや今あるものの存在価値を見直すことである。何か欲しくなったら、今あるもので何とかならないだろうか。改良できないだろうか。レンタルで済ますことはできないだろうか。などと考える癖をつけていくことである。森田でいう「物の性を尽くす」ということである。そして社会の問題、例えば原発問題にしてもそうゆう視点から考えてみることである。核廃棄物処理が出来ない状態で原発再稼働は子孫にそのつけを押しつけることになるのは間違いない。ましてモンゴルの地下深くに埋め込むなどという発想には言葉を失う。原発再稼働を拒否するということは、電力の使い放題は許されないということでもある。計画停電も受け入れて生活を見直す用意があるかどうかを、我々人類は問われていることにもなる。そういう方向がいいか悪いかを議論するよりも、そうしないと早晩現代文明は跡かたもなく崩れ去ってしまうということが、高い確率で予測できるのである。
2017.08.05
コメント(0)
-
株式投資に森田理論を活かす
人間の心理は不思議なものである。例えば、株式投資をしている人が株を売買する場合、最初に利益目標を立てる。普通はその株が順調に上昇して10%の利益目標を達成すると決済する。これはいわゆるスィングトレードといわれる場合のやり方である。例えば、総額100万円の株だったら10万円の利益が出ると手じまいをする。その途中で現在その株が7%上昇しているとする。 7万円の含み益が出ているのである。このまま上昇して利益確定になるかと思っていると、そこから急に反転して下がってくることがある。株式投資では日常茶飯事のことである。なにしろ株価の動きは風船球のようなものだからだ。7万円の含み益が出ていたのに、その含み益がどんどん減少して、 4万円程度の含み益に減少したとする。売買ルールを持っていない投資家は、ここで大変動揺するのだ。慌てふためく。すると、最初に立てた利益目標はすっかり蚊帳の外になってしまう。4万円の含み益がこれから先、まだまだ値下がりしてゼロになるかもしれない。あるいは最悪マイナスに転じるかもしれない。そのような恐怖に襲われるのである。そこでどんな行動をとるか。 4万円の含み益があるときに慌てて手じまいをするのである。「ヤレヤレ、思っていたほどの利益はとれなかったが、ある程度の利益が取れたので、このトレードは成功した方である」と思ってしまう。本当にそうだろうか。こういう考えの人で1年トータルで資産を増やしているという話を聞いたことがない。このやり方はトレードとは言えないと思う。競馬やパチンコなどと同じようなギャンブルである。このようなやり方では決して資産形成には結びつかない。むしろ虎の子の財産を失うだろう。本来は自分の立てた売買目標、売買ルールを首尾一貫して守っていくことが重要となる。腹を据えて、途中少々儲かっていても、最初に立てた、例えば-2万円のロスカットにくるまでは、どんなことがあっても動かない。静観する。反対に、予想通り含み益が出てくると、 仮に5万円の含み益が出たときに、そこから-2万円の3万円にロスカット位置を引き上げる。下がっても許容範囲の場合は、慌ててロスカットなどはしない。 7万円の利益が出たときに5万円まで下がってきた時に初めてロスカットをする。 9万円の利益が出たときは7万円まで下げた時にロスカットをする。そのようなやり方でロスカット位置を引き上げて、最終目標を目指していくのである。このようなロスカットのやり方をトレイリングストップという。そのようなやり方で、途中少々値下がりして苦しい時を乗り越えることが常道となっている。株式投資をギャンブルと同じように取り扱っている人は、最初から思惑が外れて値下がりする銘柄があると仕事が手につかないほど頭の中がかき乱される。そんなときに、その人の本性がすぐに現れる。例えば-2万円、-3万円の含み損が発生したとする。まともなトレーダーはこの段階でロスカットをする。最悪でもー5%を下回るとすぐにロスカットをする。すぐに手じまいをしなければ取り返しのつかなくなることをよく知っているのだ。ところが、株式投資をギャンブルなみにやっている人は、損失を確定することをとても嫌がるのである。あるいは、この株は雑誌で推奨銘柄として取り上げられていたし、そのうちきっと反転してくれるに違いないと希望的観測で待ち続けてしまう。なかには思惑通り反転する場合もあるだろうが、ほとんどは自分の願いとは反対の方向に向かうことが多い。そして、含み損が-10万円、-15万円と膨らむ事は日常茶飯事である。そうなると最終的にはやけくそになってしまい、「どうにでもしてくれ」という投げやりな気持ちになるのである。経済的な損失もさることながら、精神的な苦痛も相当なものである。まともな株式投資をしている人は、最初に決めた自分の売買ルールをきちんと守っているのだ。株価が下がってロスカット位置にくれば、自動的に損切りをして手じまいする。株価が思惑通り上昇し始めると、どこまでも最終利益目標を目指していく。途中下がってきた時でもトレイリングストップを活用して、ロスカット位置を切り上げて、安易に途中で降りることはしない。できうる限り目達達成のために粘るのである。これが株式投資の世界から退場させられることなく、資産形成に結びつく道であると考えられる。なお、この投稿は決して株式投資を推奨しているものではありません。安易な気持ちで手を出すと財産を失うこともある。むしろ何もしないほうが資産を減らさない人のほうが多い。私はファイナンシャルプランナーなので、たまに株式投資の相談を受けるので投稿してみたのです。現在は他人の弱みに付け込む悪徳業者が鵜の目鷹の目で獲物を追っているので気を付けたほうがよい。この投稿は、株式投資にも森田理論の考え方が役に立つと考えているので、思い切って投稿してみたのです。
2017.08.04
コメント(0)
-
神経症の治癒のイメージ転換について
神経症の治癒とは、症状に対する心のとらわれからの解放であって、症状それ自体が消滅することではない。心臓発作恐怖症者の人の場合であれば、その発作神経症が治癒した後でも、心臓が鼓動を止める事はありませんし、死の恐怖、それ自体が人間の心の底から去ってしまうことはないのですから、恐怖と不安は恒常的なものだと言わざるをえません。心臓発作を一再ならず経験し、これを恐怖した人から、恐怖を完全に払い去るといったことができるはずもありません。対人恐怖症の人は、他人の視線が気になるという気分から完全に自由になるわけにはいきません。森田先生も次のように述べている。これらの症状それ自体は存在してもいいのだ、症状は存在していても、それのみにとらわれることなく、生の欲望にのっとって人間としてなすべきをなしていくという態度が形成されること、つまりこれが神経症の治癒である。神経症とは、過度の意識が特定の1点のみ、例えば心臓の鼓動とか、他人の視線とか、そういう特定の1点に局限され、その1点以外への意識性が希薄化した心の状態です。従って人間感情のすべてに意識がまんべんなく行き渡り、特定の1点への意識集中が相対的にその「水位」を下げていくこと、これが神経症の治癒だということなのです。ですから、症状が跡形もなく消えるのではありません。症状は詮索すればまごうことなく存在しているのですが、それの意識の集中がなくなること、これが神経症の治癒だと言うことになるのです。 (現代に生きる森田正馬の言葉1 渡辺利夫 24ページより引用)渡辺先生は神経症が治るということについて、的確にわかりやすく説明されていると思う。私たちは普通神経症が治るということイメージする場合、傷口が跡形もなく修復されることを願っている。しかしそういう目標を立てた場合、いつまでも神経症と格闘することになり、いつまでたっても治らない。跡形もなく治ることをイメージしているので、思想の矛盾に陥るのである。対人恐怖の人であれば、他人の思惑が全く気にならなくなり、あっけらかんとした別の人格を持った人間に生まれ変わり、自分の思い通りの人間関係を築いていけるようになりたい。つまり神経質性格が発揚性気質の性格に変わってしまう事イメージしているのである。しかし自分が持って生まれた神経質性格は変えることはできません。不可能なことにチャレンジすることはエネルギーの消耗を招き、自己嫌悪や自己否定の道へ突き進むことになります。ですから、そのような治り方をイメージしている人は、イメージを変える必要がある。そのときに参考になるのは、渡辺先生が説明しておられる上記の説明である。そのように言われても、今現在神経症で苦しみ、なんとかその苦しみから抜け出したいと思っている人は納得できないかもしれない。実生活の悪循環が始まると蟻地獄の底に落ちたようになる。そういう場合は応急的に蟻地獄の底から地上に抜け出す道がある。少し遠回りにはなるが、症状は横に置いて、目の前の必要なことを嫌々仕方なく手をつけていくことである。これは神経症に陥った人が最悪の状態から抜け出す時のための特効薬である。これについては良いとか悪いとか評価をする前に自分の体験で確かめてみればすぐに分かることである。問題はその次にある。観念の悪循環と実生活上の悪循環が断ち切られたとしても、その先に神経症の治しかたに対するイメージが間違っていると、神経症の苦しみや葛藤はさらに続く。むしろ増悪していく。このことは、私が長い間苦しんできたことである。その苦しみや葛藤がなくなってきたのは、まさに渡辺先生が言われているように、治り方のイメージが変わってきたことにある。つまり、人の思惑が普通の人以上に気になるという神経質性格は変えることはできない。性格を変えるための努力はエネルギーを消耗するし、不可能なことなのである。そういう心配が常につきまとうのは、私の特徴である。いや、むしろ個性といった方がよいかもしれない。それよりは神経質性格が持っているプラスの面を引き出して、とことん生活の中で活用していく方向が自分の生きる道ではないのか。治し方のイメージを、人の思惑を気にしないようになる人間になる事を目指すのではなく、それを個性として捉え、その個性の発揮に邁進していくことに転換してきたのである。そうすると実生活が好循環をもたらすようになり、人間関係も改善し、生きる葛藤や苦悩が急速に小さくなってきたのである。
2017.08.03
コメント(0)
-
不安定の姿勢から学ぶこと
森田先生は安定した姿勢よりも、「不安定」な姿勢を勧めておられる。我々が起立する時、両足を広く開き、固く踏みしめているときには、全く安定の姿勢であって、この状態では、少しも周囲の変化に応ずることができないので、ちょっと何かに突き当たられても、直ちに倒れてしまう。これに対して体操の時の「休め」の姿勢、すなわち片足で全身の重さを支え、他のほうの足を浮かして、つま先を軽く地に触れている態度は、いわゆる「不安定」の姿勢である。このときには、そのつま先で鋭敏に身体の動揺を感じることができて、周囲の変化に対して、迅速に適切に反応することができる。この「休め」の姿勢の少し足を開いたものが、剣道・柔道・薪割りなどの姿勢である。電車内でも「休め」の姿勢で立っていれば、つり革等をつかむ必要がなく、読書しながら、電車の動揺にも決してジタバタすることがなく、乗り換え場所を忘れることもなく、またスリにガマ口を取られるようなこともないのである。不安定の姿勢というのは、ことさら注意を1つのことに集中してないからこそできることである。これを生活の中で生かしていこうと思えば、 「無所住心」ということである。我々の心は最もよく働くときは、 「無所住心」と言って、心が四方に働いて、昆虫の触覚が、ピリピリしている時のように、ハラハラしている時である。剣道やピンポンのようなものは、間髪を入れない心の働きを要するもので、その時によくこの心境がわかる。必ず注意が1つのところに集中してはいけないのである。神経症で苦しむような人は、神経症の症状1点に注意を集中させている。注意を集中させると感覚が鋭くなる。いわゆる精神交互作用が発生して奈落の底へと落ちていくのである。そうならないためには、どんなに症状で苦しくなっても、注意を集中させないで、分散させることを心がけることだ。症状を軽減するために、症状と重点的にかかわり合うという態度ではなく、それを抱えたまま目の前の仕事や生活のことに注意を向けていくのだ。目の前のなすべきことに少し心を入れて取り組んでいけば、新たな感情が生まれてくる。そう言う状態が常態化すれば、自分の症状一点に悩んでいるというわけにはいかなくなる。症状を抱えたまま生活がどんどん前に進んでいくことになる。そうして、あとで振り返ってみると、症状のことは忘れていた。どうしてあんなに悩んでいたのだろう、と思えるようになる。これは実際に体験してみないとなかなかわからない。今現在、神経症で苦しんでいる人は、そんなこと言われても症状が軽くなるとは思えないのが実情だろうと思う。私も対人恐怖症で苦しい時、先輩から対人恐怖症の治し方については何もアドバイスをしてもらえず、実践課題の立て方やその結果の報告ばかりを求められた。その時は、求めるものが求められずイライラしたが、アドバイスに従って行動した結果、 1年も経つと会社の中で仕事ぶりが評価されるようになった。依然として人間関係では苦しむことが多かったが、意識を仕事の方にも向けていたので、四六時中対人恐怖症で苦しむという事はなくなった。それとともに、仕事で他人から評価されるようになったので、仕事を辞めることもなく続けることができたのだと思う。
2017.08.02
コメント(2)
-
株の達人から学ぶこと
株式投資で利益を出し続けている人の話は森田理論に通じるところがある。普通の人は、自分が買った株価が上がることだけを願って祈り続けている。しかし、株価は大空に放たれた風船のように風の向くまま気の向くままに勝手に動いていく。株価が下がって含み損が拡大してくると、本来は早く処分しなければならないが、いつか上昇してくるはずだと思っていつまでも持ち続ける。いわゆる塩漬け株である。反対に、株価が順調に上昇していても、ある日突然下げたりすると、自分の利益がなくなるという恐怖にとらわれて、少しの利益がある段階ですぐに処分してしまう。このパターンの繰り返しでは、利益は少なく、損失は大きいわけだから、長期にわたって、資産を増やすという事は夢のまた夢である。長期にわたって利益を出している人は、市場がどう動くかについては、全くわからないという。また自分の投資した株価が上がるか下がるかについても予測不可能であるという。そういう前提で株式投資をしているのである。マーケットは好き勝手に動いていく状況を認めなければならない。決して自分の期待通りに動いてくれることを期待してはならない。期待すると必ず裏切られる。負けたり裏切られると腹が立つ。恐怖や絶望が生まれてくる。自己嫌悪や自己否定する人も出てくる。マーケットはあなたに損をさせてやろうと思って意地悪を仕掛けてくる訳ではない。マーケットはあなたを毛嫌いしている訳ではない。適切に対応すれば、マーケットをあなたに利益をもたらすこともある。それなのに、マーケットが自分の思惑通りに動いてくれないからといって、投げやりになってしまうのはおかしなことだ。それでは、長期にわたって利益を出してる人はどう動いているのか。株価は動いてきた方向に素早く対応しているだけなのである。一旦買ってしまうと、株価の予想は全くしていない。「かくあるべし」を持たずに、マーケットによってつけられた今現在の株価こそが神様であるという考え方に立っている。そういう人は株を買った時点で、いくらまで下がったらロスカットをするということを決めている。たとえば100万円のお金を株に投資した場合、 2万円を超えて下がってきたらすぐにその株を売って損を確定してしまう。そうしないと、どんどん損失が拡大してしまう可能性がある。それはどうしても避けなければならない。次に、株価が上がってきた場合は、少しの利益が出た段階ですぐに利益を確定するということもしない。目標としては、 10%の利益を目指している。このスタンスで取り組んでいると5回失敗をしても、1回成功すれば、 プラスマイナス0となる。利益を出すためには、いろいろと研究して、その比率を少しプラスに持っていくという考えかただ。つまり、株価が上がるか下がるか予想はしないで、その変化に素早く対応するということにエネルギーを投入しているのである。現実を否定することから、将来に向かって何も明るい見通しは立たない。変化に全神経を集中して、その変化でいかに素早く対応するかということが、厳しい株式投資の世界で生き残る唯一の道である。株式投資の世界で成功するためには、これ以外にも、どういう銘柄を選べばよいのか。その株をどういうタイミングで仕掛けていったらよいのか。そして最終的にどういうタイミングで手じまいしていくのか。資金管理をどのようにしていくのかなど、いろいろと勉強しなければならない項目がある。普通の人は、それらを適切に行なえば、株式投資は必ず儲かるものであるという短絡的な考えかたを持っている。当然これらは徐々に勉強しなければならないことであるが、まず1番最初にきちんと理解しなければならないのは、マーケットは決して自分の思惑通りに動いてくれるものではないということである。それを理解したうえで、株式投資に取り組まないと、自分の大切な財産をドブに捨てるような結果となる。そのためには信頼できる人について正しい知識を身につけていくことである。自分独りよがりのやり方では決してうまくはいかないと思う。仮にうまくいっても長い時間がかかる。その方法は決して得策であるとは思えない。これは森田理論学習も同じである。私は信頼できる人に理論化された森田理論を正しく学んでいけば、約3年で森田理論を習得して、以後自分の人生は大きく花開いていくと考えている。
2017.08.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1