2000年12月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
「捕物の話」 【三田村鳶魚】
捕物の話(著者:三田村鳶魚/朝倉治彦|出版社:中公文庫) 三田村鳶魚先生である。名前はずっと前から知っていたが、初めて読んだ。 ですます調で、江戸時代の捕り物に関する蘊蓄が傾けられている。 ひとくちに江戸時代といってもその中で時期によっていろいろ違いがあり、世の中が変化していたことが分かる。 制度的にいろいろ問題がありながら、解決されぬままでいたことが多いらしい。江戸は治安のいい都市だったという話を聞いたことがあるが、これを読むと、どうも、江戸時代というのはあまり治安はよくなかったようにも思える。 当然の事ながら、著者は膨大な知識を持った上で書いており、「○○と言えば誰でも知っているが」などと書いてあっても、こちらには初耳だったりすることが多い。 不思議なのは、このシリーズ、最初に書かれた通りの順番になっているわけでないので、「このことは江戸の白波に書いておいた」などとあっても、それが6巻目になっていたりする。編者にはなにか理由があってこうしたのだろうが、読者にはちょっと不親切。
2000.12.22
コメント(0)
-
「三角寛サンカ選集(第1巻)山窩物語」 【三角寛】
三角寛サンカ選集(第1巻)山窩物語 (著者:三角寛|出版社:現代書館) うーん、よく分からない。 非常に面白いのだが、「ほんとうにサンカっていたのか?」という疑問は消えない。 写真もあるし、ほかの人と一緒に調査したこともあるのだから、おそらく、少人数ながらいたのだろう。著者が言うほどの人数がいたとは思えない。 そんなにあちこちにいたのなら、もっといろいろな人が研究していてもいいはずだ。 もし、この本に書かれているのが真の姿だとしたら、サンカを有名にし、それまでの生活ができないようにしてしまったのは筆者自身だということになる。 もとはと言えば朝日新聞社の記者だったので、自分が取り上げることに世間の目を向けさせようとはしても、それによって、書かれた対象がどんな目に遭うかは全く考えていないとしか思えない。 サンカに対して、関心を持っていることは分かるが、愛情があるのかどうかも分からない。サンカの妻を「これは凄(すご)くまずい顔の女房であった」などと平気で書く。 全く同じ女性を「お雪」「お花」「お菊」と、違う名で書いていて、少しずつ違う書き方をしているのも不思議だ。
2000.12.15
コメント(0)
-

「魂のラリアット」 【スタン・ハンセン】
魂のラリアット(著者:スタン・ハンセン|出版社:双葉社) 先頃引退を表明したスタン・ハンセンのレスラー人生回顧。 プロレスラーになる前に中学教師だったことがあるというのには驚いた。 もと教師レスラーは、馳浩だけじゃなかったんだ。 出てくるレスラーは、知らない人の方がずっと多いのだが、どのエピソードも実に興味深い。 アメリカでは、それぞれの地域にプロモーターがいて、独自のテリトリーを持ち、その中でサーキットを組んでいること。前座レスラーは給与が少なく、食うや食わずであること。 ハンセンもブロディも、駆け出しの頃は貧しく、空腹に耐えかねて法に触れるようなこともしたという。 テリー・ゴディが解雇であったこともはっきり書いてある。 鶴田についても、鶴田の方ではよく、修業時代にハンセンが鶴田の持ってきたインスタントラーメンを食べてしまった、ということを言っていたが、この本の中では、鶴田の実力を高く評価はしているもののあまり触れていない。 一度書き上げた後、鶴田の死を知り、書き加えた部分に、92年に鶴田が半引退状態になるまでは「私達はリングを降りた時に必ずしもベスト・フレンドと呼べるような関係でなかったが」と書いている。 こういうところも正直だ。 馬場さんに関しては全幅の信頼を置き、忠誠を誓っていたことはよくわかるが、義理人情というような湿っぽいものではなく、ビジネスを通じての信頼が基礎である点、やはりドライでアメリカ人らしい。 ビジネスの話の窓口がはっきりしている、ということは、ウィリアムスも言っていた。 また、シンは、「馬場と仕事をしてきたので、日本人は嘘をつかないのだと思っていた」と言っていたこともある。 ビジネス面での信頼が、人間性への信頼につながっているのだ。 ファンク兄弟には、プロレスラーにして貰ったという恩義は感じていても、ビジネス面とレスラーとしてのありかたに不満を感じていたので、リングの上でその不満を爆発させていたと正直に書いている。 とにかく、何事も正直に書いてあるので驚く。 その下で働いたことのあるプロモーターにつてい、尊敬も感謝もしていないとはっきり書く。 日本に主戦場を移してから、意識してブッチャーやシンのヒールぶりを観察し、彼らに学んでヒールとしての自分を作り上げてきたことも正直に書いている。 最後の最後に、全日本プロレスの分裂騒動についても触れているが、三沢たちの行動を非難したりはしない。 自分も、よりよい条件の職場を求めて移籍を繰り返してきたのだから、三沢たちにもそうする権利がある、と割り切っている。 それでも、全日本プロレスを「自分の会社」と思い、その復興に残りのレスラー人生を捧げる、という表明で終わっている。 引退を表明した、ということは、今年一年、傾いた全日本プロレスを支え、これからも会社が続きそうだという見極めがついたのだろう。 大変興味深く、また、感銘を受ける本なのだが、不思議でたまらないことがある。 ハンセンがこの本を日本語で書いたはずはない。(奥さんは日本人だが) 一体誰が日本語に訳したのかわからないのだ。奥付にも前書きにも訳者の名はない。どういうことなのだろう。
2000.12.08
コメント(0)
-
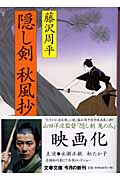
「隠し剣秋風抄」 【藤沢周平】
隠し剣秋風抄(著者:藤沢周平|出版社:文藝春秋) 舞台はいずれも架空の藩で、小藩のようなのに、命のやりとりにもつながる政争があり、超絶的な飛剣を編み出す剣士がいる。 そうした設定だけ見れば荒唐無稽にも思えるのに、そうならないのは筆力があるからだ。大袈裟に書かず淡々と書いている。 とくに、この本にまとめられているのは、主人公が精神的に弱い側面を持っていることが多く、それによって、小説の中の世界に奥行きが生まれている。 電車の中で読み終わり、ほかに本を持っていなかったので、最初の方をまた読み返したが、それでも面白かった。
2000.12.06
コメント(0)
-
「私説国定忠治」 【笹沢左保】
私説国定忠治(著者:笹沢左保|出版社:中央公論新社) 20年以上前に古本屋で買って、一度は読んでいたのだが、ほとんど覚えていなかった。 ただ、『やくざの生活』を読んだ時に、笹沢左保がこの本の中で、何かに反論していたはずだが、それは『やくざの生活』のことだったのではないかと思い、本棚から引っ張り出して読んでみた。 記憶は正しく、飢饉とはどういうものか、というところを引用し、それを否定している。 ほかにも否定していることがらがあるが、笹沢左保の方が冷静で正しいように思われる。 考証もしているが、基本的には小説である。想像で書いている部分がほとんどなのだが、国定忠治とはどういう存在だったのか、という点に関しては、資料に基づく考察の結果である。 尊皇派との結びつきがあったと思われる、という点は面白い。 たしかに、たかが上州のやくざでしかないのに、大袈裟な護送ぶりである。 それにしても、読む側に知識があるのとないのとでは、同じ本を読んで受ける印象が違うのか、というほど、今回は興味深く読んだ。
2000.12.02
コメント(0)
-

「そんな「日本語力」では恥をかく」 【日本語倶楽部】
そんな「日本語力」では恥をかく(著者:日本語倶楽部|出版社:Kawade夢文庫) ついついおかしてしまう間違いをあげ、正しくはこうだ、と指摘している。 今まで知らなかったことが随分あって勉強になった。 例えば、『「足」は足首から下、「脚」は「脚線美」のように胴から下の部分全体をいうことが多い』(p155)とあったが、中国語では「脚」は足首から先を指すので、ここは間違っているのではないかと思ったが、辞書を引くと、この説明があっていた。 疑問を感じたところ。 「生」と「産」の違いを説明し、「生」は子どもの立場から見た古戸は、「産」は母親の立場から見た言葉だ、と説明している以上、『母親なら、「長男が産まれました」でもかまわない』(p164)というのはおかしいのではないか。 主語が長男である以上、長男の立場から「生まれました」 意味が分からなかったところ。 『「善」のもともとの意味は、「膳」が語源であることからもわかるように』(p151) 「もともとの意味は~語源」という文には重複がありわかりにくい。また、「善」の字義は「ごちそう」という意味だ、ということをいいたいらしいのだが、これだけではそこまではわからない。
2000.12.01
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1










