2000年11月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-

「つぅさん、またね。」 【鶴田保子】
つぅさん、またね。(著者:鶴田保子|出版社:ベースボール・マガジン社) 今年5月、肝移植の手術中になくなったジャンボ鶴田の夫人が、出会いから死別までを綴ったもの。 マニラでの手術中の死、ということでさまざまな憶測が飛び、手術に成功しても半年の寿命だったという報道もあったが、ほとんどが誤報だったことがわかった。 肝炎に関しても、B型肝炎は、母子感染だったこと、キャリアと分かったのは、結婚から1年ほどしてからで、もしインターフェロンの注射をしていなかったら、何事もなく生涯を終えることができたかもしれないこと。 遺族の気持ちを考えない取材や報道に対しての憤りも抑えた筆致で書かれている。 「世話になったテレビ局」というのだから、日本テレビだろう。 また、入院中に、勝手に引退記事を書いたのは、たしか日刊スポーツだった。 プロレスラーでは、名前が出てくるのは、馬場さん、渕、三沢の三人だけ。この三人には心をゆるしていたらしい。 特に渕は、私生活でも相談役になっていたようだ。 故人の人柄を紹介するエピソードも、驚くようなことが多い。 保子さんへのプロポーズ、「生産性のないことはしない」という人生観、大学講師となったのは自らの売り込みによってであったこと。 やはり彼は怪物だった。肉体だけでなく、頭脳も精神力も常人を遙かに凌いでいたのだ。 故人の冥福と、遺族の安らかな生活を祈る。
2000.11.29
コメント(0)
-
「やくざの生活」 【田村栄太郎】
やくざの生活(著者:田村栄太郎|出版社:雄山閣) 書名通り、やくざの生活がどのようなものかを述べたもの。 江戸から明治にかけてのやくぜにまつわるあれこれ。特に、博打のルールなどは詳しく紹介している。「天釆」というばくちばどは、「明治二十二年頃、東京日本橋区蛎殻町米穀取引所の客引高橋某が」始めたものだ、など、来歴にも詳しい。 著者自身も、地方の親分に世話になる旅を経験しており、やくざの世界に身を置いたことがあるのかと思ったが、やくざにたいする共感などは全くない。 巻末の「裏返しやくざ列伝」は、講談などで知られる有名なやくざが、どれもみなろくでなしであったという罵倒ばかりである。 「まえがき」には、やくざを持ち上げる人を、「労働組合にも加わらない非民主的な他力主義の人たちがおおいようである。」とこきおろし、「江戸時代は末期になるほど、領主も領民も貧乏になった。その原因は封建軍国主義的政策にあった。」(p78)、「非は幕府の軍国主義にあったのである。しかしそれは、封建軍国主義の特長ではなく、君主制の特長であり」(p118)などと、左翼的な見地からの批判が散見されるのだが、このほんのどこを見ても、著者の紹介がない。 著者は、「いったい、どういう人なんだろう。 再認識したのは、やくざは貨幣経済が発達したところでないと生息できないこと。 はじめて知ったのは、浪曲などでやくざがもてはやされたのは、寄席というのがやくざとつながりの深いものであったから、やくざの親分を礼賛する話が生まれたためということ。 股旅物はフィクションであり、現実とはかけはなれたものだろうとは思っていたが、浅草のてきやの親分は、はっきり、「大衆小説のマタタビ物は、私たちの生活にふれたものではありません。実はバカバカしいもので」と語っている。
2000.11.28
コメント(0)
-
「戊辰戦争 敗者の明治維新」 【佐々木克】
戊辰戦争(著者:佐々木克|出版社:中央公論新社) 大政奉還から、新政府による東北諸藩への処罰が終わるまでを、列藩同盟の側から描く。 東北が戦地となるまでに曲折があるのだが、やはりもっとも大きいのは慶喜の優柔不断ぶりである。 薩長と戦うなら戦う、帰順なら帰順と一貫していればいいものを、身内をも欺いて保身に汲々としている姿が目立つ。 著者も、「幕府終末の危機に立ちながら、慶喜はそれを乗り越え収拾しようとする意欲も気力も、また能力もなかった」(p31)と切って捨てる。 「大政奉還」というのは、今日から見れば、大きな出来事だったが、その当時としては、徳川は、「むしろこの時点では、なにも失っていない」(p10)というのは意外だった。 著者は秋田出身で、子供の頃から戊辰戦争の話を聞かされ、当然、東北諸藩に同情的である。しかし、さすがに学者で、感情的ではない。 誰もが悪役として描く世良修蔵について、勝者の側までが、「戦争の全責任を世良に負わせ」「いけにえの役を世良にふりあてている」(p109)と述べている。 全国的な動乱をよそに、水戸藩は内紛に明け暮れていたこと、榎本武揚には独自の考えがあり、列藩同盟とは一線を画していたことなど、この本を読むとよくわかる。 それにしても、読んでいて心を打つのは、二本松の少年たちの悲劇と白虎隊の最期である。 慶喜がもっとしっかりしていれば、新政府軍がもう少し感情的にならずにいたら、と「たら、れば」が心に浮かぶ。 この本によれば、戦争を避ける機会は何度もあったのだ。 朝敵の汚名をきせられ、東北各地で無念の最期を遂げた人たちの心を思うと、歴史の冷酷さに慄然とする。 戊辰戦争が東北に残した負の遺産は、あまりにも大きい。
2000.11.21
コメント(0)
-

「あなたの字はもっとうまくなる」 【時光華】
あなたの字はもっとうまくなる(著者:時光華|出版社:青春出版社) 副題は「この4つの法則だけでたちまち見ちがえる」となっている。 生来の悪筆で、こういう本はこれまでにも読んだことがある。 しかし、読んで字がうまくなったことはない。 扉を開くと、いきなり、「この本を読むだけで字がうまくなる」と書いてある。 四つの法則を上げ、それを詳しく説明し、それを守ればうまく書ける、と説いているのだが、これでは解決しない問題があるのだ。 たとえば、横画が二本以上ある字の場合は、横画はみな平行になるように書け、というのだが、平行になるように書こうとして書けないから困っているのだ。教えて欲しいのは、どうすれば平行になるように書けるか、ということなのだが、それについては触れていない。 こういう本を書く人は、当然のことながら、字がうまい人である。きれいな字を書ける人である。こうすればきれいに書けるよ、という法則を教えてもらえば、その通りにできる人なのである。 したがって、どうすれば、その法則通りにできるのか、という前段階の問題に触れる必要があることに気づかないのだろう。 決して役に立たない本ではない。参考にはなる。しかし、読んだだけで字がうまくなるようなことはない。 現に、「見た目にはわかりにくいかもしれませんが、とても大切なことなので、身につくようにしっかり練習してください。」(p86)という文章も出てくる。
2000.11.13
コメント(0)
-
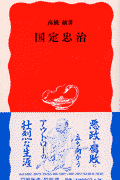
「国定忠治」 【高橋敏】
国定忠治(著者:高橋敏|出版社:岩波新書) 国定忠治が何をしたか、ということと、彼が生きた時代の上州がどんな社会だったか、という二つの面から書かれた本。 幕府の役人や領主は金をせびることばかり考えているのに対し、国定忠治がいるとこそ泥も出ない、という状況になるのでは、忠治に人気が出てあたりまえ。 また、飢饉に際しては、お上からの手当よりも、国定忠治からの施しの方が手厚い。 ただ、その金の多くは博打の上がりで、一方では博打という形で金を巻き上げていたわけだが、それについてはあまり触れていない。 さらに、自分でも人を殺しているし、浅次郎に命じて、伯父の勘助を殺させたりしている。勘助が殺されたときには、二歳の子も一緒に殺されている。講談などでは勘助は悪役になるそうだが、気の毒な話だ。 初めて知ったのは、忠治を捕らえた後、拘留して置いたり、処刑のために護送したりすると、その土地の者に費用の負担が降りかかってきたこと。これでは、つかまえた方を恨みたくもなるだろう。 当時の文書に引用も多いのだが、仮名の部分は歴史的仮名遣いなのに、漢字のふりがなは現代仮名遣いになっている。 例えば、191ページに引かれている文書では、「向(むか)ひて」という表記がある一方、「漸(ようやく)く」という表記がある。ふりがなも歴史的仮名遣いにした方が統一がとれて良い。
2000.11.09
コメント(0)
-

「ニホンゴキトク」 【久世光彦】
ニホンゴキトク(著者:久世光彦|出版社:講談社) かつてTBSで「時間ですよ」「寺内貫太郎一家」などを制作した人である。 最近は作家としても知られている。 「週刊現代」に連載されたもので、書名通り、消えつつある言葉をとりあげ、それについての思いを語っている。 知っている言葉もあれば知らない言葉もあった。知っている言葉も、知ってはいるが、使ったことがないものがほとんどだった。 言葉に関することのほかに、家庭についての考えが印象に残った。「昔の父親は多かれ少なかれ、みんないっこくで、一徹だったようである。私の家でもそうだったが、あのころの父親は、家族の中で、そういうキャラクターを多少無理しながらも演じていた節(ふし)があった。(略)頑固、強情、一徹といったアンタッチャブルな役を仮設すると、家庭内の教育は月並みではあってもうまくいくのだ。」(p25) 松田優作に関することで、初めて知ったことがあった。 漱石の『虞美人草』のテレビドラマ化が決まっていたのだ。『それから』は映画で見たが、『虞美人草』は見た記憶がない、と思ったら、脚本を書く事になっていた向田邦子の事故死で立ち消えになったのだった。 著者が松田優作と桃井かおりをつれて向田邦子に会いに行っていたことが書いてある。 向田邦子のことは何度も出てくる。そして、彼女の使った言葉を懐かしんでいる。 それでも記憶とはいい加減なもので、向田邦子が台湾へ行ったとき、『虞美人草』を持っていったのだが、69ページでは新潮文庫となっているのに、138ページでは岩波文庫になっている。 言葉に対する感覚は鋭い。しかし、偏狭ではない。「意外と」を許容している。また、「言葉というものは、誰にも共通であると同時に、こんな風に、かたくなに個人的なものでもあるのだ。」(p53)と、人それぞれの思いによって言葉を使うのが当然とも思っている。 これほどの人でありながら、「やわらかで耳ざわりのいい」(p36)という表現をしてしまっている。難しいものだ。
2000.11.07
コメント(0)
-
「昭和国民文学全集(10)角田喜久雄・国枝史郎集」 【角田喜久雄・国枝史郎】
昭和国民文学全集(10)(著者:角田喜久雄・国枝史郎|出版社:筑摩書房) 角田喜久雄の『髑髏銭』と国枝史郎の『神州纐纈城』。 『髑髏銭』は、伝奇小説ではあるのだが、おどろおどろしいところはあまりない。 主要な人物がみなつながりがあり、ご都合主義ではあるのだが、それを不自然に感じさせないくらい世界が完成している。 悪人は一人だけで、最初は悪人のように思えた男も、終わりの方では結構いい人になっている。 これでいいのだ、と圧倒される小説である。 『神州纐纈城』は、おどろおどろの連続。 結局物語としては完結していないのだが、それでも読み継がれるだけのことはある。 著者は、物語を書きたかったのではないのだ。 纐纈城のようすや、造顔術のしかた、町の人々が病気にかかり体が崩れていったりする様子を描写したかっただけなのだ。
2000.11.06
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1










