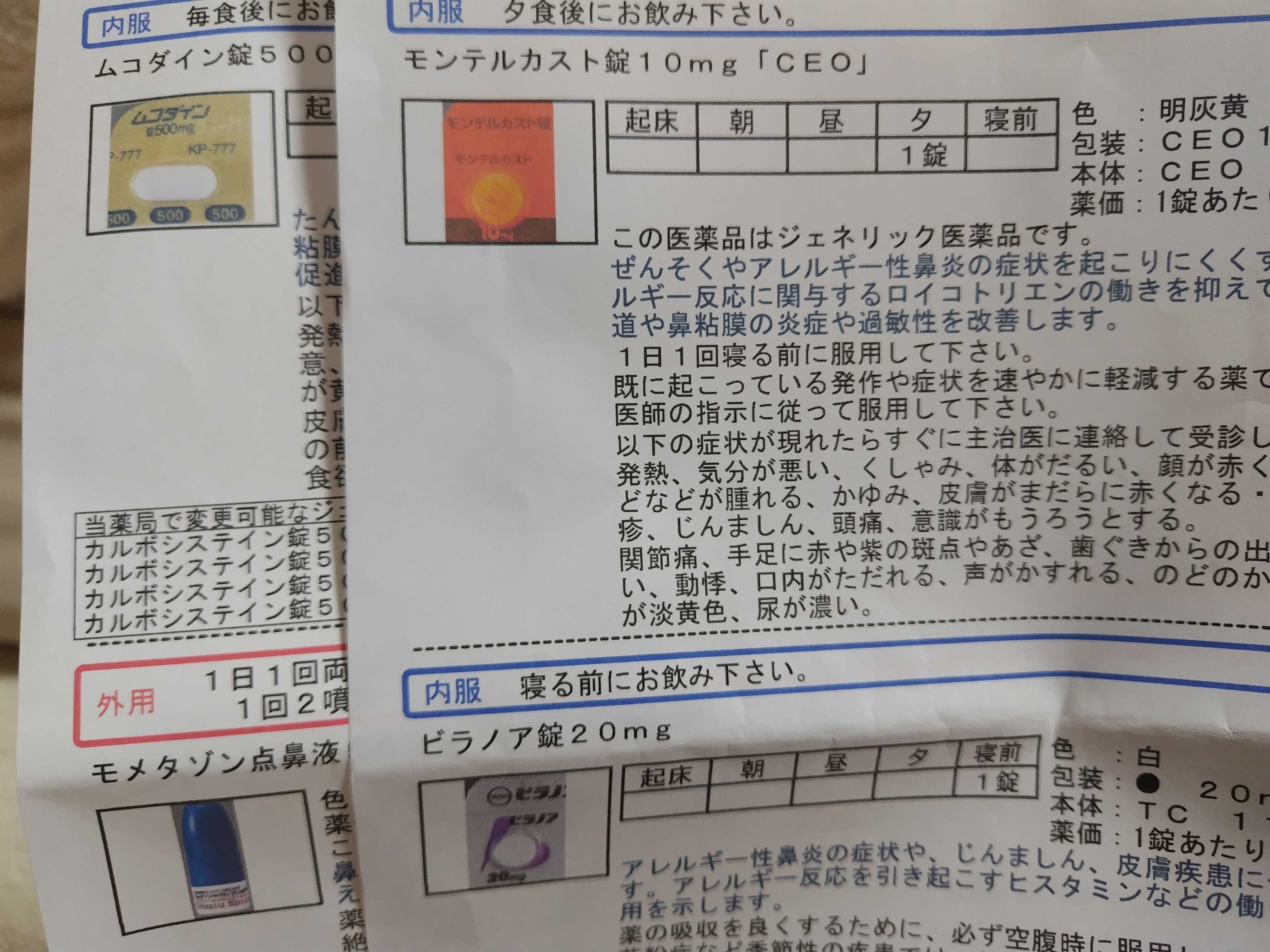2009年03月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
エピローグ。
昨夜、報道ステーションでWBC後初めてイチロー選手があのときのことを話していました。イチローしか知らないあのときの胸のうちイチローも知らなかった仲間達の胸のうちそんなお話を聞かせてくれました。ちょっと前の日記に、(2009年3月26日の日記)優勝後のヒーローインタビューでイチローさんが「実況中継していた」と話してたというのを聞いて『未来の記憶の作り方』みたいなもののヒントをもらった気がすると書きました。日記に放送されたときの動画を載せたのですが携帯でご覧の方に、印象に残った部分を書きますね。「まさかあれがくるとは思いませんでしたね。 川崎選手が代打に指名されたとき『ここで、ムネ(川崎選手)か。 おまえが一番頑張ったんだから ぜんぶ、持って行け。』 と送り出したんです。 川崎選手がフライに倒れたのを見て そこで、スイッチをぽんと入れ直した『来たか』と。『ここで打ったら、えらいことだな』『打たなかったら、もっとえらいことや』と。 そういう思いがよぎるときは 結果は、あまり出ないんですね。 雑念がいろいろ入ってきているわけですから。 でも、それがよぎってしまったので どうしようもない。 これ、消すことできないんですよ。」「一回、よぎってしまうと 自分で振り払うということはできない?」「僕の脳みそがこういう流れになっていくなら ここに便乗していこうと。 で、打席に入るときに『さぁ、この場面、 イチロー選手 打席に入りました。』 みたいな感じで入っていったんです。『ここで、イチロー選手打席に入りました。』 と、ちょっとした実況の感じを 頭で描きながら打席に入ったのです。 ファールが続いたとき『はい、ファール』『はい、またファール』という風に。」「すごく余裕がありますね?」「これは、余裕ではなく 自分の気持ちに便乗していっただけ こうなっちゃったら ちょっとマイナスのことも考えたけど『オフ日本に帰れないな』 とネガティブなことは想像しましたよ。 ちょっと楽しくしないと もうやってらんないなという感じなんです。 めちゃめちゃ怖いですよ。」 「そして、5球目ですよね。」「はい、そこの低めファール。 もうワンバウンドになりそうな低いボール あのファールをしたときに『いただきました』という感じにはなったんですね。『必ずいい結果が出る』と思ったのです。 勝負してくれれば かなりの確率でヒットが出ると思った。 なんででしょうね。 あのボールをファールにできた ということではない むしろ、あの球をヒットにできる と思って、打ちにいった。 でも、結果的にはファールになった。 あのボールをヒットにできる と思った感覚を持った自分ということだと思う これ、何がきてもいけると感じたんですね。」「そのときは、まだ頭の中の実況はされているんですか。」「そこで終りました。」こんな風にお話していました。自分を乗せていくために実況中継するそして、本当にゾーンに入ったときはその実況中継が終わる。自分を観察していって最後は、ひとつになる。これ、禅や仏教で言われる取組みそっくりです。子ども達に、集中するお話をいまいち伝えられなかったのですがすごく大きなヒントを頂きました。これについては、また改めて書きますね。そして、イチローさんを声で応援するのではなく「あなたのスタイルを応援しています」と後輩のチームメイトの人たちがイチローさんにならってストッキングをあげたスタイルするという優しさを見せて、イチローを守ろうお話や川崎選手が、イチロー選手に「今までよりももっと好きになった。 それがなぜかと言うと 打てないときのイチローさんが すごく良かったから。 最後のヒットは、一生忘れません。」というメールを送っていたというお話はすごく胸に響くものがありました。 「観ている人に自分が何かを示すときは 結果を出すことでしか示すことはできないが チームメイトたちに対して 何かを示す時というのは 結果が出ていないときに どうであるべきなのか どういなくてはいけないのか ということが大事になってくるのです。」と語り「乗り越えた感覚があるから 得るものがあったと思うのですが?」という質問に「優勝した。いいことで結果が出た という自信ではないのです。 そこに至るまでの自分のあり方 そこに自信をもったので。 これよりも怖いものは なかなか出てこないと今では思っています。」と最後に答えていたイチローさんはやっぱり、イチローさんなんだと思わせるものですね。姿で示していく何かではなくて、在り方。「そういう準備をしてくるからこそ 結果は、エピローグをしてついてくる。」インタビューした義田さんが話していましたが今年度最後の日に、すごく大きなヒントを頂きました。「結果は、エピローグである。」ここ数日読み返している引き寄せの法則関連の本とすごくつながる話で面白かったです。この番組、ご覧になられた方おられますか?≪動画1≫≪動画2≫
2009年03月31日
コメント(4)
-
ゴッドハンド。
先生に質問しない生徒が約6割、理由は「面倒」 ≪ヤフーニュース≫ 先生に質問をしない 質問ができないのではなく どうやって質問をしていけば 先生や夢を味方につけていけるか 解らないというのが 実情じゃないかなと感じています。 ちょっと前に書いた 『夢を味方に(1)』 (3月14日)『分けること。』(3月24日) というのと、つながるのですが 子どもたちに、考える時のコツとか 質問の仕方みたいなものを教えています。 「聞かれていることは、なんですか?」 ということの次は 「これを分けると?」 というのを教えています。 分けると、理解しやすくなるだけではなく 分けると、分かるようになるのです。 このあたりについて 勉強にどうしているかを書く前に 前回から書く書くと書いていた イチローさんについて、書きたいなと思います。 イチローさんがインタビューのなかで 「心が折れそうになっていた」とか 「個人的には、想像以上の苦しみ つらさ、身体の痛みではない痛みを感じた」 と言っているのを聞いた時 自分の現象を客観的に見て 問題の原因に「形」や「名前」を与え 上手に自分に質問し 「分けて」取り組んでいく という心理技術を知ってか知らずか解りませんが 活用しているんだなと嬉しくなりました。 そして、今朝、関西ローカルの『せやねん』 というバラエティ番組を見ていたら WBCを観戦しに自費で渡米していた 元近鉄監督、阪神等打撃コーチで 野球解説者の佐々木恭介さんから 興味深いお話を聞きました。 中島選手とか小笠原選手など オールジャパンの7、8人をケアしておられる ゴッドハンドと言われるような 整体師の方がいるらしいのですが 佐々木さんとその整体師さんは旧知のなかで 韓国と1、2位を決めるサンディエゴで たまたま会うことができたので 「隣の席が空いているから 一緒に観戦しませんか?」 と隣で並んで一緒に 応援していたそうです。 佐々木さんが 絶不調のイチローを観て 「こんな悪い イチローは、見たことがない。 左肩が被るイチローなんて いままで見たことがない。 先生、どう思いますか?」 と聞くと、整体の先生は 「なぜ被るかというと 右の骨盤が出ているから。 立ち姿が歪んでいる。」 と答えたそうです。 そこで、ジャパンの山田コーチに 「こういう風に言われている 整体の先生がいるから イチローを見せてくれ。」 と電話すると 「解った」とその晩に、 イチローに言ってくれて。。。 それを聞いたイチローが 整体の先生を知っている小笠原選手に 「どんな先生なの?」 と聞いてきたそうです。 小笠原選手も 「無駄なことを言わない。 すごくいい先生だよ。」 と後押しいてくれて その日に診てもらったそうです。 次の日に、先生に 「イチローどうでした?」 と電話で聞いたら 「あと2回見たら完璧やけど 今でもいいと思いますよ。」 と答えてくれたそうです。 オリックス時代調子良かった時は フリーバッティングで 10本のうち、8本か9本くらい ホームランを打ったそうなんですが 次のロスで、イチローの練習をみたら そのバッティングが蘇っていたそうです。 一緒に練習を見ていた先生に 佐々木さんは、興奮して「先生、治っている、治っている」というと 「あと、2回見たい」と先生がいうので 練習終りの小笠原さんに 「日本のためや。イチローにあと2日 先生のとこにいけって、いうてくれ。」 と頼んだら 「解りました。」と言ってくれたそうです。 しかし、整体の先生のところに 行く行かないを決めるのは イチローさん次第です。 で、決勝戦の日に 再び先生に会った時に聞いたら 「あのあと、決勝戦まで 3日続けてきました。」 と答えてくれたそうです。 最後に佐々木恭介さんは 「決勝戦の前の フリーバッティングみたら もう完璧ですよ。 絶対打つと思った。」 と話していました。 長い文章になっちゃいましたが 素直になること 相手が答えたくなるような 手を貸したくなったり 動き出したくなる質問ができること こういうことが 奇蹟を生み出すんですね。
2009年03月28日
コメント(4)
-
未来の記憶の作り方。
おはようございます。春期講習中のため決勝戦の試合も、試合の後の振り返りもまだまともに見れていないのですが食事後の時間とか、朝や晩のニュースを見ていて不思議なことに、話を聞く選手、選手から同じようなお話を耳にしています。それは、「未来の記憶の作り方」について。自分が拾っているのかもしれませんが次々と選手から同じように聞きます。イチロー選手がインタビューのなかで「僕は持ってますね。やっぱり(笑)。 いやぁ神が降りてきましたね。 いやぁここで打ったら、 もうあの打席では、あぁもうこれ 日本からの目がもの凄いことになってると思って。 それをなんか、自分の中で 実況しながら打席に入っていて、 まっそういう時って結果出ないんですけど。 いやぁひとつちょっと 壁を越えたような気がしましたね。」 と話しているのを聞いて「なるほどな。。。。」と思っていたのですが昨日、深夜に見たテレビで「同点にされた場面で、どんな感じでしたか これは、ここで負けるとか思いましたか?」と青木選手が聞かれると「次のバッターは、ダルビッシュが 打ち取ってくれるのはわかっていたんで。 そんなに心配は、していなかったのです。」と答え10回のイチロー選手につながるヒットを打った内川選手は「打席に入る前に 『これは、ヒットがでるな』 と感じて、打席に立ったんです。 そしたら、本当にヒットになって 一塁ベースで、 『自分は、すごいことしたかもしれない』 って、思って興奮しちゃって。」と話していました。また別の番組で、ダルビッシュ投手が「最終バッターを三振に抑える あの場面を振り返ってどうでしたか?」と聞かれ「投げる前に 三振になるのは解っていたので。 実際、投げたら 三振になって良かったんですけど。」と話しているのを聞いてなにか、つながるものというか共通するものを感じました。実は、今年に入って『未来の記憶の作り方』という本を読んでいてこれを自分にアレンジしたいと思っていたのですがその大きなヒントをもらった気がします。選手たちのインタビューがすごく不思議な気がして覚えておきたいと書いたのですが前回の『分ける』ということと今回の『未来の記憶の作り方』について深掘りする話は、ちょっとゆっくりできたときに書きたいなと思います。今回の選手たちのコメントに限らずなにか、心に残るコメントありますか?では、10分後に授業なので行ってまいります(^O^)/
2009年03月26日
コメント(6)
-
分けること。
決勝タイムリーを放ったイチロー外野手の試合後のコメント。 「やあ、もう苦しいところから始まって、 苦しいが、つらいになって、 心が痛んで、最終的に笑顔になりました。 日本のファンの人たちに 笑顔が届けられて最高です」。試合後ドジャースタジアムを大きな日の丸を持って1周。 「気持ち良かったですねえ。 ほぼ、いきかけました。 日本のすべての方に感謝したい」。10回の決勝タイムリーについて。 「僕は持ってますね。 神が降りてきたという感じ。 日本中のみんなが 注目しているだろうと思って、 自分の中で実況して、 普段は結果が出ないんだけど それで結果が出て 壁を越えたと思います」。 イチローさんのこの発言。彼の苦悩と思いが出ていますね。試合は、授業をしていて見ることができなかったのですがこのインタビューだけ休憩時間に聞くことができました。ここ最近、分けて考えていくことそして、自分を分析することはとても大切なことだと思っていたのですが彼のインタビューの答えにすごく大きなインスピレーションを得ました。詳しくは、授業が終わったらまた続きを書こうと思うのですがほんと、最後の最後で素晴らしい結果が出てよかったなと思います。「神が降りてきた。」すごい言葉ですね。
2009年03月24日
コメント(2)
-

最後のパレード。
WBCで日本がアメリカに勝ちましたね。テレビ解説の元巨人の槙原さんが「川崎選手の役割が大きかった」と話していましたがバントで、相手を揺さぶってみたり大切な場面でヒットを打ったりすごく活躍していました。試合の後の記者会見で 「初スタメンでしたが?」という質問に 「僕はベンチで すべて試合に出てましたから」 と答えていました。 好調であったにも関わらずチーム事情で、出番がなくてもベンチで一番大きな声を出し選手が守備から戻ってくると手を叩いて迎える。いつでも出られる準備をしてきたからこそお呼びが掛ったときにすぐに出ていくことができる。これぞ、プロですよね。さて、昨日の朝刊の広告が目に留まり『最後のパレード』という本を買ってきました。 そこには、東京ディズニーランドのキャストだけが知っている秘密のストーリーが書かれていてそれは、パークの中で実際に起こった心温まる出来事の数々なのです。それを東京ディズニーランドでは社長を含むすべてのキャストたちがそのストーリーを共有しそこから人を思いやることの本当の意味を学ぶそうです。一番最初に書かれてある『天国のお子様ランチ』というお話は以前、この日記でもご紹介したことがありました。≪一歩踏み出す≫ (2006年6月10日)≪携帯≫ 今回、たくさんの心温まるお話を読んでおもてなしの心とは、どういうものかサービスとは、どういうものなのかそういうことをたくさん感じました。実は、書棚には、たくさんのディズニーランドに関する本があるのですが今回の本が一番かもしれません。 ここ2年くらいディズニーランドが人をわくわくさせる理由はなにかまた行きたくなるのは、なぜか他のテーマパークと何が違うのか自分の生活のなかに自分の仕事のなかにディズニーランド的な要素を入れるとはどういうことなんだろうか?みたいなことを考えていました。 それも、この本には書かれてありました。『ディスニーランドで 人々が得ることができるのは 「生きている実感」です。 もっと生き生きした自分を 体験することです。』と。これって、ちょっと前に日記に書いた『ワクワクした気持ち』というのと通じますよね。(3月18日の日記)そして、何よりもうれしかったこと。実は、教室では、子供たちが宿題を書いたりポイントをスタンプする冊子を『Wish Note』(願い事帳)と名づけて各自持ってもらっているのですがその一番最初のページに引用して載せてもらっているその言葉をディズニーの方も大切にしておられたことです。 You can dream, create, design and buildthe most wonderful plase in the world...but it takes people to make the dream a reality.WALT DISNEY君たちはみんな、世界中でもっとも素晴らしい場所を夢見たり、想像したりデザインしたい、造ることができる。しかし、その夢を現実のものとするのは、人である。ウォルト・ディズニー川崎選手に、そしてこの本に今日は、大きなプレゼントを頂いた気がします。普段よりも人に対して優しい気持ちになれるって、不思議な感じですね。 ≪今日の動画≫
2009年03月23日
コメント(6)
-
茂木流、ひらめき脳。
『茂木流、ひらめき脳。黛流、アラ・モード。』と題した、講演をさっき聞いてきました。これ、奈良大学のオープンキャンパスのイベントで国文学が専門の上野教授が『俳句』をテーマに脳科学者の茂木健一郎さんと俳人の黛(まゆずみ)まどかさんから『俳句』に秘められた美意識と発想力、ひらめきとは何か?みたいなものをトークを交えて探っていくというものでした。茂木さんのお話は2ヶ月前に聞いたのですが対象が高校生であったり俳句がテーマだったりしたので年配の方も多くて前回聞かせて頂いたもの(1月23日)とはまた違った角度のものでした。いくつか記憶に残ったところを書かせていただくと黛さんの「シャンプーをしていると 俳句が浮かび上がることがあるのです。」というお話に茂木さんが「感覚を遮断するすると 外から入ってくる情報が遮断できて 過去と未来を繋げることができたり 想像力によって、創造性を 発達させることができる ということが分かっているのですよ。」と答えておられました。そして、俳句の言葉を削ぎ落とすこと読者が、余白を足していくというのに関連して言葉の到達距離というか言葉の射程距離を意識してどれくらい遠くまで言葉が届くか何を伝えられるかと世界に発信してほしいそんな風に話をしていました。最後に高校生に向けて黛さんは「自分は大学を選ぶ際に父から 『青春を刻む場だから 学ぶ環境を考えなさい。』 とアドバイスを受けて 横浜の地を選びました。 奈良は、歌に 何度も読まれる場所ですよね。 歴史を感じるこういう場で 落ち着いて打ち込めるのは 素晴らしいと思います」と答え茂木さんは「いまや、インターネットで キーワードを打ち込めば 多くの論文は読め 知りたいことは、手にすることができました。 ただ、いまのところ インターネットにはないものがあります。 これは、秘中の秘なのですが 『体系制』というものなのです。 体系だった知識というのは 体系だった知識を持った人 生きた体系制を持った人と 2、3年一緒にいないと 自分につかないのです。 大学は、それが可能な場所だと思います」と答えておられました。大学の講堂で講演を聞いたのですが久々に、アカデミックでワクワクするような熱い講義を受けてきたそんな気がしました。
2009年03月22日
コメント(2)
-
なりきる。
イチローさんのやっといい顔が出ましたね。厳しい表情や、身体に力の入ったスイングを見るたびに彼、本来のリラックスしたスイングに戻ってくれたらなと思っていたので力の抜けたいい表情になった彼の顔に観ている自分まで嬉しくなりました。さてさて。。。「なぁ、塾に来たときだけ ○○しなきゃとか思ってるだろ? 塾に来たときとか 先生の顔を見たときだけ 夢のこと思ったとしても 夢って、叶わないものなんだよ。 何にもしなくて 先生が連れていってくれる そんな魔法は、先生は持ってないよ。」去年の暮くらいだったと思うのですがそんなことを言ったことがありました。その後、お正月に見た外科研修医の成長と葛藤を描いた『ポン・ダルヒ』という韓国ドラマで「人は、夢を見続けるとその夢に似てくるんだって。」というセリフを聞いてやっぱりそうだよなと思ってこの3ヶ月間、何かあるとこの台詞を思い出し『夢を見続けるとは いまでいうと、 どういうこと?』とか『夢に似てくるって どういうこと?』と思いながら行動したり子ども達に話をしたりしてきました。それぞれが目標とする過去問を見せてそれを一つずつ項目で割り算してどうしたらそこまでいきつくかその項目をかけ算していくそういうのを繰り返し見ていたら「こんなのムリ!」と言っていた言葉から「できた!できた!」という言葉が増え笑顔になってきました。『できて当然』と思えたことは実現できる。人は、自分で「その状態が当然」と自然に思っている状態を引き寄せるものなのだということこれが夢を見続けていると夢に似てくるということ夢になりきるということなんですね。そして、もう一つ言葉が無意識に影響を与える。だからこそ、私たちは意識してポジティブな前向きな言葉優しいソフトな言葉を使うことが大切なんだなと子ども達をみて、改めて思いました。今日は、勝てて良かったです。「アメリカと対戦したい」選手たちがキャンプの時から話していたこと、実現しましたね。≪今日の動画≫
2009年03月20日
コメント(6)
-
ワクワクした気持ち。
昨日、授業をしていたら目の前で授業を聞いている子だけでなく横で自習している小学生までケラケラ笑っているんです。「ここのポイントは、何でしょう?」と聞いたら「○○」と答えてくれるのですが「ブブー」とクイズ形式にしていたり「いまやったやつ、覚えてください。 SADA'Sまんてんテストです。」と、すること一つ一つにすることのタイトルをつけたり自分としては、いたって普通なのですがどうやら、奇妙な動きをしているらしいのです。 「やる気になったら 違うと思うのです。 この子、どうやったら スイッチが入るんでしょうか?」とか「最近、この子、すごく やる気がでてきたんです。」とかいろいろ聞いていて意識を変えたらいろんなことが変わるのだけれど『うまくいくときと いかないとき 何が違うのだろう?』そんなことを思っていました。いろんなことを考えてみたんですが行きつく先は、シンプルなものでアトラクションを目に前にしたようなキモチその瞬間、その瞬間にワクワクする気持ちがあってそのワクワクした気持ちを行動に起こそうとすることどれだけ充実したかどれだけ心をこめたかということでした。そして、自分がしていることに意味を与えていくために名前をつけていくとより充実してくるんだなと子供たちに教えてもらいました。今日の野球もまた、ワクワクしますね。≪今日の動画≫
2009年03月18日
コメント(4)
-
Enjoy yourself and smile
「テレビを見たり お笑いを見るのが楽しいとか 何にもしないで ただいるのが楽しいというのと 自分の夢を拓いていくのが 楽しかったり ちょっと未来に、つながっていく というのが楽しいというもの。 子ども達と話をしていると 『ここのところが うまく伝われば』 と思ったりするのですが この二つの『楽しい』 これは、違うものなのですか?」先週、ぽんぽこ先生と話したときにそんな風に聞いてみました。すると「テレビを見て楽しい 映画を見て楽しい お笑いを見て楽しい 何にもしないで ただいるのが楽しい いろいろ楽しいというのはあるよね。 それは、前は、そこまで毎日が楽しくなかった ということなんだ。 昔、ある双子の女の子が 僕のところに来てね。 上のお姉さんは、活発で 学校から帰ると、ランドセルを置いて 外に遊びに行っちゃうんだけれど 下の子は、家にいる子だといってて お母さんも下の子自身も 『この子は、こういう性格の子供なんです。』 と思っていたのだけれど 単に、エネルギーがない子だったんだ。 それで、何回か会って エネルギーを入れてあげたらね。 表情がだんだん豊かになって 半年後くらいに 『最近、どう?』と聞いたら、 下の子も上の子と同じように 帰ってきたら、家にいなくなった ということがあったんだよね(笑) 勉強に、いま一つ乗らない子も 心のどこかでは やらなきゃと思っている。 でも、できないんだ。 する元気がないんだね。 こういう子は、いっぱいいる。 喜びや楽しみが増えて その子のエネルギーがもっと増えたら 勉強もするようになるよ。」そんな風に話をしてくれました。子どもも大人もそして、自分自身についてもそうなんですが『なんで、しっかりしないんだろう』『なんで、ちゃんとしないんだろう』と感じるとき本人の心の中ではちゃんとしようとかしっかりしようと思っているものですよね。そして、元気がないということは先ほどもいったように喜びがない、楽しくないどっかで「あぁ、つまらん」と思っているものです。そして、ライバル心が強かったり競争心が強かったりするのもエネルギーがもっと増えればゆとり、余裕がでてくるので優しくなりますよね。日々の暮らしのなかで喜び、楽しみ、仲良く心がどれだけ喜んだかと感じる自分を楽しんでみるこの状況を楽しめるかと考えてみる意識的に笑ってみるそんなちょっとしたことで確実に変わってきますよね♪Are you enjoying yourself? Are you smiling?≪今日の動画≫
2009年03月15日
コメント(6)
-
夢を味方に(1)
思考を動かしていくこと子ども達に、どのように教えているか自分がしていることについてどうまとめていこうか実は、ここ2カ月くらい思いを巡らせていたのですが前の日記で書いたおかげでいろいろ見えてきました。子ども達に教えていることなので定着させるために繰り返せるようシンプルものなのです。で、授業中は、意識して3つのキーワードを繰り返しています。一つ目は「聞かれているものは、なに?」とか「これは、なに、聞かれている?」というものです。これ、日常会話でも出てきたりテストが終わった後の答案を見ながらお父さんやお母さんがお子さんと話している会話にこれと似たようなこと出てきそうですよね。問題の雰囲気をみて早とちりしてしまったり「ちゃんと、問題読んでいたの?」なんて、言われるときって、ありますよね。こういうとき「これ、求めているものが違うよ。」とは、言わずに「聞かれているものは、なに?」と聞いてみたり問題をよく前に、何を目指しているかを確認すること、これを定着してもらうために「これ、なに聞かれてる?」と聞いています。たぶん、解いていることに時間をとられていると解き終わったことに満足したり最初に、『こんな問題だ』と思いこんで聞かれていることに、答えていないということに、なっているんだと思います。これ、日常生活にも通じていて何か、うまくいっていなかったりよくないことをイメージしてしまうとき『自分がどうしたいのか』とか『何を聞かれているか』が解らなくなったり過去の感覚を瞬時に思い出してしまいその思い込みに、はまっていまって自分をハッピーにする方向ではなく違うものが気になったりするものですよね。自分環境を前向きなものに変えるための第一歩は自分の思考のクセを変えること自分への質問を変えることですよね。こういう風に視点を変えてみるだけで「発見力のある子」(2008年1月31日)につながるなと思います。一気に、3つ書こうと思ったのですが長くなったので、次にしますね。≪今日の動画≫
2009年03月14日
コメント(4)
-
甘くて、甘いもの。
明日は、この続きを書けたら。。。そんな風に書いていたのに日記アップできなくてごめんなさい。懇談やら、新学年への準備やら授業やら、原稿の作成やらと次々とやっていたのですが遅くなりました。今日は、特にそうだったのですが今週は、子供たちに会うと「せんせ、用意は、できている?」と聞かれました。1か月前のお返しのことです。何が返されるのか毎年の子ども達は知っていて「あるよ。」というとにこっと笑い、口の中が甘く広がっています。面白いくらいみんな同じ表情をするので『あぁ、いま想像したな』と面白がってみていました。さて、お母さん方とお話していたりしていると「できるときは、 ニコニコやるんですけどね。 解らない問題になると 『わからん。』と 手が止まってしまうんですよね。 『解らないのだから』 『教えて』ってなるんです。」という話題が出てきます。実際、そういう光景を目にすることはよくあります。問題を解くときにすぐに考えの筋道が浮かんできたならばそのまま解いていけばよいし自分の持っている力の範囲で解ける問題であればスラスラ書けますよね。でも、考え方の筋道が浮かんでこなかったとき『解き方そのものを考える』とか『どうやって解くか考える』という考える手順やつまり、理論的な試行錯誤ができる方法を身につけることは、とても大切なことだと、ここ数年思っています。ちょっと前に授業見学させて頂いたときも「自分で、自由に考えて」というのとあらかじめシートが用意されていて考える手順を誘導していったりするのを見ると思考スピードは、ぜんぜん違うなと思いました。私たちは、よく考え事をします。勉強している時だけでなくなにも考えていないように見えて座っているときも、電車に乗っているときも歩いているときも、泉から水が湧き出るように考えをめぐらせています。考えごとの大半は言葉によって行われているのですが頭の中を流れるように言葉や考えを紡ぎながらいろんな絵を描いています。そこで、自分の考えていることを見えるようにして、自分の考えを絵に描くというか自分の考えを絵に落としたり紙に写し取ったりすることこれって、大きいなと思っているんです。そして、この頭の中に描くことがいちご大福を想像したときのように甘くて甘いものであったらなといちご大福を見て思いました。思考を動かしていくこと子ども達に、どのように教えているかこれをまさに「見えるように」ちょっとまとめてみたいと思います。いま編集中なのでもうしばらくお持ちください。≪今日の動画≫
2009年03月13日
コメント(0)
-
なんで?という感覚。
日々生活をしていて「なんで?」とか「おかしいな」とかそこまでなくても「違うと思うんだけどなぁ」と思うときってありますか?テレビを見ていても「それってなぁ」と思ったり『執着とか拘りとか あまり強い方ではない』と思っているのに意外に、思っているものなんだなと、ここ最近自分を見ていてクスっと笑ってしまいます。そして、生活していても子ども達とお勉強してても正しいという方向ではなくて「喜びが増える方は?」とか「楽しいとか、仲良い方は?」というのを頭に置いてやるといろんなことがスムーズにいくようになりました。また、そのことと同時に過去の自分を振り返ってみて自分自身が一生懸命していることで相手を責めてしまっていることに気がついていなかったんだと気づくようになりました。つまり、自分なりに一生懸命していることがうまくいかない相手や考え方が違う相手に責めてしまっているということに気がついていなかったんだなと思うようになりました。「おかしいなぁ」と思っていることで顔の表情であったり言葉づかいであったり知らず知らずにきつくなっていたようです。自分の手から離れたものについては自分のものではないので自分が美味しく楽しく過ごすということに、ウエートを置き相手なんて、どうでもいいというのではなくて自分の心のなかでそっと置いておくそして、自分自身をもっと大切にしておくそういう余裕がゆとりをもたらすということなんだろうなと思います。でもね、それでも「わからない」とか「わからんわ」と思うとき、ありますよね。これ、人間関係だけではなく勉強とか、学問の部分でもあると思います。「解らないことを 考えようとすること」これ、やってしまいますよね。これについてもよくよく考えてみると考えが思い浮かぶときっていろいろ考えて答えを出すものではないんです。考えて、すぐに選択肢が浮かんでこうしようと思い浮かぶときはそうしたらいいのですがいくら考えても答えが出ないときは実は、自分の考えが及ばないということなんですね。言いかえれば、自分の考えが及ばないということは自分の考える力や考えるエネルギーがないということなんです。だから、早くエネルギーを増やし、楽しむこと。人生大いに楽しんで、大いに仲良くしないとエネルギーが増えないよということですね。明日は、この続きを書けたらなと思っています。
2009年03月11日
コメント(2)
-
光り輝くトップスター。
会話が楽しかったり、面白い人とはまた、会いたいと思うものですよね。楽しいということや面白いということは自分が考えている以上に、大事なことなんだって最近よく思います。日曜日の朝、日本テレビ系列の番組でぐっさんこと山口智充さんが司会の『グッと!地球便』という番組をしていてコメディアンとしてハリウッドでチャレンジしている若者に大阪の実家のご両親が届け物をするというのを紹介していました。(番組の内容は、こちら≪放送内容≫)番組の本旨とは、違うのですがうまくいかないとか生活していけないと落ち込んでいる彼そして、その様子をビデオで見て不安に思っているお母さんにぐっさんが「自分は、25歳まで、 サラリーマンをして この世界に入ってきたのですが 吉本ってね。 笑い話で、よく例えられますが 最初の頃のお給料って ほんとに、日給500円なんです。 それじゃぁ、もちろん とても生活できないんです。 でも、自分は そのことよりも 好きなことをして 食べていけることに そのことに喜びを感じて そのことの方が嬉しくて 仕方がなかったんです。」そんな風に話していました。これを聞いた時にその前日に観たイチローさんのプレーそして、ちょっと前に見た元宝塚で、女優の涼風真世さんのインタビュー番組を思い出しました。蓮の花が咲き誇る森の湖畔にあるタナゴロータスという図書館が司書を募集しているという設定でタレントさんに採用面接をする番組なのですがその質問が面白くて深いしトップスターであるほどそれに対する答えが惚れぼれするほど、うまいんです。「あなたの趣味は、何ですか?」という質問に、涼風さんは「演じることです。」と答え「あなたを採用したら 我が図書館は何を得ますか?」という質問には「そうですね。楽しいと思います。 踊って、歌える、涼風真世。 ぜひ、お願いします。いかがですか?」と答えていました。携帯でご覧の方のためにも文章で、この面白さをお伝えできないのが非常に残念ですが面白いところ満載なのでもしよければ、動画をご覧ください。≪動画1≫≪動画2≫自分のことをどこくらい観ているか自分に、どのくらい意識を集めているか自分をどのくらい演じきっているか自分をハッピーする質問をどんな風にしているかトップスターを見ていて自分のことを光り輝かせる秘密はここにあるんだなと感じました。 明日あなたは、それをつかってとても幸せになりました。さて、何をしましたか?この番組の一番最後に出てくる質問なんですがこの質問はいろんなことに応用できそうですよね。
2009年03月09日
コメント(0)
-
光り輝くこと
◇■ ミスター観戦「イチローの安打が大きかった」(サンスポ)悟り、覚醒って、『enlightenment』と言うそうですね。一人の人の心の曇りがとれることこころのモヤモヤが晴れることがチーム全体だけではなく球場やテレビの向こう側の人までここまで、影響力があるものなんだ。昨日の、イチロー選手のヒットを見てキラキラしたエネルギーを感じました。ここ最近、自分のなかで問題が何かあるときそこに、自分がいるということそのことを承知しておくのはすごく重要だなと感じていました。自分の心を穏やかにするというか自分が心を穏やかにして心が輝いているとき自然に、相手が見えてきて相手とコンタクトが取れてくるからです。3月に入って卒業のシーズンとともに4月から始まる新しい一年に向けていろんな方とお話させて頂いて楽しいこと、嬉しいこと、困ったこと、苦しいこと当然いろんなことがでてくるのですがそのお話のなかで「○○で、困っているんです。 どうしたら、いいですか?」というとき「そのものが光り輝くには どうしたらいいのだろうか」最近、そんなことを思っていました。お子さんの勉強面のお話であってもお子さんが心身ともに元気であってそのものがイキイキして光り輝く状態であったらいろんなことがうまくいくそんなことを思って日々過ごしていました。そして、問題があるとき光が遮っていることそれが苦しみであるとき『私のせいではない』と思ってしまいがちだけれど私の中にどういうことが起きているからこの問題が起きているのか私の中の何が曇らせているのか自分が自分に問いかけるといろんなことが解決してきました。面白いものですね。2打席目のチームに何が必要かを体現したバントヒットなど昨日のイチロー選手は輝いていました。昨夜のイチロー選手の姿を見てここ数日考えていたことのヒントをもらいました。光り輝いている状態は、美しいですね。
2009年03月08日
コメント(6)
-
つながる話。
「せんせ、この問題は どうやって解くのですか?」数学の問題集を解いていた中学2年生の女の子が問題集を広げて、聞いてきました。そこには、x2+ax+bx+abと書いてあってこれを因数分解しなさい。という問題だったんですね。「これは、解る?」x2+8x+15とボードに書くと「3と5の組み合わせ (x+3)(x+5)だよね。」というので「じゃぁ、これは、解る?」x2+ (3+5)x + 3x5とまた、ボードに書くと「さっきと、一緒だね。」というので「じゃぁ、最初の問題が これと同じように見える?」と聞いたら「あぁ!!同じに見える。」と答えて、問題集の続きをしていました。『この子は、いま知っていることと 新しいことが、つながったんだな』と思いながら見ていました。さて、人間の記憶容量は、巨大で、私たちの脳は、いろいろなことを覚えています。しかし、覚えたいことをいざ使おうというときなかなか出てこないときってありますよね。そして、新しく覚えたいことがなかなか覚えられないということもあります。こういうとき、新しく覚えたいこととすでに知っていることとをつなげるまたは、新しく覚えたいもの同士をつなげるということをすると、すごく覚えやすくなります。このことは、思い出すという作業がシナプスを関連付けることであったり新しく覚えるということが脳神経のシナプスの枝葉が広がることだったり新しく広がっていったりその枝葉が太くなるということだったりと関連があるからだと思います。このつなげ方については応用していくとまさにいろんなことにつながっていて先にネットワークを張っておくというと速読とかフォトリーディングにつながるし『キイナ的速読術』(2009年2月2日の日記)映像でつなげることによって思い出しやすくするというと映像記憶につながっていきます。『思い描く力』(2009年2月23日の日記)『写し取る』(2008年9月14日の日記)あと、よく「私がいくら言っても 聞いてくれないのですが 先生が言ってくださったり テレビやどっかで聞いてきたことなら すごくよく聞くんですよね。 話してくることが 『それ、私、いつも言っているやん』 ということもあってね。。。 」と聞いたりしますよね。これも、事前に話を聞いているから新しく感じるお話を解ると思うのですよね。つまり、人は、知っていることしか解らないということです。知るということはつなげることなんだそして、つなげ上手になるにはつなげ方をたくさん知っていることこういうことが解ってくるといろいろ広がってくるんじゃないかなと最近思っています。
2009年03月04日
コメント(2)
-
ちょっぴりだけ近未来。
昨日、映画の日と知らず映画館に行ってあまりの混雑具合に、観るのを諦めて難波から南堀江、アメリカ村。。。心斎橋に行って。。。と御堂筋界隈を1時間くらい散歩してきました。1時間も歩くと、お腹もすいてきて行列ができていた和牛専門店『はり重』でビーフワン(牛丼)を食べていると背中の方から、なにやらお兄さんたちの声が聞こえてきます。ホストをされているらしい銀髪のお兄さんたちがはり重の女将さんらしき方に大きな声で、注文していたり注文したものがなかなか来ないと大きな声を出しているんですそんなやり取りがあった後3人組のリーダーらしきお兄さんが「○○達は、ほんといいよな。 新規のお客さんがついている。 新規のお客さんは、 時の『運』だけど その運すらない俺たちは、 どうすればいいんだぁ??」と、子分らしきお兄さんたちに話をしているんですね。そこから先の話は聞こえてこなかったのでどうなったのかは、ちょっと解りませんが『うまくいっていないときや ついていないと感じるときに "どうすればいいんだぁ?" と言いたくなる お兄さんたちの気持ち 解らなくはないのだけれど 時の運じゃないと思うんだよなぁ。。』と思っていました。どこにチャンスが転がっているかなんてほんと、解らないしもしかしたら、はり重の女将さんやお姉さんたちがお客さんになってくれるかもしれませんよね。で、こう考えることとお兄さんたちの考えること何が違うのだろうと思っていました。 さてさて、今日、ある小学校の授業を参観させてもらいました。総合学習の『保健』の授業で「けがの防止」についての授業でした。子ども達に、けがをしたときのことを思い出してもらって、その体験を「心の状態」「身体の調子」「危険な動作」「危険な環境」に分けてひとつずつ分析していきます。で、これに当てはまらないケースがあること危険な動作や危険な環境でないのに事故が起こってしまうことに子ども達を気付かせていました。そして、どんな時も、どこの場所も危険な動作、危険な場所になることに気付かせ絵を見て、一つ一つのケースについて『これから先に何が起こるのか? 想像してみましょう』と、先生がいいました。これを聞いた瞬間、『昨日の疑問が解けたかも?』と、とても清々しい気持ちになってニコニコ笑ってしまいました。ちょっぴりだけキンミライについてこれから先に何が起こるのか?こういったことを特別なことでなくても想像できるとき確かに歩き出す音がしたりいま始まる道の先に選んだ続きが見れたり自分が選んだ道の先にちょっぴりだけハッピーになれたりきっと何かを変えていけるそんなヒントがあるのではないか先生の授業を聞きながらそんなことを思いました。≪今日の動画≫
2009年03月02日
コメント(0)
-
褒めたところが。
◇■ ほめられる子は思いやりも育つ... 科学の目が初めて証明(読売新聞)携帯でご覧の方にニュースの一部を転記させて頂きますね♪≪ニュース≫乳幼児期に親からよくほめられる子供は他人を思いやる気持ちなどの社会適応力が高くなることが科学技術振興機構の長期追跡調査で明らかになった。育児で「ほめる」ことの重要性が科学的に証明されたのは初めて。筑波大の安梅勅江(あんめときえ)教授(発達保健学)らの研究チームは2005~08年、大阪府と三重県の計約400人の赤ちゃんに対し生後4か月、9か月、1歳半、2歳半の時点で成長の度合いを調査した。その結果、生後4~9か月時点で父母が「育児でほめることは大切」と考えている場合その子供の社会適応力は1歳半時点で明らかに高くなった。また、1歳半~2歳半の子供に積み木遊びを5分間させたときうまく出来た子供をほめる行動をとった親は半数程度いたが、その子供の適応力も高いことも分かった。調査では、〈1〉規則的な睡眠習慣が取れている〈2〉母親の育児ストレスが少ない〈3〉親子で一緒に本を読んだり買い物をしたりする――ことも、子供の適応力の発達に結びつくことが示された。(2009年2月28日14時40分 読売新聞)先週のことなんですが新しく入ってきた子が国語のプリントを解いていて解らないから、手が止まっているんです。横に座っていた女の子がその姿を見ていて「解らなかったらね。 答えを見たらいいんだよ。」と声をかけました。「えっ、答えって、 見ちゃだめなんじゃないの?」「考えても解らないものは 答えを見ていいんだよ。 でもね、さだ先生は絶対 『答えをどこから見つけたか?とか 線を引きなさいとか どうやって、答えになるかとか』 聞いてきたり 確認テストしてくるから 間違えたところ、 解らないところはね 覚えておいた方がいいよ。」と、僕の顔を見ながらコソコソ話をしていました(笑)その光景を聞きながらそういう風に感じてくれているんだと、とても嬉しくなりました。問題を解くことになれていると問題が解けたところが嬉しくて間違ったところが悲しくてって、ありますよね。そんなときに間違ったところを直したりやり方、解き方を覚えて2回目の確認テストを満点にしたりということを繰り返し褒めたり喜ぶことでその良さを分かってくれるようになったみたいです。人って、褒められたこと喜んでくれたことって嬉しいから繰り返してやろうと思うものですよね。昨夜見た、安住さんとたけしさんの情報7daysニュースキャスターの受験特集と関連して、やり方を教えていくこと褒めていくことの必要性やっぱりあるんだなと思いました。「あいの手」(2009年05月20日)
2009年03月01日
コメント(4)
全17件 (17件中 1-17件目)
1