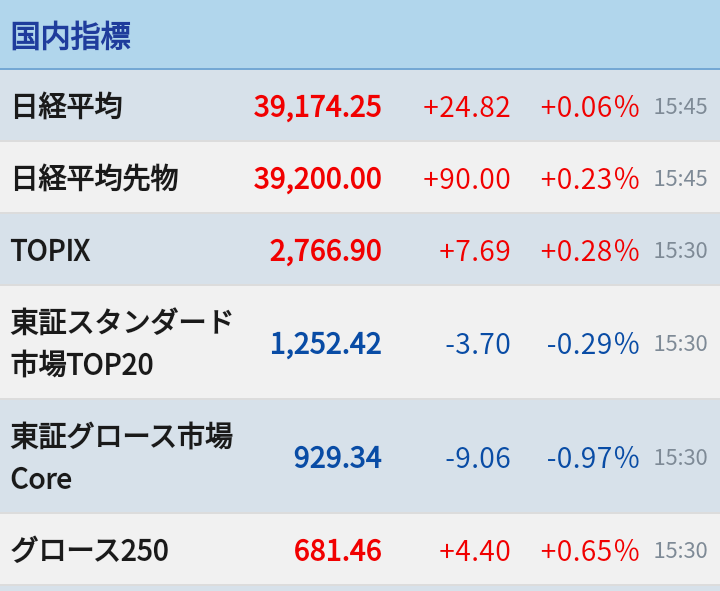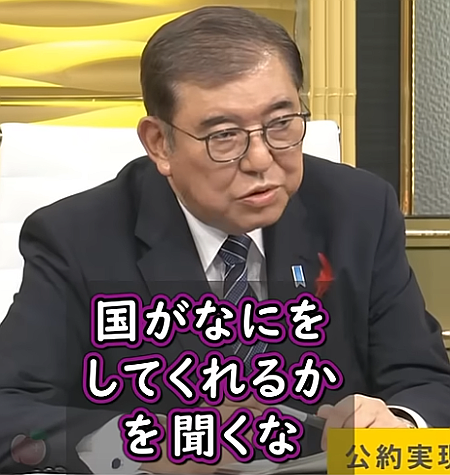2009年06月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-

愛を読むひと★ナチズム
■愛を読むひと■ 愛は本に託された。1958年のドイツ。15歳のミヒャエル(デヴィッド・クロス)は、気分の悪くなったところを21歳年上のハンナ(ケイト・ウィンスレット)に助けられる。その出会いから、2人はベッドを共にするようになり、ハンナはミヒャエルに本の朗読を頼むようになる。だが、ある日突然、彼女が姿を消してしまう…。数年後、法学専攻の大学生になったミヒャエルは彼女と法廷で再会する。彼女は戦時中の罪に問われ、無期懲役の判決を受ける。時は流れ、ミヒャエル(レイフ・ファインズ)はハンナの最後の“朗読者”になろうと決心し、彼女の服役する刑務所に物語の朗読を吹き込んだテープを送り続けるのだったが――。ベルンハルト・シュリンクのベストセラー小説「朗読者」の映画化。 何ヶ月も前から待っていた映画。ケイトの濃い一文字眉やちょっとクラッシックな顔だちが大好きで、この人の映画は、「ネバーランド」、「ホリデー」、「レボリューショナリー・ロード」など、けっこう見ている。映画館では見ていないけれど「いつか晴れた日に」や「タイタニック」も大好き。この映画、1958年のドイツが舞台。ハンナ(ケイト・ウィンスレット)の部屋には、キッチンがあり、ホーローの鍋がかけてあった。キッチンの隣には、バスタブも仕切りのない質素な部屋。15歳のミヒャエル(デヴィッド・クロス)がハンナに頼まれて石炭を運ぶシーンがあったが、この頃は煮炊きや暖房は石炭だったようだ。1958年ごろのドイツの暮らしが垣間見れて楽しかった。それにしても、ハンナはなぜ、文字を習わなかったのだろう。アルファベットは簡単なにに・・・。映画の中では、ナチの問題が大きい。ドイツでは、つい最近までナチズムに加担した人が裁かれていたのだと実感。この映画はケイト・ウィンスレットが第81回アカデミー賞主演女優賞に輝いた映画だ。・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月30日*サルビア歳時記:6月の季語 *・・・・・・・・・・・・・・
2009.06.30
コメント(0)
-

6月のおしゃれ手紙:環境月間
6月は環境月間。というわけで、環境問題に関するネタを書いた。ていうか、ほんらい環境問題と里山、歳時記をメインに書くつもりだったのに最近は、映画が多い。映画も書き残していないと、内容もだけど、なにを見たかさえ忘れるから・・・。 _| ̄|○毎月が環境月間でなければならないと思っている。■□■6月の書き残したネタ帳■□■*「ナラタージュ」*湯浅誠*派遣村■□■これまでのネタ帳■□■*友人とメール:派遣*住宅政策*体調の不安*花に恨みはないけれど:桜だらけ*四国紀行*古いまち並みで思う、いらない飾り*国民休暇村の「エコ」?*高知城で知る危機管理*京都府・舞鶴市の倉庫郡*舞鶴引き上げ記念館*朝鮮帰国船事故*梅の古木*日野*平凡な地名*古い地名*大根のクビ*日野の観光協会*ホエール・ウオッチング*京都ネタ*高級ホテル(高級はくせになる。朝食)*孫と遊ぶ(百人一首、その後の「桃太郎」の妄想)*オバマ大統領誕生*今年の目標、去年の目標。*茨木のり子の詩「鶴」■□■2009.6月に見た映画■□■■スラムドッグ$ミリオネア■天使と悪魔■重力ピエロ■ベルサイユの子■夏時間の庭■愛を読むひと・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月29日*探偵!ナイトスクープ:にわか *・・・・・・・・・・・・・・
2009.06.29
コメント(0)
-

江戸のエコ:「住」
■熱しにくく冷めやすい木造エコ住宅火鉢と打ち水で寒暖をすごす知恵。標高差の大きい山国である日本には、亜熱帯から寒帯までさまざまな気候の土地があり、人々は地域に適した住まいを断ててきた。江戸のような中緯度の低地では、冬でもあまり寒くないため、家中を密閉して「全館暖房」をする発想は、あまりなかった。大名屋敷でも、裏長屋でも炭火の火鉢や炬燵だけで冬越しをしていた。真夏の蒸し暑さに対しては、家の風通しを良くするほかに手段はなかった。しかし木材は石やコンクリートに比べ熱しにくい特性があるので、昼間の気温が高くても夕方になれば過しやすくなった。また、道路を石などで舗装しなかったため、打つ水すればすぐ夕涼みできる気温に下がった。「ヒートアイランド現象」もなく、現代のように熱帯夜に悩まされることはなかった。「夏をむねとすべし」(徒然草)で建てられた木造家屋はすぐれたエコ住宅だが、燃えやすいという大きな欠点もあり、火災都市・江戸もたびたびの大火に苦しんだ。石造りは不燃建築だが倒壊しやすく、地震の多い日本ではついに採用されることはなかった。作家・石川英輔 24歳まで住んでいたのは、藁屋根、土間、縁側のある典型的な昔ながらの農家だった。もちろん、クーラーはなし。でも藁屋根の深いひさしが強い日を遮ってくれた。縁側の前には瓢箪やヘチマの棚ががあって、これも日射しを遮り、涼風を部屋に入れた。風の通りをよくするために、寝る時も障子ははずしていた。土間を通る風で畳の部屋は、ひんやりしていた。障子をはずしても安全だったということも暑さ対策以上に大事だと思う。■なんて素敵にエコロジー!江戸■6月6日付けの朝日新聞の広告特集は江戸のエコ。全てを自然エネルギーでまかない、まったく無駄のない生活は、ただただ感嘆!■なんて素敵にエコロジー!江戸■■江戸のエコ:衣■■江戸のエコ:食■・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月27日*探偵!ナイトスクープ:にわか *・・・・・・・・・・・・
2009.06.27
コメント(0)
-

昔語:グイビ
春にはサイシンゴ(イタドリ)、夏にはカワニナ、秋にはアケビ、柿、椋など子どもの頃の私たちは、オヤツはすべて自分で野や山に行って調達していた。今の時期は、グミがあった。私が中学2年まで暮らした、岡山では、グミのことをグイビと言った。うちにも、グイビの木が植えてあり、この頃になると赤く色づく。しかし、赤くなるまで待てなかった。待っていると、きょうだいにとられる。だから、赤くなる少し手前のだいだい色になると採って食べた。もちろん、甘いはずもなく、ただ渋くて酸っぱいだけだった。隣村の電球などを売っている家が街道沿いにあった。その家には大きなグイビが鈴なりになっていた。しかも、誰もとらないのか、真っ赤に熟していた。私は不思議に思って父に言った。「**の家のグイビは、あんなに真っ赤になっているのは、なんで?」父は笑いながら言った。「あの家は、分限者(ぶげんしゃ=金持ち)じゃからグイビより美味いもんがあるんじゃ。」うちは貧乏だから、グイビを選んで食べるのではなく、グイビしかないのだ・・・父は言った。しかし、私たちは、豊かな自然の恵みに感謝していたし、父や母との暮らしになんの不足もなかった。先日、散歩の途中で、鈴なりになったグミの実を見つけ、ひとつ口に入れた。貧乏だったけれど心豊かだったあの頃を思いだした。・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月26日*父の麦わら帽子:目次*・・・・・・・・・・・・
2009.06.26
コメント(0)
-

江戸のエコ:「食」
米作りで自給率100%!魚主体で豊かな食生活。■小麦より米、肉より魚で豊かな食生活を!人口調査が行われるようになった江戸時代中期以後、日本の総人口は3000万人を上回っていた。今の約4分の1だが、当時としては世界有数の人口大国。しかし食料自給率は100%以上だった。国土面積の80%が山地で農地面積はせいぜい15%程度のわが国で、食料が自給できたのは、米を主要作物としたから。米は畑作物に比べて面積当りでは、何倍もの収量がある。また水田稲作のために水源となる広い山林が必要だが、これも国土の大部分が山である点を積極的に生かして、十分は米を生産することができた。南北に長い日本の国土には、さまざまな気候の地域があり、それぞれの長所を利用した農作物の栽培が盛んになった。芋、豆などその多くは今も各地の名産として作り続けられている。また、動物性タンパク質としては、畜産に頼らず、イワシ、サンマ、カツオなど魚を主な食品としたのも賢明だった。面積当りの生産力の低い牧畜は、わが国に適しておらず、沿岸漁業による魚介類を利用する方が、はるかに豊かな食生活が可能だった。とくに江戸前の魚は新鮮で美味とされた。ほとんど人力によって得た江戸時代の農業・漁業は自然調和型のエコ産業だった。作家・石川英輔穀物自給率32%の食料輸入大国で暮らしている私たちは、自分の口に入る食べ物が、どのようにして生産されているか知ることが、とても難しい状況にいます。国内の農業は、環境を保全し、安全な食べ物を生産する、本来の姿から、ますますかけ離れつつあります。エネルギーを大量に投入し、薬づけにされて生産され、長距離輸送される食べ物は、私たちの体を蝕むばかりか、産地の生態系を破壊し、砂漠化をさらに進めているのです。このままでは肥沃な大地やそこを耕す人の技術すら失われてしまいます。生態系のなかで、行きつづけていくために、私たちは何を食べていけばいいのか、どう生産し手に入れてゆけばいいのか、できるところから考えてみましょう。 「地球を救う127の方法」より60.肉食は飼料として穀物を多量に消費する(1kgの牛肉のために20kgのとうもろこし!)のでできるだけ野菜中心にした食生活にする。近海魚や豆をタンパク源として活用する。■なんて素敵にエコロジー!江戸■6月6日付けの朝日新聞の広告特集は江戸のエコ。全てを自然エネルギーでまかない、まったく無駄のない生活は、ただただ感嘆!・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月25日*「純情きらり」と「私の昭和」:手ぬぐい/日記のキーワード*・・・・・・・・・・・・
2009.06.25
コメント(2)
-

「少年時代」郡上八幡の夏
舞台は昭和40 年代初めの郡上八幡。清流で知られるこの町には、「町を流れる吉田川にかかる新橋から飛び込めば一人前の男」という伝統があった。一人前になるため奮闘する主人公と、友人、先生などの姿をみずみずしく描いた、甘酸っぱくも叙情豊かな長編青春成長小説。「少年時代」といえば、井上陽水の♪夏が過ぎ、風あざみ~・・・という主題歌のが有名だが、これは舞台が郡上八幡で時代も違うまったくの別物。去年、行った郡上八幡は、町の真ん中に吉田川が流れ、町のあちこちからせせらぎの音が聞こえる、水の町だった。そんな郡上八幡市が舞台のドラマということで、見たが40年代という時代設定に違和感がなかった。特に大きな町でもないし、有名なお寺や建物がある町でもない。しかし、郡上八幡には、どこにも負けない清らかなせせらぎがある。水の文化がある。滑り台付きのプールや流れるプールのある町よりも、吉田川の岩や新橋から飛び込める郡上八幡の子ども達が羨ましいと思った。▲町の真ん中を流れる吉田川。▲吉田川の川沿いの道「宮が瀬こみち」。少年たちが寝転んでいた。 ←水を止める板。 ←水を使う時はこうする。・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月23日*しょいこ【背負子】/雨の名前:空梅雨(からつゆ) *・・・・・・・・・・・・・
2009.06.23
コメント(2)
-

江戸のエコ:「衣」
■リサイクルしやすい着物古着流通が盛んな江戸むだのない仕立てで、究極のエコ衣服平和な時代が長く続いた江戸時代には、それまで貴重品だった木綿が普及して、誰でも着られるようになった。また、中国からの輸入が多かった絹も、国産が増えて一般化したが、手織りをしていた時代の布はすべて労力のかかった貴重品だった。日本の着物はむだのない構造で、長方形の一反の布を直線断ちして仕立てるため、洋服と違って布のむだを生じない。直線縫いのため、仕立て直し、染め直しがすべて容易であるため、流行が変わっても同じ布を新しい着物に仕立て直すことができる。子や孫が、親や祖父母の着物を着続けることも珍しくなかった。着物はこのような特性があるため、古着としての価値も高かった。正確な数字はわからないが、江戸時代の国内で流通していた着物の半分以上は、古着ではなかったかと推測できる。太陽エネルギーだけでつくられる繊維を、人力だけで糸につむぎ、染めて手織りして、むだのない仕立てをする「エコ衣服」。着物は最初のオーナーの手を離れても、大勢の人が着続けることのできるリサイクル型エコ衣服だったのである。作家・石川英輔かつて、着物の古着を売るステキなお店があって、羽織を買って寝巻きの上から羽織ったりしたことがある。紺に小さな模様のある木綿の昔の普段着の着物は、ほどいて、3枚に切ってスカートにしたことも。美しい紫の着物は、モンペにしてもらって、NYの蚤の市にはいていった。最近は、使わなくなった着物や帯は、リサイクルショップに売っている。下の娘は、アンティーク着物が好きで、着たりしている。とにかく、箪笥の肥やしにだけはしたくないと思っている。■なんて素敵にエコロジー!江戸■6月6日付けの朝日新聞の広告特集は江戸のエコ。全てを自然エネルギーでまかない、まったく無駄のない生活は、ただただ感嘆!・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月21日*「船乗り込み」:川のある町づくり/佐賀のがばいばあちゃん★がばい語録*・・・・・・・・・・・・・
2009.06.21
コメント(2)
-

エコアクション7:キャンドルナイト
今すぐスタート!地球に出来る30のこと:その7■夏至の日はキャンドルナイトに参加。一年で一番夜が短い日、夏至。8時から2時間、ライトを落としてキャンドルの灯りで過すことを呼びかけている「100万人のキャンドルナイト」。これまでに、小泉今日子さんや東野翠れんさんといった、エコ意識の高いアーティストが賛同して、毎年、輪を広げてきた。日の光の落ちた後のひとときを、キャンドルナイトで過してみては?***環境問題を意識した生活を送る、と考えるとなんだか難しそう。でも本当は、頭で考えるよりずっと簡単なことばかり。今すぐできる小さなアクションから地球を守ろう!「エル」よりこの行事、キャンドルナイトというおしゃれな響きに若者も共感したのか、すっかり定着した感がある。しかし、年間2回のしかも2時間消灯ということで満足していていいのだろうか?大事なのは、毎日。コンビニを24時間開けない方がキャンドルナイトよりもよほど、効果はあるだろう。その代わりに、冬至と夏至には、オールナイトでもいいではないか。でんきを消して、スローな夜を。100万人のキャンドルナイト。 ■今すぐスタート!地球に出来る30のこと■・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月19日*キャンドルナイト記念・トリビアの井戸:イッチョウラ/♪よしわらタケノコ~ *・・・・・・・・・・・・・
2009.06.19
コメント(0)
-

おしゃれ手紙4◆ゆかたデビュー
天地 はるな様素敵な方にお会いできてよかったですね。ホント、「大人の女」って憧れます。私は、ある作家の影響で「年をとっていく」ことに恐怖をいだいていた時期がありました。若いときは、ちやほやされても、そのうちに誰も振り向いてくれなくなる・・・と(私のバヤイ、残念ながらバラ色の日々はなかったのですが)。でも、それって自分に自信がなかったからなんですよね。今では地図も手に入れ、自分の現在地や進んでいく道が見えてきたし、ステキな人たちに囲まれて、私って捨てたもんじゃなかったんだわーなどと、自分自身を受け入れられるようになってきたから、年なんて、どうでもよくなってしまいました。お年を召した方でも、うーんとステキな人は沢山いるし、若くても、思いっきり老けた人もいますもんね。要するに「キモチ」の問題ですよね。目指せ!「おしゃれな大人の女の人」なのです。 私も、昨年から着物に挑戦!しています。と、いっても「ゆかた」ですが…。自分で着られるような「らくちん着物系」に惹かれたのです(着物って「位の高いおひと」や「舞子さん」は例外として、本来はみんな自分できていたと思うのですが)。着物はステキだと思います。しかし、どうしても「新地のママ」みたく、ゴージャスな着物をイメージしてしまって、ちょっと抵抗がありました。上手く表現できないのですがこんな「着物」は「偽物」のようで好きになれませんでした。ラフなTシャツやジーンズのような「着物」もあったのでしょうが、そんな感覚の着物が着てみたいと思い、「ほな、ゆかたやで」となったのです。昨年、5年越しに「お気に入り」を見つけ着付けの特訓。汗だくで、なんとか、手順を覚えました。下駄は6年前に買ってあったので(へんなところのみ準備のよい私)、その下駄で「花火」の日に 「ゆかたデビュー」 。慣れないもんだから、靴ずれ、ならぬ、下駄ずれの受難にも、負けず今年も「ゆかた」に挑戦するぞと、意気込んでいる、私です。おばあちゃんが着ているような、あの着くずしが出来るよになったら、いっちょまえやんと思っています。はるなさんが買われた着物、是非、見せて下さいね、楽しみにしています。 浜辺 遥◆◇◆おしゃれ手紙◆◇◆◆これは今から10年以上前に書いた公開往復書簡です。・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月17日*父の麦わら帽子:蛍 /大阪しぐれ:マサコさん *・・・・・・・・・・・・・
2009.06.17
コメント(0)
-

エコアクション6:コーヒーのフィルター
今すぐスタート!地球に出来る30のこと:その6■コーヒー好きのお家には、1000回使えるフィルターを!環境意識の高まりとともに、無漂白の紙フィルターでコーヒーを入れることが定着してきたが、さらにその上をいくスーパーフィルターがこの「ミル・カフェ」。Mille(ミル)がフランス語で1000を意味するように、このフィルターは洗って1000回使えるエコ製品。紙のフィルター1000枚分のゴミを削減してくれる。アウトドアにも持参したい。***環境問題を意識した生活を送る、と考えるとなんだか難しそう。でも本当は、頭で考えるよりずっと簡単なことばかり。今すぐできる小さなアクションから地球を守ろう!「エル」より胃が弱いからコーヒーは、めったに飲まない。もし飲んでも、インスタントだから、フィルターは使わない。以前、近所に住んでいた友人が大のコーヒー好き。コーヒーは豆を買っていて、それを、手回しのコーヒーミルでガリガリと挽いていた。挽き終わるとネルのドリップに入れ、ゆっくりと熱い湯を注いだ。その一連のゆったりとした手さばきに、うっとりとしたものだった。彼女は、コーヒーのカスを靴箱に入れて再利用していた。毎日使うものや食べるもの、飲むものは、一生のうちに、けっこうなゴミやCO2になる。コーヒーをふた口飲んで まだ来ない 秒針ふるふる震える心 俵万智『とれたての短歌です』・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月15日*こごめ/トリビアの井戸:はかどるの語源*・・・・・・・・・・・・・
2009.06.15
コメント(0)
-

夏時間の庭★オルセー美術館
■夏時間の庭:あらすじ■誰にでも思い出が輝く場所がある。パリ郊外にある、画家であった大叔父のアトリエに一人で暮らしていた母が亡くなり、3人の子供たちには広大な家と庭、そして貴重な美術品が遺される。相続の手続きをする中で、3人が向き合うのは、思い出に彩られた家への愛着と現実とのジレンマ、そして亡き母への想いだった――。母から子へ、また孫へと永遠に受け継がれていく家族の絆を描いた感動作。 『夏時間の庭』に登場する美術品は、絵画を除いたすべてが美術館や個人所蔵から貸し出された本物です。どっさりと書類が置かれている美しい机は、アール・ヌーヴォーの家具デザイナー、ルイ・マジョレルの作品。パリの芸術家に日本の美を広げたフランス随一の印象派銅版画家フェリックス・ブラックモンの花器には、庭で摘んだ花が活けられます。観賞用ではなく、劇中では日常的に使われているという設定の美術品の数々を堪能できるのも本作の大きな見所です。また、アトリエと広大な庭があるのは、セザンヌやモネなど印象派の画家たちが愛してやまなかったパリ郊外のイル・ド・フランス地方ヴァルモンドワ。オルセー美術館開館が全面協力して製作された作品。そんな美術品のような家具が邸宅の中に普通に使われている。けれどそれゆえ、持ち主が亡くなれば、それらは、家具ではなく美術品となり、お金となる。思い出は大切だけれど、今を生きる人にしてみれば、お金も大事。そんな葛藤が描かれている。最後、家具や花瓶は、美術館にいく。それでよかったのかもしれない。●写真は島根県の松江ガーデンミュージアム。・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月13日*時計の無い暮し/関西人気質 *・・・・・・・・・・・・・
2009.06.13
コメント(0)
-

ベルサイユの子★ホームレス
■ベルサイユの子:あらすじ■寒くても、お腹がへっても、手を握っていてくれたら、ぼくは泣かない。17世紀フランスの繁栄の証で、いまなお観光名所として多くの人々で賑わうフランスの世界遺産、ベルサイユ宮殿。しかし、その宮殿の森に現在、多くのホームレスが暮らすことを知る者は少ない。社会からはみ出て生きる男・ダミアン(ギョーム・ドパルデュー)は、ある日突然、母親に置き去りにされた5歳児のエンゾ(マックス・ベセット・ド・マルグレーヴ)の世話をする羽目に。全てを諦めたかのような男と、右も左も分からない子供の間には、いつしか本当の親子以上の情愛が生まれるのだが…。37歳という若さで他界したギョーム・ドパルデュー主演で贈る美しい絆の物語。ベルサイユの森にホームレスが沢山住み着いているというのは、この映画のことを知ってから。日本の都会に暮らすホームレスとは大違い。緑の森の中に小屋を作って、焚き火をし煮炊きや暖をとる。ちょっとしたアウトドア生活、「森の生活」のようだ。他のホームレスとも仲良く暮らしていて、調味料の貸し借りをする。時には、大勢(映画の中では10人くらい)が集まって飲んで歌って踊る。死人が出れば、みんなで葬式をする。小さな共同体だ。しかし働いていない彼らは、現金を手に入れることが出来ない。だから、捨ててある食料を拾って食べようとする。しかし、捨てたものさえ、拾うことを許さない人がいる。そういう人々は、捨てた食料の上に、洗剤をかけるのだ。どうせ捨てるなら、拾わせればいいのに・・・。かつてヨーロッパには、■落穂拾い■という風習があった。落穂拾いとは、中性から近世にかけてのヨーロッパの農村共同体で、収穫後の耕地に散乱する落穂を老人、寡婦、孤児、障害者などに拾うことを許した慣行である。これは社会の弱者を保護し扶養する手段のひとつであった。今より中世の方が農村の暮らしは大変だっただろう。なのに、豊かな今、拾う人を排除するとは許せない。しかし、さすが、フランスのホームレスに対する対応は日本とは大違い。若い母親が小さな子どもを連れて野宿していると、夜回りの警察官が来て、清潔なベッドに連れて行く。森で暮らすホームレスが病気になった時にも、入院させた。日本はというと、師走の寒い中、自殺しようとるするホームレスを見た警官が連れて行ったのは、ボランティアで運営する「派遣村」!!映画に出てくる幼いエンゾ役の年は6歳くらいだろうか。あるときは、母親を、あるときは、森の男と一緒にさすらう姿が切ない。しかし可愛い。主演の森に一人で住む男を演じる、ギョーム・ドパルデュー。彼は2008年10月、急性肺炎で37歳という若さでこの世を去った。( ̄人 ̄)・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月11日*里山のオキテ *・・・・・・・・・・・・・
2009.06.11
コメント(2)
-

重力ピエロ★遺伝子
■重力ピエロ:あらすじ■家族の愛は、重力を超える。連続して起こる放火事件と、現場近くに必ず残される奇妙な落書き。その謎は、幸せそうに暮らす奥野一家の24年前の哀しい過去へと繋がっていく…。遺伝子研究をする兄・泉水(加瀬亮)、落書き消しをする弟・春(岡田将生)、そして病いと闘う父(小日向文世)――強い絆で結ばれた家族の決断とは?常識を超えた大きな愛に心で泣く、感動ミステリー。伊坂幸太郎の大ベストセラー同名小説が原作にした、家族の愛と謎の物語。今をときめく、俳優、加瀬亮、岡田将生を目当てに行った。もちろん、マー君こと岡田将生の顔の美しさには、やられたが、内容も負けないくらいによかった。この映画は、ミステリーだ。いろんなところに、複線がはってある。連続放火事件、アートな落書き、泉水(いずみ)と春(はる)という主人公の兄弟の名前。過去のいまわしい事件、母親の死・・・。全てが絡まっていている。映画の冒頭、満開の桜の花びらが散るのを見て「春が二階から降ってきた」というくだりがあるが、その後、弟の春が降ってくるという出だしも素敵だ!その春は終わりでも二階から降ってくる・・・。素晴らしい!これ以降は、ネタバレになるのでこれから映画を見ようという人は読まない方がいいかも・・・。泉水(いずみ)と春(はる)兄弟の奥野一家の不幸は、兄弟の母親がレイプされたことに始まる。母親は妊娠してしまう。そして夫婦は悩んだ末、出産することに決めた。なんで?犯罪に巻き込まれても、そこでストップすればいいじゃないと私は思う。なんで、その不幸をいつまでも引きずるような出産をするのかと・・・。犯罪者の子どもは、犯罪者になる可能性が高いという意見もある。犯罪の遺伝子が子どもに伝えられることになる。父親は違っても俺たちは最強の家族だと言っても、不幸には代わりはない。笑っていれば、重力に逆らえるというけれど、そう簡単なことではあるまい。・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月10日*トットが来たら豆を蒔け:時の記念日*・・・・・・・・・・・・・
2009.06.10
コメント(2)
-

「私の気ままな老いじたく」吉沢久子
自分の人生の仕上げの時期を、自分なりに楽しく生きなければ、つまらないではないか」と考えるようになったのです。老いは死を待つ時間ではなく、未知への道すがらなのですから、すべてを終える日まで、無理なく素直に自分らしく生きていくのが一番いい。旅じたくのバッグに旅の楽しみを入れていくように、道の老いへの道すがらにも、楽しいことはいっぱいあるにちがいない、と思いついたのです。(「はじめに」より抜粋)「私の気ままな老いじたく」を読んだ。人は誰しも老いていくもの。最近、そう思うことが多いからだ。だから老いじたくをしようと・・・。私の老いじたくは、「モノを持たないこと!」。父母が実家の岡山から老人ホームに住むようになったときに、要らないものがあまりに多いと思ったから。妹と、ビニール袋に入れながら、もったいないという思いでいっぱいだった。それから、私は本を買わない。まったく買わないとは言えないけれど、ほとんど買わない。この「私の気ままな老いじたく」も図書館で借りたもの。化粧品もそれまでは、欲しいと思うままに買っていたのが、使っているものが、なくなってから。この当たり前のことがなかなか出来なかったのだ。■置き場所、しまい場所は確認して。という章があった。最近、眼鏡がないと細かい字が見えない。で、眼鏡を使う。それを何気なく置いて次に使うときに探す・・・。薔薇の花を切ったハサミを何気なく置く。それを探す・・・。そんなことが多いのだ。お隣の奥さんに話したら、「分かる、分かる。私なんか、鍬の置き場所を忘れたもん」と2人で笑いあった。それをなくするためには何気なく置くをなくすることだという。気をつけよう。・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月9日*里山の歌・夏はきぬ/植物のチカラ:イグサ *・・・・・・・・・・・・・
2009.06.09
コメント(0)
-

なんて素敵にエコロジー!江戸
■世界最大の都市・江戸、究極の循環型社会を実現!江戸時代の日本や社会は、国内産の植物資源を徹底利用することで、ほぼ完全な循環構造になっていた。光熱源は、胡麻(ごま)、菜種油などの植物油、薪炭などすべて国内のバイオマス燃料を使い、動力の大部分を人力に頼ったため、環境に与える負荷も最小限だった。食料は、穀物を主としたが、すべて国内産であり、その生産には太陽エネルギーしか使わなかった。人力以外の動力だった畜力(牛馬)、水力(水車)、風力(帆船)も、すべて太陽エネルギーの直接的あるいは間接的利用である。現代と同じ基準で計算するなら、社会全体がゼロ・エネルギーによって運営されていたことになる。江戸時代の工業は、注文生産に近い程度の生産力しかなかったが、それだけに「物」が貴重であった。リサイクルがごく自然に行われるため、廃棄物はほとんど出なかった。人力による生産は肉体的には安楽ではなかったが、「無から有」を生じるため、エネルギー効率は現代社会とは比較しようもないほど高かった。排泄物も肥料として再利用するなど、江戸ではきわめて自然にエコ社会が成立していたといえる。作家・石川英輔6月6日付けの朝日新聞の広告特集は江戸のエコ。全てを自然エネルギーでまかない、まったく無駄のない生活は、ただただ感嘆!最近、やっと日本でも電気自動車が実用化したが、それを作る過程で、電気を使い時を考えると、CO2が全く出ないわけではない。そう思うと、江戸の暮らしはすごい!■大江戸トイレ事情■・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月7日*「暁すばる」:すばる満時、夜は七つ*・・・・・・・・・・・・・
2009.06.07
コメント(0)
-
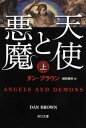
天使と悪魔★イルミナティ
■天使と悪魔:あらすじ■ヴァチカンを光と闇が包み込む・・・。ロバート・ラングドン教授(トム・ハンクス)は、歴史上最も謎に包まれた秘密結社“イルミナティ”の復活の証拠を発見し、彼らが最大の敵とみなす“カトリック教会=ヴァチカン”に致命的な脅威が迫っていることを知る。イルミナティの計画が密かに進行していることを突き止めたラングドンはローマに飛び、400年の歴史を持つ古代の“シンボル=暗号”をたどりながらヴァチカンを救う唯一の手がかりを探っていく…。「ダ・ヴィンチ・コード」の著者、ダン・ブラウンによるベストセラー小説「天使と悪魔」を映画化した『ダ・ヴィンチ・コード』シリーズ第2弾。前作に引き続き、トム・ハンクス扮するラングドン教授が、イタリア・ローマを舞台にヴァチカンの存在を揺るがす、伝説の秘密結社の存在に深く迫る!「イルミナティ」・・・。この世にはもう存在しないはずの最古の秘密結社。その正体は、長きにわたり、カトリック教会から弾圧を受けた、ガリレオ・ガリレイを中心とする科学者集団。彼らは復活し、ついにカトリックの総本山であるヴァチカンに復讐の牙をむく。そのローマ教皇が逝去し、新しい教皇を選出sるコンクラーベの時だった・・・。ラングドンはガリレオが歴史の闇に隠した古(いにしえ)の暗号をたどりながらヴァチカンを救う唯一の手掛かりを探っていく。*****「イルミナティ」という言葉はこの映画を知るまで、全く聞いたことが無かった。テレビでもこの映画公開に際して、「イルミナティ」を解説しているのがあった。それによると、宗教によって、科学者が弾圧され、その多くは殺されたという。有名なのがガリレオ・ガリレイ。当時、輝かしい経歴の科学者だった彼も、地動説を唱え、異端として教会から最終的に、1992年、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世は、ガリレオ裁判が誤りであったことを認め、ガリレオに謝罪した。ガリレオへの刑は無期刑であったが、直後に軟禁に減刑になった。しかし、フィレンツェの自宅への帰宅は認められず、その後一生、監視付きの邸宅に住まわされ、散歩のほかは外に出ることを禁じられた。すべての役職は判決と同時に剥奪された。そして、ガリレオの名誉が回復したのが300年以上たった1992年!!ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世は、ガリレオ裁判が誤りであったことを認め、ガリレオに謝罪したのだ。遅すぎ!!とはいえ、2003年9月、ローマ教皇庁教理聖省(以前の異端審問所)は、ウルバヌス8世はガリレオを迫害しなかったという主張を行ったり、2008年1月16日の毎日新聞によると、ローマ教皇ベネディクト16世が17日にイタリア国立ローマ・ラ・サピエンツァ大学での記念講演を予定していたが、90年の枢機卿時代にオーストリア人哲学者の言葉を引用して、ガリレオを有罪にした裁判を「公正だった」と発言したことに学内で批判が高まり、講演が中止になったという。21世紀の今も、世界の各地で、戦争が行われている。その多くが、宗教がらみ。無宗教でよかった。映画は意外な展開で終わる。映画の場面は教会、教会、教会・・・。ヨーロッパの文化はよくも悪くも、キリスト教と切っても切れない関係にあるのがわかる。・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月6日*父の麦わら帽子:へんなれぽんなれ*・・・・・・・・・・・・・
2009.06.06
コメント(1)
-

関西人の好きな小さな「っ」
関西人は、特に大阪人は、小さい「っ」が好き。例えば、「小さい」は「ちっちゃい」とか「ちいっこい」。「一番」は「いっちゃん」というように。そんな大阪に住む私が先日、八百屋に行った。 季節の野菜に混じって、タケノコが!!今は、ハチクの季節。大阪人はここでも、小さい「っ」を使う。 ↓ ↓ ↓ 「はっちく」!! _| ̄|○・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月5日*京都・白川の語源*・・・・・・・・・・・・・
2009.06.05
コメント(0)
-

スラムドッグ$ミリオネア★運命
■スラムドッグ$ミリオネア:あらすじ■運じゃなく、運命だった。インドのスラム街で育った孤児のジャマール(イルファン・カーン)は、世界的な人気番組「クイズ$ミリオネア」で、あと一問で全問正解という状況にいた。だが、無学の少年が答えられるはずないと、司会者には疑われ、賞金の支払いを渋るTV番組会社の差し金で警察に連行され、尋問を受けることになる。一体なぜ、ジャマールは100ドル札に印刷された大統領の名前や、ピストルの発明者を知り得たのか…? 警察の尋問、クイズが続く番組、そして彼の子供時代の記憶を行き来しながら、貧富の差が混在するインドを生き抜いた少年の人生を描く。世界中で絶賛され、数多くの映画賞に輝いた感動のドラマ。貧しい若者がつかみとった一攫千金のチャンスと、その裏に隠されたせつない人生模様をドラマチックにつづる。5月15日付けの朝日新聞では、「スラムドッグ$ミリオネア」で中心人物の子供時代を演じ、人気を博したスラム出身のアザルディン・イスマイル君(10)らの住居など、市内のスラムに建つ約50の小屋を強制撤去したと報じていた。市当局は、下水溝の上の違法建築物撤去が目的と説明するが、イスマイル君をはじめエキストラとして出演した約20人の子供たちも家を失い、路上生活を余儀なくされることになった。イズマイル君は「どこにも行くところがなく、暑い中、路上にいるしかない」と悲しみに沈んでいるという。作品のオスカー受賞に貢献したイスマイル君らは、ムンバイのあるマハラシュトラ州から住居を供与される約束だが、いまだ実現していない。小屋としかいえないような住まい。その小屋さえも取り上げられ、なんの保証もなく路上に放り出される子ども達。貧乏、宗教による差別、暴力、悪い大人、差別・・・。(この映画でインドには、宗教の違いによる差別などもあるのを知った。)インドのスラム街で暮らす子ども達の厳しくも、生き生きとした現実を描いている。ゴミの山を駆け回り、泥水の中で泳ぎ回る子ども達を見ていると、ここは、アトピーなんかないんだろうなと思うほど、子どもたちは生き生きと、真剣に暮らしている。辛い現実を描きながら、最後、ほっとするような幸せな気分になれた。主人公ジャーマル役の男の子と彼の初恋の人役の女性は、私生活でも恋人同士だとか。これも運命?(^-^)第81回アカデミー賞■作品賞■監督賞■脚色賞■撮影賞■編集賞■作曲賞■オリジナル歌曲賞■音響賞(録音賞)の8冠に輝いた作品。・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月4日*すべらない話:しらこい*・・・・・・・・・・・・・
2009.06.04
コメント(0)
-

エコアクション5:電気はこまめに消す
今すぐスタート!地球にできる30のこと:その5■電気はこまめに消す。気がつくと以外にムダ使いをしてしまっているのが電気。誰もいない部屋の電気がついていたり、見ていないテレビがつけっぱなしだったら、すぐにスイッチを消して!ちりも積もれば山となる、で、ちょっとした電気ので節約は気がつくとかなりの量になるもの。電力消費がダウンすれば、CO2排出量も削減されるので、地球温暖化にも効果が期待できる。身の回りのスイッチは地球につながっているのだ。***環境問題を意識した生活を送る、と考えるとなんだか難しそう。でも本当は、頭で考えるよりずっと簡単なことばかり。今すぐできる小さなアクションから地球を守ろう!「エル」より電気のスイッチはもとより、コンセントを抜くようにしています。コンセントを入れているだけで、わずかかけれど電気が通ってるから。今、家の中でもったいないと思うのは、トイレ。トイレは使う時間より、使わない時間の方が圧倒的に多いのに、なんで便座だの消臭だのといろんな電気が入りぱなしになってるんだろう。もったいない!■今すぐスタート!地球にできる30のこと■・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月1日*昭和恋々:金魚/大江戸トイレ事情*・・・・・・・・・・・・・
2009.06.03
コメント(0)
-

サルビア歳時記:6月の三箇条
■私的「更衣(ころもがえ)」をする。夏服に衣更えをする1日には、学生のころの、皆が着てきた白いブラウスに染まった教室のまぶしさがなつかしくなります。涼しげに見える色、デザインの服を新調してみませんか?■「梅雨寒(つゆざむ)」に注意。梅雨どき、気温が上がらない日を「梅雨寒」といいます。冷たい雨に濡れて風邪をひかないように。ちなみに、「梅雨」という言葉は中国からきたもの。梅の実が熟すころの雨だから、だそうです。■傘のお手入れ、忘れずに。傘に水滴が残ったまましまいこむと、かびたり、骨が錆びついたりして、だいなしになってしまうことがあります。傘はよく乾かしてから閉じるようにしましょう。 探してはいるけれど、最近、これ!!という服に出会わない。若い人が、フリルやレースが沢山ついた服を重ね着などを楽しんでいるのを見るのは楽しい。しかし、背中の肉がはみ出したような、どうみても年配としか見えない女性が同じような服を着ている。それも多くの人が・・・。私は5年くらい前の病気ダイエットで同じくらいの年齢の人よりは、だいぶ細い。しかし、贅肉はついている。重ね着など、よっぽどスレンダーな体型でないと、ただ見苦しいだけだと思う私は、無理。そんなわけで、夏のお気に入りの通勤の服(上)は、白い開襟ブラウス(40年以上前のもの)、ハワイアンな感じのシャツ2種類と白、黒のTシャツ。白と黒のポロシャツ、50年以上前のものと思われる派手な柄のブラウス(手作り)をとっかえ、ひっかえ着ている。本当に欲しいのは、新しい服より、メリハリのついた、スレンダーな体型かもしれない。■サルビア歳時記:1月の三箇条■■サルビア歳時記:5月の三箇条 ■・・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月1日*サルビア歳時記:6月の季語*・・・・・・・・・・・・・
2009.06.01
コメント(0)
全20件 (20件中 1-20件目)
1