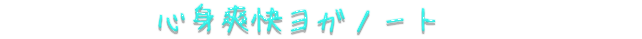2008年02月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-

ヨガ指導実習☆ヨガを伝える事とは!
半年間通った、龍村ヨガ指導者養成も残す所あと1回になりました。きのうは、指導の実習(シュミレーション)を各自数分受け持ってみんなの前に立ち行ないました。実際に人前で、やるのは難しいし、緊張しますね。(*^_^*);>僕は敢えて、話しながらやると、ふらついたりしがちなものに挑戦!片足立ちバランス・立ち木のポーズ(ブリクシャアサナ)を、”軸をつくるというテーマ”でやらさせていただきました。・まずはターダアサアナ(山のポーズ:直立立ち)で両足を ぴたっとつけた一本の軸を通した感覚を説明。・そこから片足をあげたときもそれを軸の一本に残すようにする。 というとこに進み。・シルシアサナのときもこの軸を生かして 逆立ちするというのを解説しながら実演。・足を上げたときの腰の左右前後のふらつきをなくすための 股関節回し(前の内回し・前で外回し・横に開き前後の回し)を やってもらいました。 これは自分の片足立ちのオリジナル練習です。・そこから立ち木のポーズの誘導。 ポイントとして 軸を生かしたまま足を上げる 視線の大事、 呼吸を安定すること、 やじろべえバランスの取り方などを説明。こんなことをさせていただきました。でも人の指導実習をみていると、実際にインストラクターをされてる方は上手ですね。流暢だし、呼吸をつかんで流れを作っています。僕は、そうは行きませんが、実際に自分で感じた身体感覚やオリジナル練習などをいれ、個性を生かしてやって行きたいと思います。マニュアル的でない自分スタイルのヨガを作ります。伝える方法はオリジナル=個性で行きます。そして伝える内容は”真実:核心”をです。真実をつかむ方法を伝え真実を相手が感じてもらうお手伝いをするのがヨガを伝えていくということですから。龍村修先生の言葉をご紹介します。 「ヨガの権威は、真理(真実)です。 偉い先生だから権威なのではありません。 有名だから偉いのではありません。 真実を知っているから権威なのです。 ヨガは自分で真実をつかむ感じる、行法哲学です。 だから、知らないうちは聞きに行く。 体験する。そうして自分でつかんでいく。 そうしていくうちに、聞きに行っていたものが いつのまにか人が聞きに来るようになります。」深い言葉です。聞きに来るからといって自分が偉いんだと勘違いしてはいけません。自分が権威なのでなく、自分がヨガの真実を伝えるから人が聞きに来ているんです。だから龍村先生は「ヨガを教えている」× のではなく 「ヨガを教えさせていただいてる」○ と言いなさいと教えてくれます。真理、真実というものを伝えさせていただいてるだけですから。日本ヨガの父、沖 正弘先生の愛弟子の龍村先生は日本のヨガの歴史の流れからいってもすごい人です。また人格者です。その話を聞くだけで自分の考え方の歪みに気づけます。一般で言えば”ヨガの権威”です。でも威張ったとこなんか微塵もありませんし宣伝も控えめです。いや一般に広めすぎないようにしているのかも知れません?人の肩書きや資格が偉いと勘違いするから、組織や社会で間違いや問題が起きるんですね。ヨガや精神世界の組織でもあることです。龍村先生はそれを言っているんです。自ら、教えさせていただくという境地を実践されています。あいさつも「お願い致します。」と合掌して始まります。こういうことが修了証という形の資格ではなく心から心に渡されたヨガ指導の資格なんだと思います。 師にヨガの真実に感謝(合掌) Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOKヨガ指導実習☆ヨガを伝える事とは!
2008/02/29
-
その子は手を上げて?
今朝、前を行く自転車の お母さんの後ろ、幼児用後部座席で 小さい子が手を上げていた。 ふかふか暖かそうな毛糸の手袋をした手だ。 頭も同じ毛糸の帽子で すっぽりと包まれている。 その子は ずっと手を上げているので 何かに挨拶や合図しているのかな? と思って見ていたら その子もじっと見てる。 自分の上げた手を。(^O^)/ 正確には 自分の手袋の甲に書かれたイラストを。 そこには 子供達が大好きな まんまる顔の熊 プーさんが描かれていた。 ご満悦だったんだ こんな幸せ見つけた朝。・・・・
2008/02/28
-

園児に学んだ`☆´今に生きる
きのうの朝、狭い道を通り掛かるとゴミ収集車がバックしていて、通行をせき止められました。助手席の方が、車から降りてバックの誘導をしています「オーライ~」「オーライ~」とすると僕と一緒に止められたお散歩?の保育園の園児たちがその”オーライ”を復唱し始めました。 小さな子供たちが手を振りながら、 可愛い声で\(^o^)/オーライを繰り返します。「オーライ~~~♪オーライ~~♪」通勤途中の大人、急いでいる人ならこういう場面、少しの時間ですが通行を止められたらどんな気持ちになるか?「おーい勘弁しろよ、こっちは急いでいるんだから!」なーんてなりますね。d(^-^)それが園児たちは違います。今をそのまんま楽しんでいます。「オーライ~~~♪オーライ~~♪」「オーライ~~~♪オーライ~~♪」それを見ていた僕は、うんーーすごいな、小さな子供の感じ方は・・今を楽しむ感性、いいなと関心してしましました。 時間の中のわたしたちは、 瞬間瞬間に生まれ変わっていくともいえます。 さっきの自分はもういません。 今の自分だけがいます。 また未来の自分はまだいません。 今の自分がいるだけです。 そうすると今の自分というものが 生きることをつないでいるのです。 今 怒りというエネルギーを 次に来る 今に つないでいくか 今 楽しむというエネルギーを 次に来る 今に つないでいくか これを業(カルマ)と昔のインドの人はいいました。 難しいことではありません。 今、やるべきことを気づいている、 知っているかです。大人は今を楽しんでいる子供にいらいらする姿を見せてはいけません。それを見た子供は「ああ こういうとき大人は怒るものなんだ」と覚えてしまいます・そんなマイナスエネルギーを、多数の人の未来へつないでしまう。これが罪というんです。次にヨガの事でいいます。これは、IYCのインストラクターメグミ先生におととい伺った話が元です。 ↓↓↓ 「今あるヨガポーズができなくて苦しんだり 固執したりするとします。 それで悪い自我が出てきたり、 苦しんでいる自分が続いていってしまうという事がおこります。 悪いエネルギーの循環になります。 アシュタンガヨガのビンヤーサは 車輪のようにエネルギーをまわしていると 例えることができます。逆戻りや 止めることは不自然です。 また書道のように筆を紙につけ書き始めたら 墨が跳ねようが、擦れようが氣にしないで 書き終えるものにも同じです。 アシュタンガヨガのメニューをするうえでも そうで、忘れて抜かしてしまったポーズに戻ったり できないポーズにとどまり固執しないのが原則です。」今を楽しむことを教えてくれた園児たちや聡明な智慧をもつメグミ先生のような方に出会えて僕はしあわせです。(*^_^*)Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK園児に学んだ`☆´今に生きる
2008/02/27
-

ヨガの真髄`☆´ブッタの教えの真髄
「今に気づいている女の人をヨギーニといいます。 今に気づいている男の人をヨギーといいます。 ヨガポーズをしてるからヨギーニ・ヨギーではありません。 そして全てに気づいている人を昔のインドの人は”ブッタ” (目覚めた人)と呼びました。」これが龍村修先生(龍村ヨガ研究所)の教えです。ヨガ(ヨーガ)をするとは、今!現在に気づき、今!やるべきことを知っていることです。すなわち、今という瞬間、瞬間に己の枠を越えて結んでいることです。それに気づくための、アサナであり呼吸であり瞑想がヨガの手段なんです。 それでは人間としてのブッダの教えを今につないでいる、スリランカ、テーラワーダ仏教(上座部仏教)の教えをアルボムッレ・スマナサーラ師の著書から「ブッダは『一切智者』であり、仏教は『智慧を完成する道』です。」「なぜ人間にすべてを知ることが出来るのか?という問いに」「私たちは宇宙の一部です。みなさんも宇宙の生態の一部であってなにひとつ欠けているわけではありません。そうであればすべてを知ることができないはずがない。むしろ知ることができて当たり前でしょう。」 「ブッダ・大人になる道」 アルボムッレ・スマナサーラ ちくまプリマー新書よりこの二人の言葉は同じことを言われています。さらにこの龍村先生の言葉を・・・ 「みなさんの体の中で働いているミネラル元素、 たとえば鉄の原子ひとつ! これは宇宙が出来たとき一緒に出来たものです。 ですからその小さい粒に、 宇宙全体の情報が入っている。 こうも言えますね。 そしてみなさんの体を作っている DNAは生命進化の全て、地球の全てを記憶しています。」気づく能力は小宇宙としての私たちの心身に備わっているんです。全ての人が悟れる力、悟りえる能力を”仏性”と沖ヨガや仏教では呼びます。仏性とはすばらしい能力です。が、超能力のことではありません。気づく能力であり、感情的には慈悲をそして知性的には智慧を完成させる能力です。その慈悲・智慧とひとつになる状態がパタンジャリのヨガの8支則の最終段階、三昧(サーマディ)すら超えることなのです。暴力はいけない。これはヤマ(禁戒)のひとつです。アヒムサとインドの言葉で言います。でも暴力はいけないと強く”敵意”で人を非難することはまた暴力なんですね。そこでこの仏性の登場です。ヤマ・ニヤマの車輪を正しく回す為には愛(慈悲と智慧)のエネルギーでもって回すのです。ここまで行為と今という時間と、小さい自我(エゴ)を超えてこそヨガでありブッダの教えなんです。結ぶ(ヨーガ)”今に気づく”ということはこういうことです。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOKヨガの真髄`☆´ブッタの教えの真髄
2008/02/26
-

脳梗塞で動かなかった腕を動かしたもの!?
ヨガ(ヨーガ)とは結ぶ、繋ぐという意味のインド古代からある言葉で、神(宇宙)と自分を繋ぐ体と心を繋ぐ生活と自分を繋ぐといろいろに使える便利な言葉(笑)ですね。”関係の哲学”といってよいかもしれません。そして「ヨガの体操法は脳の開発、神経の通路を開発することでもある。」とよく龍村先生はおっしゃいます。体の中の情報伝達回路である、神経を繋いでいくのもヨガなんです。そのため、やったことのない姿勢や動きをヨガレッスンに取り入れていくというのがそのため沖ヨガにはたくさんあるのです。自分で自分にする能力・脳力開発&リハビリなんです。それに関係して本を読んでいてこういう例を見つけました。「ストレスから自分を守る脳のメカニズム」 高田明和著 角川ソフィア文庫 という本です。動かなかった腕を動かしていくリハビリでなにが起こったか。 ある人が脳梗塞で左脳がやられ、 その後遺症で右腕が動かせなくなってしました。 ご存知のように脳の大脳皮質という最後に進化した人間の脳の部分は 右脳、左脳とふたつにわかれていて それぞれ交差した神経をもって体の半分を受け持っています。 右脳は左半身を、左脳は右半身を・・です。 この方は左脳をやられていたので右半身に後遺症が残っていたのです。 その右腕をリハビリで動かしていく訓練をしていくうちに 少しずつ腕が動かせるようになっていったそうです。 動かそうとする努力が、それを実現させているのですが、 これが私の学んでいるヨガの考えでは ”脳の神経を結んでいくヨガ” ”目的と方法を結んでいくヨガ”と言えるのです。壊れた左脳の神経が繋ぎ合おう・繋ぎ合おう・・としていきます。それでもなかなか、壊れた脳の神経は回復してくれません。しかし希望をもってリハビリを続けていくと奇跡的なことがおこります。本来の受け持ちでない脳の半分、この場合右脳の神経が、左脳から出る、右腕を動かす神経に向かって補助の手を差し伸べていくそうです。動かない右手を動かそうとうする行為が、体の新しい回路をつくっていきます。ついには、左脳、右脳が協力して回路をつくります。新しい神経の道が出来ました。 マヒしていた腕が動いていきます。 感覚が少しずつ戻っていきます。♪ 自分の腕が、戻って来ました。\(^o^)/なんかこの部分を本で読んだとき人体の奇跡に、すごく感動してしまいました。前回に「感動の受容体を開いて、セミナーやワークショップを受ける。本を読むときもそうだ。」という 自分のやり方を書きました。自分にとっては”感動の回路のヨガ”なのかも知れません(笑) こんな拙い文章でも読んでくださる方が いらっしゃることを感謝いたします。 ありがとうございます。 (合掌)Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK脳梗塞で動かなかった腕を動かしたもの
2008/02/23
-

感動の受容体!☆吸収力の秘密
よくワークショップや今受けている龍村ヨガの講座について「よくそんなに内容や言葉を覚えているね」と言われることが多いです。その秘密は、d(^-^)感動の受容体を開いて、感性で聞く、体験しようと待ち構えていることにあります。別に録音機(ICレコーダー)などで隠し録りをしているわけではありません(笑) 例えれば目の奥にある視神経には、明暗の差によく反応する視神経細胞色それぞれに反応する視神経細胞があります。後者の色の細胞は光の3原色をキャッチする3種類の神経細胞で明るいところでよく働きます。が暗いところが苦手です。一方、前者の明暗細胞は暗いところでも良く働くことができます。その代わりモノクロ映像として見えるのです。これが、さまざまな状況で、”見ることが出来る”目の仕組みです。 こういう感じ取る側の仕組み受け取る側の仕組みを”受容体(レセプター)”といいます。他に人体には、物質に反応して働く酵素の受容体、ホルモンの受容体などがあります。 これを心に当てはめてみると感動する受容体疑問に思う受容体反論する受容体なんかがありますね。この無数の心の受容体の中で、僕は”感動”の受容体を開くことで体験や先生の言葉をキャッチしようとしています。そうすると感性を通し覚えられるのです。その補助としてノートに筆記する。図解でイラストでノートするがあります。この感性、感動の受容体を開きすぎてすぐウルウルしてしまいますが(笑)この方法?が自分にはよく合っているのです。 それをこう言うところで発表、表現するときに感謝の念でお返しするようにしています。 「感動で受け取り、感謝を返す」 本を読むときもそうです。知識整理のため、資料の本を読むときは違いますが、沖 正弘先生の本を読むとき!中村天風先生の本を読むとき!佐保田鶴治先生の本を読むとき!自分に対し、自分たちに対し・・ 本を書いた偉い先生がたが、大事なことを話し掛けて下さっている。こう言う気持ちで読みます。「ご講義お願いいたします。」と沖ヨガの合宿生活で坐学のよき皆で挨拶しますが、その言葉を本に対し心の中で唱えて本を開きます。 今は亡き先生方、先輩方がこんな私に直接教えて下さっているまさに”在り難い”状況です。心の感動の受容体でキャッチ、感動の心の音を出す弦が共鳴そして心にそれを響かせる。響いたものが自然と表現として外に出て行く。そんなことが起こります。これも、ひとつの心のヨガ!Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK感動の受容体!☆吸収力の秘密
2008/02/22
-
徳本?!o(^o^)o
いま地下鉄のなかで゛医療概論゛という 東洋医学学校用のテキストを読んでいる。 これの日本の医療の歴史部分に 永田徳本なる江戸初期の人物が出ている。 なんでも牛にまたがり薬を売って、 諸国を漫遊した伝説的人物らしい。 思想的には漢方の古典゛傷寒論゛の思想に戻れという 復古主義の人だったという。 それはさておき、 永田徳本って名前の とくほん!って あの製薬会社に関係があるのかな?
2008/02/21
-

ナーディと経絡を結んだシルクロード
「気功・導引は広い意味で中国のヨガです」私の先生、龍村修先生はこういいます。このことを書いて見ます。ヨガでいう人体を通るプラーナの通路(ルート)をナーディといいます。(この記事の最後に*参考として 私が書いた”ヨガの思想・基礎知識の原稿の中から ナーディの部分を抜粋しますので目を通して下さい。) 「スシュムナー=脊椎に気、プラーナを通すイメージで~」 などとインストラクターのお姉さんが言っているのを 聞いたことがあるはず。d(^-^) もう一方、私たちが暮らす日本では、経絡という人体の気の道が馴染み深いものとしてあります。中国の古い医学から来たものです。気功や導引(気功の元になったもの)でこの経絡の考えは使われています。経絡(けいらく)はご存知なくともツボ(経穴:けいけつ)のことはぞ存知ですね。 たとえば手の親指と人差し指の根元の間(第2中手骨側)を もう一方の手で挟むように押してみてください。 つよく刺激が感じるところがあると思います。 そこは合谷(ごうこく)というツボです。 合谷は手陽明大腸経(てのようめいだいちょうけい)という 経絡(氣のルート)上にあるツボの一つで 大腸と関係ありますから、便秘に効くツボとして そして歯痛にも効くツボとも言われています。 歯痛に効くということも大腸経のルートをみると理解できます。 手陽明大腸経は人差し指の爪の根元にあるツボ”商陽”から始まり 手の甲がわ、腕の陽の当たる側を通り、肩より2つに分かれます。 大腸へ下降するルートと 鼻の横”迎香”というツボに上がる氣のルートです。 歯痛にはこの上に上がるルートで効くらしいですね。 (陽明とは”陰陽”の陽側のレベルを表す言葉です。)このナーディと経絡、なにか関係があるようですね。プラーナと氣の概念も似ています。このことを研究されている方に本山博博士がおられます。アーユルヴェーダやこの方面の研究の大家です。本山博士の著書の中に、この関係の元になった歴史的事実を記述しているところがあります。ヨガと気功の関係を研究するときの重要な文章です。「中国の経絡思想は、いわゆる春秋時代に入って出来てきたもののようです。それ以前、中国には「経絡」ということばはないし、「気」ということばもなかった。それが2400~2500年ぐらい前の戦国時代にコータンとカシミールを結ぶ中印雪山道、さらにはタリム盆地の南辺を通って秦の国に至るオアシスルートの道が出来たのです。・・中略この時代になるとインドで行なわれていたような外科手術を扁鵲がするようになった。それは山越えの道がインドと中国の間にできて、医学的な技術も伝わったのだと思います。そのころに外科医学やヨーガを含む医学が伝わって、ナディというのが経絡になったわけです。」 以上 「チャクラの覚醒と解脱」 本山博著 宗教心理出版刊よりインドと中国の二つの氣の道、ナーディと経絡は実際の道、シルクロードが結んだんですね。だから気功や導引は中国のヨガ(瑜伽)なんです。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOKナーディと経絡を結んだシルクロード *参考 nobo∴著 「ヨガの思想・基礎知識」より7 ヨガの身体観7-1 人体は小宇宙 人体は小宇宙だといいます。それをハタヨガ(クンダリニーヨガ)の古典シヴァ・サンヒターのなかに見ることができます。 「この肉体のなかにメール山があって、七つの島に囲まれている。 そこには、河があり、海があり、山があり、田地があり、領主がいる。」 「そこには、リシ(聖仙)やムニ(聖者)も住み、すべての星宿、惑星もおられる。 そこには、巡礼の聖地もあり、神殿があり、神殿の神々がおられる。」 シヴァサンヒター 2・1体内を自然環境、地球の縮図を見ています。星々や神々まで人体の中にあるという、ヨガの身体観を著わしたものです。”人体は小宇宙説”その元になる文章のひとつです。文の中にある、メール山(須弥山)は人体の脊柱だと考えてください。そこの中心をスシュムナー管というエネルギーが通るメインの道(河)があり左右にイダーとピンガラーという側道があり、月(陰)のエネルギーや日(陽)のエネルギーが昼夜運行しているとされます。7-2 気道・ナーディー(ナディ) 気道ナーディーとは気のエネルギー、プラーナの通り道をいい、人体に7万2千本(シヴァサンヒター説では35万本)の道が走っているとされます。実際の肺に空気を通している”気道”ではなく、中国医学で言う経絡に近い考えのものです。主要なものは 1) 中心気道 スシュムナー 2) 左気道 イダー 3) 右気道 ピンガラー の三本です。一般的に、スシュムナーは尾骨の先から頭頂までのまっすぐな管、イダーとピンガラーは尾骨(骨盤底:ムーラダーラ)から、(イダーは左に、ピンガラーは右に)いったん出て、上部にあるチャクラ(エネルギーセンター)を挟む形で交差を繰り返し上昇する管です。顔の付近では,イダーは左鼻を通り、ピンガラーは右鼻を通ります。その後、アジナーチャクラ(額のチャクラ)でスシュムナーに合流します。他の主要なナーディーとしてシヴァサンヒターでは、つぎのものを名前だけ挙げています。 4) ガーンダーリー 5) ハスティジフヴィカー 6) クフー 7) サラスヴァティー 8) プーシャー 9) シャンキニー 10) パヤスヴィニー 11) ヴァールニー 12) アランブサー 13) ヴィシュヴォーダリー 14) ヤシュヴィニー7-3 プラーナー(プラナ) プラーナーは中国の気功で扱う”気”のエネルギー概念と同じく広い意味で自然の気エネルギーを表わし、狭い意味で生体の気エネルギーを表わしたことばです。 これを、操ることをプラーナー・アーヤーマー、略してプラーナーヤーマといいます。ヨガの8支則の4番目です。 ここでは狭い意味のプラーナーを見てみます。人体内で働く、気を総称し”ヴァーユ(風)”と呼び10種のヴァーユを、ハタヨガの古典、ゲーランダサンヒターならび、シヴァサンヒターで挙げています。10種のヴァーユ、(プラーナーを代表とする体内の気) 1) プラーナー 人体の胸(心臓)から鼻までではたらく気 2) アパーナー へそから足までにはたらく気 3) サマーナー へそから心臓までにはたらく気 4) ウダーナー 鼻から頭にはたらく気 5) ヴィアーナ 全身に行き渡る気 6) ナーガ おくび(ゲップ) 7) クールマ まばたき 8) クリカラ くしゃみ 9) デーヴァダッタ あくび 10) ダナンジャ 声の気とくにこの中で 1)プラーナー と 2)アパーナーは上半身の気、プラーナ、下半身の気、アパーナとしてよく出てきますので大事です。7-4 クンダリニー クンダリーとも呼ばれるこのエネルギーは、眠れる蛇とも、シャクティ女神とも呼ばれる力です。性エネルギー・女神のエネルギー・始源エネルギーとも例えられます。このクンダリニーはスシュムナー管の最下部入り口、ムーラダーラチャクラに三回り半のとぐろを巻いて寝ているそうです。ハタヨーガプラディーピカーにも書いてあるように、これを覚醒させ、頭上のチャクラ(サハスララチャクラ:シヴァ神の坐)まで上昇、合一させるのがハタヨガ(クンダリニーヨガ)の目標なのです。そのための方法として、ムドラーと呼ばれる特殊なヨガポーズやいろいろなプラーナヤーマがあるのです。
2008/02/20
-

経絡刺激?のゴムカアサナ
前回にガルダアサナで中国古典医学の肺経という経絡を刺激できるということを書きました。こんどは背後で手を繋ぐゴムカアサナ(牛の顔のポーズ)で応用してみます。親指を除く他の指どうしをつないでいきます。以下仮説ですが、 1 人差し指で大腸経 2 中指で心包経 3 薬指で三焦経 4 小指で心経と 小腸系 という経絡に刺激をすることができるのでは ないでしょうか。全体的にこのゴムカアサナは肺経に対し強い刺激を、自分は感じるんですが・・・・Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK経絡刺激のゴムカアサナ
2008/02/19
-

「ヨガのイーグルポーズと、中国の鷲を射るポーズに共通するもの」
二つの鷲のポーズを研究中国の導引気功体操に”八段錦(はちだんきん)”というものがあります。錦は織物=動きを組み立て、織り込んでいる。という意味で用いられているようですから、インド風にいったらアシュト・スートラまたは、アシュタントラって言うかも知れません。この中に出てくる第2段左右開弓似射ちょう(ちょうは鷲の異字)が肺経の脈絡を刺激し呼吸をしやすくする動きだとこの間の長谷川智先生のワークショップで教えていただきました。第2段の動きは”鷲を弓で射るポーズ”とも言われています。その中のポーズを取り出してワークショップでは実験しました。 腕を左右に開き、手の人差し指を立て拳を軽く握り 掌側を真横に向ける。 そして顔をどちらかの手の方に向ける。 そうすると親指から腕の内側を通る刺激が肺の上部までつながって 感じられる。 これは手の親指の爪の外下にあるツボ”少商”と 肺上部にあるツボ”中府”を繋ぐ経絡(氣のライン)で、 手の太陰肺経という経絡です。 経絡はヨガ的にいったらナーディの事です。 これをする前とした後に呼吸を感じるチェックをしておきます。これにヒントを得て、見つけました。ヨガの方の鷲のポーズ(ガルーダアサナ)です。ガルーダは厳密には鷲ではありませんが、それはさておきます。腕を体の前で複雑に絡めた姿勢をとるこの”ガルーダアサナ”この腕のポーズをすると腕の内側を強く押し合い先にあげた八段錦の鷲を射るポーズと同じ刺激が得られます。いや沖ヨガでいう抵抗法にあたりさらに効果UPできそうです。肺、胸までいちど縮めた姿勢で抵抗を掛けているのでそれを解いたとき、関係する所の氣の通り、血行すべて良くなっています。試してみてください。ガルーダアサナの腕。呼吸をしやすくします。
2008/02/19
-
その2☆レポート長谷川智先生WS
”ヨガは体得する修行です。”前回の日記よりのつづきです。呼吸法をしやすくする調整法のあと実際のヨガプラナヤマを行ないました。これも実際指導する場合 「やり方だけ説明して、しばらくやってもらい 効果&変化を各人が体感してもらうようにするとよい」というアドバイスをいただきました。1 カパーラバディ プラーナを上げていく意識 目の前が明るくなる 頭がすっきり、はっきりする。2 ウジャイ 通常のウジャイ*と違う 副交感神経刺激の沈静するためのウジャイ! 鼻腔上部に吸う息を当てかすかな音、自分だけに 聞こえるような音を立てていく。 当てる鼻腔の位置を変えていく。 下部の脳に刺激を与えるらしい。松果体とか・・ 長谷川先生はウジャイは瞑想のためのプラナヤマだと ご説明。 (*通常のウジャイは勝利の呼吸と訳される 喉の呼吸擦過音を出す胸式呼吸で 交感神経刺激の興奮タイプです。)3 ムールチャ 舌を巻き上げるケチャリムドラ(ジフヴァバンダ)をし 上を向き頭を後ろに倒しながーくクンバカ。 気絶のプラナヤマ。(*○_○*)4 バストリカ ふいごの呼吸 これも長谷川先生は、氣を下に下に降ろしていくものだという ご説明、地球の真中までつながるように カパーラバディとベクトルが逆にというご説明! この呼吸をしたあと先生はしばらくバンダ・クンバカをして いらっしゃいました。 通常のチンムドラー(智慧の印)は掌上向きですが 先生はこのとき印を下向きにご自分の膝に当て・・ 下に下にグランディングされています。 その姿は感動に値する姿勢(アーサナ:坐法)でした。 崖の上で坐して大自然に対峙し修行する行者の姿が 自分の心にオーバーラップしてきました。今回のWSでは、呼吸の調整とプラナヤマの実際の効果を確認しながら行ないました。他の人は「自分の知っている呼吸法と違う」と戸惑っている方もおられるかな?でも自分はどんなやりかたが来ても、吸収します。ヨガは体得する修行ですから龍村先生にもこう教わっています。 「同じ名前のヨガポーズでも、やりかた・角度・スピード・ 呼吸を変えることにより いろいろな効果を出せるしまた、無数のやり方を作っていける。 そのために自分で体得していくんです。 それが出来てこそいいヨガの先生です。 ひとつのやり方が正しいと押しつけるのは ヨガロボットを作っているようなものです。」とそして長谷川智先生の言葉をご紹介します。この言葉だけでも覚えておきたいです。 「心を伴わせること。 呼吸法は長く息が止められるのがいいとかではない。」 「確かめながら進む。無理しないで。 無理してるかどうか認識がないからケガをする。 具合が悪くなる。」ヨガは体得するものです。体得をモットーとする行法哲学であり体験する宗教=密教ですから。その意味から教えてくれる先生はやはり本物だと思います。またすばらしい先生に出会えました。長谷川先生、そして先生を紹介していただいたACO先生にいっぱい(*^_^*)感謝いたします。 (合掌)
2008/02/18
-

その1☆レポート長谷川智先生WS
昨日ロータス8で行なわれた長谷川智先生のワークショップ(以下:WS)のレポートです。今回は「自分の合った呼吸法の見つけ方深め方と体の調整法」というテーマでした。これは「身体を壊さないためのヨガの教え方学び方」シリーズのテーマで行なわれている長谷川先生WSの、呼吸法編ということです。はじめて行くヨガスタジオ・ロータス8ロビーで、長谷川先生をACO先生(長谷川先生に師事)にご紹介していただきました。名刺交換で戴いた2枚の名刺。一枚は”心身技術研究所副所長”もう一枚は”桐朋学園大学音楽学部講師”とあります。体を有効利用した音楽へのアプローチをされるプロでも在られます。温厚な感じの方です。修験道に興味がありますとお話したら「行きたいとき声を掛けてよ。」と言っていただきました。 長谷川智先生プロフィールをロータス8ブログより引用長谷川智プロフィール 筑波大学大学院体育学科研究科修士課程修了。心身技術研究所副所長。ヨガや瞑想を実践指導すると同時に東洋的身心論を実践的に研究。羽黒派古修験道先達(二十度位)で、1日に数十キロ歩いても疲れない身体の使い方を習得。一方で、西洋的なボディワーク等も研究し、西洋的なアプローチと東洋的なアプローチを踏まえて、科学的な裏づけに基づいた、より日本人にあった指導をしている。カルチャーセンターをはじめとした数々のワークショップは、すぐに満員になる。共著に「骨体操で身体が元気になる」「ナンバの身体論」など。1 まず呼吸法についての質問をつのるところからWSはスタート2 そして呼吸法をしやすくする体の調整法。 2-1 東洋医学の経絡とくに手の太陰肺経のラインや 経穴を利用するもの。 たとえば八段錦の第2段左右開弓似射ちょう(ちょうは鷲の異字)の動き このとき肺経のラインに響きを感じられる。 親指から腕の内側ラインを通り肺の上部まで響く感覚がきます。 また肺経の表面上にあらわれる始めのツボ(経穴) ”中府”刺激や、 膀胱経のツボで第3胸椎の脇にある肺兪もつかいました。 肺兪は文字通り、肺の字が付いていますね。 第7頚椎の刺激で声の出方、響きが変わる実験もしました。 首の回し方も2種類 第7頚椎を支点にする深い首回し そして第1~2頚椎を支点にする鼻に効く首回しです。 先生はこういうことも言われていました。 「クンバカ(止息)を無理にすると腸をやられる!」 そういうデータもあるようです。 実験を心身技術研究所ではされているんでしょう。 (ヒント`☆´中国古典医学では、肺経を巡った気は、 つぎに大腸経(手陽明大腸経)に流れていきます。) これらの刺激で呼吸を通りやすくしていきます。 2-2 さらには骨体操、骨格を意識して動かす体操です 5種類の呼吸・骨体操を教えていただきました。 (この意味と効果は私のヨガの先生、 龍村修先生の呼吸体操と同じと感じました。) 骨体操というものは、筋肉を意識した動きより 骨を意識して動かした方が 無駄が無く合理的と いうことから 考えられた、体操法です。 ”筋肉は意識しやすいが正確に仕事してくれるかわからない 動きの誤差が生じやすい”と 長谷川先生の共著「ナンバの身体論」光文社新書に書いてあります。 ここまでは主に胸の上を開く操法 大事な、覚えておかなくてはいけない言葉をいただきました。 「都会など空気が汚いところに住む人は 胸の上部が詰まっている。氣が滞っている。」 汚い空気を入れないようにする防衛反応だと思います。 肺の下部分、お腹や真中で深く呼吸!ということは 呼吸法のポイントで、よく言われますが 胸の上の部分は浅い呼吸になるということから 重視していませんでした。 ここの詰まりを意識して取るようしていきたいと思います。 2-3 胸の下・お腹を動かす操法 ・腹式呼吸などで現在の呼吸の深さをチェックしてから ”呼吸活点”という個所の刺激法とポーズを実習。 ・関元(任脈経)と仙骨に手を当てて腹式呼吸を深くする 実験。 ・ナウリ、お腹の筋肉をぐるぐる回す内蔵マッサージ これを腹直筋を立ててやるのではなく 横隔膜を使い腹圧コントロールでやるという考えのものを教わりました。 最初は前後にお腹をうごかし、つぎに小さな楕円を描くように回し始めると 良いそうです。 ・クンバカの時の注意点 脳圧が上がり危険なので、氣を降ろすようにしながら行なう。 `☆´長谷川先生の、”東洋的身心論”という観点は私の学んでいる沖ヨガ・龍村ヨガの考え方と共通点が多くあり非常に共感するところがありました。「ヨーガと合一した人は全てを平等に見ている。」 バガヴァットギーター 長谷川先生は、そんなバランスいい人柄の方です。 長くなりますので数回に分けます。つづく d(^-^)Yoga☆Memorandumその1☆レポート長谷川智先生WS
2008/02/17
-

ロータス8☆長谷川智先生WS
今日始めて、日本橋にある、あのd(^-^)ヨガスタジオ”ロータス8”に行く。ここはヨガ雑誌「ヨギーニ」と関係あるスタジオでさまざまなワークショップや色々なスタイルのヨガのクラスが行なわれています。今回受けに行くのは長谷川智(さとし)先生の「自分に合った呼吸法の見つけ方、深め方と、身体の調整法」というワークショップです。失礼ですがm(__)m長谷川先生って知らないですよね。少なくとも僕は知らなかった。・・・以下長谷川智先生プロフィールをロータス8ブログより引用長谷川智プロフィール 筑波大学大学院体育学科研究科修士課程修了。心身技術研究所副所長。ヨガや瞑想を実践指導すると同時に東洋的身心論を実践的に研究。羽黒派古修験道先達(二十度位)で、1日に数十キロ歩いても疲れない身体の使い方を習得。一方で、西洋的なボディワーク等も研究し、西洋的なアプローチと東洋的なアプローチを踏まえて、科学的な裏づけに基づいた、より日本人にあった指導をしている。カルチャーセンターをはじめとした数々のワークショップは、すぐに満員になる。共著に「骨体操で身体が元気になる」「ナンバの身体論」など。実は先立って受けたワークショップのACO先生が師事しているというので申し込んだしだいですが・・・ACO先生が言うには、長谷川先生は古武術家・身体研究家の甲野善紀氏(最近は古武術を生かした介護方などで有名)とも親交がある方という。そこでピンときて! 本棚を探しました。ありました。僕の本棚にヨガコーナーでなく身体操法&武道関係コーナーに長谷川先生の本が 「ナンバの身体論」矢野龍彦氏らと4人の共著 光文社新書知らずに読んでいたんです。こりゃ期待出来ます♪甲野善紀先生の本も以前は愛読し、その井桁理論とかうねらない動き、体を割って使うとか研究していました。またこんな形で、そちら系の理論と出会うとは不思議です。 今日は 1・なんちゃってヨギと 2・なんちゃって武術家の 二つの顔d(^○^)(^-^)を持って ロータス8まで行ってきます。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOKロータス8☆長谷川智先生WS
2008/02/16
-

相対的幸せと絶対的幸せ`☆´
タン ヴィディヤードゥフカサンヨーガヴィヨーガンヨーガサンジタムサ ニシュチャエーナヨッタヴィヨーヨーゴーニルヴィンナチェーターサー苦悩の緊縛からの解放が、ヨーガと言われる。人は失望せず、決然とそのように、ヨーガの修行に励まねばならぬ。バガヴァットギーター 6-23 ギーターサール インド思想入門 Aヴィディヤーランカール著 長谷川澄夫訳 より 「人は失望せず、決然とそのように、 ヨーガの修行に励まねばならぬ。・・」失望なき心を決意して、臨むのがヨーガ修行だとギーターで言ってます。最初から希望を持って、また持ちつづけるのが大事なんです。結果”苦悩の緊縛”から解放されるのでなく心を悩ませまいと決意するのが道でした。次に龍村修先生の言葉です。 「ヨガをすると自分のなかに幸せがあるのに気づく お金があるから幸せだとか、 地位が得られたから自分は偉いとかでなく、 自分の中に充足感が湧いてくる。 自分で決める! 自分が先生! 自分の内に神がいる! ”他に依存しない真実の幸せ”がそこにある。」 他に依存する幸せは、相対的で相手により変動する不確実なものです。自己から湧き出る幸せは、自己の命=神から出てくる絶対的な幸せです。龍村先生には、つらいときでも、その辛さに心を支配されるのでなく命を傷つけるマイナスエネルギーを”笑い”で中和解毒しなさいとも教わっています。笑えなくとも笑ってみる、それが訓練です。体の内分泌を不幸なときの状態から、幸せなときの状態に持っていくようバランスをとるのです。ヨガの”絶対的な幸せ”は、自分で決意して作るものです。d(^-^)Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK相対的幸せと絶対的幸せ`☆´
2008/02/13
-

雪の中☆かもめのジョナサンの気持ち?
緑一面から雪一面に変わった~外ヨガの場所です。夏の外ヨガの場所の写真よくここでヨガをしています。朝出かけに寄り朝日を浴びながら・・、帰りに寄り真夜中に星空の下で・・ヨガしてる場所です。先日の雪でこんなになりました。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK雪の中☆かもめのジョナサンの気持ち? いまは体育館のマットスペースなど利用していますがやはり外は気持ちいいし 体育館などの閉鎖的なところでは 「これ見よがしに体の柔らかいのを見せ付けている」 みたいに思われるらしいので、いごこち悪いです。 和を尊ぶ?日本ヨガの世界でもそういう事がありますし・・(-.-)自分なんか、ハタヨガを突き詰めようとしている人からみれば取り組み方も甘いし、アシュタンガヨガを毎日、早朝に汗かきながらやってる方々からみればぜんぜん出来ていません。 やはりそういう面を追及する場や人の中に入るしかないのでしょうか? マイソールクラスに通うのがいいのでしょうか??飛ぶことを追求することで、普通のかもめ社会?にいられなくなった”かもめのジョナサン”の気持ちがよくわかります。 生活の中で生かすヨガと 専門家的なヨガの間を揺れ動いています。
2008/02/10
-

マイ携帯ストラップ`☆´公開(笑)
携帯ストラップにいろいろなマスコットをたくさん付けている方がいますね。そういう人からみれば、自分はシンプル派かな?よく始めてお会いする方と「青い携帯もって○○に立ってます」と目印にすることもあります。奈良のあっちゃん一行と待ち合わせしたときがそうでしたね。その携帯にはこういうストラップがついています。・紫色の玉(パワーストーンらしい)で出来た人形 エスニック雑貨屋で購入・勾玉の根付 国立博物館で購入・青い玉 娘にもらったこれを写真に取ると人と月(勾玉)、青い星が並んでいるように見えます。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOKマイ携帯ストラップ`☆´公開(笑)
2008/02/09
-
これ教えて下さい☆インストラクター模擬試験
ヨギーニ13号、p26にあるインストラクター模擬試験を遅ればせながらやってみました。一問だけ分からなかった問題があります。 「上半身でバランスを探るときはこの内臓を正す」 a肝臓 b心臓 c肺答えは a肝臓 らしいんですがこれの意味を分かりやすく教えてくれる人いませんか?問題の意味も具体的にはどういう事なのか?分かりませんしm(__)mよろしくお願いします。 ヨガのコミュニティサイト ”ヨガヨムSNS”でも同じ質問を出していますが・・・
2008/02/08
-

盲点だった!(^0_0^)内臓位置を整えるヨガ
森信子先生の修正行法の時間(沖ヨガ本部道場)で、よくこういうことをやりました。椅子とかを利用してぶら下がる姿勢(イラスト参照)をとりみぞおちや硬いところをほぐしたり、下垂した腸や胃を正しい位置に戻す操作をしながら10分~15分いるんです。アイアンガー先生の本にもこれをしている写真が出ています。ヨガポーズ(アサナ)というと筋肉の伸びとか、骨格意識とか思うのが普通ですが、これ! 内臓位置とかを考え、感じるヨガポーズのアプローチ忘れていました。 IKKi先生の写真に、グリンさんのコメント 「細いわね~内臓入っているの?!」 ↑これで、思い出しました。ヨガ、とくに生理的ヨガとしてのハタヨガは全部ひとつのもの、ホリスティックなものとして心身を見ることが大事ですが、練習、取り組み方として段階的な、こういう考えが出来るのではないかと研究しています。1筋肉のヨガ2骨格のヨガ 3神経のヨガ4内臓のヨガ1や2は普通みなさんがやられているヨガアサナです。3はやりにくい動きとか、感覚の鈍いところマヒしているところを開発していくヨガです。4が今日ここでいっていることです。ヨガに詳しい人は、”ナウリ”とかご存知ですよね。腹直筋を自由に波打たせるお腹の操作ああいうのは4のためですね。3から4は内容的にヨガの階梯でいうアサナからプラナヤマ、プラティヤハラや浄化法の要素も多く含まれるようになる段階です。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK盲点だった!(^0_0^)内臓位置を整えるヨガ
2008/02/07
-
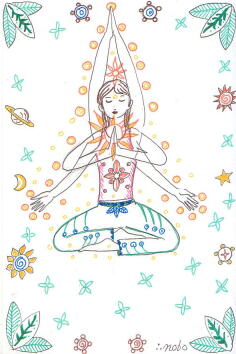
新☆ヨガイラストを描き始めました
なかなか新しいイラストを描けなかったですが今日あたりから空き時間をつかって新しいイラストを描き始めます。これらのイラストは、ヨガの出会いの場でプレゼントしたり。遠く離れたブログ友達に送ったりします。まずは明後日3日に参加する沖縄から来るIKKI先生のワークショップで渡す分ともう一月で修了する、龍村ヨガ指導者養成の仲間たちにプレゼントするものを考えています。今朝、描いたイラストは沖ヨガ式の合掌のあいさつです。周りに宇宙とそのエネルギーをイメージした紋様を描いて見ました。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK 新☆ヨガイラストを描き始めました
2008/02/01
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
-

- 活き活き健康講座
- ☆トレーニングスリッパ☆
- (2025-09-22 20:40:58)
-
-
-

- 歯医者さんや歯について~
- スーパーテクニック・シリーズ29.0(…
- (2025-11-23 13:36:34)
-
-
-

- 入浴後の体重
- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…
- (2025-06-30 17:00:00)
-