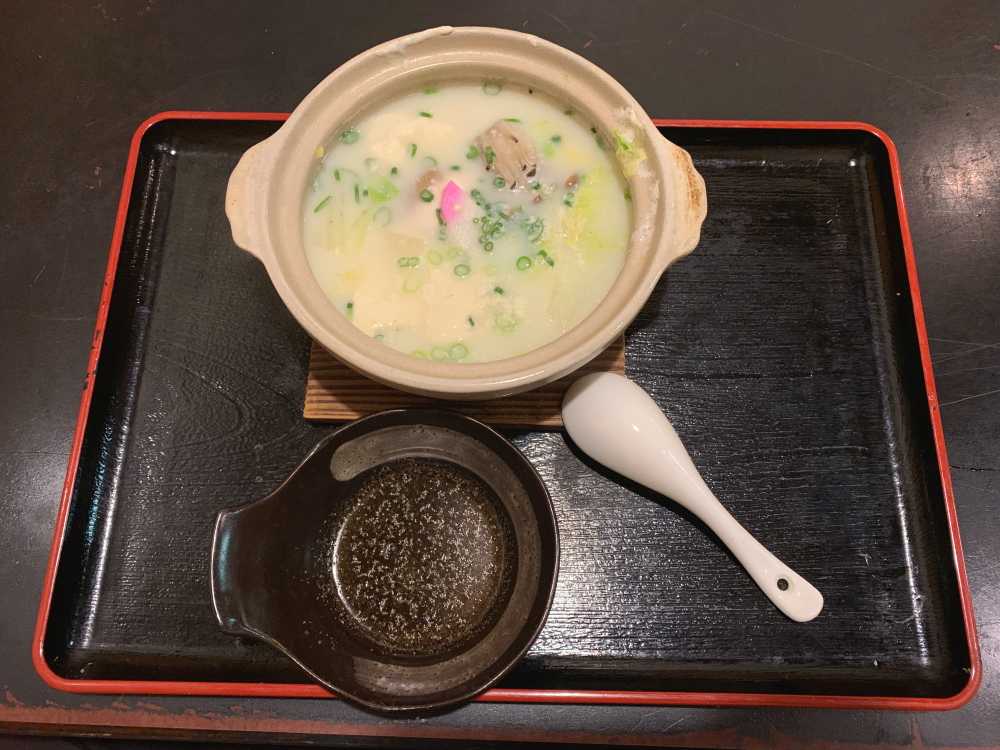2011年08月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
「粉ふきいも」
じゃがいもを使ったシンプルな料理。これ単独では、アイルランドの貧しい主食みたいですが、今回はハンバーグの付け合わせにするつもりで作りました。わたしは煮込みでも炒め物でも味噌汁でも、男爵よりメークインが好きなのですが、コフキイモに使うじゃがいもも、お好みでお選びください。昨今では、キタアカリとかインカの目覚めとか、いろんなじゃがいもが出回っていて、とても全部の特徴を把握しきれません。あり合わせのおいもで、どうぞ(^_^;)。皮をむいたじゃがいもは、同じぐらいの大きさにコロコロになるように切ります。まん中へんを4つに割るか6つに割るか、それぐらいのサイズを基準にします。鍋にいもを入れてひたひたに水を張り、水から茹でます。塩少々を加えておくとよいでしょう。沸いたら、中まで火が通るまで茹でます。茹で汁だけを捨てたら、湯がいたいもを弱火で、転がしながら炒りつけます。表面に粉がふいてきたら、できあがり。お好みで塩・こしょう少々を振り、冷まします。茹でこぼす(お湯を捨てる)際、火から外したまましばらく置くと、沸騰状態にあったいもが縮み、そのときに煮汁を取りこむので、ベチャッとします。火から下ろしたらすぐにお湯を捨てましょう。味付けは、塩・こしょうだけでなく、マヨネーズや粉パセリなど、何でもOK。小学校の家庭科実習で作ったぐらい、失敗の少ない調理法です。ただし、できたとき、鍋肌にいもの粉が一面にこびり付くのを見るたびに、もったいないなあ、と思ってしまうのですが。
2011年08月27日
コメント(2)
-
「春雨の酢の物」
冬場に鍋物に使うことが多い春雨は、夏にはつるつるした食感を利用してサラダや酢の物にするといいでしょう。細い物には細い物を合わせると混ざりやすいので、野菜などもみんな細く切ります。春雨は透明ですから、ほかに緑のもの、黄色いもの、赤いものを用意すると、彩りもいいですね。春雨は材料や太さでいくつか種類がありますが、袋の記載に従って茹で、水に取って冷まします。まな板に広げて十字に包丁を入れると、混ざりやすく食べやすくなります。緑の材料は野菜。きゅうりの細切りかキャベツのせん切り、あるいは両方。黄色は錦糸卵。赤はにんじんの細切りかハムの細切り。にんじんは生またはサッと湯に通して。これらと茹でた春雨を用意したら、ボウルに入れて適当に混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やします。酢やドレッシング、マヨネーズなど、調味料をかけるのは、食べる直前にしましょう。春雨が余分に水分を吸ってしまって、ぼやけた感じになるとともに、調味料を多めに使ってしまう結果になります。で、よく冷えたところで、市販の中華ドレッシングでもフレンチドレッシングでもいいので、調味料であえたら、盛り分けて食卓へ。涼やかな夏の一品です。なお、拌三絲(バンサンスー)という料理名があって、3種類の細切りのものを混ぜたもの、という意味ですが、この「春雨の酢の物」の異名だそうです。わたしはなじみがありませんでしたが、中華料理店のメニューには拌三絲という表記も見られます。ちょっと専門的でカッコイイかな、とも思っています。
2011年08月09日
コメント(2)
-
「かちわり」
かち割る、といえば、ドタマか氷に決まっていますが、今回は氷です(^_^;)。もっとも、氷であってもオリョオリとはいえませんが、夏の風物詩の食品であるということでご容赦を。一般には、大きな氷をこぶし大より小さく割ったものを指し、辞書に「欠き氷のこと」とあるのは誤りです。削り氷(けずりひ)ではありません。そのまま口にポイと放り込んでなめ、涼を取ります。口の中が冷たくなりすぎると、いったん出して深呼吸し、また口に含みます(^o^;)。きょう6日、阪神甲子園球場で夏の高校野球が始まりました。球場の名物として売られている「かちわり」は、両手に入るほどのサイズのビニール袋にゴツゴツとした氷が入っていて、200円です。ここのは口に含むというより、袋ごとうなじに当てて体を冷やしたり、袋にストローを挿して、溶けた氷水を飲んだりします。ツワモノは、別にジュースを買って、中身をかちわりの袋に移して飲むそうですが、昨今は容器ごと凍らせたドリンク類も売り子が売っています。他に添加物がない分、水の美味しさが命です。甲子園のかちわりは、どこの水なんでしょうか。それと、見た目には透明に凍っているのが涼やかで良いですね。このあたり、家庭で水を器に入れて凍らせても、うまく行きません。さすがは業務用の氷だけあります。でも、家で丼かラーメン鉢で凍らせた大きな氷を、2ツ3ツにかち割って、何人分もの冷やそうめんを入れた桶に入れるならば、多少白く凍っていてもいいじゃないですか。郷土の代表校の熱戦をテレビ観戦する際に、スタンドの風景を思い起こして、かちわりも用意しましょう!
2011年08月06日
コメント(2)
-
「きんぴらごぼう」
油で炒めて砂糖としょうゆで味付けする調理法を「きんぴら」といいますが、代表的なのはごぼうのきんぴらで、しかもマッチ棒ではなくささがきにしたものが美味しいと思います。「ささがき」は笹掻きという字のごとく、笹の葉状に包丁で薄くそぐことです。ごぼうは他の野菜より繊維がきついので、繊維に沿って、しかも薄く切ることで、歯ごたえを残しつつ、味しみを良くします。調理時間の多くを費やすささがきを終えれば、ほぼできたも同然です(^o^;)。土のついたごぼうは、調理台の上に新聞のチラシなどを敷き、包丁を皮に垂直に当てて、土と皮をこそげます。土と皮は一緒に丸めて捨てましょう。ごぼうを流しで軽く洗ったら、水を張ったボウルの中に、鉛筆を削る要領でごぼうをささがきにして落としていきます。やりにくければ、まな板に乗せたごぼうを回しながら端から削っていき、適宜水に落とします。削って短くなったごぼうも、まな板の上で薄切りなどにします。水であく抜きができますが、よほど水が黄色くなって気になるようなら、1回ぐらいは水を替えてもかまいません。フライパンか鍋にサラダ油かごま油を熱し、水切りしたささがきごぼうを炒めます。しんなりしたら、だし汁少量を加え、砂糖、酒、しょうゆで味付けします。お好みで輪切りのタカノツメ少々か、仕上げにラー油を加え、火を止めてから黒ごまを振ります。薄いごぼうが油で透けて、しょうゆの滋味が加わった一品です。常備菜にも好適です。ぜひ、ゆっくりでいいので、ささがきは薄く薄く削ってみてください。分厚いものはまな板で薄切りし直してもいいので。
2011年08月05日
コメント(0)
-
「キング」
母親の里が奈良県の平群(へぐり)。今では大阪のベッドタウンですが、わたしが小学生のころは充分に田舎でした。夏休みの8月6日は集落の「墓参り」の日。この日に母に平群に連れて行ってもらい、夏休みが終わるころまでずっと、おじいちゃん・おばあちゃんと過ごしたことが何年もありました。かえるやちょうちょやとんぼ捕り。風呂も便所も家の外で、いっぱい蚊に咬まれました。そして庭には、大きなキングの木があって、たくさん実をつけていました。黄色くて甘酸っぱいキングは、すももの仲間です。食べ物の季節感が今よりもずっとあった時代で、夏はすいかの甘さは(奈良県でもあり)群を抜いていますが、この庭になるキングも、とても甘く感じました。黄色い皮の黄色い中身で、昨今出回っているすももの大石早生やソルダムよりも、いくぶん小ぶりな感じです。大石早生が赤い皮で黄色い実、ソルダムが緑色っぽい皮に赤い実ですから、かなり違います。何より、木で完熟しているのが、一番の違いです!当時はありがたみが解らず、毎日毎日おやつがキングだと、「え~、また?」「たまにはすいかとか…」などと、ぜいたくな注文をつけていましたが、もうかなり前に木が枯れてしまい、祖父母から代替わりして木も倒されて、思い出のキングはなくなってしまいました。栽培する農家が少ないからでしょうか、キングはスーパーなどでも見かけることは無く、そうなるとかえって、今では口に入らなくなったキングが、祖父母の面影とともに懐かしく思い出されます。
2011年08月01日
コメント(4)
全5件 (5件中 1-5件目)
1