2015年08月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

品川宿を歩く(その3)
青物横丁駅の北東に鎮座する諏方神社。「諏訪」神社ではないようです。 調べて見ると「諏訪」とせず、「諏方」と使っているのは古来の表記であり、かつては神社名には、この方が多かった。現在は全国で一万有余ある諏訪神社のうち、この諏方神社は3~4社のみになったとのこと。案内板等は見当たらないのでググってみると、諏方神社の北西側すぐの場所にある顕本法華宗鳳凰山天妙国寺の開基である天目が、自身の生国である信州から諏訪神社を勧請して弘安年中(1278~87)に創建されたと伝えられているのだと。 日蓮宗 光照山真了寺 山門。延宝元年(1673)に天妙国寺塔頭寺院として建立。 鳥居のようなそしてインド寺院を思わせる金属製の山門の足元を、2頭のゾウがこの山門を支える。 お釈迦様の母が白象を見てお釈迦様を身ごもったとされる白象?が山門の左右に配されていた。異国情緒たっぷりの山門には見事な彫刻が、そして裏にも。本堂。この本堂の中にはペット霊園があるらしく、ペットの供養がされるとのこと。2体の黄金仏がやはり黄金像の上で鎮座。 再び旧東街道の保土ヶ谷の松。 品川寺(ほんせんじ)。品川寺は大同年間(806年~810年)に弘法大師空海によって開山された品川で最も古いお寺。 真言宗醍醐派の寺院である。山号は海照山。本尊は水月観音と聖観音で、江戸三十三箇所観音霊場の第31番。銅造地蔵菩薩坐像 - 東京都指定有形文化財(彫刻)山門前左手にある露座の仏像。宝永5年(1708年)に造られた、江戸六地蔵の第一番。1708年に造立され、高さ2.75m。現存する江戸六地蔵像のうち唯一頭上に傘を載せていないのだと。震災で失ったとのこと。海雲寺。東海七福神のひとつである品川寺(ほんせんじ)の南隣で、青物横丁駅の東側に。曹洞宗の寺院。山号は龍吟山。「千躰荒神」を祀る寺として知られる。平蔵地蔵。江戸の末1860年頃、近くの鈴ヶ森刑場の番人だったとされる平蔵の地蔵。平蔵はある日、大金が入った財布を拾うのですが、その財布を誠実に落とし主へ返した。しかし、平蔵はその正直さゆえに仲間から裏切られ亡くなったと。平蔵の損得勘定のない清らかな心に感銘を受けた人々のお参りは、今も絶えないと。 えんの行者像。 本堂。 正面に鰐口(わにぐち)と大鈴が付いた入母屋造りに唐破風の向拝を付したお堂。 私もガラガラと鳴らしお参りさせていただきました。天井の多くの奉納額は実に立派。 力石。境内には若者達の力競べに大正の中頃まで使われていた「力石」が。当時門前付近には大勢の漁師や、親船から積み荷を小舟に写し取る瀬取(せどり)と呼ばれた人々がいて、この石を何個持ち上げられるかや、本堂の間を何回持って歩けるかを競ったのだと。 鐘楼も歴史を感じさせてくれた。 そしていよいよ鮫洲駅下の稲荷神社に到着。鮫洲の地名の由来は諸説あるが、鎌倉時代、品川沖で大鮫が浮いていて腹を割いてみると、聖観音の木像が出現。この聖観音は鮫洲観音と呼ばれ「鮫洲」の地名になったと。鮫洲 八幡神社大祭のポスター。品川宿の散策を終え、鮫洲駅から京浜急行に乗り再び品川駅に戻ったのであった。 東海道は5街道の中で最も重要な街道であり江戸と京を繋いでいたのだ。その東海道の宿場の中で最も江戸に近かった品川宿を慌しく散策。かつての品川宿は概ね現在の京浜急行の北品川駅付近から青物横丁駅付近にかけての範囲に広がっていたのだ。今でも街道沿いには飲食店などが建ち並び、人々の往来も多い。「旧東海道」は車両通行可能な一般道だが、東西に大きな道路があるからか、通り抜ける車は多くなく、散策には車の通行をあまり気にする事もなかったのであった。。歴史ある町であることを物語るように古い建物も所々に軒を並べていた。道沿いには寺社も多く、我々観光客のための案内板なども設置され、かつての品川宿の姿を想像しながらの散策が出来、学びの時間であったのだ。
2015.08.31
コメント(0)
-

品川宿を歩く(その2)
正徳寺の赤煉瓦塀。この塀は元々はこの寺のものではなく工場で使っていた煉瓦塀だと。 虚空蔵横丁を入ったところにある寺は、虚空蔵菩薩のある明鏡山善光院 養願寺。養願寺の御本尊 虚空藏菩薩は木像で空海作と傅えられていると。商店街(旧東海道)に面して可愛らしい山門が。 豊盛山 延命院 一心寺。江戸時代、大老井伊直弼によって開山。本尊を不動明王とする真言宗智山派の寺。 本堂には、不動のほか、聖観音菩薩像や東海七福神の寿老人が安置されていると。 この辺りに最も近い京急の駅が新馬場(しんばんば)駅。この看板はその駅名の由来が書かれている説明板。品川宿には幕府公用の旅人に対して1日当たり馬百匹、人足百人を無償で提供する義務があり、従事する馬小屋があったためつけられた地名であると。南北品川宿に馬場町があり、北品川宿ということで北馬場といったのだと。高架化工事の際に北馬場駅と南馬場駅を統合し、両駅の中間地点に建設されたのだと。聖蹟公園(せいせきこうえん)(品川宿本陣跡)。江戸時代は、大名が宿泊する本陣が置かれた場所。品川宿の本陣も、南北の品川に一軒づつあったようだが、南品川宿は廃れ、江戸時代中頃から北品川宿本陣のみとなったと。こちらは滋賀県甲賀郡土山町から贈られた松。公園の中に入ると石碑が。明治天皇が休憩した行在所としても使われたことから「聖蹟」の名が残ると。夜明けの像。(新聞配達少年像)再び旧東海道に戻ると東海道品川宿と刻まれた石柱が。交差点の文字は「東海道北品川」の文字が。山手通りを渡る。荏原神社。品川橋。品川がかつては海辺のまちであったことを知る貴重な場所。下を流れるのは目黒川。日蓮宗寺院の海徳寺は、自覚山松陽院の号。海徳寺は、大永2年(1522)鳥海和泉守(法名自覚院岸日性)が出家し自宅を寺としたといい、松陽院日増(天文14年1545年寂)が開山したと。堂内にはお地蔵さんも数体。ホームラン地蔵。元巨人軍の王貞治選手が新人のころ、心臓病の少年にホームラン王になることを誓った。少年は残念ながら14歳で亡くなったが、王氏は度々少年の墓を参ったり、ホームラン世界記録を樹立した時にも報告に訪れたのだと。バットを抱き、ボールを持った地蔵像がこの少年の墓。旧東海道品川宿のシンボルとなる街道松『品川宿の松』。東海道が取り持つ縁で、29番目の宿場町があった静岡県浜松市の有賀氏から寄贈された、樹齢80年の黒松。三岳(説明板)。現在、南品川2丁目の通称「三岳」と呼ばれているところは、江戸時代には二日五日市村(ふつかいつかいちむら)、の集落があったところで、三岳神社の近くであったことからそのようになったと。南品川 児童公園。三島宿の松。天台宗 常行寺山門。号は熊野山報恩院。常行寺は、慈覚大師が開基となり、嘉祥3年(850)に創建、長保年間(999-1003)には恵心僧都が住持を勤めたという古刹寺院。城南小学校。顕本法華宗の天妙国寺は、鳳凰山と号し、顕本法華宗の別格山。天妙国寺山門。天妙国寺 鐘楼。本堂。岡松畳店。安永8年創業の畳店。仙台藩下屋敷のお抱え職人から現在7代目。
2015.08.30
コメント(0)
-

品川宿を歩く(その1)
先日、「東海道品川宿」を散策して来ました。「東海道品川宿」は、江戸時代に宿場町として栄えた品川駅近く旧東海道沿いのエリア。北品川から鈴ケ森までの3.8キロメートルにわたって、江戸時代と変わらぬ道幅が「旧東海道」として残っており、昔の道が、今は商店街となっているのです。品川駅から京急線で北品川駅で下車。品川駅よりも南に位置するが、本来品川と呼ばれていた地域(品川湊周辺一帯)の北側に立地することから、北品川と名付けられたとのこと。徒歩で5分ほどで旧東海道に出る。「北品川本通り商店会」の文字が。「問答河岸跡」の石碑。かつて海岸先に波止場があり、3代将軍徳川家光が東海寺に入るとき、沢庵和尚が迎え出て禅問答をしたとされる場所に建つ石碑。将軍「海近くして東(遠)海寺とはこれ如何に」和尚「大軍を率いても将(小)軍と言うが如し」この東海寺、今は海岸線からずいぶんと離れた目黒川近くの位置にあるが、何ともほほえましい情景が浮かぶと。「善福寺」藤沢の遊行寺を総本山とする時宗のお寺で、1294年鎌倉時代後期に、遊行寺第二世他阿真教によって開かれた寺。(山号)音響山伝相院。 伊豆の長八こと入江長八の龍のこて絵が残っていた。入江 長八は江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した名工(左官職人)。利田神社(かがたじんじゃ)横のモニュメント鯨(セミクジラ)。江戸時代、品川沖に迷い込んだクジラの骨が埋められた塚。寛政の鯨事件として品川宿を大いに賑やわせた有名な鯨。寛政10年(1798)5月1日、品川沖に迷い込んだ鯨を漁師たちが 天王洲の浅瀬に追い込み、捕らえて浜離宮まで曳航し第11代将軍家斎も上覧されたと。鯨はシロナガスクジラ(?)といわれ体長16.5m、高さ2.04m。このクジラの骨を埋めて、その上に建てられたのがこの富士山の形をした鯨塚。「鯨碑」には上記の説明が刻まれていた。利田神社。旧目黒川の河口にできた砂嘴(きし)の先端に弁天堂が祀られていた。洲崎弁天ともいわれ浮世絵師歌川広重(うたがわひろしげ)の名所江戸百景の一つにも描かれている。寛永3年(1626)、今から約360年前に沢庵和尚が弁才天を祀ったことに始まると伝えられる。明治になって利田神社になり、祭神も弁才天から市杆島姫命にかわったと。御殿山下台場(砲台)跡。この地、台場小学校の敷地は幕末、江戸の防衛のために築かれた「品川台場」のひとつである砲台跡地。レプリカのこの灯台は1870(明治3)年から1957(昭和32)年まで使用されていた品川灯台(国の重要文化財に指定)であり、周りの石垣は旧目黒川に架かっていた品海橋(今の台場交番前)を築いた石であると道を戻ると釣り船乗船場が。「品川浦舟だまり」江戸湾には、漁を専業とする人々の集落がいくつかあり、漁師町または浦といった。品川周辺には「品川浦の品川漁師」と「御林浦の大井御林漁師町」があり、収穫した魚介を江戸城に献上していたと。力レイ・あいなめ・車海老などをはじめ、様々な魚介類が獲れたと。現在は、つり舟や屋形舟の発着場として賑わっており、「品川浦とつり舟」で"しながわ百景"に制定されていると。「品海公園」。公園としては小規模だが、公園入口に【品川宿】の石碑が立っていた。もちろん品川宿は東海道五十三次の第一宿。五代目の品川宿の松が植えられていた。現代の品川宿東海道沿道には様々な宿場の松が植えられていた。ここは地元の品川の松のようである。日本橋から2里(約8km)、川崎宿まで2里半(約10km)の場所。品川宿は「一六〇〇軒、人口七〇〇〇人規模で賑わっていた」と書かれた説明板が。「臨海山 法禅寺」。浄土宗寺院の法禅寺は、臨海山遍照院と号すと。明徳元年(1390)に言譽定賢が創建。東海三十三観音霊場31番札所。門前に「品川小学校発祥之地」という石碑も。レンガ造りの建物内には石造の供養塔が収められていた。「法禅寺板碑」。板碑は鎌倉時代から戦国時代にかけてつくられた石造の供養塔で、関東を中心に広く分布しているとのこと。この寺の板碑は、品川御殿山から出土したものの一部で、破片を含め121基も。古いものは1308(徳治3)年の銘があると。「流民叢塚(るみんそうづか)碑」。天保の大飢饉で亡くなった人たちを祀る供養塔。品川宿は農村などから流浪してくる人が多く、病や飢餓で倒れた人が891人を数え、法禅寺と海蔵寺で葬っているとのこと。 「本堂」。南北朝時代の末の開創。芝増上寺の末寺であると。堂内には木造等身大の阿弥陀如来坐像が安置されていると。「布袋様」。ふくよかなで恰幅のあるほがらかな表情が、暑い日差しの中なんとも心を和ませてくれたのであった。私の身体は布袋様に似てきたが、このほがらかな表情も似たいのあるが・・・・。法禅寺の「イチョウ」は推定樹齢350~400年。樹高約25メートル。
2015.08.29
コメント(0)
-

オレンジ色の朝
昨日の朝の我が家近くからの朝焼けです。先日訪ねた、五重塔の如き横浜薬科大学の図書館棟方面がオレンジ色に輝いていました。 刻々とオレンジ色の色彩が微妙に変化。 そしてこの日の日の出。 我が養蜂場を守るマネキンも朝の陽光を浴びていました。 日本大学生物資源科学部校舎と遠く丹沢山塊。 私の影。農地もオレンジ色。 オレンジ色に変身したサルノコシカケ。ヒイロタケ?朝の陽光を浴びていっそうオレンジ色が濃く。畦道端の花ショウガ(生姜)も白い花の中心そしてオレンジ色。別名ジンジャー・リリー。民家の窓に反射する朝のオレンジ色の光。 「オレンチ(自宅)」に戻り、朝日を浴びる隣家を朝顔と共に。 そして我が家のスパイラルホースもオレンジ色にお色直し。 トウガラシも朝のオレンジ色の光を浴びて更に深紅に。赤のパブリカもオレンジ色の陽光を目一杯吸い込んでいました。
2015.08.28
コメント(0)
-

箒草(ホウキグサ)
今年も我が家の庭の片隅の箒草(ホウキグサ)が大きく成長し、高さは1mくらいになり茎がいっぱい枝分かれし、見事な球形となり楽しませてくれています。。 今年も去年の種が発芽し、妻が元気な株を残し育ててくれました。美しい淡緑で、別名コキア、箒木とも呼ばれています。東北地方では、若い芽は浸しや和え物として、種はとんぶりと呼ばれる料理とし食べるのです。 秋になると美しい紅色となり更に楽しませてくれるのです。そして茎は既に赤く変化して来ているのです。
2015.08.27
コメント(0)
-

俣野公園へ
先日、久しぶりいや10年以上ぶりに近くにある俣野公園へ妻とドライブして来ました。この公園は私が子供の頃、横浜ドリームランドがあった跡地に作られた公園。閉園したのは確か平成14年?。五重塔の如き建物が旧ホテルエンパイアで現在は横浜薬科大学の図書館棟になっているのです。そして手前は講義棟、厚生棟(食堂)。春日大社横に車を停め散策開始。相州春日神社の入り口の鳥居。柱径が太く,わずかに内側に傾き,島木・笠木の反りは少なく,額束がある春日神社の鳥居の形式。そしてその先に奈良春日大社の建築様式にならう県下唯一の楼門が。正面に拝殿が。稲荷大明神。春日大社の一角に稲荷神社が。神鹿苑。奈良の春日大社の鹿を賜っているとのこと。奈良の春日大社と同じ血を引く鹿の子孫たちがここ神鹿苑で暮らしているのです。鹿がここにいるとは知りませんでした。横浜市営霊園・メモリアルグリーンのレストハウス。合葬式慰霊碑型納骨施設と芝生型納骨施設がある模様。こちらは芝生型納骨施設。市営霊園・メモリアルグリーン周りの池。硬式野球場『俣野公園・横浜薬大スタジアム』。子供達が暑さに負けずに練習中。旧横浜ドリームランドの夏:プール、冬:アイススケート場のあった場所は緑の大きな広場に。木々も大きく成長。マンホールの蓋は横浜ベイブリッジ。そして再び旧ホテルエンパイア、現在は横浜薬科大学の図書館棟が。横浜ドリームランド・ホテルエンパイア時代はこの最上階は回転展望レストランになっていたのです。確か1時間に1周し、江の島や大島そして富士山等を展望できたのです。横浜薬科大学の図書館棟いや旧ホテルエンパイア全景。久しぶりに訪れた閉鎖された横浜ドリームランドの跡地は、様々な施設に生まれ変り、中でもホテルエンパイアと何度と通ったボーリング場が大学の施設として再利用、遊園地の各種遊具跡は野球場そして霊園に変わっていたのでした。高校時代はクラスメートの女性の父親がこの横浜ドリームランドの関係者であり何度か招待券?を頂きクラスメート達で遊んだ事も懐かしい想い出。更に思い起こせば、昔はJR大船駅からここドリームランド駅を結んでいたドリーム開発運営のモノレール路線があり乗車した記憶も。しかしながら開通翌年?の1967年に運行が突然休止され、一度も再開されることなく2003年に正式に廃止され現在に至っているのです。私が高校1年の秋=1967年に突然休止した事は何故かはっきり覚えているのです。更に路線免許申請はなかったようですが、ドリームランド駅から、当初は小田急江ノ島線の六会駅(現・六会日大前駅)まで、後に長後駅までの路線を開通させる計画も有った事を亡き父から聞いたことも。そのために、ドリームランド駅付近の軌道の一部に複線用の橋脚が建設されているのだとも。廃止の原因はモノレール車体の設計荷重からの大幅重量オーバーによるコンクリートの橋脚等の強度不足が結論であったと記憶しています。暫くの間はコンクリート橋脚がそのまま残っており、テレビ番組の廃墟特集等でも何度か取り上げられたほどであった事を想い出したのです。そして現在に至ってもこの旧横浜ドリームランド、現横浜薬科大学そして巨大団地「ドリームハイツ」へのアクセス手段はバスかマイカーのみ。そして団地開設後40年以上経過して、高齢化問題も発生している事間違いなしのこの陸の孤島の「豪華団地」の将来は如何に?。
2015.08.26
コメント(0)
-

陸上自衛隊・富士総合火力演習へ(その3)
後段演習は「島嶼部に対する攻撃への対応」。島嶼部の防衛にあたっては、「平素からの部隊配置」「実力部隊の緊急的かつ急速な機動展開」「水陸両用部隊による奪回」の3つの段階が重要と。万一、島嶼の占領を許した場合には、陸海空自衛隊の統合火力の支援のもと、水陸両用作戦によって「奪回」を行うのだと。 03式中距離地対空誘導弾(右)と88式地対艦誘導弾(左)03式中距離地対空誘導弾は純国産の中距離防空用地対空ミサイル・システム。搭載車体には73式大型トラックを使用。ミサイル本体は発射筒を兼ねた角型コンテナに収められた状態で、発射装置及び運搬装填装置に各6発ずつ搭載されており、垂直発射方式。発射筒が垂直状態に向かって移動中。88式地対艦誘導弾。ウルトラビジョンにはP-3C 哨戒機の映像が映された。上空に轟音を轟かしF-2戦闘機が。F-2戦闘機には13ヵ所の火力搭載のための搭載ステーションがあり、任務に応じてさまざまな形態を執ることができるとのこと。そして上空を猛スピードて飛行し過ぎ去って行ったのであった。F-2戦闘機から爆弾投下か?96式多目的誘導弾システムの運転隊員が地上に降り射撃準備。地上で銃を構える隊員。長い間同じ姿勢で微動だにしないのであった。中距離多目的誘導弾。照準は赤外線画像(IIR)またはミリ波レーダーで行なうのだ。観測ヘリコプター(偵察機)OH-1。敵陣に忍び込み情報を得る任務から、『ニンジャ』の愛称。特徴的なテールローターは8枚ブレードで、低空飛行時に樹木などと接触する危険を減らすためにダクテッド方式(機内埋め込み式)。観測ヘリコプターOH-6.多用途ヘリコプター UH-1.機内から多くの戦闘隊員が外に出てきた。多用途ヘリコプター UH-60。 隊員がロープを伝い降下。 そして敵陣地に向かい配置。そしてヘリコプターから出てきた偵察用オートバイが猛スピードで敵陣地に向かう。輸送ヘリコプター CH-47。タンデムローター式の大型輸送用ヘリコプター。 タンデムローターとは、ヘリコプターにおいてカウンタートルクを打ち消す方式の1つで、ローターが前後に2つ配置されているヘリコプター。機内から隊員が地上に。そして隊員に誘導されCH-47ヘリコプタ機内から出てくる高機動車。後ろには弾薬車両?を牽引。87式偵察警戒車。愛称を「ブラックアイ」として、陸上自衛隊が使用している偵察戦闘車(装輪装甲車)。軽装甲機動車から発射、弾道が赤い点線で(+プレートの下)。74式戦車が再び。88式地対艦誘導弾 発射!!いたる場所で白煙が。そしてヘリコプター軍団が飛来。見事な編隊飛行。10式戦車もフィナーレに向かって。各種戦車、装甲戦闘車が集合一斉発砲。猛烈な火炎と白煙。物凄い爆音と白煙で演習は完了したのであった。そして混雑待ちの為15分ほどベンチの椅子に座ったまま様子を見る。見る見る手前のシート席の迷彩模様のシートが姿を現す。そしてシャトルバスに乗車する為に駐車場に向かう。しかし高塚行きのバスに乗るために1.5hrの行列の時間が必要なのであった。帰宅してのニュースによるとこの日22日は約2万3千人が訪れていたと。そして本番の23日の演習では2万6千人余りの一般客らを前に、およそ3億9千万円相当の実弾が消費されたと。また23日の演習では74式戦車のキャタピラ脱落と戦車とキャタピラの回収作業が行われたと。またバイクも転倒したと。また、演習の直後にはアメリカ軍の新型輸送機オスプレイを飛行させ、導入に向けてその重要性を演出したとニュースで。そしてこのオスプレイが15時近くに我が家の上空を通過し、厚木基地方面に向かったと、蜜蜂の師匠からメールが。
2015.08.25
コメント(0)
-

陸上自衛隊・富士総合火力演習へ(その2)
96式装輪装甲車が先導。キャタピラとは違い車輪付きの車両ならではのスムーズかつ豪快な走行とこのあと後部ハッチから飛び出す隊員の姿が。特科火力(203mm自走りゅう弾砲)特科火力(99式自走155mmりゅう弾砲)目標地域説明図。3段山に着弾。大きな土煙が舞い上がる。203mm自走りゅう弾砲から白煙が。トラックに牽引されて登場した155mm自走榴弾砲FH70。しかしその名の通り”自走”砲で、トラックがなくても内蔵したエンジンを使って自力走行することが可能とのこと。3段山手前で連続的に真っ赤な火の玉が炸裂。次に中距離火力が登場。重迫牽引車の後ろに120mm迫撃砲 RTが。牽引されるため、砲身に車輪が付いているのが迫撃砲120mm迫撃砲 RT。その横に砲弾が。81mm迫撃砲L16を車両から降ろす隊員。人が運べる小型の迫撃砲。そして近距離火力演習に移る。対人狙撃銃を匍匐(ほふく)で構える兵士。近距離火力を先導する軽装甲機動車。軽装甲機動車のルーフから01式軽対戦車誘導弾(軽MAT)を射撃。低伸弾道モードと一度高く飛翔してターゲットを真上から捉えるダイブモードで射撃可能。今年はダイブモードでの発射を披露。96式多目的誘導弾、中距離多目的誘導弾が集合。中距離多目的誘導弾の発射。2名の兵士で共同で偵察演習。再び96式装輪装甲車B型。着弾し大きな白煙が。AH-1S 対戦車ヘリコプター(コブラ)。本格的武装ヘリコプター。航空部隊に攻撃力を与え、火力支援、対機甲戦闘が可能。武装は機首に20mm機関砲を装備。胴体左右にTOW対戦車ミサイルと70mmロケット弾発射筒を搭載。戦闘ヘリコプター AH 640(アパッチロングボウ)。前席には射撃手、後席には操縦手が搭乗する。89式装甲戦闘車。戦車に随伴する装甲兵員輸送車に武装と装甲を施した車両、日本初の歩兵戦闘車。84mm無反動砲(カールグスタフ)」を抱える隊員と砲弾を待ち続く隊員。一通りの射撃を終え、装甲車から普通科隊員が降りてきて射撃。87式自走高射機関砲。砲塔の左右に35mm対空機関砲を1門ずつ、2門装備し、砲塔上部の後方に索敵レーダーと、追尾レーダーが配置。74式戦車。構造説明図。90式戦車。10式戦車。10式戦車は陸上自衛隊の4代目となる最新国産主力戦車。そして前段終了し15分の休憩。Eスタンド下の喫煙所には多くのスモーカーが。これぞ愛煙者の凄まじい「火力」なのであった。そして後段演習が始まるまでの間、会場では再び散水作業等が行なわれた。気がつけば、シート席も完全に満席状態。
2015.08.24
コメント(1)
-

陸上自衛隊・富士総合火力演習へ(その1)
今年も近所に住む同僚と静岡県御殿場市の陸上自衛隊東富士演習場で行われる陸自の実弾射撃演習「富士総合火力演習」の予行演習を見に行ってきました。陸上自衛隊が毎年一般公開している最大の演習「富士総合火力演習」の入場チケットがプレミアム化している。2015年8月23日に行われる今年はチケット申し込みが約15万通あり、倍率が29倍になったとの報道。 早朝6時に同僚が車で自宅に迎えに来てくれました。そして鵠沼に住む同僚宅に向かい合流し御殿場に向かう。新湘南バイパスを利用して車を進める。鵠沼に住む同僚の話によると、朝の5時ごろに自宅横の小田急線線路近くが騒がしいので、何事かと踏み切りに行って見ると、線路の途中に乗用車がと。ニュースによると、小田急江ノ島線の線路上に乗り捨てられた無人の乗用車と始発電車が衝突する事故があった模様。 【Yahoo ニュースより掲載】車を進めると、西湘バイパスは台風16号による高波(うねり)による通行止めとのことで、圏央道から東名高速を利用して御殿場に向かうことを決断。 御殿場ICに順調に向かう。斜張橋の東名足柄橋の下を通過。リニューアルオープンした。『EXPASA足柄』にてトイレ休憩。昨年は雨と霧による視界不良の為、早々に火力演習会場を引き上げたのであったが今年は、EXPASA足柄から望む富士山の姿もはっきり確認でき一安心。指定された駐車場は高塚地区。 第2駐車場に誘導され8時前の予定時間に到着。ここからシャトルバスに乗り換え、演習会場まで20分。 演習会場の近くの駐車場でシャトルバスを降りる。 そして細い林道を会場に向かう。続々と見物客が続き長蛇の列。 若き自衛隊員も今日は教育の一環の演習体験。 会場MAP。 スタンドには「平成27年度富士総合火力演習」の文字が。 そしてその下の土産物売り場も賑わっていた。富士総合火力演習は下図の如く4回行われるのだ。そして今日は(3)教育演習の日、そして明日23日(日)が本番。短時間であるが夜間にも行われているのであった。今年の席は訓練用標的、着弾地点に最も近いEスタンド席。2015年度ポスター。『最新鋭の装備を駆使して行われる陸上自衛隊国内最大の実弾射撃演習!!日本の力を見届けよ。』の文字が。 富士山も青空の下、見事な勇姿を見せてくれた。 巨大ウルトラビジョンも近くに見える絶好のポジション。 標的も解りやすく色つきの表示板が。 この色を標的場所として事前に説明してくれるので、標的に当たる瞬間や着弾時の火炎や白煙を瞬時に見れるので迫力が倍増。広大な東富士演習場(畑岡地区)内に置かれた標的も真正面に。10時開催までの時間を利用して、陸上自衛隊音楽隊の演奏も行われた。 ウルトラビジョン用画像をこの場所からのカメラで。 富士山の僅かに残る雪渓とその下には5合目の山小屋の姿をズームで。 そして演習場所には散水車群団が見事に均一な水撒きを披露。 そしていよいよ10時になり火力演習のスタート。
2015.08.23
コメント(3)
-

羽田空港から東京駅へ
青森からの帰路は、再び青森空港から羽田空港へ。 離陸後は雲の上でしたが、途中、田沢湖が機窓から。 茨城県の海岸。 茨城県東海村付近の阿漕ヶ浦(あこぎがうら)の水面が輝いていた。そしてこの日は羽田空港から長野県上田市に向かう為に東京駅へリムジンバスにて。旧管制塔そしてビルディング。 旧管制塔のこの施設はバックアップ用として今も残され、緊急事態にいつでも対応できるようになっているのです。首都高速湾岸線から 首都高速11号台場線の有明付近から。 台場公園。 お台場海浜公園から続く、東京湾に突き出た公園となっていて、周囲は石垣で囲まれ、その上に土手があり、中央が低い構造になっている。1辺が160メートルの正方形。台場公園はペリーの黒船来航に備え東京湾上に作られた砲台の跡地第三台場を利用して1928年7月7日に開園。台場公園の横を通りレインボーブリッジ方面に向かう。 (株)フジテレビジョン本社。 2棟のビルの間にそびえる球体は展望台。レインボーブリッジを通過。レインボーブリッジは、東京港の新しいシンボルとして、また開発が進む臨海副都心と都心を結ぶ架け橋として、平成5年8月にオープン。芝浦ふ頭のループ橋。 そして東京タワー。 東京駅南口に到着し、JR東日本北陸新幹線にて上田に向かう。
2015.08.22
コメント(0)
-

立佞武多祭(その3)
2015年新作「津軽十三浦伝説・白髭水と夫婦梵鐘(つがるとさうらでんせつ・しらひげみずとめおとぼんしょう)」。新作は、十三湖にまつわる悲しい恋の伝説を題材に。むかし、十三湖が十三浦(とさうら)と呼ばれていた頃、たびたび襲ってくる大洪水や津波を人々は「白髭水(しらひげみず)」と呼んでいたと。何でも、白髪の老人が波に乗りやってくるからだと。 1715年、現在の五所川原市飯詰にある長円寺で、開山一世聖眼雲祝大和尚の報徳の梵鐘をつくることになり、これを喜んだ兄寺の弘前市にある長勝寺でも同様の鐘をつくることになったと。この一対の梵鐘の制作は、洛陽(京都)の近藤丹波藤久に依頼され、翌年の1716年に完成した一対の夫婦梵鐘は、京都から山を越え、海を越え、ついに十三浦までたどり着いたのだと。ところが、船が十三浦に入港しようとした時、海が大荒れし、夫婦梵鐘は海深くに沈んでしまった。その後、長円寺の雄鐘は無事引き揚げられたが、長勝寺の雌鐘はとうとうみつけられなかったと。このため、長円寺に納められた雄鐘をつくと「十三恋しやゴーン」と、そして、それに呼応するかのように十三浦では「長円寺恋しやゴーン」と引き裂かれた悲しみに溢れた音色がすると。また、もう一説には、夫婦梵鐘は龍の形をしたつり金具で区別されており、その金具の雌龍に一目ぼれした十三浦に住む龍が、我が物にしようと海に引きずり込んだという説もあると。見返り絵。2013年度『陰陽 梵珠北斗星』梵珠山に点在する7つの寺社を結ぶと、そこに浮かび上がる北斗星の謎が。見返り絵。さかえ立佞武多。大きな佞武多「三日月祈願 山中鹿之助」が戻ってきた。2014年作『国姓爺合戦 和藤内』。巨大な山車が力強いお囃子と「ヤッテマレ!ヤッテマレ!」の掛け声のもと、次々と五所川原市街地を練り歩いたのであった。巨大なもので高さ約23m、重さ約19トンもある山車の、その圧倒的迫力は感動そのもの。山車の一台一台がテーマを持ち、それを表現するために細かな造形と鮮やかな色使いが施されていたのであった。 そして余韻を楽しみながらホテルに戻り軽く腹ごしらえ。「若生(わかおい)おにぎり」を1ケ。「若生昆布おにぎり」とも呼ばれ、薄く柔らかい生育一年ほどの若い昆布を使ったおにぎり。五所川原市金木出身の文豪 太宰 治が帰郷の際好んで食べたと。そしてシジミ汁も。 ・・・もどる・・・ ・・・完・・・
2015.08.21
コメント(0)
-

立佞武多祭(その2)
ねぶた自主製作運行団体 誠和會 『船弁慶』 平知盛。 独眼竜政宗と言えば「伊達政宗」。 『毘沙門天』 『百鬼夜行 狐の嫁入り』『水天』囃し方も元気。 横に広がる形のネプタ「一寸法師」。 見返り絵 跳ね子。 五高の立佞武多が続く。 「岩木双子 馬捨」 『国姓爺合戦 和藤内』 「幸村推参!大坂夏の陣」『武田信玄』 見返り絵。武田信玄は男性も女性も愛せるバイセクシャル?五農立佞武多「不動明王」。四連太鼓。横笛集団。見返り絵。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2015.08.20
コメント(0)
-

立佞武多祭 (その1)
五所川原・立佞武多祭を見てきました。送迎バスにて、ホテル近くのエルムから五所川原駅裏口まで。陸橋を渡っていると、右下に五所川原駅が。JR東日本・五能線の駅そして隣接しているのは津軽鉄道線の津軽五所川原駅。五所川原駅横の立佞武多格納倉庫。 折りしも、立佞武多出陣の時。五所川原高校の立佞武多。五所川原農業高校の立佞武多 「不動明王」。 そして夕日を浴びたJR五所川原駅も賑やかになってきていた。 そして各佞武多もスタートの場所へ。 碇知盛(いかりとももり)。人形浄瑠璃「義経千本桜」二段目の通称。渡海屋銀平に身をやつした平知盛が義経を討とうとするが果たせず,碇綱を体に巻きつけ岩の上から入水する豪快悲壮な場面。一寸法師。左上の小さな一寸法師がコンボウを振り回す鬼と戦っている様子。 水天。水天は安産・子育ての神・子供の守り神として信仰。 狐の嫁入り。干ばつの被害に喘いでいた村人が、雨乞いの為、狐を生け贄にして、なんとか雨を降らそうと、村一番の男前の村人を婿にしたて、狐の娘を騙して嫁入りさせようと、企んだ場面。毘沙門天。 毘沙門天とは、おもに武神として知られる仏様。船弁慶。開催日は8月4日~8日迄。 立佞武多の館。高さ20mを越す大型の立佞武多を常設展示・保管し、制作スペースとすることを目的として2004年(平成16年)に竣工、開館。立佞武多は年に一基製造され、それが3年間使用されることから、祭りでは常に3基のねぷたが出陣する(祭りではこのほかに町内・学校などで作られる中型・小型のねぷたも出陣し、総計18基ほどとなる)。このため立佞武多の館でも常に3基の大型ねぷた(当年制作、前年制作、前々年制作)が館内の展示室に展示。すでに2基は出陣し、残るは最奥の今年の立佞武多のみ。立佞武多の館正面にある、「母神」像 。協力会社の社長ご夫妻がビル屋上の特等席を予約して下さっていました。 そしていよいよ立佞武多祭のスタート。 毎年、祭りのスタート時には地元金木町出身の歌手・吉幾三の乗った移動ステージ車が各山車を先導し、生の歌声を聞かせてくれるのが恒例となっているのです。 作詞・作曲・唄: 吉幾三の 『立佞武多』 のテーマ曲が聞こえてきました。「やってまーれやってまーれ!」のコール&レスポンスが祭り気分をさらに盛り上げ、またその後ろに控える巨大な山車が生き物のようにこちらにせまってきて、その迫力にも圧倒されたのです。ヤテマレー… ヤテマレー… ヤテマレー… ヤテマレー…♪♪遠く聞こえて 津軽の古里に 笛と太鼓と 立ちねぷた 街を見下ろし 歴史が通る 津軽平野は 五所川原 ヤテマレー… ヤテマレー… 勝った戦の 立ちねぷた 夏を彩る 風も踊れよ 立ちねぷた 立ちねぷた♪ ♪私も周囲の方々に負けじと「吉幾三!!」のコールを送り、吉幾三が笑顔で手を振ってくれたのであった。先導車も出陣。五所川原市「立佞武多祭」とは、平成10年に約80年ぶりに復刻した青森県は五所川原市にて開催される夏祭り。【立佞武多】と呼ばれる、高さ約23m、重さ約19トンの巨大な山車が「ヤッテマレ!ヤッテマレ!」の掛け声のもと、五所川原市街地を練り歩き、その圧倒的迫力で沿道の観客を魅了。運行は立佞武多の館に展示している3台の大型立佞武多と町内・学校・愛好会などでつくられる中型、小型のねぷたと合わせ、15台前後が出陣。県内は各地にねぶた・ねぷた祭りがあるが、代表格の青森ねぶた、弘前ねぷたと共に東北でも有数の夏祭りへと発展。五所川原市会議員の方々もパレードに参加。そして大太鼓2台を縦に重ねた「忠孝太鼓」の上部に、大きな佞武多「三日月祈願 山中鹿之助」が。 それにしても巨大太鼓。 そして操るのは2名。山中鹿之助 幸盛(やまなか しかのすけ ゆきもり)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての山陰地方の武将。尼子氏の家臣。実名は幸盛(ゆきもり)、幼名は甚次郎(じんじろう)。優れた武勇の持ち主で「山陰の麒麟児」の異名を取る。尼子十勇士の筆頭にして、尼子家再興のために「願わくば、我に七難八苦を与えたまえ」と三日月に祈った逸話は有名である。(ウィキペディアより) ・・・つづく・・・
2015.08.19
コメント(1)
-

十二湖へ
この日は秋田県にある八峰町訪ねました。五所川原から日本海沿いを五能線に沿って101号線を走る。途中、深浦の千畳敷で休憩。1792年(寛政4年)の地震で隆起したと伝えられる海岸段丘面。物珍しがった津軽藩の殿様が、そこに千畳畳を敷かせ大宴会を開いたとされることからこの名がある。三角測量の基点の石柱に海鳥のツガイ?が羽を休めていた。 嘴の色は黄色で、先端が赤くその内側に黒い斑紋が入っていることからウミネコ。 肝っ玉母ちゃんのいる『民宿 田中』 で早めの昼食。たくさんのイカが干されていた。うに丼を食べたかったが、この日は不漁で無しとのこと。「牡蠣食ってけ」と商売上手のおっかさんに声をかけられて生牡蠣を。 食べ終わり蓋を合わせると、巨大な牡蠣であることを再認識。 サザエも焼いてもらった。 刺身の盛り合わせ定食を注文。 千畳敷周辺一帯は大仏岩、兜岩など奇岩奇石が多い。 そして再び日本海、そして五能線沿いに車を走らす。前方に行合崎が見えて来た。 太宰の宿『ふかうら文学館』。太宰治の小説「津軽」にも出てくる太宰が宿泊したとされる「太宰宿泊の間」では 太宰が宿泊した当時の部屋が再現され、初公開の書簡や貴重な資料を展示。 建物は地方の旧家のような旅館の造りはそのままで窓から、かすかに漁港の香りがする風を感じることができると。 前方に白神スロープカーの線路が前方に白神スロープカーの線路が現れた。五能線の踏み切りで『リゾートしらかみ』 に出会う。立派な深浦町役場の庁舎。更に車を進め、目的地の八峰町に到着し客先挨拶&現場調査。 そして帰路に十二湖に立ち寄る。森の物産館キョロロの先の駐車場に車を留める。 そして青池に向かって歩く。王池。 越口ノ池。 湖面には倒木が。 そして目的地の青池に到着。 十二湖の湖沼を代表する池で、水中には枯れたブナが横たわる静寂の池。 見事な青。地下水より深い層からから沸き出る深層水であること、そして含まれる酸素の量が極端に多い水であると。光(陽)が当たる角度によって色が変化するのであった。池の水に銅も溶けているのであろうか?。 自然が作り出した奇跡のブルー。 そして来た道を駐車場に向かって戻る。鶏頭場ノ池にも倒木の枝が顔を覗かせていた。 そして帰路も日本海の奇岩を車窓から楽しんだのであった。 冬の日本海とは異なり、こちらも青の日本海。
2015.08.18
コメント(0)
-

鶴の舞橋
この日の朝は近くにある池、そして橋の散策の為の早朝ドライブ。車から美しい橋の姿が。全長300mのこの橋は、三連太鼓橋では日本一長い木橋「鶴の舞橋」。そしてこの池は、長期にわたる努力と地域住民の献身的な働きかけにより昭和16年から県営事業として築堤工事に着手しその後国営工事に切替られ、総工事費約4億円を投じて昭和35年に現在の堤防が完成。 春の増水期には1,100万トンの貯水量を有し、このうち木造新田地方の補給用水として566万トンをかかえ、水深約7m、満水面積281.28ヘクタールと県内でも人造湖としては最も大きな貯水湖であり西津軽一円の農業にとって欠くことのできない重要な役割。 また、このため池の特徴として周囲11kmのうち堤の延長4,178.44m、堤高7.08mは他に例がなく、ことに堤長に関しては日本一。そのうえ大溜池の中に壮大な岩木山を映す様はまさに『津軽富士見湖』の愛称どおり"美"そのものであると。 駐車場に車を留め、散策開始。津軽「富士見湖」パーク案内図。 鶴の舞橋に向かって緑濃き林の中を鶴の舞橋に向かって歩く。 鶴の舞橋入り口。 「鶴の舞橋」の概要。長さ:300m 幅:3m直系30cm(樹齢150年以上を700本)青森県産「ひば」1等材丸太3千本、板材3千枚日本一長い木の橋「鶴の舞橋」は「日本一長生きの橋」 とも呼ばれ人気の橋。丹頂鶴自然公園に向かって、長生きを願って橋を渡る。そして折りしもこの日は「橋の日」 。小ステージの休憩場が見えた。 この池の正式名称は「廻堰大溜池(まわりぜきおおためいけ)」 。小ステージの大きさは9m×9m。 大ステージに向かって真ん中の太鼓橋を歩く。大ステージは10m×21m。この下には新設?された休憩用ベンチが置かれていた。「津軽富士見湖の伝説」説明板。今から600年前、津軽鶴田町を統治していた清水城の城主・間山之守忠勝は、隠里の太右衛門の娘・白上姫と出会い恋に落ちた。しかし、間山之守はほかの女性と結婚。姫は悲しみのあまり大溜池に身を投げ、その遺恨は白龍となり、忠勝を苦しめ続けたと。 古記によると、このため池は岩木山を水源とする白狐沢からの自然流水による貯水池であったものを万治3年3月(西暦1660年)に四代藩主津軽信政公が、樋口権右衛門を廻堰大堤奉行に任命し、柏村地方の用水補給のための堤防を築き用水池にしたものと記録されていると。 その後、豪雨、融雪と自然災害により元禄、寛政、文政、明治、大正と堤防が決壊し、そのたびに大修理が加えられ関係者の苦難がそそがれてきた。 しかし、この長期にわたる努力と地域住民の献身的な働きかけにより昭和16年から県営事業として築堤工事に着手しその後国営工事に切替られ、総工事費約4億円を投じて昭和35年に現在の堤防が完成したと。 3連の太鼓橋を渡り終え、丹頂鶴自然公園側から。 鶴田町B&G海洋センター。 B&Gとは、青い海(ブルーシー:B)と緑の大地(グリーンランド:G)の意味か?シャッターは閉じていたが艇庫の模様。鶴がモチーフの石碑。そしてその横には「佇立渚辺望秀峰 心静如水 漫歩玉橋観鶴舞 歳月入夢」 の歌碑が。秀峰を望み、渚辺に立ちて佇めば 心 静に水の如し。玉橋を歩み楽しめば 鶴 空に舞うを観 時を忘る。鶴田町長 中聖挙司氏の作品。橋の右側から。 つがる富士見荘前の散策道のジグザグ橋?を歩く。 小ステージを望む。両側には美しい曲線が。 再び橋を渡り戻る。大自然の中に遊戯施設がいくつか見えた。 大ステージから小ステージを望む。 湖面、湖岸には白い稚魚、ワカサギ?の多くの死骸が。酷暑による水温の上昇による酸欠か? 公園には赤、ピンクのベコニアの花々が。 早朝の売店には人の姿なし。 帰宅してネットで調べて見ると『江戸時代の頃、青森県鶴田町には数多くの鶴が飛来したといわれています。平成4年(1992年)に「生きた丹頂鶴誘致」の声が高まり、平成5年に中国黒龍江省より2羽を譲り受け、平成9年にはロシア連邦アムール州よりつがいを譲り受け飼育されました。2012年1月には当地で出生した鶴や多摩動物園から借り受けしている丹頂鶴オス5羽、メス5羽が飼育され、同年5月27日ヒナが誕生しました。』と。しかし現在もこの周辺は鳥獣保護区に指定され白鳥やガン・カモ等渡り鳥の越冬地となっているとのこと。
2015.08.17
コメント(0)
-

五所川原花火大会
第66回五所川原花火大会「水と光と音の祭典」を楽しんできました。開催場所の岩木川河川敷「北斗グラウンド」に夕焼けが。 ポスターには「がんばろう東北」 「水と光と音の祭典」の文字が。開催時間は19:30~21:00。最大4号(直径12cm)、打揚数 約5,000発の大型花火大会。そして翌日から開催される『立佞武多祭り』の前夜祭。以下、拙い写真ですがお楽しみください。 花火と音楽が絶妙にシンクロする大小様々なスターマインで構成され、フィナーレは300mワイドスターマインとライトアップされた幅80mのウォーターカーテンなど、水と花火と音楽のコラボレーションは絶品。 1.5時間の花火大会を大いに楽しみ帰路へ。 ホテルへの途中、居酒屋へ立ち寄る。津軽三味線の生演奏を楽しむ。撥を叩きつけるように弾く打楽器的奏法と、テンポが速く音数が多い巧みの技にしばし聞き入る。 店には小型の立佞武多が飾られていた。
2015.08.16
コメント(0)
-

青森・田舎館 田んぼアート 2015 『風と共に去りぬ』へ
青森・五所川原を訪ねた折、近くにある田舎館村の田んぼアートを見学に行って来ました。この田んぼアート会場は田舎館村役場庁舎の裏側にある田んぼ。この村役場庁舎の天守閣?(展望台)がある役場の建物を、どう活用するかということから生まれた田んぼアート。 この日も観光客の団体がバスで来ていました。 最上階の展望台に上がる為に200円の鑑賞券を購入。 今年の田んぼアートテーマは『風と共に去りぬ』。アメリカの南北戦争の時代を背景 に、南部の大地主の家に生まれたスカーレットの激しく燃え上がる恋と、激情家ゆえに苦難の道をゆく生き方を描いた長編時代小説そして映画。言わずと知れたハリウッド映画の代表作、アカデミー9部門獲得の金字塔作品。(http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/17/52/1fe23d602741e1675ab6711d9d0ebb4f.jpgより)団体観光客が押し寄せていたこともあり、1Fホール内を行列して展望台へのエレベータの順番を待つ。 ホール内には過去の田んぼアートが年代順に紹介されていた。最初の1993年 『岩木山』1994年 『モナリザ』そして技術も年々進歩して2010年は『弁慶と牛若丸』2011年は『竹取物語』 2012年は『慈母観音と不動明王』 2013年は『花魁とマリリンモンロー』2014年は『富士山と羽衣伝説』30分程並び漸くエレベータに乗る。 展望台から村役場入り口門が。 田んぼアートは田んぼをキャンバスに見立て、色の異なる稲を植えることで巨大な絵や文字を作るのです。大規模なものの多くは斜め上から見る前提で図案を設計し、これに基づいて遠近を考慮して植えられているのです。 使用される稲は主に現代の食用に広く栽培されている米と、古代に栽培されていた稲である「古代米」、または餅米や観賞用品種の稲であり、これらの葉や穂の色によって緑色、黄緑色、濃紫、黄色、白色、橙色、赤色といった7色11種類の品種で作られているとのこと。1993年、青森県南津軽郡田舎館村で村起こしの一つとして田舎館役場裏手の田んぼで始められ、その後2010年以降になるとこれが日本全国にまで広まり、全国田んぼアートサミットも開催されているとのこと。 そして漸く、今年2015年の田んぼアート『風と共に去りぬ』の全貌が眼前に。今年の図柄『風と共に去りぬ』の田植えには、過去最高の約1,800 人が参加したった1日で田植え完了したと係員から。広角レンズ機能の無い私のデジカメでは、この巨大なアート全体を1枚の写真には収められませんでした。 1つ1つ手で植えられた稲で描かれる巨大な絵画。この様々な稲、高い位置から見て整合性がとれる絵づくりなど、田舎館村の技術が日本各地の田んぼアートにも活かされているとのこと。 映画の主人公 スカーレット・オハラが活き活きと蘇ったのです。ヴィヴィアン・リーとクラーク・ゲーブルの有名なワンシーンが、田んぼに! 地元の新品種の米『青天の霹靂』も、しっかりアピールされていました。人の顔のパーツや影など、とても細かいディテールまで再現する田んぼアート。CGで綿密にデザインを考えてから、手作業で色の違う稲を何種類も植えていくことで、実現している苦労が理解できたのです。クラーク・ゲーブルの1本1本の髪の毛や、シャツの陰影に、感嘆。そして、ヴィヴィアン・リーの美貌にも。そして微風にそよぐ稲で顔の表情が時々刻々変化しているのではと感じる事が出来たのです。ボランティアを募って田植えをしていて、シーズンごとに刈り取ってしまう。毎年6月~10月までの時間に限りのある作品。これだけ労力のかかることをしておきながら、1年ごとに消えてなくなる儚さ・刹那が大好きな日本人。これぞ日本の仏教思想?。7色11種類の稲の品種の利用箇所の説明板。 展望台下の土産物屋。帰りはこの階からエレベータ利用。地上から見るとこんな感じで何がなんだか・・・解らないのです。 辛うじて『天』 の文字は解ったのですが。しかしアートの巨大さだけは、下からでも十分理解できたのです。見上げた天守閣にはまだまだ多くの観光客が。 田舎館と言えば,横綱「栃ノ海(10代春日野親方)」の出身地。私が小学生高学年の頃、この小兵横綱の活躍に全国が沸いたのです。相撲は,地元あっての国技。役場内に立派な額が掲げられていました。そして五所川原の『立佞武多』の今年のポスターも。
2015.08.15
コメント(3)
-

薩摩半島へ(その2)
鹿児島空港への帰路に枚聞神社(ひらききじんじゃ)でトイレ休憩。枚聞神社は、鹿児島県指宿市開聞十町にある神社二の鳥居から望んだ勅使殿。本殿は入母屋造妻入で、屋根銅板葺、千木・鰹木を置き、正面に縋破風で1間の向拝(社殿の屋根の中央が前方に張り出した部分)を付ける。平成2年(1990年)に鹿児島県の有形文化財に指定されたと。 神馬。 池田湖と開聞岳。池田湖は薩摩半島南東部にある直径約3.5km、周囲約15km、ほぼ円形のカルデラ湖。九州最大の湖。湖面の標高は66m、深さは233mで、最深部は海抜-167m。 湖岸にはイッシーくんが。 1961年頃より池田湖には巨大水棲生物が存在していると噂され、ネス湖の未確認生物ネッシーになぞらえて「イッシー」と呼んだと。『天璋院篤姫』と『浜崎太平次』の説明板。浜崎太平次は文化11(1814)年に指宿村湊のヤマキという商家に生まれた。少年時代より家業の海運業を志し、那覇、大阪、新潟、佐渡、函館などに支店を設け、薩摩藩の後ろ盾もあって事業を拡大し、当時幕末の動乱の中にあった薩摩藩の財政の立て直しに大きく貢献。石碑には『女の道は一本道 定めに背き 引き返すは 恥にございます』と。「女の道は一本道にございます。定めにそむき、引き返すは恥にございますよ」篤姫のしつけ役菊本の魂の叫び。知林ヶ島(ちりんがしま)は鹿児島湾(錦江湾)の入口付近に浮かぶ、湾内で最大の島。島に松が茂っており、付近を夜間に航行する船乗りが、風が松を揺らして立てる音を頼りに航海したことから知林ヶ島と呼ばれるようになったと。 道の駅「喜入」でマンゴーソフトを楽しむ。 海岸沿いに巨大タンク群が。 JX日鉱日石石油基地とのこと。日本国内の石油使用量約2週間分に相当する原油735万キロリットルを貯蔵することができるのだと。 左手の山の上に巨大な白きロケットの姿が。 錦江湾公園のロケット広場に設置されたH-IIロケットの実物大模型とのこと。鋼製の高さ約50メートル。1989年の鹿児島市制100周年記念博覧会「サザンピア21」会場に三菱重工が展示。そのまま鹿児島に“嫁入り”し、本体を分割して同公園に運んで設置したと。。頂上が雲と噴煙で覆われた桜島と錦江湾。 フェリーターミナルからの桜島。 鹿児島港南埠頭ターミナルビル。 そして鹿児島空港へ到着。 航空展示室「SORA STAGE」 を散策。鹿児島空港の歴史や、現在就航している航空会社についての紹介をはじめ、世界的に有名な航空機の機体をモデルプレーンやパネルを展示。また、なかなか触れることのできない実物大のエンジンのパーツや翼の一部なども展示しており、航空機の大きさを体験することができる。コックピットゲーム。 屋外に出る。 帰路の利用便。 JAL652 17:25発。 そして定刻に羽田空港に向けて離陸したのであった。
2015.08.14
コメント(0)
-

花瀬望比公園へ
花瀬望比公園に立ち寄る。「望比」(ぼうひ)とは、比島(フィリピン群島)を望むという意味。薩摩半島の南端の象徴である開聞岳のちょうど西側にある花瀬崎は、初期噴火のときに流れ出た縄状玄武岩でおおわれている海岸で、イソギンチャクが殻の中から五色の花を咲かせている群落があったことから花瀬の名称が生まれたと。以前からあった花瀬公園に、比島戦没者慰霊碑が建設され、安らぎの鐘や祈念像なども造られ、公園の名前を『花瀬望比公園』と改称したと。 太平洋戦争では、フィリピンにおいて従軍兵士の四分の三に当たる47万6千人が戦死し、その屍の多くが山野に散乱していた。戦死者を慰霊するため、フィリピンを望む本土最南端のこの地に望比公園が整備されたと。 「死生の扉」『戦没者数47万6千余柱、比島作戦に果てた同胞の形骸は朽ちても全ての御霊が永遠に比島にとどまっていると思いたくありません。異域の地で戦友に抱き起こされ、押し上げられて不死鳥の様によみがえり、1,900kmの天空を駈け戦場で見続けた祖国に帰ってくる姿を願う…。』そんな祈りを込めて造形された「死生の扉」であると。 死生の扉の先には鉄兜、機関銃そして「戦士のおもかげの像」 が。鉄兜。遺骨収集の際に機関銃とともに日本へ。 「日本軍の92式重機関銃」 。係りのオジサンの説明によると、未だ多くの遺骨が比島に残っているため銃の先を比島には向けていないと。戦士のおもかげの像(戦友に抱き起こされ、押し上げられて・・・) 想比母子の像。比島に出兵した将兵の妻子は夫や父の安全と無事帰還を祈っていた。この像はフィリピン群島に向かい祈る母子の姿を象徴した像。後ろはレイテの森と開聞岳。 見つめる先は。 この先1900kmの彼方に比島が。 「殉国戦士面影の像」。戦没者の鎮魂と世界民族の永久の平和を祈念し、激戦地フィリピン群島で生命をかけ戦い矢つき玉尽き、尊い生命を落とされた殉国戦士の面影を象徴したもの。 五重塔。 「大鐘桜」・「安らぎ之鐘」1,900kmの彼方、フィリピン群島の島々に響き渡り比島に眠る将兵の御霊を慰め、世界平和と万民 の平穏功徳を祈る望比鎮魂之鐘(平安之鐘)として建立。 望比鎮魂之鐘。比島の方角を指し示す石標。碑文には『岬の突端との延長線上1,900km先に 多くの同胞の果てた 比島がある』。親子亀も。 観音像。 黄金の望比観音像。開聞岳頂上の雲も漸く晴れる。 レイテ沖海戦は、第二次世界大戦中の1944年10月23日から同25日にかけてフィリピン及びフィリピン周辺海域で発生した、日本海軍とアメリカ海軍とオーストラリア海軍からなる連合国軍との間で交わされた一連の海戦の総称。そして、その規模の大きさ、戦域が広範囲に及んだことなどから史上最大の海戦と言われる戦いであったのだ
2015.08.13
コメント(0)
-

薩摩半島へ(その1)
この日は、坊津そして頴娃町(えいちょう)にある現場へ。昨日と同じくバスにて坊津に向かう。青い海が見えて来た。手前に大浦干拓、そして後方に崎ノ山半島が見えて来た。石垣群の里 大当(おおとう)。 目前に突然、100戸を越える民家が段々状の配置で密集している一集落が。笠沙町大当(おおとう)地区。集落の入口に、『100万個の自然石積 石垣群の里大当』と。山が海岸線まで迫って平地が少ない地形のため、人々は山裾(やますそ)の傾斜地に百万個といわれる自然の丸石を野面(のづら)積みして宅地を確保し集落を形成。 延べ長さ1,250mの小路の両側も、敷地の境界も石垣。集落がまるごと石垣の家並みは独特の景観を呈していた。 高崎鼻の海岸線の風景。 巨大な奇岩は仲がよさそう。野間半島の山並みには10機の風力発電が元気良く回っていた。 野間漁港先端からの奇岩。 先ほど通過してきた高崎鼻方面。 紺碧の空そして海。 反対側の野間半島先端方面。 斉藤茂吉の歌碑。「神つ代の 笠沙の碕に わが足を ひとたびとどめ 心和ぎなむ」。 野間半島の南を望む。太い槍のようにとがった岩が、天を突くようにしてそびえていた。 笠沙美術館と、その下後方には沖秋目島(枇榔島)が。 地域の芸術家育成や活動拠点を主な目的に平成10年4月にオープンした美術館。黒瀬展望ミュージアムの別名を持ち、館から望む東シナ海や複雑な岩場など美しい眺望も作品のひとつのようになっていた。笠沙 杜氏の里。 古来より、ここ黒瀬集落の男たちは焼酎醸造の技術を伝承し各地に赴いて活躍、黒瀬杜氏と呼ばれていると。沖秋目島(オキアキメジマ)。坊津入り口。 ここから2ヶ所の現場視察。絶景を望む坊津の海岸、中でも坊浦の双剣石一帯は国の名勝に指定。坊浦の入江に穏やかな波間に対峙するようにそそり立つ鋭く尖った二つの岩が双剣石。雌雄があり、大小の剣を立てた姿に似ていることからその名がつけられたと。 坊津歴史資料センター「輝津館」。輝津館には、中国や琉球等との交易の隆盛を伝える資料や、一乗院を中心とした坊津の仏教文化にまつわる資料、漁具をはじめとする様々な民族資料など、貴重な文化財が展示・公開されていると。日本最南端の始発・終着駅「枕崎駅」 。東シナ海に立つ枕崎のシンボル立神岩。 番所鼻自然公園からの開聞岳。 薩摩藩の番所があったことから名づけられた番所鼻自然公園。日本地図作成のために立ち寄った伊能忠敬が「天下の絶景」と称讃した景勝地。開聞岳には松が似合う。頂上の雲がしつこかった。そして頴娃町(現南九州市)に入り、この日2番目の現場調査。今回の幹事から、昔のアイドルの高田みずえ(現・二所ノ関親方の若嶋津の夫人)の出身地であることを聞く。そして最近は芸能活動を再開していると。
2015.08.12
コメント(0)
-

鹿児島市内 「時標(ときしるべ)」
九州新幹線も停車する鹿児島市内の交通の起点・鹿児島中央駅と、市内随一の繁華街・天文館は1.5km程離れていて、酷暑の下での徒歩では微妙に遠い距離。しかしながら、「時標」(ときしるべ)という7種の像が建設され、それらを順番に巡れば、薩摩の歴史が分かるとのガイドブック情報から、面白そうなので、実際に全部徒歩にて巡ってみました。 多くの偉人を輩出したここ鹿児島市。「時標(ときしるべ)」は近代日本に影響を与えた薩摩の人々を、より身近に感じるために、人と場所、出来事を結びつけて紹介する新しい街歩きのガイド。歴史を動かした人々の思い、活躍した様子を体感できたのです。 廻った順番は下記の順番ではありませんでしたが、時標1~7の順番で紹介します。像の横にはガイド板も置かれており、出来事の説明が英語、中国語、台湾語、韓国語でその隣の面には登場人物の紹介と誕生地を示す地図また薩摩年表によるその出来事が色を変えて示されており、歴史上の位置づけが理解しやすいようになっていた。 (時標1) 1863年「イギリス艦、鹿児島湾に現る」(加治屋町交差点) 大山巌、西郷従道、山本権兵衛イギリス人に死傷者を出した生麦事件を解決するため、翌、文久3(1863)年、イギリスは薩摩に7隻の艦隊を派遣した。いわゆる薩英戦争の始まり。イギリス艦隊入港の知らせを聞いて、大山巌、西郷従道、山本権兵衛も港へ急いだ。驚きから口を開けて、イギリス艦の出現を見に駆け付けようとしている走る姿がリアルであった。(時標2)1858年「樺山、黒田、大いに語る」(高見馬場交差点) 樺山資紀、黒田清隆安政5(1858)年、幕府の大老に井伊直弼が就任し、将軍継嗣問題で、薩摩藩主島津斉彬を含む一橋派と激しく対立。樺山資紀や黒田清隆など多くの薩摩の若き志士たちが、藩や日本の将来について日々語り合ったと。左は後に初代台湾総督になる樺山資紀、右は後に第2代内閣総理大臣になる黒田清隆。二人のやりとりが聞こえてきそうであった。(時標3)1914年「黒田清輝、桜島の噴火を描く」(商工会議所ビル前) 黒田清輝、弟子(山下兼秀)大正3(1914)年、鹿児島に滞在していた黒田清輝は桜島の大噴火に遭遇。創作意欲を刺激された黒田は、この爆発を主題に絵を描いた。一連の絵は現在、鹿児島市立美術館に収蔵。噴火中の桜島をスケッチするため、黒田は弟子(山下兼秀)と共に港に向かったと。黒田清隆の心配そうな顔が見事に表現されていた。(時標4)1866年「龍馬、お龍と薩摩でひと休み」(いづろ交差点) 坂本龍馬、龍慶応2(1866)年、薩長同盟締結直後に坂本龍馬は京都の寺田屋で負傷。小松帯刀や西郷隆盛の勧めにより温泉で傷を癒すため、妻のお龍とともに薩摩を訪れた。小松別邸に滞在し、霧島にも訪れた。これが日本初の新婚旅行といわれていると。お龍の坂本龍馬を見つめる顔が印象的。(時標5)1779年「重豪、薩摩の科学技術の礎を築く」(天文館・ぴらもーるアーケード) 島津重豪、家臣(水間良実)安永8(1779)年、島津家第25代当主島津重豪は天文台の明時館(天文館)を設置し、薩摩暦を作成した。重豪はそのほかにも藩校造士館や医学院などを創設。その先進性は第28代斉彬に継承され、明治維新への基礎を築いた。重豪は自らも家臣(水間良実)と共に天文について語り合ったと。立っているは島津重豪で、座っているのは家臣の水間良実。ここに天文台が設置されたことから、この繁華街は今でも天文館と呼ばれている。二人の空を見つめる顔が技術屋そのもの。(時標6)1860年「伊地知、吉井、政変について語る」(中央公園南側) 伊地知正治、吉井友実幕府と改革派の覇権争いの中、安政7(1860)年に起きた桜田門外の変で井伊大老は暗殺され、幕府は勢力を弱めていった。ここ薩摩の伊地知正治、吉井友実、大久保利通ら精忠組(誠忠組)の間でも、この政変をめぐって様々な議論を重ねていたと。伊地知正治、吉井友実の苛立ちと焦りの表情が見て取れたのであった。(時標7)1869年「ウィリス、高木に西洋医学を説く」(県民交流センター横) ウィリアム・ウィリス、高木兼寛江戸駐在の医師ウィリアム・ウィリスは、明治2(1869)年に薩摩藩に招聘され医学校長となり、赤倉病院を創設。イギリス式医学教育を行い、西日本における医学の中心を築いた。現在の東京慈恵会医科大学を創設した高木兼寛もここで学んだと。医師ウィリアム・ウィリスが弟子高木兼寛に語る姿に自信が溢れていた。時標1~7の順番と年代との関係、そして建設場所との関係が十分理解出来なかったが、この様なストーリー&発想での取り組みは日本ではあまり見たことが無く、面白いそしてユニークな取り組みなのであった。日本の城下町等、古い歴史を持つ街の新しい街歩きのガイドとして、水平展開して欲しいと感じたのであった。それにしてもこの日の夕方は、酷暑に負けずに鹿児島市内を慌しく歩き回ったのであった。
2015.08.11
コメント(0)
-

鹿児島城・鹿児島市内散策へ
鹿児島中央駅への帰路にバスの窓からは頂上が雲に隠れた開聞岳。 武家屋敷近くの知覧役場前交差点。「武家屋敷群」 と刻まれた石碑が見えた。鹿児島中央駅でバスを降りる。 鹿児島県歴史資料センター黎明館に向かう。 薩摩藩の居城・鶴丸城(鹿児島城)の本丸跡に建てられた県の歴史資料センター。鹿児島の歴史民俗や文化遺産に関する展示・研究が行われており、貴重な文化遺産が15万5千点も収蔵されているとのこと。 天璋院 篤姫像。2008年のNHK大河ドラマ『篤姫』の人物。指宿の今和泉島津家に生まれ、島津本家の養女となり、五摂家筆頭近衛家の娘として徳川家に嫁ぎ、江戸幕府第13代将軍徳川家定の御台所に。その後は最後まで江戸城にとどまり,徳川家の存続に力を尽くした。そして再び鹿児島の地をふむことはなかったと。折りしも、大河ドラマ篤姫の衣装・小道具展が行われていた。大河ドラマで使用された籠。 篤姫役の宮崎あおいが撮影で使用した衣装とのこと。 ここで98個目の日本百名城スタンプをGET。 男性の彫像。 館内ロビーに展示さていた銅板のレリーフ。 中庭の竹林の緑が暑さを忘れさせてくれた。 黎明館を囲む池。 鶴丸城(鹿児島城)は, 慶長7(1602)年に島津家18代の家久が築城を始め,以来,島津氏の居城。城は,「人をもって城となす」という方針から天守閣のない屋形づくりの建物だったと。本丸御殿入り口。 石垣下部は工事中?それとも遺跡発掘中? 石垣を間近に見てみると、石垣の表面にはいくつもの穴が開いていた。これは無数の弾丸痕で西南の役の激しさを物語っていた。 大手門である御桜門復元計画も進んでいるとの事。大手門との間に架かる石橋。 堀には蓮が茂っていた。 かごしま県民交流センター。 鹿児島県立図書館。 図書館前庭の屋外展示の作品。鹿児島市立美術館。美術館前の彫刻。ザッキン「オルフェ」。ロダン「ユスタッシュ・ド・サン=ピエール」。 ブールデル「サッフォー」 西郷隆盛銅像。 江戸城無血開城や明治新政府樹立など明治維新に最大の功績を残した「西郷どん」。征韓論に敗れ下野。 その後、西南戦争で新政府軍と戦い敗北し、この城山の地で自刀。城山を背景に仁王立ちする高さ8メートルの堂々たるモニュメント。 道路を隔てた 「西郷銅像撮影ひろば」、この場所で銅像と記念写真が撮れます。鹿児島県教育会館。 明治の風にフロックコートをひるがえす、大久保利通のモニュメント。西郷隆盛、木戸孝允と並び明治維新の3傑と言われた人物で、明治政府の中心的役割を果たした鹿児島に生まれた政治家。ライオンズ公園噴水。 戦災復興記念碑。鹿児島市は太平洋戦争末期の昭和20年(1945)3月18日以来8回の空襲を受け、実に市街地の93%を焼失したと。 高見橋脇にたたずむ女性像。「母と子供の群像」。説明板によると女性は母親で、「強さと厳しさを秘めながら優しく、子供たちを見守る母の姿」を表現しているのだと。彼女の視線の先には、子供たちが。母親像の視線の先、欄干に多数の子供たちのブロンズ像が。子供の群像で、「子供たちが健やかでたくましく育つ姿」を表現。 「若き薩摩の群像」。JR鹿児島中央駅前にある1865年の薩摩藩英国留学生19名のうち薩摩藩出身の17名を銅像にしたもの。1863年の薩英戦争でヨーロッパ文明の偉大さを知った薩摩藩は前藩主島津斉彬の遺志を継いで英国へ新納久修以下の留学生並びに外交使節団を派遣したと。
2015.08.10
コメント(0)
-

知覧・特攻平和会館へ
時間に余裕があるとのことで、知覧特攻平和会館へ立ち寄りました。バスから降りると、知覧茶をPRする急須と湯飲みの大きなオブジェが。 知覧平和公園内 施設案内板。知覧特攻平和会館、陸上競技場、多目的球場、サッカー場、庭球場、弓道場、相撲場、武道館等各種施設がありました。敷地内に入ると、先ず目に付くのは特攻隊員像と飛行機が。この飛行機は航空自衛隊初等練習機『T-3』。航空自衛隊防府北基地で長年活躍し、平成17年に用途廃止され、知覧町が借り受けたものであると。一式戦闘機「隼」。一式戦闘機は、第二次世界大戦時の大日本帝国陸軍の戦闘機。太平洋戦争における主力機として使用された。総生産機数は5,700機以上で、旧日本軍の戦闘機としては海軍の零式艦上戦闘機(零戦(ぜろせん))に次いで2番目に多く、陸軍機としては第1位。これは実物ではなく復元模型とのこと。 特攻銅像「とこしえに」。像の解説板には「特攻機は、ついに帰ってきませんでした。国を思い、父母を思い永遠の平和を願いながら 勇士は征ったに違いありません。御霊のとこしえにやすらかならんことを祈りつつ りりしい姿を永久に伝えたい心をこめて開聞の南に消えた勇士よ」母の像「やすらかに」。像の解説板には「特攻隊の若い命は、ついに帰らず出撃の瞬間まで求めたであろう母の姿この晴れ姿をせめて母上に一目最後の別れとお礼を一言胸も張り裂けそうな、その心情は母もまた同じであったろう今ここに立つ母の姿とこしえに母を 共にやすらかに母の温かいみ胸で御霊のやすらかならんことを世界の平和を祈念して」 巨大な石灯籠。 特攻隊の歌の石碑。一 ああ薩南の此の地より 敵撃滅の命を受け まなじり決し若人が 翔び立つ姿尊しや その名特別攻撃隊 こちらの石灯籠の前の碑には「散るために咲いてくれたか桜花 散るこそものの見事なりけり」と。増田利雄軍曹 飛行第105戦隊 21歳の歌とのこと。知覧特攻平和会館。 知覧は、太平洋戦争末期の沖縄戦において、陸軍の特攻基地が置かれた町。この特攻平和会館は、その当時、人類史上類のない爆装した飛行機もろとも肉弾となり敵艦に体当たりした陸軍特別攻撃隊員の遺影、遺品、記録等貴重な資料を収集・保存・展示。当時の真情を後世に正しく伝え、世界恒久の平和に寄与するもの。二度と悲劇が繰り返されぬよう、戦争の悲惨さ、平和・命の尊さを教えてくれたであった。 館内は撮影禁止。特攻隊員の写真と手紙が出撃順に展示されていた。皆若い。若いゆえに手紙の内容は、母親へ宛てたものが多いが皆達筆。先日のニュースでは、遺族も高齢化し、手紙、遺書をこの平和会館に寄贈する人が多くなって来たと。 しかし、遺された写真の中で、少なくとも悲愴な様子をしている隊員は見当たらないのであった。子犬を抱いたり遊びに興じたり・・。出撃前の瞬間に微笑みを浮かべている者すらいるのです。しかしその裏で知覧特攻平和会館の展示は悲哀に満ちていたのです。特攻隊員と遺族の慟哭が聞こえてきたのです。そしてロビーには知覧飛行場の歴史を紹介する映像(CG)や陶板絵画(知覧鎮魂の賦)、映画「月光の夏」で知られるフッペルのピアノ等が展示されていた。三角兵舎。特攻隊員の寝床。 敵の目を欺くため、松林の中に半地下壕をつくり、屋根には杉の幼木をかぶせ擬装してあったと。ここは暗く狭く、寂しいところ。 特攻兵の中には、この寝床でガタガタ震えたり、泣いたりしていた人も居たのだと。特攻平和観音堂。特攻で無くなった1,036名の慰霊のために建てられた。特攻の母・トメさんの尽力もあったと。私も合掌。ミュージアム知覧。南薩摩の歴史と民族を多角的に紹介している博物館。音や映像で楽しむシアターや武家屋敷の調度品や古文書を展示しているギャラリーなどがあるとのこと。「帰るなき機をあやつりて征きしはや 開聞よ 母よ さらば さらばと」(飛び立つ直前に詠んだ辞世の句)。特攻隊員は開聞岳方面へ飛び立つのだと。ホタル「石碑」 。特攻隊員から母親のように慕われた女性が、軍の指定食堂「富屋食堂」の女将「鳥濱トメ」。6月6日、宮川三郎軍曹はトメに言った。「俺はホタルになって、おばちゃんに会いに来るから、宮川来たかと追わないでくれよ。」と・・目に涙を溜め・・・。 トメと家族は送り出した。そしてその夜、本当に一匹のホタルが富屋食堂に舞い込んで来た。トメは叫んだ。「このホタルは宮川三郎さんですよ。同期の桜を歌って下さい。」と。出撃を待つ特攻隊員、トメや娘達も、泣きながら同期の桜を歌ったのだと。そしてこの日が、ほぼ最後の沖縄特攻作戦となったのだと。旧陸軍戦闘指揮所跡には「映画 ホタル ロケ地」の案内板が。2007年に元東京都知事の石原慎太郎が「俺は、君のためにこそ死ににいく」という映画を製作総指揮。その記念にか、このような石碑が建てられていた。「短い青春を 懸命に生き抜き 散っていった特攻隊の若者たちが 「お母さん」と呼んで慕った富屋食堂の女主人 鳥濱トメさんは、折節にこの世に現れ 人々を救う菩薩でした。」 と刻まれていた。平和会館の前庭にある平和の鐘。コミュニティセンター知覧文化会館。 戦後70年。日本人は過去の「戦争の真実」を見つめ、国を守ること、平和を守ること、生きることと死ぬこと、そして他国との交わりを真剣に考えなければならないのである。我々はここ「知覧からの手紙」の真意をしっかり胸に受け止め、子供達にそして世界に伝えていかねばならないと。 そして酷暑の中、今日は長崎に原爆が落とされた日そして70年目の終戦記念日が近付いて来たのである。
2015.08.09
コメント(0)
-

鹿児島へそして知覧武家屋敷へ
この日は1泊2日で鹿児島へ。羽田空港に到着し、第1旅客ターミナルビル エアポートラウンジにて時間調整。利用便はJAL643便 8:15発鹿児島空港行き。 定刻に離陸し、鹿児島空港近くまでは雲の上。国分上野原テクノパーク、右には上野原遺跡が。 京セラ(株) 鹿児島国分工場。 天降川(あもりがわ)。鹿児島空港に着陸。 滑走路は3000m。「KAGOSHIMA」の文字が。ここからチャーターバスにて鹿児島中央駅へ。ここで他の参加者を乗せ知覧に向け出発。 頂上に雲のかかった桜島の姿が。 手蓑マザーパーク横を通過。これはTHE EARTH IN LEAVES というモニュメントで、知覧中学校の作品をモチーフにしたデザインで、3枚のお茶の葉が地球をやさしく包み込んでいる様子とのこと。 知覧・麓川(ふもとがわ)は前日までの雨で水量が多かった。 知覧の石橋の代表、矢櫃橋(やびつばし)も見えた。武家屋敷を模した知覧観光案内板。知覧節の歌碑。「井手のせゝらぎ そよ吹く風に 螢すごしや 麓川 ホッソイ ホッソイ」 。麓川に架かる 「城山橋」も見えた。武家屋敷の近くに「こかんばし」と言う橋が。「河上」と書いて「こかん」と読むとのこと。武家屋敷駐車場受付。 武家屋敷庭園案内図。約260年余り前、知覧領主(18代)島津久峰時代の武士小路区割の名残りで、武家屋敷通りと屋敷庭園が保存されている風致地区。武家屋敷群は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、庭園は国の名勝に指定されているとのこと。 麓川沿いを歩く。 昼食は高城庵(たきあん)にて。 見事な瓦塀。江戸時代から続くこちらのご主人の自宅を郷土料理の店として使用していると。案内された店内は、古い武家屋敷そのままで、古い箪笥、掛け軸、人形などが飾ってあった。初めて来た場所にも関わらずなぜか懐かしい場所に来た気持ちに。ガラス戸を通して見ることの出来る中庭の緑が美しかった。昼食は高城庵セットを楽しむ。藩政時代のお膳を用いた鹿児島の郷土料理セット。梅酒、芋こんにゃくさしみ、鶏さしみ、ゴマよごしの小鉢そして田舎にしめ、酢の物、香の物などで美味。自家製野菜入りさつま揚げそして鹿児島名物の酒めしも。竹の器に入って錦糸玉子とキビナゴみたいな小魚が乗っていた。最後におそばも小椀で出てきた。高城庵入り口を内部から。 武家屋敷通り。雨上がりの陽光の下、低い石垣とその上に設けられた垣根に挟まれた小路は緩い曲線を描きながら、整然と延びていた。整然とした美しい町並み、母ヶ岳の優雅な姿を借景に取り入れた武家屋敷の庭園の佇まいが、別名「薩摩の小京都」とも言われる美しい武家町。森重堅邸の門。知覧武家屋敷の庭園は木々と石で表現された枯山水が多いが、この武家屋敷にだけ池があると。 茅葺屋根を葺き替えている建物も。残念ながら、時間の関係上、武家屋敷群の国の「名勝」に指定されている7庭園をゆっくり見学できなかったが、もう一度訪れたい場所なのであった。
2015.08.08
コメント(0)
-

ユーカリが丘 散策
翌朝は朝食前にユーカリが丘を妻と二人で散策。駅前にはユーカリが丘らしくコアラの親子のマスコット像が。ユーカリが丘はニュータウンで、ユーカリが丘1-7丁目・南ユーカリが丘・西ユーカリが丘1-7丁目・宮ノ台1-6丁目などを中心とする地域。1971年に不動産会社の山万が開発を始め、1979年に分譲が開始されたニュータウン。「自然と都市機能の調和」、「少子高齢化」、「安心・安全」、「文化の発信」、「高度情報通信化」の5つのキーワードに沿った、一貫した開発が行われている。キャッチコピーは「未来の見える街」。世帯数7,178戸、人口17,936人(2015年5月末現在)。 駅前の歩道橋 ( イオン シネマ ユーカリが丘への連絡橋 ) 上に大きく手を広げた彫刻が。この作品は日展会員の久保浩が制作、「森の耀き ( 木の葉の着物を着た大山祇 )」、「水の燦き ( 水の衣を纏った天水波女 )」 との記載が。宿泊ホテル。 モノレールの山万ユーカリが丘線に乗り散策開始。 この路線は、不動産会社である「山万」が開発、第三セクターをのぞく純民間企業経営の新交通システムとしては日本初の事例であり、日本における純民間資本による新交通システムはこの路線と西武鉄道山口線の2路線しか存在していないとのこと。車両には可愛いイラストが。 ユーカリが丘 - 公園の区間は両方向に運転される単線、公園 - 女子大 - 公園の区間は片方向にのみ運転される環状線になっており、ユーカリが丘駅を出発した列車は公園駅から環状線を反時計回りに環状運転して、同駅から再びユーカリが丘駅に戻るのだ。 車両には宿泊ホテルで行われる予定の「坂本冬実」のポスターが。この時期に有名歌手がホテルでデイナーショー??よくよく見ると「坂本冬休み」の文字に気がつく。ものまねタレントで以前は「加藤めぐみ」で出ていたが2011年、芸名を「坂本冬休み」に改名したとのこと。 駅名も「公園」、「女子大」と具体的でないのが面白かった。 ユーカリが丘南公園を車窓から。 環状線を1周し車窓の風景を楽しみ、合流駅の公園でモノレールを下車。目の前に環状線の往路と復路が。 公園の巨大なライオンが迎えてくれた。 キリンも。 そして環状線内の自然道をのんびり散策。 池には野鳥がのどかに。 そして再び公園駅方面に戻ると、頭上をモノレールが通過。 温泉や予備校など各種施設が。印旛沼に代表される緑と高層ビル群とが調和した、印象的な風景を見る事ができたのであった。そしてホテルに戻り長女夫婦、孫と朝食。散策の話をすると、長女家族も我々と同様にモノレールを楽しみに向かったのであった。
2015.08.07
コメント(0)
-

佐倉市民花火大会へ(その2)
印旛沼湖畔に咲き誇る百花繚乱約1万6,000発 (打上最大花火 2尺玉4発)をシャッターを押しながらそして歓声を上げながら大いに楽しんだのです。 打ち上げ時間 19:40~21:00の花火を。 日本の夏の文化そして桜と同じく儚く、一瞬で消えてしまう美学を楽しんだのです。毎回思いますが、日本の花火は「職人芸」であり「技術」。そしてこの日まで花火造りに努力した「花火師」の姿を思い浮かべながらホテルへの帰路に往路と同じ道を。Fさん、今年も我が家の家族全員でお邪魔し、巨大花火を楽しませて頂きました。本当に毎年毎年ご準備いただきありがとうございます。今年同様に、来年も「大切な人」と迎えたい年中行事のこの花火大会を。
2015.08.06
コメント(0)
-

佐倉市民花火大会へ(その1)
今年も、長女の嫁ぎ先のご両親から、佐倉市民花火大会へのご招待をいただきました。12時前に自宅を出発し、戸塚駅から横須賀線で船橋へ。途中、やや霞んでいましたが東京スカイツリーが車窓に。 京成電鉄のユーカリが丘駅近くにの宿泊ホテルで長女夫婦そして孫、長男夫婦と合流し京成臼井駅近くのご自宅へ。そして、ご準備いただいた冷たいアルコール、飲料、食料類をそれぞれキャリーカートに乗せ30分ほど歩き会場へ到着。場所は印旛沼湖畔の佐倉ふるさと広場周辺。2015年のポスター。 今年は、関東最大級の二尺玉を4発打ち上げるほか、音楽に合わせて10分間で6,000発のビッグプレミアムスターマインを打ち上げると。席はS会場の特等席。今年は座り心地のよい椅子席。そして、ご準備いただいたお弁当を早速、花火開始前に楽しませていただきました。こちらも色美しく配置され、綺麗な花火を予感させてくれたのでした。 手筒花火を観客に持たせ説明するハッピ姿の職人さんの姿も。 廻りも薄暗くなり、遠く夕焼けも。 オランダ風車「リーフデ」 の前のカメラアングルにとっても特等席。帆を外した風車の枠格子からも夕焼けが。 そして手筒花火から今年の花火大会のスタート。わがグループは総勢12名での花火鑑賞。 手筒花火は、1メートルほどの長さの竹筒に火薬を詰め、それを人が抱えながら行う花火。 火柱が10メートル近くにも噴きあがり迫力満点。そして巨大なスターマインが。 高圧線鉄塔も借景として頑張ってくれました。 休むまもなくBGMに合わせて次々と様々な色と形の花火が。 1歳10ヶ月になる孫娘も音や光に驚くことなく楽しんでいました。 私は3脚にデジカメをSETし、花火を見ながら右手でシャッターを押し捲りました。 ビールも進み酔いも加速し、ピンボケもかなりありましたが・・・・・。
2015.08.05
コメント(0)
-

花オクラ
今年もわが農園で栽培している花オクラが毎朝、黄色い花を開かせています。 高さは1.5メートル以上に達し、葉は掌状に。茎には細くて堅い棘があるのです。トロロアオイ(黄蜀葵)とも呼ばれ、オクラに似た花を咲かせることから花オクラとも。原産地は中国。この植物から採取される粘液はネリと呼ばれ、和紙作りのほか、蒲鉾や蕎麦のつなぎ、漢方薬の成形などに利用されているとのこと。 花弁は5つ。花の大きさは10から20センチで、オクラの倍近いのです。朝に咲いて夕方にしぼみ、夜になると地面に落ちる花も。この日も早朝に花を摘んできました。 花の色は淡黄からやや白に近く、濃紫色の模様を花びらの中心につけています。 ガク部分には細かいとげがあるので、注意して花びらの部分を切り取り水洗いしました。鍋に水を入れ、沸騰したら花オクラをいれます。(お湯も薄い黄色になります)30秒程度たったらお湯を捨て、冷水に晒すのです。この日は酢の物で。手でぎゅっとして水気をとり、お皿にもり、ポン酢をかけて楽しみました。名前の「オクラ」はカタカナで書きますが、これは外来語に対して使われるのと同じで、「オクラ=Okra」は英語名とのこと。鮮度が「命」のため…流通していません。栽培者だけの特権を楽しむことができるのです。そして天ぷらでも。
2015.08.04
コメント(0)
-
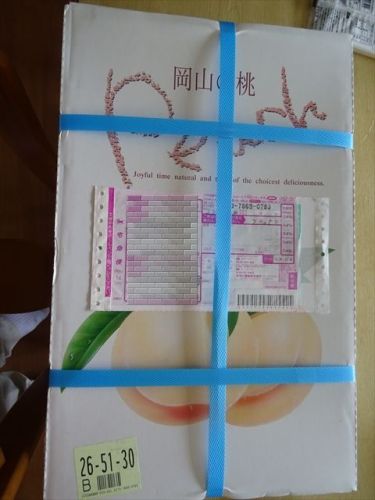
白桃
今年も、岡山の親戚から白桃を送って頂きました。 箱には「岡山の桃 Peach」と。そして「Joyful time natural and taste of the choicest deliciousness」の文字が。自然豊かな極上のうまさでうれしい時間をお過ごしください の意味か。ダンボールの蓋を開けると、保護シートの下に白桃が行儀良く。 白桃の特長である真っ白い果実。そして上部がほんのりと淡いピンク色。そして純白の緩衝材に包まれていました。 岡山を代表する桃の品種と言えばやはり『清水白桃』とのこと。皆、笑顔で挨拶しているが如し。 太陽の光をたっぷり浴びて、白い皮にほんのり淡いピンクで見た目も美しく。早速、ご馳走になりました。果肉は柔らかく、ち密で甘みが高く、芳醇な香りが。妻が娘に連絡すると、昨年以上の速さで、早速子供を連れて家族で取りに来ました。
2015.08.03
コメント(0)
-

ブルームーン
7月31日(金)は満月そして「ブルームーン」でした。ひと月に2度満月が生じるとき、2度目の満月のことを俗に「ブルームーン」というとのこと。会社から帰宅して我が家から満月を撮影。月の満ち欠けは約29.5日周期。基本的に1カ月に1回しか満月にはなりませんが、誤差による月の周期のずれにより、数年に1度ブルームーンとなるのだと。ちなみに、2015年7月は、2日と31日が満月。前回は2009年12月2日と31日。次回は2018年1月2日と31日と。ブルームーンを直訳すると「青い月」ですが、実際に月が青く輝くわけでもなければ、月食のような天体ショーが起こるわけでもありません。見た目はいつもと変わりない満月。それなのに、ブルームーンがめぐってくるたびに話題となるのはなぜでしょう?英語には「once in a blue moon」という表現があって、辞書を引くと「ときたま」「めったに......ない」とあります。ここから転じたのか「ブルームーンはめったに起こらない幸運なこと。見れば幸せになれる」という(出所がはっきりしない)言い伝えがあるのだと。そして先日我々夫婦の金沢旅行は「フルムーン」旅行。いよ!! 座布団3枚!!
2015.08.02
コメント(0)
-

金沢へ(金沢駅そして帰路へ)
金沢旅行最終日のホテルからの金沢の早朝の街並み。 遠くに金沢の山も。 香林坊に向かって歩き、途中片町の九谷焼・諸江屋に立ち寄る。人間国宝であった三代徳田八十吉や武腰潤、山本長左などの有名作家の作品を鑑賞。釉薬で色彩を調整した鮮やかな群青色「彩釉磁器」の三代徳田八十吉の作品の美。グラデーションが、九谷焼の歴史に新たに刻まれる「彩釉(さいゆう)」という技術。そしてこの旅で何回か利用した香林坊のバス停より金沢駅へ。香林坊の交差点の一角に目を惹くオブジェが。逞しい?しかし何か奇妙な足のオブジェ、タイトルは「走れ」とのこと。バスで金沢駅に到着。金沢駅東口のシンボル「鼓門」 。木製の「鼓門」は、金沢の伝統芸能である加賀宝生の鼓をイメージした2脚の柱に、緩やか曲面を描いた格子状の構造となっている屋根をかけたもので、伝統と革新が共存する街である金沢を象徴する堂々たる門。構造材には全て米松構造用集成材が用いられており、重ね梁や屋根の面格子は、相欠きにされた材で見事に組み上げられています。又、柱の内側には、もてなしドームに降った雨水を再利用する為の送水管や地下の排気口が造られているそうです。高さ:13.7m 天幅:24.2m 。金沢駅の文字が。 「もてなしドーム」は、アルミ合金製の骨組みに3,019枚の強化ガラスを組み合わせた大屋根で、1本3Mのアルミパイプを6,000本組み合わせて造った日本で最大のアルミトラス構造。アルミ合金の構造体としては全国最大のもの。 噴水。 噴水がデジタル時計になっていた。10:38と表示。 金沢駅 観光案内所を訪ねる。「ひゃくまんさん」。ひゃくまんさんは、石川県の郷土玩具であり、縁起物の「加賀八幡起上り」をモチーフに、石川の多彩な文化をギュッと凝縮し、百万石の豪華絢爛さをイメージさせるデザインで、北陸新幹線開業PRキャッチコピー「いしかわ百万石物語」を象徴するキャラクターとして作成したのだと。 マスコットキャラクターの愛称については、全国から5000件もの応募から、選考の結果、「ひゃくまんさん」に決定したと。 石川県内各地の名品も展示。 能登「キリコ祭」。「キリコ」または「奉燈」と呼ばれる高さ数メートルの巨大な灯籠を使うことを特徴とするもの。主として7月から10月に掛けて夏祭り・秋祭りとして行われており、疫病退散を願って始まったとされるものが多いと。七尾 「和ろうそく」。和ろうそくは植物ロウを主原料に、芯は和紙と灯芯を使った手作りのろうそく。金沢漆器。 そして昼食は駅ビルの上階で。私は蕎麦と天丼SETを注文。 妻は冶不煮と蓮蒸しの郷土料理を注文。 そして帰路の新幹線は「はくたか 566号」。立山の山には雪渓が残っていた。 黒部宇奈月温泉駅。 黒部峡谷付近の山々。そして帰路は3時間で東京駅に到着。 久しぶりの妻との旅。今年2015年3月14日(土)に北陸新幹線が開通し、東京から2時間30分で金沢へ。気軽に金沢観光へ来ることができる時代になったのであった。加賀百万石と言われる加賀藩の中心であった金沢。1546年に金沢の中心となる御山御坊が作られ、佐久間盛政、前田利家と城に入り城下町の形成が始まったのだ。浅野川、犀川に挟まれたこの場所は武家を中心にして発展。京都の公家文化に対して金沢は武家文化と言われているのであった。度重なる火災からも復興を遂げ今なお多くの文化が進化する武家の都市である金沢市内をバスと徒歩で、そして酷暑に負けずに慌しく見学したのであった。そして65歳以上入場料無料も体験し、「新たなステージ」の旅でもあったのでした。
2015.08.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 日本全国のホテル
- 【岐阜】天然温泉 陣屋の湯 スーパ…
- (2025-11-23 10:12:24)
-
-
-

- 皆さんの街のイベントやお祭り
- 令和7年 八朔祭 菅原神社 海船濱…
- (2025-11-23 06:24:53)
-
-
-

- フランスあれこれ・・・
- 【France】【Beaujolais nouveau 202…
- (2025-11-22 04:48:07)
-







