2015年06月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 2日目(中城城)
入り口にボランティアのオジサンがおり、案内してくれると。 平成12年12月、中城城跡を含む「琉球王国のグスク及び関連遺産群」が国内11番目の世界遺産として登録。前方に『三の郭』が。後に増築されたため「新城(ミーグスク)」とも呼ばれ、石積み技法の最も進んだ相方積み(亀甲乱積み)によって築かれていた。 中城城跡全景の模型。 物語を刻む世界遺産の中城城跡は、北中城村から中城村にわたる標高167メートルの高台に、東北から南西にほぼ一直線につらなる6つの城郭からなる城で、琉球王国時代に築城家として知られる護佐丸が、勝連半島で勢力を伸ばしていた阿麻和利に対する備えとして、読谷の座喜味城から移されて築いた城だといわれています。自然の地形を巧みに利用した美しい曲線の城壁に囲まれ、一の郭と二の郭は「布積」、三の郭と西北側の郭は「あいかた積」と呼ばれる手法で築かれており、その築城技術は高く評価されています。当時の琉球は、沖縄本島南部の佐敷から興った第一尚氏によって、国家が統一されていく過程にあり、その最終段階でこの城が果した役割は大きいものがあったと。護佐丸の滅亡後、この城がどのような使われ方をしたのかについては定かではないが、第二尚氏になると中城の領地が王の直轄領となっていたことからすると、中城城は王子の居城としてしばらく使われていた可能性も高いといわれていると。護佐丸が増築したとされるこの郭は、曲線の美しさと技法の高さが琉球のグスクの最高美と称賛されているのだ。 北東に向かって建てられた裏門。1853年に黒船でペリー提督一行が沖縄に立ち寄った際、中城城を測量し、「要塞の資材は石灰岩であり、その石造建築は、賞賛すべき構造のものであった」と『日本遠征記』に残しているのだと。 『あいかた積み』の北の郭・物見台。護佐丸が井戸を取り込み増築したとされる北の郭。井戸を取り込む事により、長期の籠城にも耐えられるようにしたとされるとのこと。二の郭へ向かう。 美しい曲線の石垣。 一の郭から南の郭へ抜ける拱門だが、本来あるはずの屋根の石積みが なく鉄骨で補強されていた。中城の碑。二の郭に建てられている石碑は、日露戦争の戦没者を祀った慰霊碑だと。 中城城跡で最も眺めの良い場所といわれる二の郭。 、 晴れた日は沖縄のほぼ半分の地域が見えると。海沿いに見える吉の浦火力発電所は沖縄電力の天然ガス火力発電所。沖縄電力初のLNG(液化天然ガス)火力であり、初のコンバインドサイクル発電方式を導入した発電所。一の郭への入り口門。 中城城跡の中で最も大きな敷地の一の郭、中城城の主郭で殿舎が建っていた場所。のちに間切番所が立てられ、廃藩置県後は中城村役場がここにあったそうだが、先の沖縄戦で焼失してしまったのだとか。門の石垣の中には、新たに交換されたと思われる白い石も。 「御當蔵火神(うとぅくらひぬかん)」の文字が。琉球国王が住む首里城を拝む場所。それに「火神(ひぬかん)」があるということは、ここでは火を扱っていたのであろう。沖縄では、火を扱う竃や台所には「火神(ひぬかん)」を祀る風習があって、今も受け継がれているのだと。現在の住宅でも、台所にに「火神(ひぬかん)」を祀っているお宅が多いと。 狭間か? 正門。南西に向けられて建てられた正門(やぐら門)。門を挟むように両側に石垣がせり出している。また、正門の近くには城壁の一部を取り除いた部分があるが、これは第二次世界大戦当時、日本軍が防空壕を作ろうと工事を始めたが、石垣の構造がとても堅固で作業が難航したため、諦めて撤退したとされている。 廃墟となった中城高原ホテル。一度も日の目を見なかった廃墟ホテル。山の稜線沿いに1階から4階建ての傾斜に合わせて建築しようとしていたホテル。昭和50年(1975)、今から32年前、沖縄海洋博に合わせてオープンさせようとしていたようだ。どう考えても壮大な違法建築?。 散策道の脇には多くのクワズイモは自生していた。マムシクサに似た赤い実が。ワズイモの名前の由来はシュウ酸カルシウムという毒があって食べられないから。もちろんこの実も食べると大変なことになる(はず)。
2015.06.30
コメント(0)
-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 2日目(古宇利島、中城城へ)
今帰仁城から更に車を進め古宇利島(こうりじま)内にある古宇利オーシャンタワーに到着。古宇利島は、沖縄本島北部にある屋我地島の北に位置し、今帰仁村に帰属する有人島。離島ならではの美しい海や「沖縄版アダムとイヴ」と呼ばれる伝承があることで有名。 2013年にオープンした古宇利オーシャンタワーは、古宇利島の海抜82mからの絶景を楽しむことができるスポット。しかし入場料が800円と高価な為、オーシャンタワー入場は諦めたのであった。 そして帰路、古宇利大橋(こうりおおはし)が見える絶景ポイントで車を止める。古宇利大橋は今帰仁村の古宇利島と名護市の屋我地島を結ぶ長さが1960mで通行は無料。対岸の屋我地島から見た古宇利大橋と古宇利島。2005年に開通して古宇利大橋は当初は日本で一番長い無料で渡れる橋だったと。 ドライブインでトイレ休憩。マンゴーのソフトクリームを楽しむ。 沖縄北インターで沖縄自動車道を降りる。 沖縄県中部の与勝半島というエリアには、東洋一の長さを誇る無料の海中道路が。しかし、“海中道路”といっても、海の中を潜る海中トンネルではなく、海の上を渡る“海上道路”のことをさします。沖縄本島から、浜比嘉島、平安座島、宮城島、伊計島へアクセスすることができる離島への玄関口で、全長4.7KMの道路はほぼ一直線。橋の両脇には目の覚めるようなコバルトブルーの海がどこまでも続き、車でドライブすると何とも爽快な気分にさせてくれるスポット。 吊り橋になっていて、赤い橋脚が印象的。 沖縄県中部の与勝半島というエリアの案内図。 橋の中ごろには、沖縄の特産品販売や料理が楽しめる「海の駅あやはし館」という休憩所が。風に風力発電も頑張っていました。 橋の終わりは平安座島。 面積5.44km²、周囲約7km、標高115.6mの低平な島。島の大半を近代的な石油コンビナートが占めていますが、ドライブをしている上ではあまりタンク類は見えないので気にならなかった。ちなみに海中道路はこの石油コンビナートが作られた見返りとして建設されたらしい。次の目的地中城に向かう。 中城城跡の表示板が前方に。そして目の前の山の上に石垣が見えて来た。 幾多の歴史ドラマをはらんだ中城城は、中城村が村づくりの起爆剤として位置づけている「中城公園整備事業」、「古城周辺整備事業」で、今、新たな時代を迎えていると。 中城城入り口にてチケットを購入し城址内へ。 そしてもちろん日本百名城スタンプ97城分をGET。残り3城に。
2015.06.29
コメント(0)
-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 2日目(今帰仁城)
沖縄県国頭郡今帰仁村に位置する城跡 ・今帰仁城(なきじんぐすく、なきじんじょう、別名:北山城(ほくざんじょう、ほくざんぐすく))を訪ねる。この城跡は4年前に妻と訪ねているが、その時は日本百名城スタンプラリーには参加していなかったので、今回はそのスタンプGETも目的の一つ。グスク交流センター内部。 このセンターの受付がスタンプのある場所。 96個目のスタンプをGET。今帰仁城めぐりの前に昼食を。私がオーダーしたのは、 海ぶどうそば。そして世界遺産の今帰仁城跡巡りに向かう。 14世紀、琉球王国成立以前に存在した北山の国王・北山王の居城であったのだ。南北350 m、東西800 m、面積37,000 m²。県内最大級の城(グスク)として名高い。 今帰仁城跡の石垣の特色はその特殊な積み方、つまり野面 積にある。石材の特質や、あまり手を加えていない自然石をそのまま使った荒っぽさのなかに、屏風型に美しい曲線を描いて造りあげたところにあるのだと。 大隅(うーしみ)の石垣。高さ3~8mの城壁からは圧倒的な強さを感じたのです。未だ発掘中の場所も。 平朗門(へいろうもん)。平郎門は今帰仁城の正門で、その名称は『琉球国由来記』に、「北山王者、本門、平郎門ヲ守護ス」として登場。現在見る門は、昭和37年(1962年)に修復されたもので、左右に狭間があり、門の天井は大きな一枚岩を乗せた堅牢な作りとなっていた。 平朗門を潜り、左右の狭間を門の内側から確認。平郎門から大庭(うーみやー)まで続く参道は戦前に地元民によって桜の植栽とともに直線道に整備されたと。 絶世の美女と言われた【今帰仁御神】を詠んだ歌が石碑になっていた。「今帰仁の城しむないの九年母 志慶真乙樽がぬきやいはきやい」訳:高齢で病気がちの城主の側室 志慶真乙樽に待望の子供が出来た 側室は目に入れても痛くないほどの可愛がりようである。今帰仁城跡内には2つの御嶽がありました。一つ目は大庭の北西部にある「ソイツギ」。ソイツギと呼ばれる御嶽(ウタキ)は、五穀豊穣を祈願した聖域。大隅(うーしみ)からエメラルド色の海が。 御内原(ウーチバル)。御内原は今帰仁城に仕える女官の住んでいたところ。海の見晴らしは絶景で、正面に伊是名島と伊平屋島が重なって見え、よく晴れた日には北の方角に与論島を見ることができると。 志慶真門郭は主郭から見下ろす位置にあった。志慶真川に沿って城壁が築かれ、志慶真門(裏門)の跡が。 主郭にはしっかりした礎石が残っていて、往時建物があった事を示していた。 主郭(俗称本丸)。主郭は日本の城郭の本丸にあたる部分ですが、天守閣はない。標高100メートルで今帰仁グスクの最上部。主郭は城主の住居があったところで、山北王と今帰仁監守の住居跡が確認できるのだと。 主郭から志慶真門郭へ向かう途中の石垣。ここの城壁は野面積みといわれるほぼ原型に近い形で残っていた。按司の家臣たちが生活した家が建っていた場所と言われており、多くの異物が出土したと。主郭の右手奥の道を下って行くと志慶真門郭に出ました。今帰仁城の東側には志慶真川の深い谷があり、これが天然の要害となっているのだ。 志慶真門郭からも遠く海が見えたのであった。 志慶真門郭の奥の石垣。主郭の裏側(南側)に位置し、搦手門に当たる裏門の志慶真門を持つ郭。 志慶真門郭の発掘調査で4棟の掘立柱建物が発見されたと。今は芝を張り、建物の大きさが分かるように丸太で柱を表す整備がされていた。7~12坪程度なので、それほど大きくはなし。志慶真門郭から主郭方向を見る。空の青、海の青、エメラルドグリーン、山の緑、そして石垣。 主郭の裏側(南側)の法面にも礎石の如き石垣が。 帰路に着く。かつては平郎門からはいって右よりを石垣に沿って狭い曲がりくねった石敷きの小 道があったと。これが城内に通ずる道で大庭の南端に至るように造られ、現在、大庭の近くにわずかばかりその痕跡をとどめている。道に沿って大きなフクギが茂っていたが、道とともに1942年頃にとりこわされたと。 平朗門の先の発掘中の現場。 2000年11月に首里城跡などとともに、琉球王国のグスク及び関連遺産群として、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されたのです。今帰仁城の入口にある城跡の屋外模型。
2015.06.28
コメント(0)
-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 2日目(沖縄美ら海水族館、備瀬フク木並木通り)
海洋博公園内にある沖縄美ら海水族館(おきなわちゅらうみすいぞくかん)を訪ねる。沖縄本土復帰記念事業として1975年(昭和50年)に本部町で開催された沖縄国際海洋博覧会において、海洋生物園が出展されたのが始まり。 イルカの像の下からはミスト状の水が出て観光客を歓迎。入り口近くのオブジェ「花やどかり」がウィンクして迎えてくれました。花マンタ? 水族館に向かう。 この水族館の「うり」はこの銅像の通りジンベイザメ。 花カメ。 水族館の下に広がる海もエメラルド色。 遠く伊江島の姿も。高くそびえる城山(ぐすくやま)は。伊江島の中央にそびえる島のシンボル。標高は172.2メートル。 沖縄戦の初期、昭和20年4月16日から21日まで、「六日戦争」と呼ばれる日米の激しい戦闘がこの伊江島で繰り広げられたのだ。日本軍約2000人、村民約1500人がこの6日間で戦死したと。美ら海水族館の建物を海側から眺めて。 ウミガメ館の水槽の中では係員がウミガメの世話を。 水族館は4階建てになっていて、入り口は3階。3階までエスカレーターであがっていき、そこから順番に見ながら下に降りていく仕組み 。この日は水族館には入らなかった。そして車で5分ほどの備瀬地区のフクギ並木を訪ねる。 防風林として家を取り囲むように植えられたフクギが連なり、備瀬崎までのおよそ1kmの並木道になっていた。 フクギの葉は対生で、長楕円形または卵状楕円形で長さ8-14cm。 観光客を乗せ牛に引かせフクギ並木を案内する老人の姿も。 差し込む日差しとフクギの葉擦れ、落ち着いた静けさは、かつての沖縄の集落の様子と、ゆったりとした時間の流れを感じさせてくれたのでした。
2015.06.27
コメント(0)
-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 2日目(美浜アメリカンビレッジ,残波岬、真栄田岬、瀬底島)
沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 2日目は沖縄中部地区の観光。朝食を早めに済ませ、7時前にホテルを出発し58号線を北に。最初に訪れたのは美浜アメリカンビレッジ。美浜アメリカンビレッジは、那覇市内から車で約40分。沖縄本島の中部にある北谷(ちゃたん)町に、平成10年(1998)から順次、商業施設がオープンしてきた一大リゾート。 シネマコンプレックス、ボウリング場、カラオケボックス、ゲームセンターなどが建ち並び、飲食店や雑貨屋などが集まる若者向けのエリア。地元の若い子達の集まる所、そして嘉手納の直近なので、米軍関係の方々も家族連れで沢山来るので、ちょっと、不思議な空間とのことであるが未だ早朝に付き人影が少なし。 その名のとおりアメリカンな感じで、沖縄に来たなって雰囲気を人こそ殆ど見なかったが、建物はその名のとおりアメリカンな感じで、沖縄に来たなって雰囲気を感じることが出来たのであった。観覧車は夜は華やかにライトアップされており、北谷町の名物。 『デポアイランド』は、ファッション・雑貨・飲食店・ギャラリーなど約60店舗が入居している、美浜の新しい顔となる商業施設。 アメリカの国旗の外装の店屋。 ほかにもカラフルな建物があり、さまざまな店が集まっていました。開店していれば、ひとつの区画だけでもゆっくり見ているだけで相当な時間を楽しめそう。そして車は残波岬灯台(ざんぱみさきとうだい)へ。残波岬灯台は、沖縄本島の中ほどにある読谷村の残波岬突端に立つ、白亜の大型灯台。泰期の像。泰期は14世紀後半、沖縄が琉球王朝時代の頃、中山王の命を受けて初の進貢使として中国に渡り、大交易時代の幕をあけた人物。泰期像は約180cmで中国福建省の方向を指さしているのだと。 断崖絶壁と白い灯台が目印の岬。高さ30m以上のさんご礁の絶壁が続き 砕け散る波しぶきの迫力そして、遠くまで広がる青い海が美しい景勝地。 沖縄本島で一番高い灯台。塔高31メートル、灯高44メートル。この灯台は参観灯台なのだがこの時間は未だ閉鎖中であった。30mもの断崖絶壁が約2kmも続く、雄大な景観が広がっていた。 次の訪問地は真栄田岬(まえだみさき)。 沖縄本島北部の恩納村にある真栄田岬はダイビングとシュノーケルのスポット。整備された階段を下りる。 目の前にはエメラルドの波静かな海が広がっていた。シュノーケリングとダイビングで賑わっていた。人気の青の洞窟ツアーのスポットになっていると。 ダイビングとシュノーケルの生徒が懸命に学んでいました。ここで我が長女夫婦もダイビングを学んだのだと。 展望台からは真栄田岬周辺のきれいな海を楽しめたのでした。 多くの船がダイビング観光客を乗せて。 透明度の高い海が一面に広がっていたのです。 車は更に進み、エメラルドの海沿いを走る。 ドラゴンボートを楽しむ観光客。ゴム製のチューブに座って、ボートで引っ張られて振り落とされないように懸命な姿が。 白波でサーフィンを楽しむ青年の姿も。 瀬底大橋を渡り瀬底島へ。 瀬底島は沖縄美ら海水族館で有名な沖縄県本部町にあり、周囲約8キロメートル小さな島。橋を渡りきり、暫く進むとユニークな人形が歓迎してくれた。 1985年(昭和60年)2月に瀬底大橋が開通。全長762mは当時沖縄県内では最長の橋だったと。 瀬底大橋開通前は対岸の本部港から1日10往復の定期船が就航していたとのこと(所要時間はたった6分)。 本部港~伊江島を結ぶ連絡線か?
2015.06.26
コメント(0)
-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 1日目(美々ビーチいとまん、国際通り)
夕日を 楽しむために、美々ビーチいとまんに立ち寄る。手前に奥行きのある白砂の浜辺が。人工のビーチだが、海の色は美しいエメラルドグリーン。日没まではまだ1時間以上。エメラルドグリーンの海が光る海に。 待つこと1時間、漸く周囲が赤くなってきた。 遊歩道の橋を渡り、防波堤に向かう。屋根付きベンチに座り夕焼けを楽しむ。遠く渡嘉敷島が見えた。沖縄戦では、米軍の激しい攻撃に晒され、米軍上陸後に住民の約半数にあたる368名が集団自決した島。 那覇空港を離陸した飛行機が上空に。 そしてF-15戦闘機も訓練中? 太陽が水平線に近付いて来た。 海も赤く染まりだす。 流れてきた雲も共演。 そして日没間近。 太陽が益々大きくなる。 そして渡嘉敷島の奥に沈む。 時間は19:25前。 夕焼けを楽しんだ後はホテルに向かう。ホテルは琉球サンロイヤルホテル。チェックイン後、一休みし那覇・国際通りに夕食に向かう。国際通りは、那覇市の県庁北口交差点から安里三叉路にかけての約1.6kmの通りの名称。戦後の焼け野原から目覚しい発展を遂げたこと、長さがほぼ1マイルであることから、「奇跡の1マイル」とも呼ばれる。沖縄県で最も賑やかな通りであり那覇最大の繁華街。 多くの沖縄料理の店が。 国際通りの新名所として注目されている『御菓子御殿』。首里城をモチーフにしたその外観は、まさに沖縄のシンボルで、撮影ポイントとしても人気上昇中とのこと。 娘からお土産にと依頼された古酒泡盛40度を購入し自宅に送付。娘の義母の縁者が関係する老舗酒屋の人気の高い泡盛とのこと。 この店に入る。 店の名前は。 ビールのつまみのメニュー。 定番のゴーヤチャンプルを注文。 アーサの天ぷら。古くから沖縄の食卓には欠かせない海藻のアーサ。海ぶどう。沖縄では、昔から食べられており、その形状から海ぶどうやグリーンキャビアと呼ばれている。生で、醤油や三杯酢等をタレのように浸けながら食べる。 食後は店を楽しみながらホテルに向かう。ハブ酒が陳列してあった。 ハブを泡盛に漬け込み、密封し、長期貯蔵したリキュール(薬味酒)。ハブは沖縄県および鹿児島県奄美諸島に棲息する猛毒を有するマムシ科のヘビ。ハブが大きく口を開けていた。旅友のSさんは蛇類が大の苦手。見るのも嫌とそそくさと行き過ぎる。 シーサー。シーサーは、沖縄県などでみられる伝説の獣の像。建物の門や屋根、村落の高台などに据え付けられる。家や人、村に災いをもたらす悪霊を追い払う魔除けの意味を持ち、屋根の上に設置されるケースが多いとされる。
2015.06.25
コメント(0)
-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 1日目(ひめゆりの塔、平和祈念公園へ)
さらに車を進め、『ひめゆりの塔』 を訪ねる。ひめゆりの塔は、沖縄戦末期に沖縄陸軍病院第三外科が置かれた壕の跡に立つひめゆり学徒隊を祀った慰霊碑。ひめゆりの塔の記。この石碑はひめゆりの塔の入口に建立されていた。二十歳にも満たない多くの尊い命が戦場に散ったのだ。『合掌』。「ひめゆり」は学徒隊員の母校、沖縄県立第一高等女学校の校誌名「乙姫」と沖縄師範学校女子部の校誌名「白百合」とを組み合わせた言葉で、もとは「姫百合」であったが、戦後ひらがなで記載されるようになったのだ。「塔」と名はついているが、実物は高さは1メートルにも満たない。これは、終戦直後の物資難な時代に建立された事と、アメリカ軍統治下に建立されたという事情によるものであるとのこと。 写真の一番右にあるのが『ひめゆりの塔』。第三外科壕跡と慰霊碑(納骨堂)。慰霊塔の前に穴があいている洞窟が沖縄陸軍病院第三外科壕跡。洞窟や壕のことを沖縄の方言で「ガマ」と呼ばれている。ひめゆりの塔が建っているガマ(写真中央の穴)には当時、ひめゆり学徒を含む病院関係者や住人などおよそ100名がいたと。解散命令後の6月19日に米軍のガス弾攻撃を受けて80人余りが亡くなられたのだと。 ひめゆり平和祈念資料館。資料館内には、第三外科壕を底から見上げた形で原寸大のジオラマが作られている。また、同じく館内には南風原陸軍病院壕の一部を再現した原寸大模型があり、そこで以前は語り部の証言を直接聴くことができたが、語り部の方の高齢化により、2004年4月のリニューアル以後は証言映像の上映に切り替えられた。第四展示室は学徒隊の亡くなられた生徒や教員の写真が壁中に貼られており、また、生前の人柄や亡くなった時の状況が文章で解説されている。今回は入館せず。仲宗根正善先生の哀悼の歌『いはまくら碑』『いわまくら碑』は、学徒隊引率教師であった仲宗根政善氏が、第1回ひめゆりの塔慰霊祭(1946年4月7日)で、戦死した教え子を悼み霊前に捧げた歌の碑。 いはまくら かたくもあらん やすらかに ねむれぞといのる まなびのともは 『固いごつごつとした岩場で亡くなったのはさぞ無念で辛かったでしょう。心安らかに眠って欲しいと学友たちは願っています。』という哀悼の歌(現地案内板から)。ひめゆりの塔前の道路沿いには多くの土産物屋が並んでいた。 平和祈念公園に向かう。平和祈念公園は本島南部の「沖縄戦終焉の地」糸満市摩文仁の丘陵を南に望み、南東側に険しく美しい海岸線を眺望できるのであった。前方に沖縄平和祈念堂が見えて来た。高さ45m、七角形の堂塔。第二次世界大戦で最後の激戦地となった沖縄は、軍民合わせて約24万人余もの尊い人命を失った。この悲惨な戦争を二度と繰り返さぬよう世界の人種や国家、思想や宗教のすべてを超越した“世界平和のメッカ”として昭和53年10月1日、この平和祈念堂は開堂。堂内に安置されている高さ12mの平和祈念像は沖縄の人々あるいは全人類の平和のシンボル。6月23日の「慰霊の日」の戦後70年 沖縄全戦没者追悼式(沖縄県主催)開催の準備が行われていた。式典会場入り口と書かれたの大きな表示板。金属探知検査を行う模様。ドローン飛行禁止の文字も。 多くのテントが既に設営されていた。 平和祈念公園内の池。ここ平和祈念公園ではことさら別の意味を持つのだと。戦争中、傷付き倒れ戦没された方々は水を求めながら亡くなったと。この場所に池を設け水を湛えることは戦没者の慰霊の意と。沖縄戦で亡くなった人々の名前が人種、民族、敵・味方に関係なく刻まれた記念碑 「平和の礎」 。 その氏名の数は実に約24万人。 現在も刻銘は続いていると。 神奈川県出身の戦没者の礎。 外国人の名も。ここには、日本人だけでなく、朝鮮人やアジアの人々、そして欧米人も含め、名前が判明している沖縄戦犠牲者のすべてが記録されているのであった。「平和の礎」内にある広場の中央には「平和の火」が灯されていた。円錐形に造られた 「平和の火」 は池の地図上で沖縄の位置に建っているのであった。「平和の火」は、沖縄戦最初の米軍の上陸地である座間味村阿嘉島において採取した火と被爆地広島市の「平和の灯」及び長崎市の「誓いの火」から分けていただいた火を合火し、1991年から灯し続けた火を1995年6月23日の「慰霊の日」にここに移し、灯したもの。 平和祈念公園の海岸。青い海が広がるそして太平洋を望む断崖絶壁の絶景。「平和の火」から「平和の礎」を望む。 沖縄県平和祈念資料館。悲惨な沖縄戦の実相及び教訓を後世に正しく継承するとともに、平和創造のための学習、研究及び教育の拠点施設。 沖縄平和祈念公園モニュメント。 このモニュメントの前の広場で式典などが行われるのです。見学を終え駐車場に向かう。
2015.06.24
コメント(0)
-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 1日目(平和の塔、魂魄之塔へ)
喜屋武岬にある『平和の塔』 を目指す。カーナビの地図で目的場所を指定し進んだが、近くに来ると新たな道が工事中でありややカーナビも道に迷ったがなんとか辿り着く。ここを訪れるのは2回目。屋武岬は「観光地」として整備されているわけではなく、小さなトイレと休憩所はあるものの、売店などは一切無く「見はらし台」があるのみ。曲線でデザインされている美しい慰霊碑。円、球は平和への願いの象徴とのこと。海そして空の青さにこの日も感動。沖縄最南部の荒崎が見えた。海岸一帯は隆起サンゴ礁(琉球石灰岩)から成り、高さ約7mの海岸段丘崖が東西に形成されていた。右側の具志川城跡方面の海岸線。 少し下に目を移すと、そこは断崖絶壁。写真では解り難いがかなりの高さ。 この付近一帯は沖縄戦の激戦地で、太平洋戦争末期に、アメリカ軍に追いつめられ、行き場を失った人々が極まって身を投げた悲劇の地。そこに、平和の塔が建立され、恒久平和と鎮魂の思いが込められています。この平和の塔は、 沖縄戦終結前の6月20日に亡くなった第62師団の将兵の方々を悼んで昭和27年に建てられたと。現在でも自殺の多い場所なのであろうか。『いのちをたいせつに』の文字が。喜屋武崎灯台。この灯台は、戦後現在地の東方およそ120mの所にアメリカ軍によって設置された荒埼灯台を前身とし、施政権返還後の1972年(昭和47)6月22日に設置、初点灯されたとのこと。 灯塔高は14.91m。 次に向かったのは『魂魄之塔』 。糸満市米須部落の南方300mの海岸よりにある。ここは沖縄戦最後の激戦区であり、日本軍も住民も米軍に追い詰められて逃げ場が無く、陸海空からの激しい攻撃を受けて倒れた者が数多い。敗戦後、米須は真和志村民が移動収容されたところであった。この旧真和志村民が米軍の許可を得、遺骨収集班を結成して道路や畑、丘や森に散っていた遺骨を集め納骨堂を完成して祀ったのがこの『魂魄の塔』。魂魄の塔そばには、いくつかの県の慰霊塔がある。これは、讃岐の塔。香川では奉公さんという人形があるらしい。側仕えしていたお姫様が病気になり、自分にうつして身代わりに亡くなった事から、奉公さんと言われて人形として伝わっていると。ひろしまの塔。 子供達が太陽に向かって,永遠の平和を祈り、英霊の魂が金色の鳥となり,空高く昇天する情景を表現したと。 奈良 大和の塔。モチーフは百万塔。 北海道の塔。沖縄戦では北海道出身者が沖縄を除く全都道府県で最も多い犠牲者を出したのだと。また、この塔は全都道府県で最初に建立された塔。遠く寒さ厳しい北海道から、ここまで来るだけでも大変な思いだったはず。 「ひめゆりの塔」建立の中心にもなった金城和信(きんじょうわしん)。戦前は沖縄県の小学校長などを歴任、真和志村村長(沖縄戦で2人の愛娘を戦死させた村長夫婦は、旧陸軍第3外科壕周辺の遺骨を収集し、1946年4月5日に「ひめゆりの塔」を、また、同年4月9日に男子学生を祀る「健児の塔」を建立。そして住民と協力して周辺に散らばった遺骨を収集し、魂魄の塔の建立に貢献 したと。これが魂魄の塔。 納骨所は米軍提供のセメントや古寝台の鉄骨を使い周囲から石を積み上げて作ったという。その後も集骨作業は続けられ、やがて35,000余名を納める最大の慰霊塔となった。遺骨は1975年1月戦没者中央納骨所へ納骨され、さらに79年、国立戦没者墓苑に移された。中央上部には『魂魄』と刻まれた碑が。 魂魄(こんぱく)とは、「魂」は「たましい」、「魄」は浮遊霊の意味。戦後最初に沖縄で作られた慰霊碑。沖縄で最大の慰霊塔。 和歌山県の紀伊國之塔。奇しくも今日、6月23日は、太平洋戦争末期の沖縄戦で組織的戦闘が終わったとされる日。沖縄県糸満市摩文仁(まぶに)の平和祈念公園で、沖縄全戦没者追悼式が開かれた。翁長雄志(おながたけし)知事は平和宣言で、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設問題をめぐり、安倍政権の姿勢を真っ向から批判。平和を祈る戦後70年の式典は、政権と沖縄県の溝を映し出した異例の展開となった。追悼式には安倍晋三首相や衆参両院議長、キャロライン・ケネディ駐日米国大使らも参列し、1分間の黙禱(もくとう)を捧げたのであった。
2015.06.23
コメント(0)
-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 1日目(旧海軍司令部壕へ)
空港からレンタカー会社の送迎バスにのる。そしてレンタカー営業所で手続きを完了し市内観光に出発。今夏のレンタカーの運転担当は私。カーナビをセットし「旧海軍司令部壕」へ。10分ほど走ると駐車場に到着。1944年、日本海軍設営隊によって沖縄県豊見城市と那覇市の市境に掘られた壕で、当時は450mあったと言われている。カマボコ型に掘った横穴をコンクリートと杭木で固めてある。この防空壕は沖縄戦において大日本帝国海軍の司令部として使用されたのだと。駐車場横にある松尾家の巨大な墓。石碑には「松尾門中之墓」と刻んであった。「門中(もんちゅう、琉球方言:ムンチュー)は、沖縄県における、始祖を同じくする父系の血縁集団のこと。高台にある駐車場からの那覇市内、青き太平洋の眺め。海軍戦没者慰霊之塔。昭和33年、沖縄海友会ならびに海軍戦没者慰霊之塔建立発起人会によって建立。公園内にある仁愛の碑。自決前に太田少将が海軍次官宛に発信した電文が記載されていると。太田少将の沖縄県民への思いが書かれていると。沖縄戦の参加部隊名、参加艦艇の刻まれた碑。海軍壕公園ビジターセンターは旧海軍司令部壕への受付と入口となっており、館内には沖縄戦当時の多くの遺留品や写真などが展示されていた。ビジターセンタ内の展示品。日本唯一の地上戦・沖縄戦の旧海軍指令部壕・沖縄戦の軌跡が説明されていた。沖縄戦は太平洋戦争末期の1945年3月26日から9月23日の6ヶ月間に渡って沖縄県で繰り広げられた日本軍とアメリカ軍の間で勃発したのだ。3月26日早朝、アメリカ軍は沖縄進攻作戦「アイスバーグ上陸作戦」計画に基づき、沖縄島上陸前に慶良間諸島の上陸作戦を展開。そして4月1日、早朝からアメリカ軍機は北、中飛行場方面に対地攻撃を加え、07:00頃から熾烈な艦砲射撃を開始。08:30頃から米軍の上陸用舟艇が嘉手納海岸に達着して上陸を開始したのだと。旧海軍司令部壕見取図。米軍の艦砲射撃に耐え、持久戦を続けるための地下陣地で、4000人の兵士を収容。戦後しばらく放置されていたが、数回に渡る遺骨収集の後、昭和45年(1970年)3月、観光開発事業団によって司令官室を中心に300mが復元されたのだと。券売所や売店の有る建物を裏に抜けると、司令部壕の入口が有った。壕入り口階段。105段、30mほどの階段を降りると、通路が縦横に張り巡らせた壕内へと続く。20m深さの所に分岐が。壕内見取り図および順路図。作戦室。 幕僚室。幕僚が手榴弾で自決したときの破片の跡が残っていた。更に壕の奥へ進む。薄暗い通路が無数に張り巡らされ、迷路のようになっていた。左側に医療室。医療室には当時のこの部屋の様子が描かれた説明図が。発電室。大田司令官が海軍次官宛に発信した電文。(沖縄県民 かく 戦えり の電文)結末の電文では、『沖縄の実情は、言葉では形容のしようもありません。一本の木、一本の草さえ全てが焼けてしまい、食べ物も6月いっぱいを支えるだけということです。沖縄県民はこのように戦いました。県民に対して、後世特別のご配慮をしてくださいますように』と。下士官室。玉砕の近い6月ごろ、この部屋は立錐の余地もない程兵士たちが入り、立ったままで睡眠や休息を取ったと。司令官室。 室内には「神州不滅」の額が掛かっており、太田指令官外8名の幕僚の最期の場所。太田司令官の辞世の句 である、「大君の御はたのもとにししてこそ 人と生まれし甲斐でありけり」が残されていた。部屋の隅には供養の仏像が安置されていた。壕内分岐点。当時の米軍の進軍の様子を示すパネル。米軍上陸全般図。沖縄戦の写真パネルも掲示されていた。壕出口の外装は綺麗に修復されていた。沖縄の最初の訪問としては『重い』場所であったが、平成という時代に平和なこの沖縄を楽しませてもらっている一方、この様な厳しい時代がそして惨劇が現実としてあったことも日本国民として決して忘れてはならないと、今更ながら思ったのであった。そして『合掌』。
2015.06.22
コメント(0)
-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 1日目(那覇空港へ)
旅友と2泊3日の沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅に行って来ました。折りしも70年前の「国内唯一の地上戦」とも言える沖縄戦は、1945年3月26日から始まり、主要な戦闘は沖縄本島で行われ、組織的な戦闘は6月20日前後に終了したのであった。この旅行ではその激戦の地も訪れたいのであった。旅友が知り合いの旅行会社に格安ツアーのアレンジをお願いし往復ANA飛行機、朝食付きホテル2泊、3日間のレンタカー代全て込みで42000円のツアーとなりました。出発便はANA471便 11:05発。利用したANA便。 ボーイング777-200は306席。進行方向右側のK席を確保。 定刻に出発そして離陸。東京湾上空を旋回し、太平洋上を沖縄にむかう。眼下に横浜・八景島シーパラダイスが。 そして見慣れた造船所も眼下に。 三浦半島を横断し相模湾に出る頃には残念ながら雲の上に。 そしてソフトドリンクを飲み、ウトウトとそして爆睡。気がつくと既に奄美大島名瀬上空か?遠く硫黄鳥島(いおうとりしま)が見えた。 沖縄県における最北端の島で、同県に属する唯一の活火山島。14世紀後半から明王朝へ進貢する硫黄の産地として知られ、琉球王国が滅亡する19世紀中頃まで、琉球と明・清朝の朝貢関係を繋ぐ重要な島。1903年の久米島移住後も硫黄採掘が行われたが、1959年の噴火により住民は島外へ移住、それ以降は完全な無人島となった島。粟国島(あぐにじま)。那覇市の北西約60kmに位置し、産業は主に農業と漁業で、近年では製塩業も有名。那覇空港より不定期運行、美しい慶良間諸島を眼下に20分で到着できると。 遠く渡嘉敷島、そして手前に前島その前に珊瑚礁の浅瀬が。那覇空港に定刻に到着。航空自衛隊、海上自衛隊、陸上自衛隊の航空機を主体する部隊が那覇空港飛行場内に。航空自衛隊捜索救難機が停留中。航空自衛隊 救難ヘリコプター。こちらは海上自衛隊の文字が。 三菱重工業が国内製造した多くのF-15J Eagle戦闘機が。那覇空港 管制塔。6月初めに、この那覇空港で自衛隊ヘリが上空を横切り、離陸しようとしていた全日空機が滑走路で緊急逆噴射で停止し回避したというNEWSを思い出したのであった。 那覇空港の文字が。 「めんそーれ」 の文字が。WELCOMEの意。出口に向かう。 那覇空港内にはミニ水族館。沖縄旅行気分を盛り上げてくれました。
2015.06.21
コメント(0)
-

胡蝶蘭
36年前に、我々の結婚の仲人をお願いした方から1ヶ月ほど前に電話があり育てている胡蝶蘭が蕾を持ったので下さると。早速、車で頂きに行き、いただいて帰りました。そして玄関横で水を定期的にやりながら育てました。そして見事に開花しました。花の色は咲いてのお楽しみ とのことでしたが純白。胡蝶蘭の中でも、特に「白」が多いのは、白い花はどんなシチュエーションにもぴったり合い、周りの雰囲気を壊さず、なおかつ花としての存在感があるからと。また、白の品種改良が一番進んでいるので、同じ花の数でも他の色と比べると大きく、花のもちも一番良いところがあると、我が家の近くにあるわいわい市の店員から以前に。名前のとおり、蝶が羽を広げた様な蘭。ちょっと透明感のある白い胡蝶蘭。胡蝶蘭は長く花を楽しめます。一般的には、半分ほど枯れてきたら、花茎を根元から切り落とし切花にして楽しむのが株には理想的とのことですが・・・・。胡蝶蘭は花が散ってしまっても、きちんと手当をしてあげれば、何度でも茎が伸びてきて、花を楽しむことができる生命力の強い植物だということも解っているのですが・・・・・。何度かTRYしましたが、なかなかうまくいかないのです。だからこそ高価なのですが。
2015.06.20
コメント(0)
-

ナンテン(南天)の花
我が家の裏に植えてあるナンテンの木が白い小さな花をつけています。音が「難を転ずる」に通ずることから、縁起の良い木とされ、鬼門または裏鬼門に植えると良いなどという俗信がある木なのです。 真っ赤な果実が美しく、さほど横に広がらないので場所を取らず、性質が丈夫と言うこともあり、縁起木として玄関先や庭によく植えられる定番の実もの庭木のひとつ。梅雨のこの時期を選んだかのように満開のナンテンの花。正月の生け花や出産祝いのお赤飯などの上に葉を添え、毒消しがわりの縁起木として昔から珍重されてきました。 梅雨空に白い米粒のような花が映えていました。太いオシベが真ん中にそして黄色いメシベが6本。 既に散り、雨にぬれた地面に白く点々と。
2015.06.19
コメント(0)
-
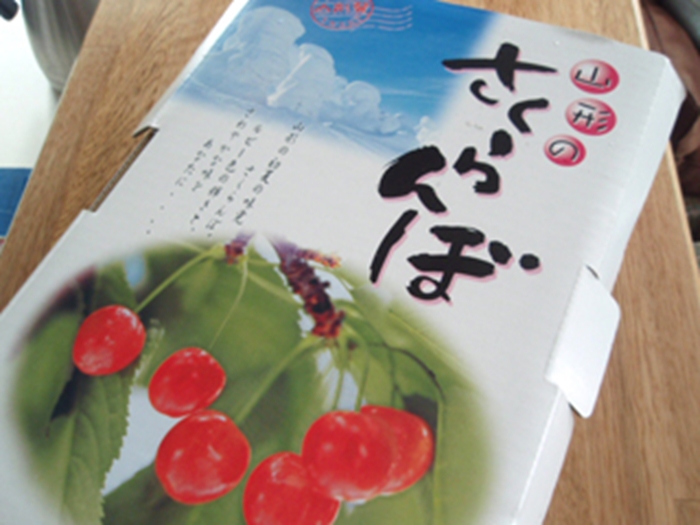
サクランボ
嫁いだ娘夫婦が、先日我が家にサクランボを送ってくれました。妻の誕生祝と父の日を兼ねているとの事。 箱を開けると、ピンクのスポンジで覆われていました。そしてその下には、 鮮やかなルビー色に輝くその果実が。果樹園の宝石ともいわれるさくらんぼ「佐藤錦」。まさにキラキラ輝く赤い宝石。 まん丸で、果肉は乳白色。甘みが多く、果皮が厚くて、ぷりぷりとした張りがあったのです。生産者の方のメッセージも添えられていました。 濃密な甘さが醸しだす、ほとばしるような果汁の美味しさを「やめられないとまらない」 で楽しんだのでした。
2015.06.18
コメント(0)
-

キンシバイ(金糸梅)と我がミツバチ
我が家の玄関横のキンシバイ(金糸梅)が黄色い花をつけています。花の形が良く梅に似ており、色が黄色であることが名前の由来。庭木や地覆い用植え込みとして、我が家の近くのお宅にもやや花の形は異なりますが色々な種類が植えられています。いっぱいある黄色のおしべを「金の糸」に、5弁の花を「梅」にたとえたのです。そして近くに寄ると、ブンブンと羽音が。多くの我が?ミツバチが訪花していました。脚には大きな花粉玉をつけていました。ミツバチが花粉を集める植物を蜜源植物といい、セイヨウミツバチではレンゲやアカシアなどが有名。このキンシバイもミツバチの大切な蜜源植物。そして早朝の梅雨に、花も少し濡れている様子。よって蜜蜂も少し濡れていたようなので花粉が良く付くようです。体中花粉だらけになっていました。こちらは我が?西洋ミツバチではなさそうです。日本ミツバチ?大小の昆虫が花と戯れていたのでした。
2015.06.17
コメント(0)
-

関空から我が家への帰路
関西国際空港内での仕事を終え、関空から羽田空港への帰路。 2階が国内線の出発ターミナル。 遠く生駒山系の山々を背景に連絡橋そして宿泊したスターゲイトホテル関西エアポートが見えた。関西国際空港連絡橋は、大阪府泉佐野市のりんくうタウンと関西国際空港島を結ぶ、橋長3,750mの世界最長のトラス橋。関西国際空港島の唯一の陸上アクセスを担い、スカイゲートブリッジRの愛称が付けられている。料金は普通車で片道800円とのこと。 この日の便はスターフライヤーのANAコードシェア便。 「瞬時に認知できる」コーポレートカラーとして黒を選択したのだと。離陸後しばらくして大きく旋回後に眼下に再び連絡橋が。 そしてこの日は雲の上の飛行が続く。 房総半島の鴨川市江見上空。 千葉県富津市のメガソーラー発電所が眼下に。富津の東京湾工業地帯。右側には新富運河が見えた。 富津岬上空を通過。 富津市にある東京電力(株)富津火力発電所・新日鐵住金君津製鉄所。 そして大きく旋回し眼下に東京湾アクアラインが。 木更津人工島海ほたる風の塔。風の塔は、川崎市浮島の沖合約5kmに作られた直径約200m、深さ75mの人工島。風の塔の上には、高さ90mと75mの大小2つの塔がそびえている。これらは東京湾横断道路のトンネル内部の空気を排気したり、外から空気を送気したりするための施設。そして定刻に羽田空港に到着。 バスにて首都高速湾岸線で自宅に向かう。 左手に川崎マリエンが。正式名称は川崎市港湾振興会館。愛称の「マリエン」とは、マリン(海)とエントランス(玄関)から成る造語。その名の示す通り、世界に広がる海の玄関をイメージした凱旋門型のユニークな外観が印象的。 バスの前方両サイドに巨大なタンクが見えた。 JFE東日本製鐵所。 鶴見つばさ橋を通過。 大黒ふ頭。 大黒JCT。 横浜ベイブリッジを通過。 日本有数の国際貿易港、横浜港にある本牧埠頭。 横浜マリンタワーが見えて来た。 そしてバスを降り私鉄に乗り換え帰宅。青森・五所川原⇒兵庫県・柏原⇒関西空港での3泊4日の仕事を終えたのであった。
2015.06.16
コメント(0)
-

関西国際空港へ
この日は関西国際空港内にある我が社の関係会社と打ち合わせの日。宿泊したホテルはスターゲイトホテル関西エアポート。その高さは圧倒的、54階、256m 。低層階はロビーや宴会場・会議場など諸施設、28階に屋外チャペル、29〜50階までが客室、52〜54階はレストラン・バー・宴会場となっている。ホテル以外の8〜27階は「りんくうゲートタワービル」としての各企業や団体が入居する賃貸オフィスとなっているとのこと。この日の早朝散歩は関西国際空港内の散策。早めにチェックアウトし、荷物を持ってりんくうタウン駅に向かう。 JR関西空港線と南海空港線が乗入れる「りんくうタウン駅」この日はJRにて関西空港に向かう。 先頭車両から連絡橋の姿を撮影。 大阪方面側の連絡橋。メンテ用の階段も見えた。 関西空港に到着し、Terminal 1に向かう。 Terminal 1入り口。関西空港は第1ターミナルビルと第2ターミナルビルに別れている。4階が国際線出発、2階が国内線の出発・到着、1階が国際線到着となっていて、利用者が垂直方向の移動だけで国内線と国際線を乗り継ぎできるサンドイッチ構造が採用されている。エスカレータで3階に上がる。コインロッカーに荷物を預け、散策開始。屋根は、飛行機の翼をイメージした緩やかな円弧状のカーブを描く独特の形となっており、効率的に空調による風を館内に回すようになっている。天井内側に張られたテントは、空調の風を受け止めて流す役目と、下のライトからの照明を照り返して間接照明をする役目を果たしているとのこと。 流線型の屋根の下で舞うフライングモビールは、翼を持った生き物の如し。テントに写った影も美しかった。 4階が国際線出発。多くの航空会社のチェックインカウンターが。以前利用した記憶によると、4階でチェックインの後、手荷物検査を受け、3階の税関・出国審査を経て出国エリア(トランジットエリア)へと進むのでは。 関西空港の見所はやはり柱のない屋根。最上階のタクシー乗り場から関西国際空港の管制塔を見る。高さ約80mあり、空港島のほぼ中央に設置されています。 支柱、屋根のトラス構造。 トラスの壁貫通部は不等沈下対策が。 支柱付け根部分も沈下対策? 再び3階のレストラン・ショップエリアに向かう。日本のお土産の数々。 豊かな海づくりのために空港島周辺護岸で育成している藻場や、リサイクルによる水・エネルギーの再利用などを、パネル展示で紹介。 関西国際空港内に計約11,600キロワットの発電出力を持つ大規模太陽光発電施設(メガソーラー)「KIXメガソーラー」事業のパネル。 滑走路脇の約1・2キロメートルにわたる遊休地や貨物倉庫の屋根などに、太陽光の反射が航空機の運航に影響を与えない特性を持つ太陽光パネル約7万3千枚を設置。年間電力量は一般住宅の約4100世帯分に相当する約1200万キロワット時の発電量とのこと。 空港の航空写真パネルも展示されていた。 連絡橋の繋がる側がA滑走路:3500m、下側がB滑走路:国内最長の4000m。当然現在就航中の航空機全ての離発着が可能。第2ターミナルはB滑走路側にある。ホテル日航関西空港。関西国際空港島内唯一のホテル。関西国際空港旅客ターミナル及び鉄道駅とコンコースで直結されている。 関西国際空港第一ターミナル2階からコンコースが渡されていて、コンコースの真ん中は徒歩で、両サイドには動く歩道が設置されていた。コンコースからの関空連絡橋方面。ホテル日航関西空港の中で同僚の迎えを待つ。そして同僚の車に乗り、セキュリティーゲートで手続きを完了し空港内部の関係会社へ。
2015.06.15
コメント(0)
-

兵庫県丹波市柏原町へ
宝塚駅から「こうのとり号」に乗車。こうのとりは、新大阪駅⇔福知山駅・豊岡駅・城崎温泉駅間を東海道本線⇔福知山線(JR宝塚線)⇔山陰本線経由で運行する特急列車。「かしわばら」「かしわら」ではなく「かいばら」駅で下車。JR柏原駅舎。個性的な駅舎。1990年に大阪で開かれた、“国際花と緑の博覧会”の会場内アクセス路線として運行されていた『ドリームエキスプレス』の「山の駅」を移築した駅舎とのこと。なるほど山小屋風。駅前の田捨女(でんすてじょ)の像。田捨女は1634年、丹波国氷上郡柏原藩(現在の兵庫県丹波市柏原地域、当時の藩主は織田信勝)に、柏原藩の庄屋で代官も務めた田季繁の娘として誕生した。6歳のとき『雪の朝 二の字二の字の 下駄の跡』という俳句を詠み、周囲にその才を認められた江戸時代の女流歌人・俳人。『城下町 かいばら』の表示が。柏原藩は織田信長の弟、信包から始まったが3代で断絶。その後柏原はしばらく天領となっていたが、信長の次男、信雄の子孫がここに国を移され明治まで10代続いたのだと。前期柏原藩で3万6千石、後期柏原藩で2万石と小藩であったが国指定の柏原藩陣屋跡や長屋門、太鼓やぐらなど当時の歴史遺産が随所にあり、城下町の姿を良く残しているのだと。氷上市内での仕事を追え、往路と同じ特急電車を利用すべく柏原駅に戻る。特急列車まで時間があったので、城下町を車で散策。かいばら観光案内図。太鼓櫓明治初期に移築された櫓。説明板によれば、かつては大手通りにあったようだ。名前の通り、時報として使用。江戸時代に建てられたものなので、貴重な遺構。3階建ての櫓で、最上階には“つつじ太鼓”という大太鼓があるらしい。丹波市の公式ガイドによれば、建立の時期、移築の時期、何れも詳しい記録は残っていないとある。時の太鼓櫓と厠(トイレ)。ここは、やぐら公園という場所。案内板によれば、商店街活性のため、太鼓櫓を模したハイテクの“時打ちロボット”を街の玄関口に設置した、とある。定時ごとに“丹波のあした”というメロディが流れながら、人形が太鼓を打つらしい。からくり時計か? 丹波市役所柏原支所。木の根橋の隣に建つ洋館。旧柏原町の役場として昭和10年に建てられたらしい。ケヤキの木の根が太く成長し、川をまたいでいることから「木の根橋」。樹齢1000年とも推定される巨木で、目通り幹径6m、樹高21m、枝張各25mを測る丹波市内では最大のケヤキ。本樹の根の一本が太く成長し、直下を流れる奥村川をまたいで対岸の地下にもぐり込み、長さ10mにも及ぶ自然の橋梁を形づくっていることから「木の根橋」と称されているとのこと。帰路も『こうのとり号』で大阪駅へ。加古川沿いを走る。のどかな水田地帯を走る。 道場駅近くの、工事が進む新名神「武庫川橋」 そして宝塚駅。 神埼川を渡る。 そして大阪駅に到着し、関空快速にのりかえこの日のホテルのある「りんくうタウン」駅へ。ホテルは「スターゲイトホテル関西エアポート」。以前は全日空ゲートタワーホテルと呼ばれていたが、いつの間にか・・・・・・。ホテルフロント前。1Fの天井&シャンデリア。 我が部屋のある37Fからの眺め。和歌山方面。 手前に高さ85mの大観覧車「りんくうの星」。そしてその向こうにりんくう公園マーブルビーチ。そして我が部屋からの大阪方面。阪神高速4号湾岸線の海側は全て埋立地であることが解る。手前にいずみさの関空マリーナが。そして遠く神戸・六甲の山並みも。
2015.06.14
コメント(0)
-

50万回突破
昨日6月12日(金)の朝7:40過ぎにブログにアクセスするとアクセス回数「499860」 の表示が。アクセス回数50万回も直前。2008年04月10日のブログ開始から2619日。 そして昼休みに再びアクセスしてみると既に「500107」 の表示が。祝!!50万回達成。これからも「つれづれなるままに、ひぐらしパソコンに向かひて、心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。 」で、つれづれなるままに我がブログを、備忘録として続けて行きたいと思っているのです。
2015.06.13
コメント(0)
-

青森空港から大阪伊丹空港へ
青森空港から大阪・伊丹空港へ移動しました。この日は雨の青森空港。 利用便はプロペラ機の通称ボンバルディア “ダッシュ 8”(Dash 8)。機内は片側2列74座席。 2000年に運用が開始され、胴体延長及び74座席に性能向上したバージョン。 車輪、タイヤを点検する地上スタッフ。 型式の正式名称は「DHC8-Q400」 。通称Q400ですが、Qは“Quiet"の頭文字。名前の通り静かな飛行機。プロペラだと風を切る際に気流を乱し音がが大きいのですが、ボンQは気にならなかったのです。機内CAがボンQの写真をくれました。 日本では2003年に日本エアコミューターが運航を開始、その後ANAウイングスも運航を開始したとのこと。 離陸後は一面の雲の世界。 そして機窓からの夕焼けを楽しむ。 雲の切れ間から赤く染まった水田の水面が。 暫くは夕焼けの色と雲の変化を楽しむ。 飛行機で夕日を追いかけるという体験。 そして日没の時間に。 沸き立つ雲の先端が筋の様に輝いていた。 赤の色合いが刻々と変化していくのであった。 飛行機の直下には雪の残った山が。 そして日没に。 だんだん暗くなっていく光景を楽しむ。 朱の世界。夏の夕闇がにわかに濃く迫ってくるそして大阪上空に。 光り輝く街並み。そしてここから着陸態勢に。 伊丹空港に無事着陸し、空港近くのホテルに送迎バスで向かったのであった。
2015.06.12
コメント(0)
-

五所川原 みどり亭
五所川原での昼食は、協力会社の社長ご夫妻が予約してくれた「みどり亭」 へ。この日は予約で一杯であったが、みどり亭の御主人が無理を聞いてくださったのでした。車で20分ほどで到着。目の前に見るからに古い2階建ての趣のある日本家屋が。入り口のこれも古き歴史を感じる木製の門が。城の大手門の如し。 広い庭には様々なルピナスの花が満開中。苗を育て植えたのであろうか?それとも自然に?数年前、北欧を旅行した折、ルピナスの花が道路わき一面に雑草の如く咲き乱れていたのを想い出したのであった。ルピナスは耐寒性の強いマメ科の植物であるので冬を越せるのであろうか。「みどり亭」 玄関口。築120年以上の建物とのこと。中に入ると、見事な龍の水墨画と今年の立佞武多(たちねぷた)のポスターが。 そして「登録有形文化財」 の証が。ここ阿部家の住宅主屋と文庫蔵が平成26年4月25日に文化財として指定されたと。通称「大阿部」と呼ばれている羽野木沢の阿部家は元和3(1617)年から続く五所川原地方の大地主とのこと。現在も阿部家の方々が居住しており、食事処「みどり亭」来客者にのみ住宅の一部を公開しているとのこと。庭の緑も美しかったが豪雪地帯での管理が大変なのであろう。 京都の名刹を訪ねている気分に。壁には、この4月に旅したモロッコの街を想い出される風景の絵画が。 2Fに上がらせていただく。 2Fには「床の間」付きの和室4部屋と洋間1部屋、そして西と東に広い屋根裏部屋があるようであった2F和室からの前庭の姿。 「羽阿部」 の文字と家紋?の暖簾が。「丸に三つ柏」に似ているが?羽は羽野木沢の意か?なんでも鑑定団に出したい水墨画屏風。 我が母校の校歌が達筆で書かれた額縁入りで。 どなたか阿部家の縁者が私の先輩?そして暫く待つと、注文した天ざるが。 山盛りの天ざる。やや太めの蕎麦はコシがあり、ボリュームたっぷりで美味しく食べ応えがあったのですそして粒餡入りの「そばがき汁粉」も楽しみました。じっくり煮詰められた極端に甘くない小豆に、大きな塊のの「そばがき」が入っていました。「そばがき」を箸でちぎりながら小豆と一緒に口に運ぶと、落ち着いた甘さの中に蕎麦の香ばしさが際立ち、何ともいえないハーモニーを奏でてくれたのです。 主屋「ざしき」。大きな床の間が。 当主が貴族院議員時代に贈られた孫文からの書。「阿部先生 福寿 孫文」の文字が。辛亥革命を起こし、「中国革命の父」と呼ばれる孫文の書とのこと。阿部家のご先祖は幅広い交友関係をお持ちだったようです。現在の当主は17代目とのこと。床の間の掛け軸の富士山の絵。 欄間など瀟洒な細工が施されていた。 見事な竹林の姿が彫られた欄間。 棟方志功32才の富山時代の書と。第二次世界大戦末期の昭和20年4月から26年11月までの6年間、板画家棟方志功は、富山旧福光町に疎開していたとのことだが、その時は40歳を越えていたはずであるが?玄関の先の囲炉裏のある和室。 個人所有の国登録有形文化財で思わぬ昼食を楽しむことができたのであった。それにしても、およそ一万坪の広さという屋敷の大きさ、そして棟方志功や孫文の書にビックリ。そして雨の中、青森空港へ向かう途中の楠美家住宅を車から。楠美家住宅は津軽地方を代表する大型民家で、五所川原市有形文化財(建造物に指定され高野地区より狼野長根公園に移築して市内外の人々に公開しているのであった。 飛行機の時間もあり、この楠美家住宅には入らなかったが、阿部家邸宅と同様に多くの歴史ある書や絵画が鑑賞できるのであろう。次回はゆっくりとこの住宅に。
2015.06.11
コメント(0)
-

青森空港へ(その2)
窓の下に青く光る田沢湖の全景が。 田沢湖は、秋田県仙北市にある淡水湖。直径は約6kmの円形、最大深度は423.4mで、日本で最も深い湖であり、国内で19番目に広い湖沼。湖面標高は249mであるため、最深部の湖底は海面下174.4mということに。この深さゆえに、真冬でも湖面が凍り付くことはない。そして、深い湖水に差し込んだ太陽光は水深に応じて湖水を明るい翡翠色から濃い藍色にまで彩るといわれており、そのためか日本のバイカル湖と呼ばれていると。玉川ダムは放流中。一級河川・雄物川水系玉川に建設されたダム。白き水の落下が確認できた。湖の名は宝仙湖 上が玉川ダム湖を横断する橋が男神橋。下が宝仙湖の北西部の国道341号の湯渕橋。秋田焼山には残雪が。青森県黒石市にある大穴ダム。二庄内ダム。水田の中に突然巨大タンク群が。1基は建設中。青森市 野沢配水池。直径約44m、高さ約12m、貯水量10000m3。配水池は、給水区域の需要量に応じて適切な配水を行うために、水道水を一時貯えるタンク。八甲田山。青森県中央部にある火山群。海抜1584メートルの大岳を中心とする北群と海抜1516メートルの櫛ヶ峰を中心とする南群とから成る。青森湾に出る。眼下には下水処理場の八重田浄化センターが。 飛行機は青森湾上で旋回し青森空港を目指す。右手には津軽半島が。 合浦海水浴場と合浦公園が中央下に。 青森県観光物産館アスパムの三角形の建物が。 「AOMORI」の「A」をイメージした正三角形の建物であることは以前同僚から。地上15階、高さが76mある青森の情報基地。そして青森空港へ無事着陸し駐機場へ。 青森空港ターミナルビル。 レンタカーで五所川原に向かう。岩木山にもまだ残雪が。 見る場所で山頂の姿が微妙に変わって行く岩木山。標高は1,625 mで、青森県の最高峰。日本百名山および新日本百名山に選定されている。その山容から津軽富士とも呼ばれるほか、しばしば「お」をつけて「お岩木(山)」あるいは「お岩木様」とも呼ばれている。 150年程は静かにしている火山ではあるが・・・・・・。
2015.06.10
コメント(0)
-

青森空港へ(その1)
この日は再び青森・五所川原へ向かうため羽田空港へバスにて。晴天に恵まれバスの車窓からの風景を楽しむ。横浜マリンタワー。 みなとみらい21方面。 これから渡る横浜ベイブリッジ。 横浜ベイブリッジからみなとみらい21。残念ながらこの日は富士山は見えず。 扇島太陽光発電所。 パネル:我が家と同じ京セラ製、パネル枚数:約6万4000枚、発電出力:13,000kW羽田空港から青森空港への利用便はJAL。 羽田空港旧管制塔ビル。 定刻に離陸。上空から機窓からの風景を楽しむ。千葉県松戸市にある八柱霊園。面積は105ヘクタール(約1平方キロメートル)東京ドーム約20個分の面積に相当すると。周辺一帯は起伏に富んだ地形となっており、霊園も小高い丘とその谷間に造られている。なだらかな丘は芝生でおおわれ、谷間にはフランス風の幾何学模様の庭園が。海上自衛隊下総航空基地。 利根川湾曲部水面には大きなアオコの群落が。 霞ヶ浦上空へ。 国立研究開発法人土木研究所(通称「国総研」)の実験施設。延長6152mの試験走路も見えた。筑波山麓。 UDトラックス茂木試験場。 しばらく雲の上を飛行。そして宮城蔵王の刈田岳山頂の御釜が見えて来た。 御釜は噴火後の火口に水がたまってできた火口湖。エメラルドの水が輝く巨大な御釜。五色沼(ごしきぬま)とも呼ばれる。蔵王連峰の観光のハイライト。 新鶴子ダム(しんつるこダム)は山形県尾花沢市、一級河川・最上川水系丹生川に建設されたダム。高さ96メートルのロックフィルダム。ダムによって形成された人造湖は、平成湖(へいせいのみずうみ)と命名。 秋田県湯沢市の雄物川水系皆瀬川の皆瀬ダム湖。
2015.06.09
コメント(0)
-
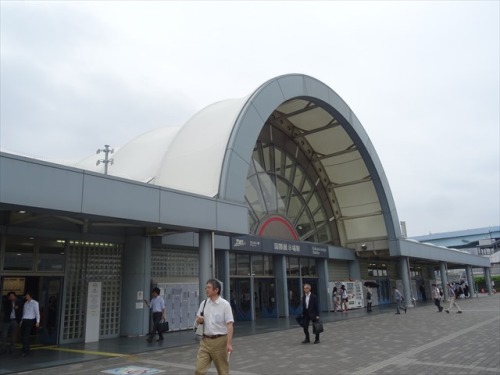
東京ビッグサイト(東京国際展示場)へ
先日、東京ビッグサイト(東京国際展示場)で行われている「環境展」 に行って来ました。大崎からりんかい線 で「国際展示場」駅で下車。駅舎は、幌馬車をイメージして作られており、屋根全体が白い膜で覆われています。左手には東京ベイ有明ワシントンホテルが。 イーストブロムナードを歩く。正面に東京ビッグサイト(東京国際展示場)が。 東京ビッグサイト(Tokyo Big Sight)の愛称で親しまれている日本最大のコンベンションセンター。会議棟は東・西展示棟をつなぐ中心施設。高層部は逆三角形の形態でシンボル的存在となっている。東京ベイ有明ワシントンホテルは藤田観光が運営するホテル・チェーン、「ワシントンホテル」のひとつであり、1999年(平成11年)に開業とのこと。 お台場海浜公園方面。 江東区青海にあるテレコムセンタービル。2つの塔は地下から地上5階と地上20、21階でつながっている。地上1-5階は各種イベントに対応できるアトリウム(多目的ホール)、地上21階には臨海副都心を一望できる展望台も設置されているそして右手奥にはパレットタウン大観覧車が。直径:100m/高さ:115m。東京ビッグサイト(Tokyo Big Sight)正面。巨大な逆三角形が連なった建物がトレードマーク。会議棟、西展示棟、東展示棟の3棟からなる、日本最大のコンベンションセンター。2020年東京オリンピック・パラリンピックの競技会場にも使用される予定。東京ビッグサイトへ向かうと右手下に、高さ15.5mの真赤で巨大な鋸(のこぎり)のオブジェが。『Saw, Sawing(切っている鋸)』と題したオブジェで、アメリカのポップアートを代表する作家クレス・オルデンバーグ氏の作品とのこと。斜めに配置された鋸はまるで地球を切り進んいるように見えたのです。この作品は”問題解決のプロセス”を表現しているとのこと。ゆりかもめの国際展示場前駅方面。 環境展の案内板。アジア最大級の環境イベント。入場者数は毎年15万人以上。環境展のホームページには『企業の社会的責任が問われる時代に入り、環境との共生を無視しては企業の存続すら危ぶまれる時代になりました。また持続可能な循環型社会の構築にむけ環境汚染問題や地球温暖化問題の解決は避けて通れない課題です。とりわけ資源有効利用や多様な新エネルギーの活用は、環境対策にとり最重要の取り組みです。そうした中、各種課題に対応する様々な環境技術・サービスを一同に展示情報発信する事により環境保全への啓発を行い、国民生活の安定と環境関連産業の発展を目的とします。』 と。ホール内に入ると売店の上に掲げられた巨大な熊手が。ビッグサイトは外国の人も結構来るので日本らしい飾りは好評「地球温暖化防止展」も併せて開催中。 「動く歩道」を利用し会場に向かったのであった。
2015.06.08
コメント(0)
-

我が家のサクランボ
我が家の横の菜園の隅に植えてあるサクランボが赤く実りました。昨年はパチンコ玉程度の大きさで落ちてしまいましたが、今年は初めて見事に実りました。品種は「佐藤錦」、苗を植えたのは5年以上?前。昨年、会社の同僚2名が我が家を訪れた折、手伝っていただき膨張ネットを樹木全体に掛けたのです。1個は網の間から新芽が伸びそこに実をつけていたため、ビニール袋で覆っておきました。良く見ると3個大きくなっており、この内の2個を収穫しました。早速妻と仲良く1粒ずつ味わいました。甘くこれぞ「初夏の味覚」だったのです。「赤い宝石」と呼ばれる自家製のサクランボを味わうことが出来たのです。
2015.06.07
コメント(0)
-

オオスズメバチ
先日、我が趣味の西洋ミツバチの内検を行いました。順調に群勢を強めて来ていました。ところが内検中に巨大なオオスズメバチが近くの巣箱の入り口近くでホバーリングしているのを発見。慌てて虫取り網を持ち出し、緊張しながら捕獲し長靴で踏みつけ殺しました。動かないのを再確認し、ゴム手袋で羽をつかみブロックの上に乗せ撮影。オオスズメバチは、体調も4~5センチほどありスズメバチ類の中では世界最大。オオスズメバチ(ミツバチ以外のハチ)は、女王蜂のみが越冬して、その他の働き蜂らは冬に死んでしまうのです。春になると女王蜂は、自ら小さな巣を作り数十匹の働き蜂を育てます。それが6月頃に成虫になって現れます。そして、その働き蜂たちが巣を大きく作っていくのです。女王蜂は、卵を産むことに専念します。オオスズメバチの食糧は、昆虫や動物などの肉とハチミツ(糖類)等です。西洋ミツバチも大好物なのです。越冬した女王蜂は、場所によっても違いますが5月上旬頃から巣作りを開始するようです。そして産卵を続け、6月中旬~7月になると働き蜂が生まれて来るようです。この初期の働き蜂は女王蜂1頭で営巣・餌集め・育児を行うため十分な栄養を摂りきれず、かなり小さいため、まるで親子ぐらい大きさが違うとのこと。このまま巣は拡大を続け、8月末から10月にオオスズメバチはピークを迎え我が西洋ミツバチの巣を襲ってくるのです。よって今回捕まえ殺したのは、成虫になった働き蜂ではなく、女王蜂の可能性が大なのです。その後オオスズメバチの飛来を確認していませんので女王蜂で間違いないのでは。女王蜂を失った集団では、働き蜂による産卵も行わますが、生まれるハチは全て雄で、巣は遠からず廃絶するのです。今年の晩夏から秋にオオスズメバチが来ないことを願っていますが、毎年多くの黄色スズメバチが来ますのでこちらの方は覚悟しなければなりません。
2015.06.06
コメント(1)
-

羽田空港の紫陽花(アジサイ)
「紫陽花」と書いて「アジサイ」。羽田空港国際線に紫陽花の季節がやってきました。その前の「藤棚」は撤去されて、梅雨の季節に向けて「紫陽花」の装飾に変わったと。国際線ターミナルの4階・江戸小路内の江戸舞台。日本の四季を感じさせる、涼しげな演出。紫陽花が生けてあるというより、鉢植えが置かれているのではと。水の管理も大変なのであろう。以下、様々な色の紫陽花、様々な種類の紫陽花の写真を撮りまくって来ましたのでお楽しみください。6から7月初旬にかけて見頃を迎えるあじさいは、梅雨や初夏を楽しむ風物詩。あじさいの花の由来は、和名の「あじさい」は集(あづ)・真藍(さあい)が変化したもの。集(あづ)は集まる、真藍(さあい)は青い花という意味。つまり、アジサイは「青い花が集まって咲いている」花の姿を表現した言葉と。「あじさい」は、江戸時代にオランダ商館の医師として日本に滞在していた、シーボルトのお気に入りの花。この地で運命の女性・お滝さんと出会い、イネという娘をもうけながら、国外追放の身となって最愛の人と引き裂かれたシーボルト。シーボルトは、大好きなあじさいに愛する人の名前から「オタクサ」と学名をつけ、ヨーロッパに紹介したのです。あじさいの花の色が”七変化”に変わっていくところから、「移り気」「浮気」「ほらふき」「変節」「無情」「冷淡」「高慢」といった花言葉が、あじさいには付けられているのです。関東以西は既に梅雨入り。うっとおしい梅雨の季節に、鮮やかな花を咲かせて、気分を晴れやかにしてくれる、人気のある花、紫陽花。小さい花がよりそって、一つの美を作り上げている紫陽花の花。日本人らしい、相手を想い寄り添う気持ちというのを、連想させるために日本人に愛される花。紫陽花の赤、青、紫と色づく部分は、実は花ではなくガク(萼)。紫陽花が根を張る土が酸性だとあじさいの青が濃くなり、アルカリ性だと赤が濃くなります。我が家の紫陽花は青が中心、これは土が酸性のためなのです。以下 紫陽花の花をズームで。 そして我が家の紫陽花です。 これから色ずく紫陽花も。がく紫陽花。「紫陽花」の言葉が似合います。
2015.06.05
コメント(0)
-

羽田空港 国際線ターミナル(その2)
3Fの航空会社のチェックインカウンターを見下ろす。お祭り広場。イベントの時だけに使用される空間のようで、普段は憩いの場となっていました。 祭り広場の一角に「願掛けコーナー」があり、沢山の願い事を書いたプレートが掛けられていました。しかし、この場所での願掛けの効果は如何に?? 日本に対する感謝の言葉も。展望デッキに出てみました。「Tokyo international Airport」 の文字が。広大な東京の風景を背景に、離発着する航空機が間近に見える広々とした展望デッキは、開放的で魅力的な空間。新旧の羽田空港管制塔。2010年に供用が開始されたD滑走路は、旧管制塔(背の低い左側の塔)からかなりの距離があるため発着する飛行機を視認しづらくなり、さらに高い管制塔が必要になったと。そこで同年、現在の新管制塔が完成。その高さは約115.7メートル。バンコク、クアラルンプールに次いで世界第3位の高さ。A〜Dの4本の滑走路を管制可能な、航空交通の安全を司る司令塔。遠くスカイツリーも見えました。 出発を待つANA787型機。離陸するANA機。 土産物のにぎり寿司の蝋細工。 外国人が土産に買っていく人気商品。見事な作品そして旨そう。こちらは醤油絵皿。醤油を注ぐと見事な姿が浮かび上がってくるのです。 醤油の量による絵柄変身アート。坂本龍馬の妻「おりょう」をテーマにしたリード曲「おりょう・よばなし」のCDがお土産に販売されていた。沖田総司をテーマにした「総司の独り言」も。着物のボトルカバー。ワインボトルを日本の伝統的な着物スタイルで飾るユニークなデザイン。外国人の友人やホームステイ先のご家族への贈り物として喜ばれること間違いなしか。 TOKYO POP TOWNのCOOL ZONE入り口。ここには、プラネタリュームや土産物店がありました。3F 出発口付近。モロッコ旅行はここから。 出発階3Fの「情報ひろば」には、着ぐるみではない「固いカスタム君」が常設されていました。 CIQ官庁(C:税関、I:入国管理局、Q:検疫所、動物検疫所、植物防疫所)が海外旅行者や空港見学者に、出入国手続など知って得する情報提供を通じて、CIQの仕事に親しみをもってもらうための“情報ひろば”。CIQの紹介パネルと知的財産侵害物品の展示コーナーもありました。羽田空港からの入国者数の多い国籍のパスポートの見本も展示されていました。 世界中のパスポートの表紙の写真が載っているサイトをご紹介します。下記URLのページのPassportsから見たい地域と国を選んでください。http://www.worldpassports.org/国際線ターミナル展望デッキからの旧管制塔。旧管制塔の施設はバックアップ用として今も残され、緊急事態にいつでも対応できるようになっているのです。
2015.06.04
コメント(0)
-

羽田空港 国際線ターミナル(その1)
出張で羽田空港を利用した日に、早めに家を出て、再び国際線ターミナルに立ち寄りました。前回はモロッコ旅行に出発した4月16日の夜、約1ヶ月半ぶり。 バスを降りエスカレータで3Fに。 3Fは国際線出発ロビー。 3Fターミナルの天井を見上げる。空をテーマにすじ雲のイメージか?正面に3F⇒4Fへのエスカレータが エスカレータで4Fに上がると正面に江戸舞台が。美しい生花の紫陽花でいっぱい。日本の四季を感じさせる、涼しげな演出。そして江戸小路。 「和」と「江戸」をテーマにした飲食店とショップが並んでいます。メインストリートの江戸小路は江戸時代の街並みを再現。 江戸時代の歌舞伎演芸場を模した店先。 今は亡き中村勘三郎さんの「招き看板(まねき)」が飾られていました。総檜(そうひのき)づくりの「はねだ日本橋」を下から。 ホンモノのひのきで作られた全長25mの「はねだ日本橋」。 「はねだ日本橋」への階段。 日本橋の横の壁には江戸図屏風が。17世紀前半の江戸の町の様子がわかる絵画は、ほとんど残っていないのだと。江戸図屏風はそのころを知ることができる貴重な資料。江戸幕府3代将軍徳川家光の行った事を称える為に描かれたと。 「はねだ日本橋」の前に立っている看板。昔も今もここから旅がはじまるのです。 江戸湊、向井將監武者船懸御目候所。向井將監(むかいしょうげん)率いる幕府船団が描かれている。向井家は代々将監(しょうげん)を名乗り船手頭を世襲し、将軍御座船の指揮をとったのだと。芝増上寺、台徳院殿御仏殿、家光御仏殿へ御参詣之所。 台徳院殿御仏殿は、江戸幕府二代将軍徳川秀忠の霊廟建築。芝増上寺に造営された。江戸時代初期を代表するの豪華な彫刻で飾られ東京を代表する観光地として知られていたが、東京大空襲で焼失。向かって左側には台徳院霊廟が。中央から下にかけて御成門、勅額門、そして五重塔が見えます。この絵の右側に増上寺が描かれています。京橋(右)、新橋(左)周辺。いずいれも太鼓橋を思わせるような、湾曲度の大きい(アーチ型)のもので実物を見て描いたか疑われますが、当時の認識をうかがわせます。橋脚が三組しかなく、長い橋を支えられたものとは思えないのだと。(橋はアーチ型で橋脚は三組に描くとの認識かと)江戸城。屏風には、家光の盛時を示す意図から江戸城天守が大きく描き込まれている。この天守は江戸城としては 3度目のものとして、寛永15年(1638)に完成。基壇から上端までの高さは、約60m。しかし、明暦 3年(1657)の大火の折に焼失し、以後再建されることはなかったと。日本橋。 経済の中心地としての町の賑わいが鮮やかに描かれていて、大店が軒をつらね、水陸交通の中心と多くの人々が行き交い、米や材木などの物資が集散されている様子、橋の下を通り抜ける屋形船、橋のたもとには魚河岸があり、船から荷を下ろす様子、幕府の重要な法令を掲示した高札場と、それを見つめる人々、江戸の中心としての活気に満ちた賑わいが描かれている。神田、神田筋違橋。神田川、筋違橋、吉原(現在の人形町付近)、浜町など。筋違橋は、「すじかいばし」 と読みます。最近「すじかい」という言葉はあまり聞かれなくなりましたが、交差するという言う意味で 建築用語としてはかなり使われています。向かって側には湯島天神が描かれてます。湯島天神を参詣する老若男女や、参詣客相手の店が描かれています。また境内で弓の練習をする武士の姿も。寛永寺。東叡山寛永寺は、京の比叡山延暦寺にならい、江戸城東北の鬼門を守護するために創建された。増上寺とともに、徳川将軍家の菩提寺であった。寺院や神社の境内地は、江戸の総面積の約15%という広大な土地を占めていたと。五重塔も描かれている。現在の芝公園丸山古墳付近にあったものと推察されるが、 台座に至るまで全てが灰と化し何も残っていないとのこと。浅草、浅草寺、隅田川の渡し、浅草寺門前の露店周辺。江戸に入府した徳川家康は浅草寺を祈願所と定め、寺領五百石を与えた。浅草寺の伽藍は中世以前にもたびたび焼失し、近世に入ってからは寛永8年(1631年)、同19年(1642年)に相次いで焼失したが、3代将軍徳川家光の援助により、慶安元年(1648年)に五重塔、同2年(1649年)に本堂が再建された。このように徳川将軍家に重んじられた浅草寺は観音霊場として多くの参詣者を集めたとのこと。現在の五重塔の位置近くに寛永8年(1631年)に焼失した三重塔が描かれている。 日本橋を振り返る。 右手に江戸図屏風が。
2015.06.03
コメント(0)
-

アイスプラント
我が菜園の「アイスプラント」が収穫時期を迎えています。早春にネットで種を購入し、育てたものです。 名前の由来は表皮に塩を隔離するための細胞があるため葉の表面が凍ったように見えることから。 乾燥に耐えるとともに、耐塩性が高い塩生植物の一つであり、海水と同程度の塩化ナトリウム水溶液中でも水耕栽培が可能とのこと。 茎の表皮には大きさは1ミリ前後の透明でキラキラと輝く粒粒が。この白き粒粒が実は味の秘密。葉っぱにも。元々は南アフリカ原産の多肉植物とのことですが、今、日本でブレイクしつつあるミラクル野菜なのです。 早速妻がサラダに。我が家のキュウリとトマトと一緒にドレッシングをかけて。ひと口噛んでみたら……、水泡から出る水分に、わずかな塩味と酸味が感じられ、プチプチという食感が心地いい。 しかも多肉質の葉が柔らかく、最初から味がついているからドレッシングなしでも十分イケるのです。しかし昨年に比べて塩味が薄いような気もしています。アイスプラントの刺身も旨いとネットに。次回はアイスプラントの淡白な味をワサビ醤油で。
2015.06.02
コメント(1)
-

ズッキーニ
我が家の横の菜園のズッキーニが花をつけています。 早春に種を蒔き、ビニトンの中で育てたものです。最初に蒔いた種は発芽しましたが、一時的な遅霜、低温でやられてしまい、再度蒔きなおしたもの。果実の外見はキュウリに似ていますが、カボチャの仲間なのです。主に緑果種と黄果種がありますが今年も緑の種類。 既に花の下にズッキーニが出来始めています。キューリに比べやや硬い果皮をもつこともあり、主に加熱して食べるのです。フランス料理やイタリア料理の食材として知られています。 花は「花ズッキーニ」と呼ばれ、花心を取ったものを食用とするとのこと。 通常のズッキーニよりさらに未熟で花のついた状態で収穫し、花をつけたまま販売されるズッキーニも「花ズッキーニ」と呼ばれていると。そういえば、我が家の近くの「湘南 わいわい市」 でも花つきのズッキーニが販売されていました。また雌雄異花のため、受粉にはミツバチ等の昆虫や人の花粉媒介を必要とするのです。「蔓なしカボチャ」とも呼ばれ、カボチャと異なり蔓が延びないので、栽培に広い面積を必要としないので、何本も栽培できるのです。1本を今年初めて収穫しました。キュウリと異なり、表面に小さな白き斑点が。油との相性も良く鉄板焼き、フライなどにも向きますので楽しみたいと思っていますが今週は明日から週末まで日本国内の行脚?いや仕事での移動です。
2015.06.01
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1










