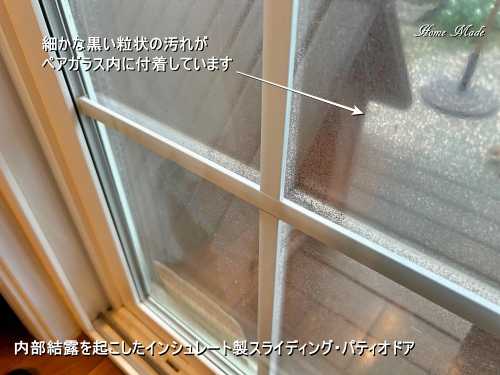2005年09月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
まな板の鯉
osama さんとの、パンダ杯の対局の話。 彼の人気のおかげで、思いがけず相当の反響になったようだ。お互いに決め手を逃しているうちに、最後は微妙な劫争いに勝負がかかる3時間近い熱戦となった。とにかく、楽しんでいただけたようで良かった。 ただ、nipparatも相当にヘボだなという事がバレてしまったは、間違いない。前回、囲碁ボケ記念対局では、おさま流の布石に対して、一隅かかりから先手をとって2隅目もかかったが、挟まれて序盤早々に一本とられた。今回は2隅目は相手にしまらせて打とうと思ったのだが、結局、自分からかかる展開になり、ここで醜い悪手連発でツブレ寸前の状態になってしまった。 しかし、おさまさんも無意識的にここで潰しては面白くないと思ったのであろう。奇跡的に助け起こしてもらい、熱戦に突入したのだ。 私は定石を知らないこともあり、実はしばしば序盤早々に潰れる。つい先日も基本定石を間違えて、観戦者に呆れられたばかりだ。 一番苦い思い出は、数年前の支部対抗戦全国大会の決勝戦。私の碁が週刊碁に載ったのだが、序盤早々にひどい潰れ方をした碁が全国囲碁ファンの目に晒されてしまい、ひどい目にあった。私のコツコツと積み上げた物を返してくれと言いたくなった。アマとは悲しいもの。いくら、「たまにはいい手も打つのよ」と言い訳しても、10級の手を平気で打ってしまうので、どうにもならない。 ただ、見る方にしてはヘボ手が所々にある方が、面白いものだ。なかなか面白い酒の肴になったのではないかと思う。 こうなったら、みんなでまな板の鯉になって、囲碁ブログ選手権をやりますか。
Sep 28, 2005
コメント(18)
-
美少女の話
これまでいろいろな人が対局する様子を見て、印象深い思い出はいろいろあるが、今日はもっとも衝撃を受けた体験談。 おそらくまだ私が学生の時だったと思う。日本棋院で行われた何かの大会に参加していた時のこと。何気なく2階の一般対局室を眺めていて、ある対局に目を奪われた。大人の男性と対局しているのは、小学生くらいの女の子だ。この女の子を見てハッと息を飲んだ。 私が今まで見たことがない美少女だった。小説などで美少女という言葉はよく使われているけれど、それと実感するような経験はあまりない。かわいい子は大勢いるけれど、美少女とは違う。その子は、私が生まれて初めて見る、まさしく美少女だった。 しかし、驚いたのはそれだけではない。少女の打ちっぷりを見て衝撃を受けたのだ。見事な手つきでほとんどノータイムで力強くビシビシと打っている。しかも、すごく筋が良くて強い。これは自分より強いかも知れないと思った。こんな少女がこれほど打てるとは、何者だろうと興味を抑えられなかった。 たまたま、大会に参加していた友人が彼女のことを知っていて話かけていたが、少女はほとんど喋らず黙っていた。それがまた神秘的な印象を受けた。 この時の印象が鮮烈で、その後少女の事がずっと気になっていた。あれほどの打ち手が、埋もれるはずはないと思ったが、ずっと名前を見る事はなかった。しかし彼女は大学に入ってから一気に有名になり、その後プロ入りした。梅沢ゆかりプロである。
Sep 25, 2005
コメント(10)
-
棋士の対局姿はしびれます
昨日の話に関連した話。 記事によると、名人戦で、子供達が最初だけ対局の様子を観戦して大喜びだったと言う。非常に良いことだと思う。過去にもタイトル戦の様子を見た人達の感想を見ると、真剣勝負の張り詰めた雰囲気に感動してそれだけで強くなった気がする、と言っている。それはよく理解できる。私はタイトル戦は見たことはないが、普通のプロの対局を見てもたいへんためになる。やはり、棋譜だけ並べるのとは全然違うと思う。 ただ、残念なことにプロ棋士同士の真剣勝負を観戦する機会は非常に少ない。対局は日常的に行われているが、ほとんどアマチュアには公開されてはいない。 棋士にしてみれば、そばに何をしでかすかわからない素人がいては集中できないというのは、当然ではあると思う。ただ、棋士は棋譜だけを世に残せば良い、というのでは味気ないし勿体ないと思うのだ。なぜならば、観戦して勉強になるだけではなくて、棋士の対局姿ほど、絵になりしびれるものはないからだ。 アマチュアでも、菊池先生や高林先生などの対局姿は格好よくてしびれる。本人達も、おそらく相当に見られることを意識していると思う。高林先生などは、時計を叩くしぐさまでが、美しく一つの芸術作品なのである。 もう10数年前だと思うが、世界戦の対局を応募者から抽選で当った人に一般公開していたことがある。私もたくさんハガキを出して、幸運にも当選したので日本棋院に出かけたのだ。 棋院2階の対局場に、一流棋士が勢ぞろいして対局していた。大竹、林、武宮、加藤、石田、趙治勲、小林光一、小林覚、徐ボンス、チョフンヒョン(ソウクンゲン)、ジョウ衛平、馬暁春、曹大元など。夢のような光景であり、忘れることができない。特に売り出し中の小林覚や馬暁春の颯爽とした打ちっぷりが印象的であった。 いつか機会があれば、イセドルや、チャンハオの対局姿を見てみたいものである。
Sep 24, 2005
コメント(0)
-
菊池先生魅せてくれました 答え
昨日の局面から下記のように進んだ。実戦図黒1と当て込むと、白も気合で割り込みたくなる。その調子で5に打とうという作戦である。さらにこの後、黒から2線にカケツギが来ると隅の白の味が悪くなる。 見せられるとなるほどと思うが、なかなか気づかないものである。菊池先生の碁を見ていると、ハッとすることが多い。今回は、大サービスで紹介した。 ところで、このすばらしい碁を観戦しているのは、10人以下だった。いつも思うのだが、こういう大会を若い人はもっと見に来れば良いのにと思う。大会には若い人もたくさん参加しているが、負けてすぐ帰ってしまうのも、何と勿体ないことかと思う。 アマの碁でも生の真剣勝負を見るのは勉強になる。紙やネット上のプロの棋譜を何百局も並べるよりも、はるかにためになると実感している。なぜかは良くわからないが、直接自分の5感に染み渡るからであろうか。 こういう感性は古いと言われるのだろうか。
Sep 23, 2005
コメント(6)
-
菊池先生、魅せてくれました
本日の局面 先日観戦していたアマトップ同士の対戦、菊池対平岡戦から取材した。この局面で黒番の菊池先生はどう打ったかという問題。今、左辺で白が黒の一目の頭をハネテある所が焦点。単純に一目引くのでは重い感じがする。しかし他に良い手もないかな、と思っていたら、ここで魅せてくれた。 黒の作戦は?
Sep 21, 2005
コメント(3)
-
勝負どころで、勝負せず土俵を割る。
本日の局面 この局面は、人生を左右するほどの緊迫の局面である。これに勝てば、頂点も見えてくる。次の相手は、これまで何局も打って手の内を知り尽くしたM君。最近は分が悪いが望みはある。 私の黒番、地合では大差で白が良いが、左辺の白の生死に勝負がかかっている。取れなくても、上辺や下辺の白の構えを良い形で蹂躙すれば、勝負になる。ここで、打った私の黒3の手は実に中途半端であり、実戦はあっさりと生きられてしまった。 黒1で白2のところに打つか、黒3で2の右側にはねていく手があったのではないかと思う。ただ、難解すぎて今のところまだ読みきれない。どうなるのだろう。 黒3は、上辺の黒の味を心配したのだが、左辺白の目も完全に奪っていない意味もあって、ひどい手であった。特にはねる手は読んでいたのに、それで勝負しなかったのは、本当に悔やまれる。 こんな大事な局面で、勝負する前に土俵を割っているようでは、いつまで立っても突き抜けない。
Sep 19, 2005
コメント(13)
-
滑稽な広告見つけました
わけのわからないツボやら、お守りを高額な値段で売ろうとしている広告を見て、「こんなの買う人いるんだな。滑稽だなあ。」と思ったことはないだろうか。こんな滑稽な話は人ごとだと思っていたが、つい最近かなり身近にそれに似た広告を見つけた。 この広告によると、どうもたいそう価値のあるというお守りのような紙を売ろうとしているらしい。どの家庭でも歳出削減に必死になっている時代に、実は紙切れ一枚を100万円で売ろうという、大胆不敵な広告である。相当に滑稽である。 ところが、どうも当事者はその滑稽さに気づいていないふしがある。これがまた、滑稽なのである。このような広告の場合、多くは詐欺的行為と知った上での行為だと思うが、どうもこの広告主は相当に純粋な気持らしいので、まさしく「滑稽」と言うのがピッタリである。 実はその昔、この紙には相当な価値があったのは確かであるようだ。この紙には権威があって、取得することで確実に持ち主の能力の証となり、宝となったのである。 しかし、だんだんとこの紙の価値は落ちてきてしまった。それは、この紙を乱発したのが原因であるらしい。組織の中には、そのことに途中で気づいた人間もいたかも知れないが、圧倒的多数派は元手の掛からないこの紙が生み出すうま味を忘れることができなかったのだろう。行き着くところまで、行き着いてしまった感がある。 昨年この組織は、新しく最高の価値があるとされる紙を100万円で売り出した。ネット上の情報によると、当然ながら思惑通りには売れなかったらしい。この失敗は、相当に致命的な失敗に思える。この最高の紙が売れなかっただけではなく、従来からあった紙の価値を落としてしまい、そろそろ一家に一枚買おうかと考えていた人たちの購買意欲を完全に消し去ってしまったのである。あまりにも稚拙である。稚拙すぎて言葉もない。 ところが、これに懲りずにまた今年も100万円の例の紙を売るらしい。今年は、ネット上で簡単に応募できるようにしている。それについては頭を使ったなと思うが、こんなことでは焼け石に水である。 そろそろ、根本的な構造改革をしないとジリ貧であろう。そのためには、「この組織をぶっこわす!反対するやつは、切り捨てる!」と叫ぶ改革者が必要なのだろうか? この組織はけして詐欺集団でないので、おそらく愛すべき人の良い甘ちゃん集団なのであろう。この広告を出している組織は、日本伝統の卓上競技を管轄している組織らしい。伝統の組織
Sep 12, 2005
コメント(26)
-
実戦詰碁の答え
前回の実戦詰碁の答えは、以下。実戦詰碁の答え 一本道で難しい枝分かれがないので、詰碁作品になるようなものではない。しかし実戦では、こういうのを30秒の秒読みで読めるかどうかが勝負の分かれ目になる事が多い。
Sep 8, 2005
コメント(6)
-
巨大実戦詰碁
ネット対局から取材した巨大実戦詰碁。黒先で、左辺の黒大石の生死は如何に?一本道なので詰碁としては難しくないが、実戦でこんな綺麗で豪快な詰碁ができるのは珍しい。本日の問題 有段者は目で追っていただきたいが、動かしたい方のために以下。本日の問題
Sep 5, 2005
コメント(0)
-
NHK杯を見て開発者を思う
最近、小目の高ガカリに一間高ハサミが多く、NHK杯でも最近流行の変化が出現していた。つけ引きを決めて辺の石をつけ切っていくのは、韓国発なのだろうか?序盤でつけ引きを決めてしまうのは、現代流のドライ考え方から生まれたのであろう。 個人的には、いかにも味気なくて好きな打ち方ではない。その前は、以下のような形がよく打たれていた。 変化図1 この三三のつけ一本を打つ手は、比較的新しい。次に、ぶつかりの利きや2の2に更に跳ねていく手を見ているのだが、辺で戦いが始まった後からでは間に合わない可能性があるので、すぐ打ってしまおうという発想である。 強豪でこの手を最初に打ち始めたのは、おそらく高林共平氏である。20年以上前だと思うが、誠文堂の月刊「囲碁」誌上で、プロに挑戦とか、若手アマ強豪総当たり戦(三浦、中園、今村氏らが出ていた)などの対局がよく載っていた。この時の何かの誌上対局で、つける手を見たと思う。 その時の解説が、たしか大竹九段だったと記憶している。解説によると、つけ一本は、以下のように打たれて持ち込みであるから良くない、とのことであった。当時は、こんな石をポン抜かせるという打ち方はあり得なかったのだ。変化図2 その後いつのまにか、世界中のプロが当たり前のように、このつけ一本の手を打つようになったのである。碁の世界に特許がないのは、幸せなことである。
Sep 4, 2005
コメント(2)
-
度肝を抜く創造力
前回の局面で黒の高林氏が打った手は、以下の図の下つけである。実戦図1続いて、以下のような変化になった。実戦図2 ここでは、上下どちらかにつめるのが普通の手である。しかし、つめる手自体が狭いのがやや不満であるのと、白が軽くて持て余す危険もある。私も、黒番でこのような布石をよく打っていたことがあるのだが、普通につめて攻めに行った後で、何手も手を抜かれてひどい目にあったことがある。そこで黒は、白を重くして責任を持たせながら迫る手を考えた結果、下つけに思い至ったのだであろう。今見ても凄い手であるが、当時はまだミニ中国流での韓国流のつけのような手も普及していなかったので、この下つけの奇抜さは今の比ではなかった。 その後のわかれの善悪は私の棋力では判定不能であるが、そんな事は些細なことである。少しでも良い手はないかと、従来の常識に囚われない手を考えて、しかも打つということが、素晴らしいことだと思う。 高林先生の碁の最大の魅力はここにあると思う。追々紹介するが、おそらく高林先生が打ち出した手で、最初に見たプロは否定していたのに、今やどのプロも常用しているという手段が、いくつもあるのである。 これは、村上文祥さんや、菊池先生にも共通する魅力である。このような、魅力的なトップアマはそれゆえにプロからも高く評価されいるのである。プロのどのクラスと打って勝負がどうか?などという視点だけで、評価しようとしたら大間違いである。平凡なプロとは比較にならない魅力にあふれているのである。 せっかくなので、高林対鮫島戦の棋譜を載せておく。公式戦の決勝戦なので問題ないであろう。解説は、不要である。凄まじい力を誇る二人の迫力ある熱戦を並べたら、間違いなく興奮するはずである。棋譜
Sep 3, 2005
コメント(4)
-
常識の逆転
地方紙で、いよいよ依田対結城の碁聖戦の棋譜解説が始まった。第一局では、黒番の依田碁聖の打った序盤早々のつけの手には驚いた。以下。 実戦図 どういう解説になるかなと楽しみにしていたが、「打ったことがない手を打とうと思った。」というあっさりした一文だけであった。この場面は、上に跳び出して辺の白石をはさみ返して攻める打ち方もよくあり、従来の常識では辺の白につけて固めてしまうのは、考えられなかった。 最近は、特に韓国で序盤早々にとんでもない相手の石につけていく手を見るようになった。一時は常識の逆転に戸惑ったが、最近はだいぶ見慣れてきたせいか、なんとなく受けいれられるようになった。韓国流のこの図は、白に軽く立ち回る余地を与えずに、いやおうなしに黒の構えを作ってしまう感じであろう。 依田碁聖の新手からの変化を見ると、黒はそこそこの地を持って治まり、上の白の厚みも、場合によると標的になる可能性もないわけではない。結局いい分れなのであろうか。 以下の碁は、平成11年に打たれたアマ強豪同士の公式戦で、黒は高林共平氏、白は鮫島一郎氏である。今白が右辺に割り打ちした場面。この局面で黒はどう打ったかという問題。本日の問題
Sep 1, 2005
コメント(4)
全12件 (12件中 1-12件目)
1