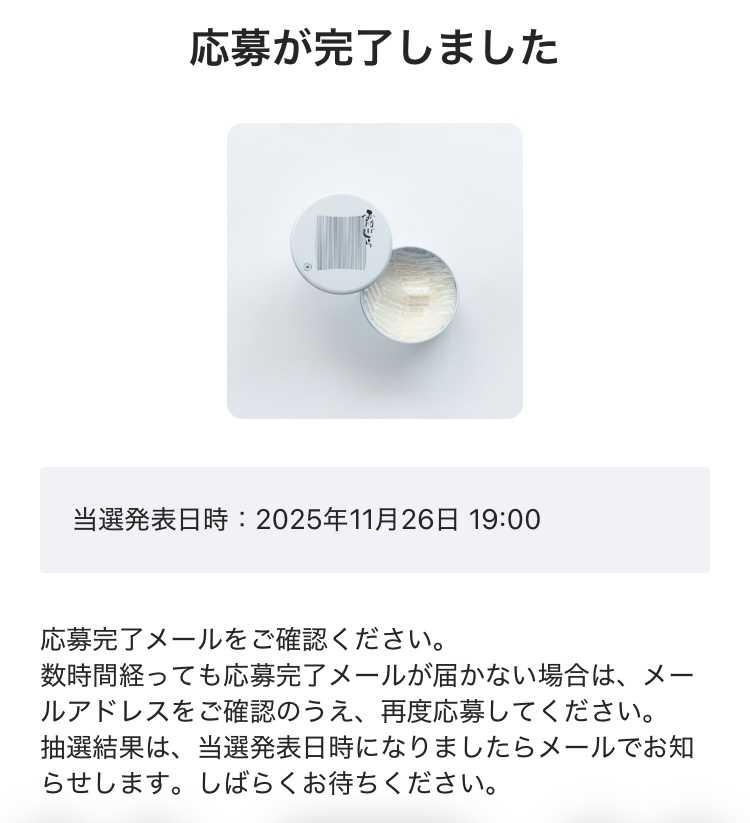2018年08月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

犬矢来、虫籠窓、ばったん床几♪
〇京の町家で生まれながら町家の暮らしを知りません。余りにも幼かったので記憶にないのです。しかし、父方の祖父・祖母に会いに行く時は、京都銀行本店真裏にある借家まで出向き、春休み、夏休み、冬休みには寝泊りしました。借家は心なしか右側に傾いているように見えましたが、造りそのものは頑丈に出来ていてビクともしません。道路に面する部屋は”店”と言って、木綿製品を並べたり、客の応対をする場所でしたが、戦時中に廃業していましたので、祖父夫婦の居間でした。+ 奥には二階へ上る階段、食事をする居間があって、その正面は台所で井戸もあれば水甕もありました。階段の下は富山の薬箪笥のように物容れになっていました。+ その又奥の部屋は寝室兼仏間で日中は暗い部屋でした。縁側の向こうには小庭と厠などがありました。台所が比較的明るいのは天窓があったからでしょう。布袋さんが並んだ荒神棚もありました。店の真上に当たる二階は屋根裏部屋で、殆ど物置き場になっていましたが、後年、叔母の手で綺麗な部屋になっていました。犬矢来、虫籠窓、紅殻格子、ばったり(ん)床几なども懐かしい造りでしたが、今はありません。 近頃はこの京風の町家がリフォームされ、画廊や喫茶店や和装小物の店などに再利用されていることは喜ばしいことですが、出来るだけ”本物”の京ものを販売して欲しいなぁと思っています。+ 光の明暗がくっきり浮かぶのは空気の澄んだ秋。入日も風情があるし、ほんのり橙色の灯火の入った町家も心を落ち着かせることでしょう。
2018.08.31
コメント(0)
-

リフォーム当時の日記♪
〇12年前の日記から、リフォーム当時の様子を覗いてみます。<玄関口へいざなう勾配が緩やかになった表の石段。その両側の自転車昇降坂の工事中でした。玄関の靴箱にも戸が入り、和室には押入れの襖、玄関口への両襖、増築した寝室への仕切り障は障子襖で、そのいずれもが明るい薄緑色。かなり上品な和室になりました。寝室の東側は深い焦げ茶色のウッドデッキで、幅を150cm取りましたので、小さなテーブルも置けそう。また蛸足の物干しも中で吊れそうと家内が嬉しそうにしていました。このデッキは洋間からも出入りできるようにしましたので便利だし、蒲団も2枚干せます。洋間の白壁の塗装も済み、随分明るいままダイニング・キッチンに続いています。仕切りの戸3枚の中央にはガラスをはめ込んでいますので、洋間の戸を閉めても台所はそれほど暗くならない見込みです。照明に関しては従来から馴染みの電気屋さんに正式に依頼しましたので、来月は、2つの物置にぎゅうぎゅう詰めした生家の家具等を配置し、中旬頃、向日町の家にの一時退避していたタンス等の家具を運び入れる段取りです。
2018.08.30
コメント(0)
-

缶コーラ標高二千の泡を噴く すばる♪
〇父の句に寄せて。 缶コーラ標高二千の泡を噴く すばる+ 何とも涼しげな句。缶の蓋を捩じった時に発する音まで聞えて来そうな勢いを感じますね。標高二千と言えば気圧はかなり希薄になっている筈。まして発泡性の高い缶コーラを開けたのだから。+ サイダーや鎖となりて泡のぼる すばる+ 同じ飲み物でも、こちらは少し放置されています。おそらく真夏日の会議室での様子でしょうか。社運をかける議題の論戦に拍車がかかって誰ひとりとして給されたサイダーに手をつけようともしない。ただ泡粒が鎖状になってコップの表面に消えてゆくだけ。+ 現在は豊かな時代だから、清涼飲料と言っても数え切れない種類のものをコンビニやスーパーで見かけますが、我が少年時代は、夏の飲み物と言えば、渡辺のジュースの素(粉末)かみかん水か、サイダー・ラムネぐらいでした。生ジュースはお中元で貰った時だけ。カルピスも結構な飲み物でした。
2018.08.29
コメント(0)
-

創作落語「大坂の陣」その最終章♪
(マスター)「まこと、その通りで御座った。勘弁仕うまつる。淀君様、これは軍議で御座れば、何事もそれがしにお任せ下さりませ」(田代)「爺がさほどに申すなら、我慢しようぞ」+てな具合で、波瀾に富んだ軍議が再開されました。+ (石田)「東方の軍容は如何ほどで御座るや?」 (真田)「某(それがし)が忍びに探らせた処、秀忠の率いる部隊が未だ到着していないようで御座る」 (石田)「それは好都合。幸村殿の言われる夜討ちが最良の手だてと存ずる」 (後藤)「いかにも、それが良策で御座ろう」 (義経)「夜討ちとは何のことよ」 (後藤)「義経公は夜討ちを御存知ないか?」 (義経)「我等の時代は白昼堂々と名乗りを挙げて、1対1で腕を競うのが常道なれば」+ マスター)「あのねぇ、義経はんの時代と違て、今や鉄砲・大砲が戦の主力ですがなぁ。時代錯誤も甚だしいじゃありませんか」(石田)「これっ!六三郎殿、また平成の言葉を使っておじゃる。時は慶長・元和の御世なれば、文語でお話しあれい」(マスター)「これは失礼仕った。どうも義経公は仲間数には勘定出来かねまするな」 (義経)「今一つこと問わん。鉄砲・大砲とは如何なるものに候や?」(後藤)「軍議が横道に逸れては心もとのう御座るによって、略して申せば飛び道具で御座る」 (義経)「さすれば何か、弓矢に代わって新しい武器が発明されたと申すのじゃな?」後藤)「いかにも、五十間離れた所から敵を打ち崩すことが出来まする」 (義経)「なれば騎兵隊とは趣が違うようじゃな」 (後藤)「ご納得が行けば、会議をとくと進めることに致す。・・・夜討ちの人数じゃが・・・」+ とまぁ、軍議の捗々しくないことったらありぁ~しません。一方、東軍は何事もスマートに運ぶようで、(福島)「西軍は毛利、島津、長曽我部の残党も増えて、大軍になっていると聞き及ぶが、各々方、如何致したものであろう」+ (藤堂)「大御所様の仰せになる通り事を運べば、烏合の衆の西軍など問題では御座らん」 (福島)「いかにも仰せの如く、大砲で天守閣を脅かし、太閤の堀を逐一埋めて行けば、裸城も同然。故太閤の常套手段、大がかりな土木作業を併せて行うのが良策に相違あるまいて」(藤堂)「城方の慌てふためく様が見えるようじゃ、ワッハッハッハッ!」+ 時に家康公は若い時は信長公に義理立てされ、立派な武将であったンですが、太閤秀吉が「浪花のことは夢のまた夢」という辞世の歌を残して亡くなってからは智謀の限りを尽くした為に、人気は陽気な太閤さんの足元にも及びませんな。でぇ~何で御座います。大坂方はいつまで経っても埒が行かないようで、(義経)「弓矢隊が必要とあらば、義経直属の部隊を遣わせても苦しゅうない」 (マスター)「義経はんは未だ理解できたはらへんようですな。アンタの時代と違て、世の中回転が速おますンや。弓矢なンて、ぎゅーうと絞っている間に、ズダーンであの世行きですがな。もおええ加減に時代について来て貰わなどもならん!」+ (石田)「これっ!六三郎、控えぬか!」 (マスター)「関西弁であろうとなかろうと、そんなン気にしてられまへん。イライラしますがな」 (石田)「静かに召されい。・・・時に義経の殿、静御前は大層な美人だったと専らの噂で御座るが、まことのことに候や?」+ (義経)「ふーむ。あれほど綺麗な女子(オナゴ)は居らぬわい」 (石田)「色が抜けるように白かったンでしょうな?」 (義経)「色が白い上に餅肌であった」 (マスター)「ちょっちょっ一寸待って下さい。その辺で何の話、しているンですか。大坂の陣はどうなるのですか?」(後藤)「大坂の陣よりこっちの方が面白い。ねぇ皆さんそうですな?」+ もうこうなって来ると話がごちゃごちゃになってしまいます。源平なら源平、大坂の陣なら大坂の陣とどっちかに纏めなくては、にっちもさっちも行かなくなります。(後藤)「義経さん、貴方がジンギス汗だという裏話もあるンですが、其処ン処はどっちですか?」 (義経)「はぁーて、そんな話になっていたンですか。とんと身に覚えありませんが」 (後藤)「なら、あの話は嘘ですね?」 (義経)「嘘です。きっと天狗の仕業でしょう」+ (後藤)「何でそんなに自信持って言われるンですか?」 (義経)「元はと言えば私ゃ~牛若丸、一緒に暮らした天狗のしそうな事ぐらい分かります。」<ドドド~~ン太鼓の入りで おしまい>
2018.08.28
コメント(0)
-

創作落語「大坂の陣」その6♪
(G女=お江)「忘れ物したの。ネッカチーフありませんでしたぁ?」 (マスター)「今、取り込み中です。何でも好きなもん持って帰りなさい」 (G女=お江)「あらっ!お姉様じゃないの、私よ私」+ (田代=淀)「あぁ、お江かえ。なんで私ら姉妹が西と東に別れて争わないかんの。女は不幸やわ」 (G女=お江)「姉さん、大坂城落城の目に遇われて、お気の毒でしたねぇ。私みたいに上手に世渡りせんといかんよ!」 (田代=淀)「放っといて、もっと自分に正直に生きなあかへんやんか」+ (G女=お江)「姉さん、完全に関西弁になってるわよ」 (田代=淀)「うっ・・・心得ました。そなたと私は敵味方、とっとと片隅に引っ込んでおりゃれ」 (G女=お江)「いけずなお方。フン!」+ 皆が皆、昔に戻れる訳ではないのです。ジャガーの兄さんは今度はそのままなンです。・・・これ困りますよ。東軍が一人増えたので、彼が西に就かないと不公平になります。それがどうしてもそうは行かないので西軍に分が悪くなりました。今回こそ協議し直して歴史を覆す意気込みでしたンですけど、大変ですわな。(石田)「前回の戦では、淀の御方様が差しで口を挟まれたゆえ、全軍を率いるそれがしも苦労致した。今回は幸村、又兵衛両氏の戦法を第一と致したい。各々方、異存は御座りますまいな」(後藤)「無論もろ手を挙げて賛成仕ります」 (真田)「大坂城から一歩も出なかったのが敗因で御座った。今度は夜討ちを掛けたいと思うが如何で御座ろう」+ (田代=淀)「出て行くは勝手じゃが、秀頼は放しませぬぞ」(後藤)「これ淀君、また口をお出しになる。女子供は評議には関わりの無いこと。お控え召され」 (田代=淀)「今度は必ず勝てると申すのじゃな。秀頼を死なせることは無いと申すのじゃな?」(後藤)「じゃから男共にお任せあれと申して居る」 (田代=淀)「随分横柄な態度じゃな。身分を弁(わきま)えよ」 (後藤)「止ーめた。こんな評議は御免被(こうむ)る。いずれも様、退座致すで御座る」+ 一番目に怒ったのは後藤又兵衛。歴史は繰り返すとは本当の話ですな。 (Y男=義経)「あいや待たれい!後藤殿」急に口を開いたのは、困りきっていたジャガー君です。+ (後藤)「待てとお止めなされしは、身共がことに御座りまするか」 (Y男=義経)「そのセリフは白井権八では御座らぬか。ちょっと不釣り合いで御座る」 (後藤)「いや、失礼申した。で、そなたはどなたで御座る」Y男=義経)「余は九郎判官義経なるぞ」 (マスター)「ちょっと待って下さいよ。何でこんな処に義経が出て来るンですか?変ですよ変!」+ ここで東軍の連中が、どっと笑います。(Y男=義経)「そう言ってもみんな楽しそうに大坂の陣に参加されているじゃーありませんか。例え時代が古くっても参加させて下さいよ」(マスター)「はい、分かりました。ほんなら義経さんは大坂方という約束で、こっちの仲間に入って貰います。いいえいな、今も聞いての通り、こっちはもう分裂状態でっさかいに、+ 義経さんであろうがなかろうが、一人でも多く仲間に入って貰て、何ですがな、今度こそ狸親父の鼻あかしてやらんといけませんなぁ。よろしゅう頼ンます」(石田)「もし、・・・もし、六三郎殿、我々は皆武士で御座る。そなたの話しようは町人のようで、軽軽しいですぞ。しかも戦の評議で御座れば、もう少し重々しく話していただかねば困るで御座る」
2018.08.27
コメント(0)
-

創作落語「大坂の陣」その5♪
(マスター)「淀? 淀って淀君の淀ですか?」 (田代)「ええ、変な名前でしょう、私困ってるの」 (マスター)「淀君さまに御座りまするか、お懐かしゅう御座います」 (田代)「えっ ?」 (マスター)「爺の六三郎に御座りまする」(藤堂)「おい、マスター急に何を言ってるンだ」 (田代)「六三郎、そなたは大坂冬の陣の前に、わらわを残して死んでしまったではないか」+ ねぇー、ここから四百年前に逆戻りするンで御座います。(マスター)「はい、無念で御座いました。もっと長生きしたかったので御座いますが、運命には逆らえぬものでして」 (藤堂)「ウン?そちらは大坂方か?片桐は如何致した。最近とんと城内の様子を知らせて寄越さんが・・・」+ (真田)「オイ、藤堂、お前何言ってるンだ。それに田代さんも、マスターもさっぱり訳の解らないことばかり言って・・・」 (藤堂)「ムムー!貴様は音に聞こえた真田幸村に似ているぞ。隠すな隠すな」 (真田)「俺は何も隠しちゃーいないよ、マスター助けてよ、皆変なンだよ」 こうなってしまっては只一人、昔に戻らない真田君は大変です。捨てる神あれば拾う神ありで、運よく別のグループが入って来ましたンで、ちょっと中休みってぇ所です。しかし時は悪戯もんで、新しく入って来た客五人も、このけったいな大坂の陣に組み込まれてしまいます。+ (石川)「片桐殿は、いよいよ間者の立場がばれて、江戸城まで逃げ込まれたそうではないか」 (藤堂)「ちょいと待て、お主らは東方の者か、ここで席替えを提案する。マスター、一体誰と誰が大坂方で、誰が東軍側か、はっきりさせてくれ」+ (マスター)「分かりました。挙手願います。田代淀子さんを中心として、大坂方の方、手を挙げて下さい。・・・あぁ判りました。+真田さんは文字通り、真田幸村で、れっきとした大坂方ですなぁ。さっき石田と言うて居られた石田さん、アンタは石田三成さんですか、ハハ~なるほど。で、そこで手を挙げてなさるアンタ、そうそう貴方ですが、どちらさんですか?」 (後藤)「後藤又兵衛で御座る」 (マスター)「なるほどそれで後藤さんて誰か最前言ってられたンですな。もう大坂方は居られませんか?・・・居られんようやな。では大坂方は淀君に、真田、石田、後藤さん、これだけですか?」+ (福島)「オィ マスターあんた最前六三郎とか言っていたみたいだが・・・」 (マスター)「あぁそうか、私は淀君の爺やだから大坂方か」 (藤堂)「東京もん、おや、江戸もん、これもおかしいな。東軍は残り全部ということになる訳だよな」 (石川)「藤堂さんとやら、アンタが仕切ってどうするンや。こっちにはもっと偉い人が居て下さるから、あまり出しゃばらん方がいいよ」+ (藤堂)「その偉い人ちゅうンはどなたですか?」 (加藤)「加藤清正じゃ」 (マスター)「へぇー、あの裏切り者の虎之助がアンタか、太閤殿下になり代わり、成敗してやる」 (石田)「まぁーまぁー六三郎はん、慌てなさんな。これから歴史の塗り替えじゃ。皆でどうしたら東軍に勝てるか協議しよやないか」+ (後藤)「身共も賛成で御座る。のう幸村殿」 (真田)「いや、まったく持って同感で御座る。淀君様、それで宜しゅう御座いますな?」 (田代)「良きに計ってくりゃれ。今度はわらわも嘴入れる積もりは無い」+ えらいことになって来ました。ちょっと東軍のメンバーを整理して申し上げますと、加藤清正、藤堂高虎に、福島正則、それにもう一人、三河の英雄石川数正とその家来、これまた錚々たる人が、たまたま集まったことになります。そこへ先程の二人が戻って来ました。
2018.08.26
コメント(0)
-
創作落語「大坂の陣」その4♪
(藤堂)「マスターいつものブランデー頼む」 (マスター)「いらっしゃい。今日はお一人ですか? この間のお連れさん、えっと」 (藤堂)「あぁ、真田君のことか」 (マスター)「そうそう真田さんでした。苦味走ったいい男でしたね」+ (藤堂)「そりゃーそうかも知れんが、俺はどうなんだ?」(マスター)「いえー、藤堂さんも何しろお歳より貫禄があって、その辺の女が黙ってませんやろ?」 (藤堂)「そうだといいンだが、未だ独身て言うのは推して知るべしちゅう処かな?」 (マスター)「大丈夫、大丈夫、何せ藤堂さんは仕事の手際が良いと聞いていますから、別嬪さんゲットされるに決まってます」+ (藤堂)「まぁそうして置くとして、俺が店に入る前、何やワーワーと騒いでいたみたいだけど」 (マスター)「えっ、そんなこと無いですよ、ねぇー」 (Y男)「ええ、僕達は静かに飲んでいましたけど?」 (藤堂)「そうですか、まるで喧嘩していたように聞こえたけど」 (マスター)「この辺は最近カラオケばかり歌う客が増えて来たので、うるさかったン違いますか」+ という訳で、この場は丸く収まりました。先程えらい剣幕で言い争っていた恋人同志も場所を変えるンですか、勘定払って出て行きました。(藤堂)「マスター、ロトシックスって知ってる?」 (マスター)「ええ、でも六つの数字が当たらないと駄目なンでしょう?」 (藤堂)「ミニロトは五つで済むけれど、配当はシックスの方が大きいからね」 (マスター)「私ら夜の商売ですから、宝くじを買う時間帯は寝たり、何かしていてチャンスが無いンです」 (藤堂)「そりゃ気の毒。この間やっと四つ当たったンだけど、配当幾らだと思う?四つも当てて、たったの八千円。ジャンボの方が魅力的かなぁ」(マスター)「どっちにしても夢のような話。当たってなんぼの世界と違いますか」 (藤堂)「そう言ったら実も蓋もない」+ なンてくだらん話をしている処へ、グラマーな美人連れで真田君がやって参りました。 (真田)「ヤぁー今晩は」 (藤堂)「あれっ、真田、その人紹介しろよ」 (真田)「君は知らなかったのか、一橋商事の受付嬢:田代さん」 (田代)「初めまして、田代です」 (マスター)「真田さん、美人のお客さん連れて来ていただいたンで、ちょっとだけ割引させて貰います」 (真田)「マスター、そんなら今夜はタダか?」 (マスター)「タダ言う訳には行きませんけど、割引させて貰います。今後もどんどん連れて来て下さい」+(マスター)「このお嬢さん、何とおっしゃるンですか?真田さん」 (真田)「田代さんって紹介したじゃーありませんか」 (マスター)「いえ、お名前の方です」 (田代)「珍しい名なンです。淀子って父がつけたンですよ」
2018.08.25
コメント(0)
-
創作落語「大坂の陣」その3♪
初めに申しましたように、この盛り上がった処へ、前世の記憶が二人とも急に甦るンで御座います。+ (G女)「ちょうどあの時、私は幼い皇子(みこ)を抱いていたわ」 (Y男)「えっ、今何て言ったの?」 (G女)「だから私は群がる源氏から逃れるように、皇子を抱いて舟に乗ったのよ」 (Y男)「皇子って誰のこと?」 (G女)「私一度死んでしまったから、皇子の名前は忘れたわ。・・・あぁ、思い出した。安徳天皇よ、そうよ源氏への恨みは忘れはしない。あんなに平和な平家の世だったのに・・・。」+Y男)「源氏やら平家って、一体何の話なンだ」 (G女)「あらっ!貴方は義経! 我ら平家の者を海へ沈めた憎い仇!」Y男)「源氏やら平家って、一体何の話なンだ」 (G女)「あらっ!貴方は義経! 我ら平家の者を海へ沈めた憎い仇!」 (Y男)「ちょっと待ってよ!今、平成の時代だよ。平家源氏は鎌倉時代の話だよ・・・。」 (G女)「そんなの関係無いわ。貴方は私達の仇、九郎判官義経公ね。皆になり代わって貴方に一矢報いてやる!マスター、其処のナイフ貸して頂戴!」+ (マスター)「お嬢さん、此処はBAR、ダン・ノーラですよ。壇ノ浦ではありませんよ」 (G女)「じゃかましい!取って呉れないンなら、カウンターに上がるまでよ」 (マスター)「えらいことになってしまった。お客さん、早くこのけったいな人連れ出して下さい」+ (Y男)「そう言うお前は熊谷直実。余が命令じゃ。この女を連れ出し、幼き皇子の所在を確かめて参れ!」(マスター)「貴方まで何をおっしゃるンですか、困ったなぁ、どうしよう」 (G女)「まことそなたは熊谷ぞ。我らが勇士惟盛殿を討ち取った男ぞな。もう許しゃせぬ。わが身はどうなろうと、二人とも生かして置かぬぞえ~!」 (マスター)「一体、何が何やら、さっぱり訳が解らん。−−−まぁ、強いて言えば、近藤勇君は知っていりけどなぁ」+ (Y男)「誰じゃい、近藤勇って」 (G女)「誰なのよぅ、近藤って」 (マスター)「へぇ~、あんたら知りませんか、あの有名な近藤勇を。我々勤皇志士を目の仇にした奴ですがな」 (Y男、G女)「そんなン、知らん」 (マスター)「そらそうですな。あんたらは源平合戦時代のこと言うてなさるし、こっちはもっと時代が下がって江戸幕府崩壊の頃ですからな」+ ワーワ、ワーワ言うている中へ、別の客が入ってきました。不思議と言うかひょんなことと言うか、今までの会話が急に終わってしまいました。
2018.08.23
コメント(0)
-

高瀬川に寄せて♪
〇京は木屋町二条の西、一之船入から始まる高瀬川は伏見の宇治川合流地まで10キロの人工の河川です。慶長16年(1611)秀吉公が方広寺大仏殿再建のため、物資搬入用に角倉了以に命じて作らせたものです。高瀬舟は全長凡そ14メートルの平船底の小型舟で、当初は木材搬入に使われましたが、後年、木炭や米、味噌、醤油などの生活用品を運ぶようになりました。文献によれば、江戸中期には188艘もあったとか。岸辺から6人の男が綱を曳く図が残っていて、この掛け声が「ホーイホーイ」。高瀬舟が全廃されたのは、大正9年。(参向図書:三浦隆夫著「京都ことわざ散歩」)
2018.08.22
コメント(0)
-

『日本系譜総覧』という史料♪
〇『日本系譜総覧』には「歴朝一覧(天皇)」及び「皇室御系図」、「大名一覧」(これは領地ごと、慶長から明治まで五段階の時期を領地高も一緒に掲載)、「将軍及武家一覧」、「武家重職一覧」、「国母一覧」(玉依姫命から九条節子まで)、「神宮・官国弊社一覧」など。 + + 京都に在る官幣大社には上賀茂・下賀茂、岩清水八幡、松尾、平野、稲荷、平安、八坂神社の八つがあります。官幣中社には梅宮、貴船、大原野、吉田、北野の五つ。 + +別格官幣社には、和気清麿を祀る護王神社、信長の建勲神社、秀吉の豊国神社、三條実美の梨木神社など。 + + 古代から戦国までの関所一覧には、大山崎・山崎の山崎関、大江関、木幡関が載っていました。系図で興味を惹いたのは、孝元天皇の後裔に「紀」や「蘇我」があって、紀貫之と蘇我入鹿が遠い親戚。敏達天皇の後裔に小野妹子、小野道風、小野小町がいること。 + + 天武天皇の系統に清原深養父、清少納言、菅原系統に紫式部が絡んできます。お茶では、千利休の弟子として信長、秀吉、高山右近、毛利輝元、茶屋四郎次郎の名前などが載ってきて面白い。
2018.08.21
コメント(0)
-

頭脳力アップに挑戦♪
〇永石彊男さんの『文字のパズル』から引用しますが、(問)1週間単位の日、月、火、水、木、金、土この7つの字を幾つか組み合わせて、1つの漢字を10個以上作って下さい。理論的には25個あります。但し、火を火偏、水をさんずい、木を木偏などとして使ってもよろしい。埜=野の古字、椙=杉の国字、杜=森の国字、淦=船底の垢屈原が入水した汨羅の淵、淼もあれば焱も。サンズイに圭、金に炎、火に圭。火4つ、土4つなど百を超える。
2018.08.20
コメント(0)
-

天照大御神と榊♪
〇神前でお祓いをする時、必ずや榊をお供えしますね。なら、どうして榊は神聖なのでしょうか。古事記を繙けば、天照大御神が天の岩戸にお隠れになった時、大御神を岩戸から誘い出す為、<天の香具山の五百筒真賢木(イホツマサカキ)を根こじにこじ>て、多くの枝に八咫鏡、勾玉、木綿や麻布をかけ、岩戸の前にかけたと記されています。日本人が古来より崇める神は、透明で目に映らないので、神様の拠り所となる”依代(ヨリシロ)”に降臨して戴きます。 天照大御神の依代として”五百筒真賢木”が立てられています。このことから真賢木が神聖な境の木として考えられました。この境の木が神に関係の深い木ということで木偏に神を充ててサカキと読ませ、神に捧げる木の意味を持たせるに至りました。 なお伊勢神宮などで用いられている榊はツバキ科の常緑樹でマサカキと呼ばれるもの。長楕円形の先が尖った葉には光沢があって、ギザギザがありません。近畿以西に自生します。(参考図書:瓜生 中著「神社と祭り」)
2018.08.19
コメント(0)
-

泥棒に因んで♪
〇泥棒には入られたくありませんね。万が一入られたとしても、「ドロボー」と叫んで居ては誰も助けに来てくれません。だから「火事だぁ~」と叫ぶのが賢明かも。 + +泥棒に因む言葉を集めてみました。 + +泥棒、泥的、万引、万買、置引、掏摸、巾着切、箱師 + +こそ泥、梁上の君子、護摩の灰、枕探(捜)、搔払、 + +空巣狙、邯鄲師、銀潰、追剥、引剥、追落、居直強盗、 + +義賊、海賊、匪賊、山賊、緑林、山立、白波(浪)、 + +馬賊、夜盗、夜摩、夜客、倭(和)寇、野伏(臥)。これだけあるんだから、気をつけないと・・・。 (参考図書・永石彊男著『文字のパズル』)
2018.08.18
コメント(0)
-

阿弥陀経を唱えた貴族♪
〇父は趣味の多かった人でアフターファイブを有効に使っていました。その父より遥かに上回るのが慶滋保胤(ヨシシゲノヤスタネ)なる人物。上横手雅敬著『日本史の快楽』を参照してまとめてみました。 門閥が物を言う平安期、従五位下、大内記に留まりながらも、円融・花山天皇の詔勅の草案を練るなど有能な官吏であった慶滋保胤は天元5年(982)に記した『池亭記』に、自分の邸宅を詳細に述べています。50才近くになって六条に広い土地を購入、邸内に池を掘り、その西には阿弥陀堂、東には書斎を造り、北に家族を住まわせました。地所に占める割合を言うと、建物が10分の4、池が9分の3、田が7分の1、ほかに松の生えた島や白砂の汀、紅鯉、白鷺、橋や船も浮かべてあったそうな。 彼の生活は起床・洗顔のあと、先ずは西の堂にて阿弥陀経を唱え、法華経を読み、食後は東閣にて、白楽天の詩などを読書。仕事を終えて帰宅したら子供を船に乗せ庭園を眺めたり、菜園の様子をうかがったり・・・。職務を立派に果たしながらも、自宅での仏に帰依する時間を大切に暮らしました。源信の教え、来世の極楽往生を信じて念じ、子が成人すると出家という道を選んだようです。
2018.08.17
コメント(0)
-

戦時中の手紙♪
〇昭和19年8月17日付の父から戦局に居る叔父宛に送られたものです。叔父はいわゆる”神風特攻隊”として後年、正に出撃を明日に控えた時、玉音放送による敗戦宣告がなされて助かったのでした。 <大へん御無沙汰しました。元気に御勤務のことと存じます。戦局の苛烈化に伴い愈、お忙しいことと拝察してゐます。小生 今夏はどういふものか健康にめぐまれず、微熱を出したり腹をこはしたり痔に悩んだりしてゐます。 + +子供達はお蔭で三人揃って元気です。○○(母)、□□(次姉)、おりく(私・仮名)の三人は先月末十日ほど住吉へ行ってゐまして、昨日、お母さん(母方の祖母)に送られて帰って来ましたので家の中急に賑やかになりました(この手紙は京都市高辻烏丸西の木綿問屋兼居宅から発信)。 + +△△(長姉)は今度お留守番に廻りましたが、けんくわ相手の□□が居らぬと とても大人しくて一寸したお手伝ひもします。先日 おばあさん(父方の祖祖母)のお使ひで、五十銭札を持って煙草屋へ”響”を買ひに行きましたところどう聞きたがへたか、ヒカウキを下さいと云って五十銭札を出したらしく、 + +煙草屋のをばさんにヒカウキは五十銭ではつくれませんと云はれたと云って帰って来たので大笑ひでした。 いつの間に覚えたか、折紙でカブトを折ります。お父ちゃんカブトおしへてあげようといふものですから うんうんといひかげんに一緒に折ってゐたのですが、 + + だんだん折ってゐるうちにカブトらしくなってくるのでコレハコレハと驚いた次第です。それで今度は△△にオルガンを教へてやりました。それでこの二つの△△の作品をここに同封でお目にかけます。□□が帰って来た当座はやはりなつかしいものか、二人で頭をくっつけあって仲よくしてゐましたが、しばらくするともうお互ひの所有権を主張しあって一つのものをひったくりなどして わんわんさはいでゐます。 + + △△はおりくをとても可愛がります。□□はまだ甘えたい気持ちあるのでおりくを抱いてゐると抱けと云ってやきもちをやきます。残暑きびしい折柄 健康にご注意下さい。 八月十七日 父の名 叔父の名 + +この手紙を読むと母乳不足で成長が遅れがちな赤ん坊の私は結構可愛がられていたようです。
2018.08.16
コメント(0)
-

言葉の変遷♪
〇「ヤバイ」という言葉が新旧両方の意味で使われ、同時に飛び交う局面に居たとすれば、理解する側は大変。古語でも「なかなか」という語は、中途半端、なまはんか、かえって、とうてい、かなり、その通りという具合に時代によって意味が変化しています。全然という単語もつい最近までは否定的な意味を持つ言葉を誘引する使い方が主流であったものが、程度を表わす用法となって肯定の言葉を伴うようになりつつあります。平成10年3月第3版発行の鈴木棠三著「日常語語源辞典」(東京堂出版)は父が亡くなる1、2年前に購入したと思われますが、俳句を嗜む者として言葉の語源を知っておくべきと父も考えていたのでしょうか。鈴木棠三氏は中世から近世の庶民生活風俗研究家のようで諺や語源に明るい人。興味あるジャンルの書を沢山書いておられます。太古の頃に生まれた言葉が万葉、平安、鎌倉・・・と時代を経て表現が直されたり、或いは埋もれてしまったり、逆に新語として根付き現代に及んでいるなど、言葉の歴史が日本歴史の一面を物語っているようです。幸い、この本は五十音順にならべてあり、愛敬、相槌、敢えて、青、あかぎれ・・・と続き、田舎、稲妻など、どれ一つをとっても面白そうな内容です。俳句という十七文字の芸術・文学に身を置く者として、日本古来の言葉を知ることは、いわゆる温故知新を地で行くものと思われます。毎日少しずつ味わってみる積りです。
2018.08.15
コメント(0)
-

言と事とは切り離せないもの♪
〇万葉集を繙けば 志貴島の日本(ヤマト)の国は事霊(コトダマ)の 佑(サキ)はふ国ぞま福(サキ)くありこそ <人麻呂> 神代より言伝て来らく虚(ソラ)みつ倭の国は皇 神(スメガミ)の厳(イツク)しき国 言霊の幸はふ国と 語り継ぎ 言ひ継がひけり 今の世も 人も悉(コトゴト)を 目の前に知りた り <憶良> 柿本人麻呂も山上憶良も日本という国は言葉の 霊が幸いをもたらす国だと語り繋いできたことを 詠っています。 豊田国夫氏は「古代社会では 口にしたコト言 は そのままコト(事実・事柄)を意味したし、また コト(出来事・行為)は そのままコト(言)と して表現されると信じられていました。 + + それで、言と事とは未分化で、両方ともコトとい う一つの単語で把握された」と述べられています。 + + 若い女性向きのファッション雑誌のモデル達が 使う行き過ぎた 「簡略ことば」は、先人達が培って来られた日本 の「和ことば」、特に語彙の多さを崩してしまう 破壊行為、日本の文化を損なう元凶そのものでし ょうね。
2018.08.14
コメント(0)
-

バブル時代の再到来?民放浮かれ過ぎかも♪
〇もの申す。今日のテレビ放映では、芸能人やお笑い 系のタレントが 一切れ5千円もするような上等の食材を口にほおばり、 それをUPで捉えます。 我ら茶の間の者や会場のお客に対し、これ見よがしに 勝者側としての栄誉・ご褒美を無頓着に放映していま す。 テレビ局のディレクターやそれを許す重役連中に良識 という意識が欠如しているのでしょうか。 一方で貧乏生活も良いもんだというような番組を拵え、 まるで勝者と敗者の対比のような番組を放映していま す。 こんな日本に変わったのは、テレビ画面を巧みに利用 しマジックで国民を導いた小泉政権の産物ではないで しょうか。 莫大な広告代金を徴収し、その豊かな金銭面の資源 をバックに、 一種の<成金王国>が形成されているゆえ、あのよう に物事への良識ある尺度を失ってしまっているのでは ないでしょうか? 女子アナウンサーの大半はタレント化し、冷静さを欠 いた素顔でのはしゃぎっぷり。 + + NHKの体質に問題がない訳ではないと思いますが、 矢鱈高額な広告料を大手の企業に要求し、 元禄文化みたいなお祭り騒ぎの視聴率最優先の番組に バブル時代の再現なのかなと、ふと、思うのです。
2018.08.13
コメント(0)
-

阿波踊りに寄せて♪
〇400年の歴史を誇る本場の阿波踊りは大幅な赤字を抱え、また内紛めいた衝突もあるようですが、想い出話を綴ります。昭和54年の夏だったか、同僚の徳島出身のK君の誘いに応え、阿波踊りの時節、彼の実家に2泊。 + +実は、万国博覧会が終わった年、本場の阿波から指導に来られ、銀行の本店営業部の一部の人々が教えて貰い、万博会場で踊ったことがあった経緯もあって応じた次第です。 + +男舞の基本は、身のこなしの軽やかさにあり、泥棒の抜き足、差し足を真似れば良いと思っていたので、その様に舞いました。一方、女舞は腕を斜め上方に伸ばしながら指先で表現すること、そして足のバネを活かせて踊れば良いと思い、あの晴れがましい観覧席通りにて、尻からげした浴衣の裾を下ろし、女舞も披露しました。 + +また、名だたる団体は、飛び入りなど受け入れてくれませんので、学生の団体連に加えて貰って、男舞、女舞を一人で演じました。長い道のりでしたから、息が切れかかったことを覚えています。
2018.08.12
コメント(0)
-

さるすべりは空のかんざし♪
〇連日続く猛暑の中で、わたし達の目を癒し、こころを和ませてくれる植物に、百日紅がありますね。たまにどっち着かずの薄色のものがありますが、ほど良いピンクは優しさを、濃い目の紅は強さを象徴しているかに見えます。あの桃色の花は、仏教で言う輪廻に似ていて、新しい花が生まれては落下していきますが、あのあどけない塊を、”空の簪(かんざし)”と詠んだ句もあります。初夏から晩秋近くまで咲く忍耐強い花で、恰も大和撫子、日本女性そっくりの”しなやかさ”です。数年前に植えた百日紅、まさに私の観音さま。 + +なお、輪廻転生をテーマにした創作落語は近日ご披露致します。
2018.08.11
コメント(0)
-

本拳・虎挙・じゃんけんぽん♪
〇何か事あるごとに順番や勝ち負けを決める手段として登場する便利屋が「じゃんけん」。 + + 中国では「拇拳」とか「酒会」と呼ばれ、二人が向き合い、掛声を掛け合いながら手や指先の形を変えて勝負を争う、言わば酒宴での座興で「本拳」と言われました。 + +江戸の元禄初期に我が国に伝わってきたようですが、派生して「藤八拳」とか「虎拳」、「虫拳」などに変化、現在の「じゃんけん」へと移り変ったようです。 + + 藤八拳は庄屋、キツネ、鉄砲が三つ巴で競う仕組み。定かではありませんが、祇園茶屋遊びのじゃんけんに相当するのが「虎拳」なのかも知れません。 + +中国の本拳はペルシャを経てイタリアに移り「モーラ」に変わったようで、右手の親指、人さし指と小指の三本を使い、親と子に分かれて行うとか。三本のうち一本出し、双方が同じなら親の勝、違えば子の勝ちで、親は三回、子は続けて勝つことが条件だとか。 + + 中国では「三すくみ」の原理で、蛙は蛇に恐れをなし蛇はなめくじを怖がり、なめくじは蛙を恐れるという言い伝えが源のようです。これを拳に取り入れたのが「虫拳」、それが石と紙と鋏の形になって「石(ジャク)拳」となったという次第です。 (参考図書:「日本人の知恵」中央公論社)
2018.08.10
コメント(0)
-

手役、出来役の妙、花札♪
〇正月や夏休み期間、わが家には親戚が集まり、大人も子供も興じるものは花札。用意するものは花札2組(茶色地、黒地)、金物製の点棒入れ、麻雀の点棒や土で拵えたカラフルな達磨さん(小指の爪より小さい)、記録簿、手役出来役一覧表。 + + + 3人で行い、一月から十二月までの12回でひと括りになるのですが、3人を超える場合は、配られた手札と相談にらめっこの上、親から順に降りることが出来ます。降りる(ゲームからリタイヤ)場合は、親が罰金10円、親の隣は20円と順に増えて行きます。 + + + 例えばのっけから5人で花札を開始した場合、7枚づつ5人に札を配られますが、この状態で手役という役(並札ばかり6枚に10点札が1枚とか、くっつきと言って麻雀のニコニコみたいな、その他沢山の役があります)があって、親もその隣も、そのまた隣もゲームに参加する意思を表示したら、残り二人は止む無くゲーム不参加になるのですが、この時、手役があれば、面前で公開して、手役の点数を他の者から貰うことが出来ます。ゲームを進行して、その途中で作った出来役、20点札4枚の四光、5枚の五光、そして赤い短冊を3つ(松、櫻、梅)、或いは青い短冊(牡丹、菊、紅葉)を3つ揃えたら出来役としての点数を他の二人から徴求できます。手役は配札による運の如何ですが、出来役は、それが完成するのを他の二人が協力したり、或いは裏切ったりしながら阻止する訳です。シンプルなルールゆえ、返って頭脳ゲームとしての面白さがあるのです。ゲームに興じながら、相手のキャラを冗談でディスったり・・・などで、洋間は賑やかな話声と笑いに包まれていました。これらの思い出は、わが実家の歴史に例えれば、青春時代のような華やかな時代でした。
2018.08.09
コメント(0)
-

『お経 浄土宗』藤井正雄著(講談社)から♪
〇〇〇「懺悔偈(サンゲゲ)」 我昔所造諸悪業(ガシャクショゾウショアクゴウ) 皆由無始貧瞋痴(カイユムシトンジンチ) 従身語意之所生(ジュウシンゴイシショショウ) 一切我今皆懺悔(イッサイガコンカイサンゲ) + + 私たちが長い間犯してきた罪過(ツミトガ)は昔から心の中にもっているむさぼり、いかり、愚痴といった迷いが私たちの身体と言葉と意(ココロ)を通して現れたものです。いまみ仏のみ前に心から懺悔いたします。 + + この本にはこの他、香偈、三宝礼、四奉請、歎仏偈、三尊礼、開経偈、無量寿経四請偈、本請偈などのお経のほかに、年中行事、仏事の基礎知識が、懇切丁寧に書かれています。日本人である限り、お寺やお経と無縁で居られる道理もありませんので、偶には、お経や仏教に触れてみるのも良いと思うのです。
2018.08.08
コメント(0)
-

西陣空襲の爆弾破片と山中油店♪
〇外回りの折、お客様からお聴きしたことの一つに千本下立売近辺に空襲があって大きな被害があったという話でした。昭和20年1月16日東山区馬町にB29が爆弾を落としたのを皮切りに、3月中旬右京区、4月中旬に2度(右京区と北区)、5月半ばに上京区と右京区に。そして6月26日早朝、上長者町通、下立売通、大宮通、浄福寺通に囲まれた地域に7発の爆弾が落とされ、死者50人、負傷者66人、被害家屋が300軒近くに達したようです。軍部からの制圧で正しい情報が伝えられなかった事情が当時にはあったようです。それから恐ろしいことに、原爆投下の第1番目の候補地が京都だったとは驚きです。 + +新規先として度々訪問していた油問屋の「山中油店」には油絞り器のほかに、西陣空襲の爆弾の破片も飾られているようです。(参考図書:「京都の不思議」黒田正子著)
2018.08.07
コメント(0)
-

噴水に寄せて♪
〇子供の頃から慣れ親しんできた噴水。住宅街にある噴水、植物園や公園にある噴水、ビル街の一角にある噴水、催し会場内に設置された噴水、随分いろんな噴水に接して来ました。大阪は吹田市千里山住宅街ロータリの芯にある噴水。都銀への就職内定したので、大の大人が小学生に混じって算盤を弾いていました。 大阪花の博覧会では、わが銀行グループが、舞台に人形の指揮者にタクトを振らせ、音響と光の噴水を演じるコーナーを設けていました。大音響と光の織り成す噴水の世界・・・これは現代風で、それなりの意味がありました。噴水の水しぶきの中に多量に生まれるマイナスイオン。それが人々を癒してくれます。やさしくなれるから、恋人同志が愛を語るのにも相応しい場所なのかも。
2018.08.06
コメント(0)
-

地球解明、南極の氷♪
〇某年の京都新聞の「凡語」欄には、涼しい氷の話題が載っていました。<グラスに弾ける太古の大気。意外に大きな音に驚いた記憶がある。かつてスーパーでも簡単に手に入った南極の氷が懐かしい。オンザロックが一段とうまかった。>と筆者が記して居られる。彼の地は人類共有の財産として、鉱物資源活動の禁止や環境の保護などが徹底され、南極大陸から持ち帰ってよいものは氷だけ。この氷は数万年前に降り積もった雪が凍てたもので、太古の空気を孕んでいるが故に、”大気のカプセル”と呼ばれているそうな。南極大陸には地球全体の空気が集まって居、平均の厚みが二千メートルを超える氷層は、地球の歴史を解き明かす宝庫とも。ドームふじ基地の深さ三千余メートルの氷床から掘削された氷柱は凡そ百万年前のものと言われ、その分析による地球の歴史の解明は楽しみの一つです。
2018.08.05
コメント(0)
-

義祖母の旅日記♪
(画像はイメージ、借り物)〇30余年も前、96才で没した義祖母の高等女学校時代の旅日記や明治・大正時代の古い写真などが大切に残されている段ボール箱を見つけました。宿題として提出したものもあれば、青春の想い出となるよう自主的に遺したものも沢山あって、全てが和綴じ、半数は鮮やかな岩絵の具を配した、日本画法の代物です。 「鎌倉の一夏」は幾つかの家紋付きの陣垂れ幕に白鳩数羽が描かれて居り、綴じものの裏側まで続いています。 + +「序」には<春も花と共にいつしか去って梢のみどりもいとふかく夏も今やたけなはとなった><この楽しい休暇を歴史にゆかりの多い鎌倉ですごす事となった・・・明治44年之夏 由比ガ浜小波の音をきゝつゝ サイン> + +30数頁のものですが、7月22日~8月末までの数日を取り上げ、流麗な毛筆の文章の合間には、旅館の窓から眺めた海や島のカット、雷雨に番傘の人、ごつごつした巌の島、家屋を黒塗りにした夕景、簾と風鈴、神武寺や極楽寺など絵心のあるカットが適宜つけてあります。「もみぢの多びの記」いかにも山麓を思わせる構図に紅葉と幹だけの表紙。この日記はかなり気合の入った筆遣いで、びっしり詰まった文章は、ところどころ太めの文字を配してあるので、すこぶる見映えのする出来映えです。 + + 大正2年の京都紀行文は”日記のあらま志””比叡山へ”<・・・清きながれの音また百舌鳥の群などきゝつゝやがて我等がくるまは八瀬の宿に着きぬ>”四明ケ嶽にて””のりば””小督の局の阿とを訪ふて””祇王寺”<・・・嵯峨野の奥の祇王寺に訪れぬ、竹やぶの中なる苔の細道を落葉ふみて登る事志ばしにして小さ紀その屋根の門にたどりつきぬ、つと入りて・・・片折り戸をたゝけば老いたる尼僧一人いで来りてわれを迎へぬ>こういった雰囲気の和綴じ本ですが、明治・大正期の子女には古来日本の習い事が身に沁みていて、戦後教育のわたし達とは雲泥の差のあることを感じました。
2018.08.04
コメント(0)
-

台風に姿あるごと予報聞く 吉田すばる♪
〇今年はかつて無かったような転変地変による被害の年ですが、以下は2003年に綴ったもの。 台風に姿あるごと予報聞く 吉田すばる 〇 〇 沖縄、九州を襲った台風は今夜半関西に到達するという。折りしも亡父の詠んだ台風の句があったので紹介したい。二百十日の頃、日本人は大なり小なり、この招かざる客が、逸れると言えば一喜、襲うと聞けば一憂する。そして頼りにするのは天気予報。受信料支払いに多少の不満はあるものの、この時ばかりは、NHKさまさま。ラジオで聞いても、テレビで見ても、台風という姿、形ある生きもの、魔物のように擬人化して捉えてしまう。風神に非ず、昇竜にも非ず、漠然とした中にまるで意思を持った生きもののように錯覚する。・・・被害の出ないことを只管祈るのみ。
2018.08.03
コメント(0)
-

舞台に観る夏の宵♪
〇暮れ行く夕景は何と言っても、夏の宵ですね。子供の頃、亡父に連れられ歌舞伎をよく観ました。舞台で演じる役者さんの芸の力量は尤もながら、舞台装置に携わる陰のスタッフの技も楽しめますね。 + +私は今頃の夕方の空が好きなンです。淡いブルーから次第にコバルト色に移り行き、 歌舞伎の舞台では一番星を追っかけてあちらで一つ、こちらに一つ、星が黄色に輝き始めます。 + +まるで、空に星型の挟みで剪り取ったような星(舞台ではどんな手法を使っているのだろう)が十(とう)、二十と増える頃には、夏の空もすっかり深い藍色になってしまいます。 + + 宵空の濃くなりゆけば蝉止みぬ 吉田 星子
2018.08.02
コメント(0)
-

祭笛吹くとき男佳かりける♪
〇亡父の新聞の切り抜きにある高橋治さんの文章、挿絵は色鮮やかに風間完氏(青春の門の挿絵の人)。宝物にしたいような素敵なシリーズです。本文は全てわが拙文です。 祭笛吹くとき男佳(よ)かりける 橋本多佳子 普段パッとしない男だが、紺色の浴衣を着て、首をかしげるように一心不乱に祭笛を吹く様は、男の色気を感じさせる。 顔寄せて団扇のなかの話かな 下田 実花 寄り合いの席や夕涼みの縁台に並んだ女性同士の秘密めいた話。表情が隠れてしまって尚更気になる内緒ごと。 身にひしと乙女の頃の水着着る 赤松 恵子 脂肪がのった身体に無理やり通した水着。ひしとの一語に女性の覚悟のほどが表現されている。 手加減のなき夫のあと泳ぎ行く 成田 清子 男の身勝手さをよく捉えた句。 単衣きりりと泣かぬ女と見せ通す 鷲谷七菜子 夏浴衣の女性は美しい。日本の女性は栄養が足りているのか、欧米並みにグラマーな体形になった。残念なことに、着物はズンドウに近い、細身の小柄な女性の方が似合うとは皮肉なことである。 籐椅子の飴色の艶母屋かな 吉田 星子
2018.08.01
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1