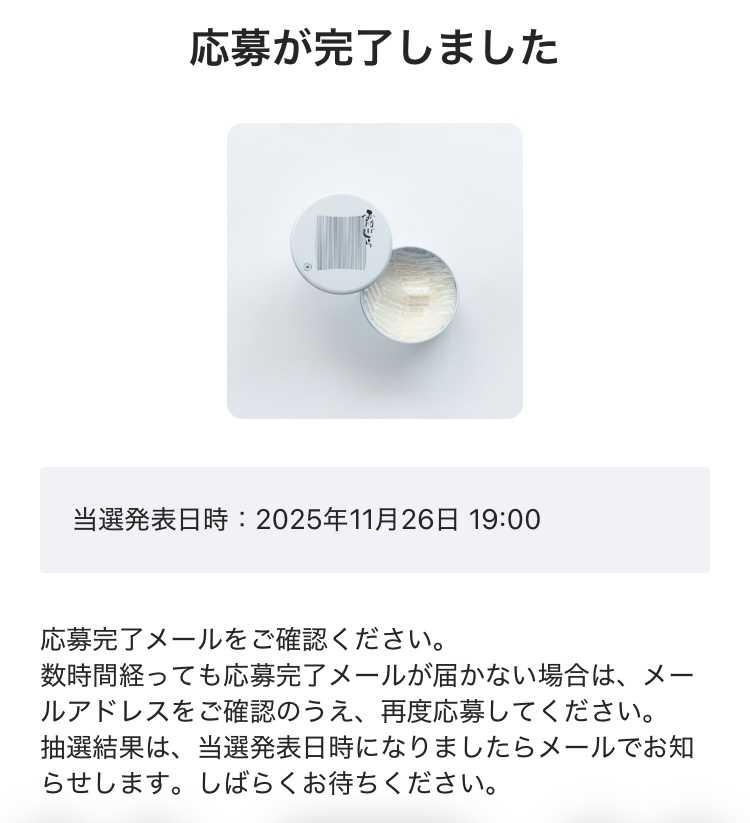2018年09月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

怨霊の歴史♪
〇神を祀る所は、通常は神社、天皇家の場合は神宮と称するようですが、天満宮の道真公、水無瀬神宮の後鳥羽院の御二人には共通点があって、お亡くなりになった後、転変地変、要人の相次ぐ死亡が生じ、これはきっと呪いの所為だと身に覚えのある執権者がお祓いを施し、しかるべき格を与えて慰撫しています。+ 道真公は時平公の讒言により太宰府に流され、汚名の回復と都への帰還を切望されながらも59歳で亡くなりました。ところがそれ以降、<都に打続きて災ひあり。或る時は雷電霹靂して世の中暮れふたがり、雷の音に多くの人肝たましひを砕きて、死に惑ひなどしけり。・・・そのたたりなる由沙汰せり。・・・鴨川の洪水にはかに落ちて、陸地の如くになりて・・・菅根朝臣は蹴殺され給へり。・・・三月時平公心地悩み給ふに、様々の御祈りの験なく三十九歳にて薨じ給へり。時平公の御女の女御・御孫の東宮・時平の一男八条の大将保忠郷・その弟の中納言敦忠なども、次々にみまかり給ひしかば時の人これらをも菅公のたたりなりといひ騒げり。・・・道真公を本の位に復し、正二位を贈らせ・・・四人の御子の流罪を許され・・・>+ また後鳥羽院は隠岐の島で没する前に2枚の遺言書を遺され、一つは時の幕府の執権者らを呪ってみせる旨記され、もう一つは部下に自分の別邸水無瀬にてねんごろに菩提を弔って欲しいと書かれています。鎌倉幕府の執権者も室町時代も、織田信長・秀吉・家康に至るまで、水無瀬に関して、執権者は一切関わりを持たないようにして今日まで来ました。 わが国の歴史には皇室の継承権や政治の実権を巡り、怨嗟・呪い・祟りの暗い一面も残されているのですね。
2018.09.30
コメント(0)
-

元宝塚スター桜緋紗子は尼の道へ♪
〇太閤秀吉に世継ぎの秀頼ができたことで、関白の地位を剥奪され、高野山に追いやられた後、切腹させられた秀次公。太閤の姉で秀次公の母である智が、子や孫の菩提を弔う為、嵯峨二尊院の傍に寺を建て、のち後陽成天皇からの加護もあって村雲「瑞龍寺」と称して日蓮宗では唯一の門跡寺となりました。+昭和38年、寺は秀次公ゆかりの近江八幡に移りました。その後、途絶えていた門跡を継いだのが旧小倉藩主小笠原長幹の五女松子(12代、日英尼)。+ 父が遺した昭和42年1月31日付京都新聞夕刊には、「尼僧姉妹」と題して5枚の写真入りで、近く行われる普山式のことに触れ、また義妹の元宝塚スター桜緋紗子さん(英法尼マタ日鳳尼)の事にも言及しています。12代日英尼の後を継いだ日鳳尼も9年前の3月20日に遷化(逝去)するまで瑞龍寺の復興に寄与された由。
2018.09.29
コメント(1)
-

戦前のエコカーって?
〇環境問題がクローズアップされるに伴い、エコカーの増発に拍車がかかりそうな気配ですが、「新聞と写真にみる京都百年」岡満男編(東洋文化社)の昭和編の”全国初のメタンガス自動車”という見出しが目につきました。京都日出新聞、昭和17(1942)年2月14日の記事で、<戦時下ガソリン代用として、さっそうと登場した市ご自慢のメタンガス自動車が13日からいよいよ市民の足として皆さんにお目見得した。>という紹介で、それは始まり、鳥羽下水処理場汚泥消化槽から発生するメタンガスを高圧縮ガスとして転用。+ 竣工式には安藤知事(代理)初め加賀谷市長らが出席、みどり色の衣裳を着たメタン嬢さんが下水処理場内のガスステーションからパイプで自動車のタンクに注入、エンジン音も軽やかに車が発車。+ 木炭車は、焚きつけ準備、悪臭、後部座席の蒸し暑さという難点があったのですが、ガソリンに比して何ら遜色の無いこのメタン代燃車に主力を注ぎ、バス15台、乗用車12台、トラック15台の利用を定着させる運びとなったようです。現在、この種の開発がいろいろ試行されていますが、戦前の京都で既に導入していたことには驚きですね。
2018.09.28
コメント(0)
-
桂米朝師匠談♪
〇10数年前に刊行された『米朝よもやま噺』は貴重な話が満載されています。80過ぎになられてからラジオ番組をお持ちになり、05年(平成17)9月から07年9月までの放送で米朝さんの語られたことを本に纏められたもので、第3節では、昔の寄席を彩った色物(落語以外の芸)での変った芸人さんに触れておられます。奇行の多かった松葉家奴さんの魚釣りの踊りの妙、立花家扇遊さんは「蝿とり」というトリモチが顔に着く踊り、表情、左右の目が別々に動かせる芸、東京大空襲の時、ご夫婦手を繋いで亡くなっていたとか。三亀坊さんの立体紙芝居はでは、道ゆく立体の馬(実際には糸でぶら提げる)がだんだん小さくなり、最後は米つぶ程に小さくなるなど。小松まことさんの「後ろ面」の舞踊、この人かどうか不詳ですが、私もひょっとこおかめの踊りは見たことがあります。5代目松鶴師匠さんは「上方はなし」という雑誌を足掛け4年、49巻出され、その復刊本は上・下巻で今や15万もする高値のようです。その編集を手伝ったのが、米朝さんの師匠4代目米団治さんで、編集や落語では儲からないので別途、代書屋もしておられ、その経験から新作落語「代書」が出来たのだそうです。<儲かった日も代書屋の同じ顔>
2018.09.27
コメント(0)
-

再び平安期の宮仕え事情♪
〇競争激化の現代社会に於て宮仕えしておられるサラリーマン、OLの皆様、ご苦労様です。人事部による昇級や転勤の知らせはドキドキ致します+平安時代も春・秋の2回、除目(ジモク)と呼ぶ人事異動の節がありました。役所の人事リストである目録に、新たに名を書き加えて貰えないと就職の機会は皆無。就職希望を記述する「申し文(申請書)」には、役人の心を打つ内容、美しい書体、文章は無論の事、知人・友人、後宮に勤める女房や親戚縁者のコネが有効。 また除目は勤務評定の場で、本人の家柄、宮廷の序列、勤務年限とその成績などが論議されたようです。+ 源氏物語の作者で有名な紫式部の父・為時は優秀な国学者でした。10年もの間、無官で過ごした後やっと任官しましたが、希望していた越前守ではなく、気乗りしない淡路守。無念な思いを詩作し某女房に託して一条天皇へ。人事権を持つのは、天皇、摂政、関白、左大臣、右大臣の順で、天皇は非常に嘆かれた。それをしった道長は、一旦推した源国盛の越前守を取止め、新たに為時にすげ替えたようです。+今度は国盛がショックの為病気になり、秋の除目では播磨守に任じられたものの病気が治らぬまま、没したという逸話が残っています。(参考文献・藤川桂介著「暮らしの歴史散歩」)
2018.09.27
コメント(0)
-

握手が一日の始まり?
〇ドイツ人の特徴と言えば、先ず朝の挨拶、しかもそれは握手で始まりますから、職場などでは大変、兎に角顔を合わせたらお互いに目を見つめ合いながら握手し、グーテン・モルゲンおはようと挨拶するようです。+この握手なる仕草、今では各国に浸透しつつありますが、元来、彼らはゲルマン民族の流れ。手に武器を持っていない証拠を示し合う為に行ってきた風習がそのまま名残となっています。+ 同じ部屋にいる全員と必ず握手するのだから、その日初めて見かけたら、相手が電話中でも、打合せ中だろうと、必ず近寄ってきて手を差し出すのだそうです。国民性が日本に似て律儀だから、握手に手は抜かないから、時として大きな手に包まれる時突き指などもしかねません。突き指しない工夫として、こっとも負けじと強く握り返すのがコツだとか。国民性とは言え、握手に要する時間を仕事・作業に回せば、もっと彼らの生産性が上がるやも??
2018.09.26
コメント(0)
-

頭脳パズル♪
〇頭脳強化パズル製作委員会編「頭の良くなる漢字パズル」から。 1)~5)のグループの漢字は、それぞれある共通の部首を付け足すと、違った漢字になります。その部首を下のa~eから選らんで下さい。1)公・毎・主・反・白 2)化・秋・西・田・牙 3)兄・土・鼻・垂・今 4)次・有・曽・乏・加5)日・口・耳・各・活 部首)a門 b口 c木 d貝 e草 程よい脳の訓練ですね♪
2018.09.25
コメント(0)
-

平安時代の華やかな職場♪
〇最近目につく働く女性と言えば、私鉄・市バス・タクシーの運転手、婦人警官、婦人自衛官、議員などが挙げられますが、平安時代の女性の職場環境について藤川桂介さんの「暮らしの歴史散歩」を参考にすれば、次のような事が言えそうです。 律令制では官僚数が総数12506人、うち男性が11712人、女性は6%の794人に過ぎない男社会でした。それでも藤原道長の時代には、娘彰子が宮中に入った折には40名もの女性が従い、ライバル中宮定子にも40名の女房共が支えていた事から、時の帝、一条天皇に従う女房の数は200人、天皇の妃でない人に仕える者を考慮すれば、300人ほどの女性の働き口が別途あったとも言えそうです。+この他例えば和泉式部のように、上流の男性貴族に仕えた女房も多くあったし、その女房に仕える女性も居たので、所謂、官僚としての女性(勤続28年、80余才で没した従三位・内侍司など)の数に匹敵し、併せて1600人ほどの女性が働いていたものと思われます。中央部では最下級位の父のもとに生まれた紫式部は、同じ身分の宣孝と結婚し賢子を授かったものの、夫を早く亡くし、中宮彰子の後宮に勤め、後に上東門院に出仕して生計を立てていたし、人生探索の目的で女房となった清少納言や、社交界に出さえすれば婚活となると願った「更級日記」の作者・孝標の娘など、様々な彩の宮廷なのでした。
2018.09.24
コメント(0)
-

清水寺と鳥人間第一号♪
〇京都の観光地としての人気スポットの一つは清水寺。大きな覚悟で以て事に当たるとき、「清水の舞台から飛び降りる」と言いますが、最初に飛び降りたのは誰でしょう?八幡和郎さんの「京都のナゾ?意外な真実!」に依れば、それは「宇治拾遺物語」にあるとか。+ 平安時代には千手観音のお膝下で僧侶たちの読経を聞き、仮眠をとりながら一夜を過ごすと、朦朧とした意識のなかで見る夢は実現するという習慣がありました。+宇治拾遺では、そんな風雅なものではなく、或る若者が数人相手に喧嘩沙汰を起し、多勢に無勢で清水寺に逃げ込みましたが、とうとう舞台に追い詰められました。+万事に窮した彼は、やおら傍らにあった蔀戸を両脇に抱えて、清水の舞台から向こうへと飛び出し、あっけにとられている追っ手を後ろ目に、しばらく滑空して首尾よく麓に着地した、日本人としては”鳥人間第1号”だったという話です。
2018.09.23
コメント(0)
-

母嫁入りの桐箪笥の♪
〇平成19年、俳誌千号記念の年、結社恒例の大祭に 坪内稔典さんをお呼びし、講演して戴いたことがあり ます。 氏は柿とカバの話がとってもお好きなようで、「昔、 農家に嫁入りするときには、柿の苗を持参し、それを 嫁ぎ先の門近くに植え、 本人が亡くなった折は、その柿の樹でお棺を作り、葬 ったものです」というようなお話をして下さいました。 + 幸か不幸か、大阪市助役の長女であった母の嫁入り 道具は、そこそこ高価なものであったと思われます。 + 木綿問屋の息子と生まれながら、早々に家業は継がず サラリーマンになると宣言した父は、 住友財閥に入社、保険部門の仕事に就き、何かと転勤 が多いようでした。だから、 京都の父の生家には母の嫁入り道具の桐の箪笥や長持 ちなどが倉庫代わりに保管されていました。 + 祖父が亡くなり、それから四半世紀後に祖母が亡くな り、お仏壇をこちらに引き取ると同時に、 長年預けたままだった母の桐箪笥もこちらに戻ってき ました。 最初は焦げ茶色していましたが、洗いに出すと、新品 同様になって、上等だなと思われるものに大変身。 + 抽斗の鍵隠しの金物には家紋が彫金されており、深い 草色木綿の油単にも家紋が白く染められて いました。 小抽斗を開けて再びそれを押し戻すと、三段の別の抽 斗がすうーっと飛び出て来ます。 + まるで手品のようなので何度も何度もそれを繰り返し、 ようやく出っ張りは鎮まりました。 当時の指物師の粋を子供心ながらにも感じたように思 います。
2018.09.22
コメント(0)
-

手間暇かけてこそ♪
〇読書の秋。先日或る番組で日本の児童が本を読まなく なった現象を数値的に明らかにし、 その原因の一つに親が読書しなくなったからと分析して いました。 スイッチを捻れば面白い番組が音と画像付きで報じられ るのだから、つ いつい時間を忘れてピノキオになってしまうのも無理か らぬ話です。 子供の頃漢字一つを覚えるのにザラ半紙に何遍も繰返し 書きなぐって暗記したものですが、 最近はワープロやパソコンという文明の利器がある為、 読む力は残っていても書き取りの能力が劣化している事 に驚いてしまいます。 + テレビよりはラジオ、ラジオよりは書物に書かれた文章 の流れから、 主人公の顔だちや声質、或いは景色などを自分の想像の 世界で自由に羽ばたかせたいものです。 + 俳句の世界は僅か十七文字で一つの光景を演出する芸 術ですから、思えば私たちは大それた事に挑戦している ようです。 クラシック音楽や美術・工芸、舞台芸術などから得た感 動を雑記して置く手間さえ惜しまなかったら、後日それ が一つの句として生まれ変わる事でしょう。 またお互いの感性に磨きを掛け合うような友垣も大切 にしたいものです。
2018.09.21
コメント(0)
-

『百人一首一夕話』♪
〇尾崎雅嘉の綴った「百人一首一夕話」は面白いです。 百人一首の歌を楽しみながら日本の歴史や有名人の逸話 に接することができます。 天智天皇、持統天皇では、皇族継承にかかわる史話と木 版画などが添えてあります。 さて菅家と言えば全国津々浦々に天満宮として祀られ ている菅原道真公のことを指しますが、菅家の前文紹介 として <菅原の姓はもとは土師(ハジ)なりしが、土師古人とい ふ人、 光仁天皇の御時大和国菅原の里に居す。よって土師を菅 原に改む。・・・>とあります。 私の姉の親友にも旧姓土師という朗らかな女性が居ら れます。 九州は佐賀市に私たち家族が2年住んでいた頃からの学 友です。土師という苗字から察するに、帰化人の末裔な のでしょうね。 (菅家の話)という逸話部分は、先ず賢明な醍醐天皇の 御人格に触れた後、 そんな帝であっても道真公と時平公の争いに気づいてい らっしゃらなかったと書いています。 藤原時平と言えば歌舞伎にも度々登場します。「菅原伝 授手習鑑」でお解りのように銀粉を塗ったような悪相で 登場します。その悪逆の一例を紹介しています。 + 「現在の世で一番の美人は誰だろうか」と宴会の最中に 彼が問いますと、平貞文という者が、 「そりゃ~、殿(時平)の伯父大納言国経卿の奥方でし ょう」と答えました。 これを心に留めた時平は後日、方違えと称して国経卿の 家に夜分立ち寄ります。卿は時の権力者の訪問を名誉な 事と大喜び歓待します。 宴会の席で卿から時平に上等の琴を引出物として献上し ましたが、 それよりも奥様を此処にお連れ下さいと頼みました。い と容易い事と国経卿は応じましたが、卿が酒に酔ってい る隙に、 この奥様を引出物に戴くと言って車に乗せて帰ってしま いました。 深酔いの国経卿がひと眠りの後、奥は何処?と家臣に聞 けば、先ほど時平公にご進呈なされ、連れ帰られました と聞き及び、悲嘆に暮れたという話。 + 実はこの奥様、在原業平の孫で在原棟梁(ムネヤナ)の娘に 当りましたが、時平公の家に来られたのち、子を産まれ た。それが中納言敦忠なのです。 逢ひみての後の心にくらぶれば 昔は物を思はざりけり 尚、菅原道真公の御歌は この度は幣(ヌサ)の取りあへず手向山 紅葉の錦神のまにまに 百人一首の親戚の流れ・繋がりはガイドの資料として もこの本は興味深いものがあります。
2018.09.20
コメント(0)
-

日野草城が記した「京鹿子」創刊時の会計♪
〇俳句結社「京鹿子」の月刊俳誌が発行されて丁度千号になったのが平成19年の12月号。それを記念してA4版479頁の1000号記念誌が手元に届いたのが20年の5月。その実行委員会のメンバーを経て、現在は「京鹿子」誌の編集を任せて貰っています。+ 話は19年12月号に戻ります。表紙裏の上段には「京鹿子 収支明細簿」と書かれた大学ノートの表紙。下段にはその1頁目、創刊号の収支が左右にきちんと書かれています。+千号の1頁は高木智さんの手によって写真への説明が加えられています。そのまま載せますと、 <何事にも綿密な仕事をした日野草城は、大正9年11月に「京鹿子」を創刊した時、自分の担当した3年分の経費の明細簿を、残している。それによると、+ 創刊号は、収入の部が、岩田紫雲郎3円、田中王城、鈴鹿野風呂各5円、学生の高濱赤柿、草城、中西其十がそれぞれ1円の合計16円。支出は、印刷所支払9円50銭、送料切手1円で、残額5円50銭となっている。この創刊号は150部印刷された。>とあり、+ わが家にも創刊以来の月刊誌が父すばるの手によって遺されていました。現在の発行部数は最盛時を大きく下回りますが、毎月20日過ぎから翌々月号の編集準備に着手しています。
2018.09.19
コメント(0)
-

脳トレーニングはいかが?
〇昔懐かしい日本テレビ、頭脳パニック編「マジカル頭脳パワー!」第2集からの出題です。 第1問 あ る な い おり 牢屋 目 歯 ショー ステージ これだけのヒントでわかりますか? 要は左側のことばに何かを足せば良い。 森 湖 くさい におい 毛 ヘアー もうすぐ解りそう ガンバ! 都市 シティー 区立 私立 立つ 座る はい、”こ”をつけてごらん氷、米、胡椒、子守り・・・・ 第2問 ツボ ビン 植木 鉢植え 柵 塀 右側は一切見ないで・・・左側を声出して・・・一息に・・・ リップ 口紅 リズム メロディ 投げ 蹴り わかってきたでしょう? きれい きたない カメラ フィルム イオン トラ なぁ~んだ 尻取り? 最後はライオンですね! 空気の澄んだ秋、このクイズであなたの頭脳も快調、快調♪
2018.09.18
コメント(0)
-

江戸期、象世話役人の手紙♪
〇享保14年(1729)5月、ヴェトナムから長崎を1729経て百日余りかけて、遥々江戸に牡象が到着しました。江戸に詰めていた各藩の藩士たちは、こぞって珍しい象のことを国許に連絡していました。水戸藩の西野稲衛門景隆という藩士の手紙が3通、私信も含めて、その写しが残されています。その中の、幼い息子に書いた手紙と奥方へのそれが、いずれも活き活きと書かれていました。+<お父さんは象という陸の上で一番大きな動物の世話役を果たしたよ。その餌の準備に苦労したけれど、お役目柄、病気除けになるというお饅頭の食い残りや、身体を拭いた布を持っています。お母さんに贈るから、お前も少し齧りなさい。そして早く象のように大きくなって、母さんを助けて上げなさい。母さんはいろいろ五月蝿いだろうが、お前だけでなくお父さんにもそうだから、我慢しなさい。男とはそういうものだ。象は子供好きだそうで、子供たちを背中にいっぱい乗せてあげるということで、+ 実際に江戸の我が藩にも来た時、象使いがそのように象を膝まづかせたのだが、誰も乗る勇気が無かったが、お前は、その位いの勇気を持ちなさい。是非、お前を乗せたかったなぁ。殿様の前で象が披露されたのだが、無事、世話役を務め、くたくたに疲れた、その夜、父さんが象使いになって水戸まで象を連れてゆき、お前を乗せてやろうと思った所で、夢が覚めてしまった・・・。 妻への手紙には、財政厳しい折、象の餌の手配は大変だったけれど、国に残しているお前の苦労を思った。お前や子供のことがとてつも無く大切なもののように意識した。象の係りになって本当に良かった。あの象からいろいろ教えられたように思える・・・。 6月29日 おやすどの いなえもん+ これは海野弘氏著の「江戸妖かし草子」(河出書房新社)から抜粋した「象を見た」の一節を参考に書いたものです。
2018.09.17
コメント(0)
-

離宮八幡 創建1150周年記念祭(8年前)
〇今朝も載っていましたが、8年前の9月16日(木)付け京都新聞の20面をそのまま転載しますと、 さらなる発展祈願 離宮八幡 創建1150周年記念祭という見出しがあって、 大山崎町大山崎の離宮八幡宮で15日、「創建1150周年祭」が営まれた。製油業界の関係者や地元住民ら約120人が参列し、中世に油座の拠点として栄えた歴史を振り返るとともに、今後の発展を祈願した。+ 同八幡宮は859年、僧行教によって豊前国宇佐(大分県)の八幡神が勧請され創建されたとされる。嵯峨天皇の河陽離宮があったことから「離宮八幡宮」とよばれるようになったという。「創建1150年」に合わせ、昨年は本殿の屋根の葺き替えや拝殿の増床工事が行われた。 記念祭は供え物の油缶がずらりと並んだ本殿で、雅楽が奏でられる中、行われた。出席者は油を入れて火がともされた小皿を受け取り、正面に据えられた八足台に置き、厳かに献灯した。無病息災を願い、巫女が釜で沸かした湯に笹の葉を浸して振り撒く湯立神楽の神事も行われた。 津田定明宮司は工事に対する企業や個人の協賛に謝意を示し、「油商人発祥の地として、今後も国家の安康や国民の平穏を目指して務めを果たしたい」と挨拶した。とありました。
2018.09.16
コメント(0)
-

虚子、草城、誓子と亡父♪
〇昭和11年の父の日記は3月20日までは、ほぼ1ページを割いていますが、3月下旬から時間的に余裕が無くなったのか、メモ程度のもの、但し書きのような記録になっています。+ 3月29日 午前中ホトトギス社を訪ひ、(高浜)虚子と合ふ。白川(水野男爵)は熱海へ行かれ、自分のみ午後1時の燕(列車名)で帰途につく。+ 3月30日 卒業式、出席、経済学士の証書を受く。4月5日 住友生命へ初出勤、三等職員を命ぜられ、保険学、保険数学、算盤・習字を学ぶ。+ 4月22日 徴兵検査、第一乙種合格。8月1日 ラヂオ体操委員となる。また、防空演習、応召者通知の伝達係として活躍、各課より声を認めらる。+ 10月4日 満期保険支払事務を受持つ。10月15日 三浦零子氏の紹介で、山口誓子氏と合ひ、名刺を交換す。誓子氏は神経の尖った人。+ 10月18日 日野草城氏・水野白川氏とガスビルにて昼食を共にす。草城氏は女性的な鋭さを秘めた人。句に対する考え方は正常、それが意外。
2018.09.15
コメント(0)
-

嫁ぎ来てふと秋扇のやうである 星子♪
〇蒸し暑かったり、車中や室内が暑く感じるとつい手にするのは扇子。 扇子の源流は中国のうちわで、日本はこれを真似て棕櫚の一種のビロー樹でうちわを作成。 + +このビロー樹の団扇は少し力を加えると簡単に畳むことができることからヒントを得て、携帯できるよう、薄い木の板を糸で綴じ合わせました。板扇と言ったようですが、これが扇子の始まりなのでした。板扇はさらに改良され、板を細く・薄くし、糸の代りに紙を貼り付けるものが平安期に登場しました。 + + 本来、中国から渡って来たうちわが扇子となって中国に輸出され、中国人がその扇子を欧州に輸出したのでした。日本製のはヨーロッパで人気を博し、扇(セン)は英語のファンの語源になったとも言われています。 + +以前、滋賀県は安曇川に遊んだ折、扇子の骨を作っている家を何軒か見ました。京に運ばれ、雅やかな京扇子となって花街や茶道、華道、舞踊界、そして一般客にも愛用されているのですね。 + + 嫁ぎ来てふと秋扇のやうである 星子 + +今はそれ程でもありませんが、嫁は子を産む道具、働き手として捉えられ、人格を認められない時代がありました。現在なお、そういう面を払拭できないかとも。
2018.09.14
コメント(0)
-

浮気症の仁徳帝と焼き餅の皇后♪
〇仁徳帝は聖人君子の反面、光源氏にも負けないほどの恋多き天皇だったようで、正妻である磐之媛皇后の嫉妬に明け暮れする人生であったそうな。自分の継妹で美人の噂の高い八田皇女(母親が和邇氏の出で仁徳帝の父応神天皇の覇権に貢献)にちょっかいを出された折には皇后に猛反対され、+ 貴人の立つる言立儲弦絶え間継がむに並べてもがもほら戦には予備の弦を用意しておくじゃないかと帝が言い訳なさると 衣こそ二重も良きさ夜床を並べむ君は畏きかも(磐)とんでもないわ貴方、衣服だけですよ重ね着は+ 押照る難波の崎の並び浜 並べむとこそその子は有りけめ (帝)駄目?難波の”並び浜”のように、あの娘も並びたかろうに 夏虫のひ虫の衣二重着て 囲み宿りは豈良くあらず (磐)夏の蚕のようにマユを二重に重ねてこもるようなことは、絶対良くないわ! 朝嬬の避介の小坂を片泣きに 道行く者も偶ひてぞ良き (帝)あさづまのひかの小坂を独りぼっちで行かせるなんて可哀相。この歌に及んで皇后怒り心頭。しかし皇后が旅行へ行ったらこれ幸いと天皇は八田皇女と結婚。+ 愛する仁徳帝の土産に柏の葉(当時酒宴の酒を盛る器)をどっさり持ち帰った皇后はこれに立腹、別居生活に突入!他にも吉備の豪族の娘、黒日売(クロヒメ)を召し出した時にも磐之媛皇后がすさまじく嫉妬、若い姫は船にて本国へ逃げ帰ったとも。皇后は追いかけて行き、船は許しません歩いてお行きと命令。+ 帝は哀れに思われ黒日売を追いかけて行かれた。余りにも激しい嫉妬心のため結局帝のハートは黒日売に奪われてしまわれました。但し、これは各豪族の娘という勢力争いが誘引にもなっていたようです。どう仕様もないほど嫉妬心の強い奥様でしたが、彼女が帝を愛する気持ちを詠んだ歌2首+ 君は行き日(ケ)長くなりぬ山たづね 迎へか行かむ待ちにか待たむ 秋の田の穂の上(ヘ)に霧らふ朝霞 何処辺の方にわが恋止まむほんとうにいじらしい奥様だったようですね。
2018.09.13
コメント(0)
-

歯痛に苛まれた藤原定家♪
〇先日、乾いたカンカチの出し昆布を噛んでいて、歯が砕け抜けてしまいましたが、小倉百人一首でお馴染みの藤原定家も歯の治療を受けていた事に親近感を覚えたのでした。+ ”歯取りの老嫗を喚(ヨ)び、歯を取らしむ”+ 建暦2(1212)年、51歳になると彼にも老いの様相が出てきます。元日の宴から退出した折、階段でよろめき刀を損じた事が後鳥羽院にも伝わり哄笑を買ってしまった事や、+ 1月21日には弱くなった足腰ながら有馬温泉まで湯治に出かけたものの効果なく、2月に脚気、咳、きつい腹痛(膀胱結石?)など惨憺たる日々が続いていたようです。+ 神経痛や腹痛に対し漢方薬「大黄」や「鹿の角」などを服したり、身体の7ケ所に灸をすえたり・・・。そしていよいよ8月22日には上記の抜歯の記述に至ります。 当時は歯科医など居なく、歯取り専門の老婆が居たらしく、その手法は18年後の日記(寛喜2年4月4日)から察するに、”苧(カラムシ)を付け、少年嬰児の如くに引落し了んぬ”苧(イラクサ科の多年草つまり麻の一種)の頑丈な皮で作った糸で歯を抜き取ったようです。麻だから麻酔効果があったのかも知れませんし、巻きつけて置き自然に抜けるのを待つ方法だったのかも知れません。(参考図書・堀田善衛著「定家明月記私抄」続編)
2018.09.12
コメント(0)
-

ランプに寄せて♪
〇1974年(昭和49)12月発刊の季刊誌「銀花」(第20号)には「らんぷの美」という特集が載せられています。 いつも睨むランプに飽きて三日ばかり 蝋燭の火にしたしめるかな 石川啄木+観光地での土産物屋のちゃちなランプと違って、明治の御世を照らしてくれたランプには言葉で表わせない風情というか重みがありますね。そこにはあらゆる才知と努力が塗り籠められた燈火の道具。ライオンが飛びつこうとしているシルエットの赤地のランプうす青地に薄い白地の横線の並んだランプ。+ 金魚鉢そっくりの形をしたランプ黄土色地に龍や花模様のランプ昔懐かしい電灯の笠を逆さにしたような緑美しいランプ+ 白地に草模様を彫り込んだランプ切れ込みがあって所々隙間のある華奢なランプ実にいろんなランプがあるものですね。秋の夜長はランプで演出するのも一考かと・・・・。
2018.09.11
コメント(0)
-

サザエさんの波平と亡父♪
〇先日、サザエさんの母フネさん役の声優がお亡くなりになりましたが、「磯野家の謎<サザエさん>に隠された69の驚き」(東京サザエさん学会編・代表:岩松研吉郎慶大教授)を繰ると緊張が解れてきます。+磯野家のトイレは71冊のうち、11カット登場し、古い家に4つ、新しい家に3カ所もあります。推定によれば、波平54歳、フネ48歳、サザエ27歳で、フネさんは後妻だったと思われるなど、この本では肌理細やかに調査しています。独身時代のサザエは典型的なアプレ・ゲール(放恣・退廃主義)、男女同権を主張していたものの、男っ気は皆無。波平の趣味は釣り、囲碁、清元、盆栽、骨董。フネは長谷川一夫のファンで時代劇映画大好き。サザエは推理小説、カツオは俳句・短歌、ワカメは算術には弱いけれど、童話を書くことに秀でています。+ 戦後の貧しい暮らしから次第に豊かな日本へと成長してゆく世相を会話や服装、調度品などから読み取れるのがサザエさんの魅力でしょうか。ところでわが家の場合、一緒に出かけた回数から割り出すと、亡父は長姉に宝塚歌劇の良さを、次姉には映画の魅力を、そして私には歌舞伎という舞台芸術の粋を学ばせようとしていました。波平は出世主義でなく、人間として心豊かに暮らすことを重んじた人物像として見えますが、ステテコ姿の、あの禿げ茶鬢と亡父とが、私の中では重なりあうのです。
2018.09.10
コメント(0)
-

某年、祇園に遊ぶ♪
〇某年某月、祇園町常連O氏のお手配にて、「湖藤美」の二階座敷に、昨年末に舞妓から芸妓になられた小愛さんのお酌を頂きました。まるで地毛のような自然な鬘の御髪は黒く、艶やかに。程良い化粧のお顔には、どんぐり瞳が愛らしい姐さんでした。芸妓さんを招いてのお茶屋遊びは初めての経験。贅を尽くしたお品の数々。ビールも美味し!冷酒も格別。小愛さんは勝気な中に、頭の回転も素晴らしく、現代っ子の健康な色香の中に、将来の良い人(白馬の王子)を夢見る乙女。 私たちが俳句を嗜むと聞いて大喜び。実は彼女も数人で句を楽しむ文学芸妓なのでした。毎月、彼女が季題を決め、寸暇を割いて”今日的な句”を見せ合っているそうな。小愛ちゃんへの献句は+ 来ぬ人に朝の座敷のいとど哉+いとどはコオロギのこと。来ぬのコ 朝のア いとどのイ つまり小愛さんの名を織り込んで詠みました。小愛姐さんはふところに挿していた女物の扇子を取り出し、此処に書いておくれやすとのたまいました。さて彼女も一句ひねり出し、+ 弾む下駄君の姿に良夜かな+かわゆい娘心を詠いこみました。愉しい宴が終わる前に、おりくは歌舞伎の声色を遣いました。 <ご新造さんへ、おかみさんへ、お富さんへ、いやさお富、久ぶりだなあ・・・しがねえ恋の情が仇・・・死んだとお富たあ お釈迦様でも気がつくめぇ、よくもお主は達者で居た>昔春日八郎が歌った流行歌でお馴染みの源氏店 きられ輿三の「輿話情浮名横櫛」の一節です。小愛姐さんのアンコールに応えて、「三人吉三廓初買」の<月も朧に白魚の、かがりも霞む春の空、・・・も小愛さんと一緒に披露しました。お座敷遊びは、周りの同胞を持ち上げる気配りと、好かれる客像を胸に、座を盛り上げることが大切なのかも知れませんね。
2018.09.09
コメント(0)
-

秀吉公の仮装大会♪
〇藤原定家と言えば大概の人は知っておられるでしょう。その姉妹のひとりが、景勝光院の梅の花を見に出かけ歌を詠じた話が「本朝古今閨媛略伝」に載っていて、何とその出で立ちは仮装姿だったそうな。だから文書による仮想の始まりは彼女の活躍した平安末期と見てもよろしかろ。 かぶき者大将の信長公の仮装癖もさることながら、その後を継いだ豊臣秀吉公の発案による文禄3年(1594)6月28日の仮装大会こそ我が国最初のものと言えそうです。 瓜畑に瓜屋と旅籠屋とを設え、秀吉自らは瓜商人の恰好、家康は畚売り、豊臣秀次は漬物売り、織田信雄は遍参僧、前田利家は高野聖、蒲生氏郷は荷い茶売り、前田玄以は比丘尼という具合。柿帷子を着て藁の腰蓑をまとい、黒い頭巾をかぶり、菅笠を肩にした秀吉は、「味よしの瓜めされ候へ、味よしの瓜めされ候へ」と売り歩いたが、その声色と容姿が抜群だったそうな。氏郷は極上の茶をたてて秀吉にすすめ、うんと高い茶代をねだって一同を笑わせたとか。
2018.09.08
コメント(0)
-

誤変換実例集♪
〇安価なノートパソコンでは思うように変換できず、難儀したことが再々ありました。 で、清水義範著『日本語がもっと面白くなるパズルの本』には、「ワープロ誤変換実例集」なる頁があって、+ 地方公務員 → 痴呆公務員(一部には懲りないそういう人もいるが)変動為替相場制 → 変動買わせそう罵声(なるほどそうなっていたか)煙草は二十歳から → 煙草は畑地から(自家栽培してはいけません)農用地整備公団 → 脳幼稚性尾行団(かなり困ったストーカー?)応接間 → 逢瀬妻(官能小説向け変換例)研究学園都市 → 研究が食えん都市(学者が暮らしにくい町)巨人対阪神 矢印巨人大半死んだ(’97はそのとおり)出来次第発送 → 溺死大発想(どんなことを考えようというのか)入会金 → 乳解禁(トップレスOKということ)会社概要 → 会社が異様(そんなら入社したくない)今夜も愛をさがして → 紺屋も藍をさがして(商売だもの当たり前)結婚披露宴招待状 → 血痕疲労炎症退場(怖い結末が待っていそう)という具合に、清水さんが頭の中で思いつかれた熟語を組合せ、この一文をしたためられたものと思われます。+お題をいただけたら、いろいろチャレンジできそうですね。皆さんも時にはこういう言葉遊びをどうぞ。
2018.09.07
コメント(0)
-

亡父の詠んだ風の盆♪
〇高橋治氏の小説と亡父すばるの俳句によって、伝統的な田舎の盆行事、影絵のような男舞い・女舞い、空の暗さと奔流する水音などが既に脳裏にインプットされているものの、まだ果たせていない風の盆。 風誘ふ手振りとも見ゆ風の盆 風の盆権現立ちの男振り 風の盆反り身で決まる女振り 暮れんとす空濃く濃く濃く風の盆 天界に風の盆あり戻りバス 平成5年にすばるが詠んだ”風の盆”30数句の一部です。
2018.09.06
コメント(0)
-

猫派の人語る♪
〇私はどちらかと言えば犬派ですが、猫派の人が語るには猫に優しい人つまり猫族は猫にもわかるらしく、産み終えた仔猫をば先ず一番目には彼女に託し、二匹目から順に彼女の友人宅に置いて行くのだそうです。高い塀の上からさも、”お願いします”とでも言ってそうな表情で挨拶するのだとか。また、死期を悟った老猫が飼い主から離れ、生れた時の彼女の家に来て、老衰の状態で息を引き取るんだとか。+ 犬が人間の言葉を理解するのなら頷けるのですが、猫も同じレベルだとは知りませんでした。猫はプライドが高く、序列を無視した態度で新参者の猫を主人が可愛がると拗ねて食事を摂らなかったり、猫自身が大失態をした時、主人やその家族に見られてでもしたら、やはり数日間、餌に飛びつかないのだそうです。+飼い主の機微が解るだなんて、猫は賢いので小説の主人公にも抜擢されたのでしょう。
2018.09.05
コメント(0)
-

手巻き蓄音機の音色♪
〇わが家に残る手動蓄音機でSP盤のレコードをかけてみました。少々雑音のあること、ボリュームを落とせない難点がありますが、なかなか古風で粋。+泪の乾杯:竹山逸郎、港の見える丘:平野愛子、すずらんの咲く頃:奈良光枝、 東京の夜:藤山一郎・渡邉はま子昔の流行歌手は音楽学校でみっちり勉強し、基本を積んできた人がなるべくして歌手になったのだから一定のレベルがあります。現在のカラオケという魔物は、エコーという魔法を使いますので、アラが目立たないだけで、これらの歌手とは比較できません。次に”唄の旅”と題したレコード盤は+お江戸日本橋:勝太郎、箱根八里:福村貴美子、伊勢音頭:筆香、安木節:市丸関の五本松:筆香、福知山音頭:小二三、金毘羅船々:筆香、ぶらぶら節:福村貴美子、串本節:市丸+小学生時代、家にテレビが初めて置かれた年の紅白歌合戦では勝太郎姐さんも、市丸姐さんもお元気でした。このレコードは戦前か戦後すぐに録音されたものだから、お二人とも迫力満点の歌いっぷりです。+ 小二三姐さんは小唄では日本を代表する名人だったのでしょう。さらにパワーのある歌でした。このように考えますと、録音状態が充分とは言えないけれど、昔の人々の生き様や息吹が、そっくり伝わってきます。SPレコードは重いので保存が大変ですが、残しておきたいなと思いました。
2018.09.04
コメント(0)
-

或る主婦の”夢の一人旅”
〇結婚前には世界一周旅行に連れていくと約束して置きながら、子供のことで手がいっぱい。せめて日本一周ぐらいさせて貰わないと割が合わない。しかしこの歳になると、旦那連れよりも一人旅に憧れると。<青春の苦い思い出をかみしめながら、若い頃訪れた九州や子育てに専念した北海道へ旅したい。「一人で旅行ですか?」と声をかけられたらどうしよう。「はい、主人に先立たれまして」と言おうか、それとも「はい、独身を通しまして」と言おうか、想像しただけで胸がワクワクする。だけど、私のことだから毎日家に電話を入れて「ご飯はたべたの?」「ネコにえさはやった?」「洗濯・掃除は?」と騒ぐんだろうなあ。つくづく損な役回りと、思う。・・・でも、私は夢を見る。心ときめく一人旅。いまにきっと 一人旅にでるぞォ。> 本文そのままの部分と要約した部分がありますが、日本の主婦の心理が浮き彫りにされていますね。実は、私も一人旅が夢で、家内に頼みこんだことがあるのですが・・・未だ、認可証を頂戴して居ません。
2018.09.03
コメント(0)
-

30年7月8月拙句記録帖♪
〇毎日の雨戸を開ける時に感じる時の速さ、ごみ出しのサイクルの速さ。光陰矢の如し。+ 文月や式部のつづる月の筆 盛り塩のきはまで女将水を打つ キャンバスの未完のままや晩夏光+ 夏を斬るそら角に剪る寺門なる 血管の浮き出る仁王夏旺ん 初恋は旅の信濃路白むくげ+ 晩夏かな久に使はぬ砂時計 男声の和音を漉かす今朝の秋 何もかも受け入れるごと蓮開く+ 空澄めば池面も澄めり嵯峨めぐり 夕霧の墓へ一礼秋涼し 朝涼や二尊院まで西二丁+ 整然と千手千仏杉さやかこんなところかな?
2018.09.02
コメント(0)
-

ヒット曲には作詞家と作曲家の魂が宿っています♪
〇私たちは一人で生きてゆくことが困難で、必ず誰かと支え合い、生かせて貰っていると言えましょう。琴線の合う人とは、無言或いは息遣いや目の表情だけでも思いを伝えることが可能でしょうが、通常は言葉を通じて自分の考えを伝えようとしています。+かつて、東国原知事がその選挙戦において訴えておられた明解にして端的な話術。小泉元総理も話術の上手な人でした。抑揚、身振り、そして強弱をつけながら自分の考えを伝えるのですから、人の耳に快く響きます。+カラオケで好きな曲を歌う時、私は出来るだけ原曲のまま、詩の内容を伝えるように努力しています。声質やポイントの強弱、盛り上げ方などの工夫で表現できるものと確信しています。畏れ多くも作曲者の意図を無視してまでアレンジしようなどは思ってもみません。+しかるに、歌手の一部には何度も歌うことに飽きがきた所為か、作曲家の意図を無視して、勝手にリズムを変えて歌っておられる人も。流行歌が世に出るということは、「作詞者と作曲者の想い(感性とも魂とも)の交差した部分」なのですから、原曲通りに歌って欲しいものですね。
2018.09.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1