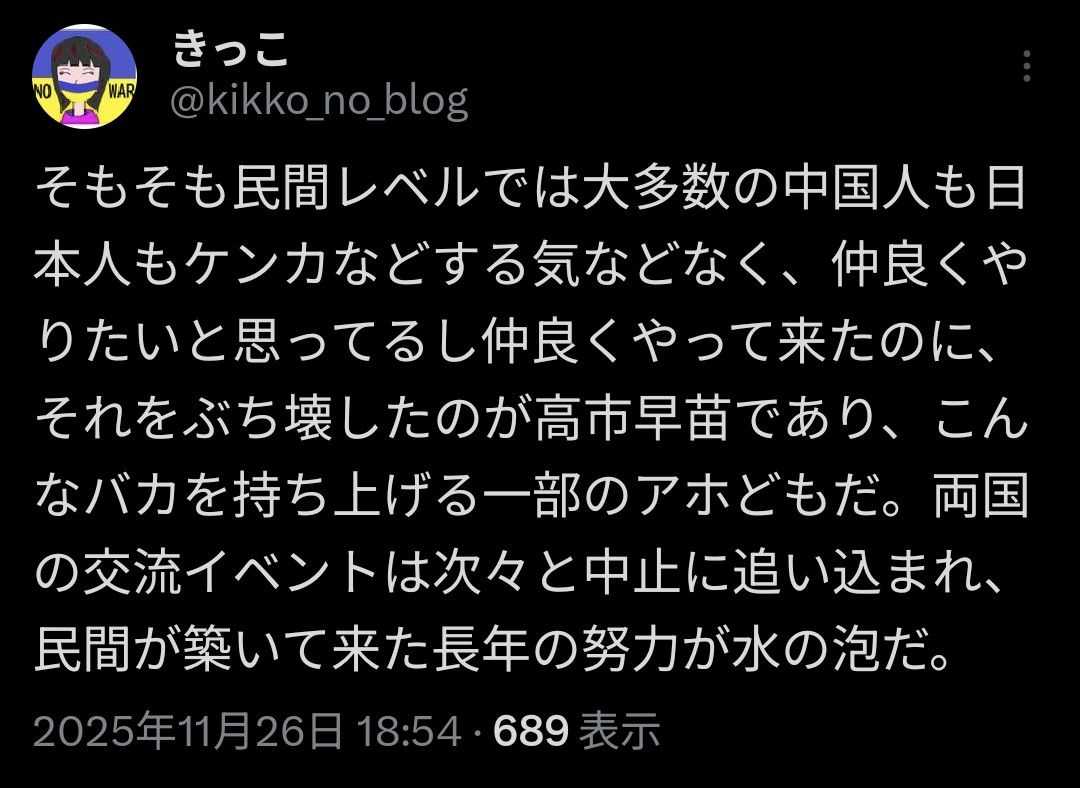2008年01月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
スーパー戦隊シリーズの新作
先日「バトルフィーバーJ」について書いた。今回も「スーパー戦隊シリーズ」について、書く。 もしや僕はオタクではないかという疑いをお持ちの方もいるかも知れないがそんなことは決してなくてその証拠に、内容については毎回殆ど触れていなくてこうやって書くとそれが尚更「オタク疑惑」につながるのかも知れないがこっちもそれをある部分で狙ってこういう文体で書いていて結局、僕はオタクではありません。ただ、バカバカしいこと、どーでもいいことが好きなだけででもなかなか「仮面ライダー」以上のものは書けませんね~。(↑軽く宣伝♪) さて、僕は「スーパー戦隊」のマニアではないが2月から新シリーズが始まることを知りその題名を見ていてもたってもいられなくなった。 2月17日、テレビ朝日系列で放送開始。スーパー戦隊シリーズ、第32作。 炎神戦隊ゴーオンジャー ゴーオンジャー。 どこで切って読めばよいのかかなり迷う。 「ゴー・オンジャー」だろうか 「ゴレンジャー」は「GO、レンジャー」であり、「5(人)レンジャー」でもあるという。今回も5人のようだし「5」と「GO」をかけているのか。 ・・・オンジャーってなんだ? 一応、辞書で調べてみたがそういう単語はなさそうだ。でも「オンナンタラカンタラソワカ」とか言うサンスクリット語なら可能性はある。僕は残念ながらサンスクリット語はあまり知らないので「オンジャー」という語があるのかどうかわからない。 「ゴーオン・ジャー」だろうか。 これが正解だった。 メンバーの名前が「ゴーオンレッド」とか「ゴーオンブルー」だからだ。そうか「GO ON」だったのか。 ・・・ジャーって、なんだ? 水がジャーだろうか。ジャージャー麺のジャーだろうか。 僕は、炊飯ジャーであると推論する。 「炎神戦隊」だからだ。炎を関係しそうな「ジャー」は炊飯器以外に、ない。 「轟音炊飯ジャー」である。 「ご飯が炊けましたぁぁぁっ!!!」(どかーん) ・・・いらねぇ。 スーパー戦隊シリーズの題名は「掛詞」でできている。が、中には掛かっているようで、実はなんにも掛かってないヤツもいる 全32作のタイトルを見てみよう 1.秘密戦隊 ゴレンジャー 2.ジャッカー電撃隊 3.バトルフィーバーJ 4.電子戦隊 デンジマン 5.太陽戦隊 サンバルカン 6.大戦隊 ゴーグルファイブ 7.科学戦隊 ダイナマン 8.超電子 バイオマン 9.電撃戦隊 チェンジマン10.超新星 フラッシュマン11.光戦隊 マスクマン12.超獣戦隊 ライブマン13.高速戦隊 ターボレンジャー14.地球戦隊 ファイブマン15.鳥人戦隊 ジェットマン16.恐竜戦隊 ジュウレンジャー17.五星戦隊 ダイレンジャー18.忍者戦隊 カクレンジャー19.超力戦隊 オーレンジャー20.激走戦隊 カーレンジャー21.電磁戦隊 メガレンジャー22.星獣戦隊 ギンガマン23.救急戦隊 ゴーゴーファイブ24.未来戦隊 タイムレンジャー25.百獣戦隊 ガオレンジャー26.忍風戦隊 ハリケンジャー27.爆竜戦隊 アバレンジャー28.特捜戦隊 デカレンジャー29.魔法戦隊 マジレンジャー30.轟轟戦隊 ボウケンジャー31.獣拳戦隊 ゲキレンジャー32.炎神戦隊 ゴーオンジャー 疲れる 実際、紙一重な名前が結構ある。パソコンも疲れてきたのか変換途中「各レンジャー」とか「目がレンジャー」とか「針賢者」とか、出てきた。「オーレンジャー」なんかは全く内容を知らないから名前だけで想像するしかないのだが「オレンジ」まで掛かってそうで全員オレンジ色の戦隊をイメージしてしまう。あるいは「Oh!レンジャー」だ。実際、オーレンジャーのメンバーはオーレッドとかオーブルーだから「オー」に区切り目がありそうなのだが彼らの武器は「オーレバズーカ」というからもう、イギリス、アメリカ的なものからスペイン、フランス的なものまで想像され気になってしょうがない。 「救急戦隊」というのも気になる。救急は119番に任せておけばいいのにヒーローが出てきてしまったことで余計ハナシがややこしくなった。 おまけに名前が「ゴーゴーファイブ」。 どうも「アゲアゲ」的な響きがあってその辺は郷ひろみのせいでもあると思うけれど救急という割には不謹慎である。 「救急だ。ゴーゴーゴーゴー!」 なんか、喜んでいるように聞こえる。 そういう名前の中でもゴーオンジャーは異彩をはなっていて期待できる。 打ち切りになったシリーズがひとつだけある。 「ジャッカー電撃隊」 名前はマトモなのになぜ子ども達の支持を得られなかったのか。 ナゾは、比較的簡単に解けた。 これを見ればわかる。 単に、カッコ悪い。 他のヒーローたちは例えば何かのマークをモチーフとしていても黒い部分が目っぽくなっていたりデザイン性がある。 なんなんだ、こいつらは。 ビー球にトランプのマークを貼り付けただけだ。 なんの努力も感じられない。 真ん中にいるレインボーマンみたいなヤツがリーダーだというのだがコイツなんて、スーパーボールだ。 カッコ悪い。あまりにカッコ悪い。 手抜きは、子どもにこそバレるのだ。子どもを甘くみてはいけない。 ゴレンジャーは「5(人)レンジャー」だというから、僕は長いこと「ゴダイゴ」も「5人のダイゴ」だと思っていた。中学生になって歴史の勉強をするようになると「後醍醐天皇」のことだと思った。地理で「五大湖」が出てきたから余計ややこしくなった。「五代後」かと疑ったこともあった。 答えは「GO-DIE-GO」だった。 分かりっこ、ない。 Kama
2008.01.31
コメント(3)
-
合格報告届いてま~す(6)
今日の合格。これで私立高校推薦入試の発表はすべて終わりです。 西武文理学園高校(エリート選抜東大クラス) おめでと~! 締めくくりはこの高校でした。 これで本当に愛夢舎中3生は私立高校前期入試全勝を達成しました。 入試事前相談で良い返事をもらえなかった人もいましたので、私立前期(推薦)とはいえかなり良い結果であると思います。 みんなよくがんばりました。進学先が決定してしまった人はゆっくりしてね。これからが本番の人、もうひとふんばり!いっしょにがんばろうね。
2008.01.29
コメント(0)
-
人間の小型化
こんばんは、鎌田です。僕は身長174センチ。中学時代はバスケ部に所属し、キャプテンナンバーの「4」をつけていました。腰の骨に欠陥があって、高校では陸上に転向したのですが。 そんなハナシを中学生にしていて先日、こう言われました。 「じゃあ、ポジションはセンターだったの?」 センターというのは、バスケットのポジションのひとつで、ゴール下を定位置として、パスを受け取って、高い位置からゴールを狙う。スラムダンクの赤木キャプテンとか魚住キャプテンのポジションと書いた方が分かりいいでしょうか。背の高い人がつくことの多いポジションです。 が、実際には僕のポジションは、ガードでした。 シューティング・ガードとでもいいましょうか、同じ、スラムダンクではミッチーこと、三井寿選手のポジションです。 どちらかと言うと、中くらいか、むしろ背の低い人がつくことの多いポジション。 それもそのはず、僕のチームのレギュラーメンバーには、180センチ以上のヤツが2人いた。クラスの背の順でも僕は高い方から数えて6~7番目くらいだったと思う。 中学を卒業してから背が伸びたのではありません。3年生の頃で、だいたいそんなもん。それ以降は2センチも伸びていません。つまり、中学3年の時点で僕のチームには180センチ以上が数人いた。僕は、決して「背が高い」人ではなかった。 僕のチームだけではない。他の学校のチームにも、必ず180以上がいたので試合の中で、僕はやっぱり中くらいだった。 それを言うと、今の中学生はとても驚く。どんだけ巨人がそろっていたんだ、って。 僕はむしろそのことにびっくりなのですが、ここで、ひとつの極端な推論に思い当たった。 もしや、人はどんどん小型化しているのでは。 日本人の平均身長を歴史をひもといてみてみると現在の日本人は、江戸時代の頃より大分背が高くなっている。年々、平均身長は高くなっているような気もする。 でも、ここにきてひそかに人は「小型化」の流れに入っていったのではないか。 人だけではない。昨今のペットブームをみてみれば一目瞭然。 しばらく前はゴールデン・レトリバーとかシベリアン・ハスキーとか、コリーの「ラッシー」とかピレネー犬の「ジョリー」とか、大型犬が人気があったけど最近ではチワワの「くーちゃん」、トイ・プードルとかミニチュア・ダックスとかさらにはティーカップ・プードルとか、小さいヤツの人気がすごい。 ミニモニは大人気だったが、デカモニ、メガモニ(←また出た…)は出てこない。 時代が、地球が、小さいものを求めているのだ。 なぜ? そのことにいち早く気が付いて風刺小説を発表して人類に警告を与えていた人物がいる。 スウィフトだ。 スウィフトは「ガリバー旅行記」の中で「小人の国」を登場させた。お読みの方はおわかりだと思いますが、ガリバー旅行記はまったくもって「童話」ではなく、だいたい、小人の国はほんの一部分にすぎず、空に浮かぶ「ラピュタ」、ガリバー最後の旅となった馬の国などぞっとするほど怖い国であってそれらはことごとく当時の社会風刺であるとされています。 小人の国。 人はなぜ小さくならざるを得なかったのか。 解釈のひとつに人口増加と環境破壊への風刺であるというのがあります。人が住める土地は限られている。にもかかわらず、人は、食物連鎖のヒエラルキーから逸脱して勝手にどんどん増えている。 小さくならざるを得ない。 日本人は確かに時代を追うごとに平均身長が高まってきたかも知れません。でも、それはわずか2000年程度の日本の歴史に限ったこと。 地球全体の歴史でみれば、10メートル以上の恐竜が闊歩していた頃からすると今の生物はどれだけ小さくなったことか。 プテラノドンというヤツがいたということだけれどもプテラノドンが飛んでるのとスズメが飛んでるのを比べればその小型化は一目瞭然。 そう、地球上の動物は、どんどん小型化しているのです。 植物は、おそらくサイズを変えていない。今生えている木は恐竜がいた頃にも同じくらいのサイズだったはず。ならば、そもそも「木」というのは僕らにとってのタンポポとかヨモギとかそういう程度の「草」であって「木」を見上げる僕らは当時のネズミやリス程度の大きさなのだろう。 さあ、だんだんコワイ仮説になってきた。 このまま植物などのサイズが変わらず、動物の小型化が進むとどうなるか。 雨が降ると必ず洪水になって溺れてしまう動物だらけになる。 ヤシの実やヒマワリの種の落下で死ぬ人が増加する。 「母を訪ねて三千里」が「母を訪ねて三十万里」くらいに翻訳される。 アメリカでは毎年、でっかい野菜コンテストがあってウソみたいにデカイかぼちゃが出品されるけれどアレはかぼちゃがデカイ以前に人が小さくなったためでそのうちデカイ「ゴマ」コンテストもできる。「セサミストリート」が誕生する。 どうでしょう。 相変わらずアホみたいな空想劇を書いているわけですが、あながちそうでもないかも知れませんよ。 金魚は、環境に合わせて体のサイズが変わります。 狭い金魚鉢に大勢の仲間とともに暮らしているからあのサイズですが広い池で、一匹だけ、ゆうゆうと生活させると体長50センチ以上の金魚になります。 コレ、ホントです。Kama
2008.01.28
コメント(2)
-
合格報告届いてま~す(5)
今日の合格は 聖望学園高校で~す。おめでと~!まだ全勝記録は続いていますよ。
2008.01.27
コメント(0)
-
合格報告届いてま~す(4)
今日の合格は 狭山ヶ丘高校 西武台高校 埼玉平成高校です。おめでと~!もちろん、今のところ私立高校全勝です!
2008.01.26
コメント(0)
-
メロンパン
菓子パンが好きだった。 いや、何も過去形で書くことはないかな、今でも好きです。ただ、生徒にはよく知られていることですが、僕は、甘いモノが苦手なのです。それでも、チョコとかアイスとか、洋モノはまだ大丈夫なのですが、ショートケーキを一つ食べると胸がムカムカしてくる。アンコは限界値突破。全身に鳥肌が立つ。昔は好きだったんです。いつの間にか食べられなくなってしまいました。菓子パンは、やはり甘いモノが多いから、過去形にしてみました。でも、パンは好きで、今も昼食の8割以上は、コンビニのサンドイッチ。 そんな僕が、こだわりを持っているパンがあります。 菓子パンの王様、メロンパン。 僕は、メロンパンにはうるさい。昨日、テレビを見ていたら、広島では円形のメロンパンを「サンライズ」というらしい。なかなか良いネーミングだ。でも、メロンパンはメロンパンだ。 メロンパンは、丸いのが当たり前だ。 ところが、丸くないメロンパンがあるという。しかも、結構な市民権を得ているともいう。 そのメロンパンは紡錘形。 なんてこった!丸くなければ、メロンパンにならないじゃないか! メロンパンは、形が丸くてメロンっぽいからメロンパンなのだ。紡錘形なのは、カレーパンだろうが! ところが、最近では紡錘形でないカレーパンもある。 ・・・。 今回はメロンパンなので、カレーパンは置いておきます。 メロンパンは、形がメロンっぽいからメロンパンという。丸いだけでなく、色がやや緑がかった黄色。まるでメロンだ。そして、黄色の表面には数センチ平方の正方形を作る溝というか筋というかが走っている。ますますメロンだ。食べるときには、この筋を目標に、1ブロックを歯で噛みとってじっくり口の中で味わう。一度に2~3ブロックを口にしてはいけない。あくまで1ブロック。やや小さめな噛みとり方がよい。増して、大きな口をあけてパンの半分をいきなりほおばるようなのはメロンパンの食べ方として、なってない。メロンパンの内部には、ほとんど味がついていない。表面の黄色のヤツにほのかな甘味がついているだけだ。これが良い。噛みとられた1ブロックをじっくりと口の中で噛んでいくうちに唾液の効果からか、やがて味気のない小麦は甘味を帯びてくる。そのためには、中は味のないモサモサした感じ、表面はブロックごとに噛み切るそのアクセントとしてカリッとしていることが望まれる。カリッと噛み切ったあと、人は内部のモサモサに、しばしがっかりするかも知れない。しかし、次第に甘味を増してきて、口の中で完成形に至るそのモサモサは、アリストテレス的な可能態であったのかも知れない。 ところが、このメロンパンの醍醐味をぶちこわす商品が多くなってきた。 チョコチップ・メロンパン。 いかん、これはいかん。せっかくの口の中での熟成の楽しみを安易な甘味でジャマしているにすぎない。ダメなのだ、メロンパンが初めから甘くては。 表面がしっとりしているヤツもいかん。カリッと噛みとれないではないか。 さらにヒドイのがいる。 中に、なんか、クリームが入っちゃってるメロンパン。 究極。 メロンの味がするメロンパン。 台無しだ。ホント、台無しだ! 昔から日本人は、色々な食材をほかのものに見立ててきた。比喩といってもよい。日本人は、動植物をほかのモノに例えてそこに言葉・文化の妙を楽しみ、それこそが風流だった。 メロンパンが、メロン味でどうする! ご先祖様が泣いている。 メロンパンは、菓子パンの歴史の中でもかなり早い時期に作られた。 色々な可能性を含む黄色のパンを高級果物 メロンに見立てたそんな風流人のパン屋さんの「粋」をむげにしてはいけない。 ・・・表面の黄色がメレンゲだからメロン・・・。 ・・・。 そんな説もあるようだがそれは聞かなかったことにする。 メロンパンを食べていると人は色々な想いにかられる。それは、メロンがメロウに通じるからだ。(・・・。) チョコチップ入りも、クリーム入りも、メロンの味がするのも、パンとしては非常においしい。だから僕も好きだし、パンとして、ひとつのジャンルであろう。 でも、メロンパンは違う。 違うのだ。 メロンパンに入ってよいものは昔から入っているレーズンだけだ。 僕も、レーズンはあまり好きではない。だからいなくてもよい。 でも、いて良いとすれば、レーズンだけだ。そのジャマさ加減が、またメロンパンを人生のように苦楽あるものに昇華させるからだ。 僕は、アンパンマンには詳しくない。 アンパンマンの必殺技、「アタマ丸ごととっかえ」がさまざまな疑問と疑惑を生み、常識で考えたらスプラッタ以外の何モノでもないあの衝撃映像の主人公がヒーローであることに違和感を感じるからだ。(・・・。) アンパンマン、パンだけかと思ったら、野菜なんかも登場するんですね。 そんなアンパンマンにもメロンパンは登場するようだ。 ところが、メロンパンナちゃんの顔は網か鉄格子を押し付けられたかのようだ。 まあ、しょうがないな、メロンだし。 でも、リアルにメロンっぽくしたらメロンパンナちゃんはもっとヒドイ顔になる。リアルなマスクメロン同様の網目をつけたら、それはもう、スパイダーマン級の網加減だ。 だいたい、アンパンマンには色々なパンが登場しすぎる。 にもかかわらず、全国的に有名なあのパンが登場しない。 ドラえもんパン。 ・・・。 ・・・そっか、そりゃそうだね。 甘いモノが苦手になった僕が今現在好きなパンは、焼きそばパンです。Kama 注:どこまで本気でどこまでネタかは 読者の方々で勝手に判断してください。
2008.01.26
コメント(8)
-
バトル・コサック
久々にこのマーク…。 これまで、「仮面ライダー」とか「ムーミン&バーバパパ」なんかを書いてきて、一部では相当のマニアと思われているようだが、そんなことはない。実際には、男の子向け番組は、あまり見てこなかった。例えば、「ガンダム」は、ほとんど知らない。「キン肉マン」もあまり知らない。「北斗の拳」は、後から知った。「ドラゴンボール」は途中であきた。 そんな僕であるが、物心ついた頃に大好きだった番組がある。 「バトルフィーバーJ」。 戦隊、変身、ヒーロー、ロボット・・・。大好きだった。 特に、乗り物が変型したり、合体したりするのは大好きだった。だから、仮面ライダーも好きだし、「デンジマン」とか「サンバルカン」とか、「ギャバン」「シャリバン」「シャイダー」の宇宙刑事シリーズも好きだった。最近では「♪1万年と2000年前から愛してる~」のロボットアニメが流行のようだが、僕の「合体」、「変身」好きはもう30年近く前からだから、1万年と1970年たった位からは同じ穴のムジナということか。(なんのこっちゃ) で、その僕が好きだった「バトルフィーバーJ」。 幼稚園に通っている頃だったろうか。毎回欠かさず見ていたし、主題歌もソラで歌えた。 ・・・が、この年になって改めて気がついた。 「バトルフィーバーJ」。 この名前じゃあ、パチンコ台と思われてもしょうがない。 バトって、フィーバーしちゃって、機種番号だかなんだかわからない「J」とかついてる。 姉妹品として「バトルフィーバーMX」あたりは出てきてもおかしくない。 ご存知の方には言うまでもないが、実際には「J」は「JAPAN」の「J」だ。 男の子の憧れだった戦隊ヒーローもの。「ゴレンジャー」、「ジャッカー電撃隊」に続く「バトルフィーバー」は、どういうわけだか、各国の代表の戦士たちが敵と闘うのだ。その豊かな国際色に僕は魅せられたのかも知れない。 リーダーは「バトル・ジャパン」。他に、リーダーのライバル的な「バトル・フランス」、野性的な「バトル・ケニア」、紅一点の「ミス・アメリカ」。 そして、サブリーダー。 「バトル・コサック」。 ・・・。 こさっく? どこの国じゃ、それは?! ひとりだけ国名ではなく、部族の名前で登場だ。 今思うと、あまりに不自然だ。日本、フランス、アメリカ、ケニアときたら、あとはオーストラリアかロシアでいいではないか。中国でもよい。なんなら、南極でもいいぞ。 なぜ、コサック・・・。 各戦士には得意技があって、例えば「ジャパン」は槍、「フランス」はフェンシング。 「コサック」の必殺技・・・。 それは「コサック・ダンス」。 おかしい、おかしいぞ! あの、腕組みして腰を落として、足を交互に蹴り出すダンスで敵を倒す・・・。なんなら「トロイカ」でもかけようか。 そこまで思い出して、どうして僕はアレが好きだったんだろう・・・フシギに思ってしまった。 挙句の果てに、「バトルコサック」は途中で戦死してしまう。 プロデューサーか誰かがロシアに恨みでもあったのだろうか。それとも、日露戦争での想いが我々日本人には染み込んでいるのだろうか。 突然こんな記事を書いてしまってなんなんですが、とにかく「少年」にとって戦隊ヒーローはとても大きな存在だったのです。 「こさっく」・・・。 僕なんかは、ゴレンジャーの必殺技、アメフトのボールの形の爆弾を5人でパスした挙句に蹴り出すというアレを見てアメフトのルールを覚えたもんだ・・・ ・・・と書こうとも思ったが、いくらなんでもそれはウソなので、やめておきます。 しかるに、最近のヒーローものはどうなんだろう。 これが、今回の記事のきっかけです。 あれは、数年前のことでした。 僕は、朝起きると、とりあえずテレビをつけます。家に帰ってきても、とりあえず、つけます。別に、何かを見るということではなく、BGM的につけるのです。 その日は日曜日でした。 普段、チャンネルはフジテレビに合っているのですが、その日はどういうわけか、テレビ朝日になっていた。 その頃、戦隊モノは「爆竜戦隊アバレンジャー」だった。 そのオープニングだか、エンディングだかの歌が流れてきたのです。一応つけているだけで、まるで見ていない僕の耳に、その曲は流れ込んできた。 「♪アバアバアバアバアバレンジャ~」 腰が抜けた。 僕は、曲を書く。詞は書かない。 しかし、これには文字通り、口が開いた。 僕は今に至るまで「ぎゃふん」と人が言ったのを聞いたことがないのだが、このとき誰かが僕に「どうですか?」と尋ねていたら間違いなく「ぎゃふん」と言っただろう。 平仮名で書くと、なおすごい。 「あばあばあばあばあばれんじゃあ~」。 赤ちゃんでももう少しマトモにしゃべる。 それを日曜の朝っぱら、なんの予備知識、準備もなくつまり、まったくの無防備の状態で聞くことを想像してごらんなさい。 いきなり、「あばあばあばあば・・・」ですよ。 もう、「ぎゃふん」以外に言いようがない。 実際、戦隊ヒーローものには「ぎゃふん」と言わされっぱなしだ。 「マジレンジャー」が「マジ(本気)」なレンジャーだと思っていたら「マジカル」なレンジャーだったときの衝撃。 「バイオマン」では「レッドワン」、「グリーンツー」という具合に色と番号が呼び名になっていて、3人目が「ブルースリー」であったときの衝撃。 「アバレンジャー」。 暴れるなよ・・・。 こさっく・・・。 Kama
2008.01.25
コメント(8)
-
合格報告届いてま~す(3)
1月24日夜報告を受けた合格です! 埼玉平成高校 東野高校です。おめでと~!
2008.01.24
コメント(0)
-
じまんデス♪
こんばんは、鎌田です。今日はオフをいただいております。なもんで、狭山ヶ丘、秋草の合格は塾長佐々木の↓の記事で確認しました。 いっこだけ、自慢。 S学園、古文出題、完全的中させました。(おほほほほ~) 普段、アホみたいなことを書いてる僕ですが、ちゃんと仕事するときはします。 実は、この4年で、5校くらいは的中させています。その前、古くは、都内A学院大学付属も的中。実際のところ、古文は当たります。偏差値60~65くらいの学校のある「クセ」に気がつけば。 ところで、S学園もS丘高校も、なんだってあんなに難しい古文を出すんでしょう。完全に中学校範囲を超えてます。いや、ウチの高1生でもできないでしょう。(だって、古文法を出すんだもん)おかげでウチはそこをねらい目とした対策が取れるのですが、アレ、ちゃんと古文指導をしている塾に通っている人じゃないとできませんよ、まったく。過去問を解くだけでは理解できないし、高校生向けの古文参考書は細かすぎるし、もちろん、中学校の教科書には全く載っていないことばっかりだし。まあ、ともあれ、よくぞ合格してくれました。オメデトウ。Kama
2008.01.24
コメント(0)
-
合格報告届いてま~す(2)
今日の合格は2校。 秋草学園高校 狭山ヶ丘高校です。合格おめでとう! 私立挑戦校、県立高校に向けてまだまだ走れ走れ~!
2008.01.24
コメント(1)
-
合格報告届いてま~す
昨日の私立高校推薦(前期)入試の合格が発表されています。現時点で 白梅学園高校 聖望学園高校 豊南高校 保善高校受験者の合格が出ました。 もちろん全員『合格!』です。みんなおめでとう!このあとも県立第1志望者は気を抜かず、全力で走りましょう!
2008.01.23
コメント(0)
-
タラ
先ほど出勤する前に家で何気なくテレビをつけていたら某番組のコーナーで、鍋の季節ということからか、「タラ」の特集を組んでいた。タイトルコールのBGMの選曲にプロデューサーだかディレクターだかの遊び心を感じたのは、僕だけではないでしょう。いいな、こういう上品なシャレは♪ かかっていた音楽は、映画「風と共に去りぬ」のテーマ曲。 「風と共に~」、原題「GONE WITH THE WIND」は映画史に残る、名作中の名作ですよね。マーガレット・ミッチェルによって書かれたこの作品は、南北戦争当時のアメリカを舞台とする小説です。原作本より、とにかく映画化されたものが有名です。 スカーレット・オハラを演じた主演のビビアン・リー。あまりのウエストの細さが話題になりました。相手役のクラーク・ゲーブルは、「伊達男とはまさに・・・」といった感じ。スケールの大きさと音楽の素晴らしさに僕も子どもの頃から大好きな映画の一つとして挙げてきました。 ・・・で、それと「鍋」と何の関係があるか・・・。 舞台となったのがアメリカ南部、ジョージア州アトランタあたり、スカーレット・オハラの農場があった架空の場所が「タラ」という地名なんです。 あの重厚な曲、「タラのテーマ」っていうんですね~。 CMなどでもこういう曲名をひっかけたシャレは意外と多く、「気づかれるかなぁ、気づかれねぇだろうなぁ・・・」という作った人のイタズラ心を垣間見るとなんか、クスっと笑ってしまいます。Kama
2008.01.19
コメント(0)
-
広辞苑
こんばんは、鎌田です。昨日、テレビを見ていたら、「今、一番売れている本」という特集をやっていました。 第一位はダントツで「広辞苑」(第6版)だそうです。 それにちなんで、広辞苑のこれまでの「歴史」的なモノをやっていて、戦争前からその原点はあったそうな・・・。愛夢舎に置いてあるのは「第5版」。結構いい値段なので、僕個人では買いません。ただでさえ部屋が狭いのに、あんなデカいのは・・・。ただ、場所に余裕ができれば一冊は置いておきたいと思っています。 辞書と地図帳は、毎年とまではいきませんが、せめて5年に一度くらいは買いなおしたい。今回の広辞苑の改訂は10年ぶりだそうです。 ところで、最近は「辞書」と言っても「電子辞書」が主流ですね。 僕は、辞書については「本=紙」のものが良い、と常々言っております。 電子辞書は、持ち運びもラクだし、色々な機能があって、確かに便利です。 が、僕は、この「便利さ」に落とし穴があると思っている。 紙の辞書で目的の語を調べると、どうしたって、その前後の言葉、同じページのそのほかの語に目がいく。だから、知りたくもなかった知識が余分に手に入る。 これが紙の辞書をおススメする理由です。 僕は大学生時、誰だかの薦めで、英語関連の辞書は3冊持ち歩いていました。「英和」、「和英」、「英英」の3冊。(実は、和英を使ったことは殆どないけど) 国語辞書もそうですが、こと英語やフランス語の辞書になるとその前後の単語というのは語源を同じくする語であったりして、つまりそこに目がいくことでさらに深く知ることができる。 「そんなら、電子辞書だって関連語は調べられる。」 そうかも知れませんが、わざわざ関連語を調べようという人はなかなかいませんよね。僕だって、一語調べるのだって、面倒だった。面倒くさいながらも調べて、同じ「画面」に別のことが載っているからいつの間にか「得」をしているわけです。初めから知るつもりなら、それは「得」ではない。 以前、「テレビに一家は一台」ということを書きましたが、同じことです。僕らは見たくもない番組を他の誰かにつきあってみていたから現時点で自分の興味の範疇にない事柄をいつの間にか知っていた。 そこで、辞書もそうですが、「便利さ」というのは「広がり」を妨げるな、と。 不便さがあるからこそ、現時点の自分を超えたところに触れる機会ができて、「広が」っていく。そんな風に思います。 そんな折、「広辞苑」がベストセラーというのは少々意外。やっぱり「紙の辞書」の不便さに魅力を感じる人は少なくないのでしょう。 そう、「不便」こそ、人の広がりにつながるのかも知れません。僕の家なんか、いまどき珍しい二層式洗濯機で、しかもタイマーが壊れているもんだから、水流が自動で反転することがなく、仕方がないので、僕がたまに立って手動で切り替えなければならなくて、足腰の運動になる。テレビも、片方のスピーカーが壊れていてだから、ステレオの音楽が片側チャンネルだけ聞こえて、各パートをはっきり聞き取ることができる。DVDプレイヤーも壊れてしまって、偶然にしかディスクを読み取らないからその間、毎回福引気分でドキドキ感を味わえる。また、ディスクが回転して、機械が必死に読み取ろうとしている動きが手に取るように分かる。唯一の暖房器具であるハロゲンヒーターもたまにタイマーが壊れて朝起きても点きっぱなしになっていることがあって、寒い朝は助かる。洗濯物を外に干せないから、室内干しをすると、今の乾燥する季節には、ほどよい湿気を与えてくれる。どうです、不便って、いいでしょ?Kama ・・・書いていて、さすがに悲しくなってきた。今年は、いい加減に引越ししようかな・・・。
2008.01.18
コメント(2)
-
初雪
昨夜、ついに雪が降った。 「昨夜」というのがややこしいけど、もう1月18日になっているけど、ちょうど24時間ほど前、つまり1月17日の午前1:00ごろ、要するに、16日(水)の勤務を終えた帰りのことである。 初雪だ。 僕が寝ている間にもしかしたら既に降っていたのかも知れないけれどもでも、僕が寝ている時間帯はたいてい日が昇っている間であって「降った」というハナシを聞いていないから、おそらく昨晩のが初雪だろう。 入間に初雪が降った。 こんなときには、ジョージ・ウィンストンの曲が、よく似合う。 センター試験が近づくとよく雪が降る。 そういえば、僕がセンター試験を受けたその日も雪だった。 長野県で暮らしていた僕は確か共通一次からセンター試験に移行して間もない頃の受験生だったが、初日の試験を上田市で受験し、そのまままっすぐは帰宅せず、悪友たちと軽井沢まで電車を乗り過ごして、雪の中、森の中、一軒だけ、ぽつんとたたずんでいる珈琲屋さんを見つけて、その日のテストの出来は一切触れず、将来の夢物語を、3人で、したのだった。確か僕は、プロ・ミュージシャンになることを語っていたと思う。 センター試験が近づくと、よく雪が降る。 雪を見て、クリスマスを思い出す年齢は過ぎ去ったようだ。 僕は、雪を見ると、センター試験を、思う。 今朝起きると、見事な晴天で、雪は跡形もなくなっていた。Kama
2008.01.17
コメント(0)
-
遅れちゃったけど「成人おめでとう!」
一昨日の夜、我が塾3期生のT君から電話がありました。 「じゅくちょう!飲みに行きましょう!」 そっか、成人したんだね。とってもうれしい誘いでした。 でも、現在塾は入試直前です。残念ながら今回は断ってしまいました。 もう少し落ち着いたら、こっちから絶対連絡するからね。 私たちの塾も今回の受験生を送り出すと、第8期生まで送り出したことになる。 第1期生のメンバーで大学に行った子達は今年から社会人です。彼らからも「飲み会」の誘いを受けているのですが・・・。なかなか全員の都合が合わなくて、実施されていません。 それにしても、第1~7期生のそれぞれの中で頻繁に塾に顔を出してくれる卒業生がいます。とってもうれしいことです。「もと塾生」と「先生」の関係でなく、一緒に働く仲間(先生)になった者もいます。今現在も、自分が学んだ学び舎で先生として働きたいという者も結構います。これも何かの縁なのでしょうね。「宇宙の神秘」を感じます(笑)。 今度の第8期生でもそんな関係が続く生徒が現れてくるかもしれません。とても楽しみです。 じゅくちょう
2008.01.17
コメント(0)
-
死に至る病
不吉なタイトルでございますね。大丈夫です、「死」とかそういうモノを扱うわけではありませんから。 哲学・思想・精神世界方面をかじられた方ならお分かりだと思いますが、デンマーク出身の哲学者キェルケゴールが1849年に発表した「死に至る病」という著作があります。冬期講習で、中学3年生の国語の授業を担当したのですが、テキストの文章の一節に、キェルケゴール的な部分があって、毎年その文章は扱うのですが、その意味が理解できる子とできない子が半々くらいに別れ、今回は比較的、理解できる子の方が多かったのですが、その「難しいバージョン」ということで最近、「死に至る~」が少し話のネタになっています。僕は大学時代にこの本を読んだのですが、「書いてあることは読めるし、それぞれの言葉の意味も知っているけれど書いてある内容が理解できない」という奇異な体験をした、思い出のある本です。結局、なんとなく言わんとすることを理解するまでに半年近くかかったかなぁ。それは、第一編のド頭にはじまります。紹介してみましょう。 -----------------------------------------------人間とは精神である。精神とは何であるか?精神とは自己である。自己とは何であるか?自己とは自己自身に関係するところの関係である、すなわち関係ということには関係が自己自身に関係するものなることが含まれている―それで、自己とは単なる関係ではなしに、関係が自己自身に関係するというそのことである。人間は有限性と無限性との、時間的なるものと永遠的なるものとの、自由と必然との、綜合である。要するに人間とは綜合である。綜合とは二つのものの間の関係である。しかしこう考えただけでは、人間はいまだなんらの自己でもない。二つのものの間の関係において関係それ自身は否定的統一としての第三者である。それら二つのものは関係に対して関係するのであり、それも関係のなかで関係に対して関係するのである。たとえば、人間が霊なりとせられる場合、霊と肉との関係はそのような関係である。これに反して関係がそれ自身に対して関係するということになれば、この関係こそは積極的な第三者なのであり、そしてこれが自己なのである―(以上、岩波文庫版より引用)------------------------------------------------ ・・・と、この調子で延々と続いていくのですが、「関係」という言葉が連発してくるあたりでもうワケが分からなくなってきますね。土台、日本語で理解しようとするから余計難しいというハナシもありますが、まあ、よくもこんなに分かりづらく書くことができるもんだと、哲学科出身の僕からして、思いますよ、ホント。さて、中学3年生は、もちろんこの文章を読んだわけではありません。もっと簡単に、核となる部分だけを書いたものがあって、それは次のような感じです。 -----------------------------------------------自己を観察するのは、他人を観察するのとはちがう。私はこういう人間であるという結論に私が到達した瞬間に、その結論は必然的に誤りとなるだろう。なぜなら私はこういう人間ではなく、私がこういう人間であると考える人間だからである。しかし実は、そういった瞬間に、私は、もはや私がこういう人間であると考える人間ではなく、私がこういう人間であると考える人間だと考える人間であろう。(加藤周一氏「日本人とは何か」より)---------------------------------------------------- どうです。大分、分かりやすくなったでしょう?(・・・そうでもないですか?)この一節でキェルケゴールと同一なわけではありませんが「関係連発部分」で言わんとしていることと大分近いと思います。もっとも、中学生にとっては、それでもやっぱり難しく思える場合が多いのですが。(だから結局、僕が図式化して説明することになる)さて、なんで突然こんな文章を持ち出したかというと、いよいよ入試が迫ってきて、ここで言われている人の自己認識の多重構造が結構な役割を果たす場合が出てきているからです。例えば、昨日、受験生を集めて、それぞれの志望校の過去問をテスト形式で一斉にやってみるという機会を作りました。 張り詰めた空気の中、真剣に問題に挑む。 その場で採点をして、結果を目の当たりにする。 合格できるとは到底思えない得点・・・。 ある生徒はパニックに陥ります。またある生徒は「もう、どうにでもなれ」と自暴自棄になる。強がりで「アハハ、こりゃひどい!」と、涙目で笑ってみせる生徒もいる。 練習で問題を解いただけでそんなに大きな衝撃を受けてしまう、いったい、受験というものは15歳の子たちにとって大変な重圧なんですね。 ところで、ここで例の「多重構造」が登場します。「今、自分は落ち込んでいるなぁ・・・」そうやって自己自身に関係する自己がいるかどうか。 自分が落ち込んでいる、自分がパニックになっている、その「自己自身」をとらえ、分析する「自己」は冷静です。ともすると、パニックに陥っている自己自身をみて「おやおや、大変だよ、このボクは。もっと冷静になりなさい。」と、自己自身に指示を与えることすらできる。 反対に、自己と自己自身との区別がなくなって構造の多重さが失われると、これは理性をはなれ、ただ感情に流されるままになってしまう。そうすると、勉強も手につかないし、食事もノドを通らない。 これは大変難しいことだとも思いますが、だから、自分の様子を冷静に見ている「自己」を感じること。これは、難局を耐え、乗り切るときにひとつの方法として役に立ちえます。 僕なんて、その多重構造が結構ハッキリしているもんだから「お前から『冷静さ』をとったら何も残らない」と大学時代、学友から揶揄されたもんで、それはそれでどうかと思いますが。 ただ、面白いのは、そんな僕が、構造の多重さを見失って、感情の起伏を自分の根幹にダイレクトに受けるときどうも僕は「人間らしく」なるようです。 だから、そのバランスが重要ということになりますよね。 受験のプレッシャーにオロオロしている彼らはとても人間らしい。自分の状態を冷静に分析して平然としている15歳は、確かに、気持ち悪いかもしれない。 そうは言っても、15歳、18歳の子たちが明確に「冷静な自分」を感じるということはそんなに簡単なことでもないでしょう。だから、大丈夫。それでもそういう自分を少しでも見出せたら多少は気がラクになるかも知れませんよ。 ここまでくると、知識の定着とかそういう以前にメンタルヘルスの方がよほど気になります。それこそ、胃に穴が開くんじゃないかというほど彼らは思い悩むもんで。それを乗り越えたとき確かに、彼らは大きな財産を得ているのですが。Kama
2008.01.14
コメント(3)
-
ライブの準備も地味に
入試本番直前なので生徒や保護者の方々も一番ナーバスになる時期。 おおっぴらに「愛夢舎バンドライブ」のことは口に出せない(もちろん、私たちの頭の中は受験のことでいっぱい)。 でも彼らの進学先決定直後に開催予定のライブの準備もしないわけにもいかない。 昨日私はオフをいただいておりましたので、ライブで演奏予定(候補曲)のドラムをイメージトレーニング。今月中に2回目のスタジオ(メンバー全員で合わせる)を予定しているためです。 私はオフ等を利用して一気に練習を済ませます。愛夢舎バンドのメンバー(って全員先生だろが)はみんなそのような練習の仕方をします。 ですから、スタジオに入ったときには基本的にある程度カタチになっています。 スタジオでは「グルーブ感」とか「アレンジ」とかそういったものを仕上げていく方法です。 こうでもしなければ、私たちのような社会人バンド(オジサンバンド?)はライブなんてできません(笑)。しかも、練習時期と「生徒たちの人生のかかった入試」時期はほぼピッタリと重なっている。 なんでこんな茨の道を愛夢舎は選ぶのか・・・。 先生たちの趣味だから・・・それもある。でも、やっぱり生徒たちのリクエストがあるからです。 生徒たちが誰も「ライブ」のことを言わなくなったら、やめるんだろうな・・・。 いやいや、音楽のすばらしさを伝えるために、強引に開催するかも・・・。 どちらにしても生徒たちが一生懸命勉強してくれて、私たちが納得のいく生徒指導ができている、ということが前提の企画です。 どうか、みんながすばらしい結果を出して、気持ちよくこのイベントを盛り上げてください。 P.S.ライブ参加したい生徒諸君どんどん声かけてね!(卒業生・生徒諸君のお友達も歓迎) ジュクチョウ
2008.01.12
コメント(0)
-
出陣式
愛夢舎では毎年この時期に「出陣式」なるものを行っている。 目前の入試に「勇気を持って立ち向かえる」ように中3・高3全受験生に講師陣がエールを送る会です。 小田切先生の「入試当日注意事項」から始まり、各先生から「激励の言葉」、私からは全先生を代表して「合格祈願のお守り」をひとりひとりに手渡した。最後に「ダルマの右目を入れ」、全員で記念撮影。 「出陣式」だというのに感極まった生徒も数名。おいおい、入試はこれからなんだぜ。涙は合格発表の日に「うれし涙」として流そうよ。涙の無駄遣いはいかんぜ。 「楽しい受験勉強」もあと少ししか楽しめないんだ。どうせなら存分に楽しんでやれ! ジュクチョウ
2008.01.10
コメント(0)
-
主人公 ヒーローの変遷
僕は、普段テレビドラマを見ません。キライというわけではありません。正確には、「見ない」のではなく「見ることができない」。何しろこの仕事をしていると家に帰る頃には日付が変わっている。いわゆる「ゴールデンタイム」は、バリバリ授業中です。観るテレビ番組は午前中遅めの情報番組か、深夜番組に限定される。そんな僕ですが、冬期講習が終わって休みだったので昨夜、実にめずらしく、ドラマを見てみました。というのも、少し前から生徒たちが「ハチクロ、ハチクロ・・・」と言っているのを聞いていて、何のことだかさっぱり分からなかったのだけど、そんなに人気があるのなら、まぁ、観てみようかな、と思った次第で。実際、一般に人気のあるものは、一応知っておかねばと思っています。だから、大ブームになった「冬のソナタ」なんかも観ておけばよかったと今さら思う。 さて、ドラマを見ていて、興味深く思ったことがありました。ただ、これは「ハチクロ」ではなく、その後にやっていた別のドラマについてなんですが。 「あしたの、喜多善男」。主演の小日向文世さんは、前から味のある演技をする人だなぁと思っていて、その小日向さんの、意外にも初主演ドラマ。その程度の予備情報はありましたが、ぶっちゃけ「ハチクロ」のついでにそのまま観た。ところが、コレが意外と色々な気付きを与えてくれた。昨日、「1秒」のハナシを書きましたが、それに通じるものもあるかも知れない。主人公の「喜多善男」は11日後に自らの命を絶つことを決めているというなんともブラックな、奇想天外な設定。初回であった昨晩は、その「喜多」が、死ぬ前にやりたいことをいくつかやっていました。よく、「死ぬ前に何かひとつ食べるとしたら」というなぞかけがありますが、そして僕はなんとなく「寿司」と答えることにしているんですが、そういうのって、いよいよ死ぬことを意識してからでないと本当には分からない。残りの時間を意識してこそ、本当に必要なものが見えてくる、そんなこともあるかも・・・。・・・って、ドラマの内容ではそんなことを思ったり・・・。 ただ、ドラマの内容そのものではなく、その「つくり」というかなんというか、そういう部分で思ったことが、他にあるのです。 主人公のキャラクター像、だいぶ変わりましたよね。 僕が幼かった頃は主人公といえば、「憧れ」の存在だった。ドラマでもアニメでも特撮でも、男性のキャラクターであれば、強く、優しく、カッコいい。大体において、「アイドル」も、その言葉どおり、「偶像」的な存在でした。 ところが、昨晩の「喜多善男」なんかはこれでもかというくらいにカッコ悪く、弱く、ダメダメなヤツであった。 昨日の回のラストシーンではネガティブな自分の心と対峙。「分かってるよぉ!世界はオレを必要としていないんだ!オレも世界を必要としていないんだ!みんな、喜多善男のことが大キライなんだ!そして、オレも喜多善男が大っキライだぁ!」そんな風に絶叫した。(なかなか印象的なシーン・・・) そこで思い当たるのは、いつの頃からか、主人公は「憧れ」ではなくなってきていたということ。 ドラマだけではありません、アニメでも特撮モノでもそうです。 例えば、一時代を築いたあの「エヴァンゲリオン」。主人公の少年は、強くもなく、カッコよくもなく、心はとても弱く、いじいじ、内向的であって、ヒーローらしさのかけらもない。 だから、僕は「エヴァンゲリオン」は究極の18禁だと思っている。面白い作品だけど、子どもが見る場合にはペアレンタルガイダンスが必要か、と。 今さら言うまでもなく、今の主人公像にあるのは「憧れ」ではなくて、「共感」です。 「エヴァンゲリオン」は、あれほどの社会現象になったので関連する著作が、えらい量、出版された。そうした中で、ある方が「主人公がああだから、人気が出た」と分析されていた。「主人公が自分と同じような、平凡で、どちらかと言えば弱い少年で、そこに自己投影することで感情移入する」と。だから「エヴァ」はタチが悪い。子どもたちの「共感」を集め、はじめの方は、何のふくみもないような、純心無垢なロボットアニメのような体をして、視聴者が自己投影しきった頃に訪れるラストがアレですからねぇ。 アイドルも「偶像」ではなく「共感」になった。どこにでもいるような平凡で身近な存在、ともすると、現実の自分よりも可愛くも、賢くもないと見えるのかも。 「喜多善男」は、やはり共感を生むキャラでしょう。 先ほど、「カッコ悪く、弱く、ダメダメなヤツ」と書きましたが、そこで、「イヤ、カッコ悪くないよ。人はみんなそうやって悩んでいるし、弱いから『人』なんだし。それを「ダメダメ」と言う、カマタ、お前の方がダメだ!」と思っていただけていたら、まさに僕の予定どおりです。 ぶっちゃけ、この「 」の中の批判と同じように人としての僕は感じる部分もある。で、これが「共感」。 「カッコいい」の定義がぐらついているのです。 スポーツも勉強も苦手で、性格にどこか歪んだ部分があって、人とコミュニケーションをとることもヘタで、自分自身に疎外感を感じてしまう。これが「カッコいい」のが現代。この真逆のキャラクターは現代では「悪役」ですよね。 なんなんでしょ、コレ。ムリヤリ教育に結びつけるとするならば、政界では未だ怪物扱いされるあの「●●根元首相」が教育改革で求めた「個性を重んじる」ということの結果なのでしょうか。でも、子どもたちだけでなく、オトナの僕らでも昔ながらの「憧れ主人公」より「共感主人公」になじんでしまっているから、別に教育方針の問題でもないようにも思うし・・・。 少し大げさかも知れませんが、弱さの具現化であるかのような主人公を見て、自分の弱さを肯定する、あるいは、自分はそこまで弱くないから自分より「ダメ」に見えるヤツを見て安心している。そんな気持ちが僕の中になければよいなぁ。 あとは、子どもたちには「カッコいい!」ことに憧れてほしいと思う。で、それを言うと、「現代に『カッコいい!』人がいないからしょうがない」って言う人がいるんだけど、そんなことは決してないでしょ。 どうだろう。たまには「共感主人公」ではなくて、昔ながらの「憧れ主人公」のドラマを作るっていうのは。主人公は全国模試でトップ10に入るくらいの秀才で、スポーツも万能で、各クラブからヘルプを頼まれる。容姿端麗、性格も明朗、女子にも人気があって、ユーモアもある。他の男子たちはひがむだけだが、そんな性格の悪い級友のことすらも彼は肯定し、強いリーダーシップを発揮する。家はお金持ちで、豪邸に住む彼は芸術もたしなむ。結婚を決めた彼女もいて、なんのトラブルも起こらず、東大法学部に進学した彼は、26歳にして衆議院議員になり、やがては世界初の首相としてのオリンピック出場を果たす。そして金メダルを・・・。そういう完全無欠のキャラを主人公にしてひたすらそれを肯定し、「あの人を見よ!」とオトナたちは推薦番組にする。 ・・・書いてる自分が「やっぱり、コレ、悪役っぽいなぁ・・・」と感じてしまうあたりがフシギです。Kama
2008.01.09
コメント(0)
-
一秒と一言と一人 ~最終決戦
こんばんは、鎌田です。普段僕は、このブログにおいては極力、「塾」や「勉強」とは一見関係なさそうなことを書くことにしています。実は。(・・・「実は」も何も、書いているアホなことを見ていただければ分かるか)もっとも、「一見関係なさそう」というだけでこれは狙っているわけではないのですがそもそも「仕事は仕事、私生活は私生活」と器用に分けられるタイプではないので僕が考えることは、どこかしら「それっぽく」なってしまっているのでしょうが、それでも、だからこそ塾と関係のない方面の方にも読んでいただけているのではないかと思っています。が、今回は塾と受験のことを書きます。今回は逆で、塾や受験のことが、そのまま僕やみなさんの「私」にも関係あるかも知れないから。 佐々木が先に書いておりましたが、昨日、冬期講習会が終了しました。ウチの冬期講習は、それほど長い期間はやっていません。「やりっぱなし」をよしとしない方針なので、1日は丸々、講習会の学習範囲の復習をする日、(この日は授業はありません。演習&質問大会です)最終日は、理解度の確認テストの日で、いわゆる授業を行う日はわずか6日間です。もっとも、復習の日があるのとないのとでは学習効果に何倍もの違いが出ると思っていますからこの日をはずすわけにもいきません。受験学年は(中学3年生と高校3年生。ウチは中学受験はやってません)コレに「正月特訓」が加わります。1月2日と3日。朝9時から夜7時くらいまでみっちり勉強します。だから、僕ら講師に正月はない。諸々の準備があるので、大晦日だって仕事です。1月1日だって、仕事です。年間業務予定上は休みですが結局、何かある。カレンダーが変わったって生徒たちはまだ頑張っているので僕らにとっての「新年」は、やっぱり受験学年が卒業した3月になる。昔は「正月特訓」は元旦からやってました。1月1日、午前6時集合。昔というのは、愛夢舎になる前、佐々木や小田切、僕が別の塾で働いていたころです。僕は愛夢舎メンバーとしては新しい方なので戻ってきたら元旦がなくなっていたという感覚なのですが、元日に行わない理由をこのように解釈しています。1月1日まで塾に来なければならないほど時間がないのか?普段、これ以上ないほどの最大効率で勉強し、可能な限りの時間を費やして、それでも足りないなら1月1日もやむを得ないが、そんなことって、普通、ないだろう?だったら、普段、時間をムダにしないこと、同じ時間で、より効率よくできる方法を考えた方がよい、と。元旦に塾に来るのには、精神面の効果もあるとは思う。が、一瞬足りとも気を抜くことができないほど受験って切羽詰ったものなのか、と。電車で会社通勤をしていたサラリーマン時代、電車内でPCを広げて仕事している人を見ると僕は内心、小馬鹿にしていた。そんなわずかな時間を使わねばならないほど、仕事の効率が悪いのだ、と。じゃあ、ほとんど休みをとらず仕事しているお前はなんなんだと言われても仕方のない動きを僕もするのですがまぁ、それはそれで小馬鹿にされてもよいと思ってます。ただ、僕は一日の時間を限界まで使うのがイヤで、だったら数日に分散したいだけ。最大効率ではやっているとは思ってる。・・・少し脱線しましたが、ともかく、冬期講習は終了しました。実に、僕にとってはこの短い講習会が受験への最終決戦であり、まさに「時間と効率への闘い」であります。そんなことを言うともう受験は終わったかのようですが、もちろん本番の入試はこれからです。まだまだ、生徒たちには伸びる余地がある。が、受験勉強というくくりにおいて、この講習会ほど1秒を重く感じる場はないのです。例えば、僕は生徒たちに「コレはよく出題されるから覚えておけ」とか、反対に、「コレは今まで出題されたことはない」とか、そういうことを言います。もちろん、過去の出題を分析した結果であって、テキトーをしゃべっているわけではありません。しかし、その一言が彼らの人生のベクトルの向きを変えるかも知れない。僕は、受験に関して、学校は偏差値が高ければ高い方がよいとは全くもって考えていません。進学した先で、人生の成否が決まるとも思っていない。どう進むか、進んだあとどう考え、生きるかが全てを決めると思っています。が、どこに進むかでベクトルの向く方向が多少定まるのも確か。また、受験に関して言えば、合格ラインからほど遠い結果で涙をのむということも、普通はありえない。わずか数点、数問の差で明暗が分かれる。埼玉県の模擬テスト、北辰テストで偏差値を「5」上げるのなんか簡単だと僕は言います。なぜなら、北辰テストで「1点」点数が違うと、偏差値は1.3程度変わるわけで、そしてテストの配点は1問2点がほとんど。ならば、計算問題でもなんでも、2問正解すれば、偏差値が5上がるということになる。(もっとも、この「2問」が難しい)そこで、いよいよ受験を強く意識した彼らにとって冬期講習の「一秒一言」は大きな意味を持つ。その一秒で僕がしゃべった一つの知識、彼らがその瞬間にアタマに刻んだ一つの言葉、それが彼らの人生のベクトルの向きを変えるかも知れない。僕のしゃべった「『ぜったいぜつめい』の『たい』は、対決の『たい』じゃないよ、カラダだよ!」という一言が、運命を変えるかも知れない。「『治安維持法』は覚えておけ」という一言が受験の成否を決めるかも知れない。 前にも似たようなことを書きましたが、この冬の講習は、自分のしゃべる一言一言に自分自身が怖さを覚えるのです。そして、これも前に書きましたが、だからといって、僕は受験の結果を自分自身の責任とも思いつつ、でもその責任は自分にはないとも思う。彼らの運命を決めるのは彼ら自身であって僕が運命を決めたら、それは僕が神になってしまってただの「奢り」であるから。それでも、やっぱり自分の責を感じてしまう。あのとき、その一言を僕が発していたら・・・。いやいや、いかん。それは僕の奢りだ。そんな思いが錯綜する時期が近づいてきたのです。そこで改めて思うのが受験に限らず、僕自身の生き方のベクトルもやっぱり一秒一言が大事であるな、と。これには、成否はないでしょう、たぶん。それは、その後の自分が決めることだし。第一、毎秒毎秒そんなことを考えていたら何もできなくなってしまうからほとんどそういうことは思いません。この時期、彼らから、それを思い知らされる。冬は、僕にとってそんな時期です。ウチでは生徒はタイムカードで在塾時間を計算しているのですが、12月、ある生徒は180時間以上塾にいた。受験生は、ほぼ全員月に100時間以上、塾にいる。180時間という時間は、それ以上増やそうとしても物理的に不可能な時間です。塾が開いていて、自分が来られる時間の全てを塾で過ごして得られる時間だから。だから、あとは効率の問題です。その180時間の中で僕らはどれだけの「一言」を与えられたか。彼らは、親や周囲の人々、僕らからの期待をプレッシャーに感じて、それにつぶされないように必死で立っている。(たまに泣き崩れる子もいるけど)僕らは僕らで、180時間もの時間を僕らに頼ることに費やしてくれた彼らの信頼と期待をプレッシャーとして受ける。が、僕らと彼らは対等ではない。僕らはオトナで、彼らは子どもで、僕らは「職業」で、「プロ」であるから。彼らが月に180時間、塾に頼るならそして僕が彼らにそれをさせるのなら、僕は180時間以上、彼らに応えねばならない。さて、冬期講習は終わりました。言ってみれば、オリンピックや全国大会の前の特訓期間が終わりました。あとは、最終調整をして、会場入り、選手村入りをして、調子を崩さぬよう、試合の時間を待つのです。いよいよ出陣です。Kama
2008.01.08
コメント(0)
-
生徒諸君お疲れ様でした!
今日は冬期講習会の締めくくり「確認テスト」の日です。 今も中1・2がテスト中ですが、合間を縫ってこのブログを書いています。 午前中は小学生、午前から夕方5時にかけて中3・高3の受験生、昼間は高1・2生、そして夜が中1・2です。 合計10学年14クラスのテストを実施。 先生たちは1分1秒単位で動く。試験監督、採点、テスト中ではない学年の生徒の指導、を網の目のような予定表に基づき、遂行する。(もちろん、講習中の夜中に14クラス×教科数分のテストも作成) いや~本当に先生たちの頑張りがあって、成し得る愛夢舎講習会です。これが年3回あるんですよ。 あれっ、生徒のことを褒めようと思って書き始めたのに「身内自慢」になってしまいましたね。 生徒諸君、冬期講習最後までよくがんばりました。受験生では毎日13時間塾にいた子もいたし、昼間は部活やクラブチームで夜は塾という中1・2生もたくさんいました。途中居眠りしちゃう子もいて、私は後ろから何回もハリ扇かましたけど、心の中では「えらいぞ、がんばれ」と言っていたんですからね。 確認テストですばらしい結果を出した人はもちろん、ずっこけた人も今回の講習会の勉強は必ず今後に活きてくる、と信じてください。 受験生は今月来月の入試本番で、他学年の生徒はじわじわと効いてきますからお楽しみに。 生徒諸君、先生方本当にお疲れ様でした。そして、見守ってくれた保護者のみなさんありがとうございました。 ジュクチョウ
2008.01.07
コメント(0)
-
この体質・・・イヤな季節。
唐突だけど、僕は「ネコ型人間」である。そう言うのには、もちろん理由がある。1.性格がネコっぽい。 人の性格・タイプをイヌとネコに大別するなら、 僕は断然、ネコ。 人見知りするし、結構、勝手気ままだし。 2.体質がネコ。 寒いのが大キライ。 ネコ舌なので、インスタントコーヒーを入れるときは お湯で溶かして、後は水でうすめる。3.ネコ年生まれ。 ちがいました。寅年です。4.ネコの言葉がわかる。 きっと勘違いですが。残念ながら、見た目はドラえもんではありません。 そんな僕にとって、イヤな季節になりました。 ネコ型と関係あるのかどうだか、分かりませんが、僕は、静電気体質でもあるのです。 服を脱ぐときに体中にはりついてペリペリいうのはもちろん、金物に触るとバチっとくる。これが、たまらなくイヤだ。 車に乗るのにドアに手をかけると「バチッ!」。 家のドアに触っても「バチッ!」。 もちろん、痛い。 自分でそれを分かっているから金物に触るときはドキドキするんだけど、ついうっかり手を出してしまって、「しまった!」と思ったときには既に遅し。「バチッ!」とくる。 他の静電気体質の方と痛さや音のでかさ、頻度などを比べたことがないのではっきりは分かりませんが、とにかくバチバチ、ホントに音がする。 同じ静電気体質の人と書類なんかを手渡しすると大変だ。僕の指先とその人の指先の間でハッキリと火花が飛び散る。 誇張や冗談ではない。ホントに、指と指とが、火花でつながる。もう、リアルE.T.なのである。(・・・で、お互い痛みにしゃがみこむ、という・・・) 今シーズンは割と平気かと思っていたら、今日はバチバチ、来た。もう、痛いし、びっくりするし、怖くてしょうがない。覚悟のしようがないから、いつまでたっても慣れない。おまけにこの静電気というのは「バチッ!」ときたその怒りをどこに向けようもない。ただひたすら迷惑なのだ。 それに、何の役にたっているとも思えない。それこそ、自分の気分ひとつで指先から電光を走らせることができればそれはそれで面白いだろうし手品のひとつもできるだろうし少々痛くても、ガマンのしようもあるが、実際には一番ビックリするのは自分自身である。省エネにも何にも役に立たない。いつ火花が飛ぶか分からないので周りの人に見せて喜んでもらうこともできない。 まあ、生き物だからしょうがないんだけど、どうもこういう何の役にも立たないくせに自分にとってはえらく迷惑ということがいくつかある。 例えば、足の小指をぶつけるヤツ。 アレ、なんなんでしょう?戸棚の角にしこたま小指をぶつけて指が取れたかと思うほど痛くて、でも悪いのは自分に決まっているから怒りのやり場がなくて、周りの人も何が起こったんだか分からないから笑いもとれない。 まるでいいことなしだ。 半分くらいは冗談で書いているのですが、とにかくですねぇ、静電気体質の人間にとってはイヤなシーズンなのです。 ユーウツだ・・・。 せめて火花が飛び散るのを見て、周りの人に「きれいだなぁ」くらい言ってほしい。 もっとも、実際に言われたら余計腹が立つのだろうけど。Kama
2008.01.02
コメント(4)
-
そんなの関係ねぇ.2 ~おぞましい・・・
みなさん、新年をいかがお過ごしでしょうか。以前、このブログで「そんなの関係ねぇ」が、ともすると思考中止の文化につながり得るということを書きました。 「そんな大げさな・・・」と、多くの方はお思いでしょう。また、「シャレやギャグの通じない、アタマの固いヤツだ。」とお感じの方もいらっしゃることでしょう。 でも、こりずに「そんなの関係ねぇ」です。 今朝、出かけるために身支度をしているとき流れていたテレビ番組を何気なく見ていたら、例のあの人が登場しました。なんでも、寅さんの故郷である柴又・帝釈天で芸人さんたちが新年のあいさつ、ひいてはネタを披露するという。そんなコーナーでした。断っておきますと、僕は概ね、お笑いが「好き」です。「そんなの~」の人にしたって、さんざん苦労してきたんだろうなぁと思いますし、こうして花開いたのをみると、知り合いでもないクセに「よく頑張ったね、努力は裏切らないね」なんて生徒に思うようなことを思ってしまったり。まったく、人は何がきっかけで大成するか分からんものです。 ・・・いやいや、そういうことではなくてですね、とにかくその番組ではあの人が、ほんの短い時間で「そんなの関係ねぇ!」をやってみせたわけです。 ・・・で、その後。 「それでは最後に、ここ、帝釈天にお集まりのみなさんで一緒に~!」 で、帝釈天は大合唱です。 「でも、そんなの関係ねぇ! でも、そんなの関係ねぇ! でも、そんなの関係ねぇ! ハイ、おっぱっぴー!!」 リアルに想像してみてくださいな。年端もいかない子どもたちが地面に向かってコブシを叩き込みながら「そんなの関係ねぇ!おっぱっぴー!」ってやってる。 この際、何が関係ないのかはどうでもいいわけです。子どもたちにしたって、別に何のことだか分からないわけで。 でも、初詣でにぎわう境内が「そんなの関係ねぇ!」の大合唱で埋まった光景は正直言って、身の毛もよだつほどでした。あの人だって、仮にも日本最高峰の大学を卒業しているわけだしあのギャグが苦肉の策で出てきたもので真剣に考えるべきときは、相当真剣であると思う。そうでなければ、どんな形でも、世に出て活躍しているはずがない。が、どんな問題であっても「関係ねぇ」の一言で片付けるのはやはり「反省」の拒否であると思う。反省というのは「ゴメンなさい」とは違う。振り返ってみること。良いことにしろ、悪いことにしろ。自分と直接的に関係のあることはもちろん、一見、本当に自分に「関係のなさそう」なことであっても。「どうしてこうなったんだろう?」それを考えることが次の思考や行動につながると思う。 もちろん、年端もいかない子どもたちが現実の話題に即して「関係ねぇ!」とやってるわけがありません。ただ、それが習慣化しいつの間にか思考を拒否する文化が定着することが怖いと思うのです。さらに、一緒になって「関係ねぇ」とやってる大人。どうも日本全体が思考拒否を容認するような文化になってきたようにすら感じる。だからこれは、あの人への批判ではなくて、そんな文化に移り変わりつつある僕らの文化はホントに大丈夫か、と、そういう話題なのですが、ただここで難しいのは、では、かつての文化が絶対であるかというとむろんそんなこともなく、その時代、その時代にある文化が即、その時代には正しいものであって、だから「昔は良かった」論は無意味であって、とすると、単純に「日本はそうなってきていますよね」と言えるのみなんですけどね。でもなぁ、何百人だか何千人だか分からないけど、みんなで一斉に「そんなの関係ねぇ!」ってやってるのはやっぱり、なんだか怖いなぁ。 「パキスタンでブッド元首相が暗殺されたって」「でも、そんなの関係ねぇ!」 「地球温暖化防止のための会議がさぁ・・・」「そんなの関係ねぇ!」 「韓国の政権が変わったらしいよ」「そんなの関係ねぇ!」 「薬害肝炎問題がついにさぁ・・・」「おっぱっぴー!」 ・・・。 そりゃあ、地球の裏側で起こっていることは直接、今日の僕らの生活には「関係ねぇ」のかも知れないけど、でも、「関係ねぇ」で済ましてしまうクセがつくとホントにそうなりかねない。「憲法改正の国民投票だね」「オリンピック、東京でやることになったね」「裁判員制度、始まったよ」「でも、そんなの関係ねぇ!おっぱっぴー!」 今の子どもたちがそういう思考にならないと誰が言い切れます?だからオトナはギャグの見かたを子どもたちに教えなければならないし、僕ら自体が常にこれらが反定立である可能性を考えて楽しまねばならないと思う。そうでないと、今日、明日の自分の損得だけを考える文化になってしまうかもしれないから。 そんなことを考える僕は神経質すぎですかね(笑 であれば、それこそ「そんなの関係ねぇ!」と笑い飛ばしてくださいな。とにかく、正月早々の「そんなの関係ねぇ!」の大合唱は大変、精神衛生上、よくなかった。Kama ・・・ときに、アレがこれほどはやるのは、リズムに乗せているからだというのは間違いないでしょう。かつてワーグナーが利用されたように、また、北欧の思想中心バンドが布教活動に音楽を利用しているのもそのため。リズム、音楽の力って、ものすごい・・・。
2008.01.01
コメント(6)
-
あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます!今年も愛夢舎は、子どもに愛と夢を与え続け、子どもたち、周囲のみなさんから愛と夢を与えられながら、がんばります。今年もよろしくお願いいたします。 ところで、占いを信じるつもりもお薦めするつもりもありませんが、風水での今年の運勢をご紹介します。-------------------------------------------------------------【平成20年 戊子 】戊子の「戊」(つちのえ)は土性で、土性はあらゆるものを土に還元し、また新たに再生するの意。加えて「子」(ね)は植物の種=ものごとの始まりを意味する。種子はまだ表にその力を発現することはないが、地下で着々と滋養を蓄え、来るべき時に備えて密かに時を待つ状態である。更に加えて、一白水星は「子」の定位置にあたり、子=一白水星=水の象意を裏付けるもの。これを人間界の社会活動に即して見れば、この時期は目に見える成果を期待する時ではなく、じっくりと休養し、来るべき時に備える雌伏の期間にあたる。地道な下積みの研究や、準備期間には最適だが、時にそぐわない行動を取ると、貧病争のトラブルに見舞われること必定。世界的に、陰気の極まりとともに好転の兆しも現れるが、まだ目に見えた効果は出ない。背伸びをせず、地道に細く長く着実な努力をする人にとっては、末広がりに福が福を産む種撒きの年となるが、結果を焦ると落とし穴が待つ。(こちらのページより引用)--------------------------------------------------------------う~ん、当たるも八卦、当たらぬも八卦。信じるも信じないも、自分次第ですね。
2008.01.01
コメント(0)
全24件 (24件中 1-24件目)
1