2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年01月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
ビジネスようちえん お食事会 in 名古屋
今日は『ビジネスようちえん』のお食事会に名古屋まで行ってきました。ビジネスようちえんが諸事情により無期休園になってしまったため、お詫びによるお食事会でした。この『ビジネスようちえん』はビジネスというものを解り易く説いたものでした。毎月送られてくる通信をいつも楽しみにしていただけに今回の休園はとても残念に思いました。また改めて再開する事を心待ちにしております。さて今日のお食事会では主宰者の一人である、後藤芳徳さんと事務局の松本さん、園児である私と名古屋のお一方の計4人での会合となりました。後藤さんは、会社の経営者であり、経営コンサルタントでもあり、また数多くの本を出版される著述家でもあります。是非お会いしてみたい方でしたので、今回その夢が一つ実現し、とてもうれしく思いました。意外にも少人数の会合だったので、とても濃密で贅沢な時間を過ごすことが出来ました。後藤さんの著書【チャンスと出逢うための人脈大改造】の中で、「凄い人と会うことによって自己イメージは書き換えられる」と言っておられるところがありますが、この事は実際に今日体験して“間違いない”と肌で感じることが出来ました。お話の中からは私が知りえない事がポンポン飛び出してきました。帰りがけの新幹線の中で思ったことは、自分の世界観はいかに狭いかを痛感しました。凄い人と会うことで自分の世界観が広がります。やはりチャンスをモノにするためには、人との出逢いというご縁は、とても重要だと感じました。今回このようなすばらしい設えを用意して下さったことは、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました!
January 28, 2006
コメント(1)
-
『売り上げをあげる5つの視点』
昨日は、今年最初のセミナーへ参加するため、静岡まで出かけてきました。私にとって“静岡でセミナー”と言えばインフォビッツ(考動研究会)さんです。今回は広告マーケッターである原崎裕三さんを迎えての販促プランニングに関する内容で、全6シリーズの第1回目でした。原崎さんとは昨年、女性書道家の成澤さんのセミナーで初めてお会いしました。開演前に少し時間があったので、改めてご挨拶させて頂いたところ、「あの時のセミナーでお会いしましたね」と、覚えてて下さっていて、とてもうれしかったです。原崎さんからは、名刺代わりにと著書【「バカ売れ」の法則+7】を頂きました。もちろんこの本は既に読んでいましたが・・・頂いた本は処女作の文庫版で、当時とはデザインは異なっています。3年ほど前にこの本を書店で見た時、とてもインパクトのあるタイトルと強烈なイラストで、思わず手に取ったのを覚えています。ちょうどこの頃、ベストセラーになった「バカの壁」がブレークした時でもあり、“バカがつく本”といえば、この2つを思い出します。さて講演ですが、原崎さんが、かつてドン底の状態から這い上がった経験則を元に、独自のノウハウを確立されて来たものだけにあって、とても緻密な内容でした。自らが経験したこともない学者が語る、机上の空論とは大違いです。やはり修羅場を経験した人は、言葉の重みが違いますね。それにしても、考動研究会さんが主催されるセミナーの講師は、すばらしい人ばかりです。ここでなければ聴けないような講師陣ばかりです。ですから、リピーターも多いんでしょうね。私も新幹線で行く甲斐があります。次回、誰が講師に招かれるのかを聞いたところ、これがまたスゴイ人でした。是非会ってみたいなと思っていた人でした。これを逃したらたぶん二度と聴けないかも・・・次回もまた外せませんね。
January 22, 2006
コメント(2)
-
保険広告の規制強化
昨日の地方紙に、金融庁が今年の4月から保険会社の広告の規制を強化するため、業界の広告が大きく変わるとの記事が載っていました。テレビCMやチラシなどの多くは、安い掛け金のみを目立つように、メリットだけを大きく表示する反面、不利な条件は小さく表示、あるいは全く表示しないなど、デメリットはできるだけ目立たないようにする傾向にあります。私はこれには、いつも首をかしげていました。保険に加入させるだけさせておいて、後々デメリットの部分に遭遇したら、「ここにちゃんと書いてありますから・・・」とでも言うのでしょう。こんなことを行っているから、トラブルが続出し、いつまでたってもこの業界は信頼されないんだと感じます。どんな商売でも同じだと思いますが、まずデメリットをしっかりと相手に伝える事のほうがよほど良いと思うのですが・・・・そのほうが信頼を高め、後々のトラブルも少なくなるため、よほど賢い売り方だと感じます。保険の場合は、カタチのない無形商品ですから尚更です。保険を販売する者に対して、実はこんな規制があります。例えば、「自社と他社との商品比較した資料をお客様に見せてはいけない」といったものです。他社比較は、中傷・誹謗に値する可能性があるからというのが理由です。これを他社が見つけた場合、相手保険会社へクレームを出したりします。つまりデメリットを知られたくないわけです。こんなことが業界でまかり通っているんです。「知られたくないことは、お互い隠し合いましょう」って事なんでしょうね!?保険会社の常識は、世の非常識。こんな風に思ってしまうのは私だけでしょうか?こういった記事は消費者のためにも、マスコミにはもっともっと報道してほしいと願っております。
January 13, 2006
コメント(5)
-
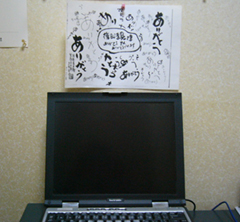
“ありがとう”FAX
“ありがとう”の言葉を全国に広める『笑顔屋本舗』の通称 徳ちゃんから“ありがとう”FAXが届きました。徳ちゃんの店はお茶屋さんですが、“ありがとう”茶といった、ちょっと変わったお茶を販売されています。抹茶でできた“ありがとう”飴や“ありがとう”ハガキ、“ありがとう”のぼりといった、“ありがとう”に関するとてもユニークなグッズも販売されています。ちょくちょく購入させていただいているんですが、先日FAXで注文したら、すぐにお礼FAXが届きました。右上の画像がそうですが、このようなFAXが届くと、とてもうれしくなりますね。徳ちゃんのアイデアいっぱいの商品は、私のお客様からもとても好評で、すごく喜んでもらえます。以前にも頂いたFAXは、下のように壁に貼っていつでも目に入るようにしています。徳ちゃん、いつも斬新なアイデアをありがとう!
January 11, 2006
コメント(4)
-
1941.12.16に完成した超弩級の不沈艦
昭和20年4月7日に轟沈した戦艦 大和。その最後の真実をドキュメント化した映画『男たちの大和』を観に行きました。この映画は広島県道尾市にて、原寸大で再現された大和を元に撮影されたそうです。戦争映画が好きな私は、この映画もまた戦闘シーン、バリバリの内容かと思っておりました。壮絶な戦いのシーンはもちろんありましたが、何よりも、そこで戦う人たちの闘志や無念・悲しみ、そして家族愛といった、人の心の奥底に響きわたるとても深い内容となっていました。今まで観てきた映画の中で感動するものは多くありましたが、今回のように感銘を受けたのは初めてでした。正直、とても泣けます。私は、TVドラマや映画を観てもジーンとくることはあっても、泣けるまでには至りませんが、この映画だけは、知らぬうちに涙が流れていました。かなりこらえていたつもりでしたが、ダメでしたね。劇中で、大和が出陣する前に甲板で「死ニ方用意」と書かれた黒板が出てきました。この言葉を見たときは、とても衝撃的でした。当時の人たちがこれを見たとき、一体どんな気持ちだったのか、それを考えると、とても悲痛な思いになりました。この映画はたぶん、名作として残るんではないでしょうか。少なくとも私の中では名作となりました。DVD化されたら、即行で買いたいと思います。また多くの方に観てもらうためにも、是非TV化もしくはTV上映してほしいと思います。観に行く前は、血が騒ぐような(笑)内容だと思っていたのが、思わぬ展開となりました。
January 9, 2006
コメント(4)
-
嫌悪感を感じる電話営業から学ぶ
ちょくちょく事務所へ色々な会社から売込みの電話が掛かってきます。昨日は、商品取引(先物取引)の会社から掛かってきました。商品取引は、過去に手を出したことがあり、とても痛い目にあったので、もう二度と手を出すまいと心に決めています。なので、この手の電話はすぐさま切りたいところですが、ここは怒りの気持ちをグッとこらえて(笑)、どんな営業トークを展開するのか聞いてみることにしました。相手はとても元気いっぱいに挨拶から始まります。どうやら前にもこの会社から電話があったようです。相手 「以前にも前の営業の者がお電話したことがありますが、覚えていますか?」自分 「覚えてないです!」(ホントはうっとうしい電話だったので覚えています。(笑)))相手 「今、ガソリンが大変なことになっていましてぇ・・・」自分 「へぇ~ 何が大変なの?」相手 「今までにないほど相場が上がってきています」自分 「あッ そう~」(無関心を装う)相手 「実はですねぇ これからガソリンが供給不足の状態になりまして・・・」自分 「そうなんですか~」(そんなことは既に知っている) 中略 (なにやら電卓をはじいている音がする)相手 「120万ほどの資金が500万円ほどになると思いますよ」自分 「それはすごいですねぇ~ でも私は興味ないです!」 中略自分 「そんなにいい話なんだから、もちろんあなたは自分でもやってるんでしょうねぇ?」相手 「えっ、自分はやってないです」自分 「どうして???」相手 「それは・・・」自分 「お前な~、そんないい話だったら真っ先に自分がやるだろーッ!」 「そんなもの人に勧めるんじゃね~よぉーーッ!! 」 “ガチャ”この間15分ほど冷静さを保って会話してましたが、最後にはとうとうキレてしまいました(笑)(本当は紳士的に会話を終わらせるつもりだったんですが・・・(^^ゞ )“スグに電話を切ればいいのに”と言われそうですが、私も営業をしているため、どんな営業トークをするのか聞いてみたくなるんです。でも最近この手の電話はだいたいシナリオがよめます。たぶんこの手の会社では、ロールプレイ(応酬話法)の勉強をしていると思われます。私はまず素人を装って、相手がどんな切り口で話を進めてくるかを聞いてみます。その後、先にも書いたとおり、私は先物で痛手を負ったため、自分なりにかなり勉強したので、相場で起こりうるリスク等々、専門用語を使って話し出します。意外な展開になるので、相手もちょっと拍子抜けしたような感じになります。(このあたりが結構おもしろいんです・・・ちょっと意地悪ですかね?(笑))私が思うに、電話はとても便利な道具ですが、その行為は本来とても失礼なものだと思っています。それは、相手が忙しいさなかだろうが、突然構わず鳴るからです。(当たり前ですが)だから相手にそれなりの気配りを心がける必要があるわけです。今回もそうですが、先ず相手に対する心配りが全くできていません。そのあたりから再考しなければ、この業界のイメージも払拭できないと思います。(電話の相手のイメージが悪い → その会社または業界のイメージが悪い)嫌悪感を感じる会話はどんな感じなのかを知ることは、自分としても勉強になるので、そういった意味でも、このような電話の会話は勉強になります。自分がイヤだなと感じたことは、どんなことだったか考えてみることで、相手への心配りもかなり改善できると思うからです。少し余談ですが、「先物取引は現物を持った商社がリスクヘッジするために行うもの」というのが私の自論です。くれぐれも一個人が手を出さないように。
January 7, 2006
コメント(2)
-
ブログ ビジネス編
今年の目標のひとつに、ビジネス用のブログを立ち上げることを掲げています。ブログといっても、このような日記形式のものではなく、どちらかといえばHPをブログ化したような感じです。当初は、Movable Type(ムーバブルタイプ)を使って、自分で作成しようかと考えていましたが、知識を習得し自ら作成するのは、とても時間を費やしてしまうため、これには断念。 プロに依頼することにしました。テンプレート・デザインや構成、そしてサイト名もほぼ決まり、あとはコンテンツを盛り込むだけです。このHPの場合、元はブログなので更新も非常に楽になります。また元々ブログは検索サイト対策(SEO)にも長けていて、検索に引っかかりやすくなるため、これからどうなっていくの非常に楽しみです。このHPの目的は、見込み客を集めることに絞ります。HP上で直接商品を売るのではなく、興味のある方にガイドブックやメールセミナーをお送りし、集客に対してのふるいをかけます。いわば、ツーステップ・マーケティングですね。ある程度、コンテンツがまとまったら、このブログでも告知ならびにリンクを張りたいと考えていますので、その際はどうぞ見てやって下さい。 m(_ _)m
January 6, 2006
コメント(2)
-
こころ和むイラスト
今日はとってもステキなこころ和むイラスト集を手に入れました。右にあるイラストがそうです。なかなかいい感じだと思いませんか!?これは、小冊子作成を行っている『はなまる企画』のあらがみさんから購入させて頂きました。彼女のブログで掲載されているのを見て、すばらしいイラストだな~と、いつも思っていました。そう思っているうちに販売されると知り、早速 購入&使用させて頂きました。イラストは京都在住のマンガ家、エトー ユキさんが描いたものだそうです。このようなタッチのイラストは今までお目にかかったことがなかったので、とてもこころに響きました。色々な種類のイラストがあるので、これからこのブログでも随時アップしていこうかと思っています。また自分が発行するニュースレターでもこれらのイラストを取り入れて、これからは、なごみ系で行こうかと考えています。かなりイケてますね、この素材は・・・
January 5, 2006
コメント(4)
-
成功への第一歩は伝統の放棄
4日付の日経MJ新聞でまちづくりの成功条件として、滋賀・彦根市の『四番町スクエア』が取り上げられていました。私は某団体で“まちづくり”に参画してきたため、とても興味深い記事でした。この『四番町スクエア』は、彦根城から800mの場所にあり、昔は「本町市場商店街」という名で、大正末期から彦根市民の台所を支えてきたそうです。しかし、昨今の大型商業施設の到来で街の衰退が始まり、一度は再開発事業に挑むが断念。このままでは、中心市街地がゴーストタウンになってしまうと、危機感を募らせた若手店主が勉強会を発足し、再興に取り組んだそうです。実はこの中で今回の成功となるカギが隠されていました。それは、成功への第一歩は、「彦根市民の台所を支える」という伝統の放棄だったそうです。これには、かなり周りとの葛藤があったのではいかと推測できます。しかし当初の勉強会が若手で行われたのが功を奏したのではないでしょうか。昔ながらの伝統を捨てることは、とても勇気のいることですし、エネルギーも費やします。しかし、この記事を読んで、新たな成功局面に向かうためには、時にはいさぎよく捨てることも選択し、次なる成長カーブの波に乗っていかなければならないと、深く感じました。
January 4, 2006
コメント(0)
-
里見八犬伝
TBSテレビの50周年特別企画で、『里見八犬伝』が2、3日と放映されましたね。キャストもすばらしいので、見た方も多いかもしれませんね。中学生の頃、一度本で読んだことがあったんですが、なんせその時代は本嫌いだったので、途中で読むのを挫折してしまいました。(笑)TVの感想はかなりの方が書いていると思われるので、あえてここでは書きません。私が注目したのは、『里見八犬伝』の題字と劇中に出てくる筆文字です。この字は、若手書道家「武田双雲」氏によるものです。私が以前、筆文字で名刺を創ったことをこのブログでも書きましたが、その創作が実は彼によるものだったのです。昨年は愛・地球博においてグローバル・ハウスでの筆文字による創作、今回の里見八犬伝での題字・劇中筆文字、そして今月中旬からテレビ朝日で放映される『けものみち』の題字と、最近ではかなり露出するようになってきました。このような偉大な方に、名刺を創って頂けとても光栄に思います。近頃、この名刺を自分で見ていると、“自分はまだまだ名刺に負けてるな~”なんておもってしまいます。(笑)今年はこの名刺に負けないよう、しっかりと自分自身に磨きをかけ、成長していかなければと、肝にすえました。もしこの名刺を今後、手にされた方がいらっしゃいましたら、“おまえ、まだまだ負けているぞ!”と、遠慮なく私に喝を入れてください。(笑)
January 3, 2006
コメント(1)
-
一風変わったキャラクター
正月のこの時期は毎年、私の住む周辺は交通規制がかかり、通行止めとなってしまいます。ここには日本三大稲荷の一つ「豊川稲荷」があるからです。通行許可証を持っていない車両は、規制区域に入ることができません。区域内に住んでいる私は、許可証を発行してもらっているので大丈夫なんですが、なんせ人だかりで車を出す気になれません。ですからよっぽどのことがない限り、日中には車では出かけません。ここ数年、三が日は家にこもることが多いです。あまりこもってばかりいると変になりそうなので、少し外へ出てみました。すると、家の一階にあるミニストップで、面白いグッズをワゴン販売していました。キティちゃんの豊川稲荷バージョン・キャラクターグッズです。豊川稲荷といえばキツネですので、キツネの帽子をかぶっているところがなかなか笑えます。ふと、周りを見渡すとのぼりが目に入りました。そこのは今まで見たことがないキャラクターが描かれていました。こんな感じです。→→→どうやら昨年11月に一般公募で決まったらしいです。(地域住民なのに知りませんでした)名前は『狐娘』。“ここ”ちゃんって読むらしいです。(笑)やはりこれも笑えますが、私的には好感が持てます。今までキツネのキャラクターに統一性がなかったので、足並みをそろえたかったようです。豊川稲荷周辺の“まち”は、今一独自性に欠ける町でしたので、これで一歩前進したように感じます。あっ、それはそうと、豊川稲荷に初詣に行くのを忘れてた。。。(笑)
January 2, 2006
コメント(8)
-
行動すれば次の実現
あけましておめでとうございます。今日から2006年の幕開けですね。“一年の計は元旦から”と言われます。それ故、年頭である一日は、気を引き締めて過ごさないといけないと感じています。まずシステム手帖の中身を入れ替え、今年の目標を明記しました。そして今日一日のページには、“行動すれば次の実現”と筆書きしました。この“行動すれば次の実現”という言葉は「営業マンは断ることを覚えなさい」で有名な石原 明さんの言葉です。著書『成功曲線を描こう』で書かれていたのを読んで、とても強烈な印象だったのを覚えています。どんなにすばらしいノウハウを持っていたとしても、行動に移さなければ、それを成し遂げることはできません。年頭に、この言葉を頭に中に植えつけました。ここで掲げた目標の一つを公開すれば、メルマガを発行しようと思っております。そして質にこだわりたいと考えています。題材は「保険」。保険という形のないもの、また普段みんながあまり興味を示さないものを、どのような切り口で展開していくかが課題です。活字を通して語ることは、自分自身の1年後2年後、そして5年後と、ブランディング構築には必要不可欠だと感じました。皆さんの今年の目標は何ですか?
January 1, 2006
コメント(6)
全12件 (12件中 1-12件目)
1










