2007年11月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
「宇宙は否定形を知らない」
何かを避けようとすることはできません。しかし、その逆で、何かをつくり出してもらうことはできます。そのためには、ポジティブな姿勢で物事に取り組まなければなりません。「天」に向けられた願いは、こうあるべきです。「健康でありますように」――この願いはシンプルではっきりしています。これで、病気ではなく、健康という願いに取り組んでいることになるのです。(つづく)
November 30, 2007
コメント(0)
-
「宇宙は否定形を知らない」
たとえば、「病気になりたくない」は、宇宙にとっては「病気になる」という意味になります。でも、どうしてそうなってしまうのでしょうか?「ない」状態をもたらすことはできません。私たちは、「何か」をつくりだすことはできても、「ない」状態をつくりだすことはできないのです。「つくり出さない」と考えただけでも、そのつくり出したくない結果がもたらされてしまいます。問題は、宇宙が「ない」という言葉を知らないことだけではありません。(そもそも、どうやったら「ない」になれるでしょうか?)願いの背景にある病気への不安が、健康への願いよりも大きいことが問題なのです。(つづく)
November 29, 2007
コメント(0)
-
「宇宙は否定形を知らない」
2.また、エネルギーは、つねに、注意がうながされているほうに向かいます。よいことであれ、悪いことであれ、気にかけている出来事を引き寄せるのです。ですから嫌なことを引き寄せてしまわないように、注意しなければなりません。避けたいことほど向かってくるのです。不安を抱きながら願っているときは、実際には何かを避けようとしています。どんなにポジティブな言葉で表現しょうとしても、「私は~をしたくない」とか「~が欲しくない」という思いが背景にあるのです。しかし、宇宙は「~(したく)ない」という言葉を知りません。否定形で状況を変えることはできないのです。何かを避けるためにやらない、というのも同じことです。このように願うと、ほとんどの場合、本当の願いとは全く逆の効果がもたらされてしまいます。つまり、宇宙は「ない」という言葉をリクエストから除き、そのまま実行してしまうのです。(つづく)【「宇宙に上手にお願いする法」】ピエール・フランク著/中村智子訳 サンマーク出版
November 28, 2007
コメント(0)
-
「宇宙は否定形を知らない」
1.心配ごとをたくさん背負った願いには、用心したほうがいいでしょう。不安は巨大な磁石のようなものです。避けようとすると不安がそれを引き寄せるからです。「不安」には、いろいろな感情が入り交じっています。ですから、不安の中には並外れた強いエネルギーが潜んでいます。さらに私たちは、心配すればするほど、そこに注意を払います。つまり、最悪のシナリオを細かく思い描いては、何度も考えをめぐらせてしまうのです。私たちは、幸せなことよりも、心配なことのほうに目を向けます。その結果、何もかもが順調なときでさえ、それに気づかず、陰気な不安のエネルギーの中に自ら浸ってしまうのです。(つづく)【「宇宙に上手にお願いする法」】ピエール・フランク著/中村智子訳 サンマーク出版
November 27, 2007
コメント(0)
-
「逆境が脳を鍛える」
薬学博士 池谷裕二逆境を乗り越えた達成感の脳が人生を豊かなものに2逆境と脳の関係を考えるとき、このことはたいへん示唆的だと思います。生死の瀬戸際のように思えた大きな逆境でさえ、一度それを乗り越えてしまえば恐怖ではなくなり、むしろ逆境を楽しむ余裕すら生まれるのです。それは、人間も同じではないでしょうか?たとえば、私は少年時代には人見知りが激しく、人前で話すことも大の苦手でした。しかし最近では、講義や講演などで大勢を前に話すことが、むしろ楽しくて仕方ありません。かつての私にとって、人前で話すことはそれ自体が逆境でした。「スピーチがうまくできた」という成功体験を積み重ねることによって、逆境ではなくなったのです。そのように、「逆境を乗り越える体験」を積み、そのときの歓喜に満ちた達成感を脳に記憶することによって、人生はより豊かなものになります。逆境はそれ自体が「脳を鍛えるチャンス」ですが、「逆境を乗り越えた体験」は、さらに輝かしい「人生の宝」なのです。そして、「逆境を乗り越えた体験」が豊富な人こそが、“打たれ上手”なのでしょう。【パンプキン】07年10月号(おわり)池谷裕二(いけがや・ゆうじ)1970(昭和45)年生まれ。薬学博士。98年、脳の海馬研究により、東京大学大学院薬学研究科で薬学博士号を取得。2002~2005年、米コロンビア大学生物化学講座客員研究員。現在、東大大学院薬学系研究科準教授。著書に「進化しすぎた脳」(講談社ブルーバックス)、「脳は何かと言い訳する」(祥伝社)、「海馬――脳は疲れない」(糸井重里氏との共著、新潮文庫)などがある。
November 26, 2007
コメント(0)
-
「逆境が脳を鍛える」
逆境を乗り越えた達成感の脳が人生を豊かなものに1脳科学の世界でよく用いられる、「水迷路(すいめいろ)」という実験装置があります。一か所だけ浅くなっている水槽で、水が不透明になっているため、どこに浅瀬があるのかは目に見えません。この水迷路にラット(ネズミ)を入れ、浅瀬の場所を記憶するまでの時間と試行回数を測ることで、学習・記憶能力に関するさまざまな実験を行うのです。浅瀬にたどりつけなければ溺れてしまうので、ラットは必死に泳ぎ回って浅瀬を探します。この水迷路に入れられることは、ラットにとってまさに「逆境」なのです。しかし、一度浅瀬の場所を記憶してしまうと、ラットは急に余裕たっぷりになり、水路の中で水遊びさえするようになります。(つづく)
November 24, 2007
コメント(0)
-
「逆境が脳を鍛える」
薬学博士 池谷裕二「あきらめない気持ち」が脳を活性化させる?2声を出すことと能を活性化することとの因果関係は、まだよくわかっていません。ですが、私はそれを、「あきらめない気持ちが脳を活性化させる」と解釈してみたいと思うのです。たとえば、スポーツの試合でピンチに陥ったとき、「まだいけるぞ!」「勝てる勝てる!」などと鼓舞の声を上げることは、あきらめずに打開の道を探すことにつながります。もちろん、声を上げずに頭の中だけであきらめないこともできるでしょうが、声を出すことによって「あきらめない気持ち」がいっそう強まるのでしょう。そして、懸命に打開策を探して脳をフル回転させるからこそ、脳細胞も活性化するのではないでしょうか?(つづく)
November 23, 2007
コメント(0)
-
「逆境が脳を鍛える」
薬学博士 池谷裕二「あきらめない気持ち」が脳を活性化させる?1逆境を「脳を鍛えるチャンス」として効果的に活用するためには、「あきらめないこと」が肝要です。逆境に出会って「もうダメだ」とあきらめてしまう人より、「絶対に乗り越えてみせる!」と最後まであきらめない人のほうが、脳が活性化しやすいでしょう。たとえば、スポーツの試合に際して「声を出すこと」の重要性が、最近、脳科学の研究からも立証されてきました。ベンチから声援を送ったり、円陣を組んで「よし、いくぞー!」と互いを鼓舞したりと、スポーツの試合では監督や選手たちが盛んに大きな声を出していますね。「声を出したからといって何も変わらないよ」と思う人は多いでしょうが、じつはそうではありません。まったく声を出さないで試合に臨んだ場合より、声を出し合った場合のほうが能力が発揮しやすく、試合に勝ちやすいのです。そのことは、以前から一部の心理学者が研究に取り組んでいましたが、近年になって脳科学の分野からも研究が進められています。そして、鼓舞する声を出すことによって脳が活性化することが、立証されはじめています。(つづく)
November 22, 2007
コメント(0)
-
「逆境が脳を鍛える」
薬学博士 池谷裕二逆境と認識すれば脳はフル回転するあらゆる逆境は、脳を鍛えるための重要な機会となります。なぜなら、脳は逆境のときにこそ、その潜在能力を存分に発揮するからです。ヨットで海に出ることを考えてください。順風満帆のときには、何もする必要がありません。逆風になってヨットが前に進まないときにこそ、ヨットマンはあれこれ知恵をしぼってその状況に対処するのです。それと同じで、逆境にぶつかったときこそ、私たちの脳はフル回転しそのことによって鍛えられます。逆境を乗り越える戦略を立てることと、「次に同じ逆境にたったときどうするか?」を考えておくこと――二重の意味で「頭を使う」のです。仮にも、もって生まれた脳の力が同じレベルで同年齢の2人がいたとしたら、順風満帆の人生を歩んできたAさんより、たくさんの逆境を乗り越えてきたBさんのほうが、脳がより活性化しているはずです。ただし、逆境を「脳を鍛えるためのチャンス」にするためには、一つの条件があります。「それが逆境であると十分に認識すること」です。自分が進むべき方向が定まっていない人には、そもそも逆境は存在しません。「かくありたい」という目標があり、それに向かって前進しようとするからこそ、行く手を阻む強い力を逆境として認識できるのです。目標が定まっていなければ、逆境もただの圧力としか感じられないでしょう。だからこそ、それを跳ね返そうとする意欲も湧かず、ただ「へこむ」ことになってしまうのです。いうまでもなく、「へこむ」だけではけっして脳は鍛えられません。「逆境こそが人間を成長させる」とよくいわれますが、それは脳科学からみてもうなずけます。人間の生活は消去法のくり返しです。日々行っている小さな選択から、人生の分かれ目となるような大きな選択まで、大小さまざまな失敗を繰り返しつつ、次回は同じ失敗を避けるように働くことで、私たちは生きています。脳は、心の中にあるたくさんの選択肢に、「前にAを選んで失敗したから、Aは選ばないようにしよう」という×印をつけていく――その作業をくり返して、脳はいわば「検査値を上げていく」のです。つまり、逆境に出会って「トライ・アンド・エラー(試行錯誤)」をくり返した経験が豊富な人ほど、心の中の選択肢に「×印」がたくさんついており、その分だけスムーズに選択を行って前進できるのです。「逆境に強い」「打たれ強い」ということを脳科学的見地から説明すれば、そういうことだと思います。(つづく)
November 21, 2007
コメント(0)
-
「逆境が脳を鍛える」
薬学博士 池谷裕二日本人は“打たれ下手”になった?「昔に比べて、日本人は、“打たれ下手”になった」――最近、そんな意見を耳にしました。「打たれ下手」とは、「打たれ強い」という言葉をふまえた造語でしょう。たとえば、「最近の若手社員は、きつく叱るとすぐに会社を辞めてしまう」という話をよく聞きますね。仕事上の失敗をして上司に怒られたとき、「なにくそ!」と失敗をばねに成長しようとする人が少なくなって、ただ落ち込んだり、あっさりと仕事から逃避してしまう人が増えているのかもしれません。学生達と日常的に接している私にも、思い当たることがあります。いまどきの若者は、「へこむ」という言葉を実に頻繁に使うのです。ボールの抜けてへこむように、心がしぼんでしまう状態――それが「へこむ」なのでしょう。空気満タンのボールは壁にぶつければ勢いよく跳ね返りますが、しぼんだボールはぶつけても下に落ちるだけです。いまの若者には、そのような“逆境に対する弱さ”を感じさせる人が少なくありません。(つづく)
November 20, 2007
コメント(0)
-
大宇宙と共に!
大聖人の仰せのままに、南無妙法蓮華経を広宣流布している団体は、創価学会しかない。南無妙法蓮華経と唱え、それを広宣流布していこうという心は、創価学会にしかないのだ。この大法則に則って進む学会が、どれほど偉大か。広宣流布しようという私たちの心が、どれほど尊いか。いわば、南無妙法蓮華経は、大宇宙を貫くリズムであり、私たちの住む太陽系も、南無妙法蓮華経の音律で大驀進しているのである。こうした深遠なる妙法を分からずに、学会の存在を軽く考えたり、使命深き学会員を見下すようなものがいたならば、その末路はあまりにも厳しい。私も長い間、多くの人を見てきて、明確にそういいきることができる。【全国代表幹部会】聖教新聞07・11・2「聖教新聞」宝さがし地道な学会活動を軽んずることなかれ。コツコツと活動している人を見落としてはならない。賛嘆せよ。守りに守れ。
November 19, 2007
コメント(0)
-
H地区部長 Y地区婦人部長さま
創価学会 創立77周年本年、I支部、10世帯目の折伏が実りました。 昨夜、10時からK宅にて、男子部が折伏座談会を開催。T地区の男子部・YMくんは絶対に折伏してみせると、満々たる決意で、BS学園に学ぶ友人のNTくんを連れてきました。 吉田くんは13日深夜2時、K部長とともに中村くんに仏法対話をして題目を一緒に唱えています。 2時間あまりの対話の結果、NTくんは12時ごろ入会を決意。 男子部の執念の戦い。本当におめでとうございます。ならびに、T地区、バンザーイ!11・18 創立記念日 折伏の戦いをもって迎えることができました。
November 18, 2007
コメント(1)
-
現在の生き方で未来の運命が変えられる
山本伸一は、『人間の運命』の内容を踏まえて、ショーロホフに質問した。 「人間の運命を変えることは、一面、環境等によっても可能であるかもしれません。 しかし、運命の変革を突き詰めて考えていくならば、どうしても自己自身の変革の問題と関連してくると思います。 この点はどのようにお考えでしょうか」 彼は、大きく頷いた。 「そうです。運命に負けないかどうかは、その人の信念の問題であると思います。一定の目的に向かう信念のない人は何もできません。 われわれは、皆が“幸福の鍛冶屋”です。幸福になるために、精神をどれだけ鍛え抜いていくかです。 精神的に強い人は、たとえ運命の曲がり角にあっても、自分の生き方に一定の影響を与えうるものです」 伸一は、身を乗り出して言った。 「まったく同感です。 たとえ、どんなに過酷な運命であっても、それに負けない最高の自己をつくる道を教えているのが仏法なんです。 その最高の自己を《仏》と言います。また、そう自分を変革することを、私たちは《人間革命》と呼んでいます。 仏法では、生命を永遠ととらえ、過去世からの自分自身の行為や思考の蓄積が、宿命すなわち運命を形成していくと説いているんです。 したがって、現在をどう生きるかによって、未来の運命を変えることができる。今をいかに生きるかがすべてであるというのが、仏法の考え方なんです」 ショーロホフは、目をしばたたき、盛んに頷きながら、伸一の話に耳を傾けていた。 彼は、社会主義国ソ連を代表する文豪である。しかし、人間が根本であり、精神革命こそが一切の最重要事であるという点では、意見は完全に一致し、強く共鳴し合ったのである。 人生の達人の哲学、生き方は、根本において必ず仏法に合致している。いな、彼らは、その底流において、仏法を渇仰しているのだ。 日蓮大聖人は民を助けた賢人たちについて、「彼等の人人の智慧は内心には仏法の智慧をさしはさみたりしなり」(御書一四六六ページ)と仰せである【新・人間革命 懸け橋56】聖教新聞07・10・4
November 17, 2007
コメント(0)
-
信心は不可能を可能にする
高校卒業後、大阪のプレス機会の会社に就職した船さんに、試練が襲った。金属を平面加工する作業中、機械が故障。左手を挟まれ、薬指を第1間接と第2関節の間で切断してしまったのだ。近くの病院へ駆け込むと、医師は告げた。「この指は、たとえ接合手術をしても、くっつかないでしょう。万一、接合部分が腐ったら、手首から切り落とさなければなりません。それでもいいですか」船さんは迷うことなく手術を受けた。“もし、この指がくっつかなかったら・・・・”激しい不安にさいなまれていると、男子部の先輩が見舞いに来た。「湿れる木より火を出(いだ)し乾ける土より水を儲けんが如く強盛に申すなり」(御書1132頁)との御金言を拝し、力強く励ましてくれた。「君はそこまで真剣に祈っているか?不可能を可能にするには、今こそ唱題だ。真剣に祈れば必ず治る!」船さんは医師と相談し、退院。帰宅するや、一心不乱に唱題に励んだ。“どうかこの指に使命を下さい”数日後、池田会長と男子部の代表との記念撮影会が行われた。負傷した指をかばいつつ“師匠に会いたい”一心で、船さんは参加した。翌日、指の接合部分から、黄色い膿が流れた。「やっぱり駄目か」。医師は言った。が、それから肉が盛り上がり、見る見るうちに、指がくっついたのである。27日間で完治。無事、職場復帰を果たした。“真剣な祈りが不可能を可能にする”との大きな確信をつかんだ。【「人生行路」】聖教新聞07・9・29
November 16, 2007
コメント(0)
-
理性は奇跡を起こさせない
☆ 成功への信念が、成功をもたらす☆ 受け入れるのも、妨げるのも私たちの想像力次第☆ エネルギーは注意の向いている方に発せられる☆ 一人で懸命に努力するよりも宇宙といっしょに働く方が大事大切なのは、願いごとへの信念だけといってもいいでしょう。成功への信念が成功をもたらすのです。信念は、願いごとに絶えずエネルギーを与え、「信仰は山をも動かす」の言葉どおり、超人的なことを成し遂げる力となるのです。理性は奇跡を起こさせない信念とは反対に、理性というのは物事を理論的に判断します。そして、願いごとはかなわない、と私たちを説得にかかります。ポジティブな経験や、成功の体験を積み重ねていかなければ、願いはかなえられると納得できないのです。理性は学習能力がとても高いのですが、経験したことや理解したこと意外は、認めることができません。それゆえ、理性は奇跡を起こすことはできないのです。それどころか、起こりうるあらゆる奇跡を、徹底的に取り払おうとします。理性の世界観に合わないことは、存在してはならないのです。願いはかなわないものではありません。常に、それも例外なしにかなうものなのです。ですから、もし理性が再び疑いをかけてきたら、きっぱりと理性に対抗しましょう。一つは、はっきりさせておきたいことがあります。それは、どんな大きな願いごとも、小さな願いごと同様に、必ずかなうということです。宇宙にとって、願いの大きさは、関係ないのです。受け入れるのも、妨げるのも私たちの想像力次第なのです。【「宇宙に上手にお願いする法」】ピエール・フランク/中村智子訳 サンマーク出版
November 15, 2007
コメント(0)
-
題目は凄い!
題目というものは本当に凄いということを体験しました。先日地区総会でO副支部長さんがTさんという友人を誘い参加されました。しかしその日は仏法対話をすることもなく帰えしてしまいました。せっかくK地区の総会に参加されているのに、その翌日、となりのS支部で入会をされたと聞きました。ショックでした。昨日の協議会で、そのことが話題になり、悔しい思いが地区部長や地区婦人部長の心にあると見て取れました。いや、O副支部長さんが一番悔しいく辛い思いをされたことでしょう。私も悔しい思いをし、反省もしました。「なにボケッとしてんねん!」と自身を責めました。せっかく地区総会に友人が参加していただいているのに、何の対応もしないで帰すなんて。朝、いつものように題目をあげ、「K地区は絶対に折伏できます。有難うございます」と祈りました。するとどうでしょう、ひょんなことから「信心をしたい」という人と遭遇したのです。昨年入会された方のお宅へ訪問した際、なにやら悩みがありそうな友人がいたのです。今晩、19時からS宅にて新来者(KYさん55歳)を交え、座談会を持ちます。明日の夜、入会式の予定です。07・11・6*******************************絶望と苦悩に打ちのめされていたKYさんは、一閃の希望の光を求め、地区の方の歓喜の中、11月7日に無事入会。新しい人生のスタートを切られました。
November 14, 2007
コメント(1)
-
7年ぶりの関西指導に壮年部員、感動のエピソード
K地区の壮年部 Nさんは長年、腰痛で悩んでおられました。Nさんは7年まえ、奥様の勧めで形ばかりの入会。信心には全く無理解です。私の会合の誘いも、言下に拒否する状態でした。今年の十月中旬、その腰痛がますます悪化して、救急車で入院。ヘルニアぐらいだろうと安易に思っていたところ、精密検査の結果、難病であることが分かりました。病名は「頚椎骨化症」、つまり頚椎の靭帯が骨のように硬くなる珍しい病気です。尻餅でもついたりしたら、硬くなった頚椎の靭帯が折れ神経を断裂し、全身不随になることがあります。治すためには手術しかありません。早速手術になりました。Nさんは心の中で題目を唱えました。地区の同志の皆様も題目を送られました。無事、手術は大成功。しかし、術後の経過が大事なのです。奥様のS子さん(副白ゆり長)は、不安と恐怖で大パニック。早速、S地区婦人部長・K支部副婦人部長の配慮でY関西副婦人部長に指導を受けられました。「一日3時間の唱題と10部の新聞拡大をし、先生が関西におられる今このとき、しっかりと結果を」との激励をいただかれました。S子さんは先生に猛然と決意のお手紙をしたためられ、その手紙をY関西副婦人部長は直接、先生に渡されました。11月11日、思いがけなく先生から自愛あふれる激励のメッセージが届きました。病床にあるNさんは感激のなか、見舞いにきた友人になんと、新聞啓蒙をされたのであります。今まで、信心に全く興味を示さなかった方が、先生の激励で発心したのを目の当たりにし感動しております。池田先生の関西指導の最中、感動のドラマでした。
November 13, 2007
コメント(0)
-
壮年部は中核であり重鎮
壮年部は中核であり重鎮夏期講習会壮年部全国大会 昭和41年8月3日私はまだまだ若い会長であります。未熟であり、欠点もあります。戸田前会長や牧口初代会長の遺訓を達成するために、会長になり、立ち上がったのです。あとはなにもない。これが師弟の道であり、同志の契りです。外道であっても、またどこの団体であっても、本当に人間らしい生き方をした、契りを結んだ師弟とか同志は、そういう姿を示しております。まして、最高の仏法に生きる私どもは、絶対に戸田前会長のご遺志を実現するのだという決意で進んでまいろうではありませんか。したがって、皆さん方はまず御本尊を一生涯忘れず、学会を守りきって、日々、月々、年々に成長していただきたい。たとえ半身不随になろうが、どのような立場になろうが、その一念をもった人が立派であり、霊鷲山会において大聖人にお目通りにかない、おほめの言葉をいただける人です。だからといって、戦いに無理があってはなりません。体は大事にしてください。皆さん方がうんと長生きして、事故なく、そして福運をつんで、人生最高の総仕上げをしていただきたいということを、朝な夕な私は御本尊に祈っております。次は青年部、学生部、高等部、中等部、少年部が待っております。その人たちに、個人においても、学会においても、立派にバトンタッチをして、後は彼らが、伸びのびと、それこそ口笛を吹きながら、大手を振って勝ち戦の前進ができるようにしてあげようではありませんか。事の一念三千の当体であり、因果具時ですから、御本尊にこの決意で、異体同心の信心をもって祈っていくならば、必ず目的を成就していくことができます。今まで私が申し上げたことを、どうか忘れることなく、一緒に元気で頑張りましょう。(おわり)
November 12, 2007
コメント(0)
-
壮年部は中核であり重鎮
壮年部は中核であり重鎮夏期講習会壮年部全国大会 昭和41年8月3日ほんとうに大聖人の仏法を、御本尊を受持して、一生を全うしたい人は戦いきってください。戸田前会長のおかげで、創価学会の今日があり、その恩を奉ずるところに学会精神の真髄があることを自覚して、ともに学会っ子として、人生を生ききろうという人は戦っていただきたい。江戸時代、島原の乱において、原城を守った天草四郎をはじめ三万八千人の同志は板倉候等の幕府軍二十万四千余人の攻撃に負けず、莞爾として守りきった。最後は松平候の策略等によって滅ぼされたけれども、寛永十四年十月から翌年の二月までの五ヶ月間、それは命をかけるどころの騒ぎではなく、もう死ぬのはわかっている戦いでありました。全滅することがわかっていながら、天草 四郎のもとに結集した信者は三万八千二位で、その中には子供も、女の人も、老人もいました。しかし、その中で同志を裏切ったのは山田右衛門作という壮年ただ一人であったことが、今でもキリスト教徒の最高の誇りになっているのであります。外道であっても、これだけ純粋な同志の団結をもって、立派に生涯を飾っております。いわんや、われわれは独一本門の同志であります。幸福になり、偉くなり、人々から尊敬されながら、それでなおかつ裏切るような者があったならば、無間地獄に堕ちるのはあたりまえではないでしょうか。島原の乱の時に、三万八千人の中で裏切り者はただ一人。わが学会壮年部は一生涯、ただの一人も裏切り者も出さないという団結で進んでいくべきであると思います。(つづく)
November 10, 2007
コメント(0)
-
壮年部は中核であり重鎮
壮年部は中核であり重鎮夏期講習会壮年部全国大会 昭和41年8月3日私は、戸田前会長がどうしても広宣流布をしなくてはならないという強い強い決心であられたことはよく知っております。しかし敵は多勢、味方は無勢でありました。敵はあらゆる権力と財力と陰謀を持って、創価学会にかかってまいりました。学会は信心という二字で戦ってきた。あまりにも純粋であり、あまりにも清浄な戦いでありました。創価学会の力によって、日蓮正宗もこれだけ栄え、創価学会の力によって、日蓮大聖人の御遺命がやっと実現されてきた。今日の発展の大原動力となって戦われたのが戸田前会長であります。戸田前会長がおられたがゆえに、また牧口初代会長がおられたがゆえに、私どもが幸せな生活をし、社会的にも、人生にあっても、どれほどか誇り高く、裕福に、堂々と進んでいるか。その恩を報ずるために、創価学会の同志は、よく団結して前進し、多くの民衆に“学会は凄い、真に民衆をすくい、社会を救う力ある平和の団体である”といわせることが、遠くは日蓮大聖人、また近くは牧口初代会長、戸田前会長が、最も喜んでくださる道であるがゆえに、私は戦うのであります。(つづく)
November 9, 2007
コメント(0)
-
壮年部は中核であり重鎮
壮年部は中核であり重鎮夏期講習会壮年部全国大会 昭和41年8月3日八番目に申し上げたいことは、遠く日蓮大聖人は大難四たび、小難数を知らず、日本民族の根本救済のため、全世界の人々を救済するため、いな、末法万年、尽未来歳の衆生を救済なさるために、難を忍んで、三大秘法の御本尊をお残しくださいました。私どもは日蓮大聖人の弟子であり、家来であり、子供であります。大聖人の御遺命を全うするのは、弟子としても家来としても、また子供としても、当然の義務であるし、権利であります。二祖に日興上人、また三祖日目上人も、代々の御法主上人方も、その日蓮大聖人の御精神を受け継がれ、幾たびか国主諌暁をなさり、他宗教が栄華を追っているなかにあっても、厳然と謗法から施を受けず、今日まで法灯連綿と大法を堅持してくださった。いま、広宣流布の機熟し、大聖人も日興上人も、日目上人も、どれほどか喜んでくださっているかと確信いたします。(つづく)
November 8, 2007
コメント(0)
-
壮年部は中核であり重鎮
壮年部は中核であり重鎮夏期講習会壮年部全国大会 昭和41年8月3日七番目に申し上げたいことは、折伏をした人は、学会の宝であり、大事にしていただきたいということであります。折伏は非常に難事です。どんな有名人でも、どんな金持ちでも、折伏はなかなかできない。一工員であり、一お手伝いさんであり、一庶民であっても、折伏を立派にしきっていける人はたくさんおりますが、その人たちこそ地涌の菩薩として、最高の活躍をしておる人であります。地涌の菩薩ですから、あらゆる姿を現じて生まれてきていることは当然です。創価学会は折伏の団体であります。たとえ信心の新しい一般会員であっても、どんなに地位もなにもない人でも、折伏をしている人を、絶対にバカにしてはならない。その人を心から大事にして、学会の宝として、守りぬいていただきたいのであります。なお、トントン拍子に理事になったり、幹部になったりした人がいます。やはり折伏しぬいてきた人と、折伏をしないできた人は、かならずあとで大きな差がついております。折伏をしないでトントン拍子にきた人は、メッキみたいなところがあります。折伏をしぬいてきた人は、非常に着実に、遠回りのようであるけれども、一年ごとに実力が発揮されております。とくにこれから注意しなければならないことは、才能や学歴がある等々で、私もときにはそのような人を抜擢する場合がありますが、折伏をせず、訓練等をうけずして、あるいは世間的、社会的に力があるから、その人を重要視する、ということは、いい場合もあるだろうし、それ自体が今度は学会を危険におとしいれる場合もあります。そういう点を十分に考えて、どんな時代がきても、あくまでも折伏をしきってきた人、折伏の功労者を、けっして見落とすことなく、その人たちを擁護し、大事にし、尊敬していっていただきたいことを心から念願するものであります。(つづく)
November 7, 2007
コメント(0)
-
壮年部は中核であり重鎮
壮年部は中核であり重鎮夏期講習会壮年部全国大会 昭和41年8月3日六番目に申し上げたいことは、きのうまでの功績に酔ってはならない。もしか、これまでの功績に酔うような人は、五老僧の眷属です。五老僧は大聖人のもとで、大聖人滅後まで活躍してきたという功績に酔って、日興上人に師敵対して、地獄に堕ちております。幹部になった、理事になった、総務になった、おれはこれだけの組織をつくったのだ、おれはまえは最高幹部だったのだ等々、過去のことに酔って、今の瞬間を大事にしなかったならば「只今を臨終と思って、妙法を唱えなさい」という大聖人の御金言に反します。功績主義で、功績のみにとらわれて信心をなくしてしまうようになったならば、そのような人は成仏できない。むしろ、その人は、魔の存在に変わります。したがって、瞬間瞬間、生命のあるかぎり題目を唱え、より以上福運を積んでいこう、広宣流布に御奉公しようという、その信心、その求道心を堅持しつつ、絶えず未来をめざして進む人が、最も福運を積み、成長しきる人であり、子孫末代に大功徳を回向しきっていける人であります。(つづく)
November 6, 2007
コメント(0)
-
壮年部は中核であり重鎮
壮年部は中核であり重鎮夏期講習会壮年部全国大会 昭和41年8月3日五番目に申し上げたいことは、壮年部は、とくに豊富な経験をもっておる人々であります。したがって、豊富な人生経験を、後輩の指導に十分に生かしていただきたい。とくに、悩み多い人たちと、ひざ詰めで語りあってもらいたいのです。形式などはいりません。学会はひざ詰めで話しあう民主主義の縮図を実践しております。何千、何万の人を擁しておる指導者の皆さん方も、そうしております。それが最良の方法であり、いちばんよくわかる、いちばん尊い実践なのであります。何千人、何万人の前で、立派な口をきいて「あの人はたいしたものだ」「この人はえらい雄弁だ」「立派そうだ」などといわれても、それは幻影にすぎない。ひざを突きあわせて話しあったときに、その指導者の進化がわかるのであり、それをやっていける人は偉大であります。とくに考えていただきたいことは、いつも後輩を自分以上の人材に育てようという指導者、その自覚をもった幹部、この人は偉い人です。その人こそ、民衆の総大将としての貫禄をもった人であります。自分が後輩に抜かれては困ってしまう、そんなヤキモチを焼いているような人物は小さい。あまりにも小さい。後輩をどんどん偉くして、泰然自若とそれをニッコリ喜んで、送り、見ていける人は、総大将でしょう。私は、その精神一本で来ました。皆をよくしてあげよう、皆幸福になってもらいたい、これだけが私のほんとうの気持ちです。だから私は強いのです。内外ともになにも恐れないし、なにをいわれても平気なのです。御本尊が見てくださっている、戸田前会長の指導どおりにやっている、これは私の最高の自負心です。(つづく)
November 5, 2007
コメント(0)
-
壮年部は中核であり重鎮
壮年部は中核であり重鎮夏期講習会壮年部全国大会 昭和41年8月3日四番目に申し上げたいことは、個々の指導に最大の力を注いでいただきたい。これがいっさいの戦いの勝利の源泉であります。全体観に立って指導をしなければならない問題もあるでしょう。それとともに個々の問題の解決は欠かすことはできません。この両方の指導ができて、初めてほんとうの勝ち戦ができるのです。昔は、ほとんど個々指導で学会は進んでまいりました。だから強かった。人数が少なかったということもあるでしょうが、幹部はほとんどの後輩の名前も顔も正確も、一家の実情も、信心経歴も、ぜんぶわかっておった。それが核になって、今日の学会の大発展があるのです。いくら膨大な組織になり、多数の同志が集合するようになったといっても、この基本精神、個人指導という根本の方程式だけは、忘れてはなりません。昔の大名のなかでも、優秀な大名は、一万や二万人の家来の内情は、ぜんぶ知っておったといわれております。もしも、組織のうえにあぐらをかいて、後輩が雲の上のように見えてしまったならば、それでおしまいです。つねに気をくばって、個人指導をし、また側面から、全体の指導というぐあいに、深く入っていかなければ、自分自身の成長が止まってしまいます。私は、五百八十余万世帯の人たちに対し、一から十まで、なんでもさしあげるというわけにはいきませんけれども、私なりに努力しているつもりであります。一般会員の同志とも会って、意見を聞いております。理事室にも、いろいろな点で意見を求めて、また実際にも見ており、その戦いはいまだかつて止まっておりません。自分の成長をはかっていくためにも、そのもっとも大事な方程式は忘れないでまいります。(つづく)
November 3, 2007
コメント(0)
-
率先の行動者に
戦いの要諦は、リーダーの「率先の行動」である。難しいこと、面倒なことは人にやらせて、自分はやっている格好、やっている振り、ではいけない。リーダーは、人々の中に飛び込んでいくのだ。人にやらせようという、ずるい考えではなく、自分が先頭を切って、動き語るしかない。真っ先に行動する。そして、堂々たる結果を出す。そのように私はやってきた。 ◇「創価学会の勝利」が「広宣流布の前進」である。学会が勝たなければ、広宣流布は進まない。皆もついてこない。また、広宣流布の戦いであるがゆえに、戦った人は絶対に功徳が出る。広宣流布に生き抜く私たちは、社会に民衆勝利の偉大な足跡を残しているのである。【全国代表幹部会】聖教新聞07・11・2「聖教新聞」宝さがしこの師匠の叫びに、じっとしていられない。しかし、自分はなんとのんびりしているのだろうか。やっているつもりでいるならば、師匠の心が、まだ分かっていないのだ。心のどこかに、慢心がある。深く反省し、勇気の一歩を踏み出していこう。
November 2, 2007
コメント(0)
-
壮年部は中核であり重鎮
壮年部は中核であり重鎮夏期講習会壮年部全国大会 昭和41年8月3日三番目に申し上げたいことは、正論には謙虚に聞いていただきたい。私たちは、お互いに凡夫です。万能ではなく、必ず欠点があり、知らないこともたくさんあります。したがって、多数の人に意見を述べてもらい、それを冷静に判断して「この人は学会のためを思い、信心のうえから述べていることであり、全体の幸福のことを考えている正論である、これは皆で聞こう」こういう度量のある指導者であり、壮年部であっていただきたい。学会は権威主義、ならびに名聞名利であっては絶対にいけない。それでは必ず行き詰ってしまいます。自分のたんなる感情で、下からの意見を抑制しては絶対にならない。伸びのびと皆が意見を述べられるようにしてあげ、それで、よい意見は取り上げて、実行に移す。よい意見をいった人は、ほめなければいけない。なお、会員を自分の部下のように思って、命令で動かそうと思ってはならない。それでは権威主義であり、信心ではない。学会の根本的な行き方ではありません。しょせん、絶対に威張らぬことです。そして、とくに陰で苦労している人に、暖かい思いやりをもっていただきたい。(つづく)
November 2, 2007
コメント(0)
-
壮年部は中核であり重鎮
壮年部は中核であり重鎮夏期講習会壮年部全国大会 昭和41年8月3日二番目に申し上げたいことは、幹部は個人プレーであってはならない。ということであります。おのおのの特色、個性、これは大いに発揮していい。しかし、人々を小バカにし、人々を抑えて、自分だけ有名人になろう、自分だけいい子になろう、ということは「異体同心なれば万事を成し」(同1463頁)という大聖人の本義に反するのです。地涌の菩薩は、全員使命があります。一人として、ムダな人はいない。したがって、根本的には、尊敬試合、助け合い、後輩が、伸びのびと成長していくための幹部である、自分であるのだということを自覚しなければならない。その人が偉いのです。自分だけが偉くなり、他の人は偉くならなくてよい――これは、者宗教の行き方であります。先日会ったある評論家も「いままでの学者は、自分がいちばん偉いと思って、わけもわからないことばかり書いておいて、ほんとうに、学生が、一日も早く立派に本を書けるようにしよう、という根性がない」といっておりました。そういう行き方は、正しい行き方ではありません。私どもは、お互いに善智識であって悪知識ではないのです。幹部と後輩との関係は善智識であり、同志であり、後輩の信心を、より以上すすませ、より以上、立派にさせていこうということが、幹部の存在意義であります。したがって、全会員が張り合いをもって、喜々とし、伸びのびと活動していけるように、心をくばっていただきたいのであります。なかんずく婦人部、女子部に対しては、心からいたわってあげねばなりません。婦人部を叱ったり、女子とケンカしたり、小バカにするような壮年部であれば、すでに、大人としても、指導者としても失格です。婦人部、女子部、そして、これから伸びていく青年部等を心から包容して、その団結の中心に、どっしりと壮年部の皆さん方が位していただきたいのであります。婦人部や、女子部からとやかくいわれること自体が、すでに壮年部の最高指導者として、敗北であり、失格であります。したがって、四者が、それぞれの特徴を生かしきり、その上で全体を調和させていける中枢になっていただきたいのであります。(つづく)
November 1, 2007
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 「覆面パトカー」の見分け方は? 「…
- (2025-11-15 15:00:05)
-
-
-
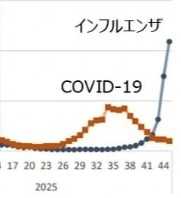
- 気になったニュース
- 抗インフルエンザ薬”ゾフルーザ”に、…
- (2025-11-15 14:06:05)
-
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 反論の美学
- (2025-11-15 08:08:25)
-






