2016年10月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

デルフト(Delft) 6 旧教会(Oude Kerk) フェルメールの墓
鎖国時代の日本でも長崎の出島でオランダとの交易が行われていた事は学校で習ったが・・。実は長崎の出島は最初ポルトガルの為に造られた場所だった。それがいつ? なぜ? オランダに取って代わったのか?簡単に言えばボルトガルはカトリック国で、オランダはプロテスタント国だったと言う理由だ。カトリックの浸透により国勢に影響が出始めた事を幕府が嫌いオランダの甘言にのって交易相手を乗り替えたと言う事だ。まとめてもけっこう長くなったので詳細は次回にまわします。リンク デルフト(Delft) 7 プリンセンホフ博物館と 番外、出島問題(中世日本の交易)デルフト(Delft) 6 旧教会(Oude Kerk) フェルメールの墓旧教会(Oude Kerk)宗教改革(Protestant Reformation)における因習破壊主義者(iconoclast)ヨハネス・フェルメールの墓碑(Johannes Vermeer gravestone)創設は1246年頃、デルフト(Delft)最古の教会である。教会のアドレスがHeilige Geestkerkhof 25(精霊の墓地25)前回触れたゴシックの塔は高さは75m。それは1325年~1350年の間に建造されたようだ。実はこの塔は斜塔と呼ばれている。実際運河沿いの地盤の悪い所に建てられた塔は当初から傾きがあったようだ。それ故1843年には屋根を外して修復された経緯もあるようだが、この斜塔現在登る事が可能なのである。確かに写真見てわかるよう斜めっていますね 新教会の所で紹介したが、階段は煙突の中を上るように非常に狭く、圧迫感すら感じる狭さ。すれ違いも気持ち広めの所までどちらかが後退しないとすれちがえない。とにかく厳しい狭さです斜めっていたとは気付かなかったです。眺望はたいした事なかったような・・。(写真撮ってませんでした)前に紹介した写真であるが、新教会からのみ旧教会の全景が見える隣接してネーデルランド連邦共和国の初代君主となったオラニエ公ウィレム1世(Willem I)の宮殿がある。(写真では塔の後ろ)※ 宮殿は現在プリンセンホフ博物館(Municipal Museum Het Prinsenhof)として公開されている。教会は何度か増改築されている。薄いブルーのラインは教会が最大に大きかった時のライン。下方グリーンの円・・・塔下方オレンジ・・・・・・・メイン・パイプオルガン下方ブルーの四角・・・トイレ左中ピンクの星・・・・フェルメールの墓碑右中六角紫・・・説教壇1949年~1961年と1997年~2000年、20世紀に入り2度復元。ステンドグラスの窓もその時に復元されているようだ。図面で見れば元は三廊式教会であり写真は身廊。ところがここには祭壇が無い。宗教改革(Protestant Reformation)における因習破壊主義者(iconoclast)1566年と1572年のプロテスタント改革派の因習破壊主義者ら(iconoclasts)によってステンドグラス含む美しい教会内部の装飾は破壊された。ブロテスタントの教義の中(十戒)に偶像崇拝禁止の項があり、宗教改革(Protestant Reformation)の時、強い因習破壊主義者(iconoclast)は欧州のいくつかの都市で過激な破壊運動を行っている。以前ゲントの時も修道院の貴重な蔵書が何万冊も川に投げ込まれたと書いたが、特にオランダ、ベルギー、北フランスは1566年夏に広範囲に渡り教会や修道院が襲撃され文化遺産ともなる貴重な名画や彫刻、聖書などが焼かれたりうち捨てられている。以前紹介した新教会の入り口のティンパヌム(tympanum)が削られたのもこの理由だろう。かろうじて生き残ったのは1548年製の説教壇だけ。身廊の先にあるのは(図A)Piet Hein tombPieter Pietersen Hein(1577年~1629年)オランダの海軍提督で西インド会社の司令官。写真がボケていたので拡大は無しです 左の聖堂(図B)にはElisabeth Morgan tomb → D 方面 奧がかつての右の側廊↓ P 方面パイプオルガンの裏側が塔であり入り口方面 ↑ 右の側廊・・先が減築されている。下はもちろん墓石の床である。←C 方面左の翼側 ピンクの ↓ がJohannes Vermeer gravestone(ヨハネス・フェルメールの墓石)位置ヨハネス・フェルメールの墓碑(Johannes Vermeer gravestone)※ ヨハネス・フェルメール(Johannes Vermeer)(1632年~1675年)実は現在ヨハネス・フェルメールの墓碑は2箇所にある。1975年300回目の命日で作られた簡素な墓碑(墓石1)と2007年1月26日に置かれた西の通用口の近くの新しい墓碑(墓石2)である。ヨハネス・フェルメールの墓石1 ・・・1975年製ヨハネス・フェルメールの墓石2 ・・・2007年製フェルメールは旧教会(Oude Kerk)内の床の下に埋葬されたのは間違いない。そこはフェルメールの義母が1661年に権利を購入していた場所だ。しかし彼が亡くなった時にフェルメール家はお金がなくて墓石は造られなかったのである。だから実は正確な墓の場所は特定できていない。墓石1も2も「およそそこら辺」と言う場所に据え置かれているにすぎない。※ フェルメールの生家にいては、「デルフト(Delft) 2 (マルクト広場とフェルメール)」の中、「空飛ぶキツネ亭(De Vliegende Vos)とメッヘレン(Mechelen)」「義母と同居した家」で書いています。リンク デルフト(Delft) 2 (マルクト広場とフェルメール)※ デルフト全般にフェルメールとなっています。プリンセンホフ博物館の絵画より旧教会内部を描いたもので、製作した画家はフェルメールと同じ年に亡くなっている。墓は石のプレートをはずして埋めるだけのシンプルそのもの。入場口の付近にトイレが増設されている。教会内にプレハブの小屋を置いてあるような感じだ。教会内、しかも聖堂内にトイレが設置された教会は知る限りここくらいだろう。墓石をはがして設置されたトイレにものすごく恐縮したものだ 旧教会(Oude Kerk)おわりBack numberリンク デルフト(Delft) 7 プリンセンホフ博物館と 番外、出島問題(中世日本の交易) デルフト(Delft) 6 旧教会(Oude Kerk) フェルメールの墓リンク デルフト(Delft) 5 (新教会からのデルフト眺望)リンク デルフト(Delft) 4 (新教会とオラニエ公家の墓所と聖遺物の話)リンク デルフト(Delft) 3 (市長舎と新教会)リンク デルフト(Delft) 2 (マルクト広場とフェルメール)リンク デルフト(Delft) 1 (デルフトの眺望)リンク ヨハネス・フェルメール(Johannes Vermeer)とメーヘレンリンク デルフト焼き(Delfts blauwx)
2016年10月28日
コメント(0)
-

デルフト焼き(Delfts blauwx)
数年前に古物商の許可証を警察に返却したのですが、今年、なぜか講習会の案内が届いた。うちの市は管区の警察が招集を掛けるシステムになっているので、警察に「もしかして名簿が間違っていませんか? 」と、あきらかに私に来るのはおかしいし、例年来ていなかったのに変・・と案内状の配信ミスを教えてあげた所・・。「自分は今年初めて担当した。古い名簿が残っていたのだろう。自分は全て出すように言われたからしただけだ。」と、全く失敗に対する反省もなく、当たりまえのように弁明をされ「申し訳ない」の一言もなかった。古い名簿が残っていたのでなく、貴方が違うファイルを開いたのだろう・・と突っ込みたかったが・・。とにかく私は関係ないのだから今年の出席者名簿からはずすように伝え電話を切った。そして切った後に諸々と不安が・・ 彼は、私の指摘を上司に報告しないのではないか?ミスをそのままごまかして(ごまかしきれないと思うが・・)過去の名簿をこっそり全て消去するのではないか?もし過去の登録者の名簿を全て消去したらとてもまずいと思う。古物商の許可証はそもそも都の公安委員会の管轄で、取得する時も履歴書まで提出。犯罪に利用されやすい分野だけに管理も本当は厳しい筈なのだ。それに今回の案内は往復の返信葉書できている。間違い郵便の損害は大きいはず。彼の上司に同情すると共に日本の未来に改めて不安がよぎる。これが昨今の驚きの新人かー。警察の中にもいるんだー。さて、今回は「デルフト(Delft)の旧教会」予定でしたが変更して先に「デルフト焼き」入れました デルフト焼き(Delfts blauwx)デルフト・ブルーと聞いて、最初はデルフト焼きの青い絵付け色の事かと思っていた。どうもデルフト・ブルー(Delfts blauwx)でデルフト陶器そのものを表す名詞になっているようだ。ところでデルフト焼きは陶器である。磁器ではない。陶器としてのルーツはマョルカの陶工達によるものであるが、見た目の特徴である白地に青の姿は、当時人気のあったエキゾチックな東洋の磁器をモデルとして誕生している。※ デルフト・ブルーの青は、最初は中国陶器に似せたもの。そして後に有田焼の青がルーツになる。オランダ東インド会社(Vereenigde Oostindische Compagnie) 略してVOCが仕入れて欧州に売っていた東洋の磁器は、非常に高価な品。持つ事ができたのは王侯貴族である。※ 中国の景徳鎮(けいとくちん)が入手できなくなり、代替えとして日本の有田焼が選ばれ伊万里港から船積みされ当時大量にオランダに渡っている。しかし人気はあったがいずれにせよ磁器は高価な品。そこで代替え品? 人気にあやかり? デルフト焼そのものを磁器に似せるようスズのグレーズで釉掛けしてベースを白く造ったのである。(その方が後から彩色する青もより映える。)これにより、あくまで磁器の代替え品であるにもかかわらず、デルフト焼きは1600年から1800年頃までの間、裕福な人々の間で人気が高まりコレクターも現れたそうだ。しかし、最盛期に33あった陶工も、現在残っている会社はデ・ポルセライネ・フレス(De Porceleyne Fies)一社のみらしい。(観光ツアーでは必ず訪れる所)デ・ポルセライネ・フレス(De Porceleyne Fies)看板型どりからベースと彩色、焼き、にいたる行程陶板の絵付けチューリップの花瓶の絵付け絵皿はフェルメールのターバンの女。完全オランダ土産ですね工房の居間にはレンブラント(Rembrandt)の夜警(De Nachtwacht)が陶板に描かれている。実はこの絵の正式な名前はフランス・バニング・コック隊長とウィレム・ファン・ラウテンブルフ副隊長の市民隊(De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh)た゜そうだ。原画はアムステルダム国立美術館にあるが、表面のニスが変色し黒ずんだ為に長らく夜と間違われてきたらしい。本当は昼間なのだそうだ。このレンブラントの絵は一人100ギルダーで、レンブラントには計1600ギルダー支払われている。それなのに彼はみんなを平等のサイズに描かなかった事で問題が起きている。余談であるが、当時のオランダでは絵の中の登場人物が多いほど絵に価値がもたれていたようだ。だからフェルメールの絵は人物が少ないので安くしか評価されなかったようだ。お店の展示品 アンティックなのか不明だが、意匠はジャパンですね。デルフトの絵模様には、中国、日本、ペルシャの影響が見てとれる。それらが参考にされたのは間違いない。チューリップの花瓶チューリップの正式な生け方はこのようなチューリップ用の専用花瓶に挿すのが本当ようです。下は造花だから一列にならんでいるけど、実際のチューリップなら陽の無い方にクネクネする(成長ホルモンは陽が嫌い)ので本物の花ならもっと面白い姿になったのかもしれない。初期のデルフト焼きプリンセンホフ博物館(Municipal Museum Het Prinsenhof)まだマヨルカ焼きの要素が残っている。かなりチープ。ちよっと楽焼きのようです。プリンセンホフ博物館(Municipal Museum Het Prinsenhof)輸入の陶磁器がアジアから入るとデルフト陶器は売れなくなったそうだ。だから生き残りをかけて磁器のような陶器の制作に入った。残念ながらアジアの陶器や磁器の制作過程を知らなかったのでこのようなスズをかけて地を白くする・・と言う方法を思いついたのかもしれない。しかし、結果はオーライで、今までの西洋の陶器ではなく、また中国の磁器とも似つかないが、新しい感覚のこの陶器はその珍しさもあり顧客を獲得。18世紀までは非常に売れたのだそうだ。1656年製 プリンセンホフ博物館(Municipal Museum Het Prinsenhof)まるでホウロウのような軸薬の濃さ・・。この白さと面白さは、イギリスがボーンチャイナを出すと衰退してしまう。デルフト焼き、2度目の危機である。磁器以外に白さを出す方法をイギリスは発見したのである。それはデルフトの白よりも美しく自然。ジョサイア・ウェッジウッド(Josiah Wedgwood)(1730年~1795年)と息子ジョサイア・ウェッジウッド2世 (Josiah Wedgwood II)は白色粘土の代用品として牛の骨灰を陶土に混ぜる事により乳白色の陶器の開発に成功したのだ。それがウェッジウッド(Wedgwood & Corporation Limited)である。以降イギリスの中でボーンチャイナは主流になりいろいろなメーカーが生まれている。どう見てもデルフトとは比べものにならない品質である。今後デルフト焼きの再起はあるのか? と言ったところで終わります。徹夜になりましたが、本日大阪に移動し2週間弱滞在。旧教会のところで後発のオランダ東インド会社(V O C)がなぜ日本にビジネス参入できたか? の経緯など紹介予定ですが、ひょっとすると旧教会の前にまた別の内容をはさむ可能生もあるので悪しからず・・
2016年10月20日
コメント(0)
-

デルフト(Delft) 5 (新教会からのデルフト眺望)
追記しました宗教改革以降、ステンドグラスのガラスの質が落ちた?アメリカ、装飾デザイナーのルイス・コンフォート・ティファニー(Louis Comfort Tiffany)が自らガラスまで製作するにいたった理由だ。※ ティファニー商会のルイス・コンフォート・ティファニーはアメリカの上流社会の邸宅の装飾や劇場他、ホワイトハウスの装飾まで手がけたデザイナーである。前回紹介したステンドグラスがマンガチックで近年の? と書いたが、人物の顔を見ても解るように彩色焼き付けの上、色ガラスも、着色によるカラーに見えたからです。(着色ガラス故の濃淡のなさで作品は単調に・・。 感動が無かったのでほとんど撮影していなかった。)以前「ティファニーランプ ポピーのランプシェード」の中でルイス・コンフォート・ティファニー(Louis Comfort Tiffany)がガラスの開発もしていた事をすでに書いていますが、彼は当時アメリカに輸入されていたイギリスやバイエルンのガラスの質が悪かった事を嘆き 自ら昔の技法に回帰した金属酸化物を加えた丁寧なガラス造りからの創作を始めたようです。欧州の教会のステンドグラスのガラスはもともと吹きガラスを開いて板状にした手間もコストもかかる製法。宝石のように光輝くガラスは主にインテリアや建築方面で利用された事だろう。だがルイス・ティファニーはそれだけでなく、一歩進んで新たにランプ用の濃淡ある色ガラスの開発も成功させている。それはまるで油絵の具を塗り重ねたモネの絵にも似た質感のガラスだ。つまり、ティファニー商会のティファニーランプ(Tiffany Lamp)などのガラス製品は、そのデザインのみならず、ガラス自体から台座にいたるまでティファニーのこだわりがつまったティファニー商会のオリジナルとなっていると言う事だ。※ ティファニーのガラスについては「ティファニーランプ 蜻蛉シェード 」で少し触れています。リンク ティファニーランプ 蜻蛉シェード話がそれたので戻すと・・。プロテスタント化が進んだ所では、信仰以外のあらゆるものが簡略化されたのだろう。美麗な装飾や調度品の無いプロテスタントの教会が増える一方、今までカトリックの教会の為に、神にささげる為に金に糸目をつけず渾身の作品を造り出して技術革新していった職人は廃業に追い込まれた。(他に移った者もいただろうがか、 いずれにせよ職人は育たなかったと言う事だ。)その分野の質の劣化が始まったのは必然と言える。それはきっとガラスだけではなかったはず・・。※ 19世紀に入ってからの産業革命はそれに追い打ちをかけたと思われる。さて、前振り関係なく、今回は新教会からのデルフトの景色が中心です。それこそ「デルフトの眺望」と言える内容です デルフト(Delft) 5 (新教会からのデルフト眺望)新教会(Nieuwe Kerk)の展望テラスから追記1632年10月31日。ヨハネス・フェルメール(Johannes Vermeer)(1632年~1675年)はこの新教会(Nieuwe Kerk)で洗礼を受けました。※洗礼を受けたと言う事は、それ以前に誕生しているはずですが、記録に残っているのは洗礼日だけだったのでしょう。だから誕生日は不明です。以前「デルフト(Delft) 3 (市長舎と新教会)」の所でフェルメールの結婚について紹介しましたが、彼は結婚を機にプロテスタントからカトリックに改宗しています。そもそも自らプロテスタントになった訳ではなかったので、彼がカトリックに改宗する事にそれ程抵抗はなかったのかもしれません。因みにカトリックに改宗した後から彼の作品に宗教画が加わっています。「マルタとマリアの家のキリスト」 1654-1655年頃勘違いして新教会でお墓を探している人達がいるようですが、彼は亡くなる時にはカトリックの信者であったので、彼が埋葬された教会はカトリックの旧教会の方です。下は塔に上るゲート口チケットを入れて、バーを押すと回転する仕組み教会の塔へ上がるのはどこもたいてい有料です。エレベーターが付属している所は希(まれ)で、ほぼ螺旋階段をテクテク上るのが一般的です。オランダ2番目に高いと言われる塔。新教会の塔の高さは108.75m。ここの螺旋は幅広い方。上がる人と降りる人とですれ違いができる余裕がある。が、後に登った旧教会の方は恐ろしく狭くてキツキツで、私でも閉所恐怖の怖さがあった。太めの人は無理。一人で上がるにも体をよじりながら。すれ違いはどちらかがバックしてどこかすれ違いできる箇所に張り付いて回避しなければならない状態。かつて一番狭かったかも・・。ガイドブックによれば展望テラスまで階段は376段だったらしい。数えていないけど・・。下がテラス階出口矢印のあたりがテラス階360度紹介しますが、まずは正面市役所から(西)見えるのが旧教会(西北西)ハーグから市電で来ると、停留所は旧教会の向こう側になる。写真下の黄色で囲った所がフェルメールの時代に火薬庫が爆発した爆心地。(北西)写真の水路は旧デルフトの街を囲んでいた運河。左が旧市街(北)たぶん遠くに見えるビル群がハーグの街かも・・。教会の聖堂側(北東)並木がある所はほぼ運河。昔は他の街までつながる交通路である。デルフトには今は小さくなっているが、かなりの運河が残っている。新教会の身廊の屋根マリア・ファン・イエッセ教会(Maria van Jesse Kerk)(南東)前に紹介しているよう、フェルメールが結婚してから割と長く住んだ義母の家が後にこの教会の一部に・・。デルフトの眺望を描いた場所(南) 赤い矢印Zuidkolk(南の池)と呼ばれる場所の住所はHooikadeと地名が付いている。橋の左がスヒーダム門スヒー川などかつては運河が交錯する交通ポイント。ところで、新教会にはカリヨン(carillon)が付いている。かつては18鐘のカリヨン(carillon)と書いてあったが、今は小さいのをいれたらもっと付いているのだろう。教会の入り口真下には動力巨大な歯車が置かれている※ カリヨン (carillon)については、「ブルージュ(Brugge) 3 (鐘楼とカリヨン)」で紹介しているのでよかったら見て下さい リンク ブルージュ(Brugge) 3 (鐘楼とカリヨン)Back numberリンク デルフト(Delft) 1 (デルフトの眺望)リンク デルフト(Delft) 2 (マルクト広場とフェルメール)リンク デルフト(Delft) 3 (市長舎と新教会)リンク デルフト(Delft) 4 (新教会とオラニエ公家の墓所と聖遺物の話) デルフト(Delft) 5 (新教会からのデルフト眺望)リンク デルフト(Delft) 6 旧教会(Oude Kerk) フェルメールの墓リンク デルフト(Delft) 7 プリンセンホフ博物館と 番外、出島問題(中世日本の交易)リンク ヨハネス・フェルメール(Johannes Vermeer)とメーヘレンリンク デルフト焼き(Delfts blauwx)
2016年10月12日
コメント(0)
-

デルフト(Delft) 4 (新教会とオラニエ公家の墓所と聖遺物の話)
プロテスタントについて書いたリンク先を追加しました。聖遺物崇敬(せいいぶつすうけい)のルーツは古代ギリシャ時代からあった英雄や偉人に対する崇敬に発したようです。まだキリスト教が公認される前の2世紀頃でも、その聖人の徳を墓前で後世語り継ぎ賛美すると言うシンプルな殉教者崇敬だったようです。それ故、初期の対象はあくまで聖人の遺骸であり、ローマ時代は遺骸をバラス事は禁じられていたので分骨されたり、一部と言うのもあり得なかったそうです。聖遺物の重要性が唱えられるのは6~7世紀頃。東と西、双方の教会会議で教会や祭壇に絶対聖遺物を置かなければならないと言うおふれが出された事。しかし教会の数は増えて行くのに聖人の遺骸(聖遺物)には限りがある。そこで聖遺物売買や盗掘、他の教会からの窃盗なども多発したと言う。面白いのは窃盗されても、聖人がそこに行きたかったからだ・・と言う理由で罪が許されていた? 感がある事。また、偽物? かなり怪しい物も出回ったようだ。聖遺物たる遺骸が分割され始めたのは10世紀あたり? 遺骸の解体と言う禁忌の意識が薄れたのか? 専用の容器に入れられ、移動できるサイズになり分割が一般化され始めたようです。例えそれが指先一かけらでも威力は聖人の一人分としての効力を放ったらしい。そんな聖遺物崇敬は11世紀にはかなり盛り上がり、同時に聖遺物の恩恵を受けたい巡礼者ブームも到来。十字軍への一般人の参加はそんな聖遺物をあわよくば持って帰ろう・・と言う動機も多分にあったと思われる。中世半ばになると1度に多数の聖遺物が集められ、出展のリーフレットもできたた大がかりな展覧会のようなイベントも開催されたと言う。聖遺物崇敬も時代の変遷?当時教皇庁より贖宥(しょくゆう)の軽減と言うサービスが聖遺物に加えられた事によりこうしたイベントへの巡礼者が増加して人気は加速。※ 贖宥(しょくゆう)とは罪の償いであり、煉獄での罪を償う日数を大幅に軽減させると言うもの。その日数をお金で買ったのが贖宥状(しょくゆうじょう)であり、免罪符(めんざいふ)と言われる御札。つまり聖遺物を1度に多数見られるイベントに行けば、わざわざ遠くに旅して回らなくても安易に贖罪の日数を減らせるのだから好都合。免罪符同様に楽に天国の門に近づける裏技となったのは言うまでもない。ルターが怒った問題の一つがこの教皇庁の造り出した贖宥の軽減。聖遺物を多く見たりお金で買って得た贖宥。罪深い市民が、本当の意味で神に償う・・と言う意識さえも失った事を嘆いたのだろう。当時ヨーロッパ最大の聖遺物を有していたヴィッテンベルク(Wittenberg)の教会。ヴィッテンベルク大学神学教授であったマルティン・ルター(Martin Luther)(1483年~1546年)はヴィッテンベルク市の教会に95ヶ条の論題を打ちつけ、宗教改革の口火を切ったのである。※ ルターに関しては、「ポルディ・ペッツォーリ美術館(Museo Poldi Pezzoli)」と「クラナッハ(Cranach)の裸婦 1」で紹介しています。特にクラナッハとの関係性とルターの聖書発行の履歴ものせています。リンク クラナッハ(Cranach)の裸婦 1 (事業家クラナッハ)リンク ポルディ・ペッツォーリ美術館(Museo Poldi Pezzoli)※ 免罪符についてはあちこちで書いていますが、その誕生の真実について書いてます。リンク アウグスブルク 6 フッゲライ 2 免罪符とフッガー家今回紹介するプロテスタントの教会はルター派でなくカルヴァン派の教会であるが、ルターの宗教改革運動が浸透した各所では聖遺物崇敬は停止され聖遺物は破壊されたり捨てられたり悲惨な運命をたどる事になった。そんなわけでプロテスタントの教会に美しい調度品は一切ないのであるプロテスタントの教義などについては後年書いています。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭デルフト(Delft) 4 (新教会とオラニエ公家の墓所と聖遺物の話)聖遺物崇敬のルーツと贖宥問題新教会(Nieuwe Kerk)オラニエ公ウィレム1世の離婚問題オラニエ公ナッサウ家の地下墓所前回紹介したように元はカトリックの聖ウルスラ(St. Ursula)教会として建設された教会です。聖堂の構造からそこが元カトリックの聖堂であった事は一目で解ります。ルターの宗教改革の嵐がおきた頃、この教会が信者と共にプロテスタント化した為に聖ウルスラ(St. Ursula)教会は失われたのだと思います。しかし、そもそも聖ウルスラ伝説がどうも本当に伝説だけの話? 実在の記録がとれなかったようで1969年以降 カトリックの典礼暦(てんれいれき)から除外されたらしい。それにしても調度品が全くありません。まさにシンプル。マンガチックなステンドグラスです近年入れたものかも・・。゜教会の聖堂部の天井はシンプルに木造です。ハーグのビネンホフ(Binnenhof)のリッデルザール(Ridderzaal)(騎士の館)の舟形の天井を思いだしました。カトリックで言う内陣の聖堂の下はネーデルランド連邦共和国の初代君主となったオラニエ公ウィレム1世(Willem I)の霊廟が安置。当時教会内の工事をしていたので定かに解らないが、礼拝所らしきものは無かった気がする。オラニエ公ウィレム1世(Willem I)(1544年~1584年)「デルフト(Delft) 2」で紹介したようにウィレム1世はオランダ独立のきっかけになる80年戦争(1568年~(休戦1609年~1621年)~1648年)の中心人物。スペインとの戦いの渦中デルフトの住まいである宮殿プリンセンホフで1584年7月に暗殺されている。1584年遺骸はこの教会に安置されたが霊廟ができるのはもう少し後だろう。霊廟の製作者は前に市長舎でも紹介した当時有名な建築家であるヘンドリック・デ・カイザー(Hendrick de Keyser)とピーテル・デ・カイザー(Pieter de Keyser)オラニエ公ウィレム1世の離婚問題ウィレム1世の経歴を見ていたら彼は4回結婚してたくさんの子供をもうけている。死別と言うより妻とはほぼ離婚である。カトリックでは離婚は認められていないが、プロテスタントでは離婚ができる。だからなのか? と思ったが・・。よくよく見て見ると結婚もダブっている時期があるし、子供の年齢も混ざり合っているではないかこれは複数愛人を抱えて後から適当に籍を入れていったのか? と思わざるおえない。これはカトリック教徒であれば大罪である。「離婚」と言えば、ルターだって聖職者なのに「結婚」している。いいのか?教義が緩(ゆる)くて細かい事を気にしない? 面倒くさくない? お金もかからない? そんな所が支持されてプロテスタントは増えたのだろうか?カトリックのように美麗な調度品を造る為のお金はかからないだろうがやはり運営費や修繕費は必要。墓以外に目に留まったこんな箱が・・。For Restoration of the church(教会の修復のために)由緒ありそうな浄罪箱である。教会の床には墓標がちらほら・・。摩滅して消えたものもあるのだろう。床そのものがお墓になっている所がほとんど。しかし、こちらの教会はさらに地下に王家の墓(Koninklijke Grafkelders)がある。写真奧で下をのぞいている人達の場所Koninklijke Grafkelders オラニエ公 ナッサウ家の地下墓所聖堂内陣部の床にはガラス床になっている部分が一箇所。ここにはウィレム1世以降のオラニエ公 ナッサウ家の棺が納められる墓所である。つまり現王室の墓所でもあると言う事。近年では2004年に 前オランテダ女王(ベアトリクス)の母であるユリアナ女王(Queen Juliana)と夫君Prince Bernhardが葬られたと言う。基本王家のプライベート墓地なので公開されていないが、このように床にガラスがはめられていて、地下の様子が少し見えるようなサービスがされている。確認してこなかったが、見えている部分が近年の新しい棺ではないか?だとすればオランダ国民が弔問に来た時用の窓なのかもしれない。一部墓所の図Back numberリンク デルフト(Delft) 1 (デルフトの眺望)リンク デルフト(Delft) 2 (マルクト広場とフェルメール)リンク デルフト(Delft) 3 (市長舎と新教会) デルフト(Delft) 4 (新教会とオラニエ公家の墓所と聖遺物の話)リンク デルフト(Delft) 5 (新教会からのデルフト眺望)リンク デルフト(Delft) 6 旧教会(Oude Kerk) フェルメールの墓リンク デルフト(Delft) 7 プリンセンホフ博物館と 番外、出島問題(中世日本の交易)リンク ヨハネス・フェルメール(Johannes Vermeer)とメーヘレンリンク デルフト焼き(Delfts blauwx)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)
2016年10月04日
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- アメリカ ミシガン州の生活
- いよいよ日本へ本帰国
- (2025-01-11 13:13:28)
-
-
-

- あなたの旅行記はどんな感じ??
- 帰路へ 楽しい旅ももうおしまい
- (2025-11-16 22:43:16)
-
-
-
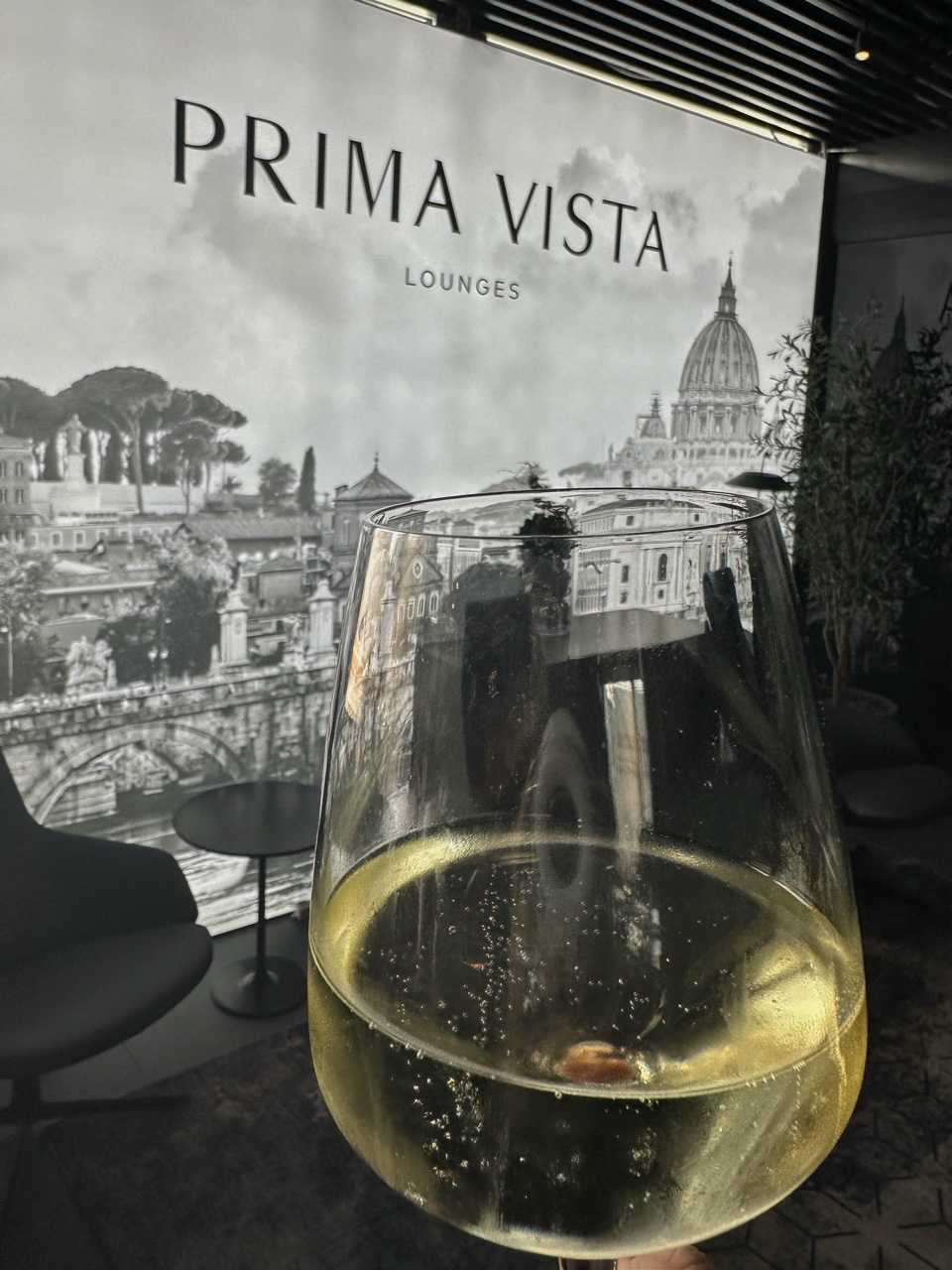
- 海外旅行
- 【イタリア】ローマからアブダビ経由…
- (2025-11-19 15:00:04)
-







