2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年06月の記事
全40件 (40件中 1-40件目)
1
-
マナーとトラックバック
トラックバックにまったく関係ない記事が。彼女のサイトは、どうやらSeesaaブログに登録。さて、同じ内容のトラックバックを7件も。削除するまえに、すべて記録をコピー。問題のトラックバック1.人権侵害に相当として考えてみる。人権侵害の被害とは。・差別的取扱い・暴行、虐待・いじめ、いやがらせ・プライバシー侵害・セクシュアルハラスメントなど法律違反行為に限らず、憲法や人権に関する条約、世界人権宣言に反する行為のほか、公務員の職務執行、私人間での人権侵害が相当する。常設人権相談所(法務局・地方法務局・支局内人権侵害申告書はこちらから2.名誉毀損と考えてみる。【IT media LIFESTYLEより】実際はいくつかに分類することができる。名誉毀損の法律上の定義は「公然と事実を摘示し、人や企業の名誉を毀損すること」。事実を摘示せずに公然と他人を侮辱した場合は「侮辱」、虚偽の風説を流布するなどして人の信用を傷つけた場合は「信用毀損」と呼ばれる。実際にネット上で名誉が傷つけられたときの対応は。・はじめは静観・影響が大きいと判断した場合は、メールを使って本人へ警告・プロバイダへ削除を要請2001年11月22日に成立した「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」~通称「プロバイダ責任制限法」は、インターネット上に公開されている情報で個人のプライバシーや著作権の侵害があったとき、プロバイダーが負う損害賠償の「責任範囲を規定」したものだ。ネット上名誉毀損のガイドラインは。・名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン・著作権関係ガイドライン名誉毀損のメール無料相談3.インターネット犯罪と不法行為による脅迫罪「一般的に人を畏怖させるに足りる害悪の告知」の相当。4.精神的な被害を主張まずは、静観し、この後の精神的被害を記録しようか。23:37削除(3時間掲載事実あり)
Jun 29, 2005
コメント(24)
-
Do more with less-より多くを果たし、より少数とともに-2
Do more with less -より多くを果たし、より少数とともに-「やることが違うんじゃない?」 かるてーかさんの投稿記事から2005/06/28 10:01:18 PM私の住んでいるところは田舎だ。当然都会のように働き口がたくさんあるわけではない。さらにここ数年はどんな会社にも派遣や業務請負が入り込んで、正社員で雇用という求人はなかなかないのが実情である。直接雇用でもパートや契約社員(たとえそれがフルタイムであっても)だったりする。月ごとに発表される有効求人倍率は1割をきったまま。しかもその中にはそれこそ派遣も業務請負もパートも契約もゴタマゼに入っているのだ。一つの会社に業務請負が何社も入っている場合、求人が重複するのであるが、そのあたりを職安が丹念に計算して数字を出しているとは思えない。さらに求職者数って、雇用保険が切れた段階でカウントされなくなるのだそうだ。つまりあの有効求人倍率だの就職率だのは、まったく実態に即していない数字ということになる。で、どこで働けって言うの?派遣で働いていたら、結婚も難しかったりするのに。業務請負は、数ヶ月仕事をしたら数ヶ月仕事がなかったり平気でするのに。おなじ業務内容で、パート扱いだとボーナスも貰えず、保険だって有ったり無かったりという状態で腐るなって?国がしなけりゃいけないことは、企業に安定した雇用を求めることじゃないのだろうか。使い捨ての駒であることがわかっていてなお働かざるを得ない状況に、好きで甘んじる馬鹿はいない。それでも食っていかなきゃならないから、フリーターや派遣で働く。それを揶揄されたんじゃたまらないつーの。(全文ではありません)それで、さきほどのDo more with less 1「義務」と「権利」を読み返してほしい。私たちには「義務」と「権利」がある。「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」国民にその生存を維持するための具体的手段として労働権を保障する規定。義務とは何か。法的意味は積極的ではなく、代々の遺産によって、衣食住を満たすことができるなら「働かない自由」は認めるが、正当な理由なくして、能力をもちながら、勤労の義務を履行しない者に対して、国が最低限度の生活の保障を行なわないという消極的側面としての意味なのだ。【いま、社会にとってキャリアカウンセリングは、職業と勤労者のミスマッチを減少させ、技能の需給結合を促進させる重要な役割を持っている。すなわちキャリアカウンセリングによって、特定の職業や職業分野を選択し、特定の職業における技術、技能、知識、態度を身につけさせることである。企業にとって、技術革新、グローバリゼーション化、高齢化、リストラクチャリングの推進になど、産業変化のなか、効果的な労務管理をおこなうためにキャリアカウンセリングは重要である。個人にとって、こういった環境激変の中、『働き方や生き方の選択肢が増し、』どういった生き方を選択すればよいかのライフキャリア、組織内外を問わず、どういったワークキャリアを選択したらよいのか、意思決定をできず、悩んでいる人は多い。-キャリアカウンセリングの重要性から-】『個人の働き方や生き方の選択肢の多様化』 本当にそうだろうか。実際、企業はギリギリの最少人数ではないか。 Do more with less -より多くを果たし、より少数とともに-かるてーかさんの記事投稿を読むと、働き方や生き方の選択肢が多様化したわけではないことがわかる。『それでも食っていかなきゃならないから、フリーターや派遣で働く。それを揶揄されたんじゃたまらないつーの。』 -まったくもってそのとおり。-
Jun 28, 2005
コメント(13)
-
Do more with less 1 「義務」と「権利」
Do more with less -より多くを果たし、より少数とともに- そのまえに 「義務」と「権利」 を確認社会権には、勤労の権利・労働の基本権がある。勤労の権利とは、世界人権宣言第23条1に「すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する」と規定されている。これが、憲法27条の国民の「三大義務」のひとつ。厚生労働省の職業安定局は、ハローワークの上部機関。ここに、雇用対策法の規定を施策とする雇用政策課があり、雇用情報の活用のための組織を維持・整備する、職業に関する調査研究、求職者に対する指導、求人者に対する指導、男女均等な機会、雇用に関する援助を定めている。ハローワークは、職業安定局の基本施策の根拠に対し、業務の具体的手続きとして、職業安定法を規定。用語の定義とし、職業斡旋と職業指導、労働力の需給に関する調査、標準職業名として、職業ハンドブックの作成、職業紹介、職業指導の実施、適正検査、学校の職業指導への協力及び紹介、民間職業紹介に関することがあげられる。つまり、官庁によるハローワーク、民間の職業紹介は、この基本的人権の保障を出発点とし、職業選択の自由から、両者は共存すべきものとしているのだ。勤労の権利のほかに、社会権には、第28条に労働基本権がある。労働者生存権の「人たるに値する生活」確保のために保障される基本的権利とし、労働者の団結権は、労働組合を結成し、組合運動をする権利。また、団体交渉権とは、労働組合が、使用者または使用者団体と賃金・労働時間その他の労働条件を維持改善するために交渉する権利で、使用者はこれに応じる義務を有するとされています。争議権は、労働者が団結し、労働条件の改善などの目的を貫徹するため、ストライキその他の争議行為をする権利の三つの権利(労働3権)によって構成される基本的人権の一つ。さて、労働基準法は、なぜあるのか。民法は個人と個人の間の契約関係を取り扱う法律である。法律は、国と個人として、「会社も個人」と扱う。契約においては平等なはず。このような契約には、過重労働、過酷な労働もあり、日本国憲法第二十五条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と定めたのだ。
Jun 28, 2005
コメント(6)
-
ジェロントロジー 1
シニアのライフキャリアプランのためには、加齢にかかわる諸問題の学問分野が必要とされる。シニアを3区分とすると、前期(ヤング-オールド)を65歳~75歳未満とし、中期(ミドル-オールド)を75歳~85歳未満、後期(オールド-オールド)を85歳以上と考え、医学・心理学・生物学・経済学・政治学・社会学などの自然科学、社会科学を統合することによって生まれた学問で、人の加齢にかかわる諸問題を総合的視野に立ってプランニングする。この“倫理と高齢化から死”までを探求する学問は、米国生まれの「ジェロントロジー:gerontology」と表現する。また、それを修めた人を「ジェロントロジスト」と呼ぶ。「ライフコース life course」は、人生の始まりから終わりまでを「あんなことがあった」「こんなことが」と経過や出来事で表す時に使う言葉。ライフサイクルそのものの考えは、ユングが最初である。少年期、成人前期、中年期、老人期の4つのステージで捉え、ユングは特に、特に中年期の転換期が人生最大の危機となるだろう、と。エリクソンは老年期の最後の儀式化は「哲学的なもの」としている。またエリクソンは「英知」を「死そのものに向き合う中での、生そのものに対する超然とした関心」と述べている。「それまでの人生を振り返って、うまくいったことも、うまくいかなかったことも含めて、自分の成し遂げたことを総体として自己肯定できること」カウンセリングで発見してほしいのは、「ありのままの自分、ありのままを見つける」ことである。livedoor life carrer counselingにおもしろい記事があった。「別の年から借りてきたものでは決してないものになるように、本気でとりかかるわ。そうだわ、それが私のすることだわ。」・・・たんぽぽのお酒 恐るべき子供たち Posted by life carrer・・・たまたま、ブラッドベリのたんぽぽのお酒から、ベントレー夫人の話を記事投稿しているのだが、過去にあったものごとになろうと努めているベントレー夫人に、恐るべき子供たちの言葉や表情、行動に傷つきながら、自問自答して答えをだした。恐るべき子供たちが、ベントレー夫人にとって、手痛いカウンセラーであったのではないか?シニアのライフプランニングには、ジェロントロジスト、カウンセラーのほか、サービス介助士、シニアライフアドバイザーなども。ただし「家族」や「友人」がベストプランナーなのかもしれないね。
Jun 28, 2005
コメント(13)
-
アファメーション
AFFIRMATION(アファメーション)とは 肯定的な宣言の「言葉」を意味する。「ワーク・ライフ・バランス」という視点で捉えると 自分を止める否定的信念(自分の弱みを知る)アファーメーションの概念(大脳生理シナプスとニューロンの関係)アファメーションの創造(強みを作るアファーメーション)アファメーションの効果(身体と言葉による宣言) ・・・つまりセルフモチベーションを高め、自己実現に・・・ビジネスマンならマーケティングのセグメンテーション戦略におけるSWOT分析を想像してもらっても構わないと思う。ビジネスセミナーにおいては、マーフィー、ナポレオンヒル、フランクリンなどの思想家のプログラムによるイメージトレーニングとして活用する。また、超聴に適したトレーニングでもある。 では、今回のテーマ「ライフ・スタイル・バランス」の視点では? ・個人的な「誓約」をする事 ・ヒーリング・瞑想というリラクゼーション ・自分自身の思いを、強くはっきりさせることで、 「今・ここにあるのだ」という現実を作り出す 例えば、 ・「私の病気は必ず治る」 ・「私はいつも満たされている。」 つまり ・「~したい」から「~です」 ・言葉を自分自身で作り、繰り返し唱える。 ・紙に誓約する。学校教育のなかでは?ストレス・マネジメントの統合リラクセーションとして活用される。「私はとても大切な人間です。」「私は私のままでいいのです。」「私は皆と仲良くして、これから元気に生きていきます。」心理療法としては?・ヒプノセラピー(前世・催眠療法)・ミルトン・エリクソンの催眠療法―解決志向アプローチすべてに共通していることは、肯定的な宣言により、潜在意識を目覚めさせ自分自身の意識や心のあり方を変えて、自分にとって望ましい方向へ進んでいく。 ただし、言葉に束縛されるのは危険な事。 実現化したいと思っている本質を「感覚」を全身で感じることだ。
Jun 26, 2005
コメント(14)
-
ストレス・マネジメント イントロダクション
ぱぴ1729さんの投稿から『次の学級活動でストレス・マネジメント(その2)という授業をします。2.ストレスの対処法 対処法は1つではない。効果的かどうか判断が必要。 たとえば 妹に八つ当たり → 怒られる → 余計いらいらでは逆効果。』実は、この「八つ当たり」という行動が、初期のストレス・コーピング(ストレスの対処)に多い行動である。つまり、ストレスに対し、自分なりに対処する最初の対処法にもなるわけだ。そして、次の対処として、周囲ではなく、今度は自分を責める対処を覚える。「他人のせいではなく、自分のせい」これも、まだまだ初期の対処法である。ストレスによる対処は、人間的な深み、成熟によって変化する。「自分を責める」ことは、第二段階の対処行動だ。ここに、CCさんのコメントを引用したい。アメリカの社会生理学者 ホームズとレイ(Holmes&Rahe)が43項目のライフイベントからなる社会的再適応評定尺度を作成したのは、生活上のあらゆる出来事がストレス源になることに着目したからである。CCさんのコメントに、「たとえば、ある学生の両親の死」という部分である。ライフイベントからトピックすると、両親の死は、「近親者の死」になるので63のストレス強度になる。この得点が他の項目と加算され、200点から300点になると、約半数の人々が、翌年くらいに、ストレス症状がこころか身体に表れるであろうというものだ。生活上のできごととストレス強度 (43項目からトピック)配偶者の死100離婚73 夫婦の別居65刑務所などへの勾留63近親者の死63自分のけがや病気53結婚50解雇47夫婦の和45退職や引退45家族が健康を害する44妊娠40つまり、CCさんのコメントには、「八つ当たり」という行動が、「たとえば、ある学生の両親の死」という学生に当てはめると、寂しさ、悲しさ、不安が、周囲にむけて、悲しさの表情、さびしさを回避する行動、なぐさめの言葉によって、支えられるが、それを「求めてはいけない」。「求めることによって八つ当たり」に変わってしまうということを云われている。周囲や相手を、自分の感情に巻き込むことが「八つ当たり」なのだということだ。(CCさん。おっしゃりたいことは、間違いない?)つまり、ストレスは、ストレスを持っている人間から、「八つ当たり」をとおして伝染していくとのことだ。そういった、他者のストレスによるストレスに対しての項目が、授業計画にあるのですか?ということなのですね?両親を失ってしまった学生に対して、人としてのココロや行動が生まれるが、その気持ちは、その時のものである。周囲の各学生にもさまざまな日常生活がある。喜びのライフイベントをもっている学生もいる。その状況で「喜び・楽しみ」が伝えられないこともある。つまり、周囲に「規制・自粛」する反応を与えてしまう。その本人が、気持ちを切り替えていかないと、逆に同情を求められ、愚痴を聞かされるような、「強制・義務」の表情・行動も生まれ、その心理に対し、「規制・自粛」によるストレスを、自己嫌悪などのように、「自分を責める」という対処も生まれてくる。CCさんのコメントから、私はそんなふうに考えてみた。さて、ぱぴ1729さんの(1)ストレスの対処法のいろいろに移っていきます。ストレス耐性とは、人は日常生活の中で様々な出来事を経験する中には、「いやだ」、「負担だ」と感じるものがある。 これがストレッサー。一般にストレッサーを経験すると、抑うつ感や不安感、怒り、無気力などの様々なストレス反応が生じる。ストレスコーピングstress coping(対処行動)とは、ストレス反応を低減させる、あるいは現状よりも増大することを防ぐ行動のことを言う。ストレスの対処行動として、第三段階である。・自己一致とアサーション(自己表現)初期段階(ぱぴ1729さんの「ウ 逃避」)悪いのはすべて自分以外の人の所為だと考えること。(効果はあります。)自分の悪い部分や醜い部分を知らなくても生きてゆくことが出来る。このストレスコーピングの欠点は成長しないこと。第二段階(ぱぴ1729さんの「オ 気分転換」)うまく行かない原因はどうも自分にあると考える。自分が頑張れば何とかなる。ところがうまくゆかない。 心的栄養失調になる恐れ。(心的栄養とは将来に対する希望では無いか) この対処が気分転換。 ・休養・休息 ・手軽なリラクゼーション・リラクゼーション法(自律訓練法)・リラクゼーション お茶でリラクゼーション 無農薬でリラクゼーション第三段階ストレスマネジメントstress management集団の中で、組織的に考える。⇒リラクゼーション、ストレスチェック、スケール※ストレスチェック1.ストレスのもとになるストレッサーの軽減あるいは回避2.わずかな刺激をストレスと感じてしまう認知の修正3.ストレスと感じた情報に対して、体が過剰に反応しないようにする生体反応のコントロール4.ストレス反応を軽減する要素:対処行動の発展5.ストレス反応を軽減する要素:社会的支持基盤の確率「ストレスコーピングstress coping(対処行動)」とは・問題解決スキル(ぱぴ1729さんの「ア 問題を解決する。」)問題の定義、解決法の選択肢の公安、意思決定、解決法の遂行とその検証という過程から成り立っている。ストレッサーを知る パーソナリティを知る 支援の形成は 道具的支援(実体的)は 情緒的支援は※たぶん、ここで、エリクソンの青年期のアイデンティティ形成に関連させていくのでしょうかね。・社会的スキル(CCさんのコメント)円滑な対人関係を形成し、それを保持するための技能。周囲の人々との問題解決がよりよく行われ、協力や援助を受ける可能性が高まり、人間関係において自分自身をコントロールできるようになる。※人権問題などの例もいいかもしれませんよね。※Ethics of Interview(ケア倫理面接、ERC) 人との関係性を強調する見方として、ギリガン(ギリガン,1986)の理論に基づく もの(エリクソンの自己に対し、人との関係性を強調) ERCはコールバーグの正義(公平、justice)に基づく道徳発達の段階の並行したも のであり、ケアの倫理について階層的な発達を測定する。 自己と他者へのバランスのとれたケアは、個人的心理成熟の重要な面だ。・自己効力感(セルフエフィカシー)特定の結果を得るために必要な行動を、どの程度上手く行うことができるかという認知。セルフエフィカシーが高いほど、ストレスに対処することが容易。1.自分で実際に行い、成功体験を持つこと(遂行行動の達成) 2.うまくやっている他者の行動を観察すること(代理的経験・モデリング) 3.自己強化や他者からの説得的な暗示をうけること(言語的説得) 4.生理的な反応の変化を体験してみること(情動的喚起)・身体的健康(ぱぴ1729さんの(2)リラックス体操)ストレスに対処するには、相当量の身体的エネルギーが必要。解決困難で慢性的に持続するようなストレス状況の場合など。疲労や消耗に耐えうるような健康な身体が重要。リラクゼーション法参考Biz&キャリア等尺性リラクゼーション斬新的リラクゼーションリラクゼーション・デザインソーシャルサポート(ぱぴ1729さんの「イ サポートを求める。」) なぐさめや励ましを受けたり・・・情緒的サポート 問題解決のために役立つ情報を提供してもらったり・・・情報的サポート 問題を解決するための手助けをしてもらう・・・実体的サポート 最後に、自分以外を「許容・受容」することが「自己の解放」であり、ストレス・コーピングなのかもしれないね。参考Biz&キャリア新しい生き方セオリーセオリー 2セオリー 3
Jun 25, 2005
コメント(17)
-
ストレス・マネジメント 「ライフ・スタイル・バランス」の視点
ストレス・マネジメントの投稿があり、私たちのライフスタイルに、「ストレス」がどのくらいの距離を保っていけばよいのかという「イントロダクション」である。ストレスって何?・ストレスってどうしておこる?・ストレスって悪いものか?・ストレスになったらどうなる?はじめに、ストレスに「勝つ・負ける」はない。ストレスも「人」とおなじように、「おつきあい」をしなければならない。「人」は「人」を支配してはならないし、できないものである。「人」が支配できるのは、「自分」だけである。しばらくは、こういった視点で「ストレス」を、ワーク・ライフ・バランスではなく、ライフ・スタイル・バランスから取り上げていこうと思う。20:00~21:00の間に、コメントにあるぱぴ1729さんの参考になるような記事投稿を考えています。トラックバックやご意見お待ちしています。(私の訪問者は、ゲストさんが60%を占めています。どうぞこの機会に、リンクをかねて、トラックバックやご意見をお聞かせください。)メンタルヘルスケア├メンタルヘルス├リラクゼーション├ウェルネス├アウェアネス参考blog.livedoo記事メンタルヘルスケア身-心的アプローチ・心-身的アプローチ ※ストレス・コーピングストレスが引き起こす行動※「3つのA」 ■心のストレス症候群 ■からだのストレス症候群ライフ・スタイル・バランス・飲食の癖・センサリー・アウェアネス ※有機体ココロってどこにあるの?・何を感じる?・感情と事実って?・理性と本能って?参考blog.livedoo記事たんぽぽのお酒たんぽぽのお酒 料理と人間たんぽぽのお酒 おばあちゃんの料理スタイルたんぽぽのお酒 恐るべき子供たちたんぽぽのお酒 孤独の人
Jun 25, 2005
コメント(3)
-
デザートブーツ 3
「登校拒否」”school refusal” 2 より -1970年代の頃-冬休みは塾通い。深夜帰宅の父は、私にだけこっそりケーキを買ってくる。正直、成績は偏差値Dランクであったので、高望みをせず、「受かりそうな学校」を選んだ。午前中は、「妹の家庭教師(次年時の内容が理解できる頭)」と自宅で勉強。午後は、決まって図書館に行く。顔見知りがいることと、閉館後に、クラスの友人がたむろしはじめ、塾までの道のりが面白かった。図書館にはIやMというクラスの秀才が揃っている。閉館後の階段下には、OやY達が集まっている。Mが私に、「どこを受験するの?」と訊ねてくる。「Oだよ」「なんだ。高校もいっしょかと思ったのになー。」行きたいよ。でも、行けるわけないでしょ。M君が受験する高校は!「Tは?」「うん、まだ迷っているんじゃないか」そうそう、Tとは、電話で話しているが、塾は別で、図書館にも来なかった。塾は、あの「脳内出血で入院」していたSが加わった。とにかく冬休みも、クラスの友人と、ひっきりなしに会う機会があったわけだ。始業式の前日、Tから電話がはいる。旅行に行っていたらしく、おみやげがあるらしい。だから、朝、こっそり渡すからねと言っていた。始業式。Tは欠席した。Tの“登校拒否”のはじまりだった。
Jun 24, 2005
コメント(9)
-
グローバル・バイイング・マーケット
BuyMaとは?バイヤーになることも、バイヤーに頼めることもできる グローバル・バイイング・マーケット バイヤーが「トレンド」をみつけ、「BuyMa」にアクセス。 画像、価格・コメント、有効期限を入力する。 BuyMaを閲覧する購入者のオーダーがはいる。 バイヤーは、商品を購入し、配送をする。バイヤーへリクエスト 欲しい/探している商品がある場合、「リクエスト」を、バイマに登録 バイヤーが、「リクエスト」商品を見つけてきて、バイマに出品 「リクエスト」に対する出品から選択し、購入する 「指名リクエスト」という機能もある。ネットオークションとは違う、セレクトされた商品。今までにないスタイルの新しいマーケットサイト。もう、知っていた?アフィリエイトもBuyMaも、もしかすると、ビジネスチャンスになるかもしれない。考え方とシステムつくりで、もっと新しい働きかたを創ることが可能だ。
Jun 24, 2005
コメント(7)
-
泣くこと・笑うこと
以前に、私の印象は、「空かした・生意気」であると記したように、この40数年は、そのスタイルを継続している。それが、自分自身に適しているとかではなく、コミュニケーションがとり易いわけでもなく、それが自分だから。親に叱られたとか人の死以外は、泣いたことがない。以前の上司が、「泣かないとダメだよー。」と、とぼけて肩をポンとたたいてくれたことがあったが、「何をいっているんだろう」としか思わなかった。いまでも自分のために「泣くこと」はない。これからはあるかもしれないけれど。そのかわり、「笑う」ということは好きである。ところが人を笑わせる方ではない。笑わせてもらうほうである。とくに「かづさくら」を拝見すると、なんだか笑ってしまうのだ。人を笑わせる力ってすごい。人って笑うことで癒されるでしょ。人って笑いで救われるということだ。
Jun 23, 2005
コメント(6)
-
カウンセリング
今週のはじまりは、クライエントの応対に忙しく、ちょっとパワーダウン。昨日、私自身もカウンセリングに行ってきた。カウンセラーがカウンセリングを受けることは、自分へのケアのほかに、「職業倫理」であり「義務」であるのかもしれない。日本という国民性、人間性善説から、性格と諸行動の意味を理解することに対して、対処法・予防法がある。(私の場合は、臨床ではないが、その知識は必要とされる。)対処法は、家庭や社会の問題として、不登校、虐め・苛め、モラル・ハラスメント、離婚、不倫、犯罪、ジェンダー問題のほかも含め、原因を分析的に理解し、問題行動への論理的に解決を図ることが対処法である。ただ、個人個人によって原因が様々であることである。個人個人によって原因が様々であることに、「具体的な行動や経験」を文脈する力が双方にほしいところだ。
Jun 23, 2005
コメント(16)
-
モラリスト
ジャン・コクトー「おかしな家族」は、コクトーの生涯1冊の「絵本」らしいが、ファンタジックというより、ナンセンス絵本だ。この「おかしな家族」は、読み手のライフロールやライフステージによって、「受け取り方」が変わってくるのではないかと思う。訳者の高橋洋一氏が、「面白い」といったお嬢さんの感想が、出版にいたる原動力になっていると思うのだが、一体何が面白かったのだろうか。ナンセンスとは、「意味のないこと。ばかばかしいこと。」をさす。Nonsenseとは、無意味な言葉、戯言(ふざけて言う言葉。冗談。)、戯詩をいう。ナンセンス文学とは、言葉の意味よりも地口や洒落(しやれ)に重点をおいた文学だ。このナンセンス絵本を、ただの戯言として読むのは、もったいない。コクトーも、ナチス・ドイツによるパリ占領下時代にも、書き継いだ「占領下の日記」あたりから、フランスのモラリストの伝統に接近していく。フランス文学で17世紀ころから使われ始めたモラリスト。(※モラリストの原点に、モンテーニュ,パスカル,ラ=ロシュフーコーがいる。)現実の人間、社会を観察し、人間性や風俗・習慣に様々な視点から考察を加え、これらを鋭利で圧縮した文章でまとめあげていく作家たちを称している。そういう、コクトーの環境や背景を考えていくと、この作品は、大戦後の荒廃した人心に、無邪気さを取り戻そうとした作品であることが考えられる。太陽と月の夫婦、悪くて手に負えない子供たち、家庭教師の犬が、ユニークな物語を展開していく。そこから読み手が加わり、自分との類似に、共感を覚えたり、つまらなかったりするのではないか。つまらないと思ったら、その書き手を知ることにより、あらたな発見がある。犬の家庭教師が必要になるのかわからないが、「ライフ・スタイル・バランス」って、現実の人間、社会を観察し、人間性や風俗・習慣に様々な視点から考察を加えた「こだわり」ではなく、「あるがまま」ではないだろうか。
Jun 22, 2005
コメント(6)
-
カンタベリー物語 ブログの語り手
古典には、「デカメロン」、「千一夜物語」など、順番に話をしてく作品が多い。「カンタベリー物語」も、その職業も身分もまったく違う二十九名の巡礼たちの巡礼がカンタベリー大聖堂へ向かう道すがら、順番に話をして行く。騎士、騎士の息子の騎士見習い、騎士の盾持ち、尼僧院長、助手の尼僧、3人の僧、修道僧、托鉢僧、貿易商人、学僧、高等弁護士、郷士、小間物屋、大工、織物商、染物屋、家具装飾商、料理人、船長、内科医、機織り(バースの女房)、教区司祭、農夫、粉屋、賄い方、家扶、召喚吏、免罪符売り、タバード宿屋の主、詩人(チョーサー自身)と、途中二十九名を超えていく。ブログのコメントは、まさにカンタベリー物語のように、語り手の職業や性格にふさわしい「お話」を残してくれる。
Jun 19, 2005
コメント(13)
-
普通の人々
ジュディス・ゲストの原作「Ordinary People」は、1980年のロバート・レッドフォードの初の監督作品として、第53回アカデミー賞で最優秀作品賞、監督賞、脚本賞などを受賞した。タイトル“普通の”アメリカの家庭とは、WASP (White Anglo-Saxon Protestant)が支配する。つまり、夫は大学を出た英国系白人士官、妻は高卒以上の英国系白人で、宗教はプロテスタントだ。「普通に生きていく」ことが難しいというが、普通だから、危うさや幻想、脆さがあるのではないだろうか。「普通の人々」に描かれているのは、思春期の不安定な精神状態を理解しない夫婦と、母親に溺愛されている長男、母親から疎まれている次男が、事故や思い病気に患うことなく、日常生活を送っている。その危うい「普通の家庭」が、ボート事故で長男が亡くなったのをきっかけに、精神を病む両親と、自殺が未遂に終わったが為に罪の意識に苛まれながら生きる次男が、望み通りにことが運ばない苛立ちや、肉親同士の葛藤で、崩壊する。「普通の人々」とは、生きる途中で、何かが崩壊するのだ。そうでなければ、特別な人生などありはしない。
Jun 18, 2005
コメント(24)
-
アイデンティティ
デザートブーツ 2 -1970年代の頃-アーノルドパーマのVカーディガンにポロ。ボタンダウンのシャツ。スクールソックスまで、ワンポイントを揃え、スポーツバックはアディダスだった。私も、だいたい同じ世代ですが・・・その頃は学校で、苛め方や苛められ方を学んだような気がします。学校という箱の中の、児童、生徒同士の狭い社会で“快”“不快”を嗅ぎ分け、何を選べばよいか・・・それは今でも、私の人格を形成する上で、重要な学びであったと思います。(Jun 18, 2005 10:09:45 AM)まんまる84さんのコメントから児童、生徒同士の狭い社会で“快”“不快”を嗅ぎ分け、何を選べばよいか・・・ここに、まんまる84さんのアイデンティティの確立がみえる。アイデンティティの確立とは、社会の関わりの中で身につける自分の役割が、他人を喜ばせ(快)、その“快”があって、自分自身の価値について確信できるのではないだろうか。ところが、“快”“不快”を嗅ぎ分け、何を選べばよいかという模索の努力が怠っている。モラトリアムは、そういった選択の猶予期間でもあるが、何かを捨てなければ得られないものである。いま、まんまる84さんは、ケアマネージャーで、「福祉」から“快”を発信している。「私-わたくし-」 かけがえのない自分自身に、トラックバックにあるBiz&キャリア「私-わたくし- T・Kのディキャリアから」 は、なんと、「アタックNO1」の鮎原こずえが登場。読んでみてください。
Jun 18, 2005
コメント(6)
-
「私-わたくし-」 かけがえのない自分自身
スクールウォーズのコメントからぱぴ1729さんのコメント2時間ほど、読ませていただいて、ここでコメントすべきだと思い書き込んでいます。・・・・・今年から人権・同和教育の担当になり、・・・・・(Jun 18, 2005 01:15:24 AM)Re:自治体からジャンプさん (ゲストさん)このブログの「深代惇郎 -コメントへ- 」から「差別とか偏見というのは、人間を(一人の確固たる)人間としてみる目を失い、その属性で一括して判断するときに始まるのだと思う。」・・・・・・・・・・留学の経験のある深代は、人種や差別など、属性といえば、ドイツ人とかユダヤ人ということなのでしょうけれど、部落出身にもあてはまります。「人間としてみる目」が大切なんです。教育の現場にいて、かつ人権・同和教育の担当は、酷なこともおありでしょうが・・・・・(Jun 18, 2005 01:52:49 AM)Re:Re:ぱぴ1729さん「人権を学べば教師が変わり、教師がかわれば生徒が変わり、生徒が変われば学校が変わる。学校が変われば山でも動かす」と言う言葉があります。・・・・・教育現場で人権・同和教育の担当「ぱぴ1729さん」が、スクールウォーズへ寄せてくれたコメントに、Re:自治体からジャンプさん (ゲストさん)→Re:Re:ぱぴ1729さんのやりとりである。ここで「部落出身」という言葉がある。-回想-A君の家は、大きな窪みの中にあった。中学の校庭から見下ろすと、崖の底に7~8件ほどの家が小さく見えるように。春でも、夏でも、秋でも、冬でも、昼も、夜も、いつも煙が途絶えることがなく、数軒の「煙突」は、いつも働いているようだ。中学3年の1学期の終了と同時に私は転校する。母と私は、職員室の担任のF先生へ、この時期の「転校」が内申に響くかもなどという相談で訪れていた。離れたところにA君が、担任のC先生と話し込んでいた。生徒会役員をする優等生のA君。職員室から退出するときに、A君の横を通る。母と私の気配に、その先生は、すっと立ち上がって、会釈をする。私も母も会釈をする。ふと見るA君の「顔」。あの表情は、私にとって一度限りの「表情」だ。あれから、あんな表情をみることがない。記し難い表情であった。A君が部落出身だったことは、誰も知らないと思う。A君の住む地形だけではなく、その後の進路も、とても不思議であった。その頃から「なぜ・なぜ・なぜ」と考える癖が生まれたのだろうか。A君が部落出身だったことは、高校生になってからだった。当時新聞にも掲載されていた「同和問題」の連載が、A君の境遇への「なぜ・なぜ・なぜ」という疑問を明かした。もうひとつ、その大きな窪みには、道らしい道がなかったのである。─人権学習は,誰のために?─・マイノリティ 多文化理解から多文化共生ヘー国際化,多文化・多民族社会化・メディア・リテラシーの確立 プライバシー保護と情報公開への課題・ファシリテーターの人権感覚と人権問題の認識・行政・市民・地域社会の人権の促進 社会的に不利な立場にある人々のエンパワーメント (empowerment:本来持っている能力を引き出し,社会的な権限を与えること)─“人権”をどう学ぶ?─・マスメディアをはじめとする多様な情報から.客観的・公平な結論を導き出す・アイデンティティの確立 セルフ・エスティーム(Self-esteem) 「かけがえのない自分自身」 アサーティブネス(assertiveness) 意見を聞き,議論し,否定せずに自己主張できる能力・違い(差異)を認め,受け容れる能力・人権教育=民主主義のための教育 圧政・迫害・自由の剥奪,南北問題・地球環境保護 ジェンダー 人間の専厳 ※参考 人権問題と同和問題 中川 喜代子日記タイトルは、小説「私-わたくし-」から部落出身者との結婚を悩む姉を知り、高校生の「私-わたくし-」が、家族、学校など日常生活から、私ってなんだろうという経験を重ねる。現在は、廃刊になっているかも・・・
Jun 18, 2005
コメント(11)
-
デザートブーツ 2
「登校拒否」”school refusal” 2 より -1970年代の頃-その地方はすぐに寒くなる。当時はアイビー、トラッド、アメカジ、ワンポイントが学生の間で流行る。自然に皆そろいのものが多くなっていく。アーノルドパーマのVカーディガンにポロ。ボタンダウンのシャツ。スクールソックスまで、ワンポイントを揃え、スポーツバックはアディダスだった。Tと親しくなるように、Iとも親しくなっていく。Tは時々休む。体育があるときだ。そのため、体育の授業は偶数で、「余り」がいなかった。秋になり、スニーカーからリーガルのローファーに履き替える頃の話だ。Iが話しかける。「Tと揃いでデザートブーツを買うんだって?」「そう。11月の20日過ぎにね。」「ガキだね。」えー、そうかい・・・そこでYが、「じゃあ、今度はさ、長袖のポロ買いにいこう。」と誘う。「いいよ。」「でさ、映画もみてさ」「うーん。行くー!」それが次の日曜だった。母が、「色は、白よ。そのほかの色は、お母さんが返品に行くからね。どうせ買わなきゃいけないものだからいいけど、予定としては、セーターと、カーディガンと、コートだけだから。12月の第2週目くらいかな。その頃ね。」という。もう、その他は約束するなということだ。次の日に、Tを誘う。「うーん。どうしようかな。考えておくね。2人で行くならOKなんだけど・・・」Tは時々そんなことを言う。クラスは、結構みんなが仲がよかった。(例外はいるとして)男子も女子も。とにかく、わざと抱き合ったり、男子の膝に座ったりする女子が多い。(前の中学では考えられない)そのうち、男女混合で遊んだりするようになる。いろんなグループと混ざったり、とにかく受験期でも楽しかった。Yとは、約束してからずっと一緒にいるようになる。Iは、「励ましの行為」以外は一人で机で本を読んでいる。太宰治、谷崎潤一郎のほかに、ブラッドベリなど。0は最近Mと付き合いだして、皆の冷やかしをよそに、始終くっついていた。土曜日は午前授業で、もう一度TにYが確認をする。Tは「うーん。どうしよう・・・」「行こう。」と私が誘う。「うん。そんなに誘ってくれるなら。」そういうわけで、3人で行くことになる。結構、皆、機嫌よく日曜を過ごした。はじめて友達同士で服を選ぶ楽しさに、私はとても満足してた。月曜日、0がYといっしょに、そっと来いよというカンジで、私に目配せをした。「おい。聞いたぞー。Tの奴、ずいぶんだな。」えー。今度は何?「お前よ。Tが嫌だったら、Yと一緒にいろ。わかったな。なんかあったら、なんでも俺にいうんだぞ」ちがーう。「うん。何でも0にいうよ。友達だから。でもTは、全然いいよ。すごくいいよ。」「えー、あんなにもったいぶってさ。」とY。「そうなの?でも、またYと映画に行きたいな。Tだって来るよ。」「うん。映画いこう。あいつは誘わないけど。」またー!こういうカンジで、友達関係が微妙になってくる。そんな時、Iがやってくる。「ちょっと。」私の手を引っ張って、外に行く。どうしてなのか、「嫌われている」と0が云っていたが、誰も逆らえない。「適当にあしらうんだよ。」「うん。適当に?」Iが云う。「本当に面倒くさい奴らだよ。ガキだな。話を合わせておきな。」「わかった。」0とYは心配そうな顔つきでこっちをみる。Iは、1冊の本を私に渡す。「あいつらに説明すんの面倒だからサ、これ返してきて。図書室に。放課後でいいから。そう云われたっていえばいい。それからTのことは、見放すな。」Iってカッコいいぞと思った。やってることは凄いけどね。なんだろうね。そうして11月になり、約束どおりTと二人で「デザートブーツ」を買いに行った。夕方は、Tの家で夕飯をご馳走になる。「仲良くしてくださいね。」なーんて上品なお母様なのだろう。そして帰りは、「ケーキ」をお土産に。当時、「ケーキ」というと、クリスマスや誕生日以外には与えてもらったことがない。帰宅すると、母がすぐお礼の電話をかけていた。そんなふうに、中学3年の2学期が終了した。
Jun 17, 2005
コメント(14)
-
ライフ・スタイル・バランス
ライフ・スタイル・バランスとは、衣・食・住から自分の日常を考察する。今回は「住」という視点から、「住まう」ことについて投稿する。 ※環境心理学より※マクロ的だと「街づくり」にも及ぶことなのだが、「家原病」について知ってもらいたい。 手軽なリラクゼーションを使っても、 リラクゼーション法(自律訓練法)を試しても ストレスは増すばかりという方は、 唯一安らぎを感じなければならない「家」に 問題はないだろうか家族との関わりがレイアウト、インテリアで改善されていくのである。 カビやダニが原因のアトピーやアレルギー、 新建材が原因のホルムアルデヒトの被害、 個室化による家族の断絶が自然欠乏症による家原病。それが、肥満、生活習慣病、ストレスやノイローゼ、凶悪犯罪や虐待、ひきこもりや離婚、成人病などの問題を引き起こすことがあるのだ。 風が当たらず、適度に湿り、暖かい・・・ つまり密閉された状態が 空気の流れ家族の流れを 断絶する国連開発計画(UNDP)が 1994 年に発表した「人間開発報告」で初めて“人間の安全保障”(Human Security)という表現が用いられ、すべての人間の自由と可能性の実現を確保するような生活の条件を整備することの重要性が唱えられた。 世界保健機構WHO は、 安全性(safety) 保健性(healthy) 利便性(efficiency) 快適性(comfort) 持続性(sustainability) 居住環境の基準として、あげている。さて、感性福祉研究と感性論では「居心地の良さ(well-living)」という尺度を用いた環境評価がある。感性福祉は、五感に訴える療法があるが、安心感というのは、ある種の感じ方であり、個々人の感性と社会環境に依拠する 人間関係を中心とするストレスに対して、 ストレス・マネジメントによる対抗スキルは セキュリティ・マネジメントを検討すると 安らぎ(ease)を求め、その確保に向けて行動変容するらしい 住空間の安心感と安全性は、 1.「安」と security 誰にとって どのような環境の安全で 対象は何か 2.住空間(livable space) 居室・住宅 近隣地区 都市圏 国土 地球 地球外居住 Human Security System 安堵住宅、安心住区および安全都市を構想安堵住宅(secured house) 住宅・居室 (所有、利用、行動自由、構造強度、衛生、防犯、防災など) 家族・同居者 (自己尊厳、相互扶助・支援・介護、好悪感、別居選択など) 安堵内容の強化 (住宅改善、支援外部化、行動変容、関係発展、情報交信、見守り強化) 住様式の洗練 (趣味活動、室内外美化、静謐確保、交流発展、文化発信など) 住宅内不安の解消 (部屋閉じこもり、家引きこもり、虐待、孤立、依存など)吉田寿三郎は、家原病という言葉を用い、人間関係を含む広範な住まいの条件が、多くの病い(精神病含む)を生み出すと警告している。では、私たちはどのように暮らすべきなのか。「住まう」ということで、住宅内不安の部屋閉じこもり、家引きこもり、虐待、孤立、依存などを対処していくことができるのか。それは、また次回に。※参考 ・奥山 文朗 「住空間の安心・安全研究:序論」・Environmental Psychology. McAndrew, F. T. (1993) Brooks/Cole.・Handbook of environmental psychology (I, II), Stokols, D. & ALtman, I. (eds). 1987. John Wiley & Sons.・The image of city. Lynch, K.( 1960). M.I.T. Press.・Psychology of the home. Gunter, B. (2000). Whurr Publishers. ・Personal space. Sommer, R. (1969). Engelwood Cliffs. ・Defensible space: Crime prevention through environmental design. Newman, O. (1972). New York: Macmillan.
Jun 17, 2005
コメント(10)
-
スクールウォーズ
生徒の側には、教師、親、友人(学校・学校外)がいる。保健の先生、スクールカウンセラー、塾の先生もいる。さまざまな形で応援者がいる。ただ、それが「問題」になったり、被害、加害の立場をとったり・・・「先生」には、校長、同僚、家庭、友人など、応援者もいるだろう。だけど絶えず「批判」もつきまとう。「教壇」は「ステージ」と同様だ。ただ、芸能人のように、「ファン」ばかりが目の前にいるわけでもない。その教師に対する「好意」だけではないということだ。「嫌悪」、「不満」などの態度、言葉など、「ステージ」へ投げかけられる。親は、平気で「教師」の悪口をいう。親同士、「あの先生は」がはじまる。私も親を経験しているので、その様子がわかる。オットーさんのコメント私が経験したのは、先生へのいじめ。私の両親は、ひどく心配し、加わらなかったのですが、そのため、私も、両親も一時嫌がらせが・・・集団で「担任」を攻撃した当時の親は、一人の人生を台無しに。それってなんの罪の意識もないし、咎めもない。あれから10年経て、私は新米教師。あの「出来事」を知っているからこそ、「いい先生」と思われたい。それは、良い授業や良い指導ではなく、親の都合に合わせることなんです・・・(Jun 17, 2005 12:53:59 PM)こういうことは、なかなか話題にあがらない。いったい「親の都合」とはなんだろう。しかしその「親の都合」こそ、教師を壊していくのでは・・・オットーさん、どうぞ「被害者」にならないでね。さて、いつだったか「メンタル」の弱いものを教師に採用するなという投稿が。それでは、「集団」からの攻撃に屈するのも「メンタル」が弱いからなのか。「親」って一体なんだろう。親だって、「メンタル」で悩む。でも、人間失格なわけじゃない。教師と親のためのカウンセラーも必要な時代ではないだろうか。
Jun 17, 2005
コメント(17)
-
デザートブーツ 1
「登校拒否」”school refusal” 2 より記憶をまた遡る。(1970年代)転校した中学では、私のスタンス(空かした、生意気)が妙に受け、人に好かれるっていいなーと思い、その後20年近くにわたり、人間関係は良好であった。(後日、記事にする予定だが、20年後は人間関係大波乱がはじまる)そんなクラスにも一人、私と同じスタンスの生徒Iがいた。「あいつ嫌われ者だから、近寄るな。」といわれたが、なぜか「友達になりたい!」と思ったのだ。「修学旅行で一度会っている」ことをネタに、近寄ってみた。「あー、そういえばH中と揉めたワ。弱い犬が吼えてたっけね。」あー、Sのことだ。で、話は終わった。次の休み時間にトイレに行くと、男子トイレも女子トイレも「生意気な後輩」が、囲まれている。その中心的な存在がIである。男子にも、女子にも「はげましの指示」を出す。「あいつ嫌われ者だから、近寄るな。」といった0は、Iを無視していたが、「はげまし」の行為はとまらない。Iは、「はげましの行為(気持ちを入れ替えさせる)」といっていた。まず、トイレで正座をさせる。姿勢が少しでも崩れると、モップの柄で、肩をたたく。「はじめて見た。」つい言葉を発してしまった。Iは、ジロリと私をみて、「よし、終わりだ」といって、私より先に行ってしまった。0は、「はじめて見たのか。今度やらせてあげるからな。」と暖かく私をみる。ちがーう。そうじゃなーい。教室にもどると、はじめてみる生徒がいた。3時間目くらいだったかな?みんな、私を紹介する。ちょっとだけ休んでいた生徒Tだが、頭もよさそうで、「良家」の印象があった。何よりも、皆の話の中心で、「人気者」のようだ。そういえば、もうひとつ机が空いている。気になって0に聞くと、「あと2週間くらいで退院してくるのさ。いっしょに見舞いにいこう。」「うん。行く。なんの病気?」「スキー部のOBにさ、ストックで殴られて、脳内出血で入院してるのさ。」ひぇー。そして、放課後、みんな運動系のクラブに入っているので、終わるまで待って、いっしょに帰るのが、習慣になっていた。その日、Tは、「今日いっしょにかえろ。」と声をかけてきた。みなが「おぉー」といった。0が、Tはいい奴だからいっしょに帰ってもいいぞといった。そして、下駄箱で、Tも私もお揃いのスニーカーであったことで、Tと急速に仲がよくなる。「兄が、今年の冬は、編み上げかデザートブーツを買うっていってたけど、デザートブーツをお揃いで買わない?」「いいよ。」わー。はじめて友達と買い物するっていい気分。まだ先のことだけど、「わくわく」が冬の買い物まで続くのだった。
Jun 16, 2005
コメント(11)
-
ブログ編集
「トップ自由欄編集 」を久々に手をつけた。とにかく疲れた・・・19:00から企業研修の講義もあるのに、すべてを使いはたしたカンジ。メモ帳で編集し、いざ登録すると、幅があわない。何度も見直し、一人でアクセスをあげている。あまり、気にすると、手の施しようがなくなっても困る。あー疲れました・・・
Jun 16, 2005
コメント(4)
-
壊れているなら直さない
「その人の人格の持続的な成熟」-ゲシュタルト療法-の目的だ。「もし壊れているなら直さない」ゲシュタルト・アウェアネス・プラクティスのメッセージであることは、以前の投稿にも記してある。放っておくのとわけが違う。過去や未来ではなく「あるがまま」の自分の現在。誰も分析せず、誰も強要せず、誰も判断をはさまないそれが壊れているなら直さないという真理である。ボディワークを実践するのがゲシュタルト・アウェアネス・プラクティス。ところでゲシュタルト療法とは?・今に生きる・ここに生きる・想像から現実的に・考えることより、感じること・判断するよりも、表現する・不快な感情の受け入れ・権威者をつくらない・自分自身の責任・自分であること -ありにままの自分-つまり、このように「生きる」ことが、ゲシュタルト(全体のかたち)なのだ。だから、放っておくのではない。「あるがまま」の自分。そして「相手」をあるがままに受け入れることが、成熟なのではないだろうか。
Jun 15, 2005
コメント(12)
-

リード・マネジメント 1
コメントにある質問「リード・マネジメント」について、おおまかな概念を説明する。リード・マネジメントは、「人を管理する」ところでは、職場に限らず実践することが可能。リード・マネジメントとは、「気配り」である。人に優しく対応し、どんなものが求められているかを説明すれば、良い仕事をしてくれるはず、という理論である。それは、どのようなシステムづくりと信条をもつのか。4つの要素1.成功のために、仕事の質と経費について、全従業員に話し合いをしてもらい、改善にむけて、励ましながら、提案を引き出していく。2.リード・マネージャーの期待が、正確に伝わるよう模範を示し、従業員は、どのように改善できるのかの考えを述べるよう励まし、従業員自身の仕事に、コントロールできるものが大きくなるようにする。3.経費をかけないで、品質改善をおこなう方法は、従業員自身がよく知っており、点検する責任もある。高品質は、従業員とリード・マネージャーの間の信頼レベルに依存している。4.上質の本質は、耐えざる改善であることを教え、道具・訓練など仕事のしやすい友好的な「場」を提供することにより、改善を促進することが目的であることを明白にし、それにより「利益率」が増大したときに、利益の分配のシステムを構築する。つまり、自由裁量、自己統制への信頼関係が、成功に導くのだ。グラッサー博士の選択理論幸せな人間関係を築くために著者: ウィリアム・グラッサー 15人が選んだ幸せの道選択理論と現実療法の実際著者: ウィリアム・グラッサー
Jun 14, 2005
コメント(5)
-
ボス・マネジメント
上司との関係についてのコメントがBBSにある。ここから、個人の問題としてではなく、人間関係を築くという視点で展開したい。リーダシップ、オーナーシップといわれている時代。しかし、そのリーダーシップは、上司だけのものではないよ。ボスをコントロールするのではなく、上手に、セルフコントロールするのもワークキャリアデザイン。それがリード・マネジメントと同じ選択理論から可能になる。リード・マネジメントは、リアリティ・セラピーで有名なウィリアム・グラッサーの選択理論から、意識と行動変革を促すことなのだけれど、本当は、管理職層(ボス)に向けた教育プログラム。古典だけれどX・Y理論ってあったよね。X理論は、強制統率で、いまのボスマネジメントの特徴でもある。この強制統率がプレッシャーを与え、評価の対象外は手をつけなくなる。だから5つの基本的欲求(所属・力・自由・楽しみ・生存)に基づいた鮮明な願望を理解し、外的評価ではなく、自己評価に基づく評価システムを確立し、グラッサー博士の提唱するリードマネジメントを実行していこうということだ。日本では、セルフ・イメージとして誤解を招きやすいが、グラッサー博士の「自己評価」は、「人は他人を公に評価してはならない」ということである。では、部下が上司を含め、変革を起こしていくきっかけはどうするのか。じつはこの選択理論の「内的コントロール」というのが、上司・部下に限らず、人間関係を築くための方法である。傾聴し、支持し、交渉し、励まし、愛し、友情を育て、信頼し、受容し、歓迎し、尊敬することが、外的コントロールとの違いであり、内的コントロールである。選択理論には4つの要素があり、「基本的欲求」に、「上質世界」(クオリティー・ワールド)、「行動(行為、思考、感情、生理反応)」、「クリエイティビティ」がある。「上質世界」とは、私たちがもつ個人的世界が、欲求を最も満足させてくれる具体的なイメージ写真によって成立するところ。1.わたしたちがともにいたいと思う人2.わたしたちが最も所有したい、経験したいと思うもの3.わたしたちの行動の多くを支配している考え、信条これがしばしば、不幸を選択していることもある。要するに、相手の「上質世界」に、入り込むことなのだ。そのためには、「7つの致命的習慣」を除かねばならない。・批判する・責める・文句をいう・ガミガミ言う・脅す・罰する・ご褒美自分が不満を持っていると、相手も不満はもっているもの。「私は精一杯やっている」と思い、相手に対しては「十分でない」と感じている。つまり、感情レベルで同じ事を感じているのだ。「私の意見なのですが・・・と思います」「その状態だと・・・と予測できます」「許可さえいただければ・・・実行します」「アドバイスがあれば、ぜひ教えていただけたらと思います」ボス・マネジメントには、選択理論的アプローチで、会話をしていこう。効果があるかどうかは、まずやってみて。「すべての不幸な人がかかえている中心問題は(貧困や、不治の病、政治的な横暴といったことを除けば)、お互いが望んでいるのに、互いにうまく関わっていけないことにある」ということだそうだから。
Jun 14, 2005
コメント(5)
-

アウェアネス
コメントを読んでいると、本文掲載記事から、それぞれが自分でコメントを書き、御自身でその回答をしている「アウェアネス(気づき)」を体験しているように思われる。つまり、ご自身の経験に「アウェアネス(気づき)」から自分で答えを発見しているということ。・アヤ・エイジアさんのコメントどんな幸せな環境にいても「自分はたった一人」という「脳」をもつ人たち。・・・・・それは、「澄みきった」暗闇なのか、わからないけれど、そういう「自分はたった一人」という状況を愛する人も、苦しむ人もいるのでしょうね。(Jun 9, 2005 03:40:33 PM)・石田雨竜さんのコメント 今週号の主人公「一護」をみて、「誰かを救えたことが彼自身を救った」と感じました。・・・・・「澄み切った孤独」で生きているのが石田雨竜です。(Jun 9, 2005 04:17:45 PM)・シカマルさん のコメントずーっと閉じこもっていた時期があるが、「引きこもり」と意識したことがない。まわりは思っていたのかな。「少年ジャンプ」の漫画のコメント引用が目立ったので、我愛羅も紹介したい。物心がついた時から「自分の存在価値」を求め、いま意識を失いながらも、「自分の存在価値」を考える。我愛羅が登場するたびに、社会にどれほど我愛羅がいるのかと思う。一度読んでほしい「NARUTO」の我愛羅。(Jun 9, 2005 06:15:26 PM)・おしゃれさんのコメントからHINOKIOが主人公なのかサトルが主人公なのか、題名からするとHINOKIOなのでしょうが、もし、私がサトルだったら、HINOKIOに嫉妬するかもしれない。だって、サトルが操作していても、体験するのはHINOKIOでしょ。・地球人さん ・・・・・「人」を天に置かずという意味の「地球人」と自分は受け取りました。犬もネコも、子供のおもちゃも「こころ」がある。だから、おもちゃやお人形も地球人だ。(Jun 8, 2005 08:47:10 PM)・ひきこもりさん HINOKIOはいらない。もう一人の自分の面倒をみる余裕がない。(Jun 8, 2005 08:03:23 PM)・ピノキオさん ・・・・・童話「ピノキオ」、映画「IT」では人間に執着するけれど、「地球人」ではなく、結局「存在価値」が「人」なんでしょうね。(Jun 8, 2005 07:30:08 PM)・自宅勤務さん 自宅勤務という配慮のもとに、人、仕事からの煩わしと集団のなかの孤独感から解放されたが、アラン・シリトーの「長距離ランナーの孤独」のように、ただ一人レースを走りぬく孤独感が・・・結局、自分ってわがままなのかな。(Jun 9, 2005 01:36:59 PM)・「朝日と日経とってます」さんHINOKIOとは、・・・・・なぜか「消耗品」として誕生させられた気がするのは自分だけ?(Jun 9, 2005 12:16:00 AM)ひきこもりとHINOKIO のコメントから※全文掲載はしていません。誰かに、アドバイスや意見を求めているのではなく、書くことによって、自分の気持ちや意思、状況を確認している。あえて、お一人ずつコメントのお返事をしませんでした。なによりも、私の投稿記事より、「経験」や「ココロ」の声なので、このブログにアクセスしてくださった方にも、じっくり読んでほしいなーと思う。これらのコメントは、ご本人自身がそのコメントと自分との対話をしていることが、わたしを刺激します。アウェアネスって何か、どうしてアウェアネスなのか。自分との関係に重きをおくゲシュタルト・アウェアネス・プラクティス(手法)や存在感、実在感や臨場感等の「アウェアネス」(気付き)というグループウェア環境を構築など、アウェアネスは、個人から団体、ナレッジマネジメントにも及び、ワークもさまざまである。私が、「アウェアネス」のなかでもライヒやゲシュタルト療法のパールズなどにも大きな影響を与えた「センサリー・アウェアネス」をメンタルヘルスというカテゴリーでTOPICしている。つまり、今ここにある自分がどのように感じ、振る舞い、存在しているかを自由に軽やかな好奇心をもって探るワークと考えていただきたい。センサリー・アウェアネス「気づき」ー自己・からだ・環境との豊かなかかわり著者:チャールズ・V・W・ブルックス/伊東博「感覚、からだ、ムーブメント、呼吸、重力・人間・環境とのかかわり、といった人間の基本的な条件を、具体的な実習をとおして体験で学ぶ。カウンセリング、心理療法、教育、体育、ダンス、演劇、瞑想などに新しい光を投ずる。日本の禅を、日常生活に生かしているものともいえよう。」 (あとがき)それで、思ったのが、コメントの「書く」という作業は、キーボードを叩きながらという「刺激」がある。そこに「読む」「考える」「書き込みする」という一連から、自分に向き合っているのだと思うと、とても貴重なものだ。これからのカウンセリングや心理療法の方向に対しても取り入れられているボディワークは、「指先」からも味わうことが出来るのではないだろうか。「今ここにある自分がどのように感じ、振る舞い、存在しているかを自由に軽やかな好奇心をもって探る」というその答えがコメントにある。「もし壊れているなら、直さない・・・」エサレン研究所の講師、クリスティン・プライスの「ゲシュタルト・アウェアネス・プラクティス」のメッセージである。つまり「ありのままの自分」ではなく、「いま、あるがままに」という状況を受け入れ、なんらかの機会であるとういう意味への方向転換なのではないだろうか。
Jun 14, 2005
コメント(9)
-

半世紀前の日記
「二十歳の原点」の高野悦子の日記。1962年1月から日記を書き始め「小百合」と日記に名前をつける。これを読んだのは、昭和54年である。明るさから、ニヒリズムへと変化。「独りであること、未熟であること、 これが私の二十歳の原点である。」 ・1969年6月24日未明、鉄道自殺「二十歳のエチュード」は原口統三の小さな3つのノートに記されていた繰り言。私には難しく、理解に困難な箇所もある。芸術家の気質が、なお文章を難解にさせている。しかしシニカルで、読む人を自己投影させてしまう。「表現は所詮自己を許容する量の多少のあらわれにすぎぬ」「誠実さは常に全き孤独の中にある」 この箴言の前に、謙虚であろう。 それはこのエチュードを止めて抛り出すことだ。 そして、僕を含めてすべての人に貼り付けていたレッテルを はがしてしまうことだ。 僕はもう自分を誠実であったと言うまい。沈黙の国に旅立つ前に、深く謝罪しよう。「僕は最後まで誠実でなかった」と。 1946.10.1 赤城山にて・1946年10月25日深夜、入水自殺 19歳10ヶ月Dear Kitty,(親愛なるキティ)の呼びかけで始まるアンネの日記。1929年6月12日に生まれて、将来への夢、友情、恋が、ホロコースト(ユダヤ人に対する大虐殺)な状況で、「隠れ家の中で」記されている。はじめは、同性に対するあからさまな感情や、異性からの賛美が記されている。それが、ある時期から、叙情的に自己を記すようになる。1944年4月5日「・・・・・周囲のみんなの役に立つ、あるいはみんなに喜びを与える存在でありたいのです。わたしの周囲にいながら、実際にはわたしを知らない人たちにたいしても。わたしの望みは、死んでからもなお生きつづけること! ・・・・・ 書いていさえすれば、なにもかも忘れることができます。悲しみは消え、新たな勇気が湧いてきます。とはいえ、そしてこれが大きな問題なんですが、はたしてこのわたしに、なにかりっぱなものが書けるでしょうか。いつの日か、ジャーナリストか作家になれるでしょうか。 そうなりたい。ぜひそうなりたい。なぜなら、書くことによって、新たにすべてを把握しなおすことができるからです。わたしの想念、わたしの理想、わたしの夢、ことごとくを。」・1945年3月1日強制収容所で病死※スウェーデンのディトライブ・フェルデラー(Ditlieb Felderer)とフランスのロベール・フォーリソン(Robert Faurisson)によってまとめられた証拠は、この有名なアンネの日記が捏造文書であることを最終的に確定した。※1958年に始まったローラー・スティーロの裁判でアンネの筆跡鑑定が行われて日記が本物だと認定された。アンネの日記増補新訂版―2種類の「アンネの日記」の存在。その2つを編集した完全本。アンネの童話書き遺していた童話とエッセイ自己を記している日記には、漱石などもいるが、高野悦子や原口統三は、自殺。「孤独」という言葉やニュアンスが受け取られる。予期せぬうちに孤独になったのが高野悦子。孤独、マゾヒズムを自らレッテルに使用したのは原口統三。アンネ・フランクは病死である。15歳だった。なんて「生」に溢れている日記なのだろう。アンネ・フランクの文脈は。やはり「生きる」という情熱がそこにある。「そうなりたい。ぜひそうなりたい。」アンネ・フランクの言葉がいまでも聞こえるではないか。「わたしの望みは、死んでからもなお生きつづけること!」それは「それでも人生にYESと言う 」の著者V.E.フランクルと交差する。
Jun 13, 2005
コメント(9)
-

孤独の心理を測る
孤独を楽しんだり、孤独という空間で、研ぎ澄まされた感性で生きることは可能だと思う。ただ、「稀」なのかもしれない。「孤独」という状況を好んでいるか、好んでいないかが問題で、「孤独」という言葉自体には、特別な闇を感じない。ナカニシヤ書店で、宮沢秀次・二宮克己・大野木裕明編著に「自分でできる心理学」というのがある。そのなかから、孤独感を紹介したい。それから、この記事を読んでいる方に、ぜひ左右されないでほしいと思う。私が、大学で心理学を選択科目で履修したときに、読んでいくと、自分にあてはまることが多数ある。(恐ろしいほど)引き続き、この年齢まで続けると、いろいろな「名称」が増えてきたことの驚く。もし、日常生活や周囲に多大なる「障害」や「困難」さがあるのであれば、「自分にあった」専門医とカウンセラーの支援を受けてほしいかな。それでは、「孤独感」って何か。自分の期待する状況や気持ちと、現実とのギャップが広がるほどに、「孤独」を感じていく人がいる。「自分でできる心理学」では、「願望水準」と「達成水準」とされている。私の独自の考えでは、自分の期待する状況を、相手にも期待し、相手がいることにより達成することで、「孤独」が深まったり、共感が生まれるのではないかという自論がある。人は、些細な表情、しぐさ、言語から、あるいは行動の結果から、さまざまな心理の状態に陥り、さまざまな気持ちを抱き、「孤独」と遭遇する。その孤独の心理のスケールだが、測定値を「決して感じない」これを「1」とする。2 「めったに感じない」3 「ときどき感じる」4 「たびたび感じる」次の項目を、その測定値を用いて、「整理」のひとつの方法にしてほしい。1.私は周囲と調子よくいっていない2.私には、頼りにできる人がいる3.私は、親しい仲間たちのなかで欠くことのできない存在である。4.私には、周囲との共通点が少ない5.私は、だれとも親密にしていない6.私には、私のことをよく知っている人がいる7.私は、望むときにはいつでも、人とつきあうことができる8.私には、知り合いはいるが、私と同じ考えの人はいない以上である。結果の手順であるが、項目1・4・5・8は、測定値の数値をそのまま合計し、A得点とする。B得点は、項目2・3・6・7の測定値の数値をそのまま合計し「20-B得点」が得点Cとなる。孤独感の測定は「得点A+得点C」であり、高い数値ほど孤独感が高いとされている。(数値判断の基準:最低8点・最高32点)「孤独」が障害になっている人とは、「孤独」によって、仕事、家庭、学校生活に支障を感じているかどうか。「孤独」を好む、好まざるに限らず、人を巻き込み、トラブルになっていないかなどで、判断してほしい。「孤独」が障害だと感じる人への解消を、「自分でできる心理学」から参考にすると、対人関係においてである。1.対人関係の「願望水準」を低める2.対人関係の「達成水準」を高める3.「願望水準」と「達成水準」のくいちがいを低めたり、「程度」を過小に見積もる。これは、仕事の達成、評価、量なども考えることができそうだ。ただ、その人個人の対人的技能や周囲の環境で、どれだけ対処できるのかが問題である。また、高い数値がでたからといって、対人関係の技能が劣るわけではないと思う。孤独から生まれる「すばらしい生き方」だってあるにちがいない。・自分でできる心理学・孤独感に関する社会心理学的研究
Jun 12, 2005
コメント(8)
-
はじめての死
奇数と偶数から葬られた友人の死の前に、いま突然にして記憶が甦ったもう一人のクラスメイトの死。記しておこう。M君。ごめん。正直フルネーム忘れている。皆より少し小さくて、目が大きく、頬がいつも赤く、髪の量に特徴があってね、君の姿は、はっきり覚えているんだ。心臓が悪いなんて誰も知らなかったと思う。そんな君も「洗礼」を受けたね。1年か2年か覚えていないけれど、定期試験前後に休んだんだ。「精神的苦痛」かと思っていた。先生が、授業前に、君の心臓の手術の話をした。亡くなった君に聞かせようかどうか迷ったのだけれど、話してしまう。その時、数人の誰かが、「死んでしまったりしてさ」って言ったんだ。先生や他のクラスメイトは、一瞬声がでなかった。それから先生は、静かに君の話をしたよ。1時間ずっと君の話だよ。だけどね、彼らは「死ぬ」なんて思わなかったから、あんな軽口がでたんだね。君が死ぬなんて誰も思わなかったんだよ。記憶に違いがなければ「量徳寺」というお寺に参列した。ぼんやりした記憶。Sと待ち合わせして行った。SとAとは、号泣していた。あの2人もいい奴だ。素朴も泣いていた。M君について、本当に記憶が飛んでいました。5年前に、中学時代を過ごした地域に、仕事の関係で出向いたときに、偶然2人の同級生と顔を合わせた時の会話で、「まだ誰も亡くならずに、がんばっているね」という言葉に「本当だね」なんていっていた自分。これからは、度々思い出そう。
Jun 10, 2005
コメント(7)
-
「登校拒否」”school refusal” 2
「登校拒否」”school refusal”・「不登校」”school absentee”は、第2期時代を迎えていた時代。 私の次の「洗礼者」は、「素朴」というあだ名があった。まったく「素朴」な性質で、いまでも時々思い出し、「いい奴だよなー」と思う。小・中の5年間同じクラスである「素朴」君。あの「素朴」君に洗礼があったのは、「冬」の季節であった。ほとんどの男子学生は、「冬」でも「ズボンした」など穿かない時代に、「素朴」君は、穿いていた・・・その地方は、冬の季節になると2階建て校舎のまわりも雪が積もり、「休み時間」はストーブの周辺が賑わう。そのストーブの賑わいが疎ましい連中は、一角で富島健夫の「小説ジュニア」連載からドフトエスキーの難解な書物を朗読する。朗読役は、いつも私とMが交代しながら朗読する。(その後、MとはNHKの就職試験で出会う。二人とも落ち)。人気は富島健夫の「婚約時代」だったような気が・・・(その後富島健夫氏は官能小説で大活躍!)。結構、すかした男女のほかに初心な奴も、集まってきていた。そんな時間帯に、「素朴」の「ズボンした」が発覚した。「うぅー・・・」という悲痛な叫びと悔し泣きの「素朴」は、腰から膝まで「ズボンした」が・・・「死んでやるー」といって、身を乗り出し、するりと身体は、窓の外へ。そのとき、誰も、手をかさなかった。足が雪の上についていることは承知の上でも・・・そして始業ベルは鳴った。出席を取り始める前に、なんとか自力で「素朴」は這い上がることができた。当時、「素朴」は私の前の席である。「素朴」何しているんだろうと思って、キョロキョロする。「素朴」は床を這っていた。教壇の教師からみると、「素朴」は見えず、他の学生は前を向いているので、私の姿勢に「激」がとぶ。当時、教師は尊敬されていた時代。「○○君が床を這っているんです・・・」といった瞬間、クラス中が大爆笑になった。そのF教諭は、「素朴」を抱きしめ事情を知る。「お前らは暴力をふるったんだぞ!リンチをしたんだぞ!全員がだ。誰がやったのではない!クラス全員だ!」私はしばらく自分の言葉への罪悪感が消えなかった。しかし、翌日から「素朴」は元気に登校したのを覚えている。「ズボンした」をはいて。それから私は、2年生になり、今度は自分に降りかかる。「空かした・生意気」は、私のレッテルとなる。たかだか1ヶ月ほどだが、クラス全員の無視がはじまった。しかし味方を教えてくれる機会でもあった。だから「屈する」ことなく、自分のスタイルというか、スタンスを変えずに過ごすことができた。この時代「不良」という言葉があるが、インテリと硬派の2グループに勢力は分かれていた。そのときの味方には、「不良とよばれて」いた数人も。この「空かした・生意気」は、それから20年後にも大波乱を巻き起こす。さて、3年生になり、高校受験を控えた私は、また父の転勤で学校が変わった。半年だけの学校であったが、生涯記憶に残る出来事があった。「不良とよばれて」というスタンスの多い学級であった。なんといっても、「空かした・生意気」な印象は、「不良とよばれて」いる学生の「ガン」を飛ばされつつ自己紹介が終わる。1時間目がはじまり、そのクラスの担任の授業だった。いきなりその教諭は、窓から嘔吐。不良たちが甲斐甲斐しく「あんまり飲みすぎんなよ。」といって介抱する。その1時間、とにかく「クラスのリーダー格」の視線を感じつつ、雑談の授業は終わる。恐怖の休み時間がはじまった。瞬間「トイレ」には行かないでおこうと私は思った。前の中学は、インテリ不良が多く、暴力沙汰のない学校であった。また、精神的虐めは、不良ではない。しかし、ここは違う。明らかに鈍感な奴でも、何か「暴力的」な雰囲気がわかる。私は、まだ続く「視線」に思いきって対抗した。彼の方をみて、「満面の笑顔」で、視線をそらさず相手の次の行動を待った。一瞬相手が緩む。そして近づいてきた。「慣れたか?」いやー、まだ来たばっかりだよーと思いつつ、「うん」という私に、好きな食べ物、好きな音楽などいろいろ尋ねてくる。「クラスのリーダー格」が興味を持ったと知って、どんどん周囲に人が集まり、卒業するまで、私はクラスの「人気者」という不動の地位を20年近く経験することになる。さて「空かした・生意気」なのは私だけではない。そのクラスに1名いる。しかも、前の中学の修学旅行時に1度会っている。その彼女も含めて、私が転入したことで奇数になったクラスは、1名を葬ることになる。「死」へ。
Jun 10, 2005
コメント(8)
-
「不登校」”school refusal” 1
「不登校」”school refusal”が大きく社会問題化されて10年過ぎた。アメリカでは「学校恐怖症」“school phobia”と記載があるらしい。日本は、1960年代にも一時目立ったが、1980年代は低下傾向を示し、再び1990年代に入って急増している。1950年代後半~1970年頃 児童精神科医たちによる病理としての問題1970年代後半~1980年代半ば 専門家以外の取り組み1980年代半ば~1990年代半ば フリースクールなどの登場1990年代半ば~現在 ホームエデュケーションの広がり(自宅学習)アメリカ、1950年代後半~1970年頃は、神経症や精神障害が不登校の原因として、臨床心理の専門家たちが治療にあたっていた。さて、1968年、私が小学校1年生であるが、クラスに一人だけ「登校拒否」”school refusal”あるいは「不登校」”school absentee”とよばれる状態の児童がいた。いま、文部省は一応「学校ぎらい」を理由にして、年間50日以上学校を欠席するような児童・生徒の状態を指している。これに対して法務省は「何らかの心理的さらに環境的な要因によって登校しないか、登校したくてもできない状態」と定義している。その児童がどちらの「定義」にあてはまっていたのか。さて、1971年、私が小学校4年生である。その私は、文部省の定義にあてはめると、年間50日以上学校を欠席していた。「理由」対処に面倒なクラスメートを避けるため。(私の所持品を盗む、隠す)自分の時間を割いてまで、そのクラスメートとの”やりとり”が面倒であったこと。つまり、クラスメートをたしなめたり、返却を求めたりする”交渉”が面倒なのだ。その理由を母に話すまでは、かなり時間がかかった。まず、彼・彼女らはいじめではなく、単なる”からかい”と”羨望”だったからだ。その”からかい”と”羨望”という表現を、どのように話せば、誤解なく伝わるのかがわからない。服、文房具などを含めて、皆と違うモノを身に着けていたことが興味・関心の的になる。しかし、「皆と同じもの」も、自分の性質上ちょっと困る。そういった複雑な事柄を巧く伝えられない。要するに「休む」ことが自分にとって「解決」の方法であった。その後、父の転勤で、解決したような・・・それからは大学を卒業するまで、普通に登校するようになる。(大学はサボリを覚え、もちろん遊んでいましたよ)ただ、私の中学時代は、「いじめ」が流行だったので、無視、はずしなどは、「洗礼」されたが、それは、私だけではなく、順次クラスの一人一人が受ける洗礼である。そういった時は、屈せず登校していた。それが“すかした奴”という印象を与え、相手が少しエスカレートしそうになったが、次の洗礼者へ移っていく。(いまでも第一印象は“すかした奴”であるらしい。)※講義の時間なので失礼します。まだ続きます。
Jun 10, 2005
コメント(9)
-
4年前
4年前、大阪教育大付属池田小学校の事件があった日だということを、ワークショップの参加で思い出した。もう4年なのか、まだ4年なのか。家族も、児童も時間はとまったままなのかもしれない。
Jun 9, 2005
コメント(6)
-
ひきこもりとHINOKIO
「檜」が素材の遠隔操作可能のHINOKIO:H-603ロボット。コンピュータを通してHINOKIOが得た情報を受け取りながら、ひきこもりの少年サトルは、キーボード操作で、「言葉」を音声化しながら、クロスする心と心の過程を描くファンタジックな映画「HINOKIO」のストーリ。HINOKIOは、「不登校児童対策プロジェクト」から誕生した。「地」に存在することが「地球人」と等しく見なすならば、近未来のコミュニケーションだろうか。HINOKIOが現実に普及しはじめたら「ひきこもり」を実際に経験する人々にとっては、どのような存在価値を感じるのだろうか。「ひきこもり」だけではなく、さまざまな身体の病気や心の苦痛を解放するパートナーであり、外にむかうもう一人の自分として、あるいは自己投影の存在?遠隔操作で、TVをとおし、会議や授業が受けられることは、すでに始まっている。仕事も学校も、通勤・通学せず自宅で勤務・教育の時代が来るといわれている。これで、「何か」がケアされて、人間の原点に戻れるのなら、HINOKIOは、映画のように、感動を与えてくれるだろう。
Jun 7, 2005
コメント(10)
-
コメントから
ReI can ism 匿名氏&CAN氏のコメントから同じライフスタイルは7年以上続かないといわれている。同じ状態でも、さらに悪くなったり、あるいは良くなったり。webコンサルティングのサイト「アイビーネット」で、「自分の考え(知識)の移り変わりを見ることができる」のがBLOGであるという文章に目がとまったことがある。I can ism とは、自分の価値観と自己評価が一致し、「・・・している」という「流儀」から生まれると記したのは、常にリフレーミングしながら、自分の考えの移り変わりをしっかり理解し、ベースを整えると「造語」に依存するようなI can ism は生じないと考えている。お二人のコメントにあるように、家族、友人、住む場所、会社、好み、身体の変化も要素であり、「造語」で精神的苦痛を味わう人もいる。また「造語」に陶酔し拘り過ぎると、大切なものを見落とすことになる。そういうことですよね。※CANに「トイレ・便所」って意味あったんですね。全然記憶になかった・・・ワーク・ライフ・バランス 男女共同参画さん 、ブログさん 、訪問者さん からのコメントから「これは、女性のための取り組みなのかと誤解される。」というコメントは、そのとおりで、最初は女性のケアのため、いま厚生労働省が取り組んでいるワーク・ライフ・バランス は、男女のため。また、おっしゃるとおり、両親と死別し、祖父母に愛されて育った子供達がいることも忘れてはならないこと。それから、アメリカの有能な女性社員に対するケアから生まれているというのも確か。今後、社会全体が取り組めるかどうかが問題だと思いませんか。タイムマネジメントはじめての投稿さん、ffさんのコメントから育児休暇取得で「キャリアが空洞化し、その隙間を啓発しなければならない」という不安なメッセージは、「心得」と思ったほうが。時間はどんどん過ぎるので、いま何を優先するかが決め手。ヒマを与えられたらダメ。ヒマをつくる。kenta1977さん のブログに、最強の人は「ヒマ人間」ってありました。ホント!顔のみえない誰かさんのメッセージからフィードバックしてみた今日のブログ。これは第1弾。コメント、BBSには本質を突く言葉があるから。
Jun 7, 2005
コメント(4)
-
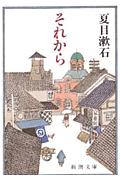
漂泊人「Landstreicher」
カウンセリングは、インテーク面談といって、クライアントの持つ相談事、つまり「主訴 chief complant」をはっきりさせるために、今までの経歴(あるいは病歴)やその他のことを、クライアントのペースに沿って聞いていく。「来談経路」や、趣味、友人・知人関係、教育歴、そして、職業、健康状態、家族のことといったファミリー・ヒストリーから入り、自尊心を傷つける可能性がある性質は無理に聞き出さないという「心理に立ち入らない形で」はじめていく。「相談」が人生相談になって話すことは、COやCCとして、望ましくない。人生相談は、相手がCOやCCの「話」に依存していく傾向があるらしい。「潜在性精神病 latent psychosis」というのがある。これは、相談(あるいはカウンセリング)を行うことで引き起こすことがある。基本的には自由に話させ、触れたくなさそうなテーマやクライアントの人生(life history)の中でフィードバックしたり、似た反応をした体験に特に注意を払っていく。いま、Not in Employment, Education or Trainingについてさかんに問題視されているが、英国で社会問題になった労働政策の中で「職に就かず、学校等の教育機関に所属せず、就労に向けた活動をしていない15~34歳の未婚の者」を指している。肝心なのが、「学校等の教育機関に所属せず」というフレーズである。貧しい階級を指す。だから、日本の”NEET”とは一致しない。”NEET”と言う単語は、英国では普及していない。”NEET”という単語を類型化したのは、独立行政法人労働政策研究・研修機構の小杉礼子氏である。”NEET”が増加することによって、何が問題なのか。青少年犯罪への関与・将来的な失業率の上昇・社会福祉受給者の増加等である。マスマディアなどがセンセーショナルに事柄をあげ、「働かずに生活することは甘え」という固定観念を植え付けているのだろうか。日本の4つの類型化された「レッテル」には、実際にはほとんど存在しない「ラベル」が貼られているらしい。これがマスマディアの脅威でもあるのだろうか。”NEET”へのメッセージも、「良い・悪い」という区別の範囲や、”NEET”という個人の存在に対しての批評ではなく、社会全体としての言及が必要だ。人生相談的視点では、つい、個人の存在に偏りがちである。だから”NEET”を扱う発言には、ファミリー・ヒストリーや、ライフ・ヒストリーなど、性格や特徴を考えなければならない。ヘルマン・ヘッセの「クヌルプ」は、生産社会(ドイツのマイスター制度時代)から離れた「傍観者」としての人生を過ごす。定職はなく、各地をさすらう。しかし、彼の気位の高さ、人々を魅了するみずみずしさをもつ「クヌルプ」を自宅に迎えいれることを、人々は名誉なことと好む。漱石や川端康成の小説にも見られるが、明治時代に、帝国大学等の高等教育機関を卒業しながらも、親の援助を受けながら一日中遊び歩いていた「高等遊民」は、人々から羨望の眼差しで見られていた時代とクヌルプが交差する。中年を過ぎたクヌルプは、魅力も褪せ、死が近づくにつれ、過ごしてきた漂泊人「Landstreicher」という人生を振り返り、間違いではなかったか、もっと別のあり方があったのではないかと後悔する。しかし神は「それでいいのだ。世の中の多くの者は定住して生きているが、時にお前のような存在も必要なのだ。」という。そしてクヌルプは、雪山で凍死する最後となる。クヌルプ改版新潮文庫著者: ヘルマン・ヘッセ /高橋健二 出版社:新潮社ISBN:4102001050サイズ:文庫 / 130p 発行年月: 1983年 09月 本体価格:324円 (税込:340円)
Jun 6, 2005
コメント(12)
-
スーパービジョン カウンセラースキルアップ
今日は、スーパービジョンを経験した。(冷や汗)スーパービジョンとは何か。臨床心理学を学ぶ人にとってもカウンセリングを受けようとする人にとっても重要なことだが、受け持ったクライアントに対するカウンセリングを指導者(supervisor)の前で報告したり、指導を受けたりすることだ。スーパービジョンはオーディエンス 【audience】聴衆、観客、聴取者の前で、公開することだが、オーディションとも呼ぶことがある。今回は、オーディションとしておこう。志願者のテストである。2人組になり、クライエントとカウンセラー役を交互に行い、スーパーバイザーにアドバイスを受ける。スーパービジョンの定義は「方法や技法,すなわちスキルに関する自己盲点に気づかせる」ことで、自分の面接の「傾向・癖」に気づかせてもらう職業倫理である。私の場合は、治癒ではなく、教育・開発のカウンセラーなので、「構成的グループエンカウンターのリーダーとしてのスキル」,「キャリアガイダンスのスキル」,「サイコエデュケーション展開のスキル」,「カウンセリングを生かした授業のスキル」,「特活,グループ指導などのグループワークのスキル」,「個別指導のスキル」,「リサーチのスキル」を、人的ネットワークからリファーする。アメリカでは、「カウンセリングのスーパーパーザー(スーパーバイザー)は誰か?」,「教育分析は誰に受けたか?」,「リサーチに関するスーパーパーザーは誰か?」ということが必ず,質問される。それほど重要なことなのだ。今日、「T・Kは、相槌が少々はやい気がしますね。ケースバイケースで、その相槌が効果を成すこともあるでしょうが・・・云々」さすが、スーパーバイザー。よいカウンセリングを受けて帰ってきたという気持ちであった。
Jun 5, 2005
コメント(3)
-
セレブ系ワーク エアライン
外資系・エアラインのインタビューに備えたヘアメイクというコメントをこの場からANSしたいと思う。ヘアメイク以前に、姿勢、ウォーキング、立ち居振る舞いのほかヴォイストレーニングも重要。外見の印象は、グルーミングといって、前回の記事で、「メトセク」で説明してますので、5Pを確認して。インタビューのヘアメイクということだが、誰でもインタビューへと進むわけではない。外資系のエアラインを例にすると、スクリーニングに通過し、セレクション・プロセスに入る。セレクション・プロセスには、プレミナリー・インタビューがある。このプレミナリー・インタビューは、ウォークイン・インタビューの形式をとる場合がある。(スクリーニング+プレミナリー・インタビュー)筆記、グループセッション、アセスメントツール(心理)、グループインタビュー(多様なグループインタビュー)がある。そして、ファイナルステージへと進み、インタビューを終え、キャンディデートとしてメディカルチェック(重要)を行い、採用を待つことになる。ヘアメイクに関しては、海外と国内では、また各社によってちがう。聞いたことがあると思うが、A社は○○顔が好まれるなど、事前のリサーチが必要で、自分はどこの風土やスタイルにあうかで、合格の可能性を探る。ヘアはロングならシニヨン。髪一筋も乱れてはいけない。履歴書の写真を撮影するまでには、サロンに行き、完璧なヘアを知ることが必要。プロを見習いマスターしなければならない。まず、ヘアメイク、マナー(ビジネス&プロトコール)、ウォーキングなどはCAのスクール、フィニッシングスクールに通い、ひろい教養と知識を身につけることも。国内では、カジュアル(カジュアルな服装指定)面接があるので、カラーなどの配色も指導していただくとよい。つまり、ヘアメイクだけではなく、姿勢、着こなし、趣味のよさ、すべてがパーフェクトでインタビューに望まなければならない。TOEICは、本来就職ではなく、留学の基準となるものだが、このあたりはすでに受験していることと思う。・AC、外資系、国内一流企業就職対象のアカデミー講座・エコール ド プロトコール モナコ(プロトコール)・AICA東京チャプター(国際イメージコンサルティング)・その他・矯正・審美歯科(歯・舌)、眼科、整体こういった、パーソナル・アピアランスのほかメディカルなケアが必要。ヘアメイクとコメントにありましたが、スクールへの通学も考えていたのではないでしょうか。また、2年生ということで、リサーチもしていないのでは?7PとはPrior Perfect Planning & Preparation Prevents Poor Performance「事前の完璧なプランニングと準備が、乏しいパフォーマンスを防ぐ」GROOMING(身だしなみ)とは ・Practical ・Palatable・Proportionate・Purposeful・Proud・Penetrateここまで、事前準備を怠らない人がいるということです。※外資系は、ジャパン社や職種により、対応が違いますので、今回はお答えしかねます。MAILよりメッセージをください。
Jun 3, 2005
コメント(7)
-

タイムマネジメント
ワーク・ライフ・バランスは、女性の働き方のケアから始まった話は、すでに記している。長時間労働の弊害、労働の価値観の変化から仕事の再設計とトレーニングをパク・ジョアン・スックチャのタイムマネジメントスケールで、男女の区別のないライフ&ワークスタイルの自己把握と自己実現に向ける事ができる。1.仕事2.配偶者・パートナー3.家族4.友人5.健康6.自己成長7.余暇・趣味、8.精神的安らぎ現実と理想を8つの項目で、0~10の数値で表すと、どのくらいのギャップが生じているのだろう。時間管理、タイムマネジメントというと、どれがけ効率よくこなしていくか、に重きが置かれ、仕事とプライベート両面において時間管理をうまくリンクさせることについては、決して十分ではなかった。「Priority」を実現するために、「Focus」していくために、どうしたら、仕事やプライベートでの生産性を上げられるのだろうか?この冒頭は、スティーブン・R・コヴィー著「7つの習慣」のフランクリン・コヴィー・ジャパンのメッセージでもある。フランクリン・プランナーの魅力は、最優先事項を達成するために、セミナー、書籍ほか、日々の生産性を高め、「価値観」を明確にする ツールがある。PDA版フランクリン・プランナープランナー商品コンピテンシー・モジュール1.自分の態度・考え方・行動を学ぶ2.優先順位を決める3.信頼を勝ち取る 4.自分の影響範囲に集中する 5.模範を示す 6.自分のミッションを持つ7.生活のバランスを保つ 8.緊急事態を減らし業務のオーバーフローを防ぐ 9.優先順位に従って計画する 10.効果的に協力し合う 11.相違点を認め合って協力する 12.理解するために聴く13.自分を磨く 14.行動パターンを改善する 15.学習の成果を共有する 16.利害の一致点をみつけ対立を解消 Web Counseringでも紹介している。
Jun 2, 2005
コメント(2)
-

パク・ジョアン・スックチャ「会社人間が会社をつぶす」
99年のアメリカは、働く女性のケアから、保育など主に働く母親を対象とした「ワーク・ファミリー・バランス」(又は「ファミリーフレンドリープログラム」)への取組を始め、男性に関してもライフ・バランスを企業が環境整備を進めていくという考えのもとに、「仕事以外にも大切なこと」である私生活の充実が、豊かな経験と広い教養を啓発し、それがシゴトに発揮されていくということ。National Worklife Initiative(NWI)は、ワークライフバランス促進協会(the Alliance for Work/Life Progress;AWLP)、フォーチュン誌、アメリカ経営者連盟(American Business Collaboration ;ABC)選出の9社の代表から構成され、「全国仕事・家庭月間」の普及、家庭に優しい職場環境の構築、フォーチュン誌は、仕事と生活の調和に関する特集を組むことで、全経営者が健康的な職場環境を整備するために情報提供などの支援を行い、それにより仕事、個人そして地域の充実を目指すことを使命としている。日本では、厚生労働省が、ワーク・ライフ・バランスへの取組について 審議。フレックスワーク、保育・介護・養子縁組サポート、転勤サポート、EAP、ヘルス&ウェルネス、フレキシブル保険制度、休暇制度、教育サポートなどパク・ジョアン・スックチャ「会社人間が会社をつぶす」から作成している。 米国におけるワーク・ライフ・バランスへの取組について(厚生労働省)私生活が会社を救う?仕事優先、家庭二の次の時代は終わった。アメリカン勝ち組企業では、大切な資源=人材確保のために、福利厚生としてではなく、ビジネス戦略としてワーク・ライフ・バランスを取り入れている。自分の仕事、家族、生きる目的を大切にしている社員ほど、業績に貢献しているという統計があるからだ。アメリカが元気になったビジネス戦略。
Jun 2, 2005
コメント(3)
-
I can ism
ライフスタイルにもキャリアがある。その人の関心事、好きな対象(人・モノ)、ファッション、グルーミング、住まい方、インテリア、コネクション(personalrelationships)、そしてそれを選択する見方や考え方。たとえば、その考え方を言葉にすると、「○○な生活」。人によって、「○○」というスペースにあてはまる言葉が、現実であったり、理想であったりするけれど、結局は「そう生きたい」という思いである。「シンプル」という言葉を何人かが選択したとする。それぞれが選んだ「シンプル」を具体的にすると、考え方が伺える。シンプル=フランス流倹約生活、シンプル=無機質な生活空間、シンプル=自然派など、=「考え方」の違い。canは、「・・・できる」、「・・・のやり方を知っている」、「・・・している」という表現だ。だから「can」といっても、知っているだけ、しているの大きな違いがある。自分にレッテル、ラベリングを好む傾向が多くなってきて、「自分流」、「私流」、「○○流(族)」などがあるけれど、本質はどこにあるのかな。だから、ニート、フリーター、少子化、年金問題などが話題になっても、「自分流」に生きるから、困らない限り「自由な選択肢」と捉えている。よく、「個人のライフスタイルの選択肢が多様化して・・・」という表現があるけれど、それだけ、生活者のクラスに「大差」がでてきたのではないだろうか。ライフスタイルのキャリアって、「・・・している」ということ。経験と、いろいろなスタイルを深く理解して、自分の価値観と自己評価が一致し、「・・・している」という「流儀」が生まれる。トレンドだったり、使ってみたいとか、そう思われたいというレッテルでは、すぐ剥されてしまうから気をつけて。ちなみにcanは、「名詞」にすると、留置所、刑務所の意味があるんだって。
Jun 2, 2005
コメント(2)
-

ワークスタイル
独立契約のシゴトをはじめてから3年ほど経過。契約している企業は13社。職務がまったく異なり、教育・学校では外部講師、リテール業界では、教育研修講師やキャリアコンサルタントで契約。広告・出版では、委託に関したプロジェクト、あるいはマーケティングのプロジェクトに参加したり、自治体の要請を受けたり、一言では説明できない「職業」の悩み。初めて会う方は、相手の「外見」「言葉・会話」「しぐさ・表情」+「マナー」の振る舞いで、第一印象を決定。まず、顔から足元、そしてまた顔に視線を移しながら自己紹介か名刺交換。名刺交換のない場合は、「職業は」という質問を受けることが多い。週の4日のうちに、学校や企業に赴くが、空き時間が結構ある。たとえば、学校が14:30で終了すると、次の予定の企業研修は、17:00からであったりするので、「すきま」時間を埋めるのに苦労。カルチャー的な講座に出席したくても、決められた時間内での受講も難儀で、結局、ブログをはじめることに。また、毎日「同じ場所、同じ時間」ではないので、生活のライフスタイルのサイクルも変化。以前より「家族」との接点はあるけれど、特別に団欒の時間が増えたわけでもないけれど。このごろ「同じ場所、同じ時間」の繰り返しもよかったなーと思う。人からみると、「週3日もお休みで」となるが、委託の企画・提案業務や、講義の資料作成、コンサルティングのカルテの作成、講演の準備など、活字とペーパーに埋もれ、メリハリを自分でマネジメントしなければならないし・・・気分転換が家事であったり、それこそ家族との会話や食事でもある。が、ドリンクやビールを飲みながら、煙草を吸いながらのスタイルは、週3日もお休み状態にみえるかも。 DESK 上段はGWATHMEY & SIEGEL Desk:ガスミー & シーゲル デスク といい、チャールズ・グワスメイと、ロバート・シーゲルが、グワスメイ/シーゲル・アンド・アソシエーツを開設。彼らのデザインは、相互理解、相互批判をもってして、個人ではなし得ない能力を互いに引き出す努力より生まれ、ゆえに、敷地、方位、形態、機能と総ての要素に関し、分析する過程を尊重する。 このデスクは 、形態からしても、機能からしても、実に素直な印象。唯一施された把手のディテールを除けば、一見ごく普通。そこに彼らの、意味の含有、秩序性といった抽象性をくみ取る事が出来る。 下段は、NELSON Desks:ネルソンデスク。1950年代、世界に先駆けてL字型を採用したエグゼクティブ向けデスクシステムで、シンプルで直線的なライン。建築家でもあったGeorge Nelsonの感性が十分に生かされている。残念ながらSold Outである。 こんなDESKが自宅にあれば、ながら仕事にならないだろうな。 イントレックス・ストア イントレックス・ストアは、毎日暮らしている家に、それぞれの作り手の想いの量を備えた、気持ちがいい暮らしのプロダクトに重視している。人の感性を刺激して、それは、最高のリラクゼーションなのかも。
Jun 1, 2005
コメント(0)
全40件 (40件中 1-40件目)
1
-
-

- 懸賞フリーク♪
- 森永乳業フェアでホテルランチに行き…
- (2025-11-18 16:55:25)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-
-
-

- みんなのレビュー
- 内勤です。⛅️(8度)寒い秋模様🍂
- (2025-11-18 17:12:55)
-






