PR
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(290)時代の事変・変貌
(256)幕末
(104)中世
(1126)戦国
(1078)江戸後期
(133)近世
(40)古代史
(254)江戸時代
(606)安土桃山時代
(346)明治維新
(86)大正・昭和
(360)温故知新
(0)魏志和人伝
(4)王朝伝説の群像」
(3)徐福
(0)江渡泰平の群像
(1)「傘連判状
(5)室町管領の攻防」
(20)徐福・桃源郷に消え」
(1)江戸泰平の群像
(294)石徹白騒動
(7)大名のお家騒動
(64)信西と信頼の興亡
(5)嘉吉の乱
(43)応仁の乱の群像
(46)戊辰戦争の群臣
(69)幕藩一揆の攻防
(55)ジョン万次郎の生涯
(2)太閤の夢の夢」
(79)平治の乱
(43)西南戦争
(42)保元の乱
(38)天正壬午の乱
(43)小牧長久手
(42)治承寿永の乱
(43)高杉晋作
(49)コメント新着
キーワードサーチ
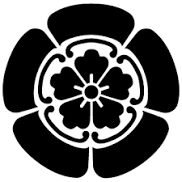
「 織田 達定」 (おだ たつさだ / みちさだ)は、室町時代後期から戦国時代にかけての武将。尾張国下四郡守護代。通称は五郎。官位は大和守。清洲城主。
略歴
織田寛定の子として誕生。
継承時期については不明であるが、先代(叔父とされる)織田寛村の名が文献から途絶え、文亀3年(1503年)、清洲に勢力を持つ守護代として妙興寺に政札を出していることから、この頃に「大和守家」(清洲織田氏)を継いだと思われる。
また一説に嫡流「伊勢守家」(岩倉織田氏)の当主にもなった説もある。
初名については不明だが、後に尾張守護・斯波義寛の跡を継いだその子義達の一字「達」の偏諱を受け、達定と名乗った推定される。文明14年(1482年)、斯波義寛に従軍し、近江国へ出陣したという。
永正10年(1513年)、義寛の跡を継いだ守護・斯波義達に対して反乱を起こすが敗れて自害する(遠江国遠征を巡って対立があったといわれている)。
達定に代わり、一説に弟でその養子とされる達勝が新たな守護代となる。没年月日について『定光寺年代記』では4月14日、『東寺過去帳』には5月5日とあり、諸説ある。】
尾張守護代を世襲した織田氏惣領家は代々伊勢守を称したため伊勢守家と呼ばれ、主君である斯波氏とともに在京生活を送って中央政界での権力闘争に終始し、尾張には在国の又守護代(守護又代とも)として、代々大和守を称する一族(大和守家)を配置して統治を行っていた。
なお、室町将軍のブレーンであった醍醐寺座主・満済の日記(『満済准后日記』)によれば、正長元年(1428年)8月6日、織田常松は病に侵され危篤状態にあったとされ、満済が常松の許に見舞いの使者を送った際、織田弾正という者が応対したという記述があり、これが織田弾正忠家(後述、織田信長の家系)の史料上の初出と見られている。
4、「応仁の乱と織田氏の分裂」
織田氏の主君である斯波氏は 7 代当主の斯波義淳の没後、 8 代義郷・ 9 代義健と短命の当主が続き、家中の実権は執権の甲斐氏をはじめ織田氏・朝倉氏などの重臣層と、斯波一族の大野家などが握っていた。やがて重臣層と一族衆の対立が深刻化し、寛正6年(1465年)には重臣層が推す渋川義鏡の子義廉と大野家出身の義敏が家督を巡って対立する武衛騒動が起こることとなった。
この争いが将軍家・畠山氏の家督相続と連動したため、応仁元年( 1467 年)の応仁の乱が勃発、義廉と甲斐氏や織田氏などの主だった重臣層は西軍となり、義敏と斯波一族、そして一部の重臣やその庶流は東軍となり争った。
この時、義廉は京都で西軍の主力として戦い、義敏は守護職回復を狙って越前で戦っている。また義敏の子義良(義寛)は尾張に居たと思われ、文明7年(1475年)遠江国は東軍である駿河守護今川氏の侵攻を受け、同じく東軍であった遠江守護代甲斐敏光とともにこれを防ぎ、今川義忠が敗死に追い込んでいる。
しかし、越前国では西軍から東軍に寝返った朝倉孝景が越前守護を称して西軍の勢力を越前から一掃していき、さらに文明13年(1481年)頃までには朝倉氏は同軍であり主君でもある義敏・義良親子の勢力も駆逐してしまった。
この間、義廉も将軍足利義政の不興を買って管領職・三ヶ国守護職・斯波氏家督の全てを剥奪され、都落ちを余儀なくされている。
尾張国では、守護代の織田敏広(伊勢守家)が西軍ということもあって西軍の優勢な地域であった。この頃、尾張の守護所が下津城 ( 中島郡 ) から清洲城 ( 春日井郡 ) に移されたという。
このため都落ちを余儀なくされた義廉も尾張へ落ち延び、敏広とともに勢力の巻き返しを図ることとなった。
しかし、応仁の乱が終結した翌年の文明10年(1478年)、東軍であった尾張又守護代・織田敏定(大和守家)が室町幕府第9代足利義尚から正式な尾張守護代と認められると、敏広と義廉は兇徒と断じられて討伐対象に指定されて清洲城を追われた(義廉は以後の記録には見えなくなる)。
しかし、伊勢守家は、織田敏広の岳父であった美濃国の斎藤妙椿(旧西軍)の支援を得て盛り返し清洲城を包囲した。この時、織田敏定は右目に矢を受けたという。
翌文明11年(1479年)、再三の幕府の介入により、織田敏広と斎藤妙椿は清洲城の包囲を解き、尾張上四郡(丹羽郡、葉栗郡、中島郡、春日井郡)を伊勢守家、尾張下四郡(愛知郡、知多郡、海東郡、海西郡)を大和守家が治めることで和睦したとされる(しかし、実際には知多郡と海東郡は一色氏が分郡守護であった)。
文明13年(1481年)3月に伊勢守家は大和守家と争って勝利した。織田敏広の後を継いだ寛広は斯波義寛(義良)に帰順した。
文明15年(1483年)には京から尾張に下向した斯波義寛が清洲城に入城し、守護・斯波義寛、守護代・織田敏定の体制で尾張はひと時の安定期を迎えた。
守護・義寛のもとで安定化した尾張であったが、長享元年(1487年)に近江守護・六角高頼攻め(長享・延徳の乱)が起こると義寛は両織田氏を率いて将軍の元に参陣した。
-
「細川忠興の群像」細川忠興の出自。 … 2024年06月27日
-
「細川忠興の群像」目次・はじめに・川村… 2024年06月27日
-
「長宗我部氏一族の群像」南北朝・室町時… 2024年06月15日










