PR
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(290)時代の事変・変貌
(256)幕末
(104)中世
(1126)戦国
(1078)江戸後期
(133)近世
(40)古代史
(254)江戸時代
(606)安土桃山時代
(346)明治維新
(86)大正・昭和
(360)温故知新
(0)魏志和人伝
(4)王朝伝説の群像」
(3)徐福
(0)江渡泰平の群像
(1)「傘連判状
(5)室町管領の攻防」
(20)徐福・桃源郷に消え」
(1)江戸泰平の群像
(294)石徹白騒動
(7)大名のお家騒動
(64)信西と信頼の興亡
(5)嘉吉の乱
(43)応仁の乱の群像
(46)戊辰戦争の群臣
(69)幕藩一揆の攻防
(55)ジョン万次郎の生涯
(2)太閤の夢の夢」
(79)平治の乱
(43)西南戦争
(42)保元の乱
(38)天正壬午の乱
(43)小牧長久手
(42)治承寿永の乱
(43)高杉晋作
(49)コメント新着
キーワードサーチ
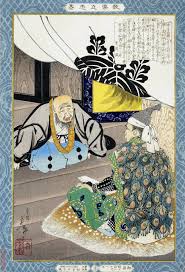
(たけだ のぶしげ)は、戦国武将の武将。安芸武田氏の一族である。武田信実が逃亡した後に、安芸武田氏の家督を継いで当主になったとする説や、安国寺恵瓊の実父の説がある。
安芸武田氏の当主・武田元繁の子、武田下野守(名は不明。伴繁清とする説もある。)の子であるとされ、当主を継いだ武田信実とは同世代の親族関係にあるとされる。ただし、安芸武田氏の家系図には疑問点も多いとされるため、史実として正確であるとは断定されていない。
武田信実は天文4年(1535年)に武田光和が死去した後(異説あり)に若狭武田氏から養子として迎えられて当主となったが、養子のために家中の統率ができずにいた。
天文10年(1541年)の吉田郡山城の戦いで出雲国の尼子詮久が毛利元就に敗れて出雲に撤退すると、尼子と同盟関係にあった武田方の佐東銀山城は孤立無援となり、信実は城を捨てて尼子の援軍であった牛尾義清らと共に出雲に逃亡した。
しかし、城兵300人ほどは一族の信重を擁立してなおも抵抗する。しかし勝敗は既に決しており、毛利元就に攻められて佐東銀山城は落城し、信重は自害した。
これにより、安芸武田氏の勢力は滅亡した(佐東銀山城の戦い)。同時期、信重の父とされることもある伴繁清もまた、伴城に籠るも討死している。
子孫
銀山城(伴城とする説もある)落城の際、武田信重の遺児が家臣に連れられて安芸国の安国寺(不動院)に逃れた。後に安国寺恵瓊として毛利元就に仕える外交僧となり領地をも得て、戦国の世に名を馳せることになる。
伴 繁清 / 武田 繁清 (とも しげきよ / たけだ しげきよ)は、戦国時代の武将。安芸武田氏の一族で、武田元繁の子とも弟とも、娘婿とも言われている。
略歴
永正14年(1517年)の有田中井手の戦いでは、武田元繁配下として出陣し、品川信定らと有田城包囲軍に加わる。しかし、突出した熊谷元直に引き続き、毛利元就によって総大将・武田元繁が又打川で討死するに及び、撤退した。その後は元繁の遺児・光和を支えて大内氏やその傘下の毛利氏と対抗する。
天文2年(1533年)、安芸武田氏と家臣であった熊谷氏が対立。光和は熊谷信直討伐を企てて、繁清は総大将として香川光景、己斐直之、山田重任、温科家行らを従え、三入高松城下へ出陣、横川表の戦いとなる。この戦いでは少数の熊谷勢が武田勢を圧倒。繁清も負傷して退却した。
天文10年(1541年)、吉田郡山城の戦いで出雲国の尼子詮久(後の尼子晴久)率いる尼子軍が敗れて撤退すると、安芸武田氏の居城・佐東銀山城から当主・武田信実が尼子方の援軍(牛尾幸清ら)と共に出雲に逃亡、実質安芸武田氏は滅亡した。佐東銀山城では武田家臣らが信重を擁立し、繁清は居城の伴城に籠るも、同年(翌年説もある)に毛利氏らの攻撃を受けて両城は落城、信重は自害(佐東銀山城の戦い)、繁清は討死した。
滅亡時に繁清の孫(信重の子息)が伴城から脱出するが、この遺児が成長して安国寺恵瓊と名乗る事となる。
3「東福寺時代」
天文10年(1541年)、 毛利元就 の攻撃で安芸武田氏が滅亡すると、家臣に連れられて脱出し、安芸の 安国寺(不動院) に入って出家した。その後、京都の 東福寺 に入り、竺雲恵心の弟子となる。恵心は 毛利隆元 と親交があったため、これがきっかけとなり毛利氏と関係を持つこととなった。
僧としては天正2年(1574年)に安芸安国寺の住持となり、後に東福寺、南禅寺の住持にもなり、中央禅林最高の位にもついた。慶長4年(1599年)には 建仁寺 の再興にも尽力している。このほか方丈寺、霊仙寺といった寺院を再興し、 大内義隆 が建立した 凌雲寺仏殿 を安国寺に移築するなどした。
毛利 元就 (もうり もとなり)は、戦国時代の武将・大名。毛利氏の第12代当主。安芸(現在の広島県西部)吉田荘の国人領主・毛利弘元の次男。毛利氏の本姓は大江氏で、大江広元の四男・毛利季光を祖とする。
家紋は一文字三星紋。
元就は用意周到かつ合理的な策略および危険を顧みない駆け引きで、自軍を勝利へ導く策略家として知られており、家督を継いだ時点では小規模な国人領主に過ぎなかった毛利家を、一代で山陽・山陰10か国を領有する戦国大名の雄にまで成長させた(しかも、完全な老境に入ってから版図を数倍に拡大させている)。子孫は長州藩の藩主となったことから、同藩の始祖としても位置づけられる人物である。
家督相続
明応6年(1497年)3月14日、安芸の国人領主・毛利弘元と正室の福原氏との間に次男として誕生。幼名は松寿丸。出生地は母の実家の鈴尾城(福原城)と言われており、現在は毛利元就誕生の石碑が残っている。
明応9年(1500年)、幕府と大内氏の勢力争いに巻き込まれた父の弘元は隠居を決意した。嫡男の毛利興元に家督を譲ると、松寿丸は父に連れられて多治比猿掛城に移り住む。
文亀元年(1501年)には実母が死去し、松寿丸10歳の永正3年(1506年)に父・弘元が酒毒 ] が原因で死去した。
松寿丸はそのまま多治比猿掛城に住むが、家臣の井上元盛によって所領を横領され、城から追い出されてしまう。この困窮した生活を支えたのが養母であった杉大方である。杉大方が松寿丸に与えた影響は大きく、後年半生を振り返った元就は「まだ若かったのに大方様は自分のために留まって育ててくれた。
-
「細川忠興の群像」忠起の人物像。 … 2024年06月27日
-
「細川忠興の群像」戦後の転封。 … 2024年06月27日
-
「細川忠興の群像」東軍で関ケ原を戦う。… 2024年06月27日










