2014年07月の記事
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-
原発と集団的自衛権
池田信夫世界ではいつも戦争が起こっている。日本だけは攻撃を受けないと思い込んで「自衛官の命」だけを心配するのは幻想だ。---例によって池田信夫の暴論の紹介です。池田信夫は、ことあるごとに「原発事故では誰も死んでいない」ということを言いたがるわけですが、実際には、「福島の原発事故では」「放射能の直接的影響で」「これまでに確認された」死者はいない、と言うことに過ぎません。今後も死者が出ない、などということは保障の限りではありません。そして、「世界ではいつも戦争が起こっている」ことは事実でも、日本が第二次大戦以降は戦争をしていないこともまた事実であり、中国から(他の国でも同様ですが)戦争を仕掛けられて死者が出た事例も、これまでのところは皆無です。もちろん、これまで死者が出ていないから今後も出ないとは保障できませんが、それは原発も同じことです。いずれにしても、集団的自衛権を認めないことによって外国に攻め込まれて犠牲者が出る可能性と、集団的自衛権を認めることによって関わる必要のない外国の紛争に関わって犠牲者を出す可能性と、どちらのほうがより高いのか、ということです。後者の可能性の方がはるかに可能性が高いと考えざるを得ません。こんなことも書いているようです500年に1度で死者ゼロの原発事故の避難計画が完成しないと原発を動かせないのなら、30年以内に1万人死ぬ首都直下地震の死者をゼロにする避難計画ができてない東京都からは退避するしかない。---東京都から住民を全員退去させることは、物理的に不可能であり、かつ日本国内に大地震のリスクのない土地は皆無と言っていいので、移転先も存在しない以上、選択肢はありません。しかし、原発に関しては、原発抜きの発電が現状すでに実現しています。コストはちょっと高いかもしれないけれど、その点を除き、利用者にとっての利便性は、原発だろうが火力だろうが水力だろうが、電気が供給されている限りは差はありません。この差は、決定的に大きい。
2014.07.31
コメント(5)
-
A380
エアバス、スカイマークとの交渉打ち切りを表明新興航空会社のスカイマークが欧州旅客機大手エアバスから大型旅客機「A380」の購入契約の解除を通告された問題に関し、エアバスの日本法人は30日、読売新聞の取材に対し、「交渉は終わっている」と述べ、スカイマークと今後、協議を行わない考えを明らかにした。違約金などの解約条件については「契約書に沿って我々が権利を行使するだけだ。決定権はこちらにある」と述べた。スカイマークの西久保慎一社長は29日の記者会見で、解約条件について「協議している最中だと思っている」と述べていた。スカイマークは当初6機を導入する予定だったが、2機の導入を延期し4機の契約を解除する案を打診。エアバスは6機の契約解除を通告した上、契約変更を言い出したのがスカイマーク側だったことから、700億円規模の違約金の支払いを求めているとされる。---日本で、他の航空会社が巨人機A380に手を出さない中で、スカイマークだけが6機を発注していたことに関しては、いち飛行機ファンとしては、日本にもA380を飛ばす航空会社があることをうれしいと思う反面、航空会社の規模に対してあまりに大きすぎる機体で、大丈夫なの?という思いも、正直言ってありました。どちらかと言うと、「びっくり!」と言うよりは「やっぱり!」という印象です。ただ、非常に残念。発注している6機がどこまで完成しているかは知りませんけど、少なくとも最初の1機はもう完成しており、半分塗装した状態でテスト飛行している写真が公開されています。その他の機体も製造はかなり進んでいるのでしょう。これ、A380だけの問題では済みません。論争の原因にもなった、ミニスカ制服のスチュワーデスが乗務するA330も、スカイマークは10機を発注していて、2月に2機受領していますが、その後何機受領しているのでしょう。その後はまだ受領していないか、せいぜい1~2機でしょう。まだ未受領の機体が相当数あるはずですが、もう納品はされないでしょう。違約金700億円、とも報じられています。スカイマーク側は常識を逸脱した法外な違約金と言っているようですが、契約の内容がどうなっているかは知りませんけど、すでに完成している機体もあるし、それ以外の機体も製造はかなり進んでいるでしょう。座席の配置などは航空会社ごとに考え方が違うので(そうでなくても、スカイマークは全席ビジネスクラスという特殊な仕様)、転売するにも内装は全部やり直さなければならないし、転売先にも足元を見られるから格安で売るしかないだろうから、それらの要素を考えると契約価格1900億に対して違約金700億は、それほど法外でもないのではないか、という気がします。この世界の慣行は知りませんけどね。あと、この1900億という契約金額には、エンジンは含まれているんでしょうか。エンジンは別会社が作っている(スカイマークの機体のエンジンはロールスロイス製)し、通常新造機の値段は機体とエンジンで別々だと記憶しています。1900億というのがエンジン別の契約金額だとすると、エアバスへの違約金以外にロールスロイスへの違約金も発生するかもしれません。これも、6機分24基のエンジンの値段はいくらなんでしょうね。200~300億くらいだろうと思うのですが。一緒の契約なら、エンジンの分も含んだ賠償額かも知れません。そのあたりは正確には分からないので措くとして、前金で払ってある265億円も戻ってこない上に700億の損害賠償(ということは、追加の請求が435億?)となると、年間売り上げ800億円台の航空会社は・・・・・・本当に倒産するかも。それは残念なことだけど、やっぱり年間売上が800億円台の航空会社が6機で1900億円の巨人機のお買い物、というのは、やっぱりちょっと(いや、かなり)不自然ではあります。
2014.07.30
コメント(2)
-
他人のふり見て我がふりなおせ
朝鮮人の責任も問い韓日和解を説く「帝国の慰安婦」が訴訟騒ぎになる韓国の常識韓国における慰安婦問題は反日も絡んで根が深く、一筋縄では行かない。その象徴的な出来事が最近起きた。韓国で昨夏出版された「帝国の慰安婦」の内容が問題視され、元慰安婦9人が今年6月にソウル東部地裁へ販売差し止めの仮処分を申請し、著者である朴裕河・世宗大教授を名誉毀損で提訴した。原告側が用意した報道資料によると、同書が元慰安婦らを「売春婦、日本軍の協力者」と描写し、「(元慰安婦たちは)日本軍の同志であったことを認め、大衆に被害者としてのイメージだけを伝えるべきではない」と主張し、元慰安婦らの名誉を傷つけたとしている。一方、被告側は本の内容が歪曲されて受け取られている、として争う姿勢を見せている。朴氏は慶応大や早稲田大で学んだ知日家で、慰安婦問題をめぐる論客の一人でもある。「慰安婦は強制連行された日本軍の性奴隷」といった韓国の“常識”を覆す主張を繰り広げ、日本に謝罪や賠償を求めている支援団体「韓国挺身隊問題対策協議会」などが朴氏の言動を警戒してきたことは想像に難くない。問題となった同書について、韓国の主要紙、朝鮮日報が韓国のKAIST大教授の書評を掲載している。「慰安婦問題では朝鮮人も責任を避けられない、という指摘は認めざるを得ない。娘や妹を安値で売り渡した父や兄、貧しく純真な女性をだまして遠い異国の戦線に連れて行った業者、業者の違法行為をそそのかした区町村長、そして何よりも、無気力で無能な男性の責任は、いつか必ず問われるべきだ」と朴氏の主張に一部、同調している。また「本書を細かく読んでみると、韓日間の和解に向けた朴裕河教授の本心に疑う余地はない。元慰安婦を見下したり、冒涜したりする意図がなかったことも明白だ」と擁護している。この訴訟騒動について、ハフィントンポスト韓国版に、木村幹・神戸大教授が寄稿している。「『帝国の慰安婦』は昨年8月に既に出版されたものであり、今の段階で突如販売差し止め請求がなされるのはかなり奇異な感がある。背後には慰安婦運動をめぐる、支援団体と朴裕河間の対立も指摘される」という。さらに木村氏は「司法や社会の“常識”を利用して、ある特定の議論を封殺しようとするのは、慰安婦問題の解決、糾明を妨げるばかりでなく、その運動の信頼性を自ら大きく傷つけているだけだ」と支援団体を批判した。保守系の韓国紙、東亜日報は、朴氏がフェイスブックを通して反論した内容を伝えている。「支援団体とマスコミが作った“韓国の常識”とは違う意見を言って無事だった人はいなかった。大統領も支援団体の批判を受けて自身の主張を曲げたことがある」と朴氏は指摘している。---なるほどね、韓国でそういう訴訟が起きている、という話は初めて聞きました。問題となっている本は読んだことがない(そもそも、日本語版が出ているかどうかも知りませんけど)ので、その内容が妥当かどうかは私には分かりません。「娘や妹を安値で売り渡した父や兄、貧しく純真な女性をだまして遠い異国の戦線に連れて行った業者、業者の違法行為をそそのかした区町村長」にも責任がある、という主張は、それ自体はそのとおりだと私も思いますが、どのような文脈で書かれているのかが分かりません。それはともかく、第二次大戦期の歴史的な事実を巡る著作が訴訟の対象になるのは、別に韓国だけではありません。「『帝国の慰安婦』は昨年8月に既に出版されたものであり、今の段階で突如販売差し止め請求がなされるのはかなり奇異な感がある。」「司法や社会の常識を利用して、ある特定の議論を封殺しようとするのは、慰安婦問題の解決、糾明を妨げるばかりでなく、その運動の信頼性を自ら大きく傷つけているだけだ」というのは、そのまま、日本にも当てはまることなんじゃないかな、と思います。奇しくも、上記の記事の前日に、同じ産経新聞からこんな記事が出ています。いわれなき誹謗中傷、慰安婦問題に断固反論し日本の名誉守る 稲田朋美行革担当相講演詳報福岡市中央区の西鉄グランドホテルで26日に開かれた九州「正論」懇話会第113回講演会。行政改革担当相として安倍晋三内閣を支える稲田朋美氏が、慰安婦問題や公務員制度改革、クールジャパン戦略などについて語り、「日本を世界中から尊敬される国にしたい」と決意を述べた。(中略)それをきっかけに「百人斬り訴訟」に関わるようになりました。戦時中、中国人の100人斬り競争をやった-という、嘘の記事を基に、2人の日本軍将校が戦後の裁判で処刑されたのです。2人の将校、向井敏明少尉と野田毅少尉の遺族らを原告に、朝日新聞や毎日新聞、本多勝一さんらを相手に、(記事で遺族の名誉を毀損されたことに対する)裁判を起こしました。最高裁で負けましたが、高裁判決文に「2人の将校が日本刀を抜いて競争した事実はとても信用できない」と書いてくれたのは大きなことでした。(以下略)---記事にある「百人斬り訴訟」に、私も少々関わっていたし、稲田大先生(当時はまだ代議士先生じゃなかった)のご尊顔を東京地裁で見たこともありますので、この記事を見たとき、思わず失笑してしまいました。記事には「裁判を起こしました」としかありませんが、訴えの内容は、各書籍の出版、販売、頒布の差し止め・謝罪広告の掲載・損害賠償金の連帯支払でした。しかも、訴訟の対象となった各書籍は、『中国の旅』が1970年代、『南京への道』は1980年代、『南京大虐琴否定論13のウソ』も1999年に発行されており、それを2003年になって提訴している。昨年8月に既に出版されたものを今の段階で突如販売差し止め請求するのが、「かなり奇異な感」だとすると、1970~80年代に出版されたものを2003年の段階で突如出版差し止め請求するのは、どれだけ異常な行為だよ、という話になります。「司法や社会の常識を利用して、ある特定の議論を封殺しようとするのは、問題の解決、糾明を妨げるばかりでなく、その運動の信頼性を自ら大きく傷つけているだけだ」という言葉も、そのまま、百人斬り訴訟や、その後の沖縄ノート裁判(大江健三郎の「沖縄ノート」に対する名誉毀損裁判)に降りかかってきます。これらの裁判の原告側を、産経新聞は大々的に支援したのだから、いったいどの口が、韓国の名誉毀損裁判のことを批判できるんだよ、と思います。他国の裁判を揶揄するなら、自分の国で自分たちが関わった裁判を振り返ってみたらどうかね、という話。ちなみに、百人斬り裁判も沖縄ノート裁判も、原告側の前面敗訴です。稲田朋美は最高裁で負けましたが、高裁判決文に「2人の将校が日本刀を抜いて競争した事実はとても信用できない」と書いてくれたのは大きなことでした。などと書いていますが、実に馬鹿馬鹿しい負け惜しみです。「2人の将校が日本刀を抜いて競争した事実はとても信用できない」などという文章は、高裁判決のどこを探しても存在しません。高裁判決の該当部分の判決文は南京攻略戦当時の戦闘の実態や両少尉の軍隊における任務、1本の日本刀の剛性ないし近代戦争における戦闘武器としての有用性等に照らしても、本件日日記事にある「百人斬り競争」の実体及びその殺傷数について、同記事の内容を信じることはできないのであって、同記事の「百人斬り」の戦闘戦果は甚だ疑わしいものと考えるのが合理的である。しかしながら、その競争の内実が本件日日記事の内容とは異なるものであったとしても、次の諸点に照らせば、両少尉が,南京攻略戦において軍務に服する過程で、当時としては、「百人斬り競争」として新聞報道されることに違和感を持たない競争をした事実自体を否定することはできず、本件日日記事の「百人斬り競争」を新聞記者の創作記事であり、全くの虚偽であると認めることはできないというべきである。というもの。日日新聞の当時の報道のとおりとは信用できないけれど、ほぼそれに近い競争はあっただろう、というのが高裁判決の事実認定です。稲田の言い分は、ガダルカナルの敗北を「転進」などと言い換えた大本営と同じです。ちなみに、法廷で何回か稲田を見かけた印象としては、弁舌は立つ人です。その面の能力は優秀なのだと思います。しかし、弁護士としての実務面の能力はかなり低い。原告側証人が、原告の主張を否定する内容を主張したり、裁判官忌避の申し立てをするタイミングを間違えたり(そのとき出廷していた原告側弁護士は稲田ではなかったけど)、自爆としか思えないような失点をいくつも重ねていた。もっとも、裁判に勝つことなど一切考えず、政治ショーとして支持者にアピールすることだけに徹したとするなら、「自爆」もまたアピールの手段なのかもしれません。そうだとすると、弁護士としての能力が低いのではなく、能力をわざと発揮しなかっただけ、なのかも知れません。どのみち、今は弁護士としての業務なんてやっていないでしょうから、弁護士としての能力より政治家としての能力の方が大事なんでしょうけど。
2014.07.29
コメント(2)
-
なぜ日本軍は餓死したのか
日本軍はなぜ半分も餓死したのかきのうアゴラ読書塾で話したことだが、日本軍は戦争に負けたのではなく、補給の失敗で自滅した。その原因はいまだに十分解明されていないが、これは資源配分の問題と考えると理解できる。これには二つの解法がある。一つは市場経済などによってボトムアップで答を見つける方法、もう一つはトップダウンの計算で解く方法である。~これに対して、1940年代にはこうした最適解を計算する手法が開発され、戦時経済における物流や生産の管理に実際に使われた。こうした手法は、オペレーションズ・リサーチ(OR)と呼ばれた。ORは「作戦研究」という名の示すとおり、もとは戦争において補給を効率的に行なうシステムとして開発された。こうした手法は、戦争のように目的関数がはっきり決まっていて変化しないときには有効だ。ある作戦に、武器と石油と食糧という三つの資源が必要だとしよう。いくら武器がたくさんあっても、石油がなかったら動けないし、食糧がなくなったら兵士が飢え死にしてしまう。こういうときの基本的な考え方は、なるべくバランスよく予算を割り当て、ボトルネックをなくすことだ。かりにすべての予算を武器に割り当てたとすると、石油も食糧もないので戦力はゼロだ。そこで石油と食糧に一単位ずつ予算を配分すると、戦力は一単位ぶん増えるが、武器が余ってしまう。そこで余った武器予算をまた他の資源に割り当てると戦力が増える…というようにシミュレーションを繰り返し、戦力が増えなくなったところでやめると、最適な資源配分が求められる。資源の数が増えると、この計算は非常に複雑になるので、コンピュータが必要だ。米軍は、こういう手法で補給を手厚く行なったが、日本軍は補給を考えないで、ほとんどの予算を武器につぎ込んだため、第二次大戦の戦死者230万人のほぼ半数が餓死という悲惨な結果になった。このように市場経済で解く方法とORで解く方法は、最適解が一つしかない場合には同じで、これを双対性と呼ぶ。しかし答が一つではない場合は、結果は大きく違う。与えられた価格をもとにして個人が消費や生産を決める計算は簡単だが、その集計が全体最適になるのは例外だ。他方、経済全体の需要と供給を集計して最適解を計算することは通常は不可能だが、戦争のように計画主体と目的関数がはっきりしている場合は一発で解ける。日本社会では、すべての問題をボトムアップで(分権的に)解こうとする。これは平時には有効だが、戦時には調整に時間がかかって解が求められない。米軍はORを使って補給の問題をトップダウンで(集権的に)解き、戦死者はわずか10万人だった。ORは軍事機密で、これを経済学に応用したKoopmansはノーベル賞を受賞した。このように戦争をボトムアップでやったことが日本軍の本質的な失敗で、この教訓は現代にも通じる。20世紀の製造業では目的関数が与えられていたので、それを現場主義で解いて集計する日本企業の手法が有効だったが、21世紀の情報産業では目的関数の設定で勝負が決まる。バラバラの部分最適の集計が全体最適になることはまずない。要するに、現代の資本主義は戦争に近づいているのだ。そこで必要なのはコンセンサスではなく命令であり、合理的な(一貫した)目的関数を設定して独裁的に実行するスピードだ。これが戦争の好きなアメリカ人がグローバル資本主義で強い理由である。ーーー例によって池田信夫が、本質的なところから目をそらした原因究明をやって見せています。日本軍の戦死者の大半が、実際にはいわゆる戦死ではなく、餓死(事実上の餓死である戦病死も含めて)であることは、明らかです。その点は池田信夫が言うとおり。いや、実際は餓死者は半分よりもっと多いと思われるけど。で、問題はその理由です。資源の配分を誤ったというのは、現象としてはそのとおりですが、ではなぜ資源の配分を誤ったか。ORとか、ボトムアップとか、本質とは外れたところばかり見ていても、どうしようもない。日本軍は補給を軽視したことは事実ですが、無視したわけではなく、一応は補給の計画を持ってはいました。ただ、それは二つの理由で、容易に破綻してしまったのです。第一に、補給線の防御に、あまり注意を払わなかった。これも、まったく注意を払わなかったわけではないけれど、守りが甘かった。第二に、そもそも想定した補給の所要量が全然少なかった。これは、食糧よりも弾薬の話です。食糧は、体格の差で多少の所要量の差はあっても、兵士一人当たりの食料必要量に5倍も6倍も違いがあったわけはありません。しかし、弾薬は違います。日本軍が必要と想定した必要弾薬量と、米軍のそれでは、それこそ何十倍、何百倍の差があることも珍しくはありませんでした。だから、日本軍砲兵が1発撃つと米軍砲兵から100発お返しがくる、というような事態が生じたのです。相手がソ連軍で、しかも補給線を脅かされたことがないノモンハン事件でさえ、同じような状況がありました。では、なぜ日本軍が必要と想定していた弾薬量が少なかったのか。実に単純な話です。それまではそれで済むような戦争しかしてこなかったからです。日中戦争では、火砲1門あたり毎日何百発も発射するような戦いはしたことがなかったから、その延長線上でしか必要量を考えることができなかったのです。そしてもう一つ、食料に関しては、日中戦争では現地調達(つまり、略奪)で賄ってきたから、太平洋で米軍との戦いでも、同じようにすればよいと考えていたということもあります。しかし、中国大陸とは違って、太平洋の戦場は、日本軍の大軍を養えるほどの農業生産力はなかった。略奪するつもりで、「行けばなんとかなる」と進軍してみたら、そこには住民がいなかったのですから、飢えるのも当然です。要するに、日中戦争とは次元の違う戦いだ、ということに思い至らず、今までの延長線上で考えていたから、破綻をきたしてしまったわけです。ただし、もう一つ忘れてはならないことがあります。そもそも、充分に補給できるだけの弾薬や食糧が、いったい日本のどこにあったのか、という問題です。日本本土でさえ、戦争末期には飢餓一歩手前になっていたではないですか。補給線の防御を軽視したと書きましたが、仮に重視しようと考えたとしても、技術水準(電子装備の立ち遅れから、夜間は潜水艦に対して無力だった)や装備の不足(海上輸送路を守りきれるほどの数の護衛艦艇は建造できなかった)から、おそらくは実現不可能だったのです。太平洋戦争時の、口径8ミリ未満の小銃弾の生産量は、1941年から44年まで、年間4億発程度で推移しています。それに対して、この銃弾を使う銃はどれだけ生産されたか。三八式歩兵銃340万丁、九六式軽機関銃4万丁(以上口径6.5mm)、九九式小銃250万丁、九九式軽機関銃、九二式重機関銃各5万丁前後(以上口径7.7mm)。すべてあわせると600万丁くらいになる。年間4億発というとすごい数に見えるけど、1丁あたりにすれば、年間たった70発。当時の日本陸軍歩兵は、120発の小銃弾を携行することになっていました。機関銃は、当然それよりずっと多い。この携行定数をすべての銃について満たすだけでも2年くらいかかるほどに、弾薬の生産量が少なかったのです。食糧にしろ弾薬にしろ、そして兵器そのものの質と量においてすら、日本軍は米軍とまともに張り合えるほどの生産力を持っていなかったのです。ORだろうが何だろうが、生産力の上限を超える生産はできません。そもそもそんな戦争を始めてしまったこと自体が誤りなのです。
2014.07.28
コメント(6)
-
アルゼンチン対ハゲタカ・ファンド
<アルゼンチン>デフォルト目前…30日期限アルゼンチン政府が再び債務を返済できなくなるデフォルトに陥る恐れが目前に迫っている。全額返済を求める米ファンドと反発するアルゼンチンが今月30日までに和解しなければ、ファンド以外の債権者への利払いができないためだ。しかし、24日のアルゼンチン政府とファンドとの協議は不調に終わるなど進展がみられず、このまま時間切れになる可能性も高まりつつある。◇ファンドとの協議難航「本日、アルゼンチンは来週にデフォルトを選択することを明確にした」。米ヘッジファンド、エリオット・マネジメントが運営するNMLキャピタルは24日の協議後、「アルゼンチンは問題を解決する気がない」と非難する声明を発表した。米連邦地裁は、アルゼンチンに対し、NMLなどのファンドに債務全額の約15億ドルを支払うように命じた。さらに仲介人を指名し、デフォルト回避に向けて支払い方法などをファンドと協議するよう促してきた。24日はアルゼンチン政府と、ファンド側の代表者がニューヨークの仲介人のもとに集合。仲介人はそれぞれの代表者と個別に話をしたうえで、双方に初の直接対話を提案したが、アルゼンチン側が拒否し、実現しなかったという。アルゼンチンは2001年に国債のデフォルトを宣言。9割超の債権者が債務減額に応じたが、米ファンドは格安で債権者から減額前の債権を買い取り、全額の支払いを求めている。これに対し、アルゼンチンはファンドを「ハゲタカ」と非難。裁判所に支払い命令の一時停止を求め、ファンドに対する債務返済を拒んでいる。しかし、このまま30日の期限を越えれば、アルゼンチンは債務減額に応じた債権者への利払いが滞ることになる。アルゼンチン政府は、支払い原資の外貨準備を約280億ドル持っていて、「払う意思があり、デフォルトではない」とデフォルトを宣言しない構え。だが、国債の信用力を判断する格付け会社などは、支払い余力があるにもかかわらず債務が返済できなくなる「テクニカル・デフォルト」とみなす見通しだ。格付け会社の影響力は大きく、国際金融市場では事実上のデフォルトと受け止められそうだ。アルゼンチンは最初のデフォルト以降、国際金融市場で国債を発行しておらず、「再デフォルトによる市場への影響は限定的」との見方が大勢だが、一時的な混乱も予想される。アルゼンチン政府がファンドへの返済を拒んでいるのは、デフォルト後の債務削減で減額に応じなかった債権者を特別扱いしないことを約束する条項を設けたためだ。一部のファンドに債務全額を払えば、すべての債権者に全額を支払う義務が生じる恐れがある。その場合の債務返済額は1200億ドルに上る可能性があり、アルゼンチンの外貨準備を大きく上回って本当に返済不能に陥ることになる。フェルナンデス大統領は「国を危機にさらすような合意はできない」としている。一部の債権者を特別扱いしない条項は今年末で切れるため、米ファンドへの返済を来年以降に先延ばしし、他の債権者への利払いは続けるデフォルト回避案も浮上している。アルゼンチンとファンドは、25日以降も仲介人とともに協議を進める予定で、ぎりぎりの駆け引きが続きそうだ。---今から13年前の2001年12月、私がボリビアに旅行に行っていたちょうどその時、アルゼンチンはデフォルト騒動のただ中にありました。ホテルのテレビで見たCNNスペイン語放送は、ひたすらアルゼンチンの経済破綻を報じ続けていました。問題のそもそもの発端は、1989年から99年までの10年間、アルゼンチン大統領だったカルロス・メネムの経済政策にあります。メネムは、ペロン党(正式名称は正義党、ペロン元大統領が創設し、伝統的に反米民族主義的な傾向をもつ)出身にもかかわらず、反米民族主義を捨てて、親米的な新自由主義経済を採用しました。その一環として、1ドル=1ペソという固定相場制を導入し、安定的な為替レートで外資を呼び込むことに成功します。ただ、1ドル=1ペソというのは、物価水準などの経済実態に基づいて考えれば、異常にペソ高の為替レートでした。私は、メネム政権が絶好調だった1994年に、チリとアルゼンチン、ボリビアに行ったのですが(アルゼンチン滞在は2日間だけでしたが)、隣国チリと比較して、(ドル換算での)あまりの物価の高さに仰天した記憶があります。そんな異常なペソ高政策では輸出産業はやっていけないかと思いきや、実際にはそうでもなかったのです(楽ではなかったでしょうが)。というのは、当時はブラジルやメキシコなどラテンアメリカの主要国が揃って自国通貨の交換レートを設定していたし、アジア諸国も総じて同様の傾向があったからです。赤信号、みんなで渡れば怖くない、ではないですが、競争相手もみんな自国通貨高政策を取っていたので、アルゼンチンだけが不利になることはなかったのです。しかし、1995年メキシコ・ペソ暴落、1997年のアジア通貨危機、1998年にはロシアが危機、1999年にはブラジル危機などによって、各国が軒並み自国通貨高政策を維持できなくなったことで、状況は一変します。アルゼンチンはラテンアメリカの中では経済大国なので、頑張ってペソ高政策を維持できてしまったのですが、その結果、アルゼンチンだけが自国通貨高の政策に固執することになってしまったのです。「赤信号、みんなで渡れば怖くない」のはずが、気がついたらひとりアルゼンチンだけが赤信号の真っ只中に立ち尽くしていたわけです。こうなると、輸出産業は死にます。アルゼンチンは農産物の輸出大国ですから、輸出産業が引っくり返れば、国の経済が引っくり返ります。危機回避のためには、先手を売って1ドル=1ペソの固定相場を放棄すればよかったのですが、これができなかったのです。ペソ高政策で誘導された外資が、ペソの切り下げを許さなかった。また、自動車や住宅のローンや銀行預金にドル建てが多かったため、ペソを切り下げると、ローンが返済できなくなる人が続出したり、銀行の経営に致命的な打撃を与えるからです。要するに、1ドル=1ペソが(実際には12年しか続かなかったのに)永続することを前提とする経済の仕組みが出来上がってしまったために、身動きが取れなくなってしまったのです。結局、アルゼンチンは主体的にペソ高政策を放棄することができないまま、2001年に破滅のときを迎えました。デフォルト、つまり債務不履行です。国として倒産状態に至ったわけです。このときには、メネムは大統領を退いていましたが、この事態を招いた責任者がメネムであったことは明らかです。で、その後大統領に就任したのが、ネストル・キルチネルです。メネムと同じペロン派ですが、メネムは親米右派、キルチネルは反米左派(中道左派くらいのところですが)で、両者は政治的に決定的に相容れない。政治的だけでなく、人間的にも反目しあっていましたが。キルチネルは、IMFの再建手法を拒否して、独自の、反新自由主義的な再建を目指し、そしてそれに成功します。2001年の経済崩壊を底として、アルゼンチン経済は低迷状態を続けることなく、急激に経済成長を遂げていきました。現在の大統領、クリステイーナ・フェルナンデス・デ・キルチネルは、そのキルチネル前大統領の妻でした。キルチネル自身が次の大統領選に立候補すれば再選されたはずですが、何故か自分が立候補はせずに、後継に妻を据えた。「次の次」の大統領選に再び立候補するつもりだったかもしれませんが、そうなる前に本人は心臓発作で亡くなってしまいました。アルゼンチンが、経済破綻以降急激に復活したのは、ひとつには、1ドル=1ペソというペソ高政策が破綻して、ペソの価値が暴落したことによって、輸出産業が息を吹き返したことがありました。これ自体は、別にキルチネルの功績というものではないかもしれません。しかし、もうひとつは、債務の減額を断行したことで、債務の重荷から解き放たれたおかげです。アルゼンチン政府は、債務の7割減額を提示して、9割の債権者はそれに応じています。残りの1割が減額を拒否して、米国で法廷闘争に持ち込み、勝ってしまったことが、今回のデフォルト危機の原因です。引用記事にもありますが、債務減額を拒否した1割の投資家の多くは、もともとアルゼンチン国債を持っていたわけではなく、アルゼンチンの経済破綻のあと、二束三文で国債を買い叩いたヘッジファンドだと言われています。紙切れと化したアルゼンチン国債を二束三文で買い叩いておいて、それを額面どおりに支払えという、まさしく「ハゲタカ・ファンド」の名に恥じぬ厚顔無恥の要求を、米国の裁判所が認めてしまったことが今回の騒動の原因です。今のアルゼンチンは2001年のアルゼンチンとは違うので、物理的には、今回裁判に勝った連中に債務を返済するだけの外貨準備はあります。再建削減を拒否した1割の投資家がみんな全額返済を求めたとしても、それを支払えるだけの外貨準備もあるのです。ただ、払えるとはいえ、その額は150億ドルにもなり、アルゼンチンの外貨準備(280億ドル)の半分以上にも及びます。しかも、このところアルゼンチンの外貨準備高は急減しつつある。支払い不能ではないけれど、アルゼンチンにとってとてつもなく大きな負担であることは明らかです。更に、減額拒否した連中、それも、前述のとおりデフォルト以降に、元の債権者から二束三文で国債を買い集めたようなハゲタカファンドの連中に全額返済を認めてしまったら、モラルハザードに陥ります。7割減額に応じた大半の債権者に対して、説明がつかないですから。拒否すれば全額返してもらえる、なんてことになれば、7割減額に応じた債権者だって「ならば俺たちも」ということになります。減額に応じた債権者の分も含めたアルゼンチンの債務は1200億ドルに達するそうで、これは明らかに、どうやったってアルゼンチンには支払い不能な額です。どういう解決策に落ち着くかは分かりませんが、フェルナンデス大統領が、ハゲタカファンドの要求に全面屈服することはないでしょう。もともと、2001年のデフォルト以降、アルゼンチンは新規国債を国外で発行することはできない状態が、現在に至るまで続いており、近いうちに国債が発行できる見通しもありませんでした。だから、今更国債の格付がどれだけ引き下げられようが、それほど致命的な影響はありません。逆にいうと、バラマキだ何だと競争原理主義者たちに批判されながらも、キルチネル夫妻は国債の新規発行に一切頼ることができない状態で、経済復活と社会政策の充実に成功してきたのだから、これはなかなかにすごいことではあります。年金基金の国有化で財源を確保するなどの手も使ってのことではありますけどね。
2014.07.27
コメント(0)
-

南アルプス・聖岳の写真
聖岳のリバーサルフィルムの写真ができましたので、アップします。最終日以外は天気が今ひとつだったので、風景写真はあまり良いものがありませんが、花の写真はそれなりにいろいろ撮れました。行程は、7月18日聖沢から聖平まで(8時過ぎに出発、午後2時過ぎ到着)7月19日聖平から聖岳まで往復して、聖沢に下山(聖平5時発、山頂7時着、下山開始の時間は記録忘れましたが、聖平10時着、聖沢午後4時頃着)7月20日は椹島ロッジに泊まり、そのまま帰宅。聖平に登る途中で撮影しました。位置的にいって、笊ヶ岳(2629m)だと思われます。白峰南嶺と呼ばれる、北岳・間ノ岳・農鳥岳から南に下ってきた稜線の、南端の山です。いつかは登りたい。アプローチが長く、山小屋がないのでテント必須です。ハクサンシャクナゲ。亜高山帯に多いシャクナゲの仲間です。これは、ちょうど咲き始め頃。この写真は聖平の手前、海抜2000m前後のところで撮ったように記憶しています。聖平です。先の記事にも書いたように、かつては高山植物(厳密には、まだ亜高山帯ですが)のお花畑で、ニッコウキスゲなどが咲き乱れていたそうですが、鹿の食害で花はほとんどなくなってしまいました。視界のある気持ちのよい草原であることは変わらないのですが。聖平から、目指す聖岳が見えました。登るにつれて、富士山が見えてきました。富士山をもう1枚。小聖岳(2662m)付近から聖岳(前聖)の堂々たる山容です。山頂の少し手前から、稜線を振り返ります。上河内岳、茶臼岳、易老岳、そして日本最南端(世界でも最南端)のハイマツ自生地である光岳へと続きます。ただ、光岳は写真から切れてしまったような・・・・・・。撮影したのは、7時少し前、山頂まであと10分か15分くらいの場所で、このときはまだこれだけ視界があったのです。しかし、十数分後に山頂についた時は、もう周囲はガスの中。特に北側に続く赤石岳、荒川三山がまったく見えなかったのは残念です。聖平を5時に出て、山頂着が7時過ぎでした。あと30分早く出ていれば、というところですが、これは仕方がない。それにしても、この日は3連休の初日です。もちろん、朝にこの場所にいるためには、聖平に前泊しなければ不可能なのですが、それを考え合わせても、私が聖平を出てから聖平に戻ってくるまでの間に通りかかった登山者は、十数人というところでした。南アルプス北部や北アルプスに比べると、圧倒的に登山者が少ない。山頂は視界がないので、奥聖に向かいました。前聖と奥聖と言うと、奥聖の方が高そうに聞こえますが、前聖のほうが高く、奥聖はわずかに3000mを切ります(2978m)。なので、奥聖まで向かう登山者は、そう多くはない。このときは、すれ違った登山者は1人だけでした。奥聖はチングルマのお花畑がきれいだ、という話だったのですが、まだ全然咲いてなかった。しかし、キバナシャクナゲが満開だったので、満足です。キバナシャクナゲは、先に紹介したハクサンシャクナゲより更に高い、高山帯を中心に分布するシャクナゲです。ミヤマシオガマ。派手な高山植物です。ヨツバシオガマ。上記のミヤマシオガマに近い仲間ですが、こちらの方が山ではよく見かけるような気がします。写真を撮ったのも、初めてではありません。シナノキンバイ。場所によっては、絨毯のように一面に密生して、派手なお花畑を造ることがありますが、このときは、わずかに生えていただけでした。聖平まで引き返してきて、当初予定では上河内岳を越えて茶臼小屋まで行く予定でしたが、テントの荷物を担いで更に標高差600m近くを登る気力がなかったこと、天気が悪く、雷まで鳴り出したため(高山帯の稜線上で雷に襲われたら、最悪、どころか命に関わる)、椹島まで降りることにしたのは、以前の記事に書いたとおりです。クルマユリ。これは、下山時、聖平を通り過ぎて、それより少し下の樹林帯で撮影しました。この少し後で、足を踏み外して左ひざ内側を強打してしまったのです。派手なあざになってしまいました。登りは聖沢から聖平まで、テントの荷物を担いで6時間ちょっと(ほぼ登山地図のコースタイムどおり)で登り、聖平から山頂までは、最低限の荷物なので、コースタイムより大幅に早い2時間で登りましたが、聖平から聖沢への下山は、膝強打の影響と疲労蓄積のせいか、なんと登りとほとんど同じ、約6時間を要してしまいました。で、その日は疲労困憊して(激しい雷雨のせいもありますが)椹島ロッジに2食付で宿泊してしまいました。そうしたら、翌日早朝は快晴になったのです。もっとも、晴れたのは朝方だけで、その後は曇り→雷雨になったようですが。おかげで、椹島から畑薙ダムに下るバスの中から、初めて素晴らしい天気の山の写真を撮ることができました。赤石岳だそうです。聖岳だそうです。上で見るのと、だいぶ形が違います。天気が今ひとつだったとはいえ、まずまず満足すべき山登りでした。でも、南アルプス南部、また行きたいです。
2014.07.25
コメント(0)
-
大いなる勘違い(外国人と生活保護)
「外国人に生活保護受給権なし」最高裁が初判断永住資格を持つ外国人に生活保護法上の受給権があるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「生活保護法の適用対象は日本国民に限られ、外国人は含まれない」との初判断を示し、受給権を認めた2審の判断を取り消す判決を言い渡した。生活保護申請を却下した大分市の処分取り消しを求めた中国籍の女性(82)の敗訴が確定した。各自治体は裁量で、永住資格を持つ外国人に生活保護に準じた措置を取っており、判決の影響は事実上ないとみられる。原告の女性は出生時から日本で生活しており、2008年12月、大分市に生活保護を申請。十分な預金があるとして却下されたため、取り消しを求めて提訴した。1審・大分地裁は訴えを退けたが、2審・福岡高裁は「永住資格を持つなど、日本人と同様の生活を送る外国人には生活保護を受ける法的地位がある」と認め、却下処分を違法とした。この日の判決は「生活保護法を外国人に適用する根拠はない。行政措置によって、事実上の保護対象になり得るにとどまる」と判断した。---大筋において、「そんなところだろうな」というのが感想です。この判決の趣旨には、少なくとも反対ではありません。個人的には、日本生まれの外国人(国籍が日本ではない、というだけで実際は日本人と変わらない)に対しては日本人と同様の取扱いをすべきと思う一方、来日外国人、特に成人して以降自分の意思で来日した外国人(日本人世帯の一員である場合を除き)の生活保護には、どうしても違和感を感じざるを得ないのです。裁判になった問題の女性は、日本生まれで日本語が母語で国籍だけが中国籍、とのことですから、こういう人が生活保護を受けることに関しては、違和感は感じません。もっとも、それ以前の問題として、引用記事によれば、原告の女性が提訴に至ったのは「2008年12月、大分市に生活保護を申請。十分な預金があるとして却下された」ことが原因だそうです。具体的な預金額は報じられていませんが、定めれた基準以上のお金を持っていれば生活保護は受けられないのは、外国人も日本人も同じことです。別報道によれば、この女性は実際にはその後生活保護の受給が認められているそうです。却下の原因となった預金を使い果たしたのでしょう。この経緯を見れば、原告の女性は、外国人だから生活保護の申請を却下されたわけではないことが分かります。彼女が日本人だったとしても、同じ結果にしかなっていないはずです。(具体的な預金額が分からないと確実にはいえませんけど)しかし、判決そのものの是非はともかくとして、この判決の趣旨について、ものすごく勘違いしている意見が、ネット上には満ち溢れているようです。すなわち、「外国人は生活保護を受けられなくなった」「外国人の生活保護は廃止になる」等々です。判決を伝えるマスコミの報道をちゃんと読めば、そのような理解はまったく間違いだ、ということはすぐ分かります。上記の引用記事にも各自治体は裁量で、永住資格を持つ外国人に生活保護に準じた措置を取っており、判決の影響は事実上ないとみられる。って書いてあるじゃないですか。引用されている判決要旨にも行政措置によって、事実上の保護対象になり得るにとどまると書かれています。生活保護を受給する権利はないが、行政の裁量によって生活保護に準じた取扱い(生活保護の準用)はできる、ということです。簡単に言えば、今までの運用を追認した、ということに過ぎず、この判決は画期的な内容でも何でもないのです。どこにも誤読する余地などないように思えるのですが、なぜ、かくも多くの人たちが「外国人の生活保護は廃止」などと誤読してしまうのか、大いに謎です。報道の見出しだけを見て本文を見なかったのかも知れませんね。聞いたところによると、早速、「外国人の生活保護は廃止にしろ」という電話やら何やらがジャンジャンかかってきている福祉事務所もあるらしいですけどね。権利として認められていなくても、実際には可能である、なんてことは、世の中にいくらでもある話です。例えば、憲法第26条にはすべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。という規定があります。「すべて国民は」教育を受ける権利があり、子女に教育を受けさせる義務がある、のですから、外国人には教育を受ける権利も受けさせる義務も規定されていません。でも、日本の公立小中学校には、外国籍の児童生徒は大勢いるじゃないですか。外国人の子どもには教育を受ける権利は保障されていないけれど、「権利がないから日本の学校に通わせない」なんてことは行われていません。また、外国人には、日本に入国する権利は保障されていません。これは、憲法に明文の規定はありませんが、常識的に言って外国人に対して入国の自由を保障している国なんてないし、日本でも判例はそうなっています。しかし、だからと言って日本は鎖国をしているわけではなく、現に多くの外国人が日本にやってきています。それとも、外国人の子どもは日本の学校から追い出せ、外国人を一切入国させるな、ということなのでしょうか。ネトウヨはそんなことを言い出しかねない感じもしますが、現実にそんなことが不可能であることは言うまでもありません。
2014.07.24
コメント(4)
-
ああ、「歴史戦」だと
慰安婦ツアー 7月23日《そこへどやどやと、長ぐつをはいたあくまが、はいってきました》。「あくまは長ぐつをはいてきた」という物語である。悪魔にたとえられた旧日本軍の将兵が、中国の村民を広場に集め、皆殺しにする場面に続く。▼かつて、大分県の小学生の冬休み用教材に掲載されていた。県教職員組合が編集したものだ。たまたま自宅で目にした父親は、あまりに偏った内容に衝撃を受けたという。▼平成20年に発覚した、大分県の教員の採用をめぐる汚職事件では、県教育委員会と教職員組合との長年にわたる癒着体質が指摘された。外部のチェックがきかない、特異な組織のありようを、当時のコラムで、秘密結社になぞらえたものだ。▼その秘密結社が、今度は旅行業に乗り出した。県内の中学生と保護者を対象に、新聞広告で韓国旅行を募集していた。旅行業法違反だが、問題の本質はむしろ、旅行の内容にある。訪問先のひとつ、「日本軍『慰安婦』歴史館」は、元慰安婦女性が共同生活を送る「ナヌムの家」にある展示場だ。韓国通の同僚記者によると、ボランティアの説明を含めたあらゆる展示が、慰安婦=性奴隷であることを強調している。▼「西大門刑務所跡」では、日本による弾圧の歴史を学ぶことになっている。韓国と日本の左派勢力の言い分そのままの、日本の“悪行”をたっぷり見せつけられるわけだ。このツアーが格安なのは、県教組が助成金を出しているからだという。金の本当の出どころが気になるところだ。▼日本の観光客が最近激減している韓国にとって、渡りに船の企画であろう。しかも、子供たちに反日思想をたっぷり刷り込むことができる。慰安婦問題を中心にすえた、歴史戦にますます精が出ることだろう。---「旅行業法違反」だそうですが、実際のツアーの実務自体は、登録された旅行会社が行っているわけで、大きな問題ではないでしょう。いみじくも、引用記事にあるように、「問題の本質はむしろ、旅行の内容にある。」というところが、産経の言いたいところなのでしょう。「歴史戦」という言葉が産経は好きで好きで仕方がないようですが、まあ実に、戦争が好きなんですねえ。「歴史戦にますます精が出ることだろう。」とありますが、精が出ているのは自分自身だろ、と言いたくなります。自分にとって気に入らない歴史観を、「戦争」で排撃して、自分好みの歴史観で国内を統一しよう、ということなのでしょう。世が世なら、私など本当に粛清されちゃうかもね。いや、冗談抜きに、最近本当に「世が世」になりそうな気配もありますが。産経にとって不愉快なツアーだということは分かりますけどね、だからと言って任意で一般公募するツアーの内容にイチャモンをつけてもはじまりません。お前らがそれに反発するなら、対抗して「愛国ツアー」でも開催してみろよ、ということに尽きます。しかし、産経はそういう道を選ばずに、反戦ツアーの実施を妨害する道を選んだわけです。言論の自由も思想信条の自由もない、というわけです。まあ、産経がそういう体質の新聞であることは、今にはじまった話ではないですけどね。
2014.07.23
コメント(2)
-
この短絡ぶりは・・・・・・
<岡山女児保護>容疑者「好み通りに育て結婚するつもり…」岡山県倉敷市の小学5年の女児(11)が行方不明になり、岡山市北区の無職容疑者(49)が監禁容疑で逮捕された事件で、容疑者が県警の調べに「4月に通学路で偶然見つけ、気に入った。好み通りに育て、結婚するつもりだった」と供述していることが21日、捜査関係者への取材で分かった。一方、女児は「無理やり車に乗せられた。怖かった」と話していることも判明。県警は容姿を気に入った容疑者が一方的な願望で事件を起こしたとみて、未成年者略取容疑で再逮捕する方針を固めた。女児は今月14日夕、学校から帰宅途中に行方不明になった。県警によると、容疑者は自分の車の脇に女児といる姿を同級生に目撃されている。この際、容疑者は女児にナイフを見せて「殺すぞ」と脅し、車に連れ込んでいたという。車は約8キロ離れた藤原容疑者宅へ直行し、女児は1階洋間に5日間、監禁された。容疑者は外出の度に外から鍵をかけていたという。県警は、女児が強く脅迫されたことで、抵抗できない心理状態になっていたとみている。県警は21日、容疑者を岡山地検に送検した。---命にも健康状態にも別条がなく保護されたようで、不幸中の幸いでした。49歳で11歳の子どもを捕まえてきて、「好み通りに育て、結婚するつもりだった」とは、おぞましさしか感じません。頭の中で何を妄想するのも個人の自由ですが、妄想を具体化しようと犯罪行為に走る短絡ぶりは、言語道断というものです。それにしても、49歳といういい大人が、何をやっているのか。そもそも、この犯人、無職と報じられています。車は持っているし、自宅のリフォームに1000万円かけたという報道もあるので、金は持っているのでしょうが、それにしても49歳で無職という状況で、11歳の子どもを育てて結婚するに当たって、いったいどういう人生設計を考えていたのでしょうか。いや、そんなことは考えていなかったのでしょう。ひとことで言えば、「頭がおかしい」ということです。頭がおかしいと言っても、ある種人格障害のようなものでしょうから、心神耗弱とか心神喪失が認められるとは思えません。さすがに有罪、実刑は確実と思われますが、どのくらいの量刑なのでしょう。奇しくも、私もこの被害者と同じ学年の子どもをもつ親の立場ですから、他人事とは思えません。「一日でも長く、刑務所にブチ込まれ続けてほしい」という感情しか、抱くことができません。逮捕監禁罪の量刑は、懲役3年から7年なんですね。今回の例では殺したり傷つけたりはしていないので、それ以上の罪名はつかないのでしょう。だとしたら、ぜひ最高刑の懲役7年を。最低限、執行猶予のつかない実刑を、と願うばかりです。
2014.07.22
コメント(6)
-
ウクライナ情勢の破綻
マレーシア航空機がウクライナ東部で墜落マレーシア航空のアムステルダム発クアラルンプール行きボーイング777型機が17日、ウクライナ東部で墜落した。同機には乗員乗客298人が乗っていた。ウクライナ政府は「テロリスト」が同機を撃墜したと非難している。米高官はCNNに対して、米政府も同機が撃墜されたとの結論に至ったと語った。ウクライナの政府高官によると、同機はドネツク州トレーズ近郊に墜落した。高度約1万メートルを飛行中だったという。現地のフリーランスの米国人記者、ノア・スナイダー氏は目撃者の話として、飛行機は上空で爆発したような様子で、機体や乗客などあらゆるものが降ってきたと述べた。ウクライナのポロシェンコ大統領は、墜落は「テロリストの行為」が原因だと非難。同国内相も交流サイトのフェイスブックで、テロリストが地対空ミサイルを同機に向けて発射したと述べた。---ちょうど私が聖岳に登っている間に起こった墜落事故、いや、事件です。ミサイルによって撃墜されたことがほぼ確実で、使われたのはロシア製の「ブク」地対空ミサイル(SA11)と言われているようです。このミサイルは、ロシア製ですが、ロシア軍、ウクライナ軍、そしてウクライナの親ロシア派武装組織の3者が保有しています。しかし、撃墜された現場が親露派武装組織の支配地域であること、その他の状況証拠から、犯人は親露派武装組織であることが、ほぼ確実と見られているようです。一部報道によると、親露派の武装集団の一員が、墜落直後に「ウクライナ軍の輸送機を撃墜した」とツィートして、墜落したのがマレーシア航空機と分かると、慌てて削除という顛末もあったようです。最悪の事態、と言わなければなりません。以前にウクライナ問題については一度記事を書いたことがあります。ウクライナ、絶対善も絶対悪もないが・・・・・・親欧米派、親露派ともに、「どっちもどっち」としか言いようのない状況なのですが、それにしても民間航空機を撃墜する行為は、いかなる意味でもまったく弁護の余地がない。それが親露派の犯行だとすれば、結果として彼らの国際的な立場(後ろ盾であるロシアも巻き込んで)を決定的に悪化させる愚行です。「ロシアの関与」などという報道もあるようですが、いくら何でも撃墜という行為にロシアが直接関与したはずがなく、報道を読んでも、親ロシア派への武器供与に関与した、という意味であるようです。報道によれば、事故の調査団を親ロシア派武装集団が妨害とか、フライトレコーダーとボイスレコーダーを持ち去ったらしいとか、挙句の果てに乗客の遺品であるカード類の不正使用を試みた輩がいるとか、いろいろと信じ難い出来事が起こっているようです。泥酔した兵士が調査団を威嚇、という報道もありました。内乱は、かくも人の心を荒廃させるものなのか、ということを実感させられます。で、それはそれとして、です。ウクライナの親ロシア派は、この撃墜事件の数日前にも、ウクライナ軍の輸送機を地対空ミサイルで撃墜しています。その時点では、ウクライナ側は「ミサイルはロシアから発射された(かも)」と主張していたのですが、結果として、今回の事件によって「ウクライナの親露派武装勢力は地対空ミサイルを持っていないから、撃墜したのはロシア(かも)」という疑惑も消失したことになります。ただ、いずれにしても、現地の上空ではすでに多くの飛行機が撃墜されていたことは事実であり、すでにそのような状況になっている空域を漫然と飛行していたマレーシア航空、あるいは、飛行に関して注意喚起を行わなかった航空管制当局にも、問題は多々あったと言わざるを得ないでしょう。マレーシア航空は、昨年までは一度の墜落事故を起こしたことのない、世界でもっとも安全な航空会社の一つだったのに、今年に入って、3月に370便行方不明事故(いまだに残骸はまったく見つかっていない)と、今回の17便撃墜、7ヶ月で2度の重大事故で、あわせて500人以上の死者行方不明者を出してしまった。安全性への信頼は、確立するのに何年も、何十年もかかるけど、ぶち壊すのは一瞬でできてしまう。恐ろしいことです。私は、マレーシア航空には乗ったことがありませんが、今後も多分乗らないでしょうね。他に、乗りたくない航空会社には台湾の中華航空があります。日本に乗り入れていない航空会社も含めると、北朝鮮の高麗航空なんかも、ご遠慮したいところです。
2014.07.21
コメント(2)
-

南アルプス・聖岳
また、山に登ってきました。木曜夜に東京を出て、3日間の日程で、南アルプス最南端の3000m峰、聖岳に登ってきました。登山口です。南アルプス南部はかなり交通の便が悪いので、登山者はあまり多くはありません。ここの標高が1140mです。天気はあまり良くなく、どんよりした曇り空のした、樹林帯をひたすら登ります。荷物は15kgくらい。(登りは16~17kg、食料と水を消費した下りでは15kgを切っていたかも)でも、ほぼコースタイムどおりくらいのスピードで、どんどん登ります。途中、2箇所つり橋があります。これは上のほうのつり橋。ここは、それほど谷底は深くありません。昭文社の登山地図には「岩頭滝見台」とあります。現地にそのような表示はないのですが、これがその場所だということは一発で分かります。写真では分かりにくいですが、垂直、ひょっとしたらオーバーハングの断崖絶壁で、下がない。怖いので、あまり縁に近寄らないで写真を撮りました。やっとたどり着いた聖平、海抜2250mくらい。この日の宿泊場所です。朝8時頃登山口を出発して、2時過ぎに着いたので、6時間ちょっとかかったわけです。山小屋では、何故か登山者に寒天フルーツが無料でふるまわれていました。疲れ果てた体には、この世のものとは思えないくらい、すごく美味かった。聖平の草原。かつては高山植物お花畑だったようですが、シカの食害で花はほとんど見られなくなってしまったようです。聖平付近より、上河内岳を望む。当初の予定では、聖岳に続いてこの山も登る予定でしたが、結局は登りませんでした。目指す聖岳、3013mです。天気は今ひとつですが、この時間(19日の朝6時頃)は、まだ視界がありました。この日は3連休の初日でしたが、聖平から山頂まで、この時間帯の登山者は20人に届くかどうか、というところでした。さすがに、南アルプス南部は、北アルプスや南アルプス北部に比べると、登山者がはるかに少ない。富士山も見えました。この日は、大きな荷物は聖平に置いて、最小限の荷物なので、前日よりは速いペースで登りました。5時に聖平を出て、山頂に着いたのが7時過ぎ。しかし、そのときには、もう周辺はガスの中。あと10分早ければ・・・・・・。まあ、言っても仕方がないですが。聖岳(前聖)から20分ほどのところに奥聖岳(2978m)があって、この近辺はチングルマのお花畑がすごいらしい、と聞いていたので、行ってみました。視界は、このとおりの状態です。しかも、チングルマは咲いていませんでした。まだ花期に少し早かったのでしょうか。(さすがに、この高さまではシカは上がってこない、と思うので)しかし、その代わり・・・・・・キバナシャクナゲがたくさん咲いていました。これも、なかなかきれいな花です。そのほかにも、いろいろな花が咲いていたのですが、さすがに小さな花はiPadのレンズではまともに撮影できないので、花の写真はまた後日。海抜2200mあまりの聖平から、3013mの聖岳に往復して、当初の予定では、上河内岳を越えて、茶臼岳まで行く予定でした。しかし、聖岳の往復だけでも、荷物は最小限とは言え、標高差750mくらいを登って降りている。更に15kgの荷物を担いで、2803mの上河内岳まで標高差550mを登って、2500mあまりの茶臼岳まで降る・・・・・・、ちょっと無理かな、と思ってしまいました。ちょうどそのタイミングで、雷がゴロゴロいい始めるに至り、上河内岳は中止(森林限界上の稜線で雷に襲われたりしたら、逃げるところがない)して、聖沢登山口まで下山することにしました。しかし、これが長かった。実は、聖平から1時間くらい下ったところで、転倒して膝の内側をしたたかに石にぶつけてしまったのです。あまりの痛さに、5分間くらいはただ棒立ち。しかし、そこはまだ海抜2000m前後の高さです。後900mほどくだらなければなりません。しかも、結構な急斜面で、さらに雨。最悪。でも歩かなければ降りられないので、とにかく歩いた。背中の15kgの荷物が重い。しかし、30分ほど歩くと、痛みはほぼなくなり、まあ、問題なく歩けました。ただ、雨で濡れた急斜面、という現実だけは、変えようがありません。2箇所のつり橋のうち、登山口に近いほうです。写真で分かるように、ここは川まで結構な高さがある。行きはよいよい帰りは怖い。登りのときは気にもせずに通り過ぎたけど、下りのときは雨だし、膝は痛めているし、ちょっと嫌な感じでした。結局、2250mの聖平から3013mの聖岳まで往復して、さらに15kgの荷物を担いで1140mの登山口まで一気に下山。さすがに体力の限界でした。もう、テントを張る気力もなく、自炊の気力すらなく、椹島ロッジで2食付きの宿に泊まってしまいました。夜、膝の状態を見たら、派手な青あざ。しかし、その痛みよりは筋肉痛の痛みのほうが大きかったような。で、今朝は快晴なのです。くそー、今日も悪天候だというので下山したけど、こんな天気と分かっていたら、聖平にもう1泊滞留しても良かったな、と一瞬思ったのですが、しかし快晴は早朝の短い時間だけで、すぐに雲が湧き始め、天気予報も悪天候の予想だったので、やはり下山して正解だったようです。今ひとつの天候とはいえ、聖岳に登る間はまあまあの視界が保たれていたので、そんなに悪くはない山登りでした。帰路は、聖平でであって、さわらじまでも再会した方に、畑薙ダムから新富士まで車で送っていただきました。ありがとうございました。そのおかげで、当初予定よりずっと速く帰宅しました。何にしても、南アルプスで最後に残っていた未踏の3000m峰が聖岳でした。初めて登った3000m峰が1992年の仙丈岳だったので、22年かかって、やっと全部登ったわけです。残る未踏の3000m峰は、北アルプス(と乗鞍岳)だけになったのですが、残念ながら3000m峰の完全制覇は難しいかな。乗鞍岳・大喰岳・中岳・南岳・前穂高岳の5座は、多分登れる。しかし、最後の一つ、ジャンダルムだけは、命がけでないと登れない。まあ、ジャンダルムは奥穂高岳の支峰なので、一般的には独立した3000m峰の一つとはみなされていないけど。
2014.07.20
コメント(0)
-
超巨大噴火
川内原発:火山対策、予知頼みの無謀 専門家警告原子力規制委員会による九州電力川内原発1、2号機の適合性審査が、大詰めを迎えている。安倍政権は「再稼働1号」と期待するが、周辺は巨大噴火が繰り返されてきた地域だ。このまま通して大丈夫なのか。他にも同様のリスクを抱える原発がある。東大地震研究所火山噴火予知研究センターの中田節也教授(火山岩石学)に聞いた。規制委が川内原発の審査を優先したのは、九電による地震や津波の想定を「妥当」と評価したからだ。火山については「稼働期間中に巨大噴火が起こる可能性は十分低い」という九電の説明を、大筋で了承した。だが、川内原発のある南九州は、巨大噴火による陥没地形「カルデラ」の集中帯だ。「カルデラ噴火は日本では1万年から数万年に1回起きており、同じ場所で繰り返すのが特徴です。姶良カルデラは前の噴火から約3万年、阿多カルデラも約10万年が経過しており、両カルデラのある錦江湾の地下にマグマがたまっているというのは火山学者の常識。そろそろ何かの兆候があっても不思議はありません」。中田教授はそう警告する。昨年7月に施行された新規制基準では、原発の半径160キロ以内にある火山の火砕流や火山灰が到達する可能性を調べ、対応できないと判断されれば「立地は不適」として廃炉になる。こうした火山リスクは、福島第1原発事故の前にはほとんど議論されなかった。その理由を中田教授は「近年の日本の火山は異常に静かだから」と言う。(中略)もし今、カルデラ噴火が起きたらどうなるのか。「軽石や火山灰が火山ガスと一緒に火山の斜面から流れ下る火砕流に巻き込まれれば、原子炉建屋は破壊されます。炉自体の破壊は免れても、火砕流内の温度は推定400度以上と高熱ですから炉内の冷却水は蒸発してしまい、暴走して結局は爆発する。いずれにしろ大量の放射性物質が大気中に放出されるのは避けられないでしょう。実際、川内原発と玄海原発の近くでは火砕流堆積(たいせき)物が見つかっています」と中田教授。姶良カルデラ噴火を上回る規模だったとされる阿蘇カルデラ噴火(約9万年前)の火砕流は、四国西端の伊方原発がある場所近くまで到達したと考えられているのだ。洞爺カルデラに近い北海道・泊原発などにも同じリスクがある。九電は当初、過去の巨大噴火で川内原発に火砕流は到達していないとしていたが、3月の審査会合で約3万年前の姶良カルデラ噴火による火砕流が川内原発に到達していた可能性を初めて認めた。火砕流が到達しなかったとしても、火山灰のリスクがある。九電は桜島の大噴火で火山灰が敷地内に最大15センチ積もると想定。電源や食料を確保するほか、換気設備や発電機のフィルターは交換、除灰で対応するとしている。「施設から火山灰を取り除く対策は工学的には正しい。しかし火山灰が数センチ積もれば車が動かなくなります。灰が降り積もる中で、除灰する人の確保や物資の運搬をどうするのか」昨年2月、週刊誌に中田教授を含む火山学者らが巨大噴火を警告する記事が掲載された。その直後、中田教授は規制委の事務局である原子力規制庁に呼ばれた。「私は『GPSで地殻変動などを観測していれば噴火の前兆はつかめる。ただ、噴火がいつ来るのか、どの程度の規模になるかは分からない』と説明しました。しかし、規制庁は『前兆はつかめる』という点に救いを見いだしたのでしょう。いくら時期も規模も分からないと繰り返しても『モニタリングさえすれば大丈夫』との姿勢を崩さなかった」九電は巨大噴火の前兆を把握した場合、社外の専門家を含めて本当に噴火するのかを検討し、原子炉を止めて核燃料を別の場所に運び出すとの方針を打ち出した。規制委は「搬出先や搬出方法は電力会社が決める」との立場を取っている。米原発メーカーで原発技術者を18年間務めた佐藤暁さんは「稼働中の原子炉から取り出した使用済み核燃料を搬出する前に、まず原子炉建屋内の冷却プールで5年以上貯蔵しなければならない。さらに搬出作業にも輸送用容器の手配などが必要で、とても数カ月では完了しない。搬出中に噴火が起これば貯蔵中よりも危険。噴火が迫ってからやるべきことではない」。中田教授が「安全に核燃料を運搬するために数年前に噴火の予兆を把握することなど無理だし、保管場所も決まっていない。詰めるべき点はたくさんある」と批判するように、机上の空論なのだ。(以下略)---何度か紹介したことがありますが、川内原発付近を舞台にして超巨大噴火を描いた「死地日本」というパニック小説があります(石黒曜著)。小説ですが、科学的な事実に忠実に描かれているため、火山学者などから絶賛を浴びています。記事中に「近年の日本の火山は異常に静かだから」という表現がありますが、「そんなバカな」と思う向きもあるかもしれません。親燃岳の噴火があったではないか、桜島はいつも噴火しているではないか、雲仙普賢岳の噴火もあったではないか、と。しかし、それらの噴火と、超巨大噴火は、桁がいくつも違うのです。2011年の新燃岳噴火の噴出量は2000万立方メートル、9万年前の阿蘇山噴火は6000億立方メートルですから、3万倍もの違いがあります。地震に関しては、なんだかんだと言って、人類は多くの科学データを蓄積しつつあります。日本でいえば、過去100年くらいは地震計の測定データがある。この間、M9クラスの超巨大地震も、東日本大震災をはじめとして、何回か経験しています。ところが、超巨大噴火に関しては、人類は一度としてその噴火の過程についての科学的なデータを手にしたことはありません。超巨大地震に比べて、はるかに発生頻度が低いからです。噴出物の総量が1000億立方メートル(100立方キロ)を超えるような噴火を、便宜的に超巨大噴火と呼びますが、世界的に見ると1815年にインドネシアのスンバワ島で起きたタンボラ山の噴火(約150立方キロの噴出物があった)が最後です。1812年から火山活動が始まり、1815年4月10~12日の大爆発音は1,750キロメートル先まで聞こえ、500キロメートル離れたマドゥラ島では火山灰のため3日間暗闇が続いた。高さ3,900メートルあった山頂は2,851メートルに減じ、面積約30km²、深さ1,300mの火口が生じた。この大噴火による噴出物の総量は150km³におよび、半径約1,000キロメートルの範囲に火山灰が降り注いだ。地球規模で気象に影響を与えた。 というのがWikipediaの記述です。どれだけ凄まじい噴火か分かろうというものです。しかし、この噴火だって、その過程が科学的に記録されているわけではありません。何年か前から前兆現象があったことは分かっているけれど、その具体的なデータがあるわけではないのです。これだけの規模の噴火にあたっては、引用記事にあるように、その前兆は絶対つかめるはずです。つかめないわけがない。それは確かなのですが、その兆候が噴火のどのくらい前から生じるのか、どの程度の規模の兆候なのか、ということは、見当がつきません。だって、そんな規模の噴火は観測史上一度も起こっていないんだから、分かるわけがない。仮に、数日前に「とてつもない規模の噴火になりそうだ」と分かったとしても、燃料棒の取り出しはとても間に合わないでしょう。私の想像では、今までにない規模の噴火が起こりそうな兆候が見つかったとき、その深刻度を巡って揉めに揉めて、結局運転停止、燃料棒撤去という決断ができないままに破局のときを迎える、という事態が、一番可能性が高そうに思えます。観測史上に記録がない=起こらない、ということなら良いのですが、残念ながらそうは行かない。観測史上に記録がなくても、超巨大噴火は確実に起こります。日本の場合は、7300年前に鬼界カルデラ(鹿児島南方の海上)が噴火したのが、超巨大噴火の最後の例です。火砕流は海を越えるので、このときの噴火による火砕流は九州南部に押し寄せ、これによって南九州の縄文人はいったん絶滅したと言われます。確かに、超巨大噴火の発生頻度は、1万年に1度以下なので、地震よりはるかにまれだし、30年かそこらの原発の稼動期間中にそんな噴火に遭遇する可能性はかなり低いことは事実です。でも、1箇所ではそうだとしても、川内原発に被害を及ぼす可能性のあるカルデラは、何箇所もある。他の原発でも同様です。しかも、仮に今後も永続的に原発を維持するとなると、30年後に川内原発が廃炉になったとしても、結局同じ場所に新しい原発を建設する、ということになりそうです。そういうことを続けていけば、いつかは超巨大噴火に行き当たることになりそうです。もっとも、そんな規模の噴火が起きてしまったら、原発云々以前にその周辺の人間はみんな死んでしまうだろうから、原発だけ気にしてもはじまらない、という考え方もあるかもしれません。規模が規模だけに、そういう考え方も分からないではない。しかし、例えば数日前に「とんでもない規模の噴火が起きる」と分かった場合、原発の燃料棒はもはや逃げようがない。でも、人間なら、数日の猶予があれば、全員は無理だとしても、相当の人数を避難させることはできるでしょう。そして、噴火が沈静化して何年か経てば、生き残った人は再びそこに帰ってくることはできるはずです。原発事故がなければ、です。燃料棒ごと原発が吹っ飛んでしまえば、それもできなくなります。
2014.07.17
コメント(0)
-
安全とは言わないが稼動してかまわないと?
川内原発:田中規制委員長「安全だとは私は言わない」原子力規制委員会は16日、九州電力川内原発1、2号機について、「新規制基準に適合している」とする審査書案を定例会で了承した。今後、30日間の意見公募などを経て審査書を決定する。川内1、2号機は、東京電力福島第1原発事故の教訓を踏まえ、安全対策を強化した新規制基準をクリアする初の原発となる。地元同意手続きや設備の使用前検査なども必要となるため、再稼働は10月以降になる見通しだ。ただ、規制委は「基準に適合しているかどうかを審査するだけで、稼働させるかどうかには関与しない」との姿勢を崩さず、政府も「稼働させる政治判断はしない」との立場だ。実質的に再稼働の判断は電力会社と立地自治体に委ねられ、国策でもある原発が、国の責任があいまいなまま稼働する可能性もある。現在、川内1、2号機を含め、12原発19基が規制委の安全審査を受けている。事実上の「合格」第1号が出たことについて、田中俊一委員長は「基準への適合は審査したが、安全だとは私は言わない。これがゴールではないので、(九電は)努力していく必要がある」と述べた。審査書案は約420ページ。九電が示した地震や津波の想定、事故対策などを個別に検討した。九電が想定する地震の最大の揺れ「基準地震動」を従来の540ガルから620ガルに、想定する最大の津波の高さ「基準津波」を約4メートルから約6メートルに引き上げたことを、いずれも妥当とした。また、九電が周辺14火山の過去の噴火間隔やマグマだまりの膨張傾向などから「安全性へ影響する可能性は小さい」と判断したことを受け入れた。ただし、規制委は継続的な火山の監視を求めた。また、福島第1原発で起きた炉心損傷や全電源喪失などの過酷事故への対応は、幅広い事故の想定▽事故時の作業要員の確保方法▽機能喪失を防ぐ設備の準備▽対応手順−−などを求め、九電が示した対応策をいずれも了承した。航空機が施設に落下した場合やテロ対策についても対応の手順書や体制、設備の整備方針を認めた。九電は昨年7月に川内1、2号機の安全審査を申請した。当初は基準地震動を原発事故前のままとするなど、安全対策に消極的な姿勢も見られたが、いち早く基準地震動の引き上げに応じたため、3月から優先的に審査が進められた。審査書案は今後のモデルケースとなるため、他原発の審査が加速するとみられる。川内1、2号機に続き、基準地震動が決まった関西電力高浜原発3、4号機の審査が先行している。---昨年9月にすべての原発が停止してから10ヶ月、それ以前も大飯原発の2基が動いていただけなので、実質的には2012年5月からほとんどの原発が止まったままで2年以上が経過していますが、燃料費高騰はあるものの、電気が足りなくなるような事態は起こっていません。それにもかかわらず、川内原発を10月以降に再稼動するのだというのです。私自身の個人的意見としては、安全面に最大の配慮をしたうえで、かつこのままでは電力が足りないという具体的な危険性があるのであれば、将来の原発全廃を前提としての再稼動には、必ずしも反対ではないのですが、その条件は一つとして満たされていません。規制委員長が自ら「安全だとは言わない」と明言しているにもかかわらず、「基準には適合している」のだという。つまり、基準が安全を保障する内容にはなっていない、ということですね。稼動が10月ということは、1年の中でも一番電力需要の少ない時期であり、当然そんな時期に電力が足りなくなるような具体的な危険性があるわけがない。そして、いうまでもなく自民党政権は今後も原発を続ける気満々で、脱原発などまったく考えていない。九電が想定する地震の最大の揺れ「基準地震動」を従来の540ガルから620ガルに、想定する最大の津波の高さ「基準津波」を約4メートルから約6メートルに引き上げたことを、いずれも妥当とした。のだそうです。近年日本を襲った大地震で記録されている揺れの強さは、軒並み620ガルなどという数字を超えています。例えば2004年に起きた新潟県中越地震は、マグニチュード自体は6.8しかありませんでしたが、揺れの最大加速度は2515ガルを記録しています。津波に関しても、東日本大震災で記録された津波の高さが6メートルをはるかに超えていたことは、今更いうまでもないことでしょう。いや、東日本大震災よりはるかに規模の小さな北海道南西沖地震や日本海中部地震(マグニチュード7.7から7.8)でも、最大波高10メートルを超える津波が記録されています。対策としては甘すぎと思わざるを得ません。震災の後、初めて再稼動された大飯原発3・4号機も似たようなことがありました。地震に備えてあんな対策、こんな対策を講じましたといううたい文句で、2012年7月にいったん再稼動されたわけですが、実際にはそれらの対策は、×年後に実施という予定を決めただけで、その時点ではまだ実行されていたわけではないにも関わらず、対策はできたとして再稼動されてしまったのです。この堤防で大丈夫とは思えないつまり、書類上の形だけ整えたから再稼動、ということです。今回も同じです。その基準をクリアしても「安全だとは言わない」つまり、形式を整えただけということです。規制委員会は、「基準に適合しました」と、つまり言い換えれば形式は整いましたと宣言するだけです。安全だとは保証しない。で、政府も「政治判断はしない」と、つまり誰も主体に判断することから逃げたまま、再稼動だけが着々と進んでいく。不思議で、かつ恐ろしいことです。
2014.07.16
コメント(0)
-
個人情報漏えい
ベネッセ流出:再委託先SE逮捕へ 情報売却の疑い通信教育大手ベネッセホールディングスの顧客情報漏えい問題で、警視庁は14日、顧客データベース(DB)の保守管理を担当していた外部業者のシステムエンジニア(SE)の男について、一両日中にも不正競争防止法違反容疑で逮捕状を請求する方針を固めた。約760万件もの顧客情報が流出した問題は、刑事事件に発展する見通しとなった。関係者によると、DBの保守管理はベネッセのグループ企業「シンフォーム」に委託され、同社がさらに複数の外部業者に再委託していた。男はこのうちの一社に派遣社員として勤務し、DBに接続できる端末が置かれているシンフォーム東京支社の一室に出入りしていた。男にはDBへのアクセス権限があり、昨年末に同支社の部屋から男のIDでログインし、複数回にわたり顧客情報をダウンロードした履歴が残されていた。警視庁の任意の事情聴取に対し、男は顧客情報を持ち出し、名簿業者に売却したことを認める供述をしたという。USBメモリーなどの記憶媒体にコピーして持ち出したとみられ、複数の名簿業者を経て、通信教育事業を手掛けるソフトウエア会社「ジャストシステム」に販売された。警視庁は男の勤務状況とDBのダウンロード履歴の照合や、持ち出された情報が同法で定める「営業秘密」に当たるかどうかなど、詰めの捜査を進めている。他に関与した人物がいないかも慎重に調べる。ベネッセによると、漏えいしたのは通信教育講座「進研ゼミ」などの顧客情報で、最大2070万件に上る可能性がある。---少し前の記事に触れたように、ジャストシステムに流れた個人情報の中に、我が家の分も含まれていたようです。というのは、うちも2年くらい前にベネッセの「こどもちゃれんじ」を取っていたことがあって、なおかつ先日ジャストシステムからスマイルゼミという通信教育のダイレクトメールが送られてきていたからです。正直言って、その時は気にも留めていませんでした。日々、いろいろなダイレクトメールが届いていて、その発送元の会社をいちいち気にしてはいなかったからです。報道を見て、うちの子が取っていた「こどもちゃれんじ」がベネッセの教材であったことを知ったことから、流出したデータに我が家の分も含まれていたと知ったような状態です。怖いといえば怖いし、薄気味悪い事態であることは間違いありません。ただ、ジャストシステムに流れた個人情報だけで230万件、流出した全体では2070万件という、あまりに巨大すぎる流出量のせいで、逆に感覚がマヒしてしまうところもあります。だって、2000万件ですよ。日本の全世帯数は約5000万世帯ですから、その4割ですしかも、ベネッセが持っている個人情報の大半は子ども(少なくとも未成年)のいる世帯のものでしょうから、子どものいる世帯に限定すれば、流出被害遭遇率は相当の割合になるんじゃないでしょうか。(同じ世帯について重複するデータもあるでしょうけど)赤信号、みんなで渡れば怖くない、という言葉がありますが、流出被害も、みんなが被害者だと怖くない、という感覚はあります。これだけの規模になってしまったら、我が家の個人情報が悪い奴らに渡って、犯罪に利用される、というような事態に巻き込まれるのは、天文学的に低い確率になってしまうだろうと思われるからです。それに、よく考えてみれば、これまで送られてきていたダイレクトメールだって、怪しいものはあるはずです。思い返すと、今から20年以上前、私が大学生4年生になったとき、リクルートなどから大量の就活関係の資料が送られてきていましたが、この住所に就職活動中の大学4年生が住んでいる、ということを、ああいう求職情報誌はどうやって知ったのでしょうね。役所で住民記録データを閲覧したか、各大学から学生情報を取得したか、いずれにしても、当時は個人情報保護法もなかった時代ですから、今以上に個人情報ダダ漏れだったはずです。ある意味、ダイレクトメールなんてものは人畜無蓋な部類で、勧誘電話の類のほうがよほど厄介です。マンション買いませんかとか、投資信託とか、そういう類の勧誘電話が、一時期頻繁にかかってきたことがあります。職場にかかってくることもあったので、おそらく勤務先から従業員名簿が流出したのだろうと思うのですが、中にはかなり悪質なのもあって、冷たくあしらうと逆ギレして威嚇してくるような手合いもいた。あれも、脅して話を聞かせようという作戦なんでしょうかね。自宅では、そういう手合いに対しては、倍返しで怒鳴りつけて電話を叩ききったりするわけですが、やっぱりそういうやり取りをすると疲れるし、無用に気が立ってしまうので、嫌だなー、と思ってしまうのです。それに比べると、今回の情報流出は、現時点では、実害は乏しいというのが正直なところです。ただし、これから先流出したデータがどのように使われてしまうのか、というところは気になるところではありますけど。それにしても、ベネッセの委託先(子会社)の委託先の派遣社員とは、原発労働者の孫請け曾孫請けと似た構図ですね。とはいえ、いくら孫請けの派遣社員が安月給だったとしても、だから個人情報を流出させてよい、ということにはならないでしょう。しかも、別報道によると情報を1回数十万円で、数回に分けて売却し、数百万円を得て、ギャンブルなどで使ったのだそうで、あまりに分かり易すぎる動機で、かけらほどの同情の余地もない。いや、まあギャンブル依存だとすれば、同情の余地はあるのかも知れませんが、少なくとも私の感情面では同情しようという気にはなりません。
2014.07.15
コメント(4)
-
摩訶不思議な産経新聞
摩訶不思議な官邸前抗議集会と実態を報じないNHK~NHKは1日夜のニュース番組で、閣議決定に関する安倍晋三首相の記者会見の内容を報じたのに続き、集会の模様も伝えた。「戦争反対」「戦争する国にするな」などのプラカードを掲げた参加者が、「若い人が声をあげないとだめだ」といった趣旨のことを訴える映像も流した。これを見た視聴者は、いかにも首相が国民の声を無視して横暴を働いていると感じたかもしれない。首相は記者会見で「戦争をする国にする」とは一言も言っていない。そうはいっても閣議決定の受け止めは人それぞれあっていいと思うが、いくら公平性が大事だとはいえ、反対者の意見を無批判に垂れ流すとは、公共放送として果たして正当なのだろうか。~抗議集会の参加者の間には多くの「のぼり」がはためいていた。現場でみればすぐに分かることだ。「○△教組」「○×労連」など、特定の野党と関係が深い団体のものがほとんどだった。最も目をひいたのは、警察庁が極左暴力集団と認定している団体の真っ赤な旗だった。だが、こうした映像はNHKでは映されない。集会には共産党や社民党の国会議員も参加し、マイクを握って安倍政権批判を展開し、参加者が同調していた。これも映らない。だから、「ごく普通の善良な一般市民が、暴走する安倍政権への抗議に集まった」との印象を受けた人もいるだろう。参加者の言葉遣いは総じて聞くに堪えないほど品がなかった。否が応でも耳に入ってきてしまう訴えを聞いているだけで不快な気分だった。一国の首相を「安倍!!」と呼び捨てにし、「ファシスト」呼ばわりする。「安倍は人殺しだ!!」というのもあった。文字にするのもはばかれる罵詈雑言もあった。こんな過激な集会には、子供の姿もあった。日本は憲法で集会や表現の自由が保障されている。とても自由な国だ。だが、そこにも常識的な限度というものがある。集会には主催者発表で1万人超が参加したという。人数の真偽を確認する術はない。中には、いわゆる「普通の市民」もいただろう。その集会が、どんな許可を得て開かれたのか知らないが、官邸前の道路には明らかに参加者がはみ出していた。だが、警察が道路交通法違反の現行犯で検挙したとの報道はない。毛沢東の「造反有理」よろしく、「善良な市民の純粋な正義の行動」の前では、道交法違反など小事なのだろうか。深夜まで続いた静寂を破壊する大音量の楽器と叫び声もそうだ。集会参加者の訴えによると、安倍政権の閣議決定は「民主主義を壊す」のだという。常識の尺度が違うのだと思うが、閣議決定がどうして民主主義を壊すのかが分からない。民主主義の象徴である衆院選で、今回の集会に国会議員が参加していた共産、社民両党は計10議席を獲得した。閣議決定の前段として与党協議を続けてきた自民、公明両党は計325議席だった。これは民意ではないということのようだ。~「容認するなら憲法解釈ではなく憲法改正が筋だ」と訴えた参加者もいた。筋論としては、そうだ。だが、憲法改正に反対する人に限って、そういうことを言う傾向が目立つ。日本を取り巻く環境は憲法改正が実現するまでの時間的な猶予を与えるだろうか。「戦争に巻き込まれる」との訴えもあった。戦争に巻き込まれたくなくても日本の領土を不法に占拠し、日本海に向けてミサイルを放ち、日本の領土に領海侵犯を繰り返しながら、なんら悪びれない国が近くに複数いる。集会参加者は「侵略」が大嫌いだと思うが、日本への侵略的行為が常態化され、その事態を拡大させない、あるいは抑止し、解決するためにも重要な日米同盟の連携には反対というのが不思議でならない。集団的自衛権の行使を想定した事態として首相が5月の記者会見でも示した「邦人輸送中の米艦防護」などの事例について、「そんな可能性は極めて低い」という指摘もあった。民主党や結いの党、そして公明党までもが「蓋然性が低い」「個別的自衛権や警察権で対応可能」などと指摘している。確かに可能性は低いかもしれない。しかし、ゼロとは言い切れない。政府が邦人保護のために万全の準備をしておく必要はあるはずだ。大地震や大津波が起こる可能性は極めて低くとも、命を守るためにはそれなりの備えが必要だ。それが東日本大震災や原発事故の教訓だったはずだ。同じ国民の命を守ることなのに、なぜか特定の思想を持った人は安全保障に関することになると過剰に拒否反応を示す。集会参加者によると、「自衛隊は今まで一発も銃を撃たず、人を殺さず、殺されなかった」「今度は自衛隊が人を殺すことになる」という。個別的自衛権の行使の場合でも、自衛隊が任務のために銃を撃つ事態になることは当然ある。なぜ日本を守るための集団的自衛権行使になったとたんにダメなのか。(以下略)---愚にもつかない駄文としか思えないのですが、こんなものに金を払って購読する人がいるんだから、世の中というのはよく分からないものです。私自身、7月1日に首相官邸前にいた人間ですが、確かに労働団体、市民団体ののぼりがたくさん立っている一角があったことは事実ですが、そういうのぼりが全然見当たらない一角もあり、参加者がみんな特定団体のメンバーであるかのような書き方は、言いがかりでしかないと思われます。もっとも、労働団体であれ市民団体であれ、もちろん社民党や共産党の友好団体であれ、日本に於いては等しく言論の自由、表現の自由が認められているのですから、そういう団体が意思表示をすることの、何が悪いの?としかいいようがありません。参加者の言葉遣いは総じて聞くに堪えないほど品がなかった。否が応でも耳に入ってきてしまう訴えを聞いているだけで不快な気分だった。一国の首相を「安倍!!」と呼び捨てにし、「ファシスト」呼ばわりする。「安倍は人殺しだ!!」というのもあった。のだそうですが、このあたりはまさしく「感性の違い」としか言いようがありませんが、「一国の首相」だからという理由で呼び捨てはけしからんという言い草には、失笑してしまうのです。必ずしも首相に限りませんが、有名人一般に、その名が敬称略で人々が口にするのは、かなり自然なことです。個人的に親交がある場合は別にして、会ったこともない有名人の名にいちいち敬称をつけるほうがまれでしょう。それは、ある種の有名税のようなものです。私自身、当ブログにおいて、個人的に親交がある場合など特殊事情を除いて、政治家を含む著名人は原則として敬称略です。安倍はもちろん、菅直人や鳩山由紀夫だって、志位だって、敬称略です。で、「ファシスト」呼ばわりにいたくご立腹のようですが、こんなのはお互い様としか言いようがないのです。左派よりの政治家に「反日」とか「売国奴」と叫ぶことは良くて、右派よりの政治家に「ファシスト」と叫ぶことがけしからぬ、などというのは、理屈の通らない話しです。日本は憲法で集会や表現の自由が保障されている。とても自由な国だ。だが、そこにも常識的な限度というものがある。この人の持っている「常識的な限度」が右側に対しては広く、左側に対して極度に狭いことだけは、よく分かりました、というところですね。官邸前の道路には明らかに参加者がはみ出していた。だが、警察が道路交通法違反の現行犯で検挙したとの報道はない。この駄文の中で一番失笑したのはこの部分ですね。道路交通法の、どんな条文に基づいて路上にはみ出た参加者を検挙するんですか?ちなみに、道路交通法は、確かに第10条で歩行者は歩道を歩くことを求めていますが、この規定に罰則はないのです。もちろん、車道を歩けば車にはねられる可能性は高まるし、事故にあったとしても自動車側の過失責任が相対的に軽くなるとは思います。そのリスクは車道に出てしまった人自身が負うしかありませんけれど。だいたい、車道に出た歩行者がみんな検挙されるようなことになったら、日本中の留置所がパンクしてしまいますが。閣議決定がどうして民主主義を壊すのかが分からない。何度も書いたことですが、憲法には改正の規定が明記されているにもかかわらず、その手続きを踏まず、裏口入学のように実質的に憲法を変えてしまうから、「憲法を壊す」と言っているわけです。戦争に巻き込まれたくなくても日本の領土を不法に占拠し、日本海に向けてミサイルを放ち、日本の領土に領海侵犯を繰り返しながら、なんら悪びれない国が近くに複数いる。のだそうですが、それはすべて、個別的自衛権の範疇に属する問題であって、集団的自衛権とは関係のない話です。日本を取り巻く環境は憲法改正が実現するまでの時間的な猶予を与えるだろうか。確かに可能性は低いかもしれない。しかし、ゼロとは言い切れない。この2つの言葉は、見事なまでに相互矛盾をきたしています。産経自身が「可能性が低い」と認める事態に対処することを、なんでそんなに急がなければならないのか。ちなみに、「邦人輸送中の米艦防護」なんてほとんどありえない事態(確かに、論理的には可能性ゼロではないかもしれないが)で日本人の命が救われる可能性と、集団的自衛権を認めたがゆえに、参加する必要のない戦争に参加して、日本人(自衛官)が命を落とす可能性を天秤にかければ、後者のリスクの方がはるかに高いと思います。個別的自衛権の行使の場合でも、自衛隊が任務のために銃を撃つ事態になることは当然ある。なぜ日本を守るための集団的自衛権行使になったとたんにダメなのか。個別的自衛権の行使とは、すなわち日本が外国の攻撃を受けて、身を守ることです。そして、これまで日本は個別的自衛権を行使する必要がなかった、つまり外国の攻撃を受けたことがなかった。それに対して、集団的自衛権は、日本が直接攻撃を受けていないのに、戦争に参加するということ。自分自身の身を守るためではなく武器を使うことになるんだから、戦争に参加する可能性は、国政の担当者の胸先三寸で、いくらでも高まることになる。何しろ、米国はいつも世界中で戦争をやっており、日本もそれに参戦するよう要求される可能性も、間違いなく大幅に高まる。そんなことも分からないほど、この筆者は馬鹿なんですねえ。
2014.07.13
コメント(6)
-

誰かさんのパーカッション・デビュー戦
一般公開の演奏ではなかったので、告知していませんでしたが、今日は、「ティエラ・クリオージャ」というグループで演奏してきました。ティエラ・クリオージャは、本来のメンバーは5人なのですが、そのうちの一人は最近極度に忙しく、このところは事実上4人編成で演奏しています。加えて、今日はボンボ(太鼓)奏者も都合が悪くて、出られないため、助っ人のボンボ奏者をお願いしました。人前でボンボを叩くのは初めてという助っ人です。堂々のセンターですよ(笑)この曲は、クエッカという6/8拍子のリズムで、たいていの日本人にとっては、かなり難易度が高い。他の曲はともかく、この曲を叩くのは無理だろうから、この曲だけはボンボ抜きで演奏でも仕方がないと思っていたのですが、何と、ちゃんと叩いてくれました。もっとも、私の隣でリズムを破壊しようとしている人が、約1名いるような、いないような・・・・・・。そしてもう1曲カルナバルのメドレーです。この曲も6/8拍子。やはり、日本人にはあまり馴染みのないリズムです。しかし、やっぱり問題なく叩いてくれました。さすがに、吹奏楽部でパーカッションをやっているだけのことはある。もっとも、吹奏楽部に入ってから、まだ半年も経っていません。ということは、もともと持って生まれたリズム感があるのかな。ボンボは、以前参加していた「グルーポ・インカコーラ」というグループで使っていたもので、ながらく押入れに鎮座したままで、人前での演奏に持ち出したのは十数年ぶりです。ピンク色の派手なポンチョも、やはりグルーポ・インカコーラで使っていたもので、これも十数年ぶりに使いました。これが、毛糸の暖かいポンチョでして、つまり、今の時期に使うのは、かなりきつい。今日はエアコンが効いている部屋だったので大丈夫でしたが、昔、夏祭りにこのポンチョを着て演奏したことがありました。夜でしたが、屋外だったのですごく暑かった。それにしても、大先生を拝み倒してボンボを叩いていただくのは、なかなか一苦労ではありました。タダでは叩いてくれなかった。わが子が、スマイルゼミという通信教育をやりたいというので、それを釣餌にして、やっとボンボを叩いてもらいました。ところが、このスマイルゼミ、今話題のジャストシステムが運営しているのです。我が家にもダイレクトメールが送られてきた。で、以前は「チャレンジ」という、これまた今話題になっているベネッセがやっている通信教育をやっていた時期があるのです。ということは、ベネッセから流出してジャストシステムに買い取られた230万件という個人情報に、我が家の分も含まれていた、ということだよね。うーーーーん、このままスマイルゼミを取るわけにもいかないか。と思っていたら、うちの子が「やっぱりゲーム機がほしい」と言い出してしまった。さて、どうしたものか。
2014.07.12
コメント(2)
-
それで少子化問題が解決すると?
少子化が進む成長戦略にするな 麗澤大学教授・八木秀次東京都議会のセクハラやじ問題は、外国メディアにも報道されたことで、日本は女性の人権を軽視する野蛮な国であるとの「日本たたき」の道具に利用された。新聞もテレビも、「ポリティカル・コレクトネス(PC、政治的正しさ)」順守で硬直化しているせいか、もはやきれい事しか述べなくなっている。≪非婚化、晩婚化食い止めよ≫やじは品位に欠け、決して擁護するつもりはないが、やじを発した議員の真意は、少子化問題が深刻化する中で、独身の女性議員に対し、少子化対策の一般論を述べるのも結構だが、自分が結婚して子供を産んではどうか、と言いたかったのではないか。もちろん、さまざまな事情で結婚-妊娠-出産できない女性も存在し、やじはその点に対する配慮に欠ける。だが、深刻化する少子化という背景を捨象して、発言だけを問題視することには違和感を覚える。少子化対策は、今日のわが国の最大の課題といっていい。「日本創成会議・人口減少問題検討分科会」が5月に発表した試算は衝撃的な内容だった。超少子化と東京への一極集中によって2040年には全国の約半数に当たる896自治体で、子供を産む中心世代である20~39歳の女性が5割以上も減少し、現在の教育・福祉など幅広い行政サービスの維持が難しくなるという。昨年の出生数も1899年以降最少の102万9800人にとどまっている。原因は端的にいえば、非婚化と晩婚化である。80年には男性で8・5%、女性で5・5%だった35~39歳の未婚率は、2010年には男性で35・6%、女性で23・1%と急増している。1975年には男性で27歳、女性で24・7歳だった平均初婚年齢も、2011年には男性で30・7歳、女性で29歳と上昇し、第1子の平均出産年齢も30歳を超え、昨年生まれた子供の母親で年齢が35歳を超えているケースは26・9%を占めるに至っている。少子化を解決するには、結婚、早期の出産、多産を促し、国や社会がそれを支援するしかない。≪子供は女性にしか産めない≫そんな中、政府は6月24日、今年の成長戦略を閣議決定した。目玉の一つは女性の活躍促進だ。その柱は以下の通りである。保育所の待機児童解消に加え、子供が小学校に入学すると預かり先がないという「小1の壁」も解消すべく、放課後の児童クラブの受け皿を19年度末までに30万人に拡大する。指導的地位に占める女性の割合を20年までに30%に引き上げ、税・社会保障制度も女性の働き方に中立的なものに見直し、女性の活躍加速化へ向けて新法を制定する-。「女性の働き方に中立的な税・社会保障制度等への見直し」とは、年収103万円以下の主婦について所得税や住民税を控除する配偶者控除の廃止、年収130万円未満の主婦については年金保険料を免除する「第3号被保険者制度」の廃止を指している。これらは女性の就労を抑制するとして見直しが主張されてきた。要は、女性も、結婚、妊娠、出産、育児といった事情にかかわらず退職せずに働き続ける社会の構築を目指そうということだ。「新法」とはそれを担保する法的措置のことで、今通常国会での成立は断念されたものの、法案は既に用意されている。しかし、この成長戦略で少子化が解決するとは思えない。むしろ逆に進行するのではないか。確かに少子化と相まって人口減少、とりわけ労働力人口減少の問題は深刻だ。それだけに女性の活躍を期待するのは理解できる。女性が男性にない発想や視点を提供することは社会の発展にも寄与する。だが、同時に留意すべきは、子供は女性にしか産めないという厳然たる事実ではないのか。≪育児終えた後の活躍推進を≫当の女性たちは、「子供が3歳くらいまでは母親は仕事を持たず育児に専念」という意見に20~30代の子育て世代の80%が賛成している(国立社会保障・人口問題研究所『全国家庭動向調査』08年)。成長戦略は、この思いを抑えて結婚・妊娠・出産・育児に関係なく働き続けるよう勧め、独身や子供のいない人と「平等」な税・社会保障制度を構想している。しかし、これでは妊娠・出産・育児という“負担”を引き受ける動機付けとはならない。必要なのは育児を終えた女性の活躍であり、それを推進すべきではないのか。成長戦略はまた、日本人女性の「活躍」を推進すべく家事・育児の負担を軽減するために、外国人メイドの受け入れにまで言及している。だが、異文化を持った外国人が家庭に入り、育児にも従事すれば、日本の文化構造や子供のアイデンティティー形成にも大きな影響を与えることが予想される。少子化を解消するには、女性が結婚・妊娠・出産・育児の意欲を持てるような動機付けが必要だ。政府にはそのための制度設計を望みたい。ーーーまあ、いかにも産経らしい主張ではあります。問題の議員がヤジを飛ばした真意など、本人にしか分らないことではありますが、私には、そんなに高尚な考えに基づく発言ではないように思えます。が、真意はどこにあるとしても、そんなことは問題ではありません。私も、あまりに極端な少子化は問題がある、と思いますし、その限りにおいては八木と問題意識を共有している部分はないこともないのですが、他ならぬ私自身も、子どもは一人しかいません。重要なことは、少子化は、子どもを作らない個々の女性の問題なのか、ということと、ではそういう女性に対して、早く結婚して子どもを作れと言うことが(仮に、あのような低劣や野次ではなく、穏やかな説明だったとしても、です)、何か効果があるのか、ということです。私には、どちらも否であるとしか、思えないのです。結婚しない、子どもを作らない個人を批判して解決するような問題ではないし、「早く結婚しなさい」「早く子どもを作りなさい、何人以上作りなさい」などと言われて、「はい、そうですか」と、効果が現れるような、そんな単純な話ではないのです。女性も、結婚、妊娠、出産、育児といった事情にかかわらず退職せずに働き続ける社会の構築を目指そうということだ。~しかし、この成長戦略で少子化が解決するとは思えない。むしろ逆に進行するのではないか。以前にも、やはり産経新聞で似たような主張がありましたが、あまりに時代錯誤的な事実認識です。女性がどういうライフスタイルを望み選択するかは、個人の判断です。ただし、現実には本人だけの意思で、完全に自由に選択できるわけでもありません。夫の意思もあるだろうし、そもそも経済的な条件というものがある。当の女性たちは、「子供が3歳くらいまでは母親は仕事を持たず育児に専念」という意見に20~30代の子育て世代の80%が賛成しているのだそうですが、それが可能な状況なら、私だってその意見に、少なくとも反対ではありません。他ならぬ我が家も、相棒はいったん専業主婦になりましたから。だけど、現実に妻が育児に専念できるかどうかは、夫の収入や雇用の安定性次第です。2人世帯で2馬力だったものが、3人世帯で1馬力になれば、何もなくても生活は苦しくなる。そもそもそれでは生活が成り立たない家族だって少なくない。まして、妻が育児に専念したところで夫が解雇されたりしたら、目も当てられないことになります。それを考えれば、妻が育児に専念という選択はなかなかできないし、それを無理強いすれば、少なくとも後先を考える理性がある人は、これまで以上に子どもを作ることに慎重になり、なおさら出生率が下がるのは明らかであると、私には思えます。どう考えても、「子どもができたら育児に専念」などという考えを推進することが女性が結婚・妊娠・出産・育児の意欲を持てるような動機付けになるわけがない。
2014.07.11
コメント(0)
-
いよいよ大詰め、ワールドカップ
開催国ブラジルが、準決勝でドイツ相手に、まさかの1-7の歴史的大敗。ネイマールと守備の要シウバの欠場から、不利とは予想されていましたが、それにしてもあのブラジルが7点取られるとは・・・・・・。今回ワールドカップ最大の驚きです。で、もう1試合の準決勝が今日行われました。応援したのは、もちろんアルゼンチンです。朝5時には起きられなかったので、後半戦から見ました。予定では試合終了を見届けて出勤するはずが、延長戦に突入、結局、延長戦後半からは電車の中でネット中継で確認しました。アルゼンチン、24年ぶりの決勝進出です。やったーーーーーーー!それにしても、24年ぶりなのか。あの、あまりにも有名な「神の手」で優勝したのが1986年、そしてその次の1990年は決勝でドイツに敗れ、それ以降アルゼンチンは決勝に進めなかった。1994年大会の途中でマラドーナのドーピング疑惑が発覚して、大会から追放されて以降の低迷は、アルゼンチンのサッカーにとってマラドーナの存在がいかに巨大だったか、ということでもあるのでしょう。これで優勝すれば、メッシはマラドーナの再来だ!!と、言いたいところではあるのですが、冷静に考えると、ブラジル相手に7点取ったドイツのほうが、やっぱり有利だろうなあ。しかし、もしドイツが優勝すると、南米開催の大会で史上初めてヨーロッパか優勝することに。はてさて、どうなることやら。ともかく、可能性ではなく願望として、アルゼンチンが3度目の優勝!!と書いておくことにします。しかし、決勝戦は日本時間の月曜朝4時だそうで。さすがに、私は起きられるのだろうか??起きられたとして、長い1週間の始まりが寝不足でスタートというのは、ちょっとキツイ。
2014.07.10
コメント(4)
-
そのウソは本当か?
<集団的自衛権>行使容認の一問一答、内閣官房HPに掲載政府は内閣官房のホームページで、集団的自衛権の行使を容認した1日の閣議決定の内容を説明する「一問一答」を掲載した。6月作成の想定問答集に明記した「集団安全保障での武力行使解禁」や「戦時の機雷掃海など集団的自衛権の8事例容認」などは削除。自衛権発動の「新3要件」が歯止めになると訴え、国民に理解を求めている。一問一答は計22問。集団的自衛権の行使容認は「必要最小限の自衛の措置だけだ」とし、具体的な事例には触れていない。「自衛隊員が海外で人を殺し、殺されるのでは」との質問には、「自衛隊員の任務は我が国と国民を守ることだ」、地理的制約も「海外派兵は許されない」との表現にとどめている。---問題のホームページはこちらです。「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の一問一答何と言うか、見事なまでに表層的な回答で、突っ込みどころが満載と考えざるを得ません。【問1】 なぜ、今、集団的自衛権を容認しなければならないのか?【答】 今回の閣議決定は、我が国を取り巻く安全保障環境がますます厳しさを増す中、我が国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るため、すなわち我が国を防衛するために、やむを得ない自衛の措置として、必要最小限の武力の行使を認めるものです。個別的自衛権についての説明としてなら理解できますが、集団的自衛権、つまり他国同士の紛争に日本が首を突っ込む理由としては、とても納得できる説明ではありません。【問7】 憲法解釈を変え、平和主義を放棄するのか?【問8】 憲法解釈を変え、専守防衛を放棄するのか?などの問に対する回答も同じことが言えます。自国が攻撃されたわけでもないのに、同盟国に対する攻撃を自国に対する攻撃とみなして共同「防衛」を行うことを、専守防衛とはとても呼べません。【問3】 なぜ憲法改正しないのか?【答】 今回の閣議決定は、国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るために必要最小限の自衛の措置をするという政府の憲法解釈の基本的考え方を、何ら変えるものではありません。必ずしも憲法を改正する必要はありません。でも、与党である自民党は、憲法改正を党是としているわけです。「必ずしも憲法を改正する必要はありません。」と言い切るならば、与党自民党の党是も変更して、日本国憲法改正草案などというものは、早々に撤回すべきでしょう。そうしないで、ただ「憲法改正の必要はない」などと言っても、口先だけの弁解としか受け取れません。【問10】 徴兵制が採用され、若者が戦地へと送られるのではないか?【答】 全くの誤解です。例えば、憲法第18条で「何人も(中略)その意に反する苦役に服させられない」と定められているなど、徴兵制は憲法上認められません。いや、集団的自衛権も「憲法上認められない」ものだったはずです。一内閣の解釈変更だけでそれがひっくり返して見せたのだから、「徴兵制は憲法上認められません。」という解釈だって、時の内閣の胸先三寸で変えることができる、ということになります。【問11】 日本が戦争をする国になり、将来、自分達の子供や若者が戦場に行かされるようになるのではないか?【答】 日本を戦争をする国にはしません。そのためにも、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しくなる中で、国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るために、外交努力により争いを未然に防ぐことを、これまで以上に重視していきます。これも、冒頭に書いたように、個別的自衛権の説明なら納得もできるけど、集団的自衛権の説明としては納得し難いものです。【問12】 自衛隊員が、海外で人を殺し、殺されることになるのではないか?【答】 自衛隊員の任務は、これまでと同様、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるというときに我が国と国民を守ることです。これは、よく見てみると、質問に対する回答になっていないのです。殺し殺されることになるか否か、について、何も言っていないからです。しかし、当然のことながら、自衛権を発動して敵と戦う、ということは、戦争であり、つまり殺し殺されることです。鉄砲やミサイルを撃って、誰にも当たらず、誰も怪我も死亡もしない、なんてことは有り得ないですからね。それは個別的自衛権の話であっても同じですが、ただ個別的自衛権は「国内に攻め込んできた敵を撃退するため」の行為だから、「海外で」殺し殺されるわけではない。しかし、集団的自衛権というのは、当然「海外で」人を殺し殺される行為につながっていることは明らかです。【問13】 歯止めがあいまいで、政府の判断次第で武力の行使が無制約に行われるのではないか?【答】 国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置としての武力の行使の「新三要件」が、憲法上の明確な歯止めとなっています。さらに、法案においても実際の行使は国会承認を求めることとし、国会によるチェックの仕組みを明確にします。これも徴兵制と同じで、これまでの「三要件」は「憲法上の明確な歯止め」だったのですが、それが一内閣の解釈変更で反故にできるのでは、全然「明確な歯止め」にならないではないですか。他にも突っ込みどころはいろいろありますが、夜も遅いのでこのあたりにしておきます。要するに、全然説得力がない、ということです。
2014.07.09
コメント(0)
-
在特会に高裁判決
在特会に二審も賠償命令=朝鮮学校への街宣禁止―ヘイトスピーチ訴訟で・大阪高裁朝鮮学校周辺での街頭宣伝活動で授業を妨害されたとして、学校を運営する京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と会員ら9人に街宣活動の禁止と損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。森宏司裁判長は、学校の半径200メートル以内の街宣禁止と約1226万円の支払いを命じた一審京都地裁判決を支持し、在特会側の控訴を棄却した。人種や国籍などで差別するヘイトスピーチ(憎悪表現)に対する高裁の判決は初めて。在特会側は最高裁に上告する方針。森裁判長は、在特会の街宣や、その様子をインターネット上で映像公開したことについて「在日朝鮮人をわが国の社会から排斥すべきと公開の場で主張し、映像を拡散させて被害の再生産を可能とした」と批判し、「社会的な偏見や差別意識を増幅させる悪質な行為」と述べた。また、朝鮮学校の被害に関し「民族教育を軸に据えた学校教育の場として形成された社会的評価が低下させられ、教職員らの心労や負担も大きかった」と指摘。学校の移転先での街宣禁止についても、「在日朝鮮人の人格を否定し、差別意識を世間に訴えることに(街宣の)主眼がある。新校舎周辺でも不法行為の恐れがないとは言えない」として認めた。---まことに当然の判決が、地裁に続いて高裁でも出た、ということです。在特会の乱暴狼藉に関しては、過去何回か当ブログで取り上げましたが、彼らの「街宣」の口汚さといったら相当のもので、どう考えたって「一般人」は退いてしまうような内容です。おそらく多くの支持を集めることを目的とせず、攻撃相手に対する嫌がらせを主目的としていること激しい言葉を使う自分自身に酔ってしまい、それが他人からどう見えるかが見えなくなっているというあたりが原因なのだろうと思います。それにしても、です。YouTubeには彼ら自身がアップした、下品極まる「街宣」の動画がたくさんあります。下品すぎるので、とても当ブログで紹介する気にはなれませんが。演説しているその場では、勢いで過激なことを言ってしまったとしても、それを後刻改めてYouTubeにアップする時点で、自分たちの言動がいかに恥ずかしいものかという神経が働かないのかな、というのが不思議で仕方がありません。まあ、そういう神経が働かないから、嬉々として自ら公開しているんでしょうけど。私自身、連中の傍若無人な街宣は、動画だけでなく、何度か実際に目撃したことがあります。反原発集会に対する嫌がらせ行動が多いかな。それ以外にもいくつかあった。わざわざあの連中にお近づきになりたいとは思わないから、「しばき隊」とかに参加したことは一度もないけど。地裁の判決以降、在特会の街宣活動は止まっているそうで、その意味ではこの判決はかなりの効果があったようです。考えてみると、以前は、反原発集会に参加するたびに、在特会の嫌がらせ行動を目撃しましたが、最近は、反原発、秘密保護法反対、集団的自衛権反対などの集会で、彼らの嫌がらせ行動は見かけなくなったように思います。私がたまたま見かけなかっただけ、かも知れないけど。上告するそうですが、いくら何でも、最高裁がこの判決をひっくり返すようなことはしないだろうと思われます。というか、ひっくり返すようだったら日本もいよいよ末期的と思わざるを得ないところですが。ただ、この記事のコメント欄が、またヘイトスピーチの場になっているという、なんとも救いのない現実があるわけです。日本中がプチ在特会的になってしまったので、結果的に目立たなくなってきた、という側面もあるのでしょうか。
2014.07.08
コメント(0)
-

筑波山
実は、急遽筑波山に登ってきました。自宅から半日で登れる山、というと、今まではだいたい高尾山だったのですが、さすがに高尾山は2月に登ったし、そういえば、筑波山は登ったことがなかったなと、思い立ってしまったのです。つくば駅からすぐ着くのだろうと思ったら、とんでもない。バスで更に40分近くかかりました。バス代も片道720円と、意外に高い。つくばエクスプレスの電車代と合わせると、往復で4000円近い。東京からごく近いと思っていましたが、案外お金がかかる山でした。登山口の筑波山神社です。ここから、ケーブルカーが出ているのですが、ケーブルカーの終点から山頂までは徒歩15分だそうで、それじゃあ登ったうちに入らないので、ケーブルカーは使わないことにしました。ところが・・・・・・筑波山って、標高877mしかないし、登山者もものすごく多いので、かなり甘く考えていまして、足回りは普段履いているジョッギングシューズだったのですが、これがすごいぬかるみ道だったのです。昨日までずっと雨だったせいもあるんでしょうが、とにかく滑りやすい。まあ、登りでは転倒はしませんでしたが、靴はドロドロになりました。でも、そのドロドロ道を登る人も、結構多かったのです。ドロドロの登山道を抜けると、ケーブルカーの終点です。この場所で、なんと職場の同僚とばったり出くわしてしまいました。奥に見えるのが男体山。でも、筑波山の最高地点はこちらではないので、まずは女体山に登ります。あっという間に山頂です。ケーブルカー終点からは徒歩15分となっていました。さすがにこの距離だけを登って「筑波山に登りました」とは言いにくい。見てのとおり、山頂はすごい混雑でした。筑波山は、高さは1000mにも届かないですが、だだっ広い関東平野を一望できる山で、この景色は(今日は視界がそんなにはなかったけど、それでも)確かになかなかのものです。筑波山にはケーブルカーのほかに、ロープウェーもあります。女体山から男体山を望む。男体山のほうが、ほんの数メートルだけ低い。その男体山にも行ってみました。こちらにも登山者は多かったのですが、多分女体山の方が多かったかな。この写真は、視界の広い場所を探して撮ったのですが、全般的に女体山からの方が視界は広いです。で、下り。ケーブルカーの終点まで降りて、さてどうしようかな、降りは手抜きしてケーブルカーで降りちゃおうかな、とも思ったのですが、結局はドロドロの登山道を降ることにしました。そして、案の定、降り始めた途端に足を滑らせて尻餅をついちゃいました。木の階段は滑りやすいのです。ただ、その場所は、まだそんなにドロドロではなかったことと、リュックから地面に着いたので、リュックの底は泥だらけになりましたが、ズボンはそれほどひどいことにならなかった。そこから先は慎重に降ったので、以降は転倒しないで済みましたが。でも、靴とズボンのすそは、こりゃもうしょうがない。しかし、筑波山、甘く考えていたけど、ちゃんとした登山靴で登ったほうがよかったようです。または、何日も晴天が続いたときに登るべきかも。で、実は登山口のバス停まで下りてきて気がついたのですが・・・・・・登山口からでも、かなり素晴らしい見晴らしなんですね。(のぼりは、一目散で歩き始めたから気がつかなかった)
2014.07.06
コメント(11)
-
たいていの場合はMVNOのほうが安くつく
iPadの新モデル、「SIMフリー」に米アップルは1日、タブレット型端末「iPad(アイパッド)」で、利用者が携帯電話会社や通信会社を自由に選べる新モデルを発売した。アップル直営店やオンラインショップで販売する。価格は「iPad Air」の16GBモデルが6万1800円(税別)など。iPadで携帯電話会社と契約する機種は、利用者の情報を記録したSIMカードを差して通信するが、その会社のSIMカードしか使えなかった。新モデルはロックが外されて「SIMフリー」となり、他社に自由に乗り換えられる。ただ、携帯電話会社は顧客を囲い込むため、通信料金を負担する代わりに端末代金を割り引くプランを用意している。例えば、NTTドコモでiPad Airの16GBモデルを購入した場合、2年使う契約の端末代金は6480円(税込み)になる。このため、SIMフリー端末がお得かどうかは、使う期間などで判断する必要がありそうだ。---SIMフリー端末がお得かどうかは、使う期間などで判断する必要がありそうだ、とありますが、ほとんどの場合はMVNO+SIMフリーの方が安く上がると思います。61800円を2年で割ると、月々2575円になります。つまり、大手キャリアとMVNOで、月額料金の差が2575円以上であれば、MVNOの方が得、ということになるわけです。さて、大手キャリアの中では比較的通信料がやすいソフトバンクには、「タブレットセット割」というのがあって、月額料金が(端末代込で)3662円、今なら14000円のキャッシュバックで月額3077円だそうです。これなら、月額1000円以下のMVNOより、端末代込の値段が安く上がるじゃないか!と、一瞬勘違いしてしまいそうになるのですが、実はそうではありません。「タブレットセット割」の適用条件をよく調べると、1回線目にはデータ定額パック(パケットし放題フラット)加入が必須になっています。そして、このパケットし放題フラットは月額5700円もする(もちろん、他に基本料もかかる)。タブレット(iPad)を持っているのに、スマホでパケット定額の元が取れるほど大量の通信をすることが、果たしてあるんでしょうかね。結局、あわせれば月額1万円近い金額になる。※今年5月までは、タブレットセット割の月額料金は、1000円台だったようです。が、そうだとしてもスマホとあわせればやっぱり月額8000円くらい。一方、私のように「ガラケー+スマホ」をソフトバンクでやると、ガラケーはホワイトプランで月1008円、iPad air単独の契約で5615円、合計623円。むしろこっちの方が安く上がるようです。でも、月6600円です。私のようにガラケー+MVNOだと、3000円未満。端末代の差を考えに入れても、間違いなくこっちの方が安いのです。もちろん、MVNOは、高速通信できる量が限られています。私が契約しているIIJmioの972円のプランだと、高速通信は月1GBまでです。でも、私の場合、これまでこの量で足りないと感じたことはない上に、高速通信を切って低速で使っていても、それほど極端に使いにくいという感じはしません。最近は、MVNOから通話可能なプランも登場しています。IIJmioからも、通話+インターネット(高速通信は1GB)で1728円というプランが出ています。ドコモ+MVNOより、更に1200円も安いじゃないか!でも、以前の記事に書いたように、MVNOではテザリングができないスマホが多い(iPhoneはみんなそう)ので、この場合は通話もネットもスマホ1台で、ということになります。更に、留守電機能がない。iモードメールも使えない。私がドコモから抜けると相棒の携帯が家族割が利かなくなる、無料通話がない(通話とiモードメールをあわせて、月に500円から700円分くらいは使っています)などの条件を考え合わせると、それほど得にはならないようです。いずれにしても、です。MVNOはずいぶん安い値段ですが、いずれもドコモから回線を借りて営業しているわけです。(最近、auの回線を使うMVNOも登場したが)ドコモがMVNOに貸し出す回線使用料は、国の指導で安く押さえられているのでしょうが、それにしても、少なくとも赤字ではないはずです。そして、MVNOも、自社の営業利益を乗せた上で、月額1000円未満の料金を提示しているはずです。ということは、3大キャリアは、いったいどれだけの暴利を得ているんだ、ということになります。その暴利はシェア増大のキャッシュバックなどにつぎ込まれているのでしょうか。とすれば、私のように10年以上もずっとドコモを使っているユーザーは、いいようにむしりとられているだけ、ということになりそうです。もっとも、月1900円では、むしりとられているうちにも入らないかもしれないけど。
2014.07.05
コメント(2)
-
恣意的な調査結果?
世論調査の選択肢づくり産経新聞社とFNNの合同世論調査で、集団的自衛権行使を全面的に容認する回答が11.1%、必要最小限度の行使を認める回答が52.6%という結果が出ました。安倍政権は限定容認論の立場をとっているので、この2つの回答を合わせた63.7%が今回の与党の方針に賛成しているとみていいでしょう。一方、他紙をみると、単純に賛成か反対かの二者択一で問うている調査があり、「反対」が多いという結果が出ています。しかし、これでは集団的自衛権をあらゆる場面で行使することに反対なのか、きわめて限定的な行使にすら反対なのかあいまいです。本当の世論を浮き彫りにするためには、きめ細かな選択肢の提示が必要なのです。恣意的な調査結果を導き出さないよう選択肢づくりには工夫が欠かせません。---恣意的な紙面づくりが大好きな産経が、他紙を恣意的だと揶揄していますが、「安倍政権は限定容認論の立場をとっているので、この2つの回答を合わせた63.7%が今回の与党の方針に賛成しているとみていいでしょう。」という分析こそ、恣意的の最たるものでしょう。ほぼ時を同じくして、産経と同じく集団的自衛権を推進してきた読売新聞の世論調査結果が公表されています。集団的自衛権、事例は理解・総論慎重…読売調査読売新聞社は2~3日、集団的自衛権の行使を限定容認する新たな政府見解の閣議決定を受け、緊急全国世論調査を実施した。政府が集団的自衛権の行使にあたるとした8事例のうち、海上交通路周辺での紛争中に、自衛隊が国際的な機雷掃海活動に参加できるようにすることに「賛成」と答えた人は67%に上った。紛争中の外国から避難する邦人を乗せた米輸送艦を自衛隊が守れるようにすることについても「賛成」が67%だった。一方、集団的自衛権を限定的に使えるようになったことについては、「評価する」が36%で、「評価しない」は51%と半数に上った。限定容認によって、日米同盟が強化され、抑止力が高まると思う人は39%で、「そうは思わない」が49%。政府が集団的自衛権を巡る問題を国民に十分に説明していないと思う人は81%を占め、理解が広がっていないことが浮き彫りとなった。---推進派の読売としては、「理解が進んでいない」ことにしたい気持ちは分からんではありませんが、「集団的自衛権を限定的に使えるようになったことについては、「評価する」が36%で、「評価しない」は51%と半数に上った。」ということは、63.7%が与党の方針に賛成しているという産経の分析は、大ハズレ、ということになります。やはり、政府が行った「限定容認」に対して、反対多数ということは間違いない。もちろん、これは、憲法改正の発議→国民投票という正しい手続きを取らず、閣議決定で解釈変更という裏口入学的手法をとったことに対する、手続き面の批判も含んだ数値ではあるのでしょうが。ちなみに、自衛隊が国際的な機雷掃海活動に参加できるようにすることと、紛争中の外国から避難する邦人を乗せた米輸送艦を自衛隊が守れるようにすることには賛成多数だとありますが、これらの事例は実際には個別的自衛権で対処できる問題だと言われており、実際機雷掃海活動については実例もあります。もっとも、紛争中の外国から避難する邦人を米国が輸送してくれることなど、現実には起こらないと思いますけどね。過去、世界では様々な国際紛争があって、日本人が現地から避難しなくてはならない事態は多々ありましたが、米軍が日本人の避難のために輸送艦なり輸送機なりを差し回したことなどあったでしょうか。
2014.07.03
コメント(4)
-
そこまでして米国に尽くしたいか
苦節35年、集団的自衛権の時がきた 元駐タイ日本大使・岡崎久彦ついに集団的自衛権の行使容認が閣議決定された。35年間、待ちに待った決定である。私が防衛庁に勤務していた1980年ごろ、ソ連艦隊はベトナムのカムラン湾に基地を構えて、南シナ海の航行を脅かした。イラン・イラク戦争が勃発して、ペルシャ湾の航行も脅かされていた。この日本にとって死活的な重要性のある、東京湾からペルシャ湾までのオイルルートの防衛は米国第7艦隊の任務だった。それは楽な勤務ではなかった。甲板上は昼は40~50度となり、当時の船の冷房では、夜もろくに気温は下がらず、ゆっくり眠って体を休めることもできなかった。当時来訪した横須賀基地の米軍司令官は私に訴えた。「そういう辛い任務をしていると、来る船来る船日本のタンカーだ。私には日本の政治事情は分かるが、水兵たちには分からない。どうして日本の海上自衛隊はパトロールに参加しないのだと不平が収まらない。そういう状況だということだけは分かってほしい」と。しかし、海上自衛隊はパトロールに参加できなかった。自分の艦は守れても、一緒に行動している米艦は守れない。また、日本の船は守れても、米国やアジア諸国の船は守れない。さらに、日本の船なるものがない。ほとんどがリベリア船籍かパナマ船籍である。それを守れるかと法制局に聞けば、集団的自衛権行使の疑いがあると言われてしまう。当時の解釈ではそれでおしまいだった。奇妙なことに、今回の集団的自衛権論議の最中に、ここにあるような事例は事実上ほとんど解決されてしまった。反対論は、何も集団的自衛権と言わなくても、個別的自衛権で解決できるではないかという議論が中心となった。確かに日本にとって死活的な石油ラインを守るための米艦の防護であり、外国籍でも日章旗を掲げた船を守るためであるならば、個別的自衛権でもよいという拡大解釈はあり得る。従来の政府解釈を現実に即して変更するというのなら、現在政府がとっている立場とほとんど同じであり、国民的総意は既にできているといってよい。いずれにしても、政府解釈の変更はもう決まったのだから日本はパトロールに参加できる。ただ、具体的な武力行使となると場合によっては法律の整備が必要となる。関連法案提出は政府の公約であり、この秋に整備されよう。ただ、その前でもパトロールには参加できるし、参加すべきである。慎重を期せば、法的に問題のある武力行使は、法整備までは米側に任せておけばよい。参加するだけで抑止力になるし、世界最高を誇る日本の哨戒能力だけでも参加の価値がある。何よりも、米軍とともに汗を流すことが同盟の絆を固める。これで、35年間失われていた海上自衛隊への信頼が回復し、日米同盟は強固になり、日本国民の安全がそれだけ高まるのである。私個人の感触では、それにとどまらない。もしあの時、海上自衛隊が常時パトロールに参加していたら、日本人の規律、能力が抜群であることは誰の目にも明らかに映り、また、沿岸のアジア諸国にとって脅威となるような海軍でないことも明らかになっていたであろう。東南アジアは、日本が戦後半世紀以上営々として経済、技術協力の面で貢献してきた金城湯池であるにもかかわらず、日本は政治、軍事面では無能力者だとこの地域で思われてきたが、そのイメージを払拭できる。(以下略)---岡崎と言えば、安倍のブレーンであり、安保法制懇のメンバーでもある。以前の記事で指摘したように、インタビューで「自衛隊は戦争する軍隊になりますよ」と断言した人物でもあります。その岡崎の書いているこの文章を読むと、彼が「いかに米国様に忠誠を示すことが日本の安全保障にとって重要か」という視点しかないことが分かります。それは楽な勤務ではなかった。甲板上は昼は40~50度となり、当時の船の冷房では、夜もろくに気温は下がらず、ゆっくり眠って体を休めることもできなかった。というのは、そこを航行している商船も同じだとしか思えません。旧ソ連がベトナムのカムラン湾に基地を置いていたといいますが、そこに派遣されていた艦隊は規模も小さく、米国の海軍力に対抗できるような代物ではなかったし、そもそも米ソが直接戦争を行っていたわけではなく、まして日本自身がソ連とことを構えるべき必然性などあるわけもなかったのですから、そんなところで軍(あるいは自衛隊)が商船を護衛しなければならない必然性などなかったのです。それに対して、イランイラク戦争は、現に戦争が行われており、タンカーが攻撃される事態があったことは事実です。でも、当時、米ソフランスを中心に、東西問わず、世界中の主要国が、もっぱらイラクを援助していました。米国は、イランと激しく対立していたし、何度か実際に戦火を交えています。その中で、日本は、米国との同盟関係はあれど、イランとも、友好国、とまでは言わないけれど、そう悪くはない関係を維持していた。かと言って、イラクと敵対してしていたかというと、そうでもなく、イランイラク間でいわば等距離の関係を保っていました。もし、海上自衛隊が米海軍と共同でペルシャ湾をパトロール、ということになったら、それは実質的には米国の対イラン対決政策の一端を担う、ということになったはずです。少なくとも、イランはそう見なしたでしょう。そうすることが、日本にとって望ましい選択だったようには、私には思えないのです。それにしても、1980年代、今からわずか30年前です。当時米国は旧ソ連と敵対し、日本も同様でした。ベトナムも、ソ連の同盟国ですから、日本との関係は良くなかった。逆に日中は友好関係にありました。イラクは米国(だけではないが)の援助を受けていた。たった30年で、なんという激変でしょうか。それから10年と経たずに、イラクは米国の不倶戴天の敵になった。日ロ間には今も北方領土問題はあるけど、かつてのような対立はなく、ベトナムとは、友好国同士のような状況です。逆にその15年前は、日中は敵対関係だったし、そもそも70年前には日米は戦争をしていました。つまり、国際関係は永久不変ではない、ということです。米関係が大事だ、というのは分かります。しかし、その米国と軍事的に一体の関係を永久に維持し続けることが日本のためである、というのは、ある種の思考停止としか思えません。戦後日本政府は、米国が行った対外戦争をただの一度たりとも批判せず、常に支持してきました。しかし、それでも実際に米軍と共同で軍事行動を行うようなことだけは、なかった。その最後の一線が取り払われてしまった今、日本は本当に米軍と一緒に軍事行動を起こすかもしれない。自衛隊が戦争をする軍隊になることを求めてやまぬ岡崎にとっては、それは大いなる喜びかもしれないけれど、日本が取るべき道としては、大間違いであるとしか、私には思えません。
2014.07.02
コメント(4)
-

裏口から憲法改正
集団的自衛権の行使容認=憲法解釈変更を閣議決定―安保政策、歴史的転換政府は1日午後、首相官邸で臨時閣議を開き、集団的自衛権の行使を容認するための憲法解釈変更を決定した。自衛隊の海外での武力行使に道を開くもので、「専守防衛」を堅持してきた戦後日本の安全保障政策は歴史的転換点を迎えた。憲法改正によらず、権利を保有していても行使できないとしてきた従来の政府解釈と正反対の結論を導き出した手法も含め、安倍政権は説明責任を問われる。安倍晋三首相は閣議決定を受けて記者会見し、集団的自衛権の行使容認の狙いについて「いかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らしは守り抜いていく」と説明。日米同盟が強化され、抑止力が高まるとして「戦争に巻き込まれる恐れは一層なくなっていく」と述べた。政府内に法案作成チームを設置し、自衛隊法改正案など関連法案策定作業に直ちに着手する方針を明らかにした。憲法解釈変更に関しては「現行憲法の基本的考え方は今回の閣議決定でも何ら変わらない。海外派兵は一般に許されないという従来の原則も全く変わらない」と強調。「日本が戦後一貫して歩んできた平和国家の歩みは変わることはない」とも語った。一方、公明党の山口那津男代表は国会内で会見し、自民党との合意を経た閣議決定について「(行使に)厳格な歯止めをかけられた」と評価。「国会審議を通じて国民に趣旨を理解してもらえるよう説明を尽くしていく」と述べた。閣議決定の核心は、自衛権発動の要件緩和だ。従来は「わが国に対する急迫不正の侵害の発生」としてきたが、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」で、国民の権利が「根底から覆される明白な危険がある場合」は自衛権を発動できると改めた。他に適当な手段がないことと、必要最小限度の実力行使にとどめることとした要件は維持した。---今更繰り返すのも気がひけまはすが、集団的自衛権とは、他国が攻撃を受けた場合に、それを自国に対する攻撃とみなして反撃する権利のことです。自国が攻撃されているわけでもないのに参戦するわけですから、本質的に関わる必要のない戦争に関わるという話です。それが「戦争に巻き込まれる恐れは一層なくなっていく」とは、悪い冗談としか思えません。「いかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らしは守り抜いていく」ために必要なのは、「自国が攻撃を受けたら撃退する(個別的自衛権)」ことであって、集団的自衛権ではない。要するに、黒いものを白だと言い張っているようなものと私には思えます。そもそも、憲法は、他の法律とは違って、国家の根幹を定めた法律です。だからこそ、改正要件は厳密に定められていて、国会の両院の発議によって国民投票にかけることになっているわけです。ところが、憲法の条文の字面を変えることなく、その解釈を変えて、事実上の憲法改正を行ってしまう。国会の発議も国民投票もなく、閣議の決定だけで、黒いものを白だと言い換えるような解釈の変更を行う。裏口入学のようなものです。憲法を変えるのは敷居が高いから解釈を変える、もっともらしいですが、入学試験を受けても合格できる学力がないから裏口入学します、と言っているようなものです。こういうやり口に関して、私には「卑劣」という以外の言葉を思いつきません。遅ればせながら、首相官邸前の抗議行動に参加してきましたので、その写真など。国会議事堂このあたりから、人があふれて、前に進むのが至難の業になりました。それでも、少しずつ進む。地下鉄の国会議事堂前駅の出入り口付近。やっと、ほぼ先頭付近までたどり着きました。横断歩道の向こう側は、全部警察。これも結構な人数でした。抗議の隊列の一番先頭付近。そして、その先に・・・・・・安倍がいる(この時間に、実際にいたかどうかは知りませんけど)首相官邸。これ以上近づくことは不可能です。そのうち、ここが大本営になるんだろうか。
2014.07.01
コメント(0)
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-
-

- みんなのレビュー
- 気になっていた寝ホンをついに購入!…
- (2025-11-25 20:44:46)
-
-
-
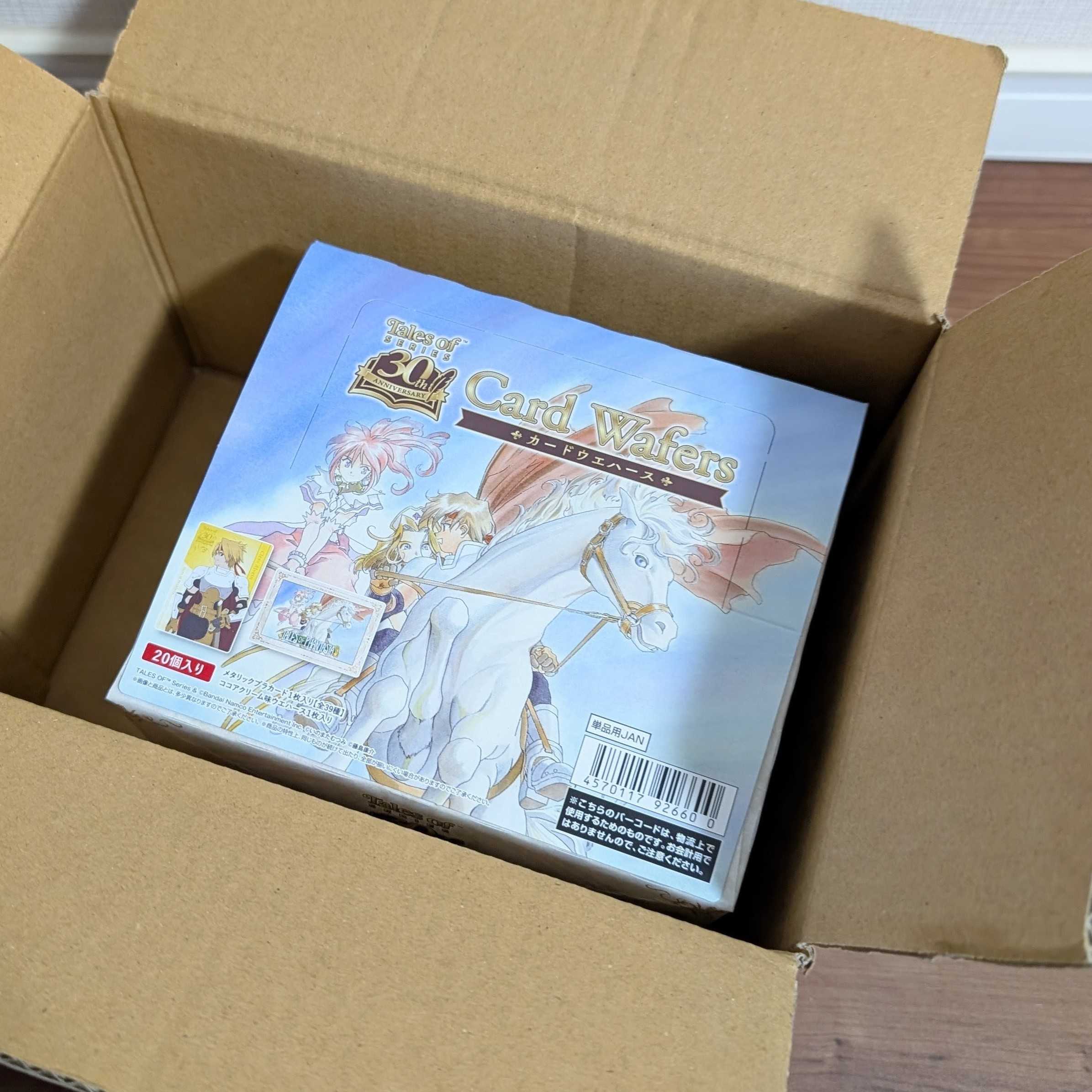
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 【楽天】人生初!胸アツ買いのテイル…
- (2025-11-25 21:50:38)
-
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 決断する時は、こうするのです。
- (2025-11-25 08:54:08)
-







