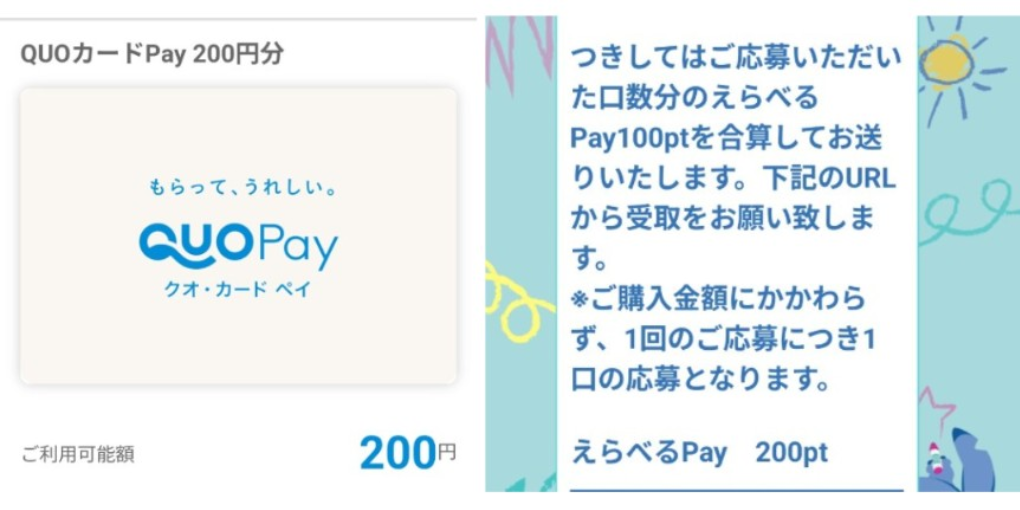2013年11月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
京都はじまり物語(感想)
トイレ、映画、学校、サッカー、喫茶店などなど、その発祥はみな京都だったそうです。 ”京都はじまり物語”(2013年9月 東京堂出版刊 森谷 尅久著)を読みました。 1200年の歴史を紡ぐ京都発祥のものごとがいろいろ紹介され、古都が紡ぎだす68ものはじまりの物語が描かれています。 森谷尅久さんは、1934年京都市生まれ、立命館大学大学院文学研究科修士課程修了、都市文化史、生活文化史、情報文化史を専攻、京都市歴史資料館初代館長、京都市文化財保護審議会委員、平安建都1200年記念協会理事、京都大学講師などを経て、武庫川女子大学名誉教授です。 京都の文化をはじめ、祭事、歴史、風俗における第一人者です。 京都は日本で最も古い伝統と歴史を受け継いできた街です。 その長い歴史をひもといてゆくと、私たちの身近にあるさまざまな文化や祭事、遊び、衣食住に関わるはじまりの多くが京都にあったことに気づきます。 古代から歴史と文化の中心地で、天皇、公家、僧侶、武将など、各時代の最高の文化人が集まっていたのだから当然です。 地理的にも、三方を山に囲まれた典型的な盆地であったため、独特の気候風土が生まれ、そこから京都ならではの野菜や特産品や独特の食文化も育まれました。 そして、古い伝統を重んじながら、新しもの好きの京都人は、斬新な文化を生みだしてきました。 京都は昔から、伝統的なものと相反するような若者文化の発祥地でもあります。 京都検定の監修者として、京都ほど歴史的遺産や伝統芸能、衣食住の文化が豊かな街はないと感じます。 そこで、全国に先駆けて京都が発祥となった事物について集めてみたそうです。 古くは記録が残されておらず詳細が不明なものや、発祥の地がいくつも存在するもの、京都が発祥と断定できないものもあります。 それゆえ、異論を唱える方もおられるでしょう。 この後、新たな発見があって別の発祥説が登場するかもしれません。 平安時代から現在に至るまで、伝統を重んじながら進取の気質に富んできた京都の新たな魅力を感じていただきたい、といいます。1章「食」の発祥物語 松花堂弁当/京都三大漬物-しば漬、千枚漬、すぐき漬け/肉じゃが/にしんそば/鯖寿司/いもぼう/湯葉/饅頭/みたらし団子/フランスパン/湯豆腐2章「暮らし」の発祥物語 トイレ/公衆トイレ/銭湯/喫茶店/中央卸売市場/町内会3章「娯楽」の発祥物語 九九の始まり/かるた/能楽/歌舞伎/落語/囲碁/映画/流鏑馬4章伝統・文化の発祥物語 茶の栽培/絵馬/葉書/華道/舞妓・芸妓、花街、お茶屋5章 服飾文化の発祥物語 友禅染/養蚕/西陣織・絹織物/風呂敷/扇/丹後ちりめん/学生服・セーラー服6章「物づくり」の発祥物語 島津製作所-気球、レントゲン、蓄電池、人体解剖模型/琵琶湖疏水、水力発電所/鉄筋コンクリート建築/貨幣鋳造所/近代医学/電車7章 学問・スポーツの発祥物語 学校-小学校、中学校、女学校、幼稚園、庶民のための私立学校/図書館/音楽学校/盲学校・聾唖学校/駅伝/国民体育大会/サッカー/競馬8章 建築文化の発祥物語 茶室/町家/書院造り/法堂/寝殿造り/能舞台/障子/神社建築
2013.11.26
コメント(0)
-
80時間世界一周(感想)
ジュール・ヴェルヌの80日間世界一周はよく知られているが、80時間世界一周とはどんなものであろうか。 ”80時間世界一周”(2012年3月 扶桑社刊 近兼 拓史著)を読みました。 格安航空会社と大手航空会社のディスカウントチケットを組み合わせて、80時間で世界一周したレポートです。 近兼拓史さんは、1962年神戸生まれのライターで、1985年よりフリーライターとして活動し、1990年に地元Kiss-FM神戸の設立より番組制作、脚本ライターを務め、放送分野で活動し、その後、ウィークリー・ワールド・ニュース・ジャパン編集長、ラルースパブリッシングCEO、インターナショナル・スクール・オブ・モーションピクチャーズ日本事務局長を務めています。 80日間世界一周は、イギリス人資産家フィリアス・フォッグが執事のパスパルトゥーを従え、後期ビクトリア朝時代の世界を80日で一周しようと試みた波瀾万丈の冒険物語でした。 それから140年経った2012年に、今度は、格安航空会社と大手航空会社の飛行機を使って、80時間で世界一周しようという試みです。 茨城空港からスタートして、上海、モスクワ、デュッセルドルフ、チューリッヒ、ニューヨーク、ロサンゼルス、そして羽田へと、5カ国6都市を、機中泊中心に0泊3日半で回ったそうです。 最初のコース設定と、その間のLCCチケットの確保が、とても大変だったといいます。 時差や乗り継ぎを自分で計算して、最速乗り継ぎと最安価格を計算したそうです。 航空運賃は、底値限界値の13万円くらいでした。 短い滞在時間で入出国を繰り返したため、運び屋やテロリストと間違われたこともあったといいます。 ほとんどの時間を飛行機での移動に費やすため、肉体への負担もハンパではありませんでした。 LCCは機内食がなく野菜が取れなかったので、サプリメントやビタミン剤は必携かも知れないといいます。 機中泊だけでは疲労が溜まるので、途中どこかで1泊するとか、空港の仮眠施設を利用すれば、体調の維持も可能ではないかということです。 しかし、駆け足で回ったからこそわかる世界の国々の文化の違い、LCCの上手な活用法など、面白くて役に立つ内容も少なくないようです。第1章 チケット手配はジグソーパズル!第2章 さらばニッポン!茨城空港から上海へ第3章 アエロフロートで、いざモスクワ!第4章 ドイツでご先祖様に会う!第5章 チューリッヒで路頭に迷う!第6章 トラブル・イン・USA!
2013.11.18
コメント(0)
-
一度は乗りたい絶景路線(感想)
鉄道ファンには、乗りテツ、撮りテツ、模型テツ、収集テツなど様々な楽しみ方があります。 一般の人にも受け入れやすいのは乗りテツ、すなわち鉄道旅行だと思われます。 乗りテツの原点は、やはり美しい車窓風景に見とれることではないでしょうか。 ”一度は乗りたい絶景路線”(2009年9月 平凡社刊 野田 隆著)を読みました。 この本は、初心者でも分かるように、乗りテツについてコンパクトにまとめたものです。 絶景車窓を求めて経験豊富な旅行作家がイチオシの必乗路線を紹介しています。 野田隆さんは、1952年愛知県名古屋市生まれの旅行作家で、早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院前期課程修了後、長らく都立高校の教諭を勤めていましたが、2010年3月で退職、以後フリーランスで活動しています。 まとめ方は、地域別にするのも一案でしょうが、ここでは、川、海、山といった車窓から眺められる地形別にオススメ路線を取り上げています。 大方の列車は、絶景地点をあっけなく通り過ぎてしまいます。 見逃してしまっても後の祭りなので、路線図を中心に地図をチェックし、沿線情報をキャッチし、乗る列車をチェックすることをお勧めします。 普通列車で普通の座席しがない場合は、誰も何も教えてくれないでしょうから、進行方向のどちら側に座ったらいいのか、自分で調べる必要があります。 指定席を予約する場合は、左右どちらの座席をゲットしたらよいか、決めなくてはなりません。 満席の場合も考慮して、列車にフリーラウンジのようなフリースペースがないかどうかチェックしておきましょう。 このようなポイントを知っているかいないかで、車窓の楽しみ方はかなり変わってきます。はじめに──絶景を求めて車窓の旅に出ようPART1 川を楽しむ1 新緑きらめく千曲川を遡って──飯山線2 飛騨川、渓谷美を満喫する旅──高山本線3 「究極のイヴェント車両」から眺める清流・吉野川──徳島線コラム 日本三大車窓1 姨捨(篠ノ井線・長野県)PART2 海を楽しむ4 海と馬と昆布の車窓──日高本線5 海辺をたどり紀伊半島ぐるり一周──紀勢本線・参宮線6 山陰の潮騒と詩情、そして絶景──山陰本線コラム 日本三大車窓2 真幸~矢岳(肥薩線・宮崎県&熊本県)PART3 山を楽しむ7 雄大、壮大、火の国横断の旅──豊肥本線8 車窓に迫る「日本の屋根」を堪能する──中央東線・大糸線9 山岳路線ならでは、ループ線と長大トンネルを楽しむ──上越線コラム 日本三大車窓3 狩勝峠(根室本線・北海道)PART4 花を楽しむ10 房総の春は菜の花に満ちて──いすみ鉄道11 桜さくら、お花見は車窓から──御殿場線、東北本線12 首都圏で紅葉狩りを楽しむ──箱根登山鉄道、JR青梅線コラム モノレール&新交通システムは身近な穴場
2013.11.11
コメント(1)
-
諸国一ノ宮山歩(感想)
一ノ宮は、平安末期から中世にかけて、民間でつけられた社格の一種です。 由緒正しく最も信仰のあつい神社で、その国で第一位とされたもので、武蔵国の氷川神社、下総国の香取神宮など、各地に地名として残っています。 ”諸国一ノ宮山歩”(2012年7月 風媒社刊 若宮 聡著)を読みました。 東海、近畿、中国、四国、九州、北陸、関東、東北まで全国にある一ノ宮とその背後にある鎮守の森を紹介しています。 若山聡さんは、1957年愛知県海部郡佐織町生まれ、岐阜大学大学院修了、天王文化塾塾生、鍋の会会員、元日本山岳ガイド協会認定ガイドです。 通常単に一ノ宮といった場合、令制国の一ノ宮を指すことが多いです。 一ノ宮の次に社格が高い神社を二ノ宮、さらにその次を三ノ宮のように呼び、一部の国では四ノ宮以下が定められていた事例もあります。 選定基準を規定した文献資料はありませんが、一定の形式があるとされています。 原則的に、令制国1国あたり1社を建前にしていました。 祭神には国津神系統の神が多く、開拓神として土地と深いつながりを持っていて、地元民衆の篤い崇敬対象の神社から選定されたことを予測できます。 全て927年に制定された延喜式神名帳の式内社の中から選定された1社ですが、必ずしも名神大社に限られていません。 必ずしも神位の高きによらないで、小社もこれに与かっています。 また、諸国一宮が少なくても、次のようなそれぞれ次元を異にする3つの側面を持つとされています。 氏人や神人などの特定の社会集団や地域社会にとっての守護神であり、一国規模の領主層や民衆にとっての政治的守護神であり、中世日本諸国にとっての国家的な守護神です。 律令制において国司は任国内の諸社に神拝すると定められていて、通説では一ノ宮の起源は国司が巡拝する神社の順番にあると言われています。 律令制崩壊の後も、その地域の第一の神社として一ノ宮などの名称が使われ続けました。 現在ではすべての神社は平等とされていますが、かつて一ノ宮とされた神社のほとんどが何々国一宮を名乗っています。 江戸時代初期の神道者・橘三喜が、1675年から23年かけて全国の一宮を参拝し、その記録を”諸国一宮巡詣記”全13巻として著し、これにより多くの人が一宮の巡拝を行うようになったといいます。 その後、明治時代に明治政府が天皇陛下を中心とした絶対君主制を裏付けようとして、人々が崇める神社を一ノ宮として国家が格付け管理しました。 本書は、全国各地に存在する由緒ある神社”一ノ宮”とその御神体の山を訪ねた記録集”諸国一ノ宮山歩”をまとめたものです。 著者による山の難易度と山の霊力度が、各項の巻末に入れられています。山の難易度:★ 歴史散策のみ、ハイヒールでも可★★ 軽いハイキング、スニーカーが望ましい★★★ 一応登山(初心者向き)、軽登山靴が望ましい★★★★ 本格的な登山(初級者向き)、山の知識が必要★★★★★ 登山中級者向き、十分な山の知識が必要山の霊力度:☆ 数歳若返ります☆☆ 5歳若返ります☆☆☆ 10歳若返ります一ノ宮って、何?・東海地方の一ノ宮巡り 1.愛知県の一ノ宮巡り 尾張国一ノ宮 尾張国二ノ宮 尾張国三ノ宮 三河国一ノ宮 三河国三ノ宮 2.岐阜県、長野県の一ノ宮巡り 美濃国一ノ宮 美濃国二ノ宮 美濃国三ノ宮 騨国一ノ宮 信濃国一ノ宮 3.三重県の一ノ宮巡り 伊勢国一ノ宮 伊勢国二ノ宮 志摩国一ノ宮 伊勢神宮 伊賀国一ノ宮 4.静岡県、山梨県の一ノ宮巡り 遠江国一ノ宮 駿河国一ノ宮 甲斐国一ノ宮 伊豆国一ノ宮・近畿地方の一ノ宮巡り 1.京阪神の一ノ宮巡り 山城国一ノ宮 近畿地方一ノ宮 河内国一ノ宮 丹波国一ノ宮 丹後国一ノ宮 2.奈良県、和歌山県の一ノ宮巡り 大和国一ノ宮 紀伊国一ノ宮 3.兵庫県の一ノ宮巡り 播磨国一ノ宮 但馬国一ノ宮・西日本の一ノ宮巡り 1.中国地方の一ノ宮巡り 安芸国一ノ宮 中国地方一ノ宮 2.四国地方の一ノ宮巡り 阿波国一ノ宮 伊予国一ノ宮 四国地方一ノ宮 3.九州地方の一ノ宮巡り 肥後国一ノ宮 九州地方一ノ宮 薩摩国一ノ宮・北陸・関東地方の一ノ宮巡り 1.北陸地方の一ノ宮巡り 加賀国一ノ宮 北陸地方一ノ宮 越中国一ノ宮 越後国一ノ宮 2.関東地方の一ノ宮巡り 下野国一ノ宮 関東地方一ノ宮 上野国一ノ宮・東北地方の一ノ宮巡り 1.東北地方(陸奥国)の一ノ宮巡り 東北地方の一ノ宮 岩代国一ノ宮 陸中国一ノ宮 津軽国一ノ宮 2.山形県(出羽国)の一ノ宮巡り 出羽国一ノ宮 出羽三山
2013.11.05
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1