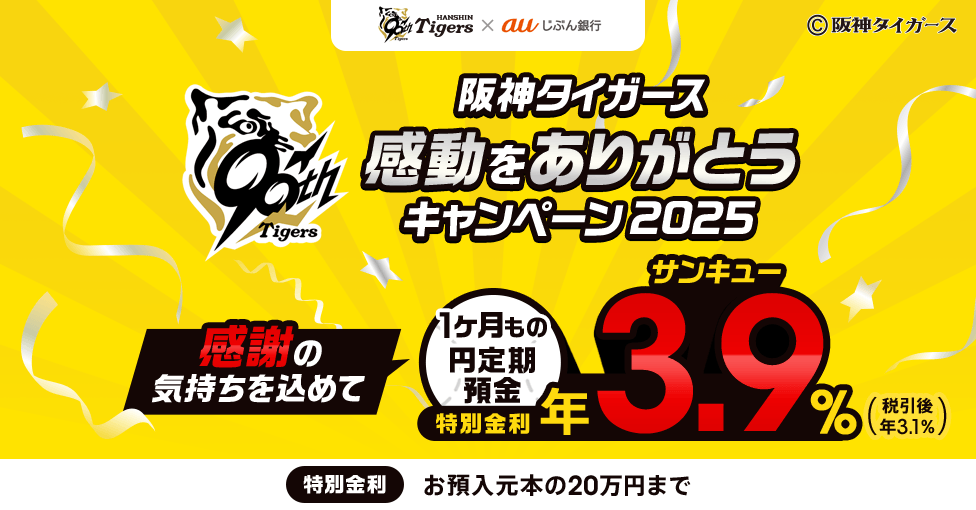2017年06月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
沖縄・奄美の小さな島々(感想)
沖縄県は日本で最も西に位置する県で、沖縄本島を中心に363の島々から構成されています。 沖縄諸島は南西諸島の中央部に位置し、琉球諸島北半分を占める島嶼群です。 明治時代から1972年の本土復帰まで沖縄群島と呼称されていましたが、復帰後は沖縄諸島に統一されて呼ばれるようになりました。 ”沖縄・奄美の小さな島々 ”(2013年7月 中央公論新社刊 カベルナリア吉田著)を読みました。 最初からガクッとつまずく島の旅で、沖縄・奄美でもローカルな島ばかり歩いた旅のエッセイです。 沖縄諸島は、沖縄本島をはじめ、本島の北西海上に位置する伊平屋伊是名諸島、勝連半島沖の与勝諸島、慶良間諸島や久米島などの島々を範囲に含みます。 また、沖縄本島の東方海上約400kmに位置する大東諸島は、琉球弧に含まれないため、地理学上では沖縄諸島に属さないことがありますが、行政的には含まれるのが一般的です。 奄美大島は九州南方海上にある奄美群島の主要な島で、単に大島ともいいます。 本州など4島を除くと佐渡島に次ぎ面積5位の島で、大きな方から順番に、択捉島、国後島、沖縄本島、佐渡島、奄美大島となっています。 年間の日照時間が日本一短く、大島海峡沿岸や湯湾岳などは奄美群島国立公園の一部となっています。 指定区域に含まれる島には、奄美大島、加計呂麻島、請島、与路島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島があります。 大きく揺れ動き変動しているのは沖縄本島だけでなく、瀬底、多良間、鳩間等の小さな島から奄美までも同じような傾向が見られる、といいます。 ローカルな島々を歩き回って、現地の人と触れあい島のいまを伝えています。 カベルナリア吉田さんは1965年札幌市生まれ、早稲田大学卒業、読売新聞社、女性雑誌、情報雑誌で編集の仕事を行い、2002年よりフリーとなりました。 航空会社機内誌、島旅雑誌、旅行ガイドなどにエッセイを提供しています。 沖縄を自分の足で隅々まで歩き、沖縄のいまを見たいという気持ちで沖縄旅を重ねています。 最近は、基地問題や再開発による街づくりなど時事、社会問題をテーマに歩くことが増え、気がつくと沖縄本島ばかりを歩いていたどうです。 島を歩くのを忘れていたわけではありませんが、長い間ご無沙汰してしまった島がたくさんあるとのことです。 2003年に沖縄の有入46島を全て歩き、その旅を本にまとめました。 そして、2005~2006年にかけて沖縄を自転車で走り、歩いて旅するには大きな島を中心に、いくつかの島を歩きました。 それ以来、沖縄の島だけを歩く旅をしていません。 この10年で沖縄の社会情勢と、観光を取り巻く環境は大きく変わりました。 リゾートが出来たり出来なかったりで島が観光化され、手つかずの風景が荒れ、島人の濃密なコミュニティにもヒビが入ることもあります。 のどかな風景にちらりと映る暗部が気にかかります。 島は本来あるべき姿から逸脱しつつあるのではないでしょうか。 そして、変わりゆく島の姿は日本全体の縮図かもしれません。 基地、尖閣問題が本土でも連日報道される一方で、ドラマ人気により八重山人気が爆発、そして収束しました。 移住人気も一緒に盛り上がった、と思ったら沈静化しました。 10年前に島を旅したときは、海と空の美しさにただ感動して、人がひたすら優しく見えて旅は終わりました。 久々に歩いたら、前は気づかなかった別の一面も見えてくるかもしれません。 そう思い、数年ぶりに沖縄の島旅に出ることにしたそうです。 観光化が進んでいない、小さな島を中心に歩こう。 そのほうが、よそ行きに飾っていない、島の素顔が見えるはずだからです。 そして、沖縄だけでなく、今回は奄美の島も歩こう。 奄美も元々は、同じ琉球王国に属していました。 沖縄にとどまらず、琉球を知るためには、奄美もそろそろ歩き始めたいです。 沖縄にも冬は来ます。 そして冬の間は海が荒れ、島行き船が予定通りに出ないことも多いです。 だから春になり空気が緩み始めたら、この旅を始めよう。 そう思ったのですが、3月の頭に沖縄はもう春だろうと思っていましたが、冬がグズグズと居座っていました。 伊是名島の玄関口仲田港は北西からの風に弱く、冬場はしばしば定期船が欠航します。 波5メートルでは、船はたぶん着かないでしょう。 でも、飛行機の時間が迫るのでとりあえず乗ろう。 その先のことは沖縄に着いてから考えよう。本島周辺 瀬底島/今度こそ伊是名島/伊平屋島・野甫島/屋我地島/与勝諸島(平安座島・浜比嘉島・宮城島・伊計島)/津堅島/慶留間島・外地島/奥武島/渡名喜島/粟国島宮古・八重山 池間島/下地島/多良間島/黒島/鳩間島奄美 加計呂麻島/請島/与路島
2017.06.25
コメント(0)
-
保科正之 民を救った天下の副将軍(感想)
名君の誉れの高い保科正之は徳川3代将軍家光の実弟で、1611年に2代将軍秀忠と乳母の侍女だったお静の間に生まれました。 正之の出生は、秀忠側近の老中、土井利勝や井上正就他、数名のみしか知らぬことであったといいます。 ”保科正之 民を救った天下の副将軍”(2012年11月 洋泉社刊 中村 彰彦著)を読みました。 会津藩領民に仁政を施し江戸復興を成し遂げた保科正之の、卓越した判断力とリーダーシップを紹介しています。 近世武家社会においては、正室の体面・大奥の秩序維持のため侍妾は正室の許可が必要で、下級女中の場合にはしかるべき家の養女として出自を整える手続きが必要でした。 また、庶子の出産は同様の事情で江戸城内で行なわれないことが通例で、幸松の出産は武田信玄の次女である見性院に預け、そこで生まれた幸松は見性院に養育されました。 見性院は武田家御一門衆で甲斐国河内領主穴山信君の正室でしたが、1603年に穴山武田氏は断絶し、見性院は家康、秀忠に庇護され江戸城田安門内の比丘尼邸に居住していました。 中村彰彦さんは1949年栃木県栃木市生まれ、東北大学文学部国文科在学中に第34回文學界新人賞佳作入選、大学卒業後の1973年から1991年まで文藝春秋に編集者として勤務しました。 1991年より執筆活動に専念し、1993年に第1回中山義秀文学賞、1994年に第111回直木賞を、2005年に第24回新田次郎文学賞を受賞しました。 主に、歴史小説・時代小説を中心に執筆し、会津関係の著作が多く、会津観光史学の一翼を担っています。 1617年に正之は信濃高遠藩主保科正光の養子となり、その後継者として育てられ、1631年に亡くなった正光の跡を継いで、高遠藩3万石の藩主となり、従五位下肥後守に叙任されました。 1632年に従四位下に昇叙し、肥後守は兼任留任しました。 1634年に兄将軍家光に供奉して上洛し、侍従に任官し肥後守は兼任留任しました。 その後、1636年に出羽山形藩20万石となり、さらに、1643年に陸奥会津藩23万石の藩主となり、会津南山5.5万石の幕領を預かりました。 1645年に左近衛権少将に転任し、肥後守は兼任留任し、その後、従四位上に昇叙し、左近衛権少将及び肥後守は留任しました。 そして、3代将軍家光、第4代将軍家綱の2代に亘って幕府の輔弼役を務めました。 1651年に家光最期に際し、後継将軍家綱の補佐を厳命されました。 1653年に従三位左近衛権中将に昇叙転任しましたが、従三位昇叙は固辞し、以後、会津中将の称を生じました。 その後、正四位下に昇叙し、左近衛権中将及び肥後守は留任しました。 サブタイトルの副将軍という身分は江戸時代にはなく、それは德川光圀を意識した呼称のようです。 保科正之は会津松平家初代で、徳川家康の孫にあたり、3代将軍家光の異母弟で、3代から4代にわたって幕閣に重きをなしました。 文治政治を推し進め、末期養子の禁を緩和し、各藩の絶家を減らしました。 会津藩で既に実施していた先君への殉死の禁止を、幕府の制度としました。 大名証人制度の廃止を、政策として打ち出しました。 玉川上水を開削し、江戸市民の飲用水の安定供給に貢献しました。 1657年の明暦の大火後、焼け出された庶民を救済しました。 一方、今後の大規模火災対策として、主要道の道幅を6間から9間に拡幅しました。 また、火除け空き地として上野に広小路を設置し、両国橋を新設、芝と浅草に新堀を開削、神田川の拡張などに取り組み、江戸の防災性を向上させました。 また、焼け落ちた江戸城天守の再建に際し、天守台は御影石により加賀藩主によって速やかに再築されました。 この時代の幕閣である、酒井忠勝、松平信綱、阿部忠秋なども、正之の建言を受けて、幕政において400万両超の蓄財を背景にして、福祉政策、災害救済対策、都市整備などに注力しました。 また、藩政にも力を注ぎ、留物令によって、漆・鉛・蝋・熊皮・巣鷹・女・駒・紙の八品目の藩外持ち出しを手形の有無で制限しました。 一方、許可なくしては伐採できない樹木として漆木を第一にあげるなど、産業の育成と振興に務めました。 また、飢饉時の貧農・窮民の救済のため社倉制を創設し、一方で産子殺しを禁止しました。 相場米買上制を始め、升と秤の統一を行いました。 藩士に対しては殉死を禁じ、朱子学を藩学として奨励し好学尚武の藩風を作り上げました。 また、90歳以上の老人には、身分を問わず、終生一人扶持、1日あたり玄米5合を支給しました。 正之は1668年に会津家訓十五箇条を定め、第一条に、会津藩たるは将軍家を守護すべき存在であり、藩主が裏切るようなことがあれば家臣は従ってはならない、と記しました。 以降、藩主、藩士は共にこれを忠実に守りました。 幕末の藩主・松平容保はこの遺訓を守り、佐幕派の中心的存在として最後まで薩長軍と戦いました。 正之は、同時代の水戸藩主徳川光圀、岡山藩主池田光政と並び、江戸初期の三名君と賞されています。第1章 将軍の御落胤、誕生/第2章 名君への道/第3章 天下の副将軍/第4章 真のリーダーシップが発揮された明暦の大火/第5章 諸藩の先駆けとなった会津藩政/第6章 会津に眠る/特別対談 山内昌之×中村彰彦
2017.06.19
コメント(0)
-
東京どこに住む? 所得格差と人生格差(感想)
人が住む場所はかつて郊外化や人口分散から閑静な郊外の住宅地でしたが、最近はにぎやかな都心に移行しています。 都市に人が集まるのは自然な現象ですが、家賃が高くても都心に住むメリットはなんでしょうか。 ”東京どこに住む? 所得格差と人生格差”(2016年5月 朝日新聞出版刊 速水 健朗著)を読みました。 東京に変化が起こりどこに住むかの重要性が高まっている時代での、都市暮らしの最新のルールを探っています。 速水健朗さんは1973年石川県生まれ、東海大学卒業、在学中よりアルバイトしていたアスキーにて契約編集者を務めた後、2001年よりフリーの編集者・ライターに転身しました。 コンピュータ関連の編集者出身ですが、メディア論、都市論から、ショッピングモール研究、団地研究、音楽、文学、格闘技まで幅広い分野で執筆編集活動を行っています。 江戸時代の江戸町人たちの長屋暮らしの人口密度に比べれば、いまの一極集中下の東京での都心の暮らしなんて、スカスカなものでしかない、といいます。 ほんのひと時代前までの日本人は、喧騒を離れて生きることが上等であると思っていましたが、昨今では、また久々ににぎやかな場所での暮らしが見直されています。 世界でも、ニューヨークを始めとする大都市が1970年代前後に迎えていた暗黒時代を抜け、都市再生の時代から、さらには都市復活の時代を迎えています。 東京でも、人は復活した都市に再び戻ってきて、都市生活を取り戻しつつあります。 日本人は引っ越しが嫌いで、生涯移動回数は4~5回くらいとなっています。 先進国の移動事情に比べると少なく、アメリカ人の生涯移動回数はこの4倍くらいです。 日本人には、1ヵ所に根付いた生活を送る文化が染みついています。 だが、これからの時代に、日本人は引っ越しを余儀なくされると思われます。 人口減少でこれまでどおりの経済活動の規模が維持できなくなる時代に、東京一極集中という名の人口移動が起きているからです。 都市人口が増えると、人口流動が増えるため、平均生涯移動回数は確実に上がっていきます。 さらに、人口減少が進むことによる不動産価格の変化があります。 人口が減る地域の地価は下がり続け、都心の価格はしばらく上がり続けることになるでしょう。 こうした環境の変化において、自発的にそこから移動をするかまたは定着を選ぶかで、人生は大きく変わってきます。 現代は都市間格差の時代へ変化しており、職業選び以上に、住む都市が人生の格差を生む時代です。 自分の置かれた状況を改善する手段として、住んでいる場所を変えることができるかどうかが問われているのではないでしょうか。 移動は、その人が持つ能力が試される機会でもあり、職業的能力、経済力、コミュニケーション力、テクノロジーヘの適応力が高い人であれば、どこに住もうと生きていけます。 また、より自分の生き方の好みに見合った場所を探し、楽しく生きられる場所を探して移動を続けていくことができます。 住む場所の選び方は千差万別ですが、住めば都とはよく言ったもので、人は誰しも、どんな街だろうと、住んでみることで満足できるというのは一面の真実です。 どの地にも文化があり、それがその人の将来に影響を及ぼします。 どこに住んだかで芽ばえる哲学や思想がありながら、そこに個人の事情が加わり、さらにその時代がもたらす事情が加わります。 人は、かつてよりも、住む場所に対してユーティリティーを重要視するようになっています。 ただし、コンビニに近いかどうかは、コンビニの数が飛躍的に増えたため、かつてほど便利さの指標にならなくなりました。 逆に減ったのがレンタルビデオ店で、いまどきはレンタルDVDは宅配や有料動画配信スタイルに移り変わり、住む場所とは無関係になりつつあります。 また最近では、スターバックスのような街の雰囲気を左右するチェーン店、また個性的でくつろげるカフェやワインバルがあるかどうかが重視されることもあります。 ユーティリティー以上に、街の個性が重視されているということかもしれません。 住む場所に関する最大のルール変化は、人口集中の原理です。 現在の人口集中は、これまでのそれとは性質が違っています。 かつての東京への人口流入は、東京の周辺部、つまり郊外への人口拡散を伴うものでした。 だが現在の人口集中は、都心部の人口増、つまり最都心部への集中です。 本書は、今起こっている東京への人口集中はどういったルールの変化、社会の変化がもたらすものなのかなどについて考察を行っています。第1章 東京の住むところは西側郊外から中心部へ/第2章 食と住が近接している/第3章 東京住民のそれぞれの引っ越し理由/第4章 なぜ東京一極集中は進むのか/東京内一極集中という現象/人口集中と規制緩和/景気上昇と人口集中/第5章 人はなぜ都市に住むのか
2017.06.11
コメント(0)
-
「新富裕層」が日本を滅ぼす(感想)
日本は世界の10%以上の資産を持っているのに、たった1億数千万人を満足に生活させられない国だそうです。 日本に必要なのは経済成長や消費増税ではなく、経済循環を正しくすることである、ということのようです。 ”「新富裕層」が日本を滅ぼす”(2014年2月 中央公論新社刊 武田知弘著/森卓郎監修)を読みました。 金持ちが普通に納税すれば消費税はいらないといいます。 武田知弘さんは1967年福岡県生まれ、西南学院大学経済学部を中退し、1991年にノンキャリア職員として大蔵省に入省しました。 1998年から執筆活動を開始し、1999年に大蔵省退官後、出版社勤務などを経てフリーライターとなりました。 森永卓郎さんは1957年東京都生まれ、東京大学経済学部を卒業し、1980年に日本専売公社に入社、1982年経済企画庁総合計画局へ出向しました。 1986年三井情報開発株式会社総合研究所へ出向、その後、三和総合研究所への入社を経て、2006年に獨協大学経済学部教授に就任しました。 今の日本人の多くは、現在の日本経済について大きな誤解をしているとのことです。 たとえば、あなたは今の日本経済について、こういうふうに思っていないでしょうか。 ”バブル崩壊以降、日本経済は低迷し国民はみんなそれぞれに苦しい。” ”金持ちや大企業は世界的に見ても高い税負担をしている。” ”日本では、働いて多く稼いでも税金でがっぽり持っていかれる。” ”その一方で、働かずにのうのうと生活保護を受給している人が増加し、社会保障費が増大し財政を圧迫している。” ”日本は巨額の財政赤字を抱え、少子高齢化で社会保障費が激増しているので消費税の増税もやむを得ない。” しかし、実はこれは全部、嘘なのであるといいます。 事実とは、むしろ正反対なのだそうです。 国や公的機関が発表している誰でも人手可能なデータを見るだけで、それがわかります。 たとえば、こういうことを言うと、あなたは信じられるでしょうか。 ”この10年で、億万長者が激増している。” これは、紛れもない真実であり、バブル崩壊以降、日本国民は皆苦しかったわけではなく、日本経済自体は悪くはなかったのです。 また、日本には実は世界的に見ても巨額の資産があります。 個人金融資産は1500兆円に達していますが、これもバブル崩壊以降に激増しました。 アメリカの3大投資銀行であるメリルリンチのレポートによると、金融資産を100万ドル以上持っている日本の富裕層は、ここ数年で激増しています。 2004年には134万人だった富裕層は、2011年には182万人になっているそうです。 182万人というのは、世界全体の富裕層の16.6%で、アメリカに次いで世界第2位です。 世界の人口の2%に満たない日本人が、世界の富裕層の16.6%も占めているのです。 そして、人口比率から見れば日本の方が富裕層が多く、日本は世界一の富裕層大国と言えます。 国税庁の確定申告データによると、個人事業者の年収5000万円超の者は、この10年で13倍以上になっています。 1999年にはわずか574人しかいませんでしたが、2008年には7589人に激増しています。 また、個人投資家の億万長者も激増していると思われます。 この10年間、国民のほとんどの収入は下がり続けてきました。 一方で、億万長者は激増しているのです。 なぜ億万長者がこれほど増えたのかというと、その理由は相続税の減税と高額所得者の減税です。 高額所得者は、ピーク時と比べれば40%も減税されてきたからです。 この結果、最高で26.7兆円もあった所得税収入の額は、2009年には12.6兆円にまで激減しています。 この減税分は、ほぼ貯蓄に向かったと言えるでしょう。 金持ちは元からいい生活をしていますので、収入が増えたところでそれほど消費には回しません。 ですから、減税されればそれは貯蓄に向かうのです。 その結果、景気が悪いのに個人金融資産が激増ということになったのです。 個人金融資産の大半は富裕層が持っているのです。 今、日本がしなければならないのは、これ以上、国民に我慢を強いることではなく、たっぷりため込んだ者たちの資産を有効に活用することだ、といいます。 そこで武田さんが提唱しているのは、無税国債です。 これは利息が付かない国債のことで、利子がつかない代わりに相続税が免除される点がメリットとなっています。 日本ではまだ発行されたことはありませんが、政府では無利子国債の発行がたびたび議論、検討されているそうです。 無利子国債によって、政府による金利の支払いをなくして短期的に財政の負担を軽減し、経済対策等の財源にあてることを目的としています。 しかし、長期的に見れば相続税免除によって税収が大幅に減るため、将来の財政につけが回るようになります。 また、無利子国債は、タンス預金など眠っている国民の個人資産を、国の経済対策等のために活かすことを目的としています。 しかし、相続税の免除につながることから、金持ち優遇の政策であるとの批判もあります。 これに対し森永さんは、富裕層への政策を考えるときには、彼らがカネの亡者だということを前提に考えないと実効性を担保できないと言います。 慎重に制度設計しないと、逆に富裕層を利するだけに終わりかねない、ということです。第1章 激増する億万長者/第2章 大企業は巨額の資産をため込んでいる/第3章 デフレの本当の真実/第4章 日本経済が抱える二つの爆弾/第5章 消費税が日本を滅ぼす/第6章 消費税ではなく無税国債を/第7章 普通に働けば普通に暮らせる国へ
2017.06.06
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1