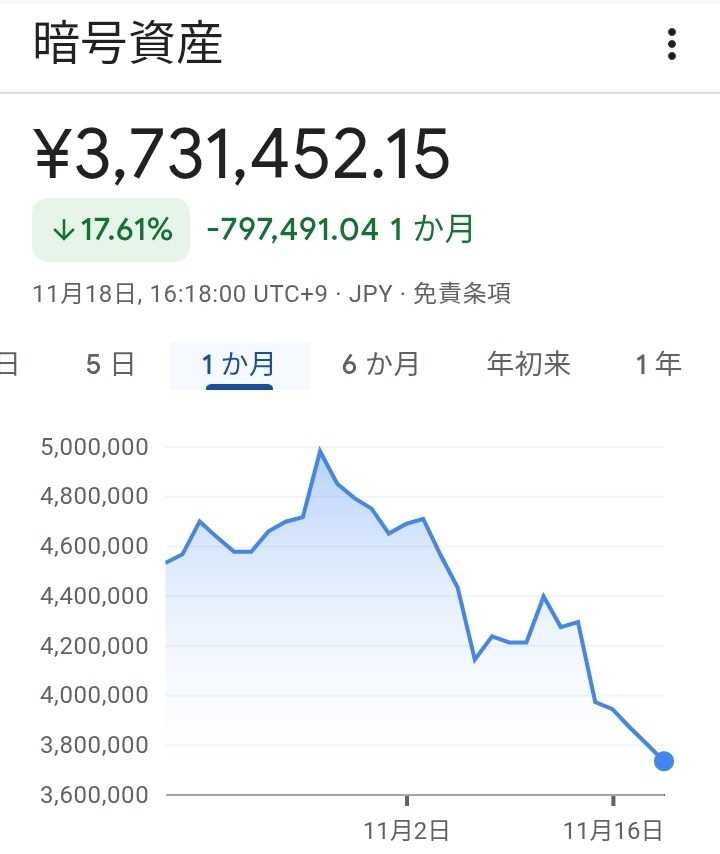2017年11月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
チェリー・イングラム-日本の桜を救ったイギリス人(感想)
ビクトリア女王時代の19世紀後半に、日本から観賞用の桜がやってきました。 大英帝国の最盛期、世界各地からいろいろなものがイギリスに持ち込まれた勢いにのって、サクラも海を渡ったのです。 20世紀に入って、ロンドンの東にあるケント州の植物収集家、コリングウッド・イングラムは3度日本へ足を運び、多くの桜を持ち帰りました。 ”チェリー・イングラム-日本の桜を救ったイギリス人 ”(2016年3月 岩波書店刊 阿部 菜穂子著)を読みました。 明治以後の急速な近代化と画一的な染井吉野の席巻から消滅の危機にあった日本独自の多種多様な桜の保護に尽力した、コリングウッド・イングラムの生涯を紹介しています。 イングラムは日本の桜とヨーロッパ産の桜を交配させて多くの新種を作り、またたく間に桜の権威となってサクラ男と呼ばれました。 阿部菜穂子さんはジャーナリストで、1981年国際基督教大学卒業、毎日新聞社記者を経て、2001年8月からイギリス人の夫と息子2人でロンドン在住です。 イギリス社会、とくに教育問題や家族政策について日本の新聞、雑誌に寄稿しています。 イギリスにはたくさんの桜が植栽されています。 イギリスでは、じつにさまざまな品種の桜が復活祭をはさんで次々と開花していきます。 花の色は白、ピンク、紅とそれぞれちがい、花期も少しずつずれているため、桜の季節は3月末から5月なかばごろまで長く続きます。 復活祭を祝う桜の光景はまるで、長い冬のあいだに眠っていた人間の魂が多様な桜の花びらとなって蘇り、そこここで生命力を躍動させるかのように見えます。 イギリスの桜の風景は、ひとことで言うと多様なのです。 日本では染井吉野がいっせいに咲いて街全体を薄桃色に染め、わずか1週間程度でまたいっせいに花びらが散っていきます。 しかし、日本生まれの桜はイギリスでは故郷とはちがう風景をつくったのです。 染井吉野一色に染まる祖国の風景を見慣れている在英日本人の多くは、イギリスの多様な桜の風景にとまどいすら覚えます。 そして、イギリスの桜は日本の桜とはちがう種類ではないだろうかとささやき合います。 この多様な桜の風景を演出したのが、コリングウッド・イングラムです。 イングラムは、ビクトリア王朝下の1880年にイングラム家の3男としてロンドンで生まれました。 祖父ハーバート・イングラムは、当時人気を得ていた世界初の絵入り新聞”イラストレイテッド・ロンドン・ニュース”の創設者です。 父親ウィリアム・イングラムは、2代目経営者として新聞事業を発展させました。 2代にわたる財産の構築により、一家は裕福でした。 大英帝国は世界中に植民地をもち、栄華を極めていました。 コリングウッド・イングラムは、少年時代をウェストゲイトの豊かな自然の中で過ごし、日々沼地や森を探索して野鳥や植物の知識を身につけました。 日本への初訪問は1902年のことで、その旅ですっかり日本びいきになりました。 長い鎖国を終えて姿を現した日本は独自の文化と芸術をもち、植物相も豊かでした。 イングラムは、1906年にフローレンス・ラングと結婚し、半年後に新婚旅行で再び日本を訪れました。 桜との出会いは、第一次大戦後の1919年のことでした。 この年に妻と3人の子供をもつ一家の主として、ケント州南部の村ベネンドンに新居のザ・グレンジを購入して転居しました。 そのとき新居の庭に植えられていた桜の大木2本が目にとまり、ヨーロッパではまだ知られていない日本の桜を収集して庭に植樹し研究しようと思い立ちました。 その後、猛烈な集中力と実行力で桜を収集しました。 日本や米国から多数の品種を輸入し、知人・友人から譲り受けるなどして集めた結果、7年後には100種類を超すコレクションをもつ壮大な桜園が誕生しました。 1920年代後半から地元で有名になり、イングラムはいつしかチェリー・イングラムと呼ばれるようになりました。 イングラムが何よりも愛していたのは、日本人が過去千年にわたって創り上げた多様な桜でした。 英国で可能な限りの桜を入手したイングラムは、より珍しい桜を求めて1926年に日本へ桜行脚に行くことを決意しました。 旅の計画を助けたのは、鷹司信輔=たかつかさのぶすけ公爵で、鳥の研究のためヨーロッパに遊学中に英国でイングラムと知り合いました。 貴族院議員でもあり豊かな人脈をもつ有力者で、まもなく日本の桜愛好家の会の会長になりました。 鷹司公爵の紹介で、イングラムは日本で大勢の桜関係者と会うことができました。 当時、日本では伝統文化が近代化の波の中で失われつつあり、園芸界にも商業主義が蔓延し、日本の多様な桜はどれも 絶滅の危機に瀕していました。 イングラムはその現実を見て、日本の大切な桜が危ないと危機感を抱き、桜を英国へ持ち帰って保存しようと決意しました。 京都、吉野、富士山麓、仙台、日光と精力的に回りながら、イングラムは懸命に珍しい桜を探しました。 欲しい桜を見つけると、地元の人をつかまえて、穂木を英国に送ってほしいと頼み込みました。 これらの穂木はすべ て、その年の冬に英国のイングラム邸に到着しました。 イングラムはさらに、野生種を人工交配させて、新種の桜を創り出しました。 こうしてザ・グレンジの庭園では、毎春、多彩な桜が3月中旬から5月末まで次々と花を咲かせ、桜の競演を繰り広げてきました。 日本の桜は、ザ・グレンジから英国各地へ 広まっていきました。 イングラムの桜は大西洋を越えて米国にも渡り、チェリー・イングラムの名は広く知られるところとなりました。第一章 桜と出会う/第二章 日本への「桜行脚」/第三章 「チェリー・イングラム」の誕生/第四章 「本家」日本の桜/第五章 イギリスで生き延びた桜/第六章 桜のもたらした奇跡/関連年表/参考文献
2017.11.26
コメント(0)
-
ハワイ官約移民の父 R.W.アーウィン(感想)
ハワイの日本人移民は、1868年以降、労働者として日本からハワイへ移住していった人びとです。 1900年までの国や民間企業の斡旋によりやって来た移民を契約移民と言い、以降1908年までの移民を自由移民と言います。 R.W.アーウィンは、1885年2月8日の東京市号のホノルル入港で第1回官約移民を実現し、東京・青山に住んで最後は日本の土になりました。 ”ハワイ官約移民の父 R.W.アーウィン”(2011年7月 講談社ビジネスパートナーズ社刊 松永 秀夫著)を読みました。 官約移民の父と言われるアメリカ人、ロバートー・ウォーカー・アーウインの生涯を紹介しています。 松永秀夫さんは1926年生れ、法政大学卒、三友新聞社に勤務し、編集局長を務めました。 現在、日本海事史学会、太平洋学会、日本移民学会の会員とのことです。 ハワイにおける移民は、急増するサトウキビ畑や製糖工場で働く労働者を確保するため、1830年頃より始められ、関税が撤廃された1876年以降にその数が増え始めました。 中国、ポルトガル、ドイツ、ノルウェー、スコットランド、プエルトリコなど様々な国から移民が来島しましたが、日本からやってきた移民が最も多かったのです。 1860年に日本の遣米使節団がハワイに寄港した際、カメハメハ4世は労働者供給を請願する親書を信託しました。 日本は明治維新へと向かう混迷期にあり、積極的な対応がなされずにいました。 カメハメハ5世は、在日ハワイ領事として横浜に滞在していたユージン・ヴァン・リードに日本人労働者の招致について、日本政府と交渉するよう指示しました。 ヴァン・リードは徳川幕府と交渉し、出稼ぎ300人分の渡航印章の下附を受けました。 その後日本側政府が明治政府へと入れ替わり、明治政府はハワイ王国が条約未済国であることを理由に、徳川幕府との交渉内容を全て無効化しました。 しかし、すでに渡航準備を終えていたヴァン・リードは、1868年にサイオト号で153名の日本人を無許可でホノルルへ送り出してしまうこととなりました。 こうして送られた初の日本人労働者は元年者と呼ばれました。 日本側は自国民を奪われたとして、1869年に上野景範、三輪甫一をハワイに派遣し、抗議を行いました。 折衝の結果、契約内容が異なるとして40名が即時帰国し、残留を希望した者に対しての待遇改善を取り付けました。 この事件を契機として日本とハワイの通商条約が議論され、1871年日布修好通商条約が締結されました。 1885年に日布移民条約が結ばれ、ハワイへの移民が公式に許可されるようになりました。 政府の斡旋した移民は官約移民と呼ばれ、1894年に民間に委託されるまで、約29,000人がハワイへ渡りました。 1884年、最初の移民600人の公募に対し、28,000人の応募があり、946名が東京市号に乗り込んでハワイに渡りました。 官約移民制度における具体的な交渉は、後に移民帝王とも言われる在日ハワイ総領事R.W.アーウィンに一任されました。 アーウィンは井上馨と親交を持ち、その関係から三井物産会社を用いて日本各地から労働者を集めました。 そして、その仲介料を日本・ハワイの双方から徴収するなど、莫大な稼ぎを得ていました。 アーウィンとの仲介料の折り合いが合わず、1894年の26回目の移民をもって官約移民制度は廃止されました。 1894年の官約移民の廃止と同時期に、弁護士の星亨が日本政府に働きかけ、民間移民会社が認可されることとなりました。 以後は、日本の民間会社を通した斡旋=私約移民が行われるようになりました。 その後、1900年に移民会社による民約移民が廃止になり、ハワイへの移民は、自由移民だけとなりました。 自由移民は、官約移民・民約移民の時代を通じて、もう一つの移民の方法として法的には並存していました。 またこの他に、密入国などの不法な手段による渡航もありました。 日本からの移民は、1902年にはサトウキビ労働者の70%が日本人移民で占められるほどとなり、1924年の排日移民法成立まで約22万人がハワイへ渡りました。 移民の多くは契約期間満了後もハワイに定着し、日系アメリカ人としてハワイ社会の基礎を作り上げてきました。 アーウィンは1844年にデンマーク・コペンハーゲンで生まれ、1866年23歳のときにパシフイック・メイル・スチームシップ日本駐在員として横浜に赴任しました。 パシフイック・メイルは1847年に設立され、サンフランシスコ・パナマ間の航路を引受けた船会社です。 1848年のカリフォルニア州のゴールドラッシュに出会い、乗船客の急増に伴って利益をあげ、基盤を築きました。 南北戦争後、1865年にアメリカ政府から年間50万ドルの郵便輸送契約を結び、サンフランシスコ・ハワイ・日本・上海・香港の定期航路に乗り出しました。 アーウィンは1869年に横浜のウォルシュ・ホール商会に入社し、長崎のウォルシュ商会に勤務しました。 このとき、後に正式に結婚する18歳の武智いきを同行しました。 1873年にフィッシャー商会の設立に参加しました。 1874にハワイ王国代理領事に就任しました。 1876年に三井物産が発足しましたが、アーウィンは1877年にロンドン代理店主になりました。 1878年にロンドンを離れ横浜に戻り、1879年に三井物産顧問役に就任しました。 1880年に三井物産に蒸気船会社設立を勧告し、在横浜ハワイ総領事代理に再任されました。 1881年に横浜でカラカウア王を出迎え、ハワイ国総領事に就任しハワイ国代理公使兼任を受命しました。 1882年に武智いきと正式に結婚しました。 これが日米間初の正式な国際結婚と言われています。 この年、共同運輸会社の発起人会で取締役待遇になり、井上外務卿により、布哇国移住民事務局日本代理者と承認されました。 1884年にハワイからイアウケア全権公使が来日し、井上外務卿から移民提議を承認されました。 アーウィンは、ハワイ国政府代理官・移住民事務局特派委員を兼任しました。 こうして、1885年の第1回官約移民を実現したのです。 1925年に82歳で永眠し、勲一等旭日大綬章に叙せられました。第1章 横浜のPM社に入社/第2章 日本人少女と巡り会う/第3章 長崎から帰り外債仲裁/第4章 三十一歳でハワイ王国代理領事/第5章 「先収会社」に加勢/第6章 新設商会で存分な行動/第7章 ハワイ国王の来遊に大役/第8章 国賓の礼遇で応対/第9章 ハワイ国歌で出迎え/第10章 フランクリン由来で紹介/第11章 私邸にカラカウア王/第12章 日本の優遇を謝す/第13章 新たに海運会社設立/第14章 ハワイ少年二人が留学/第15章 イギリスで汽船建造/第16章 特命公使の移民を諾す/第17章 「布哇に往けよ」の論評/第18章 約定書草案も掲載/第19章 府県で違った対応/第20章 天然痘で渡航延びる /第21章 ハワイ島民から厚遇/第22章 罷業があっても第二回船/第23章 渡航条約と二社合併/第24章 横浜-ホノルル直行船/第25章 好感呼んだ禁酒と教化/第26章 無賃渡航費を有料に/第27章 グアテマラで「虐待事件」/第28章 官約移民の役割を終えて/第29章 十年間・官約の意味/第30章 ハワイ国をしばしば去来/年表/引用・参考書
2017.11.19
コメント(0)
-
わたくしたちの旅のかたち 好奇心が「知恵」と「元気」を与えてくれる(感想)
異文化に触れる喜び、忘れられない出会い、旅をすることで得られる知恵と元気などを50年来の知己が初めて語り合います。 ”わたくしたちの旅のかたち 好奇心が「知恵」と「元気」を与えてくれる ”(2017年2月 秀和システム刊 兼高かおる/曽野綾子著)を読みました。 ひとりは、”兼高かおる世界の旅”で世界中を旅した兼高かおるさん、もうひとりは、各国を取材し、戦争・社会・宗教などのテーマで執筆している作家・曽野綾子さんです。 兼高かおるさんは1928年神戸市生まれ、父親はインド人です。 香蘭女学校卒業後、ロサンゼルス市立大学に留学、その後、ジャーナリストとしてジャパンタイムスなどで活躍しました。 1958年にスカンジナビア航空が主催した世界早回りに挑戦し、73時間9分35秒の当時の新記録を樹立しました。 兼高かおる世界の旅を、ナレーター、ディレクター兼プロデューサーとして製作しました。 放送は1959年12月13日から1990年9月30日にかけて30年10か月の間、TBS系列局で主に毎週日曜日朝に放送されました。 2007年5月6日からTBSチャンネルで再放送が開始されました。 取材国は約150か国、1年の半分を海外取材に費やし、放送回数は1586回、全行程は721万kmで、地球を180周した計算になります。 1986年から2005年まで、横浜人形の家館長を務めました。 外務大臣表彰、菊池寛賞、文化庁芸術選奨、国土交通大臣特別表彰、紫綬褒章受章などを受賞しました。 現在、日本旅行作家協会名誉会長、淡路ワールドパークONOKORO兼高かおる旅の資料館名誉館長、東京都港区国際交流協会会長などを務めています。 ミクロネシアのマーシャル諸島に自分の島=カオル・エネを持っているそうです。 82歳になった現在でも世界各国を飛び回っています。 時々刻々と変化する世界の情勢は常にじかに見なければならないという方針で、独身です。 曽野綾子さんは1931年東京都葛飾区立石生まれ、二女として生まれたが姉が亡くなり一人娘として育てられました。 母親の希望により幼稚園から大学まで聖心女子学院でしたが、敗戦前後10か月ほど金沢に疎開し学校も金沢第二高等女学校に変わったそうです。 1946年に東京に戻り、聖心女子学院に復学しました。 戦後父親は姻戚を頼って米軍に接収された箱根宮ノ下の富士屋ホテルの支配人となり、妻子を田園調布に置いて単身赴任しました。 曾野さんは1948年夏に実際ここに滞在しアルバイトまがいの手伝いをしていたそうです。 同年にカトリック教徒として洗礼を受け、洗礼名はマリア・エリザベトです。 1951年に臼井吉見さんの紹介で、現在の夫・三浦朱門さんや阪田寛夫さんらの第15次”新思潮に加わりました。 22歳で文学的アドバイザーでもあった三浦さんと結婚し、23歳で芥川賞候補となり文壇にデビューしました。 以後、次々に作品を発表し、30代で不眠症に苦しみましたが、新しい方向性にチャレンジするうち克服しました。 1995年から2005年まで日本財団会長職を務め、2009年10月からは日本郵政社外取締役に就任しました。 2000年に元ペルー大統領のアルベルト・フジモリが日本に長期滞在した折、自宅に私人として受け入れました。 1979年ヴァチカン有功十字勲章、1993年恩賜賞・日本芸術院賞、2012年菊池寛賞を受賞しました。 精力的な執筆活動の一方、各種審議会委員も務め、世界に視野を広げた社会活動でも注目を集めました。 昭和20年の終戦と同時に、それまで敵国たったアメリカが憧れの対象になりました。 岡晴夫さんが歌う”憧れのハワイ航路”が大流行しましたが、当時はまだ海外への渡航は自由化されていませんでした。 庶民はバラック住まいに代用食で、海外旅行など、夢のまた夢でした。 同時代を生きた二人が初めてあったのは50年前で、場所は六本木のエクアドル大使館だったといいます。 昭和34年から、日本初の海外紀行番組”兼高かおる世界の旅”がはじまりました。 番組が伝える海外の文化や風俗は、日本人の憧れと旅情をかき立てました。 観光目的の渡航が自由化されたのは、その5年後の昭和39年のことでした。 しかし、海外旅行の費用は乗用車1台分より高く、庶民にとってはまだまだ高値の花でした。 昭和45年は高度成長にわく日本の空に、初めてパンアメリカン航空のジヤンボジェット機が登場しました。 以降、高価だった旅行代金は大幅に引き下げられ、海外旅行は一気に身近になりました。 農協をはじめとする団体旅行が大ブームになり、多くの日本人が世界へ飛び立ちました。 それからも、急激な円高とバブル経済の恩恵で出国ラッシュは続きました。 昭和54年に創刊された”地球の歩き方”を片手に、貧乏旅行を楽しむバックハッカーも激増しました。 旅慣れた日本人にとつても、世界はまだまだ感動の宝庫で、アフリカとの深い縁がはじまったということです。 時代は昭和から平成になり、同時にインターネットの登場で、世界は一つにつながりました。 しかし、グローバル化が叫ばれる一方で、若者の内向き志向は加速し、海外渡航者数は年々減少の一途をたどっています。 逆に訪日外国人の数は大幅に増加し、日本の歴史や伝統文化の魅力は、外から再発見されつつあります。第一章 戦後、アメリカの豊かさへの憧れ 同時代を生きた二人/戦中・戦後の女学校/「女工さん」の仕事が好きだった/なぞの留学生/ガラリと変わった戦後の暮らし/真の国際人とは?/進駐軍と「レーション」/代用食の「身欠きニシン」はミイラの匂い!?/「お嬢ちゃま」では生きられない/紳士的だった進駐さん/富士屋ホテルでのアルバイト/ホテルは憧れだった/ハワイ経由でアメリカへ留学/初めてのカルチャーショック/強烈だったインド・パキスタンの旅/海外へ出て行く勇気をくれた英語第二章 海外はまだ高値の花 『兼高かおる世界の旅』がはじまった/日本の常識は世界の常識じゃない/出されたものは、なんでも食べた/才能は自分一人では磨かれない/「いい男」だったケネディ大統領/初めてのアメリカ暮らし/アメリカの豊かさに魅了される/「自由の国」アメリカ/日本式の「才覚」か、アメリカ式の「マニュアル」か…第三章 海外が身近になった一九七〇年代 越路吹雪さんとグアム/飛行機が元気だった時代/鄧小平とタン壺/ウォッカで乾杯!/世界は思った以上にルーズ/日本の「当たり前」を疑う/理解できない習慣もある/その国のタブーを知っておく/日本人のマナーは超一流/世界には「食」に関するタブーもある/「命をいただく」現実と向き合うこと/人を見たら「泥棒」と思え?/五分の一までは値切れる/買い物で国際交渉術を鍛える第四章 アフリカとの出会い アフリカとの深いご縁がはじまった/アフリカの古風な伝統/自分の年齢を知らない人々/砂漠の民の慈悲と掟/アフリカにはトイレがない!?/健康管理は自己責任/モーパッサンとサバイバル/旅の必需品は、ゴム草履/スーツケースに「牽引用ロープ」!/サハラ砂漠を照らす満天の星/星、そして静寂。アラブは戦とは無縁な世界だった第5章 これからの日本、そして旅のかたち 変わりゆく日本/優れた文化を伝える伊勢神宮/日本はほんとうに貧しいのか/『世界の旅』はプロローグ/大切なのは、「違い」を認め合うこと/ペルー元大統領フジモリ氏との交流/「私人」であればお助けする/民主主義か独裁か/「平等」を求め過ぎると後退する/「富」が文化をつくる/お金持ちになったら何をする?/シニア世代におすすめしたいクルーズの旅/ツアーに参加する旅もいい
2017.11.12
コメント(0)
-
ストラディヴァリとグァルネリ ヴァイオリン千年の夢 (感想)
ストラディヴァリとグァルネリは、ともに17~18世紀に活躍したヴァイオリン製作者です。 過去に幾度も本物かどうかの聴き比べが行われましたが、著名な音楽専門家でも見事に外しまくり、現代のものとの間に音色の違いはないという結果が出ています。 にもかかわらず、ストラディヴァリの相場は下がるどころか上がる一方でした。 なぜこんなことが起こるのでしょうか。 ”ストラディヴァリとグァルネリ ヴァイオリン千年の夢 ”(2017年7月 文藝春秋社刊 中野 雄著)を読みました。 1挺数億円で取引され、スター・ヴァイオリニストは必ずどちらかを使っているといっても過言ではない銘器の不思議を解明しています。 中野 雄さんは1931年長野県松本市生まれ、東京大学法学部卒業、日本開発銀行を経てオーディオ・メーカーのトリオ役員に就任しました。 その後、代表取締役、ケンウッドU.S.A.会長を歴任し、昭和音楽大学、津田塾大学講師を務めました。 現在は、映像企業アマナ等役員、音楽プロデューサーとして活躍し、LP、CDの制作でウィーン・モーツァルト協会賞、芸術祭優秀賞、文化庁芸術作品賞など受賞しました。 アントニオ・ストラディバリ(1644年 - 1737年)は、イタリア北西部のクレモナで活動した弦楽器製作者です。 弦楽器の代表的な銘器である、ストラディヴァリウスを製作したことで知られています。 ニコロ・アマティに師事し、16世紀後半に登場したヴァイオリンの備える様式の完成に貢献しました。 1680年にクレモナのサン・ドメニコ広場に工房を構えると、若くして楽器製作者としての名声を得ました。 2人の息子と共にその生涯で1116挺の楽器を製作したとされ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、マンドリン、ギターを含む約600挺が現存しています。 グァルネリは、イタリア、クレモナ出身の弦楽器製作者一族であり、 アンドレーア・グァルネリ (1626年 - 1698年)、ピエトロ・ジョヴァンニ・グァルネリ (1655年 - 1720年)、ジュゼッペ・ジョヴァンニ・バッティスタ・グァルネリ (1666年 - 1739年)、ピエトロ・グァルネリ (1695年 - 1762年)、バルトロメオ・ジュゼッペ・“デル・ジェズ”・アントーニオ・グァルネリ (1698年 - 1744年)が知られています。 単にグァルネリといえば、バルトロメオ・ジュゼッペ・“デル・ジェズ”・アントーニオ・グァルネリの制作した弦楽器を指すことが多いです。 アントニオ・ストラディヴァリとバルトロメオ・ジュゼッペ・“デル・ジェズ”・アントーニオ・グァルネリの二人の製作した楽器が、この世界で至高の逸品とされています。 その秘密に迫るべくこれまで数え切れないほど多くの、学者、研究者、職人たちが日夜研究を続けてきました。 しかし、その秘密なるものを応用して、往年の巨匠二人のような作品が誕生したという話も、量産化に成功したという話も聞いたことがありません。 その間に銘器の価格は高騰を続け、1挺の値段はいまや数億円となっています。 日本人では高嶋ちさ子氏がストラディバリウス・ルーシーを2億円で、千住真理子氏がストラディバリウス・デュランティを2~3億円で購入しているといわれています。 現代最高クラスの名手たちから今なお愛され続けています。 その美しい音の秘密はヴェールに包まれ、世界中の職人や科学者がなんとかその謎を解き明かそうとしのぎを削ってきました。 音楽家は、自分の持っている楽器の性能を超える演奏をすることが出来ません。 ヴァイオリンにしても、ピアノにしても、あるいは、管楽器、打楽器にしても、あらゆる楽器には、製造過程で造り込まれた潜在的な音楽表現能力が内在しています。 これは人間を含めた生物の世界と同じで、遺伝子の存在と似ていると言ってもいいでしょう。 一人ひとりは容貌が異なり、体格が異なり、運動能力も智力、性格も異なります。 長い人生行路の中で、努力や教育訓練によって智力も運動能力も大きく変えることはできますが、そこに天性の個体差の壁というものがあることは誰にも否定できません。 人間と他の動物との差、人間という生き物それぞれの個体差を貴らしたのは、もしかしたら神の意思かもしれないですが、音楽を奏でる楽器に個体差を付与したのは人間です。 ヴァイオリンを作るか、ピアノを作るか、フルートを作るかを決めるのは、当該の楽器を製作する楽器製作者の意思です。 ヴァイオリンを作る、ピアノを作るといっても、どんな音のする、どのような音楽表現力を持つ楽器を作るのかというのは製作者の目的意識と製作能力によるのです。 目的意識とか製作能力というのは、極めて不可解かつ説明困難な人体現象です。 何故ヴァイオリン属なる弦楽器がわれわれ音楽愛好家の関心を呼ぶかといいまと、第一にはその価格-そして、その価格の安定性です。 ストラディヴァリウスとかグァルネリとかいう銘器の大部分には、その楽器を蒐集・保管した貴族、富豪、趣味人や、演奏に使用した音楽家の名前がつけられています。 往年のコレクターや名演奏家の名前以外にも、ヴァイオリンの銘器にはさまざまな特徴的な名前が付けられています。 これらの銘器の所在は一流の楽器店主なら常時把握していて、所有者が手放す瞬間を虎視耽々と狙っています。 有名な楽器はその履歴とともに立派な図鑑に収められており、贋作を掴まされる惧れまずありません。 ただし近年、銘器の価格は異常という言葉以外では表現できないほどの急騰ぶりを見せています。 神田侑晃さんの2002年の著書には、ストラディヴァリウスとデルジェスの価格は2億円前後とされていますが、いまでは10億円以上すると言われています。 ヴァイオリンという楽器の価値を決めるのは、製作者によって楽器本体に埋めこまれた音楽表現能力です。 ヴァイオリンのなかの銘器は、古今の芸術家の作品と同じように、限られた歴史上の才能によってこの世に産み出されたものです。 作品を産み出す才能自体が、人類の歴史上、限定されたものと考えられます。 ヴァイオンについて、常に古今の芸術作品と、その創作の秘密に想いを致さなければ、市場で取引きされている途轍もない価格について理解することはできません。 さらに厄介なのは、この芸術作品-実は音楽を演奏する道具に過ぎないということなのです。プロローグ~二大銘器は何故高価なのか/第1章 ヴァイオリンの価値とは何か/第2章 ヴァイオリンという楽器Ⅰ~その起源と完成度の高さ/第3章 ヴァイオリンという楽器Ⅱ~ヴァイオリンを構成する素材と神秘/第4章 アントニオ・ストラディヴァリの生涯と作品/第5章 グァルネリ・デル・ジェスの生涯と作品/第6章 閑話休題/第7章 コレクター抄伝/第8章 銘器と事故/最終章 封印された神技/エピローグ
2017.11.03
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1