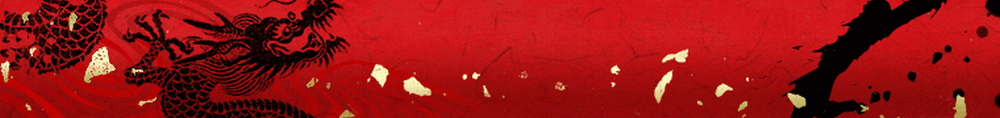全45件 (45件中 1-45件目)
1
-
緊急告知!TBSでボリビアをチェキラ!
来週、TBS系にて以下の番組が放映されます。3月6日(月)21時~22時「古代発掘ミステリー 秘境アマゾン巨大文明」ロケ地の半分以上がボリビアで、アンデスの風景はもちろん、アンデスとは一味違うアマゾン地域も見れます。ティワナク遺跡も出るみたいなので、ぜひ見てみてくださーい。
2006年03月03日
-
先住民初の新大統領就任。ボリビアの行く末は・・・?その3
前回のさらに続きです。1月22日。いよいよ新大統領の就任式の日。前日から、南米を中心にアメリカ大陸各国から大統領級の招待客が続々と首都ラ・パス入り。キューバのカストロ議長こそ来れなかったものの、ベネズエラのチャベス大統領、スペイン、チリ、ブラジル、パラグアイ、ペルー、コロンビア等の大統領がずらり。日本からも次官級の方がいらっしゃった様子。先住民の織物で作られたジャケット姿で国会に登場した新大統領は、就任式で涙を浮かべて宣誓。「権利獲得のために戦い亡くなっていった、革命家チェ・ゲバラ、トゥパク・カタリ、そして数百万の世界の先住民のために」と言って、式典出席者全員で1分間の黙祷。その後、1時間半に亘る演説では「少数の富裕層が天然資源を売り莫大な資産を手に入れる一方で、まだ電気も水もない村もあり、読み書きも知らない先住民が沢山いる」とボリビアの先住民が置かれている状況を訴え、さらに、「1950年代まで国会議事堂にも中心広場にも立入りを許されなかった先住民が、今、ラ・パスの広場に集結している。この光景は歴史的なことだ。人種差別、搾取、憎しみ、暴力のない新しい時代を築こう」訴えた。今回の大統領選挙は確かに歴史的なものだったのかもしれないなぁと思う。1492年のコロンブス到来以来、ボリビアだけでなく中南米の国々はスペインの支配下におかれた。ボリビアでは銀が沢山採れたので、スペイン王室の財政難救済のために銀の富が必要とされ、銀山で多くの先住民が過酷な重労働を強いられてきた、という歴史もある。1825年にスペインから独立したとはいえ、それは先住民の支配層からの独立ではなかったから、独立後も、先住民の状況が劇的に変わることはなかった。だから、先住民出身者が大統領という政治的トップの地位につくことなんて、これまで一度もなかったし、不可能なことだったのだ。その意味で、今回のエボ・モラレス氏が大統領になったことは、ボリビア人にとっても(特に先住民にとって)本当に歴史的なことなのだと思う。コロンブス以降500年間、先住民の誰もなしえなかったことが起こったのだから。ただ、問題はこれから。なぜならボリビアでは、政治的不安定や数々の混乱などで、独立後現在までの180年で190回(だったかな?)政権が変わっており、平均在任期間は1年未満。大統領の任期は5年だが、それをまっとうした人はゼロ。今回もいつまで持つか?という気はする。ちなみに先日、先住民系の女性と話したとき彼女はこう言っていた。「先住民のみんなはエボ・モラレスが大統領になったことで、すぐに国や自分の生活がよくなると期待するけど『すぐに』なんて無理。少しずつ少しずつしか変えられないんだから、私たちはそれを待たなくてはいけない。焦ったらよくなるものもよくならない」。まさにその通りだと思う。さてさて、ボリビアはどう変わっていくのだろうか。今回の大統領選を通して、南米事情やボリビア事情にますます興味が湧いてしまったのでした。 大統領就任を祝い、国会前広場で楽器を持ち盛り上がる先住民の人たち
2006年02月14日
-
先住民初の新大統領就任。ボリビアの行く末は・・・?その2
前回の続き。1月22日の大統領就任式に先立って前日の21日、先住民による「祝いの儀式」が行われました。毎日新聞2006年1月23日の記事を抜粋すると。----------------------------------------------------------------------http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/america/archive/news/2006/01/23/20060123ddm007030095000c.htmlボリビア:先住民、世界遺産に集結 米大陸から1万人、“同胞”大統領の誕生祝う【ティワナク(ボリビア西部)藤原章生】22日に就任する南米ボリビアのモラレス次期大統領(46)をたたえる先住民の儀式が21日、ボリビア西部の世界遺産「ティワナク遺跡」で執り行われた。メキシコやエクアドル、アルゼンチン、米国など米大陸12カ国の先住民代表ら約1万人が集まり、ボリビア初の先住民大統領の誕生を祝った。 ティワナクには、インカ以前の紀元前1580年ごろから紀元1133年まで独自の文明があったとされる。「神のエネルギー」が降り立つという儀式で、モラレス氏は自身が属するアイマラ族の祈とう者の赤と黄を基調とした衣装などを授かった。 儀式を終え、石造の寺院に立ったモラレス氏は「私の大統領就任は世界の先住民の勝利だ」と述べた。 南米最貧国のボリビアの先住民は人口の60%を占めながら、スペイン植民地時代から土地と天然資源を奪われ、90年代まで政治から疎外されてきた。貧富の格差や差別は今も根深い。 モラレス氏は国内の富裕層らに対して「我々はあなた方、ボリビアの中間層や知識人を誇りに思う。だから、あなた方も我々先住民を誇りに思ってほしい」と和解を呼びかけた。 さらに、ボリビアで処刑されたキューバ革命の英雄、チェ・ゲバラと18世紀の先住民の英雄トゥパク・カタリの名を挙げ、「彼らの夢を実現するため、先進国が貧困や惨めさを放置するような世界を変えていこう」と締めくくった。(毎日新聞 2006年1月23日 東京朝刊)----------------------------------------------------------------------というわけで、招待された各国代表が大統領に挨拶をするため次々に登壇したのですが、2度ほど観客から大ブーイング。それは米国と国連の代表者が前に出たとき。やっぱりボリビアは反米・反帝国主義の色が強いんだなぁ、と実感した瞬間。補足。キューバ革命の英雄「チェ・ゲバラ」とは・・・。本名はエルネスト・ゲバラ・デ・ラ・セルナ。1928年アルゼンチンの中産階級の出身。医学部在籍中、南米諸国を旅する中で先住民問題・労働問題など南米の社会問題に出会い、革命の必要性に目覚める。その後メキシコで出会ったフィデル・カストロ(現・キューバ国家評議会議長)とともに1959年キューバ革命を成功させる。キューバ革命後はラテンアメリカ全体の統合を目指した革命を進めるためボリビアで活動を続けたが、1967年10月ボリビア政府軍に捕らえられ、ボリビア中南部イゲラ村で処刑される(1997年にキューバとアルゼンチンの調査チームに掘り起こされるまで30年間この村に埋められていた)。現在イゲラ村近くのバジェ・グランデ市にゲバラ博物館、ゲリラ兵の墓などがある。大学時代の南米旅行を描いた映画「モーターサイクル・ダイアリーズ」が2004年~2005年にかけて日本でも上映され、大きな反響を呼んだ。この映画のサントラも好評(おススメです)。 ティワナク遺跡での儀式。7色の旗は「先住民の旗」。
2006年02月13日
-
先住民初の新大統領就任。ボリビアの行く末は・・・?その1
(今回はちょっと固めの内容です。あしからず。今から1ヶ月ほど前になりますが、去る1月22日ボリビア新大統領の就任式が行われました。新大統領誕生までの経緯を少しおさらいすると。昨年6月、反政府市民団体によるデモや暴動が活発化。それを抑えようとした警察との間で衝突が起こり、カルロス・メサ前大統領が辞任。(ここまでの内容は6月の日記にも書いているので参考に読んでみてくださいな。)その後の暫定政権を経て、去年12月18日に正式な大統領選挙が実施されたわけです(副大統領、知事、国会議員選挙も同日投開票)。大統領選挙立候補者は7名いたのですが、実際は、支持率上位2名の一騎打ち。一人は、先住民出身・反米左派のエボ・モラレス氏。もう一人は、保守系・親米のホルヘ・トゥト・キロガ氏(大統領経験者)。ボリビアの選挙は、国民による直接投票。大統領が決まるまでは、、1.選挙で過半数の得票があればその候補者が大統領に決定。2.選挙でどの候補者も過半数の得票を得られなかった場合→上位2名を対象に、国会で決選投票。という流れです。選挙前の予想は、「エボ・モラレスが首位を走ってるけど、支持率は30%台。もちろん過半数には達しないでしょ」。だったのですが・・・。ふたを開けてみると、エボ・モラレス氏が51%の得票で、「あらららっ?」という間に大統領に決まってしまいました。あっさり。で。このエボ・モラレス氏。どんな人かと言うと。1.反米左派「社会主義運動党(MAS)」の党首で、ブッシュ米大統領と対立するキューバのフィデル・カストロ国家評議会議長や、ベネズエラのチャベス大統領と親交が深い。2.米国が南米各国で主導している「新自由主義経済」を批判。「新自由主義経済」によって、外国企業がボリビア国営企業を次々と民営化。これにより、例えば、ボリビアの豊富な天然ガスは外国企業に利権の多くを握られ、ボリビア国民には恩恵が還元されていない、という状況。以前にもまして貧富の差が拡大し続けている。3.先住民アイマラ族系の貧しい農牧民の出身で、家が貧しく中学3年までしか通えなかった。→ 先住民を中心とした貧困問題の解決を訴えている。4.コカインの原料になるコカ栽培農家団体の代表。→米国政府がボリビア国内で行おうとしているコカ栽培規制策に反発。約20年前にはコカ葉合法化推進を求める運動で、機関銃を手に居並ぶ国軍兵に素手で詰め寄ったこともあるとか。※コカは先住民の間で昔からたしなまれてきた日常嗜好品。(5月31日の日記参照)。強烈な反米主義&コカ栽培推進者ということで、キューバのカストロ議長、ベネズエラのチャベス大統領に加え、ボリビアのエボ・モラレス大統領誕生で、米国にとっては「南米に新たな頭痛の種が増えた」と考えられているらしいです。ついでに言うと最近、南米の各国でますます「反米」路線が強くなってきているらしい。それから。エボ・モラレス氏は今まで下院議員だったのですが、これまで反政府運動の一環としてボリビア各地で「ブロケオ」と呼ばれる幹線道路の封鎖を頻繁に起こしてきた人。「エボといえばブロケオ、ブロケオといえばエボ」というくらい。ボリビアは鉄道が未発達なので、国内移動手段はほとんどバス。ブロケオがあると国内移動が全くできなくなるのです。何度ブロケオに泣かされたことか・・・。でもモラレス氏が大統領になったことで、今後はブロケオが各段に減るのかな?次回は、大統領就任式前日に行われた「祝いの儀式」の様子をお伝えします。 エボ・モラレス新大統領(エンジ色セーター)とキューバのカストロ議長
2006年02月12日
-
夏まっさかりのボリビアより新年のご挨拶
皆様新年あけましておめでとうございます!今年もどうぞよろしくお願いいたします。2005年はどんな年でしたか?私の2005年はボリビアに来て新しいことがたくさん始まった年でした。本当に色々なことがあったけど、この1年は実に早かった!去年の(あ、もう一昨年か)大晦日に実家で紅白を見たのがつい昨日のことのよう。ちなみに昨日の紅白は、朝6時に起きてボリビアのNHK放送でちゃんと見ましたよ。今年もさらに楽しく笑顔あふれる年にしたいと思います。ボリビアより、みなさんの益々のご健康とご活躍をお祈りいたします。
2006年01月01日
-

BRASIL × BOLIVIA
少し前の話だけど、10月9日(日)に首都ラ・パスへ行ってきた。目的は、ブラジル×ボリビアのサッカーの試合観戦~!ブラジルのナショナルチームの試合なんてそうそう観れる機会なんてないでしょ!と思い、試合前日にスクレから深夜バスでラ・パスへ。が、ラ・パスのバスターミナルに着くはずが、ラ・パスよりさらに高地、標高4000mにあるエル・アルト市でバスから降ろされた。どうやら、またブロケオ(反政府運動による道路封鎖)をやってて、ラ・パスのターミナルまでバスがたどり着けないとのこと。んで、てくてくしばらく道路を歩き、やっと別の乗り合いバスを捕まえて無事ラ・パス市内にたどり着くことができたよ。ラ・パスはすっごい寒かったーーー!!雹(ひょう)が降ってて、痛い痛い。肝心のサッカーの試合はというと、午後4時から試合開始にも関わらずブラジル選手は当日の午後2時にラ・パスに着くという噂が・・・。試合開始2時間前じゃん。そりゃあさ、ボリビア弱いチームだけどなめすぎじゃん?でも、今までにラ・パスで行われたブラジル対ボリビアの試合結果は、なんと3勝2敗でボリビアが勝ってるらしい。やっぱり高地で酸素薄いからブラジル選手すぐにバテてしまって、特に後半戦はかなり走れなくなるらしい。そうそう、本当はロナウドとかロナウジーニョとか、かなりのスター選手が来る予定だったらしいけど、結局来なくてちょっとがっかり。いよいよ4時に試合開始。ブラジル、ボリビアの両国歌が流れ、ボリビアの観客は感無量。前半にブラジルが先制点。怒るボリビア応援団(笑)。ブラジルはやっぱりすごかった!ボールを持ってからの攻撃の早さと言ったら!それに比べてボリビアチームはホームなのに、走るのも遅いし動きも鈍い・・・。ブラジル選手と比較したらまるでスローモーションのよう(苦笑)。でも頑張って後半に1点返して、試合は1-1の引き分けで終了~。ブラジル相手に引き分けるだけでも上等だよね。すごい楽しかったし!あ、ちなみに私達が見た席はかなり前の方。それでもチケットは135ボリビアーノス(約2000円)。少し離れた席には、なんと今年6月に辞任した前大統領カルロス・メサ氏が座ってたよ!もはや一市民。今から試合開始!のスタジアム
2005年10月23日
-
矯正。
突然ですが、歯の矯正始めました~。前からずっとやりたかったんだけど、日本だと高いので半分あきらめてましたが、ボリビアでは約5万円という格安なのでやることに決断。日本人の友人が1年前からやっていて、特に問題もなくきれいに治ってきてるから、そこの歯医者を紹介してもらいました。昨日ブラケッツと針金を付けたのですが、何もしてなければぜんぜん痛みはないけど、食べるときが痛い、痛い。口内炎できまくり。今日は朝からヨーグルトとカフェとスープと水しか口にしてません。痩せそう・・・・。しばらく戦いは続く・・・。あー、ほんと痛い。でも、日本に帰る頃にはみちがえるようにキレイになってるはず!そう思ってがんばります~。
2005年10月12日
-
お葬式
おとといの夜、村のおじさんが亡くなった。突然のことで正直びっくりした。病気でもなく事故でもない。その夜、お酒をかなり飲んで酔っ払い、そのまま隣の村の屋外で寝てしまい、たまたまその夜は冷たい大雨が降ったので、多分凍死の可能性が高い。こんなにもあっけなくひとつの命がなくなってしまうのかって思う。アントニオという名のその人には5歳になるルーシーという女の子がいる。私が今住んでる部屋は村の保育園の敷地内にあり、常に子供たちと接する環境で、ルーシーもよく私にちょっかいを出してくるいたずら好きの女の子。アントニオは40歳くらいだったんだけど、ルーシーは第1子。ルーシーのことをとってもかわいがっていて、農作業の合間によくルーシーに会いに保育園に寄ってくれて、子供たちのために絞りたての牛乳を持って来たり(村には酪農してる家もあるので絞りたての牛乳が飲める)、保育園の料理係の人のために薪(今でも村のほとんどは薪を使っている)を持ってきてくれていたとってもいいお父さんだった。今日のお葬式。ルーシーは「死」というものがまだ分からないらしく、棺の前で笑ったり遊んだり。とても切なかった。どうしようもできないことだとは分かっているけれど、馴染みの人が亡くなったということを自分の中で消化していかなくちゃいけないなと思っている。
2005年10月06日
-

村のこどもたち
最近、村の子どもたちを激写しまくっている。一緒に遊んだり、折り紙を教えたりしながら、彼女・彼らの自然な笑顔を、ボリビアにいる間にたくさん写真に残したいと思っている。村の子ども達の笑顔はそれはそれはすばらしく、今の日本の子どもたちにこんな笑顔ができるだろうか・・・?と思うこともしばしば。今の日本の子どもには3つの「間」が無いと言われている。「時間」「空間」そして「仲間」。遊ぶことが子どもの仕事だと思うけれど、現代日本の子どもたちは受験競争、塾通い、習い事に追われ時間が無い。空をさえぎる高層マンションの数々、その他さまざまな建物によって、子ども達が遊べる「場」がどんどんなくなっていく。そして、みんなが時間に追われているから遊びたくても一緒に遊べる仲間がいない。昨今の、子どもが自分の友人を殺したり、子どもが幼児を殺す、という信じられない事件の数々。これは、生身の人間やその痛みを感じられないバーチャルな暴力ゲーム、バーチャルなコミュニケーションによる弊害なのではと個人的には思う。もちろん他の原因もたくさんあり、それらが複雑に絡み合ってるのだろうけれど。私が住む村の子ども達には、この3つの「間」がある。「間」に加えて、子どもにとって絶対不可欠な絶大なる無条件の家族の愛に溢れている。それがこの笑顔を支えているのだろう。ナディール(8歳)ジョスマイラ(6歳)お姉ちゃん(ナイロビ・11歳)が妹(ルセラ・3歳)の世話をする。兄弟愛。
2005年10月04日
-

グアダルーペ2日目
スクレの祭り「グアダルーペ」2日目の9月10日は朝から快晴。ひとつ前の日記に書いたように祭りの1日目は学校の生徒たちがメインで踊ったんだけど、2日目は年齢層がちょっと高め。ボリビア全土からプロの踊り子集団がやってきて、その中にはスポンサー企業がついてるグループも。衣装もかなりお金かかってそうなものばかりでかなり見ごたえありでしたヒラヒラのかわいい衣装を着て優雅に踊る人。重そうなごつい衣装を着てる(というより背負ってる?)人。こわいお面をかぶってる人。ほんとにバリエーションがあって見てて全然飽きなかった。1日目と同じくゴールの教会まで5~6時間ぶっ続けで踊り続けます。すごい大変そうだった。あんな衣装着て数時間も踊るなんてかなりすごい!その中でも印象的だった踊りのひとつは「鉱山労働者の踊り」昔、中学の地理の授業で習った人も多いと思うけど、ボリビアは錫(すず)や銀がたくさん取れます。特に銀は「ポトシ銀山」という銀がたくさん取れる山があって、スペイン植民地時代はその銀を外国に売ったりしてかなり潤っていたそうです。とはいえ、この銀の恩恵を受けたのはやっぱり支配者であるスペイン人がほとんどだったらしい。そして銀山で働いていた人たちは、長時間労働・低賃金・過酷な労働環境という悪条件の下に置かれていたそうです。そんな状況に耐えかねた労働者たちが自分たちの権利を求めて、1960年代(だったかな?)に労働者革命を起こしたのですが、結局状況は劇的には改善されず、今でも同じような労働環境が続いています。長年の労働で、銀などの粉末を大量に吸い込んで寿命を縮める人もたくさんいるらしい。私が見た「鉱山労働者の踊り」は多分、鉱山労働者たちが自分らの苦悩・悲哀を表現し、訴えるための手段として発生したものなんじゃないかと思う。踊る彼らの手には、山を掘るためのハンマーなどの工具。頭には懐中電灯付きのヘルメット。背中には掘り出した銀を入れる大きな袋を担ぎ、声を荒げる。この踊りがいつどこで始まったのかというルーツは詳しくはわからないけど、人々の人生とエネルギーとたくましさ、その他いろんなことを一気にドバーっと感じさせられた踊りでした。世界中どこでも、祭りや踊りっていうのは、そこに生きる人々の歴史と文化とエネルギーと人生と、その他もろもろ沢山のことを、全感覚でダイレクトに強烈に感じられるものだとすごく思う。ボリビアにいる間にいろんな祭りを見よう。そして、来年は私も絶対踊ります!鉱山労働者の踊り。このお面を見て子供が泣いていた(笑)。日本の「なまはげ」を彷彿とさせる。「チャカレラ」という踊り。スペイン植民地時代の影響が強い優雅な踊り。「モレナダ」という踊り。衣装が重そう。よりによってこんな衣装にしなくても・・。準備中のダンサーたち。みんなかわいい!
2005年09月21日
-

スクレの祭り
先週9月9日・10日の2日間、スクレで「グアダルーペ」と呼ばれるお祭りがありました。キリスト教のお祭りなんだって。VIRGEN(ビルヘン。英語ではバージン)と呼ばれる聖女を祝うお祭り、らしい。1日目の9日は学校の生徒達が中心となって、ボリビアの伝統的な踊りを踊るというもの。総勢何グループいただろうか?50くらい?もっとかな。とにかくすごい数のグループがそれぞれの踊りを披露。しかも、町のはずれにある時計台からスタートして、ゴールは中心街の大きな教会で、延々5~6時間踊り続けてたよ!ゴールあたりではみんなぐったりだったけど、最後の力を振り絞ってみんな力強く踊ってた。でも、小学校1年生くらいの子は疲れきって半分眠りながらだったけど(笑)。おもしろいなーと思ったのは、本当に色んな種類の踊りと衣装があるということ。スクレ近郊だけじゃなくて、遠くからはるばるこの日のためにスクレに来て踊ってる人たちも多かったんだけど、その地域の気候や文化によって、こんなにも踊りや衣装が違うものか、と関心。ブラジル寄りの地域の人は「リオのカーニバル」を思わせるかなり薄着の衣装。寒い地域の人はブーツに厚着。ボリビアの文化・人種・民族・気候などの多様性を簡潔に現してると思った。その1日目の写真のっけます。2日目のはまた次の日記で。ゴール地点の教会。スクレの町並はこんなに白い!ティンクイという踊り。鮮やかな衣装!ブラジルっぽい踊り。織物で有名なタラブコ地域の衣装。
2005年09月18日
-

花
サン・フアン日系人移住地に行った時にお世話になった家の庭で、とっても綺麗な南国の花を見つけました。思わず激写。
2005年09月10日
-

日本そのまんま
ふ~、やっと新しい日記を書くことができます。このところほんとバタバタしていて、かなり疲労感。気づけばボリビアに来てもう5ヶ月。早っ!さて。去る8月20、21日にボリビアの日系人移住地San Juan(サン・フアン)の入植50周年記念祭に行ってきました。20日は式典。21日は移住地の日系人学校の運動会&盆踊り。日本人のボリビア移住は100年以上前に始まりました。サン・フアンとコロニア・オキナワという2つの日系人移住地があって、コロニア・オキナワは文字通り、沖縄からボリビアに渡ってきた人たちが入植した土地。去年、入植50周年。サン・フアンは九州出身の人が多いみたいです。日本から何ヶ月もかけて船で南米に渡ってきて、もちろん途中で亡くなった方も多いそう。何もない原生林を一から切り開いて、50年かけて今のような立派な町を作り上げたその苦労は、現代の私たちには想像もできないくらい過酷なものだったんだろうな。ちなみにこの移住地はほとんどが日本人だけど、ボリビア人も結構住んでいます。サン・フアンには、いつもお世話になってる日系人のご家族(Yさん)がいます(Yさんは6歳のときに両親に連れられてボリビアに来たそう)。そこに泊まらせてもらって、21日は早朝から運動会用のお弁当作りを手伝いました。そのお弁当、日本でみるお弁当そのもの。おにぎり、赤飯、お漬物、肉や魚のフライ、こんにゃく、きんぴらごぼう、などなど。ボリビアでは手に入らなさそうな日本の食材を、この移住地で日系人が作っているみたいです。町には日本ならではの野菜(大根、白菜とか)も売ってます。気候も土も違うボリビアで、日本の野菜作りを成功させたなんて本当にすごい!日本人ってほんとすごいなぁーと思う瞬間。Yさんの奥様は、おはぎ、饅頭などの和菓子も上手に作ります。まじでうまいです、これ!さてさて。運動会は日本とボリビアの国旗掲揚と国歌斉唱で始まり、なんと、みんなでラジオ体操~。子供たちにまじって私も参加。あー、懐かしい!小・中学校の学年別リレーや、親子3代リレーみたいなのが行われ、競技中の音楽はまさに日本の運動会で使われる音楽そのまま。さらに移住地の婦人会による花笠音頭の披露。借り物競争やパン食い競争もあって、私はパン食い競争に参加させてもらったよ。すっごい楽しかったーーー!いつ以来だろう、パン食い競争なんて。しかもね、このパン、ちゃんとアンパンなんです!アンパンも移住地で作ってるんですねー、すごいすごい。後半に、中学校・高校くらいの年齢層によるボリビアの伝統舞踊の披露があったんだけど、最後にみんなが、「おじいさん、おばあさん。私たちが今ここにいるのはあなた達のおかげです。どうもありがとうございます」と挨拶をしたのを見て、思わず涙ウルウル。移住者であるからこその気持ち、なんだろうけど。両親や祖父母、さらにその先祖に対する感謝の気持ちって絶対に忘れちゃいけないものなんだ、って改めて思いました。ボリビアにいながら、まるで日本にいるみたいな1日でとっても楽しかった!また機会を見つけて遊びに行きたい!最高においしいお弁当入植50周年記念祭の垂れ幕みんなでラジオ体操花笠音頭
2005年09月03日
-
忙しい・・・
何だかよくわからんのですが、最近やけに忙しい。なので、日記もろくに更新できてません。見に来てくれてる方、ごめんなさいね~。こないだ日系人移住地の入植50周年記念祭に行ってきたので、また書きますねー。すごい面白かったから。
2005年08月29日
-

独立記念日
今日のスクレ市はめずらしく曇り空です。さっきまで雹まじりのスコールのような雨が降ってたよ。いよいよ雨季の到来ですかね。昨日8月6日はボリビアの独立記念日(1825年スペインから独立)。どの家もボリビア国旗を掲げ圧巻。国旗を揚げなかった家は200ボリビアーノス(約3000円)の罰金らしいよ。町の中心部のプラザ(公園)では、朝から記念式典みたいなのをやってました。そして、市内の大学各学部や各種団体がそれぞれグループを作って、Desfile(デスフィレ)と呼ばれる行進をしてた。ブラスバンドの演奏付き。私の友達の一人が大学で働いてるので、彼女もその行進に参加。おもしろそうだったー。私は見るだけだったけど。スクレ市はボリビアの憲法上の首都なので(事実上の首都はラ・パス)、大統領も駆けつけて式典に参加。大統領って言っても、こないだ6月に辞任した前大統領の暫定的な後任者だけど。で、行進してる大統領を間近で見れました!ちなみに警備は「え?こんなんでいいの?」っていうくらい手薄。多分、ボリビアは銃犯罪がすごく少ないんだと思う。平和だなぁー。写真のっけます。赤・黄・緑の3色のたすきをかけてるのが大統領。軍隊の行進もあったんだけど、おもしろかったことがひとつ。行進時にブラスバンドが奏でた曲が「コンドルは飛んでいく・軍歌バージョン」。あんなのどかでやわらかーい曲が、アップテンポな軍歌にアレンジされてたよ!やっぱりアンデスの国ですねー。どこまでもアンデス調(笑)。よっ!ロドリゲス大統領!空軍の行進
2005年08月07日
-
狂犬病
狂犬病。日本では飼い犬に、年に1回とか狂犬病の予防接種しますよね。私の家でもむかし犬を飼ってて毎年ワクチン接種に連れてってました。でも「狂犬病」ってどんな病気かその時は全然知らんかった。今回ボリビアに来る前に、ボリビアで気をつけなきゃいけない病気についても勉強し、狂犬病についても「狂犬病にかかった犬の見分けかた」とか「犬に噛まれたらどう処置するか」とか色々習いました。狂犬病って、狂犬病ウイルスに感染した犬(その他ネコなどの哺乳動物)に噛まれたりして人間に感染するもので、発病したら100%死に至る病気。おぉ、こわっ。ボリビアは狂犬病の流行地とされていて、犬に噛まれる人がかなり多いとは聞いてたんだけど、去る6月、私の村からそう遠くない別の村で、子供が狂犬病で亡くなったというニュースを聞いてびっくり。その後、各村で「ワクチンを打つように」と指示が出され、看護師(獣医なんていないので人間相手の看護師が担当)がワクチン接種にがんばってます。で、こっからがほんとにびっくりなんだけど。こないだ村にいたときに「ちょっと川まで散歩しよー」と思って、川までの道を歩いてたら、な、な、な、なんと狂犬病にかかった犬を発見!日本で「狂牛病」が話題になったとき、TVとかで牛が全然立ち上がれず苦しんでる映像を見たことがあるかと思いますが、狂犬病の犬もあんな感じです。あきらかに「おかしい」状態。よだれもダラダラたらしてるし。で、これはやばいっ!と思って、すぐに村の診療所の医者と看護師に「多分狂犬病にかかってると思うんだけど」と伝えて一緒に見に行ったら、その医者も「間違いないね」とのこと。すっげー恐いよーーーっ!で、急いで飼い主を探してその犬を捕まえて、可哀相だけど絶命という処置をとりました・・・・。その後ちょっと気分が悪くなった。日本で狂犬病予防接種をしてきたとは言え、100%安全って訳じゃないからほんとに恐くなった。私たち在ボリビア日本人は予防接種もしてるし、たとえ噛まれたとしてもその後の医療処置が受けられる環境なので(その辺はちゃんと保証がある)いいけど、村の人なんて基本的な医療もあんまり受けることができてないからほんとに心配。何人かと話した限りでは、狂犬病についての知識もほとんどない。やばいって。とにかくあの日はすごい経験でした・・。
2005年08月06日
-

恐竜の足跡
スクレ市の近郊に「恐竜の足跡」を見れるところがあります。話によると、むかーしむかし恐竜がいた時代の地層が大地震によって盛り上がって発見されたとのこと。1ヶ月くらい前に、観光客向けのスクレ発「恐竜ツアー」に行ってきました。ツアーは、ガイド付き。英語かスペイン語で説明してくれます。スクレ市内から車で30分。足跡はセメント工場の敷地内にあります。そんで、盛り上がったビルみたいな地層の壁面に延々と足跡が・・・。へぇーと感心することも多かったけど、ひとつどうしてもぬぐえない疑問が。「恐竜ってこんなに歩幅狭いんだっけ???」だってね、その足跡、いや確かに足跡っぽいんだけどさ。どう考えても歩幅がおかしいんですよ。30センチとかそんなもん。どうやって歩いてたんだよっ!人間の歩幅よりせまいじゃん!と思わずツッコミたくなります。あはは。専門的なことはよくわかりませんが、ぜひその謎を解明したい・・・。ま、それなりに楽しめるので、スクレにお越しの際はぜひ。写真は、模型を使って説明するガイドさん(空が青い!)と、恐竜の足跡(わかるかな?)。ちっちゃい恐竜の模型とガイドこれが足跡
2005年07月31日
-
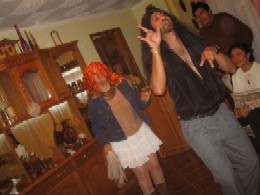
こんな上司って・・・
今、ボリビアの現地NGO(というか財団?)で働いています。こないだそこの上司の誕生日会があったので行ってきました。こっちでは、自分の誕生日に親族や友達を招いて、自分がみんなをもてなすという習慣です。上司はボリビアではお金持ち~の部類に入る人で、スクレ市内にある自宅はすんごい豪邸。星が見える天窓付きの風呂とか。家の中を案内してもらって「すげ~すげ~」と日本語で連発しちゃったよ。で、パーティーが盛り上がってきて、案の定、踊る。踊る。この上司、前々からかなりのアホキャラだとは思ってたけど、やっぱりね。自らヅラをかぶり奇妙な動きをしまくってて、気持ち悪いーと思いつつお腹抱えて笑った笑った。その脇でそんな両親を冷ややかに見つめる思春期に差し掛かった息子。最後には私もヅラをかぶって一緒になって踊ってしまいました~。写真はそんなアホ夫婦の様子。2人とも原型とどめてません(笑)。こういうヒッピーいそうだよね。しっかし、普段私が住んでる村の人たちの暮らしとは全然生活レベルが違って、そのギャップにちょっと変な感覚。村では数年前にやっと水が恒常的に使えるようになったばかりだというのにね。都市をちょっと離れただけでこんなにも貧富の差がある。これもボリビアの現実ですね。
2005年07月24日
-

15歳のお祝い
先週土曜日、またまた村の祭りに行ってきたよ。村の幼稚園で働いている人の娘が15歳の誕生日を迎える、そのお祝い。ボリビアでは、女性の15歳の誕生日は、日本の成人式みたいな意味があるらしく特に盛大にお祝いをするんです(ちなみに男性は20歳の誕生日)。お祭りは、そのカルメンちゃんの自宅で行われ、夕方から続々と村の人たちがお祝いに駆けつけ、日が暮れるころにはものすごい量の人、人、人。スクレから呼んだらしきバンドの生演奏まであったよ。金かかってるなぁー。訪れた人はカルメンの前に列を作り、一人ひとり順番に彼女にお祝いの言葉をかける。そして、それぞれ10ボリビアーノ札を彼女の服に縫い付けていく。この習慣、どんな意味があるのか聞いてないけど見ててなんか面白かった。将来お金に困らないように、とか、そんな意味があるんかな?私もみんなのやり方に習って、彼女に「Felisidades!」(おめでとう)と声をかけ、お札を縫い付けた。相変わらずみんなチチャ(とうもろこし酒)を大量に飲んで、でろんでろんに酔っ払ってた。私もまたもやしこたま飲まされましたとも・・・。祭りは明け方まで延々と続き、みんな飽きもせず踊り明かしてた様子。私は1時には帰ったけどね。あー、楽しかった10ボリビアーノ札を縫い付ける村人
2005年07月18日
-
オスカルと話した日本のこと。
こないだ村でオスカルという名のおじいさんに声をかけられた。最寄りの町スクレに比べて私の村は標高が1000mほど低く温暖なので、スクレの人の避寒地としてすんごい別荘がたくさんある。目を見張るほどの豪邸がずらずらーっと並んでる。川もあるから水遊びできるし。オスカルもどうやらvacaciones(バケーション)でその別荘に来ていた人らしく、私とは初対面だった。普段は村に住んでないし、村の人(ケチュア族)とは明らかに違う顔立ち(白人系)。ボリビアのコチャバンバという町出身。で、「どこの国から来たんだ?」と聞かれ、日本人だって言うと、「ヒロシマ、ナガサキにBomba Atomica(原爆)が落とされたよね」と。ボリビア人と話す時、私が日本人だってわかると必ずと言っていいほど「ヒロシマ」「ナガサキ」のことを聞いてくるのには、正直少し驚いている。日本人が意識している以上に、日本は「被爆国」として知られている。反対に、日本人自身はこの大事な歴史について深く考える機会をあまり与えられていない気がする。オスカルは日本のことをすごく知っていた。第二次大戦の前と後では、日本はものすごく変わったこと。特に、女性はそれまでCerrado(スペイン語で「閉ざされている」の意味)だったけど、戦後は女性の意識も社会的立場も変わったこと。そして、いい意味でも悪い意味でもアメリカの影響をものすごく受けていること。「ボリビアもアメリカの影響・コントロールが強くて、世界の色んな情報にフタがされているんだ。だから主に本を読んで世界の色んなことを勉強したんだ。日本のことも本で知った」と。確かにボリビア政府はアメリカの影響を強く受けてると聞いたことがある。コカの葉の栽培に規制をかけようとしてるのも、結局はアメリカが中南米からの麻薬流入を規制したくて、ボリビア政府に圧力をかけてるかららしいし。オスカルはアメリカをあんまり好きではないみたいだった。そりゃ、そうだよね。アメリカって南米でもひどいことをしてきた。虐殺とか。色々、いろいろ。おっと、話がそれてしまったが。ほかにもたくさん話をした。彼は戦時中と戦後数年間、ドイツにいた。戦後のドイツは焼け野原で何もなく、とても厳しい生活をしていた、と。その後、漁船に乗ってノルウェーの極寒の氷河の海で仕事をしていたこともあるそう。だから、寒いのは嫌い。そして、戦争のすべてをとても憎んでいる。私が「私の両親は原爆のこと、第二次大戦のこと、戦争の残酷さについて色々教えてくれた。もちろん両親も戦後生まれではあるけれど、それを伝える大切さを感じていたようだ。」と話すと、オスカルはとても感慨深い顔をしていた。何を感じていたのかははっきりとはわからないけれど、彼と心で通じ合えた気がした夜だった。
2005年07月17日
-
七夕
突然ですが、もうすぐ7月7日。七夕ですね。日本はまだ梅雨明けしてない地域が多いと思うので、今年の七夕も雨模様なのかな?七夕といえば、天の川。天の川、きっと日本ではどんなに天気がよくてもなかなか見ることができないんじゃーないでしょうか?その天の川。私のいる村では普通に、そしてかなり濃く見れます。毎晩空を眺めているんだけど、星も多いし、天の川が真っ白に見える。本当にすごい。これだけ天空が大きく感じられると、「空ってほんとは丸いのかも?」なんて気になってくるよ。天然プラネタリウムって感じ。こんな気持ちのいい空気を日本のみなさんへー。今年は何をお願いしよう?やっぱり、これかな。「私とつながってくれているすべての人の健康と幸せを。」ボリビアより。たくさんの愛を込めて。Con mil besos.
2005年07月04日
-
愛知万博
愛知万博、もう行きましたか?開催期間はすでに半分をすぎ、残り3ヶ月。この万博、私の実家・名古屋のすぐ近くの瀬戸市&長久手という所でやっています。私の姉がこないだ行ってきて「かなりおもしろいっ!」らしいです。7月にはうちの両親も一緒にまた行くって。あーあー、私も行きたかったなぁ!企業パビリオンでは日立とかトヨタとかの一流の最先端の技術を見れるらしい。グローバル・コモン(外国館)は、世界各地からの出展国が自国の自然・文化・伝統・習慣などを展示紹介していて、興味と理解を深めてもらおう、というもの。ボリビアも、ペルー・ベネズエラ・エクアドルと共同で「アンデス共同館」を出展してます。開幕当時、「アンデス共同館」は4カ国の足並みが揃わず(?)なかなか開館できなかったらしいけど、こないだようやく予定されていた全ての展示が公開されました。「足並み揃わない」ってところが南米っぽい・・・。ボリビア国内だけでも足並み揃ってないようだし(政治的な部分でね)。トピックスは→http://www.expo2005.or.jp/jp/E0/E1/head/0626_003.htmlボリビア情報→http://www.expo2005.or.jp/jp/A0/A16/A16.3/A16.3.2/index.html姉情報によると、ボリビアコーナーにはお土産品として、アルパカのマントとかオカリナとかボリビアンミュージックCDとか色々置いてあるそうです。ボリビアは鮮やかな色彩の織物が有名なので、それも置いてあるのかも?これを機にボリビアや南米に関心を持ってくれる人が増えるといいなぁー。万博行った人、ぜひ感想聞かせてくださいね!
2005年06月28日
-
菌
村で生活を始めて間もないのに、早くも、お腹に菌を飼っていた。!サルモネラ菌!日本では結構騒がれちゃう菌だと思いますが、こっちでは普通にみんな保菌者らしい。菌がいるって言っても、抗生物質飲めばすぐにいなくなるらしいので大したことないんですけどね。しっかし、処方してもらった薬の高いこと!ボリビアの物価と比べるとアホみたいに高くてビビリましたよ、私は。ちなみにボリビアでは1Bs(ボリビアーノス)=約15円。ミネラルウォーター600mlが1.5Bs(約22円)。おしゃれなカフェ屋でのコーヒーが4Bs(約60円)。地元の人向けのランチが6Bs(約90円)。ネット屋1時間で2Bs(約30円)。こんな感じの物価。私が買った抗生物質は1錠あたり約9Bs(約135円)!1錠あたりだよっ、1錠あたり! 1錠分のお金でネット4時間半もできるじゃんっ!!ま、医療費は所属先が全部払ってくれるので問題ないのですが。話を元に戻して。で、いつ感染?と考えてみたら、心あたりはラ・パス。ラ・パス滞在中に突然の嘔吐・下痢に襲われたことは、この日記でも書きましたが、あの食あたりの時にサルモネラ感染してたんじゃーないか、と。まぁ、薬飲んで様子見ますー。みなさんもちゃんと火の通ったもの食べましょうねー。特に日本は今から夏だものっ!ではまた。ちゃおー。
2005年06月22日
-
大統領辞任。私は再びサンタクルスへ。
6月6日(月)深夜、ボリビアの大統領が辞任しました。ボリビアは常に政情が不安定で、特に今年に入ってから反政府運動が活発化してたのですが、5月中旬からそれがかなり激しくなり混乱しまくってました。そもそもボリビアにはいろんな問題が山積しているらしい。1.天然ガスの国有化問題(天然ガスを他国に輸出しまくっているため利益が国民に還元されてないことに怒っている)。2.コカ栽培農民による反発(コカ栽培を禁止しようとする政府に、農民が反発)。3.先住民系の人々が抱えている社会的不利益に対しての権利拡大要求。4.サンタクルス県が自治権を要求して国民投票&憲法改正をを要求している。などなど、ほかにも色々問題があるようです。で、そうした反政府運動の行動のひとつとして、「ブロケオ」と呼ばれる道路封鎖がしょっちゅう全国各地で行われます。これは、幹線道路に農民が石や木などを大量において道路を封鎖し、流通や人の流れを遮断。経済もストップさせる、という地味だけどかなり痛手のある方法。5月中旬から首都ラ・パスはこの道路封鎖によって、食料やガソリンが全く入ってこなくなり、次第に水や食料が尽きてきて兵糧攻め状態でした。空路も陸路もストップしてたし。そして次第にデモが激しさを増し、ついに警察と衝突。警察が空砲や催涙弾を打ちまくり騒然とした状態がこないだまで起こってました。逮捕者も続出したらしい。私はスクレで、ラ・パスの映像をテレビで見たけど、まるでそれは市街戦のようで、信じられなかったなぁ。4月にラ・パスにいたときはほんとに何もなくて平和な状態だったけど、聞いた話によると、今年に入ってから4月だけが唯一落ち着いていた時期だったとか。ラ・パスにいる間に何もなくてほんとにラッキーだった。結局この事態を収拾できない、と判断したのか大統領が辞任表明。新大統領を決める会議が急遽スクレで行われることに(ラ・パス市内の混乱によって議員が国会にたどり着けなかったらしい)。で、その会議が行われる6月9日(木)、多分スクレでも暴動や衝突が起こるだろうということで、急遽サンタクルスへ避難することになったのです。サンタクルスからスクレへ戻ってきたばかりだというのに、またもやサンタクルスに舞い戻ることに・・・。なんてこったー。ま、でもサンタクルスは極めて平和で、ラ・パスの混乱なんてどこ吹く風といった感じ。私もやることないので、毎日映画を見に行ったり日系人移住地へ行ってみたり。新大統領が決まったけど、あくまでも暫定政権なので今後どうなるか分かりません。今の時期にボリビアにいる旅行者は大変だったんじゃないかな。南米はただでさえスペイン語できないと旅行しづらい(と思う)のに、今回みたいな政治・社会不安が起こってしまうとなおさら大変。そんなこんなでしたが、スクレももう落ち着いているとのことで今日サンタクルスから戻ってきました。日本にいる皆様ボリビアは今こんな状況ですが、私の生活圏はかなり平和なのでほんとに大丈夫です!安心して下さいねー!
2005年06月13日
-
サンタクルス
6月2日から行っていたサンタクルス市より無事スクレに戻りました。サンタクルス、かなり気にいってしまった。気候は東南アジアのタイとかマレーシアみたいに、暑くて湿気がたっぷりで、飛行機を降りたとたん、肌にまとわりつくジメジメ感がなんとも心地よかったー。アジアの心地よさを思い出しました。気候も全然違うけど、それ以上に違うのは、見渡す限りの「平地」。スクレは標高2800mだけど、サンタクルスは500m。山なんてものはどこにも見えず、生えている木も熱帯系ジャングルといった感じ。同じボリビア国内なのに、ブラジルに来たような変な感覚。人の顔つきも格好もすべてがラ・パスやスクレとは違うんですね。それから。サンタクルス市の近くにはコロニア・オキナワという日系人の移住地があります。第二次大戦後の荒廃の中、沖縄の人たちが新天地を求めて南米の各地に移住。(沖縄出身以外の日本人ももちろん移住。でも南米全体でも割合として沖縄出身者が多い)ここボリビアでも、より住みやすい場所を求めて最終的に住み着いたのが、今のコロニア・オキナワ周辺の入植地だそう。世界中で、正式な地名として「おきなわ」という名前がついているのは、日本の「沖縄県」とボリビアの「コロニア・オキナワ」だけらしいです。うーん、興味深いですねー。1年ほど前には、沖縄県の稲峰知事もコロニア・オキナワを訪問してます。(ちなみにこの訪問中に、在沖縄米軍ヘリが沖縄国際大学へ墜落したという事故が発生。稲峰知事は予定を中断して日本へ飛んで帰ったらしい)。サンタクルス市内には日系人も多いし、日本食料理屋も結構あります。久々に食べたしょうゆラーメンは激ウマでしたっ。「スーパーオキナワ」という日本食材店もあり。沖縄の「エイサー」という踊りを踊るお祭りなんかもあるそうです。楽しそうー。実は大学時代に、アメリカとハワイの日系人についての講義を受け、おもしろくてかなり惹きつけられた思い出があります。あれ以来、ずっと「日系人」について気になっていたという経緯があって、今回せっかく南米にいるのだから色んな日系人入植地を訪ねてみるのもいいかなぁと思っています。ボリビア旅行で高山病が心配なら、サンタクルスから入るのがおススメ。今回は会議で忙しかったけど、次回はもっとゆっくりサンタクルスめぐりをしてみようっと。
2005年06月06日
-
まとめて
というわけで(←どういうわけ?)、日記を何日か分、まとめて書いてしまいました。5月25日以降分、結構たくさん書いて更新したので、よかったら読んで下さいねー。明日から1週間ほどサンタ・クルスというボリビア第2の街に行ってきます。遊びじゃなくて、会議があるんですーーーー。サンタ・クルスはブラジルに近い町で、気候もラ・パスやスクレとは違い暑いらしい。人も「同じボリビア人?」というくらいブラジルっぽいと聞いてるので、またボリビアの違う面を見れそうです。帰ってきた頃にサンタ・クルス報告しますねー。
2005年06月01日
-
COCA
コカ。ご存知のように、麻薬コカインの原料はコカの葉です。コカの葉から取れる成分を精製するとコカインができるそうです。南米ではこのコカが大量に採れ、中でもコロンビアが有名ですね(怖いよー)。何だか麻薬、マフィア、密輸、なんて暗いイメージばかりが浮かびますが。が、しかーし。ここボリビアでは、農民を中心にみんなが普通にコカの葉をたしなんでいます。タバコみたいな感覚ですね。葉っぱなので、別に麻薬作用なんて無く、それはもうほとんどただの「嗜好品」という感じ。口に入れたらすぐに飲み込まずにしばらく噛み潰し味わう、らしいです。おいしいんかな?コカの葉を栽培する「コカ農家」も存在し、彼らはコカ栽培で生計を立てています。村人の中にもコカの葉を売ってる人います。葉っぱを食べるだけじゃなく、「コカ茶」もあります。これは高山病による頭痛や消化器官不良にとても有効で、私もラ・パスにいた時に毎日飲んでました。古代南米人の生活の知恵なんでしょうね。ハーブティーみたいでかなりおいしいですっ!多分日本には持って帰れないけど・・・。こんな感じで、ボリビアでは特に違法でもなんでもないのですが。一方で、どうやらボリビア政府が麻薬絡みの理由でコカ栽培を禁止しようとしているらしく、それに対してコカ農家が猛反発し、ボリビアの政情不安の一因になっているのです。栽培が禁止されたら、コカ農家にとっては生活できなくなるわけですから一大事だよなぁ。ところでCOCA COLAってCOCAの成分入ってるの?誰か知ってたら教えてくださーい。
2005年05月31日
-
イモ、イモ、そしてイモ。
はっきり言ってイモばっかりです。予想してたとおり、ボリビアの(南米の?)ジャガイモ消費量は半端じゃーありません。トウモロコシはそんなでもないけど。毎食毎食、何を食べてもジャガイモ氏が「今日もよろしくね」と言わんばかりに、姿かたちを変えて出てきます。マッシュポテト、フライドポテト、ふかしイモ、ベイクドポテト、小さく角切りされ米にまぎれてたり。おなかいっぱいになるからいいんだけどねぇ。このペースだと、この先2年間で一生分のジャガイモを食べることになりそう。いや、まじで。でも、さすがジャガイモ原産地。イモの種類はすごいです。ジャガイモだけでも100種類以上あるのです。料理の仕方によって、どの種類のジャガイモを使うか変わるらしいのですが、素人の私にはまったくわかりません。そして、日本のサツマイモみたいな甘い「カモテ」という名のイモもあります。これ、焼き芋みたいですっごくおいしいですよ!イチ押し!こんなこと書いてたらお腹減ってきた・・・・。
2005年05月29日
-
車
世界各地、どこででも日本車は走ってます。特に、「開発途上国」(と見なされている国)では、日本の中古車が溢れてることが多いですよね。ボリビアもご多分に漏れず、日本の中古車がたーーーーーくさん走っています。日本の基準ではもう使用不可となった中古車が、ボリビアではまだまだ現役で大活躍。街中ですぐにそれとわかるもの。それは、市民の足のバス。スクレのバスは、いわゆるマイクロバス、みたいなやつです。その車体には、「西○ライオンズスポーツスクール」「○×旅館」「△△自動車学校」「○×幼稚園」という文字が。日本の中古車をそのまま持ってきて、ハンドルを左に付け替えて、ドアも反対側に付け替えて使ってます。私たち日本人が「もうダメだよこれ、使えない」とか「新しいのに買い替えちゃえ」と言って廃棄されたものが、こうして他の国でリサイクルされてるんですねー。ま、資源の有効活用もしくは効率的なリサイクル、と考えれば別にいいんだけど。でも、日本の生活の中で、まだまだ使えるものを「古くなったから」と言って簡単に捨ててしまってはいないか?と考えさせられる光景です。こっちの人は、モノが壊れても簡単に捨てない。直して直してもう一度使えるようにする。その技術も普通に身に付いている。新しいのを買う経済的余裕がない=モノを大事にするっていう関係もあるんでしょうけど。ちなみにブラジルでは、日本で使わなくなった地下鉄の車両がそのままブラジル地下鉄で使われてます。車輪の幅が日本の規格とほぼ同じなので、そのまま有効活用できるんだそうですよー。
2005年05月28日
-
母の日
今日5月27日はボリビアの「母の日」でした。「27日は母の日の祭りをやるから村にいなさいっ」と前々から言われてたから、週末スクレに行こうと思っていたけど断念。午前中。村でよくご飯を頂いたり、一緒にパン作りをしている家族の長女(16歳)と一緒に、その長女のおばあさんのお墓参りに行きました。ボリビア人は所かまわずゴミを捨てる習慣があるんだけど、墓地も例外ではなかった。亡くなった人が眠る神聖な墓地(と私は思う)なのに、ペットボトルやビニール袋が散乱・・・。ま、世界各地で宗教や文化・習慣によって「浄・不浄観」が違うので、日本の基準をここに持ち込むことはできないとわかっているものの、やっぱりちょっとびっくり。墓地には、小さな棺も多く「子どもの?」と聞くと、そうだと言う。以前にも書きましたが、村には診療所がなく普通に治療が受けられない状況。よっぽど重篤な時には1時間以上かけてスクレの病院まで行くそうですが。それゆえ、乳幼児や妊婦さんやお年寄りなどは命を落とす危険性が高いとのこと。乳幼児は特に衛生環境が悪いし、抵抗力も大人ほどないので、ちょっとしたことで亡くなってしまったりします。実際、ボリビアの乳幼児死亡率は南米でダントツ1位。悲しい現実です。さてさて、昼はその家族と一緒に鳥料理を作りました。釜で焼いた鳥まるごとは、ほんとーにほんとーに旨かった・・・(思い出すだけで、あっ、ヨダレが・・・)そして夜は・・・。村人ほぼ全員が集合。母の日を祝う祭りが始まった。初めに、ある男性が「母の偉大さ、母のありがたさ」についてスピーチ。それを聞いていたみんなが、すすり泣き。私の隣に座っていた、仲良しのアリシアという女性は去年母を亡くし、スピーチを聞いて大泣き(ちなみに親族を亡くした人は2年間喪に服すため黒色の服しか着ないそうです)。私も、日本の両親を思い出し大泣きしてしまいました。村へ来て約2週間。緊張、不安、の連続で精神的に決して楽ではなかった2週間(たった2週間だけどね)。そして、私の南米行きを理解し、快く送り出してくれた両親、家族、友達。そんな色々な思いがドーッと来て、思わず泣いてしまったのでした。この場を借りて改めて。父さん、母さん、本当にありがとう。そして、私と繋がってくれている全ての人に、ありがとう。スピーチの後がすごかった。チチャ(トウモロコシで作ったドブロクみたいな酒)を「飲め!飲め」と大量に振舞われ、というよりも無理やり飲まされた・・・。そして、泥酔。さらに、ガンガン大音量の音楽に合わせてみんな踊る、踊る。私も踊る。もー、どうにでもしてくれーって感じで(笑)。このチチャという酒。トウモロコシの香ばしい香りがし、でも何か炭酸っぽい、という酒。好きな人は大好きだと思う。けど、私は蒸留酒の方が体質的にあってるので、こういう醸造酒はちょっとキツかったー、正直。歌と踊りと酒は、延々夜中の1時まで続いたのでした。村へ入って間もないこの時期に、こういうお祭りがあってよかった。村人と一緒になって酒を飲み、踊り騒ぐことで、彼らとの距離が少し縮まった気がしたのでした。
2005年05月27日
-
チュキサカ県の日
スクレの町はチュキサカ県という県に属しています。今日5月25日は「チュキサカの日」だったらしいです。どうして「チュキサカの日」なのかはまだ調べてないのだけれど・・・。私は村にとどまってましたが、スクレ市内ではパレードがあったり町の中心のPlaza(公園)でお祭りがあったりと、賑やかだったようです。あっ、ボリビアのカルロス・メサ大統領も来たらしい。そういえば、スクレという地名の由来について豆知識。そしてボリビアという国名の由来についても。まずは「ボリビア」その昔19世紀前半まで、南米大陸はスペインの植民地だったのですが(ブラジルのみポルトガル植民地)、ボリビアをはじめ南米各国の独立運動を指揮したのが、Simon Bolivar(シモン・ボリーバル)という将軍。このシモン・ボリーバル将軍の功績により1825年ボリビアは独立を達成でき、将軍の名にちなんで、この国を「ボリビア」と名づけたのでした。★補足→シモン・ボリーバルは同じ南米ベネズエラの出身。したがって、今のベネズエラの正式国名は「ベネズエラ・ボリーバル共和国」となっています。通貨単位もボリビア、ベネズエラ共に「ボリビアーノ」を使用。そして、「スクレ」ボリビア独立後、1839年この町が首都に制定され、ボリビア初代大統領スクレ将軍の名にちなみ、「スクレ」と命名された。というわけです。そして1900年代に政府の中枢機関がラ・パスに移されるまで、首都スクレはボリビアの政治の中心であったのです。シモン・ボリーバル将軍についての本を日本から持ってきてるので、ボリビアの姿を知るためにも読み始めようと思ってます。
2005年05月25日
-
村での数日
村へ移動して約1週間。今日は週末なので、スクレ市へ上がってきています。村からスクレまでは乗り合いタクシーで約1時間。スクレの標高は2800m、村の標高は2000m弱らしく、その差が約1000mあるので気候が全く違って体調を壊しやすいらしい。確かにスクレは今、結構寒いです。村では昼間は夏みたいに暑いのにねー。さて、村で数日間すごして見ましたが。今のところ、村を散歩しながら村人と挨拶を交わし世間話をし、顔見知りになることから始めています。村で生活・仕事をするのに、村人を知らないことには何もできないしね。毎日が「みんなと挨拶・自己紹介キャンペーン」みたいになってる(笑)。すでに色々と世話を焼いてくれるお母さんと仲良くなり、夜ご飯を頂いたりしています。「女の子一人で住んでるなんてかわいそう!」って感じでね。その人の家で、子供たちと一緒にテレビを見たりもしてます。村でテレビを持ってる人はかなりまれ。周辺の家の人たちが大勢集まって、広いとは言えないその部屋で肩を並べあって見てる、という状態。大勢いる子供たちは、いったい誰が誰の子供なんだか・・?子供たちは初めは私の存在が珍しいらしく、遠巻きに見ていたり、こっちが笑いかけても恥かしがって逃げていったりします。でも、こっちが顔芸したりするとかなり受けるし、そんなことをしながら、徐々に仲良くなっていってる(てなづけてる、とも言う?)どこの国でも、子供は本質的には人なつっこいものなのかも、ね。ただ、子供たちを取り巻く環境は決していいものではなさそう。栄養状態が悪いためか、年齢の割りに体がすごく小さいし、はっきり言って着てるものも汚い。そして、靴を履いてる子はほとんどいなくて、ビーチサンダルか裸足。お風呂に入る習慣もあんまりないので(というよりも家にシャワーを持ってる家庭は半分くらい?←要調査です)、衛生的に良くない状態だと言えます。足に皮膚病を持ってる子もチラホラ。もちろん、子供特有の、ところ構わず駈けずり回って遊ぶから、余計汚くなるっていうのはあるけど・・・。そして村には病院がない。ドクターもいない。少しずつ少しずつ、村にどういう問題があるのか探っていこうと思った数日でした。
2005年05月22日
-
白の街、スクレ。
5月13日(金)、首都ラ・パスからスクレ市に移動。ラ・パスを出発する飛行機の助走の長いこと、長いこと。どうやら気圧と高度の関係で離陸までにかなりの助走が必要らしい、と誰かが言ってたなぁ。飛行機の中から見る景色もすばらしかったー。山の頂上すれすれのところを飛ぶしね。さて、ここスクレは、町並み全体が世界遺産になっているところ。標高2800m。ラ・パスより「かなり酸素濃い!」。相変わらず坂は多いけど、ラ・パスの比じゃない位ゆるい坂だし数も少ないからとっても楽。スペイン植民地時代に建てられたコロニアルな建物が沢山あって、それらは全て、真っ白な建物に赤レンガの屋根。世界遺産ゆえ、新しく建物を作るときは必ず壁を白く塗らなきゃいけない、という決まりがあるそうです。町全体が白いし、どの通りもよく似てるから、いったい今どこを歩いてるんだかよくわからんくなってくる。迷いまくり・・・。でも、こじんまりしててすごーくいい町です。ラ・パスみたいに高層ビルなんてないし。大学町だから学生も多いみたい。世界各地からの観光客も多くて、「ここ、ほんとにボリビア?」と疑いたくなるようなおしゃれなカフェやレストランもたくさん。まじでびっくりした。スクレに到着した日に、配属先であるNGOの人に連れられて、活動予定地の村を視察してきました。スクレはすごく街なのに、ちょっと離れるとまだまだ本当に小さな村(と言うか「集落」)が多い。水道と電気は通ってるけど、家の中にトイレがある家庭はまだまだ少なかったり。スクレの町との格差に驚く(ちなみにラ・パスやスクレの街中では、物乞いの親子がたくさんいます)。続いて、村人の前で自己紹介。ちょっと緊張。うまく溶け込めるように頑張らなきゃねー。このあたりの集落では、スペイン語のほかにケチュア族の言語であるケチュア語も話されてます。ケチュア語しか話せない人も結構いるから、その習得も必須。あーーーーー、スペイン語もままならないのに、その上、ケチュア語かよっ!でも、住民とコミュニケーション取るには覚えるしかないからなぁ・・・。私が住む家も見たけど、本当に質素な部屋。窓が一つあるだけでほかには何もない。これからここに住むんだなぁ、とぼんやり考えてました。ちなみに村人は先住民系のインディヘナの人達です。余談ですが(前にも書いたかな?)、南米の先住民インディヘナは、元々は私達日本人と同じ人種的ルーツを持ってるという説があります。モンゴル系ってことね。アジア大陸からアラスカを通り、北アメリカ大陸に渡った後、南下して南アメリカまで来たらしい。だから、顔つきが良く似てるんです。「こういう顔のおじいちゃん、日本にもいるいるっ!」っていうことが多い(笑)。いや、まじで。そんなかんじで視察終了。むむむ、ほんとにやっていけるんだろうか、と一抹の不安を抱きつつも、いやーやって行くしかないでしょ、だって来ちゃったの自分だし、なんて思いながらスクレへ帰っていったのでした。いよいよ明日午後、活動地のその村へ移動します。生活用品も買い込んだしねー。洗濯用のタライとかバケツとかトイレットペーパーとか食器とか、いろいろ、いろいろ。あっ、マットレスも買わなきゃ。とにかくドキドキ、ワクワク、ハラハラ、ウキウキ(っつーか死語?)です。これからが本番。がんばりまーす。
2005年05月15日
-
ちょっとだけ、ボリビア教育事情
今日は語学学校の最終日。スペイン語でプレゼンをしました。私が選んだテーマは、ボリビアの小学校の就学率と識字率について。たった10分のプレゼンだったけどかなり準備が大変だったよぉ・・。全然ボキャブラリー足りないし。ボリビアの教育についてちょっとお話。小学校は6-13歳の8年間。その上に高校みたいなのが4年間、そして大学が5年間です。小学校の就学率。都市部では90%の子供が入学、最終的に卒業できるのはその半分。農村部では、たった50%の子供しか入学できず、同じくその半分しか卒業できません。また、ボリビア全体の識字率は85.6%(男性92.1%、女性79.4%)。ちなみに日本の識字率は99.8%(男性99.9%、女性99.7%)です。このボリビアの小学校就学率と識字率は、中南米の中でも最低レベルだそうです。私が調べたところによると理由は主に3つ(もちろん都市と農村部では若干違う)。●その1「お金」小学校は義務教育・無料だけど、勉強に必要な文房具や本などは実費。でも、「開発途上国」(便宜上ここではこう表現します)の多くで見られるように、貧富の差がかなり激しく、子供の文房具代さえ払えない家庭も多いです。なので、お金がないから、結果的に子供を学校に通わせることができない。さらに、そういった家庭の親は、子供が学校に行く事よりも働き手となることを望んでます。●その2「設備」ボリビアでは1990年代に入るまで30年間に渡り、新しい公立学校が作られなかったらしい(政治的な理由?だと思う)。なので、今ある校舎はかなり老朽化して、学習に必要な椅子とか机とか色んな設備が足りない。なので、子供たちにとって学習環境・設備が悪く十分に勉強できない。●その3「男・女」今でも農村部を中心に「女の子に教育は必要ない」と考える人が少なくありません。家の手伝いをして、いいお嫁さんになることだけが女性にとって大事なこと、という考え。もちろん学校へ行くくらいなら、働き手になってほしい、という社会状況も多いに関係してます。教育の問題ひとつをとっても、ボリビアの社会構造、人種構成、価値観、経済状況、政治などなど関係することがいっぱい(当たり前だけど)。でも、そうやって多面的に捉えていかないと何も見えてこないんだろうなー、と。
2005年05月10日
-
なんてことでしょう・・・
それは一昨日、さぁ寝ようと思いベットに入った直後でした。突然の吐き気。それを無視するべく一旦眠りについたのですが、1時間後に起きてしまいました。そしてトイレに直行。嘔吐。下痢。1時間おきにトイレに行ったので全然眠れず。翌朝起きてもそれは収まらず、さらに熱まで出る始末。あー、大変。多分、食あたりじゃないかと。思い当たるのは一昨日の昼に食べた鳥料理。人が言うには、往々にしてちゃんと熱が通りきってない場合があるらしい。うーん、それにしてもびっくりです。だって、今までの旅行(東南アジアが主)で、どんなに汚いゲストハウスに泊まっても、どんなに不衛生な(と思われる)屋台でご飯食べても、緑色の川の水で歯みがいても、カフェオレ色のメコン川の水を間違って飲んでも、ちっともお腹壊さなかったし虫もお腹に飼わなかったのに・・・・。多少の細菌にはかなり抵抗力あると思ってたんですがねぇ・・・。おそるべし、南米、アンデス。思うに、やはり高地での生活は、自分が自覚している以上に相当身体に負担をかけるものなんでしょうね。疲れやすくなるし、知らず知らずのうちにかなりの紫外線量も受けてるはずですし。こちらへ来て約1ヶ月。疲れがたまってくる時期でもあったんでしょう。でも、もう大丈夫です。心配しないくださいねー。ちょっとやそっとのことじゃくたばりませんから。ええ、くたばってたまるもんですかっ!しかし、病気の時はやっぱり日本の味が恋しくなる・・・。
2005年05月05日
-
遺跡と湖
今日は友達とティワナク遺跡とチチカカ湖へ行ってきました。ラ・パス市内から約1時間、延々バスに揺られてティワナク遺跡へ到着。それよりまず、みなさんティワナク文明・遺跡って何かご存知ですか?私も実はこないだまでよく知らなかったんです。マチュピチュでお馴染みのインカ文明やマヤ文明ほど有名ではないので、「なぁに、それ?」という感じでしょうか。ティワナク文明は「プレ・インカ文明」とも言われ、15世紀にインカ族によるインカ文明が花開く前に長い間、南米で栄えていた高度文明です。その期間、実に3000年!(←文化人類学者のガイドさんの話と博物館の展示パネルによる)つまりティワナク文明は、紀元前2000年頃~紀元後1000年頃まで、気の遠くなるくらい長い間、その栄華を誇っていたそうです。遺跡は、ラ・パスより更に上、標高3800mにあります。どうしてわざわざこんな高所に都市を築いたのかは未だに謎だそう。一大宗教都市としての機能も果たしていたそうです。遺跡内の石造りの建物は、石の一つ一つが「ありえないっ!」っていうくらい精巧に裁断されているし、当時の人々が使っていた用水路もちゃんと残っていました。宗教儀礼の時に大勢に向かってしゃべるための、石造りの拡声器もあって、何だかどれもこれもすごすぎて、訳がわかりません(笑)。一体どうやって作ったんでしょうかね・・・。どこの国でもそうですが、昔の人の技術って本当に素晴らしいです。感動です。便利になればなるほど、人間の能力は退化していってる気がします。ちなみに、遺跡はまだ10%しか発掘されておらず、残りの90%はまだ土の下に眠っているとのこと。もったいない・・・。どうやら、発掘調査するための資金が政府に無いらしいです。遺跡の次に、ペルーとボリビアにまたがるチチカカ湖へ行きました。ここも海抜3890m。船が航行する湖としては最高所。面積は琵琶湖の12倍。対岸はもうペルーです。ここでは色々な魚が採れるそうです。それから、ホントかどうかわかりませんが、ダイビングもできるらしい。ぜひ、一度挑戦してみたいですねー。
2005年04月30日
-
たまりません、ラテン。
こないだの日曜日は、ラ・パスの中心街を徘徊してみました。毎週日曜日、メインストリートは歩行者天国になり、おもしろいイベントを色々やってます。その中でも特に目を引いたのは、カーニバル用の色鮮やかできらびやかな伝統衣装を着た子供たち・大人たちが、代わるがわる音楽に合わせて踊りまくっている姿。本当にすごいです。まだすごく小さい子供(3、4歳?)でも、その踊りはすでに玄人並(特に腰の動き・・・)。さすがラテンな国!いつでもどこでも誰とでも、音楽と踊りは欠かせないんでしょうねー。リズム感、音感が体に染み付いてる、とでも言いましょうか。あとは、南米ではお馴染みの音楽「フォルクローレ」を演奏してる人たちもいました。東京でも、秋葉原とか銀座とか新宿あたりの駅前で、ポンチョを着た人たちがちょっと変わった楽器を演奏してますね。アレです。曲としては「コンドルは飛んでいく」がやっぱり有名どころでしょう。ケーナ(たて笛)、サンポーニャ(こちらもたて笛の一種?説明難しいです)、チャランゴ(10弦あるギターみたいなやつ)。などなど、南米独自の楽器が実にたくさんあります。そして音色が素晴らしくよいんですっ!!懐かしい、というか何というか・・・・。ラ・パスにはフォルクローレを演奏するグループがたくさんあるらしく、演奏を聞ける飲み屋も結構あるみたいです。こっちにいる間に聞きにいってみまーす。
2005年04月26日
-
すごかった!
今日はラ・パス市内でハーフマラソンがありました。私の友達のお父さん(ボリビア人)が出場するのでその応援も兼ねて、朝から見物に行ってきました。予想以上にものすごい数の人が走っていて、正直びびりました・・・。ハーフと言えど、ここはラ・パス。くどいぐらい何度も言いますが、ここ、富士山の上ですよ・・・。おまけに急な坂がものすごく多いのです。その急な登り坂・下り坂を、見事にすごいスピードで走り去って行くボリビアのランナー達。恐るべし。ホントにすごい光景でした。男性の部、女性の部、車椅子の部(年齢別になっていたかは不明)と分かれていたのですが、車椅子ランナーは見ていて本当に危なっかしいくらい、下り坂ですごいスピードを出してました。転倒したランナーもいました。そんな光景を見ていて、人間の、困難に挑戦する力強さに単純に感動しました。マラソン。これだけ高地で練習できるのだから、オリンピックとかでもっとボリビア選手が活躍してもよさそうなのに・・・って思いませんか?でも南米ではそれがなかなか難しいらしいのです。私の友人によると理由は大きく3つ。●1番目。南米でスポーツと言えば、やっぱり何はなくともフットボール(サッカー)。ということで子供・大人を問わず人みんなサッカー大好きなので、地味なイメージのある陸上競技は人気がないそうです。●2番目。陸上競技は、人気がないのに加えて、練習するための色々な道具(例えば専用のシューズとか)がとても高価らしく、一部のお金持ちしかできないスポーツになってしまっているそうです。もちろん、陸上競技が庶民に普及してないから道具が高い、道具が高いからやる人が増えない、という状況もあるんでしょうけど。●最後に3番目。選手を育てるための人材がいない、ということです。確かに、今日のマラソン大会を見ていて、こっちの人は多分すごい身体能力を持ってるんだなーと思いました。でも、素晴らしい能力を持っていても、それを引き出して開花させることのできるいい指導者がいなければ、永久にダイヤモンドはただの石のままです。今日は日曜日だったので、街の中心部はかなりにぎわってました。これについてはまた次回にでも書きまーす。楽しみにしててくださいねー。では。Ciao!
2005年04月24日
-
限界に挑戦?
今日はラ・パス事情の続編です。こないだの日記に書いたとおりラ・パスは山の中にあるすり鉢状の町です。なので、街中ははっきり言って坂しかありません。しかも、まじかよっ!?って言いたくなるくらい急な坂もたくさんあって、これを毎日上り下りしています。体力と脚力がないとこの町では生活不可能。ボリビアに来る前、私の友人(以前旅行でラ・パスに来たことがある)が、「酸素が薄くて、坂登るだけで息が切れるよ」と言っていたのですが、正確には、すぐに息切れしてしまうくらい坂が多いっていうことだったのです・・・。日本にいた時マラソンクラブで少し走っていたのですが、酸素の薄いボリビアから日本に帰ったら多分楽に走れそうな予感?そういえば、標高3700mというこんな高地で来週マラソン大会があるらしいです。ハーフマラソンらしいけど、信じられません。こないだちょっと踊っただけでかなり息切れしたのに、マラソンするなんてありえない・・・。しかもさっき書いたようにラ・パスには坂しかないのに・・・。いったい誰が出場するんでしょうかね。人間の環境順応能力に改めてびっくりです。今はラ・パス市内でホームステイしながらスペイン語学校に通っています。スペイン語まだまだですが、気長に地道に上達させていくしかないですね。それから、ブドウから作った焼酎みたいなシンガニというお酒、かなりおいしいです。すごく強いですが。すでに雰囲気かなりよいバーを発見。明日は金曜日なので、また飲みに行ってきまーす。ではでは。
2005年04月21日
-
南米生活スタート!
成田を発ち日本の裏側の、ここボリビアに到着して1週間。4月7日に成田に見送りに来てくださった皆さん、本当にありがとう。成田から12時間かけてNYに到着。NYでは、経由だけであっても一時入国手続きをしなければならず。指紋取られ、写真写され、ちょっとイヤでした。その後、ブラジルのサンパウロまでさらに12時間。途中、飛行機から見るアマゾン平原とその向こうから昇る朝日はかなり見ごたえあり。サンパウロはやっぱり何だか蒸し暑く、ラテンな匂いがプンプン漂ってました。サンパウロからさらに5時間のフライトのあと、やっとボリビアの首都ラパス(スペイン語で「平和」という意味)へ到着。ラパスの空港は標高4000mにあります。もっと空気薄いかと思ったけどそうでもなかったです。空港から市内へ向かう途中、ラパス市内を一望できる場所があり、すり鉢状のラパスの街に感動。もう、これだけ標高高いと空の近いこと!自分と同じ目線に雲があるし、イリマニ山というとってもきれいな6000m級の山がすぐそこに。信じられない光景です。そしてここは富士山の上なんだよねーって改めてびっくりしています。高山病も思ったほどではなく、朝起きた時に頭が痛いのが何日が続いたくらい。人間ってすごい。ほんの数日でこの過酷な環境に体を適応させることができるんだから。ここの標高の高さを改めて実感したのは、スーパーで売ってるプリングルスを見た時。中の紙の蓋が気圧が低いためにパンパンに膨らんでて、外側のプラスチックの蓋が閉まってません。乗っかってます。その状態で売られてます(笑)ラ・パスはかなり都会です。高層ビルあるし、携帯も結構普及してます。日本語使えるネットカフェはまだ数件しかないけど。ご飯もおいしい。若者、おしゃれです。さすがに日本人ツーリストはほとんど見かけません。時期的なものかもしれませんが。スペイン植民地時代のヨーロッパ的な要素あり、先住民系の人はアジア系の顔、そして南米独自の雰囲気もあり。今までアジアを中心に旅してきたので、なんだかとっても変な感覚です。でもとっても魅力的。南米にはまる人の気持ちがちょっとわかります。ではまた。
2005年04月15日
-
慣れてきたかも?
久々の日記UPです。毎朝6時起きの生活にもだんだん慣れてきました。「慣れ」ってほんとすごいです。ついこないだまでのだらけきった生活からは想像できないですよ、この生活。かなり健康的だし。スペイン語はかなり詰め込み授業なので、毎日毎日復習が追いつきません・・・。単語量が半端なく多くて苦戦中。毎日疲れきって寝てしまうので、日々この日記に書き込むことがなかなかできなくてごめんなさい~。気長にお待ちくださいませね。
2005年01月26日
-
久々の
今日は朝から雨。寒い寒い1日でした。そして週に1回の貴重なお休み。午前中、新橋で友人と会った後、宿舎に戻ってスペイン語の勉強を再開。スペイン語、かなり苦戦中。でも、英語とほとんど同じ単語とか多いからとっつきやすいのは確か。何気なく使ってる単語が実はスペイン語だったってわかるとなかなか面白い。車の名前って結構スペイン語からとってるのです。LARGOとかCORTOとかSERENAとか。夜は1週間ぶりに焼酎をたしなんできました。すでに行きつけの店を確保。来週も行っちゃうかも?
2005年01月16日
-
優雅な毎日?
毎朝6:30から六本木昼ヒルズをみながらラジオ体操してます。その後は3キロのランニング。相当寒いんです、この季節。毎日毎日、延々とこの生活が続きます。・・・というか、続けられるんだろうか。不安。そして、明日からみっちりがっつりのスペイン語の授業が始まります。私の講師は、もみあげとあごひげが全部つながってしまっている中米のとある国出身のネイティブの先生です。日本語、ペラッペラで、すでに日本人にしか見えません。日本語を学ぶ外国人が受ける「日本語能力検定」というのがあるのですが、その1級を持っているとのこと。1級って、かなりかなーり難しいんです。日本人の私たちが受けても難しいんじゃないの?っていうくらいのもの。さてさて、明日からの授業、どうなることやら・・・。
2005年01月10日
-
富士山
今朝、東京へ向かう新幹線から富士山が見えました。新幹線の指定席を取るときは、いつも富士山が見える方の窓側を取ります。きれいな富士の雄姿を見るにはやっぱり冬が一番ですねー。空気が澄み切ってるから本当にそれはそれは美しかった。私は少し登山をやるのですが、個人的には富士山は登るよりも見るほうが断然よい、と思ってます。今度写真載せますねー。
2005年01月07日
-
今日から
本日このページを開設しました!毎日更新できるかわかりませんが、inconstantってことでまぁぼちぼち行きましょう。今春から南米でちょっとしたお仕事をする予定。現地から大ネタ小ネタ取り混ぜてお伝えできればと思っています。ちなみにこのページのタイトル「ARCO IRIS」は、スペイン語で「虹」という意味。色々な人に見ていただけたら、と思います。
2005年01月06日
全45件 (45件中 1-45件目)
1
-
-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…
- ラスベガス パリス
- (2025-11-21 06:30:50)
-
-
-

- フランスあれこれ・・・
- 星の国ライフ フランス「サヴォワ地…
- (2025-11-21 11:46:32)
-
-
-

- 日本全国のホテル
- 【石川】三井ガーデンホテル金沢
- (2025-11-21 14:37:25)
-