テーマ: アニメあれこれ(28320)
カテゴリ: 漫画・アニメ
TBS「せかくら」を見てて驚くのは、
日本のアニメ「セーラームーン」が、
とんでもなく海外に浸透してるんだなあ…ってこと。
街なかに設置したカラオケで、
現地の女性が主題歌の「ムーンライト伝説」を歌うと、
通行人が足を止めて、みんな懐かしそうに口ずさむ。
メキシコでは、
女の子にいちばん人気のあるテレビ番組だったらしく、
ポルトガルでは、
◇
調べてみると、
アニメ「美少女戦士セーラームーン」は、
1993年にスペインとフランスで放送され、
その後はロシア、韓国、フィリピン、中国、イタリア、
さらに台湾、タイ、インドネシア、香港、そして北米へ広がり、
最終的には「世界40ヶ国で放送されている」とのこと。
2017年の世界フィギュアのときに、
メドベージェワが「ムーンライト伝説」で踊ったときは、
あくまで日本向けのファンサービスよね…などと思ったけど、
案外、そうじゃなかったのかもしれません。
◇
英語のWikipediaによると、
セーラームーンは、
フェミニズムやガールパワーなどの面で、
女性視聴者を力づけた作品と見なされてるようです。
せかくらに出てきたメキシコやポルトガルの女性も、
「セーラームーンは女の子にとっての夢だった」
「セーラームーンの主題歌は女の子にとって大事な曲」
と話してました。
世界中の女子に与えた影響力の大きさからいうと、
ジブリ作品をも上回ってた可能性がありますね。
◇
もともとセーラームーンは、
武内直子の漫画「コードネームはセーラーV」を、
東映の企画によってアニメ化したものです。
それはいわば、
・魔法少女路線
・戦隊ヒーロー路線
・セーラー服少女戦士路線
を結びつけたところに生まれている。
このうち、
東映の魔女っ子シリーズというのは、
1966年の「魔法使いサリー」にはじまっていて、
東映のスーパー戦隊シリーズは、
1975年の「秘密戦隊ゴレンジャー」にはじまります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/東映魔女っ子シリーズ
https://ja.wikipedia.org/wiki/スーパー戦隊シリーズ
◇
そして、
東映のセーラー服少女戦士の路線は、
薬師丸ひろ子の「セーラー服と機関銃」 (1981) にはじまり、
斉藤由貴の「スケバン刑事」 (1985) に受け継がれた、
と考えるのが一般的でしょう。
しかし、これについては、
以前、音楽惑星さんと話したことがあるので、
その部分をすこし抜粋しておきます。
青字 が音楽惑星さんで、 赤字 がわたしです。
もともと東映は、
バイオレンスやエロティシズムなどの表現も、
まったく臆することのない会社だし、
幼女向けの魔女っ子シリーズにさえ、
永井豪の「キューティーハニー」みたいに、
けっこうエロティックな作品があったりします。
そんな東映の作品に、
とてもフェミニズム的な観点があったとは思えないし、
むしろ少女を性的な商品とみなす発想のほうが、
はるかに強かっただろうと想像できます。
そもそも、
「魔法使いサリー」の横山光輝も、
「キューティーハニー」の永井豪も、
「スケバン刑事」の和田慎二も、
「セーラー服と機関銃」の赤川次郎も、
ことごとく男性作家なのだから。
◇
英語のWikipediaによると、
武内直子も、
「東映のアニメは男性的な視点で作られている」
との思いを抱いていたようです。
しかし、制作側の意図がどうであれ、
受け手側の少女たちは、
「魔女っ子メグちゃん」や「セーラー服と機関銃」などを、
女子を勇気づける作品と解釈した可能性はあるし、
とりわけ「セーラームーン」の場合は、
作者の武内直子が女性だったこともあり、
なるべく男性的な視点を排除して、
女子を中心とする市場にターゲットを絞ったようです。
それは端的にいえば、
男性向けのエロティックな描写を控えたってことでしょう。
そしていまや、
東映の生んだ美少女アニメが、
世界の「女性解放」を象徴する文化として共有されてる。
それはちょっと不思議なことです。
◇
余談ですが…
主題歌の「ムーンライト伝説」の冒頭のメロディは、
倍賞千恵子の「さよならはダンスの後に」のパクリなので、
著作権使用料を一部分けることで和解してますね。
◇
…ちなみに、
TBS「せかくら」のカラオケ企画は、
機械採点でランキングをつけてるのだけど、
あいかわらずカラオケの機械採点ってのは、
人間の歌を譜面に押し込む発想で設計されてて、
細かい節回しやリズムの揺らぎなどを許容せず、
あろうことかプロのジャズ歌手に低い点をつけたりしてる。
こういう機械採点は歌の多様性を殺しますよね。
人を感動させる歌の何たるかをまったく理解してない。
たとえば米国の黒人音楽なら、
自由に節やリズムを変えて歌ったりするわけだから、
こんなバカげた機械は絶対に作らないと思いますけど、
もしかしたら、
カラオケの設計をしてる日本の企業人は、
「ボーカロイドの歌がいちばん上手い」
とでも思ってるのでしょうか?

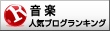

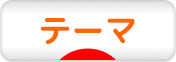
日本のアニメ「セーラームーン」が、
とんでもなく海外に浸透してるんだなあ…ってこと。
街なかに設置したカラオケで、
現地の女性が主題歌の「ムーンライト伝説」を歌うと、
通行人が足を止めて、みんな懐かしそうに口ずさむ。
メキシコでは、
女の子にいちばん人気のあるテレビ番組だったらしく、
ポルトガルでは、
◇
調べてみると、
アニメ「美少女戦士セーラームーン」は、
1993年にスペインとフランスで放送され、
その後はロシア、韓国、フィリピン、中国、イタリア、
さらに台湾、タイ、インドネシア、香港、そして北米へ広がり、
最終的には「世界40ヶ国で放送されている」とのこと。
2017年の世界フィギュアのときに、
メドベージェワが「ムーンライト伝説」で踊ったときは、
あくまで日本向けのファンサービスよね…などと思ったけど、
案外、そうじゃなかったのかもしれません。
◇
英語のWikipediaによると、
セーラームーンは、
フェミニズムやガールパワーなどの面で、
女性視聴者を力づけた作品と見なされてるようです。
In western culture, Sailor Moon is sometimes associated with the feminist and Girl Power movements and with empowering its viewers, especially regarding the "credible, charismatic and independent" characterizations of the Sailor Guardians.
せかくらに出てきたメキシコやポルトガルの女性も、
「セーラームーンは女の子にとっての夢だった」
「セーラームーンの主題歌は女の子にとって大事な曲」
と話してました。
世界中の女子に与えた影響力の大きさからいうと、
ジブリ作品をも上回ってた可能性がありますね。
◇
もともとセーラームーンは、
武内直子の漫画「コードネームはセーラーV」を、
東映の企画によってアニメ化したものです。
それはいわば、
・魔法少女路線
・戦隊ヒーロー路線
・セーラー服少女戦士路線
を結びつけたところに生まれている。
このうち、
東映の魔女っ子シリーズというのは、
1966年の「魔法使いサリー」にはじまっていて、
東映のスーパー戦隊シリーズは、
1975年の「秘密戦隊ゴレンジャー」にはじまります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/東映魔女っ子シリーズ
https://ja.wikipedia.org/wiki/スーパー戦隊シリーズ
◇
そして、
東映のセーラー服少女戦士の路線は、
薬師丸ひろ子の「セーラー服と機関銃」 (1981) にはじまり、
斉藤由貴の「スケバン刑事」 (1985) に受け継がれた、
と考えるのが一般的でしょう。
しかし、これについては、
以前、音楽惑星さんと話したことがあるので、
その部分をすこし抜粋しておきます。
青字 が音楽惑星さんで、 赤字 がわたしです。
薬師丸ひろ子は、セーラー服を着て機関銃をぶっぱなしながら「快感…!」などと呟いてしまった。これが世間の度肝を抜いてパンドラの箱を開けたのです。これが1981年の出来事なのですね。
赤川次郎の『セーラー服と機関銃』は78年の小説です。和田慎二の『スケバン刑事』の連載は75年にはじまっています。しかし、それらのイメージは、あくまでも小説や漫画の中にとどまっていて、お茶の間で共有されるようなものではなかったと思います。
やっぱり実写のインパクトは強い。
実写でいうと、72年にはじまる東映の「恐怖女子高校シリーズ」なんてのもありました。じつは、ここらへんが起点のひとつではあります。その前に日活の「黒猫ロックシリーズ」や東映の「女番長シリーズ」などがあり、それが若年化して不良女子高生のシリーズになっていたんですね。
和田慎二の漫画よりも、チンピラ映画のほうが先にあった。
もともと「スケバン」という用語も、71年の『女番長ブルース牝蜂の逆襲』という東映の成人映画にはじまってます。「セーラー服と機関銃」も東映の配給だし、「スケバン刑事」も東映のドラマだから、東映ヤクザ映画の流れを汲んでるのはまちがいない。
http://manzara77.blog.fc2.com/blog-entry-363.html#sailor
もともと東映は、
バイオレンスやエロティシズムなどの表現も、
まったく臆することのない会社だし、
幼女向けの魔女っ子シリーズにさえ、
永井豪の「キューティーハニー」みたいに、
けっこうエロティックな作品があったりします。
そんな東映の作品に、
とてもフェミニズム的な観点があったとは思えないし、
むしろ少女を性的な商品とみなす発想のほうが、
はるかに強かっただろうと想像できます。
そもそも、
「魔法使いサリー」の横山光輝も、
「キューティーハニー」の永井豪も、
「スケバン刑事」の和田慎二も、
「セーラー服と機関銃」の赤川次郎も、
ことごとく男性作家なのだから。
◇
英語のWikipediaによると、
武内直子も、
「東映のアニメは男性的な視点で作られている」
との思いを抱いていたようです。
Takeuchi later said because Toei's production staff were mostly male, she feels the anime has "a slight male perspective."
しかし、制作側の意図がどうであれ、
受け手側の少女たちは、
「魔女っ子メグちゃん」や「セーラー服と機関銃」などを、
女子を勇気づける作品と解釈した可能性はあるし、
とりわけ「セーラームーン」の場合は、
作者の武内直子が女性だったこともあり、
なるべく男性的な視点を排除して、
女子を中心とする市場にターゲットを絞ったようです。
Although the audience for Sailor Moon is both male and female, Takeuchi does not use excessive fanservice for males, which would run the risk of alienating her female audience.
それは端的にいえば、
男性向けのエロティックな描写を控えたってことでしょう。
そしていまや、
東映の生んだ美少女アニメが、
世界の「女性解放」を象徴する文化として共有されてる。
それはちょっと不思議なことです。
ムーンライト伝説。セーラームーン。この曲はメキシコの女の子にとってシンボル的な存在なの。子供のころアニメがはじまるとテレビの前で歌いながら踊ってたわ。
— まいか (@JQVVpD7nO55fWIT) January 25, 2024
メキシコの女の子が大事にしてる曲です。 https://t.co/GcHTERXm24 pic.twitter.com/KV1ZwUSe9S
メキシコではセーラームーンは女の子にとって1番っていうくらい人気。 #美少女戦士セーラームーン #SailorMoon #せかくら pic.twitter.com/cPV5J85krC
— まいか (@JQVVpD7nO55fWIT) January 25, 2024
セーラームーンで育ったようなものよ。
— まいか (@JQVVpD7nO55fWIT) January 25, 2024
セーラームーンがいちばん好き。セーラー服で戦うのが斬新だった。
セーラームーン(1997放送)ポルトガルテレビ史上もっとも観ていた人が多い番組。記録は未だに抜かれていない。 #美少女戦士セーラームーン #SailorMoon #せかくら pic.twitter.com/cfVq04zlPD
余談ですが…
主題歌の「ムーンライト伝説」の冒頭のメロディは、
倍賞千恵子の「さよならはダンスの後に」のパクリなので、
著作権使用料を一部分けることで和解してますね。
◇
…ちなみに、
TBS「せかくら」のカラオケ企画は、
機械採点でランキングをつけてるのだけど、
あいかわらずカラオケの機械採点ってのは、
人間の歌を譜面に押し込む発想で設計されてて、
細かい節回しやリズムの揺らぎなどを許容せず、
あろうことかプロのジャズ歌手に低い点をつけたりしてる。
こういう機械採点は歌の多様性を殺しますよね。
人を感動させる歌の何たるかをまったく理解してない。
たとえば米国の黒人音楽なら、
自由に節やリズムを変えて歌ったりするわけだから、
こんなバカげた機械は絶対に作らないと思いますけど、
もしかしたら、
カラオケの設計をしてる日本の企業人は、
「ボーカロイドの歌がいちばん上手い」
とでも思ってるのでしょうか?
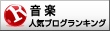

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.06.17 17:18:58
[漫画・アニメ] カテゴリの最新記事
-
ヤマザキマリと天正遣欧少年使節と長崎ル… 2025.09.07
-
宮崎駿「君たちはどう生きるか」ポニョの… 2025.05.03
-
NHKアニメ「火の鳥」太陽編&未来編。百済… 2025.03.30
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ
政治
(237)テクノロジー・科学技術
(20)ドラマレビュー!
(303)NHK大河ドラマ
(66)NHK朝ドラ
(63)NHKよるドラ&ドラマ10
(38)プレバト俳句を添削ごと査定?!
(241)メディア問題。
(46)音楽・映画・アート
(92)漫画・アニメ
(29)鬼滅の刃。
(14)岸辺露伴と小泉八雲。
(30)アストリッドとラファエルの背景を考察。
(18)アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ。
(31)日本史・世界史
(29)東宝シンデレラ
(92)恋つづ~ボス恋~カムカム!
(54)ぎぼむす~ちむどん~パリピ孔明!
(41)わたどう~ウチカレ~らんまん!
(70)汝の名~三千円~舞いあがれ!
(16)トリリオン~ONE DAY~ゼンケツ!
(29)Dr.チョコレート~ゆりあ先生!
(15)捜査一課長~恋マジ~あのクズ!
(42)「エルピス」の考察と分析。
(11)「Destiny」&「最愛」ネタバレ考察。
(20)大豆田とわ子を分析・考察!
(10)大森美香の脚本作品。
(12)北斎と葛飾応為の画風。
(20)不機嫌なジーン
(13)風のハルカ
(28)純情きらりとエール
(30)宮崎あおいちゃん
(22)スポーツも見てる!
(43)逃げ恥~けもなれ!
(24)スカーレット!
(13)シロクロ!
(13)ギルティ!
(9)半沢直樹!
(5)探偵ドラマ!
(12)パワハラ
(7)ドミトリー&ゴミ税
(40)夢日記&その他
(7)© Rakuten Group, Inc.









