2012年07月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
松風 -11-
修繕するべき箇所を、留守番の男や新しく加えた家司などにお命じになります。源氏の大臣が桂の院にお渡りになると聞きつけて、近くのご領地の人々が集まって参りましたので、大井の邸の、前栽が折れ臥した庭の手入れをおさせになります。「庭石がみな倒れたりなくなったりしているけれども、直すと趣のある庭になりますね。しかし一時の仮住まいをわざわざ風情のあるように拵えると、去る時、心残りで辛くなるものです」と、明石でのことまで仰せになって、泣いたり笑ったり寛いでいらっしゃる様子は、たいそうご立派なのです。尼君は几帳の隙間から源氏の大臣のご様子を拝見して、老いも忘れ気分も晴れるような心地になり、自然に笑みがこぼれるのでした。東の渡殿の下を流れてくる鑓水の具合を直そうと上衣をお脱ぎになり、たいそうなよやかな袿姿でいらっしゃるのを、尼君は『ご立派な御方ですこと。その御方に娘が守られる。なんと嬉しいことでしょう』と思いながら拝見しています。源氏の大臣は閼伽の棚があるのをご覧になって、尼君の事を思い出されます。「尼君はこちらにおいででしょうか。無作法な姿では失礼ですね」と、御直衣を持って来させてお召になります。尼君の几帳にお寄りになり、「姫が素直な子に育ちましたのは、あなたの仏道修行のお蔭と心から感謝申しております。俗世を離れ、心を澄ませて暮らしていらした明石の住いを捨てて、姫君のため浮き世に戻っていらしたご決心は、並々ではございますまい。あちらでは一人残ってどんなに心配していらっしゃることかと感謝もし、また一人寂しく過ごす事を思いますと、私もさまざまに感慨深いのでございます」と、たいそう親身に仰せになります。
July 31, 2012
-
松風 -10-
源氏の大臣(おとど)は親しい者だけを前駆に、ひそやかにお出掛になります。ちょうど黄昏時にお着きになりました。質素な旅の御衣(おんぞ)をお召しでいらした頃でさえ、今まで見た事もないほどうつくしい御方と思ったものですが、今日は念入りに整えられた御直衣姿で、優美で上品で、まぶしいほどですので、今までの暗い気持ちも晴れるようなのです。源氏の大臣は、久方ぶりのご対面にしみじみと懐かしくお思いになり、幼い姫君をご覧になるにつけも、今まで逢わずに過ごして来た年月が残念で、悔しくお思いになるほど感動なさいます。左大臣家の若君のことを「可愛らしい」と世間の人がもて騒ぐのは、やはり時の権勢に追従した人が、そのように見なすからなのでしたが、『世に抜きん出た人というものは、この姫のように幼い頃からはっきりしているものだ』とお思いになります。にこにこしている姫のあどけなく、愛らしく、つややかなお顔を『たいそう可愛らしい』とお思いになります。明石に下ったころはやつれていた乳母も、今では以前よりきれいになり、このごろの姫のご様子を親しくお話ししますので、源氏の大臣は『あんな塩焼き小屋のような所でどうやって暮らして来たことか』と哀れにお思いになります。「ここもたいそう人里離れた場所ですから、私が訪ねてくることも難しい。やはり二条院にお移りなさい」と仰せになります。明石の女君が、「まだとても都の暮らしには馴れませぬので、ここでいくらか過ごしましてから」と申し上げるのも尤もなのです。夜一夜、あれこれと睦まじく契り語らいながらお明かしになります。
July 29, 2012
-
松風 -9-
明石の女君は、せっかく上洛しても源氏の君がおいでくださらないので反って悩み続けています。見捨てて来た明石の家も恋しく、所在なく、源氏の君が明石を去る折に形見として残して行った琴を掻き鳴らします。たいそう哀しい気持ちのする折でもありましたので、大井という人里離れた場所に心を許して少し弾きますと、きまり悪く感じるほど松風が琴の音に調子を合わせます。もの悲しげに寄り臥していらした尼君が起き上がって、「身をかへて ひとりかへれる山ざとに 聞きしに似たる 松風ぞ吹く(尼の身となり、夫とも別れて一人帰って来た大井の邸にも、明石で聞いたのと同じような松風が吹いていますね)」明石の女君も、「ふる里に 見し世のともを恋ひわびて さへづることを たれかわくらむ(故郷明石の友を恋しく思いながら弾く拙い私の琴の音など、誰が聞きわけてくれましょうか)」こうして頼りない毎日を過ごしているのですが、源氏の大臣はなまじ明石の女君が近くに来ましたので、反って落ち着かなくお感じになります。人目も憚らず大井にお渡りになるのですが、紫の女君にははっきりと事情をお話しではありませんでしたので、どこぞからお耳に入っては大変と、お話し申し上げます。「桂に用事がございましたが、不本意ながら長い間そのままにしておりました。訪ねる約束をしていた人もその近くに来て待っているようですので、気がかりでございまして。それに、造営している嵯峨野の御堂の、新しい仏像のお手入れもしなくてはなりませんので、二三日はかかるかと思います」紫の女君は、『桂の院という所に別荘を造らせていらっしゃる、と人伝に聞いたけれど、そこに女人を住まわせるのかしら』とお思いになるにつけても不愉快ですので、「斧の柄が腐って、新しく付け替えなくてはならぬほど長い間お帰りにならないのでしょうか。ずいぶん待ち遠しいこと」と、ご機嫌斜めでいらっしゃいます。源氏の大臣は、「またしても気難しい事をおっしゃる。昔のような浮気心は微塵もないと世間の人も言いますのに、あなたはお疑いになるのですね」と、何やかやと宥めて女君の御機嫌をおとりになるうち、日も長けてしまいました。
July 28, 2012
-
松風 -8-
御車をぞろぞろ続けるのは大袈裟ですし、かといって車と舟とに分けるのも面倒です。源氏の大臣から遣わされた供人たちもひたすら目立たぬように心がけていますので、舟でこっそりと上京することに決めました。辰の時(午前八時)に舟出なさいます。人麿も「趣がある」と言った明石の浦の朝霧の中を、舟が遠ざかって行くにつれてひどく悲しくて、入道はとても仏道修行などできそうにないほど魂が抜けたように茫然としていました。尼君は泣いていらっしゃいます。「かの岸に 心よりにし海士舟の そむきしかたに 漕ぎかへるかな(出家して彼岸に心を寄せたはずの尼の私が、そむいたはずの都へ帰ることになるとは、何と言う皮肉なことでございましょう)」明石の女君も、「いくかへり ゆきかふ秋をすぐしつゝ 浮き木にのりて われ帰るらむ(私は幾春秋を明石の浦ですごしたことでしょう。それが今日は頼りない舟に乗って、ふわふわと都へ帰るというのでしょうか)」順風に乗って予定通りに都にお入りになりました。人に見咎められないようにと用心していましたので、陸路もわざと質素な旅姿にしたのでした。大井の邸の様子は趣があり、今まで住み馴れた明石の海辺に似ていますので、場所が変わったというような気持ちがせず、昔のことが思い出されて感慨深いことが多いのでした。建て増した廊などは趣ありげで、庭の鑓水の流れもおもしろく拵えてありました。まだ隅々にまでは手入れが行き届いていないのですが、住み始めれば十分間に合うにちがいありません。源氏の大臣は腹心の家司にお命じになって、ご到着の祝賀をおさせになりました。源氏の大臣は人目を憚り、大井にお越しになる口実をあれこれと考えていらっしゃるうち、月日だけが過ぎていくのでした。
July 26, 2012
-
松風 -7-
その意味では我ながら『よくぞ思い切ったことよ』と今でも思っているが、あなたが成長なさり、もの事の分別がつく年令になるに従って『どうしてこのような田舎で、錦のようにうつくしい娘を埋もれさせ申すことができようか』と、子を思う故の心の闇が晴れる間もなく嘆くまま仏、神をお頼み申し上げて祈願しておったのだ。こうも落ちぶれたわが身とともに木こり小屋のような庵で、よもや生涯を終えるようなことはあるまいと、祈る心をお頼み申し上げていた折も折、思いもよらず源氏の君との嬉しい契りを拝見することになったのだが、それにつけても、このような賤しい身分であることが悲しく、あれこれと嘆いておった。しかし姫君がお生まれになった御宿世は頼もしく、このような海辺で月日をお過ごしになるのはたいそう勿体ないことに思えるのだよ。前世からの因縁が格別な御方と思えてならないから、姫のお顔を拝見できなくなる悲しみは鎮め難いが、出家したわが身には俗世を捨てたという覚悟がある。お前たちには輝かしい未来が待っているのだから、賤しい私の心を悩ませなさるだけの前世からの因縁があるのだろう。だからこの別れの辛さを、いずれは天に生まれる私の一時の悲しみと思って、今日は長のお別れを御身に申し上げる。私の命が尽きたことを聞し召しても、死して後の供養などなさいますな。『別れ』ということに、動揺なさいますな」とまで言い放つのですが、「私が煙となる夕べまで、姫君の無事と幸運の御事を、六時の勤行の時にも未練がましく祈ってしまいそうだ」と、つい泣き顔になってしまうのでした。
July 25, 2012
-

夏の日
クルマを降りると、後ろでざぁーっという音がした。川でも流れているのかと振り返ると、一列に並んだ木々のざわめきだった。農業学校の広大な敷地内にある野菜直売所で。
July 24, 2012
-
松風 -6-
母の尼君、「もろともに 都はいできこのたびや ひとり野中の 道にまどはん(かつて都を出たときは、あなたさまとご一緒でした。それなのにこの度は私一人でございます。きっと悲しみのために、野中の道に迷ってしまうことでございましょう)」と、お泣きになる様子も尤もなのです。夫婦として契りを交わした長い年月を思えば、こんなあてにならぬ浮いた事を頼みとして、一度は捨てた都へ戻るというのも、考えてみればずいぶん心許ないことではないでしょうか。明石の女君も、「生きて又 あひ見むことをいつとてか 限りも知らぬ 世をば頼まむ(生きてまた再会できる日を、いつと決めて頼みになどできましょうか。この世での命の限りさえも分かりませんのに) せめて都まで、見送りにだけでも」としきりにおっしゃるのですが、「老年でもあり出家した身でもあって差し障りがあるから、ここを動くことはできないのだよ」と言いつつも、さすがに都への道中が心配な様子です。「私が近衛の中将の官を捨てて明石に下ったのは、ただあなたの御ためなのだよ。播磨の守となれば受領としての豊かな財力で、娘の養育も存分にできるだろうと思ったからなのだ。しかしわが身の果報の拙さが思い知らされることばかりだった。それで都に戻ったのだが、落ちぶれた貧しい元受領という身分のために、公私にわたり馬鹿な人間だとの汚名を広めてしまい、大臣であった親の名まで辱めたことの恐ろしさに出家してしまったのだと、人にはそう思われておる。
July 22, 2012
-
松風 -5-
母君もひどく気の毒なのです。これまでも海辺の家に住む入道とは離れて住んでいましたが、娘が上洛する今は、明石に留まる理由がありません。浮ついた気持ちで逢う男女の浅はかな契りでも、互いに見馴れた後での別れともなれば悲しくて冷静ではいられないものです。とはいえ夫・入道の偏屈頭のへそ曲がりではどうも頼りになりそうにもありません。しかし一方ではそれはそれなりに、明石の地こそは『限りある命の終の棲家』と思い、入道と共に暮らす約束をしてきたのですから、急に別れ別れになるのも心細いのです。若い女房たちで、明石の暮らしを憂鬱に思い、沈みこんでいた者は帰京を嬉しく思うのですが、見捨て難い海浜の景色に、もう二度とこの地に戻ることはあるまいと思うと、寄せる波の雫に加えて涙で袖の濡れる日々なのです。 秋ですので、もの寂しさが増すような心地がします。出立するその日の暁は秋風が涼しく虫の音も気忙しく、明石の女君が海の方を見ていますと、父の入道がいつもの後夜より早く起きて、鼻をすすりながら勤行をしているのでした。出発の時ですのでたいそう気をつけて不吉な言動を慎んでいるのですが、誰もが皆涙を堪えることができません。入道には幼い姫君が何とも可愛らしく、夜光ったという玉のような気持ちがして、袖から放したことがないほど可愛がっていましたから、姫君も入道に馴れ親しみまとわりつきますので、出家した我が身を忌々しく思いながら、「少しでも姫君を拝見しないではいられなかったのに、これからどうしたらいいのだろう」と、涙を隠しきれないのです。「ゆく先を はるかに祈るわかれ路に 堪へぬは老いの 涙なりけり(この別れの旅路に堪え切れないのは、涙もろい老人の涙でござる。姫君の行く先に「幸多かれ」と、遥か明石で祖父は祈っておりまするぞ)涙が止まらぬとは、何とも忌わしい事だわい」と言って、顔を拭って隠しています。
July 21, 2012
-
松風 -4-
惟光の朝臣は、源氏の大臣がお忍び歩きなさる折にはいつもお世話する人ですから、大井にお遣わしになり住いの設備などを良いようにおさせになるのでした。「邸のあたりは風光明媚で、明石の海辺に似通った風景でございました」と惟光が御報告申し上げますので『それならばきっと、住むに相応しいことであろう』とお思いになります。造らせていらっしゃる御堂は大覚寺の南に当たり、その瀧殿の趣などは大覚寺にも劣らぬほど清々しい寺なのです。明石の君の住む古邸は、大井川に面した何とも言えぬ趣ある松林の蔭にあって、格別な工夫もなく建てた寝殿の簡素な様子も、山荘の哀れな趣を見せています。源氏の大臣は、内装や設備に至るまで配慮なさいます。そうして側近の人々を、こっそり明石にお遣わしになります。明石の女君は『もはやこれまで』と上洛を決心するのですが、長年住み慣れた海辺を離れる事が辛く、また父・明石入道が一人寂しく明石に留まることを思うと心が乱れて、様々に悲しいのです。『どうしてこんなに、何事も物思いする身になってしまったのかしら』と思うと、源氏の大臣と無縁の人の運命を羨ましく思います。親たちも、長い間寝ても覚めても娘の幸運を願ってきたのですから、それが叶うのはたいそう嬉しいことにちがいないのですが、離ればなれになることが耐え難いほど辛く悲しく、明石入道は夜となく昼となく思い呆けて「これからは姫君の成長を見る事ができぬのか」と、言うばかりです。
July 20, 2012
-
松風 -3-
留守番の男は、 「私の土地ではございませぬが他に管理を受け継ぐ人もいらっしゃらないので、辺りの静けさに馴染んでひっそりと暮らしております。御荘の田畑も徒に荒れ果てておりましたので、亡くなった民部大輔の君にお譲りいただき、しかるべき地代をお納めして私が耕作しております」など、その田畑で得た貯えを取り上げられはしないかと心配しながら、髭だらけの憎らしい顔をして、鼻を赤らめ口をとがらせて言います。入道は、「その田畑の事はどうでもよいのだ。私たちが移るとしても、おまえは今まで通りそこで暮らせばよい。土地や建物の権利書はここにあるが、私は世を捨てた身として長い間放っておいたので、その事も含めてこれからきちんと整理しよう」と言うにつけても、源氏の大臣との関係をほのめかしますので、留守居の男は厄介な事に思い、その後明石入道から過分の金品を受け取り、大急ぎで建物を造りました。源氏の大臣は、明石入道の考えなど露ほども御存じありませんので、明石の女君がなぜ上洛を渋るのか合点がいかず、幼い姫君が明石のような田舎でつくねんと暮らしていらっしゃるのを『後々世間で姫君の評判を噂するとしたら、田舎育ちは外聞が悪かろうな』とお思いになる頃、ちょうど大井の邸が完成しました。明石から『しかじかの邸を思い出しまして、修繕いたしました』と御消息が届きました。源氏の大臣は、明石の女君が『都での人付き合いを苦痛に思う』と言ってきた理由は、大井へ移ることにあったと初めてお分かりになり、『見上げた心構えだな』とお思いになるのでした。
July 19, 2012
-
松風 -2-
その昔、母君の御祖父で中務の宮と申し上げた方が所有していらした土地が大井川のあたりにありましたが、その後はっきりとした後継ぎもないまま荒れ果てていることを思い出し、代々留守番のようにしている者を明石に呼びだして相談するのでした。「私は世を見限ってこのような田舎住いに身をひそめているのだが、この年になって思いがけない事が出来した。今になって都に住いが必要になったのだが、急に華やかな都に出て行くのはきまりが悪いし、田舎びた私の気持ちも落ち着きが悪い。そこで古くからある大井の邸に移り住んではどうかと思いついたのだ。必要な費用はこちらで用意するから、人が住めるように修繕してはもらえまいか」すると留守番の男は、「ここずっと領有する人もいらっしゃいませんので、お邸は見苦しい状態になっておりまして、私どもは下の雑屋を修理して住んでおりまするが、この春あたりから源氏の大臣が近くに御堂をお造らせなさっておいででして、たいそう騒がしいのでございます。荘厳で立派な御堂を建てていらっしゃいますので、多くの工匠が出入りしております。静かなお住いをご希望でしたら、無理かと存じますが」と、言います。明石入道は、「いやいや、そのようなことはない。実は源氏の大臣のご庇護にもおすがりして、と思う事もあるのだから反って都合がいいのだよ。住んでから追々部屋の設備などを調えよう。先ず急いで大体の手入れをさせておくれ」
July 18, 2012
-
松風 -1-
二条東の院を新築なさり、花散里と申し上げる御方をお移しになります。西の対には渡殿をかけて、政所には家司を置くなど、しかるべき様に配置なさいます。東の対には明石の御方を、と考えていらっしゃいます。北の対は格別広くお造りになります。そこには仮初にでも愛しくお思いになり、行く末をかけてお約束なさった女君達が集い住むようにと、幾つかに区切ってお部屋を拵えていらして、心惹かれるような見どころがあって、こまやかに配慮されています。寝殿は普段お使いにならず、源氏の大臣が時々東の院にお渡りになる折のお休み所のようにして、調度もそのように調えさせます。明石の女君への御消息文は絶えることなくあって、姫が生まれたからには上洛するべきことを仰せになるのですが、明石の女君は身分の低いことを十分知っていますので『この上ない高貴な御身分の女君でも中途半端なお扱いを受けて物思いに苦しむと聞くのに、まして世間から認められてもいない私など、どうして都の貴婦人たちと付き合うことができましょう。姫君の不面目として、わが身の賤しさが世間に知れ渡るだけのこと。人目を忍んで稀にお渡りくださる機会を待つばかりでは、世間の人の笑い者だわ。何と屈辱的なことでしょう』と思い乱れるのですが、かといって源氏の君の姫君ともあろう御方が、明石のような田舎でお育ちになり、世間から認められないのもひどく哀れですので、源氏の大臣の仰せに全く応じないというわけにもいかず、親たちも明石の女君の思いを『ほんに尤もなこと』と思い嘆くのですが、思案も尽きてしまいました。
July 17, 2012
-
絵合 -15-
源氏の大臣は、しかるべき節会なども「この帝の御世から始まった」と後の人が言い伝えるような例も加えようとお思いになって、絵合わせのように私的な御遊びも目新しい趣向でおさせになるという、たいそう華々しい御代なのでした。 それでもやはり源氏の大臣は世の中を無常なものとお思いになり、帝がもう少し大人におなりあそばされたら出家しようと心に深くお思いのようでございます。昔の例を見聞きするにつけても、若くして高い官位に昇進し、世の中に抜きん出た人の命は、決して長くはありませんでした。『私にとって今の境遇は、身分も帝からの御おぼえも過分なものがある。それも須磨や明石に身を沈めて悲しんでいた時期があったからこそ、こうして生き長らえているのだ。これから先さらに栄華を受けるとしたら、なお生きていられるか心配だ。寺にでも静かに籠って後世のために勤行し、命長らえたいものだ』とお思いになって山里の静かなところに御堂を造らせ、仏像や経典の用意をおさせになるのですが、後継ぎのお子様たちを『思う存分に、大切に育ててみたい』ともお思いになるからでしょうか、早々と世をお捨てになるのはなかなか困難なようで、どうなさるおつもりなのか、分からないのでございます。
July 16, 2012
-
平安時代のカルテット
クラシック音楽好きな茂グリさん、コメントをありがとうございます。ここでは源氏が琴の琴(きんのこと)を、権中納言が和琴(わごん)を、帥の宮が筝の琴(そうのこと)、少将の命婦(女性)が琵琶を弾いていますから、カルテットになりましょうか。辞書を引くと琴の琴と筝の琴は同じ七弦楽器のようですので、第一、第二ヴァイオリンといったところかもしれません。ご存知のように、このころの貴族階級にとって「管弦の遊び」は優雅な知識人としてのステータス・シンボルでしたから、漢詩の他に楽器の修得は必須でした。それは天皇でも同じだったようで「○○天皇は琵琶の名手で、何某はその筋を弾く演奏......」というような表現が、鎌倉時代の日記文学にも出て来ます。幼少のころから手とり足とり「名手」といわれる人から伝授されたのでしょう。そのころは誰もが共有できる楽譜というものも多分なかったため、いろいろな演奏方法による流派が生まれたのではないかと想像しています。ピアノとクラシックギター、尺八を習ったことのある人に聞いた話ですが、日本の音楽はそれぞれの楽器がそれぞれ全く違った旋律を奏でるのだそうです。一番顕著なのは津軽地方の民謡だそうで、同じ曲でも歌い手、弾き手によって別物に聞こえるほど、その唄い方、演奏が自由なのだとか。同じように琴、三味線、尺八、歌がそれぞれみんな別々の旋律を演奏しているのに、それが不思議な調和を生むのだと。そういった各パートの独立性を加味して考えると、絵合わせの中で奏でられたこの演奏は非常に即興的で、いわば各楽器がカデンツァを弾いているようなものではないかと想像します。原文で「いみじうおもしろし(たいそうおもしろいのです)」と記されているのは、この息の合った四人によって即興的に演奏される音楽(いわばジャズのような)への「おもしろし」ではないかと思っています。
July 15, 2012
-
絵合 -14-
二十日の月がさし出でて、こちらはまだ月の光に照らされていないのですが、空全体がうつくしい頃ですので、帝は書(ふみ)の司の御琴をお召し寄せになり、権中納言が和琴をお務めになります。何事にも源氏の大臣が優れているとはいうものの、権中納言もみごとに和琴を掻きたてなさいました。帥の宮が筝の御琴、源氏の大臣が琴、琵琶は少将の命婦が奉仕申しあげます。殿上人の中で優れた人をお召しになり、拍子を取らせなさいます。たいそう面白いのです。夜が明けるに従って花の色も人の御姿もほのかに見えてきて、鳥のさえずりも心地よく、申し分のない朝ぼらけです。祝儀の品々は、藤壺中宮の御方から下賜されます。帥の宮は御衣を、さらに筝の祝儀として賜ります。そのころの人々の関心は、もっぱらこの絵合わせの噂話にそそがれます。源氏の大臣が、「須磨や明石の絵日記は、藤壺中宮の御許へ」と申し上げますので、中宮はすべての絵日記を見たいと思召したのですが、「逐次お目にかけましょう」とお返事なさいます。帝におかれましても満足にお思いあそばしたのを、嬉しくお思いになります。ちょっとした趣味の事でも、源氏の大臣が斎宮の女御に肩入れなさいますので、権中納言はご自分の娘の弘徽殿女御が圧倒されるのではなかろうかと、いらいらなさるようでございます。弘徽殿女御への帝のご寵愛は、斎宮の女御が入内なさる以前からお心に深く染みついていらっしゃいますので、やはりこまやかにご寵愛あそばされる様子をそっと拝見なさっては、『いくらなんでも斎宮の女御に負けることはあるまい』と頼もしく思うのでした。
July 14, 2012
-
絵合 -13-
帥の宮は、「どのような学問でも心を打ちこまずに会得することはできないものですが、それぞれの道には師匠という存在があり、学ぶだけの価値がある所には、事の深さ浅さは分からぬとしても、学び取ろうとすれば従うべき法則があるのでしょう。書画の道と碁を打つ事は、不思議にも才覚のほどが見えるものです。たいした勉強もしていない愚か者でも、才能が与えられていれば巧みに描き、うまく碁を打つような者も出てくるのでしょうが、身分の高い子弟の中にはやはり人に抜きん出た者がいて、そういう者が何事をもたしなみ修得するように私には思えます。父・桐壺院の御前にて親王や内親王たちにそれぞれに応じた学習をおさせになりましたが、中でもあなたはとりわけ熱心に諸道の伝授をお受けになりました。その甲斐あって詩文の才能は言うに及ばず、他には七弦の琴を第一の才として、次には横笛、琵琶、筝の琴を次々に修得なさったと、お上が仰せになったものです。世間の人もそのように思い申し上げていましたから、絵は手慰み程度の余技とばかり思っておりましたが、いや、異常なまで上手にお描きになる。昔の絵の名人たちが逃げ出してしまうほどの力量とは、反って怪しからぬ技ですな」と、酔い乱れて申し上げます。酔い泣きというのでしょうか、院の御事を話題になさって涙を流し給うのでした。
July 13, 2012
-
絵合 -12-
最後に左方から須磨の絵日記の一巻が出てきましたので、権中納言の御心は動揺しました。右方でも用心して最後には格別優秀な絵巻を選び残していらしたのですが、巧みに絵をお描きになる源氏の大臣が心静かに思いの限りをお描きになったこの絵は、何物にも比べることのできぬ絶品なのです。帥の宮を始めとして一同は感動の涙を止めることがおできになりません。その当時都では「お気の毒なこと。何と悲しい」と同情したものですが、この絵巻には須磨での暮らしの様子や御心内でお思いなさった事などが、たった今起こった事のように見えるのです。須磨の風景や見たことのない浦々、磯などもすべて描き現していらっしゃいます。詞書きは草仮名に所々ひらがなを書き混ぜてあって、漢文で書いた正式な日記ではないのですが、趣のある御歌などが混じっていますので、見たいと思わずにはいられません。だれもがこの絵に見とれてしまうほどすばらしく面白いのです。それで今までの絵を押しのけて、左の勝ちとなりました。明け方近くになるほどにたいそうしんみりとしたお気持ちになられて、絵合後の宴会のお酒を召し上がる機会に、昔話などが出て参りました。「私は幼い時分より学問に身を入れて参りましたので、多少は学識がつくとご覧になったのでしょうか、故・桐壺院が仰せになるには『世間では知識や学問を重要視するからであろうか、熱心に学問する人が多い。しかし才学の豊かな人が、寿命と幸運とを手に入れるのはひどく難しい。高貴な身分に生まれ才学に恵まれなくても、人に見下げられないほどの身分であれば、命を縮めてまで学問の道を探求してはならぬ』とお諫めくださって、実際的な事をお教えくださいましたので、才能乏しきことはありませんが、さりとてまた取り立てて得意な分野もございません。ただ絵を描くことだけは、取るに足らぬ才能ではございますが、何とかして思い通りに描いてみたいと思う折々がございました。そのうち思いがけぬ須磨の山住みとなってあちらこちらの海の深い趣を見ましたので、絵の道はさらに広く、思い及ばぬ所のない画境に達しえましたが、筆の技巧には限りがありますので、この絵日記も心の思いには及ばぬと思っておりました。このような機会がなくては帝にご覧いただくわけにはいきませんが、好き好きしいように噂されないかと心配しております」と、帥の宮にお話しになります。
July 12, 2012
-
絵合 -11-
帝のお召しによって源氏の大臣(おとど)と権中納言が参上なさいます。その日は源氏の大臣の弟宮でいらっしゃる帥の宮も宮中においででした。帥の宮も絵画をお好みで造詣が深くていらっしゃいますので、源氏の大臣が密かにお誘いになったのでございましょう。特に表立ったお召しではありませんが、殿上の間に控えていらっしゃるところを帝からの仰せ事があって参上なさり、この絵合の判者をおつとめになります。 ご覧になってみますと、なるほどたいそう優れて力の限り描き尽した絵ばかりで、帥の宮にも優劣を決めかねるほどです。例の、朱雀院から斎宮の女御へ御贈りなされた年中行事の絵も、昔の巧みたちのおもしろい事柄や風景を選びながら、筆が滞らず描き流した趣が例えようもなくうつくしいと見るのですが、紙に描いた絵は幅に限りがあるので遠く続く山々や水の豊かな流れの様子を描き尽すことができないため、もっぱら筆先の技巧や絵師の構想や趣向で描かれ作りたてられていますので、今風の浅はかな新画であっても昔の絵画に劣ることなく活気があり、面白味といった点では勝っています。多くの競争がありましたが、今日は右方にも左方にも興ある絵が前回より多いのでした。藤壺中宮も朝餉の間の御襖を開けて聞いていらっしゃいますので、源氏の大臣は『中宮におかれても絵画に精通しておいでであろう』とゆかしくお思いになって、帥の宮が心もとない判定をなさる折々には意見を添えていらっしゃるのも好ましい風景なのです。優劣を決めかねて、夜になってしまいました。
July 11, 2012
-
絵合 -10-
朱雀院からの御絵は、母君の弘徽殿大后の宮より伝わったもので、今の弘徽殿女御の御方にもたくさん集まったことでしょう。朧月夜の尚侍の君も人より勝れた絵の趣味をお持ちでいらして、趣のあるふうに飾りつつ絵を集めていらっしゃいます。絵合わせの日を定めて、急なようですけれども興味が惹かれるように、しかも仰々しくなく整えて、左・右の御絵を帝の御前にそれぞれがお持ちなさいます。清涼殿西面の台盤所に帝の御座所を設け、右の弘徽殿女御方が北、左の斎宮女御方が南へと別れて座ります。殿上人は後涼殿の南北の簀子に、おのおの味方する方に座ります。左の斎宮の女御方は紫檀の箱に蘇芳の花足、敷物には紫地の唐の錦、打識は葡萄染の唐の綺です。女の童六人は赤色に桜襲の汗衫、袙は紅に藤襲の織物です。これらの衣装や用意は、なみなみならず勝れたものに見えます。右の弘徽殿方は沈香の箱に浅香の下机、打敷は青丹の高麗の錦です。足結の組紐や花足の趣向が華やかで、いかにも今風なのです。女の童は青色に柳の汗衫、山吹襲の袙を着ています。女の童たちがみなで絵の箱を帝の御前に持ってきて据えます。帝付きの女房は前後二列に並び、衣装の色で左方、右方へと分けます。
July 8, 2012
-
絵合 -9-
一年の節会などでおもしろく興ある場面を、昔の達人がとりどりに描いたものに、延喜の帝が御手づから詞書をお書きになったものや、朱雀帝が御自身の御世のことも描き加えさせた絵巻には、かつて斎宮が伊勢に下向なさった日に、大極殿で御手づから別れの櫛を挿しておやりになった、あの忘れられない儀式の様子などを詳しく仰せられて、絵師の公茂に描かせられたという見事な絵を斎宮の女御に差し上げました。優雅な透かし彫りの沈香の箱に、同じく艶な心葉のさまなどはたいそう今風なのです。朱雀院からの御消息は文字ではなく、内裏にも院の御所にもお出入りが許されている左近の中将をお使いとした口上でした。斎宮として大極殿を出発なさった折に、御輿を寄せた神々しい場面には、「身こそかく しめの外なれそのかみの 心のうちを 忘れしもせず(今の私はこのように宮殿の外に住む身ではあるけれど、かつてあなたさまと大極殿で別れた時の恋しい気持ちを今でも持ち続けています)」とだけ書かれています。お返事を申し上げないのも畏れ多く、心苦しくお思いになりながら、昔の御挿し櫛の端をほんの少し折って、「しめのうちは 昔にあらぬ心地して 神代のことも 今ぞ恋しき(内裏の内も、今では院ご在世の頃とはすっかり変わってしまったような心地がいたします。神に奉仕いたしました昔のことも、今となっては恋しく思っております)」とお書きになって、薄い藍色の紙に包んで差し上げなさいます。御使いへの禄は、たいそう上品で優雅です。朱雀院はそれをご覧になると限りなく悲しくお思いあそばされ、あの日を取り返したいとお思いになるのでした。入内をおさせになった源氏の大臣に対しても、さぞかし恨めしくお思いになられたことでございましょう。されどこれも源氏の大臣を追放なさったおん報いではないのでしょうか。
July 7, 2012
-
設定・接続 -4-
家人が今まで使っていた「らくらくホン」にも音声読みとり機能がついていたのだが、音・訓の読みやアクセントが正確でなかった。それもまたある意味で面白かったのだが、最近のスマホは思った以上にはっきりとスムースに発音する。それで家人は「らくらくホン」からタブレットに、あっさり替えてしまった。私はそれに反対ではないのだけれど、ここでの設定・接続を思うと憂鬱だった。案の定、前進と後退をくりかえし、にっちもさっちもいかぬ難行苦行の連続で、DOKOMOで設定してもらったグーグルアカウントを削除してデータを初期化し、再入力までして、やっと彼の満足する起動と相成った。設定や接続の手続きは面倒だし疲労感も大きいが、それでも新しい携帯やタブレットは楽しい。音声を正確に認識してくれないので思わず「ばーか!」と言うと、若い女性の声が「御機嫌ナナメですね」と言う。「こんばんは」と言うと「まだ夜ではありません」と来る。朝一番に「おはよう」と声をかけると「今日も一日よろしくお願いします」と、やけにしおらしく挨拶を返す。人間によって入力されたデータに基づく反応にすぎないのだが、そのたびに笑えて楽しい。音声入力もナビも非常に便利だし、TVの画像はワンセグより鮮明で見易い。★それにしても携帯電話やタブレットの料金設定は分かり難い。モバイルとWiFiでは料金がかなり違って、ルーターからのWiFiでは接続料がかからない。しかし設定や一部のアプリを使うためには、モバイルで接続しなくてはダウンロードができない仕組みになっている。ダウンロードすればモバイルでの接続料金が必ずかかるのだから、これも狡猾な課金方法に思えなくもない。とにかく設定・接続に悩まされることなく、パンフレットに謳うように「超カンタン」であればもっと楽しいのだが。
July 5, 2012
-
設定・接続 -3-
翌日再びMさんに来てもらった。彼はNTT、プロバイダ、それに富士通にまで電話して粘り強くパソコンに向かい、ひたすら原因を追究してくれた。「やっと原因がわかりました」と、疲れた顔を上げたのは、日も西に傾きかけたころだった。彼によると、私のVISTAは無線通信ソフトウエアのヴァージョンが古く(ほとんどXP)、ルーターを認識はするのだが、通信速度が合わないため接続できないのだと言う。翌日わざわざ「ワイヤレス・ラン・アダプター」を購入して、USBポートにセットしてくれた。やれやれ。ここでやっと、公衆無線ランに接続できたわけだ。Mさんによると私のパソコンと同じトラブルがもう一件報告されていたそうで、やはり同じ時期に製造されたパソコンだったという。ではXPはどうかというと、そのほとんどが有線で繋いでいるので問題が生じないらしい。★ところで携帯電話のBLUETOOTHだが、以前のスマホでは簡単に接続できたのに、今度はここでまた足止めを食っている。接続されているはずなのに、電話が接続にならないのだ。昨日は買い物に行ったスーパーの駐車場で、暗くなるまで「削除」「初期化」「登録」と何度も繰り返しやってみたのだが、どうしても「完了」にならない。頼みの「オーナーズ・デスク」もスマホの新機種やタブレットには対応できていなかった。家人と二人、クルマの中で「あーでもない」「こーでもない」果ては「俺は目が見えないんだから、キミがちゃんと読んでやってくれよ」「もぉ~、私にはできませんっ。無理でーす!今度の定休日にレクサスに持って行った方が早いですっ!」と喧嘩状態。食材を買ったのだが、こんな事ばかりしているものだから疲れ果てて、結局は外食することになってしまった。
July 3, 2012
-
設定・接続 -2-
二年前もそうだったが、依然として店員さんの知識には個人差があり、こちらの質問にうまく応じてくれず、非常にもどかしい思いをした。たかが携帯の買い替えにほとんど一日かかってしまうのはサービス業として非常に不親切だ。 先月中旬、店のルーターを公衆無線ランに変えた時も同じだった。ルーターの他に「光ステーション」というシロモノを設置するのだが、その設定に半日かかった。すると今度は「光ステーション」からの無線を、パソコンがキャッチしてくれない。有線ではネットに繋がるのだから、無線は確かに飛んで(機能して)いるのだ。しからばパソコン(VISTA)に問題があるのかと、翌日は家から「7」を持ってきところ、すんなり繋がったではないか。NTT担当者のNさんに連絡すると、「有線で使うわけにはいかないでしょうか。あるいは、もしだめなら、元に戻すとか......」と、まことに呆れたことを平気での給う。短気な私は、彼の無責任さに腹が立った。公衆無線ランに替える直前まで何の支障もなく機能していたところを半日かけて「光ステーション」とやらをやっとこさ設定したというのに。いまさら「元に戻す」といとも簡単に言うが、それだってまた設定しなおさなくてはならないではないか。「勧めたのはNさんなのだから、責任を持って接続してほしい」と言うと、「押し売りしたわけではない」と、筋違いな言い訳をする。まして「無線は飛んでいるのだから、後はそちらのパソコンの問題です」と問題を丸投げされては、堪忍袋の緒が切れるというものだ。家人は見ていられなかったようで、電話を代わってくれた。「接続できない原因をそちらで調べて、何とか接続してくれないか」と、宥めるように頼むとその日のうちに、「設定士」と言っただろうか、若いMさんを派遣してくれた。Mさんは閉店ぎりぎりから3時間かけて調べてくれたが、結局原因不明のまま午後9時半に帰って行った。結果の出ないことに、みんな疲れ果てていた。
July 1, 2012
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
-
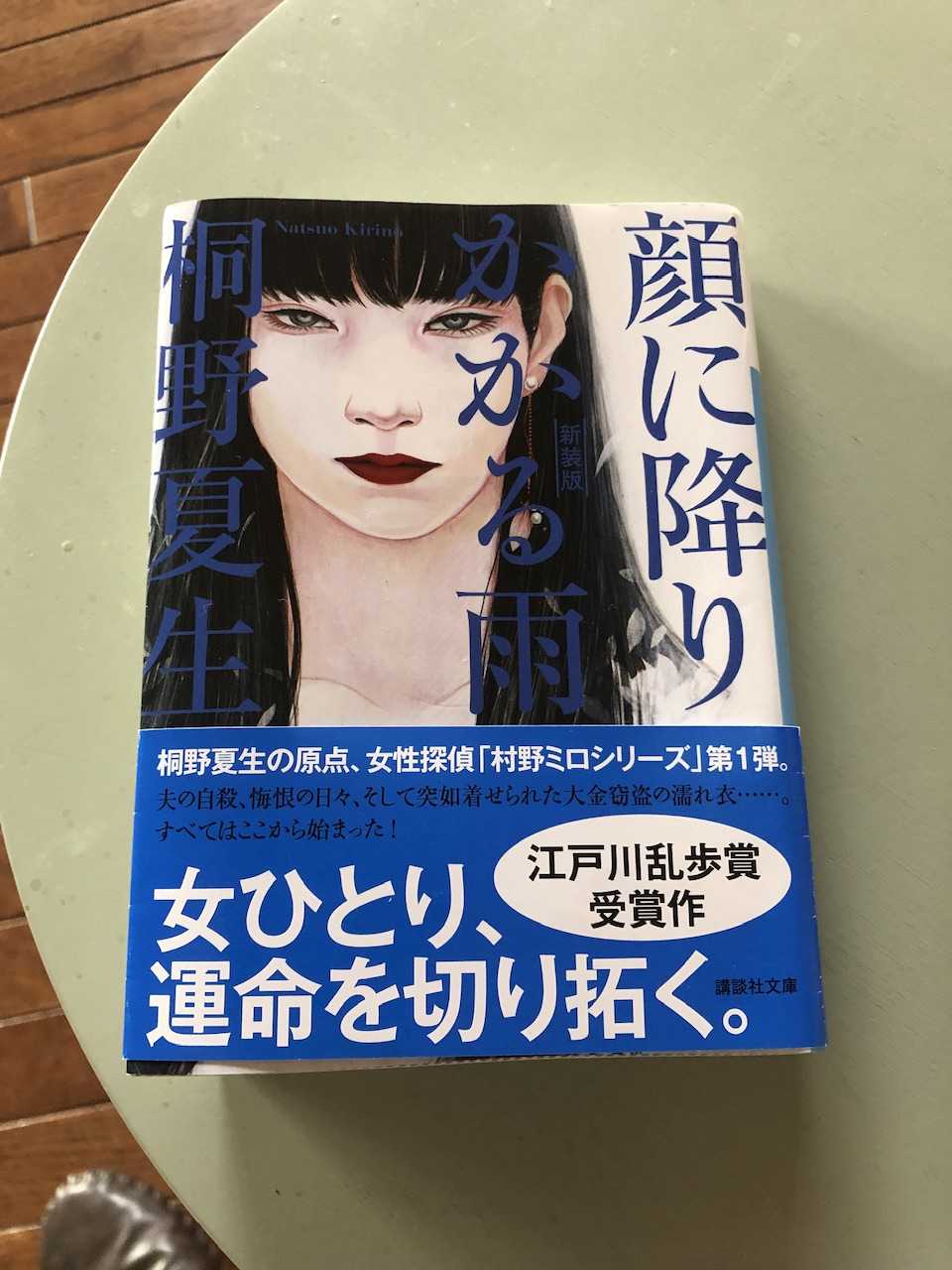
- 読書備忘録
- 10月に読んだ本 桐野夏生「顔に降り…
- (2025-11-20 11:57:45)
-
-
-
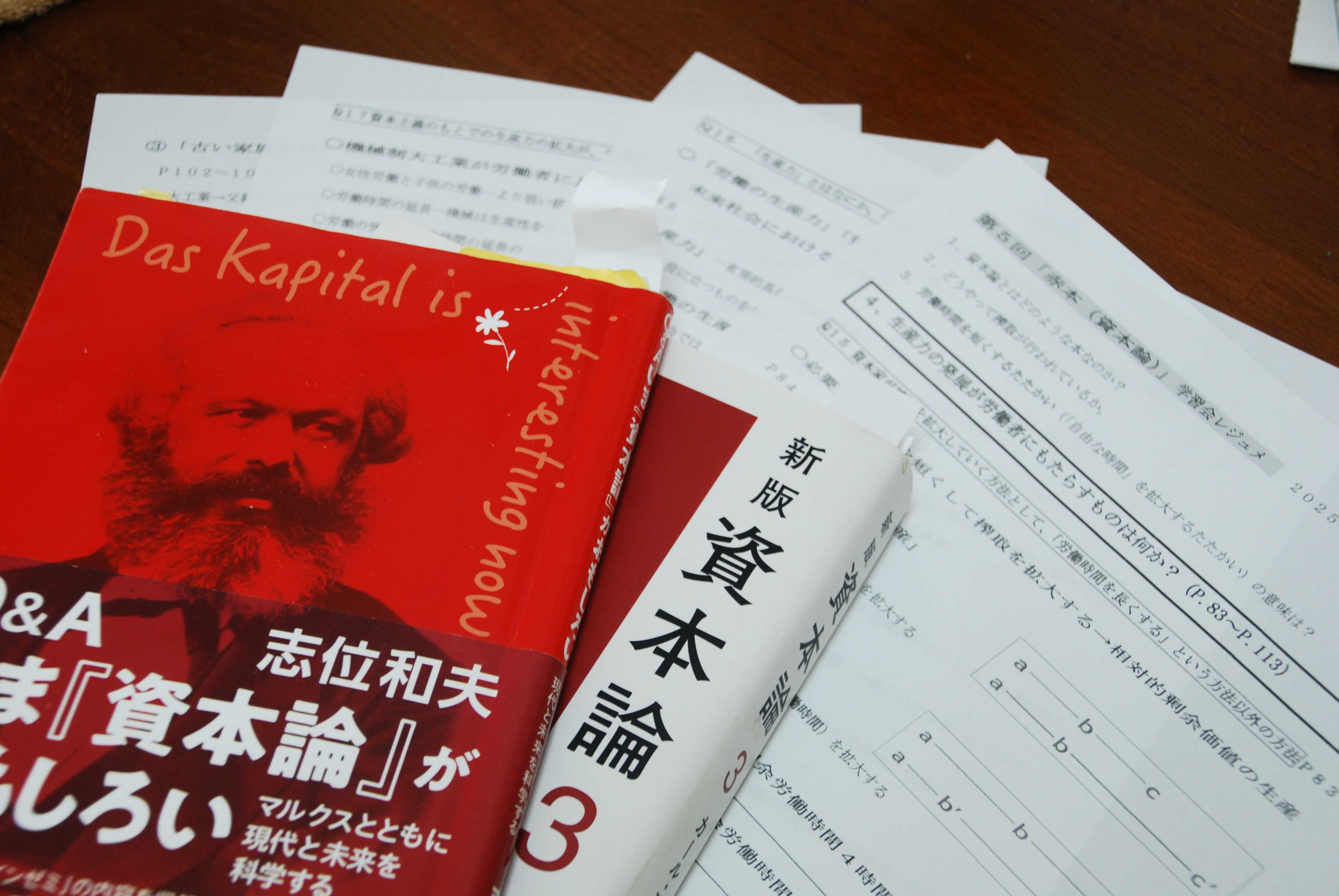
- 今日どんな本をよみましたか?
- 『Q&A資本論』の第5回学習会を前に、…
- (2025-11-20 16:49:58)
-
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- チェンマイに佇む男達 寺本悠介の場…
- (2025-11-20 10:06:55)
-







