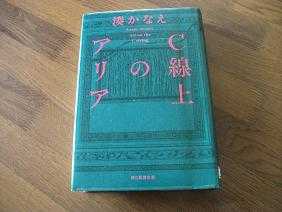2012年09月の記事
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-
朝顔 -11-
[源氏物語] ブログ村キーワード源氏の大臣は返す言葉がなく、真顔でお恨み申し上げて座をお立ちになるのですが、我ながらひどく大人げないお気持ちにおなりで、女房の宣旨に、「すっかり嫌われてしまいましたね。世の物笑いの例にもなりそうですから、決して人に言ってはなりませんよ。『いさら川』のようなことをお頼み申すのは、馴れなれしいようですからね」と、何やら懸命にささやいていらっしゃるのです。女房たちも、「まあ、お断りするなんて勿体ないことを。姫宮はどうしてこんなに薄情なお扱いをなさるのでしょうね」「軽々しく迫るようなことはなさらないご様子でいらっしゃるのに。こんな仕打ちをなさるなんて、お気の毒ですわ」と言います。ほんに源氏の大臣のお人柄の優雅さやじみじみとした趣を理解する感性について、好ましくお思いにならない事はないのですが、『私がご情愛に応じたとしても、世の中の多くの女人が憧れ、お褒め申し上げる浅はかな心と同じに見られるのではいやだわ。それに、心を開いてしまったために軽々しい心の底を見透かされるのも、ご立派な方であるだけに、かえって屈辱的な思いをすることになるのではないかしら』とお思いになると、『お慕いしているような素振りをお見せするのは筋違いですし、かといって繋がりだけは絶たないように、薄情ではない程度のお返事を差し上げて、人伝でのお返事は失礼でない程度にやり過ごしてしまいましょう』と、お考えになるのでした。そして『長年なおざりにしていた仏道修行に励みたいもの』とお思いにはなるのですが、人の口さがなさを身に沁みてご存知でいらっしゃいますので『源氏の大臣とのご交際を嫌って急に出家するような事も、反って思わせぶりな態度と、世間の人が受取りやしないかしら』と、お傍近くにお仕えする女房たちにさえ心をお許しにならず、たいそう用心なさりながら少しずつ仏道修行をなさいます。姫宮のご兄弟は大勢おいでなのですが、同腹ではありませんのでたいそう疎遠でいらして、父宮亡き後の邸内はひどく心細い状態におなりです。そこに申し分なくすばらしい御方がねんごろに御心を尽してくださるのですから、女房たちがみな源氏の大臣とのご結婚に期待をお寄せ申すのは尤もな事なのです。
September 30, 2012
-
朝顔 -10-
[源氏物語] ブログ村キーワード 朝顔の姫宮がおわす寝殿の西面では御格子を下してありましたが、源氏の大臣のおいでを厭うように思われてもいかがなものかと、一間二間ほどは下さずにおきました。月が顔を出してうっすらと積もった雪の光に調和して、なかなか風情のある夜の様子なのです。先ほどの源内侍の色めかしい懸想も『世間でよからぬ何かの譬えと聞いたことがあるな』とお思い出しになり可笑しくなるのです。 今宵はたいそう真面目に姫宮にお話しなさって、「一言でいいのです。私を『憎い』とでも、人伝でなくあなたさまから直接おっしゃってくだされば、いっそ思い切れますのに」と、熱心にお責め申し上げるのですが、朝顔の姫宮は『昔、まだ二人とも若くて世間からも大目に見てもらえる時代でさえ、それに、故父・式部卿の宮が源氏の大臣との縁談をお考えになった時も、私のほうからあってはならぬ恥かしいこととお断り申し上げたのですもの。家も衰え、年の盛りも過ぎた今の私にとって、恋愛などとても不似合い。一言のお返事なんて、ほんとうに恥かしい事だわ』とお思いになってまったく動じない御心でいらっしゃいますので、あさましく恨めしくお思いになるのです。 それでもさすがに相手がばつの悪い思いをするように突き放すことはなく、人伝でのお返事はなさいますので、反って源氏の大臣はじれったくお思いになるのです。 夜が更けると風が激しく吹き、たいそうもの寂しくお思いになりますので、流れる涙を体裁よく拭い給いて、「つれなさを 昔にこりぬ心こそ 人のつらきに そへてつらけれ(昔からあなたさまは薄情でいらしたけれど、その薄情な御心に懲りない私の心は恨めしさに加えてますますあなたさまを恨めしく思います) この気持ちの置きどころがなくて」と強く仰せになりますので女房たちは、「ほんに、ご自身でお返事なさらないなんて、お気の毒でございますわ」と、異口同音に申し上げます。仕方なく姫宮は、「あらためて 何かは見えむ人の上に かゝりと聞きし 心変はりを(あなたさまは薄情と仰せになったけれども、今あらためてどんな心変わりをお見せできましょう。私の気持ちは変わることがありませんのよ)」とお返事なさるのでした。
September 29, 2012
-
朝顔 -9-
[源氏物語] ブログ村キーワード 「桐壺院がご在世でいらした昔をはるかに思い出すにつけても心細いが、それはそれとして懐かしい声だね。親もなく病に臥せっている旅人と思って、私のお世話をお願いしようか」と、物に寄りかかっていらっしゃるご容姿に、源内侍はひどく懐かしい気持ちで昔を思い出しながら、相変わらずなまめかしい『しな』を作り、歯が抜けてすぼんだ口付きを思わせる声づかいでもごもごと、何か気の利いた事を申し上げようとしています。「私も年をとりましたが、あなたさまも同じでございましょう」と申し上げるのですが、とても聞いていられないほど恥かしいのです。 源氏の大臣は『昔から年よりだったくせに、まるで今、急に年をとったような事を言う』と、可笑しくお思いになるのですが、よく考えてみれば源内侍も気の毒なのです。『女盛りのころに桐壺帝のご寵愛を競っていらした女御、更衣たちの中でも、ある方は亡くなられ、あるいは生きる甲斐もなくみじめな境遇に落ちぶれて、世にさすらう身となった方もあろう。藤壺の宮のように三十七歳という若さでお亡くなりあそばすかと思えば、余命いくばくもなさそうな高齢で、その上心構えも浅はかに見えた源内侍が未だこの世に生き残り、のんびりと仏道修行などして余生をすごしているとは、何事も定めなき皮肉な世ということなのかもしれぬ』とお考えになっていらっしゃるしんみりとしたご様子を、源内侍は自分への好き心と勘違いして、すっかり若返ったような気分になるのです。「年ふれど この契りこそ忘られね 親の親とか いひし一言(年を経て古くなりましたけれども、あなたさまとのご縁だけは忘れることができませぬ。あなたさまがかつて「おばばさま」と仰せくだすった、あの一言を思い出しますれば)」と申し上げますので、うとましくお思いになって、「身をかへて 後も待ちみよこの世にて 親を忘るゝ ためしありやと(あなたが死んだ後には、この世で親を忘れる子の例があるものかどうか、どうぞ待って見ていてくださいな) 末頼もしいご縁ですな。そのうちゆっくりお話しいたしましょう」と、座をお立ちになりました。
September 27, 2012
-
朝顔 -8-
[源氏物語] ブログ村キーワード内々の者を前駆に、目立たぬようにしてお出でになります。「参内以外の外出は、億劫に感じる年齢になったのだろうか。桃園の式部卿の宮がご存命でいらした間は女五の宮の御世話をお任せ申していたのだが、今では頼りないご様子で暮らしておいでで『あなたさまだけが頼り』と仰せになるのも道理だし、お気の毒だからね」などと女房たちに言い訳なさるのですが、「さて、どんなものでしょうね。何と仰せになっても好色な御心がいつまでも変わらないのが玉に瑕ではないでしょうか」「そのうち軽々しいお振舞いもありそうですわね」と、ひそひそ言い合うのでした。桃園の宮邸では、人の出入りの多い北側の通用門ではなく、西側の正門に人を入れさせて、宮に訪問のご挨拶をお伝えになります。宮は、『まさか今日はお渡りになるまい』とお思いでしたので、驚いて御門を開けさせなさいます。御門守(みかどもり)が寒そうにしながら慌てて出てきたのですが、うまく御門を開けることができません。きっとこの男の他に下男がいないのでしょう、ごとごといわせながら扉を引いて、「錠がひどく錆びてしまって、うまく開かないぞ」と、独り言のように愚痴をこぼしていますのを、気の毒に思いながら聞いていらっしゃいます。『桐壺院がお隠れあそばされたのは、つい昨日か今日かと思っていたが、もう何年も過ぎてしまったのだな。私は変化する儚い現世を見限ることもできず、現世の木草のうつくしさにも心を奪われるのだ』とお思いになります。口すさびに、「いつのまに 蓬が門とむすぼゝれ 雪ふる里と 荒れし垣根ぞ(蓬が繁茂して御門を閉じてしまい、雪の降る里には荒れた垣根。いつのまにこんなに荒れ果ててしまったのであろうか)」ややしばらくして門番が無理やり開けましたので、やっとお入りになります。女五の宮のお部屋でいつものように御物語りなさいます。昔のとりとめのない話題から始めて、みな話し尽したのですが、源氏の大臣にとっては姫宮のおん事以外関心がありませんのでどうにも眠くてたまりません。ちょうど具合よく、宮もあくびをなさいます。「宵の口から眠くなりますので、ものもよう聞こえませぬ」と仰せになりますとほどなく「鼾」というのでしょうか、聞き慣れぬ音がしますので、これ幸いと大喜びしながら座をお立ちになりますと、ひどく老人めいた咳ばらいをしてこちらにやって来る女房がいます。「畏れながら、私がこちらにお仕えしておりますことをお聞き及びかと頼みにしておりましたが、この世に生きているかどうかもお考えくださらないのが恨めしく、私の方から出て参りました。かつて故・桐壺院は、私を『おばばさま』とおからかいあそばされたものでございます」と名乗りますので、源内侍だと思い出されます。『源内侍のすけは、今では尼になって、こちらの宮のお弟子として仏道修行をしている』と聞いてはいらしたのですが、今まで気にも留めていらっしゃらなかったのでびっくりしてしまいました。
September 26, 2012
-
朝顔 -7-
[源氏物語] ブログ村キーワード 『すっかりお見限りになるようなお扱いはなさらないにしても、後見もなく、源氏の大臣のご寵愛だけが頼りの、これまでのような睦み合いはもう望めないかもしれないわ』など、様々に思い乱れていらっしゃいます。これまでたいていの恨み事は可愛らしく申し上げたのですが、朝顔の姫宮とのおん事については心底辛くお思いなので、反って平静を装っていらっしゃいます。源氏の大臣も普段はお庭をぼんやりと眺めがちで、その上頻繁に宿直なさいます。朝顔の姫宮へ御文を差し上げる事を仕事のようにしていらっしゃいますので、紫の女君は、『ほんに人の噂はまんざら嘘ではないのね。でもそれならそうと、素振りにでもほのめかしてくださればよろしいのに』と、疎ましく思い申し上げるのです。十一月になりましたが、藤壺中宮の喪のために神事なども中止になって楽しみもなく、身を持て余していらっしゃいますので、いつものように女五の宮の所へ訪問なさいます。雪が舞い散って風情のある黄昏時、着慣れて柔らかくなった御衣に、今日は念入りに香を焚きしめて、日中から特別に身づくろいしていらっしゃいますので、そのうつくしさに、移り気な女房などはどんなに心惹かれることやら、と思うほどです。夕暮れになってさすがに黙っておいでにはなれず、紫の女君のもとに御暇乞いのご挨拶をなさいます。「女五の宮がご病気でいらっしゃいますので、今日はお見舞いに参ろうと存じます」と、膝をついて仰せになります。紫の女君は見やりもなさらず明石の姫君をあやしていらっしゃるのですが、その横顔がただならぬ雰囲気ですので、「このごろ妙に御機嫌ななめですね。まあ、それも無理ないことです。私のことなど見馴れ過ぎて見映えしないだろうと思い、間を置いているのに、それをまたどのように邪推なさるものやら」と申し上げますと、「『慣れゆく』とは、ほんに辛い事が多いものですわね」とだけ言って、後を向いて臥していらっしゃいます。このまま見捨てて行ってしまうのはとても辛いのですが、女五の宮にご訪問の御文を差し上げてありますので、お出掛になりました。紫の女君は、『このようないざこざがあるのが夫婦の仲なのに、私は今まで無心に過ごして来たのね』と思い続けて臥していらっしゃるのでした。鈍色の御衣をお召しではあったけれど、色合いや襲ねの具合が好ましく、雪の光に映えた艶な御姿を想像なさると『ほんとうに私から御心が離れてしまったなら、どんなに悲しいことか』と、たまらなくお思いになるのでした。
September 25, 2012
-
朝顔 -6-
[源氏物語] ブログ村キーワード 『今さら昔に立ち戻って、若者のような懸想文を書くなど、年令不相応なことだ』とお思いになるのですが、あちらから絶縁してしまうようなご様子もありませんので、今まで思いを遂げずに過ぎてしまったことが何とも残念で、このままでは済まされそうになくお思いになって、若返ったように御文をしきりに差し上げるのです。二条院の東の対に、女房の宣旨を迎えてお話しになります。斎院の姫宮にお仕えする女房たちで、たいした身分でもない男に靡きやすい女などは、間違いでも起こすのではないかと思うほど源氏の大臣をお褒め申し上げるのですが、朝顔の姫宮は、父宮がご存命でいらした頃でさえ源氏の大臣との結婚をお考えにはなりませんでした。まして今ではお二方とも恋ゆえの物思いとは無縁のはずのご年令であり、世間的にも高いご身分であることをお考えになって、『ちょっとした木草につけての御返事であっても、他の人からは軽々しいと誤解を受けるかもしれないわ』と、他人の目を怖れていらしって打ち解けなさらぬご様子でいらっしゃいますので、相変わらずかたくなな朝顔の姫宮のご性質を、世の人とは違って、珍しくも憎らしくもお思い申し上げるのです。やがてお二方のおん仲が世の中の噂になって「源氏の大臣は、前の斎院の姫宮にねんごろに御文を差し上げているそうだ。女五の宮などもこの縁談を喜んでいらっしゃるらしい。なるほどお二方はお似合いのご夫婦になろう」などと言いますのを、対の上が人伝にお聞きになります。しばらくは『その噂が本当だとしても、私に隠し立てはなさらないはずだわ』とお思いになるのですが、源氏の大臣を注意深くご覧になりますと、いつもとご様子が違いそわそわとして上の空でいらっしゃいますので、情けなく『やはり真剣に考えていらっしゃるね。それなのに気のない振りをなさって、冗談のように言い紛らしていらしたのだわ』と、心を痛めていらっしゃいます。『朝顔の姫宮も私も同じ王族の血筋を引いてはいるけれど、姫宮は世の評判も格別で、昔から高貴な御方とお聞きしていたわ。もしも源氏の大臣が御心移りなさったなら、私はどんなにみじめなことか』今までならぶ人のない厚いご寵愛に馴れておいででしたので、今さら他の女人に圧し負かされる事が残念で、人知れず思い嘆いていらっしゃるのでした。
September 23, 2012
-

手作り石鹸
初夏に作った石鹸たち。左からオリーブオイルだけのプレーンなもの。真ん中前はヨーグルト・パウダー入り。向こう側の大きめのはココナツパウダー、ブルーはペパーミント入り。どれもベースにはオリーブオイルのみを使っているが、ココナツパウダーを入れたものは真っ白になってとてもきれいにできあがった。青色は色素がちょっとダマになってしまったが、ミントがさわやかで夏の入浴にはとても気持ちが良い。いずれもシャンプーとして使えばリンスが不要だし、顔を洗ってもつっぱらないし、もう20年以上愛用している。他に竹炭入り、ゴートミルク入り、紫根入り・・・とさまざま作ってみたが、一番好評だったのがヨーグルトパウダー入りのもの。泡立ちがいいのだそうだ。
September 23, 2012
-
朝顔 -5-
[源氏物語] ブログ村キーワード 九月の末ともなると空の気色にも風情があり、風に舞い散る木の葉のかそけき音につけても、女房たちは斎院でいらした昔のことをしみじみと思い出しながら、折々に源氏の大臣から届いた御消息文について、面白くも物哀れにも拝見したご情愛の深さなどを姫君にお話し申し上げます。源氏の大臣はお気持ちがすっきりしないままお帰りになりましたので、その夜はなかなか眠れぬまま何くれと考え続けていらっしゃいます。朝は早くに御格子を上げさせなさいまして、前栽の朝霧を眺めていらっしゃいます。枯れた秋の花々の中に朝顔が、あれこれの草にからみつきながら、色も匂いも褪せてあるかなきかに咲いています。それを折らせ、御文をつけて朝顔の姫宮に差し上げます。「あなたさまにはっきりと拒絶されまして、ひどくきまりの悪い思いで帰りました。私のみっともない後ろ姿をどのようにご覧になったかと思いますと、いまいましく存じます。されど、見しをりの 露わすられぬ朝顔の 花のさかりは 過ぎやしぬらん(昔あなたさまを拝見した折に、朝顔の花を差し上げましたね。私はあれから露ほども忘れたことはございませんでしたが、あなたさまとの恋の盛りは、もう過ぎてしまったのでございましょうか)薄情なお扱いをなさるとしても、積年の思いに対して『お気の毒に』くらいは、お思いいただけるかと頼みにしておりますのに」など、書いていらっしゃいます。朝顔の姫宮は、このように抑制の利いた御文にお返事をしないのは『情趣を弁えていないようだから』と、お思いになります。女房たちも御硯を取りそろえてお返事をお勧め申し上げますので、「秋はてて 霧のまがきにむすぼゝれ あるかなきかに うつるあさがほ(花の盛りも過ぎ、飽きも果て、霧のたちこめる垣根にまつわりつき、あるかなきかに咲いている朝顔の花。それが私でございます)その色あせた朝顔のような衰えにつけても、悲しく」とだけ書いてあります。そこには何の情趣もないのですが、どうしたことやら、源氏の大臣は御文を手離し難くいつまでもじっと見ていらっしゃるのです。服喪中にふさわしい青鈍色の紙で、墨付きも柔らかく、奥ゆかしいとご覧になっていらっしゃるのでしょう。男女の御文のやりとりというものは、それを書く人のご身分や書きぶりなどで目くらましされてしまうものでございます。書いた当時は欠点がないようであっても、後でそれをそのまま物語として語り継ぐとなると、事実とはやや違ったお話にもなるようでございますから、うまく紛らわしている事も多いのでございましょう。
September 21, 2012
-

アサリの子
親指の爪ほどの可愛いアサリ。「食べるの、かわいそうね」と言うと「育てるか?」だって。
September 20, 2012
-
朝顔 -4-
[源氏物語] ブログ村キーワード「人知れず 神のゆるしを待ちしまに こゝらつれなき 世を過ぐすかな(私は人知れず、賀茂の神のお許しをお待ち申し上げておりました。あなたさまの薄情な態度をこらえにこらえて、こんなにも長い年月を) しかし今はもう斎院の任が解けたのですから、神の諫めを口実に私を避けることができましょうか。須磨への流浪の後、さまざまな苦労をいたしました。せめてその片端だけでも聞いて下されば」と、ひたむきに訴えますのも、昔よりいま少し優雅さが加わったご様子でいらっしゃいます。今は源氏の大臣もそれなりのご年令におなりなされたとはいえ、大臣という御位には釣り合わない御年ではいらっしゃるのでしょう。「なべて世の あはればかりをとふからに 誓ひしことゝ 神や諫めむ(あなたさまが通り一遍のご挨拶をなさっただけとしても、一度は神に仕えた身の私でございますから、それだけできっと神はお諫めになりましょう)」と、宣旨を介して朝顔の姫宮からお返事があります。「おや、何ということをおっしゃる。昔の罪はみな科戸の風と一緒に祓ってきましたのに」と仰せになるご様子のうつくしさは、こぼれるほどでいらっしゃいます。取り次ぎの女房・宣旨が「神はその御禊を、お受けにならないのではないでしょうか」と、ちょっとした事を申し上げるのも、姫宮にはたいそう気が引けるのです。朝顔の姫宮が男女の道に関心のないご様子は年ごとに増し、思慮深くばかりいらしって源氏の大臣にお返事も申し上げないことを女房たちはやきもきしながら拝見するのでした。「今日のお見舞いは思いがけず好色めいてしまいましたね」 源氏の大臣は深いため息をおつきになって、座をお立ちになります。「人間は年を重ねると、どうもきまりの悪い思いをするものですね。あなたさまのせいで、世にないほどやつれた私の姿を、せめて『今こそお見送りいたしましょう』とだけでもおっしゃってくださらないのでしょうか」と仰せになってお帰りになった後は、女房たちが大仰にうるさいほどお褒め申し上げるのでした。
September 20, 2012
-
朝顔 -3-
[源氏物語] ブログ村キーワード朝顔の姫宮のいらっしゃる西側をご覧になりますと、枯れた秋の前栽の風情が見渡されます。静かに物思いにふけっていらっしゃるであろうご様子が奥ゆかしくしみじみと思いやられ、堪えることがおできになりません。「こうしてお伺いいたしました機会に、斎院の姫宮にもご挨拶申し上げてまいりましょう」と、そのまますぐにお渡りになります。夕方の暗くなる時分なのですが、喪中ですので鈍色の御簾に黒い御几帳の透き影が寂しく、薫物の追風がなまめかしく吹き通る姫宮のお部屋はたいそう上品なのです。簀の子では気がひけますので、南の廂の間にお入れ申し上げます。宣旨という女房が対面して、朝顔の姫宮からのご挨拶を申し上げます。「御簾の外での人伝によるご対面とは、若者扱いでございますな。神さびてしまうほどの長い年月、私が心を尽してきた労に報いて、御簾への出入りをお許しいただきたいものと頼みに思っておりましたが」と、宣旨の取り次ぎを物足りなくお思いになります。朝顔の姫君は、「過ぎし日はみな夢のように思えますが、たった今夢から覚めたばかりでございまして『世は儚いもの』と、いまだ思い定めがたく、あなたさまの長い年月の労につきましては、後でゆっくり考えまして申し上げとう存じます」と、宣旨を介して申し上げます。源氏の大臣は『ほんに、何とも定めがたい憂き世だな』と、故・藤壺の宮のことなど、さまざまお思い続けになるのです。
September 19, 2012
-
朝顔 -2-
[源氏物語] ブログ村キーワード 「ほんにまあ、いずれにしても呆れるほかないほど無常な世を、私だけは相変わらずの境遇で生き長らえておりまする。長生きいたしますのも、恨めしい事が多いものでございますが、こうしてあなたさまが世に立ちかえり栄えておいでなさるお喜びを思いますと、あの時ご退京を拝見したまま死んでいましたなら、どんなに口惜しく思ったことでございましょう」と、お声をふるわせながら仰せになります。そして、「あなたさまはまことにうつくしくご成人あそばされましたね。まだ童でいらしたころに、私が初めて拝見いたしました時には『世の中によくもこんなに光り輝くばかりうつくしい方がお生まれになった事よ』と驚いたものですが、時々拝見いたしますたびにうつくしさが増して、怖ろしいほどでございました。今上におかれましても、あなたさまにたいそうよく似ていらっしゃると人々が申し上げますけれども、いくら何でもあなたさまほどではいらっしゃらないだろうと、私は思っているのでございますよ」と、ながながとお話しなさいますので、源氏の大臣は『本人を前にして、こうあからさまに褒めるものではあるまい』と、可笑しくお思いになります。「流浪の身となりひどく落胆して暮らしておりましたので、すっかり落ちぶれてしまいました。今上のご容貌は、いにしえの世にも並ぶ人のないほどと、ありがたく拝見しておりますので、おん叔母上の仰せには承服いたしかねまするが」と申し上げます。「時々あなたさまを拝見いたしますならば、余命短い私の命も延びることでございましょう。今日はあなたさまにお会いして、老いも忘れ、憂き世の嘆きもみな晴れた心地がいたします」と、またお泣きになります。「あなたさまの姑・三の宮は、しかるべきご縁で婿殿として親しくお付き合いなさるのを羨ましく存じておりまする。お亡くなりなされた式部卿の宮も、あなたさまと斎院の姫宮とのご縁について、いつも悔いていらしたとか」と仰せになりますので、『おや』とお思いになります。「私が婿として親しくお付き合いさせていただきましたならば、今頃はきっとお幸せでいらしたと存じます。されど宮も姫君も、私を遠ざけられまして」と恨めしそうに、女五の宮に申し上げます。
September 18, 2012
-
朝顔 -1-
[源氏物語] ブログ村キーワード 朝顔の姫宮は、父・式部卿の宮の薨去にともない、斎院をお下がりになりました。源氏の大臣は一度思いをおかけになった女君を忘れられぬご性分でいらっしゃいますので、ご弔問にかこつけて頻繁に御文を差し上げます。朝顔の姫宮はうっとうしくお思いになって、お返事もようなさいませんので、源氏の大臣はひどく残念に思っていらっしゃいます。 九月になって朝顔の姫宮が、桃園の故・式部卿の宮邸にお帰りになることをお耳になさいます。桃園のお邸には源氏の大臣の叔母宮でいらっしゃる女五の宮がおわしますので、そちらへのお見舞いを口実にお渡りになります。故・桐壺院はおん同胞の中でも女五の宮を格別大切にしていらっしゃいましたので、今でも親しく御文をお交わしなのでございましょう。同じ宮邸の寝殿の西に朝顔の姫宮が、東に女五の宮が住んでいらっしゃいます。式部卿の宮がお亡くなりあそばされてから間もないのですが、邸内がすっかり荒れてしまったような心地がして、寂しくしめやかな雰囲気なのです。 女五の宮が源氏の大臣に対面なさって、昔のおん物語をなさるのですが、まことに年老いたご様子で、咳こみがちでいらっしゃいます。源氏の大臣の姑・大宮は、女五の宮の姉宮なのですが、たいそう若々しい感じでいらっしゃるのに、五の宮は姉・大宮に似たところがなく、声は太くお身体もごつごつした感じのおん方でいらっしゃいます。「桐壺院がお隠れあそばされてから後は、何事につけ心細く思われまして、年とともに涙もろくなりがちにて過ごしておりまするところに、頼りの式部卿の宮までが私を置き去りになさいまして、ますますあるかなきかのように生き残っているのでございます。あなたさまが私をお忘れにならずご訪問くださいますので、寂しさも紛れるような心地がいたします」と申し上げます。 源氏の大臣は『畏れ多くもひどくお歳を召したものよ』と思うのですが、かしこまって、「院がお隠れあそばされてからは、何事につけても世の中がすっかり変わってしまいました。私も思いがけぬ罪にあたりまして知らぬ土地に流浪いたしましたが、朝廷のお取り立てにより再びお仕えするようになりました。なかなか落ち着かず多忙でございますので、こちらに参上いたしまして昔のおん物語を承ることができませんことを、長い間気掛かりに存じておりました」と申し上げます。
September 16, 2012
-

TAITU の食器
食器を買った。直径21センチほどの、おしゃれな楕円形のボール。ちょっといびつに作られているので、重ねてもきちんと収まらないのだが、ビビッドな赤い唐辛子が気に入った。右下は、ひっくりかえしたもの。外側にもびっしり赤唐辛子。大型なのでパスタはもちろん、どんぶりとしてラーメンや蕎麦にも使えるので思いの外重宝している。「赤色」について、中国の古代医学書である《黄帝内経素問・金匱真言論篇》には、「南方は赤色、入りて心に通じ、竅を耳に開き、精を心に蔵す。・・・その味は苦・・・」と記されている。赤はまた、「喜」にも通じる。余談だが、養*酒のCFで「男性は8の倍数、女性は7の倍数で身体が変化する」と言っているのは、上記《黄帝内経素問》の「上古天真論篇」に基づくものだ。
September 15, 2012
-
六条の院
[源氏物語] ブログ村キーワード 源氏は故・桐壺帝の御子ですから、帝から多くの遺産を継承したはずです(自邸としている二条の院は、故母・桐壺の更衣邸ではありますが)。実際須磨・明石へ流謫する際、紫の上に御荘など多くの財産管理を任せています。その上六条御息所からは娘の斎宮の後見人を任され、藤壺中宮からも冷泉帝のお世話を頼まれています。つまり前(さき)の春宮妃(六条御息所)と前の帝の中宮(藤壺)という二人の宮家の財産をも、その御子を通じて受け継いだことになりましょう。加えてその地位たるや太政大臣に昇進しています(藤裏葉では、太上天皇にまで上り詰めます)。ここに至って光源氏は、イケメンで好き者なモテ男というだけでなく、およそこの世で手にし得る最高の権力と財力を手にしたことになります。ところが光源氏という男は不思議な事に現実の生活を楽しめないようで、いつも「出家したい。仏道修行に励みたい」と言います。そのくせ「私が出家したら、あなたがお寂しいだろうと思って」と、紫の上をダシにして出家なんぞする気配もない、いい加減な男でもあります。この後「乙女」の巻で、光源氏は六条御息所の所有地を含む2万坪にも及ぶ敷地に「六条の院」という邸宅を建設し、四季になぞらえた建物を造営して女君たちを住まわせます。六条の院は源氏の理想のハーレムというわけです。しかしハーレムが女性たちにとって理想郷なはずがなく、六条の院に移り住んでから源氏ワールドには翳りが見え始めます。 渡辺淳一が「『仲の良い夫婦が幸せな人生を送りましたとさ』というだけでは、小説として成り立たない」というような事をどこかで言っていましたがまさにその通りで、「源氏物語」も青年貴族の溌剌とした恋愛遍歴だけでは退屈なわけです。時代を超越して人間の心の底に澱む「暗く深い苦悩」が描かれているからこそ、千年もの間老若男女を問わず読み継がれてきたのだと思います。その苦悩の舞台がどこあろう光源氏が理想とした「六条の院」とは、何と皮肉な事でしょう。そしてこの「薄雲」の巻での「春秋論」こそ「六条の院」建設、言い換えるなら「暗く深い苦悩」に舵を切ったターニングポイントと私には思えるのです。
September 14, 2012
-
薄雲 -25-
[源氏物語] ブログ村キーワード斎宮の女御は、いかにも秋の情趣を理解しているような顔で、源氏の大臣にお返事申し上げたことが悔しく、また恥ずかしくお思いになり、鬱々として気が晴れず、まるでご病気のようになっていらっしゃるのですが、源氏の大臣は知らぬふりをなさって、たいそう生真面目に、いつもより親らしくお振舞いになります。紫の女君に、「斎宮の女御は秋に心を寄せていらっしゃる。それも結構だが、あなたが春の曙に心惹かれていらっしゃるのも尤もと思います。私は春秋の時々につけて、草木の花を見るにつけても、あなたの気に入るような管弦の遊びをしたいものと思っていますが、公私とも多忙な私ではなかなか思い通りにはできませぬ。それに、何とかして出家したいとも思うのです。ただ出家したならばあなたが寂しいであろうと、それが気掛かりなのです」とお話しになります。大井の山里に居る明石の君へも『どうしているか』と、いつも気にかけていらっしゃるのですが、高いご身分では、自由に出かけることがたいそう難しいのです。明石の君が『如何ともし難く情けない間柄』と悲観している様子を、『どうしてそうまで思う必要があろうか。二条院で、適当にあしらわれたくないと思うのは、分不相応ではないか』とは思うものの、不憫でもありますので、例の嵯峨の御堂のお念仏にかこつけて大井にお渡りになりました。大井の山里では住み馴れるに従って寂しさが増し、鈍感な人であっても哀れを催すような侘しい場所なのです。まして源氏の大臣がめったにおいでにならぬ辛い仲ですから、さすがにこうしておいでくださるご情愛のほどを思うと、反って慰め難いほどの様子ですので、たまらない気持ちにおなりです。たいそう木の繁った間から鵜飼い舟のかがり火がちらほらして、それが鑓水の蛍のようにも見えて風流なのです。「このような水辺の住いに馴れていなかったなら、この地の景色も珍しく思えたでしょうね」と明石の君に仰せになりますと、「いさりせし 影わすられぬかゞり火は 身のうき舟や したひ来にけむ(明石の浦の漁火がここでも見えるのは、どうしてなのでございましょう。浮舟のようなわが身の憂さを慕って、ここまでやって来たのでしょうか)辛い気持ちは、今も昔も同じでございますわ」と申し上げます。「浅からぬ したの思ひを知らねばや なほかゞり火の 影はさわげる(決して浅くはない私の本心をあなたは知らないから、かがり火のようにいまだに心が騒ぐのですよ)あなたこそ、私に世を憂きものと思わせたのですよ」とお言い返しになって、お恨みになります。この頃は総じて心静な御気分でいらっしゃいますので、御堂でのお勤めをなさっていつもより長く大井にいらっしゃるせいでしょうか、明石の女君の物思いは多少なりとも紛れましたとか。
September 13, 2012
-
薄雲 -24-
[源氏物語] ブログ村キーワード もう少しで間違いもなさりそうなのですが、女御に『何と嫌な事を』と思われますのも道理ですし、ご自分でも『怪しからぬ事を』とお思い直しになってため息をついていらっしゃいます。そのご様子がひどくなまめかしいので、女御は疎ましくお思いになって、少しずつそっと奥に入ってしまう気配です。「ひどく嫌われてしまいましたね。本当に思いやり深い人というものは、こんなふうに薄情ではありませんよ。まあ、いいでしょう。しかしこれからは私を疎ましく思ってはいけませんよ。私も辛いのですから」とおっしゃって、あちらへ行っておしまいになりました。女御は、源氏の大臣のしっとりとした残り香さえ疎ましくお思いになります。女房たちは御格子を下して、「この御座布団の移り香のすばらしい事。言葉がありませんわ」「どうしてこうすばらしいものばかりを取り集めて、『柳の枝に咲かせた』ご様子をしていらっしゃるのでしょう」「うつくしさは忌々しいほどですわね」と言い合うのでした。源氏の大臣は、紫の女君がいらっしゃる西の対にお渡りになるのでしたが、すぐには奥にお入りにならずひどくぼんやりなさって、端に近いところで横になってしまいました。燈籠を遠くにかけさせ、女房たちを近くにお寄せになって、おん物語などをおさせになります。『こんなふうに無理な恋をして、胸をいっぱいにする癖がまだ私にあるなんて』と、我ながら情けなくお思いになります。『だがこの恋は、いかにも相応しくない。恐ろしさや罪深さでは藤壺の宮との恋のほうが勝るけれども、昔の好き心は若気の至りとして仏や神もきっとお許しくださろう』と心をお鎮めになるにつけても、『今ではもう昔にくらべると、我ながら危なげなく思慮深くなったものだ』と思い知るのでした。
September 12, 2012
-
薄雲 -23-
[源氏物語] ブログ村キーワード「一門繁栄という望みはともかく、移り変わる四季折々の風情を楽しみたいものでございます。春の花の林と秋の野の草花の優劣について、古来論争されておりますが、なるほどと納得できる判定はございませぬ。唐土では『春の花の錦ほどみごとなものはない』と申しますが、我が国の歌では秋の情趣を特に好んでいるようでございます。春秋いずれもその時々の景色を拝見いたしますと、花の色でも鳥の音でも目移りがして、どちらがよいか分別が付きかねます。狭い垣根の内であっても時節に応じた情趣を味わうだけの春の花の木を植え並べ、秋の草花を植えかえて、聞く人のない野辺の虫をも庭に住まわせて、あなたさまのお目にかけたいと存じまするが、春と秋とどちらの季節に御心が惹かれましょうか」と申し上げます。斎宮の女御は『たいそうな難問を』と、お返事しにくくお思いになるのですが、無下に黙ってお返事なさらないのもよろしくありませんので、「私ごときがどうして弁えられましょう。仰せのように春秋の優劣はどちらとも決めかねますが、私が不思議に恋しく思われます秋の夕べこそ、露のように儚くお亡くなりになった母・御息所の『よすが』とも存ぜられまして」と、思いのまま仰せになるご様子がたいそう可愛らしいので、我慢がおできにならず、「君もさは あはれをかはせ人しれず わが身にしむる 秋の夕風(あなたさまもそう思いでいらっしゃるならば、どうか私と気持をかよわせてください。人知れず秋の夕風が身に沁みる私なのですから)あなたさまが恋しくて、耐え難い折々もございますれば」と申し上げるのですが、どんなお返事ができましょう。『意味が分からない』といったご様子なのです。この機会に、お胸のうちに秘めていらした恋心を打ち明けて、お恨み申し上げることが多々あるようでございます。
September 9, 2012
-
薄雲 -22-
[源氏物語] ブログ村キーワード 「私は一時期須磨や明石にさまよっておりましたが、その時に帰京後はああもしよう、こうもしたいと思っておりましたことを少しずつ叶えてまいりました。東の院にいらっしゃる花散里の君は、頼りとなる人のないおん身の上なのでお気の毒に存じておりましたが、今はこちらで穏やかに過ごしていらっしゃいます。気立ての憎からぬ人でございまして、お互いによく理解し合っておりますので、たいそうさっぱりとした関係でございます。かの地から戻りまして、帝のおん後見をつとめさせていただく喜びなどはさほど深く心に感じませぬが、こうした恋心は抑え難いものでございます。あなたさまの入内に際しましても、並々ならず我が心を抑えましてのおん後見であることを、ご存知でいらっしゃいましょうか。さればせめて『お気の毒に』とだけでも私にお言葉を戴かねば、どんなに張り合いのないことでございましょう」と仰せになります。女御はどうしていいのか分からずお返事もありませんので「やはりそうですか。ああ、情けない」と、話題を変えて紛らわしてしまいました。「今は現世に未練を残さず平穏に生き、山にでも籠って心のままに往生のための勤行をしたいものと思っておりまするが、この世の思い出とするべき節のない事がやはり残念でございます。しかし明石の姫という幼い人がおりますので、成長が待ち遠しく存じます。恐縮ではございまするが、あなたさまのご尽力で私の一門を繁栄させてくだすって、私の死後も姫君の入内にお力添えを戴きとう存じます」と、申し上げます。女御からのお返事はたいそうおっとりとした様子で、辛うじてひと言だけほのかに仰せになる気配がたいそう慕わしげに聞きとれますので、しんみりと、日が暮れるまでおん元においでになります。
September 8, 2012
-
薄雲 -21-
[源氏物語] ブログ村キーワード女御は御几帳を隔てただけで、源氏の大臣とご対面なさいます。「前栽の花がすっかり開いてしまいました。凶事続きで白けた年なのに、花はちゃんと咲く時を知っているのですね」夕映えの中、柱に寄りかかっていらっしゃる源氏の大臣の御姿はたいそうご立派なのです。六条御息所がご存命でいらしたころの思い出話、あの野宮をお訪ねして立ち去りかねた曙の事などをお話しになり、たいそうもの悲しくお思いになります。女御も、母・六条御息所の事をお思い出しになって、すこしお泣きになる気配がたいそう可愛らしく、みじろぎなさる時も驚くほどものやわらかに優美でいらっしゃいます。『直接お目にかかれぬとは、残念だ』と、お胸がどきどきなさる好き心も困ったものです。「私はこれまで特に思い悩むこともなく心安く過ごして参りましたが、やはり好き好きしい事に関して物思いが絶えることはございませんでした。あってはならぬ恋ゆえに心苦しく思う事が多々ございましたが、中でも最後まで思いが晴れずに終わってしまった事が二つございます。一つはあなたさまの母・六条御息所のおん事でございます。私を不愉快な者とばかり思い詰めたままお亡くなりになられた事が、かつては私の一生の嘆きの種とまで思われたのでございます。しかるに今私があなたさまにこうまでお仕え申し、また親しく接していただきますことを心の慰めといたしておりまするが、故・御息所のお恨みが晴れぬままならば、往生の妨げになりはせぬかと気掛かりに存ぜられるのでございます」とお話し申し上げるのですが、今一つ藤壺の宮とのおん事はお話しになりません。
September 7, 2012
-
薄雲 -20-
[源氏物語] ブログ村キーワード そして、亡き藤壺の宮のおん為にもお気の毒であり、また帝が御譲位をも思召すほどお悩みあそばすのももったいなく、『一体誰が帝に奏上したのか』と、怪しくお思いになります。王命婦は、御匣殿(みくしげどの)に移り、曹司を賜って住んでいました。源氏の大臣はそこで命婦に対面なさって、「あの事を、藤壺の宮は何かの機会に、些かでも帝に奏し給うた事がおありか」とお尋ねになるのですが、「とんでもございませぬ。帝がお聞きあそばすのを何よりも心配していらっしゃいました。されど一方では、帝がご存知あそばさぬ事で、罪を負うことになりはしまいかと、帝のおん為を思召して嘆いていらっしゃいました」と申し上げるのです。藤壺の宮が並々ならず用心深くいらしたご様子などをお思い出しになって、今さらに限りなく恋しくお思いになるのです。斎宮の女御は、源氏の大臣が期待なさった通り帝のよい御世話人におなりで、帝からのご寵愛も格別でいらっしゃいます。女御のお心遣いや容姿なども源氏の大臣の理想通りですので、大切にお世話申し上げるのでした。秋のころ、斎宮の女御は二条院にお里下がりなさいました。女御のおん為に、寝殿のしつらいを輝くばかり美しく飾り立て、今ではすっかり父親になりきってお迎え申し上げます。秋の雨がたいそう静かに降り、色々に咲き乱れている前栽の花々の上に露となっています。源氏の大臣は六条御息所や藤壺中宮とのおん事をあれこれとお思い出しになられて、お袖を涙で濡らしながら女御の御方にお渡りになりました。濃い鈍色のおん直衣姿でいらして、世の中が穏やかならぬ事を口実に、藤壺中宮が亡くなられてから喪服姿のまま精進していらっしゃいます。数珠を引き隠して体裁よく振舞っていらっしゃる優雅なご様子で、御簾の内にお入りになりました。
September 6, 2012
-
薄雲 -19-
[源氏物語] ブログ村キーワード帝は王命婦に詳しく聞きたいと思召すのです。『だが、母宮が秘めていらした事を、何でいまさらと思われるだろう。大臣にも、今まで私のような事例があったのかどうかを、それとなくお尋ね申し上げたい』とお思いになるのですが、好い機会がありません。帝はますます御学問に没頭なさって、我が国や唐土のさまざまな書物を調べていらっしゃいます。すると、唐土には公然・非公然に係わらず同じような例がたいへん多かったのですが、日本(ひのもと)には見つけることがおできにならないのでした。『たとえそうした例があったとしても、このように内密にしているなら、後世の人が伝え知るすべはない。源氏の姓を賜り臣下に下った皇族が、納言や大臣になった後に再び親王となり、帝の位にもおつきになる事例はたくさんあった。源氏の大臣の人品が優れていることを理由に、位をお譲り申そうか』と、帝はさまざまお思いになるのでした。秋の司召(つかさめし)で、源氏の大臣は太政大臣に昇進なさることが内定しました。その折に、帝はかねてからお考えでいらした譲位の事を、源氏の大臣にお話しあそばされたのです。源氏の大臣はひどく恥かしく、また恐ろしくお思いになり、そのような事はあってはならぬとお返事申し上げます。「故・桐壺院は、あまたの御子たちの御中でもとりわけ私をご寵愛くださいましたが、私に帝位をお譲りになろうとはお考えになりませんでした。そのご意向に背き、及びもつかぬ地位にどうして就くことができましょう。故・院のご意向通りに朝廷にお仕えし、今より少し齢をとりましたなら心安らかな勤行で隠遁の日々を過ごさせていただこうと存じます」と、いつもと同じように奏上なさいますので、帝はたいそう残念に思召すのでした。源氏の大臣は太政大臣におなりですが、思うところあってしばらくは内大臣のままで、御位だけは太政大臣相当の正従一位に上り、牛車での出入りが許されました。帝はそれももったいなくお思いあそばされて、親王になり給うべき由を仰せになるのですが、源氏の大臣は、『私が親王となれば、政の補佐役がいなくなる。権中納言が大納言となり、右近の大将を兼任なさったが、さらに一階級昇進して内大臣となった時、すべてお譲りしよう。その後は、出家して静かに過ごしたいものだ』と、お思いなのでした。
September 5, 2012
-
薄雲 -18-
[源氏物語] ブログ村キーワードその日は偶然、『桃園式部卿の宮、ご崩御』との奏上がありましたので、帝はますます天の凶事と思召し、お嘆きあそばします。不幸が相次ぎますので源氏の大臣は二条院にもお帰りにならず、帝のお傍にお仕えなさいます。しんみりとお話しなさるうち帝は、「私の寿命は、尽きてしまうのではないでしょうか。何となく心細く、気分も悪いのです。世の中も天変凶事が続き、何事も激しく変化していきます。今までは故・母宮がご心配なさるであろうと私の身の振り方についても遠慮してきましたが、母宮亡き今は退位して気兼ねなく過ごしたいと思うのです」とお話しなさいます。源氏の大臣は驚いて、「何と、あるまじき思召しでございます。世の中が平穏でない原因は、必ずしも政にあるとは限りませぬ。すぐれた御世であってもやはり数々の凶事が起こったものでした。聖代の帝の御代にも、道理にはずれた出来事は、唐土にも出来いたしました。我が国も同じでございます。ましてこの度の凶事はそれなりの年令でございますから、寿命であったのでございましょう。思い嘆くべきことではございませぬ」とお話して、お慰め申し上げます。筆者は女の立場から政治向きの内容を語るのは気がひけますので、これ以上述べることはいたしませぬ。いつもより黒い御装束にやつしていらっしゃる帝のご容貌は、源氏の大臣と瓜二つなのです。帝におかれましても、これまで幾年も鏡に映るご自分の御姿をご覧になるにつけ『似ている』と思召していらしたのですが、僧都の話を聞し召してから実父としてしげしげとご覧になりますと、『私がこの秘密を知っていることを、何とか知らせたい』とお思いになるのです。されどやはり、源氏の大臣がきまり悪くお思いになるに違いありませんし、帝ご自身も若いお気持ち故に恥ずかしくてお言い出しになれず、ただちょっとした世間話を、いつもより特になつかしくお話しなさいます。帝がかしこまった態度をおとりになって、いつもとはご様子がちがっていらっしゃることを、賢明な大臣は不審にお思いになるのですが、まさか帝が秘事をすっかりお聞きあそばしたとはお思いにならないのでした。
September 4, 2012
-
薄雲 -17-
[源氏物語] ブログ村キーワード あまりの事実に、帝はしばらく茫然となさってお返事もありません。僧都は『勝手にこちらから奏上した事を、帝はご不快に思召したのであろうか』と困惑し、遠慮勝ちにそっと退出しようとします。帝は僧都をお召とどめになり、「何も知らずにこのまま過ごしていたら、来世にまでも及ぶ罪障となったにちがいない。今までそなたが隠していたのは、私を心配してのことだったのだね。このことを知っている人は、他にいるのであろうか」と仰せになります。「拙僧と王命婦以外に知る人はございませぬ。それゆえたいそう恐ろしいのでございます。天変が起こってしきりに戒めを現し、世の中が安寧でないのはこの為なのでございます。帝がまだご幼少で、物の道理もお分かりにならぬ間はまだしも、しだいにご成長あそばされて善悪の分別がおつきになる時になって、天はその罪を明らかに示すのでございます。よろずの天変はご両親の御世に原因があるのでございます。これらの異変の原因を帝がご存知あそばさないのが恐ろしく、これまで口外すまいと決心してまいりましたけれども、奏上したのでございます」と、泣く泣く申し上げるうちにすっかり夜が明けてしまいましたので、僧都は退出いたしました。帝は思いもよらぬ重大な事をお聞きあそばされ、様々に御心が乱れ給うのです。故・桐壺院のおん為にも気掛かりですし、実の父君でいらっしゃる源氏の大臣が臣下として朝廷にお仕えなさるにつけても申しわけなくもったいない事と、あれやこれやとお思い悩みあそばされて日が長けても夜の御殿からお出ましになりません。帝のご様子をお聞きになった源氏の大臣が、驚いて参内なさるのをご覧になるにつけても、帝はますます耐えがたく思召しておん涙をこぼし給うのですが、源氏の大臣は『きっと、亡き藤壺の母宮のおん事を思召しての涙であろう』と拝見なさるのです。
September 2, 2012
-
薄雲 -16-
[源氏物語] ブログ村キーワード 帝は、『何事であろうか。僧都にはこの世に執着の残るような不満でもあるのだろうか。聖僧とはいえ、道に外れた嫉妬心というものは深く、厄介なものだから』と思召して、「幼い頃からそなたとは心を隔てる事もなかったのに、私に言えない事を心に秘めていたとは、薄情な」と仰せになります。僧都は、「畏れ多いことでござりまする。拙僧は仏が誡めて秘密になさる真言の深い道理についてさえも、決して隠し置くことなく、帝にすべてご伝授申し上げておりまする。まして心に隠し立て申すようなことなど決してございませぬ。これは過去と未来にわたる重大事でございまする。お隠れあそばされた桐壺院と母后・藤壺入道の宮、そして只今の世をお治めなさる源氏の大臣(おとど)のおん為に、このまま隠しておきましては反ってよからぬ事として世間で取り沙汰されることになりましょう。拙僧のような老法師の身には、たとえ災禍が降りましょうとも何の悔いもござりませぬ。仏のお告げによりこの大事を奏上申すのでございます。帝をご懐妊あそばされた時より、故・藤壺の宮が心に深くお思い嘆きなさる事がございまして、拙僧に御祈祷をお申しつけあそばす事情がございました。詳しい事につきましては、拙僧の如き法師の心には分かりかねます。不慮の事件がございまして源氏の大臣がいわれのない罪に問われ、須磨の地に流されました時、故・藤壺の宮はますます恐ろしく思召して、さらに御祈祷をお命じになりましたが、源氏の大臣も須磨にてこれを聞し召し、加えて御祈祷を仰せつけになりました。以来帝の御位におつきなさるまで、拙僧には『玉体安全のご祈祷』をお申し付けになったのでございます。御祈祷を承りました事情の仔細とは」と、詳しく帝に奏上申し上げます。帝が聞し召すにつけましてもあさましく、不思議で、恐ろしくも悲しくも様々に御心が乱れるのでした。
September 1, 2012
全25件 (25件中 1-25件目)
1