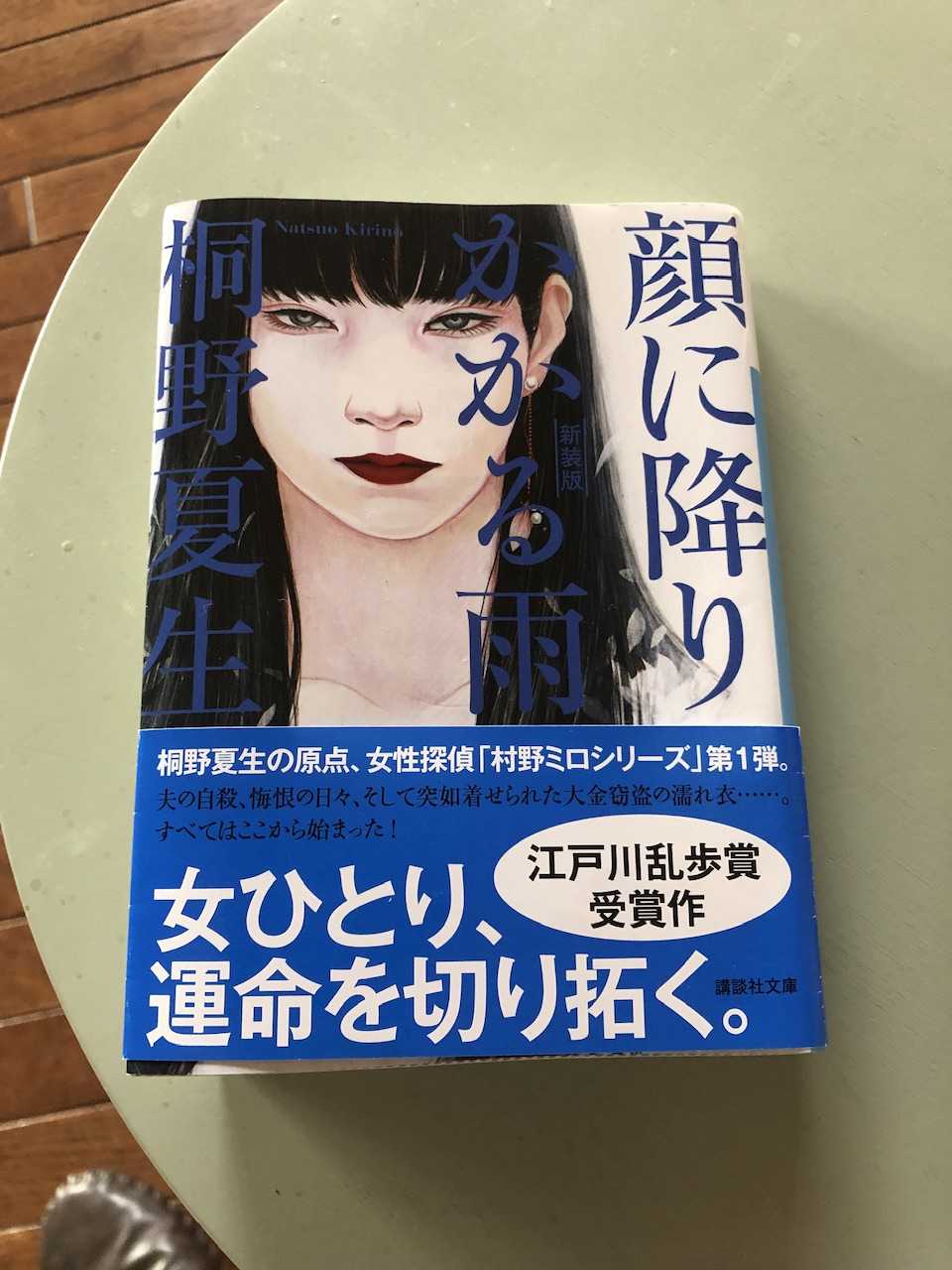2012年12月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
玉鬘 -7-
それを聞いた乳母の娘たちも泣き惑うて、「行方不明の母君の代わりに、せめて人並みの結婚をお世話申そうと思っていますのに、大夫監のような田舎者に嫁がせるなんて」と嘆いている事も知らず、自分はいかにも人望が高いと自負して文を書いて寄越しました。筆跡はさほどひどくはありません。かぐわしい香を焚きしめた唐の色紙に風流に書いたつもりなのでしょうが、どうも言葉使いに訛りがあるのです。大夫監は使者を通しただけではもどかしくなって、この家の二郎を味方にし自身が乗りこんできました。三十歳ほどの男で背が高く厳めしく肥って、むさ苦しくはないのですが田舎者と思って見るせいか厭らしく、がさつな振舞いを見るのも恐ろしいのです。顔の色つやがよく元気そうで、声はひどくしわがれて、ひどい訛りでしゃべりたてます。恋をしている人が夜の暗さにまぎれて忍んで行くからこそ『夜這い』と言うのですが、監の場合は風変わりな春の夕暮れの『呼ばい』というところでしょうか。人恋しい秋でもないのに、何とも不思議な出来事です。機嫌を損ねまじと乳母が出て参りました。すると監は、「故・少貮はたいそう情趣のたしなみが深くご立派でいらしたので、ぜひお目にかかりたいと思っておったが、それも叶わぬうちに亡くなってしまわれた。故・少貮の代わりといっては何だが、姫君に専心お仕え申し上げようと、恥を偲び己を励まして思い切って参上したのでござる。こちらにおわす女君は格別高貴な血筋と承ってござれば、田舎者の我には実に勿体ないが、我らの主君と思い申して、頭上にいただき崇めたてまつろうぞ。祖母殿が我との縁談に気が進まぬのは、よからぬ女どもとの関係をお聞き及びになってのことでござろう。しかし、そいつらと同じ待遇はいたしませぬ。后の位にも劣らぬ寵遇でお迎えしましょうぞ」と、調子に乗って言い続けます。
December 26, 2012
-
玉鬘 -6-
その中でも大夫監(たいふのげん)という、肥後の国一帯に多くの一族を持ち、声望が高く威勢のよい武士がありました。無骨な性分のなかにも多少好色な心があり、見目麗しい女を集めてみたいと思っていたのですが、この姫君の評判を聞きつけて、「どんな不具であろうとも我は気にしないので、ぜひ妻にもらいたい」と、たいそう熱心に求婚するのです。乳母はひどく不気味に思い、「どうしてそんな事ができましょう。尼になるといいますのに」と伝えたところ『出家されてはたいへん』と、肥後の国から肥前までわざわざ野山を越えてやってきたのでした。大夫監は乳母の3人の子息たちを呼び寄せて相談します。「私の思い通りになった暁には、勢力を分かち合おうぞ」それで二郎と三郎の二人は味方に付きました。「始めのうちこそ、この縁談は不似合いで可哀想に思い申したが、わが身の力とするには頼もしい男だ。これに悪く思われては、この辺りで安心して暮らせないではないか」「高貴な身分の御血筋とはいえ、親に見捨てられ世に埋もれていては何の甲斐もない。大夫監がこのように真剣にお思いくださる事こそ、今となっては姫君のご幸運というものだ」「こうなるべき宿世だからこそ、筑紫の田舎におわしたのだろう。他の地に逃げ隠れなさったとしても、何の良い事があろう」「大夫監が負けん気を起こして怒りだしてしまったら、大変なことになるぞ」と、乳母や太郎を脅します。すると太郎の豊後の介は、「大夫監との結婚は厄介だし、姫君にとっては勿体ない事だ。亡き父・少貮が遺言なさったことでもあるから、何とか工夫して、姫を都に上げたてまつろうではないか」と言います。
December 25, 2012
-
玉鬘 -5-
姫君のそうした噂を聞くにつけ、懸想文を送りたがる好色な田舎人たちがたいそう多いのでした。乳母は忌わしくも癪に障りますので、誰も相手にはしません。「姫の容姿は人並みではあるけれどひどくみっともない欠点がありますから、私が生きている限りは人前に出さず尼にして世話をしようと思います」と吹聴しますので、「故・少貮の孫娘は不具なのだそうだ。美人なのに惜しいものよ」と噂するのを聞くといまいましく、「何とかして都にお連れ申し、父内大臣に知らせたつまりつりたいものだわ。姫君が幼い時分にはたいそう可愛がっていらしたのだから、田舎育ちとはいえ、いくら何でもお見捨てにはなるまい」と言ってはため息をつき、仏や神に願を立てて上洛を念じていました。そのうち乳母の娘たちも子息たちも相応の相手ができて結婚し、筑紫に住みついてしまいました。乳母は心の内で早く上洛をと焦るのですが、反って都が遠ざかるように月日が過ぎていきます。姫君は分別がおつきになるに従って、田舎住いのわが身を辛くお思いになり、一年に三度の長精進をなさいます。二十歳ほどになりますと容姿がすっかり整い、田舎ではもったいないほどのうつくしい姫に成長なさいました。住んでいる所は肥前の国といいました。そのあたりで多少身分のある人は、まずこの少貮の孫娘のうつくしさを聞きつけて絶えずやって来るので、うるさいほどなのでした。
December 23, 2012
-
玉鬘 -4-
さて、太宰での五年の任期が終わり都に上ろうとするのですが、都は遠く格別な財力もありませんのでぐずぐずしていますうちに少貮は重い病に伏して、死を覚悟するほどになりました。姫君は十歳におなりでしたが、そのご容姿が忌々しいほど可愛らしくていらっしゃいますので、「母君ばかりか私までお見捨て申したならば、どんなに落ちぶれなさるであろう。むさ苦しい筑紫でお育ちになったことを勿体なく思い申し上げていたが、いつかは都にお連れ申して父君に知らせたてまつり、『宿縁によるご出世を見たいもの』と思っていた。都は広いから田舎育ちであることも知られまいと上洛を思い立ったのだが、それも叶わずこのまま死んでしまうことが残念でならぬ」と、不安がります。この少貮には三人の子息がいましたが、「ただこの姫君を都へお連れすることだけを考えなさい。死後の供養など考えるな」とだけ遺言しました。今まで少貮は、姫君が誰の御子であるかを家族にも知らせず、ただ『孫ではあるが、大切に養育するべき仔細のある子』とだけ言いなしていましたので、人にも見せず大切にお世話していたのです。ところが少貮が急死しましたので、乳母たちはしみじみ哀しく心細くなり、上洛の準備をしたのですが、故・少貮と仲の悪かった筑紫の国の人が大勢あったために、あれやこれやと妨害しましたので思いがけず年を過ごしてしまいました。その間に姫君は成長なさり、母君・夕顔に勝ってうつくしくおなりで、父・内大臣の気品さえ加わったからでしょうか、上品で可愛らしいのでした。性質もおっとりとして申し分なくおありなさるのです。
December 22, 2012
-
玉鬘 -3-
あちらこちらの珍しい風景を眺めながら、「夕顔の君は気がお若かったから、この景色をお見せしたらさぞお喜びでしたでしょうね」「されどもしもご存命でいらしたら、私たちは筑紫に下向することもありませんでしたわ」と、互いに言い合っては返す波が羨ましく、わが身は心細く、水夫どもが、「もの寂しくも遠くまで来たものだ」と唄う荒々しい声を聞きながら、姉妹差し向かいで泣くのでした。姉が、「舟人も たれを恋ふとか大島の うらがなしげに 声の聞こゆる(舟人も誰かを恋しく思って唄っているのでしょうか。うら哀しげな舟歌が聞こえます)」と歌えば、妹も、「来し方も 行くゑも知らぬ 沖に出でて あはれいづくに 君を恋ふらん(来し方行く末も分からぬ沖に漕ぎ出して参りましたが、恋しい夕顔の君はどこにいらっしゃるのでございましょう)都から遠い鄙の旅路で」と、思いのたけを言い合うのでした。鐘の岬を過ぎても「私たちは夕顔の君を忘れませぬ」という言葉を口癖のように言い続け、まして都からははるかに遠い大宰府に到着してからは、恋い泣きして、この姫君を大切に養育して暮らします。乳母は、たまに夢に夕顔の君を拝見する時があります。夢の中では同じ姿をした女がもう一人いらっしゃるのですが、覚めた後の気分が悪く病気になったりしましたので、『きっとお亡くなりになったのだわ』と思うようになるのもひどく悲しいのでした。
December 20, 2012
-
玉鬘 -2-
右近は、あの西の京に残してきた姫君の行方も知らず、夕顔の死をひたすら隠し、また『今さら詮ないことのために、我が名を世間に漏らすな』と源氏の君から堅く口止めされていましたので、ずっと遠慮し申し上げて安否さえ知らずにおりました。そうこうするうち、夕顔の御乳母の夫が太宰の少貮となりましたので、一緒に筑紫に下って行きました。あの姫君も四つになる年に、筑紫へ行ったのでした。乳母は姫君の母君の御行方を探して、よろずの神・仏に祈願し、昼夜泣きながらしかるべき所々を尋ねてみたのですが、ついに知る事ができませんでした。それで、『こうなったら仕方がない、姫君を母君の形見としてお育て申すことにしましょう。さりとて賤しい身分の私と一緒に、都から遠い筑紫にお連れ申すのは何とも不憫だわ。やはり姫君の父・内大臣にそれとなくお話し申そうかしら』と思うのですが、良い機会も見つかりません。「内大臣にお話しするとしても、母君の行方も分からないのですよ。もしお尋ねになったら、どうしましょう」「姫君は父上をご存知ないのですもの。そんな幼い人を内大臣にお預けしては、私たちだって気掛かりですわ」「我が子と知ったら、筑紫への同行をお許しにはなりませんわね」など、皆で話し合います。たいそう可愛らしく、今から気高く上品なご様子をしていらっしゃる姫君を、格別なしつらいもない舟に乗せて伏見から漕ぎ出でるのは、ひどく哀れに思えるのでした。姫君は幼心にも母君・夕顔を忘れず、折々「お母さまの御元へ行くの」とお聞きになるにつけ、乳母たちは涙の絶える時がなく、乳母の娘たちも夕顔を思いこがれるのですが、「舟路に涙は不吉」と一方では諫めるのでした。
December 19, 2012
-
玉鬘 -1-
たいそう年月が過ぎてしまったのですが、愛しい夕顔のことを露ほどもお忘れにならず、それぞれの女君たちのご様子をご覧になるにつけても『生きていたならば』と、しみじみ可哀想にも残念にも思い出していらっしゃいます。夕顔に仕えていた右近は、これといって優れたところのある女房ではありませんが、愛しい人の形見とご覧になって可愛がっていらして、今では古くからいた女房たちとすっかり馴れてしまいました。須磨に流浪なさった折には、女房たちを皆紫の御方にお預けになられましたので、右近もそちらでお仕えしています。気立てがよく控えめな者と紫の女君もお思いになるのですが、右近の心の中では、『もしも夕顔の君が生きていらしたなら、明石の御方に劣らぬご寵愛を受けていらした事でしょう。源氏の大殿は、さして深いご愛情もない女であっても除け者にはなさらず、お世話なさる寛大さがおありですもの。ましてご寵愛の深かった夕顔の君ですから、身分の高い紫の上と同列ではないとしても、この六条院にお移りの女君たちと親しくお付き合いなさったことでしょう』と思うと、ひどく悲しいのでした。
December 18, 2012
-
大宮と花散里@乙女の巻
乙女の巻は、何故かとても長く感じた。始めたのが10月11日だから、二カ月以上かかったことになる。内容は豊富で、朝顔の斎院の頑固な性格に始まり、夕霧と雲井の雁の恋物語、大宮と息子・内大臣とのやりとり、源氏の教育論、惟光の娘と夕霧とのちょっとした恋、継母・花散里に対する夕霧の客観的で鋭い観察眼、六条院での梅壺中宮と紫の上の春秋論などなど盛りだくさんで、どれもなかなか興味深いが、大宮と内大臣の親子喧嘩が世俗的で面白かった。乙女 -16- http://plaza.rakuten.co.jp/ototachibana/diary/201210280000/ 乙女 -17- http://plaza.rakuten.co.jp/ototachibana/diary/201211020000/ 乙女 -18- http://plaza.rakuten.co.jp/ototachibana/diary/201211040000/ 乙女 -19- http://plaza.rakuten.co.jp/ototachibana/diary/201211070000/ 乙女 -22- http://plaza.rakuten.co.jp/ototachibana/diary/201211100000/ 乙女 -23- http://plaza.rakuten.co.jp/ototachibana/diary/201211110000/ 大宮という女性は家族愛が強いだけでなく、人の気持ちを理解する情の深さと暖かさがあって好ましい。息子といえども会うときには身だしなみを調えるところには、高貴な身分の品位ある女性としてのたしなみを感じさせる。朝顔の巻では、「宮 対面し給ひて 御物語きこえ給ふ。 いと古めきたる御けはひ、しはぶきがちにおはす。このかみにおはすれど、故大殿の宮は あらまほしく、古りがたき御有様なるを、もてはなれ、声ふつゝかに、こちごちしくおぼえ給へるも、さるかたなり」(女五の宮が源氏の大臣に対面なさって、昔のおん物語をなさるのですが、まことに年老いたご様子で、咳こみがちでいらっしゃいます。源氏の大臣の姑・大宮は、女五の宮の姉宮なのですが、たいそう若々しい感じでいらっしゃるのに五の宮は姉・大宮に似たところがなく、声は太くお身体もごつごつした感じのおん方でいらっしゃいます)と、ガラガラ声で骨太の女五の宮と対比することで、若々しく女らしい大宮が浮き立つ。 また、興味深いのは夕霧の視点から花散里と比べた箇所だ。すこし長文になるが、原文を引用する。「かたちの まほならずもおはしけるかな。『かかる人をも、人は思ひ捨て給はざりけりな』と、わが、あながちに つらき人の御かたちを心にかけて『恋し』と思ふも あじきなしや、心ばへの かやうに やはらかならん人をこそ、あひ思はめ」と思ふ。又、「むかひて見るかひなからんも、いとほしげなり、かくて 年経にけれど、殿の 今に さやうなる御かたち・御心と見給うて、浜木綿ばかりのへだて、さしかくしつゝ なにくれと もてなしまぎらはし給ふめるも むべなりけり」と思ふ心のうちぞ、恥づかしかりける。 大宮のかたち 異におはしませど、まだ いと清らにおはしまし、こゝにもかしこにも「人は、かたちよきもの」とのみ目慣れ給へるを、もとよりすぐれざりける御かたちの、やゝさだ過ぎたる心地して、やせやせに 御髪ずくなゝるなどが、かく そしらはしきなりけり」乙女 -33- http://plaza.rakuten.co.jp/ototachibana/diary/201211290000 顔立ちの美醜に係わらず、女性が小奇麗に年を取るのは、案外難しい。化粧や服装で若くみせようとすると、反って醜悪になる。身だしなみ、しぐさ、立ち居振る舞いに「品位」を感じさせるこの大宮という女性は、きっと素敵なおばあさまだったに違いない。ところで、秋の好きな梅壺女御(六条御息所の娘で、斎宮女御と聞こえし御方)が、春の好きな紫の上に対してお歌を贈る場面がある。心から 春待つ園はわが宿の 紅葉を風の つてにだに見よ「春のお好きなあなたさまは、春の到来を心待ちにしていらっしゃるでしょうね。でも、私のお庭の、秋の風情のすばらしさをご覧くださいませ」という内容なのだが、そこには「春なんか、比べ物になりませんわよ」という気持ちが込められているので、源氏が「この紅葉の御消息、いとねたげなめり(この文面には小癪なものを感じますね)」と言うわけだ。紫の上もなかなかで「風に散る 紅葉は軽し」というお歌に「えならぬ作りごと(物)」を添えて返して、負けてはいない。この春秋論から、梅壺中宮は秋好中宮とも言われるようになったらしい。★他には惟光の娘が夕霧の恋文に「『をかし』と見けり」というところが、「素直でいいな」と感じた。不自然に思ったのは、夕霧と雲井の雁の恋に「源氏のコメントがないのは何故だろう」という事だろうか。
December 16, 2012
-
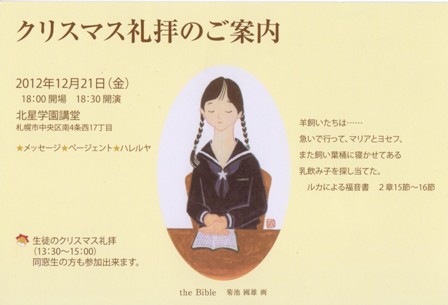
多忙の中にも。
先週だったか、母校からクリスマス礼拝の案内はがきが届いた。去年はほたほた降り続く湿った雪の中、同期の饗応夫人と張り切って出かけたのだが、今年の私は疲れが溜まって気乗りがしないのだ。礼拝は毎年同じ内容、お決まりの聖書劇、歌う讃美歌も変わり映えがしないし、何よりお説教がつまらない。夏に避暑に来た東京在住の元クラスメートに、「最近の教会のお説教って、つまらなくない?」と、訊いてみた。彼女は英国聖公会の信者なのだが、「そうなのよ。インパクトがないわよね」ランチのお皿に目を落としたまま、あっさり肯定されてしまった。饗応夫人は若いころにプロテスタント系の教会で洗礼を受けているのだが、「今年のクリスマス礼拝はパスしよう」ということになった。アメリカ在住の長兄と同居していた母上が帰国して、彼女のマンションで同居することになったので、何かと忙しいらしい。避暑夫人には女の子の孫が生まれたので、羨ましくも婆バカに忙しい。我が家も「すがもり」以後、爆弾低気圧による家屋被害の処置、母のごみ処理など一年を通じて忙しかった。ありがたいことに店においてもリピートしてくださるお客様が増えて、サポートのお手紙に追われるようになった。誰にも知らせず、広報活動もせず、ただ営業時間だけを守ってひっそりと店を開いているだけなのだが相談客のお一人お一人を大切にして接客していくなら、なんとかなるものだと、4年経ってしみじみ感じる。私の力など微々たるものではあるけれど、頼りにしてくださるお客様がいらして、何とか治してさしあげることができるならこれほど嬉しい事はない。お客様が元気になることが、私の喜びになり力になる。今年は忙しかったが、どんなに忙しくても、方向性さえ見失っていなければ、必ず良い結果を手に入れることができる。そう実感できる一年だった。
December 15, 2012
-
乙女 -43-
九月になると紅葉があちらこちらで色づいて、中宮の御前のお庭はえも言われぬうつくしさです。風が吹いたある夕暮れに、中宮は御箱の蓋に色々の花紅葉を取り交ぜて紫の女君に差し上げました。大柄な女童(めのわらわ)が濃紫の袙に紫苑の織物を重ね、たいそう着馴れた赤朽ち葉色の羅の汗衫を着て、廊や渡殿の反り橋を渡ってこちらにやって参ります。このような場合はきちんとしたお作法で、女房を通すべきなのですが、中宮はかわいらしい女童をお遣わしになりました。この女童は高貴な御方にお仕えし馴れていますので、身のもてなしも立ち居振る舞いも他の童女にはない好ましさがあって可愛らしいのです。中宮からの御文には、「心から 春待つ園はわが宿の 紅葉を風の つてにだに見よ(そちらのお庭では、春の到来を心待ちにしていらっしゃることでございましょう。せめて私の庭の紅葉を、風のたよりになりとご覧くださいませ)」とあります。若い女房たちがお遣いの女童をもてなす様子が面白いのです。紫の上からのお返事は、この紅葉の箱の蓋に苔を敷き、岩などを配置した趣向を作ります。その岩の根元に五葉の松を植え、枝に御文を結びました。「風に散る 紅葉はかろし春の色を 岩根の松に かけてこそ見め(風に散る紅葉は軽くて物足りのうございますわ。春の色を、このどっしりとした岩に生える松の緑に託してこそご覧いただきとうございます)」 この岩根の松もよく見ると、実に上手にできた作り物なのでした。このように、咄嗟に思いついた事でも趣味の良さを伺わせる才覚を、中宮は興味深くご覧になります。御前の女房たちも、褒め合いました。源氏の大殿は、「この紅葉の御文は、いかにも癪に障りますね。でも、あなたは春になって花ざかりの折に、このお返事をなさいませ。秋に紅葉を悪く言っては立田姫の思惑もおありでしょうから、今は一歩退いて、春が来た時に花盛りを盾にしてお返事なされば、強い言葉も生きることでしょう」と申し上げます。たいそう若々しくいつまでもうつくしいご様子は、どこから見てもすばらしいのですが、その上理想的なお邸で、女君達は互いに御文をお交わしになります。 大井の明石の御方は、女君達のお住いが定まったのを見て、『私のように人数にも入らぬ者は、こっそり移りましょう』とお思いになって、神無月に六条院にお移りになりました。源氏の大殿は、明石の姫君の将来のおん為をお思いになって、移転の儀式を他の夫人たちと同じようになさり、たいそう物々しく丁重にお扱いなさるのでした。
December 14, 2012
-
乙女 -42-
女君達は、彼岸のころにお移りになります。御方々が一度に移るようにとお決めになっていらしたのですが、それでは大騒ぎになろうという事で、中宮は少し延期なさいます。例の、おっとりと穏やかで気どりのない花散里の君は、その夜紫の上に付き添ってお移りになります。春のお庭の様子はこの季節にはぴったりしないのですが、うつくしさは際立っています。御車が十五、前駆の者は四位や五位が多く、六位の殿上人はしかるべき者だけをお選びになってお供させます。それほど多いということはありません。世間の非難もあろうかと簡素になさったので、何事も仰々しく厳めしい事はないのです。 花散里のご様子も紫の上に劣ることなく、侍従の君が付き添ってお世話していらっしゃいますので『ほんに、御子息として大切にお世話なさるからであろう』と思われました。何よりも行き届いていてみごとなのは、お仕えする女房たちの細かな部屋割でした。 五・六日過ぎて、中宮が宮中から六条院に退出なさいます。この御儀式がまた簡素とはいうものの、たいそうなご威勢でいらっしゃいます。すぐれたご幸運は申すまでもありませんが、お人柄が奥ゆかしく重々しくいらっしゃいますので、世間からの信頼も際だっていらっしゃるのでした。 六条院の町々の仕切りには塀を設け廊などを造り、互いに行き来できるようにして親しく打ち解け、風流な間柄になるよう造られていました。
December 13, 2012
-
乙女 -41-
八月(はづき)には六条院が完成しましたので、そちらにお移りになります。源氏の大殿は、『未申(南西)の町は、梅壺中宮(斎宮女御)の元のお邸であるから、そのままお住みなさるだろう。辰巳(東南)は我が住いとするべき町。丑寅(北東)は、東の院に住んでいらっしゃる花散里の御方、戌亥(西北)の町は明石の御方に』とお決めになりました。もとからあった池や山で不都合な所は取り崩し、鑓水や池の趣き、築山の趣向を変えて、それぞれの町に住まわれる女君たちのご希望に沿う趣向にお造らせになりました。南東は山を高く、春の花の木を数限りなく植え、池の趣きも奥ゆかしく、御前に近い前栽には五葉の松、紅梅、桜、藤、山吹、岩躑躅(いわつつじ)といった春の観賞用の木草の中に秋の前栽を目立たないように混ぜて植えてありました。梅壺中宮の御殿はもとからあった山に色の濃い紅葉を植え、澄んだ泉の水を遠くまで流しやり、その途中で水音を立てるように岩を立て、瀧を落として、広々とした秋の野の風情です。そこには今の季節にぴったりの草花が咲き乱れていて、嵯峨の大井あたりの秋の野山も見劣りするようなお庭なのです。北の東の花散里のお住いには涼しげな泉があり、夏には木陰を作るように木々を繁らせてあります。御前に近い前栽には下風が涼しいようにと呉竹を植え、木高い森のように植えた木々が面白く、山里のように周囲には卯の花の垣根を特別に回して、昔を偲ばれる花橘、撫子、薔薇、りんどうなどを植えて、春秋の木草をその中に混ぜてありました。東面には馬場殿を造り、土塀を構えてあります。そこは五月の御遊び所ですので、池のほとりには菖蒲を植えて、向かいの御厩には立派な上馬たちを揃えさせるのでした。明石の上の西の町は、北面と築地で隔てた御蔵町です。隔ての垣根にはから竹を植え、松の木が繁り、雪を観賞するのに好都合なのでした。初冬の朝霜が見られるようにと菊の籬に、我が物顔に紅葉する柞原や、名も知らぬ深山木などを移し植えてありました。
December 12, 2012
-
乙女 -40-
年が明けてからは去年にも増して御賀の用意や精進落とし、その後行われる饗宴の折の舞い人や楽人の選定などで多忙を極めていらっしゃいます。対の上は、経巻や仏像の飾り付け、法事の日の衣装や僧への禄などをお急がせになります。東の院の花散里の君にも分担して準備なさる事がありました。紫の女君と花散里の君は、この祝賀の準備を通してたいそう優雅に御文をお交わしになる仲でいらっしゃいます。この御賀は世の中の評判にもなり、お支度で大騒ぎですので、式部卿の宮もこれを聞し召して、『源氏の大殿というお人は、これまで世間でも情の深いことで知られてはいるが、私に対しては憎らしいほど薄情で折に触れて冷たい仕打をし、こちらの宮人にも御心遣いがないので、私にとっては憂わしいことばかりだったが、それはきっと根に持たれるような恨めしい事があったからであろう』と、おいたわしくも辛くもお思いになるのです。源氏の大殿と関係をお持ちになる大勢の女君たちの中でも、式部卿の宮の御娘・紫の女君へのご寵愛が格別深く、たいそう奥ゆかしくすばらしい方として大事にお世話されていらっしゃる御宿縁を、たとえ父宮までそのお蔭が及ばないとしても、名誉な事とお思いで、『そのうえこうも世間に評判をとどろかして御賀をご準備くださるのは、何とも思いがけぬ老後の光栄であることよ』と喜んでいらっしゃるのですが、宮の北の方はちっとも気が晴れず、反って不愉快に思っていらっしゃるのでした。それもそのはず、御娘が女御として入内なさる時に、源氏の大殿からは何の御心遣いもありませんでしたので、ますます恨めしくお思いなのでございましょう。
December 8, 2012
-
乙女 -39-
朧月夜の尚侍の君は、朱雀院と同じ御所に住んでいらっしゃいました。静かに往時をお思い出しになってみますと、感慨深いことが多いのでした。今でも然るべき折にはさりげなく、源氏の大殿(おおいとの)に御文を差し上げていらっしゃるようなのです。大后は、帝に奏上なさる折に、下賜される年官・年爵など何かにつけて御心に叶わぬ時には「長生きしたばかりに、このような情けない目に会うことよ」と、朱雀院の御代を懐かしんでは不機嫌になるのでした。お歳を召すごとに意地悪さも一層ひどくなりますので、朱雀院も耐え難く思召すほどでした。ところで大学の君は、その日の詩文を見事にお作りになりまして、進士(しんじ)におなりなされました。帝が、長年学問を積んだ賢者たちを選ばせ給うたところ、及第した人はこの若君を加えてわずかに三人しかいなかったのです。秋の司召には従五位下に叙せられて、侍従におなりです。かの姫君との恋を忘れた事はないのですが、姫君の父・内大臣が厳しく監視していらっしゃいますので、無理な工夫をしてまでもお逢いすることはないのです。ただ御文だけは機会をとらえてお交わしになるという、どちらにとってもお気の毒な間柄なのでした。源氏の大殿は、『どのみち静かな住いを造るなら、敷地が広く風情があり、逢うにも困難な大井の人なども一所に住めるような邸にしたいものだ』とお考えになり、六条京極の梅壺中宮(斎宮の女御)の古邸あたり四町を占めて邸宅を造営なさいます。紫の女君の父宮・式部卿の宮は、年が明けますと五十歳におなりですので、対の上は今からその祝賀の準備をしていらっしゃいます。源氏の大殿も『それは見過ごせぬ。できる事なら御祝賀も、新築した邸でしたいものだ』とお思いになり、工事を急がせます。
December 7, 2012
-
乙女 -38-
夜はすっかり更けてしまったのですが、朱雀院の母・大后の住んでいらっしゃる御殿をご訪問なさらないのも薄情ですので、帝は帰り路にお立ちよりあそばされます。源氏の大殿も伺候なさいます。大后はお喜びになって、ご対面なさいます。御簾越しに、たいそうお歳を召された気配が感じられるにつけても『このように長寿でいらっしゃる方もおいでなのに』と、藤壺の宮の早世を残念にお思いになります。「今では私もこのように老齢となりまして、昔の事をすっかり忘れてしまいましたが、こうして勿体なくもお越しいただき、桐壺院の御世を思い出すことができました」と、泣き給うのです。帝は、「頼りとなるべき父・桐壺院や母・藤壺の宮に先立たれましてからは、春の到来にも気付かぬ思いで過ごして参りましたが、今日はお目にかかってそれが慰められたように存じます。これからも参上いたしましょう」と申し上げます。源氏の大殿も、「いずれ改めてお伺いいたしましょう」と御挨拶申し上げます。大勢のお供を引き連れて慌ただしくお帰りになる様子に、大后はやはりお胸がどきどきなさって、『昔の事をどうお思いでいらっしゃるかしら。天下をお治めになるご宿縁というものは、消されるものではなかったのだわ』と、昔のお振舞いを後悔なさるのでした。
December 6, 2012
-
乙女 -37-
春鶯囀(しゅんおうでん)を舞うほどに昔桐壺帝の御前での花の宴が思い出され、朱雀院も、「あの時ほどの宴が、また見られるであろうか」と仰せになるにつけても、桐壺帝がご在世でいらしたころの事がしみじみ思い出されるのです。舞いが終わるころに、源氏の大殿が院にお盃を差し上げます。「鶯の さへづる声はむかしにて むつれし花の かげぞかはれる(鶯の囀る声は、故父・桐壺院ご在世の折の花の宴と変わりはございませんが、睦み交わした花の陰は、時と共にすっかり変わってしまいました)」 院の上も、「九重を かすみ隔つるすみかにも 春とつげくる 鶯の声(内裏から遠く離れた霞みの洞にも、春を告げる春鶯囀の舞いの声が聞こえてくるのは、嬉しいことです)」とお詠みあそばされます。 昔、帥の宮と申し上げた、今は兵部卿の宮とおなりの御方が今上に御盃を差し上げて、「いにしへを 吹き伝へたる笛竹に さへづる鳥の 音さへ変はらぬ(いにしえの笛の音をそのまま伝える春鶯囀。その竹笛の音に合わせて囀る鶯の声までも、昔と少しも変わらないではございませんか)」と、うまくとりなしてお謡いあそばされた機転が、ことさら見事なのです。帝はお盃をお取りあそばして、「鶯の 昔を恋ひてさへづるは 木伝ふ花の 色やあせたる(昔の舞いを恋しく思い出されるのは、次々変わる世の中が、昔より色あせているからであろうか)」と仰せになるご様子は、たいそう奥ゆかしくご立派でいらっしゃいます。 これはお身内だけの酒宴で、大勢の方々に盃が渡らなかったためでございましょうか、これ以上のお歌は、書きおとしてしまったようでございます。 奏楽所が遠く楽の調べがはっきり聞こえませんので、帝は御前に楽器をお召しになります。兵部卿の宮は琵琶、内大臣は和琴、筝の御琴は朱雀院の御前に、七弦の琴は源氏の大殿が賜ります。それぞれたいそうな名手でいらっしゃいますので、手技を尽して演奏なさる音色はたとえようもありません。唱歌する殿上人が大勢伺候して、催馬楽の「あな尊」、次に「桜人」を謡います。月がおぼろに差し出でて風情のある頃に、お池の中島のあたりにあちらこちら篝火を灯して大御(おおみ)遊びは終わりました。
December 4, 2012
-

三輪漬け
大根の薄切りに少量の塩をもみこんで水出しする。 水気を切った大根と、ゆずの薄切りを2:1程の割合で挟んでポリ袋に入れ、酢と醤油と砂糖を2:1:1で混合した調味液と鷹の爪を加えて数時間冷蔵庫で漬けこむだけ。「三輪(さんわ)漬け」というそうだ。写真では丸のままだが、半月切りにして供する。大根と一緒にゆずを食べてしまってもおいしい(ちょっとえぐみがあるけれど)。ところでこの「生しょうゆ」。ボトルを強く押した後「ぴー」と、甲高い笛のような音がする。少量を出す分には音がしないのだが、悲鳴のようでちょっとびっくり。(器はDANSK)
December 3, 2012
-
乙女 -36-
二月の二十日過ぎには、朱雀院への行幸があります。花の盛りにはまだ遠いのですが、三月は故・藤壺の宮の御忌月です。早くに開いた桜の花の色もたいそう風流ですので、朱雀院でも特別に美しく飾り立て、行幸に奉仕なさる上達部や親王たちを始めとして、お供の人々の衣装の用意をなさいます。供奉の人々はみな青色の袍に桜襲をお召しになります。帝は、赤色の御衣をたてまつります。帝からのお召しがあって、源氏の大殿が御前に参上なさいます。源氏の大殿は帝と同じ赤色の御衣をお召しでいらっしゃいますので、ますます同じように輝いて見紛うほどです。今日は供奉する人々の装束も用意も、すべていつもとは違うのです。朱雀院もたいそうご立派にお歳を重ねられて、ご様子もお気遣いも以前より優雅さが勝るようでいらっしゃいます。今日は特に文人をお招きなさらず、詩才のある学生を十人だけお召しになりました。式部省で行う文章生の試験になずらえて、帝からお題を賜ります。大殿のご長男の試験を賜るためなのでしょう。臆病な学生たちは頭の中が真っ白になって物を考えることもできず、各々が別々の舟に乗って池に離れ出て、途方に暮れているように見えます。次第に日が沈み、楽人を乗せた舟が二艘お池の中を漕ぎ回って、調子を調えながら短い曲を演奏しますと、山風の響きがおもしろく吹き合わせますので、若君は、『こんなに苦しい学問の道に励まなくても、人と交わり、音楽の遊びもできるというのに』と、世の中を恨めしくお思いになるのでした。
December 2, 2012
-
乙女 -35-
「母に死別した者は、その身分に応じて誰もが不憫なものですけれど、人それぞれの宿世によって一人前に出世するならば、ばかにする人などいないのですよ。何事もくよくよ思い詰めないようになさいまし。故・左大臣も、せめてもう暫くでもこの世にご存命でいらしたならと存じます。この上ない保護者としては、あなたの父上も同じようにお頼み申しておりますけれど、心に叶わぬ事も多いと感じております。内大臣のご性質もご立派でいらっしゃると世間では褒めてくださるけれど、昔とはお人柄もすっかり変わってしまいました。私には長寿も恨めしく思われますよ。あなたのように将来のある人までが、世の中を悲観して塞ぎこんでいらしゃるとは、何とも恨めしい世の中ですこと」と、泣いていらっしゃいます。★正月元日。太政大臣でいらっしゃる源氏の君は拝賀に参内なさらず、自邸の二条院でのんびり過ごしていらっしゃいます。藤原良房の大臣と申しあげた方の古例に倣って七日は白馬を引くというふうに、節会の日々は内裏での儀式を二条院でも同じように執り行い、昔よりも荘厳で立派になさるのでした。
December 1, 2012
全19件 (19件中 1-19件目)
1