2008年08月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
ドイツ・フライブルクの合理性
今日、NHKの番組で、ドイツ・フライブルクの交通事情についてのリポートをやっていたのを見ましたが、これがまたとても感心する内容でありまして。 かつてドイツもクルマから出る排気ガスで大気汚染が進み、酸性雨で「黒い森」が枯れるなどの環境被害が深刻になった時期がありましたが、あれをきっかけに国家・自治体レベルでの取り組みが進んだんですって。 で、フライブルクではとにかく市の中心部から極力クルマを排除することを決めた、と。 その代わり、トラム(路面電車)を導入し、電車との連携も強めて、脱クルマ社会の実現へ向けて舵を切ったわけ。フライブルク郊外のあちこちに無料の大駐車場を作り、市内に入りたい人はここでクルマからトラムに乗り換えるようにしたんですな。いわゆる「パーク&ライド」方式の徹底です。 で、トラムを含めた公共交通機関のパスも格安なんです。一カ月間、トラムと電車が乗り放題という「レギオカルテ」なる定期券の値段がわずか4000円ちょい。しかもこのパスは本人だけでなく、他人に貸してもいいんですって! また週末はこのパスが1枚あれば、家族4人までトラム&電車が乗り放題。ですから、標準的なサラリーマン家庭にとって、週末の家族での移動は実質無料ということになります。 もちろん、こんな料金体系ではトラムも電車も赤字なわけですが、これは議会が決めたことだから、公共交通機関の赤字分は税金で補填する。これでどこからも文句なし。 で、こうやって市内からクルマを排除した結果、エネルギー効率が3倍から4倍に上がり、市内の空気はきれいになり、騒音もなくなり、レストランのテラス席も人気復活! 市民はみな日光の下、昼食を楽しむことが出来るようになったのでありました。 またトラムは1時間1万円の格安料金で貸し切りにすることができるので、学生たちなどはこれを借り切ってトラム・パーティーをやったりして、街のトラム化を存分に楽しんでいる様子。「不便を忍ぶ」という姿勢ではなく、こういうご時世を楽しむ、という感じです。 これだけではありません。郊外の住宅もどんどん進化していて、ある地域の住民は、住宅街から少し離れたところに駐車場を作り、住宅地の中までクルマが入ってこられないようにしたのだとか。こうすることで、多少不便にはなりますが、その代わり、住宅地内では子供が交通事故の心配をすることなく遊べるようになった。もちろん住宅地全体での高気密住宅化の推進や、太陽光発電の推進にも取り組み、省エネも進んでいるのだそうです。 ・・・とまあ、そんなリポートだったのですが、どうです、素晴らしいではないですか! 何が素晴らしいって、そのドイツらしい合理性が素晴らしいよね。「問題は何か」を特定し(この場合、クルマが多過ぎるということ)、「それを解決するためにはどうしたらいいか」という解決策を打ち出し(この場合、トラムの導入とパーク&ライドの徹底)、「その解決策を押し進めるためにはどうしたらいいか」を考え(この場合、格安パスの導入や無料大駐車場の設置)、「解決策を押し進めた結果のマイナス面をどうやって解決するか」を考える(この場合、政府による赤字補填)という、この一連の合理性。うーん、美しいではないの! そして、何より素晴らしいのは、そうやって公式に決めたことを、住民が満足して実行する、ってことだよね~。ま、すべてが合理的に進められているから、どこからも不満が出ないのでしょうが。 このフライブルクの取り組みを見ていると、これこそ理性によって問題を解決していく人間らしい行き方、という感じがしますなあ・・・。 それに引き換え我が日本はどうなんですか・・・。政治家たちが何をどう決めているのかも分からないし、そうやってうやむやに決めたことが、果たして本当に効果があるのかも分からないし、分からないから国民も不満だらけだし、決めたことも実行しないし。でもなんとなく、だらだら動いている。そんな感じですな。これでよくどうにかなっているもんだ。 ま、ドイツにはドイツの問題があるのだろうとは思いますが、傍目から見て、あの気持ちのいい合理性には、感嘆と憧憬の念を抱かずにはおられないワタクシなのでありました。日本にも合理を! 日本人にも理性を!
August 31, 2008
コメント(0)
-
「どまつり」とは何の謂いぞ?
名古屋ではこの週末、「ど真ん中祭り」というのを開催しているのですが、全国的にはどの程度の知名度なんでしょうか。 ま、名古屋人というのは、自分たちの住むところが日本の真ん中だ、と堅く信じているところがあって、割とこういうネーミングが好きなんですな。 それはまあ、好き好きですからいいのですが、しかし、ワタクシがどうしても我慢がならないのは、名古屋人が「ど真ん中祭り」のことを省略して「どまつり」と称することです。 「どまつり」・・・。うーん、嫌な言い方だなあ! 「どまつり」。音数的に「血祭り」に似たところがあるし、なによりもこの「ど」という鈍臭い音を頭に置くその感性が分からん! 大体、名古屋人ってのは「ど」の音が好きなんだよなー。「どえりゃー」(→これも省略して「でら」になる)とかね。だから「ドラゴンズ」も好きなんだろうな。 ま、それはともかく、このお祭りのハイライトは、クルマの通行を止めた繁華街の目抜き通りをステージに、各地域から集まってきたダンス・チームがそれぞれ趣向を凝らした創作ダンスを披露する、というところにあるのですが、これがまたえらく盛んなもので、それこそ小学生レベルの子供から大学生、あるいはそれよりもう少し上くらい人たちまで、顔を輝かせて一心不乱に踊っている。参加チームの数も半端ではないですから、この祭りを楽しみにしている若い人たちの数というのは相当多いのでしょう。 それにしても、この種の新しいタイプのお祭りというのは、名古屋だけではなく、北海道の「よさこいソーラン祭り」など、全国各地に出現しておりますが、一体、この現象は何なのか。どのように説明すればいいのか。 一時、地方自治体の盆踊り大会などが廃れてしまって、存続すら危ういというようなことを耳にすることが多かったですけど、その一方で、こういう新しいタイプのお祭りというのが出てくると、それにはものすごい数の参加者があるというのですから、日本人の祭りに対するエネルギーが一時地下に潜ったまま密かに新しい捌け口を求めていて、その捌け口を「どまつり」的な新しい祭りが提供した、ということなんでしょうかね。 そう考えると、名古屋の「どまつり」というのも、時代にあった新しいお祭りの形ということで、それはそれで結構なものなのかも知れません。おそらく、伝統あるお祭りだって、その発端はこういうものだったのでしょうし。 が・・・。 観光化する前の「おわら風の盆」とか、郡上八幡の「郡上おどり」などと違って、「どまつり」というのは、地元の文化とはまったく無関係な若い人たちの祭典でありまして、そういうものにつきものの「わざとらしさ」みたいなものが感じられるせいか、何だかどうも、ワタクシには素直に見ていられないところがあります。それは日本テレビの「24時間テレビ」的なこれ見よがしの善意の祭典を見せられた時に感ずる思いに通じるような気がする。そういう感覚が、私だけのものなのかどうかは分かりませんが。 いずれにせよ、「どまつり」に興じる若い人たちの生き生きとした顔つきを見るたびに、これが自分と同じ同胞なのだろうか、だとしたらこの感覚のギャップというのはどこから来るのだろうか、という不思議な違和感を感じて仕方がないワタクシなのでありました、とさ。
August 30, 2008
コメント(6)
-
テナー・サックスの不魅力
昨夕、人待ちのためジャズ喫茶『グッドベイト』で時間潰しをしていたのですが、常連さんもいないようだったので、トミー・フラナガンの『エクリプソ』をリクエスト。大音量で聞くトミーの渋いピアノはステキでしたが、表題曲に関しては『オーバーシーズ』に収録されているものの方がカッコ良かったなあ。 で、その後、他のお客さんのリクエストなのか、テナー・サックスが中心となる楽曲(誰の演奏かは不明)が流れたのですが、それをじっと聴いていて思ったことが一つ。 私はテナー・サックスを中心としたジャズが好きではない。 で、なぜそうなのか考えたのですが、結局、サックスという楽器全般の特徴として、吹き手の感情とか、演奏意図があまりにも素直に、ストレートに表現されてしまうというところが、私にとっては面白くないのではないかと。 つまり、吹き手の「おーし、ここで一つ、こぶしを利かせてやるぞ~」とか「このむせび泣きを聴け!」とか「情感たっぷりに吹いているだろう、どうだ? 」みたいなのが、あまりにもミエミエなので、何だか白けるんですよね。もちろん、私にとっては、という意味ですが。 対するに、例えばピアノの場合、弾き手がいかに思い入れを込めても、その思い入れが腕を通り、指先を通り、鍵盤を通り、ハンマーを通り、弦に到達するまでに幾分薄められ、象徴化され、透明化されていって、いい具合に中性化される感じがする。その間に挟まる部分が、弾き手の直接的な感情をもっと普遍的な感情へと昇華するというのかな・・・。 管楽器で言えば、サックスよりトランペットの方が遥かに好きなのも、同じ理由じゃないでしょうか。トランペットの方が、サックスより、音に思い入れを込めるのが難しいですもんね。 要するに、あまりこれ見よがしな情感を突きつけられると、何だか低級な感じがして、うんざりしてしまうというのが私自身の感性なのでしょう。それは、音楽に対する嗜好だけでなく、その他のものにも当てはまりそうな気がする。 かくして私はまた一つ、自分が何者であるかを知ったのでした。『どろろ』の百鬼丸じゃないですけど、人間というのは、自分が何者であるかを知らずに生まれて来るので、その欠けた知識を経験によって一つずつ取り戻すしかないのでありまーす。 さて、それはともかく、私が誰を待っていたかと申しますと、昔の卒業生にして釈迦楽ゼミ四天王の一人、K君だったのでした。東京に勤務するK君が出張で名古屋に来るというので、久し振りに飯でも食おうというわけ。 で、私の家内も含め、三人でお気に入りのトルコ料理店『オリエンタルの青い月』で夕食を共にしたのですが、何年かぶりに会うK君は以前とまったく変わってませんでした。おかげでこちらまで若返ります。K君が私のゼミ生だった当時は、私も彼らの先頭に立って無茶な遊びをしてましたからね~。 が、そうは言っても立派な社会人となったK君の話を聞いていると、おお、ちゃんと社会人してるな~、と思われるところもあって、頼もしい限り。そりゃ30代も後半ですから、仕事も油が乗り始めたというところでしょう。 その一方、ファミリーマンでもあるK君。場所を移してお茶でも飲もうという時、東京のお宅からK君の4歳の長男君が出張先のお父さんに「お休みなさい」の電話をかけてきたのですが、「まだ起きてたの?」などと応答をしているK君の声がまるで優しいお父さんそのもので、微笑ましかったですなあ。 ということで、昨夜は久々に若い友人に会って、楽しいひと時を過ごすことができたワタクシだったのでありました。やっぱ、たまに顔を出してくれる卒業生ってのは可愛いね!
August 29, 2008
コメント(2)
-
高校生相手に講義する
今日は附属高校の学生100人を相手に、「アメリカ映画論」とやらを講義してきました。 これから少子化の時代ですからね。附属高校にもサービスして、「うちの大学に来てね~」的な手を打っておかないとまずいのでしょうな。 それにしても、普段50分授業の形態に慣れている高校生たちに、いきなり90分の授業を聞かせるわけですから、こちらも苦労します。連中が飽きないように、適宜、実際のアメリカ映画の映像を見せたりしながら、やさしーく、わかりやすーく講義しなくてはならない。そういうプレッシャーがあるものですから、結構、気を使いましたわ。準備も入念にしたし。 でもおかげ様で、それも無事終了。高校生たちも案外いい子にしていてくれて、集中力を途切らすことなく、最後までついてきてくれました。 ま、ワタクシが講義するんですからね、面白いのは当然か・・・。 でもね、ワタクシの講義を基準に考えちゃダメよ。他の先生方の講義が面白いとは限りませんからね~。あんまり期待しないでね! それはそうと、少子化に関連して、今日はすごい話を聞きました。同僚の知人が愛知県のとある私立大学に勤めているのですが、その大学、このところ2年連続で大幅な募集人員割れをしているらしいんです。大幅というのは、入学学生数が募集学生数の半分に満たない、という意味です。 そうなりますと、これは文部科学省の方針で、お取り潰しの方向に向かわざるを得ないんですって。その大学は伝統のある短大を持っておりますので、4大を取り潰して短大に合併する、みたいな形にするらしい。 じゃ、4大に所属していた先生方はどうなるか・・・。おそらくは現在すでに入学している学生たちの卒業年度を待って、大半が解雇でしょう。ひゃー! もはや4大の先生方の影は、半分くらい薄くなっているらしいですけど、ほとんど怪談の世界ですよね! 「ひとーり、ふたーり、さんにーん、・・・・学生が足りなーい」みたいな・・・。 ま、その知人の先生は英語の先生なので、教養英語担当として、多分、短大の方に拾われる可能性が高いですが、それにしてもヒヤヒヤらしいです。家のローンもあることだし、急に解雇されても、ねえ・・・。 いや~。現在、日本にある大学の半分近くが定員割れしているんですから、これからますます少子化が進むにつれ、この種の「大学お取り潰し」が増えるんだろうな。 また、そうなってくると、お取り潰しになった大学に通う学生も悲惨ですよ~。ただでさえ定員割れしてるのに、新入生が入ってこなくなるんですから、そいつらが4年生になるころには、ほとんど僻地の分校状態でしょう。広いキャンパス、大きな校舎に、学生はあちらに一人、こちらに一人、というようなことになりそうです。ひゃー、寂しい! でまた、文部科学省も責任とらないからね。あそこは大学設置の許可はポンポン出すけど、その後は「野となれ山となれ」の放任主義ですから。「教育は国家百年の計」だなんて、どなたかが言ってましたけど、嘘ばっかりですわ。 ま、そういうことを考えると、まだ附属高校サービスくらいで何とかなっているうちの大学なんて、マシな方なのかも知れません。 今日ワタクシの講義を聞いた高校生のみなさーん、来年はちゃんとうちの大学を受験してくださいね~!
August 28, 2008
コメント(2)
-
大丈夫なのか、日本の大学図書館?!
学会の資料室を引き受けておりますと、学会が発行している学会誌を日本中の大学に送付する、などという仕事も含まれます。国内外合わせると、それこそ300以上の大学に送ることになり、これが結構な手間だったりする。 ところが・・・。 最近、国内の大学から私のところに妙な通知が来ることが多くなりまして。曰く、「図書館のスペースが足りなくなってきたので、これ以上学会誌を送ってこないで下さい。悪しからず」。 実は今日も一通、そういうのがあったんですけどね。東京にある割と有名な私立、T大学ですよ。武士の情けで実名は明かしませんが。 しっかし、本当にもう送らなくていいのかよ?! この学会誌、この分野では最大級・最重要の論文誌だぜ! それを継続しなくて本当にいいの? といういわけで、上のような趣旨の通知を様々な大学図書館から受け取る度にビックリするわけですけど、実を言いますと、本当の意味ではビックリはしていません。なぜなら、日本の大学図書館の現状というものをよく知っているからです。 実際、日本のどの大学もそうだと思いますが、大学図書館というのは、どこも常に収容能力の限界との戦いです。「うちは書架スペースにまだまだ余裕があるよ~!」などと言っている大学図書館の噂なんて聞いたこともない。常にいっぱい、いっぱいなんですな。 ですから困るのは定年などで退職する教授の研究室図書です。これは本来、図書館に所属すべき本を、その先生が現役のうちはその先生の研究室に貸し出している、というのが建前ですから、その先生が大学をお辞めになるときは、当然、それらの本はすべて図書館に返さなくてはならない。 しかし、一人の先生の研究室には何百冊、いやいや何千冊という本がありますから、定年退職の先生が年に何人もいらっしゃる場合、それだけで何万冊もの本が一気に図書館に運ばれることになってしまいます。そしてその膨大な本を図書館員の方が分類し、仕分けし、図書館の書架に配架しなければならないのですが、そんなことをやっている暇もスペースもない。 ということで、そういう本は、図書館の地下へ通じる階段の脇に山積みにされたまま何年も放置されるとか、そういう運命を辿ることになるわけですね。 その昔、エラーい先生が亡くなったりしたとき、その方の蔵書がかつての勤務先大学の図書館に寄贈され、それが「○○教授記念蔵書」などと銘打って受け入れられる、などということがあったように聞きますが、それはもう古の語り草でありまして、今はもうそんなことはあり得ません。 だからこそ私の恩師が亡くなられたときも、その蔵書はかつての勤務先大学に寄付されることなく、別な方法で処分されたのでありました。大学図書館に死蔵されるより、人に使われるような形で蔵書を処分した方がいいと思われたからです。 今はそういう、寂しい時代なんですよ・・・。 ま、他大学のことはさておき、私の現在の勤務先大学の図書館も、増大する本の置き場に困って四苦八苦してるもんな~。 ですから、重要な学術誌の送付を断ってくる大学図書館が沢山あったとしても、私は驚かないんです。 でも、呆れることは呆れますね。スペースがないから、重要な学術誌の送付を断るってのは、研究機関として、あるいは教育機関として、本末転倒ではないの? 残り少ない図書館の空きスペースを少しでも確保することの方が、重要な学術誌を受け入れることより大事、ってことはないでしょう? いつも言うことですが、結局日本というのは、貧しい国なんですな。学問のために図書館を増設するお金はないんです。国立大学にも私立大学にも。国民がかつかつ食べるので精いっぱいの国なんですよ、日本という国は。 一方、外国の大学図書館は違いますねえ・・・。外国の大学図書館から通知があるときは、「お前の所の学会の学術誌、○○年の第○○号が欠けているので、ぜひ一部送ってくれ」という依頼通知ばっかりですもん。間違っても「もういらないです」なんて通知は来ない。彼我の違いを痛感するなあ・・・。 ということで、今日もまた、この国では最上位の教育機関ですら、学問というものに対してこういう態度をとるんだ、ということを思い知ったのでありました、とさ。情けなや、情けなや・・・。
August 27, 2008
コメント(6)
-
独身時代を思い出す
今日は所用で家内が家を開けているので(いや、別に喧嘩して家内が家出したわけではありませんヨ!)、私は一日、一人ぼっち。家の中がガラーンとしております。 で、仕方がないので仕事をしたり、本を読んだりしました。やたらに捗りました。 昼食も一人で食べました。夕食も一人で食べました。今日のメニューは冷凍食品のチャーハンです。 一度も笑いませんでした。っていうか、そもそも、一言もしゃべってません。 あ、ウソだ。テレビでニュースを見ながら、「ではこの地方のニュースをお伝えします」というアナウンサーに対し、「お願いします」と相槌を打ったな。 テレビ見ててもつまらないので、じきに消してしまいました。 はあ~。つまんね~。 何だろう、この感覚・・・。 あ、そうだ! 独身時代の感覚だ! そうそう、15年ほど前、ワタクシは毎日こういう生活をしていたんだった! あの頃ね~。東京から右も左も分からぬ名古屋に赴任してきて、まだ知り合いもあまりいなくて。ま、平日は大学で授業しているからいいですけど、週末、2日間まるまる沈黙の生活をするのが辛かったな~。この働くのが嫌いなワタクシにして、週明け、大学に行くのが嬉しかったですもんね。少なくとも人間としゃべれるというわけで。 いや~、今日は一日一人ぼっちだったので、その頃のことを思い出しましたよ。 もちろん、一生のうち一度くらいはそういう孤独な時期があるということも大事だと思いますが、やっぱり、家の中はある程度賑やかな方がいいですな。どちらかというと一匹狼的なワタクシですら、そう思います。 ということで、家内殿、早く帰っておいで!
August 26, 2008
コメント(2)
-
夏だけが終わるのは
先日、実家に居た時、我が大学4年生の姪っこが、「どうして夏だけが終わるの?」と洒落たことを言っていました。 確かに「夏が終わる」とは言いますが、「春が終わった」とか「秋が終わる」とはあまり言いませんね。「冬」は「終わる」というよりは「去る」ですし。「かくて失意の冬も去り」とかね(from『リチャード三世』。嗚呼、教養が迸る!)。 結局、夏というのは四季の中で唯一、「永遠に続いて欲しいと思っていたものが終わっちゃった・・・」という感慨を抱かせる季節だからでしょうか。夏の休暇も終わって欲しくないし、今年の場合はオリンピックも終わって欲しくない。でも、終わっちゃったなあ・・・って感じ。 そしてひと夏の恋も。なーんつって。 「どうして夏だけが終わるの?」か。我が姪よ。でき過ぎたセリフだぜ。 さて、そんなうたかたの恋なんぞとは無縁のワタクシ。今日、大学からの帰りにスーパーマーケットに立ち寄ったのですが、自動ドアが開いた途端、ワタクシを襲ったのは芳しい果物の香りでした。見れば桃、葡萄、そして梨などが山積み。ははあ。つまりこれが「夏が終わった」ということですな。 秋。豊かな収穫の季節。目にはさやかに見えねども、木々の実りは着実に生じているようでございます。 夏の終わりは寂しいけれど、来るべき豊穣の季節に期待することにしましょうかね。
August 25, 2008
コメント(4)
-
部屋の模様替え・願望
2週間ぶりに名古屋の自宅に戻り、我が城、すなわち書斎に陣取って思えらく・・・何なんだこの混沌と無秩序は!? 書斎などと言い条、そこはそれマンションの一室、広さはもとより知れています。そこへもってきて日々増殖する本と雑誌、そしてCD。そして鎮座まします3台のパソコン。もうほとんどまともに掃除機をかけるスペースすらないという・・・。 久し振りにこのカオスを目にして段々腹が立ってきました。そうなんだよ、大体、ワタクシがいつも原稿を書く時間より、資料を探すのに手間取るのは、この部屋がこういう状態だからじゃないかっ! しかし、ここに秩序を導入するには、まずあれとこれとそれを捨てなくちゃなるまい。引っ越して来た当初は希望に満ちて入れた家具類。こいつらを捨てるとなると、一体どうすりゃいいんだかさっぱり。いらない大型家具とかを引き取ってくれる業者とかがあるのでしょうか? 加えてワタクシの生来の不精癖が・・・。「こうしよう」と計画してから実行までが長い、長い! ということで、いつのことになるやら分かりませんが、願わくば夏休み中に、この混沌の巣窟をなんとかしたいと思っているワタクシなのでありました。あーん、スッキリ広々した書斎が欲しいよ~!
August 24, 2008
コメント(0)
-
名古屋に戻る
オリンピック、男子400メートルリレー、銅メダルとって良かったなあ~! これで朝原選手も最後の晴れ舞台を飾れたし。苦労人は報われる。 オリンピックで目指す色のメダルとって日本に戻ってくる時の気分は、さぞ、よろしいものなのでございましょうなあ。 翻って私、今日、名古屋に戻るのですけど、その心の重いことよ。また仕事かあ・・・。一生夏休みだったらいいのに。 ま、それでも一足先に名古屋に戻っている家内に会えるから、それを楽しみに愛車プジョーのハンドルを握ることといたしますか。 さて、東京は現在小雨ですが、雨の東名で事故でも起こさない限り、明日からまた名古屋からのお気楽日記です。道中の無事を祈っていて下さいね~!
August 23, 2008
コメント(4)
-

横書きのココロだ~
聞くところによると、最近、ゴマブックスが「ケータイ名作文学」と称して夏目漱石の『こころ』や太宰治の『人間失格』などを横書きに組み、発売して、これが意外な人気を博しているのだとか。この先も芥川龍之介の作品なども横書きの体裁で順次発売されていくらしい・・・。 いや~。ついにそういう時代になりましたか・・・。さすがに私の世代だと、日本の小説を横組みで読むというのは抵抗があるけどなあ・・・。 ところで、私自身のことを申しますと、私はちょうどこれと逆の経験をしたことがありまして。某雑誌に横書きで掲載していた文章を、単行本として出版する際、縦書きに組み直したことがあるんですな。すると・・・ ・・・全然違う。感じが狂う。 はれ~。文章って、横書きと縦書きでこんなに違うものか・・・、って思いましたわ、その時。だから全文見直したんですよ。横書きっぽい文章を縦書きに合うような文章になるよう、ところどころに修正を加えていった。もちろん個々の修正は微妙な修正ですけど、必要な修正だったと思います。 ですからね、もともと縦書きで書いてある小説を横書きで組んだら、やっぱり少し変な感じになると思うんですよね~。夏目漱石にしても太宰治にしても、自分の作品にそんな改変を加えられたと知ったら、墓の下で身悶えしてるんじゃないかしら。 ま、漱石だ太宰だってのは近代小説ですから、まだいいか・・・。『横書き・平家物語』なんてのが出てきたりしたら、ちょっとガクガクっとなりそうな。『横書き・枕草子』も、なんだか軽過ぎる感じになりそうだなあ。 でも・・・、『横書き・徒然草』だったら、案外、読めるかも・・・。あと、『横書き・源氏』も意外と行けるか? それはさておき、出版社、とりわけ文庫本の出版元ってのは、なかなかしぶといもんですな。小説が売れない時代とは言え、表紙をモダンにしたり、版組を変えたりしながら、手を変え品を変え売っちゃうんだもの。古今東西、ペーパーバックの出版社には、元々そういうタフでしたたかなところがあるけれど、日本のそれもまたしかり。その点では、私も敬服しちゃいますね。 ということで、さすがに買ってみるところまではいかないと思いますけれど、「怖いもの見たさ」の気持ちで、その横書きの『こころ』とやら、いずれ書店で立ち読みでもしてみましょうかね。これこれ! ↓こころ(上)こころ(下)
August 22, 2008
コメント(4)
-
雷&集中豪雨に出くわす
今日の午後、恩師S先生のお宅にお邪魔して近況報告をしたり、先生の近況を尋ねたりして来ました。休みで東京に帰っている時は必ず行う行事ですが、84歳になられたS先生、まだまだお元気で、同人誌に小説を発表されたり、読書会の指導をされたりといった生活を送っておられるご様子。恩師がご健在というのは、本当に嬉しくも頼もしいものです。 で、夕方、先生のお宅を辞して帰宅の途に就いたのですが、途中、多摩川を超えたあたりから雲行きが怪しくなり、家に着く頃にはものすごい雷雨に。たちまち道路は川と化し、雷鳴は耳をつんざき、稲妻が目を眩まします。ひゃー、コワいよ~。豪雨は好きだけど、雷は苦手だ~! それにしても今年はあちこちで集中豪雨ですね。昼間異常に暑いので、入道雲が発達し、夕方から激しい雷雨、ということになるのでしょうが、これも畢竟、地球温暖化の影響なんでしょうな。いや、恩師S先生の言葉を借りれば、『地球温暖化』ではなく、『地球高温化』ということになりますか。 とはいえ、それでも朝夕は大分過ごしやすくなってきた今日この頃。デパートなどでもディスプレイされているマネキンの格好が次第に秋めいてきました。雑誌はさらに気が早いですから、もうすっかり秋模様ですね。 というわけで、あれこれ雑誌をめくっていると、ジャケットなんかの広告が目に入るようになるわけですけど、そんな中、私の目に止まったのは「H&M」、すなわち「ヘネス&マウリッツ」です。 ちょっとカッコいいデザインだなと思ったジャケットの値段が1万5千円ちょい。あらら、随分安いのねと思って他のアイテムを見ると、ズボン(「パンツ」とは口が裂けても言わない)が7,990円、ネクタイが1,290円、Vネックニットが5,490円・・・。ひゃー、どれもカッコいいのに安い~! で、あれこれ調べると、このH&Mというのはスウェーデンの会社で、今、世界中にお店を出店している会社なんですってね。日本で言えばユニクロ、スペインで言えばザラ、アメリカで言えばGAP的な位置づけなんでしょうけど、そこはそれ北欧デザインのお国柄、カール・ラガーフェルドやステラ・マッカートニーら超一流のデザイナーに依頼しているらしい。実際、私もまずはそのデザインの良さに目が行ったわけでありまして。 で、それがこの秋、日本に上陸すると。まずは銀座、そして渋谷と原宿。そこで今、日本でもH&Mに注目があつまっているのだとか。なーるほどね~。 で、名古屋にはいつ出店してくれるの? そこが不安ですが、いざとなれば東京の実家に戻った時に買える強みのあるワタクシ。ライバルが極端に少ないからとはいえ、「学内一のベストドレッサー」との呼び声の高い釈迦楽教授。この秋はH&Mで決めちゃおうかな! ということで、期待も込めてこの秋、H&M、教授のおすすめ!です。
August 21, 2008
コメント(0)
-
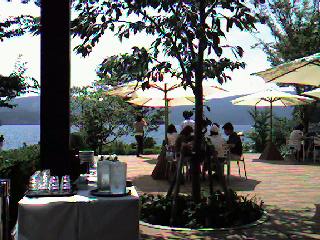
玉村豊男ライフアートミュージアムを訪れる
今日は両親と姪っこを連れて箱根にある「玉村豊男ライフアートミュージアム」というところに行って来ました。 玉村豊男さんというと、エッセイスト、画家、そしてワイン醸造家として多面的な活躍をされている方ですが、その玉村さんの絵を展示するミュージアムと、イタリアンのシェフとして名高い日高良美氏がプロデュースしたレストラン「アクアパッツァ・テラス」が合体した施設が箱根・芦ノ湖畔に出来たということで、箱根を「我が家の庭」、芦ノ湖を「うちの池」と豪語する釈迦楽家としては、とりあえず一度は行っておこうということになったんですな。 で、東名・小田原厚木道路・箱根新道と乗り継いでちょうどお昼頃芦ノ湖畔・元箱根に到着した我ら一行は、すぐさまアクアパッツァ・テラスに乗り込んだ・・・のですが、既に待ち人多しの状態。が、ここがなかなか洒落ているところで、席が空くまで隣接する玉村豊男ライフアートミュージアムに入って絵を見ていると、お店の人が呼びに来てくれるサービスがあるんですな。ということで、とりあえず食事の前に玉村さんのアートを鑑賞しようということになったわけ。 で、レストランで割引券をもらい、400円(リーズナブル!)の入場料を払った上で隣接する「玉村豊男ライフアート・ミュージアム」に入って見たのですが、この小ぶりなミュージアムは展示が3室に分かれておりまして、最初の部屋は主に植物や静物を題材にした版画が展示されている。ま、玉村さんの描く絵の傾向をご存じの方は分かると思うのですが、非常に細密な、上手なんだか下手なんだかよくわからない、そういう絵です(どういう絵だ!)。でも、実物を間近に見たのは初めてだったので、それなりに面白かったですし、中には「あ、これなら買ってもいいかな」と思うようなものすらあったりして、ちょっと見直しましたよ。 また、これは一つ勉強したのですが、玉村さんのいわゆる「版画」というのは、「ジグレー」と呼ばれるタイプで、これは要するに水彩画を一度コンピュータに取り込み、インクジェット・プリンターでプリントアウトしたものなんですな。とはいえ、もちろん、売り絵にするものですから、プロのプリント業者が高性能のプリンターで出力しているので、見た目はほとんどオリジナルの水彩画のようです。 しかし、この「ジグレー」という版画手法の存在は、私にとっては、いささか「コロンブスの卵」的な感じでしたね。コンピュータに取り込んで、それをインクジェットプリンター出力するなら、それは「版画」というより「ポスター」に近いわけで、「絵」としては価値がないじゃん、というふうにも思えてくるわけですが、それでもよく考えてみると、インクジェット・プリンターというのは色を紙に直接吹き付けるわけですから、確かに「版画」と呼んでもいい側面がある。なるほど、インクジェット・プリンターで出力したものは、「版画」なんだ・・・。 とまあ、そんなことをあれこれ考えながら第2室に向かいますと、ここはオリジナルの水彩画が展示されている部屋でありました。しかも、花の絵ではなく、中国やパリの街角風景を描いたものばかり。ほ、ほう、玉村さんってのはこういう風景画も描くのか・・・。 ま、その風景画も、私の目から見ますと、「素人以上、玄人未満」という感じがしますが、玉村さんはもともと本当の絵の玄人ではないわけですから、それはそれでいいのかも知れません。それに、彼の絵の最高の出来のものは、少し(ほんの少し)荻須高徳っぽい感じを出しているものもありますからね(褒め過ぎか?)。 そして第3室。ここはほんの3、4点ですけど、玉村さんの油絵作品が置いてあって、これは割と出来が良かったですねえ。今、玉村さんというと水彩画が有名ですけど、案外、彼は油絵の方が合っているのではないでしょうか? というわけで、そんなに期待しないで入った割に、結構、楽しく玉村さんの絵を鑑賞することが出来、予想外に大満足! だけど、それにしても玉村さんのライフスタイルって、傍から見るとうらやましいな。エッセイ書いて、自分の好きなワインを醸造し、それを売りもし、自分の作ったワインに合う食事を出すレストランも作り、その脇で好きなように絵を描いて、それが売れもし、ミュージアムにもなり・・・。もちろん、玉村さんだからできることでしょうけれど、憧れるなあ・・・。 ・・・それはともかく。 ちょうどうまい具合に、ミュージアムの方の展示の大半を見終わった頃にアクアパッツァ・テラスの店員の方から呼び出しがありまして、レストランへ再度移動、いよいよ待望のランチをいただく仕儀と相成った、とお思いくだせい。 で、その「アクアパッツァ・テラス」に入ったのですが、これがね、とにかくシチュエーションが素晴らしい。室内からも、またテラス席からも芦ノ湖が一望でき、しかも湖を渡ってくる涼しい風が心地よく、立地としてはグッドなのではないでしょうか。とりあえず私たちが陣取った席からテラス席越しに見える芦ノ湖の映像をお楽しみ下さい。これこれ! ↓ ね、いい感じでしょ? で、こんな素敵な席に座りながら、「日高良美シェフ御監修」のピザだのパスタだのサラダだのを注文して食べたのですが、そのお味は・・・うーん、まあまあですね。普通においしかったけど、特筆するほどではないかも。でもいいんです。涼風を受け、景色を楽しみながら食べていれば、気分はサイコー!なんですから。むしろ、あれですね、食事をとるというより、つまみをとってビールを楽しむとか、カフェとしてドルチェとエスプレッソ(イリーのコーヒーが使われているようです)を楽しむ、といった感じで利用してもいいのかも知れませんね。 さて、ここで気分のいいランチタイムを過ごし、ミュージアム・ショップで絵葉書を買ったり、玉村さんの本を買ったりしてから、その次に我ら一行が向かったのは・・・やっぱり仙石原にある「箱根湿性花園」でした! 「また?」と言われそうですが、ここ、好きなんですもん。さすがに日差しはまだ夏を思わせるものでしたが、吹く風と、そしてミソハギやワレモコウ、オミナエシにオニユリといった草花の色に、秋の気配が感じられましたねぇ。こんな感じ! ↓ かくして、今日は「玉村豊男ライフアートミュージアム」と「アクアパッツァ・テラス」、そして湿性花園の草花を堪能し、過ぎゆく夏の一日を堪能したのでありました、とさ。 ところで、ミュージアム・ショップで買ってきた玉村さんのご著書、家に帰ってから読み始めたのですが、とても面白いです。玉村さんがヴィラデストを開く前、軽井沢に移住した直後のことを書いたエッセイなんですけど、軽井沢の自然に抱かれて過ごす日々の暮らし、軽井沢の山の幸の話など、この手の話題に弱いワタクシとしてはたまらん内容です。話の中に出てくる料理(これがマジうまそう!)のレシピもついていますので、料理好きの方にもおすすめ。興味のある方は是非!これこれ! ↓軽井沢うまいもの暮らし
August 20, 2008
コメント(0)
-
我が家の「アートな写真」論争
このところ父の「芸術談義」がうるさくて仕方がありません! 最近デジカメに凝っている父。花の写真を撮ってはせっせと自分で絵葉書に加工し、友人・知人に送りつけておりまして。要するにレスポンスが欲しいんですな。レスポンスというより、「素晴らしい!」という賞賛の言葉が欲しいのでしょうが。私に似て、父も褒められたい人なもので。(というか、私が父に似たのか・・・) ところが運の悪いことに、親戚に写真の腕前がセミプロ級というのがいまして、この人が、(止せばいいのに)父の「作品」を評して「芸術作品とは言えないけれど、なかなかよく撮れている」みたいなことを言って寄こしたらしいんです。 で、父はこれにカチンと来た、と。 そりゃ、父としては自分の写真は紛れもないアートだと思っておりますから、それを「アートとは言えないが・・・」などと言われたら腹も立つでしょう。で、ここ数日、不毛な芸術論を罪のない我ら家のものに吹っかけてくるわけ。つまり、「『芸術写真』と『そうでない写真』の区別はどこにあるのだ」と。もう、うるさい、うるさい・・・。 ま、私も「文学」なんぞを研究する身、「父上、それはですね・・・」と即答したいところですが、なかなかそうも行かない。だって、芸術と芸術以外、文学と文学以外のものの線引きなんて、あんまり興味ないんですもの。そんなの、人それぞれでいいんちゃうのん? 自分で「これはアートだ!」と思えば、すなわちそれがアートなのでありまして。 それに、何となく「感じ」で分かりますよね? たとえば私は最近、ジェフリー・ディーヴァーのサスペンスにはまってやたらに読んでいますが、これとて、ディーヴァーの作品を、例えばフォークナーの作品と同列の「文学作品」として評価しているという意味ではありません。そこはやっぱり区別しているのでありまして、ただ、どこがどう違うとはうまく言えないだけ。感じ、ですよ、感じ。フィーリング。 しかし、そういう回答では父は納得しそうにありません。「そうかなあ・・・。」と言った5分後には、「僕の写真はアートではないと言われたけど、アートって一体なんだ?」と言い出すに決まっています。 そこで私も父が納得するような答え方を考えてみた、と。特に「写真」について、ね。「アートな写真」と、「ただきれいに写った写真」の違いは何ぞや? で、思いついたのが、「アートな写真とは、『アート』すなわち『人の手』が加わっていることが明確に見てとれる写真である」という定義なんですけど、どう? 父の写真は、被写体を鮮明に、構図よく撮るということを念頭に置いたものです。ですから一応、バランスよくきれいには撮れている。しかし、そこから撮り手の意図はあまり伝わって来ないんですね。「こういう風にきれいに見えた」と言っているだけで、「こういう風に見せてやる」という意思が感じられない。 結局、そこじゃない? 「アートな写真」とは、端的に言えば「人工的な写真」、つまり自然を自分の意思に従って捻じ曲げて写す写真のことなのでは? たとえば、通常「汚いもの」と思われているものを写真に撮って、「ここに美を見ろ!」と押しつけるのもアートな写真と言えるでしょうし、カメラの機能を使って、あるいはコンピュータ処理して、人間の目に映るのとは異なる映像を見せた写真もアートな写真と言えそうです。わざと逆光で撮ることだって、アートな写真を作る手段かも知れません。とにかく、自然を撮り手の意思で捻じ曲げた写真がアートなんだ、と言えば、当たらずといえども遠からず、って感じがしません? 父がそういう写真を撮りたいかどうかは別として。 自分ではしてきました。 ということで、今度父が「ところで、この間、僕の写真はアートではないと言われたんだけど・・・」と言い出したら、そう言ってやろうと思います。これで釈迦楽家のにわかアート談義も終結! ・・・いや。いやいやいや。一つ忘れていました。父の気質の一つは、「家族のものの言は受け入れない」なのでした。私がいかに真っ当な「正解」を言おうと、それは父の耳には馬耳東風。誰か、世間的にエラーイ人が言ってくれないと、父は決して信用しないのであります。 ということで、この先当分、「ところで、この間、僕の写真はアートではないと言われたんだけど、アートな写真って何だ?」の問いかけを聞かされる羽目になりそうな釈迦楽家の面々なのでありました、とさ。どなたでもいいですけど、世のエラーイお方、父を説得してくださーい!
August 19, 2008
コメント(4)
-

ジェフリー・ディーヴァー『The Coffin Dancer』を読む
それにしてもアブラゼミの死にざまってのは今一つパッとしませんなあ。道端でもベランダでも、どこでもところかまわずドデーンとひっくり返っていて。で、死んでるのかな? と思って足の爪先でツン、なんて突っついてみたりすると、突如復活! 「ギャ、ギャ、ギャッ!」などと叫んで暴走(暴飛?)し、こちらのキモを冷やしてくれるし・・・。 もっとも死にざまの悪いのはアブラゼミだけで、他のセミが道端で無様にひっくり返っているのなんて見たことありません。その差は一体どこから来るのでしょうか。・・・育ち? さて、それはともかく、先日来読んでいたジェフリー・ディーヴァーの『The Coffin Dancer』を読み終わりました。車椅子の探偵ジェフリー・ディーヴァーものの中でも傑作の誉れの高い作品ですが、さすがに読ませますねえ。 簡単に粗筋を紹介しますと(ネタバレ注意!)、ある所にフィリップ・ハンセンって悪の親玉がおりまして、近々法廷に出ることになっているんですが、こ奴、自分の罪を立証するようなやばい証拠物件を飛行機の上から海に投げ捨てたらしいんですな。で、たまたまハンセンが密かに証拠隠滅の飛行に出た時、それを目撃してしまった運の悪い人間がいた。小さな商業航空会社を経営する経営者兼パイロットの夫妻、エド・カーニーとパーシー・クレイ、それに共同経営者のブリット・ヘイルの3人です。で、この3人はハンセンを裁く法廷に出廷し、ハンセンに不利な証言をすることになったのですが、それを防ぐため、ハンセンは腕利きの殺し屋「コフィン・ダンサー」を雇い、3人の証人の抹殺にかかるわけ。そして小説の冒頭、ダンサーはエドの操縦する飛行機に爆弾を仕掛けて飛行機ごと爆破。最初のターゲットをモノにしてしまいます。 かくして残った2人の証人の命を守り、かつコフィン・ダンサーを逮捕することが、車椅子探偵リンカーン・ライムの任務となるんですな。実は数年前、ライムの部下2人がダンサーに殺されており、その意味でこの仕事はライムにとって報復戦でもある。しかし、同時にダンサーの殺しのテクニックの凄さを熟知しているライムとしては、今回の仕事は非常に困難なものになるだろうという予想をせざるを得ない。 実際、ライム対ダンサーの攻防はめまぐるしく展開します。ライムが罠を仕掛ければ、ダンサーはそれに感づいてまんまと罠をくぐり抜け、逆にダンサーの襲撃は、先を読んだライムによって未遂に終わる。そんな息詰まる展開に読者は翻弄されっぱなし。 しかし、ついにダンサーは2人目の証人ブリット・ヘイルの殺害に成功、残るは女性パイロットのパーシーだけになってしまう。ライムは何としてもパーシーの命を守ることを誓うのですが、パーシーにはパーシーの事情があり、夫やブリットと立ち上げた小さな航空会社を破産の危機から救うため、どうしても法廷に立つ前に一度、飛行機を操縦してある荷物を運ばなければならないんですな。ダンサーからしてみれば、こんな恰好の襲撃チャンスはありません。さて、パーシーは無事、飛行を終えて法廷に立つことができるのか、それともダンサーがライムの裏をかいてまんまと証人抹殺に成功するのか?! というような話です。 サスペンスの粗筋をこんなに明かしてしまっていいのか? と思われた方、ご安心下さい。ジェフリー・ディーヴァーのサスペンスがこんな簡単な展開で済むわけがありません。実は、ここから事態は二転三転、いや四転くらいするんですよ。最後のページを読むまでどうなるか分からない。そこがディーヴァー作品の面白いところでして。とにかくハラハラ、ドキドキ、手に汗握る読書体験ですから、まだ読んだことのない方はぜひ。教授のおすすめ!です。ライムの右腕、美貌のアメリア・サックス捜査官や証拠物件分析担当官メル・クーパー、さらに証人警護のプロたるローランド・ベルなど、「リンカーン・ライム・サスペンス」でおなじみのメンバー総出演ですぞ!これこれ! ↓The Coffin Dancerコフィン・ダンサー(上)コフィン・ダンサー(下) ただ一か所だけ、この作品に関して私には理解できない部分がありまして。パーシーの飛行にトラブルが生じた際、ライムははっきりと「対処法を思いついた!」と言うのですが、その対処法が何だったのか、作品に書かれていないのではないかと・・・。その辺、もし「いやあ、あれはこういうことなんだよ」と説明して下さる方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。よろしくお願いいたします。
August 18, 2008
コメント(3)
-
日本柔道は寝技にもっと注目を!
北島選手をはじめとする男子400メートル・メドレーリレー、なかなか良かったですねえ! それぞれの選手が死力を尽くしての日本新記録、そして銅メダル。素晴らしい! それから2大会連続の金メダルに輝いた女子レスリングの伊調馨選手、そして惜しくも銅メダルとなった浜口京子選手もよく頑張りました。いつも不当な誤審に泣かされている(今回も準決勝で相手選手をフォールしかけていたのに、何故止められたのでしょうか?)「ザ・日本の娘」京子にはぜひ金メダルを取ってもらいたかったですけど、笑顔の銅メダル、ワタクシもアニマル浜口さんに唱和して京子の健闘を讃えたいと思います。 さて、一昨日の柔道・100キロ超級、石井慧選手の金メダル獲得がひとつの契機となったのか、日本の柔道界もようやく「一本を取る柔道」から「なんでもいいから勝負に勝つ柔道」への転換を考え始めているようですが・・・ ・・・遅いよね! もうそんなこと、3大会位前から考えなきゃいけないことだったんじゃないでしょうか。 大体、「一本を取る柔道」というのは、野球の打撃にたとえてみれば、「常にホームランを狙って打席に立て!」と言っているようなものでしょう? 高校野球レベルだってそんな指導をする監督はいないのではないでしょうか。「内野安打でも、デッドボールをくらってでも、とにかく塁に出ろ」というのが普通なのでありまして、それを柔道に翻訳すれば「相手の反則を誘ってでも勝負に勝て」ということになる。もちろんそれを潔しとせず、あくまで一本を取る柔道を貫くというのであれば、国際試合でメダルが取れなくても悔しがる必要はないのでありまして、「メダルは取りたいです、一本も取りたいです」というのは、少なくても「Judo」界では非現実的過ぎる。・・・と、素人目には思えます。 その一方、日本柔道たるもの、姑息な手で勝ってもらいたくないという気持ちがあることも認めざるを得ません。そこが日本のいいところなんですからネ。 で、思うのですが、日本柔道は「立ち技中心主義」から「寝技中心主義」に転換すりゃあいいんじゃないでしょうか。 そりゃ、「内また」とか「一本背負い」とかでバーンと一本取ればやってる方も見ている方も気持ちいいですけど、外国人選手はそういう日本柔道の立ち技主義をすでに十分研究しているので、なかなかその手は食わないですよ。逆にこちらが仕掛けた技を返してきて、返し技一本!ということになってしまう。また突っ立って戦うから「朽木倒し」みたいなレスリング技に引っかかるのであって、立ち技中心でやってたらこの先も日本柔道の未来は暗いです。 だから、寝技ですよ、寝技。そして絞め技。今回男子柔道で金メダルを取った内柴選手にしても、石井選手にしても、寝技の得意な選手でしょ。だから安定して勝てるのでありまして、日本柔道にとって寝技の強さは相当なアドバンテージになっているはず。巴投げ気味に寝技に引き込んで、あとは関節技と絞め技の地獄にお招きすればいい。必ずしも強い選手が勝てるとは限らない立ち技とは異なり、寝技は実力がそのまま順位に出ます。日本柔道の思うつぼじゃないですか! 国内の試合はともかく、国際試合において、すべての階級、すべての試合を寝技中心で攻め、「腕拉ぎ十字固め」はもちろんのこと、「送り襟締め」「三角締め」「袖車」といった国際試合ではめったに出ない技の数々を、決まり手として並べてみせましょう。そうやって日本柔道の新しいスタイルというのを見せつければ、外国人選手たちがその対策を練るまでに相当な時間がかかるはず。オリンピック2大会分くらいは楽勝でしょう。 スポーツだって、最後は頭ですよ、頭。頭のいい奴が勝つ。ここはひとつ、釈迦楽教授の頭脳作戦に任せて、日本柔道は「寝技中心主義」へ舵を切るべし!
August 17, 2008
コメント(0)
-
見知らぬ街を走る
それにしても女子レスリングの吉田選手は強いですね! あそこまで他を圧倒する強さを見せる日本選手ってあまりいないので、格闘技好きのワタクシとしてはもちろん彼女の大ファン。今日も見事な金メダルへの道のりを堪能させていただきました~! さて、今日の私ですが、私より一足先に名古屋に戻る家内を送るため、新横浜駅まで行くことに。いつもですと電車を乗り継いで行くのですが、今日はふとクルマで行ってみることにしました。荷物もあるので、その方が楽かな、と。 でもその前に腹ごしらえです。今日は前からちょっと気になっていたイタリアンの新しいお店「Buonappetito cucina」というところに行ってみることに。ここ、1年位前にできたお店ですが、家からごく近い割に、まだ行ってなかったんですよね~。 で、行ってみると、ほ、ほう。白亜の洋館風の建物がなかなかいい感じじゃないですか。ちなみに、ここのオーナーは「アルファ・ロメオ」のファンなのか、店に隣接するご自宅の車庫には「アルファ・ロメオ147」と「アルファ・スパイダー」が並んで止まっています。スパイダーは新型ではなく、映画『卒業』でダスティン・ホフマンが乗っていたクラシック・タイプ。私のようなクルマ好きに言わせていただきますと、こういう車に乗っていること自体、センスとこだわりのあるオーナーに違いないという確信が持てます。これは期待できそうですね。 さて、店内に導かれてランチ・メニューを見ると、「肉料理」「魚料理」「パスタ」とあってどれも1,000円。前菜とパン・ライスが付きます。で、これに300円をプラスしますと、食後のデザートと飲み物が付く。これは予想以上にリーズナブル。今日は私が魚料理、家内がパスタを、どちらもデザート&飲み物付きで注文しました。 パスタの方は「小海老とホウレンソウのパスタ」、魚料理の方は「サンマの燻製、香草サラダ添え」。どちらもおいしかったですけれど、私が食べたサンマの燻製は、燻製されたサンマが一本、香草サラダの敷かれた皿にどーんと乗って来るもので、燻製の度合もよろしく、なかなかおいしかったです。考えてみれば私にとって今年の初サンマですね。 で、料理も良かったのですが、私が注文した食後のアイスティー、これがおいしかった。氷に負けない濃さと香りをしっかり持ったアイスティーで、ここまでおいしいアイスティーに出くわすことはなかなかありません。また店員さんたちのサービスも心のこもったもので、その点での高感度も大。東京・町田市、小田急線黒川駅近くにあるイタリアンの名店「ボナペティート・クッチーナ」、教授のおすすめ!です。 さて、ここで心地よくお腹を満たした我らは、新横浜目指して車を飛ばしました。と、これがまた意外や意外、私が考えていた以上に近いんですな。電車だと何度も乗り換えをしないといけないので、案外時間がかかるのですが、車だとほとんど直線距離で行けるので、ものの50分ほどで着いてしまいました。途中、「IKEA」の港北店の前を通ったりして、あらら、こんなところにIKEAがあったのか、などと再認識。こんなに近いなら、今度ここで家具でも見てみようかしら。 しかし、そこから先が問題アリ。今日は土曜日だったせいか、新横浜駅周辺の駐車場がどこも満車で、空いている駐車場を探して右往左往すること4~50分。結局、どこに止めていいか分からず、ロータリーみたいなところで家内を下ろし、その場で見送ることにしました。いつもはホームまで見送るので、ちょっと寂しい感じ・・・。 でももっと寂しい、というか、心もとないのは帰り道。何せワタクシは極度の方向音痴ですから、家内のナビなしで無事帰りつけるのか? という不安で一杯。が、それでも何度か道を間違えつつ、よろよろと帰宅の途に就いたのでございます。良かった、良かった。 それにしても、アレですね。人間の土地勘なんて頼りないもので、自分のよく見知ったテリトリーを一歩踏み出して、見知らぬ土地を車で走ったりすると、見るものすべてが新鮮というか目新しく、またその反面ちょっと怖くもあり、いずれにしても強烈な印象を受けます。家からほんのちょっと走ったところですらそうなのですから、他府県のことまで含めたら、自分が死ぬまでに一度も通らない道というのがどのくらいあるのだろう、自分が死ぬまでに一度も通過しない町が幾つくらいあるのだろうという思いが湧き起こります。 でも、そういう「見知らぬ通り」、「見知らぬ街」で、やっぱり人間の暮らしが営まれているわけでありまして・・・。 ま、ただそれだけのことなんですが、なんだかその当たり前のことが、考えれば考えるほど不思議なことのように思えて仕方がない。 というわけで、今日見た見知らぬ街の色々な風景が、なかなか目の奥から消えないなあ、という思いを抱いているワタクシなのでありました、とさ。
August 16, 2008
コメント(2)
-
昔の家を見に行く
夏休みの間しばし帰省していた姉は、明日仙台に帰りますが、受験生を抱える姉とこの次に会えるのは、甥っ子の大学受験が終わった春休み以降になりそうです。寂しい~! ということで、今日は姉のリクエストに応え、子供の頃住んでいた「東林間」という街を姉と一緒に散策することにしました。姉は二十数年前に引っ越して以来、ここを訪れるのは初めてとのこと。 お昼頃到着した我ら姉弟は、まず「巴屋」というお蕎麦屋さんに向かいました。昔、このお蕎麦屋さんでよく食べたんですよね。で、店内に入ってみると、たたずまいはほぼ昔のまま。笑顔の似合う店のおばさんの顔も、なんとなく覚えています。で、懐かしきお蕎麦をいただいたわけですけど、昔ながらの、いかにも街のお蕎麦屋さんの蕎麦らしい味がしましたネ。それにしても、我々が入店した後から続々と馴染みの客が入ってきて店はほぼ満席状態。ごく普通のお蕎麦屋さんにして、以前と変わらぬこの繁盛ぶりは、まこと慶賀すべきことであります。巴屋、フォーエバー! そして、満腹した我らは昔住んでいた家やら、その近くにあって当時姉弟して習っていたピアノの先生のお宅などを見て回ったり、昔よく行ったスーパー(三和&東急ストア)を覗いたり、さらには昔よく通った和菓子屋さん(松月)で水ようかんを買ったりして往時を懐かしんだ後、さらに子供のころ、誕生日とかクリスマスにケーキを買った「アマンデン」という洋菓子屋さんでケーキを買ったりもしました。 本当は、これまた子供の頃、嫌というほど菓子パンを買った「神田ベーカリー」というパン屋さんに寄って菓子パンを買いたかったのですが、残念ながら今日はお盆休みの最中。ロールケーキとペストリーが買えなかったのは残念でしたが、懐かしいパン屋さんが、以前とまったく変わらぬ店構えで経営を続けていることに快哉を叫びたくなりました。 それにしても、子供の頃過ごした街というのは、大人になってから再訪すると、どうしてこう小さく見えるんでしょうかね? この通りはもっと広かったはず、この道のりはもっと遠かったはず、と思うのですが、今歩くとまるで手のひらの上の街みたいに小さく感じられます。不思議なものです。 ま、そんな不思議な思いを抱えながら、姉と一緒に子供時代を過ごした街を訪問して、懐かしい思いに浸ることができたのでした。戦争とはまるで別な話ではありますが、「昔のことを思い出す」という意味では、終戦の日にふさわしい過ごし方だったかも知れませんね。
August 15, 2008
コメント(2)
-
奥深いハーレーの世界
今日は家内と友人Tと共に新百合ヶ丘にあるフランス料理店「ビストロ・パリエ」でランチと洒落込みました。 実はTの奴、最近、アメリカン・バイクの雄、ハーレー・ダヴィッドソンを買いまして。1.6リッターのバイクですから、ほとんど自動車並みのエンジンを積んだものすごいバイクです。で、つい先日、バイク仲間と総走行距離800キロというロング・ツーリングに出たんですな。 ところが、何せまだ買ったばかりでバイク自体に慣れていない上、まだハーレーを乗りこなすほどには運転技術が向上していない状態で、ほとんどぶっつけ本番でツーリングに出たせいか、Tにとってはなかなかハードな道中になったらしいんです。 例えば、自宅を出ていざ東名に乗ろうという時からして、雹混じりの土砂降りに逢い、1時間半ほど様子見のためのストップを余儀なくされるという、幸先の悪いスタートだったんですな。しかし一向に止む様子がないため、仕方なく雨に打たれながらの初高速走行となってしまった。 で、それが禍したのか、走行中に荷台に積んであった旅の荷物を高速道路上に落したまま、気付かずに浜名湖あたりまで走ってしまったというのです。後でそのことに気づき、道路公団に連絡すると、すでに警察が回収していたようで、それを取りに戻ったところ、どうもトラックか何かに何度も轢かれたらしく、ケータイの充電器から予備のメガネからすべてぺしゃんこだったそうで・・・。まさに踏んだり蹴ったり。 で、その日は三ケ日にいるツーリング仲間の家に泊めてもらい、翌日、この仲間と共に諏訪方面に向かったのですが、これが8時間ぶっ通しで山岳道路をぶっ飛ばす過酷なツーリングだったらしく、初心者のTは、仲間の後にくっついていくだけで必死。その挙句、急カーブを曲がり切れずに転倒。大けがこそしなかったものの、ピカピカのハーレーの新車が傷だらけになるというTにとってはショッキングな出来事もあり。かくして、ほうほうの体で諏訪までたどり着いたTは、翌日、「今日は霧ヶ峰を走ろう!」という仲間の誘いを断って、中央道で東京の自宅まで戻ってきたのだとか。 ま、そんな武勇伝というのか何と言うのか、珍道中の話をTからさんざん聞かされることとなったわけですが、それでも「ハーレー」というバイクの愛好家の間の絆というのは相当なものがあるらしく、道中のあちこちでハーレー仲間から声が掛かるんですって。特に諏訪の周辺を走っていた時には、全国的に有名な諏訪の伝説のハーレーライダーに偶然出会ったそうで、「今度諏訪に走りに来る時は、声を掛けてくれ。一緒に走ろうぜ!」などと言ってもらったのだとか。そういうのは、ちょっと面白いですね。 バイクというものに、まんざら興味がないわけではないワタクシ。ハーレーに乗りたいとは思いませんが、中型免許くらいとってもいいかな、なんてちょっと思ったりし・・・。 というわけで、今日は友人のちょっとしょぼい武勇伝を楽しんだワタクシだったのであります。
August 14, 2008
コメント(2)
-
本はいかに出版されるか
今日は書評を頼まれている本を読んで過ごしていました。もう前に一度読んだのですが、執筆前にもう一度おさらいしておこうかと思いまして。 で、私が書評することになっている本というのは、アメリカ文学の研究書ではあるのですが、専門用語などは極力使わずに書いてあるし、また内容的に一般の人が読んでもそれなりに楽しめる内容になっていて、まあ一言で言って「いい本」です。 が、出版元が英米文学とか英語系の教科書とかを手掛ける地味な出版社ですし、そういうところの常として、もともと出版部数もそんなに多くないと思われ、しかも値段が3400円ですから一般の人が買う本ではないですね。多分、そういうものとして、ベストセラーになることもなく、ロングセラーになることもないまま、闇から闇へ葬られ、息絶えることでしょう。 いい本だからと言って、売れる本になるとは限らない。これが出版ビジネスの面白い、というか悲しいところでありまして。 ところが逆に、大したことない本だなあ、と思う本がベストセラーになることはあります。ここがまた不思議なところなんですよね・・・。 私はアメリカの出版ビジネスを専門に研究している身ですし、大学出版会に身を置いて本を出版しているくらいですから、日本の出版ビジネスについてもまるで知識がないわけではありません。しかし、日本の出版ビジネスに関して一つ、どうしてもわからないことがあります。それは「大手出版社」と言われるところがどうやって有望新人の原稿をゲットするか、ということです。 もちろん、小説の場合ならわかります。小説の場合は色々な「新人賞」がありますからね。自分でなかなか面白い小説が書けたと思えば、そういう新人賞に応募して評価を待つ、ということが可能でしょうし、そこで賞の一つも取れば、そこから先の道も開ける、ということはいくらもあるでしょう。 しかし、小説以外の書きものの場合は? たとえ書いた当事者としていいものが書けたつもりでも、それを大手出版社から出版するのは至難の業です。なぜなら、大概の出版社は「原稿持ち込みお断り」が原則だからです。試しに頭に思い浮かぶ出版社のHPをご覧ください。そこには必ず「原稿持ち込みお断り」と書いてあるはずです。 でも、持ち込み原稿を断ってしまったら、出版社はどうやって無名新人の才能を見出すことができるのでしょうか? 実はこういう矛盾はどの社会にもあることでありまして、たとえば大学なんかでも、非常勤講師を募集する時に「非常勤講師の経験のある人」という条件をつけることがよくある。これは非常に馬鹿馬鹿しい矛盾でありまして、こんな条件をすべての大学がつけたとすると、たとえ大学院を優秀な成績で出た有望新人がいたとしても、その人を雇うことができないわけですよね。 それと同じで、どの出版社も「原稿持ち込み禁止」を原則にしてしまったら、才能ある新人ライターを発掘できないと思うのですが・・・。 しかし、こうした日本の出版会の慣行と矛盾するように、大手出版社から突然、無名の新人が本を出すことがあります。ここがまた不思議なところで、じゃあ一体、そういう人はどうやってその出版社と渡りをつけたのか・・・? 出版社自体が、どうにかしてそういう新人に目を留め、声をかけたということなのでしょうか? ま、そういう不思議なことがあるとはいえ、原則的には「持ち込み原稿お断り」という妙な慣行があるので、日本では有名な人しか大手から本を出せないというところがあります。逆に言えば、有名でない人はいつまで経っても大手から出版できず、その結果いつまでも有名になれないというわけです。もちろん例外的にこの構図を突破する人はいるでしょうが、それはあくまで例外的なことでありまして。 だからこそ「自費出版」というビジネスが存在する余地ができるんでしょうなあ。とにかく自費でもいいから出版して世間の人に見てもらおう、そうすればいずれ大手から声が掛かるかも知れない・・・。そういう幻想が生まれるのも、わかる気がする。しかし、実際には自費出版の出版物が注目されるなんてことはほとんどないのでありまして、幻想は幻想で終わってしまうことが多い・・・。 ま、それはともかく、私が今回書評する本にしても、多分、1000部位しか売れないんじゃないかしら。もう少し短くした上で新書版かなにかにして大手から売ったら、それなりに売れそうな本なのに、おそらくそういうことにはならないんだろうなあ。私が書評でいくら絶賛しても、多分そういうことにはならない。そこがちょっと残念、というか、むなしいところなんですよね。 いい本が売れるとは限らないし、売れている本がいい本とも限らない。この重大な矛盾が解消される日は来るのかしら。そんなことを考えつつ、「いい本だけど、売れない本」のために書評の筆を執りつつあるワタクシなのでありました、とさ。
August 13, 2008
コメント(0)
-
コストコでお買い物を楽しむ
東京の実家に戻った以上、一度は行っておかないわけにはいかない会員制マーケット「コストコ」。会費を払っているわけですから、なるべく何度も行って元を取らないとね! というわけで今日は家内と姪を連れてここにショッピングに行ってきました。 ま、初めてだった前回と比べ、今回は店内の様子や商品の配置も大体分かっていますから、今日は落ち着いてじっくり、必要なところを重点的に回ることができたという。いわばベテランの域に達した感じです。 で、今回の目玉は前回買いそびれた「コーンブレッド」を買ったこと。なんせ36個入りで628円ですよ! 買わずにはおられんじゃないですか! このコーンブレッドは、コストコの目玉商品らしく、たいていの人が買っています。中には3袋、計100個以上買っている人もいたりして、さすがにこの分量をどうやって消費するつもりなのかしらと思いますけど、とにかく買ってしまいましたよ。明日の朝食が楽しみです。 それから、これもコストコ名物であるオーストラリアからの輸入品のビールも買っちゃった。これ、24缶入りの箱買いで3000円弱。1本あたり124円。発泡酒以下の値段で本物のビールですから、相当なお買い得です。あとニュージーランドのアイスクリーム、1リッター入り378円。これも今日の食後のデザートに登場しましたけど、美味しかった! その他、食料品から日用品、薬品に至るまでなんだかんだ2万円分くらい買っちゃっいましたかね。でも、同じ量を一般のスーパーで買ったら3万円くらいはするんじゃないか、というような内容ですから、お買い得感たっぷり。いや~、いいですね、コストコ。名古屋にもできないかなあ。もし名古屋にあったら、牛肉とかもキロ買いしちゃうんだけどな。 ということで、今日はアメリカ的物量の世界に浸り、なんだか大船に乗ったような、大らかな気分になっているワタクシなのであります。今日も、いい日だ!
August 12, 2008
コメント(0)
-
一社にケーキ屋発見!
またまた名古屋でおいしいケーキ屋さんを発見してしまいました。 名古屋から地下鉄・東山線に乗って「一社」で下車、東西に流れる大通りのすぐ南、大通りと並行して東西に流れる通りを3分ほど歩いたところにある「ミロアール」というお店です。 住宅街にひっそりと立つ、その佇まいが前から気になっていたのですが、今回ここで初めてケーキを買ってみて、私の目に狂いはなかったと知りました。 今回買ったのは「イチジクのタルト」と「シブースト・マロン」、それに「シェルジャン」というドライケーキでしたが、どれも非常においしかった! 「イチジクのタルト」はタルトもいいけれど、乗っているイチジクの味が濃くて、いかにもイチジクを食べている、という気になります。しかし、それ以上に驚いたのは「シブースト・マロン」ですね。私がこれまでに食べたシブーストの中で一番おいしかったかも。 一方、シェルジャンは、一口食べて「うまーい!」と叫びたくなるような、派手なおいしさはないんですが、もぐもぐと食べているうちに、ジンワリと小麦の風味と上品な甘さがにじみ出してくるという感じとでも言いましょうか。これはこれで渋いおいしさです。 お店のパンフレットによると、フランスからお菓子づくりの名人を招聘して勉強をしたり、フランスへ赴いて最良の材料を調達したりと、刻苦勉励を重ねているとのこと。確かにその成果は出ているようです。私たちが行った時はすでに売り切れになっていましたが、今流行りの「塩キャラメル」味のロールケーキなんかも、きっとおいしいのでしょう。次はぜひこれにチャレンジしてみたい! ということで、一社にあるケーキの名店「ミロアール」、教授のおすすめ!です。名古屋にお住まいの方、一度ぜひ! さて、11日は午後から名古屋を出て、一路東京に戻って来ました。お盆休みが始ったところで東名の渋滞を心配しましたが、逆方向であることもあってさしたる渋滞もなく、あっさり到着。名古屋よりは若干、東京の方が涼しい、かな? かくして古巣・東京の人となった私。しばし実家での生活を楽しみたいと思っております。それでは、また。
August 11, 2008
コメント(6)
-
恒例・傑作誤字集
明日から東京の実家に帰省する予定のワタクシ、つまらん雑用はこちらにいるうちに済ませてしまおうというわけで、ここ数日、期末テストの採点をしておりました。今回は論述問題の少ない科目が多かったため、楽しい学生たちの誤字で爆笑させてもらうチャンスもあまりなかったのですが、一応、恒例となりました誤字集、行ってみましょう!「登上」:「飛行機に」という前置きがあるので、多分「搭乗」のことでしょうね・・・。「売収」:逆だよね。「買収」でしょ。「撮映」:「映画」を撮るから「撮映」。むしろ合っているような気もするけど、一応「撮影」と書いて!「自間」:まさか「時間」を書き間違える奴がいるとは想像もしませんでした!「貢績」:「貢献」とごっちゃになったか? 「功績」かな。「衝激的」:惜しい! 「衝撃的」ですね。「南北アメリカ戦争」:何だかアメリカとブラジルが戦争したみたいだなあ! それを言うなら「アメリカ南北戦争」って言って!「世界恐怖」:すっげー怖い感じがしますけど、1929年以降の「世界恐慌」のことですな。 そして今回の爆笑誤字(?)大賞は・・・ 「ジプシー効果」でした! 「シナジー効果」と言うべきところを間違えたらしいのですが、「ジプシー効果」というのも、なかなか趣がありますね。ほんとにそんな言葉がこの先、経済学用語として使われるようになったりして。「トヨタは、生産拠点をタイからブラジルに移しました。このジプシー効果により、今年度上半期の経常黒字を上方修正することになった模様です」なーんてね! さてさて、明日から私はしばらく東京の人。職場から遠く離れて、リラックスすることにします。明日以降、東京からの「お気楽日記」、またご贔屓に!
August 10, 2008
コメント(2)
-
オリンピック開幕
いよいよオリンピックが開幕しましたね。私も他の多くの同胞と同じく、この時期だけはあからさまな愛国者になりますので、日本選手の応援に力が入ります。特にオリンピック初日は柔道軽量級がありますからね。隠れ格闘技ファンの私としてはなおさら楽しみ! ・・・なんですが・・・。 オー、ノー! 谷選手、ヤワラ様、残念!! 毎回思いますけど、国際試合の審判って、一体何を見ているんですかね? とにかく組み合おうと思っているのは谷選手の方で、相手選手はそれを嫌ってひたすら組み合わない作戦なのに、何で谷選手の方に指導を出すんだよ! あんな判定、まったく納得できない!! 指導が来た時の谷選手の表情、「え? わたしだけ?」というあの一瞬の驚愕の表情、あれは忘れられないなあ・・・。戦っている選手が納得するような判定ができないなら、審判の資格なんかないね。 それでも、必死に気を取り直して銅メダルを確保した谷選手、あんたは偉い! 本人にとってはちっとも嬉しくないかも知れないけれど、その欲しくもないメダルをとる気力だけでも、称賛に値すると思いますね。素晴らしい。 一方、男子の平岡選手・・・。試合後半に一瞬、十字固めが決まりそうになったけれど、あれを逃したのが一生の不覚。緒戦敗退となってしまいました。この階級は野村選手の階級ですから、「やっぱり野村を出しておけば・・・」と言われるだろうし、彼はこれから随分、いやな思いをしなければならなくなるでしょうね。気の毒ですなあ。日本代表選手になるってのは、名誉なことではあれ、辛いことの方が多いような感じがしますね。 というわけで、特に節穴審判の不当な判断による谷選手の準決勝敗退に、釈迦楽家にも何となくどんよりとした無念感が漂っておりますが、まだまだオリンピックは始まったばかり。各選手には健闘を期待したいものでございます。
August 9, 2008
コメント(8)
-
サザン30周年
今日、夕食後、何となくテレビを見ていたら、どこかの歌番組でサザン・オールスターズの特集をしていて、つい最後まで見てしまいました。デビュー30周年、そして予定されている「活動休止」間近ということでの特集なのでしょう。 それにしても、30年か・・・。 彼らが「渚のシンドバッド」でデビューした頃、私は中学生くらいでしたけど、「何だかチャラチャラしたのが出てきたなあ」という程度の認識でした。要するに、全然認めてなかった、ってことですな。歌詞にしても何言っているか分かりませんでしたし。ま、友人たちは割と面白がっていましたけど、私はもうその頃から筋金入りの洋モノ・ロックファンでしたから、日本のバンドなんてそもそも目もくれず。ですから、まさかあのチャラチャラしたバンドがその後30年も頑張り続けるなんて、想像もできませんでしたね。その点では、私に先見の明がなかったことを認めざるをえません。 しかしあれから30年。その間、特にスランプに陥ることもなく、ずっと一線で活躍していたのですから、大したものです。その活躍の長さたるや、荒井(松任谷)由美のそれ以上。ましてや、サザンと同じ頃デビューして人気のあった「ツイスト」なんてバンド、もう記憶の彼方でしょ。30年トップを走ったバンドなんて、日本の歌謡史を見渡しても、他にいるのでしょうか? すっかり大御所になって、3年に1遍くらい新曲を出す、というような形で長く命脈を保った人は以前にもいたでしょうが。 結局、桑田佳祐の特異な作詞能力とメロディーメーカーとしての破格の実力のなせる業、なんでしょうな。日本のバンドにほとんど興味のない私ですら、彼の曲は否応なく耳にのこりますからね。 特に、ラップだか、ヒップホップだか、昨今のメロディーのない曲(というと矛盾ですが・・・)の流行にはほとんど左右されず、一貫してメロディーを書いてきたところが桑田氏の偉いところなんじゃないかしら。やっぱり、メロディーは歌の命ですからね。メロディーに乗せて、記憶というものは蘇るわけだし。 ということで、サザン・オールスターズの名曲メドレーを聴きながら、大したもんだなあと思いつつ、30年前のことなんかもぼんやり思い出していたワタクシだったのでした。それにしても彼らの「活動休止」っていうのは、一体どういう意味なんですかね・・・。
August 8, 2008
コメント(2)
-
ミッドランドスクエア参上!
今日は名古屋の駅前、ミッドランドスクエアなるところにショッピングに行って来ました。 名古屋駅前再開発の一つの目玉であるミッドランドスクエア、もう完成してから1年以上経つのかな? でも、私がここを訪れるのは初めて。情報キャッチは早いが、行動が遅い。それが釈迦楽家の伝統なのでありまーす。 で、なんで今さらミッドランドスクエアか、と申しますと、ここのテナントに「ヴァルカナイズ」というセレクトショップがありまして、ここが「グローブトロッター」のバッグを専門に扱っているからでございます。先日、名古屋・栄のザ・コンラン・ショップでグローブトロッターのアタッシェケースを見て以来、やっぱり買うしかないかと思い、どうせ買うなら専門店で買おうということになったんです。 ちなみにグローブトロッターのバッグは「ヴァルカン・ペーパー」という特殊加工した紙でできているのですが、「ヴァルカナイズ」というセレクトショップの名前も、多分、この紙からとったのではないかと。 さて、お店に入ってみると、あるある、グローブトロッターのバッグがあれこれと。で、前に目をつけておいたアタッシェケースを見せていただいたのですけど、やっぱりカッコいいねえ。これに決めたっ! ・・・と思ったら、私が欲しいサイズのものは紺色のしかないという・・・。もともと黒いのにしようと思っていたので、ちょっとガッカリ。 で、紺色のでもいいか、と一度は思ったのですが、さんざん悩んだ末、やっぱり黒い色のアタッシェケースの実物を見てからどちらにするか考えることにし、今日は買わないでおくことにしました。せっかく高いものを買うのですから、100%好みに合ったものを選びたいですからね。 ということで、私の当てはとりあえず外れてしまったのですが、せっかくここまで来たのだし、家内の誕生日が近いということで、次に家内が欲しがっていた新しいお財布を見ることにしました。で、家内と一緒に色々見た結果、ケイト・スペードのものを買うことに決定! いや、気に入ったものがあって良かった、良かった。 しかし、それにしてもこのミッドランドスクエア、いわゆるブランドショップが目白押しですな。ヴィトンにディオール、カルティエにロエベ、ショーメにセリーヌ、バカラ、それから・・・レクサスか。1階フロアに「ヴァンクリーフ&アーベル」のテナントもあったので、ちょいとウィンドウショップしてきましたけど、ウィンドウに置いてある時計が、一個1千万単位ですもんね。ひゃー、こんなの誰が買うんだろう? で、そういう高級ブランドの商品を見ながら思ったのですが・・・、ひょっとしてワタクシ、こう見えて買い物、好きかも・・・。いつか一度、こういうブランドショップの立ち並ぶところで、「これでもかっ!」という位、買い物してみたいという願望が、なくはないですね。ま、そういう身分になれる可能性は、宝くじが当選する確率と完全にイコールなんですけど、それはそれとして。無論、ブランド品の満艦飾というのはイヤミですけれど、結局、いい品物だから高級なのでありまして、いい品物が欲しいという願望は、あながち否定すべきものではないのではないかと。ですから「ブランド品志向」というのを、ワタクシは必ずしも悪いとは思わないんです。 ただ問題は、その「悪いと思わないこと」を実行に移せないということでございまして。 ま、それでも今日はささやかなものとはいえ、家内の誕生日のプレゼントとして「ブランド品」を買いましたからね。庶民としては大満足でございます。 というわけで、その戦利品を大事に抱え、ニコニコしながらミッドランドスクエアを後にした我ら夫婦だったのでありました、とさ。今日も、いい日だ!
August 7, 2008
コメント(2)
-

ジェフリー・ディーヴァー『The Twelfth Card』を読む
先日来、すっかりファンになったジェフリー・ディーヴァーですが、私にとって『The Cold Moon』に続いて2冊目となる『The Twelfth Card』という作品を読みきってしまいました。 さて『12番目のカード』なる作品ですが(以下、若干のネタバレ注意)、冒頭、ニューヨークの図書館で自分の祖先のことを調べていた黒人の少女ジニーヴァ・セトルがレイプ狙いの暴漢に襲われそうになるところから物語は始まります。ところがこのジニーヴァという子がなかなかはしっこい子で、見事暴漢の裏をかき、まんまと襲撃を逃れてしまうんです。 が、これはどうも単なるレイプ目的の襲撃ではなかったらしいんですな。その証拠に、犯人は大胆にも犯行現場の図書館に戻ってきて、捜査協力をしていた司書を銃撃して殺害、さらに一旦仕留め損なったジニーヴァ・セトルを再度襲うため、刑務所を出所したばかりの黒人のならず者を雇い入れ、彼を使って2度目の襲撃まで試みます。 一方、この事件を担当することになった車椅子の名探偵リンカーン・ライムは、腕利きの証人ガード専門官たるローランド・ベルを使ってジニーヴァをガードする一方、犯人がなぜそれほどまでに貧しい黒人少女の命をつけ狙うのか、その理由を探っていく。そしてその謎を解く鍵は、今からおよそ140年前、アメリカ南北戦争直後の黒人解放運動で活躍したジニーヴァ・セトルの祖先、チャールズ・シングルトンの謎めいた行動にあるらしい・・・。 とまあ、そんな感じのサスペンスですね。 でまた、この小説には上で述べたドラマとしての筋書きの他にもう一つ読みどころがあって、それは「麻痺」をめぐる物語なんですね。事件を追う探偵のリンカーン・ライムは、もちろん四体麻痺に悩んでおり、色々とリハビリに取り組んではいるものの、内心では「果たしてこんなことをしても無駄なのではないか、自分はいつまで経ってもこのままなのではないか」という疑念と格闘している。 一方、犯人のトンプソン・ボイドはというと、こちらは精神的な麻痺に悩む男なんですな。子供の頃のトラウマのせいか、それとも長年死刑執行官という職業に就いていたことのツケが回ってきたためか、ボイドという男は人間性が完全に麻痺しており、人を殺そうが何をしようが、まったくなんの感慨も抱けない状態になってしまった。しかし、この状況から彼は何としても逃れ、再び普通の人間らしい感情を抱きたいと念じている。彼もまた、心の麻痺状態からの再生を願ってもがき苦しむ男なんです。 ですからこの小説には、「追う側と追われる側の双方が、共に麻痺と戦う男だった」という側面があるわけ。そこがまた、いいところなんですな。ね、面白そうでしょ? で、確かに面白いのですが、そうですね、正直なところを申しますとね、私が最初に読んで虜になった『The Cold Moon』と比べてしまうと、ちょっとサスペンスの度合が低いかな・・・。『The Cold Moon』の方が2ページに1回ハラハラするとすると、こちらの作品は10ページに1回ハラハラする、みたいな感じ。どちらをより強力に薦めるかといえば、圧倒的に前者です。やはり、もしディーヴァーのサスペンスに興味があるならば、まずは『The Cold Moon』の方から読まれることをおすすめします。 しかし、ちょっと不思議に思うのは、ディーヴァーのタイトルの付け方ですね。あれだけストーリーを構成するのがうまいディーヴァーなのに、なぜかタイトルの付け方だけは下手だなあ! 『The Cold Moon』にしても、邦訳のタイトルである『ウォッチメイカー』の方がよほど内容を的確に表していますし、本作『The Twelfth Card』にしても、登場するタロットカード自体は作品中であまり大きな意味を持つわけではないので、もっと別なタイトルの付け方があったのではないかと思うのですが・・・。 さてさて、かくのごとく2冊のディーヴァーものを読んでしまった私ですが、実はもう3作目を読み始めているのでございます。今読んでいるのは『The Coffin Dancer』という作品。噂によると、本作はリンカーン・ライムを主人公とした作品の中でも傑作の誉れが高いそうで、まだ最初の20ページほどしか読んでいないものの、出だしはなかなか好調です。 というわけで、この夏はどうやらディーヴァーのサスペンスで明け暮れようとしているワタクシの読書ライフなのでありました、とさ。これこれ! ↓The Coffin Dancer
August 6, 2008
コメント(2)
-
追悼・ソルジェニーチン
英語に「gulag」(グーラグ)という単語があるんですが、これ「強制収容所」という意味で、その語源はロシア語。もちろん、ソツジェニーチン氏の小説『収容所列島』のタイトルから来ているんです。 英語に「グーラグ」という言葉を定着させたそのロシア作家・ソルジェニーチン氏が、ついに亡くなりましたね。しばしば「19世紀的作家」という、褒めているんだか「古い」と貶しているのかよく分からないタイトルをつけられることの多い作家ですから、21世紀まで生き延びたということ自体、象徴的には3世紀をまたがって生きた作家、というような感じがします。 もっともお恥ずかしい話ながら、私は彼の作品を一つも読んでいないという・・・。彼の主要作品の持つ「共産党批判」というコンセプトが、若き日の私にとってすら時代遅れに感じられたことに加え、「20世紀のドストエフスキー」的なキャッチフレーズも、「だったら本物のドストエフスキーを読むわ」という、売り言葉に買い言葉的な意味のない反発を私の中に生じさせたんですな。 かくして大学生くらいの時に、何度か「読んでみようかな」くらいは思ったものの、そのままにしてしまった・・・。ソルジェニーチン氏の作品みたいなものは、それこそ20代の早いうちに勢いで読まないと意味がないような気がするので、そういう意味では、私は氏の作品を読み損ねたのかも知れません。今の私の年になってから、あらためてじっくり、というのは、ちょっと厳しい気がしますね・・・。ま、先のことは分かりませんが、今のところ、私には縁のなかった作家、ということになりそうです。 しかし、それはそれとして、氏の経てきた大変な生涯を思えば、「巨星、墜つ」という感慨があることも確か。氏のご冥福をお祈りいたします。 さて、今日の私ですが、またまた朝方、妙な夢を見まして。 事情は定かでないものの、とある幼稚園のPTAに招かれ、幼稚園児とその父兄の集まりの前で「アメリカにおける放任主義について」という題目で講演をする、ということになったんです。 で、当日、会場に行ったわけですが、講演開始まであと10分という時点で、原稿を打ち込んだパソコンを家に忘れてきたことに気がついた。やばい! と思ったものの、取りに帰るだけの時間はありません。もう、このままぶっつけ本番でやるしかない。 で、幼稚園児とその父兄たちが居並ぶ講演会場で演台に拍手で迎えられた私は、覚悟を決めて即興で講演をすることにした、と。 「皆さん、今日はお招きいただき、ありがとうございます。さて、『アメリカにおける放任主義』ということですが、折しも今、アメリカでは大統領選挙の真っ最中ですね。アメリカでは選挙というと民主党と共和党の一騎討ちですが、民主党というのは『大きな政府』を目指すものでありまして、政府の権限を強化し、何でも政府主導で社会のあり方を統制して行こうとするものであります。一方、共和党はと言いますと、こちらは逆に『小さな政府』を目指す党なので、政府が余計な介入をしなければ、社会というのは自然とうまくバランスをとっていくものだ、というコンセプトを持っている。つまり、『放任主義』なわけですね。このようにアメリカには放任主義と統制主義という二つの柱があって、社会全体が振り子のように、この二つの柱の間を代わりばんこに行ったり来たりする。そういう社会なのであります。」 と、ここで盛大な拍手。父兄はもちろん、幼稚園児までも私の話に引き込まれている様子。 しかし、ここで私のネタは早くも尽きたのでありまして、「さて、このことをもう少し、私の専門であるアメリカ文学に引きつけて申しますと・・・」と言ったきり、何を言ったらいいのかさっぱり分からなくなってしまった。で、期待に満ちた目で私の次の言葉を待ち受ける幼稚園児&その父兄と、言葉に詰まった演台上の私が互いにお見合いをしながら、放送事故のように1秒、また1秒と、沈黙の時間が過ぎ去っていく、その耐え難い状況に心中のたうち回りながら・・・ 「ふわぁっ!」と叫びながら私は夢から覚めたのでありました、とさ。 それにしても、私の見る夢ってのはどうしてこうリアル、かつ独創的なんでしょうか。アメリカにおける放任主義について、幼稚園児の前で講演するって、一体どういうこと!? 如何に不条理な夢の中とはいえ、どこをどう押したらそういうシチュエーションが出て来るもんですかねえ・・・。もう、わけ分からん!
August 5, 2008
コメント(0)
-

塩味スイーツブーム
どうも今、日本のお菓子界では「塩キャラメル」ブームが来ているようで、新製品が続々ですね。ま、エンジェル係数(収入に占めるお菓子代の割合)の高い釈迦楽家でも、結構頻繁にこの手のお菓子が登場します。 で、最近お気に入りのベスト3はと言いますと・・・ 第3位「キットカット 塩&キャラメル」 まあね、素の「キットカット」自体が抜群に美味しいんですもん。それに塩を混ぜようが、キャラメルを練り込もうが、不味くはできないですなあ。 第2位「小枝:美ら海と大地の恵み 宮古島の雪塩&沖縄産サトウキビ使用赤糖の夏チョコレート 期間限定」 おそろしく長い名前ですが、要するに森永製菓の名作「小枝」のスピンオフですね。でも、これ、かなりイケてます。赤糖の風味がちょっとカラメルっぽいので、それがかすかに塩味の利いたホワイトチョコレートの小枝とマッチして絶妙の味。「期間限定」という言葉にも惹かれます。今のうちですよ~! そして第1位「明治 アーモンドチョコレート 塩キャラメル」 これも定評のあるアーモンドチョコのスピンオフですけど、すばらしい出来です。何がいいって、ただ単にアーモンドをチョコで包んであるのではなく、アーモンドの周りに薄ーいクッキーの層があるんですよね。これがために、パリッ、サクッと噛み砕いていく時の快感たるや、まさに口福。で、かすかな塩味とキャラメル味が、一層、アーモンドチョコの風味を複雑にしているんですよね~。近年の大ヒット。 ということで、このところこれら「塩キャラメル系」のお菓子が我が釈迦楽家の冷蔵庫から絶えることがないのでありました、とさ。どれも教授のおすすめ!です。これこれ! ↓明治アーモンド塩キャラメル 10コ入り6月~8月限定販売6月24日新発売小枝<美ら海と大地の恵み>5個入
August 4, 2008
コメント(6)
-
追悼・赤塚不二夫
随分以前から身体の具合が悪いとは聞いていましたが、ギャグマンガの祖、赤塚不二夫氏がついに亡くなりましたね。享年72歳。今日的基準からすると早過ぎる死でした。 赤塚不二夫氏というと、まずは『天才バカボン』なんでしょうが、私はあの漫画にはほとんど縁がなく、アニメ版もほとんど見たことがありません。というか、そもそも赤塚漫画そのものにあまり興味がなく、強いて言えば子供の頃、テレビで『おそ松くん』を見ていたことを覚えているくらい。あと『もーれつア太郎』かな・・・。『秘密のアッコちゃん』も見ましたが、横山光輝の『魔法使いサリー』の方が好きだった。 ですから、私は赤塚不二夫の善き読者ではないんです。ま、私は手塚治虫氏をはじめ、トキワ荘系の漫画家の作品とは何故か非常に相性が悪いもので。 しかし、そういうこととは別に、私と赤塚不二夫氏を結びつけるものがあるとすれば・・・ そう、「シェー!」ですね。「イヤミ」なるキャラクターがどうかした時に発する意味不明の叫び声とポーズ。私の子供の頃の写真(当然、白黒)を見ると、そのほとんどすべてで「シェー!」のポーズを決めています。そして多分、これは私だけのことではなく、少なくとも私の同世代の、つまり40代半ばの人間なら全員そうだと思います。 赤塚不二夫という漫画家は、ああいう「イヤミ」のような特異なキャラクターを生み出すのがそれだけ上手だった、ということなんでしょう。実際、赤塚氏が考え出した妙なキャラクターの数の多さはスゴイですよ。「イヤミ」の他にも「レレレのおじさん」、「ニャロメ」、「うなぎ犬」、「ケムンパス」、「目のつながったホンカン」、「ベシ」、そして「バカボンのパパ」と、数え上げたらキリがない。 そういう意味でも、我らは異才の漫画家を失った、ということになりましょうなあ・・・。 善き読者ではなかったとはいえ、私の幼少の折の写真をすべて「シェー!」にしてしまった赤塚さんが亡くなったと聞いて、また一つ、昭和が遠くなったなあ、という感慨があります。 赤塚さん、どうぞ安らかに。天国に居る神様ってのは案外、「レレレのおじさん」みたいな風貌かも知れませんよ!
August 3, 2008
コメント(4)
-
読みたい雑誌がないざます!
一般に、私くらいの世代の男というのはどのような雑誌を読んでいるのでしょうか? ちなみに私はと言いますと、何しろクルマが好きなもので、クルマ関係の雑誌はあれこれ読みます。が、クルマの雑誌にも色々ありまして・・・。 例えば老舗と言っていい『NAVI』。ま、これは確かにクルマの雑誌で、扱うのは国産車・外国車問わず。ただ、クルマ以外のことが載っていないところと、やや内容が俗っぽいところが私としてはいま一つ、というところでしょうか。一方、これが『モーターマガジン』とか『CG(カー・グラフィック)』になりますと、俗っぽさがなくなる代わりに、よりメカ好き御用達みたいになってしまって、それはそれでどうなのか、というところがある。 で、クルマのことと同時にライフスタイルのことも載っている雑誌として、私が買うことが多いのが『エンジン』ということになるわけですが、これがまたやたらに上級嗜好の雑誌で、特集するクルマのほとんどが1000万円級。私の好きな外車中心ですから、私としては涎を流しながら読んでしまうのですから、結局、ここに載っているクルマに自分が乗ることは一生ないんだろうなあと思うと、涎だけじゃなくて涙も流れてしまうという・・・。あと、この雑誌には「クルマ好きは時計好き」という決めつけがあるらしく、確かに私も時計好きではありますが、それにしても高級時計のページがあまりに多過ぎるのもどうかと思います。ようやく最近、オーディオのことなんかも取り上げ始めましたが、そういうのも含めてもう少し幅広いモノを扱って欲しいですなあ。 またその他としては『Pen』だとか『エスクワイア』だとか、はたまた『カーサ・ブルータス』や『エル・デコ』なんかも買うことがありますが、これは特集に興味があるかどうか、ですね。日本版『PLAYBOY』もたまに食指を動かされる特集をすることがありますが、あれはいまだにセンター・フォールドがあるでしょ。40代にもなってセンター・フォールド付の雑誌を買うのもちょっと、ねえ・・・。と思っていたら、この雑誌、廃刊らしいですね。結局、「プレイボーイ」という人種が日本には居なかった、ってことかな。 というわけで、なかなか自分の趣味・関心にドンピシャリという雑誌がないのが悩みの種。誰か、クルマと文房具と時計と美味しいものと別荘ライフと美術とオーディオとジャズを毎回扱う雑誌を、誰か作ってくれないかしら。 が、「読みたい雑誌がない」という悩みは、男性よりもむしろ女性の方が深刻なようで、私の家内に言わせると女性誌というのも、なかなか選択が難しいらしい・・・。 例えば彼女は今、『オッジ』とか『ミス』とか、まあその辺の雑誌を愛読していますが、女性誌というのは男性誌と違って、「扱うテーマ」で読者を選ぶのではなく、「年齢層」で想定読者を輪切りにするものでありまして、今挙げた『オッジ』や『ミス』はせいぜい30代前半くらいまでが対象ですから、この年齢を越すと、別な雑誌に乗り換えなくてはならなくなります。 ところが家内に言わせると、この年齢を過ぎると、もはや乗り換える雑誌がない、というわけ。 例えば『オッジ』の読者が30代半ばを過ぎると、業界の思惑的には『ドマーニ』を読む世代になるわけですが(イタリア語で『オッジ』は「今日」、『ドマーニ』は「明日」の意)、実際のところ『ドマーニ』というのはキャリア向け雑誌でありまして、齢30代半ば、いよいよ中間管理職的な地位に付き始めたキャリア女性のファッションがテーマになる。 ところが、『オッジ』の読者の大半がキャリア組になるわけではないわけでありまして、例えば30歳前後で結婚して主婦になった女性が、『ドマーニ』の提案するキャリア・ファッションなんかを見ても、参考にならんのですな。主婦は企業の戦略会議なんかには出席しませんからね。 じゃあ、ってんで、その時点で「主婦向けファッション誌」に切り換えたとしましょう。例えば『LEE』なんかがその代表です。 ところがですね、『LEE』というのは、いわゆる「子持ち」の、かつ「ナチュラル志向」主婦を想定読者にした雑誌でありまして、この雑誌が提案するファッションというのは、いかにもナチュラルな生成りベージュの服だったり、子育て真っ最中の女性にぴったりなヒールのないペッタンコ靴だったりする。『オッジ』読者からの移行組にしてみれば、「何だか急に所帯染みちゃったナ・・・」という印象があるわけですよ。現実世界に引き戻されるというか、夢を売る雑誌じゃないんですな。 で、それはどうかってんで、『VERY』に行くとしますと、これはまた逆に「おハイソ主婦向け雑誌」でありまして、「1万円ランチをするならこのお店!」みたいなイヤラシイ特集があったりする。と、一体どこのどいつが1万円のランチ食ってるんだ、って話になるわけですわ。 というわけで、『オッジ』的な雑誌を読んできた女性が、30代後半を迎える頃になって次に乗り換える女性誌がないんですな。実際、家内の世代の女性が集まると、「雑誌、何読んでる?」という話題がよく出るそうで、それだけその世代の感性にぴったり寄り添う雑誌がない、ということなんでしょう。つまり、30代半ばで主婦だけど、その年齢にあった洒落たファッションをしたい、という女性向けの雑誌がスッコーンと抜けている。 ま、それを突き抜けた後には、もしかして『主婦の友』とか、そういうのが待っているのかもしれませんけどね・・・。 それは冗談として、男性雑誌にしても、女性雑誌にしても、なかなか「コレ!」というものがない、ということですな。この状況は雑誌出版社の市場調査の至らぬところであり、また逆に言えば、大きなチャンスでもあるんじゃないかしら。特に女性誌の場合は、雑誌の空白部分にすごく大きな読者層があるんですもん。 ということで、雑誌出版社にお勤めの皆さん。もしこれを読んでいたら、早速企画会議を開きなさい。そして私と私の家内を、アドバイザーとして招聘しなさい。悪いようには、しませんよ~!
August 2, 2008
コメント(12)
-
トウモロコシの味
トウモロコシの最盛期なのか、先日スーパーで2本100円で売っているのを見かけました。もちろんゲットして茹で、夕餉の一品に添えましたけど、やはり旬のものだけあって美味しかったですね。 トウモロコシというと、子供の頃に住んだ家のことを思い出します。その家はかなり広い庭があったのですが、私の両親は当時、庭いじりなどする方ではなく、ほんとに自然のまんま、雑草も生え放題という状態でした。今から考えると、むしろイングリッシュ・ガーデンの趣があってなかなか風流なものでしたが、周辺の家にお住まいの方から見れば、我が家の庭だけ手入れのしてない原始の状態で、さぞご迷惑だったことでしょう。 で、そんなある時、近所の方から「家庭菜園でもしてみたらどうか」というサジェスチョンをいただいたんですな。で、それはひょっとすると、「どうでもいいけど、少しは雑草でも刈りなさい」という意味だったのかも知れませんが、人の言葉を疑うことを知らぬ我が両親殿は、この示唆を真に受け、庭の一部をささやかながら耕し、そこに何を思ったかトウモロコシを植えることにした、と。家の西側の窓辺一杯、10メートルほどの長さに一列だけ植えた、というのですから妙な具合です。 しかも、種を植えたはいいが、その後の世話は一切見ないという完全放置主義。 それでも、直に芽が出て、そして弱々しいながらも少しずつ大きくなって行ったと思って下さい。そして幼稚園生くらいだった私の背丈もついに越し、ヒマワリほどの高さになったと。まるで一列に並んだ兵隊さんのようです。 で、そうこうしているうちに、ついに実がなった。子供心に、ははあ、トウモロコシとは、このように実がなるものであるかとビックリしたことをよく覚えています。 で、ある夏の一夕、それを収穫して食べたんです。ま、もちろん肥料も何も与えていないので、実そのものは貧弱なものでしたが、それでも一応トウモロコシだと分かるようなものが、我が釈迦楽家初の自給野菜として食卓に乗った。それはもう一大事なわけで、その日のことは今でもよく覚えています。何しろ、もともとそういうのに興味のない我が家のこと、野菜を育てるなんて、結局そのトウモロコシの一回だけで終わってしまいましたから、まさに空前絶後の思い出なんですね。 そんな時代もありましたなあ・・・。我が釈迦楽家自体、若かった。父も母も若かった。 さて、そんなことを思い出しながら、今、トウモロコシを食べてみると、このウン十年の間にトウモロコシというものの色や味や食感が随分変わったものだと痛感させられます。昔はねえ、トウモロコシの実というのはもっと濃い黄色で、もっと縦長で、もっと堅いものでしたよ。今どきのトウモロコシなんて、まるで生っ白くて、横長で、柔らかくて、そしてやたらに甘いですもんね。これも、時代の嗜好なんだろうなあ。 でまた、そういうトウモロコシ自体の変化のせいか、トウモロコシの茹で方も昔とは違うようで、昔はグラグラ沸騰したお湯にトウモロコシを入れて、それこそ15分も20分も茹でたような気がしますが、今は水から茹で始め、沸騰後3分で火を止め、そのまましばらく冷ますだけでいいんだそうですが、その辺も何だか納得できないというか、軟弱になったなあ、という気がします。 とはいえ、こちらも大分年をとってきましたので、最近のトウモロコシの柔らかさ、甘さも歓迎しないわけじゃないですけどね・・・。 というわけで、トウモロコシを食べる度に、昔のこと、とりわけ今までに経てきた色々な夏のことを思い出します。この野菜だけは、まだ夏の季節との結びつきが十分に残っているからでしょうか。
August 1, 2008
コメント(2)
全31件 (31件中 1-31件目)
1










