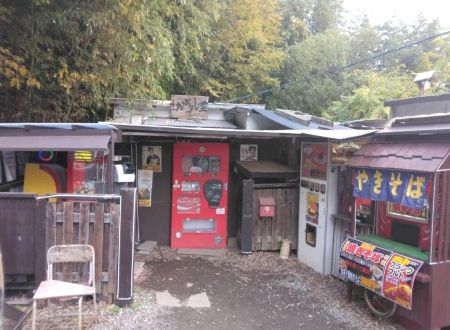2005年10月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
四種曼荼羅の話3
そして、種字曼荼羅というのは「本尊を表す梵字の一音節字(種字)と、秘密にして真実の語句(真言)」(空海コレクション2 P75)といわれています。本尊様の梵字のみで描かれた曼荼羅です。これも描かれた曼荼羅に限らず、ありとあらゆる音に代表される波のどの力で現れてきます。最後に羯摩曼荼羅は「もろもろの仏・菩薩のさまざまのあり方や働き」同書です。すなわち、生き物を生かしている何か不思議な働きがこれにあたります。この世の中のすべてのものは、以上に述べたような4つの現れ方をしています。1つ目は生き物、2つ目は生き物ではないもの(と思われているもの)3つ目は音に代表される波などの力、4つ目は生き物を生かしている何かの力です。その元になっているのが六大です。この世の中は、六大が4つの現われ方をしている、と定義することができます。 素光参考文献 空海コレクション2 宮坂宥勝監修 ちくま文芸文庫
2005年10月31日
コメント(2)
-
四種曼荼羅の話2
四種類の曼荼羅のうち、大曼荼羅というのは佛、菩薩の姿を現したものであります。ところで密教には四種法身という考えかたがあります。法身というのは仏教の始祖である釈尊を生身の肉体を持った覚者(色身)として、その釈尊をそう導いた本体の教えが法身であるという考えかたです。その法身が4つの現れ方をします。1つ目はさとりの本体として(大日如来)2つ目は悟りを他に広めるものとして(他の佛・菩薩)3つ目は歴史的に出現する仏として(釈尊)4つ目は現実に生きている私たちです。私たちが仏であるというのはちょっと信じがたいことですが、何らかの理由によって存在していることは事実です。私たちだけでなく、すべての生き物が理由があって存在しています。それゆえ大曼荼羅というのは私たちすべての生き物が現れていることをさしています。次に三昧耶曼荼羅というのは法具や仏様が持っている持ち物(蓮華など)によって描いてある曼荼羅です。こちらも、持ち物や法具だけに限りません、この世の中の物すべてが理由を持って存在しています。すなわち生き物でないものはすべてこの三昧耶曼荼羅として現れます。 素光参考文献 空海コレクション2 宮坂宥勝監修 ちくま文芸文庫
2005年10月30日
コメント(0)
-
通夜の話
昨日喪主さんがお寺へ葬儀の打ち合わせに来られました。そのときに、お通夜ではどんなものを用意したらいいですか?と聞かれ困りました。お軸をかけて、お供えをしてもらったらいいです、と答えたました。すると「具体的にはどんなものを」と言われ困りました。昔はそのあたりの準備は近所の年寄りに聞いてしていたのでしょうが、最近は仕事を休んでまで近所の葬式の手伝いをすることは、あまり無い様でかなり年配の方でも存じない方もいらしゃるようです。とりあえずお通夜にお伺いして不都合があったらそのとき考えましょう、と答えておきました。お通夜は身内が無くなったという慌しい中で行うものですから、形よりも、まずお供えする気持ちのほうが重要です。わざと、手抜きしたように不完全なお供えをする作法もあるくらいですから、まあ、誰かに言われたら直そうぐらいの気持ち(なかなかそうはいきませんが)で気楽に行ってください。 コウユウ
2005年10月27日
コメント(2)
-
四種曼荼羅の話 1
曼荼羅は最近ではチベット密教が注目されていることもあって一般にも知られるようになって来ました。また、さまざまなものが入り混じっているような場合に「~まんだら」というような使われ方をする場合もあります。本来の曼荼羅の意味は、松永有慶氏によると「壇、集合体、道場、本質を備えたもの、丸い形をしたもの」(密教P157)となっています。曼荼羅はもともと、土で壇を作りその上に描かれていたもので、儀礼が終われば取り壊されいました。それが中国に渡り紙の上に描かれるようになったと言われています。真言宗の道場では金剛界、胎蔵界の2種類の曼荼羅が掛けてあります。金剛界曼荼羅は金剛頂経、胎蔵界曼荼羅は大日経というお経に基づいて描かれています。この2種類の曼荼羅については、またの機会にお話します。さて、弘法大師の即身成仏義によると曼荼羅には4種類あります。大曼荼羅、三昧耶曼荼羅、種字曼荼羅、羯摩曼荼羅です。 素光 参考文献 密教 松長有慶 岩波新書
2005年10月27日
コメント(0)
-
八戒の話
宗教の信者になることは、すなわちその宗教の精神にしたがって生きていくということです。すべての宗教にはそれぞれ決められたことがあります。仏教にもありそれが戒律です。日本ではあまり出家者(僧)も一般の信者もこの戒律を重視していませんが、戒は仏教の三学の一つであり、まず戒を守り、定(静かな瞑想)によって悟りに至る知恵が生まれてくる、といわれています。ですから、一般信者にとっても戒を守ることが大切になってくるのです。といっても出家者の戒は250といわれておりとても守れるものではありません。(言い訳ではありませんが、250戒は古代インドで決められたために現在の日本では守ることが不可能な戒も多くあります。)そこで、一般信者は五戒というものが定められています。1、生き物を殺さない。2、盗みをしない。3、みだらな性交をしない。4、うそをつかない。5、酒を飲まない。お酒に関しては日本では規制されるのが不思議ですが、1~4までの行為をしやすい状態になりやすいからでしょう。さらに、八戒というものがあります。これは、先の五戒に加えて6、午後食事を取らない。7、観劇、化粧などをしない。8、広く大きな寝床で寝ない。の三つを加えたものです。この三つはちょっと理解しがたいかも知れませんが、一言でいえば禁欲生活をすることによって宗教的境地を高めることです。この八戒は守るべき日が決まっており、8日、14日、15日(旧暦の半月毎)となっております。今日は下弦(8日)です。せめて心だけは、八戒を守るように心がけましょう。 素光 参考文献 戒律の思想と歴史 上田天瑞 密教文化研究所
2005年10月25日
コメント(0)
-
五鈷杵を忘れた話
先週から、愛用の五鈷杵(ごこしょー写真下)が行方不明になっていました。いつも一緒にしている散杖(さんじょう)と洒水器(しゃすいき)はあるので、どこかに置いたのだろうかと思い、捜し回りますが見つかりません。五鈷杵というのは密教の法具でもともとは、インドの武器をかたどったものです。最近では、チベット密教の影響か時々魔よけとか幸福を招くものとして一般にも売られているようです。それはさておき、真言宗では加持や結界のときに使います。洒水器の香水を加持するとき、通常は五鈷杵で数珠をこするので音が出ます。無くても手印でいけますが、音が出ないと手抜きしていると思われかねませんので、やはり、無くては困ります。ひょっとして、法事をしたお宅に忘れたのではとも思いましたが、忘れたら持ってきてくれるか電話ぐらいあるのでは、と甘く考えておりました。しかし連絡はありません「商売道具を忘れました」とは言いづらいのですが電話してみました。すると「ありますよ」との答え。どうやら、誰の物か判らなかったようです。持ってきて呉れると先方は言いますが、こちらの手落ちです、すぐに取りに行きました。よかったと思いましたがただもう反省した一日でした。 コウユウ
2005年10月24日
コメント(1)
-
地蔵講
今日は月例の地蔵講の日です。当院の本尊様の地蔵菩薩様にちなんで毎月23日の2時から行っております。本来お地蔵さんの縁日は24日です。法要を行う場合は23日の宵か、24日の午前中に行います。午前中は何かと忙しいので、23日の宵の分を前倒しして、2時から行っています。まず、私が略式の祈願(参拝者の先祖供養、家内安全、所願成就)を行い、その後で仏前勤行次第を唱和します。まず礼拝から始まり、懺悔(さんげ)、三帰、三境、十善戒、発菩提真言、三摩耶戒、と続き、開経偈、般若心経、観音経偈、理趣経偈、舎利礼文、諸真言、祈願文、回向まで約25~30分くらいです。そのあと一応法話をしてお茶をいただきます。いつも困るのが法話です。この文章を読んでいただいたら判るように、あまり話をするのは得意ではありません。お葬式や法事は何種類かの話をまわしていますが、こちらは毎月なので、当日に焦って本棚をひっくり返して考えます。ところが初めての話は途中で忘れてしまったりして、しどろもどろになることがたびたびあります。そんな状態ではありますが、毎月楽しみに来てくれる人があるのはありがたいことです。 コウユウ
2005年10月23日
コメント(2)
-
法事の話ー自宅法要のすすめ
今日は10時からお寺で檀家さんの回忌法要がありました。準備に大忙しでした。最近お寺で回忌法要をされる方が増えてきているようです。自家用車で来られる方が増えたため、駐車場の確保が難しい(特に都市部)とか、また住宅の形が昔と違い多人数が入る部屋がない、とかの理由もありますが、最も大きいのは法事の準備をするのが面倒らしいということです。本来、法事(葬儀も同じです。)は自宅でするものです。なんで、という人は自分に質問してください。あなたが死んだらお寺へいきますか?残るとしたら自宅ではありませんか?それでも、自宅ですると、親戚が来て疲れる、用意が大変という方はには、考えていただきたいのです。実は自宅で法要をすると功徳があるんです。1つには掃除ができること。掃除が面倒な人も多いでしょうが、法事に来る人のためと思わず、自分をきれいにするチャンスと思ってしましょう。2つには人が来ることは原則として吉相です。気の入れ替えのためにも多くの人に気持ちよく来ていただきましょう。3つにはお経を唱えて邪気払いができます。最近は法事で檀信徒向けの勤行次第をお唱えすることも多いので、よりいっそうの効果が期待できます。以上の3つにより自宅法要のメリットがお分かりいただけたでしょうか。 コウユウ
2005年10月22日
コメント(0)
-
六大の話3
密教では、形あるものとしての五大があります。これは、塔婆や五輪塔にある地、水、火、風、空と呼ばれています。たとえば、木を燃やすとまず(火)となり、煙(風)が出て燃えかすは(水)に溶け土(地)に還ります。それ以外のものとして、(空)を置きました。ただし、この五大は構成要素ではなく、形あるものを代表するシンボルのようなものであります。それに対して、生きているものを、生かしている物質以外の何かが識大です。この識大と五大を加えたものが六大と呼ばれています。この六大によりこの世の中のものはすべてできているのです。さて、この六大によりこの世の中が、どうできているか。それは、四種曼荼羅の話でお話します。 素光
2005年10月21日
コメント(0)
-
今日は御影供2
今日は新暦(という言い方はおかしいかな?)の21日です。弘法大師の月命日です(祥月命日は3月21日)。御影供という法要がありましたのでいって来ました。11時に集会で始めます。まず禮文という懺悔(仏教ではさんげと濁らずに読みます)の文に節をつけて読みます。続いて理趣経をお唱えし、次は讃という仏様を讃嘆する文章に曲が付いたもの(声明という仏教音楽です)を行います。最後に般若心経3巻にいくつかの真言を唱えて終わりです。ほぼ毎月近隣の寺院が持ち回りで行っています。1200年経っても毎月命日を祀られる弘法大師の遺徳は大変なものがあります。 コウユウ
2005年10月21日
コメント(1)
-
六大の話2
昨日の話の続きです。ここに1本の木があります。この木の枝を切ります。切った枝を挿し木にすることは可能でしょう。さらに枝の皮を剥いた状態でも挿し木にすることは難しいかも知れませんが、培養することは可能です。ところが、皮を剥いた状態で1年も置いておくと培養することもできないでしょう。世の中にたくさんの木製品が出回っていますが、その木から挿し木をする人はいません。では、その木はいつ死んだのでしょうか。そして、生きている状態と、死んだ状態、その境があるとしたら物質的には全く同じはずです。木を例にあげましたが木だけではなくこの世のすべてにいえることです。さらに、可能性を言えば生きていないとされるものに対しても生というものを与えることが、できるはずです。いわゆる御札がそうです。 素光
2005年10月20日
コメント(0)
-
六大の話
現代では量子力学により、素粒子というものが考えられていますすなわち、人間もその他の生き物もさらにはこの世の中を作り上げているすべてのものが、じつはどんどん細かくしていくと素粒子という同じものでできている、というのです。これは驚くべきことで、人間が自分の体と思っているもの(部分)とそうでないほかのすべてのものには密度に違いがあるだけで境というものはないのです。では、なぜ人間は自分の体と思っているもの(部分)を自由に動かせるのでしょうか。こんなことを考えたことはありませんか。また、なぜ生き物は生まれるのでしょう。そして、なぜ死ぬのでしょうか。いわゆる、物質だけを考えていたのでは、いつまで経ってもこの答えは出ません。「六大無碍にして常に瑜伽なり」というのは五大(いわゆる物質)と識大(物質でないもの)が互いに妨げることなく融合した状態で存在していることをあらわしています。 素光
2005年10月19日
コメント(1)
-
月食の日ー続き
昨日、日記を書いてから外へ出てみました。残念ながら雲が広がっており、とても月食を見られるような天候ではありません。月食を見るのはあきらめて、阿字観に入りました。いろいろ思うところもあってなかなか禅定の状態にはなりません。しばらく座っていると心が落ち着いてきます。禅定の状態はその日の体調などに左右されるのでしょうか。深く入り込めるときと、そうでないときがあります。今日はあまりよくありませんでした。しばらく座っていましたが、切り上げました。そしてふと外を見ると、明るいのです。急いで外へ出ると雲の切れ間から月が姿を現しました。わずか5秒ぐらいですぐに雲の中へと隠れてしまいましたが、確かに右下が欠けていたようでした。もし、阿字観を行わなかったら、月食を見ることはなかったでしょう。 素光
2005年10月18日
コメント(0)
-
月食の日
今日は月食です。月食の日は密教では特別な日とされています。虚空蔵菩薩求聞持法と言う行があります。この行法は虚空蔵菩薩の真言を1日1万遍を100日間または2万遍を50日間唱えます。弘法大師が何度も行い、室戸岬で口から明星が飛び込んだたとされています、かの日蓮上人も行ったとされています。この行を始める日または終わる日が食(日食、月食)の日とされています。この虚空蔵菩薩求聞持法は特別な施設(求聞持堂)が必要ですが、全国に10ヶ所程度しかありません(と思います)。今日はその行に臨む人の無事を祈り、終える人に感謝しながら、これから私も阿字観に入ります。 素光
2005年10月17日
コメント(0)
-
とらねこ
とらねこ、生まれてすぐに親と別れました。他の兄弟はよそへもらわれていきました。3年前の交通事故で後ろ足が不自由です。でも、まだ生きています。 ゆうき
2005年10月16日
コメント(0)
-
法事の話4
今日も朝から法事に行ってきました。よく見かけるのですが、お仏壇にお酒、タバコなどがお供えしてあります。先日、高野山に行ったときも、法話で「お酒の好きだった人にはお酒をまつってあげる」と言っているのを聞いて絶句してしまいました。仏教ではお酒は僧侶のみならず、一般信者も飲んではいけません。生きているうちはともかく亡くなった方にお酒を勧めるのはやめましょう。タバコは戒律にはありませんが、やめましょう。 コウユウ
2005年10月16日
コメント(0)
-

自利行と利他行について
仏教の行には自利行と利他行があります。自利行とは文字通り自分のための行で上座部(かつては小乗仏教と呼ばれていました)の仏教がそう呼ばれています。一方利他行というのは自分が救われるよりも、まず他者を助ける行で、大乗仏教の菩薩(修行者)は自分が救われるよりもこちらを重視していました。誤解されやすいのですが、利他行というのはボランティアなどで他者を助けることではありません。もちろん現実に何か行動を起こすことも重要です。しかし、それ以上に広く大きく、この宇宙全体に利益を施していくものです。そんなのできるか。と言われそうですがそれができるのです。なぜかについてはまたお話します。ともあれ、密教では自利の行と利他の行が一体化しています。すなわち、自らを救うことが他者を救うことにもなっています。 素光
2005年10月15日
コメント(1)
-
七日の話
今日は先日お葬式をしたところへ七日法要に行ってきました。七日法要というのは、四十九日までの間、七日ごとに生前の行いについて裁きが行われる、という教えに基づいてされています。仏教では(というよりも古代インドでは)死んでから四十九日目に六道(天界、人間界、畜生界、修羅界、餓鬼界、地獄界)の何処へ生まれ変わるか決められる、と言われていますので、四十九日までがとても重要なのです。では、何で1周忌、3回忌・・・とするの、と聞きたくなりますが、その話は改めて。それはさておき、七日法要には亡くなった方の供養というよりも、これから生きていく人たちのためのものであります。皆が集まりお経を唱えることにより、心の安定を図ると共に、邪気を祓い、故人のタマシイ(識)の浄化(ちょっと適切な表現ではありませんけど)を行っていくものです。ですから、身内の方の法要には参加してください。自分のためでもあります。 コウユウ
2005年10月14日
コメント(0)
-
今日の講演会
今日は昼2時から真言宗大覚寺派主催の講演会「空海とマンダラ」に行ってきました。さすがに四国大学の真鍋教授とあって(といっても全国的には有名ではない)100人までは行かないが70人位は集まっていました。最初から雑談のようにぼそぼそ話し始められましたので、眠くなってしまいました。大学の講義のようで(当たり前ですが)マンダラを美術としてみる方には面白い話かもしれませんが、私はどうも・・・。やはり興味のある話とそうでない話では当然関心も違ってきます。このブログの運営についても考えさせられる講演でした。真鍋教授お疲れ様でした。 コウユウ
2005年10月13日
コメント(1)
-
雨上がりのお寺で
このところ雨の日が目立ちます。雨も必要晴れ間も必要ですが、続くと困ります。祈願文の中にも真言宗の目標である即身成仏と密厳国土(密教による浄土)の次に風雨順時(天候が不順でない)とあります。それくらい天気というものは重要ですが、最近のように異常気象が普通になってしまうのはとても恐ろしいことです。この世の中のものはすべて原因がありその結果としてさまざまなことが起こります。また、この世の中のものはすべてつながっています。離れて存在しているわけではありません。 素光
2005年10月12日
コメント(0)
-
即身成仏と即身仏
よく「高野山の奥の院には空海のミイラがある」などと言う話を聞きますが、全くのでたらめで高野山ではそんな話は聞いた事がありません。なぜそんな話が出るかというと、即身仏と即身成仏を混同しているからです。即身仏というのはいわゆるミイラのことで(厳密に言うと違いますが)出羽三山などにあります。それに対して、即身成仏とは生きたまま仏となることで、生きる、死ぬという枠を超えることです。死んでしまったら即身成仏とは言いません。したがって即身成仏した弘法大師(空海)は生死を超越しており現在も生きているというのは間違いではありません。 素光
2005年10月11日
コメント(7)
-
法事の話3
この3連休で法事が4件ありました。法事ではいろいろと質問されます。一昨日の法事でも真言は「おん~」で始まるが、この「おん」の意味はどんな意味というように聞かれます。この「おん」は聖語であまり意味はないのですが、いきなり言われると答えに戸惑うことがあります。また、何で生き物を殺してはいけないか、と聞かれたときにもしどろもどろになった事があります。これは、日本ではあまり一般的ではありませんが、仏教は輪廻を基本の思想にしていますので、そこらにいる虫が、1年前に亡くなったおじいさんの生まれ変わりということもあるからです。質問されるとこちらも勉強になるので坊さんにはどんどん質問しましょう。 コウユウ
2005年10月10日
コメント(0)
-
タントラとスートラ
経典にはタントラとスートラがあります。スートラというのは一般的に経典といわれている阿含経典(原始佛典)般若経、法華経などです。これには教えの内容が書いてあります。それに対して大日経、金剛頂経などはタントラと呼ばれます。こちらには、教えの内容も書いてありますがそれよりも行の仕方が書いてあります。それがどうしたといわれそうですが。実は大変な違いがあります。スートラを根本経典とする分にはその教えの内容から著しく外れる事はありません。ところがタントラの場合には行をした結果が重要ですので反社会的な覚りの内容を導き出す恐れもあります。ですから、タントラに基づいて行をする場合にはあらかじめ柵を作っておくようになっています。 素光
2005年10月09日
コメント(1)
-
国勢調査終わりました
きょうは法事がありました。雨降りですが午後から本堂の掃除です。明日、寺法要があるので雨でもしなければなりません。夕方、国勢調査の調査票の回収に行きました。このところ不在が多くなかなか手間取っていましたが、やっと終わりました。皆さんがんばってください。 コウユウ
2005年10月08日
コメント(0)
-
雨の日の行について
今日は甘露日(大吉祥日)です。何事をするにも良い日です。朝から雨が降っています。雨降りは行をするのに最適です。雨の音が周りの音をかき消してくれます。また、昆虫も動物も静かに身を潜めています。静かにリラックスした状態で座ると、晴れた日の騒々しさとは違った ゆっくりとした行ができます。また、読経も同じです。世の中に自分一人だけしかいないような感覚が味わえます。 素光明日は尾宿、家に植木、祭祀ごとにはいい日です。お墓参りしましょう。 コウユウ
2005年10月07日
コメント(0)
-
悟りの話
今日は羅刹日(大凶日)気をつけておとなしくしてましょう。コウユウよく仏教では悟りを得るなどといいます。ところが、その悟りとは何か。禅宗ではこの悟りというものを大切にしています。禅問答などというと大人のとんちのように思われるかもしれません。事実禅宗(臨済宗)で使われる公案は、「片手で手をたたくには」「穴の開いたひょうたんで水をすくうには」のようになぞなぞまがいですところが、なぞなぞと違い答えを出すことに意味があるのではなくその当人の意識を見るのです。ですから、悟りを得た当人と同じ答えを言うことには意味がありません。 素光明日は甘露日(大吉祥日)何事をするにも良い日です。コウユウ
2005年10月06日
コメント(1)
-
吉野の話
昨日は高野山から下りて、吉野へ行ってきました。共に世界遺産に登録されていますが吉野の方が大々的に宣伝して活用しているようです。一般家庭でも「世界遺産」の提灯が吊られています。蔵王堂は高野山の金剛峰寺よりはるかに大きな建物です。(ちなみに高野山真言宗(金剛峰寺)のほうが蔵王堂(金峰山修験本宗)よりも何十倍も信者が多いから「何で」と思いますけど)本尊様の蔵王権現さんが見れなくて残念でした コウユウ
2005年10月05日
コメント(0)
-
法事の話2
昨日はいろいろと忙しく朝から明日(10/3)の葬儀の依頼がありました。今日は先達で高野山へ行く予定です。完全にバッティングで困った。法事は11時からです。食事を一緒にと言われていましたが、キャンセル。よく誤解されていますが、葬儀も法事も仏事はみな檀那寺の本尊様にお願いするものです。その名代として僧侶がいきます。ですから、普通は食事はお受けするのですが・・・お酒が入ると絡むおじさんがいたりして面白いですよ。 コウユウ
2005年10月03日
コメント(0)
-
行の話
行というと、滝に打たれたり、山中をひたすら歩いたり、汗を垂らしながら護摩を焚いたりというような厳しいイメージを持つ方が多いかと思います。また、それ以外でも、厳しくないと行ではないような先入感があるようです。ところが、実際の行はある種の快感を伴うことがあり、なんともいえない心地よさがあります。(最近医学的に言われている苦痛に伴う脳内麻薬の放出とはなんとなく違うような気がします)また傍目から見るほど苦痛ではないことが多いようです。ですから、結構楽しいですよ。 素光
2005年10月02日
コメント(0)
-
阿字観の話
密教の修法の中で阿字観というものがあります。梵字(五輪塔、塔婆などに書いてあります)の阿字の前で座りその阿字と一つになる行であります。座っている形が座禅と同じなので真言禅とも呼ばれます。ただ観想(思い浮かべること)がいわゆる禅とは違います。阿字観は阿字の掛軸を前にしてその阿字を観想するのに対し、禅宗の曹洞宗は座るだけ(只管打座)、臨済宗は公案(この公案が「片手で手をたたくにはどうしたらよいか}といった「とんち」のようなもの)を使うようです。上の三つのどれを使っても到達するところは同じかと思いますが(たぶん)、でも面白さはぜんぜん違うじゃないかな。 素光
2005年10月01日
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1