この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
広告
posted by fanblog
2021年06月10日
映画「炎628」‐ 舞い上がる炎の下で少年が見た地獄
「炎628」
(Иди и смотри) 1985年 ソビエト連邦
監督エレム・クリモフ
原作エレシ・アダモヴィチ
脚本エレム・クリモフ
エレシ・アダモヴィチ
撮影アレクセイ・ロジオーノフ
第14回モスクワ国際映画祭最優秀作品賞受賞
〈キャスト〉
アレクセイ・クラヴチェンコ オリガ・ミロノヴァ

恐ろしい映画です。
実際に起こった虐殺事件を題材に、一人の少年の目撃と体験が、そのまま私たち観客にも恐怖の追体験として目の前に迫ります。
ナチスの蛮行はユダヤ人への迫害が広く知れ渡っていますが、ここで扱われるのは、かつてソビエト連邦の構成国の一つだった白ロシア、現在のベラルーシです。
ヨーロッパの東に位置するベラルーシは、ポーランド、ウクライナ、リトアニア、ラトビアなどと国境を接し、ナポレオンのモスクワ遠征の際にはフランス軍に蹂躙された歴史を持ち、第一次世界大戦では熾烈(しれつ)な激戦の地ともなりました。
そのような白ロシア(ベラルーシ)で、ナチス・ドイツによるポーランド侵攻とともにヨーロッパを席巻したナチスの支配が白ロシアにまで及んだ時代。
1943年、ドイツ占領下の白ロシア。
フリョーラ(アレクセイ・クラヴチェンコ)は、土地の古老が止めるのも聞かずに、砂地から一丁の銃を掘り出します。
フリョーラは喜びましたが、しかしそれは少年フリョーラにとって忌まわしい日常への発端となります。
銃を手にしたフリョーラは、家を出ていかないでと泣いて頼む母親の意見を振り切るようにしてパルチザンに加わり、母親と幼い双子の妹たちを村に残して、パルチザンの同志が潜む森へと入ってゆきます。
パルチザンに加わることはできましたが、フリョーラがまだ少年であるためなのか、一人、森へ取り残されてしまいます。
森の中で出会った若い女性グラーシャと共に、森をさまよいながら故郷の村へと帰ろうとするフリョーラは、ドイツ軍の爆撃を逃れながら、空腹を抱えて村へとたどり着きます。
しかし、村には人の姿は無く、静まり返った家へ戻ったフリョーラとグラーシャが見たものは、床に散乱した壊れた人形でした。
異様な気配を感じた二人は家を飛び出し、「村の人たちはあそこにいるんだ!」と叫びながら走るフリョーラの後を追いかけるように走るグラーシャが振り返って見たのは、裸にされて殺された村人たちの死体の山。
村人たちが虐殺されたことに気づいたグラーシャでしたが、それに気づかず狂気のようになったフリョーラは沼に飛び込み、後を追うグラーシャも飛び込み、溺れそうになりながらも岸へ上がった二人は、森へ逃れていた難民たちの群れに加わることになります。
難民たちの食料は乏しく、食料調達のためにフリョーラは男たちと共に4人で食料を探しに出かけますが、地雷原で二人が吹き飛ばされ、近くの村から牝牛を調達して喜んだフリョーラたちでしたが、ドイツ軍の激しい銃撃に遭って一人は死に、度重なる銃撃で牝牛も殺されてしまいます。

フリョーラは一人、深い霧の中をさまよいながら農夫の荷馬車を見つけ、盗んでいこうとしますが、農夫にとがめられ、口論の中、ドイツ軍の車両に遭遇、行き場を失ったフリョーラは農夫の孫になりすまし、農夫の村に身をひそめることになりますが、それはフリョーラにとって阿鼻叫喚の地獄を経験することにつながるものとなります。
一風変わった題名の「炎628」は、フランソワ・トリュフォー監督の傑作「華氏451」(1966年)を意識して改題されたと思われますが、原題は「来なさい、そして見よ」。
聖書の最終章である「啓示(黙示録)」の第6章7節から8節による、青ざめた馬に乗った“死”が食糧不足と殺戮をもたらすことが描かれ、これが原題になったと思われます。

「炎628」の終盤、フリョーラが身を隠した村ではドイツ軍が続々と押し寄せ、村人たちを教会へ押し込めて教会の中は騒然となります。
窓から外へ顔を出した農民が射殺されたことをキッカケに悲鳴と号泣は極度に達します。
フリョーラは窓から体を乗り出して外へ逃れますが、ドイツ兵たちもフリョーラがまだ子どもだと思ったためか、薄汚れた野良猫のごとくあしらいながら見逃します。
悲鳴と号泣の教会の中へ手榴弾が投げ込まれます。
ここまででも、その凄まじさは見る者に戦慄を与えますが、さらにそこへ火が放たれ、火炎放射器が轟音を放ちます。
炎を上げて燃える教会へ射撃が行われ、笑い興じるドイツ兵たち。しかし、その中でも、涙を拭きながら射撃を行う者、嘔吐する者、多少は人間性を持った兵たちが少なからずいたことが描かれたことは、一方的にドイツを悪と決めつけていない冷静な視点があったように思います。
一カ所へ村人が集められて、建物もろ共焼き殺される残虐な事件は、ニキータ・ミハルコフ監督の秀作「戦火のナージャ」(2010年)でも描かれていますが、「戦火のナージャ」はコンピューター・グラフィックスを上手く使っているためか、一歩距離を置いて見ることができますが、「炎628」はまるでドキュメンタリーフィルムを見るような現実感があります。
冒頭の森の中でのパルチザンの様子やグラーシャの登場などはツルゲーネフの小説を思い起こさせますが、その雰囲気はドイツ軍による落下傘部隊の降下と、誰もいなくなったパルチザンのキャンプへの空爆で一転。
パルチザンに対する殲滅作戦が始まったことが分かります。

もともと工業化の進んでいなかった白ロシア(ベラルーシ)ですから、あたりは森と湿地帯、ぬかるんだ道、古い農家、見ようによっては牧歌的な東ヨーロッパの風景ともとれますが、戦争の狂気が取り巻く環境は、飢えと恐怖が支配する寒々とした世界。
ひとすら逃げ惑(まど)うフリョーラとグラーシャも泥と土ぼこりにまみれ、そしてたどり着いた村で体験した惨劇によってフリョーラの顔はまるで老人のように変わり果てている。
一方のグラーシャは放心状態で笛を口にくわえさせられ、両足の、おそらく股間から血を流し、ドイツ兵たちによって激しいレイプを受けたことをうかがわせます。
戦争映画で、これほどの惨状を描いた映画は、ちょっと記憶にありません。反戦映画と呼ぶには少し違うような気もします。ここで、こういうことが起きた、この事実を知ってもらいたい、そういう意図で作られたようにも思います。
監督は「ロマノフ王朝の最後」(1975年)などのエレム・クリモフ。
苛烈な題材を扱いながら、決して過剰な演出に陥ることなく、かなり衝撃的なシーンのひとつである虐殺された村人の死体の山をグラーシャが目撃する場面でも、グラーシャが振り返った一瞬に見えるだけで、そのまま二人の狂乱へとつながっていきます。
改題の「炎628」とは、白ロシア国内の628もの村が住民もろ共焼き尽くされた数字であることが最後に判ります。
これほどの殺戮(さつりく)が、同じ人間同士によって何故引き起こされるのか。
パルチザンに捕えられた将校らしき男が言います。「共産主義を根絶することが我々の使命だ」
理由はそうであっても、それが暴力や虐殺にまで発展するのは、ディケンズの「二都物語」に描かれたような、死刑判決を受けた人間の八つ裂きの処刑を見ることを楽しみに待つ群衆のような、暗い心理が潜んでいるように思われます。
恐ろしくも、深く考えさせられる映画です。

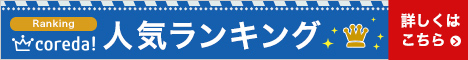

監督エレム・クリモフ
原作エレシ・アダモヴィチ
脚本エレム・クリモフ
エレシ・アダモヴィチ
撮影アレクセイ・ロジオーノフ
第14回モスクワ国際映画祭最優秀作品賞受賞
〈キャスト〉
アレクセイ・クラヴチェンコ オリガ・ミロノヴァ

恐ろしい映画です。
実際に起こった虐殺事件を題材に、一人の少年の目撃と体験が、そのまま私たち観客にも恐怖の追体験として目の前に迫ります。
ナチスの蛮行はユダヤ人への迫害が広く知れ渡っていますが、ここで扱われるのは、かつてソビエト連邦の構成国の一つだった白ロシア、現在のベラルーシです。
ヨーロッパの東に位置するベラルーシは、ポーランド、ウクライナ、リトアニア、ラトビアなどと国境を接し、ナポレオンのモスクワ遠征の際にはフランス軍に蹂躙された歴史を持ち、第一次世界大戦では熾烈(しれつ)な激戦の地ともなりました。
そのような白ロシア(ベラルーシ)で、ナチス・ドイツによるポーランド侵攻とともにヨーロッパを席巻したナチスの支配が白ロシアにまで及んだ時代。
1943年、ドイツ占領下の白ロシア。
フリョーラ(アレクセイ・クラヴチェンコ)は、土地の古老が止めるのも聞かずに、砂地から一丁の銃を掘り出します。
フリョーラは喜びましたが、しかしそれは少年フリョーラにとって忌まわしい日常への発端となります。
銃を手にしたフリョーラは、家を出ていかないでと泣いて頼む母親の意見を振り切るようにしてパルチザンに加わり、母親と幼い双子の妹たちを村に残して、パルチザンの同志が潜む森へと入ってゆきます。
パルチザンに加わることはできましたが、フリョーラがまだ少年であるためなのか、一人、森へ取り残されてしまいます。
森の中で出会った若い女性グラーシャと共に、森をさまよいながら故郷の村へと帰ろうとするフリョーラは、ドイツ軍の爆撃を逃れながら、空腹を抱えて村へとたどり着きます。
しかし、村には人の姿は無く、静まり返った家へ戻ったフリョーラとグラーシャが見たものは、床に散乱した壊れた人形でした。
異様な気配を感じた二人は家を飛び出し、「村の人たちはあそこにいるんだ!」と叫びながら走るフリョーラの後を追いかけるように走るグラーシャが振り返って見たのは、裸にされて殺された村人たちの死体の山。
村人たちが虐殺されたことに気づいたグラーシャでしたが、それに気づかず狂気のようになったフリョーラは沼に飛び込み、後を追うグラーシャも飛び込み、溺れそうになりながらも岸へ上がった二人は、森へ逃れていた難民たちの群れに加わることになります。
難民たちの食料は乏しく、食料調達のためにフリョーラは男たちと共に4人で食料を探しに出かけますが、地雷原で二人が吹き飛ばされ、近くの村から牝牛を調達して喜んだフリョーラたちでしたが、ドイツ軍の激しい銃撃に遭って一人は死に、度重なる銃撃で牝牛も殺されてしまいます。

フリョーラは一人、深い霧の中をさまよいながら農夫の荷馬車を見つけ、盗んでいこうとしますが、農夫にとがめられ、口論の中、ドイツ軍の車両に遭遇、行き場を失ったフリョーラは農夫の孫になりすまし、農夫の村に身をひそめることになりますが、それはフリョーラにとって阿鼻叫喚の地獄を経験することにつながるものとなります。
一風変わった題名の「炎628」は、フランソワ・トリュフォー監督の傑作「華氏451」(1966年)を意識して改題されたと思われますが、原題は「来なさい、そして見よ」。
聖書の最終章である「啓示(黙示録)」の第6章7節から8節による、青ざめた馬に乗った“死”が食糧不足と殺戮をもたらすことが描かれ、これが原題になったと思われます。

「炎628」の終盤、フリョーラが身を隠した村ではドイツ軍が続々と押し寄せ、村人たちを教会へ押し込めて教会の中は騒然となります。
窓から外へ顔を出した農民が射殺されたことをキッカケに悲鳴と号泣は極度に達します。
フリョーラは窓から体を乗り出して外へ逃れますが、ドイツ兵たちもフリョーラがまだ子どもだと思ったためか、薄汚れた野良猫のごとくあしらいながら見逃します。
悲鳴と号泣の教会の中へ手榴弾が投げ込まれます。
ここまででも、その凄まじさは見る者に戦慄を与えますが、さらにそこへ火が放たれ、火炎放射器が轟音を放ちます。
炎を上げて燃える教会へ射撃が行われ、笑い興じるドイツ兵たち。しかし、その中でも、涙を拭きながら射撃を行う者、嘔吐する者、多少は人間性を持った兵たちが少なからずいたことが描かれたことは、一方的にドイツを悪と決めつけていない冷静な視点があったように思います。
一カ所へ村人が集められて、建物もろ共焼き殺される残虐な事件は、ニキータ・ミハルコフ監督の秀作「戦火のナージャ」(2010年)でも描かれていますが、「戦火のナージャ」はコンピューター・グラフィックスを上手く使っているためか、一歩距離を置いて見ることができますが、「炎628」はまるでドキュメンタリーフィルムを見るような現実感があります。
冒頭の森の中でのパルチザンの様子やグラーシャの登場などはツルゲーネフの小説を思い起こさせますが、その雰囲気はドイツ軍による落下傘部隊の降下と、誰もいなくなったパルチザンのキャンプへの空爆で一転。
パルチザンに対する殲滅作戦が始まったことが分かります。

もともと工業化の進んでいなかった白ロシア(ベラルーシ)ですから、あたりは森と湿地帯、ぬかるんだ道、古い農家、見ようによっては牧歌的な東ヨーロッパの風景ともとれますが、戦争の狂気が取り巻く環境は、飢えと恐怖が支配する寒々とした世界。
ひとすら逃げ惑(まど)うフリョーラとグラーシャも泥と土ぼこりにまみれ、そしてたどり着いた村で体験した惨劇によってフリョーラの顔はまるで老人のように変わり果てている。
一方のグラーシャは放心状態で笛を口にくわえさせられ、両足の、おそらく股間から血を流し、ドイツ兵たちによって激しいレイプを受けたことをうかがわせます。
戦争映画で、これほどの惨状を描いた映画は、ちょっと記憶にありません。反戦映画と呼ぶには少し違うような気もします。ここで、こういうことが起きた、この事実を知ってもらいたい、そういう意図で作られたようにも思います。
監督は「ロマノフ王朝の最後」(1975年)などのエレム・クリモフ。
苛烈な題材を扱いながら、決して過剰な演出に陥ることなく、かなり衝撃的なシーンのひとつである虐殺された村人の死体の山をグラーシャが目撃する場面でも、グラーシャが振り返った一瞬に見えるだけで、そのまま二人の狂乱へとつながっていきます。
改題の「炎628」とは、白ロシア国内の628もの村が住民もろ共焼き尽くされた数字であることが最後に判ります。
これほどの殺戮(さつりく)が、同じ人間同士によって何故引き起こされるのか。
パルチザンに捕えられた将校らしき男が言います。「共産主義を根絶することが我々の使命だ」
理由はそうであっても、それが暴力や虐殺にまで発展するのは、ディケンズの「二都物語」に描かれたような、死刑判決を受けた人間の八つ裂きの処刑を見ることを楽しみに待つ群衆のような、暗い心理が潜んでいるように思われます。
恐ろしくも、深く考えさせられる映画です。

2020年10月09日
映画「地獄の戦場」名匠ルイス・マイルストン隠れた戦争映画の傑作
「地獄の戦場」
(Halls of Montezuma)
1950年 アメリカ
監督ルイス・マイルストン
脚本マイケル・ブランクフォート
撮影ウィントンC・ホック
ハリー・ジャクソン
〈キャスト〉
リチャード・ウィドマーク カール・マルデン
ジャック・パランス ロバート・ワグナー

第二次世界大戦において太平洋を主戦場とした日本軍対アメリカ軍(アメリカ海兵隊)の攻防を描いた傑作。
太平洋の島々をめぐる攻防を描いた映画は数多く作られてきました。それだけ凄惨な戦いが繰り広げられ、様々なドラマや悲劇が存在してきたといえます。
映画「地獄の戦場」は舞台である島の名称をあきらかにしていません。
テレンス・マリック監督の「シン・レッド・ライン」などのように、歴史的事実の再現というよりは、戦場に投げ込まれた兵士たちの生と死の苦悩を描いたドラマということができるでしょう。
原題は「モンテズマの玄関(広間)」。
モンテズマはアメリカ合衆国のコロラド州にある郡のひとつで、歴史は古く、千数百年以前から人間が居住していたようですが、数多くの混乱のために荒廃を極め、19世紀になって再び開拓が進んで今に至っているようですので、そのあたりの経緯から付けられた題名ではなかろうかと思います(違っているかもしれません)。
アンダーソン少尉(リチャード・ウィドマーク)率いるB中隊は、ガダルカナル、オタワなどの激戦を戦い抜いてきましたが、数々の戦場の恐怖からアンダーソンは片頭痛に悩まされています。
そんな中アメリカ軍は、日本軍が陣地を築いている島への上陸と基地の攻撃を命じられます。
元高校教師のアンダーソンには、かつての教え子のコンロイ(リチャード・ハイルトン)も部下として配属されており、コンロイもまた戦場の恐怖に脅かされています。
やがてB中隊を含む海軍は島への上陸を決行。
日本軍が陣取るトーチカからの猛攻撃を受けたアンダーソンは戦車部隊を要請。揚陸艇からシャーマンが送り込まれます。

火力にすぐれたシャーマンの火炎放射によって日本軍の攻撃はいったん収まり、B中隊は島の内陸へ進撃を開始しますが、そこへ襲い掛かったのは日本軍にはあると思われていなかったロケット砲による攻撃の嵐でした。
ロケット砲にさらされたアメリカ軍は、ギルフィラン中佐(リチャード・ブーン)を中心に対策を講じますが、ロケット砲の発射基地を皆目つかめず、焦りとあきらめが漂う中、日本軍の捕虜を獲得することに成功します。
監督は「西部戦線異状なし」(1930年)で、第一次世界大戦におけるドイツの若者たちの参戦の悲劇を描いて、第3回アカデミー賞最優秀作品賞と監督賞を受賞したルイス・マイルストン。
主役のアンダーソン少尉に「死の接吻」(1947年)で冷酷非情な殺し屋を演じて注目された個性派リチャード・ウィドマーク。
リチャード・ウィドマークはその後も「ワーロック」(1959年)、「アラモ」(1960年)、「西部開拓史」(1962年)などの西部劇でも重要な役を演じ、ドン・シーゲル監督の「刑事マディガン」(1968年)ではタフでありながら、上司の警察委員長のヘンリー・フォンダに頭の上がらない人間的魅力を持った刑事を好演。

酒好きだが戦場では頼りになるスラッテリーに「探偵物語」(1951年)、「キリマンジャロの雪」(1952年)、「ネバダ・スミス」(1966年)のバート・フリード。
元ボクサーのピジョンに、後の「シェーン」(1953年)で存在感のある悪役を演じたジャック・パランス。
そのピジョンを慕い、大物になって世間を見返そうとする“坊や”に「拳銃王」(1950年)、「封印された貨物」(1951年)のスキップ・オーマイヤー。
陽気で気のいいコフマンに「動く標的」(1966年)、「タワーリング・インフェルノ」(1974年)、「ミッドウェイ」(1976年)などのロバート・ワグナー。
負傷して失明するゼレンコ軍曹に「第十七捕虜収容所」(1953年)、「ハックルベリー・フィンの冒険」(1960年)、「トラ・トラ・トラ!」(1970年)、「死の追跡」(1973年)のネヴィル・ブランド。
そして、アンダーソンの親友で信仰心の厚いドクに、「欲望という名の電車」(1951年)、「波止場」(1954年)、「パットン大戦車軍団」(1970年)などの名優カール・マルデン。
さらに、ギルフィラン中佐には「聖衣」(1953年)、「アラモ」(1960年)、「ラスト・シューティスト」(1976年)のリチャード・ブーンといった一癖も二癖もある俳優陣がズラリと顔をそろえ、また、実際に戦争体験者も多く含まれていることから、破れて引き裂かれた軍服で行軍し、戦う姿などにも演技を超えたリアリティーが生み出されています。

ただ、そういった傑作でありながらも、ところどころ挿入される実写フィルムには少し違和感があり、むしろ実写フィルムは使わなくてもよかったのでは、とも思いました。
日本でも、当時の東映の戦争映画などで実写を混在させたりしていましたが、実写と作り物の差が歴然とするためにシラケてしまうことがよくありました。
また、あきらかに香港あたりの日本語を話す中国人俳優を連れてきたと思われるヘンなアクセントで話す日本兵にはいささか辟易とさせられ、どうしてホンモノの日本人俳優を使わなかったのかと思いましたが、製作が終戦間もない1950年(昭和25年)であってみれば、敗戦国で敵国であった日本人を使えなかったのかもしれませんし、ニッポンとしても敵国であったアメリカの映画に出演することを潔(いさぎよ)しとしなかったのかもしれません。
「戦場にかける橋」(1957年)でも、斎藤大佐の早川雪州や三浦中尉の勝本圭一郎以外の日本兵のエキストラには、ヘンな日本語をしゃべる怪しい日本兵がたくさん混じっていましたしね。
命令一下、バタバタと倒れる味方の屍を超えて進もうとするも、頑強な敵の猛攻の前に屈しながら、なおも進路確保のために凄惨な戦いを余儀なくされる。
この状況設定は、後のテレビ「コンバット」の中の傑作“丘を血に染めて”でも兵士たちの苦悩が描かれたように、戦争の悲惨さがよく伝わってきます。
「地獄の戦場」という改題が示すように、戦場のリアルさを描いたものであると同時に、兵士一人ひとりの心の動きなども追いながら、人間はいかに生きるべきかを問いかけた傑作です。



1950年 アメリカ
監督ルイス・マイルストン
脚本マイケル・ブランクフォート
撮影ウィントンC・ホック
ハリー・ジャクソン
〈キャスト〉
リチャード・ウィドマーク カール・マルデン
ジャック・パランス ロバート・ワグナー

第二次世界大戦において太平洋を主戦場とした日本軍対アメリカ軍(アメリカ海兵隊)の攻防を描いた傑作。
太平洋の島々をめぐる攻防を描いた映画は数多く作られてきました。それだけ凄惨な戦いが繰り広げられ、様々なドラマや悲劇が存在してきたといえます。
映画「地獄の戦場」は舞台である島の名称をあきらかにしていません。
テレンス・マリック監督の「シン・レッド・ライン」などのように、歴史的事実の再現というよりは、戦場に投げ込まれた兵士たちの生と死の苦悩を描いたドラマということができるでしょう。
原題は「モンテズマの玄関(広間)」。
モンテズマはアメリカ合衆国のコロラド州にある郡のひとつで、歴史は古く、千数百年以前から人間が居住していたようですが、数多くの混乱のために荒廃を極め、19世紀になって再び開拓が進んで今に至っているようですので、そのあたりの経緯から付けられた題名ではなかろうかと思います(違っているかもしれません)。
アンダーソン少尉(リチャード・ウィドマーク)率いるB中隊は、ガダルカナル、オタワなどの激戦を戦い抜いてきましたが、数々の戦場の恐怖からアンダーソンは片頭痛に悩まされています。
そんな中アメリカ軍は、日本軍が陣地を築いている島への上陸と基地の攻撃を命じられます。
元高校教師のアンダーソンには、かつての教え子のコンロイ(リチャード・ハイルトン)も部下として配属されており、コンロイもまた戦場の恐怖に脅かされています。
やがてB中隊を含む海軍は島への上陸を決行。
日本軍が陣取るトーチカからの猛攻撃を受けたアンダーソンは戦車部隊を要請。揚陸艇からシャーマンが送り込まれます。

火力にすぐれたシャーマンの火炎放射によって日本軍の攻撃はいったん収まり、B中隊は島の内陸へ進撃を開始しますが、そこへ襲い掛かったのは日本軍にはあると思われていなかったロケット砲による攻撃の嵐でした。
ロケット砲にさらされたアメリカ軍は、ギルフィラン中佐(リチャード・ブーン)を中心に対策を講じますが、ロケット砲の発射基地を皆目つかめず、焦りとあきらめが漂う中、日本軍の捕虜を獲得することに成功します。
監督は「西部戦線異状なし」(1930年)で、第一次世界大戦におけるドイツの若者たちの参戦の悲劇を描いて、第3回アカデミー賞最優秀作品賞と監督賞を受賞したルイス・マイルストン。
主役のアンダーソン少尉に「死の接吻」(1947年)で冷酷非情な殺し屋を演じて注目された個性派リチャード・ウィドマーク。
リチャード・ウィドマークはその後も「ワーロック」(1959年)、「アラモ」(1960年)、「西部開拓史」(1962年)などの西部劇でも重要な役を演じ、ドン・シーゲル監督の「刑事マディガン」(1968年)ではタフでありながら、上司の警察委員長のヘンリー・フォンダに頭の上がらない人間的魅力を持った刑事を好演。

酒好きだが戦場では頼りになるスラッテリーに「探偵物語」(1951年)、「キリマンジャロの雪」(1952年)、「ネバダ・スミス」(1966年)のバート・フリード。
元ボクサーのピジョンに、後の「シェーン」(1953年)で存在感のある悪役を演じたジャック・パランス。
そのピジョンを慕い、大物になって世間を見返そうとする“坊や”に「拳銃王」(1950年)、「封印された貨物」(1951年)のスキップ・オーマイヤー。
陽気で気のいいコフマンに「動く標的」(1966年)、「タワーリング・インフェルノ」(1974年)、「ミッドウェイ」(1976年)などのロバート・ワグナー。
負傷して失明するゼレンコ軍曹に「第十七捕虜収容所」(1953年)、「ハックルベリー・フィンの冒険」(1960年)、「トラ・トラ・トラ!」(1970年)、「死の追跡」(1973年)のネヴィル・ブランド。
そして、アンダーソンの親友で信仰心の厚いドクに、「欲望という名の電車」(1951年)、「波止場」(1954年)、「パットン大戦車軍団」(1970年)などの名優カール・マルデン。
さらに、ギルフィラン中佐には「聖衣」(1953年)、「アラモ」(1960年)、「ラスト・シューティスト」(1976年)のリチャード・ブーンといった一癖も二癖もある俳優陣がズラリと顔をそろえ、また、実際に戦争体験者も多く含まれていることから、破れて引き裂かれた軍服で行軍し、戦う姿などにも演技を超えたリアリティーが生み出されています。
ただ、そういった傑作でありながらも、ところどころ挿入される実写フィルムには少し違和感があり、むしろ実写フィルムは使わなくてもよかったのでは、とも思いました。
日本でも、当時の東映の戦争映画などで実写を混在させたりしていましたが、実写と作り物の差が歴然とするためにシラケてしまうことがよくありました。
また、あきらかに香港あたりの日本語を話す中国人俳優を連れてきたと思われるヘンなアクセントで話す日本兵にはいささか辟易とさせられ、どうしてホンモノの日本人俳優を使わなかったのかと思いましたが、製作が終戦間もない1950年(昭和25年)であってみれば、敗戦国で敵国であった日本人を使えなかったのかもしれませんし、ニッポンとしても敵国であったアメリカの映画に出演することを潔(いさぎよ)しとしなかったのかもしれません。
「戦場にかける橋」(1957年)でも、斎藤大佐の早川雪州や三浦中尉の勝本圭一郎以外の日本兵のエキストラには、ヘンな日本語をしゃべる怪しい日本兵がたくさん混じっていましたしね。
命令一下、バタバタと倒れる味方の屍を超えて進もうとするも、頑強な敵の猛攻の前に屈しながら、なおも進路確保のために凄惨な戦いを余儀なくされる。
この状況設定は、後のテレビ「コンバット」の中の傑作“丘を血に染めて”でも兵士たちの苦悩が描かれたように、戦争の悲惨さがよく伝わってきます。
「地獄の戦場」という改題が示すように、戦場のリアルさを描いたものであると同時に、兵士一人ひとりの心の動きなども追いながら、人間はいかに生きるべきかを問いかけた傑作です。

2020年03月05日
映画「シン・レッド・ライン」−壮絶な戦闘と美しい自然, 戦争の背後にうごめく邪悪な闇
「シン・レッド・ライン」
(The Thin Red Line)
1998年 カナダ/アメリカ
監督・脚本テレンス・マリック
原作ジェームズ・ジョーンズ
撮影ジョン・トール
音楽ハンス・ジマー
〈キャスト〉
ショーン・ペン ジム・カヴィーゼル
ニック・ノルティ
イライアス・コティーズ ベン・チャップリン
第49回ベルリン国際映画祭金熊賞受賞,
第65回ニューヨーク映画批評家協会賞監督賞/撮影賞受賞,
第10回シカゴ映画批評家協会賞監督賞/撮影賞受賞,
他受賞多数
戦争映画としては圧倒的に他を抜き去る迫力とスケール。
戦争という極限の状況に置かれた兵士たちの生や死についての思想世界が、戦争映画としての枠を突き抜けて、人類の背後にある神の存在や、死と邪悪をもたらす霊的で巨大な闇の支配といった、人類を牛耳るどうしようもない力の存在を突き詰めようとする思想的深みを持った映画で、前作「天国の日々」(1978年)以来、実に20年の沈黙を破ってメガホンを取った巨匠テレンス・マリック、期待を裏切らない傑作です。

ズブリと沼に浸(つ)かって姿を消すワニの異様なシーンで始まる映画「シン・レッド・ライン」は、ストーリーらしいストーリーは存在しません。
西太平洋ソロモン諸島のガダルカナル島での連合軍対日本軍の激戦を主軸に、戦場に送り込まれた兵士たちの心の動きを、目をみはるような素晴らしい映像がとらえた自然の風景の中で、生と死、善と悪、自然と人間を綾として織り成してゆきます。
ワニのシーンから一転して南海の島で原住民たちと楽しく過ごす青年の姿が描かれますが、楽園とも思える自然の中で母の死について考える彼の内面的世界は、そのまま「シン・レッド・ライン」を貫く一本の太い線として全体につながっていきます。
その青年、ロバート・ウィット二等兵(ジム・カヴィーゼル)は戦友と一緒に無断で隊を離れ、島の子供たちと楽しい日々を送っていましたが、島へ現れた哨戒船によって隊へ連れ戻されます。
本来であれば軍法会議で処罰の対象とされるウィットでしたが、二等兵から格下げになるものの、ウェルシュ曹長(ショーン・ペン)の計らいで負傷兵を運ぶ担架兵としての任務に就くことになります。

太平洋の制海権を狙う連合軍は、日本軍がガダルカナル島に飛行場を築いている情報を入手。
家族を犠牲にし、死を覚悟して戦場にのぞんだC中隊の指揮官ゴードン・トール中佐(ニック・ノルティ)はクインタード准将(ジョン・トラヴォルタ)からガダルカナル島奪還を命じられ、日本軍が布陣を張るガダルカナル島への上陸を開始。
激戦の火ぶたが切って落とされます。
静から始まった「シン・レッド・ライン」は、ここで一気に動への展開となり、高地での戦闘と日本軍が築いたトーチカの破壊までが続くのですが、その凄まじさは同時期に封切られた「プライベート・ライアン」のノルマンディー上陸作戦での激戦の凄まじさと比肩できるほど。
中でも、丘の奪還を命じられたスタロス大尉(イライアス・コティーズ)率いる部隊は、日本軍から丸見えの状態で狙撃を受けて死者が増え、これ以上の進撃は自殺行為で、みすみす部下を死なせることはできないと考えたスタロスと、何が何でも進撃しろ! と厳命をとばすトール中佐との激論は見どころのひとつと言ってよく、上官の命令であっても従うことはできないと一歩も引かないスタロスに業を煮やしたトールは、自ら現場に乗り込み、ベル二等兵(ベン・チャップリン)ら7名の決死隊を募って丘の偵察に向かわせます。

おびただしい血と泥と汗の戦場で、ベルは故郷に残してきた妻との甘い追憶を胸に高原を這い、日本軍のトーチカを発見。
トーチカ攻撃のためにジョン・ガフ大尉(ジョン・キューザック)らが志願し、激しい戦いの末にトーチカは壊滅。丘を奪取します。
勝利の勢いに乗ってそのまま日本軍の拠点まで攻め寄せようと決死の進撃を試みたトールの作戦は功を奏し、日本軍は壊滅。
C中隊には一週間の休暇が与えられます。
兵たちが休暇を楽しむ中、ベルには愛する妻からの手紙が届いていました。
しかしそれは、空軍大尉と出会って恋に落ちたから離婚をしてほしいという、夫のいない寂しさに耐えかねた妻の、裏切りともとれる内容でした。
上官の命令に服さなかったスタロスは解任、休暇を終えた中隊は再び前線への移動を開始します。
島の奥地での日本軍への奇襲に成功した中隊でしたが、その後、日本軍の増援部隊と遭遇。担架兵から隊へ復帰して、ヤバイときには自分が行く、と進んで危険な任務にあたったウィットは日本軍に取り巻かれて力尽き、死を迎えます。

「シン・レッド・ライン」は群像劇といってもよく、ジム・カヴィーゼル(ウィット二等兵)、ショーン・ペン(ウェルシュ曹長)を始めとして、ベン・チャップリン、ニック・ノルティ、ジョン・キューザックなどの主だった人物が登場するほか、ジョン・サヴェージ、ジョン・C・ライリー、ウディ・ハレルソン、エイドリアン・ブロディなど、誰が主役になってもおかしくないほどのそうそうたる顔ぶれが揃い、これだけの俳優陣の中に埋没することなく、それぞれが個性を発揮しています。
またジョン・トラヴォルタやジョージ・クルーニーなどのドル箱スターもチラリと顔をのぞかせ、とにかくテレンス・マリックの映画に出たいんだ、少しでいいから出してくれ! といった感じで出演しているのも面白いところ。
第71回アカデミー賞には作品賞や監督賞の他、脚色賞、撮影賞、音楽賞など7部門がノミネートされましたが、惜しくもこの年には「恋におちたシェイクスピア」がほぼ独占しました。

戦闘シーンの凄まじさもさることながら、戦争そのものというより、その背後に隠れた大きな邪悪なものの存在や、美しい自然を創り出した神の存在などを深く掘り下げた内容であるため、この戦争が一体どんな戦争なのかということについてはほとんど語られておらず、ガダルカナルという言葉も、トール中佐の言葉と手紙の中にチラリとあるだけで、テレンス・マリックにとっては、太平洋戦争であろうとベトナム戦争であろうと、戦争の歴史的事実の再現は特に問題ではなかったのだろうと思われます。
題名の「シン・レッド・ライン」ですが、レッドラインは文字通りの赤い線ではなくて、“超えてはいけない一線”というような意味合いがあるようで、その一線を超えることでまったく違う運命が待ち構えている、といった含みがあるようです。
例えば、トルストイの小説「戦争と平和」の中で、ナポレオン率いるフランス軍の猛攻に立ち向かうロシア軍の兵士たちの心情、「…彼我のあいだには両者を分けて、あたかも生者と死者とを隔てる一線のような、未知と恐怖のおそろしい一線が横たわっていた。だれもがその一線を意識し、自分たちはその一線を踏み超えられるのだろうか、踏み超えられないのだろうか、どんなふうに踏み超えるのだろうという疑問に彼らは胸を騒がせていた」(北垣信行訳)そんな描写があって、おそらく「シン・レッド・ライン」という題名も、そんなふうな一線を意味するのではないかと思います。
いずれにしても、3時間近い上映時間にもかかわらず、いっさい手を抜くことなく、首尾一貫したテーマの追求はお見事としか言いようがなく、静かな海辺に浮かぶヤシの実から芽を出しているラストシーンの美しさは素晴らしい余韻を残しました。



1998年 カナダ/アメリカ
監督・脚本テレンス・マリック
原作ジェームズ・ジョーンズ
撮影ジョン・トール
音楽ハンス・ジマー
〈キャスト〉
ショーン・ペン ジム・カヴィーゼル
ニック・ノルティ
イライアス・コティーズ ベン・チャップリン
第49回ベルリン国際映画祭金熊賞受賞,
第65回ニューヨーク映画批評家協会賞監督賞/撮影賞受賞,
第10回シカゴ映画批評家協会賞監督賞/撮影賞受賞,
他受賞多数
戦争映画としては圧倒的に他を抜き去る迫力とスケール。
戦争という極限の状況に置かれた兵士たちの生や死についての思想世界が、戦争映画としての枠を突き抜けて、人類の背後にある神の存在や、死と邪悪をもたらす霊的で巨大な闇の支配といった、人類を牛耳るどうしようもない力の存在を突き詰めようとする思想的深みを持った映画で、前作「天国の日々」(1978年)以来、実に20年の沈黙を破ってメガホンを取った巨匠テレンス・マリック、期待を裏切らない傑作です。

ズブリと沼に浸(つ)かって姿を消すワニの異様なシーンで始まる映画「シン・レッド・ライン」は、ストーリーらしいストーリーは存在しません。
西太平洋ソロモン諸島のガダルカナル島での連合軍対日本軍の激戦を主軸に、戦場に送り込まれた兵士たちの心の動きを、目をみはるような素晴らしい映像がとらえた自然の風景の中で、生と死、善と悪、自然と人間を綾として織り成してゆきます。
ワニのシーンから一転して南海の島で原住民たちと楽しく過ごす青年の姿が描かれますが、楽園とも思える自然の中で母の死について考える彼の内面的世界は、そのまま「シン・レッド・ライン」を貫く一本の太い線として全体につながっていきます。
その青年、ロバート・ウィット二等兵(ジム・カヴィーゼル)は戦友と一緒に無断で隊を離れ、島の子供たちと楽しい日々を送っていましたが、島へ現れた哨戒船によって隊へ連れ戻されます。
本来であれば軍法会議で処罰の対象とされるウィットでしたが、二等兵から格下げになるものの、ウェルシュ曹長(ショーン・ペン)の計らいで負傷兵を運ぶ担架兵としての任務に就くことになります。

太平洋の制海権を狙う連合軍は、日本軍がガダルカナル島に飛行場を築いている情報を入手。
家族を犠牲にし、死を覚悟して戦場にのぞんだC中隊の指揮官ゴードン・トール中佐(ニック・ノルティ)はクインタード准将(ジョン・トラヴォルタ)からガダルカナル島奪還を命じられ、日本軍が布陣を張るガダルカナル島への上陸を開始。
激戦の火ぶたが切って落とされます。
静から始まった「シン・レッド・ライン」は、ここで一気に動への展開となり、高地での戦闘と日本軍が築いたトーチカの破壊までが続くのですが、その凄まじさは同時期に封切られた「プライベート・ライアン」のノルマンディー上陸作戦での激戦の凄まじさと比肩できるほど。
中でも、丘の奪還を命じられたスタロス大尉(イライアス・コティーズ)率いる部隊は、日本軍から丸見えの状態で狙撃を受けて死者が増え、これ以上の進撃は自殺行為で、みすみす部下を死なせることはできないと考えたスタロスと、何が何でも進撃しろ! と厳命をとばすトール中佐との激論は見どころのひとつと言ってよく、上官の命令であっても従うことはできないと一歩も引かないスタロスに業を煮やしたトールは、自ら現場に乗り込み、ベル二等兵(ベン・チャップリン)ら7名の決死隊を募って丘の偵察に向かわせます。

おびただしい血と泥と汗の戦場で、ベルは故郷に残してきた妻との甘い追憶を胸に高原を這い、日本軍のトーチカを発見。
トーチカ攻撃のためにジョン・ガフ大尉(ジョン・キューザック)らが志願し、激しい戦いの末にトーチカは壊滅。丘を奪取します。
勝利の勢いに乗ってそのまま日本軍の拠点まで攻め寄せようと決死の進撃を試みたトールの作戦は功を奏し、日本軍は壊滅。
C中隊には一週間の休暇が与えられます。
兵たちが休暇を楽しむ中、ベルには愛する妻からの手紙が届いていました。
しかしそれは、空軍大尉と出会って恋に落ちたから離婚をしてほしいという、夫のいない寂しさに耐えかねた妻の、裏切りともとれる内容でした。
上官の命令に服さなかったスタロスは解任、休暇を終えた中隊は再び前線への移動を開始します。
島の奥地での日本軍への奇襲に成功した中隊でしたが、その後、日本軍の増援部隊と遭遇。担架兵から隊へ復帰して、ヤバイときには自分が行く、と進んで危険な任務にあたったウィットは日本軍に取り巻かれて力尽き、死を迎えます。

「シン・レッド・ライン」は群像劇といってもよく、ジム・カヴィーゼル(ウィット二等兵)、ショーン・ペン(ウェルシュ曹長)を始めとして、ベン・チャップリン、ニック・ノルティ、ジョン・キューザックなどの主だった人物が登場するほか、ジョン・サヴェージ、ジョン・C・ライリー、ウディ・ハレルソン、エイドリアン・ブロディなど、誰が主役になってもおかしくないほどのそうそうたる顔ぶれが揃い、これだけの俳優陣の中に埋没することなく、それぞれが個性を発揮しています。
またジョン・トラヴォルタやジョージ・クルーニーなどのドル箱スターもチラリと顔をのぞかせ、とにかくテレンス・マリックの映画に出たいんだ、少しでいいから出してくれ! といった感じで出演しているのも面白いところ。
第71回アカデミー賞には作品賞や監督賞の他、脚色賞、撮影賞、音楽賞など7部門がノミネートされましたが、惜しくもこの年には「恋におちたシェイクスピア」がほぼ独占しました。
戦闘シーンの凄まじさもさることながら、戦争そのものというより、その背後に隠れた大きな邪悪なものの存在や、美しい自然を創り出した神の存在などを深く掘り下げた内容であるため、この戦争が一体どんな戦争なのかということについてはほとんど語られておらず、ガダルカナルという言葉も、トール中佐の言葉と手紙の中にチラリとあるだけで、テレンス・マリックにとっては、太平洋戦争であろうとベトナム戦争であろうと、戦争の歴史的事実の再現は特に問題ではなかったのだろうと思われます。
題名の「シン・レッド・ライン」ですが、レッドラインは文字通りの赤い線ではなくて、“超えてはいけない一線”というような意味合いがあるようで、その一線を超えることでまったく違う運命が待ち構えている、といった含みがあるようです。
例えば、トルストイの小説「戦争と平和」の中で、ナポレオン率いるフランス軍の猛攻に立ち向かうロシア軍の兵士たちの心情、「…彼我のあいだには両者を分けて、あたかも生者と死者とを隔てる一線のような、未知と恐怖のおそろしい一線が横たわっていた。だれもがその一線を意識し、自分たちはその一線を踏み超えられるのだろうか、踏み超えられないのだろうか、どんなふうに踏み超えるのだろうという疑問に彼らは胸を騒がせていた」(北垣信行訳)そんな描写があって、おそらく「シン・レッド・ライン」という題名も、そんなふうな一線を意味するのではないかと思います。
いずれにしても、3時間近い上映時間にもかかわらず、いっさい手を抜くことなく、首尾一貫したテーマの追求はお見事としか言いようがなく、静かな海辺に浮かぶヤシの実から芽を出しているラストシーンの美しさは素晴らしい余韻を残しました。

2020年02月27日
映画「ノー・マンズ・ランド」−予想を超えたラストの残酷な滑稽さ
「ノー・マンズ・ランド」
(No Man’s Land) 2001年
ボスニア・ヘルツェゴビナ スロベニア イタリア
フランス イギリス ベルギー
監督・脚本・音楽ダニス・タノヴィッチ
撮影ウォルター・ヴァンデン・エンデ
〈キャスト〉
ブランコ・ジュリッチ レネ・ビトラヤツ
フィリプ・ショヴァゴヴィッチ
第54回カンヌ国際映画祭脚本賞/ セザール賞最優秀新人監督賞
第74回アカデミー賞外国語映画賞/他受賞多数

ボスニア・ヘルツェゴビナの紛争下、両軍の中間地帯(ノー・マンズ・ランド)に取り残されたボスニア兵とセルビア兵の二人の憎しみや、ふとした会話から芽生え始める融和。
しかし、ボスニア兵の死体(後に生きていることが判明)の下に仕掛けられた地雷の撤去をめぐって、国連の防護軍やジャーナリスト、サラエボ本部の二転三転する緊迫した状況が展開され、一瞬たりとも目が離せません。
戦争の残酷さを、ときにはユーモアを交えて突き付ける反戦映画で、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争が扱われますが、戦争という普遍的なテーマを追求しているためなのか、その背景となっている紛争の説明はほとんどありません。
なので、簡単に経緯をたどってみましょう。
中世から20世紀初頭にかけてヨーロッパに君臨して絶大な権力を誇ったハプスブルク家の帝国のひとつオーストリア=ハンガリー帝国が第一次世界大戦を経て解体され、1918年にバルカン半島の西にユーゴスラビア王国が誕生。
第二次世界大戦ではナチス・ドイツや他の諸国によって侵攻を受け、ユーゴスラビア王国はそれらの国々の支配地域のために分断されてゆきます。
後にユーゴスラビアで大きな影響力を持つことになるチトーの登場と、ナチス・ドイツの降伏、ゲリラ戦を戦い抜いたパルチザンたちの手によってユーゴスラビアの統一と独立がなされ、ユーゴスラビア連邦が樹立。
しかし多様な民族を抱えたユーゴは民族紛争が激化、内戦に突入します。
1991年にはスロベニアが独立。続いてマケドニアが独立。
さらに分離独立とセルビア系住民との対立からクロアチア紛争が勃発し、激しい戦いの末にクロアチアが独立。
1992年にはボスニア・ヘルツェゴビナも独立しますが、ボスニアからの独立を目指したセルビアとの間で、「ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争」が勃発することになります。
映画「ノー・マンズ・ランド」はボスニア・ヘルツェゴビナの紛争における戦場の一コマを扱い、人間同士の憎しみや、戦場においてひとつの命を救うことの困難さと地雷という小さな兵器ひとつに右往左往させられる悲劇的な滑稽さを描いた人間ドラマです。

ボスニア・ヘルツェゴビナの紛争地帯。
闇に紛れて霧の中を進むボスニア軍の兵士たちは道に迷ってしまいます。
セルビア軍の陣地にまで入り込んだことが判ったときにはすでに遅く、夜明けと共に始まったセルビア軍の攻撃にさらされたボスニア軍の兵士たちは壊滅しますが、チキ(ブランコ・ジュリッチ)とツェラ(フィリップ・ショヴァゴヴィッチ)の二人は、両軍の中間地帯(ノー・マンズ・ランド)にある塹壕の附近まで走り込み、容赦のないセルビア軍の砲撃によってチキとツェラは吹き飛ばされてしまいます。
砲撃を停止したセルビア軍の陣地から、古参兵(ムスタファ・ナダレヴィッチ)と新兵のニノ(レネ・ビトラヤツ)の二人が偵察に向かいます。
一方、塹壕の中で意識を回復したチキは、銃を手に物陰に隠れ、セルビア兵の様子をうかがいます。
地面に倒れているツェラの死体の他に誰もいないことを確認した古参兵は、ツェラの死体の下に地雷を埋め込みます。
どうしてそんなことをするのか、と聞くニノに古参兵は答えます。
「こうしておけば、こいつを動かそうとした途端に、爆発だ」
二人は立ち去ろうとしますが、物陰に潜んでいたチキは隙をみて飛び出し二人を銃撃します。
古参兵は死亡しましたが、ニノは負傷しただけで助かり、チキとニノの間には緊張した空気が生まれます。
チキの隙を見て銃を奪ったニノと、武器を失ったチキの立場が逆転する中で、死んだと思っていたツェラは意識を失っていただけで、体の下に地雷が設置されていることを知ったツェラは、自分が身動きの取れない状況に置かれていることを知ります。
簡単に取り外せるものと高を括(くく)っていたチキとニノでしたが、それは特殊な地雷で、自分たちの手に負えないとみたチキとニノは、両軍に停戦を呼びかけ、地雷撤去のために国連の防護軍が現場に向かうことになりますが…。

「世界の火薬庫」と呼ばれたバルカン半島(地政学的にはバルカン地域)。
多くの民族、宗教、言語が混在し、紛争の絶え間のないバルカンでは幾度となく国境線が塗り替えられ、作り替えられてきました。
戦争の世紀と呼ばれた20世紀が過ぎ、21世紀になった現在でも数々の紛争は世界各地で起きており、おそらく、地球上に人類が存在する以上、地上から戦争がなくなることはないと思います。
「ノー・マンズ・ランド」では、一体どうしてこんなことが起こるんだ! お前たちが悪いんだ! いや、お前たちだ! といったやり取りがチキとニノの間で交わされますが、紛争に明け暮れたバルカン地域の中で、もう何がどうなっているのか、そんな絶望的な状況をヤケッパチとも思えるユーモアをぶつけて描き出しました。
そこには勝者もなく、敗者もなく、ただ、無意味で残酷な結末が観る者に戦争の愚かしさを突き付けます。

監督はボスニア・ヘルツェゴビナ出身のダニス・タノヴィッチ。
「ノー・マンズ・ランド」以降も「「鉄くず拾いの物語」(2013年)、「汚れたミルク/あるセールスマンの告発」(2014年)、「サラエヴォの銃声」(2016年)など、社会性のある話題作を発表。数々の賞を受賞しています。
ボスニア兵チキに、俳優でミュージシャンでもあるブランコ・ジュリッチ。
セルビア兵ニノにクロアチア出身のレネ・ビトラヤツ。
サラエボ本部のソフト大佐に「アマデウス」(1984年)、「眺めのいい部屋」(1985年)、「オペラ座の怪人」(2004年)などの名優サイモン・キャロウ。
セクシーで美人の秘書を常に従え、状況を把握しながらも大事の中の小事は切り捨ててしまう、イヤな軍人像でありながらも強い印象を残しました。
野心に燃えるマスコミのジェーン・リヴィングストン特派員にカトリン・カートリッジ。
この人は「ノー・マンズ・ランド」の翌年2002年「デブラ・ウィンガーを探して」の出演を最後に41歳の若さで病死しています。
二転三転するストーリー展開、ひとり取り残されるツェラの映像と哀切な歌が流れるラストは、愚かしくも滑稽で、かつ残酷な人間世界の断面をえぐり出したといえます。



ボスニア・ヘルツェゴビナ スロベニア イタリア
フランス イギリス ベルギー
監督・脚本・音楽ダニス・タノヴィッチ
撮影ウォルター・ヴァンデン・エンデ
〈キャスト〉
ブランコ・ジュリッチ レネ・ビトラヤツ
フィリプ・ショヴァゴヴィッチ
第54回カンヌ国際映画祭脚本賞/ セザール賞最優秀新人監督賞
第74回アカデミー賞外国語映画賞/他受賞多数

ボスニア・ヘルツェゴビナの紛争下、両軍の中間地帯(ノー・マンズ・ランド)に取り残されたボスニア兵とセルビア兵の二人の憎しみや、ふとした会話から芽生え始める融和。
しかし、ボスニア兵の死体(後に生きていることが判明)の下に仕掛けられた地雷の撤去をめぐって、国連の防護軍やジャーナリスト、サラエボ本部の二転三転する緊迫した状況が展開され、一瞬たりとも目が離せません。
戦争の残酷さを、ときにはユーモアを交えて突き付ける反戦映画で、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争が扱われますが、戦争という普遍的なテーマを追求しているためなのか、その背景となっている紛争の説明はほとんどありません。
なので、簡単に経緯をたどってみましょう。
中世から20世紀初頭にかけてヨーロッパに君臨して絶大な権力を誇ったハプスブルク家の帝国のひとつオーストリア=ハンガリー帝国が第一次世界大戦を経て解体され、1918年にバルカン半島の西にユーゴスラビア王国が誕生。
第二次世界大戦ではナチス・ドイツや他の諸国によって侵攻を受け、ユーゴスラビア王国はそれらの国々の支配地域のために分断されてゆきます。
後にユーゴスラビアで大きな影響力を持つことになるチトーの登場と、ナチス・ドイツの降伏、ゲリラ戦を戦い抜いたパルチザンたちの手によってユーゴスラビアの統一と独立がなされ、ユーゴスラビア連邦が樹立。
しかし多様な民族を抱えたユーゴは民族紛争が激化、内戦に突入します。
1991年にはスロベニアが独立。続いてマケドニアが独立。
さらに分離独立とセルビア系住民との対立からクロアチア紛争が勃発し、激しい戦いの末にクロアチアが独立。
1992年にはボスニア・ヘルツェゴビナも独立しますが、ボスニアからの独立を目指したセルビアとの間で、「ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争」が勃発することになります。
映画「ノー・マンズ・ランド」はボスニア・ヘルツェゴビナの紛争における戦場の一コマを扱い、人間同士の憎しみや、戦場においてひとつの命を救うことの困難さと地雷という小さな兵器ひとつに右往左往させられる悲劇的な滑稽さを描いた人間ドラマです。

ボスニア・ヘルツェゴビナの紛争地帯。
闇に紛れて霧の中を進むボスニア軍の兵士たちは道に迷ってしまいます。
セルビア軍の陣地にまで入り込んだことが判ったときにはすでに遅く、夜明けと共に始まったセルビア軍の攻撃にさらされたボスニア軍の兵士たちは壊滅しますが、チキ(ブランコ・ジュリッチ)とツェラ(フィリップ・ショヴァゴヴィッチ)の二人は、両軍の中間地帯(ノー・マンズ・ランド)にある塹壕の附近まで走り込み、容赦のないセルビア軍の砲撃によってチキとツェラは吹き飛ばされてしまいます。
砲撃を停止したセルビア軍の陣地から、古参兵(ムスタファ・ナダレヴィッチ)と新兵のニノ(レネ・ビトラヤツ)の二人が偵察に向かいます。
一方、塹壕の中で意識を回復したチキは、銃を手に物陰に隠れ、セルビア兵の様子をうかがいます。
地面に倒れているツェラの死体の他に誰もいないことを確認した古参兵は、ツェラの死体の下に地雷を埋め込みます。
どうしてそんなことをするのか、と聞くニノに古参兵は答えます。
「こうしておけば、こいつを動かそうとした途端に、爆発だ」
二人は立ち去ろうとしますが、物陰に潜んでいたチキは隙をみて飛び出し二人を銃撃します。
古参兵は死亡しましたが、ニノは負傷しただけで助かり、チキとニノの間には緊張した空気が生まれます。
チキの隙を見て銃を奪ったニノと、武器を失ったチキの立場が逆転する中で、死んだと思っていたツェラは意識を失っていただけで、体の下に地雷が設置されていることを知ったツェラは、自分が身動きの取れない状況に置かれていることを知ります。
簡単に取り外せるものと高を括(くく)っていたチキとニノでしたが、それは特殊な地雷で、自分たちの手に負えないとみたチキとニノは、両軍に停戦を呼びかけ、地雷撤去のために国連の防護軍が現場に向かうことになりますが…。
「世界の火薬庫」と呼ばれたバルカン半島(地政学的にはバルカン地域)。
多くの民族、宗教、言語が混在し、紛争の絶え間のないバルカンでは幾度となく国境線が塗り替えられ、作り替えられてきました。
戦争の世紀と呼ばれた20世紀が過ぎ、21世紀になった現在でも数々の紛争は世界各地で起きており、おそらく、地球上に人類が存在する以上、地上から戦争がなくなることはないと思います。
「ノー・マンズ・ランド」では、一体どうしてこんなことが起こるんだ! お前たちが悪いんだ! いや、お前たちだ! といったやり取りがチキとニノの間で交わされますが、紛争に明け暮れたバルカン地域の中で、もう何がどうなっているのか、そんな絶望的な状況をヤケッパチとも思えるユーモアをぶつけて描き出しました。
そこには勝者もなく、敗者もなく、ただ、無意味で残酷な結末が観る者に戦争の愚かしさを突き付けます。

監督はボスニア・ヘルツェゴビナ出身のダニス・タノヴィッチ。
「ノー・マンズ・ランド」以降も「「鉄くず拾いの物語」(2013年)、「汚れたミルク/あるセールスマンの告発」(2014年)、「サラエヴォの銃声」(2016年)など、社会性のある話題作を発表。数々の賞を受賞しています。
ボスニア兵チキに、俳優でミュージシャンでもあるブランコ・ジュリッチ。
セルビア兵ニノにクロアチア出身のレネ・ビトラヤツ。
サラエボ本部のソフト大佐に「アマデウス」(1984年)、「眺めのいい部屋」(1985年)、「オペラ座の怪人」(2004年)などの名優サイモン・キャロウ。
セクシーで美人の秘書を常に従え、状況を把握しながらも大事の中の小事は切り捨ててしまう、イヤな軍人像でありながらも強い印象を残しました。
野心に燃えるマスコミのジェーン・リヴィングストン特派員にカトリン・カートリッジ。
この人は「ノー・マンズ・ランド」の翌年2002年「デブラ・ウィンガーを探して」の出演を最後に41歳の若さで病死しています。
二転三転するストーリー展開、ひとり取り残されるツェラの映像と哀切な歌が流れるラストは、愚かしくも滑稽で、かつ残酷な人間世界の断面をえぐり出したといえます。

2020年02月16日
映画「鬼戦車T-34」- ナチスの包囲網を突っ切れ! 爆走するT-34
「鬼戦車T-34」
(Жаворонок) 1965年 ソビエト
監督ニキータ・クリーヒン
レオニード・メナケル
脚本ミハイル・ドウジン
セルゲイ・オルロフ
撮影ウラジミール・カラセフ
ニコライ・ジーリン
〈キャスト〉
ヴャチエスラフ・グレンコフ ゲンナジー・ユフチン
ワレリー・ポゴレリツェフ ヴァレンチン・スクルメ
第二次世界大戦のさなか、ドイツ軍の捕虜収容所で捕虜となっていたソ連の兵士たちはドイツ軍が開発中の新型砲弾の射撃訓練の標的にされていて、このままでは殺されてしまうから逃げようぜ、といって脱走を図るお話で、ソビエト兵3名とフランス兵1名の4人が一台の戦車に乗り込んだまま逃走を図った実話によります。
捕虜収容所からの実話をもとにした脱走劇といえば「大脱走」(1963年)が有名ですが、この「鬼戦車T-34」も娯楽性にあふれた、かなり見ごたえのある映画です。

1942年、ドイツ東部の捕虜収容所。
ソ連軍の捕虜イワン(ヴャチェスラフ・グレンコフ)は戦車操縦の経験を買われ、収容所で行われている戦車の整備を命じられます。
戦車の整備には他のソ連兵もあたっていましたが、イワンだけがドイツ軍に特別視されていることで、彼は捕虜仲間からは冷たい視線を向けられます。
ドイツ軍が取り組んでいたのはソ連戦に対しての新型砲弾の実験で、ソ連の最新戦車T-34に向けての射撃訓練でした。
演習場での訓練にあたって、その標的とされた戦車に乗り込んだのはイワンを始めとして、ピョートル(ゲンナジー・ユフチン)、アリョーシャ(ワレリー・ポゴレリツェフ)、そして、フランス兵ジャン(ヴァレンチン・スクレメ)の4名。
次々と砲弾の飛び交う中、イワンの操縦するT-34は砲弾をかわして走りますが、このままではやられてしまうと判断したイワンは、衣類を燃やして煙を出し、砲弾が命中したフリを装い、ドイツ軍が油断をしたスキを見て、そのまま演習場を突っ切って逃走を図ります。
慌てたドイツ軍は、30分以内に捕まえろ! とT-34捜索に軍用犬まで駆り出してやっきになりますが、相手は戦車とはいえ快速をもって聞こえたT-34。そう簡単には捕まりません。
森を抜け、街を突っ走り、街道を爆走してT-34はソ連領を目指しますが、じりじりと迫りくるドイツ軍の包囲網の前にジャンが倒れ、ピョートル、アリョーシャも死に、行動力の権化のようなイワンだけが残り、ドイツ軍が待ち構える中、道路を突っ切ろうとしたT-34の前に、道を横切ろうとした少年がつまずいて倒れ、戦車を止めて駆け寄ったイワンをめがけてドイツ軍の銃弾が火を吹きます。

原題は「ヒバリ」。
爆走に次ぐ爆走、記念碑や映画館をぶち壊し、死に物狂いで突っ走る戦車の映画で“ヒバリ”とはのどかすぎて感覚がズレているような気もしますが、チャイコフスキーのピアノ曲にもあるように、ロシアでヒバリは新しい生活をもたらす、といったような特別な意味があるらしく、T-34に乗って必死で逃走するイワンたちにとって、その先にあるものは新しい人生であるはずでした。
邦題の「鬼戦車…」というのは少年漫画にでも出てきそうな題名で、映画の内容からすればたしかに鬼のような戦車の話であるのには間違いないのですが、一方で、次第に芽生え始めるイワンたちの友情や、捕虜のロシア女性たちの牧草地での労働、花畑、森林、流れる小川、それらの詩情あふれる映像などは素晴らしく、娯楽性の中に抒情性を盛り込んだ、深みのある内容を持つ映画です。

それまで、ソ連の戦車は快速性はありましたが防御力に難点があり、その快速性を受け継ぎながら防御力を強化したのが機動戦を重視した中戦車T-34で、実戦投入されたのが1941年6月に始まった独ソ戦序盤のバルバロッサ作戦でした。
T-34を攻略すべくナチスは新型砲弾の開発を急いだのですから、「鬼戦車T-34」の主役はまさしく戦車T-34になろうかと思いますが、「ヒバリ」という原題が示すように、T-34をヒバリになぞらえ、それに乗って新たな人生に進もうとしたイワンたちの人間ドラマでもあるともいえます。
しかし、演習用の戦車ですから砲弾は無く、燃料も限られています。
「暁の七人」(1975年)のような悲劇的な末路が透けて見えるのですが、行動力あふれるイワンの存在が大きいためか、悲壮感はあっても一面では「俺たちに明日はない」(1967年)や、「明日に向かって撃て!」(1969年)のようなアメリカン・ニューシネマ的雰囲気を持っています。

ソ連映画といえば、国家予算をつぎ込んだ長大な映画が多い中で、エイゼンシュテインに代表される芸術的に優れた映画、レフ・トルストイの原作を忠実に映画化した超弩級の大作「戦争と平和」(1965年)、戦場での勲功によって、母親に会うために休暇をもらった通信兵の心の動きを追った「誓いの休暇」(1959年)などの名作があります。
そういったソ連映画の中で「鬼戦車T-34」は娯楽性、抒情性ともにすぐれた傑作で、分けても、捕虜となって農作業に従事しているロシア女性たちの間を縫って走るT-34と、味方だ! と叫んで戦車の後を追いかける女性たちの悲愴と歓喜の入り混じった映像は、白黒であるだけ余計に現実感をもって迫ります。
また、街に突入したT-34が、ドイツ将校たちのたむろする酒場を目がけ、実弾の入っていない砲身を向けて脅し、ビールをかっさらってくる場面の粋なこと。
アメリカン・ニューシネマならぬ、“ロシアン・ニューシネマ”と呼んでもいいような傑作です。



監督ニキータ・クリーヒン
レオニード・メナケル
脚本ミハイル・ドウジン
セルゲイ・オルロフ
撮影ウラジミール・カラセフ
ニコライ・ジーリン
〈キャスト〉
ヴャチエスラフ・グレンコフ ゲンナジー・ユフチン
ワレリー・ポゴレリツェフ ヴァレンチン・スクルメ
第二次世界大戦のさなか、ドイツ軍の捕虜収容所で捕虜となっていたソ連の兵士たちはドイツ軍が開発中の新型砲弾の射撃訓練の標的にされていて、このままでは殺されてしまうから逃げようぜ、といって脱走を図るお話で、ソビエト兵3名とフランス兵1名の4人が一台の戦車に乗り込んだまま逃走を図った実話によります。
捕虜収容所からの実話をもとにした脱走劇といえば「大脱走」(1963年)が有名ですが、この「鬼戦車T-34」も娯楽性にあふれた、かなり見ごたえのある映画です。

1942年、ドイツ東部の捕虜収容所。
ソ連軍の捕虜イワン(ヴャチェスラフ・グレンコフ)は戦車操縦の経験を買われ、収容所で行われている戦車の整備を命じられます。
戦車の整備には他のソ連兵もあたっていましたが、イワンだけがドイツ軍に特別視されていることで、彼は捕虜仲間からは冷たい視線を向けられます。
ドイツ軍が取り組んでいたのはソ連戦に対しての新型砲弾の実験で、ソ連の最新戦車T-34に向けての射撃訓練でした。
演習場での訓練にあたって、その標的とされた戦車に乗り込んだのはイワンを始めとして、ピョートル(ゲンナジー・ユフチン)、アリョーシャ(ワレリー・ポゴレリツェフ)、そして、フランス兵ジャン(ヴァレンチン・スクレメ)の4名。
次々と砲弾の飛び交う中、イワンの操縦するT-34は砲弾をかわして走りますが、このままではやられてしまうと判断したイワンは、衣類を燃やして煙を出し、砲弾が命中したフリを装い、ドイツ軍が油断をしたスキを見て、そのまま演習場を突っ切って逃走を図ります。
慌てたドイツ軍は、30分以内に捕まえろ! とT-34捜索に軍用犬まで駆り出してやっきになりますが、相手は戦車とはいえ快速をもって聞こえたT-34。そう簡単には捕まりません。
森を抜け、街を突っ走り、街道を爆走してT-34はソ連領を目指しますが、じりじりと迫りくるドイツ軍の包囲網の前にジャンが倒れ、ピョートル、アリョーシャも死に、行動力の権化のようなイワンだけが残り、ドイツ軍が待ち構える中、道路を突っ切ろうとしたT-34の前に、道を横切ろうとした少年がつまずいて倒れ、戦車を止めて駆け寄ったイワンをめがけてドイツ軍の銃弾が火を吹きます。

原題は「ヒバリ」。
爆走に次ぐ爆走、記念碑や映画館をぶち壊し、死に物狂いで突っ走る戦車の映画で“ヒバリ”とはのどかすぎて感覚がズレているような気もしますが、チャイコフスキーのピアノ曲にもあるように、ロシアでヒバリは新しい生活をもたらす、といったような特別な意味があるらしく、T-34に乗って必死で逃走するイワンたちにとって、その先にあるものは新しい人生であるはずでした。
邦題の「鬼戦車…」というのは少年漫画にでも出てきそうな題名で、映画の内容からすればたしかに鬼のような戦車の話であるのには間違いないのですが、一方で、次第に芽生え始めるイワンたちの友情や、捕虜のロシア女性たちの牧草地での労働、花畑、森林、流れる小川、それらの詩情あふれる映像などは素晴らしく、娯楽性の中に抒情性を盛り込んだ、深みのある内容を持つ映画です。
それまで、ソ連の戦車は快速性はありましたが防御力に難点があり、その快速性を受け継ぎながら防御力を強化したのが機動戦を重視した中戦車T-34で、実戦投入されたのが1941年6月に始まった独ソ戦序盤のバルバロッサ作戦でした。
T-34を攻略すべくナチスは新型砲弾の開発を急いだのですから、「鬼戦車T-34」の主役はまさしく戦車T-34になろうかと思いますが、「ヒバリ」という原題が示すように、T-34をヒバリになぞらえ、それに乗って新たな人生に進もうとしたイワンたちの人間ドラマでもあるともいえます。
しかし、演習用の戦車ですから砲弾は無く、燃料も限られています。
「暁の七人」(1975年)のような悲劇的な末路が透けて見えるのですが、行動力あふれるイワンの存在が大きいためか、悲壮感はあっても一面では「俺たちに明日はない」(1967年)や、「明日に向かって撃て!」(1969年)のようなアメリカン・ニューシネマ的雰囲気を持っています。

ソ連映画といえば、国家予算をつぎ込んだ長大な映画が多い中で、エイゼンシュテインに代表される芸術的に優れた映画、レフ・トルストイの原作を忠実に映画化した超弩級の大作「戦争と平和」(1965年)、戦場での勲功によって、母親に会うために休暇をもらった通信兵の心の動きを追った「誓いの休暇」(1959年)などの名作があります。
そういったソ連映画の中で「鬼戦車T-34」は娯楽性、抒情性ともにすぐれた傑作で、分けても、捕虜となって農作業に従事しているロシア女性たちの間を縫って走るT-34と、味方だ! と叫んで戦車の後を追いかける女性たちの悲愴と歓喜の入り混じった映像は、白黒であるだけ余計に現実感をもって迫ります。
また、街に突入したT-34が、ドイツ将校たちのたむろする酒場を目がけ、実弾の入っていない砲身を向けて脅し、ビールをかっさらってくる場面の粋なこと。
アメリカン・ニューシネマならぬ、“ロシアン・ニューシネマ”と呼んでもいいような傑作です。

2019年10月25日
映画「硫黄島からの手紙」- 激戦36日間の攻防 戦いの中で兵士たちは…
「硫黄島からの手紙」
(Letters from Iwo Jima)
2006年 アメリカ
監督クリント・イーストウッド
脚本アイリス・ヤマシタ
撮影トム・スターン
〈キャスト〉
渡辺謙 二宮和也 伊原剛志 加瀬亮 中村獅童
第79回アカデミー賞音響編集賞/第64回ゴールデングローブ賞最優秀外国語映画賞/全米映画批評家賞/サンディエゴ映画批評家協会賞/他受賞多数
東京都から南に約1100?q。小笠原諸島の南の端に位置する硫黄島は、東西8?q、南北4?qの小さな島です。
活火山の火山島であるため硫黄の臭いが強く、それがそのまま島名の由来になっています。
昭和19年(1944年)、本土防衛のため、大本営は小笠原諸島の防備の強化を開始。
陸・海部隊合わせて6245名が硫黄島に進出。
さらに参謀本部は小笠原諸島防備の増強を決め、第109師団を創設。
栗林忠道中将を師団長に任命し、栗林は昭和19年6月8日に硫黄島へ着任します。
栗林着任のほぼ一週間後の6月15日、米軍はサイパン上陸と合わせて硫黄島を空襲。
激戦の火ぶたが切って落とされます。

「硫黄島からの手紙」は、前作「父親たちの星条旗」に続く、二部作ともいえる硫黄島の激戦に取り組んだクリント・イーストウッドの監督作品で、アメリカ映画でありながら登場人物のほとんどが日本人で占められた異色作。
「父親たちの星条旗」がアメリカ側の視点でとらえた硫黄島のその後であったのに対し、「硫黄島からの手紙」では硫黄島の激戦そのものに焦点を当て、本土防衛のために捨て駒とされた絶海の孤島で、圧倒的な物量を誇る米軍に対し、日本軍2万129名が戦死。さらに米軍の戦傷者は2万8686名という壮絶な戦いを強いられた日本軍兵士たちの心の葛藤を丁寧に、そしてリアルに描き切った傑作です。
2006年。
硫黄島の戦跡調査隊は、日本軍がアメリカ軍を迎え撃つために潜(ひそ)んでいた地下陣地を調査中、おびただしい数の封書を発見します。
それは、硫黄島で戦い、死んでいった兵士たちが家族に宛てた手紙で、栗林忠道中将を始めとする帝国陸軍小笠原兵団の肉声ともいえるものでしたが、その手紙が家族の元に届くことなく、多くは遺骨となった彼らは、この島で何を思い、激しい戦いの中でどう生きたのか。
昭和19(1944)年6月8日、太平洋戦争の戦況が悪化する中、硫黄島を本土防衛のための砦とするため、日本軍守備隊として小笠原方面最高指揮官・栗林忠道中将(渡辺謙)が島へ降り立ちます。

駐在武官としてアメリカやカナダでの生活経験を持つ栗林の着任は、それまで、精神論に固執し、兵士たちに厳しさを押し付ける上官たちと違い、命の大切さを説く新鮮で暖かみのある指揮官として、応召兵で陸軍一等兵の西郷(二宮和也)たちに明るい光を投げかけます。
また、1932年のロサンゼルスオリンピック馬術競技金メダリストの西竹一中佐(伊原剛志)も愛馬と共に硫黄島へ着任。
チャーリー・チャップリンや“ハリウッドのキング”と呼ばれたダグラス・フェアバンクスとも親交のあった、ハンサムでダンディーな西の存在もまた、西郷たちの過酷な灼熱の日常に新鮮な風と空気を送り込むことになります。
しかし、アメリカ軍を迎え撃つために徹底抗戦を叫ぶ副官の藤田中尉(渡辺広)や伊藤大尉(中村獅童)たちに対して、米軍との兵力の差があり過ぎることを憂慮した栗林は、地下壕を掘り、島全体を要塞化してゲリラ戦に持ち込む作戦を提言。藤田中尉たちとの間に摩擦が生じます。
栗林の指揮のもと、地下陣地の構築が始まり、昭和20(1945)年2月19日、圧倒的な兵力をもってアメリカ軍が硫黄島への上陸を開始。
地下陣地に立てこもった日本軍は、トーチカのすき間から一斉に射撃を開始します。

日本軍とアメリカ軍では、兵力や物量の上であまりにも違いがあることから5日ほどで終了すると思われていた硫黄島の戦いは、36日間に及ぶ激戦の末にアメリカ軍の戦傷者の数が日本軍の戦死者の数を上回る結果となり、上陸部隊指揮官のホーランド・スミス海兵隊中将に「この戦いを指揮している日本の将軍は頭の切れるヤツだ」と言わしめた硫黄島の戦い。
しかし、映画「硫黄島からの手紙」は指揮官である栗林忠道中将を英雄視することなく、酒を酌み交わす間柄の西少佐とも確執の芽があることを淡々と描いていきます。
招集された一等兵・西郷の目を通して語られる「硫黄島からの手紙」は、戦場には不釣り合いなほど静かに流れるピアノの音色が、悲愴な血の臭いを浄化させるような不思議な雰囲気を醸し出し、死と静寂の世界を創り出していきます。
それは、戦場の兵士たちも家庭にあれば良き夫であり、戦争がなければごく普通の家庭人として平凡で静かな人生を送りえたであろう哀切さを、兵士たちが家族に宛てた手紙とともに、普通の生活が送れることへの裏返しの哀しさが込められているように思います。

そしてアメリカ軍上陸に始まる激戦は、ドリームワークスを率いるスティーヴン・スピルバーグが製作に参加していることもあって「プライベート・ライアン」のノルマンディー上陸に劣らない壮絶さ。
敗色が濃くなり、玉砕を叫び自決を強いる地下壕での凄惨さ。
栗林の命令を無視して夜間攻撃を仕掛ける伊藤大尉の無謀さと、だらしのない滑稽さ。
投降する日本兵に対し、こんな奴らのお守りはゴメンだとばかりに射殺してしまうアメリカ兵の非人道性。
けっして一方に肩入れすることなく、戦場で起こることのすべてをありのままに描こうとするイーストウッドの姿勢は、見る者の心に深い感動となって染みこみます。
栗林忠道中将に「ラストサムライ」(2003年)、「インセプション」(2010年)など、ハリウッドでも知名度の高い渡辺謙。
西郷一等兵に、アイドルグループ「嵐」のメンバーで、「母と暮らせば」(2015年)などの二宮和也。
伊藤大尉に、歌舞伎役者で、「利休」(1989年)、「レッドクリフ」(2008年)の中村獅童。
馬術競技金メダリストの西竹一中佐に、「病院へ行こう」(1990年)、「十三人の刺客」(2010年)の伊原剛志。
余談として、現在では硫黄島の読みは“いおうとう”に統一されていますが、歴史的には“いおうじま”“いおうとう”の両方があり、映画にも登場する「硫黄島防備の歌」の中でも“いおうじま”と歌われています。
明治時代に作成された海図にも“いおうじま”と表記されていて、アメリカ軍はこの海図をもとに“イオージマ”と呼んでいたようです。



2006年 アメリカ
監督クリント・イーストウッド
脚本アイリス・ヤマシタ
撮影トム・スターン
〈キャスト〉
渡辺謙 二宮和也 伊原剛志 加瀬亮 中村獅童
第79回アカデミー賞音響編集賞/第64回ゴールデングローブ賞最優秀外国語映画賞/全米映画批評家賞/サンディエゴ映画批評家協会賞/他受賞多数
東京都から南に約1100?q。小笠原諸島の南の端に位置する硫黄島は、東西8?q、南北4?qの小さな島です。
活火山の火山島であるため硫黄の臭いが強く、それがそのまま島名の由来になっています。
昭和19年(1944年)、本土防衛のため、大本営は小笠原諸島の防備の強化を開始。
陸・海部隊合わせて6245名が硫黄島に進出。
さらに参謀本部は小笠原諸島防備の増強を決め、第109師団を創設。
栗林忠道中将を師団長に任命し、栗林は昭和19年6月8日に硫黄島へ着任します。
栗林着任のほぼ一週間後の6月15日、米軍はサイパン上陸と合わせて硫黄島を空襲。
激戦の火ぶたが切って落とされます。

「硫黄島からの手紙」は、前作「父親たちの星条旗」に続く、二部作ともいえる硫黄島の激戦に取り組んだクリント・イーストウッドの監督作品で、アメリカ映画でありながら登場人物のほとんどが日本人で占められた異色作。
「父親たちの星条旗」がアメリカ側の視点でとらえた硫黄島のその後であったのに対し、「硫黄島からの手紙」では硫黄島の激戦そのものに焦点を当て、本土防衛のために捨て駒とされた絶海の孤島で、圧倒的な物量を誇る米軍に対し、日本軍2万129名が戦死。さらに米軍の戦傷者は2万8686名という壮絶な戦いを強いられた日本軍兵士たちの心の葛藤を丁寧に、そしてリアルに描き切った傑作です。
2006年。
硫黄島の戦跡調査隊は、日本軍がアメリカ軍を迎え撃つために潜(ひそ)んでいた地下陣地を調査中、おびただしい数の封書を発見します。
それは、硫黄島で戦い、死んでいった兵士たちが家族に宛てた手紙で、栗林忠道中将を始めとする帝国陸軍小笠原兵団の肉声ともいえるものでしたが、その手紙が家族の元に届くことなく、多くは遺骨となった彼らは、この島で何を思い、激しい戦いの中でどう生きたのか。
昭和19(1944)年6月8日、太平洋戦争の戦況が悪化する中、硫黄島を本土防衛のための砦とするため、日本軍守備隊として小笠原方面最高指揮官・栗林忠道中将(渡辺謙)が島へ降り立ちます。

駐在武官としてアメリカやカナダでの生活経験を持つ栗林の着任は、それまで、精神論に固執し、兵士たちに厳しさを押し付ける上官たちと違い、命の大切さを説く新鮮で暖かみのある指揮官として、応召兵で陸軍一等兵の西郷(二宮和也)たちに明るい光を投げかけます。
また、1932年のロサンゼルスオリンピック馬術競技金メダリストの西竹一中佐(伊原剛志)も愛馬と共に硫黄島へ着任。
チャーリー・チャップリンや“ハリウッドのキング”と呼ばれたダグラス・フェアバンクスとも親交のあった、ハンサムでダンディーな西の存在もまた、西郷たちの過酷な灼熱の日常に新鮮な風と空気を送り込むことになります。
しかし、アメリカ軍を迎え撃つために徹底抗戦を叫ぶ副官の藤田中尉(渡辺広)や伊藤大尉(中村獅童)たちに対して、米軍との兵力の差があり過ぎることを憂慮した栗林は、地下壕を掘り、島全体を要塞化してゲリラ戦に持ち込む作戦を提言。藤田中尉たちとの間に摩擦が生じます。
栗林の指揮のもと、地下陣地の構築が始まり、昭和20(1945)年2月19日、圧倒的な兵力をもってアメリカ軍が硫黄島への上陸を開始。
地下陣地に立てこもった日本軍は、トーチカのすき間から一斉に射撃を開始します。
日本軍とアメリカ軍では、兵力や物量の上であまりにも違いがあることから5日ほどで終了すると思われていた硫黄島の戦いは、36日間に及ぶ激戦の末にアメリカ軍の戦傷者の数が日本軍の戦死者の数を上回る結果となり、上陸部隊指揮官のホーランド・スミス海兵隊中将に「この戦いを指揮している日本の将軍は頭の切れるヤツだ」と言わしめた硫黄島の戦い。
しかし、映画「硫黄島からの手紙」は指揮官である栗林忠道中将を英雄視することなく、酒を酌み交わす間柄の西少佐とも確執の芽があることを淡々と描いていきます。
招集された一等兵・西郷の目を通して語られる「硫黄島からの手紙」は、戦場には不釣り合いなほど静かに流れるピアノの音色が、悲愴な血の臭いを浄化させるような不思議な雰囲気を醸し出し、死と静寂の世界を創り出していきます。
それは、戦場の兵士たちも家庭にあれば良き夫であり、戦争がなければごく普通の家庭人として平凡で静かな人生を送りえたであろう哀切さを、兵士たちが家族に宛てた手紙とともに、普通の生活が送れることへの裏返しの哀しさが込められているように思います。

そしてアメリカ軍上陸に始まる激戦は、ドリームワークスを率いるスティーヴン・スピルバーグが製作に参加していることもあって「プライベート・ライアン」のノルマンディー上陸に劣らない壮絶さ。
敗色が濃くなり、玉砕を叫び自決を強いる地下壕での凄惨さ。
栗林の命令を無視して夜間攻撃を仕掛ける伊藤大尉の無謀さと、だらしのない滑稽さ。
投降する日本兵に対し、こんな奴らのお守りはゴメンだとばかりに射殺してしまうアメリカ兵の非人道性。
けっして一方に肩入れすることなく、戦場で起こることのすべてをありのままに描こうとするイーストウッドの姿勢は、見る者の心に深い感動となって染みこみます。
栗林忠道中将に「ラストサムライ」(2003年)、「インセプション」(2010年)など、ハリウッドでも知名度の高い渡辺謙。
西郷一等兵に、アイドルグループ「嵐」のメンバーで、「母と暮らせば」(2015年)などの二宮和也。
伊藤大尉に、歌舞伎役者で、「利休」(1989年)、「レッドクリフ」(2008年)の中村獅童。
馬術競技金メダリストの西竹一中佐に、「病院へ行こう」(1990年)、「十三人の刺客」(2010年)の伊原剛志。
余談として、現在では硫黄島の読みは“いおうとう”に統一されていますが、歴史的には“いおうじま”“いおうとう”の両方があり、映画にも登場する「硫黄島防備の歌」の中でも“いおうじま”と歌われています。
明治時代に作成された海図にも“いおうじま”と表記されていて、アメリカ軍はこの海図をもとに“イオージマ”と呼んでいたようです。









