この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
広告
posted by fanblog
2021年04月18日
映画「心の旅路」‐ 記憶を失った男がたどる愛の名作
「心の旅路」
(Random Harvest) 1942年アメリカ
監督マーヴィン・ルロイ
原作ジェームズ・ヒルトン
脚本クローディン・ウェスト
ジョージ・フローシェル
アーサー・ウィンペリス
撮影ジョセフ・ルッテンバーグ
〈キャスト〉
ロナルド・コールマン グリア・ガースン
スーザン・ピータース ヘンリー・トラヴァース

「失われた地平線」「チップス先生さようなら」などのベストセラー作家ジェームズ・ヒルトンの同名小説を映画化。
記憶喪失になった陸軍大尉がたどる心の変遷を、情感あふれるドラマ構成で描いた名作。
1918年、4年間続いた第一次世界大戦も終わりを迎えようとする秋のころ。
戦場で負傷し、記憶を失ったイギリス陸軍大尉ジョン・スミス(ロナルド・コールマン)は、軍人障害者施設に入院しています。
自分が何者なのかを知ることのできないもどかしさを感じている彼は、ある日、病院を抜け出し、街に出かけます。
折しも街では終戦を祝う祝賀ムードの喧騒にあふれ、雑踏を避けようと入った煙草屋で、ジョン・スミスは旅芸人の踊子ポーラ・リッジウェイ(グリア・ガースン)に出会います。
記憶喪失のスミスに同情し、深いやさしさと美貌を持ったポーラにジョン・スミスは惹かれ、やがて二人は恋に落ちます。
ポーラは踊子を辞め、記憶は戻らず体調も思わしくないジョン・スミスと二人で喧騒の街を離れ、小川が流れ、庭に桜の木が枝を伸ばしている、ある静かな田舎の小さな家で暮らし始めます。
ポーラは、ジョン・スミスを愛称の「スミシー」と呼び、二人だけの穏やかな生活の中でポーラは妊娠、子どもが生まれます。

文才のあったジョン・スミスは執筆を始め、原稿を見た新聞社から採用通知を受け取ったスミシーはリバプールへ出かけますが、路上で車にはねられてしまいます。
怪我は大したことはなく、意識を回復したスミシーは、なぜ自分がここに居るのか理解できません。事故のショックで、記憶喪失になる以前の自分がよみがえり、逆に記憶を失ってからのポーラとの生活のすべての記憶が消失してしまっていました。
以前の記憶が戻り、ジョン・スミス(スミシー)ではなく、チャールズ・レニアとしての過去を取り戻して自宅へ帰ったチャールズは、父の葬儀と、遺言によって莫大な遺産を相続し、富豪としての生活を送ることになるのですが、ただ、ひとつの気がかりとして、事故の時に身につけていた玄関の鍵と思われる鍵と、なぜ自分は事故のときにリバプールにいたのか、という疑問がつきまといます。
一方、自宅へ戻ったチャールズに恋心を持つ少女がいました。
チャールズには姪にあたるキティ(スーザン・ピータース)です。姉の娘ではあるが、実の娘ではなく、夫の連れ子であるキティとは血のつながりがないため、キティはチャールズへの愛を燃やします。

実業家として成功したチャールズのオフィスには、子どもを失った失意のポーラが、マーガレット・ハンソンと名前を変えて、秘書として雇われていました。チャールズの現在を知り、自分とのつながりを失ってしまったと悟ったポーラは、なんとか彼の記憶を取り戻そうと考えるのですが、チャールズはポーラに気づくこともなく、月日は過ぎてゆきます。
キティとの交際は続き、彼女の愛を受け入れようと、やがてチャールズはキティとの婚約に踏み切りますが、チャールズには空白の記憶が障害となって心にわだかまり、そんなチャールズの気持ちを察したキティは自ら身を引いてゆきます。
時は流れ、国政選挙に打って出たチャールズは当選を果たし、政治家として活動を始めます。そして、それまで秘書として自分を支えてくれたマーガレットを妻として迎えようと考えます。
しかし、自分の愛を受け入れてくれたマーガレットには、誰か自分以外の男性の影がつきまとっていることを知ります。
どこかちぐはぐな関係を続けていたチャールズ(スミシー)とマーガレット(ポーラ)でしたが、どうしても彼の記憶が戻らないことに悲観したマーガレットはチャールズから離れ、南米へと旅経つ決心をします。

マーガレットの心が理解できないまま、チャールズは駅までマーガレットを見送り、所要で向かったメルブリッジの街でストライキに遭遇。やがて事なきを得たストライキの歓喜と喧騒の中、記憶の断片が現れ、知るはずのない煙草屋に立ち寄ったことから、おぼろげな記憶がよみがえりはじめます。
数年前の事故のとき、自分はなぜリバプールにいたのか、チャールズは記憶を追い求め、小川の流れる一軒の小さな家にたどり着きます。
一方、チャールズが記憶を取り戻しはじめたことを知ったマーガレットは、かつて彼をスミシーと呼び、仲睦まじく暮らしていた自分たちの家へと急ぎます。
軋んだ庭の扉を開け、桜の枝に頭をひっかけたチャールズは、鮮明になろうとする過去の思い出の中で、手にしていた鍵で家のドアを開けると、背後から彼の名前を呼ぶ声が響きます。
「スミシー!」
記憶喪失を題材にした作品にはアンリ・コルピ監督、アリダ・ヴァリ主演の「かくも長き不在」(1961年フランス )などの名作があり、戦争の暗い影が背景に重く揺らいでいます。ハリソン・フォードが主演した「心の旅」(1991年 マイク・ニコルズ監督)は、ややエンターテインメントに傾きましたが、自己を見つめ直す一人の男の姿が感動を呼びました。
また、手塚治虫の漫画「ブラック・ジャック」の一連の作品の中で「ネコと庄造と」では、ヒューマニズムにあふれる「ブラック・ジャック」の中でも特に胸に残る佳作でした。
「心の旅路」は、「哀愁」(1940年)、「ミニヴァー夫人」(1942年)、「ガス燈」(1944年)、「傷だらけの栄光」(1956年)などで手腕を発揮して、アカデミー撮影賞で数々の受賞をしたジョセフ・ルッテンバーグのすぐれた映像と、「心の旅路」と同年の「ミニヴァー夫人」でアカデミー主演女優賞を受賞したグリア・ガースンのスケールの大きな演技が生んだ名作です。
しかし、この映画はグリア・ガースンにとどまらず、チャールズを恋する一途な少女キティを演じたスーザン・ピータース(狩猟事故による後遺症で1952年に31歳の若さで死去)も助演女優賞候補になるなど脇役も素晴らしく、「ミニヴァー夫人」でアカデミー賞助演男優賞にノミネートされたヘンリー・トラヴァースも村の医者として顔をのぞかせています。
また、一度見たら忘れがたい風貌を持ったウナ・オコナー。ジョン・スミスとポーラの出会いの場所となる煙草屋の女店主で、この人は、ビリー・ワイルダー監督の傑作ミステリー「情婦」(1957年 タイロン・パワー主演)でのアクの強い家政婦役は、主演のマレーネ・ディートリッヒと共に強く印象に残りました。
ただ、チャールズが記憶を取り戻してゆく過程では、なんとなく都合が良すぎるような印象がありますが、そういった欠点も、ラストで二人が抱き合う感動的なシーンで吹き飛んでしまうくらいのもの。
「哀愁」(1940年)を手がけ、後に「キュリー夫人」(1943年)、「若草物語」(1949年)などの名作も手がけた名匠マーヴィン・ルロイのメロドラマの名作。



監督マーヴィン・ルロイ
原作ジェームズ・ヒルトン
脚本クローディン・ウェスト
ジョージ・フローシェル
アーサー・ウィンペリス
撮影ジョセフ・ルッテンバーグ
〈キャスト〉
ロナルド・コールマン グリア・ガースン
スーザン・ピータース ヘンリー・トラヴァース

「失われた地平線」「チップス先生さようなら」などのベストセラー作家ジェームズ・ヒルトンの同名小説を映画化。
記憶喪失になった陸軍大尉がたどる心の変遷を、情感あふれるドラマ構成で描いた名作。
1918年、4年間続いた第一次世界大戦も終わりを迎えようとする秋のころ。
戦場で負傷し、記憶を失ったイギリス陸軍大尉ジョン・スミス(ロナルド・コールマン)は、軍人障害者施設に入院しています。
自分が何者なのかを知ることのできないもどかしさを感じている彼は、ある日、病院を抜け出し、街に出かけます。
折しも街では終戦を祝う祝賀ムードの喧騒にあふれ、雑踏を避けようと入った煙草屋で、ジョン・スミスは旅芸人の踊子ポーラ・リッジウェイ(グリア・ガースン)に出会います。
記憶喪失のスミスに同情し、深いやさしさと美貌を持ったポーラにジョン・スミスは惹かれ、やがて二人は恋に落ちます。
ポーラは踊子を辞め、記憶は戻らず体調も思わしくないジョン・スミスと二人で喧騒の街を離れ、小川が流れ、庭に桜の木が枝を伸ばしている、ある静かな田舎の小さな家で暮らし始めます。
ポーラは、ジョン・スミスを愛称の「スミシー」と呼び、二人だけの穏やかな生活の中でポーラは妊娠、子どもが生まれます。

文才のあったジョン・スミスは執筆を始め、原稿を見た新聞社から採用通知を受け取ったスミシーはリバプールへ出かけますが、路上で車にはねられてしまいます。
怪我は大したことはなく、意識を回復したスミシーは、なぜ自分がここに居るのか理解できません。事故のショックで、記憶喪失になる以前の自分がよみがえり、逆に記憶を失ってからのポーラとの生活のすべての記憶が消失してしまっていました。
以前の記憶が戻り、ジョン・スミス(スミシー)ではなく、チャールズ・レニアとしての過去を取り戻して自宅へ帰ったチャールズは、父の葬儀と、遺言によって莫大な遺産を相続し、富豪としての生活を送ることになるのですが、ただ、ひとつの気がかりとして、事故の時に身につけていた玄関の鍵と思われる鍵と、なぜ自分は事故のときにリバプールにいたのか、という疑問がつきまといます。
一方、自宅へ戻ったチャールズに恋心を持つ少女がいました。
チャールズには姪にあたるキティ(スーザン・ピータース)です。姉の娘ではあるが、実の娘ではなく、夫の連れ子であるキティとは血のつながりがないため、キティはチャールズへの愛を燃やします。

実業家として成功したチャールズのオフィスには、子どもを失った失意のポーラが、マーガレット・ハンソンと名前を変えて、秘書として雇われていました。チャールズの現在を知り、自分とのつながりを失ってしまったと悟ったポーラは、なんとか彼の記憶を取り戻そうと考えるのですが、チャールズはポーラに気づくこともなく、月日は過ぎてゆきます。
キティとの交際は続き、彼女の愛を受け入れようと、やがてチャールズはキティとの婚約に踏み切りますが、チャールズには空白の記憶が障害となって心にわだかまり、そんなチャールズの気持ちを察したキティは自ら身を引いてゆきます。
時は流れ、国政選挙に打って出たチャールズは当選を果たし、政治家として活動を始めます。そして、それまで秘書として自分を支えてくれたマーガレットを妻として迎えようと考えます。
しかし、自分の愛を受け入れてくれたマーガレットには、誰か自分以外の男性の影がつきまとっていることを知ります。
どこかちぐはぐな関係を続けていたチャールズ(スミシー)とマーガレット(ポーラ)でしたが、どうしても彼の記憶が戻らないことに悲観したマーガレットはチャールズから離れ、南米へと旅経つ決心をします。
マーガレットの心が理解できないまま、チャールズは駅までマーガレットを見送り、所要で向かったメルブリッジの街でストライキに遭遇。やがて事なきを得たストライキの歓喜と喧騒の中、記憶の断片が現れ、知るはずのない煙草屋に立ち寄ったことから、おぼろげな記憶がよみがえりはじめます。
数年前の事故のとき、自分はなぜリバプールにいたのか、チャールズは記憶を追い求め、小川の流れる一軒の小さな家にたどり着きます。
一方、チャールズが記憶を取り戻しはじめたことを知ったマーガレットは、かつて彼をスミシーと呼び、仲睦まじく暮らしていた自分たちの家へと急ぎます。
軋んだ庭の扉を開け、桜の枝に頭をひっかけたチャールズは、鮮明になろうとする過去の思い出の中で、手にしていた鍵で家のドアを開けると、背後から彼の名前を呼ぶ声が響きます。
「スミシー!」
記憶喪失を題材にした作品にはアンリ・コルピ監督、アリダ・ヴァリ主演の「かくも長き不在」(1961年フランス )などの名作があり、戦争の暗い影が背景に重く揺らいでいます。ハリソン・フォードが主演した「心の旅」(1991年 マイク・ニコルズ監督)は、ややエンターテインメントに傾きましたが、自己を見つめ直す一人の男の姿が感動を呼びました。
また、手塚治虫の漫画「ブラック・ジャック」の一連の作品の中で「ネコと庄造と」では、ヒューマニズムにあふれる「ブラック・ジャック」の中でも特に胸に残る佳作でした。
「心の旅路」は、「哀愁」(1940年)、「ミニヴァー夫人」(1942年)、「ガス燈」(1944年)、「傷だらけの栄光」(1956年)などで手腕を発揮して、アカデミー撮影賞で数々の受賞をしたジョセフ・ルッテンバーグのすぐれた映像と、「心の旅路」と同年の「ミニヴァー夫人」でアカデミー主演女優賞を受賞したグリア・ガースンのスケールの大きな演技が生んだ名作です。
しかし、この映画はグリア・ガースンにとどまらず、チャールズを恋する一途な少女キティを演じたスーザン・ピータース(狩猟事故による後遺症で1952年に31歳の若さで死去)も助演女優賞候補になるなど脇役も素晴らしく、「ミニヴァー夫人」でアカデミー賞助演男優賞にノミネートされたヘンリー・トラヴァースも村の医者として顔をのぞかせています。
また、一度見たら忘れがたい風貌を持ったウナ・オコナー。ジョン・スミスとポーラの出会いの場所となる煙草屋の女店主で、この人は、ビリー・ワイルダー監督の傑作ミステリー「情婦」(1957年 タイロン・パワー主演)でのアクの強い家政婦役は、主演のマレーネ・ディートリッヒと共に強く印象に残りました。
ただ、チャールズが記憶を取り戻してゆく過程では、なんとなく都合が良すぎるような印象がありますが、そういった欠点も、ラストで二人が抱き合う感動的なシーンで吹き飛んでしまうくらいのもの。
「哀愁」(1940年)を手がけ、後に「キュリー夫人」(1943年)、「若草物語」(1949年)などの名作も手がけた名匠マーヴィン・ルロイのメロドラマの名作。

2020年11月29日
映画「運び屋」‐ 麻薬の“運び屋”は90歳の老人, イーストウッドが魅せる円熟の一作
「運び屋」
(The Mule ) 2018年 アメリカ
監督クリント・イーストウッド
脚本ニック・シェンク
音楽アルトゥロ・サンドバル
撮影イブ・ベランジェ
〈キャスト〉
クリント・イーストウッド ブラッドリー・クーパー
ダイアン・ウィースト アンディ・ガルシア
「運び屋」という題名から、宅配業者か、引っ越し屋さんの話かと思ったら、ヒョンなことから麻薬組織に関わった男の話で、それも、90歳という高齢でヘロインの“運び屋”をすることになった男の実話をもとに、仕事、家族、老い、人生の意義といった普遍的なテーマを追求したクリント・イーストウッド監督・主演による、心に染み込む佳作。

“デイリリー”の栽培を手掛け、園芸家として名を馳(は)せて仕事一筋に打ち込んできたアール・ストーン(クリント・イーストウッド)でしたが、インターネットの普及とともにネット販売による打撃を受け、家は差し押さえられて経済的困窮に陥ります。
家族を顧(かえり)みずに仕事一筋に生きてきた結果が仇(あだ)となって、娘の結婚パーティーからも締め出しをくったアールでしたが、そこで、一人の男に声をかけられます。
「いい仕事があるんだ、やってみないか?」
それは簡単な仕事で、自分のオンボロトラックでハイウェーを走り、ある品物を届けるだけ。
無事故無違反を誇るアールは気楽にその仕事を引き受け、指定の場所に品物を届けて車に戻ってみると、仕事の報酬として誰かが置いていった封筒の中に厚い札束が入っている。
大金を受け取ったアールは、家を買い戻し、資金不足で活動が危ぶまれていた退役軍人会を復活させます。
“運び屋”の仕事は続き、二度、三度と重ねるうちに運ぶ品物の量は増え、それにつれてアールの報酬も上がり、オンボロトラックを新車に替えたアールでしたが、品物を運ぶ途中、偶然にそれが大量のヘロインであることを知ります。
犯罪の泥沼に足を踏み込んでいたことを知ったアール。しかし、目の前にチラつく大金と、朝鮮戦争の経験もあって怖いもの知らずのアールは、組織の中で一目置かれる存在となって麻薬組織のボス、ラトン(アンディ・ガルシア)の屋敷に招待され、美女を集めた豪華なパーティーにも招かれるようになります。

一方、麻薬組織撲滅に執念を燃やすベイツ捜査官(ブラッドリー・クーパー)とトレビノ捜査官(マイケル・ペーニャ)のもと、緻密な捜査網が敷かれ、“運び屋”の行動が明らかになっていきます。
捜査の手が伸びていることを知ったアールでしたが、組織の内紛によって厳しい監視がつく中、運び屋としての仕事を続けますが、そんなアールのケータイに、妻メアリー(ダイアン・ウィースト)の病状の悪化と危篤の電話が入ります。

“デイリリー”は学名をヘメロカリス。アジア原産の多年草で、赤やピンク、白、オレンジなどの美しい花を咲かせます。
英語名のデイリリーは文字通り一日しか花が開かないことから、その名がつけられたと思われ、その花をアールがこよなく愛している、心優しい園芸家であると同時に、臆することなく麻薬組織のボスとも友人のように付き合う一風変わった個性の持ち主のアール・ストーン。
映画「運び屋」はユニークな個性を持ったひとりの男のドラマであるといえます。
たとえば、こんなシーンがあります。
ハイウェーで“仕事”の途中、パンクをして途方に暮れている黒人の男女がいます。二人はパンクの直し方が分からず、男性はスマートフォンを片手にさかんに誰かと交信をしようとしているらしいのですが、電波が届かない。
アールは二人に近寄り、修理をしてやろうとします。
そのときアールは独り言で「おれはニグロのパンクを…」
悪気でつぶやいたわけでもないのですが、その言葉を聞きとがめた男はサングラスをはずし、こう言います。
「いまはそんな言葉を使っちゃいけないんだ」
アールは応えます。「ふうん、そうなのか」
とかく老人というのは頑迷固陋(がんめいころう)で、自分の主張を、いいも悪いもなく押し通そうとしますが、時代にズレているアールの生活感覚と、間違いを指摘されて気色ばむこともなく、ああ、そうなのか、とそのまま聞き入れる精神の柔軟さ。
これが90歳近い老人であるところに不思議な心の高まりを感じます。
なんでもないシーンですが、アール・ストーンのユニークな人間性はいくつかのエピソードの中で描かれていって、アールの監視役として、いつもアールに反発していた若いギャングのフリオ(イグナシオ・セリッチオ)に対してアールはこんなことを言います。
「こんなことをいつまでも続けていたらダメだ。アシを洗ったらどうだ」
「勝手なことを言うな。おれはラトンに拾われてここまでになったんだ」
…そうか、悪かったな。そうやってアールは引き下がります。
エンターテインメントとシリアスな人間ドラマを織り交ぜた「運び屋」の主要なテーマを色濃く表しているのが、後半からラストにかけてでしょう。
ハイウェーで妻の危篤を知ったアールは、大量のヘロインを運んでいる最中であり、組織の監視に付きまとわれている身として、そのまま仕事を放り出して病院へ駆けつければ殺されてしまうことは分かり切っています。絶体絶命の中、アール・ストーンはハイウェーを去り、妻の死を看取ることを決意します。

監督・主演のクリント・イーストウッドは、これが自身39本目の監督作品。
「恐怖のメロディ」(1971年)、「アイガー・サンクション」(1975年)、「ガントレット」(1977年)、などいくつか面白い映画もありましたが、全体としてイーストウッド監督作品は、暗く、重い印象のほうが強くて、監督はしないほうがいいんじゃないかなあ、などと思ったりしましたが、おそらく、そういった過去の失敗作やB級としての評価しか受けなかった映画を作り続けた中で磨かれてきた感性が花開いたのが、第65回アカデミー賞の作品賞に輝いた「許されざる者」(1992年)の快挙だったのでしょう。
役柄のアール・ストーンとは、ほぼ同年齢のイーストウッドは老いを恥じることなく、年齢なんか関係ない、と言わんばかりですが、むしろここでは、見放すがごとくほったらかしにしてきた家族に対する反省と悔恨の心情が湧き出る泉のように溢れていて、それがベイツ捜査官や、死の床にある妻との会話の中でじっくりと語られ、イーストウッド自身の半生と重なって深みのある映画となっているのでしょう(売れない時代に陰で支えてくれた最初の妻マギーをないがしろにして、若い愛人と戯れるイーストウッドの写真や記事が、当時の映画雑誌をにぎわせていましたしね)。
妻のメアリーを演じたダイアン・ウィーストも良かったなあ。
ウディ・アレンが監督した傑作コメディ「ハンナとその姉妹」(1986年)でアカデミー賞助演女優賞を受賞した次女の印象も強いですが、ティム・バートンの「シザーハンズ」(1990年)の化粧品のセールスの場面が特によかった。ドアのチャイムを鳴らして、出て来た相手に、にこやかな顔で自分の頬をこする仕草をしながら「エイボン化粧品です」。
この場面が特に良かった。
「運び屋」では、家庭を顧みない夫に愛想を尽かしながらも、心の深いところでやっぱり夫とつながっている、妻として傷つきながら、穏やかな表情を絶やさない妻メアリーは絶品。
ベイツ捜査官らの上司、主任特別捜査官にローレンス・フィッシュバーン。
組織のボス、ラトンにアンディ・ガルシアなど、脇をガッチリと固めた布陣も素晴らしく、熟成されてますます深みと味わいを増したクリント・イーストウッド円熟の一作。



監督クリント・イーストウッド
脚本ニック・シェンク
音楽アルトゥロ・サンドバル
撮影イブ・ベランジェ
〈キャスト〉
クリント・イーストウッド ブラッドリー・クーパー
ダイアン・ウィースト アンディ・ガルシア
「運び屋」という題名から、宅配業者か、引っ越し屋さんの話かと思ったら、ヒョンなことから麻薬組織に関わった男の話で、それも、90歳という高齢でヘロインの“運び屋”をすることになった男の実話をもとに、仕事、家族、老い、人生の意義といった普遍的なテーマを追求したクリント・イーストウッド監督・主演による、心に染み込む佳作。

“デイリリー”の栽培を手掛け、園芸家として名を馳(は)せて仕事一筋に打ち込んできたアール・ストーン(クリント・イーストウッド)でしたが、インターネットの普及とともにネット販売による打撃を受け、家は差し押さえられて経済的困窮に陥ります。
家族を顧(かえり)みずに仕事一筋に生きてきた結果が仇(あだ)となって、娘の結婚パーティーからも締め出しをくったアールでしたが、そこで、一人の男に声をかけられます。
「いい仕事があるんだ、やってみないか?」
それは簡単な仕事で、自分のオンボロトラックでハイウェーを走り、ある品物を届けるだけ。
無事故無違反を誇るアールは気楽にその仕事を引き受け、指定の場所に品物を届けて車に戻ってみると、仕事の報酬として誰かが置いていった封筒の中に厚い札束が入っている。
大金を受け取ったアールは、家を買い戻し、資金不足で活動が危ぶまれていた退役軍人会を復活させます。
“運び屋”の仕事は続き、二度、三度と重ねるうちに運ぶ品物の量は増え、それにつれてアールの報酬も上がり、オンボロトラックを新車に替えたアールでしたが、品物を運ぶ途中、偶然にそれが大量のヘロインであることを知ります。
犯罪の泥沼に足を踏み込んでいたことを知ったアール。しかし、目の前にチラつく大金と、朝鮮戦争の経験もあって怖いもの知らずのアールは、組織の中で一目置かれる存在となって麻薬組織のボス、ラトン(アンディ・ガルシア)の屋敷に招待され、美女を集めた豪華なパーティーにも招かれるようになります。

一方、麻薬組織撲滅に執念を燃やすベイツ捜査官(ブラッドリー・クーパー)とトレビノ捜査官(マイケル・ペーニャ)のもと、緻密な捜査網が敷かれ、“運び屋”の行動が明らかになっていきます。
捜査の手が伸びていることを知ったアールでしたが、組織の内紛によって厳しい監視がつく中、運び屋としての仕事を続けますが、そんなアールのケータイに、妻メアリー(ダイアン・ウィースト)の病状の悪化と危篤の電話が入ります。
“デイリリー”は学名をヘメロカリス。アジア原産の多年草で、赤やピンク、白、オレンジなどの美しい花を咲かせます。
英語名のデイリリーは文字通り一日しか花が開かないことから、その名がつけられたと思われ、その花をアールがこよなく愛している、心優しい園芸家であると同時に、臆することなく麻薬組織のボスとも友人のように付き合う一風変わった個性の持ち主のアール・ストーン。
映画「運び屋」はユニークな個性を持ったひとりの男のドラマであるといえます。
たとえば、こんなシーンがあります。
ハイウェーで“仕事”の途中、パンクをして途方に暮れている黒人の男女がいます。二人はパンクの直し方が分からず、男性はスマートフォンを片手にさかんに誰かと交信をしようとしているらしいのですが、電波が届かない。
アールは二人に近寄り、修理をしてやろうとします。
そのときアールは独り言で「おれはニグロのパンクを…」
悪気でつぶやいたわけでもないのですが、その言葉を聞きとがめた男はサングラスをはずし、こう言います。
「いまはそんな言葉を使っちゃいけないんだ」
アールは応えます。「ふうん、そうなのか」
とかく老人というのは頑迷固陋(がんめいころう)で、自分の主張を、いいも悪いもなく押し通そうとしますが、時代にズレているアールの生活感覚と、間違いを指摘されて気色ばむこともなく、ああ、そうなのか、とそのまま聞き入れる精神の柔軟さ。
これが90歳近い老人であるところに不思議な心の高まりを感じます。
なんでもないシーンですが、アール・ストーンのユニークな人間性はいくつかのエピソードの中で描かれていって、アールの監視役として、いつもアールに反発していた若いギャングのフリオ(イグナシオ・セリッチオ)に対してアールはこんなことを言います。
「こんなことをいつまでも続けていたらダメだ。アシを洗ったらどうだ」
「勝手なことを言うな。おれはラトンに拾われてここまでになったんだ」
…そうか、悪かったな。そうやってアールは引き下がります。
エンターテインメントとシリアスな人間ドラマを織り交ぜた「運び屋」の主要なテーマを色濃く表しているのが、後半からラストにかけてでしょう。
ハイウェーで妻の危篤を知ったアールは、大量のヘロインを運んでいる最中であり、組織の監視に付きまとわれている身として、そのまま仕事を放り出して病院へ駆けつければ殺されてしまうことは分かり切っています。絶体絶命の中、アール・ストーンはハイウェーを去り、妻の死を看取ることを決意します。

監督・主演のクリント・イーストウッドは、これが自身39本目の監督作品。
「恐怖のメロディ」(1971年)、「アイガー・サンクション」(1975年)、「ガントレット」(1977年)、などいくつか面白い映画もありましたが、全体としてイーストウッド監督作品は、暗く、重い印象のほうが強くて、監督はしないほうがいいんじゃないかなあ、などと思ったりしましたが、おそらく、そういった過去の失敗作やB級としての評価しか受けなかった映画を作り続けた中で磨かれてきた感性が花開いたのが、第65回アカデミー賞の作品賞に輝いた「許されざる者」(1992年)の快挙だったのでしょう。
役柄のアール・ストーンとは、ほぼ同年齢のイーストウッドは老いを恥じることなく、年齢なんか関係ない、と言わんばかりですが、むしろここでは、見放すがごとくほったらかしにしてきた家族に対する反省と悔恨の心情が湧き出る泉のように溢れていて、それがベイツ捜査官や、死の床にある妻との会話の中でじっくりと語られ、イーストウッド自身の半生と重なって深みのある映画となっているのでしょう(売れない時代に陰で支えてくれた最初の妻マギーをないがしろにして、若い愛人と戯れるイーストウッドの写真や記事が、当時の映画雑誌をにぎわせていましたしね)。
妻のメアリーを演じたダイアン・ウィーストも良かったなあ。
ウディ・アレンが監督した傑作コメディ「ハンナとその姉妹」(1986年)でアカデミー賞助演女優賞を受賞した次女の印象も強いですが、ティム・バートンの「シザーハンズ」(1990年)の化粧品のセールスの場面が特によかった。ドアのチャイムを鳴らして、出て来た相手に、にこやかな顔で自分の頬をこする仕草をしながら「エイボン化粧品です」。
この場面が特に良かった。
「運び屋」では、家庭を顧みない夫に愛想を尽かしながらも、心の深いところでやっぱり夫とつながっている、妻として傷つきながら、穏やかな表情を絶やさない妻メアリーは絶品。
ベイツ捜査官らの上司、主任特別捜査官にローレンス・フィッシュバーン。
組織のボス、ラトンにアンディ・ガルシアなど、脇をガッチリと固めた布陣も素晴らしく、熟成されてますます深みと味わいを増したクリント・イーストウッド円熟の一作。

2019年12月28日
映画「ひまわり」− 戦争によって引き裂かれる一組の夫婦, 原野に咲くひまわりの意味とは…
「ひまわり」
(I Girasoli) 1970年
イタリア/フランス/ソ連(当時)合作
監督ヴィットリオ・デ・シーカ
脚本チェーザレ・サヴァッティーニ
アントニオ・グエラ
ゲオルギ・ムディバニ
撮影ジュゼッペ・ロトゥンノ
音楽ヘンリー・マンシーニ
〈キャスト〉
ソフィア・ローレン マルチェロ・マストロヤンニ
リュドミラ・サヴェーリエワ
戦地へ出征して、なんらかの理由でそのままその地にとどまった兵士は少なからず存在したのだろうと思います。
数年前にNHKのラジオニュースで、インドネシア(だったかな?)で、元日本兵が存在しているというニュースが流れたことがあります。
でもその人は、横井庄一さんや小野田寛郎さんのように終戦を知らずに戦後数十年をその地で過ごしていたわけではなく、戦争が終わっても帰国をせずに、現地で家庭を持って静かに暮らしていたということです。
竹山道雄の名作「ビルマの竪琴」の主人公・水島上等兵のように、戦死して無縁仏のようになった兵士を弔うため、僧になってビルマをさまよった人もいたかもしれません。
戦争という歴史の大きな歯車によって、思わぬ方向へ人生がねじ曲げられてしまう悲劇を描いた「ひまわり」は、巨匠ヴィットリオ・デ・シーカによる永遠の名作です。
電気技師のアントニオ(マルチェロ・マストロヤンニ)と勝気で陽気なナポリ女ジョバンナ(ソフィア・ローレン)は、出会ってすぐに恋に落ちます。
戦時中であり、アフリカ戦線への出征が決まっていたアントニオは、結婚をすれば12日間の休暇がもらえるし、その間に戦争は終わるだろうと、気楽な二人は結婚式を挙げ、12日間の新婚生活を楽しみますが(卵24個を使ったオムレツを食べるシーンは秀逸)、それも夢のように過ぎてしまい、兵役を回避するため二人は一芝居打ちます。
妻のジョバンナをナイフで突然追いまわし、精神異常を装ったアントニオでしたが、偽芝居はあえなく露見。
懲罰のためアントニオはロシア戦線へ送られることになります。
ミラノ駅で夫を見送るジョバンナに「すぐに帰ってくる」と言い残して、アントニオは大勢の兵士と共にミラノ駅を後にして出征してゆきます。

年月は過ぎ、夫の帰りを待ちわびていたジョバンナは終戦の知らせを受け、帰国するであろう夫を迎えるためミラノ駅へ向かいます。
アントニオの写真を手に、列車から到着する復員兵たちの中にアントニオの姿を探しますが、夫の姿はありません。
落胆するジョバンナでしたが、列車から降りた復員兵の中に、ドン河付近でアントニオを見かけたという男がジョバンナに語りかけます。
…迫りくるロシア兵と、見渡すかぎりの雪原に舞う吹雪。
退却を余儀なくされた部隊は極寒と飢えの中で、ひとり、またひとりと倒れ、その中でアントニオも雪原に倒れてしまったのです。
しかし、アントニオの死を確認した者はなく、彼は生きているはずだと思い詰めたジョバンナはアントニオの消息を確かめるべく、スターリン亡き後のモスクワ行きを決意します。

広大なロシアの地でイタリア軍が戦ったとされる戦域を訪ね歩いたジョバンナは、外務省の担当官から見渡す限りの野に咲くひまわりの群生地に案内されます。
そこはイタリア兵とロシア軍の捕虜が埋葬されている地で、兵士だけではなく、女性や子どももドイツ軍によって埋められている、いわば原野の墓場であり、そこに咲いている何万本とも知れぬひまわりの数だけ死者が眠っていることを意味しています。
「生きて帰ったイタリア兵はいない」と言われ、夫の探索をあきらめるよううながされたジョバンナでしたが、どこかで生きているであろうアントニオを信じるジョバンナはあきらめず、アントニオの写真を手に村々を訪ね歩いたジョバンナは、ついに夫の消息をつかみますが…。
監督は、「自転車泥棒」(1948年)、「終着駅」(1953年)、「昨日・今日・明日」(1963年)の巨匠ヴィットリオ・デ・シーカ。
ジョバンナに「島の女」(1957年)、「ふたりの女」(1960年)、「ラ・マンチャの男」(1972年)のソフィア・ローレン。
アントニオに「甘い生活」(1960年)、「イタリア式離婚狂想曲」(1962年)、「8 1/2」(1963年)の名優マルチェロ・マストロヤンニ。
そして、
瀕死のアントニオを助け、彼の妻になるロシア人女性に「戦争と平和」(1965年—1968年)のナターシャ役で世界を魅了したリュドミラ・サヴェーリエワ。
哀愁に満ちた情感漂う「ひまわり」のテーマ曲は、「ティファニーで朝食を」(1961年)、「酒とバラの日々」(1962年)、「ピンクパンサー」シリーズなど、映画音楽界の巨匠ヘンリー・マンシーニ。
独特の映像美とカメラワークは「山猫」(1963年)、「愛の狩人」(1971年)、「フェリーニのローマ」(1972年)などの名手ジュゼッペ・ロトゥンノ。

第二次世界大戦はナチス・ドイツによるポーランド侵攻によって勃発するのですが、それ以前から世界戦争の火だねのようなものは燃えていて、やがて日本・ドイツ・イタリアの枢軸国とアメリカ・イギリス・オランダ・フランスなどの連合国との戦争に発展してゆき、ヨーロッパを主戦場としたドイツに対し、その多くの戦場を太平洋とした日本。
日独伊三国同盟といわれる中で、よく分からないのがイタリアの動きで、ムッソリーニの独裁国家であったイタリアですが、半島では内戦が勃発。
1940年に地中海の制海権とエジプトでの支配を目指したイタリアは北アフリカへ侵攻。
ほどなくしてドイツとソビエトの間に交わされていた独ソ不可侵条約が破棄され、ドイツはロシアへの侵攻を開始。
ナチス・ドイツに対する追随政策をとるムッソリーニはロシア戦線へ軍を派遣することになります。
「靴みがき」(1946年)や「自転車泥棒」(1948年)によって、ロベルト・ロッセリーニなどと並んでイタリアン・ネオレアリズモの代表的な監督として知られるようになったデ・シーカですが、「終着駅」にみられるようなメロドラマの醍醐味は「ひまわり」でも存分に生かされていて、特に、ロシアの小さな村で夫の消息を知らされ、しかし、その家には若いロシア女性がいて洗濯物を取りこんでいる。
もうすでに何らかの悪い予感がジョバンナの顔に表れ始める。
この情景は何度見ても素晴らしく、ぬかるんだ田舎道、ジョバンナの周りを取り囲んだ無邪気な子供たち、ジョバンナの視線に気づいた若い女(リュドミラ・サヴェーリエワ)の顔にも、とうとう来るものが来た、といった複雑な表情が浮かびます。

家の中へ招き入れられたジョバンナは、ベッドに並んだ二つの枕を見てすべてを察し、その家の幼い娘カチューシャは二人の間に出来た子どもであることを理解したジョバンナは悲嘆に打ちのめされます。
そして、工場から帰ってくるアントニオとの駅での再会。
しかし、言葉を交わすこともなく列車に飛び乗ったジョバンナの号泣。
数年後、イタリアでの再会を果たしたアントニオとジョバンナでしたが、お互いに別々の人生を送っていることを知った二人には、ふたたび同じ人生を歩むことはできず、モスクワへ帰る列車に乗ったアントニオを見送るジョバンナ。
「すぐに帰ってくる」と言って出征した同じミラノ駅での別れのシーンは、嗚咽をこらえながら大粒の涙に頬を濡らすジョバンナと、すべてをあきらめきった表情で列車に立ち尽くすアントニオ、そしてそこに流れる「ひまわり」の主題曲、二人の永遠の別れを物語る名ラストシーンです。
「ひまわり」が女性映画であるということをいわれるのはメロドラマ的なストーリー展開にあると思われますが、その背景にある戦争、そこで死んでいった兵士、そして女性や子どもたちが眠る原野に咲くひまわりの数だけ悲しみのドラマがあることを訴える力強い映画であると思います。
「私の好きな映画ベスト10」に入る一本。



イタリア/フランス/ソ連(当時)合作
監督ヴィットリオ・デ・シーカ
脚本チェーザレ・サヴァッティーニ
アントニオ・グエラ
ゲオルギ・ムディバニ
撮影ジュゼッペ・ロトゥンノ
音楽ヘンリー・マンシーニ
〈キャスト〉
ソフィア・ローレン マルチェロ・マストロヤンニ
リュドミラ・サヴェーリエワ
戦地へ出征して、なんらかの理由でそのままその地にとどまった兵士は少なからず存在したのだろうと思います。
数年前にNHKのラジオニュースで、インドネシア(だったかな?)で、元日本兵が存在しているというニュースが流れたことがあります。
でもその人は、横井庄一さんや小野田寛郎さんのように終戦を知らずに戦後数十年をその地で過ごしていたわけではなく、戦争が終わっても帰国をせずに、現地で家庭を持って静かに暮らしていたということです。
竹山道雄の名作「ビルマの竪琴」の主人公・水島上等兵のように、戦死して無縁仏のようになった兵士を弔うため、僧になってビルマをさまよった人もいたかもしれません。
戦争という歴史の大きな歯車によって、思わぬ方向へ人生がねじ曲げられてしまう悲劇を描いた「ひまわり」は、巨匠ヴィットリオ・デ・シーカによる永遠の名作です。
電気技師のアントニオ(マルチェロ・マストロヤンニ)と勝気で陽気なナポリ女ジョバンナ(ソフィア・ローレン)は、出会ってすぐに恋に落ちます。
戦時中であり、アフリカ戦線への出征が決まっていたアントニオは、結婚をすれば12日間の休暇がもらえるし、その間に戦争は終わるだろうと、気楽な二人は結婚式を挙げ、12日間の新婚生活を楽しみますが(卵24個を使ったオムレツを食べるシーンは秀逸)、それも夢のように過ぎてしまい、兵役を回避するため二人は一芝居打ちます。
妻のジョバンナをナイフで突然追いまわし、精神異常を装ったアントニオでしたが、偽芝居はあえなく露見。
懲罰のためアントニオはロシア戦線へ送られることになります。
ミラノ駅で夫を見送るジョバンナに「すぐに帰ってくる」と言い残して、アントニオは大勢の兵士と共にミラノ駅を後にして出征してゆきます。

年月は過ぎ、夫の帰りを待ちわびていたジョバンナは終戦の知らせを受け、帰国するであろう夫を迎えるためミラノ駅へ向かいます。
アントニオの写真を手に、列車から到着する復員兵たちの中にアントニオの姿を探しますが、夫の姿はありません。
落胆するジョバンナでしたが、列車から降りた復員兵の中に、ドン河付近でアントニオを見かけたという男がジョバンナに語りかけます。
…迫りくるロシア兵と、見渡すかぎりの雪原に舞う吹雪。
退却を余儀なくされた部隊は極寒と飢えの中で、ひとり、またひとりと倒れ、その中でアントニオも雪原に倒れてしまったのです。
しかし、アントニオの死を確認した者はなく、彼は生きているはずだと思い詰めたジョバンナはアントニオの消息を確かめるべく、スターリン亡き後のモスクワ行きを決意します。

広大なロシアの地でイタリア軍が戦ったとされる戦域を訪ね歩いたジョバンナは、外務省の担当官から見渡す限りの野に咲くひまわりの群生地に案内されます。
そこはイタリア兵とロシア軍の捕虜が埋葬されている地で、兵士だけではなく、女性や子どももドイツ軍によって埋められている、いわば原野の墓場であり、そこに咲いている何万本とも知れぬひまわりの数だけ死者が眠っていることを意味しています。
「生きて帰ったイタリア兵はいない」と言われ、夫の探索をあきらめるよううながされたジョバンナでしたが、どこかで生きているであろうアントニオを信じるジョバンナはあきらめず、アントニオの写真を手に村々を訪ね歩いたジョバンナは、ついに夫の消息をつかみますが…。
監督は、「自転車泥棒」(1948年)、「終着駅」(1953年)、「昨日・今日・明日」(1963年)の巨匠ヴィットリオ・デ・シーカ。
ジョバンナに「島の女」(1957年)、「ふたりの女」(1960年)、「ラ・マンチャの男」(1972年)のソフィア・ローレン。
アントニオに「甘い生活」(1960年)、「イタリア式離婚狂想曲」(1962年)、「8 1/2」(1963年)の名優マルチェロ・マストロヤンニ。
そして、
瀕死のアントニオを助け、彼の妻になるロシア人女性に「戦争と平和」(1965年—1968年)のナターシャ役で世界を魅了したリュドミラ・サヴェーリエワ。
哀愁に満ちた情感漂う「ひまわり」のテーマ曲は、「ティファニーで朝食を」(1961年)、「酒とバラの日々」(1962年)、「ピンクパンサー」シリーズなど、映画音楽界の巨匠ヘンリー・マンシーニ。
独特の映像美とカメラワークは「山猫」(1963年)、「愛の狩人」(1971年)、「フェリーニのローマ」(1972年)などの名手ジュゼッペ・ロトゥンノ。
第二次世界大戦はナチス・ドイツによるポーランド侵攻によって勃発するのですが、それ以前から世界戦争の火だねのようなものは燃えていて、やがて日本・ドイツ・イタリアの枢軸国とアメリカ・イギリス・オランダ・フランスなどの連合国との戦争に発展してゆき、ヨーロッパを主戦場としたドイツに対し、その多くの戦場を太平洋とした日本。
日独伊三国同盟といわれる中で、よく分からないのがイタリアの動きで、ムッソリーニの独裁国家であったイタリアですが、半島では内戦が勃発。
1940年に地中海の制海権とエジプトでの支配を目指したイタリアは北アフリカへ侵攻。
ほどなくしてドイツとソビエトの間に交わされていた独ソ不可侵条約が破棄され、ドイツはロシアへの侵攻を開始。
ナチス・ドイツに対する追随政策をとるムッソリーニはロシア戦線へ軍を派遣することになります。
「靴みがき」(1946年)や「自転車泥棒」(1948年)によって、ロベルト・ロッセリーニなどと並んでイタリアン・ネオレアリズモの代表的な監督として知られるようになったデ・シーカですが、「終着駅」にみられるようなメロドラマの醍醐味は「ひまわり」でも存分に生かされていて、特に、ロシアの小さな村で夫の消息を知らされ、しかし、その家には若いロシア女性がいて洗濯物を取りこんでいる。
もうすでに何らかの悪い予感がジョバンナの顔に表れ始める。
この情景は何度見ても素晴らしく、ぬかるんだ田舎道、ジョバンナの周りを取り囲んだ無邪気な子供たち、ジョバンナの視線に気づいた若い女(リュドミラ・サヴェーリエワ)の顔にも、とうとう来るものが来た、といった複雑な表情が浮かびます。

家の中へ招き入れられたジョバンナは、ベッドに並んだ二つの枕を見てすべてを察し、その家の幼い娘カチューシャは二人の間に出来た子どもであることを理解したジョバンナは悲嘆に打ちのめされます。
そして、工場から帰ってくるアントニオとの駅での再会。
しかし、言葉を交わすこともなく列車に飛び乗ったジョバンナの号泣。
数年後、イタリアでの再会を果たしたアントニオとジョバンナでしたが、お互いに別々の人生を送っていることを知った二人には、ふたたび同じ人生を歩むことはできず、モスクワへ帰る列車に乗ったアントニオを見送るジョバンナ。
「すぐに帰ってくる」と言って出征した同じミラノ駅での別れのシーンは、嗚咽をこらえながら大粒の涙に頬を濡らすジョバンナと、すべてをあきらめきった表情で列車に立ち尽くすアントニオ、そしてそこに流れる「ひまわり」の主題曲、二人の永遠の別れを物語る名ラストシーンです。
「ひまわり」が女性映画であるということをいわれるのはメロドラマ的なストーリー展開にあると思われますが、その背景にある戦争、そこで死んでいった兵士、そして女性や子どもたちが眠る原野に咲くひまわりの数だけ悲しみのドラマがあることを訴える力強い映画であると思います。
「私の好きな映画ベスト10」に入る一本。

2019年11月28日
映画「グラン・トリノ」− 「人を殺す気持ちを知りたいのか? 最悪だ」
「グラン・トリノ」
(Gran Torino) 2008年 アメリカ
監督クリント・イーストウッド
脚本ニック・シェンク
撮影トム・スターン
原案デヴィッド・ジョハンソン
ニック・シェンク
音楽カイル・イーストウッド
マイケル・スティーヴンス
〈キャスト〉
クリント・イーストウッド ビー・ヴァン
アーニー・ハー クリストファー・カーリー
人付き合いが悪く、頑固で片意地、自分が生きた時代に誇りを持ち、どんなに時代が移り変わろうと自分の信念のよりどころを見失わない男。
親戚にそんな人がいたとしたら、煙ったい存在として敬遠されるような男をクリント・イーストウッドが好演。
ラストの意表を突いた展開と、少数民族であるモン族との交流を通してたどる男の生きざまを描いた秀作です。

ウォルト・コワルスキー(クリント・イーストウッド)は50年間勤めたフォードの工場を退職し、愛犬とともに自宅のポーチにゆったりと座り、缶ビールを飲むのを楽しみにしています。
妻に先立たれたウォルトはますます頑固になっているせいか、息子たちとも折り合いが悪く、隣に住むモン族の一家に対しても“コメ食い虫”と嘲(あざけ)り、オレの芝生を汚すな、と不平の毎日を送っています。
そんなウォルトが大切にしているのが72年型の愛車、フォード製“グラン・トリノ”です。
デカくて優雅ですが燃費があまりよくないため、翌年の1973年から始まったオイルショックのあおりを受けてアメリカの自動車産業が燃費のすぐれた日本車にとってかわられる分岐点ともなった1972年。
そんな最後の輝きを放つグラン・トリノをウォルトは愛し、ピカピカに磨いて自宅の車庫に保管しています。

いわば歴史の貴重品ともなったウォルトの愛車グラン・トリノを、隣に住むモン族の少年タオ(ビー・ヴァン)が盗みに入ります。
タオ自身は車に興味はなく、盗みはイヤなのですが、いとこでストリートギャングのリーダーであるフォン(ドゥア・モーア)に脅(おど)され、盗みに入ったのです。
ガレージの不審者に気づいたウォルトはタオに銃口を向け、追い払います。

内気なタオは人生に迷っています。
自分の人生に自信が持てなくて悩んでいるのです。そんな気弱な性格からフォンたちに目をつけられ、ギャングの仲間に引き入れられようとしているのですが、姉のスー(アーニー・ハー)は、ウォルトの車を盗もうとしたタオに腹を立て、タオを引き連れてウォルトに謝罪に出かけ、罪滅ぼしのため、身の回りの用事をタオにさせるようウォルトに頼みます。
最初は断ったウォルトでしたが、スーの意見を聞き入れ、タオにいくつか用事をさせながら、それが機縁となって、タオやモン族一家との交流が生まれてゆきます。

ウォルトは心に重荷を負っています。
1950年に始まった朝鮮戦争に出兵したウォルトは、戦争とはいえ、年の若いアジア人を殺した罪悪感に苛(さいな)まれ、帰国後はそのために意固地になっていったともいえます。
贖罪を願うウォルトですが、亡き妻と親しかったヤノビッチ神父(クリストファー・カーリー)とは打ち解けず、現在にいたるまで罪の意識に苦しめられています。
しかしまたウォルトには、それほど遠くない将来に自分の人生に終止符が打たれるであろうことも自覚し始めています。体調が思わしくないこともあって、それまで行く気のなかった病院での検査の結果が判明。
死期が迫っていることを悟ります。
そんな中、執拗にスーたちにからむフォンをリーダーとするギャングたちがタオを傷つける事件が発生。
激怒したウォルトは、二度とタオに手出しをすることのないようフォンたちを痛めつけますが、このことがかえってギャングたちの反感を生み、タオの家に銃弾を浴びせるとともに、スーをさらい、暴行を加えた上でレイプに及び、スーは悲惨な体で自宅に送り返されます。
姉の姿を見たタオはフォンたちに復讐するべく自宅を飛び出しますが、一連の出来事が自分の行いから始まったことを悔いたウォルトはタオを自宅の地下に監禁し、ただひとり、ギャングたちのもとへ乗り込んでゆきます。
心に染みこむ余韻を残す素晴らしい映画で、中でも極めてユニークなのがモン族の存在。
元々はタイやラオス、中国の山岳地帯に住む民族集団ですが、現在のシリアにおけるクルド人と同じく、彼らはアメリカの政策に翻弄された歴史を持ちます。
第一次、第二次のインドシナ戦争を経て、ベトナム戦争へと突入すると、アメリカ・CIAは共産軍との戦いのために多くのモン族を雇い、兵士としての訓練を始めます。その任務の主なものは敵の補給ルートを絶つためのものだったようですが、やがて泥沼化した戦争からアメリカは撤退。モン族は置き去りにされ、見捨てられます。
その後、モン族の多くは、ベトナムやラオスの共産軍によって虐殺の憂き目にあい、難民化した彼らはやがてアメリカやオーストラリアなどに移住することになります。

「グラン・トリノ」は贖罪の映画としての一面を持ちます。
ウォルト・コワルスキーは朝鮮戦争でアジア人を多数殺した罪の意識を抱え、贖罪を願っていますが、それを大きく投影させたのが、アメリカが負うべきモン族への贖罪です。
変わり果てた姉・スーの姿を見たタオは復讐のために家を飛び出しますが、ウォルトはそれをおしとどめ、こう言います。
「人を殺す気持ちを知りたいのか? 最悪だ。もっとひどいのは、降参する哀れな子どもを殺して勲章をもらうことだ。それがすべてだ。
…お前くらいの年のおびえたガキさ。
ずっと昔、お前がさっき持ったライフルでガキの顔を撃った。
そのことを考えない日はない。
お前にそんな風になってほしくない」
ウォルトはタオを自宅の地下に監禁して、単身、ギャングたちのもとへ向かうのですが、このウォルトの人物像は、引退したハリー・キャラハンを思わせる雰囲気を持っているため、ギャングたちに対峙したウォルトは派手な銃撃戦でもやらかすのかと思わせますが、死期を悟っていたウォルトは自分の命を犠牲にして、タオを殺人者にすることなく、ギャングたちに重罪を負わせます。
これはアメリカが負うべきモン族への贖罪をウォルトに投影させたと考えることもできます。
さらにウォルトの遺書によって、愛車“グラン・トリノ”はタオに譲られることになるのですが、ひとつの時代を象徴し、古びてもなおその輝きを失わないガッシリしたフォードのグラン・トリノはウォルトそのものでもあり、一人の少年への魂の贈り物ともいえます。
監督・主演のクリント・イーストウッドの他には目立って有名な俳優のいない中にあって、よく知られている俳優としては、ウォルトの友人で少しだけ登場するジョン・キャロル・リンチ。
大柄でいかつい風貌なので、多くの映画で強い印象を残していますが、個人的には「ファーゴ」(1996年)の物静かな画家ノーム役がとても印象に残っています。
人生に迷っている少年と、数々の修羅場をくぐり抜けてきた百戦錬磨の老人。
老人との出会いが少年に夢と希望を与えるという、表面的にはよくある話ながら、そのスケールと奥行きの深さは群を抜いています。
海岸線を流れるように走るグラン・トリノと、それにかぶさるように流れる音楽。
味わい深い余韻を残す素晴らしいラストシーンでした。



監督クリント・イーストウッド
脚本ニック・シェンク
撮影トム・スターン
原案デヴィッド・ジョハンソン
ニック・シェンク
音楽カイル・イーストウッド
マイケル・スティーヴンス
〈キャスト〉
クリント・イーストウッド ビー・ヴァン
アーニー・ハー クリストファー・カーリー
人付き合いが悪く、頑固で片意地、自分が生きた時代に誇りを持ち、どんなに時代が移り変わろうと自分の信念のよりどころを見失わない男。
親戚にそんな人がいたとしたら、煙ったい存在として敬遠されるような男をクリント・イーストウッドが好演。
ラストの意表を突いた展開と、少数民族であるモン族との交流を通してたどる男の生きざまを描いた秀作です。

ウォルト・コワルスキー(クリント・イーストウッド)は50年間勤めたフォードの工場を退職し、愛犬とともに自宅のポーチにゆったりと座り、缶ビールを飲むのを楽しみにしています。
妻に先立たれたウォルトはますます頑固になっているせいか、息子たちとも折り合いが悪く、隣に住むモン族の一家に対しても“コメ食い虫”と嘲(あざけ)り、オレの芝生を汚すな、と不平の毎日を送っています。
そんなウォルトが大切にしているのが72年型の愛車、フォード製“グラン・トリノ”です。
デカくて優雅ですが燃費があまりよくないため、翌年の1973年から始まったオイルショックのあおりを受けてアメリカの自動車産業が燃費のすぐれた日本車にとってかわられる分岐点ともなった1972年。
そんな最後の輝きを放つグラン・トリノをウォルトは愛し、ピカピカに磨いて自宅の車庫に保管しています。

いわば歴史の貴重品ともなったウォルトの愛車グラン・トリノを、隣に住むモン族の少年タオ(ビー・ヴァン)が盗みに入ります。
タオ自身は車に興味はなく、盗みはイヤなのですが、いとこでストリートギャングのリーダーであるフォン(ドゥア・モーア)に脅(おど)され、盗みに入ったのです。
ガレージの不審者に気づいたウォルトはタオに銃口を向け、追い払います。
内気なタオは人生に迷っています。
自分の人生に自信が持てなくて悩んでいるのです。そんな気弱な性格からフォンたちに目をつけられ、ギャングの仲間に引き入れられようとしているのですが、姉のスー(アーニー・ハー)は、ウォルトの車を盗もうとしたタオに腹を立て、タオを引き連れてウォルトに謝罪に出かけ、罪滅ぼしのため、身の回りの用事をタオにさせるようウォルトに頼みます。
最初は断ったウォルトでしたが、スーの意見を聞き入れ、タオにいくつか用事をさせながら、それが機縁となって、タオやモン族一家との交流が生まれてゆきます。

ウォルトは心に重荷を負っています。
1950年に始まった朝鮮戦争に出兵したウォルトは、戦争とはいえ、年の若いアジア人を殺した罪悪感に苛(さいな)まれ、帰国後はそのために意固地になっていったともいえます。
贖罪を願うウォルトですが、亡き妻と親しかったヤノビッチ神父(クリストファー・カーリー)とは打ち解けず、現在にいたるまで罪の意識に苦しめられています。
しかしまたウォルトには、それほど遠くない将来に自分の人生に終止符が打たれるであろうことも自覚し始めています。体調が思わしくないこともあって、それまで行く気のなかった病院での検査の結果が判明。
死期が迫っていることを悟ります。
そんな中、執拗にスーたちにからむフォンをリーダーとするギャングたちがタオを傷つける事件が発生。
激怒したウォルトは、二度とタオに手出しをすることのないようフォンたちを痛めつけますが、このことがかえってギャングたちの反感を生み、タオの家に銃弾を浴びせるとともに、スーをさらい、暴行を加えた上でレイプに及び、スーは悲惨な体で自宅に送り返されます。
姉の姿を見たタオはフォンたちに復讐するべく自宅を飛び出しますが、一連の出来事が自分の行いから始まったことを悔いたウォルトはタオを自宅の地下に監禁し、ただひとり、ギャングたちのもとへ乗り込んでゆきます。
心に染みこむ余韻を残す素晴らしい映画で、中でも極めてユニークなのがモン族の存在。
元々はタイやラオス、中国の山岳地帯に住む民族集団ですが、現在のシリアにおけるクルド人と同じく、彼らはアメリカの政策に翻弄された歴史を持ちます。
第一次、第二次のインドシナ戦争を経て、ベトナム戦争へと突入すると、アメリカ・CIAは共産軍との戦いのために多くのモン族を雇い、兵士としての訓練を始めます。その任務の主なものは敵の補給ルートを絶つためのものだったようですが、やがて泥沼化した戦争からアメリカは撤退。モン族は置き去りにされ、見捨てられます。
その後、モン族の多くは、ベトナムやラオスの共産軍によって虐殺の憂き目にあい、難民化した彼らはやがてアメリカやオーストラリアなどに移住することになります。

「グラン・トリノ」は贖罪の映画としての一面を持ちます。
ウォルト・コワルスキーは朝鮮戦争でアジア人を多数殺した罪の意識を抱え、贖罪を願っていますが、それを大きく投影させたのが、アメリカが負うべきモン族への贖罪です。
変わり果てた姉・スーの姿を見たタオは復讐のために家を飛び出しますが、ウォルトはそれをおしとどめ、こう言います。
「人を殺す気持ちを知りたいのか? 最悪だ。もっとひどいのは、降参する哀れな子どもを殺して勲章をもらうことだ。それがすべてだ。
…お前くらいの年のおびえたガキさ。
ずっと昔、お前がさっき持ったライフルでガキの顔を撃った。
そのことを考えない日はない。
お前にそんな風になってほしくない」
ウォルトはタオを自宅の地下に監禁して、単身、ギャングたちのもとへ向かうのですが、このウォルトの人物像は、引退したハリー・キャラハンを思わせる雰囲気を持っているため、ギャングたちに対峙したウォルトは派手な銃撃戦でもやらかすのかと思わせますが、死期を悟っていたウォルトは自分の命を犠牲にして、タオを殺人者にすることなく、ギャングたちに重罪を負わせます。
これはアメリカが負うべきモン族への贖罪をウォルトに投影させたと考えることもできます。
さらにウォルトの遺書によって、愛車“グラン・トリノ”はタオに譲られることになるのですが、ひとつの時代を象徴し、古びてもなおその輝きを失わないガッシリしたフォードのグラン・トリノはウォルトそのものでもあり、一人の少年への魂の贈り物ともいえます。
監督・主演のクリント・イーストウッドの他には目立って有名な俳優のいない中にあって、よく知られている俳優としては、ウォルトの友人で少しだけ登場するジョン・キャロル・リンチ。
大柄でいかつい風貌なので、多くの映画で強い印象を残していますが、個人的には「ファーゴ」(1996年)の物静かな画家ノーム役がとても印象に残っています。
人生に迷っている少年と、数々の修羅場をくぐり抜けてきた百戦錬磨の老人。
老人との出会いが少年に夢と希望を与えるという、表面的にはよくある話ながら、そのスケールと奥行きの深さは群を抜いています。
海岸線を流れるように走るグラン・トリノと、それにかぶさるように流れる音楽。
味わい深い余韻を残す素晴らしいラストシーンでした。

2019年08月07日
映画「日の名残り」すれ違ってゆく男女の悲哀を描いた秀作
「日の名残り」
(The Remains of the Day)
1993年イギリス
監督ジェームズ・アイヴォリー
原作カズオ・イシグロ
脚本ルイース・プラワー・ジャブバーラ
撮影トニー・ピアース・ロバーツ
音楽リチャード・ロビンズ
〈キャスト〉
アンソニー・ホプキンス エマ・トンプソン
クリストファー・リーブ ジェームズ・フォックス
第66回アカデミー賞主演男優賞、主演女優賞、
監督賞、美術賞他8部門ノミネート
ノーベル賞作家カズオ・イシグロの同名小説を映画化。
台頭するナチス・ドイツに対する政治的判断を誤った貴族の没落を背景に、あまりにも謹厳で職務への忠実さゆえに愛をつかむことのできなかった男と、彼への愛を秘めながら、もう一歩を踏み出すことのできなかった女。
お互いに分かり過ぎるほど気持ちが分かっていながら、すれ違ってゆく男女の悲哀を、「眺めのいい部屋」「モーリス」の名匠ジェームズ・アイヴォリーが重厚に描いた秀作です。

1958年イギリス、イングランド東部オックスフォード。
広大な屋敷、ダーリントン・ホールの以前の持ち主ダーリントン卿(ジェームズ・フォックス)はすでに亡く、現在はアメリカ人の富豪ルイス(クリストファー・リーブ)の手に渡っています。
ダーリントン卿の元で長く執事を務めていたジェームズ・スティーブンス(アンソニー・ホプキンス)は、ダーリントン・ホールの持ち主が変わった現在も執事としてルイスに仕えています。
そんなある日、以前の女中頭ミス・ケントン(エマ・トンプソン)からスティーブンスのもとに手紙が届きます。
娘も成長して手が離れたから、もう一度働かせてもらいたい、といった内容に加えて、結婚生活の陰りをうかがわせる文面にスティーブンスの気持ちはゆらぎ、彼女の元へ出かける決心をします。
ダーリントン・ホールから外の世界へ出たことのないスティーブンスにルイスは車を貸し与え、
「世界を見たほうがいい」と言うルイスに対して、スティーブンスはこう応えます。
「世界のほうから、ここへやってきていましたから」
そして物語は20年前へとさかのぼってゆきます。

1938年、ダーリントン・ホールでは世界の要人が集まり、第一次世界大戦後の莫大な賠償金を負わされたドイツに対する扱いをどうするかで議論が戦わされています。
ダーリントン・ホールの持ち主ダーリントン卿はドイツへの復興援助を主張し、満場の同意を得ますが、それに真っ向から反対をしたのがアメリカ人のルイスでした。
若手の政治家として頭角を現し始めたルイスは、政治は貴族のようなシロウトがするものではなく、プロに任せるべきだと反論。満場の失笑を買います。
しかし、その年の3月にナチス・ドイツはオーストリアを併合。
11月には「水晶の夜」と呼ばれるユダヤ人への迫害が始まります。
時代が大きく動いてゆく中で、ダーリントン・ホールに新しい女中頭が採用されます。
勝気ではあるけど仕事熱心な女性、ミス・ケントンです。
初対面の面接からいきなり悪感情を持ったスティーブンスとミス・ケントンでしたが、厳格な中にも繊細な一面をのぞかせるスティーブンスにミス・ケントンは次第に興味を持ち始めます。

執事という仕事の中で最も重要な特性は“品格”だと考えるスティーブンスは、その言葉通り、柔らかな物腰と穏やかな話しぶりの中に、禁欲的な気高さを感じさせる風格を備えた男性でしたが、男女間の恋愛については、低俗な恋愛小説から学び取ることしかできない、生身の女性心理を理解できない男でもありました。
やがてミス・ケントンは以前からの同僚であったベン(ティム・ピゴット・スミス)に求婚され、スティーブンスへの密かな想いに迷い苦しみながら、ベンとの結婚に踏み切り、町を去ってゆきます。
世界は大きく動き、親ナチスの姿勢を鮮明にしていたダーリントン卿はユダヤ人排斥にも加担しますが、貴族的な人間性を失うことのなかった彼は自分の罪を悔い、世間からも非難を浴びながら次第に正気を失ってゆき、静かに世を去ります。
……そして20年後。
ミス・ケントンからの手紙を受け取ったスティーブンスは彼女との再会を果たしますが、孫の誕生と世話のためにダーリントン・ホールでの仕事ができなくなったことを彼女に告げられ、雨のそぼ降るバス停で、再会を約束することもなく、バスに乗り込んだミス・ケントンをスティーブンスは黙って見つめ、滲む窓ガラスに映るミス・ケントンの涙をこらえた表情が次第に遠ざかってゆきます。

今や名優の域に達したアンソニー・ホプキンスですが、かつて出演した「ジャガーノート」(1974年)、「エレファント・マン」(1980年)などの作品にヒット作はあったものの、神経質なイギリス人といった印象で存在感に乏しく、目立つような俳優ではなかったのですが、それがどうしたことか、突然、強烈な個性派俳優として名を挙げたのが「羊たちの沈黙」(1991年)の高度な知性と異常な精神病を併せ持ったハンニバル・レクター博士でした。
それからの活躍は、ハンニバル・レクターとアンソニー・ホプキンスがダブッて見えるほど強烈なレクター博士のイメージがつきまといました。
本作「日の名残り」ではアカデミー賞の主演男優賞にはノミネートで終わりましたが、その落ち着いた物腰からにじみ出る仕事に対する禁欲的な姿勢と、逆に恋愛に関しては臆病なほど内向的なスティーブンスの人間性は、それまでの自信に満ち溢れたレクター博士のようなキャラクターとは打って変わった人物像を作り上げました。
ミス・ケントンに「ハワーズ・エンド」(1992年)、「父の祈りを」(1993年)、「いつか晴れた日に」(1995年)など、数々の主演女優賞に名前の挙がる実力派のエマ・トンプソン。
個人的には「日の名残り」と同年の作品である「父の祈りを」で演じた女性弁護士ギャレス・ピアースの熱演がとても印象に残っています。
ダーリントン卿に「インドへの道」(1984年)、「ロシア・ハウス」(1990年)、「パトリオット・ゲーム」(1992年)のジェームズ・フォックス。
富豪のアメリカ人、ルイスに「スーパーマン」シリーズ、「デストラップ・死の罠」(1982年)のクリストファー・リーブ。
クリストファー・リーブは1995年に落馬事故を起こし、脊髄損傷のため車イス生活を余儀なくされましたが、以後も社会活動など精力的な活動を続けていましたが、2004年に心不全を発症、惜しまれながら52歳で世を去っています。
第一次から第二次への世界大戦を背景としていますが、物語の主な舞台となるのはダーリントン・ホールで、世界の趨勢(すうせい)という大局的な渦の中ですれ違う男女の恋を、20年の空白を経ながらも結局は別れてしまわなければならない悲哀を描いています。
でも、湿っぽく終わるのではなくて、ミス・ケントンと別れ、ダーリントン・ホールへ戻ったスティーブンスがルイスと一緒に部屋へ迷い込んだ鳩を逃がしてやるラストは、暗さから明るさへと解き放たれてゆくダーリントン・ホールを象徴しているようで、爽やかな後味を残しました。
1989年に英国最高の栄誉ある文学賞といわれるブッカー賞を受賞したカズオ・イシグロの同名小説を映画化したものですが、映画は原作より一歩踏み込んだといいますか、スティーブンスとミス・ケントンのロマンスは、原作では遠い日のほろ苦い思い出としてポツリポツリと語られるのに対し、映画ではかなり掘り下げて描かれました。
原作のテーマ性と格調の高さを損ねることなく描かれた恋愛映画と見ることもできますが、男女のロマンスを前面に出したことで映画的な成功を収めたといえます。
映画に劣らず原作はかなり感動的です。
大英帝国の過去の栄光と、その中心的役割を果たしたダーリントン・ホールでの国際会議。
イギリスの美しい田舎の風景と共に、そこに生活する素朴な人々との交流を通して、スティーブンスが過去を回想するという形式で語られてゆきます。
大きく動いてゆく時代の中で、ダーリントン卿とスティーブンスの主従関係を軸に描かれた小説「日の名残り」は、偉大な執事としての特質「品格」をストイックなまでに追究したスティーブンスと、没落してゆく貴族社会の華やかな過去の想い出、また、ミス・ケントンとの淡いロマンスと永遠の別れなどが溶け合って、深い哀愁を帯びた感動を与えてくれます。



1993年イギリス
監督ジェームズ・アイヴォリー
原作カズオ・イシグロ
脚本ルイース・プラワー・ジャブバーラ
撮影トニー・ピアース・ロバーツ
音楽リチャード・ロビンズ
〈キャスト〉
アンソニー・ホプキンス エマ・トンプソン
クリストファー・リーブ ジェームズ・フォックス
第66回アカデミー賞主演男優賞、主演女優賞、
監督賞、美術賞他8部門ノミネート
ノーベル賞作家カズオ・イシグロの同名小説を映画化。
台頭するナチス・ドイツに対する政治的判断を誤った貴族の没落を背景に、あまりにも謹厳で職務への忠実さゆえに愛をつかむことのできなかった男と、彼への愛を秘めながら、もう一歩を踏み出すことのできなかった女。
お互いに分かり過ぎるほど気持ちが分かっていながら、すれ違ってゆく男女の悲哀を、「眺めのいい部屋」「モーリス」の名匠ジェームズ・アイヴォリーが重厚に描いた秀作です。

1958年イギリス、イングランド東部オックスフォード。
広大な屋敷、ダーリントン・ホールの以前の持ち主ダーリントン卿(ジェームズ・フォックス)はすでに亡く、現在はアメリカ人の富豪ルイス(クリストファー・リーブ)の手に渡っています。
ダーリントン卿の元で長く執事を務めていたジェームズ・スティーブンス(アンソニー・ホプキンス)は、ダーリントン・ホールの持ち主が変わった現在も執事としてルイスに仕えています。
そんなある日、以前の女中頭ミス・ケントン(エマ・トンプソン)からスティーブンスのもとに手紙が届きます。
娘も成長して手が離れたから、もう一度働かせてもらいたい、といった内容に加えて、結婚生活の陰りをうかがわせる文面にスティーブンスの気持ちはゆらぎ、彼女の元へ出かける決心をします。
ダーリントン・ホールから外の世界へ出たことのないスティーブンスにルイスは車を貸し与え、
「世界を見たほうがいい」と言うルイスに対して、スティーブンスはこう応えます。
「世界のほうから、ここへやってきていましたから」
そして物語は20年前へとさかのぼってゆきます。

1938年、ダーリントン・ホールでは世界の要人が集まり、第一次世界大戦後の莫大な賠償金を負わされたドイツに対する扱いをどうするかで議論が戦わされています。
ダーリントン・ホールの持ち主ダーリントン卿はドイツへの復興援助を主張し、満場の同意を得ますが、それに真っ向から反対をしたのがアメリカ人のルイスでした。
若手の政治家として頭角を現し始めたルイスは、政治は貴族のようなシロウトがするものではなく、プロに任せるべきだと反論。満場の失笑を買います。
しかし、その年の3月にナチス・ドイツはオーストリアを併合。
11月には「水晶の夜」と呼ばれるユダヤ人への迫害が始まります。
時代が大きく動いてゆく中で、ダーリントン・ホールに新しい女中頭が採用されます。
勝気ではあるけど仕事熱心な女性、ミス・ケントンです。
初対面の面接からいきなり悪感情を持ったスティーブンスとミス・ケントンでしたが、厳格な中にも繊細な一面をのぞかせるスティーブンスにミス・ケントンは次第に興味を持ち始めます。
執事という仕事の中で最も重要な特性は“品格”だと考えるスティーブンスは、その言葉通り、柔らかな物腰と穏やかな話しぶりの中に、禁欲的な気高さを感じさせる風格を備えた男性でしたが、男女間の恋愛については、低俗な恋愛小説から学び取ることしかできない、生身の女性心理を理解できない男でもありました。
やがてミス・ケントンは以前からの同僚であったベン(ティム・ピゴット・スミス)に求婚され、スティーブンスへの密かな想いに迷い苦しみながら、ベンとの結婚に踏み切り、町を去ってゆきます。
世界は大きく動き、親ナチスの姿勢を鮮明にしていたダーリントン卿はユダヤ人排斥にも加担しますが、貴族的な人間性を失うことのなかった彼は自分の罪を悔い、世間からも非難を浴びながら次第に正気を失ってゆき、静かに世を去ります。
……そして20年後。
ミス・ケントンからの手紙を受け取ったスティーブンスは彼女との再会を果たしますが、孫の誕生と世話のためにダーリントン・ホールでの仕事ができなくなったことを彼女に告げられ、雨のそぼ降るバス停で、再会を約束することもなく、バスに乗り込んだミス・ケントンをスティーブンスは黙って見つめ、滲む窓ガラスに映るミス・ケントンの涙をこらえた表情が次第に遠ざかってゆきます。

今や名優の域に達したアンソニー・ホプキンスですが、かつて出演した「ジャガーノート」(1974年)、「エレファント・マン」(1980年)などの作品にヒット作はあったものの、神経質なイギリス人といった印象で存在感に乏しく、目立つような俳優ではなかったのですが、それがどうしたことか、突然、強烈な個性派俳優として名を挙げたのが「羊たちの沈黙」(1991年)の高度な知性と異常な精神病を併せ持ったハンニバル・レクター博士でした。
それからの活躍は、ハンニバル・レクターとアンソニー・ホプキンスがダブッて見えるほど強烈なレクター博士のイメージがつきまといました。
本作「日の名残り」ではアカデミー賞の主演男優賞にはノミネートで終わりましたが、その落ち着いた物腰からにじみ出る仕事に対する禁欲的な姿勢と、逆に恋愛に関しては臆病なほど内向的なスティーブンスの人間性は、それまでの自信に満ち溢れたレクター博士のようなキャラクターとは打って変わった人物像を作り上げました。
ミス・ケントンに「ハワーズ・エンド」(1992年)、「父の祈りを」(1993年)、「いつか晴れた日に」(1995年)など、数々の主演女優賞に名前の挙がる実力派のエマ・トンプソン。
個人的には「日の名残り」と同年の作品である「父の祈りを」で演じた女性弁護士ギャレス・ピアースの熱演がとても印象に残っています。
ダーリントン卿に「インドへの道」(1984年)、「ロシア・ハウス」(1990年)、「パトリオット・ゲーム」(1992年)のジェームズ・フォックス。
富豪のアメリカ人、ルイスに「スーパーマン」シリーズ、「デストラップ・死の罠」(1982年)のクリストファー・リーブ。
クリストファー・リーブは1995年に落馬事故を起こし、脊髄損傷のため車イス生活を余儀なくされましたが、以後も社会活動など精力的な活動を続けていましたが、2004年に心不全を発症、惜しまれながら52歳で世を去っています。
第一次から第二次への世界大戦を背景としていますが、物語の主な舞台となるのはダーリントン・ホールで、世界の趨勢(すうせい)という大局的な渦の中ですれ違う男女の恋を、20年の空白を経ながらも結局は別れてしまわなければならない悲哀を描いています。
でも、湿っぽく終わるのではなくて、ミス・ケントンと別れ、ダーリントン・ホールへ戻ったスティーブンスがルイスと一緒に部屋へ迷い込んだ鳩を逃がしてやるラストは、暗さから明るさへと解き放たれてゆくダーリントン・ホールを象徴しているようで、爽やかな後味を残しました。
1989年に英国最高の栄誉ある文学賞といわれるブッカー賞を受賞したカズオ・イシグロの同名小説を映画化したものですが、映画は原作より一歩踏み込んだといいますか、スティーブンスとミス・ケントンのロマンスは、原作では遠い日のほろ苦い思い出としてポツリポツリと語られるのに対し、映画ではかなり掘り下げて描かれました。
原作のテーマ性と格調の高さを損ねることなく描かれた恋愛映画と見ることもできますが、男女のロマンスを前面に出したことで映画的な成功を収めたといえます。
映画に劣らず原作はかなり感動的です。
大英帝国の過去の栄光と、その中心的役割を果たしたダーリントン・ホールでの国際会議。
イギリスの美しい田舎の風景と共に、そこに生活する素朴な人々との交流を通して、スティーブンスが過去を回想するという形式で語られてゆきます。
大きく動いてゆく時代の中で、ダーリントン卿とスティーブンスの主従関係を軸に描かれた小説「日の名残り」は、偉大な執事としての特質「品格」をストイックなまでに追究したスティーブンスと、没落してゆく貴族社会の華やかな過去の想い出、また、ミス・ケントンとの淡いロマンスと永遠の別れなどが溶け合って、深い哀愁を帯びた感動を与えてくれます。

2019年07月21日
映画「アラバマ物語」静かな感動と郷愁の名作
「アラバマ物語」
(To Kill a Mockingbird)
1962年アメリカ
監督ロバート・マリガン
原作ハーパー・リー
脚色ホートン・フート
音楽エルマー・バーンスタイン
撮影ラッセル・ハーラン
〈キャスト〉
グレゴリー・ペック メアリー・バダム
フィリップ・アルフォード
& ロバート・デュヴァル
第35回アカデミー賞主演男優賞(グレゴリー・ペック)/脚色賞/美術賞受賞
いろいろな映画を数多く見ていると、ときどき、とても心に残る映画があります。「アラバマ物語」はそうした中の一本で、最初見たときよりも二回目、二回目見たときよりも三回目、三回目よりも四回目と回数が増えるにしたがって深い感動を与えてくれる稀有な映画です。
原題の「To Kill Mockingbird」のMockingbirdはモノマネ鳥、あるいはマネシツグミとも訳され、北アメリカの中部から南に広く分布するこの鳥は、その名前の通り、たくさんの種類の鳥や動物、車の警笛まで美しい声で真似をすることで知られています。
美しい声で鳴くだけで、人間に害を加えることのないマネシツグミを殺すということは、罪のない無力な人間に対する迫害を示唆する、この映画の主要なテーマでもあり、それは映画の中で主人公のアティカス・フィンチが娘にやさしく語りかける場面に現れます。

1932年、アメリカ南部アラバマ州の田舎町。
3年前の1929年10月に起きたニューヨーク・ウォール街の株価大暴落に端を発した世界恐慌の波が地方の片田舎にも押し寄せる中、少女スカウト(メアリー・バダム)と兄のジェム(フィリップ・アルフォード)は元気に遊びまわっています。
スカウトとジェムの前に突然現れた少年ディル(ジョン・メグナ)とも仲良しになり、意気投合した3人は近所に住む風変りな男“ブー”の正体を知りたくて、ある晩、ブーの家に忍び込もうとします。
誰もその顔を見たことのないブーは恐ろしい怪人のイメージをもって知られ、壊れたフェンスのすき間からブーの庭に忍び込んだジェムは、明かりのついていない真っ暗な部屋の中を隙見しようとしますが、その時近づいてきた足音に驚き、フェンスの外で待っているスカウトとディルの元へ逃げ帰ろうします。
しかし、ズボンに引っかかったフェンスが外れず、ジェムはズボンをその場で脱ぎ捨て、一目散に家へ逃げ帰ります。
後に、そのズボンはきちんと畳んでその場に置いてあったことを知ったジェムたちは、“ブー”に対する不可解な謎を深めることになります。

いたずら盛りのジェムとスカウトの父アティカス・フィンチ(グレゴリー・ペック)は弁護士。
妻に先立たれたアティカスは、子どもたちが母親のいない寂しさを抱えていることは知っていますが、現在の自分の置かれている状況に黙って従っています。
そんなある日、貧農で白人のボブ・ユーエル(ジェームズ・アンダーソン)の娘メイエラ(コリン・ウィルコックス)が黒人のトム・ロビンソン(ブロック・ピーターズ)から暴行を受けたと主張し告訴。
アティカスは知人の判事から、誰も引き受け手のいないトム・ロビンソンの弁護を依頼されます。
黒人への差別が激しいことで知られる南部の土地柄、アティカスは弁護の依頼に戸惑いながらも引き受けることにします。
弁護を引き受けたアティカスに対する一部地元住民の反発は激しく、警察署へまで押し寄せた住民たちはトムへの集団リンチに及ぼうとするまで事態は悪化しますが、機転を利かせたスカウトの言葉が殺気立った住民の気勢を削(そ)ぐことになります。
そして裁判の日……。

よくいわれているように、「アラバマ物語」の主人公アティカス・フィンチはアメリカ人が選んだ「アメリカ映画のヒーロー」として、インディ・ジョーンズやジェームズ・ボンドを抜いて堂々の一位になっています。
ちなみに5位が「真昼の決闘」のウィル・ケーンなので、アティカス・フィンチとウィル・ケーンの共通性、選ばれた理由というのは分かる気がします。
勝てる望みの少ない事柄に対して、自分がやらなければ誰も引き受ける者がいないと分かったとき、ウィル・ケーンは死を覚悟して、アティカス・フィンチは人種偏見の激しい迫害を受けて、裁判に負ければ弁護士として無能の烙印を押されかねない状況の中で、決して気負うことなく、淡々と事に当たります。
ウィル・ケーンはかろうじて決闘に勝利しますが、アティカスは全面敗訴します。

人種差別の色濃い南部で、白人のメイエラに対する暴行事件の裁判は、被告のトム・ロビンソンが黒人であるにもかかわらず、十二人の陪審員すべてが白人という極端な不合理の中で行われます。
メイエラの顔の傷跡から、彼女に暴行を加えたのは左利きの男であるとアティカスは断定。被告のトムは左手が不自由であり、メイエラの父ボブ・ユーエルが左利きであることから、トムを巻き込んだ娘と父の争いが原因であり、被告のトムは無実であることが明らかになっていきます。
アティカスは陪審員席に向かって、公正な判断を下すよう滔々(とうとう)と説得を試みます。
しかし、十二人の陪審員全員が下した判決の結果は、トムの有罪でした。

判決後の場面は、この映画の最も感動的なシーンといってもいいと思います。
閉廷して静かになった法廷、アティカスは弁護席でひとり書類を片づけています、傍聴席の二階ではそれを見守る大勢の黒人たち、アティカスの二人の子ども、ジェムとスカウトもその中に混じっています、書類を片づけ終わって法廷を後にするアティカスを二階の全員が黙って見送ります。
誰かが拍手をするわけでもなく、二階の傍聴席の黒人たちにアティカスが応えるでもなく、裁判に負けたアティカスが静かに去っていくこの場面は、アティカス・フィンチに対する黒人たちの敬意がよく表れていて、数多くある映画の名シーンの中でも、ひときわ秀逸なシーンのひとつといえます。
後に被告のトムは護送中に逃走し、威嚇のために発砲した警察官の銃弾がそれてトムは死亡。
二審に望みをつないでいたアティカスは失意に沈みます。
アティカス・フィンチは人並み外れた特別な人間ではありません。体力の衰えを感じ始めた中年のやもめ男です。
温厚で誠実な人柄で知られ、弱い者に対するいたわりの心を持つ優しい男でもあります。
有り体にいってしまえば、どこにでもいる平凡な男ともいえますが、狂犬を射殺する射撃の腕を持っている反面、唾を吐きかけられたボブ・ユーエルへの憤怒をグッと抑える自制心の強さは、並の人間にはなかなか真似ることのできない一面です。
しかし、この人の素晴らしいところは、黒人蔑視の根強い排他的な土地で、誰も引き受ける者のいない弁護を引き受け、周囲からの迫害にも遭いながら、自らの責任や正義を声高に叫ぶこともなく淡々と行動していくところにあります。
監督は「九月になれば」(1961年)、「ジャングル地帯」(1962年)のロバート・マリガン。
後の「おもいでの夏」(1970年)では、思春期の少年の性の目覚めとほろ苦さを、爽やかな感性で描いています。
製作は、「コールガール」(1971年)、「大統領の陰謀」(1976年)、「ソフィーの選択」(1982年)など、社会派の監督として名高いアラン・J・パクラ。
アティカス・フィンチに、「ローマの休日」(1953年)、「白鯨」(1956年)、「大いなる西部」(1958年)など、出演作に名作・傑作の多いハリウッドを代表する大スター、グレゴリー・ペック。
アティカスの娘スカウトに、「サタデー・ナイト・フィーバー」(1977年)でヒットをとばし、「ウォー・ゲーム」(1983年)、「ブルーサンダー」(1983年)、「アサシン」(1993年)などの軽快なアクション映画を得意とするジョン・バダム監督の妹メアリー・バダム。
成長したスカウトが少女時代を回想するという形式で描かれるこの映画は、法廷劇を主軸にしながら、スカウトの視点でとらえた大人の世界と、古タイヤなどで生き生きと遊びまわる子どもたちの世界を、郷愁を込めて描いた名作です。




1962年アメリカ
監督ロバート・マリガン
原作ハーパー・リー
脚色ホートン・フート
音楽エルマー・バーンスタイン
撮影ラッセル・ハーラン
〈キャスト〉
グレゴリー・ペック メアリー・バダム
フィリップ・アルフォード
& ロバート・デュヴァル
第35回アカデミー賞主演男優賞(グレゴリー・ペック)/脚色賞/美術賞受賞
いろいろな映画を数多く見ていると、ときどき、とても心に残る映画があります。「アラバマ物語」はそうした中の一本で、最初見たときよりも二回目、二回目見たときよりも三回目、三回目よりも四回目と回数が増えるにしたがって深い感動を与えてくれる稀有な映画です。
原題の「To Kill Mockingbird」のMockingbirdはモノマネ鳥、あるいはマネシツグミとも訳され、北アメリカの中部から南に広く分布するこの鳥は、その名前の通り、たくさんの種類の鳥や動物、車の警笛まで美しい声で真似をすることで知られています。
美しい声で鳴くだけで、人間に害を加えることのないマネシツグミを殺すということは、罪のない無力な人間に対する迫害を示唆する、この映画の主要なテーマでもあり、それは映画の中で主人公のアティカス・フィンチが娘にやさしく語りかける場面に現れます。

1932年、アメリカ南部アラバマ州の田舎町。
3年前の1929年10月に起きたニューヨーク・ウォール街の株価大暴落に端を発した世界恐慌の波が地方の片田舎にも押し寄せる中、少女スカウト(メアリー・バダム)と兄のジェム(フィリップ・アルフォード)は元気に遊びまわっています。
スカウトとジェムの前に突然現れた少年ディル(ジョン・メグナ)とも仲良しになり、意気投合した3人は近所に住む風変りな男“ブー”の正体を知りたくて、ある晩、ブーの家に忍び込もうとします。
誰もその顔を見たことのないブーは恐ろしい怪人のイメージをもって知られ、壊れたフェンスのすき間からブーの庭に忍び込んだジェムは、明かりのついていない真っ暗な部屋の中を隙見しようとしますが、その時近づいてきた足音に驚き、フェンスの外で待っているスカウトとディルの元へ逃げ帰ろうします。
しかし、ズボンに引っかかったフェンスが外れず、ジェムはズボンをその場で脱ぎ捨て、一目散に家へ逃げ帰ります。
後に、そのズボンはきちんと畳んでその場に置いてあったことを知ったジェムたちは、“ブー”に対する不可解な謎を深めることになります。

いたずら盛りのジェムとスカウトの父アティカス・フィンチ(グレゴリー・ペック)は弁護士。
妻に先立たれたアティカスは、子どもたちが母親のいない寂しさを抱えていることは知っていますが、現在の自分の置かれている状況に黙って従っています。
そんなある日、貧農で白人のボブ・ユーエル(ジェームズ・アンダーソン)の娘メイエラ(コリン・ウィルコックス)が黒人のトム・ロビンソン(ブロック・ピーターズ)から暴行を受けたと主張し告訴。
アティカスは知人の判事から、誰も引き受け手のいないトム・ロビンソンの弁護を依頼されます。
黒人への差別が激しいことで知られる南部の土地柄、アティカスは弁護の依頼に戸惑いながらも引き受けることにします。
弁護を引き受けたアティカスに対する一部地元住民の反発は激しく、警察署へまで押し寄せた住民たちはトムへの集団リンチに及ぼうとするまで事態は悪化しますが、機転を利かせたスカウトの言葉が殺気立った住民の気勢を削(そ)ぐことになります。
そして裁判の日……。

よくいわれているように、「アラバマ物語」の主人公アティカス・フィンチはアメリカ人が選んだ「アメリカ映画のヒーロー」として、インディ・ジョーンズやジェームズ・ボンドを抜いて堂々の一位になっています。
ちなみに5位が「真昼の決闘」のウィル・ケーンなので、アティカス・フィンチとウィル・ケーンの共通性、選ばれた理由というのは分かる気がします。
勝てる望みの少ない事柄に対して、自分がやらなければ誰も引き受ける者がいないと分かったとき、ウィル・ケーンは死を覚悟して、アティカス・フィンチは人種偏見の激しい迫害を受けて、裁判に負ければ弁護士として無能の烙印を押されかねない状況の中で、決して気負うことなく、淡々と事に当たります。
ウィル・ケーンはかろうじて決闘に勝利しますが、アティカスは全面敗訴します。
人種差別の色濃い南部で、白人のメイエラに対する暴行事件の裁判は、被告のトム・ロビンソンが黒人であるにもかかわらず、十二人の陪審員すべてが白人という極端な不合理の中で行われます。
メイエラの顔の傷跡から、彼女に暴行を加えたのは左利きの男であるとアティカスは断定。被告のトムは左手が不自由であり、メイエラの父ボブ・ユーエルが左利きであることから、トムを巻き込んだ娘と父の争いが原因であり、被告のトムは無実であることが明らかになっていきます。
アティカスは陪審員席に向かって、公正な判断を下すよう滔々(とうとう)と説得を試みます。
しかし、十二人の陪審員全員が下した判決の結果は、トムの有罪でした。

判決後の場面は、この映画の最も感動的なシーンといってもいいと思います。
閉廷して静かになった法廷、アティカスは弁護席でひとり書類を片づけています、傍聴席の二階ではそれを見守る大勢の黒人たち、アティカスの二人の子ども、ジェムとスカウトもその中に混じっています、書類を片づけ終わって法廷を後にするアティカスを二階の全員が黙って見送ります。
誰かが拍手をするわけでもなく、二階の傍聴席の黒人たちにアティカスが応えるでもなく、裁判に負けたアティカスが静かに去っていくこの場面は、アティカス・フィンチに対する黒人たちの敬意がよく表れていて、数多くある映画の名シーンの中でも、ひときわ秀逸なシーンのひとつといえます。
後に被告のトムは護送中に逃走し、威嚇のために発砲した警察官の銃弾がそれてトムは死亡。
二審に望みをつないでいたアティカスは失意に沈みます。
アティカス・フィンチは人並み外れた特別な人間ではありません。体力の衰えを感じ始めた中年のやもめ男です。
温厚で誠実な人柄で知られ、弱い者に対するいたわりの心を持つ優しい男でもあります。
有り体にいってしまえば、どこにでもいる平凡な男ともいえますが、狂犬を射殺する射撃の腕を持っている反面、唾を吐きかけられたボブ・ユーエルへの憤怒をグッと抑える自制心の強さは、並の人間にはなかなか真似ることのできない一面です。
しかし、この人の素晴らしいところは、黒人蔑視の根強い排他的な土地で、誰も引き受ける者のいない弁護を引き受け、周囲からの迫害にも遭いながら、自らの責任や正義を声高に叫ぶこともなく淡々と行動していくところにあります。
監督は「九月になれば」(1961年)、「ジャングル地帯」(1962年)のロバート・マリガン。
後の「おもいでの夏」(1970年)では、思春期の少年の性の目覚めとほろ苦さを、爽やかな感性で描いています。
製作は、「コールガール」(1971年)、「大統領の陰謀」(1976年)、「ソフィーの選択」(1982年)など、社会派の監督として名高いアラン・J・パクラ。
アティカス・フィンチに、「ローマの休日」(1953年)、「白鯨」(1956年)、「大いなる西部」(1958年)など、出演作に名作・傑作の多いハリウッドを代表する大スター、グレゴリー・ペック。
アティカスの娘スカウトに、「サタデー・ナイト・フィーバー」(1977年)でヒットをとばし、「ウォー・ゲーム」(1983年)、「ブルーサンダー」(1983年)、「アサシン」(1993年)などの軽快なアクション映画を得意とするジョン・バダム監督の妹メアリー・バダム。
成長したスカウトが少女時代を回想するという形式で描かれるこの映画は、法廷劇を主軸にしながら、スカウトの視点でとらえた大人の世界と、古タイヤなどで生き生きと遊びまわる子どもたちの世界を、郷愁を込めて描いた名作です。

2019年06月08日
映画「レヴェナント: 蘇えりし者」復讐するのは我か神か
「レヴェナント: 蘇えりし者」
(The Revenant)
2015年アメリカ
監督アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ
原作マイケル・パンク
脚本マーク・L・スミス
アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ
撮影エマニュエル・ルベツキ
〈キャスト〉
レオナルド・ディカプリオ トム・ハーディ
第88回アカデミー賞監督賞/主演男優賞(レオナルド・ディカプリオ)
撮影賞受賞
19世紀初頭、アメリカ開拓時代の北西部。
入植者の白人と先住民諸部族との間に紛争の絶えなかったころ、極寒地帯を移動しながら狩猟を続ける毛皮ハンターの一団がいました。
ハンターの一人で、息子のホーク(フォレスト・グッドラック)と共に一団に加わっていたヒュー・グラス(レオナルド・ディカプリオ)は、狩猟の銃声を聞き付けた先住民の襲撃に遭い、多くの犠牲者を出しながら、残り少なくなったハンターの一団と共に命からがら船で逃げ伸びます。

ヘンリー(ドーナル・グリーソン)を隊長とする一行は、仲間のいる居住区へ向かおうとするのですが、行く手は険しい山岳地帯。
陸路をとるか、船で川を下るかでモメることになりますが、ガイドとしての知識と経験の豊富なグラスの意見に従い、船は危険だということで、陸路をとることになります。
先頭に立ち、少し先を歩いていたグラスは子熊と遭遇。
子熊の近くには親熊がいるもの。アッと思う間もなくグラスは親熊の襲撃を受けます。
それは熊の中でも最も性質が荒いとされるグリズリー(灰色熊、ヒグマの亜種)でした。
執拗なグリズリーの襲撃を受けたグラスは、肉をえぐられ、足の骨を折られ、生きているのが不思議なほどの重傷を負います。

瀕死の体を担がれながらグラスと一行は山を越えようとしますが、大自然の難路で、すでにグラスは一行の足手まといとなってしまっており、最早グラスの死は避けられないとみた隊長ヘンリーの提案によって、グラスの死を看取るようフィッツジェラルド(トム・ハーディ)に命じ、フィッツジェラルドとグラスの息子ホークと年若いジム(ウィル・ポールター)の三人を残し、グラスの死を見届けたうえで帰還するよう命じます。
かねてからグラスに敵意を抱いていたフィッツジェラルドは、自分たちを雇った毛皮商会の分け前もあり、ホークを殺し、グラスを置き去りにしてジムとともにその場を立ち去ります。
目の前で息子のホークを殺され、ひとり置きざりにされたグラスはフィッツジェラルドへの復讐の鬼と化し、苛酷な大自然の中、瀕死の体でのサバイバルが始まり、フィッツジェラルドとの死闘へと物語は展開されてゆきます。

あくまでも個人的な感想
正直なところ、個人的には賛否両論の混在する映画です。
まず、カメラが常に移動しているために落ち着きがなく、しかも広角レンズを多用してそれを動かしているから、とてもうるさく感じます。
ストーリー自体はシンプルな復讐物でありながら、ところどころ挿入される宗教観、毛皮の狩猟や乱獲における歴史的背景、また、グラスと先住民である彼の妻との関係なども映画全体を覆う芸術的思惑の中に溶かし込まれているため、見る側に訴えるというよりは監督の独りよがりな印象を受けました。

しかし、そういったマイナスの印象があった反面、本物を追求しようとする監督の意図と、登場する俳優たちの熱演、特にヒュー・グラスを演じたレオナルド・ディカプリオの役者魂には今さらながら驚かされました。
レオナルド・ディカプリオは「ボーイズ・ライフ」(1993年)のころから素晴らしい演技力のある子どもだと思っていたのですが、「タイタニック」(1997年)で一気にスターダムにのし上がってしまったのが、かえってこの人にとってはよくない結果になるんじゃないかと思っていました。
「レオ様」「レオ様」と呼ばれ始めて少年っぽさを失わないイメージが望まれていたようですから、大衆が望むイメージを保っていたら、いつまでも少年のようなディカプリオは大成できないだろうなあ、と思っていたのが「ギャング・オブ・ニューヨーク」(2002年)「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」(2002年)で徐々に変化を見せ始め、「アビエイター」(2004年)「ディパーテッド」(2006年)「ブラッド・ダイヤモンド」(2006年)で大人の男へと変貌を遂げたのはお見事。
ただ、「レヴェナント」では生肉を食い、生きた魚にかじりつくシーンは、なにもそこまでしなくても、とも思いましたが、そこまですることによって苛酷なサバイバルの現実が、より生々しく伝わってきたのもたしかです。

ピクピクと動いている生きた魚を食べるシーンでは、そばに焚き火が燃えているんだから、火であぶればいいんじゃないかと思いましたが、極寒の地方ではそのまま食べる習慣でもあったのか、そのままのほうが栄養価は高いらしいですから。
ちなみに私は生きたシラウオをそのまま食べる「シラウオの踊り食い」を経験したことがありますが、口の中でグニュグニュ動く気持ち悪さに閉口して、一度きりでやめたことがあります。
レオナルド・ディカプリオ、大した根性ですが、本物志向が強すぎて、より過激な方向へいかないかと多少心配になります。
個人的には作品の賛否が交錯する「レヴェナント: 蘇えりし者」ですが、大自然に真っ向から取り組んだ力強い映画であることに間違いはなく、カメラの動き過ぎをうるさく感じたことは上述しましたが、そのカメラがとらえた大自然の風景が圧巻であったのも事実です。
また、この映画のテーマでもあるのかな、と思われる、人間が生きることの執念。グリズリーに体をズタズタにされて死期の迫った人間が、苛酷な自然の中で、どうやって生き延びることができたのか、多少の誇張はあるにせよ、復讐という執念だけが命をつなぎ、研ぎ澄まされた命の炎は、死から再生への奇跡を生み出すことができるものであるということも考えさせられた映画でした。



2015年アメリカ
監督アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ
原作マイケル・パンク
脚本マーク・L・スミス
アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ
撮影エマニュエル・ルベツキ
〈キャスト〉
レオナルド・ディカプリオ トム・ハーディ
第88回アカデミー賞監督賞/主演男優賞(レオナルド・ディカプリオ)
撮影賞受賞
19世紀初頭、アメリカ開拓時代の北西部。
入植者の白人と先住民諸部族との間に紛争の絶えなかったころ、極寒地帯を移動しながら狩猟を続ける毛皮ハンターの一団がいました。
ハンターの一人で、息子のホーク(フォレスト・グッドラック)と共に一団に加わっていたヒュー・グラス(レオナルド・ディカプリオ)は、狩猟の銃声を聞き付けた先住民の襲撃に遭い、多くの犠牲者を出しながら、残り少なくなったハンターの一団と共に命からがら船で逃げ伸びます。
ヘンリー(ドーナル・グリーソン)を隊長とする一行は、仲間のいる居住区へ向かおうとするのですが、行く手は険しい山岳地帯。
陸路をとるか、船で川を下るかでモメることになりますが、ガイドとしての知識と経験の豊富なグラスの意見に従い、船は危険だということで、陸路をとることになります。
先頭に立ち、少し先を歩いていたグラスは子熊と遭遇。
子熊の近くには親熊がいるもの。アッと思う間もなくグラスは親熊の襲撃を受けます。
それは熊の中でも最も性質が荒いとされるグリズリー(灰色熊、ヒグマの亜種)でした。
執拗なグリズリーの襲撃を受けたグラスは、肉をえぐられ、足の骨を折られ、生きているのが不思議なほどの重傷を負います。

瀕死の体を担がれながらグラスと一行は山を越えようとしますが、大自然の難路で、すでにグラスは一行の足手まといとなってしまっており、最早グラスの死は避けられないとみた隊長ヘンリーの提案によって、グラスの死を看取るようフィッツジェラルド(トム・ハーディ)に命じ、フィッツジェラルドとグラスの息子ホークと年若いジム(ウィル・ポールター)の三人を残し、グラスの死を見届けたうえで帰還するよう命じます。
かねてからグラスに敵意を抱いていたフィッツジェラルドは、自分たちを雇った毛皮商会の分け前もあり、ホークを殺し、グラスを置き去りにしてジムとともにその場を立ち去ります。
目の前で息子のホークを殺され、ひとり置きざりにされたグラスはフィッツジェラルドへの復讐の鬼と化し、苛酷な大自然の中、瀕死の体でのサバイバルが始まり、フィッツジェラルドとの死闘へと物語は展開されてゆきます。

あくまでも個人的な感想
正直なところ、個人的には賛否両論の混在する映画です。
まず、カメラが常に移動しているために落ち着きがなく、しかも広角レンズを多用してそれを動かしているから、とてもうるさく感じます。
ストーリー自体はシンプルな復讐物でありながら、ところどころ挿入される宗教観、毛皮の狩猟や乱獲における歴史的背景、また、グラスと先住民である彼の妻との関係なども映画全体を覆う芸術的思惑の中に溶かし込まれているため、見る側に訴えるというよりは監督の独りよがりな印象を受けました。
しかし、そういったマイナスの印象があった反面、本物を追求しようとする監督の意図と、登場する俳優たちの熱演、特にヒュー・グラスを演じたレオナルド・ディカプリオの役者魂には今さらながら驚かされました。
レオナルド・ディカプリオは「ボーイズ・ライフ」(1993年)のころから素晴らしい演技力のある子どもだと思っていたのですが、「タイタニック」(1997年)で一気にスターダムにのし上がってしまったのが、かえってこの人にとってはよくない結果になるんじゃないかと思っていました。
「レオ様」「レオ様」と呼ばれ始めて少年っぽさを失わないイメージが望まれていたようですから、大衆が望むイメージを保っていたら、いつまでも少年のようなディカプリオは大成できないだろうなあ、と思っていたのが「ギャング・オブ・ニューヨーク」(2002年)「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」(2002年)で徐々に変化を見せ始め、「アビエイター」(2004年)「ディパーテッド」(2006年)「ブラッド・ダイヤモンド」(2006年)で大人の男へと変貌を遂げたのはお見事。
ただ、「レヴェナント」では生肉を食い、生きた魚にかじりつくシーンは、なにもそこまでしなくても、とも思いましたが、そこまですることによって苛酷なサバイバルの現実が、より生々しく伝わってきたのもたしかです。

ピクピクと動いている生きた魚を食べるシーンでは、そばに焚き火が燃えているんだから、火であぶればいいんじゃないかと思いましたが、極寒の地方ではそのまま食べる習慣でもあったのか、そのままのほうが栄養価は高いらしいですから。
ちなみに私は生きたシラウオをそのまま食べる「シラウオの踊り食い」を経験したことがありますが、口の中でグニュグニュ動く気持ち悪さに閉口して、一度きりでやめたことがあります。
レオナルド・ディカプリオ、大した根性ですが、本物志向が強すぎて、より過激な方向へいかないかと多少心配になります。
個人的には作品の賛否が交錯する「レヴェナント: 蘇えりし者」ですが、大自然に真っ向から取り組んだ力強い映画であることに間違いはなく、カメラの動き過ぎをうるさく感じたことは上述しましたが、そのカメラがとらえた大自然の風景が圧巻であったのも事実です。
また、この映画のテーマでもあるのかな、と思われる、人間が生きることの執念。グリズリーに体をズタズタにされて死期の迫った人間が、苛酷な自然の中で、どうやって生き延びることができたのか、多少の誇張はあるにせよ、復讐という執念だけが命をつなぎ、研ぎ澄まされた命の炎は、死から再生への奇跡を生み出すことができるものであるということも考えさせられた映画でした。

2019年06月05日
映画「さらば冬のかもめ」閉塞感への反抗
「さらば冬のかもめ」
(The Last Detail)
1973年アメリカ
監督ハル・アシュビー
脚本ロバート・タウン
原作ダリル・ポニクサン
撮影マイケル・チャップマン
〈キャスト〉
ジャック・ニコルソン ランディ・クエイド
オーティス・ヤング キャロル・ケイン
カンヌ国際映画祭主演男優賞受賞(ジャック・ニコルソン)
1969年の「イージー・ライダー」で頭角を現したジャック・ニコルソンが「ファイブ・イージー・ピーセス」(1970年)「愛の狩人」(1971年)などを経てカンヌ国際映画祭で主演男優賞を射止めたアメリカン・ニューシネマの秀作。

アメリカ東部バージニア州、世界最大を誇るノーフォーク海軍基地。
海軍下士官バダスキー(ジャック・ニコルソン)とマルホール(オーティス・ヤング)の二人に、罪を犯した新兵をポーツマス海軍刑務所に護送する任務が下ります。
護送の任務などヤル気のなかったバダスキーでしたが、護送期間一週間分の日当が支給されるということで、サッサと護送をすませて残りの日当を遊びに使おうと企んだ二人は、意気揚々と護送任務にあたります。

護送される新兵は8年の刑期を言い渡された未成年のメドウズ(ランディ・クエイド)。
大柄な体格に似合わず気の弱そうなメドウズは、基地に設置されていた募金箱の中から40ドルを盗んだために8年の刑期をポーツマス海軍刑務所で送ることになっていました。
「でも本当は盗んじゃいないんだ」メドウズは言います。「盗もうとしただけなんだ」
「…それで8年か」バダスキーは唖然とします。
メドウズが手を付けようとした募金箱は、慈善家である司令官夫人が設置したもので、そのためにことさら犯罪としての重大性を帯びたともいえますが、わずか40ドルのために貴重な青年期を刑務所で送らなければならないことになったメドウズにバダスキーは同情を覚えます。
メドウズへの哀れみと、軍隊という組織への憤りがバダスキーの中で広がり、ポーツマスへ向かう前に途中下車をして、青年期の楽しみや人生をメドウズに教えようとします。
気の弱いメドウズに、自分の主張を通させる強さを教えようと、レストランでは注文とは違った食事を出されたメドウズに、注文を変えさせろ、と迫ったり、酒場では、未成年には酒は出せないと言うバーテンダーに危うく銃で反撃しようとしたり。
そんなバダスキーに振り回された形のマルホールは、
「大物ぶるな!」とバダスキーに一喝。
シュンとなったバダスキーでしたが、その後も三人で、女を知らないメドウズのために売春婦(キャロル・ケイン)を世話したり、ホテルで酔いつぶれたり、海兵隊員相手にケンカをしたり、真冬のニューヨークやボストンでいろいろな体験をしながらポーツマスへの旅を続けます。

残り少なくなった時間を雪の舞う公園でバーベキューを始める三人。
焚き木を拾って、ニューヨークの日蓮正宗(にちれんしょうしゅう)の会場で覚えた「南無妙法蓮華経」(ナンミョウホーレンゲキョー)の題目を唱えながら焚き木を折り、その場を立ち去ろうとするメドウズ。
メドウズの逃走に気づいたバダスキーとマルホールは、やっとのことでメドウズを取り押さえ、ポーツマス海軍刑務所へメドウズを引き渡します。
護送の任務を終えたバダスキーとマルホールには、もうメドウズのことは頭になく、明日から始まる海軍の生活が待っているのです。

★★★★★
60年代の後半から始まったアメリカン・ニューシネマの流れは、「俺たちに明日はない」(1967年)「卒業」(1967年)「イージー・ライダー」(1969年)「明日に向かって撃て!」(1969年)など名作や傑作を数多く残しました。
そういった中で、どちらかといえば地味なロードムービーの印象があったためか「さらば冬のかもめ」は並みいる傑作群に比して一歩後ろへ退いている感がありました。
なし崩し的に始まったベトナム戦争が泥沼化してアメリカ国内で反戦運動が高まったことを背景に、それまでは夢や正義、力強さを語ることの多かったアメリカ映画は、体制への反抗、身動きの取れない日常からの逃避、無気力な若者など、人間性や社会の負の側面を追求した映画が主流となっていきます。
「さらば冬のかもめ」にもそういった、もがいてもどうにもならない日常が描かれ、それは、メドウズの食事や、酒場でのやり取りに見られるバダスキーの反抗心?き出しの態度など、変えようとしても変えることのできない組織体制への不満が噴き出した反抗であり、弱さから強さへの変貌を遂げたかのように見えたメドウズも結局は刑務所送りとなってしまう無力感と閉塞感が映画のクライマックスを覆います。
しかし、「さらば冬のかもめ」には、やりきれない現実というよりは、むしろ爽やかな後味が残るのは、もがきながらも精一杯反抗しようとする若者の姿が、ある種の共感を呼ぶためだと思います。

また、閉塞感の中で生きてゆくしかない現実を笑い飛ばしてしまおうとするかのようなラストシーンは、自虐的なほろ苦さと同時に国家防衛の任に当たるささやかな誇りのようなものも垣間見えた気がしました。
粗野ではあるが情に厚い一面を持ったバダスキー。現実的で常識家のマルホール。体だけは人一倍大きい割に気の小さいメドウズ。
三者三様の個性を持ったドタバタ珍道中的なロードムービーでありながら、名匠マイケル・チャップマンが撮影監督に当たったワシントン、ニューヨーク、ボストンそれぞれの真冬の風景は映画に物語の陰影と奥行きを与えています。
原題は「The Last Detail」。そのまま訳せば“最後の詳細”ですが、Detailには軍事用語で“分遣隊”の意味があるらしく、映画では“任務”と訳されていたようです。
「さらば冬のかもめ」という邦題はよく出来ていると思います。
どこからかもめのイメージが出たのか、バダスキーたち三人が水兵服を着ていることから「かもめの水兵さん」のイメージにつながったのか、当時はリチャード・バックの「かもめのジョナサン」が世界的ベストセラーになったことからの連想なのか、それはともかく、「さらば冬のかもめ」という邦題には香り高い文学的なイメージが広がります。



1973年アメリカ
監督ハル・アシュビー
脚本ロバート・タウン
原作ダリル・ポニクサン
撮影マイケル・チャップマン
〈キャスト〉
ジャック・ニコルソン ランディ・クエイド
オーティス・ヤング キャロル・ケイン
カンヌ国際映画祭主演男優賞受賞(ジャック・ニコルソン)
1969年の「イージー・ライダー」で頭角を現したジャック・ニコルソンが「ファイブ・イージー・ピーセス」(1970年)「愛の狩人」(1971年)などを経てカンヌ国際映画祭で主演男優賞を射止めたアメリカン・ニューシネマの秀作。

アメリカ東部バージニア州、世界最大を誇るノーフォーク海軍基地。
海軍下士官バダスキー(ジャック・ニコルソン)とマルホール(オーティス・ヤング)の二人に、罪を犯した新兵をポーツマス海軍刑務所に護送する任務が下ります。
護送の任務などヤル気のなかったバダスキーでしたが、護送期間一週間分の日当が支給されるということで、サッサと護送をすませて残りの日当を遊びに使おうと企んだ二人は、意気揚々と護送任務にあたります。
護送される新兵は8年の刑期を言い渡された未成年のメドウズ(ランディ・クエイド)。
大柄な体格に似合わず気の弱そうなメドウズは、基地に設置されていた募金箱の中から40ドルを盗んだために8年の刑期をポーツマス海軍刑務所で送ることになっていました。
「でも本当は盗んじゃいないんだ」メドウズは言います。「盗もうとしただけなんだ」
「…それで8年か」バダスキーは唖然とします。
メドウズが手を付けようとした募金箱は、慈善家である司令官夫人が設置したもので、そのためにことさら犯罪としての重大性を帯びたともいえますが、わずか40ドルのために貴重な青年期を刑務所で送らなければならないことになったメドウズにバダスキーは同情を覚えます。
メドウズへの哀れみと、軍隊という組織への憤りがバダスキーの中で広がり、ポーツマスへ向かう前に途中下車をして、青年期の楽しみや人生をメドウズに教えようとします。
気の弱いメドウズに、自分の主張を通させる強さを教えようと、レストランでは注文とは違った食事を出されたメドウズに、注文を変えさせろ、と迫ったり、酒場では、未成年には酒は出せないと言うバーテンダーに危うく銃で反撃しようとしたり。
そんなバダスキーに振り回された形のマルホールは、
「大物ぶるな!」とバダスキーに一喝。
シュンとなったバダスキーでしたが、その後も三人で、女を知らないメドウズのために売春婦(キャロル・ケイン)を世話したり、ホテルで酔いつぶれたり、海兵隊員相手にケンカをしたり、真冬のニューヨークやボストンでいろいろな体験をしながらポーツマスへの旅を続けます。
残り少なくなった時間を雪の舞う公園でバーベキューを始める三人。
焚き木を拾って、ニューヨークの日蓮正宗(にちれんしょうしゅう)の会場で覚えた「南無妙法蓮華経」(ナンミョウホーレンゲキョー)の題目を唱えながら焚き木を折り、その場を立ち去ろうとするメドウズ。
メドウズの逃走に気づいたバダスキーとマルホールは、やっとのことでメドウズを取り押さえ、ポーツマス海軍刑務所へメドウズを引き渡します。
護送の任務を終えたバダスキーとマルホールには、もうメドウズのことは頭になく、明日から始まる海軍の生活が待っているのです。

★★★★★
60年代の後半から始まったアメリカン・ニューシネマの流れは、「俺たちに明日はない」(1967年)「卒業」(1967年)「イージー・ライダー」(1969年)「明日に向かって撃て!」(1969年)など名作や傑作を数多く残しました。
そういった中で、どちらかといえば地味なロードムービーの印象があったためか「さらば冬のかもめ」は並みいる傑作群に比して一歩後ろへ退いている感がありました。
なし崩し的に始まったベトナム戦争が泥沼化してアメリカ国内で反戦運動が高まったことを背景に、それまでは夢や正義、力強さを語ることの多かったアメリカ映画は、体制への反抗、身動きの取れない日常からの逃避、無気力な若者など、人間性や社会の負の側面を追求した映画が主流となっていきます。
「さらば冬のかもめ」にもそういった、もがいてもどうにもならない日常が描かれ、それは、メドウズの食事や、酒場でのやり取りに見られるバダスキーの反抗心?き出しの態度など、変えようとしても変えることのできない組織体制への不満が噴き出した反抗であり、弱さから強さへの変貌を遂げたかのように見えたメドウズも結局は刑務所送りとなってしまう無力感と閉塞感が映画のクライマックスを覆います。
しかし、「さらば冬のかもめ」には、やりきれない現実というよりは、むしろ爽やかな後味が残るのは、もがきながらも精一杯反抗しようとする若者の姿が、ある種の共感を呼ぶためだと思います。

また、閉塞感の中で生きてゆくしかない現実を笑い飛ばしてしまおうとするかのようなラストシーンは、自虐的なほろ苦さと同時に国家防衛の任に当たるささやかな誇りのようなものも垣間見えた気がしました。
粗野ではあるが情に厚い一面を持ったバダスキー。現実的で常識家のマルホール。体だけは人一倍大きい割に気の小さいメドウズ。
三者三様の個性を持ったドタバタ珍道中的なロードムービーでありながら、名匠マイケル・チャップマンが撮影監督に当たったワシントン、ニューヨーク、ボストンそれぞれの真冬の風景は映画に物語の陰影と奥行きを与えています。
原題は「The Last Detail」。そのまま訳せば“最後の詳細”ですが、Detailには軍事用語で“分遣隊”の意味があるらしく、映画では“任務”と訳されていたようです。
「さらば冬のかもめ」という邦題はよく出来ていると思います。
どこからかもめのイメージが出たのか、バダスキーたち三人が水兵服を着ていることから「かもめの水兵さん」のイメージにつながったのか、当時はリチャード・バックの「かもめのジョナサン」が世界的ベストセラーになったことからの連想なのか、それはともかく、「さらば冬のかもめ」という邦題には香り高い文学的なイメージが広がります。

2019年04月08日
映画「失われた終末」アル中男の苦悩と再生
「失われた終末」
(The Lost Weekend)
1945年 アメリカ
監督ビリー・ワイルダー
脚本チャールズ・ブラケット
ビリー・ワイルダー
原作チャールズ・R・ジャクソン
〈キャスト〉
レイ・ミランド ジェーン・ワイマン
フィリップ・テリー
第18回アカデミー賞作品賞/主演男優賞(レイ・ミランド)
カンヌ国際映画祭グランプリ

ドン・バーナム(レイ・ミランド)は作家としての生活を送っていますが、才能を発揮できないままスランプに陥り、アルコールへと逃避したことから、そのまま抜け出せなくなり、アルコール中毒となって、兄(テリー・バーナム)の世話になっています。
兄は弟のために終末を利用して田舎へ連れ出そうとします。田舎の静かな環境がアルコール中毒の弟の健康には良い結果を生むと考えたからです。
しかし、そんな弟思いの兄の計画も空しく、酒を渇望するドンは出発の当日、酒を求めて町をさまよい、週末の計画を台無しにしてしまいます。
怒った兄はドンを残し、一人で田舎へと出発して行きます。
酒! 酒! 酒! 酒のことしか頭になくなったドンは金もなくなり、作家の生命であるタイプライターまで質に入れて金を工面しようとします。

その後、ふとしたはずみで階段から転落したドンは病院へ搬送され、アルコール中毒患者の施設に収容されます。
ほどなくして施設から脱走したドンでしたが、やがてアルコール中毒者特有の幻覚症状が現れるようになり、自分に絶望したドンはピストル自殺を図ろうとします。

アルコール中毒に陥った男の苦悩と絶望、そして再生までを描いた名匠ビリー・ワイルダー監督による傑作です。
私自身も酒が好きで、それも大のウイスキー党なので、この映画を観ているとやたらとウイスキーが飲みたくなります。
ほとんど毎日、酒(ウイスキー)を飲まない日はないというくらい愛飲していますが、何かの目標があって、それを達成するまでは酒をやめようと思うこともあって、1日、2日は禁酒をするのですが、やっぱり飲まないとかえって調子が悪く、さっさと飲んで、さっさと酔っぱらって、さっさと覚ますことにして目標にたどりついたりしてますから、もしかしてアルコール依存症なのか、単に意志が弱いだけなのか、…多分、後者のほうなのでしょう。

作家であるドン・バーナムは小説を書けなくなったことから酒に溺れてしまいます。
映画はドンの行動を追って展開してゆきますが、それと共にドンを取り巻く人々がよく描かれていると思います。
一人はやはりドンの兄。
弟の健康を気遣って田舎に連れ出そうとする優しいお兄さんで、どういった職業なのかは描かれてはいませんが、知的な風貌からは社会的な高さの職業であることが分ります。
さらに、ドンの馴染みの酒場の店主ナット(ハワード・ダ・シルヴァ)。
タイプライターを質に入れようとしたドンの元へ、忘れ物だと言わんばかりにタイプライターを届けに来るナットの存在は、ドン・バーナムの再生物語の重要な骨格をなしています。
そして恋人ヘレン(ジェーン・ワイマン)。
アル中だと判ったドンを見捨てることなく、最後の最後までドンの立ち直りを信じるヘレンの姿は、健気(けなげ)というより芯の強い女性、みんなが見捨てても私は見捨てない、そんな強い信念に裏打ちされた女性だと思いました。
ちなみにジェーン・ワイマンさんはアメリカ合衆国第40代大統領ロナルド・レーガンの最初の奥さんでもあった人です。
人間は一人では生きられず、自分の周囲の人間関係によって自分も育(はぐく)まれていくものでもあります。
ドン・バーナムがアル中から抜け出せたのはドンだけの意志によるものではなく、そこに関わる様々な人たちによって、一人の人間の再生が可能になったといえます。
「失われた終末」は社会の中で、人間同士の関わり合いによって絶望から希望へと導かれることができるということを教えてくれる傑作です。




1945年 アメリカ
監督ビリー・ワイルダー
脚本チャールズ・ブラケット
ビリー・ワイルダー
原作チャールズ・R・ジャクソン
〈キャスト〉
レイ・ミランド ジェーン・ワイマン
フィリップ・テリー
第18回アカデミー賞作品賞/主演男優賞(レイ・ミランド)
カンヌ国際映画祭グランプリ

ドン・バーナム(レイ・ミランド)は作家としての生活を送っていますが、才能を発揮できないままスランプに陥り、アルコールへと逃避したことから、そのまま抜け出せなくなり、アルコール中毒となって、兄(テリー・バーナム)の世話になっています。
兄は弟のために終末を利用して田舎へ連れ出そうとします。田舎の静かな環境がアルコール中毒の弟の健康には良い結果を生むと考えたからです。
しかし、そんな弟思いの兄の計画も空しく、酒を渇望するドンは出発の当日、酒を求めて町をさまよい、週末の計画を台無しにしてしまいます。
怒った兄はドンを残し、一人で田舎へと出発して行きます。
酒! 酒! 酒! 酒のことしか頭になくなったドンは金もなくなり、作家の生命であるタイプライターまで質に入れて金を工面しようとします。
その後、ふとしたはずみで階段から転落したドンは病院へ搬送され、アルコール中毒患者の施設に収容されます。
ほどなくして施設から脱走したドンでしたが、やがてアルコール中毒者特有の幻覚症状が現れるようになり、自分に絶望したドンはピストル自殺を図ろうとします。

アルコール中毒に陥った男の苦悩と絶望、そして再生までを描いた名匠ビリー・ワイルダー監督による傑作です。
私自身も酒が好きで、それも大のウイスキー党なので、この映画を観ているとやたらとウイスキーが飲みたくなります。
ほとんど毎日、酒(ウイスキー)を飲まない日はないというくらい愛飲していますが、何かの目標があって、それを達成するまでは酒をやめようと思うこともあって、1日、2日は禁酒をするのですが、やっぱり飲まないとかえって調子が悪く、さっさと飲んで、さっさと酔っぱらって、さっさと覚ますことにして目標にたどりついたりしてますから、もしかしてアルコール依存症なのか、単に意志が弱いだけなのか、…多分、後者のほうなのでしょう。
作家であるドン・バーナムは小説を書けなくなったことから酒に溺れてしまいます。
映画はドンの行動を追って展開してゆきますが、それと共にドンを取り巻く人々がよく描かれていると思います。
一人はやはりドンの兄。
弟の健康を気遣って田舎に連れ出そうとする優しいお兄さんで、どういった職業なのかは描かれてはいませんが、知的な風貌からは社会的な高さの職業であることが分ります。
さらに、ドンの馴染みの酒場の店主ナット(ハワード・ダ・シルヴァ)。
タイプライターを質に入れようとしたドンの元へ、忘れ物だと言わんばかりにタイプライターを届けに来るナットの存在は、ドン・バーナムの再生物語の重要な骨格をなしています。
そして恋人ヘレン(ジェーン・ワイマン)。
アル中だと判ったドンを見捨てることなく、最後の最後までドンの立ち直りを信じるヘレンの姿は、健気(けなげ)というより芯の強い女性、みんなが見捨てても私は見捨てない、そんな強い信念に裏打ちされた女性だと思いました。
ちなみにジェーン・ワイマンさんはアメリカ合衆国第40代大統領ロナルド・レーガンの最初の奥さんでもあった人です。
人間は一人では生きられず、自分の周囲の人間関係によって自分も育(はぐく)まれていくものでもあります。
ドン・バーナムがアル中から抜け出せたのはドンだけの意志によるものではなく、そこに関わる様々な人たちによって、一人の人間の再生が可能になったといえます。
「失われた終末」は社会の中で、人間同士の関わり合いによって絶望から希望へと導かれることができるということを教えてくれる傑作です。

2019年03月29日
映画「ブリッジ・オブ・スパイ」東西冷戦の捕虜交換劇
「ブリッジ・オブ・スパイ」
(Bridge of Spies)
2015年 アメリカ
監督スティーヴン・スピルバーグ
脚本マット・チャーマン
イーサン・コーエン
ジョエル・コーエン
撮影ヤヌス・カミンスキー
〈キャスト〉
トム・ハンクス マーク・ライランス
エイミー・ライアン
第88回アカデミー賞/ニューヨーク映画批評家協会賞助演男優賞(マーク・ライランス)

東西両陣営
1945年に第二次世界大戦が終結し、戦勝国の首脳が集まったヤルタ会談から、戦後の世界は分割協定へと動き始めます。
その主要な対立軸となったのが、超大国となったアメリカを代表とする自由主義諸国と、ソビエト連邦を盟主とする社会主義国でした。
アジアでは朝鮮半島。ヨーロッパは主にドイツが対象となって、北と南、あるいは西と東に分断。アメリカ的自由主義とソビエトの社会主義的イデオロギーは全ヨーロッパを巻き込み、政治的・経済的にも異なった価値観を持った東西ヨーロッパへと変容してゆきます。
アメリカとソ連の対立は政治のみならず、軍事的にも激しく対立。
西側の北大西洋条約機構(NATO)に対して東側のワルシャワ条約機構が生まれ、米ソの核ミサイルの開発と配備は一触即発の緊張状態へと突き進んでゆきます。
こうした現状をイギリス人の作家でジャーナリストのジョージ・オーウェルは1947年に、冷たい戦争「冷戦」と呼びました。

ジェームズ・ドノヴァン(トム・ハンクス)は法律事務所で保険裁判などを担当する弁護士。
彼はある日、ソ連の諜報員として逮捕されたルドルフ・アベル(マーク・ライランス)の国選弁護人を依頼されます。
時は1957年、東西冷戦の真っ只中。
ドノヴァンは刑事事件から遠ざかっていることや、敵国人の弁護を引き受けた場合の社会的非難、勝つ見込みのない裁判であることを考えると不安を覚えますが、弁護士としての職務に順じ、引き受けることにします。
拘置所を訪れ、アベルと面会したドノヴァンは、諜報員でありながら芸術家としての顔を持つアベルの落ち着いた物腰や、死を恐れず、国家に忠誠を尽くそうとする態度に友情にも似た感銘を受け、裁判での無罪判決に奔走しますが、陪審員の評決は有罪。
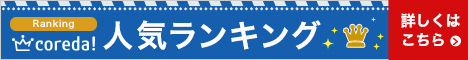
死刑だけは免(まぬが)れさせようとするドノヴァンは判事にかけあい、近い将来、スパイの交換があった場合の人質としてアベルの減刑を要求。
ドノヴァンの粘り強い交渉は功を奏し、アベルの死刑判決は退けられて懲役刑が確定します。
一方、パキスタンのアメリカ軍空軍基地ではU-2偵察機によるソ連への偵察飛行が行われようとしており、基地から飛び立ったパイロットのひとりフランシス・ゲーリー・パワーズ中尉はソ連のS-75地対空ミサイルの攻撃を受けて撃墜され、ソ連の捕虜となってしまいます。
さらに、ベルリンでは東西ドイツを二分する壁の建設が進められ、アメリカ人学生で経済学を専攻するフレデリック・プライヤー(ウィル・ロジャース)は、恋人と一緒に東ドイツから西ドイツへ逃れるべく、壁建設の混乱に乗じて脱出を試みますが、ドイツ軍兵士に止められ、捕らわれてしまいます。

ドノヴァンの捕虜交換の予想は期せずして的中した形になり、ソ連側のアベルと、アメリカ側のパワーズとプライヤーの交換交渉をするべくドノヴァンは東ベルリンへ向かいますが、CIAとKGBが入り乱れて暗躍する中で交渉は難航。
CIAの要求はアベル対パワーズの一対一の交換だという主張に対し、ドノヴァンはあくまでパワーズとプライヤーも含めた一対二の交渉を主張。
持ち前の粘り強さでドノヴァンは捕虜交換の交渉を続け、アベル対パワーズ、そしてプライヤーも含めた一対二の交渉が実現します。
交換場所はドイツ・メクレンブルクからブランデンブルク、ベルリンへと流れるハーフェル川に架かるグリーニッケ橋。
東西両陣営が対峙する橋の上で西側からはアベル、東側からパワーズの姿が現れますが、もう一人現れるはずのプライヤーの姿が見えないまま、捕虜交換が進められようとしますが、ソ連側の意図を察したドノヴァンはギリギリまで交渉を制止、交渉は決裂かと思われましたが………。

見応え十分の捕虜交換ドラマ
題名からは、暗躍するスパイアクション映画という印象を受けますが、アメリカとソ連の諜報員の交換が行われた史実をもとに、冷戦という重い空気感の漂う時代の中で、国家やイデオロギーを超えた人間同士の信頼や友情を描いた重厚なヒューマンドラマであるといえます。
特に、アカデミー賞を始めとして数々の賞を総なめにした助演男優賞受賞のマーク・ライランスの演技は素晴らしく、諜報活動をする傍(かたわ)ら、画家としての卓越した才能を持っているルドルフ・アベルを物静かな芸術家として表現。
拘置所の中で、ドノヴァンが差し入れたと思われるラジオから流れるショスタコーヴィチの音楽を、乾いた心の中に染み込んでいくように聴き入る姿、少年時代の体験をドノヴァンの置かれた立場と重ね合わせて語る場面からは、物静かな芸術家であると同時に強い信念の持ち主であり、ドノヴァンに対する信頼が芽生え始める印象的なシーンでした。
冷戦時代は破壊的な戦争が起きることもなく、1991年のソ連崩壊により冷戦は終結しましたが、スパイの交換が行われたグリーニッケ橋が東西冷戦の象徴として観光地化されているように、冷戦時代を懐かしむ声があるのは、失われてしまった、あるいは失われつつある古き時代の家族としての在り方、友情、人間同士のつながりが強く残っていた時代であり、「ブリッジ・オブ・スパイ」はそういったものをも含めて描いた傑作です。



2015年 アメリカ
監督スティーヴン・スピルバーグ
脚本マット・チャーマン
イーサン・コーエン
ジョエル・コーエン
撮影ヤヌス・カミンスキー
〈キャスト〉
トム・ハンクス マーク・ライランス
エイミー・ライアン
第88回アカデミー賞/ニューヨーク映画批評家協会賞助演男優賞(マーク・ライランス)

東西両陣営
1945年に第二次世界大戦が終結し、戦勝国の首脳が集まったヤルタ会談から、戦後の世界は分割協定へと動き始めます。
その主要な対立軸となったのが、超大国となったアメリカを代表とする自由主義諸国と、ソビエト連邦を盟主とする社会主義国でした。
アジアでは朝鮮半島。ヨーロッパは主にドイツが対象となって、北と南、あるいは西と東に分断。アメリカ的自由主義とソビエトの社会主義的イデオロギーは全ヨーロッパを巻き込み、政治的・経済的にも異なった価値観を持った東西ヨーロッパへと変容してゆきます。
アメリカとソ連の対立は政治のみならず、軍事的にも激しく対立。
西側の北大西洋条約機構(NATO)に対して東側のワルシャワ条約機構が生まれ、米ソの核ミサイルの開発と配備は一触即発の緊張状態へと突き進んでゆきます。
こうした現状をイギリス人の作家でジャーナリストのジョージ・オーウェルは1947年に、冷たい戦争「冷戦」と呼びました。

ジェームズ・ドノヴァン(トム・ハンクス)は法律事務所で保険裁判などを担当する弁護士。
彼はある日、ソ連の諜報員として逮捕されたルドルフ・アベル(マーク・ライランス)の国選弁護人を依頼されます。
時は1957年、東西冷戦の真っ只中。
ドノヴァンは刑事事件から遠ざかっていることや、敵国人の弁護を引き受けた場合の社会的非難、勝つ見込みのない裁判であることを考えると不安を覚えますが、弁護士としての職務に順じ、引き受けることにします。
拘置所を訪れ、アベルと面会したドノヴァンは、諜報員でありながら芸術家としての顔を持つアベルの落ち着いた物腰や、死を恐れず、国家に忠誠を尽くそうとする態度に友情にも似た感銘を受け、裁判での無罪判決に奔走しますが、陪審員の評決は有罪。
死刑だけは免(まぬが)れさせようとするドノヴァンは判事にかけあい、近い将来、スパイの交換があった場合の人質としてアベルの減刑を要求。
ドノヴァンの粘り強い交渉は功を奏し、アベルの死刑判決は退けられて懲役刑が確定します。
一方、パキスタンのアメリカ軍空軍基地ではU-2偵察機によるソ連への偵察飛行が行われようとしており、基地から飛び立ったパイロットのひとりフランシス・ゲーリー・パワーズ中尉はソ連のS-75地対空ミサイルの攻撃を受けて撃墜され、ソ連の捕虜となってしまいます。
さらに、ベルリンでは東西ドイツを二分する壁の建設が進められ、アメリカ人学生で経済学を専攻するフレデリック・プライヤー(ウィル・ロジャース)は、恋人と一緒に東ドイツから西ドイツへ逃れるべく、壁建設の混乱に乗じて脱出を試みますが、ドイツ軍兵士に止められ、捕らわれてしまいます。

ドノヴァンの捕虜交換の予想は期せずして的中した形になり、ソ連側のアベルと、アメリカ側のパワーズとプライヤーの交換交渉をするべくドノヴァンは東ベルリンへ向かいますが、CIAとKGBが入り乱れて暗躍する中で交渉は難航。
CIAの要求はアベル対パワーズの一対一の交換だという主張に対し、ドノヴァンはあくまでパワーズとプライヤーも含めた一対二の交渉を主張。
持ち前の粘り強さでドノヴァンは捕虜交換の交渉を続け、アベル対パワーズ、そしてプライヤーも含めた一対二の交渉が実現します。
交換場所はドイツ・メクレンブルクからブランデンブルク、ベルリンへと流れるハーフェル川に架かるグリーニッケ橋。
東西両陣営が対峙する橋の上で西側からはアベル、東側からパワーズの姿が現れますが、もう一人現れるはずのプライヤーの姿が見えないまま、捕虜交換が進められようとしますが、ソ連側の意図を察したドノヴァンはギリギリまで交渉を制止、交渉は決裂かと思われましたが………。
見応え十分の捕虜交換ドラマ
題名からは、暗躍するスパイアクション映画という印象を受けますが、アメリカとソ連の諜報員の交換が行われた史実をもとに、冷戦という重い空気感の漂う時代の中で、国家やイデオロギーを超えた人間同士の信頼や友情を描いた重厚なヒューマンドラマであるといえます。
特に、アカデミー賞を始めとして数々の賞を総なめにした助演男優賞受賞のマーク・ライランスの演技は素晴らしく、諜報活動をする傍(かたわ)ら、画家としての卓越した才能を持っているルドルフ・アベルを物静かな芸術家として表現。
拘置所の中で、ドノヴァンが差し入れたと思われるラジオから流れるショスタコーヴィチの音楽を、乾いた心の中に染み込んでいくように聴き入る姿、少年時代の体験をドノヴァンの置かれた立場と重ね合わせて語る場面からは、物静かな芸術家であると同時に強い信念の持ち主であり、ドノヴァンに対する信頼が芽生え始める印象的なシーンでした。
冷戦時代は破壊的な戦争が起きることもなく、1991年のソ連崩壊により冷戦は終結しましたが、スパイの交換が行われたグリーニッケ橋が東西冷戦の象徴として観光地化されているように、冷戦時代を懐かしむ声があるのは、失われてしまった、あるいは失われつつある古き時代の家族としての在り方、友情、人間同士のつながりが強く残っていた時代であり、「ブリッジ・オブ・スパイ」はそういったものをも含めて描いた傑作です。









