2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年01月の記事
全65件 (65件中 1-50件目)
-
MLブック
メインレッスンの準備として、メインレッスンブックを作る。中学生・高校生レベルになると、メインレッスンブックを作らない先生も多いのだけど、私は、毎回作り直す。彼らへの期待度を表すものとして有効だし、彼らの、学習意欲を鼓舞するにも大いに役立つ。幾何の作図に、色鉛筆で色をつけ、芸術的に美しいものに仕上げる。シュタイナー教育を知らない人が見たら、「そんなの時間の無駄でしょ」って言うかもしれない。時間はかかるし、色を塗るなんて子どもじみてる、って思うかも。でも、実際にやってみると分かる。作図をし、自分なりの創造性をもって、1つの芸術作品として、メインレッスンブックを作りあげていく作業。手を動かしていると、いつもより頭も働く。思わぬ気付きが湧き上がる。幾何の世界の美しさに心が躍る。美しい色や形に、歓喜する。だから、とにかく、手を動かして、やってみるといい。そうすると、この無駄とも思える作業の意味が感じ取れると思う。
2006年01月31日
コメント(0)
-

幾何の本
メインレッスンのために本を注文したのが届く。"The biginner's guide to constructing the universe"by Michael.S Schneider内容の良さに興奮してます。Sacred Geometryの本ですが、自然や科学、建築、芸術に見られる幾何の世界を、美しく見せてくれます。ふんだんに載せられた、著名人の言葉が、その美しさを引き立ててくれて。7年生、8年生のメインレッスンに、大活躍しちゃいそうです。それにしても、これ、製本と紙が酷い。どうしてアメリカ製のペーパーバックって、こんなに質が悪いんでしょう。内容が良いだけに、惜しい。もう1冊はこれ。沢山の作図、図版が盛り込まれていて、読者が実際に作図をして楽しめそうです。これもなかなか良いです。 "Sacred Geometry"by robert Lawlorかなり、興奮気味。
2006年01月31日
コメント(2)
-
お気をつけ下さい。
鉄道時刻表の冊子に、小さな注意書きが。「駅によっては、ホームが(電車より)短く、停車した際、ドアの前にホームがないことがあります。お気をつけ下さい。」さすがイギリス。(笑)
2006年01月30日
コメント(0)
-

読書会のこと
ブログ上、読書会のことを考えてます。テキストですが、シュタイナー教育入門編、ということで、「霊学の観点からの子どもの教育」はどうかな、と思っています。この2冊に違う翻訳で収録されています。基本的なシュタイナー教育の本ですが、内容はもちろん深い。具体例などを考えながら、さらに、内容を深くしていけたらいいな、と考え中。1週間に3~4ページかな。のんびり、じっくり、深く読み進んでいきたい。私の都合で、もっとスローになるかも。また、ご意見お待ちしてます。
2006年01月30日
コメント(10)
-
人智学を学ぶには
人智学を学ぶ方法はいろいろある。本を読む。ワークショップに参加する。読書会や勉強会に参加する。シュタイナー学校や、人智学共同体に関わる。など。多くの人は、本を読んで人智学を品定めしてみると思う。だって、読書会や勉強会は敷居が高い。マニアックな人がいそうな気もするし。本を読んで、もう少し人智学を知ってみたいと思ったら、ぜひぜひ、何らかのワークショップに参加することをお勧めしたい。何事も、学ぶためには、思考、意志、感情の全てに働きかけることが大切。本を読むだけだと、つい、思考に偏りがち。バランスがとれない。頭で分かったと思っても、実際に、感じ取っていなければ、本当の意味で分かったとは言えない。それに、感情、思考での理解に、意志の力が役に立つ。だから、3つの魂の力に、バランスよく働きかけることがとても大切。本を読んだだけでは、片手落ちになりがち。だから、ぜひぜひ、簡単なものでいいから、ワークショップに参加してみることをお勧めする。ぬらし絵や、手仕事、ユーリズミーなどの芸術体験のワークショップが、全国各地で開かれている。それの多くは、入門編的なものだと思う。興味がありそうなところから、飛び込んでみてほしい・・・。
2006年01月30日
コメント(2)
-
ブログ上 読書会
せっかくのブログを書いているのだから、何か役立てたいな。それで、ふと思いついたのが、ブログ上の読書会。勉強会、討論会、名前はどうでもいい。例えば、1つ、シュタイナーの本を決めて、私がその一部分(数ページ)に関する思いや私なりの解釈を書く。それに対して、読んでくれた人がコメントしあう。私 対 読者、じゃなくて、みんなが参加者になってコメントをしあう。それを週一回みたいなペースで進めて行く。というように、普通の読書会でやるような討論がブログ上でできたら面白いかな、と。もちろん、読書会、というもので学べることは限られている。だって、思考に働きかけるだけだもの。しかも、ブログ上、ということの制限もある。でも、ブログ上だから、私みたいに乳幼児2人かかえてる人も参加できるし、実際の読書会より気軽に参加できるというメリットもある。できれば、人智学を何十年も勉強してる人から、シュタイナー教育ビギナーです、っていう人まで一緒に、コメントしあえたら面白いだろうな。そんなブログ上読書会があったら参加したい、という人、いるかしら?反応があったら、本気で考えよっと。
2006年01月29日
コメント(6)
-
魂の暦
人智学を学ぶ人なら、誰もが知る「魂の暦」。シュタイナーが書いた詩。一週間ごとの魂の動きが描かれている。何ヶ国語にも翻訳されていて、日本語なら2つの翻訳(ですよね?)が出版されているし、英語なら翻訳の数は数知れず。オリジナルのドイツ語ができない私は、英語か日本語に頼るしかないけど、ドイツ人の夫に言わせると、やっぱり、「いい翻訳に出会ったことがない」という。詩なので、オリジナルならではのリズムがあり、韻も踏んであったりする。翻訳というと、意味だけとって訳してあったり、リズムは考えてあるけれど、意味がオリジナルに沿ってなかったり、と、どれも、少々難あり・・・のようだ。リズムそのものにも、シュタイナーの込める意味合いが表されているのだから、翻訳にもそれが反映されて欲しい所だけど、やはりそれが翻訳の難しいところ。日本語の2つの訳を見てみても、やはり、オリジナルから感じられる力強さがなかったり、ちょっと意味が違う、とか、いろいろ。ああ、ドイツ語できるといいな。・・・と、つくづく思う。シュタイナーのレクチャーは翻訳でもいいけど、やっぱり詩は、原文で読みたいな。
2006年01月29日
コメント(0)
-
blogお休みday
昨日は、一日ブログをお休みしてみた。ブログもいいけれど、実はコンピュータ、嫌い。昔、コンピュータ・ソフトウェア開発なんて仕事をしていたけれど、とことんコンピュータの世界に浸ったあと、コンピュータなしのアナログの暮らしの方がずっといい・・・と思う。と言っても、この不便なイギリスの町で、コンピュータなし、インターネットなし、っていうと、何にも出来なくなってしまうのが現状なので、「きっぱりやめた!」とは言えない。だから、せめて、コンピュータなしの日を作ろう、と。その分、ゆったりとして。せかせかした日常は、ちょっとお休みして。ディスプレイに広がる世界じゃなくて、目の前に現存する世界に目を向けて。なんてことを心がけた一日。ものすごく幸せな一日でした。
2006年01月29日
コメント(2)
-
メトリックとインペリアル法
アメリカでは、インペリアル法(マイル、フィート、インチ、ガロン、オンス、パイント・・・etc)を使う。10進法のメトリックは、一応学校で教えられているものの、ほとんど通用しない。イギリスでは、1970年に、公的には、インペリアル法からメトリックに変更された。とは言え、それはイギリス人のこと。未だに、道路標識はマイル表示だし、インチも使うし、体重にはストーンだ。しかも、アメリカとイギリスのインペリアル法、同じ単位の名前を使っているにも関わらず、そして起源が同じにも関わらず、微妙に違う。アメリカの1パイントは473mlイギリスの1パイントは568ml・・・など。イギリスではアメリカよりも、もう少しメトリックも普及している。そのお陰で、イギリス人は、メトリックとインペリアルの両方を使い、混乱している。例えば、ディスプレイの大きさをインチ表示するのに、「8.4インチ」なんてことを平気でパッケージに印刷する。インチは10進法じゃないから、8.4インチなんて小数では書かない。その辺のことが、子どもにも影響を及ぼす。メトリックだけをやっている日本の子ども達にとって、小数の計算など、問題はないのだけど、未だにインペリアルを最初に覚えるイギリスの子たちは、小数の計算に目を白黒させる。小数の計算ができるようになっても、やっぱり両方を混乱しながら使っている。高校生になっても、ものさしで長さを正確に読み取れない子がいる。(アメリカでは、ものさしを読めない高校教師に出会ったこともあるけど)イギリス人教師が言う。「仕方ないわ。まぎらわしいもの。」両方使って混乱して、まともに使えるようにならないくらいなら、どうして、片方だけに統一しないのかな。と言っても仕方ないので、この現状で、どうやって子ども達が、長さの概念を習得できるか、教師が頑張ってみるしかない。問題は、イギリス人教師も親も、そこに問題意識がないということ。(涙)
2006年01月27日
コメント(2)
-
サンマとシシャモ
先日、友達に日本食材店で冷凍のサンマとシシャモを買ってきてもらった。日本を出て以来、シシャモを食べるのは初めて。ということは、3年半ぶり。日本でだったら、絶対に買わないような、貧相な魚たちだったけど、久しぶりだったので、おいしくて、おいしくて。サンマは夫がお気に召さなかったようなので、残りは、独り占めさせていただきます。ふっふっふっ。
2006年01月27日
コメント(0)
-
センター試験
日本での高校教員時代からの習慣(?)で、センター試験のあとは、試験問題を見る。数学だけだけど。例年通り、一通り解いてみようかと思ったのだけど、見るからにつまらなそうな問題の羅列で、解くのをやめた。(単なる言い訳?)無機質な、味も素っ気もない問題。この問題を解く以上の能力や可能性を、見抜くどころか、つぶしかねない問題の数々。問題を見ながら、悲しくなる。この試験を解く為に、大事な時間と神経をすり減らして、「勉強」という仮の名の、単なるトレーニングに、エネルギーを費やしている、日本の高校生たちの疲れた姿が目に浮かぶ。忘れられない。私の教えていた進学校の、疲れた生徒たちの姿。こんなもののために、競争に巻き込まれて、疲れ果てて、「お休みがあったら、ただただ寝たい。休みたい。」と、ため息をついていた生徒たち。競争に疲れて自殺してしまった、私の生徒・・・・。日本の大学入試、いつまでこんなことやってるんだろう。どれだけ深く理解したかどうかを、この試験で計ることはできない。どれだけトレーニングを積んだかをテストするだけ。そんなことは、私が言うまでもなく、教育関係者も親も、何度も言っていることなのだけど、何年経っても、やはり、変わらない。多分、どう変えたらいいのか分からないのだろう。そして、教育関係者(大学教授、高校教師、親)も、深く理解するとか、本当に学ぶ、という意味を知らないのだろう。頭に働きかけることだけを「学び」だと信じているうちは、真の意味で深く学ぶことはできない。学ぶことの喜びも分からない。
2006年01月27日
コメント(2)
-
たちどまって考える
本を読むとき、新聞を読むとき、ブログを読むときだって、何か心に引っかかる言葉に出会う。そのとき、そのまま読み進まず、そこで立ち止まって、そのことについて考えてみる。それから、印をつけておいて、あとで、そこに戻って、読み直し、じっくりと考えてみる。特に、小説などのスイスイ読めちゃうような本のとき、たちどまって考えることを意識にとめておく。読みながら考えられることは限られているから。いい本には、宝物のような言葉がいっぱいある。それを読み流して忘れ去ってしまうのは、勿体無さ過ぎる。じっくり考えて、深く理解して、自分の考えを育てる。昔は読んだ後、必ず読書記録をつけていた。私が何を感じ、考えたかの記録。読書記録をつけることで、読んだことの意味が、何倍にも何十倍にもなる。読書記録、再開しようかな。
2006年01月26日
コメント(0)
-
first tooth
次男(7ヶ月)に、最初の歯、発見。嬉しいねぇ・・・。それにしても、眠い。今日は寝てくれるかな。
2006年01月26日
コメント(2)
-
シュタイナー教育は・・・理想に向けて
「シュタイナー教育は・・・」と言う時、私は理想的なシュタイナー教育のことを話す(書く)ようにしている。現実のシュタイナー学校は、人智学の理解が浅かったり、経済、人員などの問題を抱えていたり、「理想的シュタイナー教育」を実現できている学校は、世界約800校(?)のシュタイナー学校の中でも、わずかではないかと思う。でも、どの学校も理想に向けて歩んでいる。と思う。思いたい。そして、理想がなければ実現はできない。だから、いつも、理想に向けて。理想は持ちつづけて。シュタイナー学校の理想が現実になったら、もの凄くいい学校になる。でも、「理想的なシュタイナー学校ができあがった」と思ってしまうと、進歩はとまる。進歩が止まってしまうと、もう、それは、シュタイナー学校ではない。人智学をもとに、理想に限りなく近づいて、でも、更なる理想に、常に向かいつづける。そんなのが、本当の理想のシュタイナー学校。
2006年01月25日
コメント(0)
-
innocent
イギリスで売られている1リットルパック入りスムージー。名前は"innocent"パッケージが面白い。Looking after your smoothieKeep refrigeraterd 0-5℃ before and after opening. Once opened consume within 4 days or we'll come and get you. (中略)And shake before opening, not after.*****We promise that innocent smoothies will always taste good and do you good. We promise that we'll never use this stuff: NO concentrates NO preservatives NO stabilisers NO added sugar NO flavourings NO E numbers NO GM stuff NO funny businessAnd if we do you can tell our mums.So what's in the box?(リンゴの写真の下に)we pressed 10 of these (イチゴの写真の下に)we crushed 27 of these (バナナの写真の下に)we mashed 2+1/2 of these(オレンジの写真の下に) we squeezed some fresh juice form this(ニワトリの写真の下に)and we didn't add any of these久しぶりに笑わせてもらいました。
2006年01月25日
コメント(0)
-
友達とランチ
今日は、我が家で友達のユーリズミストとランチ。彼女は日本人女性ユーリズミスト。在英20年以上。たまに日本に帰ってワークショップなどをしている。基本的には、パフォーミング・アートとしてのユーリズミー。ユーリズミストとしての仕事の傍ら、翻訳の仕事や、日本語教師としての仕事もつとめる超多忙な女性。なので、徒歩3分の距離に住んでいるにも関わらず、なかなか会う暇もなく、おしゃべりできない。久しぶりのゆっくりとした時間で、話に花が咲く。ユーリズミーの話、共通の知り合いの話、学校の話、人智学の話、日本の話・・・・。シュタイナー・カレッジや日本のワークショップでお馴染みのユーリズミスト、ヘルガの話も。ユーリズミー素人の私が、ユーリズミストに向かって、ヘルガの素晴らしさを語ってしまった。きっと、彼女と我が校のユーリズミー教師とヘルガは、気が合うに違いない・・・と思うから。ヘルガをイギリスに呼びたい。と強く強く思う。
2006年01月25日
コメント(0)
-
天の瞳 の一節から
「天の瞳」灰谷健次郎著が読みたくて、私の日本の書庫から探し出して送ってもらった。灰谷文学は、いつも、自分の教育者としての姿勢を考えさせてくれる。以前は、教師としての私。今は、教師なおかつ母親としての私のあり方。昨日、これを読んでいて心に留まった文。このやり方がその子にとっていちばんいいんだと思ったときは、もうその時がその子を理解する終点になってしまっていると思う本当にそう。結論を自分の中で出してしまうと、その先、発展しない。これは子どもとの関係だけでなく、自分自身のあり方、成長の仕方にもつながる。シュタイナーのインナーワークや、ゲーテの自然観察などをしていて、「分かった」「これが答えだ」「結論がでた」と思うと、そこで思考が止まってしまう。それ以上、深く考えなくなってしまう。「分かった」と思った先に何があるのか。そこを追求すると、本当の意味が見えてくる。そして、その探求は延々と続く。子どもと接するのは、そんな永遠なる探求の繰り返し。自分を見つめるのもそう。そしてシュタイナー教育の授業もそう。「答えが出ておしまい。」「分かったね。良かったね。」じゃなくて、その先を考える起爆剤(!)みたいなのを、生徒の中に残す。それにしても、「答えが出ておしまい。」「解き方が分かっておしまい。」そんなのが学校教育である方がおかしい、と、私は思う。
2006年01月24日
コメント(4)
-
8年生メインレッスン
夫はメインレッスン真っ最中。音楽の先生とのコラボレーションで、音楽+詩+歴史の5週間メインレッスン。歴史は、「革命」。今までの2週間でフランス革命の授業が終わり、明日からイギリス産業革命に入る。産業革命に前後して、農業革命が起こったそうな。(はずかしながら初耳)ある説によると、農業革命によって、農業の作業が効率化し、仕事にあぶれた人の力が原動力になって産業革命が進んだ。別の説では、産業革命が起こりかけた時に、工場での人員が必要となり、農業人口が減る原因となった。それがもとで農業革命が促進された。実際の所、どっちがどっちだか分かってはいない。でも、多分どちらの要素も深く絡みついていて、両方が正しいのだろう。そんなことを、産業革命の導入とするんだそうだ。シュタイナー学校の歴史は深い。何がいつ起こったか、だけでなく、それがどうして起こったか、その時の人々がどういう意識だったのか、などということを、生徒達に感じさせる。生徒達に感じさせるために、教師自身が、歴史に心魂深く入り込む。無数のことが起こった歴史の中で、全てをリストアップして話すのではなくて、彼らの生徒の心に訴えることを、教師が感じ取って選ぶ。日本の歴史の先生から見れば、片手落ちの授業に見えるに違いない。教師にとって必要なのは、入念な準備だけではない。生徒たちの現状を、よく観察して、彼らに何が必要かを直観的に感じ取ることが不可欠。
2006年01月24日
コメント(0)
-
ミレ洗濯機
この週末、頼んだわけでもないのに、夫がいそいそと洗濯を始めた。先日購入したミレの洗濯機は夫の選択。一生モノの洗濯機ということで、奮発して買った、洗濯機のロールスロイス。いや、ドイツ製だからメルセデス?夫は嬉しくて仕方なくて、毎日のように洗濯機を眺めてはほくそえんでいる。確かにいい。静かでパワフル。プラスティックではなくスティール製で長持ち。お陰で100kgの重量だけど。(引越しのことは考えないでおこう。)それにしても、休日に夫が洗濯してくれるなんて。「毎日、洗濯させてあげるよ」と私。毎日と言わず、一回してくれただけでも嬉しいけどね。今は、ミレ掃除機を狙ってる夫。・・・・・家事するの、私なんだけど・・・・・。
2006年01月24日
コメント(2)
-
子どもの食事情
日本人の食生活は優れている。現代社会で、インスタント食材や、添加物の多用などの問題は大きいけれど、それでも日本人の食は、欧米のそれに比べれば格段にいい。アメリカのシュタイナー学校のあるクラスで、朝食について聞いてみた。「朝、家で調理したものを食べますか?」驚くことに、誰一人として、調理した温かい食事を食べた子どもはいなかった。朝食を食べないか、食べたとしても、シリアルに牛乳をかけるだけ。シリアルといっても、砂糖がたっぷり、人工の調味料がいっぱいのコーンフレーク。オートミールやムスリなら健康的なのだけど。小学校でも給食はないので、みんなおやつとランチを持参する。手作りのサンドイッチが入っていれば上等。大抵は、ランチ用の小さなパッケージに詰められた、既製のスナック菓子やパン。酷い場合には、袋入り「日清 出前一丁」日本製ではなくてアメリカ製のなので、普通に調理して食べても酷い味のシロモノ。しかも、教室なので調理はしない。さて、どう食べる?袋の中に、調味料を入れる。袋の口を手で抑えて、中の麺をボリボリと砕いて、シャカシャカと振る。それをそのまま食べるのだ。アメリカ人は忙しい。大抵共働きだし、片親の家庭も多い。物質的に豊かな生活を送るのが、最大関心事。でも、育ち盛りの子どものランチに、出前一丁一袋渡すって、一体・・・・!?欧米には、シュタイナー学校の父兄でも、そんな人は多いのだ。そんな子ども達の食生活を見ながら、学校で作られた、栄養のある温かな給食を実現させたいと、密かに、でも真剣に考えている。
2006年01月23日
コメント(8)
-
ユーリズミスト(オイリュトミスト)
シュタイナー教育にとって、ユーリズミーは欠かせない。でも、多分、メインストリームの人たちからみて、ユーリズミーは理解に苦しむものの代表選手に違いない。一言でユーリズミーといっても色々。教育の場で教師としてのユーリズミー。治癒ユーリズミー。舞台芸術としてのユーリズミー。セイクレッド・ユーリズミー。それに関わるユーリズミストも色々。人智学を体で感じさせてくれるユーリズミストもいれば、「これって体操の一種?」としか思えないユーリズミーをする人も。いいユーリズミストに出会ったとき、すぐに感じるのは、彼女(大抵女性なので)の空間に対する感覚の鋭さ。周りをとりまく空間。それは、目の前に広がる空間だけでない。彼女たちは、背中にも目がついているかのように、背後の空間に意識がある。もちろん、宇宙へ広がる巨大な空間の意識も。その鋭い意識のなかで、軽やかに動き回る。日常生活でさえ、彼女達は、周りに広がる巨大な空間とともに動いているかのよう。ああ、ユーリズミーがしたい。いいユーリズミストと一緒に。妊娠期間はユーリズミーができないので、2年続けて妊娠していた私は、2年以上のブランク。そろそろユーリズミーをする準備が私の中でできてきたかな、と思う今日この頃、友達のユーリズミストがレッスンを開く事を計画していると聞く。私のユーリズミー復活も近そうだ。
2006年01月23日
コメント(0)
-
お茶
昨日は、学校のユーリズミスト(オイリュトミスト)を招いてお茶。打ち合わせのついでに。人を招く時、何を出すかいつも悩む。私の周りには健康志向の人が多い。ベジタリアンかどうか、前もってチェックするのは必然。お茶に呼ぶときは、大抵、ケーキを焼くのだけれど、オーガニックの食材を使うのは勿論のこと、砂糖の量、たまごの有無・・・。昨日は、何も聞いていなかったので適当に推測。ユーリズミストだから、ちょっと健康的にキャロットケーキ?でも、ブラウニー食べたいな。彼女はアメリカ人。どう見ても、クッキーに紅茶っていうより、ブラウニーにひき立ての濃いコーヒーっていうイメージ。決めた。ブラウニーにコーヒーだ。彼女、ブラウニーを見たとたん、彼女の目がキラキラ。コーヒー豆をひき始めたのも耳敏く。大成功でした。私のご自慢ブラウニー、日本にいた頃だったら、甘すぎて食べられなかっただろうな。私も、アメリカ暮らしで、かなり甘さになれちゃった。と言っても、良質の甘さじゃないとダメだけど。
2006年01月23日
コメント(2)
-
大学入試に向けて
シュタイナー学校と言えども、やっぱり大学入試は無視できない。だって、大半が大学へ進学するのだから。お国が違えば、入試制度も違う。シュタイナー学校本家本元のドイツの入試制度も、今年から変わって、シュタイナー学校のカリキュラムも影響を受けている様子。アメリカは、SATがあるし、イギリスはGCSEとA-Levelというテストがある。シュタイナー学校でも、それに対応しなければいけないので、残念ながらカリキュラムも影響を受ける。と言っても、日本の入試とは比べものにならない。GCSEの数学上級レベルの問題を見たら、私立中学入試問題?・・・って感じだった。美術の実技を受験することもでき、自分の学校の慣れた環境で、2日間、ひたすら製作に取り組んだりする。外国語もあらゆる言語が受験可能で、シュタイナー学校の生徒達は、小学校1年生から独語、仏語を習っているから、外国語はお得意分野。どちらにしても、日本の入試のような緊迫感はない。日本の入試も、推薦枠や方法が広げられたりして、選抜方法も大分変わってきているようだけど、一般入試で試験を受けるなら、やはり受験「戦争」は免れない。日本のシュタイナー学校の生徒達は、それでも何らかの形で乗り越えていくのだろう。でも、もし生徒が、「私は、一般入試で理系を目指します!」なんて言ったら、先生は大変だろうな、と、密かに思ってしまう・・・・。決して、シュタイナー学校の生徒が、理系が苦手、と言うわけじゃない。それどころか、彼らは、よっぽど深く考えることができるし、深く理解していると思う。ただ、沢山の問題を速く正確に解かなければならない、センター試験みたいなテストは苦手・・・。
2006年01月22日
コメント(3)
-
競争社会で
ある人の問い。「シュタイナー教育で育った人は、この競争社会で生きていけますか」それに対する私の答え。「無意味な競争に巻き込まれないだけの強さを持った人になると思います」もちろん、意味のある競争なら立ち向かっていくだろう。たとえ無意味な競争に巻き込まれたとしても、それを乗り越えていく強さがあるだろう。競争に負けたとしても、それから立ち直る強さもあるだろう。もちろん、人それぞれだし、万人向けの100%の教育もないので、全員が全員そうだとは言えないけれど、やっぱり、シュタイナー教育で育った人は、内なる強さを秘めている、と思うのです。・・・・それにしても、人生の中で、意味のある競争って、そんなにないように思うのだけど。
2006年01月22日
コメント(2)
-
ブログ
ブログを書き始めて3ヶ月。毎日、いろいろ書いたもんです。(暇かしらね・・・?)いつのまにか、知らない間に、このブログのことを話してない知人も、このブログの存在を知っていたりする。そりゃ、「シュタイナー」で検索すれば確実に引っかかるものね。シュタイナー関係の友達がこのブログを読んでると聞くと、ちょっとドキッ。適当なことは書けないな。シュタイナーと関係ない友達がこのブログを読んでると聞くと、また、ちょっとドキッ。あんまり、霊とか魂とか前世とか、怪しいことは書けないかな。知らない人に読まれても平気なのに、知ってる人に読まれていると思うと妙に緊張したりする。(?)でも、やっぱり自分のまま、素直に書こう。いまさら、別に隠すことでもないし。私は私だし。あー、腰痛い。(??)
2006年01月21日
コメント(2)
-
レメディ+ハーブ
シュタイナーに出会ってから、ホメオパシーやフラワー・レメディにも出会った。ハーブはそれ以前から愛用していたけれど、日本を出て、西洋の国に来て、初めて、ハーブの利用の仕方を知った気がする。日本には日本ならではの伝統の智恵があるように、ハーブは西洋の伝統の智恵。西洋の地に息づいている。風邪を引いたときのエキナセアは欠かせない。日本でもエキナセア・ティーなどを飲んでいたけれど、こちらでは、それに加えてEchinacea Tinctureを使う。これはエキナセアのエッセンス。もの凄く苦いけど、風邪をひいたかなーーー、って感じたときに使うと効果抜群。カモマイル・ティーも、風邪には効果的。両手にいっぱいのカモマイルを少量のお湯で煎じて、ハチミツを入れて、苦くて顔をしかめるくらいの濃いものを飲む。この濃いカモマイルの煎じ液は、鼻づまりやのどの痛みにも効く。洗面器に入れて、そこに顔を近づけて、頭からバスタオルをかぶって、カモマイルの蒸気を吸い込む。それから、眠ってくれない赤ちゃんに。昼間、この濃いカモマイル・ティーを飲んでおくと、母乳を通して赤ちゃんに。赤ちゃんに安眠を。もちろん、日本でもおなじみの生姜やレモンなどの利用は、こちらでもお馴染み。ヨーロッパにいるから、ヨーロッパの智恵を学んで利用。その土地に育った智恵を使うのがとても自然で心地いい。と言っても、日本の智恵も素晴らしいし、日本人の体にはウメボシよね。とも思うので、西洋も東洋も両方おりまぜて、いいとこどりをしてしまう私。
2006年01月20日
コメント(2)
-
trainers
今日初めて知りました。イギリスでは、スニーカーのこと"trainers"って言うんだって。未だに慣れない、British English.....
2006年01月20日
コメント(0)
-

春の足音
昨晩、いつものように次男の泣き声で目を覚ましたら、外から小鳥の鳴き声がにぎやかに聞こえてくるのに気付いた。もう、朝か、と思ったのだけど、時計を見たら、まだ2:30am。小鳥が、もう活発になりはじめてる。庭には、秋に植えた球根が、たくさん芽吹いている。春が少しずつ近づいてる。イギリスでは、冬が長くて、春の予感がしてから、本当に春が来るまで延々と待つ。うう・・・。5月までの辛抱。写真は、カリフォルニアのアーモンドの花。2月にあちこちで咲きます。大きな木いっぱいに花がついて、後で葉っぱが出ます。まるでソメイヨシノにそっくり。花が満開の写真はボケちゃってて、載せられません。残念・・・。
2006年01月19日
コメント(2)
-
概念
ある人智学を勉強している人が言った。「結婚って言うのはね、概念なんだよ」「・・・ケッコンっていうのはガイネン????」当時、結婚してはいたものの、結婚にもパートナーにも確信のもてないままだった私は、彼の言った言葉を理解できなかった。それでも、その言葉は、クエスチョンマークと共に、心に引っかかって残った。昨日、ふと、「そうね、結婚って概念ね」と思った。ふと分かったのだ。「しかも、生きた概念ね。死んだ概念じゃダメね」シュタイナー教育では、「生きた概念」を子ども達に植え付ける。生きた概念というのは、子どもの成長とともに、子供の中で成長していくような概念。固まったままの概念を、「死んだ概念」とシュタイナーは呼んだ。三角形を見せて、三辺と三角がある多角形のことを三角形という、と、概念だけを教えると、それは死んだ概念になってしまう。でも、三角形を体で動いてみたり、三角形を自然の中で探してみたり、三角形を芸術的に見てみたり、無限遠の三角形も考えてみたり・・・そんなふうに、三角形を体の中に染み込ませてみると、三角形の概念は、子供の中で息づく。子どもが成長するにつれて、三角形の概念も成長していく。シュタイナー教育では、そんな生きた概念を子どもの中に植え付ける。まるで、種を彼らの中に植えるように。「結婚は概念なんだよ」そう。結婚という概念。変化しつづける私達のなかで、結婚の概念も変化しつづける。結婚について死んだ概念しかもてなかったら、結婚生活は苦しいだろうな。
2006年01月19日
コメント(0)
-
自信 ・・・シュタイナー学校では
昨日、自信のことを書いた。私が自信がない子どもだったのに対して、シュタイナー学校の子ども達は、実に自信にあふれている。謙虚さがないとか、傲慢だとか、高飛車だ、という意味ではない。自分の悪い所は自覚しつつも、自分を肯定的にとらえる。悪い所を自覚しているから、前向きに努力する。自分を肯定的に捉えているから、卑屈にならない。それもそのはずだ、と思う。シュタイナー教育は人智学が基本にある教育で、生徒のありのままの姿を肯定的に受け止めているから。計算が苦手な生徒がいたとしても、その子そのものの人間価値が下がるわけじゃない。先生は、計算が苦手だという事実を受け止めて、計算ができるようになるように指導するけれど、子どもを否定的に判断することはない。親や教師に、自分という存在を、受け止めてもらえたら、自分に自信がつくのも当然。計算がちょっとくらいできなくたって、彼らの、人としての自信を失う理由にはならない。人ひとりひとり、誰でも、美しい存在。人間の美しさを、彼らは、感じている、と思う。彼らも、その美しい人間のひとり。彼らは、自分が価値のある存在だと知っている。そして、彼らの周りを取り巻く人たちも、価値のある、貴重な、かけがえのない存在だと知っている。
2006年01月19日
コメント(6)
-
テレビのこと
我が家にはテレビはない。シュタイナー教育だから、って言うわけではなく、昔からテレビは好きじゃなかった。テレビを家から排除したら、静かで、有意義に使える時間が増えて、とても気持ちがいい。テレビというモノの存在がないだけで、空気が綺麗になった気がする。そんな風に、テレビなし生活を謳歌している。もう、テレビのある生活には戻りたくない。シュタイナー教育したいけど、テレビは不可欠って言う人も多いと思う。テレビが大好きで生活の一部って言う人も多いだろう。そんな人に、「テレビはダメよ」って言うつもりは全くない。テレビなしで暮らす事が、ストレスになるくらいなら、テレビを見て幸せにしていた方がいい。(大人の場合!)でも、子どもは別。子どもがテレビから受けている悪影響を、学校でまざまざと見ながら、子どもにはやっぱり見せないでいて欲しいな、と思う。テレビは、成長過程の子どもには害が大きい。特に小さい子には、見せないで欲しいな・・・・。
2006年01月18日
コメント(2)
-
自信
昔から自分に自信がなかった。自信をつけたくて、いろいろ頑張ってみた。例えば、勉強。勉強して成績を上げれば自信がつくかと思った。成績は上がったし、志望校合格も果たした。でも、成績上がっても自信はつかなかった。だって、自分より上を見たらきりがない。いつまでたったって、自分が一番にはなれない。上がれば上がるだけ、更に自分より上がいることを思い知る。大学に入った頃、誰かの本で、「人と比べている限り自信はつかない」と書かれているのを読んで、納得。でも、人と比べて、社会の価値観で自分を評価しながら育ってしまった私には、人と自分を比べる癖は、そう簡単には直らない。人智学を勉強しながら、自分が完璧ではないということ、人間は完璧にはなれないこと、完璧ではないからこそ素晴らしいということを受け入れられるようになった。そして、今、堂々としていよう、と思えるようになった。自分が過去におかした間違いも失敗も、自分の弱点や欠点も、私自身が受け入れて、私自身が私を受け止めて、正々堂々としていよう。開き直り、じゃなくって。最近、やっと、堂々としていられるような気がしてきた。
2006年01月18日
コメント(4)
-
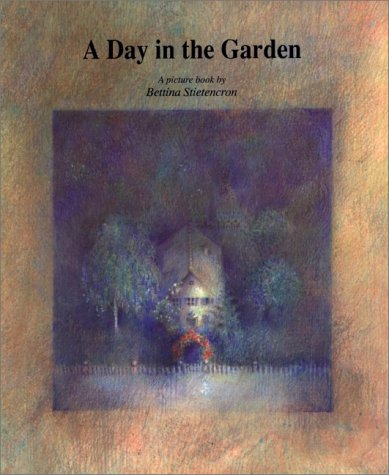
ベティーナの本
先日ドイツのアマゾンから買ったベティーナの絵本。母の私が夢中になって虜になってます。どうも日本語訳は出版されてないみたい。ドイツ語は分からないけれど、文は、とても綺麗に韻が踏んであって、リズムも美しい。これを翻訳するのは難しいだろうな。でも、絵を見ているだけで、ほれぼれ。ベティーナの本で、英語訳がないか探してみました。1冊だけ発見。人智学系出版社のFloris booksから出版されています。(やっぱりね)"A day in the garden"by Bettina Stietencron (picture)
2006年01月17日
コメント(0)
-
ポッポッポッ
鳩が鳴くのが聞こえる。リビングルームにいると、暖炉からポッポッポッと聞こえる。暖炉の煙突にとまって鳴いてる鳩さん。うちは、暖炉使ってないからいいけどね。
2006年01月17日
コメント(0)
-
進化のジャンプッ!
Dr.シュタイナーによると、進化というのは、徐々に起こるものではなくて、ある日突然に、起こるもの。人間の成長でもそう。今まで歩けなかった赤ちゃんが突然歩けるようになった。もちろん、歩けない段階で、見えないところで、毎日進歩し続けているのだけど、歩ける前と歩けるようになった後では、全く違う。大きな進歩が突然起きたのだ。人間の進化もそう。シュタイナーの言う、地球の進化もそう。土星紀から徐々に太陽紀に変化していったのではなく、土星紀から、お休みの期間に入り、ある日突然、太陽紀ができあがった。(「日」という概念はなかった思うけど)英語などを勉強していてもそう。勉強を続けていると、ある日突然進歩が感じられるときがある。進歩というものは、そんな小さなジャンプの繰り返し。毎日、子どもの小さなジャンプを見るのが楽しい。私自身も、自分の中に小さなジャンプを感じる。毎日続けている、シュタイナーのエクササイズやインナーワークのお陰かな。
2006年01月17日
コメント(0)
-
私の住む町
私の住む町は、バーミンガム郊外の町。とりたてて文化のない、味気のない町。こんな町に、人智学の施設があれこれ。シュタイナー学校(幼稚園から高校まで)キャンプヒル(障害者と健常者が一緒に暮らす施設)バイオダイナミック農場(シュタイナーの農業を実践する農場)ユーリズミー・スクール(ユーリズミスト養成の2年間の学校)グラスハウス・カレッジグラスハウス・カレッジというのは、もともとイギリスはストラトフォードで始まった、ラスカン・ミルの第2号。これは、犯罪を犯してしまったような問題をかかえる青少年の、人智学的な芸術を通して健全な精神を育てていく施設。ペインティング、ドロウイング、ユーリズミー、スピーチエクササイズ、ドラマ、クラフトなどの芸術活動をしている。人智学的教育は、そのものが治癒的。だから、いわゆる健全な子どもたちだけでなく、スペシャルニーズの子ども達や、身障者、心の病を抱えるひとたちなど、さまざまなひとに、癒しをもたらす。思考にばかりはたらきかけて、バランスを崩してしまった現代の社会。思考過多で病んでいる現代人。これ以上、思考に働きかけても癒しにはならない。バランスが更にくずれるばかり。シュタイナー教育のように、芸術を通して、手足をつかい(意志)、芸術を感じ(感情)ることが、癒しになる。
2006年01月16日
コメント(10)
-
4気質
シュタイナー教育に興味を持った人が、始めにであうものの1つが4気質だと思う。コラリック(胆汁質)サンギン(多血質)フラグマティック(粘液質)メランコリック(憂鬱質)という4つの気質。(私の中では英語の方がしっくりくるので、英語読みでごめんなさい)性格占いみたいな感覚で、気質のことを考える。でも、何の為に気質を学ぶか。それは、人と人との人間関係に役立てたり、子どもを理解するための手段になったり、それぞれの気質に合わせた教育をしたり、と、気質を知ることで、その気質の知識を実際に役立てる為にある。決して、「あの人はメランコリックね」などと、レッテルをはるためにあるのではない。シュタイナー教育の本を読んでいると、気質について説明してある本は数多くあるのだけど、気質についての知識を、実際にどうやって利用していくか、ということがかかれている本は少ないように思う。気質に合わせたケーススタディをする、なんて本があったら、面白いし、役に立つだろうな、と思うのだけど。ということで、いろいろな場面で、気質に合わせたケーススタディを頭の中で繰り広げる。この場合、コラリックの子どもだったら、どうやって対応するのがいいのだろう?サンギンだったら?フラグマだったら?サンギン+コラリックだったら?・・・などと考えて。今、考え中なのは、サンギンの子ども達に、作業に長時間集中させるにはどうしたらよいか・・・ということ。復帰早々に教えるクラスは、めちゃくちゃサンギンな子どもたちの集団なのです。
2006年01月15日
コメント(2)
-
今年はおしゃれに
今年はお洒落したい。だって、2年続けての妊娠出産、その後の授乳期間含めて3年間、着るものにも限界があって好きな服が着れなかった。今年は仕事にも復帰するし、卒乳まであと数ヶ月だし。さあ、お洒落するぞ。流行を追いかけるつもりはないけれど、やっぱり、こぎれいな格好して、私なりのセンスのファッションを楽しみたい。私も気分がいいし、夫も喜ぶし。ということで、洋裁と編物に勤しむ私。あ、ダイエットも・・・?
2006年01月15日
コメント(2)
-
気質と手作り
私は手仕事をよくする。というと、「あなたはフラグマティック(粘液質)ね」とレッテルを貼られてしまう。ところが、私は、4気質の中では、フラグマの傾向が一番少ない。難しいこととか、新しいことなど、何か挑戦することがあるときは、手仕事をするのが好きだ。もの凄い集中力で熱中する。でも、繰り返しの単調な仕事をするときは、嫌で嫌で仕方なく、「仕上げること」だけを目的にやる。フラグマの人たちは、単調な仕事を、のんびりのんびり楽しむ。私にはそれが苦痛で仕方がない。全くフラグマとは正反対なのだ。私は、7歳のときから編物を始めた。10歳の時には、セーターとか編んでた。難しい模様に挑戦するのが楽しかった。でも、ある程度できるようになってしまったら、編物がつまらなくなった。しかも、私は、シンプルなデザインが好き。難しいデザインに挑戦したっていいけど、ごちゃごちゃしたデザインは、私の趣味にあわない。着たくないもの編んでも仕方がないから、シンプルなデザインをイヤイヤ編む。そんなかんなで、今日仕上げたセーターは、イヤイヤ編んだ末、3ヶ月もかかってしまった。昔、難しいのに挑戦してた頃は、3日で仕上げたりしてたのに。編み終えた早々に、次のセーターを編み始めた。今度は、シームレスで立体的にデザインしようと思っている。普通は、前身ごろ、後ろ見頃、右袖、左袖、と編んで、縫い合わせるのだけど、今回は、全部一体になるように編んで、縫い合わせがないように、デザインしてみよう、という試み。こんな、ちょっとした挑戦があるので、少し楽しみでやる気になっている。そう、実は私、隠れコラリック(胆汁質)なんです。
2006年01月15日
コメント(2)
-
ドイツと日本
私の夫はドイツ人、私は日本人。ドイツと日本って似ている、と思うことが多い。気質もそうだけど、歴史的にも。第二次大戦のことは言うまでもない。日本の教育制度は、ドイツからの輸入。オリジナルのドイツの教育制度は、もう、すっかり新しいものになってしまった今も、日本では、相変わらず、ドイツからの教育制度を維持。それから、食べ物。日本の、「洋食屋さんの洋食」って、ドイツ料理がおおもと。コロッケ、ハヤシライス、ロールキャベツ。ドイツから輸入して日本風にアレンジしたもの。ドイツ人の夫は、日本食も大好き。でも、もちろん西洋料理は欠かせない。夫に喜んでもらおうと、コロッケやロールキャベツを作ると、逆に嫌がられる。日本式にアレンジしてあるからダメみたい。
2006年01月14日
コメント(2)
-
重ね煮
どらごんふるーつさんのところで話題になっていた重ね煮をした。船越さんのサイトも参考にして。下から、干ししいたけ+戻し汁、わかめ、ケール、じゃがいも、たまねぎの順で重ねて、最後にsea saltをふって、弱火でことことと煮る。ケール(青汁の原料)がどうなるか、興味津々だった。だって、ケールって、30分くらい煮込んでも、まだ固い。特に、うちのケールは、バイオダイナミック育ちでたくましい。たくましすぎるくらいで、ちょっと手ごわい。どう調理しても、不味くて、夫も私も苦手だった。ところが、重ね煮にしたら、美味しかった。アクがうまくとれて、やわらかくなって。そのままでもおいしかったけど、豚の生姜焼きも作ったので、しょうが+しょうゆで少し味付け。夫が気に入ってしまって、私の皿から盗んで食べていた。これで、ケールが美味しく食べられる。green doctorといわれているケールを食べて健康に。もちろん、他のお野菜もとっても美味しかったです。
2006年01月14日
コメント(2)
-
ノイズレス・ライフ
騒音のない暮らしをしたい。我が家では、もちろん、TVはない。ラジオはあるけど聞かない。たまに音楽は聴くけど、子どもが寝静まったあと。それだけでも、かなり、家の中は静かだと思う。でも、それでも家の中にはウルサイものがある。掃除機、洗濯機はその代表格。冷蔵庫だって、かすかな唸りをあげる。大人にとって耳障りな音。全身が感覚器官の子どもにとってみれば、もの凄い騒音だろう。できるだけ、そんな騒音のない暮らしをしたい。そんな騒音のない環境を子どもたちに与えたい。それに、掃除機、洗濯機のように、機械が全てをやってしまうのではなくて、実際にほうきや雑巾、モップなどを使って掃除するところを習慣的に子どもに見せたい。でも、家のほとんどがカーペット敷きの我が家。掃除機なしでは、衛生上まずい。洗濯機なしの生活も、ちょっと考えられない。ということで、掃除機をかけるときは、子ども達を他の静かな部屋に追いやる。だから、掃除機かけるのは、けっこう大仕事。これって、掃除機を毎日かけないことの言い訳・・・?
2006年01月13日
コメント(2)
-
母のナヤミ
育児に関して、不思議なほど迷いがない。ま、もともと、あれこれ思い悩むタイプではないのだけど。でも、ひとつ、育児のことで、迷っていることがある。それは、テーブルマナー。イギリスというテーブルマナーにうるさい国で、ドイツ人の夫と、日本人の私、という環境に育つ子ども達。私は、お碗に口をつけてお味噌汁を飲みたい。でも、西洋式では、食器に口をつけるなんて、とんでもない無作法だ。でも、お碗から直接お味噌汁を飲んでいる私を見て、息子は真似をする。お碗だけならいいのだけど、スープ・ボウルやお皿でも、両手で持ち上げて口をつけたがる。飲んだまねしたあと、「ぷはーっ」という。(私はそんなことしてないぞーー)子どもの教育のため、一切、西洋式でいくか、西洋も日本もごっちゃのマナーでいくか。「お家では日本式ね。でも、外では西洋式ね。」というのは、通用しない。まだ1歳9ヶ月では。
2006年01月13日
コメント(2)
-
離婚のこと
私は、バツイチだ。今の夫は二人目。そう、友達(イギリスで知り合った日本人)に話したら、「ぜいたくねーー。2回も結婚するなんて。いいわねーー。」って言われた。予想外。大抵、日本人に離婚したことを言うと、まるで私が不幸のかたまりみたいな反応が返ってくる。でも、実際は、円満離婚で、二人がそれぞれの夢を追求するために離婚を決意。結婚生活も、「友達みたいなカップル」で、仲はとっても良かった。ただ、「友達」以上にはなれなかった。今は、二人とも、好きなことを追求して、「離婚してよかった」と、双方が思っている。「いいわねーー」こんな風に明るく言ってもらえると楽なのだけど。だって、離婚した本人は、とってもhappyなのだから。西洋のように、簡単に離婚してしまう文化を、いいとは言わない。でも、結婚も離婚もそれぞれの形があり、離婚する方がいい結果をもたらす場合もある。離婚することが、失敗だとか不幸だとか、他者が決め付けられるものではない。・・・ということが、日本でも一般に通用するといいな。
2006年01月13日
コメント(2)
-
人生のパートナー
私にとって夫はとても大切な人。一番、大切な人。子どもが生まれたら、こんな素晴らしい、愛する子どもたちの父親として、それまで以上に、大切な存在になった。子どもたちには、子どもたちの生き方があり、私とは別々の生涯を歩んでいく。でも、夫は、私と共に、一緒に生きていく人。子どもは、愛してやまない存在だけれど、夫にとってかわることはない。それでも、やはり、「諸行無常」永遠なるものなど、何もない。いつかは、私達にも別れがくる。それが死別でも生別でも。それを受け入れなければならないときが、いつかくる。それを受け入れなければならないときに、受け入れられるだけの強さを、もっていたい、と思う。
2006年01月12日
コメント(2)
-
進化+成長
「人間は進化するためにこの世に生まれてくる」Dr.シュタイナーは言った。進化とまで言わなくても、せっかく人間として生きているのだから、せめて少しでも成長したい、と思う。人智学を知らない頃、自分の短所を見て、嫌になった。直したいと思った。人間として成長するために、短所の克服が必要だと思った。でも、どうしたら、直せるか分からない。成長って、難しい。学問を勉強したり、習い事をする方がよほど簡単。「どうしたら、人間として成長できるの?」その答えをくれたのは、人智学だった。人智学を学び、エクササイズを積むことで、人間として成長できることを感じた。私は、人間として、まだまだ。成長の過程。でも、少しずつでも成長している、と思う。そして、少なくとも、どうしたら成長できるか、その方法を知っている。私は、人智学に出会った。私と同じように、人智学に出会う人もいれば、出会わない人もいる。出会っても、見過ごしてしまう人もいる。多分、人智学に出会う準備ができていないか、その人には必要がないか。私には、人智学が必要だった。他の人には、人智学ではなく、他の思想や宗教が必要なのかもれない。それは、ひとそれぞれ。それでもやっぱり、「人間は進化するためにこの世に生まれてきた」と思う。どんな人も。
2006年01月12日
コメント(2)
-
記憶力
シュタイナーの言った記憶力をつけるエクササイズ。例えば、昨日会った人について、できるだけ細部まで思い出し、イメージする。思い出せない部分は、想像で補う。どんな服、顔、髪、持ち物、まわりの風景まで。記憶力は観察力のたまもの。だから、このエクササイズを続けていくことによって、観察力が増し、記憶力がよくなる。これで、ふと思うのは、私達の周りに氾濫している記憶媒体。コンピュータ、デジカメはもちろん、アナログのテープレコーダーや手帳も。使い出すと、記録することに頼ってしまい記憶力がうすれる。デジカメも、私の生活には欠かせないけれど、子どもの写真や、記念の写真は最小限しか撮らない。ファインダーを覗いているより、実際に子どもを見ている時間を大切にしたい。それに、写真を撮って、その写真を見ると、実際に私の脳裏に焼き付いている記憶よりも、写真の像の記憶の方が強くなってしまう。何年かたったとき、その事実を思い出そうとすると、思い浮かぶのは、私の眼を通して見た像ではなくて、写真のイメージだけだったりする。それは、悲しい。子どもをじっと自分の目で見て観察して、イメージを焼き付けておきたい。写真の正確な記録よりも、頭と心に残る記憶を大切にしたい。
2006年01月11日
コメント(0)
-
洗濯機購入
新しい洗濯機を買いました。イギリスに引っ越してきたときに買ったのは、中古のHoover。最初からうまく動かなくて、2回も修理してもらったのだけど、やっぱりちゃんと動かなくて、しかも、服はすぐに傷んでしまうし。我慢して、だましだまし使ってました。それをやっと、買い換え決意。今度は、ドイツのミレ。電化製品のロールスロイス、って言う位で、お値段は、他社と比較になりません。でも、とにかく質が良くて、頑丈。何十年も使うことを想定して製造されています。だから、お値段2倍でも、最低3倍は長く使える、ということで、決意しました。だって、何度も買い換えれば、地球のゴミも増えるし。それにしても、どうしてHooverって、こんなに売れているんでしょう?特に掃除機なんて、「掃除機をかける」の意味で、hooverが動詞として使われているくらい。うちの掃除機もhooverで、名前は"silent power"だけど、実際は、"noisy powerless"って感じです・・・。
2006年01月11日
コメント(2)
-
気持ちを伝える
私がいつも心に留めていること。それは、私の気持ちを伝える、ということ。例えば、予定の時間を3時間過ぎて帰ってきた夫に、「遅かったじゃない」「遅れるんだった電話くらいしてよ」「ごはん作っておいたのに、冷めちゃったじゃない」などとは言わない。こんなことを言うと、大抵、反感のこもった反応が返ってくる。でも、「帰ってきてくれて良かったー」「何かあったんじゃないかと思って心配しちゃった」「電話もないから、どうしたのか心配で」「温かい作りたての食事を食べてもらいたくて用意したんだけど、予定の時間に帰ってこなかったから冷めちゃって悲しいな」などと、自分の気持ちを伝えると、相手は、「心配させちゃったんだな」と分かるので、素直に、自発的に、「ごめんね。今度から電話するよ」などと言う。特に日本人は、自分の気持ちを伝えるのが下手。でも、もっと伝えるべきだと思うのです。相手を思う気持ちや、心配する気持ちなど、「分かってるでしょ」って思わずに、伝える。これは、トーマス・ゴードン博士「親業」の「I(私)メッセージを伝える」というテクニック。学ぶところがおおいテクニックです。
2006年01月10日
コメント(8)
-
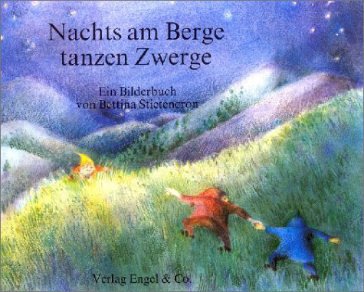
ドイツからの絵本
夫がドイツのアマゾンからオーダーした本。正統派人智学的な絵本です。とってもきれい。ほれぼれしています。ドイツ語分からないので、あとで英訳してもらうつもり。日本語には訳されているのかしら?ks_2001さん、ご存知?
2006年01月09日
コメント(4)
全65件 (65件中 1-50件目)
-
-

- ●購入物品お披露目~~●
- 【ダイソー】即買い!木製鏡餅のほっ…
- (2025-11-23 15:55:05)
-
-
-

- 楽天アフィリエイト
- 【楽天ROOM 始めやすいジャンルのご…
- (2025-06-15 15:14:58)
-
-
-

- 軽度発達障害と向き合おう!
- 【書評】『小児・成人・高齢者の発達…
- (2025-11-17 06:15:32)
-








