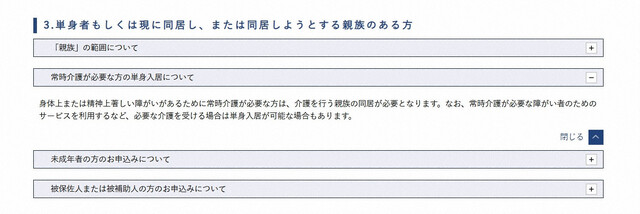2020年07月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
自分自身との対話六十七
聖書の旧約聖書の部分は、一応は、一通り読了した。けれども、内容理解に関しては殆どが 上の空 の状態にしか過ぎない。然るべき解説者がマンツーマンで付いてくれて、適切な解説を施してくれない限りは、十全な理解などは覚束無い。 これでも、若い頃からキリスト教信者ではないけれども、素人にも大まかな聖書理解が可能なような解説書やら、その他折に触れて、断片的ながら、旧約、新訳の別を問わずに、聖書には様々に接してきており、全くの初見ではなかったのだから、宗教書というものは専門家でもない限りは、十分に行き届いた理解というものは、なかなか難しいものなのであろう。 理解が難しいのは、何も宗教ばかりではない。一人の人間を正しく理解することだって、それに劣らないくらいに難しいことだ。しかし、誰に対してもその難しい作業をしようなどとは、誰も考えたりはしない。その場限りの人間関係では、その必要性も皆無だから。 しかし、自分の生涯の連れ合いともなると、そんな暢気な事は言っていられない。謂わば必死にならざるを得ないから。必死だろうが、そうでなかろうが、理解などという元から難解な作業は、その性質を変えてなどはくれないのだ。 所で、またもや私の「十八番」とも言える 悦子談義 の続きを、飽きもせずにまたぞろ書こうというのは、私の知識や関心が極端に狭隘だからという理由だけではなく、この世に生を受けて、最も強烈な影響を受けた、そのたった一つの理由による。 だから、私は自分にとって一番書きたいことだけを書くのみ。 今、悦子の幸せそうな顔がありありと脳裏に浮かぶ。「お父さん、素敵!」と満面に笑みを浮かべた悦子がテーブルを挟んで、ソファーの上に座っている。私はカラオケのマイクを片手に、五木ひろしの「細雪」か何かをいい気分で唸っている。多分、悦子の隣には彼女の親友・長谷礼子さんが、静かな佇まいで拍手かなんかを私に送っている ―― こういう実に平和で、庶民的で、無邪気な時間が、何度も、何度も繰り返し展開した。これだけでも、私の人生は比類もなく、素晴らしいものであったことが、分かっていただけるのではないだろうか。自分でも、そう思うし、何て幸福な生をエンジョイしたのだろうかと、しみじみ感じる。 しかし、私の十代は概して暗かった。暗かったばかりではなく、かなり深刻に厭世的であった。この世の苦しみを自分一人が全部背負い込んでいるような気分だった。何故そんなにまで暗く落ち込んでいたのかは、自分の事ながら皆目見当がつかない、今になってみれば…。 だから、自分に恋人、そう、恋人と呼ばないまでも、自分を愛してくれる異性が出現するなどとは、とても想像出来なかったし、ラブストーリーなどというものは、みんな他人事と考えていた。 それで、齧り始めていた覚束無いドイツ語で以て、ゲーテの「若きウエルテルの悩み」の原書に敢えて挑戦してみたり、随分と無茶苦茶なチャレンジも厭わなかった。天才で物質的にも非常に恵まれたゲーテに突拍子もなく憧れて、七十歳を過ぎた彼が十六歳の乙女と恋をした事実を知った時、思わず知らずゆだれが出るほどに羨ましく感じたことを、昨日の事の如くに明瞭に覚えている。 そんな私が、である。三十歳を目前にして、見目麗しい乙女から「愛の告白」を受けようなどとは、神ならぬ身の知ろう筈もなかったのだ。 人生とは不思議、且つ、皮肉なもので、強く願っていることは容易に実現しないで、夢にも思い描かなかった理想が、突如夢想だにしなかった形で瓢箪から駒の如き形で、実現したりする。 で、提案ですが、この世に絶望している人がこのブログを読んでいて下さったなら、もしくは、それに近い状態だと自らを自己診断される人が仮にいたとするならば、その人こそが、恵まれた輝かしい近未来を目前にしている。そう、考えて頂きたい。神は、仏は、その様な自分を過小評価している御人をこそ、第一の救済ターゲットとなさっておられるのですから。 親鸞上人の悪人正機の説をここで持ち出すまでもなく、救済の最大の目標は、実は最も謙虚なる者、自己を微弱で最悪と自己判定する人の、最悪の瞬間を待って、おもむろに救済の手が下される。いや、いや、その最も卑しむべきとの自己認識をこそ、最も尊いと尊重なさるのが真の 絶対者 たる存在の、必要が要請される刻(とき)なので、神仏はその紛れもない自己認識に照応して、慈悲心の発揚を開始するのだ。 これは、私の言葉だが、尚且つ私の言葉ではない。この事は、ある意味で自明すぎるくらいに明らかなので、これ以上の言葉を必要としない。 信じようが、信じまいが、それとは無関係に、絶対の真実は存在している。その理(ことわり)を知れば良い。 自力か、それとも他力かとの疑問がしばしば問題になる事があるけれども、二者択一でなくてはならない必然性はないわけで、自力であり、同時に他力であって、何も不都合はない。 けれど、啐啄同時という表現で表されている如くに、タイミングが非常に重要であろう。ヒナ鳥が卵から孵る際に、卵の内側から雛が殻を嘴でつつくのと、母鳥が外から啄くのとが同時でないと、上手くいかないと言う。それと同様のことが、画期的な事態の変化については言えるのである。 これは今までに、悦子にしか話したことのない、正真正銘の私の 内緒事 なのですが、内緒事と言っても別段他人に聞かれるのが憚られる様な内容ではなく、人として余り他人に大声で話さないほうが礼儀に叶っていると考えるので、それともう一つ、これに携わった相手の人が居られる訳で、そのプライバシーを大切と考えるので、誰にも話さずにいた事柄だった。 しかし、それも謂わば一種の「時効」が成立している程に時間が経過してしまった今では、実害はないだろうと判断したので、秘密の箱を開ける気になったのである。 なんだかもったいぶった、気を持たせる言い方が続いているので、単刀直入に申し上げましょう。 私は悦子と結婚する前に、少なくとも、三度、結婚していて不思議はない相手と、不可思議な擦れ違いを経験している。大真面目で、真剣にその女性と結婚するつもりでいたし、相手も私に負けず劣らずに、私との結婚を望んでいた。客観的な状況も、個人的な気持ちの在り方から言っても、それは間違いのない事実だったと思う。 しかし、何か目には見えない不可思議な力が働いて、私と相手の女性は結びつかなかった。これを運命と呼んでしまえば、それまでのことで、何も不思議などは存在しない。 ただ、悦子と電撃的な、奇妙な邂逅を経て、幸せな結婚生活へと導かれた時に、ああ、そうか、あの不思議な力は、このためにあの瞬間瞬間に私と相手の方に働きかけ、然るべき方向へと導いたのだ、とストンと納得がいったのだから、これも不思議と言えば不思議な現象ではないだろうか。 それもこれも、私が悪いと言えば、悪いのだ。何故ならば、悦子は永劫の時間の間、ひたすら私との再会をのみ念じて余念がなかったのに、私の方はと言えば気の遠くなるような永劫の時間経過があったとは言え、悦子の記憶を忘却の彼方に置き忘れてしまって、すっかり失念してしまっていたのであるから。どう考えても私が悪いに違いないのでした。 自慢ではないが、私は正真正銘の 凡人 であり、普通の盆暗(ぼんくら)なので、永劫という時間の経過に耐え切れずに、忘却という自然の流れに容易く乗ってしまった。そして、安閑として惰眠を貪ってしまった。その為体(ていたらく)が悦子に掛けなくともよい気苦労を掛ける結果と、なってしまった。悦子には実に済まない気持ちで今は一杯なのだが、次の邂逅の折にも、再び、三度、同じ過ちを犯すであろうことは自明なのであります。実に不甲斐のない自分だと反省頻りなのだが、こればかりは直すことが不可能であろうから、次の機会には精々私のなけなしの愛情を、あるったけ振り絞って、悦子の有難い愛情に応えたいと、衷心から念じてはいるのであります。 バカは死ななきゃ治らないとか。私のバカは程度が度を越しているので……。いや、いや、よそう、よそう、こんな私でも悦子は全身全霊を込めて、私を全面的に受け入れて呉れるのに間違いないので、私は自然体で彼女の愛情を素直に受け入れる事に、専念したいと思う。悦子さん、どうぞ、宜しくお願い致します。悦子の優しい笑顔が私の目の前でにっこりと笑って、無条件の許容を示してくれている。有難いことであります。有難い事であります、本当に。
2020年07月23日
コメント(0)
-
自分自身との対話・その六十六
前回、「太郎と花子の物語」の習作をデッサンしてみました。 非常に難解なテーマでしたが、かなり大勢の人たちからの興味と関心を喚起することになったようです。 成功すれば、相当にユニークで画期的な作品が実現するだろうと思われ、創作意欲を刺激されますが、現在の私には、何というか、気力に欠ける所があって、少なくとも当面は仕事に取り掛かることが、出来ません。 その時期が来たならば、駄作に終わろうが、自分の持てる全精力を傾注して挑戦するつもりでおりますが、そういう事情ですので、しばらくは御容赦ねがいます。 で、今回は、えつこ曼荼羅つれづれ草の追加を、思いつくままに草することに致します。 懐かしい悦子の思い出に関しては、既に何回もブログに書いています。重複する所も出てくるに相違ないのですが、兎に角、書いてみる事にします。 悦子の父・慶吉氏は遠洋漁業と言うか、捕鯨船に出稼ぎという形ででしたが、長年船に乗っていました。そのせいか、囲碁がとても上手でした。ヘボの横好きの私など、赤子の手をひねるようで、勝負にもならない格段の実力差でしたね。 この舅の御人柄というのか、地味ではありますが、日本男児らしい持ち味が、私は、ある意味では娘の悦子以上に好きでした。慶吉氏の如き男性のタイプは、人生で始めて出会う、そういう意味では非常に稀有なキャラクターだった。 都会で育ち、軽佻浮薄を絵に描いたような人物にばかり取り囲まれて育って来た私には、新鮮で、とても魅力のある御人でしたよ。悦子は先ず、父親の良いところを全部引き継いでいると思います。 父親だけを取り上げたのでは片手落ちになるますので、姑のとみよ刀自についても触れてみましょう。 義理の母も、良い意味の田舎育ちを持ち味とする、ユニークなお人でした。巧まざるユーモアのセンスに富み、芯はキツいのですが、物腰は柔軟で、独特の魅力を発揮する女性でした。 私は、この義母の作った「とって投げ」、つまりスイトンが大好きでした。小麦粉(?)を捏ねてから湿らせた布巾に包んで、一晩寝かせるのがコツだとか。 私の実母の作ってくれたスイトンも、なかなかなものでしたが、義母のものはそれを一枚も、二枚も上手な、上品な味わいを持っていたのを、よく記憶しています。 序と言っては何ですが、悦子の兄と弟、そして妹についても一言ずつ述べておきましょうか。長男の登さんはとても人の良い朴訥な人柄です。父親の後を追って遠洋漁業の船に乗っていた時代もあります。その頃、私は悦子と知り合って間もない夏のことですが、築地(?)の船員会館で初対面の挨拶をしたのですが、自家製のホヤの塩辛をご馳走になったのを、忘れずにいます。 弟の守さんは非常に姉思いのお人ですし、妹の累子さんはとても素直な、純朴な方です。 筆の序と言うのもおかしな表現ですが、ここまで書いたら、この素敵なお二人さんに言及しないのは片手落ちと言うことになるので、ご紹介しましょうね。 お一人は、金町小町と言うか、とびっきりの美人です。長谷礼子さん。悦子より少し年長者ですが、御心持ちのとても良い方。ハートの美人でもある。 そして、幼な馴染みの同級生で、現在でも青森県の野辺地にお住まいです。この熊谷礼子さんも、女優さんにも引けを取らないという、とびっきりの別嬪でいらっしゃる。そして、心根の方も超がつく程の優しさ。 天は二物を与えずと申しますが、このおふたりの礼子さん達は、自然にこの二つの美質を身に備えていらっしゃる。 このように書いてきますと、何か私が殊更に悦子を取り巻く親しい人々を美化して表現している如くに、或いは受け取られるかもしれませんが、さにあらず。類は友を呼ぶの譬え通りで、掛け値なしで素晴らしいお人ばかりなのですね、実際のところ。 さて、こう書いて来て、誰か忘れていませんか、と女神の悦子が耳元で囁くのが聞こえましたよ。 そうです、大切な御方を書き漏らすところでした。浅草今半の社長の澤井映子様です。 この御方も勿論美人なのですが、それよりも人使いの巧さで老舗を更なる繁栄へと導いていらっしゃる、名社長なのです。そして、悦子は生涯の最後にこの社長と運命の出会いを遂げたことで、接客者としての大輪の花を咲かせる事が、出来たのでした。悦子と澤井社長とは、お互いの長所を熟知し合った素晴らしい、幸運な出会いを遂げたのでした。本当に有難い事でした。 こうして見てくると、悦子は生家の家族以外にも、とても充実した人間関係を築き、ハッピーな生活をエンジョイするべく運命づけられていた。そう、結論づけて良いようです。 女性でありながら、女性が好きで、だから悦子の周りには美人女性ばかりが集まるという、実にもったいないような現象が、自然に生じていたわけですね。 こういう言い方もおかしいのですが、悦子は生来「男」という存在に興味や関心を持たなかった。そう言い切ってしまっては嘘になるでしょうが、私以外には強い牽引力を感じなかった。少なくとも、そんな風な表現なら、当たらずと言えども遠からずでしょうか。 それからこれは余計な事で、言わずもがなの所が多分にあるのですが、オカマなる変種の女性が大好きだった。それも、セックスアピールを少しも感じないで接する事が出来るから、という理由で。何も、本人から確認をとったわけではありませんが、私にはそんな風に感じられました。 一口に男勝りと言いますが、悦子はずばりそういう男勝りの典型でした。だから、良い意味で男っぽくてさっぱりしている。だから、女性に特有の 嫉妬 の感情などとは全く無縁だ。そう、頭から信じて過ごしていました。だから、何時だったか、電話で八戸の義弟・守さんと会話をしている際に、私がうっかり、「彼女は女っぽくないから、嫉妬など心配する必要がないから、気楽でいいですよ」と言ったところ、「何をいってるのですか、克征さん。克征さんが仕事で地方などに長期間行って、家を留守にしていた時などには、俺の所に頻繁に電話してきては、(浮気が)心配だ、心配だって、ぼやいていましたよ」と軽くたしなめられた覚えがあります。 そう言えば、彼女はほんの時折、私が「おやっ!」と思うほどに、私の前で実に女っぽい仕草としな(嬌態・科)を示す事がありました。本当に巧まずして、自然に垣間見せる女性らしい魅力あるポーズ。 そんな瞬間的でチャーミングな映像が、私の脳裏に強く焼き付いているところからすると、直ぐに忘れるともなく忘れていたのですが、私も相当にその瞬間瞬間で、悦子の「女」にチャームされていたに相違ないのでした。 過剰な嫉妬と言い、時折の仕草と言い、悦子はやはりごく普通に女だった。それを、勝手に私が男っぽいなどと決めつけていただけにしか過ぎなかった。 ごく当たり前で、普通の女だって、神仏の使い姫となることは可能だし、死後には私の守り神に変じる事も有り得ることなのだ。 「古屋さんの、家の奥さん」と仕事をご一緒した局プロがよく言っていた時期がありました。仕事以外の話題が必要な時に、私は口が滑っても、間違っても、自分の妻をネタにしておく分には、問題はないと考えたので、雑談の際に決まって家内の事を持ち出したので、それを揶揄するように言うのが、「古屋さんの家の奥さん」だったのですが、御存知の方もいらっしゃるでしょうがアメリカの刑事ドラマで『刑事コロンボ』と言うのが当時流行っておりました。それから私は安直にお借りしただけで、仕事中も家内のことばかり考えたり、思ったりしていたわけではありません。それどころか、家を一歩出ると、仕事の事ばかりが頭の中に居座っていて、悦子のえの字も思い出さない仕事一筋の人間でしたね。掛け値なしで、私はそれだけの人間でしたよ、実際のところは。 今になって考えてみると、悦子はそうした意味でも完璧な女房であって、亭主に我儘一杯を精一杯頑張ってさせてくれていたわけだった。私は、お釈迦様の手のひらの上できんとん雲で飛び回っていた孫悟空のような存在だった。 何から何まで、実に至れり尽くせりとはこの事で、私は名実共に「世界一の、いや、この宇宙で最高の果報者」であったし、今現在も、そしてこれからもそれは変わらない。 私は時折、過去を振り返って、自分が実際に経験したことでありながら、あれは本当に自分が体験したことだったのだろうか、と訝しく感じることがある。それくらい、過ぎ去ってみると、現実離れして感じる経験ばかりを閲して来ている、本当の、本当ですよ。 以前に、二人の息子たちと差しで会話を楽しんでいた際に、長男も、そして次男も、決まった言ったものでした。「お父さんの話は、要するに自慢話だけなのだ」と。私は、最初は唖然としてしまって、二の句が継げなかった。何故と言って、私には「自慢をする」などという意識はまるでなかったから。ただ、自分が経験した、ちょっとだけ他人とは違った体験を、有りの侭に、懐かしく語ったに過ぎない。 考えてみれば、芸能界で活躍する超有名人が次々に話題に登場する私の過去話は、実際「自慢げな法螺に近似した、それ故に浮世離れのした自慢話」としか、本人以外の人には聞こえなかったであろう。 実際、悦子も語っていた事があった、「あの渡辺 謙さんや松平 健さんなどというスターが、私にまで丁寧にご挨拶して下さるなどとは、夢にも考えたことはなかった」と。 おや、おや、またまた「自慢話」の方に話が逸れてしまいましたね。御退屈様でした。今回は、ここまでと致しましょう。
2020年07月13日
コメント(0)
-
自分自身との対話・その六十五
えつこ曼荼羅つれづれ草 の続きである。 例によって夢の中での諭しがあり、「太郎と花子の物語」と題する小話を作ってみるように指示された。 それで、私は半分夢から覚めかけながら、これは是非とも傑作を物しなくては、と意気込んでいた。 フィクションや創作詩は、悦子との思い出の中から、下手ではあっても、過去にいくつか創作している。 直接の体験やその時々の感懐などは、いくらでも質を問わなければ でかす 事は可能だ。 が、それでは、この世で生きて、生(なま)の感情から生まれる狭い範囲の内容しか、実現できないことになってしまう。それでは、発展性にかけてしまう憾みがある。もっと、純粋に、生そのものから生まれ出る珠玉のような作品とはならないであろう。それでは詰まらないのです。 そこで、結果の良否は問わず、女神の「えつこ」に手を引かれて、とにかくもトライしてみよう。 「 太郎 と 花子 の 物語 」 ―― 習作の 一 太郎は健康で、明朗な男の子だ。今の所、日本列島の南に住んでいる。花子は活発で、頭の回転が速い愛らしい少女である。住まいのあるのは、日本列島の北の静かな海辺の町である。 太郎には二歳下の妹が居る。名前はスミレ、聡明で、おしとやかな女の子である。 太郎は成人して、やがてふとしたきっかけから花子と出会い、そして徐々に恋に落ちる。そして、太郎は一個の青年男子として、立派に成長していく。 この兄太郎の変化を、太郎の直ぐ身近にいてじっと見守るスミレも、一人の魅力ある女性として、成熟を遂げ、自らも彼女に相応しい生涯の伴侶を得て、幸せな結婚生活に入る。 所が、スミレは彼女なりに兄太郎をこよなく愛していた。恋愛感情とは違う、妹としての深い情愛に裏打ちされた感情で以て、である。 しかし、これは本人の自己分析でしかない。作者の見るところ、スミレの兄に寄せる恋心は、タブーとして周囲はもとより、スミレ本人も無意識のうちに自らを強く自己規制していたからこそ、恋愛以上の純粋で、プラトニックと呼ぶに誠に相応しい愛情で、太陽のコロナの如く燃え上がっていた。 これも、無理はなかった。太郎は誰よりもスミレに優しかった。そしてまた、純粋無垢な、豊かな愛情で年下の幼い、愛らしい妹を愛するのを常としたのであるから。 太郎の方では、花子に出会うまでは、身近な女性といえば母親と妹、それに近所に住み同じ学校に通うクラスメイトくらいであった。異性・女性に対する太郎の理解と交際範囲はそれで十分すぎるくらいに、十分であった。少なくとも、花子という女性に出会うまでは……。 花子との不思議な恋愛体験を経てからも、妹スミレに対する太郎の感情は、少なくとも自身の認識では余り変わらなかったし、それ故に、スミレが結婚するに相応しい相手を得て、両親や兄太郎に紹介した時にも、直ぐに素直な気持ちで祝福する事が出来た。心の底から妹の幸福な未来を願った。それで何の問題もなかった。 しかし、ある時から、太郎のこの心の平安に微妙な不安定感が生まれていた。太郎自身、それに気づかなかったくらいに、微妙なものであった。 妹スミレと妻の花子は、見た目にも、当人同士の自覚からも、仲の良い義理の妹と兄嫁のそれであった。当然である。太郎も、花子も、そしてスミレも人生における最高の伴侶を得て、順風満帆、幸せの絶頂にある。 スミレの夫良夫は万人が認める善人であり、仕事も、社交も、家庭での夫ぶりも万点であると言えた。が、スミレには何故か、それゆえに何か物足りないものが感じられた。それは、非常にデリケートで微妙な感情であったから、スミレ自身がそれを始め、はっきりとは自覚しない体のそれであった。 最初にスミレの変調に気づいたのは、ほかならないほんのたまにしか顔を会わす機会が無くなった太郎の方である。スミレは確かに幸福感で一杯の、輝くように美しい若妻に相違なかった。夫良夫とも上手く行っている様子が、ひと目で分かる。それでいて、どこか本人も気づいていない軽いアンニュイの様な雰囲気が、何処からともなく仄見えて来るのだった。 それで太郎は軽い冗談のつもりで、「おや、おや、スミレ奥様は幸せ疲れなのでしょうか…」と、その時に飲んでいたビールの酔が言わせた如くに、ややおどけた調子で口にした。 スミレは一瞬ではあったが、不意を突かれたように、何とも名状しがたい表情を、美しい顔に浮かべた。そして言った、「あら、お兄さんこそ、幸福に疲れた、とんだ幸福長者様といった雰囲気を、周りの人たちに見せびらかしていらっしゃるようですわ」と。 何かがおかしいぞ、と太郎は心の中で感じたが、そんな感じは噯気(おくび)にも出さず、「御明察、さすがは私の自慢の妹御だけのことはある」と、全部冗談にして、切り返すしか手段がなかった。 その場に居た誰もが、いつも仲の良い兄妹の軽いじゃれあいのやりとりと受取っていた、事実、そのセリフの交換が、その場を更に明るく盛り上げる効果を発揮した。 しかし、太郎の新妻・花子はその時のスミレから、ある種殺気と言うか、挑戦状を突きつけられた如くに感じた。そして、始めて義妹のスミレを同性のライバルとして、明瞭に自覚したのだ。 長い間、太郎は花子とスミレの間に展開されていた、静かで、見かけは至極平穏であったが、その実、猛火の様な激しい熱気を内側に孕んだ、不気味な女同士の戦いを全く知らずにいた。 ある時に、花子の親しい女友達の睦羽から、「太郎兄さんは、今でも妹さんをとても可愛がっていらっしゃるそうですね。花子が思わず嫉妬してしまうくらいに」と言われた折に、何故か内心でギクリとしたものだ。睦羽本人は何気なく花子の言葉を伝えただけだったのであろうが、それを親友に語った妻花子の心には何か鋭い棘が感じられたから。 花子は普通の女性で、特に嫉妬深い性質ではなかったし、スミレの事を口にする時には、決まって褒めていたし、その表現には極めて自然さが感じられていたのだった。 花子が妹のスミレに 嫉妬 を感じるだって。それでも、その言葉が、太郎自身に面と向かって発せられたものであったならば、微笑を浮かべるくらいの反応で、何事もなくすんでしまったであろうに。事実、幼い頃から太郎とスミレは近所でも評判の仲良し兄妹の仲だったのだから。 以来、花子とスミレの間に、静かではあっても「凄まじい」女の戦いの火蓋が切って落とされたのであった。それは周囲の誰もが気づかない凄まじい 女の戦い となったのだ。 では何故こんな事態になってしまったのか? 誰が一体悪いのであろうか? 誰も悪くはないのだ。ただ、花子も、そしてスミレも、ひとりの「男性」太郎を普通以上にひたむきに愛してしまっただけなのだから。 そして、花子もスミレもお互いに相手を一人の女性として敬愛し、尊敬さえしていたから、相手を互いに「許せない」と感じてしまったのだ。 相手が少しでも自分より劣っていたならば、これ程の熱い戦争が繰り広げられなかったに、相違ない。 人間社会では往々にして、こういう確執が生じてしまうものだが、一見、何の問題も生じよう筈もない女性達の間に、かくも凄まじい暗闘が勃発した本当の理由は、神ならぬ身の知る由もない事だが、ここで作者が止むを得ずして想像を逞しくすれば、最低限、次の様な事を指摘できるであろうか。 事は男女間の強い愛情に関するものである。普通の愛情であれば、誰が誰を愛そうと、仮令その対象が同じ人物であっても、対立もなく、謂わば平和裡に共存は、易易と可能なのである。 所が、ひと組の相思相愛のカップルに関しては、それは無理な相談という事になる。そうならなければどうしてもおさまらない。男女の、地上の愛には肉欲が必然的に伴う事になる。一人の女性を熱烈に愛した男は、相手の女性が己以外を愛情の対象とすることを、断じて許すわけにはいかない。女性の場合にも全く同様の事が言える。 愛するカップルは、永遠に二人きりであることを、少なくとも理念の上では、望むものだ。男の浮気性と言う問題を考慮に入れても、この理想的恋愛の歓喜状態は、永遠を志向する。 ここで、スミレの太郎に対する愛情の分析入らなければいけないだろう。 この地上にあって異性を愛する者は、霊・肉共に強く結ばれたいと願う。しかし、近親者との肉の結合は慣習として、つまり部族的な習俗や文化的な背景等によってタブーとされ、それは後の科学的、優生学的な見地からも是とされ、ある種絶対的な権威として確立している。しかし、性愛欲は本能に準じる強烈にして制止不可能な欲望である。 スミレはこの殆ど絶対的なタブーの制止に遭って、身動きできない状態にある。しかし、兄太郎に対する愛情は熾烈極まりない。止むに止まれない。どうしたらよいか? どうすることも出来はしない。地獄の業火に焼かれる如くに、スミレは呵責ない責め苦の下に置かれている。しかしながら、この強烈な苦しみの中にも、激しい歓喜がある。喜悦が存在する。しかも、花子という兄太郎の正当な配偶者と言う、最強のライバルも出現している。 だからスミレは苦しみから逃れる為にも、又同時に、歓喜をいや増す目的の為にも、この「憎むべきライバル」、宿命の敵対者と死闘を演じなければ、どうしてもいられない軛(くびき)を自ら買って出ても、身に帯さなければならない宿命を負ってしまっている。 さて、この三人の男女の愛欲の葛藤は果たして美しいのか、それとも醜いのか。作者は美しいと賛美することも、醜いと非難することも可能だが、今の段階ではコメントを差し控えたいと思うのだ、 この作者の態度は卑怯でありましょうか? それとも又……? 次回まで、読者それぞれの御想像にお任せしたいと思うのです。何故なら、人生はエンジョイすることに有り、何事もプロセスが最も大切なのでありますからね。
2020年07月06日
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- お買い物マラソンで値上げされても後…
- (2025-11-30 20:30:05)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 🐼楽天ブラックフライデー🐼お疲れ様…
- (2025-11-30 22:56:15)
-