2006年05月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
友の携帯
数十年来の親しい友人に近況のメールを送ったら、アドレスがないと返って来た。 携帯電話と携帯メールだけで繋がっていて、住所も電話番号も月日と共に、無くなってしまった。 無性に寂しくなった。 電話を変えたのなら教えてもらえなかったことに対してや、諸々のことが頭に浮かんでは消えた。 もう年に一度のお誕生日をお祝いし合うこともなければ、近況メールの交換もできないのかと、たまらなく寂しいのだ。 かろうじて記憶の糸を手繰り寄せ、PCのメアドを思い出した。 もしかしたらすでに解約してしまったいるかもしれないと思いながら……。 なんと。 理由はこうである。 携帯を紛失したので、サービスを止めてあったらしい。 だから携帯メールのアドレスも機能を停止していたという。 最悪の場合まで想定し、悶々と日々を過ごしていたので、彼からの『殺すなよー』の近況メールが届いた時には、肩の力が思わず抜けた。 生きていたんだと、とても嬉しくなった。 でも、こういうことが段々と現実になることも否めなかった。 そういう覚悟もいるのかもしれない。 侮れない現実を垣間見た気がした。
2006年05月24日
コメント(4)
-
ハナミズキ (続)
せっかく書き始めたエッセィ、『花水木』の途中で、闘病生活を余儀なくされている。 大好きなこの時季に外に出られないのはすこぶる残念なのだけれど、せめてその感覚を思い出しながら書いてみようと思う。 新しい季節を迎えるたびに、色んなことが浮かんでは消える。 たまたま同室の同病者(急性膵炎)と交わす言葉の中に、遠く懐かしい日々が蘇ってきたりするのも乙なものであり、しきりに浮かぶのが亡き母のことであった。 わたしと亡き元夫とは、姑の大反対の元に婚姻した。 そんな経緯もあり、結婚はもちろんのこと、子供が誕生するに当たっても数々の苦々しいエピソードのオンパレードだった。 中でも圧巻は、亡き母に向かって姑が吐いた罵詈雑言。 今でもそのときの有様を思うに、望陀の涙なくしては語れないものがあった。 母の手の甲に落ちる大粒の涙は、膝の上にきちんと重ねられた指先を通って、正座した膝を瞬時にぬらしてしまった。 本当ならば、耳を塞ぎたかったに違いなく、じっとこらえて石のように動かなかった母の姿に、 わたしは感銘を受けていた。 と同時に、母の気持ちを慮ると、この結婚は最大の親不孝をしていると、謝罪したくて身を捩り泣き叫びたい衝動が、何度も何度もわたしの中心を貫くのだった。 「私の生んだ子供です。行き届かない娘であることは重々承知しています。それでも縁あってこうして結ばれた夫婦。どうか末永く本当の娘だと思って見てやってください。娘にも努力をさせますが、どうしても、どうしても持て余した場合は、私が責任を取ります。その時はちゃんと引き取りますから。どうかよろしくお願いします」 七十歳を目前にした母は、姑の前に土下座した。 そしていつまでも額を畳から上げなかったのだ。 わたしは、自分の意志で選んだ結婚なのだから、何があっても絶対に離婚はしない、最後まで添い遂げることが母親への恩返しなのだと、歯を食いしばって目の前の光景を胸に刻むのだった。 それなのに、夥しい時が流れわたしは彼と離婚し、彼は昨年他界した。 「そう。そんな経緯があったの」 隣のベッドの彼女がティッシュで鼻をかんだ。 「あんまり話したくはないんだけどね」 当り障りのない話でお茶を濁していた会話も、そこの部分を話さなければ、筋道が繋がらなかった。 今年の花水木を、見ることができなかった。 家族で住んでいたあの家を、そこで繰り広げられたさまざまな人生の縮図を、ふと思い出しながら、花水木の咲いていた風景が頭をよぎった。 いつか傷がすっかり癒えたなら、あの家や花水木を見事に咲かせていた、あの花の道を歩いてみたいなー、と緩やかになった痛みの中で、わたしは思った。 その日は、遠くないと自分の中で何かが終息を告げている気がした。
2006年05月23日
コメント(3)
-
雑感(近況)
かれこれもう二十日以上も、わたしはベッドに横たわっていた。 救急車で運び込まれた夜、急性膵炎と診断され、治療を受けているのだ。 まさかこんなことで入院生活を余儀なきされるとは、思っても居なかったから強いショックと、軽い諦めの境地で白い石膏ボードの天井を眺めているのだけれど。 激痛を抑えるために筋肉に打つ痛み止めは、チェーンのように二週間続き、ようやく痛みが身体を去った。 今は、最後の仕上げで、もう一息といったところ。 おかげでかなり健康を回復した。 大好きな新緑は、いつの間にか緩やかに通り過ぎて、窓から見える海は、少しずつ梅雨空の趣を添えている。 こうして寝ていると、ついつい思い出すのが、末期がんで横たわっていた今は亡き元夫の寝姿。 辛かっただろうなー。 激痛に襲われると人は、心細くて自分を持て余してしまうのだ。 際限のない痛みが続くのではと、恐怖や錯覚に苛まれ、時には涙さえあふれ出た。 本当に、その身になってみなければ分からないことが多いのだと、改めて思い、彼の姿が次々と浮かぶのだった。 あの時の、彼の末期がんの痛みは、わたしの痛みの数十倍だったろうに、じっと耐えて、耐えることが自分の宿命でもあるかごときに見せた姿は、わたしや娘たちにとって忘れられない残像となった。 本当に悪いことをした、と今となっては遅いのだけれど、そんな風に浮かんでは消えるのだった。 それと同時に父や母の、入院時の姿も浮かび、切なくて胸が痛んだ。 顔を見せてもらうだけで、患者にとってはどれほど嬉しいものなのか、と分かるからだ。 わが娘たちは、その辺りの機微を理解し、毎日覗いてくれた。 それがどれほど励みになったことか、今しみじみと感謝の思いが湧くのである。
2006年05月23日
コメント(12)
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- ◇◆◇節約 生活◇◆◇
- 料理のセンスのない専業主婦が作った…
- (2025-11-24 04:53:47)
-
-
-
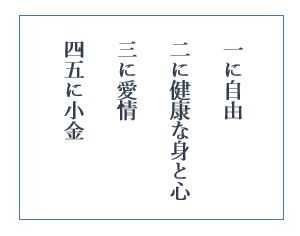
- 日記を短歌で綴ろう
- 〇☆〇この日1日のこと
- (2025-11-25 07:34:20)
-
-
-
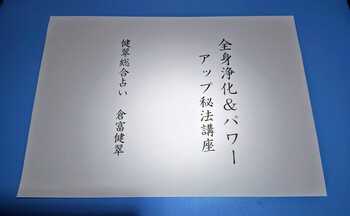
- 運気をアップするには?
- 全身浄化&パワーアップ!が手軽に実…
- (2025-11-24 23:57:10)
-







