2006年01月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
父の逝った冬
夏に生まれた長女を連れて、父の看病に帰った時のこと。 その冬はものすごくインフルエンザが流行ったと記憶している。 わたしも例外なくウィルスの洗礼を受けてしまい、寝床から抜け出せないでいた。 母の負担を軽くするための里帰りが、結局は煩わせる羽目になった。 赤子の世話と新たな病人が増えて、充分な看病ができないと知った母は、嫌がる父に頼んで病院へ入ってもらうことになったのだけれど、その時の父の様子がくっきりと脳裏に浮かんだ。 「二度とここには戻れないだろう」 そういってストレッチャーの上に起き上がったまま、名残惜しそうに自分の部屋を振り返った父。 わたしは頭も起こせないほどの頭痛で、寝床の中から父を見送ったのだった。 事実、父がそこへ戻ったのは、それから一月足らず後の如月の夕方だった。 「わしが死んだら、葬式はいらん。家族だけで密葬にしてくれ。その代わりずっとマーラーの『巨人』とチャイコフスキーの『悲愴』をかけてくれ」 が、父の遺言だった。 遺言は守られて、お通夜から告別式の間中、途切れない線香と共にこの二曲は流された。 この冬は、父の逝ったあの年に似ていた。 そういえば、もうじき父の命日がやってくる。
2006年01月22日
コメント(0)
-
雪解野(ゆきげの)
気温が緩むと…。 春が来そうで嬉しくなる。 冬の後には、絶対に春が待っている。 だから、どんなに辛いときも人は耐えられる。 わたしはいつも、そうして春を待つ。 大地が芽吹き、力強く覚醒する日は、そんなに遠くはないから。
2006年01月16日
コメント(2)
-
篝火草(かがりびそう)
篝火草とは、紅色のシクラメンの別名らしい。 大晦日。 スーパーの店先でシクラメンの大バーゲンをしていた。 なんと一鉢が500円だった。 個人的にはあまり好きではないのだけれど、真っ赤なシクラメンを見ていたら、何かに書いてあった別名の『篝火草』が浮かんで、まさにこれだと衝動買いしてしまった。 わたしは鉢植えの花をあまり好まない。 うっかりお水を忘れて、大方枯らしてしまうからだ。 でも今は花の少ない季節だから、その存在は中々大きいことに気付かされる。 今回は枯らさないようにしなくちゃと緊張していたのに、今朝花が頭を垂れていた。 あ、しまった。また水を忘れたのだ。 大急ぎでコップ一杯の水をあげると、現金なもので花はすぐに生き返った。 そういえば、亡父は毎年、冬の初めには何鉢か買ってきたものだ。 「はい、シクラメン」 と、母に渡した。 草花の好きは母は嬉しそうにそれを受け取って、花の状態を品評するのだった。 そんな何気ない光景を、今思い出す。 こういう些細なことが、我が家の冬の風物詩でもあった。 わたしの感傷とは無関係に、シクラメンは炎のように咲いている。 なるほど。まるで篝火のようだった。
2006年01月15日
コメント(2)
-
歌
長女に誘われて、久しぶりにカラオケに行った。 あまり好きではないのだけれど、気分転換には最適である。 それぞれ選曲をし、次から次へと歌った。 でも、歌というものはリアルである。 思い出があふれ出し、声にならなくなった。 生前、彼がよく歌った『珍島物語』は、不覚にも全く歌えなかった。 我ながら、この反応には少々驚かされた。 「これが母ちゃんです」 彼は、自分の行きつけの店には、ほとんどわたしを伴うのだった。 月に一度、単身赴任先の彼を訪問し、身の回りの世話をする生活が、どのくらい続いただろうか。 そんな行きつけのスナックのママが、この『珍島物語』を手ほどきし、彼がこれを歌うと、店中が静まり返ったものだ。 その時のシーンが、そのまま浮かび上がった。
2006年01月11日
コメント(0)
-
訪問着
西日がオレンジ色の優しい光を放つ午後、着物を広げてみた。 迷っていたのだけれど、久しぶりに袖を通してみようと思ったのだ。 黒の紡ぎに白糸の刺し子が施された訪問着は、結婚二十年記念に夫から贈られたものだった。 でも単身赴任中だった彼は、一度もこれを見ていない。 メールで印象を伝えて了承してもらい、その後のドサクサのうちに離婚して、そして他界した。 「黒にした」 と伝えた時、 「君らしいね」 と言ったけど、まさしくわたしらしい選択だった。 合わせる帯が見つからないまま、タンスで長く眠っていたのだけれど、ようやく遜色のない帯に出合ったのが二年前のことだった。 決して安くはなかったが、それほど高価というものでもない。 そこで頑張った自分へのご褒美にと、わたし自身がこの帯を買った。 若い頃は、よく着物を着たものだ。 初釜だ、花展だと、着る機会がかなりあったからだ。 でも、結婚して子育てをしているうちに、袖を通す機会など皆無となった。 本当にタンスの肥やしとはよく言ったものだ。 さっと羽織って、帯揚げ、帯締め、重ね襟に落ち着いた深紅を持ってきた。 銀と黒の縞模様の帯との収まりも、中々良い。 やっとお正月が来た気分がした。 さて、どこへ行こうかしらん。
2006年01月09日
コメント(0)
-
恋心という名の化粧水
体内から、恋心が抜け落ちてから早、幾歳月。 悔しいけど、悲しいけど……。 人を恋うる気持ちは、絶対に美容に良い。 潤いを与えてくれるもの……。 なのに、なのに。 殺伐とした日々。 どこかに落ちてないかなー。 恋心という名の化粧水。
2006年01月09日
コメント(2)
-
鋏の音
長い間愛用していたヘンケル製のお気に入り花鋏は、荷物の中に入れたつもりだったのだけれど、ドサクサの中姉の家に忘れてしまったらしい。 それ以来、百円ショップで買った鋏を代用しているがイマイチで、大好きな鋏の音が響かない。 本物が欲しいなーと思いながら、やはり高価な鋏はなんとなく買う気がしなかった。 昨日、何気なく寄った刃物屋のバーゲンで、なんと二千円足らずで売っていた。 思わず手にとって握ってみた。 しっくりときて、中々良い塩梅だったので購入した。 久しぶりの、本格的花鋏である。 早速、お正月に生けた花の手直しに使ってみると、大好きな鋏の音がした。 それは、とても懐かしい音だった。 18歳で出遭ったいけばなを、わたしは12年間続けた。 わたしにとってのそれは、ある種の精神修養の場でもあった。 花材を前に置いて生けこむ前の、あの緊張と研ぎ澄まされた空間が、わたしは大好きだった。 高がいけばなで、と人は笑うかもしれないけれど、わたしにとっては実に崇高で落ち着く場所だった。 どんなに辛く悲しい出来事があっても、暗く澱んだ日々が続いても、その場に臨んだ瞬間、わたしの心は穏やかで満たされたものだ。 そんないけばなに、わたしが背を向けたのは、純粋さとは裏腹の現実の人間臭さに嫌気がさしたからである。 きっと若さゆえの純粋さが、清濁併せ呑むということを拒んだのだろうと思う。 今なら、案外それを受け入れることができたかもしれない。 わたしは、断腸の思いで鋏を置いた。 そして、二度と握るつもりはないと覚悟した。 でも、やはりいけばなも、花も大好きで、それらに対する思い入れは、無理をして断ち切る必要もないものだった。 鋏の音を聞くたびに今でも当時の純粋だった自分に会えるのだし、鋏の音は、わたしに再び静謐な時を取り戻してくれるのだから……。
2006年01月07日
コメント(2)
-
お雑煮
我が家の雑煮は、亡き母の形見だ。 両親と長く暮らしていたおかげで、わたしは特に料理を教わったことはないけれど、その味は割合正確に継承しているつもりだ。 当時、ほとんど料理を手伝っていないから、母の背中の動きと味覚だけの記憶なのであるが……。 そんなある日の大晦日。 母が大量の一番だしを取っていた。 傍らの出汁カスの中に、するめを発見したのだ。 「するめで出汁?」 「そう。お雑煮には昔からするめを入れるのよ」 「へぇー」 それから幾歳月が経過して、わたしが主婦としてお雑煮を作る日がやってきた。 でも、頭の中で考えていた味が出なかった。 試行錯誤した後、わたしははたと、するめの存在を思い出したのだ。 その日から、わたしのお雑煮は母の味となった。 出汁を取りながら毎年母との会話を思い出し、無性に母に会いたいと思うのだけれど、『孝行したい時、親は無し』とひとり苦笑している……。
2006年01月02日
コメント(6)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-
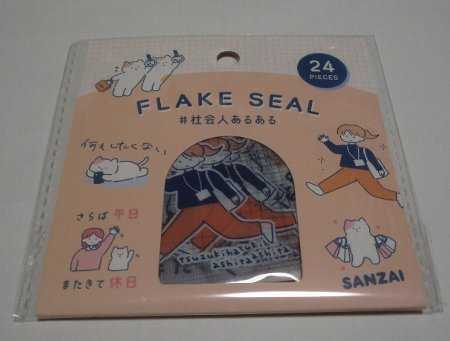
- 100円ショップ
- フレークシール・コレクションシール…
- (2025-11-25 01:19:42)
-
-
-

- φ(._.)主婦のつぶやき☆
- 神農生活近鉄あべのハルカス店
- (2025-11-25 11:50:05)
-
-
-

- 暮らしを楽しむ
- 【楽天ブラックフライデー最終日】ポ…
- (2025-11-25 11:17:17)
-







